
Flavor of Peaberry Coffee Cherry
この小説は、以前pixivで不定期連載されていた中編小説シリーズで、ゲーム「エルシャダイ」の登場人物から派生したツイッター上の非公式キャラbot「ルシフェル店長」の三次創作小説です。その旨をご理解の上、ご鑑賞下さい。
(※botとは、ツイッター上で自動的に発言するプログラムのこと。キャラボットとはある特定のキャラクターの言動や行動などを連想させ、再現するような動作を行うように設定されたbot、とお考え下さい)
■「ルシフェル店長」は、「El Shaddai」に登場するキャラクター「ルシフェル」を元にした非公式な二次創作キャラクター(一般向け/現代パロディ)であり、その二次創作設定を元にした三次創作作品になります。
※ルシフェル店長取り扱い説明書ページ http://cafeluci.blog98.fc2.com/blog-entry-3.html
後半から、同じく「エルシャダイ」の非公式キャラbotの「どSルシフェルbot」が出てきます。
※どSルシフェル取り扱い説明書ページ http://twpf.jp/salucifer
ルシフェルが二人いる時は、「店長」「S」というふうに、名称表記を分けています。
物語としては、「エルシャダイ」のキャラクターから、ルシフェル(原作本編では神に次ぐ地位の大天使)が、地上で普通の人間かつ、現代の日本でカフェの店長をやっている、という現代パロディ設定の非公式botと、その周辺について妄想したお話になります。二人のルシフェルの他に、それぞれの相方となるイーノックと、少女ナンナ(あと、神…?)も出てきます。
※注意:それほど過激な描写はありませんが、一部に流血や、(BL的な)性的な場面を暗示させる表現なども出てきます。そういうものが苦手な方は閲覧に際しては十分ご留意下さい。
邂逅

どこかで猫が鳴いている。目の前には薄汚い灰色が広がっていた。あちこちに黒っぽい染みやひび割れがあり、漆喰が剥げ落ちている箇所もある…それは、何百年という長い時間、行きかう人々の靴の底で擦り減らされた石畳の上に垂直に立つ、古ぼけた壁だった。
ゆっくりと目線を動かすまでもなく、頭上には空があるのを感じた。からりと晴れた、硬質な青が、目の前の壁にわずかに照り返している。しかし、そこに明るさは無かった。この狭い路地は、両側から高い壁に囲われていて、その底にまで太陽の光は届かなかったのだ。
口の中に中近東の砂漠の粒子の細かい砂と、微かな血の味を感じて、わずかに眉をひそめる。拭おうとして顔の前まで上げた手の甲にも、赤黒い血がこびりついていた。現地の住人が日常的に着用する、麻袋のように質素な服は微妙に乱れて、足は片方、裸足だった。
…どうして、此処にいるんだっけ…。
熱っぽい、ぼうっとした頭の中で自問した。しかし、答えは無かった。かわりに頭上で砂混じりの風が鳴くような音を立てる。目を閉じて、ゆっくりとまた開けた。
純度の高い上等のココアパウダーのような、少し甘めの色合いの、明るいブラウンの瞳。黒く長い睫毛に縁取られている。睫毛と同じ色の漆黒の短い髪が、一瞬、乾いた風に乱暴にかき乱された。風にあらわになった首筋は見た者をハッとさせるに違いない程、透き通るように白く、そしてか細かった。ひょろりと長い手足、骨格は確かに男性のものなのに、どこか艶めかしい女性を連想させた。
「のど、痛いな…。」
本来は柔らかい筈の低い声は、砂まじりの風にやられて、確かに自分の口から出た筈なのに、まるで他人のそれのように現実味なく四角い空間に響く。水を飲めば良くなるのかもしれないが、しかし、何もかもが億劫だった。
考えたくない。何も。…それでもたった一つだけ確実にわかっていることがあった。
このまま此処にずっとこうしていたら、自分は死ぬのだ、ということ―。
別に、それでもいい…。そんな風に思って、また目を閉じた。自分でもどれだけあるのかわからない体中の傷口が、ひりりと痛む。…まだ、生きているんだな。めんどうくさいや…。
「…大丈夫か?」
突然その”声”は静かな闇の中に割り込んで来た。男性らしい低音の、けれど角の無い何かまろやかなものを転がすような、その”声”を、何故か瞬間「心地良い」と感じ、彼は、内心でちょっとだけ驚いた。長い睫毛を押し開け、声のした方を見遣る。
真っ先に飛び込んできたのは「光」だった。
ゆるやかにうねる蜂蜜色の肩まで長い髪が、問いかける顔の周囲をいっぱいの日の光にきらめきながら、取り巻いている。路地を一歩出た向こう側には、午後の傾きかけた陽光が差して、自分に声を掛けた男はその光の中に立っていた。まるで「祝福」のような光…。
眩しくて、思わず目を細めた。すると男は何かを勘違いしたのか、影の中に踏み込んで、そのままずかずかと近寄って来た。彼のすぐ近くまで来ると見上げるような大きな体を「よっ」という掛け声と共に折りたたんで、しゃがみながら大きな手を突き出した。健康的な褐色の肌。色んなものを包みこめそうな、広くて、大きな掌。初めて真正面から眼と眼が合って、思わず息を呑んだ。
深い深い、どこまでも澄んだ、穏やかな海緑色の瞳。微笑しながらこっちを見ている。大きくて形のよい口が開いた。
「…君、のど乾いてる?腹減ってないか?」
聞き取れない外国語というわけではなく、しかし一瞬、本気で何を言われているのか理解できなかったので、ぼんやりと見上げていると、金髪碧眼で褐色の肌の大男がくしゃっと笑みに顔を崩した。一気に雰囲気が和らいで、まるで何か面白い遊びを思いついた子供のように見えた。差し出した手は相変わらずいっぱいに掌を広げたままだ。
「一緒に来ないか?…さっき、すぐそこで結構良さそうなカフェを見つけて…実はさ、俺も昼メシがまだなんだ!」
…何を言っているんだ、コイツは?本気でそう首を捻りながら、しかし、自分でもどうしてかわからないままに、彼は差し出されたその手を取っていた。自分の細い手首が玩具のように見えるほど、大きくて、少し砂でざらついていて、そして温かい手だった。
手をひっぱって自分の隣に立ちあがらせると男は、ヘェ~結構背が大きいんだな、俺と変わらないよ、と独り言のように驚いていた。
「じゃ、行こうか。その角を曲がったところに、肉料理の良い匂いの店が…あ、そうだった。まだ名前を聞いてなかったね!」
歩きだしかけてパッと振り返る。…この男はいちいち動作が大げさだな、なんか犬みたいだ…そんなことを考えた。
「俺はね、イーノックって言うんだ!い・い・の・っ・く…わかる?じゃあ、君の名前は?」
「…名前…?」
「そうだよ。君の名前。この近くに住んでるの?家族は?」
「…知らない。何も、覚えてないんだ…何も。」
記憶喪失、と呟いて、ふと金髪の中の顔がくもった。それを見た時に、胸がちくりと疼いた。怒らせた…?と不安になる。
「本当に、何も覚えてないのか?呼ばれていた名前とか…?」
「それならわかる。名前は―」
一つ呼吸をおいた。何故か、それを伝えることを自分が躊躇ったような気がした。
「ルシフェル。…誰かに、そう呼ばれていた気がする。」
いま、何か呪わしい言葉を口にしたのではないか?という感覚に襲われて、彼はココア色の瞳を伏せた。どうしてかは分からないままだ。目の前のこの男も、きっとそういう顔をしているのだろう。…もう、あの弾けるような笑顔は見られないに違いない…。何故だか、そのことをさびしく思っている自分を感じて、ルシフェルはあれ?と思った。
突然、力強く肩を掴まれてぎょっとなった。
「そうか。君は、ルシフェルって言うのか。うん…すごく綺麗な名前だな!」
目の前には、満面の笑みでこちらをまっすぐに見つめる褐色の顔があった。胸の奥をぎゅううっと強く握られたような感じがして、ルシフェルは思わず耳の先まで真っ赤になった。それと同時に、本人は全く気付いていないらしいが、ココアパウダーの明るいブラウン系の色調だった瞳に、瞬時にさあっと血液が集まって、まるで柘榴石(ガーネット)のような、燃えるような深みのある紅の色に染まった。
何だろう?一体何だろう、この不思議な感じは…。鼓動が耳の中で激しく鳴っている。
そんなルシフェルの動揺に全く気付かずに、褐色で金髪の大男…イーノックは、ルシフェルの手を引っ張ってどんどんと道を進み、バザールの賑やかな一角にある庶民的なカフェに入った。昼食時にはやや遅く、店内はまばらな客だけで閑散としている。
店の親父に向かって慣れた様子で手際良くメニューをいくつか注文すると、イーノックは「さて」とばかりにルシフェルに向き直る。全身から楽しげな雰囲気を発しているその姿に、ルシフェルはまたさっきの「犬っぽいな」という印象を思い出していた。
「何話そうか?!」
「え…話すって…何を?」
「本当に何も覚えてないのか?前どこに住んでいたとか、食べ物は何が好きとか…」
「知らない…何も、思い出せない…」
「ふうん…じゃあ仕方ないなぁ…」
そこへ、店の親父が注文した料理を運んできた。が、明らかに様子が普通ではない。典型的な現地の住人といった風貌のその髭面の中年男は、何か不快なものを見るような顔でテーブルについたルシフェルを見下ろした。ルシフェルと目が合うと、さっと視線をそらして口の奥で何かもごもごと呪わしいような口調で呟いた。…それは酷く卑猥な発音の、現地の性的な隠語だった…。
ルシフェルは店内を見まわした。数人しかいない客は一様に店主と同じような顔つきでこちらを睨んでいて、彼と眼が合った瞬間に全く同じようなそぶりを見せた。つまり、呪いの言葉を吐き捨てて、さも汚らわしげに目を逸らすのだった。
それを見ても、ルシフェルには特に怒りや悲しみの感情は湧いては来なかった。何も覚えていないにも関わらず、彼はその自分に対する扱いがここでは至極「真っ当な」ものだということがわかった。何故かは知らない。
あるいは、刷りこみのようなものだろうか?自分は汚い…そんな思いが条件反射的に込み上げて来て、彼は、ついさっきまで座り込んでいたあの路地に戻りたくなった。あの場所こそ、自分に似合いの空間だったのに…どうしてこんなところへ来てしまったのだろう?ここから逃げたい、誰もいない所へ…。
まだテーブルの横に突っ立って、不機嫌そうにルシフェルを見下ろしていた店主の腕をいきなり褐色の太い腕が鷲掴んだ。
その余りの腕力に一瞬げっ?となった店主の顔を、イーノックが真正面から覗き込む。しかし口から出た言葉は―
「おじさん、これ凄く旨いよ!この魚の煮込んだやつ、もうひと皿持って来てくれるかな?こっちの”彼”の分も、さ。」
「あ、ああ…わかったよ…。つ、追加だな?」
「うん。あと飲み物は何がある?もう一度メニュー見せてよ。」
慌てて厨房に引っ込んで行った店主のことは気にもせず、ぱくぱくと料理を口に放り込みながらイーノックが笑った。
「こっちのも美味しいよ!…食べないのか、ルシフェル?」
「あ…うん。あの…お前…」
「ん?」
出来るだけぶっきらぼうを装って問いかけようとしたが、イーノックの海緑色の目にまっすぐ見つめ返されて、ルシフェルは思わずココア色の目を泳がせた。何だこいつは。本当に、一体何なんだ…?
「どうして、私を連れて来たんだ?…今の、見ただろう?みんなが私をどんな風に扱っているか…あんな、汚いものを見るような目で…」
「ああ、そうだな。確かにちょっと汚れてる。でも、宿でシャワー浴びれば綺麗になるさ!…俺だってまともに風呂にはもう二週間も入ってないよ。」
「そ、そういうことじゃないだろ…!」
「?どういうことなんだ?」
「だ、だから…ああもう!いらいらするな!お前なんでそんなに変な奴なんだ?!」
「え?俺って変なのかな?やっぱり?よく言われるんだ!友達とか、あと養父母もよく笑いながらそう言ってたよ…」
二カッと笑って、イーノックがまた大きな肉の切れ端を口に放り込みながら答えた。
「二人とも、病気でもう死んじゃったけどね。…だから、俺も君と一緒だよ。帰るところって、別に決まってないんだ。」
「え…?」
「君さえよかったら、一緒に行こうよ。仲間が出来たらきっと楽しいし…バックパッカーなんだ、俺。こうやってあちこちでバイトして金稼ぎながら、世界中を旅して見て回ってるんだ。けっこう面白いぜ!…な、どうかな?」
あまりにも平然とした口調に、ルシフェルはぽかんとしてイーノックを見つめた。しかし、どうやら本気で言っているらしい。こんな適当なことで大丈夫か…?
「そ、それで、お前はいいのか…?」
「え?何が?」
「だって、私がどんな奴か、まだ何もわからないのに…泥棒かも、人殺しかもしれないじゃないか?それなのに、一緒に行くだなんて…信用、出来るのか?その…もしかして、私が…途中で―」
…途中で、私のことを嫌いになって、また、誰かがそうしたように、何処かの路地裏に捨てて行くんじゃないのか…?
ついさっきまで、一人であの路地裏にしゃがみ込んでいた時なら、こんなことは思いもしなかった。でも今は…この笑顔に見つめられて、温かい手のひらを感じて、同じテーブルで声を聞いてしまった今になってみると、そんなことは、とても耐えられそうにない…。
嫌だ…もう二度と、捨てられたくない…。そうなるくらいなら、いっそ、このまま付いて行かない方が―?
「…ぷはっ。面白いなぁ君は!」
「はっ?…ひ、ひとが、真面目に…!」
「だって面白いよ!ルシフェルは記憶が無いんだろう?出会う前のこと、名前以外何にも覚えていないんだろう?」
「ああ、そうだ…それが何か…」
なおもムキになって言い募ろうとするルシフェルの言葉を、イーノックの張りのある声が断ち切った。
「だったらさ。俺と一緒に居る時のルシフェルが”全部”じゃないか!それさえ信じてればいいんだ。簡単だよ!」
大丈夫だ、問題ない!そう言って、あははは、と腹の底から笑い転げているイーノックを、ルシフェルはただただ呆然として見つめていた。
”こいつは本物の馬鹿だ…。”
でも、と思う。
”…どうして、こんなに胸の奥が温かいんだろう?…どうして、目の奥から熱いものが溢れそうになっているんだろうか?どうして…どうして……”
「ああ、もうやめた。馬鹿らしい…」
突然こぼれそうになった涙を隠すように、ルシフェルは薄汚れたカフェの天井に目を向ける。古ぼけて調理油の染みた大きなファンがゆっくりと回って、何匹かの蠅がその周りを飛び回っている。ラジオから現地の歌謡曲を独特の節回しで歌い上げる野太い声が響き、客同士の談笑が時折それに混じる。賑やかな声が厨房の中と、外のバザールから聞こえてくる。
そして、現地風の砂糖をたっぷり入れた甘ったるいコーヒーの匂い…。
思い出したように、イーノックの声がつぶやいた。
「宿に帰る前に、ルシフェルの新しい靴を買わなきゃだな。ごめん、たった今気づいたよ…片方、裸足だったんだね…。あと、着替えと歯ブラシと消毒薬と…」
ルシフェルはそっと微笑んだ。相変わらず視線はくるくる回る天井のファンを見つめている。
「別に、そんなのどうでもいい…」
…どうして、此処は―、”彼”の隣は、こんなにも居心地が良いのだろう?
恋人たち

ルシフェルがイーノックと二人で旅をした期間は一年以上に及んだが、その全ての日々を、ルシフェルはまるでつい昨日のことのように、アルバムから色鮮やかな写真を手に取るように、ハッキリと、思い出せる自信があった。
それと言うのも、ちょうど幼い子供にとっての一日が「永遠」のように長く、満ち足りたものであるのと同じく、出会う以前の記憶を全て無くしていたルシフェルにとっては、そうやってイーノックと世界中の旅の空の下に過した日々こそが、ほとんど「全て」であり、「永遠」にも等しい、何よりも大切な、かけがえのない思い出そのものだったから。
「…イーノック、起きてるか?」
旅先の安ホテルの、一人用の狭苦しいベッドの中で体をくっつけて横になりながら、決まって一晩に一度は、ルシフェルはそう囁いた。応える言葉は無く、規則正しい寝息が聞こえるだけで、しかし、彼は心の底から満足だった。ずっといつまでも、この寝息を聞いていたい…と思った。
二人が「そういう関係」になったのは、旅を始めてから何カ月、何カ国目のことだったろうか。
もちろん、記念すべきその時の、日付や室内のこまごましたことまでルシフェルには思い出せるけれど、そんなことはどうでも良いのだ。隣に眠る彼の「体温」を、彼の全てを、あの時、初めて自分だけのものに出来た…たったそれだけで。
ある夜、寝付けないでじっと天井を見上げていたルシフェルは、隣で妙な気配を感じ…見てしまったのだった。
イーノックが、自分で「して」いるところを。
「あ…?」
「!!!」
思わず声が漏れてしまい、それにビクゥッ?!と相手が過剰に反応するのがわかった。しばし気まずい沈黙…。
「あの、ご、ごめん…!」
最初に謝ったのは、イーノックの方だった。
「…ベッドでは、絶対やめようと思ってたんだけど…ちょっと、今日はなんか、その…もう我慢できなくて…。ほんと、ゴメン…!」
そう言っておずおず顔だけ振り返ったイーノックが、夜目にも真っ赤になっているのがわかって、ルシフェルは心臓がきゅっとなった。
イーノックが自分のために物凄く「我慢」をしてくれているのは、とっくに知っていた。いや、自分がそうさせてしまったのだ。
一度、風呂上がりの裸の肩を不意に触られた時(小さな蜘蛛が乗っていたのを取ろうとしてくれたのだが)、ルシフェルは飛び上るほど驚いて体を強張らせてしまい、逆にイーノックの方が気の毒なくらいに申し訳なさそうな顔になってしまう、そんなことがあった。
それが何かルシフェルの中の「トラウマ」に関わるものなのだろう、と勝手に納得したらしいイーノックは、それ以来、決してルシフェルの素肌には触ろうとしなかった。それどころか、男同士なのに一緒に部屋で着替えることさえ避けようとした。そういう自分への気遣いが、ルシフェルは嬉しくもあったけれど、でも、やはり小さい子供同士のようにはしゃぎながら一緒にシャワーを浴びたり、裸でバルコニーでしゃべったり出来なくなるのは、大好きな相手が遠くなってしまうようで、何だかとても寂しいような気もするのだった。
…そのイーノックがいま、同じベッドの中で、恥ずかしさに消えてしまいたいような顔をして、泣きそうになりながら俯いている。
「苦しそうだ、イーノック…。」
「…えっ?」
「ごめん。私のせいで、もう我慢しないでくれ。…してあげるから。」
ゆっくりと体を起こしながら、ルシフェルは抑えた、けれども熱っぽい声色でハッキリとそう言った。本人も気づかないうちに高まる心臓の鼓動に呼応して集まった血液のせいで、ルシフェルの普段はココア色の瞳が、暗がりにも鮮やかな紅の色に染まっているのがイーノックにはわかった。本人にとっては完全に無意識の、その艶めかしさ…。
「え…。ちょ、な、何言ってるんだ…ルシ、フェ、ル?あ、あの…。」
「大丈夫。どうすればいいか、ちゃんと知ってるから…お前のために、してあげたいんだ…させてくれないか?…駄目か?男だから…」
「そ、そんなこと!…ルシフェルは男だけど、綺麗だよ…本当に。でっ、でもやっぱり無理だ、こんなこと、君に、させるなんて…んっ」
最後まで言わせたくなくて、とっさに唇を重ねた。長く、深いキス。舌を使うと、相手の目がたちまちとろん、となるのがわかった。
「あぁ。ルシフェル…やめてくれ。君を、これ以上、傷つけたくないんだ…記憶を無くす程、つらい思いをして来たのに…。俺は…」
「いいんだ。お前になら私はたぶん、いや絶対に、大丈夫だ、問題ない。…ふふ、これはお前の口癖じゃなかったのか?」
そのままTシャツ一枚のイーノックの胸に、倒れ込むように頬ずりをした。広くて温かくて、そうしていると心底から安心できた。
…ずっと、こうしたかったのは、私の方なんだ…。
「イーノック。お前に、抱いて欲しいんだ…私を。自分でなんて、して欲しくない。そんな寂しいのは、嫌だ。一緒がいい…。」
おずおずと遠慮がちに、太い腕が背中に回るのを感じた。ぎゅうっときつく抱き締められる。思わず甘やかな息が漏れた。
「…お前が何て思うか知らないけど…愛してるんだ。お前の夢も、お前の息も、嬉しいことも苦しいことも全部、一緒に感じたいんだ…だから…これ以上、我慢なんかしないでくれ…私も、お前に心配掛けないで済むように、もっと強くなるから…。う」
今度は、ルシフェルが最後まで言い終わらないうちに、イーノックの唇に遮られた。そのまま互いの腕で首を掻き抱き、髪を撫で、舌を絡ませ合いながら、むさぼるように、確かめ合った。お互いの思いの強さを、抑えこんでいた愛情を。
ルシフェルは微笑みながら、泣いていた。その涙をイーノックの唇が吸い取っては、また深いキスを重ね合った。次第に手が下方に降りて、お互いの体の感じやすい部分をまさぐると、だんだん早くなる呼吸と、衣擦れの音だけが薄暗い夜気の中にかすかに響いた。
目が覚めると、すぐ目の前にイーノックの褐色の顔と穏やかな海緑色の目があった。さっきからずっと、寝顔を眺めていたらしい。
「おはよう!ルシフェル。今日も良い天気だよ。」
「はっ…恥ずかしいな…見てたのか?寝顔…」
思わずシーツで紅くなった目から下の顔を隠す。昨夜のあれこれが急に生々しく思い出されて、顔が熱くなるのが自分でもわかった。
「うん…綺麗だなぁ、って…。ずーっと見てても飽きないよ。」
「馬鹿!よせってば!(汗)」
照れ隠しに殴る真似をすると、相手は笑いながらその手を取った。ちゅ、とわざと音を立てて指先にキスをする。
「君が好きだ。ルシフェル…。俺、ずっとずっと、君のことを大切にするよ。」
「…イーノック…。私だって…で、でも、今は恥ずかしいから嫌だ!ちょっとあっち向いててくれ!」
「あはは。わかったよ!」
涙ぐんでしまったのを朝の光の中では見られたくなくて、ルシフェルは子供のように駄々をこねた。…昨夜の熱い余韻が体の奥にじぃん、と残っていて、このまま一日中ベッドの中で過ごしたい気分だった。そんな恋人のために、イーノックが街の売店で甘いお菓子やフルーツ、透明なプラスチックのカップに入ったカフェオレなんかを買ってきてくれた。
ルシフェルにとっては、人生で本当に初めての、怖いくらいに幸せな瞬間だった。
「…店、持てたらいいな。」
「んっ?」
ベッドに座って、急にぽつりと呟いたルシフェルの言葉に、イーノックはかぶりついていた半月型のスイカからひょいと顔を上げた。まじまじとルシフェルの顔を見ながら、問い返す。
「お店って、君がやるのか?ルシフェル。」
「当たり前だろう。私が持ちたいって言ってるんだから。…何か飲み物とか、軽い食事とかを出すような…そうだ、カフェなんかがいいな。いつも旅先で入るだろ?色んな店があったな…でも、もし私が作るなら、店内は小さくて良いから、味が上等で、内装とか音楽とかにもこだわって、置いてある雑誌とか一つとっても洒落た感じの店を、さ…。」
手に持っていたカフェオレのカップを見るとはなしに覗き込みながら、ルシフェルは楽しそうに、そんな小さな夢を語っている。
その様子をじっと見ていたイーノックが、突然大きな声で叫んだ。
「いいな、それ!!」
「わっ!びっくりした…何だよいきなり…?」
「じゃあ、俺はキミのその店で出す色んな素材を世界中から買ってくるよ!作ろう、カフェ!俺達二人でさ。」
ルシフェルは驚いて、イーノックの顔を見た。海緑色の目がきらきらして、新しい玩具を見つけた大型犬みたいに興奮している。
「ルシフェルは、『フェアトレード』って知ってるかい?」
「えっ…?知らない…何?」
「あのね、『フェアトレード』って言うのは、例えばコーヒー豆とかチョコレートのカカオ豆とか…主に途上国の特産品である色んな素材や原料とかを、その土地の農民から先進国の企業なんかが不当に安く買い叩くのを防ぎつつ、”適正な価格”で独占的に契約を結び、安定した取引をしていこうとする仕組みのことだよ。」
「…取引?…適、正?えっと、ごめん。私には、あんまり良くわからな…」
「俺はさ、ルシフェル。いつか世界中の人を幸せにしたいと思ってるんだよ!!」
唐突にそんなことを言いだしたイーノックに、ルシフェルは、言いかけた言葉が一瞬にして吹っ飛んで、頭の中が真っ白になった。
「何…それ?」
「俺とルシフェルが作るその店を成功させて、そこで扱う商品を『フェアトレード』製品にすれば、いっぺんにたくさんの人を幸せに出来る!な、そう思わないか?」
あまりの話の飛躍っぷりに、ルシフェルはぽかんとしてしまった。…わからない、わからない。「世界」?どこかの、農民?それがどうしたって言うんだ?それと、イーノックと、私とカフェと…何がどう関係あるって言うんだ?わからない、イーノック…もっとよく説明してくれ…。
気がつくと、イーノックがひどく真面目くさった顔をして、こちらをまっすぐに見つめている。
「俺はね、ルシフェル。君に会うまでに、色んな国を見て来た。”自分探し”の旅って言うと、なんか格好悪くてやなんだけど、でも、実際にはそんな感じだった。行く先々の国で、それぞれに貧困や、土地とか水を巡っての争いや、不幸な人達をたくさん見て来たよ。」
「うん…。」
「でね、思ったんだ。いつか俺は、こういう不幸なことが一つも無い世界を作りたい!って。不可能だって、思われるかもしれない、笑われるだろうけど、本気なんだよ。どんなに小さな一歩ずつでもいい、その夢に向かって前に進んで、いつかきっと…―」
ぐっ、と大きな掌が、ルシフェルの細い両肩を掴んだ。頑丈な造りの、太い指の一本一本。温かい、力強い手。
「…いつかきっと、出会ったばかりの頃の君のような、哀しい目をした人が、一人もいなくなるように…って。」
「!…イーノック…。」
ルシフェルはかすれる声でやっと呟いた。知らなかった…そんな風に、思っていてくれたなんて…。
「…哀しいことも、苦しかっただろうことも…君が覚えていない過去も、存在したこと全部、丸ごと、君を愛してるよ…ルシフェル。君に出会えて、俺はやっと”一人前”になれた気がする。二人でひとつってこと。だから俺は、今度は君のために頑張りたいんだ。絶対にカフェ、成功させような。俺達の、目覚めたまま二人一緒に見る”夢”だよ…。」
はらはらと大粒の涙が、柘榴石(ガーネット)の色に染まった瞳から、真っ白い頬の上へと零れ落ちた。
「どうした?ルシフェル…」
「うん。嬉しいんだ…有り難う、イーノック…。私を、お前のその”夢”に一緒に乗せてくれて…飛びたいよ。私も、一緒に…。二人、同じ夢を見られるなんて…なんて素敵なことだろうね?なあイーノック。…有り難う…」
あふれる涙を拭い拭い、懸命に笑おうとするルシフェルを、愛おしくてならない、というように、黙ってイーノックは強く抱きしめた。
「うん。…イーノック…私も、頑張るよ…お前と、一緒に…うん。」
「みんなが集まれる、みんなが幸せになれるカフェを、作ろうな?美味しいコーヒーと、紅茶と、いい音楽と―。」
「うん、うん…。イーノック…愛してる…」
開け放した窓から南国のスコールの後の爽やかな風が吹き込んで、溶け合いそうなほど強く抱き合った二人の金と黒の髪を優しく掻き混ぜて、吹き過ぎて行く。
…今すぐ、このまま時間が止まればいい。心の底から、この瞬間ルシフェルはそう願った。
密約

資金集めするならトーキョーだよ!という、イーノックのそんな一言で二人は日本の、東京に滞在していた。
確かにここには短期でも賃金の良いバイトが多く、二人の夢であるカフェ開店のための資金作りには持って来いではあったが、その分、家賃や物価が異常に高いので、まともに考えたら余り割に合わないのじゃないか…ちょっと、そんな風にも思うルシフェルだった。
最初の頃こそ、イーノックと同じ「肉体労働」系のバイトを探そうとし、それを恋人に全力で止められて、無難に「接客」関係を探したのだが、ルシフェルのエキゾチックな外見と、まだまだ不自由な日本語のせいで、なかなか合う仕事が見つからなかった。(イーノックには不思議な才能があって、どんな国の言葉でも一週間もそこで生活すれば、ほぼ日常で不自由ない程度にマスターしてしまうのだった。)
ルシフェルがようやく見つけたバイトは、夜の…といっても別にいかがわしい方ではなく(恋人に不安な顔をさせたくなかったので)、六本木の裏通りにある、こじんまりした、あまり流行ってなさそうなバーのカウンター係だった。店のオーナーはどう考えても趣味でやっているとしか思えないような、儲ける気があるのか無いのかまるでわからない店で、客と言っても大抵は固定された面子が交代で現れる程度の、比較的「暇な」職場だった。が、給料は悪くなかったので、採用されておいて何だが、ルシフェルには不思議でならかった。
その裏通りに隠れたような小さな店には、いわゆる「お忍び」の人種…芸能人や作家、名の知れた企業のトップなどが一人でひっそりと羽根を伸ばしに来るらしい、ということを、日本育ちではないルシフェルは働き始めてからも結構長い間、知らなかった。
いつものように一人二人しか客のいない店内で、暇つぶしに布巾でグラスを磨きながら、ルシフェルは聞こえないくらいの低い声で無意識に鼻歌を歌っていた。そんな時、決まって頭の中では、イーノックとのたくさんの旅の思い出、二人で歩いた色んな街の風景、目が覚めてベッドから見た窓の形、美味しかった食事や飲み物のことなどが…イーノックの笑顔と分かちがたく結びついたそれらの記憶が、まるでかけっぱなしの映画を観るように鮮やかに蘇って来ては、彼の、一見とりつき難そうな、神秘的な白く美しい顔をほころばせるのだった。
「…ご機嫌だね。」
「!すいません…つい。」
「いいんだよ、続けてくれ。中近東あたりでよく耳にするメロディ・ラインだね、その曲は…」
「あ、わかりますか?」
声を掛けて来た男は最近わりとよく見る顔で、周りの人からはただ「社長」と呼ばれていた。しかし、この店では「先生」とか「会長」、「マエストロ」とかいうのは一種の暗号名みたいなもので、それ以上の素性を探ることは、誰もしなかった。
年の頃は40代後半くらい。いつも地味だが一目で高級品とわかる、品のいい感じの服装や小物でまとめていた。静かな雰囲気だが何処か人好きのする人物で、けしておしゃべりという訳ではないけれども、いつもエスプリの効いた豊富な話題でルシフェルを楽しませてくれたので、バイト中に暇だった彼は、いつしかその人の来店を、少しだけ心待ちにするようになっていたのだった。
「…どう?”資金集め”は捗ってる?」
この人だけには、ルシフェルは彼らの小さな「夢」のことも話していた。いつか何処かの街で自分達の素敵なカフェを開きたい、という…。
「ええまあ。でも、なかなか…二人ともお店ってやったことないんで、どれくらい掛かるのか正直、よくわかってないんですけど。」
でも、二人の夢なんで…と呟いて、はにかむように笑うルシフェルに、ふっと男が目を細めた。
「出してあげてもいいんだけどな、お金…。」
「…え?」
「まあ、ちょっとした個人的なツテでね、君たちの店にピッタリの物件を見つけたんだ。少し直せば、きっとおしゃれなカフェになると思うよ。不動産とか内装業者…そうだ、仕入れやなんかにも顔がきく人を何人か知っているから、紹介してあげてもいい…」
「ほ、本当ですか?!」
ルシフェルは思わず布巾を握りしめたまま、カウンターから身を乗り出した。店内にはその客と、ルシフェルしかいなかった。
「ああ。少しだけ、条件があるけどね…」
「何でもします!言って下さい!」
「…本当に?何でも?」
不意に、男が謎めいた目でルシフェルをじいっと見つめた。
ルシフェルはその時、全く予期していなかったものをその目の中に見出して、瞬間、自分の体が強張るのを感じた。ちりっ…と、記憶を喪失した脳の奥で、忘却に消えかけていた「傷口」が開き、血が流れ出す音を聞いたような気がした…。
「…え…?」
「そうだよ。私は、”お金”を出す代わりに、”君”が欲しいんだ。ルシフェル。」
「そ…そんな…?嘘、でしょう…?そんな、だって…」
「私は、いつだって本気だよ。君はとても美しいから。」
男は視線を外し、自分のグラスから琥珀色の液体を口に含んだ。ゆっくりと味わってから、飲み下す。
「たぶん、君だけが気づいていないだろうけど。ルシフェル。君を目の前にして、”欲しい”と思わない男なんて、いないと思うよ。」
嫌だ、聞きたくない…というように、ルシフェルは白いシャツに前掛けをした自分の両肩を震える手でぎゅっと抱いた。不安と激しい動悸のせいで、普段の穏やかなココア色から、情熱的な柘榴石(ガーネット)の紅に変わった瞳に深い影を落とす漆黒の長い睫毛を伏せ、蒼白になったうすい唇を噛みしめる。
その仕草は本人が全くそう見えるようにと意識していないにも関わらず、言い様のない妖艶さでもって男心を掻き乱し、支配欲を煽り立てるのに、十分過ぎるものだった。自覚が無い、というのが恐ろしいほどの…。
「心配なんだよ、ルシフェル。君をこんなところでこのまま働かせていたら、その内にどんな悪い虫がついてしまうんじゃないか、って…」
わざと冗談めかしてそう言うと、男は、少しだけ笑った。愛するイーノックとは全然違う、けれども、確かにその笑顔は、優しかった。
ルシフェルは許しを乞うような目で、相手を弱々しく見つめた。
「だって、私は…イーノックを…。私には、そんな…」
美しい紅の瞳に、大粒の宝石のような涙が溜まっている。
「そんな…駄目です…出来ない、私には…」
「うん。そうだろうと思っていたよ。いいんだ、気にしないで。済まなかったね…もう二度と、此処には来ないから。」
男は優雅な仕草で立ち上がり、テーブルに代金よりずっと高額なお札、それと小さな紙片を置いて、もう一度、穏やかな笑顔を見せた。
「困ったことがあったら、いつでもこの番号に連絡しなさい。私で力になれることがあれば、相談に乗るよ。」
「あ…」
「じゃ、さようなら。”いとしい人”。」
最後の言葉は、流暢な発音のフランス語だった。
その日を境に店にはパッタリと姿を現さなくなった男が、実は、国内でも指折りの巨大企業グループのオーナーであり、「神(じん)社長」という名前で時折テレビにも取り上げられるような著名な人物だったことをルシフェルが知ったのは、それからしばらく後のことだった。
その夜、大学が近くにあることから安い下宿やワンルームマンションが多い雑然とした界隈の、古びたアパートの一室に帰ってきたルシフェルが見たのは、一枚しかない布団に腹ばいになって、枕の周りに積み上げた参考書類にうずもれるようにして眠りこけているイーノックの姿だった。国をまたいだ貿易や税関等の知識、経営学や会計の本なんかが、ページを開きっぱなしのまま何冊も床に散らばっている。
「あ~あ、こんなにヨダレたらして…。おい、イーノック。起きろ。」
苦笑して、気持ち良さそうな寝息を立てる背中を揺り動かす。昼間の肉体労働で疲れているのだろう、本当はこのまま眠らせてやりたいが、あいにく、そうも行かない。
「起きろって…お風呂屋さん閉まっちゃうぞ。」
「むにゃ…あ、ルシフェルおかえり…あっ!?やばい、今ねてた?俺?」
「うん。グッスリ。…ほら、早く行かないと銭湯が…」
横の目覚まし時計はそろそろ午前1時を指そうとしている。…この家賃月三万の安アパートには、当たり前のように風呂が無かった。
慌てて二人して近所の銭湯に駆け込んだ。この辺りは学生や独身のサラリーマンが多いせいか、店の営業時間などもかなり夜は遅くて、お陰でどうにか間に合った。いつもの常連以外に客はまばらだった。初めてらしい学生っぽい客数人が、脱衣所で服を脱いでいるルシフェルの肌の白さに驚いてチラチラと見ているが、当の二人は急いでいてそれどころではなく、全く気にしなかった。
やっと忙しい入浴を終えて、深夜、人通りの少ないアパートまでの道を、二人並んで歩いて帰った。百円均一ショップで買い揃えたタオルや石けん、二人一緒のシャンプーボトル等を入れたカゴをぶら下げて帰る、この短い静かな道のりが、ルシフェルは何となく好きだった。
空には半分かけた月が出ている。何処かで猫の鳴く声が聞こえた。隣ではイーノックが風呂の中からずっと、今日勉強した貿易関係の知識をなんやかんやと説明しているが、あまり興味は持てなかった。イーノックは大学を出ているので、時々、話の内容が難しい。
…私は、イーノックが知っているようなことを、何にも知らないな…。
そう考えると、寂しい気持ちになった。大好きな人と同じ夢を見ているつもりで、自分には、彼が見ているものの、実は半分も見えてはいないのではないだろうか…?こんな自分でも何か、大事にしてくれる彼の助けになれているのだろうか…?
「…ルシフェル。ちょっと痩せたな…。」
突然、そう言われてルシフェルは驚いて思わず立ち止った。
「え?何?」
「いや、ちょっと痩せたよねって…俺がいない間、ちゃんと食ってるか?」
「も、もちろん…大丈夫だよ。バイトは賄いが出るしね…お前こそ疲れてるんじゃ…」
「ああ、俺のことだったら大丈夫だ、問題ない!最近、ガードマンのおじいさんが残った弁当分けてくれるんだよ。助かるよ、俺大食いだからね!」
そう言ってイーノックはからからと笑った。
「あと、今の現場そんなにきつくないから、もうひとつバイト増やそうかと思うんだ。」
「え?!だ、だって…今でさえ二つ掛け持ちして…そんなに無理したら、体壊すだろ…?」
「んっ?全然平気だよ。俺は頑丈なだけが取り柄だからね!はは。それに…」
―…君と俺の、二人の夢を、一日でも早く叶えたいし。
急に、真面目な表情になって、イーノックがそう言った。ルシフェルは何故だかその目をまともに見られなくて、足元のビニールサンダルに視線を落とす。二人の足音と、時折カゴの中のシャンプー類がかたんかたんと音を立てる以外、都心とは思えないほどに静かだった。
ふと、いつまでこんな生活を続けられるのだろう、と思った。さっき部屋に帰ってきた時の、バイトと勉強に疲れて眠りこんでいるイーノックの背中が浮かんだ。
自分のために…こんなに頑張ってくれているイーノックに、自分は何を返せるのだろうか?しかし、何も…思いつかなかった。
「どうした?ルシフェル、寒いのか…?」
「いや。何でもない…少し、風邪気味なだけだ…でも、大丈夫だよ…」
言い終わらないうちに、イーノックの大きな手に抱き寄せられた。広い胸に、夜風に冷え始めた頬がとん、と当たる。
「ほら。こうすれば、寒くないだろう?」
「…ああ…何か今日の湯船、塩素がきつくなかったか?ちょっと目がしみる…」
「えっ?そうか?」
「いや…。気のせい、かもしれないな…」
体を密着させているせいで時々もつれる足を、何とかしてイーノックの歩調に合わせようと苦心しながら、ルシフェルは、不意にぽろりとこぼれ落ちた涙を、そんな風に誤魔化した。
背丈の低いビルの谷間に隠れながら、傾いた半月が音も無く二人の後を付いてきた。
深夜。真っ暗な部屋の中で、布団から半身を起こしたルシフェルは、黙って傍らのイーノックの寝顔を見つめた。…本人は平気だと言っていたが、少し目の下が痩せて窪んだような気がする。やはり疲れは溜まっているのだろう。多少動いても、目を覚ます様子は無かった。
「…大丈夫だ、問題ない…。私も、ちょっとだけ強くなったからね…お前のお陰で。」
二人で旅を始めた頃を思い出していた。あの頃は、ルシフェルは記憶喪失のせいもあって、とにかく見知らぬ街の、知らない他の人間達が恐ろしくてたまらなくて、イーノックの姿がほんの少し見えないだけで、泣きたいほど不安になっていた。その恐がり方は本当に普通ではなく、人ごみでは迷子にならないように、いつもイーノックが手をつないでくれた程だった。
それが今では、一緒に夢を叶えるための資金集めのバイトのために、一日のほとんどを離れて暮らしても、大丈夫になっていた。物理的に接触していなくても見えないところで、心の中で、ルシフェルは自分が、イーノックと繋がっているのを感じられるようになっていた。
その二人の「絆」は、ちょっとやそっとのことでは、断ち切られるものではない…と信じられるまでに。自分は、強くなれたのだ、と思った。
”そうだ…これは、イーノックのためなんだ…。”
起こさないように、そうっと顔を近づけて頬に軽く口づけると、名残を断ち切るようにしてルシフェルは立ちあがった。そのまま猫みたいに足音を立てず移動し、ドアを開けて部屋の外へ出る。チラチラする蛍光灯の明かりの下に出ると、彼は、着ていた黒ずくめの服のポケットから、バイトのシフトのために契約していたケータイを取り出した。迷いのない指先の動作で、ある番号を呼び出す。
「…はい、私です。…お会いしてもらえますか?…ええ。はい、じゃあ…。」
そう言って電話を切ったルシフェルの顔には、何の表情も浮かんではいなかった。
ビター・スウィート

二人のカフェ開業のために「出資」してくれる人が見つかった、と聞いた時のイーノックの喜びようは大変なものだった。
まるで漫画やアニメのキャラクターのように、夜中だと言うのにアパートの部屋の中央で歓声を上げながらいきなりルシフェルの腰を抱き上げて、そのままその場でぐるぐると回り、畳で滑って二人揃ってひっくり返って階下に住んでいた大家の老人に後でたっぷりと叱られた。それでも、喜びを抑えきれないイーノックの姿に、ルシフェルも胸の奥がじんわり温かくなるのを感じた。あぁ、これで良かったんだ…と思えた。
出店準備もそこそこにイーノックが早速買い付けの旅に出てしまってから、ルシフェルは、社長が個人用として都内の広尾に持っている超高級マンションに招かれ、何日も、時には何週間も続けて滞在した。飛行機が嫌いなイーノックの旅は、主な移動手段が船と鉄道で(旅費を節約する意味もあったが)ひどく時間が掛かるのは明白だったから、一度出掛けたら次はいつ会えるかわからない。その寂しさを自分がやり過ごせるかどうか不安はあったが、実際には、店舗の内装工事の下見や、店に置く家具のデザイン選び、並行して社長が紹介してくれたバリスタから、自家焙煎やエスプレッソマシーンの使い方の特訓、接客の模擬練習など…カフェ開店の色々な準備で毎日は忙しく過ぎた。
「君は、少し変わったね…ルシフェル。」
ベッドの中で、まだシャワーの湿り気が残る短い黒髪を撫でながら、ふと、社長がそう呟いた。漆黒の長い睫毛を物憂げに上げて、ルシフェルが顔をそちらに向ける。
「…だいぶ物腰も洗練されて、何より落ち着きが出てきたし…。大人びて、ますます綺麗になった。」
「やだな…急になに言い出すんです?」
「本当だよ。さて…”秘密が女を綺麗にする”なんて言ったのは何処の国の人間だったかな?」
「だって、私は男じゃないですか…」
「だから驚いているのさ。あれは、女と男どっちにもつかえる言い回しだったのかってね。」
裸のままシーツの中でくすくす笑うルシフェルを、しばらく愛おしそうに眺めてから、社長はベッドサイドの卓から煙草を取り上げ、自分で火をつけた。ゆっくりと紫煙を吐き出し、ちょっとくすり、と笑ってからまた独り言のように言う。
「…イーノック君のやろうとしていることは、ただの愚かな若者の自己満足、偽善だね。」
ルシフェルは俯いたまま、じっと黙ってそれを聞いていた。
「怒ったかい?」
「いえ、そんな…怒るだなんて。社長には、何から何まで助けて頂いて…店のことだけじゃない、日本語とか、世の中のこととか…色々教えてもらって、本当に感謝しきれないくらい、有り難いと思っているんです…。」
この数週間、40代の若さで巨大企業グループを率いる神(じん)社長を間近くで見て来て、その尋常ではないストレスや、関連企業全て含めれば数十万人の人生を背負っている責任の重さを、わずかではあるが垣間見られた。
たまに珍しくスケジュールが空いた時間に、ルシフェルの日本語の勉強に付き合ってくれる時など、英語や仏語、独語、スペイン語等だけでなく、中国語やヒンディー語、さらには彼の生まれ故郷(?)の言語(さすがに方言は微妙に違っていたが)まで流暢に操るこのひとは、きっと世界中の色んな場所の、あらゆる階層の、光も影も沢山のことを見て、知っているのだろう…素直にそう思えた。…だからきっと、このひとが若いイーノックについて言うことも、間違ってはいないのだろう…。
いや。本当は自分だって、わかっているのだ。確かに、イーノックひとりがいくら個人で頑張ったところで「世界中から自分のような不幸な人を無くす」なんてことが、ありうるはずはないことも、頭のどこかでは理解してもいて…。
それでも。ルシフェルは少し、哀しかった。自分をこうやって独り置いたまま、遠くで夢を追っかけている、そんなイーノックを心の底から、愛しているから。
「…煙草、一本もらえます?」
「ああ。…やっぱり、君は変わったよ。ルシフェル。煙草もそうだが、いつも”黒”しか着なくなったね。…それは君の好きな彼への、”贖罪”の気持ちの表れなのかい?」
ルシフェルは体を起こして、もらった煙草を細く長い指に挟んで唇に運ぶと、そのまま首を伸ばして社長の火を分けてもらう。しばらく吸いつけてから、ふーっと細く長く吐き出した。
「よして下さいよ…。元々、”黒”が好きなんです。私に似合うから。」
「ふうむ。確かに、君の肌の白さを一層引き立てるがね…」
社長の真似、と言う訳ではないが、明らかに影響されて吸い始めた煙草。
ルシフェルは酒があまり飲めない。酔うとすぐに顔がひどく火照って、頭がくらくらし、所構わず眠くなってしまうのだった。
…胸の奥にわだかまる、苦いものを、酒でまぎらわして飲み下してしまうことも、忘れ去ることも出来ずに、ただ、黙って耐えるしかない時…人間には、きっと何か「こういうもの」が必要なのだろう…。
”…イーノックがこんな自分を見たら、一体何と言うだろうか…?”
つかの間、それまで茫洋としていたルシフェルのココア色の瞳が、愛する人のことを思い浮かべた瞬間だけ、きらり、と血の色の透ける柘榴石(ガーネット)の輝きを放った。けれど、それは本当に、一瞬のことだった。
待ちわびていたイーノックが初めての買い付けの旅から帰って来た時、とっくに開店を迎えて、今ではそれなりに営業も軌道に乗り始めたかに思える、こじんまりとしたカフェの入り口の前で、ルシフェルは思わず、唖然として立ちつくしてしまった。店のガラス張りの正面に並べて置いた、小さなバラの苗を植えたばかりのプランターに水をやっていたじょうろからぽたぽたと水がアスファルトの上に滴り落ちた。
イーノックが、仕入れの旅先であるアジアの何処かで買い付けた素材と一緒に、連れ帰った小さな一人の「少女」を見てしまったせいだ。
彼とはやや色味の違う、わずかに灰色を帯びた褐色肌に、神秘的な長い銀髪を紫のターバンでまとめた、年の頃10歳ほどのその少女は、目鼻や顎の部品の小さい、愛らしい顔に、何だかひどく大人びた表情を浮かべていたが、人形のように繊細な手はしっかりと、傍らに立つイーノックのシャツの端っこを握りしめていた。
何より驚いたのは、その不思議な灰青色の瞳だった。…その目が余りにも澄んでいて綺麗で、態度も自然だったので、それがどうやら「見えていない」らしいということに、ルシフェルは、店に置いてあった備え付けのスケッチブックを差し出すまで、全く気付かなかった。
「この子はね、ナンナっていうんだよ!紅茶の茶葉の農園近くの街で会ったんだ。搾りたての牛乳を売っていてね…」
しかしその牛が実は”野良水牛”で、飲んだイーノックは直後に食当たりを起こして嘔吐…などという物騒な話を、あっけらかんと笑いながらしているイーノックの日焼けした顔を、半分呆れながらルシフェルは眺めていた。
”それって、もしかして物乞いって言うんじゃ…というか、これから旅に出るたんびに気の毒な子供を連れて帰ってくるつもりか…?”
と、一瞬不安に思ったが、実際にはそれ以降、そんなことは無かったので内心でこっそり安堵したルシフェルだった。
「…ねえ。あなたって、とっても良い匂いがするわ。私、こういうの好きよ。なにか香ばしいお豆みたいのと、バターとお砂糖の甘い匂い。あと…これはタバコ?」
突然、カウンターでルシフェルが出した甘いホットミルクをすすっていたナンナが、目を閉じて歌うようにそう言った。ルシフェルの体に染みついた、焙煎のコーヒー豆と、店で焼いている焼き菓子等の芳香のことらしい。が―…、
「えっ?煙草?」
初耳だな、というようにイーノックが首を傾げる。とっさに、ルシフェルは何食わぬ風を装って会話に割って入っていた。
「…ああ、常連のお客さんで吸う人がいるんだよ。禁煙にしても良かったんだけどね、店…。でも、出来るだけ多くの人に楽しんで欲しいから。」
「へえ~そうかあ。」
飲み終わったカップを片づけている時、イーノックが席を外したタイミングを狙うように、突然、ナンナが椅子の上に膝立ちで背伸びをして、ルシフェルの耳元に小さな唇を寄せた。その仕草は余りにも自然で、本当に見えていないのか?と不思議になる程だ。
「…あのね、さっきはごめんなさい。でも、今度から気をつけるから。タバコのこと…。」
ルシフェルは驚いて、思わずナンナの顔をまじまじと見た。光を知らない灰青色の大きな瞳が、神妙といっていいような表情を浮かべ、じっとルシフェルが居るあたりの虚空を見つめている。
”…ああ、この子には、全部わかるんだ…賢い子だな…。”
お人形のような愛らしい顔に似合わず、なんて大人びた子だろう。そうルシフェルは思った。と同時に、その生い立ちに何処か自分と重なるものを感じて、きゅっと切ないような胸の痛みを覚えた。イーノックがこの子を拾って帰った訳が、少しだけ、分かる気がした。
ルシフェルは優しく、ナンナの銀色の髪をなでてやりながら、見えない彼女を安心させるために、努めて明るい声を出した。
「有り難う、ナンナ。君はとってもいい子だね。…ところで、さっそく今日は君がこれから家で着て眠る用のパジャマを買って帰ろうと思うんだけど、君は何色が好きかな?…女の子だから、やっぱり赤がいい?それともピンク?」
「ほんと?!あのね…私、見えないけどピンクって言葉すごく好きなの!ピンクって、何だか暖かそうじゃない?」
「ふふ。そうだね。じゃあピンクだ。…下はズボンのやつと、裾がお姫様のスカートみたいなやつと、どっちがいいかな…」
「うんとね!それはね…」
そこへ用を済ませたイーノックが戻ってきた。
「あれ?何だか二人ともすっかり仲良しだなあ!安心したよ!」
その嬉しそうな声を聞くと、カウンターを挟んで漆黒と銀の髪が二人、顔を見合わせて同時に、にこっと笑いあった。
その日の夜、ナンナを隣の部屋で寝かせた後(あれからカフェの近くのさすがに二間で風呂(狭い)付のアパートに引っ越していた)で、ようやく落ちついたルシフェルに向かって、急に真面目な顔になってイーノックが問いかけた。
「…どうだった?ルシフェル。俺が旅に出ていた間、何も変わりない?店のこと以外で…」
「無いよ、何も。…元気でやってる。だから、こっちのことは心配するな。」
「そうか…なら良かった。」
いつものように綺麗な歯を見せて笑うイーノックの顔を、どうしても同じように真正面からは見られない自分が、辛かった。無意識に、何かを探すふりをして、社長からの連絡用に持たされていたケータイを、出勤の時に持っていくバッグの一番奥底に押し込んだ。
そんなことは何も知らないイーノックが、熱っぽい目をしてルシフェルの白い頬に、黒髪の短い襟足に、懐かしげに指を触れる。
「…旅してるあいだ、ずっと、君に会いたかったよ…。見せたい景色がいっぱい、いっぱいあったんだ…。」
「イーノック…有り難う。でも、いいんだ。私には店があるし…まだ軌道に乗り始めたばかりだからね。」
「うん…そうだよな。」
「ああ、そうだ。…やっぱり少し、変わったかもしれないな、私!」
急に無理をして朗らかな風を装って、ルシフェルは言った。
「…これからは”店長”だからね、仕入れや会計や…店のことは、全部、最終的に私に責任があるし…しっかりしなきゃいけないからね。そう…多分、変わったと思うよ…な、わかるだろ?」
そんな言葉で、自分が一体何を誤魔化そうとしているのか?ルシフェルには段々、わからなくなっていた。わからないままに、泣きたい、こんな自分は汚い…そういう思いが、頭の中をぐるぐると駆け巡っていた。
「変わってないよ。」
「え…?」
「全然、変わってないよ。何も。出会った頃からずっと同じ、俺の大好きなルシフェルだよ…。」
そう言ってイーノックは、寝間着代わりのシャツとスウェット姿のまま床に座り込んだルシフェルを、優しく、自分の胸に抱き寄せた。Tシャツ一枚を通して、温かさと、イーノックの力強い鼓動が伝わってくる。彼が、そこにいるんだと確かに、感じられる…。
「や、やめろ…イーノック。ナンナが起きる…まだ早…」
「駄目だ。ずっとずっと我慢して来たんだ…夢の中でも、君に触れることばかり考えてたよ…こんな風に…。」
「で、でも…!」
控えめな抵抗を示すそんな言葉とは裏腹に、ルシフェルの瞳には、もう彼の高まる動悸が伝わっていて、それが血の色を透かした情熱的な柘榴石(ガーネット)の輝きできらきらとイーノックの目と理性をたやすく射抜いた。それを見た途端たまらなくなって、顔を赤らめてあたふたともがく恋人の四肢をやや強引に抱きすくめ、いまだに可愛く反抗する、そのうすい唇を、万感の熱を込めた口づけでふさいだ。
とうとう抵抗を諦め、深く長すぎるキスにすっかり息が上がってしまったルシフェルは、武骨で、不器用で、ちっとも洗練されていなくて…でも、他でもないこの自分だけを、何処までも求めてやまない…動物的なまでに素直な性急さで、互いの肌を隔てている衣服を脱がそうとし始めているイーノックの動きが、その無駄に強い力が、涙が出るほど愛しくてならなかった。…心底から、嬉しかった。
こんな頼りない自分のことを、こんなにも、求めてくれるのが…ただ、それだけのことが。
ある時点で突然、ルシフェルは自分の方からイーノックの太い首にしがみつき、熱に浮かされたような声で耳元に囁いた。
「あぁっ…壊れてもいいから、思いっきり、愛してくれ。イーノック…。私が、お前のことを毎晩…声も、熱も、匂いまで全部ハッキリと思い出せるように…。もう何一つ…忘れられなくなるくらいに…」
「ルシフェル…愛してるよ、ルシフェル…俺は、世界中で一番、君のことを…」
「…たくさん、たくさん愛してくれ、イーノック…私を、壊して…」
後は、もう二人とも言葉にならなかった。どちらが、どちらの体に触れて、愛撫して感じさせて、高められているのか判別がつかないくらいに、深く、どこまでも深く、繋がって求めあって、魂の底から、結ばれていたのだから―…。
結局、仕入れの旅から帰って来たイーノックが日本に滞在していたのは、ほんの数日間だった。けれども、ルシフェルはもう、そのことを哀しいとか寂しいとか、思うことはなかった。朝、出発前の一杯のコーヒーを最後の一滴まで飲み干してから、いつものように大きなバックパックを背負って出ていく彼の後ろ姿を、ナンナと二人で手を振りながら、笑って、店の玄関から見送った。
「さて…じゃあメニューボードを店先に出して、始めるとしようか。」
今日も一日の営業が始まる。ルシフェルは晴れ晴れとした思いで、掃除の行き届いた自分の小さな店の中を見まわした。
ガラス張りの正面から明るい陽光が降り注ぐ地上部分は、イーノックのデザイン案。数段の階段を降りて、アンティーク調のラックで仕切られた先の、少し照明を落とした大人っぽい雰囲気の半地下部分は、ルシフェルのデザイン案。カウンター脇の奥側には調理場と焙煎室と物入れ等のスペース。反対の、カウンター入り口側には、地球儀と店のオリジナル・キャラクターが描かれたスケッチブック、壁にはコルクボードに貼られた写真。
まだ数もまばらな、それは、電子機器が苦手なイーノックが仕入れ先の農園などからエアメールとともに送ってきた、写真たちだった。その中で、現地の少数民族などに笑顔で取り囲まれたイーノックが、こちらを見てさも親しげな、健康的な笑みを浮かべている。横の地球儀に刺してある黄色いピンは、今、イーノックが向かっている筈の目的地だった。…放っておくと彼は、行き先も告げずに飛び出して行きそうになったから。
「…大丈夫だ。問題ない…。」
ココア色の目を細めて、不意にそう呟いたルシフェルの顔を、カウンターの隅で粘土遊びをしていたナンナが不思議そうに、見えない目で問いかけるように見上げたが、ルシフェルの普段の空気から心配ないと判断したのか、またおとなしく一人遊びに戻る。
そこへ本日最初の客が、ドアに取り付けた鈴をかららん、と鳴らしながら挨拶とともに機嫌良く入って来た。
「ああ。いらっしゃい。ちょうど昨日、いい豆が入ったんですよ…試してみますか?」
朝の透明な陽光が綺麗に磨き上げられた木目調のカウンターテーブルと、きちんと棚に整頓されたグラスやカップ類、地球儀、そしてルシフェル店長の笑顔を、やわらかく照らし出していた。
S
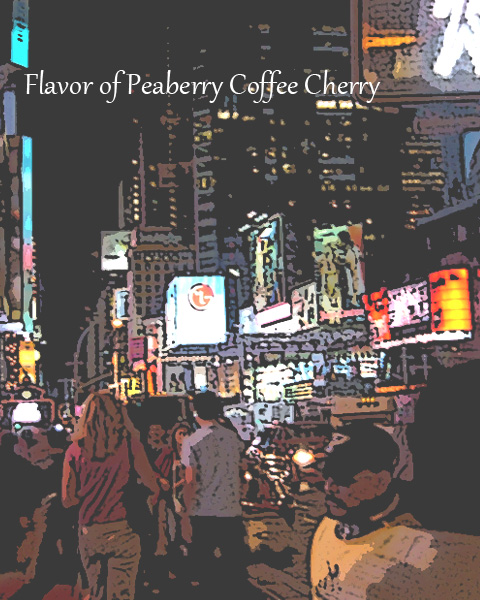
”彼”はずっと苛立っていた。「誰も、自分のことをわかってくれない」からだ。
夜の繁華街ではネオンと電光掲示板が真昼のようにどぎつい明るさで道ゆく人々を照らし、本来ならそろそろ活動時間を終えようとする筈の人間の精神を、逆なでし、奇妙に昂ぶらせる、そんなちょっと刺激的な界隈だった。
”彼”の見た目は、微妙に透ける素材の黒いシャツと、ローライズの黒いジーパン、ツンツンと空を向いて居丈高に立った短い黒髪など…十分に若いと言えるものだったが、しかし、その目付きときたら…端正な顔立ちに似合わず驚くほど鋭く尖っていて、すれ違う者は必ずぎょっと一瞬、振り返って見た。細身の肩を怒らせて、呼吸する息も荒い。
すっきりした首の後ろに回ると、形の良いうなじに、ある不可思議なものが見えた。…わずかにのぞく、黒い”炎”。不可思議と言ったのは…ごく近くに寄ってよくよく見ないとわからないが、それは、蛇の舌のように、ゆらゆらり、と不気味に動くのだ。
”…何故、私を捨てた?”
恨み。憤怒。此処には居ない「誰か」に向けられた、劫火のような荒々しい、激情。
かつての”彼”はいつも、非常に多くの熱烈な「崇拝者」に取り囲まれていた。
誰もが彼の「力」と「地位」を崇め、その姿の完璧な「美しさ」を讃え、何とかして”彼”に気に入られようと媚び諂い、ご機嫌を取ろうと、泣かんばかりに必死だった。その浅ましい様子を”彼”は心底から軽蔑したものだ。それは、彼にとって虚ろな眺めであった。
そんなにも崇め奉りながら…その実、誰一人として、自分らが祭り上げている”彼”の、その「内面」を知ろうともしなかったから。従って”彼”には当然、「友人」などという人間的なものは理解も出来なかったし、そもそも”彼”は完成された存在だったから。
…唯一、”あのひと”をのぞいては。
傲慢で不遜な”彼”にとっては唯一の、この自分を全部、余さず「理解」してくれている…と言い得る、ただ一人の存在。かけがえの無い―…。
”…なのに、堕とされた…。”
まるで、すぐそこで聞こえるように、耳の奥で、此処へ来るまでに「堕ちながら」聴いた、懐かしい声が響く。
「皆に示しがつかないからね。しばらく地上に降りていなさい。お前を呼び戻す時には、ちゃんと合図をするから。」
ふざけないでくれ。私が何をした?何もかも、勝手に自分を担ぎ上げようとした愚か者どものせいだろうが。どうして私が、自らこんなことを望むものか!…こんなにも愛している”君”に、刃向かうなどと…。
「ね~ね~!ちょっとそこの美人さんってば!いじわるしないで話くらいきいてくれよぉ!ね~待ってよ何処行くのぉ?!」
突然、ひどく卑しくて不快な音声に思考を中断される。騒がしい夜の街に似合いの風体の、いかにもナンパな外見をした、顔と言わず体と言わずピアスだらけにした若い男が、小走りになりながら”彼”に付きまとって来た。さっきからの恐ろしい不機嫌の原因の一つだ。
「その黒蛇?みたいなタトゥ(刺青)さ、マジ超かっけーよね!だから~写真撮らせてよ~!ほんの少し脱いでくれるだけでいいから!ね?ね?!」
…”彼”には、自分でしたいということが、これといって何も無かった。だから、これほど気位高くありながら、結果としては全て周囲に決められ、流されるだけ…そのことに気づいているから、余計に苛立つのだ。
ぎろり、と”彼”は路肩の反吐を眺めるのと同じ視線で、蠅よろしく自分の周りを騒ぎ回る、その下賤な人間の雄(オス)を睨みつけた。
”…こんな奴、「力」さえ失っていなければ、たちどころに「塩柱」にしてくれるものを…”
しかし、今の彼には、その煩げな、刺すような視線で男を追い払う程度の力強ささえも、不足していた。全身、とりわけシャツの下の素肌に浮かび上がった黒い蛇…ドス黒く揺れる炎のような…あの不可思議な「文様」に侵された素肌の周囲は、危険な疫病に掛かったように不気味な熱を持ち、それが一瞬ごとに”彼”から体を動かすための力と、精神力を削り取って行くのだった。
ついには不快さに耐えかねて派手な平手打ちをお見舞いしてしまい、怒った男にもの凄い剣幕で追いかけられ、ふりきるために”彼”は角を直角に曲がったすぐの所に建つ、中は薄暗いがちょうどドアの鍵がまだ開いていた、手近な店に飛び込んだ。身を潜めたドアの向こうを、汚い罵声を上げながらどたどたと走り抜けていく様子を伺った。走ったことで余計に荒くなった呼吸がいよいよ危ない感じだった。
「…すいませんねぇ。うちのカフェ、今日はもう閉店なんですよ…」
誰もいないと思って入った建物の奥から、おっとりとしたそんな声が、かがんだ背中に降ってきて、無意識にギクッとなった。
閉店準備中だったルシフェル店長は、突然飛び込んできた闖入者の方を穏やかな笑顔で見…ふと、その顔が曇った。ココア色の瞳をすがめて、咄嗟にそちらへ体を動かしかける。
「おい…どうした君?大丈夫かい…?ふらついてるぞ?」
…うるさい。触れるな、下賤な人間め…誰が貴様らの助けなど…
そう言おうとして、しかし”彼”の体はもう、さっきの全力疾走で限界だった。入口のドアに背中を押しつけるようにして、ずるずると体が滑り落ちる。ぴったりのジーンズに包まれた長い足があらぬ方向へ投げ出され、気位の高い”彼”は、床の上に、気を失って倒れた。
水晶に似た口当たりの薄い器から、冷たい水を唇に含まされて、”彼”は目が覚めた。ほっとしたように頭上から声を掛ける者がいる。
「大丈夫かい?さっき君は、うちの店の玄関のところで急に倒れてしまったんだよ…。凄い熱で…でも、何とか大丈夫みたいだね。」
よかったよかった、と馬鹿正直に安堵したような声で言いながら、前掛けをしたその長身の男はカウンターの中に消えた。しばらくして何か香ばしい匂いとともに戻ってくると、手には薄い磁器の白いカップがあって、黒っぽい液体からほわりと美味しそうな湯気が立っていた。
「目覚ましにどう?飲むと気分がすっきりするよ。…あ、コーヒー、大丈夫かな?」
全く敵意のない相手の親しげな態度にも、”彼”はむすっと黙りこくったまま、何も答えなかった。閉店後の減らした照明の明かりの下で、初めて正面から見た相手の顔に、ルシフェルはある不思議な感覚を抱いた。…何だ?このとても馴染みのある感じは―?しかし、すぐには「それ」に気付かなかった。
…「自分の顔」というのは、案外、人はそれほどハッキリと記憶しないものだ…。
短い髪と同色の漆黒の長い睫毛に縁取られた”彼”の切れ長の目は…その瞳は、ルシフェルが顔に血が上った時に見せる柘榴石(ガーネット)よりも更に鮮やかな…ほとんど燃えている氷を思わせる…完全に不純物の含まれない、純粋な紅玉(ルビー)の硬く鋭い輝きを放っていた。
そして彼らは―双子でもこうまでは行かないだろう、と思うほどに、互いに生き映しの容姿を持っていた。
魅入られたように凝視していたルシフェル店長が、まさかな…というふうに首を振ってから、ふと我に返って壁の時計を見遣る。もう夜も大分遅い時間だった。…この彼は、またいかがわしい街に迷い込んだりしそうで、ちょっと危なっかしいいな…。
「…君、もし行くところが無いんなら、今日は泊まって行くかい?ちょうど私も家は知人にまかせて、今日はこいつの試運転をね…あいつが帰ってくる前に…ふふへ」と、カウンターの隅に移動しながら楽しげに言う。丁度今日、注文していたインテリア用の星球儀が届いたので、ナンナのことは社長の知り合いの親切な老婦人にお願いして、閉めた後の店で一夜の小さなプラネタリウムを試そうと言うのだ。
灯りを完全に消して、恐竜の卵のような形の星球儀の電源スイッチを入れると、途端に周囲の闇に、針の穴のような細かい無数の光が満ちた。生き物のようにある場所では密集し、ある場所は暗黒が帯のように連なり、遠く近くの光の膨大な重なりを一層引き立てていた。
ルシフェルが首を一杯に上向けて、感嘆の吐息とともに呟いている。
「…あいつと見た空に似てるな。アラビア海近くの空は、夜は砂塵も収まって凄く澄んでいてね…思い出すよ。星が多すぎて、星座なんか一つも形がわからないくらいに…」
手で掴めそうに近く、壁や天井だったはずの場所から煌々と自分達を照らす微細な光の束を、両手の中に包むように持ったコーヒーカップからの優しい温もりを感じながら、”彼”は黙ってじっと見つめていた。
「天の上」で見ていた角度に近い―。その記憶が、あるとは思ってもいなかった「感情」を揺さぶる。いつまでも慣れない重い肉体とともに。
”…何故、堕とした?何故、わかってくれなかったんだ…?”
二人を無音で包み込む穏やかな闇の中で、ルシフェルは、この奇妙な客の頬に、一筋の涙が伝っていることに気づいていた。でも言葉は、ついに掛けなかった。ソファと椅子とに腰掛けて、一杯のコーヒーを大事に味わいながら、いつまでも、そうやってただ並んで、作りものの満天の星空を見上げていた。
朝。”彼”は見覚えのない店のソファの上で目覚めた。体にはブランケットが掛けてある。傍らを見ると、昨日「泊まって行け」と言った店の主人らしき若者が、自分はソファではなく、店の正面側の硬い木製の椅子を並べてその上に寝ている。
本来、「睡眠」などというものを必要としない”彼”だったが。しかし、大事を取って休息時間を取ったことはそれなりの効果があったようで、昨夜の全身を襲う激痛と高熱は収まっていた。体の状態はどうにか落ちつき、「力」も戻っているようだ。内からそれを感じる。
「これが、合図…なのか?」
そう言って何も無い虚空を見上げる。昨夜はそこに満天の星(人工の)が映っていたのだ。
次の瞬間、硬度の高いルビーのように冷たかった瞳が、ある「期待」にきらり、と朝の光を反射して、長い睫毛の影を揺らめかせた。
”はやく戻らなければ…彼が、私を呼んでいる…”
せわしい動作で指をならそうとして、ふと、”彼”は眠っている店長のほうを振り返った。規則正しく上下する背中を、しばらく無言で見下ろし…やがて、朝の最初の太陽光線が絵画のように光と陰影を強める店内に、ぱきん、と乾いた音が響きわたった。
店長が目を覚ました時、店には自分一人しかいなかった。
「…やれやれ、助けてやったのに、サヨナラくらい言って行けよ…」
昨夜のあの客の様子から、多分こんなことではないかな、と予想していた通りになって、思わず苦笑しながら床に落ちていたブランケットを拾い上げ、ほこりを払ってから丁寧に畳む。星球儀をカウンターの地球儀の隣にセットすると、機嫌良く鼻歌を歌いながら、また新しい一日の開店準備をする為に、掃除用具を取りだして来て店の正面玄関のドアノブに手を掛けた。
はた、と鼻歌とともに動きが止まる。
「…?」
”彼”が出て行ったであろうはずの…―しかし、ドアの鍵は昨日彼自身が閉めた時と全く同じに、内側から、閉まったままだった。
鏡の窓
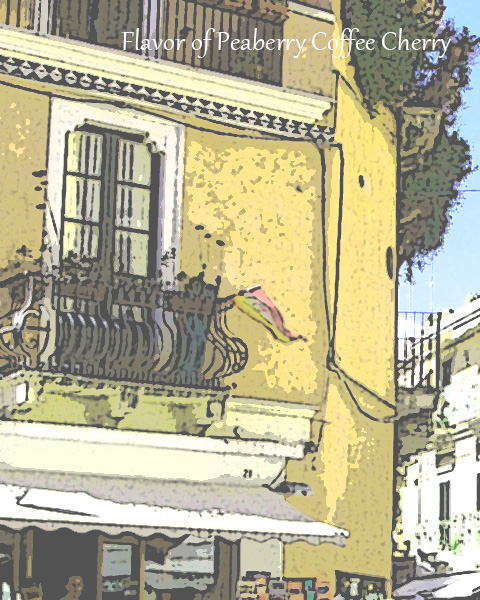
「やあ。いい天気だね」
とある休日の朝。ルシフェル店長がカフェの店先で集客のために考えたタイムサービスのチラシ配りをしていると、何処かで見覚えのある細身の姿が、明るい空気の中、そこだけ黒い影のように近づいて、数歩先で立ち止まった。ココア色の目を細め、にっこり笑って声を掛ける。
「…。」
大体予想した通り、答えはなかった。
それはつい先日、突然店に駆け込んできたかと思うと高熱を出して倒れたところを、ルシフェルが店で介抱してやった、あの”彼”だった。透き通るように色の白い、端正な顔が惜しまれるほどきつい目付きをして、無愛想に黙りこくっている。短い髪と同色の長い睫毛に縁取られた、切れ長の目。その瞳は、硬度の高い純粋な紅玉(ルビー)の色彩。そしてその顔立ちは…―。
明るい場所で改めて見てルシフェルはやっぱり、と思う。まるで鏡を見ているようだ。驚くほど自分と瓜二つな、顔。
でも雰囲気がまるで違う。自分が人にどんな風に見えているかはわからないが、この目の前にいる”彼”ほど、鋭く尖った刃物のように、触れれば切れそうな攻撃的な雰囲気は醸してはいないつもりだ…。それにしても、一体何をそんなに不機嫌なのだろうか?
挨拶した店長には明らかに「故意に」返事をせずに、数日ぶりに何処からかふらりと現れた”彼”はカフェの入り口に向かった。黙って自分でドアを開け、店内に入ってしげしげと見まわす。あたかも、かつて旅で訪れた場所を、「地球を何周もした後で」、またふらり、と訪れたような…そんな、何処か遠くから眺めるような表情だった。
”おや?彼がこの間店に現れた時から、それほど時間はたっていないはずなのに…?”
ふとそんな疑問にかられながらも、しかし実際には至って何食わぬ口調で店長は店内に立ちっぱなしの”彼”へ問いかけた。
「…カウンターあいてるけど。座らないのかい?」
一瞬、躊躇った後で”彼”がそれに従う。その、いかにも尊大に「お前が言うから、仕方なくだぞ」とでも言わんばかりの、知らない所に来て緊張し、却って無闇と威嚇している猫のような態度に、ルシフェル店長は思わず口の中で笑いを堪えるのに必死だった。
「いらっしゃい。また、コーヒーでいいかな?」
「…。(目を合わせずに、落ちつきなく後ろの棚やコーヒーメーカー類を見ている)」
「今日のおすすめの一杯っていうメニューがあってね、私がその日の気分で、気に入った豆を挽いてお出しするんだ…結構、好評でね…」
「…。(差し出された淹れ立てのコーヒーを、しつこいくらいにふぅふぅ吹いて冷ましている)」
「そうそう、知ってるかい?コーヒーに含まれるカフェインには軽い覚醒効果があってね…」
「…。(コーヒーをひとくち啜り、おっ?というような顔をした)」
結局”彼”はこの日、最後までただのひとことも、何も喋らずに、帰った。店長が機嫌よくコーヒーのうんちく話を続けている中、突然ふいっと立ち上がると、そのまま挨拶も何も無くさっさと店を出て行ってしまった。
ずっとカウンターの隅で様子を伺うようにしていたナンナが、一人遊びのねんど板から顔をあげて、素っ頓狂な声を出した。
「ねえ、たいへんよ、ルシフェル。あの人、お金を払ってないわ。」
…わかってはいたのだが。ルシフェル店長はおっとり笑いながら、こう答えるだけだった。
「そうだねぇ…でも、まあいいよ…。」
突然、背中を向けて店を出て行った”彼”の態度が、それが余りにも「自然な動作」だったので、ルシフェルは、きっと”彼”には「自分でお金を払う」と言う概念が無いのだろうと推測をしたのだった。事実、そのくらい”彼”は一種、「やんごとない」とでも言うか…「高貴な」と言ってもいい様な、ちょっと独特の気位の高さをあからさまに周囲に発散していた。恐らくは無意識に。
”あんなツッパってるけど、本当は、きっといい所の育ちなんだろうな…私と違って…”
ルシフェルは素直にそう思っていた。そして、そんな自分と対照的な彼を、不思議と「嫌いではない」のだった。
黒ずくめの細身の足が、それまでコンパスのように直線的だった運びから、急に、微妙にためらいがちな速度に落ちた。
それは「寝ぐら」にしている都内のごくありふれたマンションに帰ってきたから…だということを、”彼”は苦々しく分かってた。…―そこに、自分を待っている「相手」がいると、知っているからだ。
玄関から入ると、ダイニングのテーブルには、茶碗に白米、みそ汁、焼き魚、緑の小鉢、箸…純日本食のつつましい夕飯を用意されていた。
「スーパーでひじきが安かったから。近所の奥さんが教えてくれたんだけど、海藻類は貧血に良いそうだよ…ルシフェル…」
声の主が、キッチンで入れた緑茶を手に持ちながら、振り返った。
褐色の肌と、筋肉質の立派な体躯。肩までの長さのゆるやかにウェーブがかった蜂蜜色のたっぷりと豊かな髪。
「…そんなもの食わないと言ってるだろう?イーノック。」
「うん。…でも、”昔”のあなたとは体も違うのだし、健康に良いから、少しだけでも…」
心から自分を心配している、その俯きがちな表情を見ると”彼”―ルシフェルの、硬質な紅玉(ルビー)の瞳に、ふいに荒々しい攻撃的な光が走った。
カッとなって、テーブルの上のものを全て腕でなぎ払う。派手な大音響とともに皿や茶碗や手をかけた料理が床にぶちまけられる。みそ汁がひっくり返り、白米やおひたしやひじきが、足元にパラパラと落ちてくる。それをわざとらしく靴履きのままで踏みつけ、ぐりぐりと踏みにじる。
「…これでもか?」
昂然と顎を上げて、ひきつった挑発的な笑いを浮かべて見下ろす。さあ、何か言ってみろ。今度こそ私に愛想が尽きただろう…?
床を見て一瞬さっと頬を紅潮させたイーノックは、だが、すぐに哀しそうな潤んだ目で彼を見上げて、たった一言を発した。
「……大丈夫だ、問題ない。また作るから。」
くしゃっ、と辛そうに笑顔を作った。それを見て、逆にダメージを受けたのは、ルシフェルの方だった。
”…ああ、まただ!…いつものこの顔…”
また傷つけてしまった、という胸の疼きと、やり切れなさに、思わず顔をそむけソファにどっかと腰を沈める。そのままの姿勢で天井を仰いでいる彼の背後で、カチャカチャと割れた食器を片づける、隠れるような小さな音が断続的に聞こえている。
やがてその音が止むと、イーノックが静かに身支度を整える気配がした。
「…じゃあ、”仕事”に行ってくるよ。ルシフェル…。もし腹が減ったら、戸棚に昨日買った菓子パンが入れてあるからね…」
ルシフェルが姿勢を変えず、答えも返さずいると、聞こえないくらいに微かな溜息をついた後でイーノックは部屋を出て行った。マンションの廊下を遠ざかって行く靴音を聞こえなくなるまでじっと聴いてから、のろのろと体を起こす。両手で目を覆った。
今日の”探索”の結果、もし”敵”が見つかったらどうなる?自分がサポートについていなければ、きっと彼はまた深く傷を負って、ことによるとそれは彼の「命」に関わるかもしれない…。
苦しむ彼を見るのは辛い。しかし、それでもすぐに後を追いかける気にはなれなかった。
「どうして…わからないんだ…?」
ふと、遠い記憶が蘇る。彼と…イーノックと出会った頃からの、薄れることのない記憶。
天上で、絶対の神に反逆しようとした(彼自身は祭り上げられただけだったが)罪で、一度「堕天」寸前まで行ったルシフェルの側には、もう誰も、近寄って来ようとはしなかった。別に牢獄に繋がれていたのでも何でもなかったが、明らかに皆、すれ違うときには怯えたように彼の硬い紅玉(ルビー)の瞳と、目を合わすのを避けた。かつてはあれほど、彼の歓心を引こうと必死だったくせに。
しかし別に、そのこと自体は、元々それらを軽蔑し抜いていたルシフェルにとってさほど苦痛でもなければ、誇りを傷つけるものでもなかった。むしろ「蠅がいなくなって、周りが静かになっていい」と思うだけだった。
問題は…”子供”の方だった。それも、なんと彼から見れば、賤しい「人間」の子供。
本来なら天上にいるはずのない存在。しかし、逆らう術はなかった。何せ、神がそれを決めたのだから…彼にとっては唯一至高の。
昔の高慢な大天使の彼であれば、恐らく鼻にもひっかけなかっただろう。しかし、もう「神の右手に立つ者」としての地位を剥奪されていた彼は、ぶっちゃけると、神の話し相手をする時以外は、ひどく暇だった。
だから、暇つぶしにその子供を構ってやったのだ。ルシフェルにとっては、全くの気まぐれ…道端の「犬」に、通りすがりに食べ残しを放ってやる、くらいの軽い気持ちだった。
しかし、相手にとっては、それはどうやら違っていたらしい。
子供は…イーノックは、それ以来、馬鹿馬鹿しいほど素直にルシフェルに懐いた。彼を見つければすっ飛んできて大真面目な顔で頭を下げて挨拶し、歩いているのを見ればトコトコと畏まって後ろについて歩き、いかにも適当な彼の話を目玉を真ん丸くして聞いた。…それはまさしく「拾われた犬」そのものの、天上でさえ稀に見るような、純情きわまる「忠実さ」だった。
始めは、単純にそれを面白がっていたルシフェルだったが、徐々に、ある、らしくもない「不安」を覚え始めた。
「自分が”コイツ”の現れるのを、楽しみにしている」のではないか?などと、唐突に気づいてしまったのだ。
そんなことは、あってはならないことだった。堕ちる寸前まで行ったとはいえ、彼は誇り高い「神が最初に創った天使」であり、その美しさと力を崇め、讃えられ、畏れられてきた、誰あろう、大天使ルシフェルなのだー。
けれども、そのちっぽけな人間の少年には、そんなお題目は通用しなかった。彼は何処までも、天上に召し上げられたばかりの、一人ぼっちで寂しかった自分に「声を掛けてくれた、優しいあのお方」として、ルシフェルに心酔しきっていた…盲目的なまでに。
彼のまっすぐすぎる尊敬の眼差しが急に面倒くさくなったルシフェルが、どんなに冷たく扱っても、少年の崇拝は変わらなかった。相変わらず何処へでもついて歩き、黙って罵倒を聞き、冷淡な硬い紅玉(ルビー)の瞳を見上げ続け…ついにはルシフェルが根負けした。彼は少年…イーノックに、自分の「名」を”様”をつけずに呼ぶという破格の栄誉を与えることにしたのだった。それから、その奇妙な「友情」にも似た親しげな関係は、人間としてゆっくり成人していくイーノックとの間で、ずっと続くかに見えた。
…神が、いきなり「あんなこと」を言い付けさえしなければ。
『イーノック、地上に逃れた堕天使たちを捕縛せよ。ルシフェルはそのサポートを。』
それはルシフェルにとって、酷い屈辱だった。自分を全部理解してくれている、自分だけを特別なものとしてくれている…そう思っていたのに。
”君は、コイツをそんなに気に入っているのか―?…だから私に、コイツのサポートをしろなどと?…この大天使の私に!”
その日から、ルシフェルのイーノックに対する態度が、一変した。
…あんなに自分に懐いて、確かに可愛がってもいた「飼い犬」を、もう彼は昔のように自然に、愛することが出来なくなっていた。
静かな部屋に、突然、無味乾燥なケータイの着信音が鳴り響いて、彼のいささか苦い回想を断ち切った。しばらくそのままにして、しかし、いつまでも催促するように鳴り続ける音に諦めたように通話ボタンを押す。
「…何だ。どうせ大した用もないのに…ああ、君に言われなくてもわかっているよ。行くよ…行けばいいんだろう…?」
ケータイを切ったルシフェルは、端正な顔にまるで病を抱えた老人のような、酷く疲れた表情を浮かべていた。
翌日、開店直後に店に現れたルシフェルは、またしても当然のように、挨拶する店長を無視してずかずかと店の中に入り、だんだんと定位置のようになりつつあるカウンター席に鷹揚に座った。
そんな彼の後に続いて店内に入ってきた店長も、無言で手際良く用意した一杯のコーヒーを彼の前のテーブルに置く。
唐突に、つっけんどんな口調で、客の方のルシフェルが言った。
「…昨日、金を払うのを忘れていた。」
あくまでも穏やかな調子で、ルシフェル店長が答える。
「ああ、そのようだね。(知らなかったんじゃないのか…?)」
「何故あの場で言わなかった?」
「いやまあ、こっちが勝手に勧めたようなものだしねぇ…ふへへ」
そんな、何処かこちらのすることを面白がるような店長の顔から、不機嫌に目をそらして、ルシフェルはカウンターの上にポケットから出した小銭をじゃらじゃらと撒いた。
「この中から必要な分だけ取れ。」
それは、イーノックがいつも買い物に行く時に持っていくエコバッグの中にあった財布から、抜き出してきた金だった。天上にはそもそも「金」などというものはなく、「支払い」をするという概念など有しない彼は、一切、そういうものを持ち歩く習慣がなかったので。
「ああ、有り難う、じゃあ遠慮なく頂くよ。ウチの店も楽じゃないんでねぇ…ふっへへ。」
そう一人ごちて店長はにこやかにコーヒー一杯分の小銭を取った。最初の一杯は、サービスだ。
手を洗いながら、さりげなく店長が相手との会話の距離を詰める。
「…ところで、この店ではお客の素性は、話をされない限りは、深く聞かないことにしていてね…もちろん名前もだよ。そこで愛称を使うことになるんだが…君のことを”S”って呼んでもいいかい?」
ルシフェルがあからさまに訝しげな顔を見せる。それなりに人間界で月日を過してきたから、それが何かの”イニシャル”を表すのであろうことは推測出来るが…。
ふと、何かに思い当たったらしく、ルシフェルが白い端正な顔に意地悪そうな笑みをにたり、と浮かべた。
「そうか…あれだな?…おおかた、”サディスト”とかの頭文字だろう?」
店長は動じない。いつものようにおっとりとした笑顔で、しかし、やんわりとその推測を否定する。
「いや、違うよ。”知らんぷり”のSさ…。(くす)」
「…なんだそれは?わからん。馬鹿らしい。」
ぷいっ、と顔をそむけてしまった、そんなSを、店長は面白そうに微笑みつつ、黙って眺めるだけだった。
それから、毎日のようにSは、決まって開店直後の同じ時間帯にルシフェル店長のカフェに現れるようになった。店長は常に同じ調子で機嫌良く彼を迎え、やがてその内に、Sには徐々にわかるようになってきたことがあった。
店長は客の顔を見て二言三言かわしただけで、大体、客がその日にどんな味を欲しがっているのかを的確に当ててしまうのだった。コーヒーか、紅茶か、甘みのある飲み物か?コーヒーなら、豆はどんなブレンドか?スッキリとした酸味の強い一杯で頭を活動的に切り替えたいのか、芳醇なコクと深みのある一杯でゆったりした時間を過ごしたいのか?そんなことを、彼は直接の「言葉」以外の情報から読み取る。
Sの前に出される一杯も、毎回微妙に味わいの配合は違いながら、飲み終わった後には必ず気分が落ち着いて、冷静にこれからの「使命」とか、部屋に残してきた何か言いたげな目のイーノックのこととかを、考えられるようになる自分がいた。それがSには不思議でなからなった。一体、どんなコツがあるんだ?
「え?コツなんて、別に無いよ。…ただ私が、うちの店に来てくれるお客さんみんなを好きで、その人達にとっても興味があるっていうだけのことさ…ふふへ」
…そうやっていつも大人が子供をあしらうみたいな態度をされるのも、気位の高い彼としてはいちいち癪に障るのだが、それでも”この一杯”があるから、つい、また来てしまう。そんな風にして平和に日々が過ぎて行った。
ある日、ナンナが珍しくSに近づいて「手紙」を読んでくれ、と頼んで来た。手には両手で大事そうに一通のエアメールを持っている。その灰青色のつぶらな瞳が、見えてはいない筈なのに願いを込めて見上げている風だった。
「…なんだ。お前、私のことを嫌っていたんじゃないのか?」
「ひどい言い方。嫌ってなんかいないわ。ただ、ちょっと…闇の気配がするなぁって思って、避けてただけ。でも私、文字だけはどうしても読めないのよ…でも、店長は今忙しそうだし…困ってるの。助けてくれない?」
「ふん。そんなに急いで読まなきゃならん程のものなのか?一体、誰からだ?」
「…ほら、あの人からよ。大好きなの!私も、それに店長も…。」
「アイツ(店長)が?」
ちら、と忙しそうにカウンターとキッチンを往復している店長を見遣る。あの飄々とした奴が、「大好き」なんて何だか信じられんな…一体どんな奴が…?そこまで考えて、ふと、ナンナが指さしていた壁のコルクボードに貼られた写真の方に近付いて行く。いつもぶすっとしている顔が、写真コーナーを凝視したまま凍りついた。その異常な様子にやっと一息ついた店長が気づいた。ゆっくりとSが、店長のほうに向き直る。整った白い顔がわずかに青ざめて、硬度の高い紅玉(ルビー)のような瞳が、緊張にぎらついている。写真を顎で示して、
「…こいつは?」
無言のうちに何かを感じ取ったような、互いの視線。
「ああ。うちの仕入れ係で、いま旅に出ていてね…イーノック、って言うんだ。私の…大事な、大事な人だよ…。」
「…イー、ノッ…ク…?」
「そう。イーノック。」
呆然と鸚鵡返しのように呟くSの目を、静まり返ったココア色の目でじっと見据えながら、店長が問うていた。
”…「君」にも、居るんだろう…?そっちの、イーノックが…。”
初めて、二人のルシフェルは、まるで無限に合わせ鏡になった像の一部のように、まじまじと見つめ合っていた。そんな様子に全く気付かない周囲の雑音が、ひどく遠いところから聞こえるような気がしていた。
数日後、偶然にもSは、その「店長のイーノック」を、遠くから目にすることになった。
何故かそれは、彼が最も見たくなかったもの…満面の笑顔を浮かべた、イーノックと同じ顔をした別の男、だった。
大きなバックパックを担いで駅の方角から現れたその大柄な男は…しかし、一番にあっけにとられたのは彼自身というよりも、彼を出迎える、いつもとは全く別人のように興奮して、嬉しそうな店長の様子、だった。
遠目にもわかる、明らかに朱が差している頬。本人は完璧に抑えているつもりで、けれども、心なしか浮き浮きとした仕草。何より意外だったのは、あれほど仕事が三度の飯より好きそうだった彼が…「店長のイーノック」を仕入れの旅先から迎え入れた途端に、そのままシャッターを下ろして店を休んでしまったことだった。それも、何日も!
それからの数日間、毎朝シャッターの閉まったままの店を確認しては回れ右をして帰る、その繰り返しで、最近ではすっかり和みの場になっていたカフェに行けないSの中には、イライラがたまって行った。
そんな何日かが過ぎて。ある夜、寡黙なイーノックと二人きりの部屋に息がつまって散歩に出てきたSは、つい習慣的に、いつものカフェの方へと歩いて来た。そこで閉め切りだった店のシャッターがわずかに開いているのを発見する。お?なんだ居るんじゃないか、と思っていそいそと近づき、ドアのガラス越しに暗い室内を覗き込んだ。
照明を完全に落とした室内からは、いつかのポータブル型プラネタリウムの映し出す人工の星々の無数の光と、囁くような静かなジャズ風のカフェBGM集のメロディが流れ…。
”……!”
突然、Sは息をのんで紅玉(ルビー)色の瞳を驚きに見張った。
見慣れたカウンターと椅子のシルエットの上には、まるで一つにしか見えないくらいに…絡み合う蔓バラと樫の大木のようにぴったりと密着して…抱き合った人影が、うっすらと見てとれた。
…そこにいたのは、Sの全く知らない、店長だった。
カウンターの椅子に腰掛けたイーノックの膝の上にまたがり、自らその首にすがりつくようにして、ひどく艶めかしく腰を動かしている…見たこともない淫らな笑みを浮かべた、”彼”。二人の唇は片時も離れないで、まるで何かを確かめ合うような…いつまでも終わらない曲とともに、終わりのないかと思える愛撫を続けていた。それはイーノックがまた旅に出てしまう前の最後の夜で、ナンナを起こさないようにアパートを抜けだして、とびきり濃厚に、つかの間の別れの名残を惜しんでいたのだった…。
全く思いがけず目にしてしまった光景に、Sは、自分でも理解できないショックを受けていた。足元がふらつく。
店長が、というより…イーノックとあんなにも幸せそうな、自分と同じ容姿の彼の姿が、信じられなかった。
…何故?どうして?「自分のイーノック」は、いつもいつも、あんなにも哀しそうな目をしているのに…。何が違うんだ?何処が、間違っていたんだ?
”どうして私では、アイツを不幸にしてしまうんだ…?私だって…アイツの幼いころのような無邪気な笑顔を、また見たいと思って…なのに、どうして、こんなに違ってしまう?…同じ顔、同じ姿なのに…。”
翌日。雨模様にも関わらず、ルシフェル店長のカフェは、何事もなかったようにシャッターを開けて営業を再開していた。
しかし、ビニ傘を振り回しながらいつもより少し遅めに現れたSは、何やら複雑そうな顔をして、ずっと黙りこくっている。店長も、何かあったな…とは思うが、あえて聞き出すことまではしなかった。
その日のコーヒーは、普段よりも、ちょっとだけ苦みの強い味がした。
破線
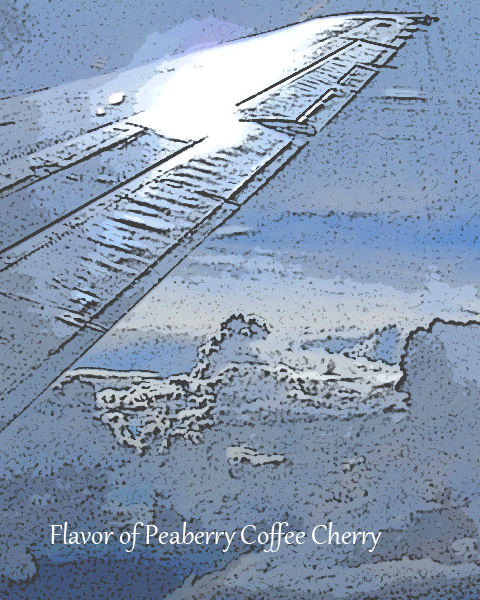
どうしてこうなったのか、わからない。
きっかけはいつものように、本当に些細なことだったのだ。しかし…気づいたら、顔面を鼻血まみれにしたイーノックが股の下であおむけに倒れていて、自分の震える青白い手が、馬乗りになった、自分よりもはるかに立派な体躯の彼の胸倉をつかんで、さらに殴りつけようと拳を振り上げた状態のまま、凍りついていた。
興奮して全身の血液が逆流し、その熱が黒シャツの下の素肌に、また、あの呪われたどす黒い刻印を刻む。
「…ルシフェル…」
切れた唇から鮮やかな血を流しながら、イーノックがどこか寂しげにほほ笑んだ。いきりたつ獣をこれ以上怯えさせないように…とでもいった、ゆっくりした動作で、その大きな掌が自分の小刻みに震える頬に、そっと触れた。
「…大丈夫だ。大丈夫だよ…問題、ない…」
頬に触れた彼の手の温もりが…その泣きべそみたいな笑顔が、鋭く割れたガラス片のように、Sの剥き出しの心にざくり、と突き刺さる。次の瞬間、耐えられなくなったSは鼻血だらけのイーノックを床に放置したまま、弾丸のように部屋を飛び出していた。…靴もはかずに。
遠ざかる背中にイーノックの、ルシフェル、と叫ぶ声が微かに追い掛けてきた。
何も考えられない頭でSは、駆けるような早足で、いつもの黒ずくめの上下に裸足のまま、本能的にあのカフェを目指していた。何故か”彼”になら…あの店長になら、今の自分をわかってもらえると思った。(しかし本当のところは、その前夜にたまたま目撃してしまった、他でもないその店長の、予想もしなかった艶やかな姿のために激しく混乱していたことが大きかったのだが。)
店の近くの街路まで来た時、目の前の路上に停まっていた黒塗りの高級外車の窓がすーっと開き、中から見覚えのない壮年の男の顔が覗いた。
「やあ、丁度良かった。いま玄関まで迎えに行こうと思っていたんだよ。」
思わずSは立ち止まって、親しげに声を掛けてきた相手を真正面から凝視した。
”……?”
「ほら、早く乗りなさい。濡れてしまうから。」
どうも相手は、自分を「誰か」と勘違いしているようだ…とそこまで考え、ふと興味を覚えたので、彼は黙って言われるままに男の隣の席に乗り込んだ。白手袋をした運転手が恭しく開けていた重そうな黒いドアを閉める。
すっかり濡れそぼった雨と、冷たい夜気のお陰で、体の熱はだいぶ引いていた。背中に浮き出たあの不吉な黒い”炎”の文様も、消えているだろうか…。
隣の座席に座った壮年の男は、地上で育ったのではないSの目から見ても、一目で「上流」の人間だと分かる、ぱりっとした仕立ての良いスーツを上品に着こなして、あくまでも落ちついた態度でじっと前を向いている。
「…てっきり私は、”彼”は、もう出発したんだと思っていたけれど。…喧嘩でもしたのかな?その足は…」
男は目ざとくSの裸足の足に気付いていた。が、それ以上深くは訊いて来なかった。ただ、寒いかな?と言って運転手に車内の空調の温度を二度ほど上げるように命じると、あとは膝の上に手を組んで目をつむった。こちらに気を使ったのだろう。
いかにも高級そうな都心の高層マンションの、その中でも最上階のフロア全てを占有する豪華な部屋の中に、車を降りたSは招き入れられた。…まるでそれが「いつものこと」のように、自然な成り行きで。
室内に置かれた家具や調度品類の目を見張るようなセンスの良さ、生活臭が一切感じられないくらいに完璧に手入れの行き届いている様子などを、この地上ではごくごく平凡な2DKのマンション住まいを余儀なくされているSは、ちょっとした感嘆の念と共に見まわした。巨大な一枚のガラス張りの窓の外に広がる、宝石箱をひっくり返したような夜景…これは、まるでここだけ「天上界」のような眺めではないか…。
そこへ、バスルームの方から男がふかふかの清潔なタオルと、湯を張った洗面器を持って現れた。ソファの脇のガラステーブルには既に救急箱がセットしてある。
「さ、髪は自分で拭きなさい。」
タオルをSの頭から肩にふわりと掛け、自分は、ソファにおとなしく腰をおろしている彼の前に、跪くような姿勢を取る。アイロンの効いたワイシャツを腕まくりすると、そのままためらいもなく、裸足でアスファルトの上を歩いたせいで細かい擦り傷だらけになっていたSの白い足を手に取り、洗面器で丁寧に両手でなでるように洗う。ちゃぷちゃぷというお湯の音とともに、少し節くれだった大人の男の長い指が、踵や甲や指の間を順番に触れてゆく感触が、まるで包んで温めてくれるようで、ほんのりと全身が暖まってとても心地がよかった。
…生まれながらの大天使として、もともと誰かに「跪かれること」に超然と慣れていたSだからこそ、気付いたことがあった。いま、目の前に跪いて自分の素足を己の掌で舐めるように洗い清めてくれている、この「手」は―…その実、少しも「へりくだって」などはいない。いや…それどころか、普段は水仕事も汚れ仕事ひとつしてはいなそうな、この滑らかな皮膚の持ち主の、この指先は……
”…むしろこれは、圧倒的に身分が上の者が、己の「所有物」を「愛玩」する時の手つきだ。…何故なら、私はこれと同じ「手」のことを、気が遠くなるほど昔から、良く知っている…。”
男が下を向いたまま、手を止めずに穏やかな口調で言った。
「…彼は…イーノック君は、なかなか舌が肥えているというべきかな…実に品質の良い素材ばかり見つけてくるものだよ。それ自体はいいことなんだがね…ただ、君たちの店の経営規模には、全く見合わないという点さえ、目をつぶれば…の話なんだけれど。」
どこか苦笑するような気配を含んでいた。答える言葉を持たないSは、ただ黙ってそれを聴いている。
「今日、店のほうで足りないと言ってた分を、いつもの口座に入れておいたから。それで仕入れ代金の不足分を払うといい。…ああ、気にしないで。会社の金ではなく私のポケットマネーで、まあ、いわば趣味みたいなものだからね…」
そう言うと、男は顔をあげて屈託なく笑う。黙って俯いているSに、男は何かを誤解したらしかった。
「いや、気にしなくていいって言ってるのに…参ったな。そんな顔をされると、こっちが困ってしまうよ。…そうだ、あれをプレゼントしたら、いつもみたいに笑ってくれるかな?もっと後で見せて喜ばせようと思ってたんだけど…」
つと立ちあがって長い脚で大股に広い部屋の隅に移動すると、クローゼットの中から縦30センチほどの長さの箱を取り出してきた。ふたを開けると、中からはひと眼で最高級に上質なものと知れる、しっとりと照明の光を照り返す美しいデザインの黒い革靴が現れた。シンプルで、シャープでありながらも、細部に遊び心を感じさせる、超一流の職人の手仕事と分かる。
また床に跪いて、男は手ずからそれをSの…ルシフェルの、象牙細工のように繊細な両足に履かせた。ぴったりと肌に吸いつくようにフィットする。当たり前のようにオーダーメイドなのだろうが、無論、Sにはサイズを計られた記憶などない。男はSをその場に立ちあがらせると、数歩後ろに下がり、しげしげ眺めてから満足そうに眼を細める。
「うん。やっぱりこれがいいな…実にエレガントだ。」
しかし、相手は黙って刺すような視線でこちらを睨みつけているだけだ。さすがに男…社長は、首をかしげた。
「…どうかした?そういう気の強そうな顔も、嫌いじゃないけどね…」
言いながら近づくと、優雅な仕草でルシフェルの細い腰を抱き寄せ、顎に指を掛けて顔を間近くで覗き込む。
「…?」
そこで初めて決定的な違和感に気付いた。まっすぐにこちらを睨みつける目はいつもの物憂げなココア色、もしくは柘榴石(ガーネット)ではなく、まるで…燃える紅玉(ルビー)のようだった。
一瞬、次の言葉を失った社長へ、腰を抱き寄せられた姿勢のまま、Sがにやり、と整った顔にわざと歪んだ底意地の悪い笑みを浮かべて見せた。
「…なるほど、そういうことか。」
言い終るか終わらぬうちに、左手で勢いよく指を鳴らす。乾いた音が鳴り響いて、次の瞬間、部屋には社長一人が残されていた。何が起こったのか理解できずに、呆然と周囲を見まわした後、社長はソファに腰をおろして、ため息交じりに指で眉間を押さえた。
「…やれやれ。まさか”幻覚”とは…そんなに疲れていたのかな…?」
閉店準備のためにシャッターを下ろしに出て、ルシフェル店長は、雨まじりの空気を背中に感じながら、入口の横に据え付けられたポストをじっと見つめた。午後に確認した通り、中身はカラだ。決まっている。イーノックはつい昨日、旅立ったばかりなのだから…。それでも、離れてたった一日だというのに、もう彼を恋しがっている自分がいる。
ふと、気配を感じて店内を振り返って、彼はあっ、と驚いた。もう店には自分以外誰もいないことを確認して、閉店準備に出てきたと言うのに…そこに人影を発見したからだ。こちらに背中を向けて立っている。黒ずくめの…
「…Sじゃないか?一体どうしたっていうんだ…」
何処から入ったんだ?と言いそうになるのを抑えて、店長はすっかり慣れ親しんできた相手にそう問いかけた。細い出口の分だけ残して、シャッターを閉め切ると、急いで中に戻る。なんだか様子がおかしいな…と思いながら。
「おい…聞いているのか?S…?」
ゆっくりと振り返ったSの顔に張り付いた表情を見て、店長は軽く息を飲んだ。氷のように冷たい、薄ら笑い。
次の瞬間、ぱきんっ、という乾いた音が薄暗い店内に響き渡ると、さらに驚くべきことが起こった。
「…え…?」
ルシフェル店長は、自分の見ているものがとっさに信じられなかった。一秒間にも満たない時間のあいだに、何故か自分の両手が「縛られて」いたのだ。それも、表の道路を走っている運送用のトラックの荷台を固定するような、幅が2~3センチはありそうな、硬くてごわごわした、ぶっとい粗ロープで。ぎりりとばかりに、きつく。
「な、ん…これ、は…っえ…?…S…?」
ぽかん、とあまりのことに呆けたようになりながら、店長はうわごとみたいに繰り返した。手品を見ているようだ。
そんな取り乱した店長の姿をにたにたと面白そうに眺めながら、Sがもう一度、甲高く指を鳴らした。次の瞬間、今度は体に鈍い衝撃が走る。モーション(動き)の途中を一切省略して、いきなり店長は、床にどさり、と倒れていた。
「ぐっ…あ!」
したたかに腰を強打して、思わず痛みに顔が歪む。全く、何が何だかわからなかった。目の前で意地悪そうな笑いを浮かべているSが関わっていることだけは判るが、それが何を意味するのかが、皆目わからない。
「…っS…一体何が…何故、私にこんなことを…?」
偶然出会ってから今日まで、店長はSから、親しまれてこそいても、ここまで「憎まれている」など思っても見なかったのだが。それは、自分一人の思い違いだったのか…?
「くくっ、いいザマじゃないか?…え?どうだ、床に這いつくばった今の気分は?似合ってるぞ?」
「…純粋に驚いているよ。まさか、君からこんなに嫌われていたなんてね…」
「はっ?馬鹿を言え。お前を”嫌って”などいるものか。誰がいつ、そんな人並みの扱いをしてやった?私はただ、お前を、顔も見たくないと思うほどに”蔑んで”いるだけさ…」
そう傲然と言い放つと、Sは、きつく縛られた店長の手を粗ロープの上から革靴でぎりぎりと踏みつけた。白い手首に血が滲むほどロープが深く食い込んで、たまらず店長がひっと悲鳴を上げる。
「お、おい、いい加減にしてくれないか…!いくらお客さんでも、私だって何でも許せるとは限らな…」
突然、尖った革靴の先端が腹にめり込んで、店長はげふっ、と体を海老のように丸めて激しく噎せ返った。
「喋るな。汚らわしい、この豚めが。よくもこの私を騙してくれたな?」
「…はっ…?(騙す、って…?)」
「チッ、まだしらを切るつもりか…。」
心底から軽蔑しきった目付きで彼を見下ろすと、Sは目を閉じて「誰か」の口真似をする感じで言い放った。
「”…うん、やっぱりこれがいいな。実にエレガントだ。”」
それを聞いた途端に、ルシフェルは全身を電撃に打たれたように硬直させた。ただでさえ白い顔から一気に血の気が引き、唇が蒼白になる。それとは逆に彼の瞳は、不安な激しい動悸に呼応してぎらぎらと血色を透かした柘榴石(ガーネット)の怪しい輝きを放った。震えが止まらない…。
「ふん。覚えがあるようだな…その顔?」
「…S…君は、まさか…”あの人”に会ったのか?そうか…私のふりをして…そうなんだな?」
最初に沸き起こったのは、恐怖。しかし、次に来たのは、鈍い失望だった。…そうか…じゃあ、あの人は、「私」と「彼」の区別が、つかなかったのだ…。
と同時に、自分のひた隠しにしてきた秘密をあっさりと暴いてしまったSへの、いわれのない怒りがこみ上げてくる。どうして、放っておいてくれなかったのだ?私のことなんか何も知らないくせに。その声にならない問いに答えるように、Sが淡々とした口調で言った。
「お前は言ったな?イーノックは私の”大事な人”だと。それは、こういう意味だったのか?」
「…!」
「あいつは…お前のイーノックは、お前が”あんなこと”をして得た金で、自分の旅や、お前の店が成り立っていると言うことを、知っているのか?…知るまいな?これまでは、お前がひた隠しにしているようだからな…しかし、いつまで続けるつもりだ?それが、お前の言う”大事な人”への、うるわしい”愛”とやら、なのか?…ええ?」
執拗に、Sは苦しげな店長をそんな言葉で嬲り続けた。必死に顔をそむけようとする相手に馬乗りになって、頬といわず顎といわずガッと鷲掴むと、無理やり自分の方に振り向けさせる。長い睫毛の影に揺らぐ柘榴石(ガーネット)の瞳にうっすら涙の膜を浮かべて悲痛な無言の抗議を示す、傷だらけの店長と眼が合うと、思わずSは、暗い嗜虐心に背筋がぞくり、とするのを感じた。もっともっと相手を痛めつければ、自分の中の何かが救われるような気がした…。
「何にも、やましいことなんかない様なツラしやがって…この嘘つきめ!」
「…!」
「なあ何故だ?…離れていて、どうして”愛情”が信じられるんだ…?他の男に抱かれて、あいつを裏切って、傷つけてるくせに、どうしてそんなに平気な顔していられるんだ?…ムカつくんだよ!滅茶苦茶にぶっ壊してやりたくなる…その澄ました顔!」
荒っぽい手つきで店長のエプロンをはぎ取り、着ていた黒いシャツを無理やり腰近くまで肌蹴させる。衝撃でボタンが飛んでコロコロと床に転がった。ジーンズのホックに手を掛けながら、声を上げようとする相手の口を、あいている方の手で強引に塞ぐ。噛みつかれたが、何度か平手打ちを喰らわせるうちにぐったりと大人しくなった。
初めこそ必死に抵抗しようとした店長だが、Sに罵倒されてるうちに、だんだんとそのための力が薄れて来るのを感じていた。きつく縄が食い込んだ手からは血の気が引き、噛みしめ過ぎた唇からも、とっくに感覚が無くなっていた。
”…私は、きっとこんな風に、誰かから、きつく叱って欲しかったのかも知れないな…”
哀しさと屈辱とから熱い涙が頬をつたって、と同時に、殴られた時に瞼でも切れたのか、目の前が真っ赤に染まる。
突然、視野が完全にブラックアウトした。
暗闇の中、荒い呼吸音。砂利道と思しき場所を乱れた足音が駆け抜ける、音と、埃、風。
場面が変わる。土壁の汚れた狭い民家のような部屋に、粗末な寝台に臥せった病人がいる。傍らには怯えた顔の老母、その周囲に同じく貧しい身なりの、かなり屈強そうな男たちがいる。一様に驚いた顔をして。
「…おおルシフェル!…なんと呪わしいことか!かわいそうな私の子…どうしてお前は戻ってきてしまったんだい?!」
年老いた父親が―…病気と聞いて、ひと目会いたくて、命がけで逃げ出してまで来た―…その親が、目にいっぱい涙をためながら、自分に向かってそう叫んだ。年の離れた大きな兄たち(そろって満足な仕事がない)が、「やばいぞ!こいつがここに来ていることがバレたら俺達家族は『奴ら』に皆殺しにされる!」「今のうちにどこかに捨ててこい…!」と口々に抑えた声で言い交わしている。
ぼろ雑巾のようになるまで実の兄たちから殴られ蹴られ、ルシフェルは、遠ざかる意識の中で思った。
”…ああ…私がいけないんだ。…帰ってきたりしたから。…私は、汚いから…”
目に入って流れ落ちるのが泥と煤に汚れた血なのか、涙なのか…そのまま気を失った彼には、判別が出来なかった。
「…殺してくれ…」
突然、うわ言のように、Sに組み敷かれたままの店長が呟いた。はた、とSの手が止まる。
「な、に…?」
「…私がいると…皆を不幸にしてしまう…。イーノック…あいつのことだって、きっと…私のせいで…だから…」
長い睫毛に翳る、深みのある柘榴石(ガーネット)の瞳から、とめどなく涙が溢れて汚れた白い頬を濡らしている。あれほど激していた頭が一瞬に醒めて、Sはその眺めに思わず言葉を失った。斃れた彫像のように、美しかった。
「…もう…殺してくれ…私を…。私は…汚い、から……」
「…あ…」
急にぽろぽろとSの目から大粒の涙がこぼれ流れて、虚ろになった店長の目の中に落ちてきた。
「…?」
自分を激しく罵って、痛めつけていたSが…半裸の自分に馬乗りになった姿勢のままで、子供のように泣いていた。店長は、ああ、と思う。…同じ顔で、そっくりな、子供のような泣き顔のままで、ふへっと微笑した。
”…こいつは、まるで昔の私みたいなんだ…ひとりで我慢して、抱え込んで、自分で傷ついて…ちっとも素直じゃなくて……”
縛られて血が滲んでいる手を伸ばし、Sのどす黒い模様が浮いた首筋にそっと触れる。
「…なあ、S。君は、孤独で、可哀相なやつだ。…私と、同じだね…。」
腕を輪っかのようにして、泣きじゃくるSの背中を、優しく抱いてやった。とんとんと幼子をあやすように軽く叩く。
「二人とも…同じさ…。”あいつ”が、いてくれないと、前も後ろも、なーんにも見えないんだ…ふへへ…おかしいね…」
気絶するように眠りに落ちていた店長が、目を覚ました時、とっくに帰ってると思ったSは、店の中にまだいた。痛みにうめきながら体を起こした店長の方を、ちろっ、と見ると、またすぐに目をそらす。少しだけ、ばつが悪そうに見えた。
「…私がのびてる間、誰も来ないように見張っててくれたんだろ?有り難う、S…」
「ばっ、そんなんじゃない!…そうやって何でも自分に都合のいいように受け取るところが、嫌いなんだ!」
「…カウンターのテーブルに座るなんて、行儀が悪いぞ…」
店長はほとんど裸みたいな恰好のまま脱ぎ散らかされた服のポケットを探ると、煙草を取り出して火をつけた。
「ちっ、そんな恰好で恥ずかしくないのか…?」
「…コーヒーでもどうだい?作ろうか。」
「…ふん。勝手にしろ…」
「ああ、勝手にするよ。…でも、うちのコーヒーはちょっと癖になるだろう?心をこめてお作りしてるからねえ。ふふっ…」
むすっとしながらも、出された一杯はふぅふぅしつつ大事そうに飲んでいるSを、店長は目を細めて眺めた。
「ああ…そろそろ夜が明けるねえ…。」
見れば窓ガラスの向こうの群青色の空に、鮮やかな朱が差し始めていた。
…そんなことがありつつ、けれども店長とS、二人の関係は、それ以前と大して変わりはしなかった。相変わらず店にいる時の店長は飄々としていて、三度の飯より仕事が好きで、SはSで、そんな店長の淹れるコーヒーのために毎朝、決まった予定のように開店直後の同じ時間に現れては、ナンナと他愛のないおしゃべりをしたり、時には忙しい店の手伝いをしたり、カップを落としてふてくされたり…そんな風な奇妙に安定した日常が続いて行くかに見えた。
あの日が来るまでは―…。
その朝、Sはいつものように店長のカフェに顔を出すために、すっかり覚えてしまった店内BGMの一曲を鼻歌で歌いつつ歩いていた。ふと、前方から人の声が聞えたようで、見るとカフェの玄関あたりに人垣が出来ている。
「おい?何だ、どうしたっていうんだ…?」
人垣を押しのけて首をつっこんで、目の前の光景に思わずSは絶句した。
金髪の大柄な体が、アスファルトの上にうつぶせに倒れている。その体に取りすがって、力なく揺さぶりながら、呆けたように同じ言葉を、繰り返し、繰り返し叫び続けているのは―…店長だ。
血のような柘榴石(ガーネット)の紅い目を一杯に見開き、短い黒髪を振り乱して…これ以上ないほど蒼白な顔で、絶望と恐怖のあまり涙さえも出ない…そんな虚ろな表情だった。これと同等の喪失感をもし探すとしたら、それは恐らく、母に置き去りにされた幼子以外にはあるまい、とさえ思えるほどの…。
「…私を置いて行くなよ…なあ、イーノック…!頼むから、置いて行かないでくれ…!なあ…死ぬなよおぉぉ!」
周囲の人垣も、ナンナや自分のことさえ、まるで目に入っていないような店長の取り乱したその姿を、Sは自分もまた魅入られたように、立ちつくしたまま凝視し続けるしかなかった。
胸を掴まれるような不安げに曇った鈍色の空から、とうとう堪え切れず大粒の雨が落ちてきた。
ピーベリー・ブレンドを君と
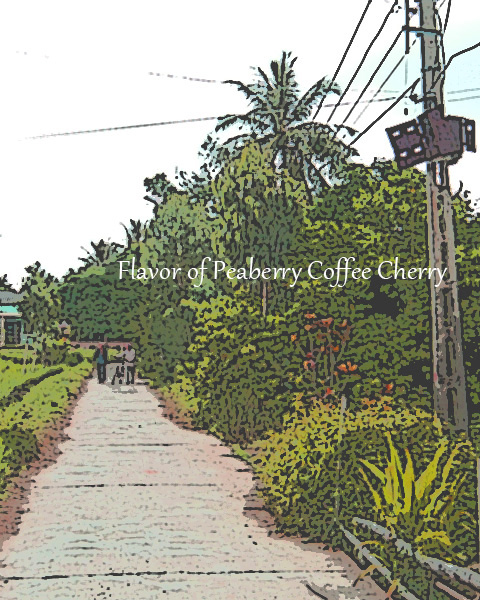
パキンッ。
空気を裂くような甲高い音が響いて、取り乱す店長にSがぴしゃりと言った。
「ばか!落ちつけ!よく見ろ。そいつは死んじゃいない」
「…?」
青ざめ、放心した表情で振り返る店長。イーノックの体に取り縋る手が、かたかたと音も無く震えている。
「でも…でも、こんなに…血が…」
「だから、よく見ろと言うんだ。全部古いし、かすり傷だろうが。倒れてる原因はそれじゃない」
「え…」
Sはいらいらしたように近寄ると、荒っぽく足でイーノックの体をひっくり返した。確かに、息はある。…と同時に、馴染みのある、いささか間の抜けた「音」が響いた。
…ぐ~っ…
「な?胃の中がからっぽなんだよ…。要するに、腹が減って倒れてるんだ、こいつは!」
「腹…からっぽ…って…」
呆然と、店長がおうむ返しに呟いた。へなへなと力が抜けてその場に座り込む。周囲の人垣がな~んだ、とばかりにぞろぞろ散って行った。後には、大の字になったイーノックと、店長とナンナ、それにSだけが残された。
「ほら。状況がわかったら、とっととこの図体でかいのを中に運び込むぞ。お前らも手伝え。一人じゃ絶対無理だからな…」
それが聞こえているのか、いないのか、しかめっ面で目をつむったイーノックが、うぅ~ん…と危機感ない調子で唸った。
「いや~俺、もう死ぬかと思ったよ!ほんとに!」
そんな言葉を自ら真っ向から否定するような底抜けの明るさで、イーノックがあはははと笑った。喋っている間にも、両手に持った店のデザート用に買い置きしてあったバナナをもっくもっくと頬張っている。このスピードだと、じきにひと房食べ終わっているだろう。
「笑いごとじゃないわよ、イーノック!!私達、ほんとに心配したんだから!」
ぷうっと可愛い頬を膨らまして、ナンナが真剣に怒っている。それを見たイーノックが慌ててごめんごめん、と平謝りした。
いつものように仕入れの旅で海外を飛び回っていた彼は、ある国のある町はずれで、いきなり運悪く強盗に遭遇したのだった。…いや、運よく?と言うべきか…強盗は彼の、下着の中に隠していたパスポートと次の渡航地へのチケット以外の荷物を、丸ごと奪って行ってしまったのだ。命だけはとらずに。相手は複数で、当然のように銃を持っていたので、やはり幸運だったと言えるかも知れない。
それで渡航地から経由して、現地の知人から金を借りて、どうにか日本に戻ってくることは出来たのだが、そこで有り金が尽きてしまった。限界ぎりぎりの空腹を抱えたまま、ひたすら都内のこの店の場所を目指して歩き続けて、やっとのことでカフェの玄関まで辿り着いた安心感から、ついに気を失ってしまった…というのが真相だった。(Sは少しだけ時間を戻し、この場面を見ていた)
「…まあでも、とりあえず無事に帰って来られて良かったよ!心配掛けてごめんな!このとーりっ!」
「もう…イーノックって、いつもこんな風なんだから!心配で見ちゃいられないわよ…まるでガキみたいなんだもん。」
「ひどいな~それ…ナンナって結構、辛辣だよな…」
急遽、閉店した店内にはイーノックとルシフェル、ナンナの三人しかいなかった。バナナを平らげて、今度は店の売り物の焼き菓子をぱくつき始めたイーノックが、叱られた犬みたいにショボンとしながら、カップに入ったホットミルクをすすった。
ふと、気配を感じて顔をルシフェルの方に向ける。イーノックが気がつく前から、ソファの脇に人形のように座った形に固まって、食べ物や飲み物を取ってきたりする時だけまるでプログラムされたロボットのような動きでカウンターに入り、また戻ってきていたルシフェルは、今もほとんど同じ姿勢のまま、イーノックの横にいた。見れば全身が細かく震えて、目の焦点も定まらない。
「…ルシフェル…?」
心配そうに覗き込んだイーノックの方に、ぎこちない動きで顔を向ける。まるで死人のような顔色をしていた。思わず、息を呑む。いつもは穏やかなココア色の瞳が、今は血の気が引き過ぎて陰鬱な黒に近い色に見えた。
「ルシフェル…だ、大丈夫か…?」
不安になったイーノックが頬に触れようと手を伸ばすと、それが合図だったかのように、固まっていたルシフェルの体が動いた。寒さに凍えてでもいるように、がたがたと震えながら彼は、浅い呼吸を繰り返していた。赤ん坊がするようにソファの上を這ってイーノックに近付くと、定まらない手つきで、その大きな逞しい体をぺたぺたとくまなく撫で回し、両手で顔を挟んで穴が開くほどその目鼻立ちを眺め回した後に…やがて、ぎゅうううっ…とその太い首周りに、華奢な体全体でしがみついた。
一向に収まらぬ震えが、そのままイーノックの体に伝わってきて、彼は初めて、恋人の怯えようが如何に深刻であるかに思い至った。こんなにも全身で恐怖に震えながら、泣くことさえも出来ない幼子のように、その姿はあまりにも悲痛だった…。
「ルシフェル…ごめん。そんなに、恐い思いをさせてたなんて、俺…ちっとも知らなくて…。ほんとに、ほんとにごめんな…許してくれ、ルシフェル…」
ありったけの思いを込めて強く抱き返すと、初めて、凍りついたようになっていたルシフェルの顔がくしゃりと歪み、蒼白な唇からは、か細いすすり泣きの声が漏れた。次第にその声が大きくなり、ひっ、ひっ、としゃくりあげながらの泣き声になるまでに、それほど時間は掛からなかった。血が止まるほどきつく握りしめた拳で、弱々しくイーノックの肩や背中を時折、駄々っ子のように叩く。そんな恋人をイーノックはただ、黙って抱きしめるしかなかった。
Sは、カフェの玄関の外の壁に寄り掛かって、その店長の切れ切れの泣き声を聴いていた。あの飄々とした店長が…まさかこんな姿を自分やナンナに見せるとは…いや、その自覚も、恐らく無いのだろう…。暗澹とした気持になりかけた時、下の方から服の裾をつんつんとひっぱられるのを感じた。
「ん?何か用か?ナンナ…」
「うん。あのね…ほら、二人があんな感じだから、今日だけ私のこと家まで送って行ってくれない?」
そう言ってちらっと背後の店内を気にする。今は泣き声は小さくなって、イーノックに抱えられるような格好になっている店長の顔は、全く見えなかった。
「…ああ…まあ、仕方ないな…。今日だけだぞ?」
「私だって、闇の気配がするから、いやよ。」
「ちっ…お前、ガキのくせに、ほんとかわいげないな…」
私のイーノックが小さかった頃の方がよっぽど…と言いかけて、危うく呑み込んだ。
店長があの調子では、食事も済ませて置いた方がいいだろう…とSにしては珍しく気をまわして、それから十数分後、二人は帰り道の途中にあるファーストフード店の窓側の席に並んで座っていた。小さな口であむっとチーズバーガーを頬張りながら、ナンナが言う。
「…私、故郷にいた頃ずっと、”死ぬまでに一度でいいからワクドナルドが食べてみたいな”って思ってたの。でも、ここに来て、店長の手作りのご飯を食べるようになってから、なんて自分は馬鹿だったんだろうって思ったわ…。見てよ、このふにゃけたパン!」
「へえ…人間てのは、そんなものを目標に生きられるもんなのか…安上がりだな…。」
皮肉でも何でもなく、Sは単純にそんな感慨を述べた。
「…あのねえ、馬鹿にしてるけどS、アナタだってそうでしょ?店長のコーヒーじゃなきゃ、美味しくないでしょ?」
「ん…確かに。こいつは実に、味も深みも足りんな…というか泥水を飲んでるみたいだ…ああ不味い。」
そう言って100円のコーヒーを口に運ぶと、顔をしかめた。
「店長、ちょっと心配だわ…私も、あんなの初めて見たから。」
「…。」
「私ね、イーノックと店長は、本当は絶対に離れちゃ駄目なんだと思うの。大体、あの二人って”ふたりでひとつ”なのよ…。だから、店長はふだん、すっごく我慢してるはずなのよ…私にはわかるの。だって二人とも大好きなんだもの。つらいわ…」
切なそうに小さくため息をつくナンナを、Sにはどうやって力づけてやるべきか、わからなかった。こんな時、イーノックだったらどう言うだろうか…?同じ人間のあいつなら、きっと…と、そこまで考えて、あとは先が続かなかった。
…よく考えたら、自分はイーノックのことを、どれだけ知っていると言うのだろう…?
隣でナンナが、残り少なくなったバニラ・シェーキをストローですする音が聞こえる。いつもだったら、店長が横から「行儀が悪いぞ」とか言うはずなのだ…しかし、今は…。ふっと、Sの目の中に寂寥感にも似た影がよぎった。記憶の中で、震えながらイーノックに縋り付いて泣いている店長の背中が見えた。消えそうに頼りなくて、小さかった。
”…もう私の居場所は、あすこには…あのカフェには、無いんだな…。”
そう思うと、何だか、天上界から堕とされた時以来、初めて彼は、寄る辺ない、儚いような気持ちを感じていた。
「…ちくしょう、何だこれは…?」
すっかり夜も更けた人気のない休日のビル街をふらつく足取りで歩きながら、Sはガンガン痛む頭を掌で押さえつつ呻いた。空いている方の手には、ついさっきコンビニで買った、蓋を開けられた炭酸果汁入りアルコール飲料の缶。中身は半分ほどカラになっていた。
ナンナをアパートに無事送り届けた後、どうしても辛気臭い自分の部屋にまっすぐ帰る気にはなれなくて、Sは地上に来てから初めて、自分で「酒」というものを買って夜の公園で飲んでみた。しかし、彼自身知らなかったので仕方ないのだが…実のところ彼は、全くの「下戸」だった。…神は、自分を酒飲みには作らなかったらしい…。
初めてのヤケ酒にふらふらになりながら、こみあげる酷い吐き気をこらえつつ、それでもSは、頑なにマンションに帰ろうとはしなかった。…帰りたくなかった。いつも哀しそうに自分を見つめるイーノックと、彼の心尽くしの食卓が、逆に、本当は安らぎに飢えている筈のSの心と、その足を、背負わされる重荷に近い感覚で、家路から遠ざけるのだった。
「ひっく…。人間のやつらは…こ、こんなもの…一体、何処が旨いんだ…?…うっぷ…」
気持ち悪さに堪らなくなって、ビルの隙間のゴミだらけの空間にさっき飲んだばかりの酒を戻してしまった。そのまま壁に火照った体を寄り掛からせて荒い息をつく。頭の中で何十という鐘が鳴っているようで、まともに物が考えられない。
「…あれ~どうかしたのキミ?もしかして、酔っ払っちゃった~…?」
突然、背後から軽薄そうな声が掛けられた。ボーッとした目で振り向いてみると、自分と負けないくらいに酔っぱらっているらしい遊び人風体の人間の雄(オス)が、壁に手をついてへらへらとこちらに笑いかけていた。
「こ~んな美人さんを一人で酔わせておくなんて、世の中おっかしいよなぁ…へへ。なあ、今から俺と遊ばないか?」
舌舐めずりしかねない、いやらしい目付きで男はルシフェルの全身を舐め回すように眺めた。相手が人事不省一歩手前と見るや、たちまち強気になって距離を詰めてくる。乱暴に腕を掴まれるとともに、安い飲み屋のよどんだ空気のような生臭い息がまともに顔にかかって、Sは余計に吐きそうになった。
”…クソッ、こんなやつ、いつもの私だったら…。触るなッ、けがらわしい…!この私を誰だと思って―…”
口応えしようにも、頭も体も全く言うことを聞かずに内心でひどく焦る。本人は刺すような目線で睨んでいるつもりなのだが、酔っているせいか、常には硬くて冷たい紅玉(ルビー)の瞳が、今はまるで哀願でもするように熱っぽく潤んで、そうして上目遣いに見上げる表情が、理性のタガがゆるんだ相手の欲情を、いっそう悪い方へと刺激するらしい。
「あははぁ…たまんねーなぁ…もう…すっげ、いやらしーよ…アンタのその目つき…どんだけ淫乱なのか、今から俺が確かめてやるからな…へ、へへ…こんな綺麗な口してさぁ…なぁ~に咥えたそうな顔してんの…?は、はっ…」
普段から肌蹴ているシャツが災いして、あっと思う間もなく無防備な胸元をすっかり暴かれていた。首筋と言わず、胸と言わず、不埒な熱い吐息混じりの舌にねっとりと蹂躙され、壁に追い詰められて、そのまま強引に覆い被さられる格好になったSの顔の上に、ぼたぼたと男の不潔な涎が糸を引いて落ちてきた。
「…!?」
次の瞬間、Sは驚きに目を見張った。明らかに様子がおかしい。今にも自分を襲おうとしている男は、眼窩から落ちそうになるくらいにガッと大きく血走った目を見開き、苦しげな指先が生き物のように服を掻き毟っている。だらんと開けっぱなしになった口から止め処なく涎を垂らして…突如そこに不気味な緑色の粘液が混じった。その液体は地面に落ちると酸特有のジュッという刺激音を立てて周囲を溶かしながら蒸発した。…当然、人間の血や体液の類ではない。
「…アア…麗シキ、大天使サマ…アナタノ…ソノ、オ美シイ魂ヲ…ドウカ私メニ、喰ラワセテイタダキタイ…」
急激にどす黒い肌色へと変わった腕が、人間にしては信じられない膂力でSの喉元を万力のように締め上げてきた。愕然とする視線の先で、みるみる相手の姿から「ヒト」の面影が消えて行く。現れたのは、禍々しい異形の姿―…。
…しまった…”敵”か…!!!
Sは、いや、大天使ルシフェルは舌打ちして、咄嗟に、酔いのせいで自由にならない己の頭と体を呪った。通常であれば「雑魚」とさえも呼ばないような、低級の”敵”だが…しかし今は―…。指を鳴らそうにもとっくに腕を封じられている。明らかな油断。…らしくもない。後悔したが、それでこの拙い状況がどうなるものでも無かった。獣じみた、粘液まみれの犬歯に、透き通るような白い喉を食い破られそうになる…。
”…私のこの体が壊れても、はたして時間は巻き戻せるものかな…?”
ぼんやりとそんな埒も無いことを考えて、思わずルシフェルは目を閉じた。眼前の醜悪な光景に、耐えられなくて。…瞼の裏にほんの一瞬、すっかり見慣れてしまった、哀しげな海緑色の瞳がよぎった…
突然、頭上から降ってきたバサバサーッという巨大な鳥の羽ばたきのような音と風圧を感じ、ルシフェルは反射的に目を開けた。次の瞬間、自分を穢れた牙に掛けようとしていた人ならぬ異形の敵が、目の前で横一閃された青白い光によって、ズダンッ!と両断された。敵はそのまま恐ろしい叫び声を上げて大気中に雲散霧消する。
「…大丈夫かっ?!」
呆然と見つめるルシフェルの前に、フード付きのアッシュ・ホワイトのロングコート(地上での戦闘用外衣)を身に纏ったイーノックが、褐色の肌に映える蜂蜜色の肩まで長い髪を振り乱して、神の叡智たる刃(アーチ)を構え、冴えた月光を背に、すっくと立っていた。
「あ…」
すぐには問いかけに答えられずに、汚れた壁に背を預けたまま、ルシフェルはぽかん、としてイーノックを見上げた。…何故、お前がここにいるんだ…?いや、私は一体…どうしてここに…任務…あ、そうか。堕天使の…捕縛を…
凄い形相で駆け寄ってきたイーノックが、ルシフェルの体に傷が無いことを確かめるや否や、華奢な体を折れよとばかりに渾身の力でガッシと抱き締めた。突然の圧力にルシフェルの喉がひゅっ、と息の漏れる細い音を立てる。
「ああ、良かった!無事で…ルシフェル…!!」
動きを止めた二人の周囲に、夜のビル街の静けさが舞い降りる。無理やり剥き出しにされてしまったルシフェルの白い胸に、激しく脈打つイーノックの心臓の鼓動がどくっ、どくっ、と響いてきた。その荒々しい拍動が、百万言の言葉よりも遥かに雄弁に、ルシフェルの身を案じてここへ馳せ参じるまでの間のイーノックの不安や恐れを伝えていた。
…どうしても失いたくない、と、”それ”は一拍ごとにルシフェルに伝えていた…。
抱き竦められて、戸惑うように視線をイーノックの金髪の向こうに泳がせていたルシフェルが、ふと手に何か違和感を覚えて目を落とした。自分を抱くイーノックの腰の辺り…ロングコートの布地に、かなり大きな黒い染みがじわりと広がっていた。それの意味を考えるうちに、徐々に、ルシフェルの頭から酔いの靄が駆逐されて行く。…これは血…?
「…イーノック…お前…傷を…?」
虚ろな自分の声が、何処か、ひどく遠い所から聞えた。自分を抱き締めるイーノックの力に変化は無い。うなじに彼の息遣いを感じる。…よくよく考えれば、それは初めから、浅く、苦しげだった…。
「おい…離せ、イーノック…これは、血じゃないか?なら、早く手当を…どうして黙っているんだ?…おい…」
いらいらして、ロングコート越しに手を差し入れて傷と思しきあたりを手探りし…そのままルシフェルは言葉を失った。ぬるぬるとした生温かい感触、その奥に人間の臓器二つ分は優にありそうな大きな「穴」が、ぱっくりと口を開けていた。その虚ろな「穴」…傷と呼ぶにも大き過ぎる傷口から、止めようも無く大量の血液が彼の肉体から失われつつあった。
「こんな、ばかな……おい…イーノック…聞いてる、の…か…?…傷…こんなに、血が……」
「…あなたが無事で良かった。ルシフェル…」
いつもと同じ、静かな口調でイーノックが言った。まるで、戸棚に菓子パンがあるから、と言うような調子で。
「…イー、ノッ、ク…?」
ルシフェルはただ呆然と、同じようなことを口走るだけだった。イーノック。ばか。傷を。血が。…何度も何度も、何度も…。
初めて、抱き絞めていた腕をほどいて、イーノックが正面からルシフェルを見た。
穏やかな海緑色の瞳が、笑っていた。
一体いつぶりだったのか、思い出せないくらい、久しぶりの…ずっとずっと昔、ルシフェルがとても好きだった、惜しみなく降り注ぐ太陽のような、イーノックの、笑顔。
「お前…こんな傷で…私を、助けに来たのか…?いや、これは…私の、せいで…そうなのか…?イーノック…お前は…」
「…大丈夫だ、問題ない。」
「ばっ…大丈夫じゃない!こんなの…大丈夫じゃないだろう…?!どうして黙っ…」
褐色の肌からみるみる健康的な血の色が失われて行く中で、相変わらず、イーノックは笑っていた。この上なく嬉しそうな、幸せそうな様子で…。緊張で一杯に見開かれたルシフェルの紅玉(ルビー)の瞳をまっすぐに見つめると、冷たくなり始めた指先で、そっと頬に触れる。
「大丈夫だ。何度でもあなたが時を戻してくれればいい。私は何度でもあなたを守ろう。」
「そんな…お前…ばかっ!ばかやろうっ!こんな…苦しい目に、どうして…!何のために?!」
ルシフェルの言葉が終わらないうちに、また、ぎゅうっ…とイーノックに抱き締められた。しかし、その力はもう、最初の時ほど強くはなかった。重なりあって立つ二人の足の下には黒々とした大きな血溜まりが出来て、夜の空を鈍く映していた。
「…無事で…良かった…。愛してる…」
「え…?」
その瞬間、急激にガクンッ!と支えきれないような重さがルシフェルの体に一気に圧し掛かってきた。自分を抱えていたイーノックの腕がだらりと体側に垂れ下がり、ルシフェルは、彼の肉体がたった今、「死んだ」ことを知った。
「おい、イーノック…起きろ。イーノック…」
自分の肩口にがっくりと顎を埋めたイーノックの頭部が、その重さ、唇に触れる金色の髪のひんやりした感覚、意思を失った逞しい肉体、腕の中にあるイーノックの全てが、こんなにも愛しいということを、ルシフェルはその時、本当に初めて、思い知った。
唇が号泣のかたちを取ろうとした、まさにその瞬間、周囲の空間にあまりにも場違いな電子音が鳴り響いた。
「…!」
ルシフェルは真っ白になった頭で、数秒間うろうろと視線を彷徨わせた後、刷りこまれた習性的な動きで、イーノックの体重にふらつく体をかろうじて壁にもたれて支えながら、ポケットから携帯を取り出した。
「どういうつもりだ?…こんな時に…」
『…お前こそだよ。ここに来てもまだ気付かないなんて、どうしたもんだろうねぇ。』
のんびりした口調に苛立ちが募る。
「何が言いたい?」
『イーノックだよ。彼が何のためにこれほどの苦しみを自ら進んで受けたのか、知りたいんだろう?』
「…!」
『頼まれたんだよ。旅に出る前、彼に…。”自分が使命を果たしたら、お前を元の地位に戻して欲しい”とね。』
ルシフェルは耳を疑った。…ばかな。イーノックが、自分を元の地位に戻すために?そのためにあんな酷い傷を…?
「う、うそだ…」
『神がうそをつくと思うなんて、お前もずいぶんグレてしまったものだねぇ…(溜息)でも、本当なんだよ。』
さて。話がわかったら、早いところ”彼”の時間を戻してあげなさい。このままでは、何もかも終わってしまうからね―…。そう言って通話は切れた。ルシフェルは通話終了ボタンを押すことも忘れて、ぼんやりと虚空を見つめた。
…イーノックが…私のために…私を、誇り高い以前の地位に戻そうと…それが、私のためになると、信じて…?
不意に、いつの頃からかそれ以外に思い出せなくなってしまった、イーノックの哀しげな眼差しが目の前に蘇った。いつもいつも、”彼”は自分を見つめていた。自分を案じ、ひたすら帰りを待ち、敵から守ろうとし続けた。…大天使として恐れる物など何もなかったルシフェルは、そんな簡単なわかりやすいことに、今まで気づかなかった…。
”彼”は…イーノックは、いつでも自分を、愛し続けていてくれたのだ。
ルシフェルの頬につうっと透明な筋が幾本か流れ、水晶のように月の光を反射した。彼は、自分に全体重を預けたまま、もう動かなくなったイーノックの背中を、愛おしむように手でさすり続けた。声も無く泣きながら、金髪に、褐色の頬に、まぶたに、唇に、順番に口づけた。そこにあるはずの、見えない何かを確かめるように。
「…よし、わかった。じゃあ、帰ろうな…イーノック。…今度こそ、楽しい旅にしよう…」
夜空に向かって、たった一人で哀しく笑う。やがてルシフェルの指先がぱちん、と乾いた音を立て、後には、静かな夜だけが残った。
明るさを絞った蛍光灯に照らし出されるマンションの台所で、ふっと何かの気配を感じたように、イーノックが振り返った。
「あれ…?ルシフェル…いつ帰ってたんだ?気付かなかったよ…」
「うん。さっきな…」
いつになく真剣な顔で、ルシフェルがイーノックを見つめた。慣れていないので、イーノックは何となくどぎまぎしてしまう。
ど、どうしたんだろう…?俺の顔に何かついているのかな…?
「…いい匂いがするな。」
「えっ、あ…これは、ロールキャベツを作ったんだ…あとでルシフェルが、レンジでチンして食べられるように、お皿によそってラップをしておくから…。(今日は珍しいなぁ?)」
慌てて”仕事”の身支度を整えるために、男女兼用のエプロンを外してハンガーにかかったロングコートに手を伸ばしたイーノックに向かって、ルシフェルがやや唐突な口調で言い放った。
「ばかもの。私は大天使だぞ…自分でレンジでチンなんかするか。お前が戻ってから、一緒に食う。だから、必ず無事で戻れ。これは命令だ。…そうしたら、その時は…」
ふと言葉を切って彼は、まだ神以外の誰も見たことが無いような、柔らかな笑みを浮かべると、こう言った。
「…話をしよう。イーノック。」
閉店した後のカフェの奥まったソファ席上に並んだ小窓から、もうずいぶん高くなった真円に近い月の明るい光が、薄暗い空間にそこだけまっすぐな細い線になって差し込んでいる。
「…大丈夫か?ルシフェル…」
大柄な体をソファに仰向きに横たえたイーノックが、その広い胸の上にうつぶせに抱きかかえられた格好のままで、今は静かに眠っているように見える恋人に向かって、そっと声をかけた。
ぱち、とルシフェルが目を開ける。まばたきする長い睫毛にはまだ、さっきまでの涙の跡が残っていた。
「うん…ごめん。イーノック…もう大丈夫…。」
「そんな…どうして謝るんだ?俺は何にも気にしてないよ。人間なんだから、泣きたかったら泣けばいい…」
自分の胸に顔を埋めたルシフェルの後頭部を大きな掌で包み込むように撫でてやりながら、イーノックが天井を見上げて、ぽつりと呟いた。
「あ…。そういえばナンナはちゃんと家に帰れたのかな?気が付いたらいなくなってたけど…後で謝らなきゃ。」
「…ナンナは…たぶん大丈夫だと思う。店によく来る知り合いが、送って行ってくれたはずだから…」
「そうか?じゃあ良かった…。安心したよ…いいお客さんに恵まれてるんだね。」
ルシフェルは、Sのことをイーノックにどうやって説明するべきか、今のうまく働かない頭でなくとも、よく分からなかったので、とりあえず「知り合い」とだけ言っておいた。実際、それは嘘ではないのだし…。
それでもルシフェルは、恋人に対してまた新しく重ねてしまった「秘密」に、今更、チクリと胸が疼くのだった。
「…そうだ!あれをまだ見せてなかったよね?ルシフェル!」
突然、そんな恋人の内心の葛藤を全く知らないイーノックが、明るい声で叫んだ。ルシフェルを胸の上から落とさないように気を使いながら上体を起こし、ソファの座面に座り直させると、つと立って灯りをつけに行った。戻って来ながら、近くの椅子の上から昼間店に帰って来た時、唯一小脇に抱えていた、両手に足りない程の大きさの包みを取り上げる。
「これこれ。強盗に襲われた後、知り合いからやっと借りられたお金で、つい、市場でたまたま見かけたこれを買っちゃったもんだから、本当にすっからかんになっちゃったんだよね…だって、なかなか手に入らないものだしさ!…ほら。見てごらんよ、ルシフェル…」
まだ何処かぼんやりとした表情で、イーノックのすることを目で追っているルシフェルの隣に腰を下ろすと、彼は、そんなことを嬉しそうに喋りながら、がさがさと袋の口を開けた。
次の瞬間、ふわり、とルシフェルにとっては大変に馴染みのある、独特の植物系の香りが空間に漂った。
「これ…は…?」
その香りに、急にはっきりした顔になったルシフェルは、イーノックに促されておずおずと中を覗き込む。袋の中には、焙煎される前の状態のコーヒー豆が一杯に詰まっていた。…しかし何かがいつもと違う。手に取って、あ、という顔になったルシフェルに向かって、嬉しそうにイーノックが頷いた。
「凄いだろ?この中身、100%”ピーベリー(Peaberry Coffee)”の豆なんだよ。一本の木に生る数自体が少ないし、全部”手選別”しなきゃだから、どうしても値が張るんだよね…小粒だけど綺麗なまん丸い実だろう?」
コーヒー豆の種類で、「ピーベリー(Peaberry Coffee)」といえば、一つの殻の中に、普通は半月型に割れて二個入っているはずの種子が、様々な事情からたった一個の実だけが残って成長した、一種の植物における”畸形”の状態である。その豆は通常のものよりやや小ぶりではあるが、焙煎の時に全体にバランスよく火が回るので、すっきりと深みのある味わいに仕上がると一般的に考えられていた。
「よく、こんなに…初めて見た…」
「そうだろ?君にどうしても見せたかったんだ…ルシフェル。これで、また美味しいコーヒーを淹れてくれよ!」
そう言ってまた、ぱあっと太陽のような曇りのない笑顔を見せるイーノックを、ルシフェルは眩しいような、何処か心が痛い様な…そんな微妙に複雑な思いで見つめ返した。けれども、相手をこれ以上心配させたくなくて、泣き笑いみたいな表情を腫れぼったい瞼にやっとのことで浮かべて見せる。ふへっ…と小さく声を立てた。
それは自らへの失笑だった。言葉には決して出さずに彼は、自分を永遠の牢獄に繋ぎたいと思うほど、責めていた。
…こんなに、ひたむきに自分のことを想ってくれている”彼”を、どうして私は、裏切ったりなど出来たのだろう…?
翌日、まだ外が暗いうちにルシフェルはナンナを起こすと、簡単な朝食を済ませてから、身支度をさせた。隣の部屋の布団では、過酷な旅から帰ったばかりで疲れきっているイーノックが、まだ深い眠りの中にいるはずだった。
ルシフェルがほとんど言葉を発しないのを、はじめのうちナンナは、彼が疲れたイーノックを起こさないために気遣っているのだろうと思っていた。
しかし、自分の手を引いてアパートを出、カフェに向かって歩くルシフェルのもう片方の手に、いつものバッグとは形の違う荷物…小さめのキャスターのようなものがあり、さらには、彼の身に付けた服が、徒歩で行ける距離にある店へ出勤する時には着るはずもない、えらく裾の長いコートのようなものであることが手触りからわかって、勘のいい盲目の少女は、なんとなく奇妙な胸騒ぎを覚えるのだった。
店についてからも、おかしいことが続いた。シャッターは半分しか開けられず、日課の掃き掃除も水撒きも、鼻歌ひとつなく淡々と手早く済まされた。こんなことは初めてだった。何より、いつまで経っても「メニュー表」を外に出す気配がない。さすがに様子がおかしいのに気付いて、ナンナが心配そうな声でルシフェルに尋ねる。
「ねえ…ルシフェル、どうしたの?何かおかしいわ…」
「…。」
答えが無いことで、ますます大きくなった不安に押しつぶされそうになりながら、ナンナが喘ぐように言った。
「…ルシフェル…何処かへ行っちゃうの…?」
ふっ、と短く息を吐いた後、ルシフェルは優しく微笑んでナンナの銀色の髪を、愛おしそうに撫でた。
「ごめんねナンナ…でも仕方が無いんだよ。哀しいけど私には、あの人の側にいる資格が無いから。…君は賢い子だから、わかってくれるよね…。開店時間になったら、いつものおばさんに君を迎えに来てもらうようお願いしてあるから。…イーノックのことを頼んだよ…。」
話の途中から、愛らしい顔をみるみる曇らせて、ナンナがとうとう泣き出す。
「駄目よ…そんなの駄目!…イーノックきっとすごく悲しむわ…ねえったら、ルシフェル…」
見えない目を見張って、ルシフェルがいるあたりに向かって虚しく両手を伸ばす。…しかし応える手は無かった。
「ルシフェル…ひとりでなんて、絶対行っちゃ駄目!…お願いだから、ルシフェル…!!」
黒鷺のようにシャープな細身のシルエットのトレンチコートの襟を立てて、ルシフェルは背中に追い縋ってくるナンナのか細い声を、ぴしゃりとガラス製のドアで遮った。きつく噛みしめた唇からは血が滲んでいる。そのまま長い脚で歩き出すと、一度も振り返ること無く、昨日イーノックが帰って来た駅の方角に続くまだ人影もまばらな道に消えて行った。
開店前のカフェのがらんとした店内にナンナのすすり泣く声だけが響く。
「ねえ…どうしてこんな時にまで鈍感なの?イーノック…どうして気が付いてくれないの…?ルシフェル、泣いてたのよ…ねえったら、早く来て…イーノック……」
開店時間にはまだ大分早い時刻に、突然、ガタガタと表のシャッターが騒々しく鳴った。
「…完全に閉まっているか、開いているかならわかるが。”半開き”とは一体どういう意味だ?」
ぶつぶつとそんなことを言いながら、しかし、全く気にする様子も無く店内に入ってきたのは、Sだった。薄暗い店内を見回し、ふと、しゃがみ込んで泣いているナンナを見つけ、眉をひそめた。
「どうした、ナンナ?何故泣いている?…”奴”は、いないのか…?」
Sが今日ここに来たのは、一応、世話になった都合上、きちんと「別れ」の挨拶をしておくつもりだった。それなのに、肝心の相手が忽然と消え失せているとは…?
泣いていたナンナが顔を上げて、お人形のように繊細な作りの手でSに縋りつく。光を知らない灰青色の大きな瞳があふれる涙で曇って、小さな肺を押しつぶされそうな不安に喘がせている。
「ああ、S…!お願い助けて…!ルシフェルが…店長が…何処か、遠くへ行っちゃう…!」
それを聞いて、Sには瞬間的に思い当たる節があった。…確か「あの夜」に、店長が言っていた言葉…。
”…S。…君は、孤独で、かわいそうなやつだ…。私と、同じだね…”
思わず舌打ちした。「店長のイーノック」がいるくせに、どうしてあんな言葉を口にしたのか?…それは何処かで、彼が、決して自分の犯した”裏切り”を「許せない」のだ、ということを意味しているように、今では思えた。
さてはあいつ、何か傍迷惑なことを思いつきやがったな…。残される奴らのことを、考えているのか?しかし今は罵倒するのは後回しだ…とりあえず奴の行き足を止めないと。そこまで考え、ナンナの前も気にせず咄嗟に指を鳴らそうとする。…が、ふとそこで止まった。
「いや…そうじゃない。これじゃあ、駄目なんだ…。」
このままの状態を維持して、いくら「時」だけを巻き戻しても、何も解決しない。…そうだ、いま「答え」を持っているのは、此処にいない、あの”彼”だけだ―…。
と、同時に、しかし…と思う。果たして可能だろうか?神の名の下に「時」を操る大天使である自分には、行使し得る力について幾つかの制限がある。例えば、「時間」を操作しても、その時代が辿り着く筈だった最終的な「未来」の姿までも変えることは出来ない、とか。
ましてや、自分は一度は堕天寸前まで行った身だ…。今考えている「これ」を実行することによって、どんな予想だにしないペナルティを新たに課せられるか、わかったものではない。本格的な堕天か、或いは、天使としての「死」すらも…。有り得ない話ではないのだ。が、一番考えられるのは、恐らく、二度と同じ時代に立ち入れなくなることだろう。それが自分達の「使命」に、どんなマイナスに働くのか、今はまだ計りようもない。
ようやく、初めて心を通わせられた…かも知れない…と思えた、優しい海緑色の眼差しを思う。すると、不思議と何も怖いものなどは無くなる。心は、凪いだ海のように穏やかだった。それもこれも、この時代の、この場所で、あの店長に出会えたからこそ、なのだ。
”…ふん。馬鹿め…この私を誰だと思っている?神の右手に立つ者、大天使ルシフェルだぞ…?その大天使に対して、無礼にも、挨拶も無しに去ろうなどと…。
「まぁいいさ。どうせ、我々はこの世界では”異邦人”だ。…それに、大事なものは、もう見つけ出した。」
そう言ってSは、ちょっとだけ皮肉な、悪戯っぽい笑みを片頬に浮かべた。
「…だが、”お前たち”は、そうじゃないだろう…?なあ、ルシフェル……」
薄暗いカフェの天井にパキン、と乾いた音が響いた。
イーノックは布団の上に座って、ぼんやりと目をこすった。自分はまだ夢を見ているのか?と思った。
「?…ルシフェル………じゃない…?」
「…ほう。”初見”でも見間違えないとは、流石、とでも言うべきなのかな?ここは…」
畳の上に堂々と革靴履きで、高飛車な口調で見下ろしながら、ルシフェルと同じ顔をした誰かは、そう言い放った。
寝起きのハッキリしない頭で、イーノックは一生懸命に考えていた。この人は、誰なんだろう…?ルシフェルに凄く似ているけど、でも、確かにルシフェルじゃない…違う人だ。…じゃあ、俺のルシフェルは、いま何処に…?
「一度しか言わないからな、よく聞け。今からお前の体を、”心の底から探し求めている相手”の元に送ってやる。精々、強く心に念じることだ…。想いが足り無ければ、何処にも辿り着けずに永遠に時空を彷徨うことになるだろう。」
「えっ…ちょっと待って…それは、どういう意味…えっ??」
「用意はいいか?では、ちっぽけな人間なりに、健闘するがいい。…大天使の祝福を…」
「はっ?え、あの…待っ…!」
黒ずくめの「ルシフェルに似た男」がゆっくりと顔の横に左手を差し上げ…指を鳴らした。パキンッ、という甲高い音とともに、生活感のあるアパートの一室から、瞬時にして寝間着姿のイーノックの姿が掻き消えた。
空港のロビーの一角にあるカフェの席で、ルシフェルは溜息をついてペンを置いた。卓の上には、白紙のまま一行も書進んでいない便箋と、一口飲んだままそれっきり放置されているコーヒーのカップがあった。
「…まだ無理か…やっぱり向こうに着いてから書いて出そう…。」
そんな独り言を呟いて、ルシフェルは売店で買ったばかりのエアメールをバッグに仕舞った。一通は社長宛てに、カフェのマスターキーを入れて。もう一通は、イーノックに宛てに…ここから出そうと思ったのだが。30分近く粘っても、何も、気の利いた言い訳ひとつ、書けなかった。そんな自分をルシフェルは情けなく思った。
ふと、締めようとした機内持ち込み用のバッグの底に、店を出てくる時に、咄嗟に掴んできた数センチにもなる分厚い紙束を見つけた。思わず手にとってしげしげと眺める。…それは、イーノックが世界を旅している間に、寂しい夜ごとに遠くの彼を思って書いた、切手も貼られず、送り先も不明の、出すあてさえもないエアメールの束だった。
”…これも、捨てようと思って、結局ここまで持って来ちゃったな…”
イーノックから送られて来た方は包みを分けてあって、そちらは大分、手紙の束が薄かった。彼から送られてくるエアメールの中身は、大体が走り書きの便箋一枚とか、絵ハガキくらいで、正直あまり筆まめなほうとは言えなかった。けれどもその絵ハガキ一枚、スナップ写真一枚が、自分にとってはどれほど大切な「宝物」であったことか…。
”ああ、いけない…未練だなぁ…。”
ルシフェルは寂しく微苦笑すると、そっと紙束を元通りバッグに仕舞いこんだ。搭乗便を知らせるアナウンスが聞こえ、立ち上がるとほとんど飲まないままのコーヒーを片づけた。…せっかくそこそこの豆を使ってるのに、焙煎が下手で焦げ臭い。やっぱり自分で淹れた方が断然、美味しい…こんなところも職業病かな…と、内心で自嘲気味にぼやく。
搭乗ゲートに向かって歩きながら、ルシフェルは通り過ぎた待合フロアの壁際に大きなゴミ箱を見かけ、”…やっぱりアレは捨てて行こう…”と改めて決意した。バッグのファスナーを開け、消印のない分厚い方の紙束を掴むと、今しがた通り過ぎた場所に向かってくるり、と体ごと振り向いた。
「…!?」
瞬間、ルシフェルは我が目と、自分の理性を疑った。気付かないまま、とっくに狂っていたのか?と思った。
まるで電流に打たれたかのように、反射的にその場に立ち竦んだルシフェルの視線の先―…、ほんの数メートルの所に、さっきまでは無かった、否、そもそもここに存在するはずのない人影があった。大柄で筋肉質で、褐色の肌…。
「イ、イーノッ、ク…何故、ここに…?」
天井まである大きなガラス張りの窓の外には、駐機中の旅客機が翼を休めている。その光景をぼんやりと眺めていた海緑色の瞳が、ゆっくりと、見慣れた蜂蜜色の肩まで長い髪を揺らしながら、こちらを振り向いた。
「…ルシフェル…?君は…本当に、ルシフェルなのか…?」
イーノックは明らかに寝起きとわかる、くたびれた白いTシャツにジャージ姿で、とどめに足は、裸足だった。ほんの数メートルを挟んで、声を忘れたように向かい合う二人を、出張に向かうビジネスマンや旅行者が一様に不審げな顔付きで、じろじろと横目に通り過ぎて行った。周囲の雑踏が今は、ひどく遠く感じる…。
「ルシフェル…その格好…それに、その荷物…どうしたの?一体、何処へ行くんだ?…俺に、黙って…?」
「…。」
「外の…ここって、空港、だよね…?なあ、ルシフェル…俺、まだ夢を見てるのかな…?」
イーノックは、まだ目の前の事態が信じられないとでも言うように、呆然と呟いている。
「部屋で寝ていたら、突然、君にそっくりな、でも違う人が現れて…指を鳴らして、気づいたら…これ、夢なのか?」
”…Sだ…あいつが…”
本能的に、ルシフェルにはこれがSの仕業だということがわかった。あの時、自分を縛りあげた場面でも、彼は指を鳴らしていた。…しかし、何故こんなことを?彼に何の関係があるというのか…?
空港ロビーと連絡通路に再度、急ぎの搭乗手続きを促すアナウンスが流れる。その音に”これは現実だ”と思い知らされたような顔で、イーノックが一歩、反射的にこちらへ歩きだすのが見えた。そのまま裸足で絨毯を踏んで、立ち竦んだままのルシフェルの前に来る。彼がさっきから手に握りしめている封筒の束に目をやり、そこに書かれた自分の名を見て取ると…ふいに寂しげな表情になってルシフェルに問いかけた。
「それ…全部、捨てるのか?もう要らなくなった…?」
まっすぐ見つめてくる海緑色の目に胸を突かれたルシフェルは、思わず顔をそむけ、震える足になけなしの力を込めて、やっと歩き出すとイーノックの横を足早に通り過ぎようとした。が、すぐに大きな手に抱き止められる。
「や、やめろ…放してくれ、イーノック!…私は…行かなきゃ…!」
「何でだよ?!何処へ行こうって言うんだよ?君の居場所は、俺の側で…あのカフェなんだろ…?それも、もう要らなくなったのか……?」
「違う!そうじゃない…駄目なんだ…イーノック、わかってくれ…!」
「わかんないよ!ルシフェル、ちゃんと説明してくれ!一体どうして…?」
突然、ルシフェルが激しい感情の揺らぎをそのまま、燃え上がるような鮮やかな柘榴石(ガーネット)の瞳に涙を一杯に浮かべて、イーノックに向き直った。相手が息を飲むのがわかった。
「…わからないのか?!お前が買って来た…あのピーベリー豆…あれは…あの品種は…」
「え?」
「あれは…大抵、北向きの、栄養分の足りない枝の先端に出来る、どんな種類の木にも一定数は存在する”畸形”の豆だって本で読んだんだ…。実が生まれてすぐに、殻の中で、一方の種子がもう一方の種子を”殺して”しまって、二つ分の栄養を独り占めにして育つから、真ん丸で、味も濃くなるんだって…。知ってたか?」
「あ、ああ…。でも、それが…?」
いっぱいに見開かれた柘榴石(ガーネット)の瞳から、大粒の涙がぼろぼろと零れ落ちる。黒ずくめの衣服のせいで余計に引き立つ白い頬にわずかな赤味が刺して、はっと息を飲むほど、その姿は美しかった。
「…恐いんだ…。私と一緒にいると、いつかお前を不幸にしてしまうんじゃないか…私のせいでお前が、死んでしまうんじゃないかって…そう考えたら、恐くて…恐くて…。嫌なんだ。そんなの、見たくないんだ…。愛してるから…」
「…ルシフェル…」
「だから…放っておいてくれ…やっと昨夜、決心出来たんだ…私は一人で、生きなきゃって…だから…だから…!」
必死で泣き叫びそうになるのを堪えながら、ルシフェルは、やっとのことでそこまで言った。どうしてもイーノックの顔を見られなくて、閉じてしまった瞼の隙間から、けれども、涙だけは止めようも無く溢れてきて閉口させる。
闇に閉ざされた瞼の向こう側で、イーノックが静かに言った。
「…それが、本当に君の望んでることなのか?」
「…。」
「もし、本当にそうなら、俺は止めないよ。…それで、君が幸せになれるなら…。でも、一つだけ、俺からも言わせてくれ。あのピーベリー豆を買って来た時、俺はこう思ってたんだ。”これって、何だか俺達二人に似てる”って…」
騒がしい通路の人波の中、まるで、そこだけ別の時間が流れているかのように、イーノックの良く通る声がルシフェルの耳に心地よく響いた。爪が食い込むくらいに握りしめていないと、すぐにでも駆け寄ってしまいそうになる…。
「俺が思ったのは、こう。…俺達は、出会った時から、もう”独りぼっち”で生きてた。ピーベリーの豆になった後で、俺はルシフェルと、出会ったんだ。でも、それで良かったと思うんだよ。…何故って、どんなに他と違った形だろうと、北向きの枝の先に生った孤独なピーベリーの実だろうと、ブレンドされて、一緒に合わされば、同じ、”美味しい一杯のコーヒー”なんだからね…。だから、大丈夫だ、問題ない!って、さ。」
聞き終って、ルシフェルがおそるおそる目を開けた。徐々に開かれてゆく視界に、蜂蜜色の髪と、褐色の肌に笑った形の口元、そして最後にこちらを見つめる、深い深い穏やかな海緑色の目が笑いかけていた。
「…イーノック…。わ、私は…」
やっと絞り出した声が震える。あんなに強かった決意が、跡形も無く溶けてしまって、別の感情に入れ替わってしまっているのを感じた。…彼と、離れたくない…ずっとずっと、一緒にいたい…でも…
”私は…お前に、言えないままのことが、たくさん、あるんだ…それなのに…望めるわけがないよ…”
「ルシフェルは、どうしたい?」
「え…?」
「君が恐れている通り、俺はどういう形にせよ、いつかは死んで、この世から居なくなるんだろう。「自分が死ぬ」のは確かにちょっと怖いけど、でも人間だからそれはどうしようもないよね。…君がそれを見たくないっていうのも分かる。俺も、養父母が死んだ時は哀しかったよ、とても…。でもね、その哀しさよりも俺はやっぱり、大好きな人たちの最後の時に立ち合えて、嬉しかった。短い間でも、彼らの人生に自分が参加出来たことは幸せだった。感謝してる。…もし、何か不思議な力で過去に戻れて、別の選択肢を与えられて、別れの哀しい瞬間を回避できる道があったとしても。…きっと俺はもう一度、同じ道を選ぶと思う。」
「…。」
「だからね、ルシフェル。君も、自分の心にちゃんと訊いてみて欲しいんだ。…昔こうだったから…とか、今こんなことだから…とかは、もういいよ。それよりも、ここから先、明日の話…君はどうしたい?…何処にいて、誰と生きたいと思う?本当の、君の”心”は、どうしたいと言ってるの…?」
ここでイーノックは一旦、言葉を切った。すう、と息を吸い込んで、ハッキリと言った。
「俺は、君と生きたい。例えその為にどんな明日が来ようと、一緒に迎えたい。これから先も、ずっとだよ…。」
「…!」
震える唇を開きかけた時、館内アナウンスが、ルシフェルが搭乗する予定の便の最終呼び出しを告げた。○○行き○便にご搭乗のお客様は、離陸時刻が迫っておりますので、どうぞお急ぎ下さい―…。
当日キャンセル分で、座席が取れた一番最初の便に乗ろうと思って来ただけで、それが何処へ行くのかも、本当のことを言うとわかっていないのだ…。
「…私は…、私は…」
建物の外で高まるジェットエンジンの音が振動となって窓ガラスを震わせている。ルシフェルの手から、手荷物のバッグと、握りしめた跡のついた消印のない手紙の束が、ばさり、と床に落ちた。
次の瞬間、ルシフェルは全身で床を蹴って、イーノックの大きな逞しい胸に、自分から飛び込んでいた。
「私も…お前と、生きたい…イーノック…。ずっと、ずっと…お前と一緒に…!」
やっとそれだけ言うと、後はもう声にならなかった。イーノックの太い腕が、背中からしっかりと抱き止めてくれるのを感じると、ルシフェルは、耐えに耐えてきたものが爆発して堰を切ったように泣き出した。けれどもその声は、今まさに離陸しようとウイングを離れて行きつつある飛行機のジェットエンジンの音にすっかり掻き消されてしまった…。
そのしばらく後。空港ビルの屋上のベンチに二人並んで、ルシフェルとイーノックは頭上に次々と駆け上がって行く飛行機をじっと眺め続けていた。手には紙コップに入ったコーヒーが握られているが、やっぱり今度も、一口飲んだだけであとは冷めるにまかせたままだった。イーノックが「君が淹れたのより全然、美味しくないや」と笑った。
「…さてと。ナンナが心配してるからそろそろ帰ろうか…。あ、ごめん。電車賃かして…(汗)」
ベンチから立ち上がってイーノックが伸びをしてから、急に思い出したように、慌ててそう言った。
「うん…」
ルシフェルは、店に置いて出て来た時のナンナの泣き顔を思い出して、済まない気持ちでいっぱいになった。もう、許しては貰えないのではないか…?なんて私は、冷酷で、自分勝手な人間なのだろう…。
また涙ぐんだルシフェルの背中を、ぽん、とイーノックが叩いた。驚く彼に、安心させようと笑いかける。
「大丈夫だ、問題ない!ナンナは、俺やルシフェルより、よっぽど大人だからね!床に正座させられて、たっぷりお説教はされるだろうけど…」
途中から神妙な顔になったイーノックがおかしくて、ルシフェルも思わず噴き出していた。それを見て、ひと安心したようにイーノックがまた笑う。…と、急に大きく手を広げて立ち止った。
「ん。ルシフェル」
「え?何?イーノック…」
ようやく高くなってきた日光を体中に浴びながら、イーノックが、満面の笑みを二カッと褐色の顔に浮かべた。
「ほら、おいで。ここが、きみの”家”だろ?……おかえり。ルシフェル…」
ルシフェルは一瞬、ためらうようにイーノックの目を覗き込んだ。けれども、いつもと同じ穏やかな海緑色の瞳に受け止められると…まるで、母親を探し当てた迷子の子どものように、くしゃっと泣き笑いに顔を崩して、広げた腕の中に身をゆだねた。
温かい胸も、力強い腕も…何だかとても懐かしく思える。首に腕を回して交わし合う、この口付けも…。
「ただいま…イーノック…。」
重なり合った二人の影の上を、ジェット機のエンジンの轟音が、速度を上げながら風を巻いて飛び過ぎて行った。
ルシフェルを抱いたまま、イーノックが思い出したように言う。
「…そういえば、あの出さなかった手紙。後で読ませてくれるよな?」
「絶対に嫌だ!」
その日の夜、閉店後のカフェの玄関脇で、店のマスターキーを差し出しながら、神妙な顔でルシフェルが言った。
「…お金は、どんなに時間が掛かってもお返しします。」
それを聞いた社長は、ゆっくりと首を振りながら、鍵を持った白い手をくいと押し返した。
「いや、それはいいから。…代わりに別の条件を出させて貰えるかな?約束だよ…必ず、幸せになること。」
問い掛ける目顔で自分を見上げたルシフェルの、柔らかなココア色の瞳を飽かずに見つめながら、社長は、ふっ…と小さく息を吐いた。どこか、懐かしいような眼差しをしていた。
「君はちょっとだけ、私の”初恋の人”に似ているんだよ…。アルジェリア出身で、仏系のハーフだった…あの頃の私より年上で、美しい人だったよ…とてもね…。」
そう言って、少し寂しげに笑う。
その人とは、どうして…?と言いかけて、ルシフェルは、しかし、そこで止めた。
「イーノック君の買い付け事業は、うちの会社のCSR(企業の社会的責任:Corporate Social Responsibility)の一環として引き継いで、買い上げさせて頂くよ…。世界中を旅したバックパッカーとして、目の肥えた彼が見つけてきた素材は、どれも中々、有望だと思っているんだ。もちろん、これからも仕入れとかの支援は続けてもいいし…。」
急に照れ臭そうな顔になった壮年の男の顔に、まるで悪戯っ子のような笑顔が浮かぶ。
「…ほんとのことを言うとね、悔しかったんだよ…。イーノック君は、まるで昔の理想に燃えていた頃の私みたいだったから…冷静に見ていられなかったんだ。でも、彼は私よりも、ずっと賢かったね。…結局は、自分の”腕”の届く範囲だけを、しっかり守ろうと、潔く決められたんだから。私には、どうしても出来なかったことだよ…」
「社長…。本当に、有り難うございました…色々…」
「うん。じゃあ元気で…ああ、最後にもう一度だけ、君にキスしてもいいかな…?」
「…ええ、もちろん…」
そっ…と男の温かい唇が、目を閉じたルシフェルの額に、触れた。…それは、いつもの紳士然とした、洗練された仕草ではなく、憧れている相手に恐る恐る触れてしまった10代の少年のような、恥じらうように優しいキスだった…。
別れ際、社長は店の入り口のプランターに植えられたバラを見て、独り言のように呟いた。
「…いつのまにか、こんなに大きくなったんだね。いつも車の窓から、遠目に眺めるだけだったから…近くで見たいとずっと思っていたんだ。」
無言で頭を下げたルシフェルの方は、敢えてちゃんとは見ないで、バラの方に向かって穏やかに語り続けた。
「…そっちの明るい透明感のある黄色の花は”ピース”で、ふんわりしたベージュ色の花弁のほうは”パフ・ビューティ”か…うん。まるで君たち二人のようだね…とっても、お似合いの花だよ…」
ある朝のカフェで。ルシフェル店長は、開店準備中の店のカウンターに、ふと覚えのある気配を感じたように思った。目を凝らしたけれども、何も見えない。店のドアの鈴も、一度も音は立てなかった。
しかし、店長は何も言わずに、ごく自然な動作で一杯のコーヒーを淹れると、カウンターのある席のテーブルの上にすっと置いた。誰もいない椅子の前で、ゆらゆらとカップから湯気が立ち上っている。
「召し上がれ…取って置きの”ピーベリー・ブレンド”だよ。ところで君は、木に生っているままのコーヒーの実を、見たことあるかい?熟しきる前の実は赤くて、ちょっとぶどうにも似ててね、なかなか綺麗なんだよ…」
お馴染みのコーヒーにまつわるうんちく話を、にこやかに始める。ひとしきり語ってから、ふと、店長は黙り込んだ。
テーブルに置かれたコーヒーは、当たり前だが誰にも飲まれることなく、すっかり冷めていた。
「帰ったのかい?…有り難う、S…。君も、そっちのイーノックを大事に、な…」
何処か、遠くの誰かに話しかけるような目をして、そう言うと店長は、静かにほほ笑んだ。
店の外でその時、朝の光の中に、そこだけ影のように黒ずくめの細身の姿がドアを素通りして出てきた。…もう同じ次元には重なっていないせいだろう、彼の姿は、この世界の誰の目にも触れることは無いのだった。
黒ずくめの彼が目をやった先に、白いロングコートを着た大柄な人影が、待っていた。彼はにっと笑うと、そちらに歩み寄って、ぽん、とその広い背中を叩いた。
”…さあ、行こうか。”とでも言うように。
―…数年後。
広い荒野の中を、地平線まで続くハイウェイの路肩に停めた一台のトレーラーハウスから、明るい声が聞こえる。
「…昨日の天気図では、そんな天気で大丈夫か、と思ったが…結構いい天気だな。」
何かの店の名前らしきロゴが印刷されたTシャツを着て、窓に腰掛けて空を仰いでいるのは、ルシフェルだ。
「ああ。ハイブリッド仕様車のソーラー発電には持って来いだな。そろそろリチウムイオンバッテリーを交換したいところだけど、次の街でメーカーの営業所があるか問い合わせてみよう。」
答えたのは、車の屋根に上って、ソーラーパネルの向きを調整をしていたイーノックだった。二人は同じデザインのTシャツの、互いに黒白色違いを着ている。
「…そういえば、さっきネット通話で話したけど、新しく取引を始めたコーヒー農場、今年の現地の作柄はよさそうだよ」
「そりゃあよかった。収穫の頃には、さっそく行ってみよう!」
二人はトレーラーハウスで移動しながら、世界中の色んな街で、短期営業のカフェを開いていた。
「…あ。いま、SNSで予約が入ったよ。この週末にね、ナンナの通ってるハイスクールで、100人くらい集まるパーティをやるから、ウエストパークあたりに店を出して欲しいって。」
「へえ!豪華だなぁ。じゃWEBで仕入れてた豆を受け取りがてら、街に寄って行こうか。一番いい焙煎を頼む!」
「もちろんだとも。」
楽しそうな二人の頭上には、何処までも続く、抜けるように晴れわたった青空が拡がっている。そして、トレーラーの壁面には、コーヒー色のベースに、洒落た書体の白文字で、こんなロゴがプリントしてあった。
『 Cafe Shaddai 』
<Flavor of Peaberry Coffee Cherry 完>
Flavor of Peaberry Coffee Cherry
pixivからこちらへの移行・掲載について、快く許可して下さった二人のルシフェルbot(非公式)の管理者様に厚く御礼を申し上げます。
「エルシャダイ」をテーマにした二次創作は他にもありますので、ご興味お持ち頂けましたら筆者の他作品ものぞいて見て下さい。
(※この物語はファンによる二次(及び三次)創作活動であり、ゲーム・周辺小説等の公式とは一切関係ありません。)


