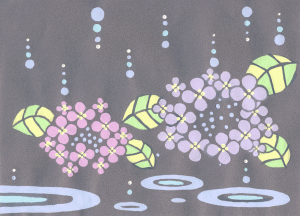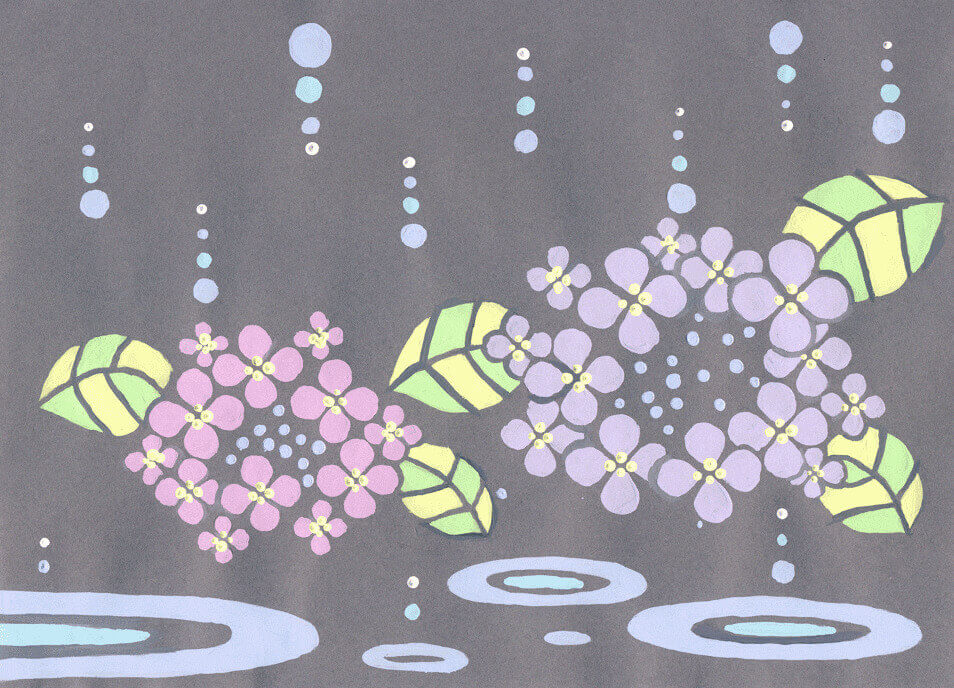
夢幻 1.0, 2.0
1.0
机の上に一通の封筒が置いてある。その表面には丁寧に書こうとしたのだろうが、どうしても子供らしさの残る字で「お父さん・お母さんへ」と書いてあった。中身はおそらく手紙で、そこには書いた者の親に対する余すところのない愛情と感謝が込められているのだろう。
その手紙の主は今、マンションの正面で地面に血にまみれて倒れている。
***
今は夜。深夜。今日と明日が入り交じる時間。
寝ずに家の中の気配を窺っていた少年は、静まりかえった家の中、一人起きた。マンションの一室の中、月明かりに照らされたせいかその横顔は蒼白かった。そしてかなり長い間起きあがった姿勢のままでじっとしていた。まるでそのまま朝が来ることを待ち望んでいるかのようだった。自分の生まれた理由を理解できない怪物もこうするんじゃあないだろうか、と少年はぼんやりと思った。
しかし、少年は朝が来るのが待ちきれなかったのか、それとも夜に急かされたのかベッドから立ち上がった。机から数日前から準備していた手紙を取り出し、机の上にそっと置いた。その手紙の全てがまるで羽のようだった。そしてなるべく音が出ないように、しかし思ったよりも音が出ないことにより恐怖を感じながら部屋のドアを開け、廊下を通り、玄関のドアを開け、立ち止まった。
廊下を振り返り、耳を澄ませ、両親の寝息が相変わらずしっかりしているのを確かめ、泣き出しそうになった。
涙が出る前に少年は家を出た。靴は履かなかった。
***
ぺた、ぺた、と足音がマンションに響く。しかし誰も気づかない、誰も彼を認識していない。それがまるで住人が彼の行為を認めているようで、少年は断頭台に向かう罪人の気分はこんなものだろうか、と特に表情もなく考えていた。
エレベーターが下へ向かう。誰とも会いたくない、誰かに出くわしたい、その両方の矛盾した願いが心の中に去来していることを少年は淡々と受け止めていた。
エレベーターは一階についた。少年は冷えて感覚のなくなってきた足を引きずるように、しかしその歩みを止めることなく出口、あるいは入り口へと向かう。
出口は開かなかった。どういう訳かいつもは開くドアが開かなかった。予想もしていなかったことに少年の眉がひそめられる。
深夜になると、中から出られないのか・・・・・・?
いや、出られるだろうが何かしらの操作が必要なのか・・・・・・?
少年はしばらくドアの周りのボタンやら何やらを眺めていたが、結局何も押さずにエレベーターへ戻った。
エレベーターは今度は上る。天国へ向かうみたいだ、と少年はぼそりとつぶやく。天国行きにしてはずいぶんとチンケだが。
エレベーターが屋上へ着く。
びゅううぅうぅ・・・・・・。冬のマンションの屋上に木枯らしが吹き荒ぶ。しかし、少年は寒さに震えるなんて下らない、と言わんばかりにぺたぺたと歩きだした。足の感覚はもうない。しかし、まだ歩ける。
四階のマンションの屋上のへりに立ち、地面を見る。深夜なので暗くて見えないかと思ったが、人間の文化は偉大だ。明かりが煌々と地面を照らし出している。四階とは言え、目のくらむような高さに少年は恐怖を覚えつつ、安心していた。この高さなら十分に死ねるだろう。四階しかないから心配していたが大丈夫だろう。
しかし、少年はへりから少し離れた。そしてエレベーターの方を見やる。その無意識の行動に気づいて少年は無理矢理口元に笑みを浮かべる。そして笑みを消し、一度悲しい目で足下を見、そのままぺた、ぺた、ぺた、とへりに立ち、母の胸に飛び込む子供のように、夜の闇に飛び込んだ。
***
少年が四階という中途半端な高さから落ちたばっかりに少年は死ななかった。正確には即死せずに、致命傷を受けた。ついでに最悪なことに意識もまだあった。飛び降りたときの音は小さく、誰も気づいていないようだった。
少年は右目を開けた。右目は無事だった。左目はつぶれてしまっていた。色々なところの感覚がおかしかった。腹の中が血の海になっているように感じた。実際その通りになっていたのだが。
少年の感覚は明らかに普段と違っていた。まず、視界が固定されていた。見渡せず、遠近もどこか狂ったように見えた。遠くのものが近く、近いものが遠く感じた。
光が聞こえ、音がにおい、冬の冷たさが見えた気がした。
全身の骨という骨が折れているように感じたが、痛みは感じなかった。脳がやられたのか、神経がやられたのかわからなかった。自信の状況を考えながら頭の中には様々なことが駆け巡っていた。
痛い。いや、痛くはない。寒い?寒い。キリンは黄色かったっけ?今流れてる曲の題名はなんだっけ?黄色だった。手が動かない。足の親指がくすぐったい。「ブラックアウト」だ。死ぬのか?はは、「停電」か。目の前に何か白いのが・・・・・・ああ、歯か。死ぬな、これは。正確には見えてるから停電じゃないな。死ぬのか・・・・・・。俺は死ぬんだな・・・・・・。
生きたかったのかな・・・・・・?
少年はもう意識すら安定せず同時に複数の思考が並列し始めた頭でぼんやりと問いかける。先ほどから自分がしきりに死について考えていることが不思議だったのか。
視界が曇る。まぶたが落ちたのではない。そもそもまぶたが動かない。そもそも無いのかもしれない。そして頭の中にこんな問いかけが浮かんできた。
生きたい?
・・・・・・わからない。
死にたい?
・・・・・・死にたくない、でも生きたくもない。
こんなふうに死にたかった?
・・・・・・絶対にお断りだった。
もう一度やり直したい?
・・・・・・何を?
人生を。
・・・・・・わからない。
じゃあ、このまま死にたい?
・・・・・・嫌だ。
そこで少年は「ああ、俺は生きたかったんだ」と思った。
どうしたい?
・・・・・・生きたい。
生きたいの?さっきと違うけど?
・・・・・・今は生きたくなった。
・・・・・・どんな代償を払っても?
・・・・・・。
・・・・・・どうなの?
・・・・・・お前は何だ?俺じゃないのか?
あなたじゃないわ。それでどうなの?払えるの?払えないの?
もはや冷静な思考を保っていたのが不思議な程の意識の中で少年はその声の主の正体もその代償の内容もどうでもよくなった。
・・・・・・払う。だから俺を生きさせてくれ。
・・・・・・承知したわ。
******
ある病室の扉を開こうとして少年の手が止まる。両手でりんごの入った紙袋とそこそこ大きな皿を持っているのだ。止まるのも当然である。
ちょっとバランスを崩しかけたが、少年はなんとかドアを開けた
部屋の中には患者が六人いて、それぞれがカーテンで仕切られた小部屋みたいな所に入っている。
「あ、やっぱり」
少年がその中でも一番奥の小部屋の主に顔を見せると、その主は静かな、しかし、どこか弾んだ声を出した。
「また、りんごだけどいいかな?」
少年は声の主のきらきらした瞳を見ながら聞く。
「りんごは好きよ。やっぱり、今日は来ると思ってたのよ」
少年は少女の傍らに置かれた小さな棚にりんごの袋と皿を置いた。
「さっきの、やっぱりってのはそういうことかい?」
部屋の隅に置いてあった椅子を引っ張ってきて少年は言う。
「そうよ。今朝からずっとそんな気がしてたの」
「へえ」
言いながら少年は鞄から短い果物ナイフを取り出し、それで器用にりんごの皮をむき始めた。
みるみる長くなっていくりんごの皮を見ながら少女は、
「ねえ、そのお皿はどうしたの?いつもと違うんじゃない?」
と少年がむいた皮を垂らしている皿と少年がいつも持ってくる皿との違いを指摘した。そしてまるで少年に見つかるまい、とでもするように、起きあがっていた上半身をゆっくりとベッドへともたせかけた。
「ああ。今日は皿を持ってきてなかったんだ。だけど来る途中で良いりんごを見つけたから買っちゃった。皿は上川さんに貸してもらったんだ」
少女の問いに少年はりんごの皮をむきながら淡々と答える。
「そうなの」
少女は短くそう返事をして窓の外に目をやり、一羽のカラスが夕日を横切って飛んでいくのを見た。
「上川さん、今度結婚するんですって」
そう少女は窓の外に顔を向けたままぽつりと言う。少年は少女の横顔を視界の端で見ながら、本当は何を考えているのだろう、と思った。
思ったが、その答えを聞くのはなんだか怖くて少年はりんごの皮をむき続ける。
やがて皮もあと一息で全部むける、というころになって少女は少年の方へ顔を向けた。
そして何か言おうと口を開きかけたが、そのまま口を閉じてしまった。少年には視界の端で全部見えていたのだが、何も見なかったかのように、
「見ろよ、月みたいだろ」
と誇らしげに見事に赤から黄色になったりんごを見せつけた。
少女は少しほほえんだ。
「そうね。とってもきれい」
と言った。
***
病室から出ると少年は鞄からマスクを取り出して着けた。
「どうだった?」
声をかけたのは病院には、というか、現代にはあまりにも異質な男だった。
一言で言えば浪人っぽい。
浪人と言っても、受験に落ちた人のことではなく、江戸時代とかの武士崩れだ。
着物を着ているのだが、あまりにぼろくなりすぎていて元の色が分からない。髪はぼさぼさでぐちゃぐちゃ。それでもそいつが侍、あるいは元侍だとわかるのは腰に日本刀を帯びているからだ。
そいつがたったいま少女の見舞いを終えた少年に声をかけたのだ。
「だめだね。効き目ない」
少年はそいつに返事した。しかし、マスクで少年の口が動いていることは傍目からは分からない。
浪人は壁にもたれ掛かっていたが少年が歩いて行くのに従って歩きだした。
「あの狐め・・・・・・。やはり嘘だったんじゃないか?」
浪人が少年へ問いかけたちょうどその時、少年と浪人は看護師とすれ違った。看護師は少年とは顔見知りらしく、軽く会釈した。少年もそれに会釈で応じる。しかし、浪人には一瞥もくれることなく彼は通り過ぎていった。
彼と十分に距離が空いたことを確認して少年は浪人の先ほどの問いに答える。
「・・・・・・嘘じゃないよ。あいつもあれが本物だと思ってたんだろ」
「・・・・・・また無駄骨か」
「そうだな」
少年は浪人のいささか毒を含んだつぶやきに低い声で答える。
少年は少女の担当看護師である上川さんに借りた皿を返しに受付に行った。上川さんはベテランの看護師で少年と少女の二人との付き合いも長い。
「上川さん、お皿ありがとう。助かったよ」
「いいのよ」
上川さんはそう笑って皿を受け取り、再び仕事へ帰っていった。今日は特に忙しそうだ。
病院での全ての用事を済ませ、少年と浪人はさっさと出口へと向かう。
外はもうさっきの夕日も沈んで夜の帳が下りかけていた。
「・・・・・・さっきお前、無駄骨って言ったよな」
出口の自動扉が開き、少年が病院の外へ出る。浪人もそれに続く。
「ああ」
「確かにその通りだ。俺がやってきたことは無駄だったし、これからも多分無駄だとは思う。それでも・・・・・・」
少年は立ち止まり下から少女のいた病室の窓を見上げる。少女は窓辺に立ってこちらを見ていたらしく、少年と目が合うと笑って手を振ってきた。
「・・・・・・それでも、やめるわけにはいかない」
少年は笑顔で手を振り返しながら、浪人にというよりは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。
2.0
気がつくと黒川心は自分のベッドの上で眠っていた。目が覚めてもしばらくの間ぼうっとしたまま動かずにじいっと天井を見つめていた。昨日起こったことを思い出そうとしていたのだ。
どうやらその試みは失敗に終わったらしく、起きあがって頭を振り、身支度を始めた。今日も学校に行かねばならない。ココロはこの上なく憂鬱な気分になりつつもカッターシャツの袖に腕を通す。
今日使う教科書、いずれもぼろぼろである、を鞄に入れ要らないものを机の棚に置く。教科書を学校において帰ったりなどしない。そんなことをすれば教科書はもう戻ってこないだろう。
このときにココロは机の上に置いてあった封筒をしばらく見つめ、机の引き出しにしまった。
支度を終え、ココロは居間へ母親の作る朝食を食べに行った。
†††
「いってらっしゃい。気を付けて」
「うん。いってきます」
玄関まで見送りに来た母親にそう言って家を出た。
エレベーターで一階まで下り、エントランスホールを出ようとしたその時、
「おはよう」
と声をかけられた。女の子の声である。
「おはよう」
ココロはその子の方を向いて返事をして更に、
「知り合い?」
と聞いた。
その娘は特に表情を変えることもなく近づいて来た。
ココロはその娘の立ち振る舞いになんとなく身構えるものを感じた。
「昨日あったでしょ?」
「いつ?」
「夜に」
「もっとはっきりと言って欲しい」
「ここの屋上から飛び降りて死にかかってたあんたを助けた者よ」
ココロはやはりか、と思った。昨日の声の主か。そう頭では理解というか直観していたが、どこか信じられないと感じたのも事実だった。
「本当に?」
「ええ」
ココロは目の前の少女の瞳を真っ直ぐに見て、
「ありがとう。助けてくれて」
と言った。
しかし、少女はココロの純粋な目に恐れをおぼえたとでもいうように目を逸らした。
「まだ・・・・・・感謝するのは早いと思う」
少女はエントランスホールのタイルを見ながらぽつりと言った。
ココロはその少女の様子に何とも言えない恐怖を感じた。こう、大きくておぞましい寄生虫が体の中を這いずり回っていると知ったときのような悪寒だった。
「どうして?」
それでもココロは尋ねた。聞かなければ悪寒は引かない
しかし少女はすぐには答えず、
「今日一日経てばどういうことかわかるわ」
とどこか申し訳なさそうな表情で言った。
†††
例の少女はエントランスホールで、
「それじゃ、また。明日の朝会いましょう」
と言って去ってしまった。
ココロとしては色々、本当に色々と聞きたいことがあった。でもなんとなく聞くのが怖かったのもあって彼女が去るのを止める時にためらってしまった。
道路に出たときにはもう彼女の姿はなかった。
ココロは学校に着いた。もう行かないと何度心に決めたか知れない。それでもココロは一度も学校を休んだことはなかった。
例えいじめに遭っていたとしても。
†††
俺は、認めたくはないが、「いじめ」に遭っている。俺は「いじめ」という言葉が嫌いだ。響きがあまりにも軽い。重みがない。
登校すればまず椅子が無い。などというのは序の口。机も無い。もっとひどい時には机も椅子もなく、ようやく見つけ出すと、椅子と机の至る所にガビョウが張り付けてあったりする。でも一番たちの悪いのは一見何も無さそうな時だったりする。
授業中は絶えず物が投げつけられる。大体は尖ったものだったが時々お菓子の箱なんかも飛んできた。
これを含めて先生が気づいていないはず、無い。無いのだが、気づいていない。気づかない。
トイレには行けない。行けばカバンの中身が無くなる。用を足している時に必ず嫌がらせを受ける。嫌がらせなんて生やさしいものではない。それしか言葉が無いから使っているだけだ。
休み時間はいたぶられる。文字通り、だ。内容は日によって様々。やる側としては「休憩」なんだろうがやられる側としてはただの苦行だ。別に俺は僧侶になりたいわけではないのだが。
これ以上のことを言うのは面倒だし気が滅入るのでやめる。もう充分だ。
もうすぐ校門前だ。いつもならこの辺りまで来ると、鬱になって今にも泣きそうな気分になるのだけれど、今日は平気だ。
・・・・・・昨日のことが影響しているのだろうか。
昨日俺は自殺した。いや、しようとした。結果的には失敗したわけだが。おそらくあの娘がいなければ更に数十分ほどあのままだったろう。そうなっていたら、きっと正気を失っていた。死の直前ではどうなろうと大して関係はないが。
そして今、俺の心境は自殺前と比べてまるで変わってしまった。
どう変わったかというと自信がついた。
今までは何をしても失敗ばかりで自信など全く無かった。しかし、自殺してみて、少なくとも実行することができて、「自分は何もできない人間じゃあない」と思えた。
この発想があまりにも幼稚だと言うことはわかっている。だが、頭でわかったところでその感情が消せるわけでもない。そして、この「自信」がおそらくは今の自分を支えているのだろう。
・・・・・・後から思えば自分はなんて下らないことを考えていたのだろうと思う。恥ずかしくなる。自殺未遂で助かって自信につながるなど呆れて物も言えない。我ながら本当に情けない。
まあ、すぐに自分の罪深さを痛いほどに思い知ることになるのだが。
†††
時間は飛んで昼休み。黒川心がクラスメートにいたぶられる様子など別に誰も望んでいないだろう。
しかし残念ながら必要な部分は書かねばならない
多少ココロの心に余裕ができようができまいが日々繰り返される出来事に何か変化が起きるわけでもない。今日も授業中ココロはかみくずだのけしかすの集めたやつだのを投げ続けられていた。
そんな授業だかなんだかよくわからないものをいつもの通りに受けていると、なにやら慌てた様子の事務・・・・・・の人が教室のドアをがらっと開けて先生を手招きした。
こそこそ話す二人に教室中の皆が注目する。やがて、
「今日は自習にします」
と先生は出ていった。教室に残されたのはココロとその敵三十六人。クラス全員。
「自習だってよ」
教室の真ん中辺りに座っているでかい奴がこちらを振り返ってにやりと笑う。毎度毎度見飽きた汚い顔だ。
こいつは「マキノ」といってクラスの中心だ。面白いし友達も多い。彼がこうだ、と言えば皆そうする。そうしなければ、「はみ出し者」になるのだ。
いつかココロは彼の意見に反対したことがあった。旅行のプランだったろうか。偶々同じ班になったので意見を出した所、それが反対意見だと取られたらしく、以降彼をはじめクラス全員が敵になった。当然楽しいはずの旅行は最悪の思い出と化した。
たちの悪いことにマキノは腕っ節まで強い。おそらくこの流れはレスリングだな、とココロが予想すると、
「レスリングだな」
とマキノは言った。ワンパターンなやつなどと余裕ぶってはいられない。マキノは関節の極め方もかじっている。それが半端にかかるものだから痛いのだ。しかも、力づくでなんとかしようとするのでなお痛い。
詰め寄るマキノの威圧感に圧されてココロが後ずさりすると、
なんと窓から紙飛行機が入ってきた。
おまけにそれはココロの手元に飛んできたではないか。
思わず手にとってみると、走り書きで
『今すぐ屋上に来い』
と書いてあった。
これはあの娘のよこした物だ、ココロは直観した。
「なんだそれ?」
マキノが迫ってくる。その声にココロは弾かれたように教室を飛び出した。
†††
はあはあと荒い息をついてココロが屋上への扉を開けるとやはりあの少女が腕を組んで立っていた。
「来たわね。よかったわ。・・・・・走ってきたの?」
少女は意外そうな声色を出した。
「急げって言ったろ」
ココロは逃げてきた、とは言わなかった。
「まあ、いいわ。右腕を出して」
少女はそう言った。
唐突だったが断る理由がなかったのでココロは素直に右腕の制服の袖をまくる。
「っ!!」
ココロは心底ぞっとした。胃袋に氷を十個ほど放り込まれたような気分になった。
肘から手首にかけてかなり大きくて真っ黒なアザができていたのだ。その墨のような黒はココロに死を連想させた。腕に突然原因不明の巨大な黒いアザができたのだ、健康にいいはずが無い。
「なんだこれ・・・・・・?俺死ぬのか・・・・・・?」
再び死の恐怖に襲われたココロに少女が彼の思いなどには興味なさそうに告げる。
「死なないわ。あなたはね」
意味ありげなその口調にココロは聞き返す。
「俺は?他の人に関係あるのか?」
「あるわ」
そこで少女は一呼吸してから言った。
「その手で触れたもの、つまりあなたが触れたもの、あなたに触られたものはあなたの意志と無関係に」
そこでちょっと言葉を止めて少女はココロの顔色をうかがうような、それでいて突き放すような眼で言う。
「死ぬのよ」
†††
「まさか」
俺の口から音が聞こえる。俺が言ったようだ。だけど声がいやに遠い。
「まさか、じゃないわ。本当のことよ。手を出して」
俺の気持ちも知らず、目の前の女はほとんど冷徹なほど落ち着いていた。
「いやいや、でも」
「手を出して」
心の整理がつかない。まるで訳が分からない。自分の右腕が何?触れたものを殺す?ばかばかしい。中二病にもほどがある。中二だってもっとまともなことを言う。
「ねえ」
司会が真っ暗になる。世界が色を失う。音が消える。
何か白いもの・・・・・・手?
白い手が見える。
揺れている。
女が目の前で手を振っていることに気づくのにしばらくかかった。
「ねえ、起きて。今はこらえて。早く処置しないと関係ない人を殺してしまうわよ」
何も考えられない。ただ女の声が頭にこだまするばかり。
「さあ、手を出して」
手を出せばいいのか・・・・・・?
言われるがままに手を、右腕を女に向かって伸ばした。もう自分の腕じゃないみたいだ。遠い、そう感じた。
「この包帯を巻くのよ」
そう言って一巻きの包帯を差し出す。巻け、と言うことか。
左腕だけで右腕に包帯を巻くという何とも難しい作業をしているうちに俺の頭も大分すっきりしてきて、少しは思考が働くようになった。
「この包帯の意味は?」
「包帯は普通の物よ。それで直接肌に触れないようにするの。それだけだと不自然だから肌に見えるようにする」
「どうやって?」
「その質問に意味はあるの?」
彼女のそんな言葉にむっとしながらも俺が包帯を巻き付けていたとき、ピンポンパンポン、と間の抜けた校内放送の音が流れた。
『えー、校内に不審者が侵入しましたので十分に注意してください。騒がずに教員の指示に従ってください』
再びピンポンパンポンと鳴って沈黙。放送はそれだけだった。暢気にもほどがあるだろう。
「今の「不審者」っていうのは私のことよ」
「そうだと思った」
そう軽口を返してもう少しで全部巻き終わる、という時、邪魔者が現れた。
マキノである。
†††
もう少しで巻き終わるという時になって、屋上のドアがぎい、とおかしな音を立てて開いた。
ドア口に立っていたのはマキノだった。
「・・・・・・!!」
これはまずい、と直観した。
マキノは俺と傍らの少女を面白いほどに大げさに交互に見て何を思ったのか、俺に突進をかけてきた。
とっさに俺はその突進を避けようとした。してしまった。
その拍子に、巻きかけの包帯が、触れたものを絶命させるという俺の右腕に巻きつけていた包帯が、
ひらひら、と。
・・・・・・地面に落ちた。
気がつくとマキノは地面に這いつくばっていた。
何をしてるんだ?俺を殴らなくていいのか?と声をかけようとしたが声が出なかった。喉がイカレたのだろうか・・・・・・。
「厄介なことになったわね・・・・・・」
口に手を当て、眉間にすこしシワを寄せて少女は考え込んだような格好をしていた。
「・・・・・・あなたは早く包帯を巻いて。これの処理は私が考えるから」
それでもなおも動かない俺を見て、俺の眼がぐるぐる回っていることに少女は気づいた。
これ?処理?そう言いたげな顔をしていたのがわかったのだろうか。少女は口を開いた。
「何が起こったか、わかってる?」
俺は少女の顔を見た。が、ぼんやりとした物しか見えなかった。
いいや、と言った。
「・・・・・・彼はあなたの右腕に触れたのよ」
†††
「・・・・・・うそだ」
ぽつり、とそんな声が口から漏れる。
うそじゃないわ、と少女。
「あなたは突っ込んできた彼に吹き飛ばされたのよ。多分そのときに右手が彼に触れたのね。あなたが立ったときにはもうそうなっていたわ」
地面にぐにゃりとくらげのように力なく倒れているマキノを何の感情もこもらない瞳で見つめながら少女は言った。
「あなたがどう思うかわからないけどその右手は私にとって大きな利益よ。あの時あなたを救って本当によかった」
ひょっとしたら俺をなぐさめようとしていたのかもしれない。右手がもたらしたこの忌まわしき事態が俺に与えたショックをこんな言葉をかけることで和らげようと、もしかすると、していたのかもしれない。
しれないが、全くの逆効果だった。
この言葉は俺にあることを気づかせた。
目の前で倒れているのは俺の右腕のせい。
右腕に突如宿った禍々しい死の闇のせい。
闇が宿ったのは女が俺を助けたせい。
俺が助けられたのは俺が死にかけたせい。
俺が死にかけたのは・・・・・・俺が四階から飛び降りたせい。
心臓を氷の手で鷲掴みにされたように感じた。
自殺がこんな、こんな結果をもたらすなんてよもや思いもしなかった。俺は間違っていない。俺は間違っていない。だって知らなかったから。
いや、そうじゃあないだろ?必死に言い繕っても頭は冷静に心に真実を突きつける。
お前は死のうとした。自分の死のせいで悲しむ人間がいると知っていながら。それは明らかな間違いだろう?そしてその間違いを犯した結果がお前の目の前に転がっている死骸の原因だ。
悪いのはお前だ。他の誰でもない。
お前が元凶だ。
マキノを殺したのはお前だ。
†††
夢幻 1.0, 2.0