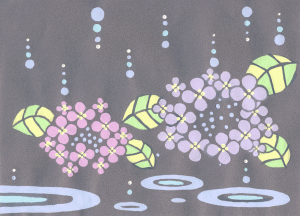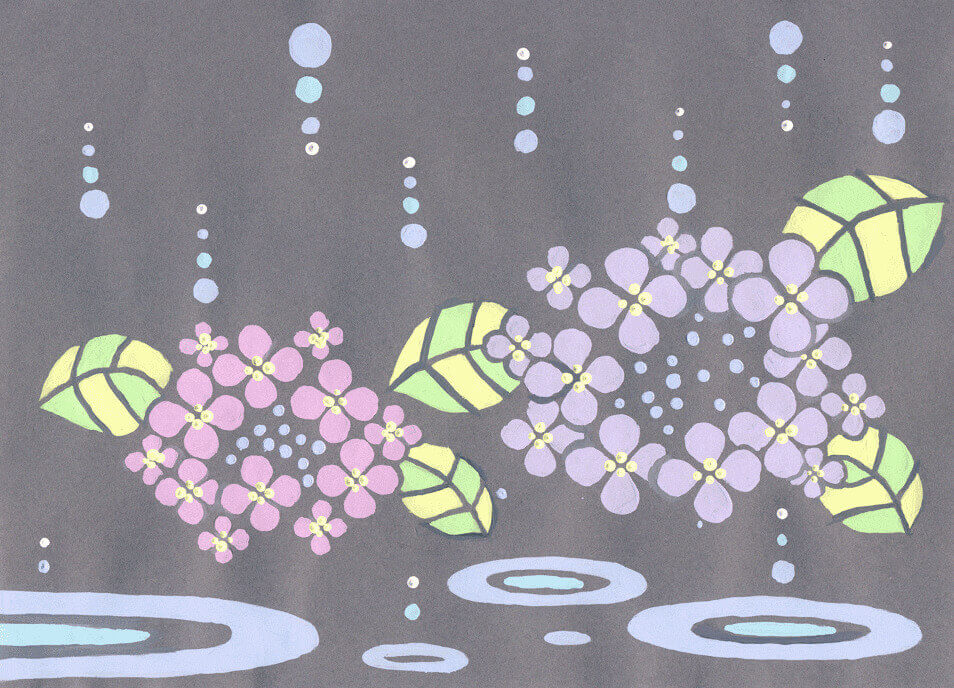
女神テミスの天秤 1.0~5.0
恋愛かなあ・・・・・・、たぶん。
1.0
鞄の中から鍵を取り出してがちゃりとドアを開けてみるとテレビが点いている音がするし、部屋の明かりも漏れている。
泥棒か・・・・・・?
泥棒が下宿する貧乏学生の部屋をわざわざ選んでくるとも思えないし、テレビを点けてくつろいでいるわけがないのだが、実際にバラエティ番組の爆笑は聞こえる。
・・・・・・というか見てる奴の笑い声も聞こえる。
静はなるべく音を立てないように中へ入り、そろりと下駄箱の裏から非常用の木刀を取り出した。
彼女は木刀の使い方を習ったことはなかったが、空手をやっていることもあって、迫力はあった。
抵抗したらこれでぶん殴ってやる。
色々な意味で彼女が危ない娘であることは認めよう。
ともかくも静はその長身によく似合う木刀を構えてじりじりと、テレビのある居間へとにじり寄っていった。近づくほどにテレビの音は大きくなる。彼女の緊張の度合いと心拍数ももがんがん増していく。
静はついに居間へのドアのノブに手をかけた。
ごくりと唾を飲み込んで静は勢いよくドアを開けた。
「うわっ!」
・・・・・・泥棒はすっ転んだ。静の愛用のファンシークッションの山に頭から。寝そべっていたのにどうやって転んだのだろう。
泥棒は寝そべってテレビを見ていたのだ。スナック菓子もつまんでいた。そこに静がばっと現れたのでびっくりしたのだ。
静があきれて絶句したことは言うまでもない。
「いきなり何だよ!び、びっくりするだろうが!」
いまだ興奮冷めやらぬ、というやつか。口ごもりながらも見当違いもいいところな文句を言っては「まだどきどきしてる」と胸に手を当てている。
泥棒(?)はそう文句を言った瞬間、静の目を見て絶望した。野獣がそこにいた。
「ああ?」
泥棒(?)はびびった。心底。
「あんた、何?泥棒?」
「い、いえ、違います」
木刀を肩に担いで眼下に転がる泥棒もどきを睨みつけるその様は誰かのトラウマになりそうな程の迫力があった。
「じゃあ、何?」
静が一歩詰め寄る。泥棒もどきの動揺も上がる。
「あ、えーと・・・・・・」
泥棒もどきは口ごもる。すると静は泥棒もどきの顔の前に木刀をびゅっと振り下ろした。
「・・・・・・!」
声もなく後ずさる泥棒もどき。静もそろそろ可哀想になってきたのか、
「正直に言ってごらん」
と笑って小さい子供に言うように告げる。しかし彼女が木刀を背負っていることを忘れてはならない。笑顔も迫力があった。
泥棒もどきはぼそりと何か言った。
「は?」
静が聞き返す。声は少々乱暴だ。テレビの爆笑が聞こえる。静は鬱陶しかったらしくリモコンでテレビを消す。
静が再び泥棒もどきに向き直ると、息を整えて、
「・・・・・・魔法使い」
と言った。
「・・・・・・は?」
泥棒・・・・・・もとい自称魔法使いの告げた言葉を静は目を閉じ約三秒かけて吟味した。
静が目を開けた。結果が出たようだ。
すがるような目で自称魔法使いも静を見上げる。
しかし、現実は非常だった。
・・・・・・自称魔法使いの右頬には丸三日間消えないアザができた。
--------------------------------------------------------------------------------
「で、あんた、何よ?」
下宿大学生の家にふさわしいちゃぶ台ほどのテーブルをはさんで向かい合わせに座って静は自称魔法使いに問いかける。
「名前はトキセワタル。魔法使いだ」
トキセと名乗った男はよく見るとそれは変な格好をしていた。魔法使い、のコスプレっぽかった。黒いローブ、黒いマント、脇に置いた黒いとんがり帽。
トキセは頬杖をついてぶすっとした顔で言い、さっきから消えているテレビを点けるべくリモコンに手を伸ばした。
その手首をがっきとつかんでぎりぎりと止める静。続いてリモコンをベッドまで投げ飛ばした。
ああ、と残念そうな顔をするトキセ。その鼻の前に静は人差し指を突きつけ、ぐいっと身を乗り出して言う。
「真面目に答えなさい」
トキセは人差し指から自らを守るように手のひらをかざした。
「人を指さすなよ。褒められたことじゃないんだろ?あと、俺は真面目に言ってる」
この時トキセは妙な言い方をした。理由はすぐにわかるだろう。
「じゃあ、使って見せてよ。そうしたら信じるわ」
自信満々で言う静。勝利を確信している顔だ。
それを苦々しい顔で見るトキセ。
「今か?」
「今よ」
静は即答した。
「一、二週間後じゃだめか?」
「何でそんなに待たなくちゃならないのよ。今よ」
トキセはふーっと息を吐いた。この上なく嫌そうである。
トキセはぴん、と人差し指を立てた。それになんとなく静も目を奪われる。
次にその指をベッドへと向けた。少し変な表情をする静。
するとベッドの向こうからふわふわと黒い物体が飛んできた。
トキセはそれを両手で捕まえ、テレビに向けた。
「ほらな」
バラエティ番組は終わって、ドキュメンタリーに変わっていた。トキセは心底残念そうな顔をした。
--------------------------------------------------------------------------------
「あ、あんたが魔法使いだってことはわかったわ」
静が再び口を開いたのはトキセが収穫したリモコンで番組の品定めを終わらせた少し後だった。初めて見た出来事を整理していたのだ。結局できなかったが。
「物わかりがいいね」
テレビからちら、と一瞬目を離してトキセは言う。
「それはそれとして、よ」
静が動揺から立ち直って言う。魔法云々は後回しする事に決めたようだ。トキセが少し首を傾けた。聞いてるよ、ということのようだ。
「なんであんたがあたしの家にいるのよ」
「あー、それなー」
テレビに目を向けたままでトキセは返事する。聞いていないのではなく、話しづらそうな感じである。
「長・・・くはないんだけど、わかってはもらえないと思うよ」
「いいわよ。説明終わったら出てってもらうから」
「・・・・・・結論から言おう」
そう言ってトキセはくるりと直角回転。静に向き合った。
「俺はこの家に住む。それも少なくとも一年は」
静はもう何と言っていいのかわからなかった。
「は、え、は?」
「落ち着いてくれ。多分その方がいい」
「どうしてあんたがあたしの家に住むなんてことになるのよ!あたしの家なのよ、勝手に決めないでよ!」
「いやまあ、その通りなんだが」
「じゃあ、さっさと出てってよ!」
トキセは参った、とばかりに頭をかいた。
「・・・・・・言い分を聞いてもらってもいいかな?」
「だめよ」
キッパリと静は断言した。
「じゃあ、悪いけど出ていくのはあんただ」
静はそのときのトキセの瞳の色を一ヶ月は忘れることができなかった。
真面目、とかそんな次元ではない。有無を言わせず実行する、というのが近いだろうか。それでも完璧な説明ではない。
「な、なんであたしが出て行かなくちゃならないのよ!あたしの家なのよ!」
「だから、そんなことは分かってる」
トキセは恐ろしい程静かに言う。
「俺がこの家に居座らなければならないのは、お前とは一切関係のない決定事項だ。もっとひどいことになってもいいのか?」
「ひどいことって何よ」
トキセは答えようとしたが口を閉じ、一瞬間を取って
「その前に俺がどこから来たかを話そう。大事な情報だ」
「どこよ?」
トキセはふ、と笑って次の言葉を接いだ。信じないだろ、と言わんばかりの笑みで。
「未来だ」
静が再び絶句したことは言うまでもない。
2.0
この回想の引き金は静の「どうして家出したの?」という言葉だった。
★付箋文★
以下は一年前の渡の回想である。つまり、渡がタイムスリップする一年前、「現在」の三百年後にあたる。このときも「現在」と同じ六月の頭だった。
「なー、トキ、「物理的に閉じた空間」の作り方今度教えてくれよ」
「あー、あれか。難しいからな。いいぜ」
トキと呼ばれた少年は渡だった。
だが「現在」の三百年後にあたるこの時代の彼の友人に彼を「時瀬渡」と認識している者はいない。なぜなら「時瀬渡」の「渡」は本名ではないからだ。「渡」は「現在」で馴染めるように、と変更された名前なのだ。彼のことをこの時代ではトキと呼ぶとしよう。時瀬だからトキである。
また言葉も「現在」とは違う。間違いなく日本語なのだが最早イントネーションが変わってしまっているので、この会話を静が聞いたとしてもすんなりと理解するのは難しいだろう。
渡は魔法で「現在」の日本語に対応しているのだ。それゆえに渡は静と普通に会話できるのだ。
トキは今、学校にいた。学校と言っても教えるのは科学ばかりではなく、魔法も教えていた。もっとも、魔法を教える学校は日本ではそう多くはなくその数は片手で数えられるほどであった。
つまりはエリート学校である。この時代では魔法は当たり前の者ではあったが使える者はほとんどいなかった。非常に限定された物だったのである。
彼がこの学校に入学できたのは彼の才能は言うまでもなく、彼の父の影響もあったためである。別に父が裏で何かしたということではなく、父の存在がトキの能力に影響を与えた、ということである。
彼の父は魔法を研究する学者であった。そしてトキは父を深く尊敬していた。
しかし、一方で自分では魔法を使えず、使える者も少ないため実験も思うように進められない父も見てきたのだった。
だから、トキは尊敬する父親に自分の魔法で研究を進めてもらうために国内で最難関である道を選んだのだった。
結論から言えば、トキはその学校の中で抜群に出来がよかった。実技でも理論でも敵う相手はいなかった。そもそも学校に通うレベルではなく最早研究するレベルであり、実際に研究を始めていた。
彼の研究は主に「絶対性」に関することであった。その魔法さえ使うことができれば他の魔法の効果を出すこともできる、そういう魔法を産みだそうとしていた。
この命題は魔法が発見されてから十年ほどで考えられ始めた。魔法は種類も多く、覚え辛い。しかも少しでも式を間違えれば予想できない効果が出てしまう。
故に昔から多くの研究者達が挑戦しては敗れ去ってきたのだ。
トキはこの問題を真剣に解こうとしてはいたが、別に本気で解けるとは思ってはいなかった。ただ、退屈とも言える授業授業の毎日に張り合いが欲しかったのだ。
とはいえ、研究はゆるゆると続き、始めてからすでに数年が経過していた。
授業など二の次。そもそも聞かなくても全部理解していたし、実践できた。
そんな彼を妬む者も当然いたが彼とつきあいがある者は大抵その毒気の無さに面食らった。授業を真面目に受けてはいないが、そんな素振りは見せないように気は使っていた。
学校での用事が全て終わると交通機関と家に帰る。魔法でぱっと帰ったりはしない。魔法はそんなにほいほい使っていいものではないのだ。交通機関の性能も「現在」とは段違いなのだ。使わなくても三十分あれば帰宅できた。
★付箋文★
「おかえり」帰宅すると家のどこかから父の声がした。
「ああ、ただいま」トキも返事をする。
荷物を自分の部屋に奥とトキは
「今からご飯の準備するから」と家のどこかにいる父に言った。んー、とか、あー、とかいう返事が聞こえた。
料理は別に「現在」の日本と変わりない。ただ機材は大きく様変わりして、はるかに使いやすくなっていた。
「できたぞー」
何十分かしてやはり書斎にいるのであろう父に向けて叫ぶ。どたどたと駆け降りてくる足音がする。父だ。父が階段を歩いて降りたためしがない。
父が席に着く。テーブルにはすでに夕食の品が並んでいた。「現在」とそうかわりばえのしない料理ばかりだ。この親子は古風なのだ。
「いただきます」
二人そろって言って食事を始める。会話は特にしない。テレビをつけているわけでもない。ただ静かに食事をとるのがこの家のスタイルだった。
母親はいない。仕事ばかりで愛想のない夫に嫌気がさした母親は離婚を提案した。母親はトキを連れていこうとしたが、トキは父親と住むことを選んだ。
「うまいな」父がぼそりと言う。
「いつもどおりだろ?」
「まあな」
その後は会話が無くなり、そのまま
「ごちそうさま」
食事の時間、この親子の数少ない団欒の時は終わった。父は書斎へ研究に戻り、トキも勉強といいつつ研究に自室へと籠もった。
とはいえ、数時間すれば夜食の時間なのだが。
★付箋文★
「さて!」
回想終わり、とばかりに渡は勢いよくソファから起きあがり、
「掃除するかあ!」と叫んだ。
★付箋文★
家事は全て済んだ。掃除は終えたし、洗濯もハプニングがあったもののやり遂げた。昼食もすませ、夕食までは時間がある。バイトもめぼしい物はチェックした。ならば・・・・・・
「散歩に行くか!」
散歩である。
町の真ん中なので緑は確かに少なかったがそれでも公園なんかには多少は残っている。そんな所をぶらぶら、雲を見ながら歩き回った。魔法使いだから自然の力を感じている、ワケではない。魔法はそんな代物ではない。
散歩だとか自然だとかは完全に彼の趣味だった。自然大好き、絶対保護!というわけでもなくただあの緑の変な形のうねうねを見ているのが好きだったのだ。雲も似たような意味で好きだった。渡以外の魔法使いでこんな風に散歩をする奴はあまりいなかった。この時代と同じである。
別に何時間でも散歩したままで過ごせるのだがそれ以外にも俗世がらみでやりたいこともいっぱいあったので彼は一時間そこそこで散歩を切り上げ、町中へと繰り出した。電化製品を見に行ったのである。
★付箋文★
そのころ静は面白くもない講義を睡魔と格闘しながらも聞いていた。ノートはとっていたがいかんせん睡魔のせいで非常に筆圧が低いわけのわからない字が書き連ねてあるだけであった。
ようやく講義が終わり、出席の紙を提出して図書館へ向かう。次のコマは空きでその次のコマにゼミがあるのだ。
「ゼミの準備をしないと」
ゼミの課題は「近年の人口増加に関してのなんたらかんたら」だった。最後の仕上げをしなければいけない。昨日の夜はとんでもないことがあってほとんどできなかったが、絶対に仕上げないとまずい。今日は発表なのだ。
確かに発表で半端な出来の物を引っ提げていくとそれは単位に響くだろうが、静の場合はそれだけではなかった。
片思いの「彼」がそのゼミにいるのだ。いや、そのゼミに彼がいるのだ。
★付箋文★
その「彼」はクラスこそ違ったが静と同じ高校の同級生だった。高校の時は別に気にもならない存在だった。彼が同じ大学に通っていることさえ知らなかった。それがまあ、ゼミをとってみると同じ高校の人間が居たのだ。静はとりあえず声をかけた。
「どうも」
「え?ああ、どうも」
彼の反応はほとんど無かった。
「あの・・・・・・、私、わかります?」
「へ?どこかであったことありましたっけ?」
静はちょっと面白くなかった。自分はこいつのことを覚えているが、こいつはあたしのことを忘れている・・・・・・。
「同じ高校よ」
「あー、うん、クラスは違うよね・・・・・・?」
完全に知らなかったらしい。というか同じクラスの人間忘れてるのか。
「違うけど、見覚えくらいないの?」
「無いね」即答だった。
「・・・・・・。じゃあ、よろしく。このゼミがんばりましょう」
「ああ、お互いにね」
そう言って静は違う席に着いた。
その後家に帰ってからアルバムを確認したところ「彼」の名前は矢部優(やべ・まさる)であった。
そしてかれこれ三週間。静は矢部を気にかけるうちに気が付いたときには好きになっていたのだった。
★付箋文★
「わははははははははははは!」
渡は静を指さして爆笑していた。静はただ赤面して黙っている。
「だはははははははははははは!なにそれ、なにそれ~?ははははははは、ぶはっ」
「殴るよ!」
「殴ってから言うなよ!」
静はその日の晩、つまり渡が来た二日目に、自分の恋について渡に相談したのだった。そう言うわけで静がどのように恋に落ちたかを少し照れながら打ち明けたのところ、渡がついにこらえきれず笑いだしたのだ。
「あんた、あたしが真剣に話してるってのに・・・・・・」
「いや、だってお前面白いもん」
「ああ?」
「ハリセン振りあげないでくれるか?ハリセンでもすごく怖ええ」
「じゃあ、笑うんじゃないわよ」
「わかった、わかった」
静はベッドに腰掛け、渡は床にあぐらをかいて座っていたがちょっと天井を見上げた。
「いーよ、手伝ってやるよ」
「本当?」
「うわ、びっくりした」
渡は静がやたらと高い声を出したことに素直なリアクションをした。
静は少し顔を赤くした。恥ずかしいらしい。
渡は頭をかりかりした。
「でもそんなには期待しないでくれよ。魔法はあまり使えないからな」
「わかってるわよ」
そういう訳で渡が静の片思いをサポートすることが正式に(?)決まった。
★付箋文★
もう二人とも布団の中に入り、部屋を仕切るカーテンも引いた後で静がなにやらごそごそする音が聞こえた。何の音かと思って渡が注意して聞いているとどうやら木刀のようだった。
「・・・・・・なあ、木刀一体何本あるんだ?」
「ひい、ふう、みい、・・・・・・」静は指折り数える。
「どんだけあんだよ・・・・・・」
「五本」
「多すぎだろ!?」
「男と同居してるのよ、これくらいしないと」
「俺をどつくためのなのか!?」
「そうよ、変なことしたら殺すわよ」
「はあ、まあ、殺されんようにするよ」
「そうよ。その方が身のためね」
「はいはい。じゃあ、おやすみ」
「ん、おやすみ」
★付箋文★
そんな感じで数日が過ぎていった。そのうちに渡はバイトを始めた。なんとかという何でも屋で雇ってもらったようだ。時給はそれほど高くはなかったが入れる時間が長かったので一月ではかなり稼げる予定だった。
そして渡がやって来てから一週間ほど経った日に静は渡を大学へ連れていった。
静は渡に片思いの相手であ矢部を見せるため、確認させるためであった。
「これが大学か。中々なもんだな」
「なんで上から目線なのよ」
「だって俺未来人だし」
「そんな理屈があたしに通じるとでも?」
「別にお前を評価してねえよ」
「評価に値しないですって!?」
「違うよ!聞けよ、人の話!」
「ところでさあ」
ふと静は話を区切った。本当にマイペースだな、と渡は思う。
「なんで言葉通じるの?あんた未来から来たんでしょ」
「言ってなかったっけ?魔法で色々してるんだよ」
「色々って?」
「説明しても構わんけどわからんと思うぜ?」
「じゃあ、いいわ」
ある教室の前まで来て静は渡に向き合って言った。
「九十分したら授業が終わるから。そうしたらまたこの教室に来て」
「わかった」
静は教室に入り、渡は大学の外にあった古本屋へと向かっていった。
★付箋文★
八十分くらいの時には渡はすでに教室の外で待機して、先ほど購入した物理の本をぱらぱらと読んでいた。そうして九十分と少し経ったあたりで学生がぽおぽろと教室から出てきた。その中に静の姿はまだ無い。
渡に矢部の姿を確認させる手順は、まず例のゼミの授業を静が受ける。渡は教室の外に控えておく。
授業が終わると矢部が出てくるはずなのでその時に静が後ろから(この人よ)と指さして渡に示す手はずになっていた。
しかしなかなか静が出てこない。まさか見逃してしまったか、と渡が心配し始めた時に一人の学生が出てきて、続いて静が出てきた。先の学生を指さしている。
ほう、と渡は思った。静が片思いするのも無理はない。
その学生はよく整った顔立ちをしていた。鼻は低すぎず高すぎずちょうどよく、髭はきちんと剃っており、目は真っ直ぐで意志の強さが現れるよう、髪は短髪で、当然染めてもいない。
硬派そうな印象をあたえるのでもてるわけではないだろうが、だからこそ静のようなややこしい女にはどんぴしゃだったのだろう、と渡は感じた。
★付箋文★
「ふー、ただいま」
「あー、おかえり」
静の帰宅の宣言に返事をしたのは渡。夕食と風呂の用意はすでにできていた。
ちなみに風呂や洗濯など、渡の男要素が生活に混じるのを静は最初はかなり抵抗して、
「風呂と洗濯は別よ!」
と叫んでいたが、四日ほど経つと、
「なんか気にならなくなったから一緒でいいわよ」
などとさっぱりと言ったので渡は少し申し訳なさを感じつつも、風呂は銭湯から家に、洗濯はコインランドリーから家の洗濯機に、代わった。
「遅かったな」
「今日はサークル仲間と話し込んじゃってね」
「そうか、なら連絡しろよ。メシが作りにくい」
「わかったわよ。家に電話すればいいのね」
「そうだな。・・・・・・」
そこで渡は少し思案顔になった。
「何よ、どうしたのよ」
「俺も・・・・・・携帯電話を持った方がいいかと、ふと思ってな」
「必要?」
「わからないけど必要になるかも」
「買っとけば?」
「そうだな。じゃあ、また今度頼むよ」
「ああ、そうね。一人じゃ買えないものね」
渡がうなずく。未来から来た彼には当然住所が無い。なので契約は静が行わなくてはならないのだ。
「さて、それはそれとして、よ」
静はテーブルのそばに座り込み、テレビを点ける。渡もその正面に座る。
テレビをかけて、ちゃぶ台大のこのテーブルを囲むのが二人の相談時のスタイルの一つだった。
「どーやって、矢部君を振り向かせるのよ」
「なんか恥ずかしいな。この感じ」
「うるさい。真面目に考えなさいよ」
ふあーっと渡はあくびをした。そしてテーブルの端にあったスナック菓子の一つを開けた。棒状のじゃがいもを揚げたやつだ。
二人でその中身をつつきつつ話し合いを進める。
「なんであんたが矢部君に会う必要があったの?」
「あいつを見ておけばいつでもあいつの居場所がわかるようになるんだよ」
静の菓子をつまむ手が止まった。
「え、なにそれ、魔法?」
「ちょっと違うね」
渡は棒状のスナック菓子をつまんでそれをくるくると回した。
「矢部の魂を見たんだよ。魔法使いならできる」
「へえ・・・・・・。なんか怖いわね」
「そうか。まあ、位置くらいしかわかんないんだけどな」
「ふーん。あたしのも見たの?」
「ああ、見えてる」
静はかなり嫌そうな顔をした。
「ああそう・・・・・・。じゃあ、あたしのピンチには駆けつけてよね」
「そりゃ、無理だね。ピンチかどうかわかんないから」
「役立たずね」
「便利屋じゃないので」
「何でも屋でしょうが」
「バイトなんで」
渡は口をとがらせて菓子を唇と鼻ではさんだ。その格好に思わず静は吹き出した。しかし顔を背けてこらえている。
「あ、あんた、やめ・・・・・・」
「おっ、これ面白い?ツボか?」
「くっ、あははははは」
さらに渡が顔を変化させたので静はたまらず笑い転げた。
「ほれほれ、ほいほい」
渡も調子に乗って変顔を連発する。
収まって再び相談するテンションまで戻ったのは十分ほどしてからだった。
★付箋文★
「じゃあ、頼んだわよ」静が家を出るときに言ってきた。
「ああ、任せとけ」渡は朝食の後かたづけの手を止めて返事する。
今日はバイトもなく、家事もたまっていない。なので午前中に家の用事を全て済ませて、午後には大学に行く予定だった。
講義をただで聞きに行くのではない、矢部とお近づきになるのだ。
「矢部君と友達になってよ」
昨夜、静が唐突に言い出したことだ。
「はあ?俺が?お前じゃなくて?」
「そうそう、あんたが」
「なんで?」
「なんでって・・・・・・。そんなこともわかんないの?」
「・・・・・・お前、あいつと直接話すのが怖いのか」
「そうよ」
「えらくはっきり言ったな」
「そうね。でもそこをぐちぐち言うと怒るわよ」
「言わねえよ。・・・・・・そんなんで大丈夫か?」
「何が?」
「俺があいつと友達になった後だよ。お前も友達になれるのか?」
「うるさいわね、そんなことは友達になってからいいなさいよ」
「へいへい」
その後もなんやかんや騒がしい押収が続いたのだが、割愛するとしよう。
3.0
結論から言うと渡はその日、矢部と友達になれなかった。
その日の午後、つまり渡が午前の家事を終え、昼食も済ませてまったり茶をしばきながらテレビを「社会勉強」と称して見ていたときである。CMで「電子書籍・・・・・・タブレット・・・・・・」とかいうのが流れていった。
渡の目が物欲しそうにその四角い黒に釘付けになる。
渡は現在ほぼ一文無しである。電車代で消える・・・・・・とまではいかないが、何度も乗れない。電化製品など買えるわけがない。
しかし、それでも渡の目はタブレットを凝視している。買えないのは百も承知。いつか買うときのために今のうちに見ておこう、などと考えているのだ。
ちら、と渡は物置棚の上に置いてある時計を見る。13時35分。矢部と友達になろうというのだから、まあ、今すぐにでも大学へ向かっても構わないのだが、渡の腰はあがらない。
ちょっと、ほんのちょっと見るだけ・・・・・・、と主人におねだりする犬のような目で時計の針をちらちら見つめていたが、
「電子書籍の*****!!」
というしつこいCMの文句を聞いて渡の中で何かがはじけた。
「どうしよう・・・・・・」
渡は絶望した表情で電気屋にある時計を見つめている。17時47分。
渡は無事電化製品店までたどり着いた。徒歩で。
しかし、その店にお目当ての製品は無かった。
まあ、仕方ないか、と他の製品を試して回る。電化製品店は二度目だから慣れたものだ。置いてある製品はほぼ全部さわり、店員にも質問し、近くの喫茶店でコーヒーも頼んだ。
しかし、それでも渡の心はあのCMのタブレットへと向かう。まるで一目惚れした乙女である。もちろん、乙女も叶わぬ恋とあきらめる心づもりだった。
だが、運がいいのか悪いのか、判断つけ難いのだが、前の席にスーツ姿の男が座ったのである。渡の席からはその男の横顔がよく見えた。
別にその男がどうというわけではないのだが、徒歩で数キロを歩いた疲労と、失恋で心身ともに疲れきった渡はその男を無意識にじっと見つめていた。彼からすれば胡乱な目つきで自分を見つめている男はさぞ不気味だったに違いない。
カフェオレを注文した後でその男は持っていた鞄の中に手を入れてなにやらごそごそと探している。渡はその様子を見ながら、そろそろ大学にいって友達にならないとなあ、とぼんやりと考えていたのだが、男が手にしていた物にそんなことはどこかに吹っ飛んでいってしまった。
彼が手にしていたのは、そう、あのタブレットである。
その男がタブレットを取り出した袋の店名を目ざとく確認し、即座にその店に向かい、タブレットとの出逢いに夢中になること一時間あまり。
気づけば時刻は17時47分。大学の講義が終わるのは18時。ここから18時までに大学に到着するのは不可能だ。どう見積もっても一時間はかかる。喫茶店に入って文無しの渡は歩きだ。
ところで覚えているだろうか?矢部を一度視認して魂を認識したので渡には矢部の位置が分かる。
だから矢部君がおそらく何のサークルにも参加していないことも、授業が終わると友達と会うこともなくさっさと家に帰ってしまうことも、何日も矢部君サーチをかけていた渡は知っているのだ。
つまり、今からどう急いだところで、大学付近までやってきた頃には矢部はとっくに帰宅しているのである。
さて、今渡の頭に浮かんだ選択肢は次の通りである。
①矢部君が帰らずに外をぶらつく、という奇跡を期待して大学に行く。
②家に帰って関にぼこぼこにされる。
③魔法でなんとかする。
④関になんらかの上手い嘘を言って事なきを得る。
⑤矢部君の家に押し掛けて友達になろうとしてみる。
渡の吟味が始まる。
①をやってもいいが失敗する確率が高すぎる。現実的な解決策ではない。・・・・・・選択肢のほとんどが現実的ではないが。
②は別にこれでもいい。関に殴られるのは問題ない。殴られるのが好きというわけではないが・・・・・・。まあ、関の機嫌をこれ以上損ねると本当に追い出そうとするかもしれない。できれば回避したい選択肢だ。
③は・・・・・・最後の手段だな。これを選ぶくらいなら②だ。
④が一番現実的な手段ではあるだろう。しかし、優先順位は③以下だな。あいつに嘘をつくくらいなら死んだ方がましだ。
⑤やってみる価値は・・・・・・無いな。
結局は②か。まあ、予想通りだ。
***
「ただいま」
渡がドアを開けて言う。
「お帰り」
静がそれに答える。その声はどこかはずんでいる。さっきまで電化製品の店ではしゃいでいた渡に似てなくもない。
静がどうしてそうなっているのかと言えば、それは当然「渡が矢部君と友達になった」と思っているからだ。彼女の押さえようとしても腹の底から笑みがこみ上げて来てどうしようもない、みたいな顔を見ると渡はいたたまれない気持ちになる。この罪悪感というものは本当に苦手だ、と渡は思った。いつまで経っても慣れやしない。慣れるわけにはいかないのだが。
「矢部君と友達になれた?」
なれたわよね?という意味ももれなくつけた口調と笑顔で渡に聞いてくる。笑顔が眩しい。まるで花のようだ。
「い、いや、だめだった・・・・・・」
渡が小さな、消え入りそうな声で言う。
その報告に静の笑顔が止まった。そして不思議なことに表情はほとんど変わらずに、ゆっくりと笑顔から生気だけが抜けていき、すぐに笑顔は完全に死んでしまった。
それはまるで花が枯れるのを早送りで見ているようだった。もはやその笑顔は活きていない。中身は死んでしまった。枯れてしまったのだ。
そしてその笑顔を枯らしてしまったのは自分だ。
渡は「矢部と友達になれなかった」と言えば静は問答無用で怒り出すと思っていた。
「・・・・・・どうして」
しかし、関は怒り出さなかった。ただ静かに聞いただけだった。か細い声で、どうして、と。
渡の頭は真っ白になった。全く予想だにしていないことだった。こういう場合は必ず怒ると思っていた。
未だ一週間ほどの付き合いでしかないが、渡は静のことを理解したつもりでいた。何か不愉快なことがあれば喚き、予想外のことがあれば叫び、時には理不尽な怒りをぶちまける。とにかくあふれんばかりの、暴力的とも言える元気のかたまり。静とはそういう女なのだと渡は勝手に思いこんでいた。
しかし、実際は違った。それを証拠に目の前で元気のかたまりは見るも無惨に萎れてしまっている。
自分のせいで。
誰のせいでもない、自分が下らないことをしたせいでこの花は枯れてしまったのだ。
だから。
だから渡はこの花をもう一度咲かせるためならどんなことでもしようと心の中で誓う。
たとえその課程でどのような目に遭おうとも、こいつの笑顔のためならきっと大丈夫だろう。
「すまない。この部屋の影響が急に変化したんだ」
嘘だ。静には決してつくまい、と決めたはずの嘘をとっさに渡はついていた。今の彼女に本当のことを言ってはいけない、と感じたのだ。今、彼女を怒らせることは、元気のかたまりにもどすことはできそうにない。きっと本当のことを聞けば倒れ込んでしまうだろう。
なら、嘘をついてショックを和らげるしかない。少しでも気が楽になるように。
「そう、無理だったのね・・・・・・」
やはり、力ない。いつもだったらハリセンで往復ビンタくらいはやっていたろう。いつもならそんな口調でもないだろう。
「ああ、本当にすまない」
いっそのことそうしてくれた方が余程気が楽なのに、今の静はただの枯れた花。ハリセンなど持てるはずもない。
「仕方なかったのね、わかったわ」
そう言って静は居間に入り、ドアを閉めた。
***
渡はそのまま夕食を作りながら思う。俺はあいつの恋心とやらをなめていた、と。
普段の彼女があまりにあまりだから、その恋もどこか子供じみたものと思っていたようだ。少なくとも「友達になれなかった」と言っただけで
あそこまで変わるとは思っていなかった。
今日は金曜日。だから友達になって、さらに上手いこといけば月曜には静自身も矢部の友達になれていたのかもしれないのだ。
おそらくは帰り道の途中もそんなことを考えながら帰ってきていたのではないだろうか。そりゃ考えるだろう、恋とはそういうものだ。
土日は渡はバイトで動けない。よって次の作戦は必然的に次の月曜になるのだ。
客観的にはこの上なくちっぽけで、しかし静にとってはこの上なく大きながっかり、だったのだ。
4.0
ある晩、いつも通り夕食を食っていたら父親がいきなり話しかけてきた。
「お前、最近は何を調べているんだ?」
「絶対性」
「えらくでかいのを選んだな。手応えは?」
「まだ全体像さえつかめてないね」
「そんなモンつかめるの待ってたらいつまで経ってもわからんぞ。見切り発車でいけ」
「わかってるよ。一度トライしたけど弾かれたからちょっと今、知識をつけてるんだよ」
「資料は足りてるか?」
「うん、今のところ充分」
「そうか」
「でも「埋め込み」しようかと思って」
「そうだな、その方が手っとり早いからな。どのくらいの情報を入れてもらうんだ?」
「まだ決めてないけど・・・・・・、五十冊分くらいかな?」
「百冊以上は考えとけ。情報量は多くても別に問題はないから」
「そんなに埋め込んで頭がパンクしないかな」
「しない。そんなに人間の頭はヤワじゃない」
「そうか・・・・・・」
「初めてだったら・・・・・・まあ百冊前後が妥当だな」
「慣れてくると?」
「一度に千冊分入れた奴もいるとか」
「それはすごいな・・・・・・」
「すごいんだが、あまりいいことじゃない」
「ただの知識になりやすいんだっけ?」
「ああ。ちゃんと活きた理解ができなければすぐに忘れてしまう。五百が限度だな、俺は」
「そういえば、最近どうなの?」
「何が?俺の研究か?」
「そう」
「行き詰まってるな」
「今も「クラッシュ」の研究?」
「ああ。クラッシュの原因を探ってるんだけどデータが少な過ぎてどうにもならない」
「仮説の立てようがない?」
「そうだ。今、観測範囲の拡大の許可待ち」
「どこまで広げるの?」
「今までは銀河レベルまでだったんだが銀河団レベルまでの拡張を申請した」
「いけそう?」
「五分五分だな。とりあえず範囲の拡大は認めて欲しい。本当はボイドも含んだ領域まで広げたいんだけどな」
「ボイドって銀河とかの数が少ない領域だっけ?」
「そう。あそこは星が少ないからな」
「抵抗みたいなものが無くて考えやすい?」
「いや、星が抵抗になるのかを見たい」
「それさえわかってないの?」
「ああ。データが無くてな」
「そりゃ大変だ」
その時、食事を終えた父親は手を合わせた。
「そうだな。・・・・・・ごちそうさま」
「じゃあ、今は何してるの?」
「とりあえず仮説の式をいくつか立てて検証してる」
「ふーん。頑張ってね」
「お前もな」
そう言って父は書斎に引っ込んだ。渡はもう少し食事を続けて、ごちそうさま。洗い物を終えて自室で研究に取りかかった。
三百年前、人間は魔法を発見した。原理がはっきりわかっていなかったので、最初はこわごわ、慣れてくると大胆に使用するようになった。
極め付きは環境問題のオールクリアだろう。史上最大の魔法の使用例だ。魔法の発見から数十年でそんなことを始めたのだ。もし、そのまま魔法の使用を続けていたらどうなったか、などとそら恐ろしい思いをした人間は多いだろう。
オールクリアした数年後、魔法で宇宙全域を観測していた(宇宙物理の)研究者達が妙な現象の報告を発表するようになった。
宇宙のどこかでいきなり前兆もなく惑星や恒星、酷いときにはその系全てが崩壊し飛散するのだ。
幸いなことにその現象は地球とはかなり離れた場所でしか観測されず、実質的な被害は無かった。それでもなんとなく魔法への恐怖が生まれ始めた。次第に魔法を大々的に使用することはタブー視されるようになった。
さらに数十年後、「クラッシュ」の位置関係から地球となんらかの関係があるという論文が遂に発表された。
実際にクラッシュが魔法による物と判って、途端にというほどでもないのだが、世界中の国々で魔法の使用が制限され始めた。
しかし、そこは人間の性。完全に禁止することは話題にはなったが実行しようという気は少なくとも政治家には無かった。
科学の研究はもちろん、エネルギーも魔法に頼っている国も少なくないし、災害復興、軍事力、etc・・・・・・。
完全に禁止するには魔法はあまりにも万能で強力だった。
そうして百数十年間は魔法の取り締まりをきつくしたり緩くしたりの繰り返しだった。時々国家事業などで大量に使用することもあった。
そしてトキの時代に至る。
この時代の取り締まりは割ときついほうだった。
研究に使用するのさえ厳しい審査を通さなければならなかった。だからまあ、トキの夢である「父を手伝う」ことはすでに難しいのだ。これは幼かったトキはまだ知らないことであった。
★付箋文★
「みつばち屋」という看板の黒と黄のコントラストがなんとも言えない雰囲気を醸し出している建物に渡は入っていった。ここが彼のバイト先であり、今日が四回目の出勤で初めて事務以外の仕事を手伝う日だった。今日は外で仕事するらしい。
「こんにちは。今到着しました」
「おう、来たか」
返事をしたのは「みつばち屋」の社長だ。といってもこの会社の従業員は社長、事務が一人、バイトが二人という、超小規模な会社だ。ちなみにもう一人いるというバイトの先輩には会ったことがない。今日が初顔合わせだ。
この会社は時給こそ低いものの仕事できる時間・頻度が高く、一月あれば二十万以上稼ぐことが可能だった。おまけに履歴書は要らず、渡の・・・・・・いや、静の家からごく近かった。ネットでバイト先を数時間かけてふるいにかけた結果の勤務先だ。社長は従業員、俺を含めて二人しか知らないが、をいつもこき使っているが、不思議といやな感じはしない。兄貴肌だからか。
「もう少ししたらクチナシが来るからな。もう少し待っていてくれ」
「クチナシ?」
「先輩のバイトだよ」
そういえばそんな名前だったかな。
「クチナシさんが来たらどうするんですか?」
「車で現場に行く。ああ・・・・・・、お前、今日初めて外に出るんだな」
「今日はどこに?」
「言ってなかったっけ?今日は部屋を掃除しに行くんだ」
「?」
「まあ、来ればわかるよ。結構腰にくるからな。覚悟しとけよ」
「はあ・・・・・・」
不透明な業務内容に対してできるのはあいまいな覚悟と返事くらいだ。
ほどなくして入り口のドアの開く音がした。恐ろしく軋むドアだ。油くらい差せばいいのに。
「あ、どうもこんにちは」
渡は入ってきた男になんとなくあいさつした。この男がクチナシだろうか。かなり大柄でがっちり、筋骨隆々。こいつにケンカを売って生きて帰ってこれるのはクマとかトラとか何かそんなのくらいだろう。それほどの体をしている。ラガーマンだろうか。
「どうも。あなたが新人さんですか?」
見かけによらず丁寧な対応を返された。
「あ、ええそうです。時瀬渡です」
「トキセ・・・・・・?」
「時間の時に、瀬戸際の瀬、渡は橋を渡るの渡です」
「ああ、なるほど面白い名前ですね。俺はクチナシタカシです」
やっぱりこの人が先輩バイトだったのか。
「どんな字ですか?」
クチナシは紙に「梔隆」と書いた。
「あなたも面白い名前ですね。梔・・・・・・。へええ」
「よく言われます」
「はいはい、自己紹介は済んだかな?」
ほのぼのとした挨拶に終止符を打ったのは社長だ。
「時間が押してるんだ。さっさと行くぞ」
★付箋文★
車で揺られること四十分。渡はなんとかパラダイスとかいうマンションの前に立っていた。そこが今日の現場だ。そこの住民の一人が先日引っ越したのでその後片づけをみつばち屋が請け負ったのだ。こんな時期に引っ越すなんてどういう事情なのだろう、と渡は内心不思議に思った。
「なにがあったんだろう?」
しかし、そう思っていたのは渡だけではなかった。梔先輩も同じだったようだ。
「そうですね。何が、」
「余計な詮索は無用!さあ、荷物を中に入れるぞ。手伝ってくれ」
社長はそう言って車の後ろを開けて掃除機やらモップやらをほいほい出していく。梔先輩もちゃっちゃとそれを受け取る。仕方ないので渡も地面に置いてあるバケツと何かわからない道具を二、三引っつかんで梔先輩の後を追う。今日は忙しくなりそうだ。
★付箋文★
そんなこんなで昼休み。今までこんな作業をしたことがなかったからか、作業服というものが肌に合わなかったのか渡は妙に乾燥したような気分になっていた。それがなんとなく気持ち悪いらしくしきりに裾をパタパタさせている。
「どうしたんだ?」
梔先輩が聞いてきた。
「気になります?止めましょうか?」
「いや、いいけど。敬語じゃなくていいぞ?」
何を言っているのだこの熊は、と渡が思ったことは秘密だ。
「え?」
「え、じゃないよ。俺、敬語言われてるのとか慣れてないし、どうも変な感じで。それに・・・・・・、あなたの方が年上でしょ?」
渡は小首を傾げた。
「そうかな?何歳?」
と、梔・・・・・・先輩を手のひらで指した。指さしは無礼だったはずだ。
「二十」
梔は無言で手のひらで渡を指し返し、年齢を聞き返した。人を指差さない。イイ奴だ、と渡は思った。
「二十一歳。そうか、じゃあ、互いに敬語・・・・・・、とか?」
「敬語は苦手・・・・・・なんですよ。使うのも使われるのも」
「使う方は慣れとけよ・・・・・・。ふう。普通に話しますか、じゃあ」
「それがいい」
「友達になるか!」
「そうしますか!」
よっしゃ、友達だ、なろうなろう、などと妙なハイテンションで盛り上がった後、梔はポケットをゴソゴソして、
「友達になった暁にアドレス交換しようぜ」
「ああ、悪りい。携帯電話持ってないんだ」
「ん?失くしたのか?水に落っことしたとか」
渡はちょっとまずい、と思った。この時代に携帯電話がどの程度浸透しているのか知らない。持ってない奴も普通にいるのか、皆持ってて当たり前なのか、持ってないと異常なのか、どの程度異常なのかもわからない。
関は持ってたっけ。持ってたな。いつも充電してる。元々持ってないと言って切り抜けられるのか?駄目だ、判断材料が少なすぎる。
「ああ、どこかに置き忘れてきたみたいなんだ」
「そうか。じゃあ、メールアドレスを書いておくから連絡してくれよ」
と言ってカバンからノートとペンを取り出す。
「いつも持っているのか?」
それを見て渡は聞く。見た目で勉強しなさそうなタイプ、と無礼にも判断していたのでそのような物を持っていることは意外だった。
ノートを少し裂きながら梔は返事する。
「ああ、いつも持ち歩いてる。こうしないと勉強する時間がとれないからな。電車の中でよく読書したり、問題解いたりしてる」
言う間に梔は電話番号とメールアドレスをノートの切れ端に書き終えて渡に差し出す。
「ん・・・・・・。じゃあ、見つかり次第連絡するよ。何日かかかるかもしれないけど気長に待っていてくれ。」
「わかった。ところでなんて呼べばいい?」
「あだ名とか?」
「そう、なんて呼べばいい?」
と言ってくれた。
呼び方。そのことで渡はしばし思案するが、
「時瀬で」
と普通に名字を名乗った。
「じゃあ、時瀬だな」
「よし。じゃあ、俺はどう呼べばいい?」
「クチナシで」
「じゃあ、クチナシだな」
言い方を合わせて返事する。梔がにやり、と笑う。こちらもにやりを返してやった。
そういうわけで今後は梔は「クチナシ」である。
***
「ただいま」
妙に疲れきった静の声で帰宅が告げられる。
やはり静は静だ。疲れきっているとはいえ、昨日の萎れ具合からは想像できないほどの回復である。
ただ、どこか無理してるんじゃないかと渡は心配してしまう。昨日はそれほどの落ち込みようだった。
昨日は食事中もほとんど何も言わず、食べ終わるとテレビを消して、
「レポートがあるから」
とパソコンで一心不乱になにやら書きまくっていたのだ。
今朝は今朝で、
「今日はサークルの集まりがあるから」
とさっさと出かけてしまった。
だから心配していたのだが、声を聞く限り疲れてはいるが大丈夫そうだ。よく見ると顔が赤い。どうもちょっと酔っぱらっているようだ。
「ああ、おかえり」
渡は玄関と同化しているキッチンに立ち、大根にとんとんと包丁を入れながら言う。バイトで一日中雑巾掛けをしていたとは思えないほどてきぱきと働いている。
「今日は遅かったな。サークルだっけ?飲み会か?」
渡はあえて明るく聞いた。昨日の件を過去にしてしまいたかったのだろう。
しかし、気づけば静はあからさまに不機嫌そうだった。なかなか脱げないらしい靴をほとんど何かを蹴り付けるように脱ぎ、忌々しげに渡を見る。しかし、別に渡に対して心からの敵意は抱いていない・・・・・・はずだ。
「そう睨むなよ。何かあったのか?俺が何かしたのか?」
渡がかける言葉に険はない。ただ力を貸そうか、とか、何か俺に至らないところがあれば・・・・・・、ということである。
静はそんな渡の言葉にほうっ、とため息をついた。
「別にあんたのせいじゃあないわよ。ちょっと不機嫌になってて八つ当たり気味なのよ」
「はた迷惑な話だな」
「何?」
「ほらほら、睨むな、睨むな。矢部君にも嫌われるぞ?」
「矢部君は関係ないでしょうが。・・・・・・もういい、着替えるわ」
そういってのし、のし、と今度は元気なく歩いて居間・・・・・・テレビのある部屋へ崩れ落ちていく。
まあ、一応は元気を取り戻したようなので渡はほっと胸をなで下ろす。
それと同時に疑問がわく。
何があったんだ?
***
正直なところ彼女は自信の所属するサークルをあまり快く思っていない。部員はほとんどががさつな、・・・・・・渡よりも面倒な男たちなのだ。しかも静は女子部員の中でただ一人の男子扱いである。今日のように稽古以外で少し部員と交流を図ったりすると、「男女(おとこおんな)」などという他人に与えられたキャラの下でひっそりと傷ついているのである。
そしてその傷は孤独な静の心に少しづつたまっていっていたのだ。
***
渡の予想通り、静には明らかに昨日とは違う何かがあったみたいだった。食事(ご飯・味噌汁・焼き魚)に対してひたすら三角食べで猛攻をしている。
つまり何も言わず食べまくっている。やけ食いに見えなくもない。だから渡は思わず聞いてしまった。
「何かあったのか?」
当然渡は心配だったから聞いたのだがその言葉に静の眉がキッと上がる。
「・・・・・・あんたには関係ないでしょうが」
地獄の底で鬼が唸るような声。いきなり怒っている。その声に怖じ気付くが、渡はなんとか言い返す。
「関係なくないだろ」
ちっ、と静は舌打ちをする。
「あんたはただあたしの家に居座ってる迷惑な奴でしょうが。あんたは黙って食事作って、掃除して、さっさ矢部君と友達になればいいのよ」
渡は言い返そうと口を開くが、そのままその言葉を飲み込むように口を閉ざした。不毛なやりとりにうんざりしたのか、言い返せないと判断したのかはわからない。
しかし、静の方の不機嫌は止まらない。その傍らのビールの缶をぐいっとあおり話を続ける。
「何なのよ、何か文句でもあるの?」
「文句はねえよ」
「じゃあ、なんでそんな目でにらんでるのよ」
渡としてはにらむような目つきをした覚えは無いが、機嫌の良い目つきでなかったことは確かだ。あんな言い方をされれば誰でもそうなるだろう。
「悪かったよ。でもにらむつもりは、」
「つもりはなくてもにらんでるのよ。今度から気をつけてよね」
「・・・・・・ああ」
渡は不本意ながらもうなずく。言い返せるような立場ではないのだ、そもそも。
静は顔を歪め、面白くなさそうに魚を食べていく。そのまま会話が戻ることは無かった。
今日の夕食はまずかった、と渡は皿洗いしながら思った。
***
5.0
今日は日曜日だ。渡は静との無言の朝食を食べ終わり、食器を洗いながら今日は家でじっとしていようか出かけようか考えていた。
すると静が突然居間とキッチンのある廊下のドアをばん、と開けて、
「出かける」
そう怒った顔でわずかな荷物を持って言い放った。渡の方をわざと見ないように玄関のドアを見て言った感じだ。宣言を終えると同時にずんずんと玄関へ向かう。
「おい、待てよ、出かけるって・・・・・・」
静は渡の言葉を断ち切るように玄関のドアを勢いよく閉めた。ドアをゆっくり閉める緩衝装置ごと。
「はあ、勝手な奴・・・・・・」
そうつぶやきながらも渡は自分の責任を少なからず感じていた。
***
静は家を出て渡がいなくなってもまだずんずんがんがん歩いていった。まるで道行く人に「私、怒ってます」と宣伝して回りたいかのようだった。
静は今、両脇に六月の桜の木が何本も植わっている古いきれいな通りを歩いている。すぐ近くには小川が流れている。水がさらさら流れる音がする。実は近くに「かえる池」と呼ばれる池があって季節になるとそこで蛙が鳴くのだが、風流でも何でもなくがあがあとうるさいだけなので近隣の住民にはその辺りはすこぶる評判が悪い。
まあ、蛙のうるさくなく鳴く季節でない今はただの単なる散歩コースである。
ところでそんな散歩コースで怒りをまき散らしている静はというと、本人にも自分が一体どうして怒っているのかよくわからなかった。明確な理由が分からなかった。怒りたいから怒っている、みたいな感じだろうか。
彼女の心の中を推測してみよう。
矢部君のことが好き、でも告白なんてできない。そんな意気地なしの自分がイヤ。それとあの図々しい居候が嫌い。あたしを助けるとか言って肝心なところで役に立たない。サークルが苦痛になってきた。練習が緩い。なのに金がかかる。一年たってもサークル仲間の中で浮いている、阻害されて陰口を言われている。それを知っている。
親が仕送りしてくれていることを考えるとすぐにも辞めたい。
文章にしてしまえばこのような悩みがいっしょくたになって、ぐちゃぐちゃに混ざりあって静の頭の中で渦を巻いているのだ。無意識な悩みが入り乱れたカオスな竜巻が静の心の中で暴れていた。
結果、静は無性に腹が立って渡に八つ当たりしたし、今も鼻息荒く、足音激しく、鬼も尻尾巻いて逃げ出すような形相で猛進しているのだ。
当然彼女に特に目指すところなど無いが、その散歩道は「もみじ山」へと続く道だった。別に散歩のために作られたわけではない。
静は歩き続けている。もちろんもみじ山に行きたいわけではない。ただ歩きたかったのだ。歩いて、足音を出しまくって、怒りも一緒に出したかったのかもしれない。頭を冷やそうと、ひょっとしたら、していたのかもしれない。
***
渡はイスに座ってぼうっとしていた。午前中は洗濯、トイレ掃除、昼食作りでつぶれた。昼食を食べ終えて今は一時くらいである。昼食の時に見ていたチャンネルをかけたままで、今は何やら芸人がまくし立てている番組を見ている。
しかし、渡がその番組を見ていたのかはよく分からない。
視線は一点を見つめたまま動かず、スタジオが爆笑に包まれてもつられてにやりともしない。普段は面白くもないところでよくつられているのに。
そのまま彼は長いこと動かなかったが、二時になり番組が変わったときにようやくほんの少し我に返り、テレビを消した。
そして、首を傾げた。
「あいつは何してるんだ・・・・・・?」
渡には人のいる位置が分かる、ということを覚えているだろうか。時々渡はほとんど無意識に知人の場所を探る。ふと匂いを嗅いだり、耳を澄ませるのと同じようなことだ。
それで静のいるところを「視た」ところ、かなり遠い所にいた。しかも全く周りに人がいない。
渡はすぐにパソコンを開き、地図を出した。感覚的な位置と方向を照らし合わせて、どうも静はなんとかという山だか森だかのまっただ中にいるらしいということがわかった。
「・・・・・・これは大丈夫なのか?」
「視る」かぎり静はほとんど動いていない。まさか迷ったのだろうか。
「まさかな・・・・・・」
しかし渡はパソコンを終了し、部屋の中をぐるぐると歩き回った。
助けに行くべきか?そんな質問が渡の頭の中に浮かぶ。
そうかもしれない。でも違うかもしれない。静はただ大自然に癒しを求めに行っただけで、今もそのリラクゼーションなるものの真っ最中かもしれない。「助けに行け」ば逆に嫌がられるだろう。
だがしかし、ひょっとしたら本当に迷っているのかも・・・・・・。
などとループ思考に陥った渡はずっと部屋をぐるぐる、ぐるぐる周り続けていた。
***
静は迷っていた。
散歩道をしばらく歩いているとちょっと勾配がきつくなってきた辺りでその道が「もみじ山」行きだと知ったのだが、意味不明に切れていた静は散歩を続行。もみじ山登頂を目指して登り始めた。
一時間ほど登った辺りだろうか、突然目の前に「危険・立ち入り禁止」の看板と注意書きがぶら下がったロープが道を遮るように張ってあった。
注意書きの方をよく読むと「この先は崖などが多く足場が不安定であり一般の方の進入は固くお断りしています。この先での事故等の責任は一切負いかねます」という内容の文章があった。
ちなみに山頂はそのずっと上。気持ちのいいくらいにまだまだだ。
この頃には静の頭も大分冷えていた。さすがに一時間歩いただけはあった。
しかし、頭が冷えても静は静である。元来の性格が登山程度で変わるはずもない。
静の目的は「登頂」。その言葉に二言は無い。無いったら無い。
静はよいしょ、と言いつつロープをくぐってまだ続いている山道を登り始めた。
この時点で十一時半くらい。
三十分後。静は無事に登頂を果たした。途中で確かに滑りやすかったり、狭い道もあったが静にとっては特に問題なく登って来れた。年輩の方や子供には厳しいかもしれないわね、と静は登っている途中でちらりと思った。
眼下には自分の住んでいる町、隣町、そのまた隣町、川、山、大学、・・・・・・まあ、そんな感じの色々なものが見えた。静は、日の出を見に来るのもいいかもね、と思ったがそこまでして見るほどでもないか、とここまでの労力を考えてすぐに打ち消した。
頂上にいたのは数分。とりあえず携帯で町を見下ろした写真を撮って下山を始めた。
山は下りの方が危ない、その言葉は静もよく知っていたため、彼女は実に慎重に道なりに下りていった。足下に意識を集中させ決して滑らないよう、滑っても大丈夫なように歩を進めていった。
異変に最初に気づいたのは下山後二十分。ふと顔を上げると全く見覚えのない所だった。静の顔が、さあっと蒼くなった。迷ったのかもしれない、そんな考えが頭をよぎった。
しかし、
「気のせいよ。たぶん・・・・・・」
と根拠のないことを言って自分を励まそうとした。だが、自分の声が思ったより震えていることを知って一層怖くなった。
「そう、携帯・・・・・・」
ふと携帯の地図とかGPSとかを思い出して藁をもすがる思いで携帯を開く。
圏外だった。
GPSもダメだった。
おまけに電池がもうすぐ無くなりそうだった。圏外だから減りが早かった。
「・・・・・・っ!・・・・・・下りればふもとにつくわよね」
そもそも迷っていないのかもしれない。行きと帰りで向きが違うから違う道に見えただけかもしれない。
そう思うと静の気はいくらか楽になった。そう思いたかっただけかもしれない。
さらに二十分後。事態は更に深刻になっていた。ふもとへ行くと言ってもそもそもが登山を禁止している道だ。当然ほとんどけもの道のような所もいくつかあった。おまけに下りたいのに道が「上り」になることも割とあった。
そうなると静の焦りは相当なものだった。下りたいのに上らなければならない。その葛藤はかなりのもので途中で何度か引き返して下り直したりした。
何度目かの引き返しの時にふと気づいた。
引き返す前の道がわからない。
元々の道がわかっていた今までは、まあ最悪の場合は頂上まで引き返すことができた。
しかし、その頂上への道さえ見失った今、それは不可能となった。
この時に静は完全に「迷った」のである。
女神テミスの天秤 1.0~5.0
恋愛だと思うよ・・・・・たぶん。