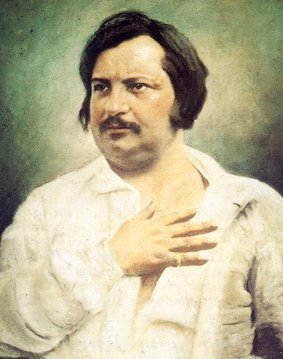天使の股ぐら
パソコンのモニターには金髪の少年が映っている。外国の少年合唱団だ。私は琥珀色の酒を飲みながらそれを眺めている。ネット経由でいくらでも少年達の映像を見ることはできた。少年合唱団のソプラノには独自の音色があるというが、黄金色をした繊細な声の織物は、女の声とも少女の声とも確かに少し違うように感じる。かといってそれは男の声では勿論ないし、少年の声ですらなかった。日常風景に存する人間の一般的な声とは違う声だった。人間の声ではないとするならなんなのか。これを表現するために陳腐な人間は「天使の歌声」なる比喩を用いるのだろう。だが私には天使という比喩は拙速であるように感じられるのだ。それは性別化される前の何者かである。人間の子ではあるが人間未満の何かである。しかし、それゆえにこそ人間にとっての何かしら核めいた要素があらかじめ覆われることなく露出しているとも思う。人間は成長するにつれて幾重にも上着を羽織る。その上着の重さ、複雑さ、絢爛さ、そうしたものが人間性の質を決める。どんな服を重ね着していくのかによって、大人になるころには各々で全く違う種類の人間に育ってしまう。だが時間をさかのぼってそれらの服を取り去ってみれば、人間にとって共通の神秘的な中心核が見えてくるように思うのだ。
モニターの中の白人の少年達は白い長い僧服のようなものを着せられている。聖歌を歌っているのだ。キリスト教の文化、というものも人間の精神にとって一つの衣服である。聖歌における歌唱法の形式も一つの衣服である。これらの衣服を一枚一枚剥ぎ取っていくと何が残るのだろうか。全部取り去ったところには何も残らないのだろうか。幼生のヒトの姿が残るだけだろうか。ヒトの幼生とは私にとっては高周波数帯域にある声だった。子供は高周波数帯で喋るのだ。成長するにつれてその周波数帯域は低くなっていく。高いところから低いところへ、という意味では、天上の世界から地に堕ちるという比喩もそう外れてはいない。つまり、子供が天使である、というような極めて俗物じみた陳腐な比喩表現は、拙速ではあれどそうそう外れていない気もやはりする。恐らくは天使という言葉に込めた意味が問題なのだろう。俗物どもが「子供は天使だ」と叫ぶとき、天使なるイメージが一人歩きするの感がある。現実の子供は忘れ去られて、天使化するのである。しかも天使とはあらかじめ人間に益を与えるものとしてしか考えられていない。しかし私が考える天使とは、そんな風に無前提に善であり無害な存在ではなかった。それは善というより単純な美であり、単純な美は善という枠組みを時に無制約的に破壊してしまうものなのである。あたかも無邪気な子供がそれと知らずとんでもなく悪いことを嬉々として行うように。
画面の中の男児を見ると、一人ひとりの顔はそれぞれに違い、天使と言ってもとても同じイデア界からやってきたとは思えなかった。声のことを考え出すといつも天使の問題に行き当たる。声には不思議な自律性がある。声が発声法や人柄や文化や骨格に関係している、ということは確かなことらしいのだが、しかしそれだけには収まらない何かがある。声はそれらの要素、いわば人間界にもっぱら属するような仮象とは無関係に存在するような存在様式を持つ。天使の天使性は、発声法や、人柄や、文化や、骨格に関係しているのではない。ましてや容姿などはまるで関係のないことなのだ。私は目を閉じてスピーカーから流れてくる声にだけ意識を向ける。歌声の主が白人であることも、西洋語で歌っていることも、幼少であることも、その全てを捨象しなければならなかった。そうした上着は悉く剥ぎ取ってしまうのだ。この周波数、この音色の時間的持続、それにこそ声の謎、天使の謎が含まれているのだ。声は、それ自体自律していて、声のほうから我々人類へと訪れてくるのだ。そうした妄想は、私の頭のなかで決して消えることはなかった。常に重要な問題だったのだ。
私は次の酒をグラスに注いだ。酒を飲むほどに時間の認識能力は麻痺していく。一瞬が永遠になり、永遠が一瞬になるのだ。天使を相手にするには、このくらいの跳躍、飛躍がなくては太刀打ちできない。当たり前のように流れている時間を私は相対化する必要があった。そのための酒だった。余人の言い方で表現すれば、酒におぼれてしまいたいと思っていたということだ。実のところ結局はただそれだけのことだった。子供の声だの天使だのと考えるのも、単に自分が子供だった時代に戻りたいという逃避的な願望が都合の良い上衣をまとって意識の表面に登壇してきているだけなのかもしれなかった。
酒を飲むといつもダメだった。本当に大事なことを考えていたはずなのに、極めて卑俗な問題へとそれがすりかえられてしまうのだった。天使の謎という人類的な問題は、わが人生の進退というきわめて取るに足りない個別的な問題へと頽落してしまった。
友人が始めた家庭教師派遣の有限会社で家庭教師業をやるようになって三年になる。友人のIと私は、早稲田の法学部を出てしばらくは就職する気もなくフラフラしていた。卒業して一年ほどしたある日、Iは学生時代からずっと続けていた家庭教師と塾講師のアルバイトからビジネスの着想を得たようで、自分の後輩達に片っ端から声をかけて独自の家庭教師派遣業を始めた。最初はIが個人として後輩学生のアルバイト口を紹介する、という形で行っており、学生は家庭に直接雇われるということになっていた。家のお母さんが、学生達に直接謝礼を手渡すわけだ。派遣先の家庭をどうやって探したのかというと、丁度知り合いの家庭教師派遣業者が撤退した際に、運よく顧客リストを流してもらって使用したのであるらしい。また、客は足で稼ぐ、という、コピー機の営業マンだった父親譲りのポリシーを働かない学生のうちから持っていたIは、自らワープロソフトで入力して作成し、町の8円コピーで刷った自作のチラシのポスティングも欠かさなかったし、毎日午前中一杯は電話営業の時間と決めてこれを怠らなかった。結局Iのビジネスを成功させたのは彼の勤勉さに他ならなかったのだ。
報酬は彼の後輩達が直接受け取っていたのだが、当然のように彼はその半分を上納させた。
「俺の紹介がなければ後輩達もこんなに優良なバイトにはありつけなかっただろうし、普通の家庭教師に比べれば悪くない給料だろう。Nよ、俺は今まで上前をハネられる側だったけれど、これからはハネる側になるよ。もちろん、とても善良で優良なさ。こんなに取り分を残してくれる仲介屋は他にいないと思うよ!」
Iは早稲田卒とはいえ麻布高校出身で、知り合いに東大や医学部の学生が多く、積極的に彼らを起用した。やはり東大生や医学部生のほうが市場価値が高いのだ。彼はバカな子供の偏差値を上げるための仕事はしたくないと度々語っていて、優良な事業には優良な顧客しかふさわしくないとの考えから名門校志望の子供しか教えないという方針をとっていた。家庭教師派遣を受注する条件として、現時点での子供の偏差値を最低65と定めており、それに満たない子供の家庭には「遺憾ながら……」といかにも残念そうな声を電話口で演じて断っていた。だから東大生と医学部生の積極起用は欠かせなかったのだ。Iの考えによれば、事業の優良さを支えるのはブランド価値である。価値の高い商品を提供している我々には、既にして価値の高い顧客しかふさわしくないのだ。それ以外の客をとることは、事業の価値をも下げてしまう。
そうした努力が実ったのかどうかわからないが、不況の時代にあって異常なほどの高値で彼は家庭教師派遣を受注した。また、口コミで家庭から家庭へと評判は広まり、受注件数は倍々ゲームで増えていった。偏差値65の壁は、奥様同士の紹介の場合には多少緩和された。そして事業を始めて一度目の入試シーズンが過ぎる頃には、彼は法人化の手続きを終えていた。
そんな場所でIと同じく早稲田出身の私が、既に学生でもないのに仕事を回してもらえているのは、友人のよしみと、事業の忙しさと、私自身の無職ゆえの暇、暇ゆえのフットワークの軽さが同時に重なったからに過ぎなかった。つまり私は「正規のアルバイト」の補欠として雇われているのだ。アルバイトの駒がどうしても足りないときは、私が代打で家庭教師を行った。たいてい長くても一ヶ月くらい働けば、Iが頭の良い本物の学生を見つけてきてくれる。家庭のほうも喜んで私をクビにして東大生や医学部生を迎え入れてくれる。家庭教師の仕事が無いときには、Iの事務仕事を手伝うこともあった。パソコンに向かってのデータ入力である。電話対応は、禁じられていた。私の顧客対応がまるでなっていないからだった。
「電話がかかってきたら、Nは用件を聞くな。俺から折り返させると言って向こうの電話番号だけ聞いておいてくれればいい」
そう言いつけられているのだ。ならば留守番電話を設定すればいいじゃないかと思うのだが、Iによれば人間が電話に出るかどうかでかなり客の印象が変わるらしい。機械音声だと、小さな会社だと思われて見下されてしまうのだそうだ。私の対人コミュニケーション能力は、かろうじて機械よりマシ、といった程度なのだろう。
そんな職場は、当然いつも見下されっぱなしで居心地としてはあまり良くないのではあるが、今更一般の会社に就職するなど私にはさらに不可能事である。私は馴致された大人しいゴリラのように、友人に従うだけであった。
こういう生活を続けていく内に、私はインポテンツになってしまった。自慰をしようとすると、何故か頭の中にIの顔だとか、家庭教師先の父母の顔だとか、性的快楽を阻害するイメージが浮かんでしまうのだ。挙げ句の果てには、勃起そのものが不可能になってしまった。どう頑張ってもこの症状は改善できず、次第に私はペニスを触ることをやめてしまった。だがそれで私が困ったということはない。ペニスを勃起させることに関心がなくなってしまったのだ。勃起させる必要性が、今の私の生活にそもそも存在しないと言って良い。当然病院にいくこともない。ただ性的な問題と社会的な問題が無意識裡に緊密に結び合っていることの不思議さを思うだけだった。
ある日Iが一件の派遣先を私に寄越してきた。
「最近とある家庭から紹介された家でね。紹介元の家の子は無事第一志望に進学できたんだが、今回の子供はどうやら不登校児らしい。参ったよ。いくら紹介とは言え、ウチはカウンセリングはやってませんからとよっぽど断ろうと思ったが、どうしてもと頼み込まれてしまってね。手が空いているアルバイトはいないこともないんだが、不登校児に教えてもどうせ合格しないだろう? 不合格が決まっているような生徒を教えても無駄弾を打ってしまうだけだ。現役の東大生を使うのは惜しい。だから、すまないが君に行って欲しいと思うんだ。金、今月も苦しいって言ってたよな? 金払いは良さそうだから君に向いてるぜ。それに今暇だろう。少々面倒な家かもしれないが、なあに、勉強する気がないから不登校になったんだ、どうせ三週間くらいで子供のほうから飽きてしまうさ。よろしく頼むよ」
手渡された資料を見てみると、派遣先は埼玉県の川越市だった。我々の事務所は、東大生をすぐ捕まえられるようにと駒場から割と近くにあったので、本来の顧客のエリアからはかけ離れていた。とはいえ郊外への出張は、客同士の紹介の場合はままあることだった。私のアパートは所沢市にあったので、事務所とは逆方向にはなるものの私にとってはむしろ好都合だった。生活圏が少しでも事務所から離れるとなると、それだけで心が軽くなるような気がした。
そのころは夏の始めで、川越の路上には蜃気楼が見えていた。顎から垂れた汗は、アスファルトの上で音を立てて蒸発しそうだった。話を貰った翌週には、早速一回目の指導をすることに決まったのである。
西武新宿線を終点の本川越まで乗り、「蔵造りの街並み」とやらを人為的かつ強権的に保存だか捏造だかしている風情ある観光メインストリートを抜け、たっぷり二十分程度歩き、新河岸川なる一級河川沿いを少し行ったところに、私の派遣された忍田(おしだ)家はあった。その家はやけに凝った造りをしていて、鮮やかな赤と白のコントラストを持ち、まるで西洋菓子のような外観をしていた。裕福な家庭らしく、住宅街の中にいきなりメルヘンチックな邸が建っているその様は、なんとも落ち着かない印象を見る者にもたらす。路地の角に位置していて、大正期の建築物のように、家の入り口も角を向いている。入り口には電子ロック式と思しき柵があり、その向こう側に玄関があった。玄関の周りは壁が円形になっているのだが、その円形に接続された四角形が家の主な生活空間であるようだった。二階建てである。家の周りを観察してみた。玄関の上、二階の窓には、隅に小さな猫のキャラクター人形が飾ってある。子供のものだろうか、と推測してみる。自分でもあきれたことだが、事前にろくに資料に目を通していなかった私は、その人形を見てようやく自分の生徒が女子生徒かもしれないということに気付いた。これは私には大変意外なことであった。女子生徒に対しては女子の学生が派遣されるのが通常である。親の子供への気遣いもあるし、そうした気遣いがあることを知っている派遣業者が自ずから女子生徒へは女子しか派遣しないという慣例を作ってしまう。もちろん少数の例外はあるが、少なくとも我々の会社では女子には女子しか派遣されないはずだった。忍田家は不登校児だから例外扱いなのだろうか。私はもう一度よく資料を確認してみる必要を感じ、訪問の時間は迫っていたものの、一度カバンから書類を取り出してみることにした。
生徒の名前は、忍田薫(かおる)と言うようだ。現在中学一年生で、私立中学への受験を親としてはさせたがっていたものの、当時から不登校気味であった子供の精神状態を案じて、家から近い学区内の公立中学へとそのまま進学させたらしい。成績は、小学生時代に受けさせた模試の記録が残っているが、悪くはない。紹介がなかったとしても、不登校でさえなければ、我々の会社でも指導を断りはしなかっただろう。だが、よく資料を読んでいると、忍田薫はやはり女子ではないらしい。志望していた中高一貫の私立は、有名な男子校である。私は額の汗をハンカチで拭いながら、もう一度二階の窓を見上げた。少女趣味のある男子生徒なのかもしれない。多少変わった生徒なのかもしれない。まあ、不登校だというからには少しくらいは変節していても想定の範囲内だ。変にひねくれていて私の知識の不正確さを指摘してくる一部の小ざかしい生意気な餓鬼などよりは、少女趣味のほうがマシというものだ。少女趣味による不登校児ならまだ大人しい性格をしていて馭しやすかろう。そんな安易なことを考えながら、私は首から提げた社員証と書類を一緒に束ねてうちわにして顔を仰いだ。あるかないかわからないような微風が顎をくすぐった。
とまれ、生徒に会ってみないことには何も始まらない。時刻はもう予定していた午後四時を五分ばかり過ぎている。私はインターホンを押した。待ち受けていたように、すぐに女性の声が迎える。
「はい」
「こんにちは、本日お約束しておりました、家庭教師のNと申しますが」
「あ、こんにちは、お待ちしておりました、どうぞ」
柵のオートロックが外れた。こんな柵、少し頑張れば乗り越えられそうなもので、防犯の役には大して立たないような気がするが、これさえつけておけば安心できるのだろう。防犯ではなく、安心を買っているのだ。続いて玄関のドアの向こうに人の足音がし、鍵の開く音がした。真っ赤な塗装をされた鉄のドアが開くと、まだ若々しい雰囲気の女性が出迎えた。
「こんにちは、忍田です。薫の母です」
「こんにちは。この度はありがとうございます。よろしくお願いいたします」
全くマニュアル通りの挨拶をした。マニュアルは社長であるIの手作りだ。
「どうぞお上がり下さい」
まさに花のような、と形容するに相応しい上品な笑顔で忍田薫の母親は私を案内した。見たところ四十歳くらいなのだろうが、母親の挙措には何か少女めいたところがあった。着ている衣服もどこか余所行きである。もちろん私という客を出迎えるから初日の今日に限ってはそれなりの服装をしているだけなのかもしれなかったが、それにしても他の家の母親とはまるで違う趣味だった。白いレースの襟がついたオレンジ色の涼しげなワンピースを着ていて、家の外観同様お菓子じみていた。家の中に入ると、中身はコンクリートの打ちっぱなしだということがわかった。夏には涼しくて適している。しかし冬はどうなのだろうか。こんな家に住んだことがないからわからない。あらかじめ用意されていた室内用のスリッパを履き、上がりかまちを踏む。こういう家でもかまちがあるのだ。外から見ていたのよりは家の面積は広いらしい。
「こちらです」
母親は階段を上っていった。階段は、壁とは間逆の軽やかな木材で出来ており、細いが丈夫そうな金属の柱で螺旋状に吊られていた。玄関の丸い形は、この螺旋階段に沿ったものであるらしい。足で踏んでも何の不安感もない。大したものだと思う。こんな妙な家を建てるからにはこの家は裕福なのであるらしい。優良な客であることには間違いない。階段を上りきったところは二階の端で、ほとんど一面ガラス張りといっていいほどだ。たっぷりと陽が入っている。先ほど外から見たのと逆の側面が、ずらっとガラスなのだ。窓からは忍田家の小さな庭と、近隣の住宅が見渡せた。母親はさらに歩いていくが、二階は殆どフロアに仕切りがなかった。リビングより以上に何かくつろげる空間として作られているようで、観葉植物が置かれ、本棚が置かれ、ソファーが置かれ、高級そうなオーディオセットが鎮座していた。しかしテレビとパソコンは無い。恐らく父親の趣味の空間だろう。本棚には自然を写した写真集の類が並ぶばかりで、活字主体のものは少ない。オーディオの脇にはクラシックとジャズのCDが並んでいる。レコードは無い。とてもブルジョワ的な部屋だと私は感想を抱く。息子の部屋はどこだろうかと思っていると、この趣味空間の端っこにドアがあって、薫の部屋、という札がぶら下げてある。札はやはり猫の姿を象ったもので、なかなか年季が入っているようだ。これだけみても、薫少年が小さな頃から既に部屋を与えられていたことが知れて、いかに愛されて育ってきたかということがわかる気がしたが、こんな父親の趣味の空間の一部として子供部屋が与えられているなんて、さぞ息の詰まる毎日だろうと、まだ会ったこともない薫少年に同情心が湧いてくるのを禁じえなかった。しかし、そうすると家を建てたのはいつなのだろうか。父親が、この母親とあまり年が変わらないとすると、三〇かそこらで家を建てたことになってしまう。それか、もしかしたら父親のほうはかなり歳なのかもしれない。
「ここが息子の部屋です」母親が部屋の前で立ち止まってやや小声気味に言った。息子の耳に聞こえないようにするためだろう。「ご存知だとは思いますが、恥ずかしながら息子は不登校で、これまでも小学生時代から度々家庭教師の先生とは揉めることが多く、指導の途中でお断りしたり、逆に断られたりしました。もちろん、私達親の教育に至らないところがあったのだろうと承知していますが、子供にはそれぞれ成長のペースがあります。私も、母親として、息子のペースを大事にしてあげたいと思っているの。ですから、色々と不愉快な思いをさせてしまうかもしれないけれど、どうか優しい心で接してあげくださいね。親の言うことで恐縮だけど、よろしくね」
母親は、言葉の途中から出し抜けに気安くなって私に念を押した。たいていの母親がこうした言動をする場合、家庭教師にある種の圧力をかけているわけなのだが、特に息子が不登校であれば、こうした態度の言わんとすることは私には到底理解も及ばないほどに複雑であろう。どうやらこの母親に限っては、気安さは威嚇のために演じられているのではなく、それよりも、本気で息子を私に託すつもりでいるようで、哀切な表情をすら浮かべている。こうも簡単に他人に心を許してしまうところにむしろ世間知らずな危うさを感じるくらいだった。だがその危うい気安さも母親特有のしたたかな演技かもしれない。我々家庭教師にとっては、その目的が判然としないような部分でこそ、母親たちはよく演技をした。結局私にはこの母親の真意は全く計りかねた。
「わかりました。初回ですので、自己紹介みたいなことをお互いにやって、普段の勉強の聞き取りをやって、あとは軽く問題を解いてみておしまいだと思いますので、そんなに刺激するようなことは何もないとは思います。とはいえ、他の生徒よりは十分に注意して、優しく接するようにいたします」
私は全く内容の無いことを言った。母親が安心したかどうかはわからない。彼女は頷くと、ドアをノックした。
「薫君、家庭教師の先生がいらしたの。入るね」
まるでよその家の子供に言うような口調だったが、私は何件かの家庭教師の経験から、親と子の間に交わされる言葉が実に多様だということを知っていたので、もはや驚きはしなかった。中学生の息子に「ボク」などと呼びかける母親は実際にいるし、お城のような家に住んでいる上流の家庭にも母親のことを面と向かって「ババア」呼ばわりする息子は実在する。もちろん「ババア」はそのたびに笑いながら息子をたしなめるのである。つまり密着的な愛情のこもった馴れ合いなのだ。どの家庭も、息子と母親の密着ぶりを示してあまりあった。塾に通う労力を子供に払わせず、逆に先生をわざわざ家庭に呼び寄せる家などは、所詮母子が密着しているような家だけなのかもしれない。だからこのときの私は、忍田家もそのような母子密着が支配する家庭なのだろうと先入見を抱いてしまった。
部屋に入ると、やや小柄の、痩せた少年が勉強机に座っていた。不登校だというからパジャマのままかと勝手に想像していたが、学校の制服じみたきちんとしたシャツとズボンを着せられている。栗色の髪の毛は地毛だろうか、男にしてはやや長めに伸ばしている。肌は夏だというのに真っ白で、確かに全然外に出ていないのだろうということがわかる。知らない人が見たら男なのか女なのか恐らく判断がつかないだろうと思えるような顔立ちで、十三歳という年齢を考慮に入れても、未分化であり未成熟という印象を私に抱かせた。薫の勉強部屋は、事前に私が予想していたほどの少女趣味はなかった。ただ、少年らしさも全くない。勉強机も、本棚も、あらゆる物が沈黙を守っている。小さな子供はよく自分の机にマンガのシールなどを貼ったりするが、そうした痕が全く見当たらない。この部屋には世界というものがない。ミクロコスモスがない。部屋自体には上等そうなマットが敷かれ、子供一人の部屋にしては割合広々としており、机もベッドもとても趣味の良い涼しげなデザインで、確かに文化的な上品な澄ました香りは漂っていたものの、それは誂え物の上品さである。少年自身の収集したこの世の手触りといったものはまるで存在しなかった。私の想像を絶する空無の中に、彼は生きているのではなかろうかと思えてしまう。この部屋の広さも、余計な物が無さ過ぎるがゆえに感じられるだけなのかもしれない。
「薫君、こちらがN先生よ。ご挨拶して」
母親が促すと、少年は椅子から立ち上がった。
「こんにちは」
ただそれだけで、自分の口から改めて名を述べることもなかったのだが、しかしその短い発声だけで彼の声質はわかった。冷気を帯びたようなソプラノだった。声変わりをしていないのだ。
実のところ、ひょっとしたら、頭がおかしくなってしまった不登校の息子に殴りかかられるかもしれない、などという可能性も少し考えて身構えてもいたのだが、予想以上にまともそうだ。こうして見ていると、不登校になるほど社会性がない子供だとは思えない。
「こんにちは。Nです」
それに比べて私の声のなんとありきたりなことだったろう。自分では自分の声を十全に聞くことはできないが、私の声を聞いた薫の反応を見るだけで、私自身がどんなにかつまらない人間であるかがわかった。薫は私が話し出した途端に身を硬くさせた。私を恐れているのだ。恐れられている当の本人からすれば、自分が誰かに恐れられる、ということが不思議な出来事である。しかしひきこもりの男子中学生に恐れられる程度には私も普通の男なのである。私でなくとも薫を怖がらせることはできたろう。私の人物とは、所詮それと同じ範疇に振り分けられる程度のものでしかない。そんな人間が薫に対して指導するということには、何か非常に脆く優美な菓子を匙で無粋につつくようなもったいなさがあった。私のようなつまらない男がこの幼い精神に触れただけでも、目の前の少年は何らかの変化を催さずにはいないだろう。私は薫の瑕にはなりたくなかった。彼に何かの性向を教え込んでこの未成熟の完全さを損なうことは犯罪じみていると思ったし、同時に、幼虫のような柔らかい発展途上段階にある薫の様子は、一つのグロテスクでもあると感じられた。子供の体は今後どのように変化していくか想像不可能な上に、成人への前段階に過ぎないというわけではないのだ。特に目の前の少年には、大人未満、といった意味での子供らしさが全くない。忍田薫の十三歳は、その時点でこそ完成するような何ものかであり、自足したものであった。あたかも人間とは別種の生き物のようだった。それは一部の少年がごく限られた時間の中にのみ許された特権的な状態である。やがて彼にも変声期が来、背が伸び、骨格が変化する時が来るだろう……そんな未来を想像してみるだけでも、私はこの世界の不条理と不可解とを強く味わう。彼は我々とは別の生き物なのだ、完全性とグロテスクさを併せ持つ。
「薫君は、普段家で自習してるんだよね? 今どのくらいまで進んでるのかな?」
私が訊ねると、薫は机に広げてあった英語の参考書を無言で私に差し出した。
「なんだ、もう一通り終わってるみたいじゃないか。やっぱり君は優秀みたいだね。これは二週目?」
家族以外の人間に褒められることが少ないからだろうが、薫は困惑したかのような顔で頷いた。しばらく学習の進度について質問をしていると、いつの間にか母親の姿は無くなっていた。薫は、殆どの科目において優秀ではあったが、数学は比較的苦手であるようだった。もちろんそれでも並みの生徒よりは優れている。私は大学受験時に数学をほとんど使わなかったので、忘れてしまっていて教えるのにそれほど自信がない。とは言え、問題を解くのを見守ることくらいならできそうだ、と判断した。質問が一通り終わり、メモをまとめ終えると、私達は休憩がてら個人的なことを軽く話し合うことにした。
「君はすごいね。一人でもよく頑張っているようだ。いつも家にいるんだろ?」
「はい。本当は学校に行かなきゃいけないんですけど……」
「まあ、今は気にしなくてもいいさ。無理に登校する必要はない。そのためにお母さんも家庭教師を呼んだんだろう。俺が中学生の頃は君ほどは勉強していなかったなあ。それに、大学時代はまさに全然学校には行っていなかったが、一人でいると全然勉強しないよね、遊んでばかりで。おかげであやうく留年しかけたんだ。それに比べると君は偉い」
「そんなことないですよ」
褒められなれていない薫の様子を見るのは楽しかった。この少年には明らかに自己評価に乏しいところがあって、しかもそれは、他人に隠した心の深層においては逆に自己評価が非常に高く、誰か自分を本当に認めてくれる人が現れるのを切望する心に由来しているのだろうと思われた。肥大化した自尊心を隠すために、外面として自己卑下が必要なのだ。もちろん、薫の場合その屈折した心理は卑屈さとしてではなく、むしろ謙虚さとして表出するという極めて穏健な形態をとっていて、さしあたり私はその様子をとても好もしく思った。
「ところで君は、勉強以外のときは家で何をやって過ごしているの? 何か趣味とか?」
「趣味は……特にありません」
「本も読まない?」
「本は、家にあるものをたまに読みますけど、あまり読まないです。あとは、インターネットでしょうか」
「ふうん。そりゃそうだ。確かにいまどき本なんか読むよりネットのほうが世界を見聞できる。昔は書を捨てよ街へ出よう、などという言葉があったらしいけど、今は街へなんか出ずネットに接続するほうが肝心だ」
「そうでしょうか」
「そうだよ。あ、それと、俺に対して敬語は使わなくていいよ。他の家の生徒だって敬語なんて使ってないからね。家庭教師なんかその程度のものなんだから、まあ、近所のお兄さんという感じで接してくれよ」
「はい。僕、年上のお兄さんみたいな人は周りにいなかったので、どうすればいいのかわからないですけれども……」
近所のお兄さん、というのは冗談みたいなものだったのだが、薫は真面目に受け取った。
「じゃあ、友達に毛が生えたような人間だと思ってくれればいい。そのうち慣れてくるだろ」
そんな話をしていると、ドアがノックされた。母親がコーヒーを持って来たのだ。盆にはシフォンケーキも乗っている。
「どうです、先生。薫はちゃんと勉強しているかしら。これ、ポタジェっていうお店のケーキなの。良かったら召し上がって」
「どうもすみません、いただきます。薫君は本当に優秀ですね。独学で勉強していたとは思えないほどです。これなら僕も教え甲斐がありますよ。今後が楽しみです」
「まあ、そうですか。薫君、良かったわね、先生に褒めていただいて」
「うん」
答えた薫の表情は、先ほどまでのはにかんだ顔とはまるで違って、感情のさざなみ一つ見て取ることができない。
「薫君、ちゃんと先生の言うことを聞きなさいね。先生がきっとあなたを助けてくれますからね」
「うん」
「じゃ、先生、よろしくお願いしますね」
母親が往っても、薫は無表情でいる。きっと母親のことが嫌いなのだろう。私自身母親がとても嫌いだったので目の前の少年の気持ちがよくわかった。母親にたっぷり甘やかされて、母親に依存している子供だとばかり思っていたので、意外な仲間を見つけたような気持ちになってしまった。彼の心をほぐすために、何か言わなければと思った。
「参ったね。助けてくれる、なんて言われちゃったよ。これは大変な仕事だ」
私は何とか笑いながらそれを言うことができた。まったくあの母親には困ったものだ。不登校のことなど気にするな、と私が話したばかりだというのに、その流れをアッサリと覆されてしまった。何しろ「助ける」などという大げさな言葉を使うのだ。そんな言葉を使ってしまったら、今日家にやってきたばかりの家庭教師が薫の不登校の面倒まで見て「矯正」してやらねばならないかのようだ。薫も、少なくとも今はまだそんなことは期待していなかろう。まだ学校になど行きたくないはずだ。かなり心内を乱されたに違いない。特に中学生の精神はふとしたことでかき乱される。事実、私が空気を取り繕おうとして言った言葉も、薫の表情を和らげるには到らなかった。
「先生。先生は、僕のこと助けてくれるの?」
思ったとおり、薫は思いつめたような質問をこちらに投げてきた。
「もちろん。勉強のことなら何でも助けてあげるつもりだよ」
「勉強以外のことは?」
「全部は無理だね。でも話を聞く位だったらできるかな」
「じゃあ、勉強に関係ない話になるかもしれないけど、聞いてもらおうかなあ」
許可を求めるかのように薫がつぶやいたので、私は頷いてそれを促した。
「僕、上手く言えないけど、世の中にちゃんと出て行けない気がするんです。学校に行けてないからだけじゃない。なんて言うか、そもそもこの社会とか、世間とか、そういうのに向いてない気がする。世の中の人みんなと、どこか目線がズレてる気がする。僕は、どこかおかしい人間なんじゃないかと思う。みんなの興味と僕の興味って、全然重ならないことが多いんだ。みんなが夢中になっているものが、僕にとってはすごくどうでも良かったり、逆に僕が面白いと思っているようなものが、みんなにはバカにされたりするんです。そうやって自分の好みがバカにされるのが怖くて、最近はあまり色んなものに興味を持たないようにしてるんだ。ねえ、こういうの社会不適合者って言うんだよね? 前にネットで見たよ。違う?」
「そうだなあ。社会不適合者、っていうのはもっとこう、仕事ができないとか、時間が守れないとか、そういうキチンとしてない人のことを言うものだと思うよ。人の話を聞けない、とかね。君はそういう意味じゃちゃんとしてるよ。社会不適合じゃない。安心しなよ」
「そうなんだ……でも僕、学校に行けてないからやっぱり社会不適合だよね? キチンと学校に通えてないもの」
まるで自分を一人前の社会不適合者として認めて欲しいかのように薫は言った。ここでも薫は自分を卑下してはいるものの、本当は自分のほうから社会などというものは願い下げなのである。その気持ちに彼が自分でどれだけ気付いているのかはわからない。恐らく、まだハッキリとは自覚していないだろう。だが彼は、もし自分が世の中の人と歩調を合わせられるようになったらと想像して吐き気を催す種族の人間に違いない。
「俺もやっぱり君くらいの歳のときは同じことを考えていたよ。もちろん君ほど明晰に考えてはいなかったけれどね。薫、薫君、中学生くらいのときは皆同じようなことを考えるんだ。そして太宰治なんかを読んだりする。自分が一番この世で不幸であるかのような気持ちになる。それはよくあることなんだよ」
「……」
「しかし、俺はそれがダメだと言いたいわけじゃない。そうじゃなくて、自分を社会不適合だと決め付けることは全然良いのだけど、ただ、そういうときに太宰なんかを読む凡庸な人間にだけはならないように、と、それだけ言っておきたいね」
「読んじゃいけないんですか?」
怯んだような顔で問うてきたので、もしかしたら本当に太宰を読んでいるのかもしれない。
「いけないというわけじゃない。読んだっていいさ、もちろん。でも、それは誰だってすることなのさ。皆が読むように、君も太宰を読んだとする。そしたらそれは、君が凡庸であって社会不適合じゃないことの証にならないか? それはもったいない。俺は、一度社会不適合と決めたからにはとことんまで社会を拒否してやるのが良いと思うよ。それがたった一つ残された、社会不適合者の処世術だ」
「社会不適合者の処世術、ですか」
薫にはシンキング・タイムを与えた。手のひらを握ったり開いたりしている。
「変な言葉ですね。こんな話を聞いたのは初めてです」
「あまり参考にならなかったかな」
「いいえ、今までで一番参考になりました。やっぱり先生も社会不適合者なんだね」
薫はやはり自分を社会から卓越させたがっているのだ。社会不適合というより、社会を突き抜けてしまった者として自分を認識したいのだろう。だから、融和よりも否定へと誘導してやれば嬉しそうにする。そういう方向へ子供を導くのが果たしてまがい物とは言え教師がやっていいことなのかはわからない。しかも、未だ現にこの問題から完全には逃れられていない私自身が子供に正しい答えを示せるとは思えない。が、なにはともあれ、薫は気を取り直したのだ。私が薫に与えた言葉には良い効果もあったということの証明だと、このときは信じておくことにした。
結局私は三時間程度薫の部屋にいた。母親からは、来週もこのくらい居てくれると助かる、と言われた。通常一回の指導は一時間半なので、よその子供の倍の時間居ることになるが、薫は学校に行っていないので、その分少しでも勉強漬けにさせたいのだろう。私は、今後の三時間の訪問時に、薫が少しでも母親や学校のことを忘れられるようにしようとぼんやり思った。
帰り際、玄関のすぐ外で母親に引き止められ、立ち話をした。季節柄、もう七時だというのにまだ外は暮れ切っておらず薄ら明るい。
「今日はありがとうございました」
「いいえ」
「N君、うちの子はどう? また学校に行けるようになるかしら?」
「このまま勉強に自信がつけば、きっと不安もなくなるでしょう」
内心、またこの話かとうんざりしながら投げ遣りに答えた。家庭教師に求めることじゃない。結局この母親は不登校のことしか頭にないようだ。彼女にとっては不登校という現象そのものだけが問題なのだ。不登校の原因や、不登校に到るまでの諸々の過程には一切興味がない。自分の子供が学校に行っていないという事態が許せないというだけだ。
「今の世の中、人々の価値観は多様化しています。お子さん達の興味関心だってそうなのです。今まで色んなお宅に伺いましたが、どのご家庭のお子さん達も本当に十人十色で、こんな子供達が同じように学校に通っている、というのが不思議なくらいです。もともと昔の日本では子供を学校に通わせるほうが珍しかったのだし、薫君が学校に行けないからといってそれがおかしいというわけでは全然ありません。むしろ、今の時代学校に行く気がしないほうが当たり前なのです。今日お話して実感しましたが、本当に薫君は聡明です。とてもしっかり自分の考えを述べるし、よそのお子さんに比べても相当賢い子であるとわかりました。なまじ頭が良すぎるからこそ、学校になど興味が持てないのでしょう」
親に対して子の欠点を報告するときは、こういう風に、長所が個性として強すぎるからなのだ、という言い方をする。そうすれば親はむしろ子供が褒められているかのような気持ちがするものなのであるらしい。これは別に私の知恵ではない。そうするようにマニュアルで決められているだけだ。実務とは関係のない、このような部分こそが顧客満足度を上げるのだ、というのが、社長である友人Iの信条だ。顧客とは勿論子供のことではなく親達のことだ。我々教育産業の従事者は、親達にこそサービスを売っているのである。親の心を満足させる為に働いているのである。決して子供の頭を通り越しているのではない。子供など最初から範疇の外なのだ。
「N君、私不安で……」唐突に母親が私の手を握ってきた。「もしかしたら子供よりも私のほうがよっぽど不安なんじゃないかって思うのよ。悩みすぎて毎日あまり眠れないし。うちって、夫がほとんど家にいないんです。仕事が忙しいみたいで。会社だって遠いし。薫があんなふうになったのも、父親と接する機会がないからじゃないかと思うの。こんなこと夫に言ってみても、俺だって子供の頃親父と遊んだりしなかった、だなんて言って聞こうとしないし。N君も薫に会ってみてわかったと思うけど、あの子には男らしさが足りない気がするのよ。もっと元気にたくましくなって欲しいんだけど、今みたいに弱々しく怯えているだけじゃ、一生外に出られないと思うの。だから、N君が父親の代わりに男らしさを薫に示してくれたらいいな、なんて勝手に期待しているのよ。うちはそういう父親代わりになってくれるような人が周りにいなかったから。いきなりこんなこと言われてもあなたも困るでしょうけど、是非力になって。お願い」
そう言って母親は、両手で私の右手を握って、上下に軽く揺すった。今日初めて会ったのに、こんな風に手に触れてくるなんて、私は軽んじられ侮辱されたような気持ちになった。だが顧客に対してあからさまに憤りを示すわけにもいかない。
「ええ。僕にできることでしたら」
「そう言ってもらえてうれしいわ。勉強時間内でもたまに薫と散歩して遊んだりしてもいいからね。薫が家の外を怖がらないようにして欲しいの。この辺は繁華街もあるし観光もできるから楽しいわよ、きっと」
母親にじっと見つめられて、私は不気味な寒気を感じた。薫は外の世界を怖がっているというよりも、むしろ外の世界を軽蔑し切っているのだ。外の世界に出ることに何の価値も見出していないのだ。薫から見れば、この母親の言動も軽蔑の対象となるのではないだろうか。息子のことを飼い猫か何かと同じように考えているらしいこの母親とずっと同じ家で過ごしていたら、ますます世の中に期待が持てなくなるだろうなと、私は薫に同情した。
「ああ、あなたみたいな人が来てくれて、本当に助かった。あまり厳し過ぎる人だったら、次回からお断りしようと思っていたのよ。薫にとっては普通の先生ですら厳し過ぎると思うの。だから、今日は朝から落ち着かなかったけれど、あなたを一目見た時から、この人ならきっと大丈夫、って不思議に安心したのよね。どうしてだかわからないけど、あなた、きっと人を安心させるような穏やかな雰囲気があるのよ! それで薫もあなたには心を許しているのね。母親の私だって、薫があんなふうに笑ったり話したりしているところ、滅多に見ないんだから!」
「そうなんですか」
「ええ、そうよ! 薫だけじゃない、私もあなたのこと気に入ったわ。是非、薫の勉強をみてもらうだけじゃなくて、私たち親子のお友達として、あなたとは今後も仲良くお付き合いしていきたいと思っているの」
母親は、握った手を少し緩め、私の手のひらを指先で軽くなぞり始めた。この時は頭の裏に鳥肌が立ったような気がしたものだ。明らかにこの母親は私に対して過ぎたことを期待している。ひょっとしたら、割と頭の緩そうな母親なので、彼女自身に自覚は無いのかも知れないが、実は家の外に出たがっているのは忍田夫人自身であって、薫を主語にして彼女の口から語られる諸々のことは、彼女本人の願望なのではないかと思われた。
私は、逃げるようにして挨拶を述べ、一番街を早歩きで歩き、本川越駅を目指した。
私は私の心を慰めるつもりで帰宅してからすぐに天使達の動画を再生し始めたのだが、今日は何故か黄金色の音の繊維をたぐることができなかった。モニターに映る金髪の少年達が、あか抜けない只の田舎者に見える瞬間すらあったのだ。私は私自身を疑った。自分が正気ではないのだと思いすらした。
夏の暑さのせいか。それとも忍田夫人の奇妙な振る舞いのせいか。身体も疲れている。頭もぼんやりする。今日一日のできごとは、私の精神から能動性を奪ってしまっていた。初めての家はただでさえ緊張して疲れるのに、時間はいつもの二倍だったのも疲労の大きな原因だ。鈍い頭痛がして、もしかしたら微熱があるのかもしれない。
卓上に転がっているキャラメルを一つ開けて口に放り込んだ。濃厚な重みある甘さが口の中に溶け出していって、脳髄が痺れるかのような開放感を感じた。忍田家で母親に出されたケーキよりも、このとるに足りない安いキャラメル一粒のほうがよっぽど安心して甘みを堪能できるというものだ。
尋常じゃなく疲れているから、パソコンのスピーカーから放出されてこのアパートの部屋中に振動しているはずの音の金糸を認識することができないのだ、とはじめは思った。しかしそうではなかった。かつて未開な耳しか持たなかった頃の私の聴覚を支配した黄金も、さらに高貴なものの前では色あせて見えるのだ。私は動画の再生を止め、自分の頭の中に鳴り響いている音に聴覚を集中させてみた。明白な音として認識できはしなかったが、代わりに浮かんできたのは一つの統覚的なイメージである。それはまず最初キャラメルとして現象した。口に含んだキャラメルがそのイメージを齎したのに違いない。私はキャラメルを音としても認識したし、視覚においても認識した。まぶたの裏の暗闇に浮かび上がってくるのは栗色の立方体だったが、この栗色はそれを思い浮かべるだけで口腔の甘みを倍加させた。なおも私はそのキャラメルの正体を探ろうと自らの心の深くに沈んでいくべく試みたが、その途中でこんな瞑想が無駄なことに気付いてやめてしまった。そこに忍田薫のイメージが強く関わっていることは考えるまでもなく明らかだったからだ。薫の栗色の髪は、私の無意識裡にキャラメルと薫を媒介した。
薫との出会いが、今の私に対して、傷ついた生活の中に束の間差した木漏れ日のような心地よさを与えていることは、私自身を驚かせはしたものの、徐々にそのことに納得していった。恥ずかしい話だが、薫は現在の私にとり唯一まともに話を聞いてくれる人間だったのだ。Iも、Iの事務所の学生達も、忍田夫人も、誰一人私の話を言葉通りに聞いてくれる者はない。私の言葉は彼ら彼女らの頭の中を上滑りしてどこかへ消えていってしまう。薫は違った。私の言葉をまとも過ぎるほどまともに受け取って、咀嚼し、私に投げ返してきた。こんなことは何年ぶりだったろう。というよりも、生まれてこのかた薫ほど私の言葉に耳を傾けた人間はいなかったかもしれない。もちろん薫の従順さは、家庭教師とその生徒、という特殊な関係性の中でのみ生まれ得たものに過ぎないだろう。私はたまさか得た家庭教師という立場を利用して、薫のような優秀な子供には本来聞かせるに値しないような下らない教説を刷り込んで満足を得ているに過ぎないのかもしれない。しかし、たとえそうだったとしても、人心との交流に飢えていた私にとって全ての利己心への反省を措いても薫のような人間の存在が必要なのだと感じられた。私は薫に感謝したい気持ちだった。私は自分が人心との交流に飢えているということすら自覚していなかったのだ。今後もこのような心地よさが継続して得られるのかはわからない。薫は聡明だから、私が実は単なる落ちこぼれに過ぎないという事実を見破るかもしれない。この幸福は今日限りのものかもしれないのだ。だから、それゆえにこそ一層今日の薫の姿が脳中を駆け巡った。来週の訪問まで、この記憶を反芻することで生きられるとすら思っていた。それほどまでに精神的な危機状態にあったということなのだが、それに今日初めて気付いたことに私は自分で呆れ返ってしまった。私の脳髄を甘やかに痺れさせていたのは、実はキャラメルではなく私の年齢の半分しか生きていない少年だった。
私が薫とのやり取りを思い出してささやかな幸福に浸っていると、月に一度も鳴らない携帯電話が珍しく震えた。Iからだ。
「もしもし」
「お疲れ様。今大丈夫か?」
「うん。どうした?」
本当は、滅多に訪れない安らぎを味わっていたところだったのでいささか不満を覚えていたのだが、Iは仕事の上司でもある。大人しく話を促した。
「いや、今日の家はどうだったかなと思ってさ。一応初日だから報告を聞いておこうと思って」
こんなことを言っているが、普段ならばいくら初回の訪問と言えど当日のうちに報告を要求してくることはない。何か別の用件があるに違いないと考えはしたものの、とりあえず私は報告を始めた。忍田薫の人物像、その母親の言葉、帰り際に頼まれたことなどをありのまま伝えた。なぜそんなことまで喋ったのかわからないが、母親に手をさすられたこともIには伝えた。
「ハッハ! そんなことがあったのか。君、珍しく気に入られているじゃないか。母親に気に入られるのはいいことだぜ! 君もようやくこの仕事に慣れてきたということかな。子供の勉強なんか適当に見ていればいいんだ。どうせ俺達の教える子供は最初から点数のとれる子供と決まってる。そういう子供は教師が何も教えなくても勝手に勉強するものさ。それよりも大事なのは親だからね。家庭教師っていうのは、実際は親に取り入ることが肝心かなめだ。俺は金儲けの勉強のために、マーケッターの書いた中身の無い本をたまに読むんだが、商売ってのは物語を売るんだとどの本にも書いてある。商品じゃなくて物語なんだと。これは俺も確かにそう思うね。家庭教師という物語を売ってるんだな、我々は。親達は、子供の成績アップじゃなくて、子供に家庭教師をつけた自分、という事実そのものが欲しいのさ。そしてその家庭教師という物語には、若い男との危険な関係、という奥様がたへの回春の物語もときには含まれているというわけだ。君、よく聞けよ、週一回でオファーがあったこの仕事な、いましがた忍田夫人から電話があって、週五回に増やしてくれと言ってきたぜ! いくら子供が不登校だからって、週五回はやりすぎだ! よっぽど好かれてるらしいな、え! こりゃ傑作だ。よりにもよって、N、君だもんなあ。ハッハ! 勉強がはかどって帰りが遅くならないように気をつけろよ! 旦那にでも見咎められたら大変だものな! 早速明日からも頼まれたから、今日と同じ午後四時から、よろしくたのむよ」
Iのこうした人をバカにしたような態度は今に始まったことではない。私はもう彼の話を聞き流すことに慣れていた。私は生まれてからずっとこうした見くびりに揉まれて生きてきた。自ら笑い声さえあげて相槌を打ったのだ。だから、電話を切って私の心に湧き上がってきたのは、Iへの怒りでもなければ、明日からの忍田夫人とのやりとりを想像しての鬱陶しさでもなく、何よりも薫との楽しい問答が毎日のように行えることへの期待であった。薫との会話においては私はごくごく幼い時以来失ったままの自尊心を回復できるような気持ちがしたのだ。私はなんとしても薫の成績を上げたいと思った。薫を他とは違う特別な人間に仕立て上げたいと思った。初めて私は職業倫理めいたものを得たのだ。結果として私は家庭教師業に就いてから初めて教師らしい使命感を持ったのであり、このことに私自身一番驚いたのであった。
最初に対面したときに抱いた、薫の完全性を毀損することへの恐れは、今となっては消えうせていた。
「ねえ、N君。今日は勉強のあと、時間ある?」
忍田家に毎日通うようになって一ヶ月が経ったころ、忍田夫人が私に言ってきた。
「特に予定はありませんが。進路についてのお話でしょうか?」
「いいえ、違うの。もうあなたがうちへ来るようになってだいぶ経つでしょう? 日ごろの感謝という意味で、お食事でもと思って。もうすぐ夏休みに入るわ。一学期はほとんど出席できなかったけれど、あの子もきっと二学期からは学校に行けるようになると思うの。昨日の夜その話を薫にしてみたらね、二学期からはちゃんといくつもりだ、って言ったの。あの子もN君のこと大好きみたいで、先生のためにも頑張って登校する、って言ってくれたのよ。私嬉しくって。これもあなたがうちに来てくれたからよね。これまでの他の先生じゃこうはいかなかったわ。だから、その恩には全然足りはしないとは思うけれど、せめてたまにはご馳走させて欲しいなと考えているの。男の子の一人暮らしだもん、普段あまり良い物食べてないんでしょう?」
「ありがとうございます。でも、夕飯もいつも頂いているのに……」
「遠慮しなくてもいいのよ。私の料理なんか飽きちゃったでしょう? この辺は意外に色々お店があってね、通りから少し外れたところには落ち着いた美味しいお店もあるのよ。実は予約してあるの。終わったら声かけて頂戴ね」
「はあ」
唐突にまくしたてて、忍田夫人は家の奥へと引っ込んでいった。忍田夫人はあれ以来本当に気安く私のことを家族同然に扱ってくれて、多少ありがたくは思ったのだが、困った気持ちのほうがそれに勝る。どのようにその好意を受け取ればいいのかはかりかねるのである。いっそ、よその家と同様に笑顔を装った厳しい目で見てくれたほうが気が楽だとすら思った。私は赤の他人に上手く甘える術を全く知らなかった。
しかし、階段を上って薫の部屋へ向かう数十歩のうちに、忍田夫人の振る舞いの不可解さに起因する不安は霧散した。指導の楽しみは、完全に私の生きがいになっていた。週五回という頻繁さも、私が他の同世代に三、四年ばかり遅れながらもついに「職業」を得たという実感と満足感を充足せしめた。
もうこの頃には私を待ち受ける薫の部屋のドアは最初から開け放たれているようになっていた。私のほうも、階段を上がりながら薫に声をかけるようになった。
「おーい、来たよ」
「どうぞ!」
薫の様子は最初来たときとは見違えるほど快活になっていた。笑顔にもなれば冗談も言う。ソプラノの声はさらに高く響いた。かといって耳を刺すわけではなく、あくまで少年の声は青く冷たく私の鼓膜を振動させた。振動したのは鼓膜だけではない。音によって視界すら微小に心地よく震えるかのようだった。
だが母親に言わせるとこうした明るさは私以外の人間には見せないらしい。もちろん親を相手に明るく振舞うことに羞恥を覚え始める年齢ではあろうし、私自身の中学生時代もそうだったのだが、私としてはその薫の演じ分けは、私を特別に同類と看做してくれた証拠だと思いたかった。もしそうであれば一層指導に熱が入ろうというものだ。私にとって幸福なことに、薫との信頼関係は日に日に強まるような気がしていた。
その日の勉強がひと段落ついてから、私はこの一ヶ月訊こう訊こうと思って訊き忘れていたことを訊ねた。
「そう言えば、初めて来たときから見かけてたんだけど、この部屋の窓に子猫のキャラクター人形が飾ってあるよな。あれは君の趣味か? いや、なんとなく気になってね」
特に大した意図もなく訊いたつもりだったが、薫は言葉に詰まりながら返事した。
「実は、あれは、ええと……お母さんが買ってきてくれたんだ。丁度、一番街にご当地とコラボレートした専門店みたいなのがあって」
「ああ、その店は俺も見たけど。君がお母さんに頼んだの?」
「いや、別に、そうわけではないんだけど。というか、確かに僕はあのキャラが可愛いと言ったことはあるけど、買ってきてくれとまでは言わなかったんだ。それをお母さんが気を利かせたつもりで、出かけたついでに買って帰ったんだけど、いらないとも言えないし、受け取るだけ受け取って……」
「置き場所に困って窓際に飾っておいたのかな?」
「そう、そう」
薫の態度は、その言葉の中にいくらか嘘が混じっていることを容易に予感させたが、それだけに一層その言葉自体は本当のことしか言ってないのではないかと思えた。狼狽して言いつくろっている振りをして、私に薫の言葉を嘘だと認識させたがっているのではないか、という疑いが私の心に生まれた。ほとんど無根拠ながら、私は、薫は全く嘘を言っていないだろうと思った。薫自身としては、実は自分の言葉を嘘として受け取って欲しいのだ。母親嫌いの彼が、暗に玩具をねだるようなことを忍田夫人に言うだろうか。きっとその事実は、自らに対しても思い出すのにかなりの心理的な抵抗を伴うに違いない。だから慌てているかのような態度で早口で言う。それはとても頭の良い少年がとっさにほぼ無意識裡に行う高度な逆説的演技であった。
いましがたの薫の態度が、あまりに誇張された演技だったため、決まりが悪くなったのか、彼は自ら本音を話し始めた。ただし、比喩として。
「あのさ、先生。日本人がヨーロッパ人になることってできると思う?」
「ヨーロッパ人?」
「うん。アメリカ人でもいいよ。韓国人だって中国人だっていい。アメリカ人になりたかったとしたらさ、まず当たり前だけどアメリカに住むじゃない? そこで英語がアメリカ人みたいに喋れるようになるよね。そして、こまかい手続きは僕にはわからないけど、アメリカ人としての国籍をとったとする。アメリカで買い物をする。アメリカの食べ物を食べて、アメリカ人風の服を着る。顔の造りがアジア人っぽい、っていうんであれば、整形してもいい。でもまあ、今アメリカにはアジア系って沢山いるみたいだから多分変じゃないとは思うけど。でさ、何から何までアメリカ風にかためて、それで日本人がアメリカ人になった、って言えると思う?」
「うーん、どうかなぁ。何をもってアメリカ人とするか、その国の人と言えるか、ってことだよね。確かに難しい問題だね」
私は、薫が何故いきなりこのような質問をしてきたのか理解できなかった。薫は続けた。
「例えばさ、法律上アメリカ人になったとしても、心の中は日本人かもしれないし。アメリカ人のファッションを真似して形だけ変わっても、性格はアメリカ人になれないかもしれないじゃない? 逆に心や性格だけがアメリカ人っぽくなったとしても、法律上の立場とか外見がアメリカ人に相応しくなければアメリカ人として認めてもらえないだろうし、そもそもアメリカ人っぽい心やら性格って何なんだろう。本物のアメリカ人だって沢山のタイプの人がいて、その全部が一応アメリカ人なんだよね。その中には僕たちがアメリカ人っぽいくない、と思っているアメリカ人も含まれてて、結局何がアメリカ人なのかわからなくなってくる」
「ふん。まあ確かにそうだね。それで?」
「何がアメリカ人かわからない、決められない、ということは、逆に言えば、誰だってアメリカ人になれるし、現にそうだ、ってことなんじゃないかと思うんだ」
「じゃあ薫もアメリカ人ってことになるのか?」
「ある意味ではそうも言える、ってことなんじゃないかと思う」
「じゃあヨーロッパ人も? 韓国人とか中国人は?」
「わかんないけど……アメリカ人ほどゆるくはないと思うけど、きっと同じような曖昧さはあると思う」
「ふうん」
はっきり言えば、私は薫の言葉を詭弁としか受け取らなかった。少年には詭弁と雄弁の区別がつかなくなるときがある。薫の年齢でその段階を通過することは、むしろ喜ばしいことだと思った。こうした迷いの通過儀礼は早めに終えておくにこしたことはない。
「僕はね、先生、自分が自分でしかないことが本当に嫌なんだ。自分が、アメリカ人か、ヨーロッパ人か、韓国人か、中国人になれたらどれだけ嬉しいだろう、っていつも想像するんだ」
「日本人のままじゃダメなのかい?」
「日本人でもいいよ。ただ、僕はダメなんだ。僕以外の人間になりたい。もし僕が先生だったらどんなだろうなぁ……」
「きっとつまらないよ。俺みたいなのになるのは、やめといたほうがいい」
「そうかなあ。そうかもね。確かに僕は、先生みたいにはなれないや。先生みたいに上手に教えたりはできなさそう」
「何も教えているつもりはないけどね。君が勉強しているのを眺めてるだけで」
話しているうちに段々わかってきたが、薫はアメリカ人にもヨーロッパ人にも、まして韓国人にも中国人にも興味が無いのに違いない。私のようになりたいというのも恐らく嘘である。ただ、確かに変身願望のようなものはあると思われる。ただしそれは、より良いものになりたいだとかいう欲望とは無縁だろう。そんな簡単なことであれば、薫はとっくの昔に実現していただろう。薫の変身願望は、理想の自己の実現、といった問題とは全く無縁である。そうではなくて、自分が何故たまたま忍田薫であったに過ぎないのか、ということが許せないのだろう。この推測は、私自身の願望を忍田薫の立場に翻訳して彼の心内を想像してみた結果である。薫にはもっと違う意図があるかもしれない。
「そろそろ再開しようか」
私は、この話については何ら薫に与えるべき言葉がないと悟り、さっさと今日の進行予定を終わらることしか頭に無かった。
「あ、その前に、ちょっとトイレ」
そう言って薫が立ち上がったが、急に立ったからなのかふらついて、もう一脚の椅子に座っていた私の上半身にもたれかかってきた。
「おっと!」
私は軽く尻を浮かせながら身構えた。予想していたよりもはるかに軽い肉体が私の胸に転がり込んできた。驚くほどの体の細さ。そのせいで、もっと大きな負荷を予想していた私の体は、いきおい薫の体をむしろ抱くような形になってしまった。色素の薄い髪の毛が視界に映りこむ。
「あっ!」
思わず私は声を上げた。薫の髪の毛が黄金色に見えたからだ。単なる金髪ではない。その髪は、自ら光を放つかのように燦爛と私の目を射た。もちろんこの金髪は、落日間近に放たれる愚直な赤色光が、猫のキャラクター人形の飾られたこの部屋の窓から忍び込んで、ほんのひと時の間だけではあるが、いまや私の両腕に収まってしまった真っ白い肌を持つ少年に西洋式天使の神秘性を付与した結果に過ぎない。つまりこれは太陽神の戯れだった。だが戯れによって思いもよらない秘密が我々の眼に開示されるということはあるものだ。このとき薫は天使以上に天使だったし、処女以上に処女であった。
ふっ、ふっ、と早くなった薫の吐息が耳にかかる。頬と頬は産毛同士が触れ合うような距離にある。私は自分の胸に生暖かい命の温度を感じていた。柑橘系の制汗剤の匂いと、シャンプーの匂いとが交じり合って私の鼻腔を通り抜けていって脳髄まで浸していった。薔薇の香りのシャンプーは、恐らく母親と同じものを使っているのだろう。私は一瞬酩酊したような心地を味わった。しかし私を酔わせるのはこれらの人工的な匂いではなかった。私はさらに自らの嗅覚を探った。するとそこに立ち上ってきたのは、汗でほのかに湿った人間の肉の匂いだった。私の腕の中で小動物のように震えながら呼吸しているこの少年の血と肉と汗から、温めたミルクのような、子供の股ぐらのような、なんとも蠱惑的な匂いが発せられているということは、私にとってどんな密教よりも神秘だった。少年を抱いたまま、私と薫のどちらもが動き出すことはなく、時間は縫い止められていた。この超時間的な時間の中で、何度金色の匂いを嗅ぎ、目で撫でたかわからない。数秒なのか、数分なのか、それすら判然としない。だが薫は、成人した同性の他人に女のように抱きしめられているという状態の特殊さにようやく気付いたようにして急に体を離し、
「ごめんなさい!」
と部屋を小走りに出て行った。薫が部屋を出て一人になってやっと気付いたのだが、私は勃起していた。この瞬間だけはインポテンツが治ったのである。私は不思議な気持ちでふくれあがった股間を見つめ、硬直化したペニスの心地よい甘い痛みを堪能していた。勃起することの嬉しさ、ありがたさを、インポになって以降初めて痛感したと言って良い。
きっと私のこの肉欲の滾りが薫の正気を呼び戻したのだろう。あれほど密着していて、下腹部に違和を感じない筈がない。
少し長いトイレから戻ってきてからは、薫は何事もなかったかのように勉強を再開したので、私もそれに従った。
忍田夫人は、勉強の時間が終わると早速私を連れ出そうとした。一目で余所行きとわかる格好で、夫人の年齢よりも二十歳は若い女子大生でも着ていそうな服を着ていた。絹のような生地の薄いブラウスに、細いプリーツの沢山入った黒色のスカートを着ている。彼女の弾んだ気持ちというものが私にも感得せられたほどだったが、ただでさえ忍田夫人の人間性のことが不可解である私にとって、今日の彼女の浮き足立った気持ちは一層不可解である。
「N君、お疲れ様。じゃあ行きましょうか。薫君、お母さんたち出かけてくるからね」
二階の自室から出てこない薫に対して、玄関から忍田夫人が声をかけた。返事はない。
「彼も一緒じゃないんですか」
「あの子、本当に外に出ないのよ。あなたは意外に思うかもしれないけれど、外食なんてもう一年以上行ってないの。大丈夫、ご飯はいつも通りリビングに用意してあるから、私達がいなくなったら勝手に食べるでしょ」
最初から薫を誘う気などなかったようだ。
私と忍田夫人は新河岸川沿いを歩いた。川べりには涼しげな風が吹いている。向こう岸を歩く家族の下駄の音や、密やかな話し声などが聞こえる。川沿いの焼肉屋が、甘みを帯びた大蒜の匂いを垂れ流していた。
通りに出ると、タクシーが呼びつけてあった。
「初音屋まで」
店までは車を使う必要などなかったのではないかと思えるほど、あっという間に到着してしまった。趣のある大きな料亭だ。料亭とは言え座敷ではなく、ホールにテーブルと椅子が並んでいて、西洋文明が日本に輸入され出した頃の、無理矢理な折衷が未開さを醸しながらも不思議に高度に文化的なあの様式を保っていた。
「明治元年からあるんですって」
私のような貧乏人は自分からは絶対に入らないような店で、出てくる料理もどうやって食べればよいのかわからないようなものばかりだった。忍田夫人から食べ方を教わりながら、なんとか格好だけは食べた。
忍田夫人は高そうなワインを飲みながら息子への愚痴と夫への愚痴を、つつましくもしっかりと披露した。
「私ね、笑わないでね、小さい頃から大学を卒業するまで、ずっとお嫁さんになるのが夢だったの。ショートケーキみたいなお家に住んで。一人だけ子供を作って。ねえ、本当だったら今夢が叶ったのを喜ばなきゃいけないのに、何だか孤独だし不安なの。どうしてかしらね」
自嘲げを装って言うのだが、要するに愚痴なのだ。しかしその愚痴がただならぬ愚痴であったことに、私は、夫人の手が私の手を触り始めた頃になってようやく、遅まきながら気付いてしまったのであった。
私は酒にばかり手が伸びるようになった。無論、夫人の手をさり気なく払いのけるためである。しかし私がグラスから手を離した途端に、彼女はおもむろに手を重ねてくる。自然、何度も酒に口をつけることになる。夫人が殆ど飲まないうちにワインのボトルが空いてしまい、結局、店を出る頃には前後も覚束なくなった。夫人が店員に言いつけてタクシーを呼び、再び車で移動し、どこかの布団に入り、寝て起きると、枕元に書置きがあって、
「昨日は楽しかった。ありがとう。精算はしてあります。駅まで歩くと遠いから、タクシー代も置いておくね 忍田」
起き上がって周囲を見渡すと、ホテルの一室だった。わけもわからずチェックアウトし、顔の見えないフロントにタクシーを呼んでもらった。左右を仕切られた待合テーブルで十分待つと、六十歳前後の田舎者じみた運転手が私の名を呼んだ。本川越駅まで乗ったが、忍田夫人が置いていった金は、まだ八千円以上余っていた。太陽が責めるように私の身を照らしている。
帰りの西武新宿線の車中で、酷い居心地の悪さを感じていた。罪悪感だ。一体誰に対しての? 忍田夫人への? そんなはずはない。記憶はおぼろげだが、忍田夫人が私を連れ出したのだ。誘惑されたのは私のほうであるはずだ。じゃあ、忍田夫人の良人に対してだろうか? まだ会ったこともないのに、そんなバカなことはない。
当然、薫への罪悪感だった。しかしこの罪悪感は、教師としてのそれではなかった。生徒の母親とセックスしまったらしいことへの罪の意識は欠片もなかったのだ。では何故私は薫に悪いと思ってしまうのか。いくら考えても釈然としなかった。釈然とせぬがゆえに一層居心地は悪かった。
結局その日はずっと気分が優れず、昼間から、普段飲まない酒を、まだ痛む胃にまたぞろ流し込み、最悪な酔い方をして寝てしまった。むろん最悪の気分だったからだ。
土日二日間の休日を挟んで、また忍田家への出勤日になった。丸二日間、ずっと忍田夫人との事件のことを振り返っていた。私が彼女とセックスをしたことが疑わしく思えてきたからである。
まず、そもそも記憶がはっきりとしていない。状況から見れば確かにセックスをしたという蓋然性が高いのではあるが、だがセックスそのものの記憶はない。ベッドの中に入った記憶はあるが、単にそのまま眠っただけではないのか。その場合忍田夫人には、誘いに乗っておきながら要求に応えず悪いことをしたということになるかもしれないが、いくら酔っていたとはいえ、セックスをした記憶が丸ごとないというのはおかしい。
その上、私はインポテンツである。あれだけ大量に酒を飲んで、そう簡単にセックスができるとは思えない。きっとふらふらになった私は、忍田夫人に連れられるままホテルに入り、服くらいは脱いだかも知れないが、そのあと彼女をおおいに失望させたに違いない。普段から勃起しない私が、セックスなどできる筈がない。
そう考えると、この二日間私の頭を割らんばかりに占めていた罪責感が、かなり緩和されてくるのだった。薫に会わせる顔がないとまで思っていたが、今私は誰に対しても私の無罪を主張できるような気でいた。ただ心配なのは、その日、私が一時的にせよインポテンツから快復していたという事実である。薫と不意に抱擁し合ったときに勃起したペニスが、また勃起の快楽の味を思い出し、薫と似た忍田夫人に対しても反応を示したかもしれない。その可能性も全くないとは言えなかった。
だが、昨日のうちに私は自分のペニスが勃起できるか実験してみたのだ。結果は、できなかった。近隣のツタヤで十枚まとめて借りた忘れ得ぬ女優達のアダルトDVDも、高田馬場のラムタラで購入した電動非電動を問わない様々なる意匠を備えた自慰用具も、私のペニスを勃起せしめるには至らなかった。己のペニスが勃起しないことは世のインポテンツ患者にとって悲しむべきことかも知れないが、この時の私にとっては祝うべきことだった。依然として私は勃起できないのだ。勃起できないということはインポテンツが治癒していないということである。ということは忍田夫人に対して勃起した可能性はぐんと低くなる。私はこの実験によって、多大な安心を得た。
とは言え不可解なのは、ではなぜ薫に対しては勃起できたのか、ということである。無論、私が実は自ら知らないうちにゲイになっていたのではないか、という可能性も考慮した。しかし二〇年以上性的には大多数の男と変わらない有様で過ごしてきた私にとって、男に対して性欲を催すなどということはどう頑張っても不可能事だった。恐らくインポを治すよりも難しい。美少年もののアダルト動画をわざわざインターネットからダウンロードしてみた次第だったが、駄目であった。
しかしながら、差し当たっての不安はこれらの実験によって薄れていた。私はいつものように忍田家を訪った。
「あら、N君。今日は少し早いのかしら」
忍田夫人は平然と私を迎えた。
「あの、先日のお金なんですが……」
とっさに出たのは、ホテルで実際何が起こったかについての問いよりも、タクシー代の釣銭のことだった。夫人は私の耳元で囁くように言った。
「とっておいて。気にしないでいいの。それより、また良さそうな時があったら……ね」
また後頭部で鳥肌が立った。良さそうな時があったらなんだというのだろう。
「あ、そうだ。ごめんなさい、今日は私出かけるの。今日から姉が東京に出てきているらしくて、食事する約束なのよ。だから、薫のことお願いね。もちろん、夕食代は薫に渡してあるから」
「そんな、悪いですよ」
しかし夫人は私の言葉を無視し、
「薫君。夕御飯、先生と二人で食べるのよ」と、階段越しに薫へ声をかけた。そして、
「じゃ、よろしくね」
と出かける仕度をしに引っ込んでしまった。私は薫の部屋へ入っていった。
「やあ。先週出した英語の問題、どのくらいまで進んだ?」
「うん、全部終わったよ」
「全部?」
先週の金曜日に、問題集のページを指定しておいたのである。だが、まさか全て終わっているとは思わなかった。これから一週間かけてやる単元だと伝えておいたからである。私は一応薫のノートをチェックした。
「へえ、本当に終わってる。頑張ったね」
「ありがとう。あとね、こないだ薦めてくれた本、読んだよ」
薫は、勉強の話などそこそこに、雑談がしたかったようである。
「何だっけ。ああ、ショウペンハウエルか」
「そう。お母さんに買ってきてもらったんだ。クレアモールの紀伊国屋で。すごい面白かった!」
私はこの少年に読書というものを教えたかった。だから、『読書について』を薦めたのである。なぜショウペンハウエルかと言えば、まず現世を否定するモメントを教えたかった。それが悪いことではないと肯定してやりたかったのだ。無論、ただ否定するだけでは良くない。否定した先に自らの価値観を作るという思考様式を教えたかった。それにはショウペンハウエルが最適だと思えたのだ。しかしこれは私の独断に過ぎない。ショウペンハウエルの現世否定を、まだ幼い薫に教えることは、ひょっとしたら思考の幅を狭めることに繋がるかもしれない。家庭教師歴三年の中で、私は初めて教育の怖さをおぼえていた。積極的な教育とは常に独断に過ぎないのだということを感じ始めていた。私は単に薫を自分の価値観に同化させたいだけかもしれなかった。それは、薫の完全性を破壊する無粋さとはまた違っていた。もう一人の私を作ろうとする、私の暗いエゴイズムである。だが、薫の興奮した様子は私の不安を打ち消した。彼が全く私の予想を裏切る読み方をしてくれたからだ。
「すごく、何かに怒ってる人だね、ショウペンハウエルは。昔の本だから、何がそんなに許せないのかよくわからなかったけど、ところどころ笑えて面白かったよ。古典語を完全無欠な言語なんて言ってるところとか、大げさだよね。それに、結構酷い罵倒してて、読みながら吹き出しちゃった」
そう言ってさぞ楽しそうに笑う。私はいたって真面目な気持ちでこの本を薦めたのだが、薫の笑顔が、ショウペンハウエルの真面目腐った顔と一緒に私の憂愁までも半ば嘲笑気味に明るく吹き飛ばしてくれるような気がして、爽やかな心地を味わった。そして私は一層この少年のことが気に入ってしまった。
「あと、ここ! 《当書店近刊案内。理論、実践かねあわせたる科学的生理学、病理学、治療学ついに出現し、風気鼓脹の名によって知れ渡りたるガス現象究明に成功す。該現象の有機的因果的連関、存在と本質、しかのみならず該現象を制約する内外の発生的諸契機の一切、さらに加うるにその徴候と病状の一切、これらすべてを、全人類の意識ならびに学問的意識に対して、体系的に叙述す。フランス書L'art de peter〔放屁術〕の意訳。補正的注釈、説明的付説つき》だって。こんな広告、本当にあったのかな」
これは、当時流行っていた大げさな誇張的文体を批判した箇所である。確かに一種落語じみた面白さがある。実はショウペンハウエルを読み違えていたのは私のほうかも知れないと思わされた。実際、彼の文章には、ドイツの思想家にしてはやたら軽快なところがあるのだ。
しばらく本の話を喋ったあと、もう今日は教えることが何もないことに気付いた。薫は今週予定していた部分を独学でほとんど完全に理解してしまっていた。そこから先は、私の予習が追いついていないので進めることができない。どうしようか思案していたら、以前忍田夫人に言われていたことを思い出した。
「そうだ、今日はもうすることがないから、外に散歩でもしに行くかい? お母さんからも、外に遊びに行ったりしていいって言われてるんだ」
「外に出るの?」
もしかしたら嫌がるかもしれないと思ったが、
「いいよ、行こう」
意外にも薫はあっさり承諾した。だが、それきり黙って動こうともしない。何か言い出そうとして言わない。
「どうした? なんか他にすることでもあるの?」
「いや、そういうわけじゃないんだけど」
手のひらを開いたり閉じたりしている。これは薫の癖なのかもしれない。やがて、口を開いた。
「あのさ、実は、変なこと言うようだけど、僕、服の趣味がおかしくて」
「おかしい?」
「今まで、外で着たことはないんだけど、たまに隠れて通販で買ったりしてるんだ」
「へえ。今は未成年でも通販できるんだ。どんな服?」
訊くと、冗談めかしてクローゼットを開けて、袖の丈が短いシャツと、やたら短い半ズボンを取り出してきた。
「こういうの」
「こういうの、って……これ、ちょっと小さすぎないか?」
いや、小さいというよりも、単純に女物である。だが、私は敢えて気付かない振りをした。
「試してみたことはあるけど、普通に着られたよ。今日は暑いし、こういうのでもいいかも、って思ったんだけど、どうかな」
明言しないが、薫には女装願望、女性化願望のようなものがあるのだろう。自分の容姿に対して自覚があり、なおかつそれを活かす方途についても鏡の前で常々想像をめぐらせているのに違いない。私は最初、教育者として考えねばならぬと感じた。それも極めて現実主義的な教育者としてである。ただでさえ薫は社会と馴染まない。その上さらに女装癖まで加わってしまえば、薫自身の疎外感も一層増すし、社会のほうだって彼を受け入れはしないだろう。当然、女装趣味者のコミュニティというものもあるだろうが、女装が好きだからといって必ずしもその集団に入り込めるわけではない。いかに薫が女装したがっても、ここは無理やりにでも押しとどめるのが教育者の態度ではなかろうか。パターナリズムと言われてもいい。そもそも薫には父が不在も同然だったのだ。ここで私がほんの少し父のように振舞ったとして何が悪かろう。父の代理こそが、雇い主である忍田夫人からも求められた役割のうちの一つではなかったか。
しかし、このような考えは私自身が自分の心に向けた建前に過ぎないと察知した。私は、そのような倫理的な教育者ではなかった。むしろ薫の教育にあたっては積極的に反社会性を教え込もうともくろんでいたからだ。それが実際に薫の心に明るさをもたらすからには、そうすることは当然だった。ということは、私が薫の女装に抵抗感を催すのには別の理由がある。それは、どうやら私自身の女性嫌悪からきているようだった。薫が女物の服を取り出したときに、私はやるせない憤りを抱いていたのだ。なぜ女なのか。どうしてわざわざそんな服を着ようとするのか。薫は女でもない、男でもない、何者でもない天使に他ならないのだ、そう熱狂的に訴えたかった。無論、そんなことを口に出すのは馬鹿げている。だから私は、女なるもの全てに対するこの憤りを、次のような言葉にして発したのだった。
「やめたほうがいいよ。男には似合わないだろう」
すると少年は、言葉が腹にでも刺さったかのように動きを止め、床を眺めた。眺めた先の床には血が滴っているのだろうか。まさかこんなことを言われるとは思っていなかったのだ。服を手にかけたまま、突っ立ったまま、じっと黙っている。私は今まで一度も薫を叱ったことがなかったが、もし怒鳴るなりしたらこういう状態になるのだろうなと思った。
「やっぱり変かな」
怯えたように薫がつぶやいた。幼い薫のことだから、先ほどの言葉一つで、私との関係がもはや崩壊してしまったと思い込んでいることだろう。そして自分の女装趣味に対してまでも理由のよくわからない罪の意識を抱いているはずだ。私が薫をいじらしく思わなかったはずがない。しかし、より強く考えたのは別のことであった。
女に対して真の意味で軽蔑を向けるならば、その態度は男や女という概念そのものを相対化することにならねばおかしいのではないか? 女が本当にどうでもよいのなら、女であることもまた許容されねばならないのだ。なぜならそれは、どうでもよいことなのだから。何か或るものを無価値と看做す人間は、その或るものが存在しようがしまいがどちらでもよいのである。その或るものの存在を許そうとしない態度は、逆にかかるものに縛られている証拠だ。そこから自由にならねば、真の意味で対象を相対化したことにはならない。ということは、一切の否定者は、一切をよしとするのでなくてはならないのだ。何かを否定することは、それを無価値と看做すことだ。それが無価値だということは、そのものが存在していようと何ら意味がないのである。女なるもの、また同様に男なるものは、それぞれ無価値であると私が看做すからには、同時にそれらは存在してもしなくてもどうでもよい。なんら薫に対して変化をもたらさない。表面上は影響力があるように見えても、実のところは何ら力を持たない。
何故私がそのように考えたかといえば、当然忍田夫人との出来事がどこか不明瞭な色で私の心に影を兆していたからである。この影は、私自身がどんなに言葉で問題ないと片付けようとしても、不穏な存在感を主張していた。私はそれを否定したかった。つまり、そんな影などは存在しないも同然だと思いたかったのだ。だから、夫人とセックスしていようがしていまいがそのようなことは別段問題ではないのだ、という風に自らを肯定したかった。そのためには、薫の女装も肯定してやる必要があった。否定と肯定は、一様に対象への無関心からしか訪れないのだった。
「まあでも、一度着てみるのはいいかもね。玄関で待ってるから、色々店が閉まる前に出よう」
そう言って私は言葉通り待っていたのだが、薫が着てきたのはやはり女物だった。よほど着る練習を密かにしていたのだろう、不自然なところはほとんどない。ただ、短い袖や裾から露出した肌のみが不可解だった。薫自身が成長途上ということもあるのだろうが、それらは男性性も女性性も帯びていない。ただのなめらかな肉と皮だった。体毛は全て処理してあるのか、それとも生えていないのか、つるりとしていた。もちろん色は白く、青い血管が透けて見えるようだった。青色は薫によく似合う。
「日差しが結構あるみたいだけど、大丈夫か?」
靴を履きながら聞いてみたが、
「うん。日傘持ってくから」
と、横にかけてあるレースの日傘を取った。母親のものだろうか。薫はスニーカーを履いた。
日傘を差して新河岸川沿いを歩いていく薫の姿は、印象派の絵にでもなりそうだった。川べりにはベンチがあり、そのすぐそばには誰が育てたのか花が咲いている。花の知識がない私には、それがなんと言う花なのかわからない。その花に薫がしゃがみこんで手を触れた。日傘の優美なレースが、花をしもべにした王女のように薫を仕立て上げていた。つい一年前まで彼は小学生だったはずなのだが、もうまるで大人のように見えていた。思うに、服装が女化しているからだ。女性性を纏うがゆえに必然的に成熟せねばならないのだ。私は、あの服を認めたことを早くも後悔しはじめた。成熟するということは不完全性を増すということだ。未成熟であるということは完全であるということだ。何者かになるなどということは心底馬鹿げている。それは自ら完全性を擲つことに他ならぬからだ。
「外に出たの久しぶり。何だか緊張する」
「そうなのか?」
「緊張するっていっても、なんか落ち着かないっていうだけなんだけどね」
ただ外出するだけで緊張するという感覚は、確かに引きこもったことがない人間にはわからない。
その日はずっと晴れ通しで、家を出る頃は丁度風も凪いでいて極めて暑苦しかった。長時間歩くのは得策ではない。だからといって別段目的があって出たわけではなく、ただ歩くために外出したのだから、歩かなければ意味がない。意味がないとはいっても、そわそわしている薫はいつもより口数が少なくなり、歩くうちに我々の間に会話が無くなってしまった。無理にでも何か喋ろうと思った。このままでは徒に消耗するだけである。
「あそこのベーグル屋、いつもここ通る度に気になってるんだ。旨いのかな?」
年をとった観光客で賑わう一番街に、洋風に建てられたベーグル屋がある。
「さあ、外に出ないからわからないなあ」
引きこもりの少年相手に全く気が利かない話題を振ってしまったものだと反省していると、当のベーグル屋まで店じまいを始めてしまった。私達が目の前に来る頃には《CLOSED》の板がかけられる。
「まだ六時にもならないのに、もう店じまいか」
さらに通りを進む。学生服を着た少女達や、少年達もいる。もしかしたら薫の同級生もいるのかもしれない。そう思い、
「そう言えば、クラスメイトに会ったりしたら大変じゃないか? 大丈夫かい?」
と訊いてみたのだが、
「中学になってから二、三回しか学校に行ってないから、誰も顔を憶えてないよ」
「小学校からの知り合いは?」
「僕の顔なんて忘れてるよ、多分。もしものときは、日傘で顔を隠すから大丈夫。それにしても暑いね」
十分と少し歩いただけなのだが、薫のシャツの背中には汗が浮かんでいた。それを目にして、私は鬱勃とした欲望を感じ始めた。温かく湿った薫の肉に触れてみたいと思ったのだ。
「久しぶりに歩いて疲れただろう、どこか休憩できる場所でも探そうか」
「疲れてはないけど……うちわか何かあるといいかな」
「わかった。もう少し歩くと、おにぎり屋みたいな店があるんだ。そこでお八つでも買って、近くの神社で涼もう。うちわはその辺で買うよ」
私は、そう言いながらさりげなくほのかに濡れた薫の背中を押した。掌に広がる温かい肉の感触。ほんの一瞬そうしただけだが、私の手は熱いくらいに感じていた。
道すがら、和風雑貨の店でうちわを買った。二枚買って、各々扇ぎながら歩いた。竹を使ったうちわなど、触るのも見るのも久しぶりだった。プラスチックのうちわと違い、強く扇ぐには適していないようだ。私は物足りなさを感じたが、薫がゆるゆると微風を楽しんでいる様は、男とも女とも言えない容姿や、その幼さと完全性のアンバランスさとも相俟って、奇妙なエキゾティズムを醸していた(そもそも、「本物のうちわ」自体が私にとってはエキゾチックだった)。
蔵造りの並びを抜けて少し歩いたところに、ワッフルの看板が見える。この店ではワッフルとほうじ茶が主な売り物なのだが、おにぎりもある。しかし、夕食も別で食べるのだからと、薫がワッフルを希望した。ほうじ茶とセットで買い、ぶら提げて神社の敷地に入った。
神社には沢山の客がいた。街中の神社なので、人の出入りが多いのだ。しかも困ったことに、座れるような場所がない。私たちはさらに歩いた。商店街の端辺りまで来たところにマンションがあって、その入り口手前に腰掛けられるようなスペースが設けてあった。風情も何も無い場所だったが、薫が、
「ここで良い」
というので座った。ワッフルを食べ、ほうじ茶を飲んだ。旨いが、二人して特に感想も出ない。しばらく無言で通り過ぎる人々を眺めていた。塾帰りの子供を迎えにくる母親。手をつないだ老夫婦。買い物袋を提げた若い男女。女子高生の集団。男子中学生の集団。ここは、都市と生活のあわいであった。誰もが互いに興味を持たない人ごみでありながら、しかしその各々は確実な生活の一部として消費を演じている。匿名でいることと、固有名を持つことが、不思議に同時に成立している。どういう仕儀か人生に流されるまま匿名の存在と成り果ててしまった私は、このような人の流れを心地よく思わないはずがなかったが、薫はどうなのだろうかとふと思った。薫には匿名でいたいという願望があるはずである。しかし同時に否応無く固有名としての忍田薫というものがあるはずである。家族との関係の中で、忍田薫は無理やりにでも存在させられてしまう。また、その反対に固有名の忍田薫に対し薫自身が期待することもあるのではないか。例えば、忍田薫のままで女になってしまいたい、というような。匿名の女装少年としてではなく、他ならぬ忍田薫として、女以上の女になりたいという願望がないとは言えないのではないか。
そうしたことを考えていると、薫が口を開いた。
「こうやって道行く人たちを眺めてると、羨ましいような気持ちになるね。この人たちには毎日の生活がある。朝起きて、家族におはようと言って、朝ごはんを食べて、学校や会社に行く。帰り道に友達と遊んだりして、家に帰るとただいまと言って、晩御飯を食べたりテレビを観たりする。お風呂に入って、何かしら話したり、マンガを読んだりして、布団に入る。たったそれだけの生活が、僕にはなにか羨ましくて、とても良いもののような気がするんだ」
「でも君は、そういう生活をしている具体的な個人にまで好ましい感情を持ってるわけじゃないだろう?」
「うん。確かに、そういう良い生活をしている人が同時に、僕から見れば何の興味も持てないような人であることが多い。だから、なんで自分がそんな普通の生活に憧れるのかわからないんだ」
薫が生活への憧れを持っていることは、私には非常に意外なことだった。もう少し歳をとらねばそういう気持ちは生まれてこないと思っていたのだ。というのは、私自身がそうだったからだ。少年の時代には生活を否定したがるのが平凡な人間で、またその同じ人間は青年時代を経て徐々に生活というものに憧れ始めるものだ。無論人が追い求める生活とは人それぞれに違うものである。貧しくとも幸せな家庭もあれば、お菓子の家に住みながら不幸な家庭もある。
「僕はね、先生」薫が言った。「誰か、ちゃんとした会話のできる相手と暮らすことができたらいいなと思うんだ」
「ちゃんとした会話?」
「だって、学校にいる人だとか、家族だとか、誰とも会話なんてできないよ。あの人たちはみんな独り言を言ってるだけだ。愚痴を言ってるだけだ。相手の愚痴を笑って聞いて、その負債を受け入れたからには、その分自分の愚痴も聞いてもらう権利がある、って考えているだけなんだ。独り言の押し付け合いなんだよ。それなのに、みんなの独り言の代わり映えの無さ。みんな自分の言葉は自分だけのものだと思って喋っているけれど、みんながみんな同じこと喋ってる。そんなの会話って言わないよ」
薫は確かにまだ世間を知らない。だからこそ「みんな」などという巨大な代名詞が使えるのだ。しかしながら、今の彼の言葉には端倪すべからざるものがあった。人の会話の「キャッチボール」なるものは、実は自分の独り言を押し付けあうだけの取引関係である。利害関係である。その意味で、人は他人を常に手段として、道具としてしか扱えない。これは素朴に響く詠嘆だが、しかし私の実感を強く刺激したのは事実である。いわば私の身体が薫の意見に同意してしまったのだ。
「じゃあ、会話のできる相手ってたとえばどういう人?」
なんという気もなしに聞いてみたが、薫は真面目な顔でこう答えた。
「先生、僕はあと何年か学校へ通って、高校まで卒業したら、そしてちゃんとした大学に入れたら、もしかしたら一人暮らしができるかもしれないと思ってるんだ。お母さんやお父さんがどう言うかわからないけど、きっと通学時間のせいで勉強ができないから、とか言えば、どうにか説得できると思うんだ」
「そうなのか。じゃあ、尚更二学期からは学校に行かないといけないな」
「もちろん、がんばるつもりだよ。先生は、今のアパートから引っ越すつもりはないの?」
と、私の意向を聞いてくる段になってようやく、私は薫が私と生活したがっているのだ、ということに気付いた。
そういう気持ちを薫が持っているということは、まずは嬉しいことだった。私と薫の絆は、一方的に私が思い込んでいるだけのものではないと、はっきり確認できた。私とて、薫との共同生活ならまんざらでもない。というより、喜んで引き受けたいくらいだった。しかしすぐ次の瞬間に、私の脳裏に浮かんだのは、「数年後」の薫の姿である。時間は、薫の完全性を奪い去ってしまうだろうと思った。薫のソプラノは消えてなくなり、天上の存在は地上の動物と化し、体毛を持て余すかもしれなかった。骨格は発達し、あの子供の股ぐらのような芳香は酸味がかった私自身がときに発するあの体臭に変化するかもしれなかった。そうしたことを、私は想像するつもりではむろんなかった。ただ、そのような時間の跳躍は、あたかも未来の世界から私の頭の中に勝手に進入するが如く、突如として脳内に映じてきたのだ。私自身、大変困惑した。そしてその困惑は、目の前の薫ですら読み取れるほどあからさまだった。恐らくは、私の困惑が何に由来しているかも、読み取れない薫ではなかったろう。薫はしばらく絶句し、ゆっくりと立ち上がった。そして往来を再び歩き出した。私は急いで薫の隣に並んだ。
「どうしたんだ、いきなり?」
自分自身白々しいと思いながらも、こういう無意味な言葉で時間を埋めないことには気まずすぎた。私たちは表通りを行かず、住宅街を歩いた。従業員のいるマルヒロの裏口を、右手に見ながら黙って歩いた。やがてベーグルの店が見えてきた。
「あれ、さっき閉まっちゃった店の支店じゃない?」
目ざとく薫がカンバンを指差す。
「へえ、そうなのか?」
何となくふらふらと店に吸い寄せられ、ベーグルを三つと、コーヒーと、オレンジジュースを買った。私が二つ食べるつもりである。結局、こんなものが晩飯となってしまいそうであった。また座る場所を探さねばならなくなる。少し歩くと、街中だというのに小さなお稲荷さんがあって、その向かいに座れる場所があった。植え込みが回りにあったので、
「蚊がいるかもしれない」
と言ったら、薫がトートバッグの中からスプレーを取り出した。家に置いてあるものを持ち出してきたのだという。
「用意がいいな」
そして座ったが、薫はまだ無言で、買ったばかりのベーグルも食べる様子がない。仕方ないので私も食べない。このような気まずさは、これまでの人生でも度々経験してきたことだ。私は人との間に会話というものを成り立たせることができない。例の「キャッチボール」というものができないのだ。だから、付き合う友人はIや忍田夫人のように自分ひとりが喋ればよいという人間ばかりになる。そういう人間は悪人が多いので、自然と私のほうから交流を断つようになる。Iが例外なのは、悪人ではあるが、いつも私にメリットを与えることを忘れないからだ。そうして、もう辞めたいと思う友人関係が、腐れ縁へと腐蝕していくのだ。私には、他人へ相対する態度に欠陥がある。この薫の無言も、また私の欠陥が原因なのかと思っていた。しかし違った。そもそも薫自身、「キャッチボール」なるものを信じていない人間だった。この沈黙は、薫の言葉が彼の体内を巡っている徴候であり、彼のはらわたで温められた言葉が、口腔から逃れ出るまでの間に起こる現象であった。そして小鳥のような薫の唇が開いた。
「先生、僕は先生にまだ色々と教わりたいことがあるんだ。高校受験が終わっても、大学受験が終わっても、多分先生は一生僕の先生だよ」
「そうかな。これから色々な経験をすれば、もっと尊敬できる先生に出会えると思うけれど」
「そうじゃないんだ。なんて言えばいいのかわからないけれど、もうN先生以外に信じられる先生は、この世にいないっていう予感がしているんだ。そんな人と、僕は毎日暮らしたい。先生が僕の家族だったらよかったのに」
薫の口調には切ない調子があった。まるで失恋を予感している少女のようだった。一方私は、現時点の完成された薫にしか、天上の世界を見出せなかったのだった。薫が私のことを家族であればよかったのに、と願うのと同様に、私は、薫がこのまま年をとらなければいいのに、と身もふたもないことばかりを念じていた。私が苦しく応答しようとしている様子を見て、少年は自分の願いが拒否されることを察知したようだった。しかし彼にはまだ言うべき言葉が残っていた。
「先生、先生が帰るといつも、お母さんが先生の話をするんだ。話といっても悪口じゃないよ。逆に、とても褒めてる。僕だけじゃない。お父さんにまでN先生の話をしているみたい」
最初私は、薫が何を言おうとしているのかわからなかった。
「でもね、なんでかわからないけれど、先生の話が原因で喧嘩になったみたいなんだ。凄くうるさく騒いでたよ。僕、寝られなくて迷惑だと思ったな」
自分の知らぬところで、自分が言い争いの火種になっているというのはいい気持ちではない。まして、顧客の夫婦である。私は、自分の背中からどっと汗が湧き出してくるのを感じた。シャツが濡れていく。
「なんでお父さんは、先生の話で怒ったんだろうね。やっぱり、焼餅でも焼いたのかな? お母さんが先生のことをあんまり褒めるものだから」
私は薫が何を知っているのか、とても気になった。このタイミングでこの話題を持ち出してくること自体、示唆するものが大きい。きっと薫は全て知っているのだ、という予感がした。私は、しきりに額を拭った。冷たい汗が次々に垂れてくるのである。私は、忍田夫人とその良人が、どういう喧嘩をしようが構わない。それでクビになることは、確かにつらくはあるが、仕方がないと思っている。私がこのように一つの家で召抱えられ続けているということのほうが例外なので、クビになったあとはまたIの居る事務所に通えばいいだけの話だ。そうしてまた屈辱を垂れ流せばいいだけだ。事務所でさえダメだというのなら、恥も構わず実家に逃げ帰ればいい。結局、私の職業観とはその程度のものだった。私には教育者たる資格など全然ないし、その資格を得ようと思ったこともまるでないのだった。しかし、雑巾を絞るように流れ出しているこの汗は、この焦りは、別のところに由来していた。私は、完全な存在に、今まさに裁かれつつあると感じていた。わっ、と泣き出して懺悔したいような気持ちだった。この短い数秒の間に、何十回逡巡したかわからない。瞬間的に喉の水分が蒸発したように感じられた。乾ききった声帯は、真空状態になり、密着し、声という声が封じられてしまった。言おうと思っても、何も言葉にならないのである。そもそも、一体私は何を言うつもりなのか? 言葉にして正しく語れることなど、何一つありはしなかった。私の身の潔白を、眼前の天使に筋道だてて紹介しようとしても、そこに生まれるのは薫の新しい疑念だけである。あるいは、むしろ薫は私の罪を確信するだろう。それどころか、私が嘘をついていると思うだろう。ラブホテルに入って、そこから先の記憶がないので、きっと君の母親とセックスはしていない、それに私はインポだ、安心しなさい。そんな馬鹿げた話を信じる頓馬がどこにいよう。しかも、薫は私の勃起を直に知っている。私がインポであるという説は、もはや薫にとって虚偽なのである。
「先生?」
訝しげに薫が私を見ている。その言葉が引き金になったかのように、私は飛び跳ね、口から出ないまま私のはわらたを対流している不定形な言葉の代わりに、座っている薫の胴体にしがみついた。我知らず、涙すら流れた。その時、私の頭を撫でる手が差し伸べられた。幻聴かもしれないが、私は撫でられながら次のような言葉が頭上から降ってきた気がした。
「大丈夫、先生が落ちこぼれであることは全部知ってるよ、だから僕がしっかりと国立の大学を卒業して、時間の余裕も給料もある、或る程度の仕事に就いて、死ぬまで先生のことを守るつもりだよ。だから、きっと僕と先生は一緒に生活すべきなんだ」
そして、私は、露出した薫の太ももに濡れた頬を擦り付けた。男のものとも、女のものとも言えないその滑らかな太ももに。そして私は天使の股ぐらの匂いを嗅いだ。完全な濃密さが、鼻腔を通り、脳に至り、胃と心臓を嬉しく収縮させた。私は、女物のズボン越しに、天使のペニスに口付けをした。あとは我と我が身を全て投げ出すだけである。私には、死ぬまで薫を愛する義務があるし、その能力も豊富にあると、その時やっと直観したのだ。
天使の股ぐら