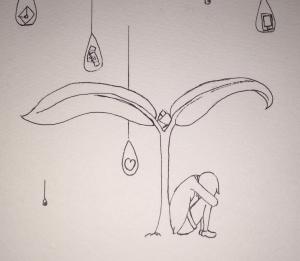姫毎
作られた話の中のお姫様達
ハッピーエンドを約束された童話
赤姫
田舎の夏休み。
蝉の声がどこまでもけたたましく響き、草木と太陽の匂いが満ちる季節。
午後1時ちょっと過ぎ。
新しくはないが、広く立派な佇まいの家から、蝉の声に負けじと女の子の声が響く。
「いってきまーす!」
その声の主は家から飛び出し走りだす。女の子は右手の脇道に入りすぐ見えなくなってしまった。
お母さんは不安でいっぱいだった。
それも、そのはず。女の子は近所に遊びに行くのではなく、女の子の祖母にあたる人物に会いにいくからだ。いつものテリトリーより、家から距離がある。
午後2時少し前。
女の子は病院への道をよく知っていた。祖母によく懐いていて、学校がない土曜か日曜はおかあさんとお見舞に必ず行っていたからだ。
道中、こっちをじっと見てくる、見覚えのある男の子がいた。多分、同い年。
こんな暑い日に、黒いパーカーを着ている。
女の子に近づく。
「やあ!こんにちは!今日も暑いね!君はよく病院にいる子だよね?」
何かがおかしい気がする。
「え?うーん…土曜日か日曜日は病院にいってるよ?」
「なるほどね!僕もあの病院によく行くんだ!それで、見覚えがあったんだ。僕を見たことない?」
女の子は思い出す。
「あっ!見たことある!」
「僕はヨルって言うんだ。よろしくね!」
「うん。そうだ!私、行かなくちゃいけない所があるの。」
「そうなんだ…それじゃ、また今度だね。次は一緒に遊ぼうね!」
「うん。バイバイ!」
「バイバーイ!またねー!」
もう病院はすぐそこだ。
午後2時ぐらい。
おばあちゃんの病室に着いた。
「こんにちは、おばあちゃん。調子はどう?」
よくお母さんが言うセリフ。
「大丈夫だよ。」
おばあちゃんが微笑む。
「お父さんは?」
「飲み物を買いに行ってるはずだよ。」
「ふーん。明日、おばあちゃん、家に来るんだよね?」
おばあちゃんはずっと入院をしていて、やっと退院の許可がおりていた。
午後3時3分。時計の針をずっと眺めていた。
「おー!いつ着いたんだ?」
お父さんが病室に入ってきた。
「ずっと前に着いた。お父さん遅いよ!」
「すまんな。お母さんがこっち来るのは4時ぐらいになるってさ。そしたら、何か食べに行こう。」
「おばあちゃんは?」
おばあちゃんが答える。
「気にしないで行っておいで。」
お父さんが女の子を説得する。
「おばあちゃんとは明日にしような。いきたい所に連れてってやるから。」
女の子はおばあちゃんを横目で見ながら答える。
「うーん…分かった…おばあちゃんはそれでいい?」
おばあちゃんは微笑みながら応える。
「おばあちゃんはそれでいいから行っといで。」
午後4時半
ファミリーレストランにて、食事と一緒に明日の作戦会議が進行中。
「で、どうする?」
お母さんが女の子に二択を迫る。
お母さんと一緒に家に帰ってあしたの支度をするか、お父さんと病院でおばあちゃんについているかの二択。
「私はおばあちゃんと一緒にいる。」
午後5時くらいに戻った。
太陽はまだ顔を出している。けど、おばあちゃんがいない。
「おばあちゃんは?」
女の子はこの時間まで病院に居たことがない。不安が胸から、せり上がってくる。
「お風呂に入ってるんじゃないかな?
お父さんの声が不安をかき消してくれた。それに、少し待ってたら、おばあちゃんが帰ってきた。お父さんが言った通りお風呂に言ってたらしい。
ジュースを飲んだり、お菓子を食べたり、テレビを見たりしてたら、時間が通り過ぎていた。
午後6時から7時。
日が暮れ出していた。女の子はおばあちゃんの傍で寝てしまっている。お父さんは椅子にかけ、おばあちゃんと静かに会話をする。
蝉の声は落ち着き始め、空はこれから来る夜の為に色を赤く染め、窓から入る風からは昼と変わらず草と太陽の匂いがした。
午後8時13分。時計の針が歪なへの字になってる。
女の子は目を覚ました。お父さんとおばあちゃんは寝てしまっている。病室を出て、トイレに向かう。向こうにあの子がいる。
「やあ!こんばんは!もう、すっかり暗いね!」
あの子だ!昼間に会った子だ!
「あれ?あの、こんばんは。もう夜だよ?お家に帰らないの?」
「うん。大丈夫だよ。ねえ、これから遊ばない?下の階のプレイルームに行こうよ。」
「私、トイレに行ったら病室に戻らなくちゃいけないの…」
「そっか、分かった。それじゃあ、また今度だね。またね!」
「う、うん。またね!」
午後9時42分。先生がそう言ってた。
おばあちゃんが死んだ。
容体が急変した為のようで、手を尽くしたがダメだったらしい。
全てがあっと言う間だった。
女の子が病室に戻る時は既に騒々しく、白い人達がたくさんいた。
お父さんは横で両手で顔を隠すように、頭を抱えている。静か過ぎてまるで、寝ているみたいだ。女の子は状況を理解できていないのか、足をプラプラさせながら、椅子に座って俯いている。
午後10時過ぎ。
お母さんが来た。とても急いで来たようだ。私はお母さんに自動販売機で飲み物を買って来るように言われた。厄介者払いだと思う。
また、あの子がいた。
「やあ!こんばんは!今夜はなんだか煩いね!」
何故か、安心感があった。この世界で唯一の理解者に会った様な安堵感があった。おかしな事にだ。
「………おばあちゃんが死んじゃったの」
「そうか…ごめんなさい。失礼な事を言ってしまったね。」
「ううん。大丈夫。」
「君は………その、悲しいとは思わないのかい?」
「えっと、分からないの…」
「実感が湧かないんだね。無理もないね。」
「どうしたら、いいのかな?」
「どうせ、子供にできる事なんて殆ど無いさ。だから、今できる事を精一杯やるしかないよね。ほら、おつかいとかさ。」
「そっか……そうだね!」
女の子は踵を返した。
「待って!これを、君のお父さんに渡してくれないか?」
そう言って、半分に折った紙と、十字架の長い所が尖った銀のペンダントを渡してきた。
午後11時くらい
女の子はヨルからの"預かり物"を渡せずにいた。渡したら、何か良くない事が起きる気がしたからだ。両手で"預かり物"を包んで。お父さんの横に座っている事しかできずにいた。
通路から足音が聞こえてきた。ペタペタと歩いて来る。病室のドアが開く。そこにはヨルがいた。女の子はそんな気がしていて驚かなかったが、お父さんは目を見開いて今まで見たことない程の驚いた表情をしていた。
「そんな……本当に……」
お父さんはヨルにゆっくり近づき、肩を掴んだ。
「君が……」
言葉が続いていない。
「はい。」
ヨルは質問されていないのに、肯定した。
お父さんがヨルを突き飛ばした。触れたくない様だった。
女の子はお父さんにしがみついた。
「ダメだよ!」
何がダメなのかは女の子自身にもよく分からなかったが、いつものお父さんに戻って欲しいという願いが込められていた。
そして、女の子は"預かり物"を落としている事に気付いていなかった。
午後11時前。
沈黙が病室に充満していた。
病室には、床にへたり込んで左手に"預かり物"を握っているお父さん。
お父さんの正面で微動だにせず立っている男の子、ヨル。
お父さんにくっついて泣いてる女の子の3人。
沈黙を破ったのはヨルだった。
「覚悟はできています。いつでも大丈夫です。」
「だが、君は子供だ!」
急な大きな音で、余計に静寂が強くなる。
12時ちょうど。
ヨルの胸からは、銀の十字架が突き出ている…
さっきとは、まるで逆の構図だ。ヨルが倒れ、お父さんが立っている。
でも、静寂は何処かへ行ってしまった。この空間には、お父さんの荒い息遣いだけがひびいている。
蝉の声は全く聞こえない時間。開け放たれた窓からは夜の冷たい空気が脳を冷やした。
夜明け。
私はお母さんとお家にいる。
お父さんは遠分帰ってこないだろう。
そして、あの夜とおばあちゃんも帰って来ない。
早起きな鳥が声をあげ始る。
まだ、夜の冷たい匂いが残っているけれど、もう少し経てば太陽の匂いが町に広がるだろう。
私は今日を迎えることができた。
鶴姫
その日は雪が降り、とても冷える日だった。
町は白色に埋まっていた
私は家に向かっていた。
会社の帰りに、居酒屋で会社の者と一杯ひっかけ、寒さも忘れて一人で心地よく帰っていたところだった。
等間隔に並ぶ街灯が眩しく、夜空の星は見えない。
鶴がいた。
こんな街中に、こんな大きな鳥がいるなんてありえないことだ。
好奇心で近づいてみると、白い羽に赤い斑紋が見えた。傷を追っていたのだ。
だからといって、私にできる事は無かった。第一、私は通勤に使う鞄しか持っていない。出血を止めることができる道具なんて持っている訳がない。
「カウ」
鶴が鳴いた。
なにやら、こっちを見ている。なんとなく、目が潤んでいる気がする。たぶん気のせいだが…
どうしたものか……
いつのまにか、酔いは覚めていた。
「ただいま。」
「おかえり。」
私には妻がいる。子供はいない。
「聞いてくれ、さっき鶴が道端にいたんだよ。」
「へ〜」
妻は興味なさそうに、テレビを眺めていた。
鍋に入っているカレーに火をいれ、温めなおす。
今の生活に不満は無かった。一般的な幸せな家庭だろう。
翌日は休みだった。
私は暇を持て余し、なんとなくテレビを眺めていた。部屋には暖房とテレビからの音しかしない。
ピンポンとインターホンが鳴る。暖房とテレビの音が少し小さくなった気がした。
若くて、綺麗な女性が立っていた。
無論、初めて見る方だ。
モニター越しで問答をする。外はきっと寒い。
問答の結果、この女性は外の雪景色に溶け入りそうな程、儚くも清楚な方だということと、私に落し物のハンカチを渡しに来たということが分かった。
私は彼女を部屋に入れていた。
外は寒い。身を切る寒さだ。
彼女の為にインスタントコーヒーを淹れた。
部屋の中は暖かい。テレビはオフにしてある。
今、私は我が家の扉の前にいる。
県営マンション。12階だての4階の真ん中の扉。
会社からまっすぐ帰ってきた。指先と足先が冷えている。きっと赤くなっているのだろうなと思う。扉を開くと、暖かい空気が解放されて、私を迎えた。
「ただいま。」
「おかえりなさい。」
白色のセーターを着た彼女が向こうから来る。儚くも清楚、そして頑張り屋な一面がある彼女は私の妻だ。
暖かい食事と暖かい空気が私を包む。
彼女は夜に家を空けることがあった。
男関係の心配はしていなかった。そういう女性ではないからだ。どちらかというと、暴漢に襲われるのではと思った。
だから、よく心配で電話をした。だけど、彼女は送り迎えはいらないと言った。いつも「明日も仕事なのだから、暖かくして寝ていて下さい」と言っていた。
彼女の話だと夜勤の仕事をしているのだとか…
なんとなく、身を切るような思いだった。冬の寒さに似ていた。
その日、私は1人で家にいた。
彼女は、私にあの台詞を置いて、仕事に行っていた。
身を切るような思いを温める為、酒を煽りに寒空に身を晒した。
その時に、彼女を見かけてしまった。2階の窓際の席。男と向きあって座っていた。暖色の柔らかい照明が二人を照らしていた。
12月も終わりそうな時期で、とても寒い日だった。
今、彼女はテーブルを挟んで向こう側にいる。
湯気が立ち昇るシチューに口をつけている。薄い赤色に染まる小さな唇が可愛らしい。私は帰ってきたばかりで、まだ体は冷えていて、手足は急な温度変化で痺れている。シチューに手が伸びない。
「少し話があるんだ」
彼女は何かを期待しているのか、目を潤ませ話を促してくる。無理もない。今日は、12月の中でも特別な日なのだ。でも、私は通勤に使う鞄しか持っていない。
思わず、手に力が入ってしまう。
あの日。鶴を見かけた日。
私はどうすることもできずに、途方に暮れていた。しかし、火照った身体に冬の夜の寒さが気持ちよくて、 鶴を保護しにくる人を待つ間、ずっと鶴に話しかけていた。主に家のこと。あいつの良いところ。悪いところ。出会い。喧嘩。仲直り。そして、好きな所。私は一般的な幸せな家庭を持っていた。
今、私は部屋に1人でいる。
彼女は私の元から飛び去った。
さっき、私はあいつに電話をした。目からは何かが零れている。
部屋は明るく、暖かだ。でも、体はまだ冷えてしまっている。暖房が私と部屋を温めようとしてくれている。テレビはついていない。
私は水で食器を洗っている。温水が出ないわけではない、なんとなく、水で洗っている。手が凍る。
私は食器を洗い終えると冷蔵庫を開いた。冷気が流れてくる。視界に入った私の手は赤かったが、気にはならない。これから、2人分の食事を作らなければならないからだ。
私は私自身に嫌悪感を覚えた。
いつのまにか、私の体は様々な感情で暑くなっていた。熱で溶け出した感情は液体になって目から溢れた。
料理は涙のせいで、上手に作れなかったが、あいつは美味しいと言ってくれた。
白雪姫
血の様に赤い唇
夜の様に黒い髪
雪の様に白い肌
世界で一番美しい少女がおりました。
少女の母親もとても美しく、幼い頃から言い寄る男性が後を断たない程でした。
少女の父親も容姿が良く、経済力もあり、心も優しい人物でした。
ある日の事でした。
父親は少女に告白をしました。懺悔とも言うそれは少女に衝撃を与えました。
「実は、母さんは2度お前を殺そうとした。1度目は生まれる前、2度目は生まれた直後。2回とも偶然で止める事ができたが、次は分からない。……だから、私と一緒に家を出ないか?」
理解できていない少女に父親は話を補足しました。父親によると、母親の動機は周りからちやほやされる我が子が許せなかった事と、己が醜く老いていく事の八つ当たりの2つが原因でした。
普段は母親の仕事で会う機会は少なかったのですが、あの優しく面白い母親がそんな事を考えていたなんて信じられませんでした。
しかし、あの父親が嘘をつくとも思えませんでした。
おそらく次の日。
私は気付くと、白い天井と白いカーテンに囲われた白いベッドに寝ていました。私は起きれずまさに寝ているかの様でした。脳と動かせない視界だけが稼働していました。
なぜ、こんな所にいるのか分かりません。少女は我が身が置かれた状況に絶望するよりも、混乱で頭の中が真っ白になりました。
暫くすると、カーテンが開きました。そこには友人達が立っていました。私の状況に驚いたのか、一瞬みんな目が丸くなっていました。ですが、役割を思い出したかの様に行動を始めました。花瓶にカラフルな花をさしたり、ひたすら話しかけてくれたり、お土産のお菓子を棚にしまってくれたり……
ハカセ、チャラ、アキコ、ヨッちゃん、ユウタ、アイ、ユーミそして、コウタロウ。
少女は友人達の気持ちが嬉しかったのですが、お礼もできず。会話にも入れない事に絶望して心が黒くなってしまったようでした。
友人達が帰って暫くすると、父親と母親が狭いスペースに入ってきました。2人とも、とても悲しんでくれました。気持ちはもちろん嬉しかったです。そう脳が処理しました。しかし、あんな話を聞いたせいか、なんとも言えない気持ちになりまし。心の芯まで、雪のように冷たい黒色に染まりました。
おそらく次の日。
この日は、母親は仕事が忙しく病院に来られなかったそうです。代わりに、父親が少女の看病をしました。それは、とても献身的に余計な程、気持が悪い程。
………これ以上は。
おそらく次の日。
コウタロウが病院に来ました。その日は具合が良く、コウタロウにお願いを伝える事ができました。コウタロウはすぐに病室から出て行きました。
入れ違いで父親が入ってきました。
少女が父親からの告白を聞いてから数日後。
少女は病院から消えてなくなりました。こんなに寒い時期のこんなに寒い日。よりにもよってこんな日に……。
当然、捜索願が出されましたが努力も実らず見つかる事はありませんでした。
父親と母親はとてもとても悲しがりました。
父親は「私がもっと優しくしてあげていたら…」と
母親は「私がもっとあの子の事を見ていたら…」と
「ここで、臨時ニュースをお伝えします。今日、午後9時頃、○○市の高校生9名が行方不明となりました。この高校生は市内の○○高等学校に通う友人同士で、午後9時頃に○○高等学校にいた所を目撃されたのを最後に消息がつかめません。事件性も懸念されていますので、夜の外出は気をつけて下さい。」
「ここで、臨時ニュースをお伝えします。今日の午後9時頃に行方不明になっていた高校生の身柄が確保されました。行方不明になっていた9名のうち7名が○○駅付近にいた所を警察が保護しました。記憶の混乱があり、行方不明になった当時の事が思い出せない様子ですが、目立った外傷もなく命に別状はないとのことです。」
妹姫
「はぁ、はぁ、はぁ…」
私は今、兄に手を引かれ濃い紺色に沈む森を犬の様に走っている。
足の裏は色々な物を踏んでもの凄く痛い。
「はぁ、はぁ、あと少しだ頑張れ!」
返事をする余裕が私にはなかった。兄も返事は求めていないかった。きっと、兄自身にも放った激励なのだろう。
兄は木に体を預け休憩をとった。私も兄に習い息を整えながら、私達の有様を見た。
汗に塗れ、土で汚れ、枝で破れた、私と兄の服はボロボロだった。でも、そんな事には気を留めていられなかった。息が整うと、今度は物音を出さないようにゆっくりと、猫の様に歩き始めた。
思えば今日は散々な一日だ。
親に捨てられ、魔女に目を付けられ、今は恐怖の真っ只中だ。それまでの生活はまだマシだった。屋根があり、食事があり、恐怖は少ししか無かった。
そもそも、母が悪いのだ!私達は何も悪い事はしていないはずだ。なぜ、こんな目に……
「ふせろ」
兄の小さな声で私は頭の中から森に引き戻された。
「出ておいで。甘いお菓子をあげよう。可哀想に。お腹が減っているんじゃないのかい?」
魔女だ!
ただ、息を殺して、離れてくれるのを待つ。思わず、両手で兄の手を握ってしまう。
私の呼吸する音でさえ……うるさい。
私達は森の中で甘い匂いを放つ、森には似つかわしくない可愛い家を見つけた。まともな食事は摂っていなかったので、花に誘われる蝶々の様に近づいてしまった。そこには母と同じ位の年齢に見える魔女がいた。今日、一番の不幸だ。
握っている手から、どちらかの震えが伝わってくる。
魔女が近づいてきた!
気づかれているのか?ばれてしまったのか?
兄は動かない。動けない?
とりあえず、兄に習って動かないでいる。今まで、兄が選択を間違った事はない。
なにも考えられない。思い起こせない。
「あ゛ーー」
汚い声が鼓膜を突つく。兄ではない。大柄な男が魔女を押し倒した。
「早く、行け!」
また汚い声が鼓膜を突つく。兄は私の手を引っ張った。私は急に腕を引かれ、転びそうになりながらも、また走りだした。正直とっくに足はクタクタだったが我儘を言ってられる状況ではない。
暫く、走ると森を抜けた。遠くの方だが街も見えた。森を抜ければ魔女は追って来ない。太陽もほとんど顔を見せている。
後ろの森からは、何かが焼ける様な不快な匂いが追ってきた。
私達にはお父さんがいた。母とよく喧嘩をしていて家にはあまりいなかった。
私は家が嫌いだった。何もかもが煩い母と、何もかもが汚いお父さん。毎日、こき使われていた。食事と部屋には感謝していた。でも良く考えて見たら、当然だと思う。家事も畑仕事もしていたからだ。兄は好きだった。いつも私に優しくして、母とお父さんから守ってくれていた。
私達は街に着いた。もし、絵本だったらこんな文で締められるのだろう。
「街についた兄妹はいつまでも仲良く2人で暮らしましたとさ。」
萵苣姫
窓際の彼女はいつも誰かを待っているようでした。
いつも同じコーヒーを注文し、読書に耽っていました。
時折、左手を頬杖にして窓から外の景色を眺めていました。
月夜の夜空をぼんやりと眺めている、塔に囚われているお姫様の様だと思いました。
彼女は毎週金曜の正午に必ず来店しました。
いつもカウンターまで来ると、ブラックコーヒーをひとつだけ注文しました。
窓際の小さなテーブル席に腰掛けると、鞄から文庫本を取り出します。
そこのテーブルはふたり用なので、イスがもうひとつあります。
ですが、そのもうひとつのイスが埋まることは一度としてありませんでした。
彼女は待つ人です。
私が彼女のことを、誰かを待つ人だと思うのはなんとなくです。
なんとなく誰かを待っているようだと思いました。
これでも私は長年、この店の店長としてお客様を近くから観察する機会が多々ありましたから、それなりに人を見る目はあるつもりです。
その私の経験から、彼女には大切な相手を待つ人の独特な哀愁があるように思えました。
彼女と言葉を交わしたことは2度程ありました。
1度目は、彼女が私に声をかけてくださった時です。
「いつも忙しい時間にコーヒーだけで入り浸ってしまって、ごめんなさい。」と謝られてしまいした。
その時は「いえ、ここを気に入ってもらえて私は嬉しいですよ。」と少し鼻にかかる言い回しをしてしまいました。
2度目は、その次の週の金曜日です。
1度目の会話の日に、彼女は落とし物をしていたので、それを渡す為に私から声をかけました。
「先週、こちらの栞をお忘れになりませんでしたか?」と少し丁寧すぎるような気がする言い回しをしてしまいました。
白と紫の花の綺麗な栞でした。
「ありがとうございます。探してたんです。ところで、店長さんはビオラの花の意味をご存知ですか?」と聞かれたのをよく覚えています。
その時は、ビオラという花すら知らなかったので、会話もソコソコに業務に戻りました。
彼女が落とした栞にプリントされている、上品な色使いの花はビオラという名前でした。
私の店には、今はもういない妻が残した趣味の面影があります。
石造りの様に見える灰色の壁面に様々な植物が飾られています。
彼女はきっと私が植物に詳しいと思ったのかもしれません。しかし、私には彼女の期待に応えられるような知識はありませんでした。
私は閉店後に自宅で妻が遺した本棚から本を数冊取り出しビオラを探しました。
コーヒーを淹れ、机上の図鑑をペラペラめくりました。
調べ物に満足してベランダに出ると、冷たい空気がとても心地良かったのを覚えています。
空いっぱいに美しい星々がきらめく夜でした。
次の週の金曜日に彼女は来店しませんでした。
その次の週も。そのまた次の週も。
枯れた葉が散り、雪が降り、年を跨ぎ、緑が芽吹き、蝉が鳴っても。
草花から生気がなくなり、街を行き交う人はマフラーで寒さを凌ぎ、頬と鼻の先を赤らめたふたりが手を繋いで暖め合う頃になっても、彼女はあらわれませんでした。
外の景色がよく見えるあの席越しに、白色に薄っすら化粧を施された街を今日も眺めてしまいます。
ビオラの花を調べた時に、聞きたいことができました。
3度目の会話の機会は二度と無いような気がしました。何かを窓際で待つ彼女と私には何も接点かないですから。
ですが、そう思っていても、なんとなく窓の外をなんとはなしに眺めてしまうのです。
私は待つ人です。
ポッカリと空いてしまったあのテーブルを埋めてくれる彼女が、いつの日か扉をカランコロンと開ける日があるのではと思ってしまいます。
そして、いつものようにブラックのコーヒーをひとつだけ注文して、あのふたり用のテーブル席に腰掛けるのです。そうしたら、私はコーヒーをテーブルに持っていくついでに、私はビオラの花の話をしようと思います。
「ビオラの花について調べてみたんですよ。」と。
そんな、コーヒーと花の優しい香りがふんわりとする金曜日がいつか来るのではないかと、私は思ってしまうのです。
私は店主。彼女はお客様。
いつか、あなたが来店して下さることをツタが絡み付いたこの店でお待ちしています。
夢姫
君に触れたいと思って、存在を確かめたいと思って、腕を伸ばした。
私の腕は空気に溶けていく君の希薄になった存在をすり抜けた。
私は勢い余って倒れ込んでしまった。
碧い方の目から雫が目尻を伝って流れ落ちた。
夢から覚めるだけなんだと君は言っていた。
夢ってなに?君は誰かの夢だったの?
私の気持ちは?胸がこんなに熱いのも夢だったの?
君は私にとても多くのモノをくれた。
あの場所にまた行こうって言ってくれたのはなんだったの?
君はこうなることを知っていたの?知っていて私に秘密にしていたの?
あまりにも唐突なお別れだった。
もう君のぬくもりに触れることはできないの?
もう君の存在に触れることはできないの?
もう……会えないの?
私は力が抜けてしまったからだに、もう一度だけ力を込めて上体を起こし振り返った。
そこに君はもう居なかった。
今でも鮮明に思い出すことができるんだ。
君の温かな体温。君の太陽の様な笑顔。君の私を呼ぶ指笛。
一緒に食べたアイス。一緒に泳いだ湖。一緒に歩いた道。
大きな瞳。絡めた指先。柔らかな口づけ。
全てが夢だったっていうの?
全てが嘘だったっていうの?
ねえ、教えてよ。
ねえ、教えてよ!
私は必死で君を呼んだ。
夢ってなに?
君は誰かの夢だったの?
私の夢ではないの?
もう会うことは叶わないの?
どうすればいいの?
どうしたらいいの?
行き場のない気持ちは、こぶしを強く強く握りしめることしかできなかった。
……夢から覚めるだけだと君は言っていた。
私は君が溶けていった空を仰いだ。爽やかな青空とは対照的に私の心の中はグシャグシャしていた。いつまでも幸せな夢の微睡の中で泳いでいたいと思った。
指先を唇ではさみ、ほんの一抹だけの希望を胸に、最後にもう一度だけ君を呼んだ。
鳥の鳴き声のような私の悲鳴は大きな空に飲まれて消えていった。
これまでの出来事がまるで夢だったかのように消えていった。
君はいつまで経っても夢に再び落ちてくることはなかった。
形のない大切な大切な記憶の欠片達は、君を模倣することでしか保てなくて。
私はバカみたいに君を思い出した。もういない君の背中を追い続けたんだ。
君を思い出す度に胸が苦しくなったんだ。本当に苦しかった。
だけど、その先には君がいるとおもったから、君を追いかける道は君に繋がっていると思ったから、耐えることができた。
何度も、歩みを止めてしまおうかな?なんて思った。その方が楽になると思った時もあったから。
だけど、足が止まりそうになると大きな不安が私を覆ったんだ。その不安はとても大きくて、とても暗い感情だった。私は怖くて走り続けたんだよ。ただ一つ、道のずっと向こうの柔らかな光を求めて。
まるで悪夢のような夢の世界を駆け抜けた。
君はいつ戻るのかな?
姫毎
一つの物語を書くことの練習で書きました。
大人な童話の雰囲気を目指しています。