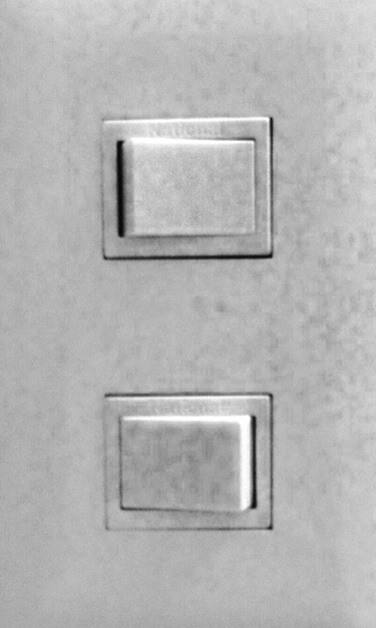
7月12日、雪
7月12日、午前10時23分、雪が降り始めた。
私はその15分ほど前からずっと窓の外を眺めていたので、すぐにそれに気がついた。
7月12日の午前9時30分にゴミを捨てるために外へ出たときは、皮膚が焼け落ちそうなほど暑かった。
湿気が少なく、からりとした、夏の朝だった。
「前島さん、外、雪が降ってます」
私は隣のデスクに座る上司の男性に言った。
「ああ?」
と前島さんは面倒くさそうに言った。
それからゆっくりと窓の方に顔を向けて、外をじっと眺め、
「地球温暖化のせいだ」
と言った。
彼はぼんやりとした目つきでしばらく雪を眺めてから、大きなため息をついた。
それから首を横に振って、背中を伸ばした。
そしてもう一度「地球温暖化のせいだな」
と確認するように言った。
胸ポケットの煙草を探すしぐさをして、何も入っていないことを確認すると小さく首をかしげた。
前島さんは、去年の9月に大型の台風が来きたときも、梅雨にひどい雨が3日続いたときも、真冬に雪が降ったときすら、地球温暖化のせいにしていた。
前島さんはね、と営業の若い男の子が言った。蟻が後ろ向きに歩いていたって地球温暖化のせいにするにするんですよ。
そのジョークには誰も笑わなかった。
「コーヒーを飲みますか?」
と私は訊ねた。
前島さんは2秒ほど考える素振りをしてから、「飲む」と言った。
彼の考える素振りがただのポーズだということは、社内の誰もが知っていた。
私はインスタントコーヒーを溶かしたものを前島さんに手渡した。
前島さんは右手で顎のあたりをさすりながら礼を言った。
36歳の男性にしては、彼の肌はつやりとしていて綺麗だ。
髭を剃った痕もニキビの痕も毛穴の陰もほとんどなく、まるで彼の愛用する白色のマグカップと双子の兄弟のようだった。
「まるで女の子みたいね」
とか
「まるで子供みたいね」
と、女子社員は彼をからかったが、彼にはしっかりと5人の子供がいた。
子供は5人とも娘だった。
「嫁の家系が女ばっかりなんだよ」
と前島さんは黄土色のネクタイの結び目を弄りながら言った。
夏でもネクタイを締めるのが彼の個人的なルールだった。
「あいつ自身も2人姉妹だし、お義姉さんのとこも女の子が2人だしな。呪いみたいなもんだな」
前島さんはコーヒーにミルクを入れてゆっくりとかき混ぜた。
彼の白いマグカップには、鹿の絵が描かれていた。
鹿は何かを訴えるようにこちらを見ていた。
草が一緒に描かれていないのが不満なのかもしれないし、餓えることを不安に思っているのかもしれない。友達がいないのでつまらないのかもしれない。
あるいは、自分の身体が桃色であることを抗議しているのかもしれなかった。
前島さんはミルクを入れたコーヒーを一口飲んで、液体をひとしきりにらめつけた後で、砂糖を一本入れた。
そして、カップを右手から左手に持ちかえた。
桃色の鹿は私の視界から消え、代わりに小さな草の絵が見えた。
それは私を安心させた。
「長女がアイドルを目指してるんだ」
前島さんはマグカップを揺すりながらおもむろに切り出した。
彼が娘の話をするのはこれが初めてだった。
ー雪の降る度に残り4人の娘のことを順番に話してくれればいいのに。
「ダンス部に入ったんだ。アイドルになることとダンス部に入ることにどういう関係があるのか俺にはわからねぇけど」
と彼は言った。
「アイドルはたいていダンスを踊るんですよ」
と私は応えた。
「でもありゃダメだな」
と前島さんは言った。
アイドルとダンスの関係性にはさほど興味がないようだ。
「顔はそこそこかわいいんだけど小顔じゃないんだわ。アイドルってのは小顔じゃなきゃなれないだろうが。俺は昔ジャニーズを生でみたことがあるんだけど、やっぱり小顔だったね。名前は忘れちまったよ、とにかくジャニーズだ」
前島さんはそう言って、長女がセーラー服を着て玄関の前で直立している写真を見せてくれた(彼はそれを手帳に挟んでいた)。
確かに色白で整った顔立ちをしていた。目の形が前島さんと同じだった。
そして、たしかに大きく見える丸い顔をしている。
☆
ちょうど同じ時刻、前島遥は公立中学校の教室のひとつで、机にうつ伏せて居眠りをしていた。
彼女は5人姉妹の長女で、12年間、自分が長女であることにうまく馴染めていなかった。
しかしそのことも、眠っているうちは関係なかった。
眠っている彼女は5人姉妹の長女ではなく、前島遥ですらなかった。
彼女の腕の下にはまだそれほど使い込まれていない英語の教科書が押しつぶされていて、その下の木製の机には大きくForever3-6と刻まれていた。
もちろん彼女は、自分の写真が父親によって部下に晒されていることも(彼女自身はその写真が好きではなかった)、雪が降っていることも知らなかった。
彼女は深い眠りの中にいた。
彼女の所属しているクラス(1年5組)は、男女の机がペアになっていて、左側に女子、右側に男子が座っていた。
アルマジロみたいに眠る前島遥の右側には、勝浦幸雄が座っていた。
坊主頭の彼は、小学生のときからカツオというあだ名で呼ばれていた。
彼自身もそのあだ名は気に入っていた。
幼い頃からそう呼ばれていたせいで、本名よりもずっと真実味があった。
カツオは眠る前島遥を見ていた。
遥はぐっすりと眠っていて、真夏に降った雪については全く関心を持っていない様子だった(眠っているのだから当たり前のことだ、とカツオは考えた)。
英語の授業はすっかり教室中から忘れさられていた。
カツオは出したままになっていた英語の教科書とノートを机の中にしまった。
ほかの生徒は窓の外を眺めたり、関係ないことを話したりしていた。
しばらくすると、ざわついていた教室が静かになった。
雪のもたらした寒さが、12歳と13歳の男女の、大人のそれよりもよりずっと温かい身体を冷やしたためだった。
灯油がないため、ストーブで暖めることができなかった。
毛布やコートなどももちろんなかった。
その前時代性にほとんどの生徒は憤っていたが、どうすることもできなかった。
英語の教師は緊急職員会議のために教室を出た。
遥は起きなかった。
「カツオ、前島死んでるんじゃね?」
とカツオの前の席の男子が言った。
男子生徒の唇は紫色に染まっていて、彼の方が死人みたいだった。
「眠ってるだけだよ」
とカツオは応えた。
声がやや震えた。
教室の隅で、誰かの歯がカタカタと音を立てるのが聞こえた。
遥の丸まった背中が規則正しく上下するのを、カツオと男子生徒は一緒に眺めた。
寝息は聞こえなかった。
「お前ら寒くねぇの」
前の席の男子は、5回上下運動を見届けてから言った。
カツオはまだ遥の背中を見ていた。
「さぁね」
とカツオは言った。
カツオと前島遥は、それほど仲の良い関係とは言えなかった。
遥はどちらかといえば派手な友達が多く、真面目でおとなしいカツオにはほんの少しの興味もないようだった。
遥はわりにはっきりとした性格で、興味のない人間や物事に関わる時間をより少なくすることで、人生はすばらしいものになると考えていた。
逆に、興味のあるものにはすべての情熱をそそいだ。
人情にも厚かった。
それはあきらかに、父親から受け継いだ性質だったが、彼女自身は母親似だと信じていた。
カツオは右腕と前髪の間から覗く、遥のアーモンド型の右目に視線を移した(もっとも今はきつく閉ざされていてコーヒー豆のようになっている)。
眠っている遥は、何にも興味を持っていなかった。
起きているときと同じで、もちろんカツオにも興味はない様子だった。
雪にも英語の教科書にも同じ態度だった。
寝ているにしたって、あまりにも全てに対して興味を持っていないような気がカツオはした。
遥は枇杷をスーツケースに詰められるだけ詰め、深く掘った穴に埋めてから、その上にカメハメハ大王の巨大な像を置いた。
遠くから時報が聴こえた。
11時ちょうど。
前島遥は先ほどと逆の手順で、枇杷を取り戻さなくてはならない。
まずカメハメハ大王の像をどかして……
カツオはそこで目を覚ました。
眠っていたらしい。
いつの間に眠っていたのか思い出せないけど、少なくとも雪は降っていて、隣の席の美少女はぐっすりと眠っていた。
カツオはぼんやりとした頭で、あんな夢を見たことを後悔した。
そして、日に焼けた首を大きく左右に振った。
しかし、カメハメハ大王は、カツオのイメージの中に居座った。
遥がカメハメハ大王のために踊ってウィンクを贈る。
するとカメハメハ大王も踊る。
雪を降らせるために。ハワイでは雪が降らないから。
「ハヤスギル」
と観客のひとりが叫ぶ。
遥とカメハメハ大王を囲むように人が集まり、そのダンスを見物していた。
そのうち、別の誰かがアコーディオンを引き出した。
また別の誰かはしりとりを始めた。
遥はしりとりをやめるよう訴える。
しかし、しりとりは広がる一方だ。
雪は溶ける。
夏の太陽は、雪を溶かすために存在するのだ。
「コマツナ」
そう言った誰かの次に、別の誰かが言った。
ナツノタイヨウハ、ユキヲトカスタメニソンザイスルノダ。
☆
私は冷房を暖房に切り替えた。
小さなオフィスはあっという間に暖かくなった。
外では相変わらず雪がチラチラと舞っていた。
「遥もな、もうちょっと顔が小さければな」
と前島さんはまだ言っていた。
「まぁ、まだ中学生なんだし、なんでも興味のあるのはいいことだ。ダンスでもアイドルでも好きにしたらいいさ」
私は同意した。
「雪、止みませんね」
今年入社したばかりの葛城さんが言った。
「お菓子、あるんですけど食べますか?仙台のお菓子です」
前島さんは2秒考えて「食う」
と言った。
葛城さんはにっこりと笑って、モナカを2つ手渡した。
「こういうのって、誰かの夢かもしれませんよ」
と葛城さんは言った。
彼女はブラインドのようなまつげを乗せた目で、雪を愛おしそうに眺めていた。
「面白い意見ね」
と私は言った。
「そうでもないです。誰だって夢を見る権利はありますから」
「他人を巻き込む権利はない。そう思わない?」
「不可抗力です」
葛城さんはきっぱりと言った。「不可抗力です」彼女は答え合わせをするようにもう一度言った。「巻き込まれてあげるくらいいいじゃないですか」
葛城さんは目を細めた。
目の下にまつげの影が降りた。
私と前島さんは同じ窓から外を見た。
雪は止みかけていた。
細かい雪が、力なく地面に引っ張られていた。
「夢が終わるのね」
と私は言ってみた。
葛城さんは何も言わなかった。
「地球温暖化のせいだな」
と前島さんは言った。
7月12日、雪

