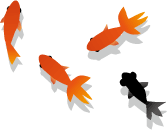薫る世界に僕一人。
僕は死んだ。
死んで___、此処に来た。
彼岸花が咲き誇り、空は黄昏の色を保つ世界。
僕はこの世界で、一体何を掴むというのだろう。
一章. Train accident.
その時自分は、朝の忙しない駅のホームに居た。
学生服の袖の取れてしまったボタンを気にしながら、電車を待っていた。
ただそれはいつもの日常。何でもない、いつもの。
そして自分は、誰かに“押された”。突然後ろから。
あまりに不意打ち過ぎて、息をすることさえ忘れた。背後からは女性の悲鳴、一層強くなる動悸。
目線の先には向かってくる、いつもの慣れ親しんでいた電車。少しくらいは、愛着があったのだが。
「・・・・・」
静かに目を閉じた。なるほど、最期というのは人は抵抗しなくなるのか。
結果論。
正直。
老衰が理想だったが、まぁ、もしかしたらこれもありかもな。そう思った。心残りはたくさんある。
好きな女子もいたし、なりたいものもあった。
しかしこの状況を冷静に考察してしまえば、もう無理だということが分かるというものだろう。
死ぬ前にもう一度、あの子の髪の匂いを嗅ぎたいと思った。思考ではなく本能で。
あの金木犀の匂いを、もう一度____。
二章. The cluster amaryllis blooms there.
金木犀の香りがした。甘い切なくなるあの香りが。
「・・・・・・・__!」
気が付けば、僕は砂浜に立っていた。夕暮れ時の海岸に。
波の揺れる音がやけに耳に張り付いて___。
「・・あれ・・・、僕・・・・?」
どうして生きている。電車に轢かれて自分は死んだ。
その疑問が脳内で満たされる。目の前は真っ白になり、波の音もオレンジ色の光も全く感じない。
気が付いたら此処に立っていた。考え事の世界から帰ってきたときのように。それに、・・・・此処はいったいどこなんだ・・。
太陽が沈もうとしている。海がその境界線を張り、まだ世界に太陽という名の全ての光を留めている。
「・・・・・?」
混乱していて全く気が付かなかったが、右目が、黒い。いや、暗い。とても暗い。全く何も見えない程に。
何となく反射的に、右目に手を当ててみる。
「____ッ・・・!」
少し触れると、強烈に痛んだ。焼けるように熱くなり、痺れた。
「・・・・・」
しばらく痛みが引くまで、座って夕焼けを眺めてた。右目は触るに触れなくて、どうなっているかの状態確認もできない。
そのうちに痛みは引き、しかしまた違う疑問が浮かんできた。
太陽が沈まない。
本当に海は太陽を留めてしまったのだろうか。先程から全く変わらない位置にある太陽を眺め、僕はあの子のことを考えた。
あの金木犀の匂いを思い出した。
***
「君は本当に役立たずだな」
「・・・・・・ごめん・・」
僕は素直に謝った。自分が情けなくなり、同時に恥ずかしい。
「その齢でパソコンのタイピングも出来ないなんて、パソコン部が聞いて呆れる!」
「・・・はい」
長い髪を揺らし、彼女は僕をにらんだ。
「大会に出ないつもり?」
「でも・・・」
「・・・・練習に付き合ってあげるから、今日は残って」
気難しいと評判の彼女から、そんなどちらかと言えば好意的な言葉が出てくるとは思わなくて、絶句する。
そう言って彼女は自分の席に戻っていった。
ゆったりと金木犀の香りが残っていた。
***
自分は、死んだのだろうか。本当に。
右目はどうしてしまったんだろうか。
此処はどこなのだろうか。
彼岸花が直ぐ近くに咲いている。それもたくさんの。
夕日に照らされて、隅でひっそりと、しかし存在は大胆に。
・・・・・・。何も、頭に浮かばない。
三章. This world.
“しばらく僕は夕焼けを眺めていた”。
やはりその間、じっくり目を凝らしてみてみても、夕焼けは全く動いていないようだった。
ああ、何だか自分はとんでもないところに来てしまった、という事をぼんやり考えていると、冷たく強い風が吹いた。
「・・・っ・・、寒・・」
海岸だけあって、風は強い。しかしこの冷たい風はまるで夜のもののようだった。
「・・・もう夜なのか・・・?」
夕焼けで時間の感覚がずれてしまう。
・・・・元々此処に来てから、あったもくそも無いが。
学生ズボンに付いた砂を払って立ち上がると、膝の関節がポキポキと鳴った。
少し向こうの海の中に、夕焼けで陰になった大きな岩が見える。あれは普段見ると、どんな色をした岩なのだろうか。
僕は海岸に背を向け、堤防の階段を上った。
階段を上ったら、今まで見えなかった簡素な道があった。道路とかではなく、草だけが除かれた簡単な道。
道は左右に自由に伸びていて、向かいは急な下り坂になっており、その先に広い森が見渡せた。
全く見覚えのない景色だった。胸の中に、じわじわとした不安が広がる。
先程まではぼんやりしていたその輪郭が、やっと定まってきた。
一体、どちらの道を行けばいいのだろう。
そんな風に途方に暮れても、背後の夕焼けは一向に沈もうとしない。それにだいぶ励まされ、左に行くことにした。
***
だいぶ歩いた。感覚で言うともう一、二時間は経っている気がする。
全く変化しない景色とオレンジ色の光。そんな中歩いていると、いい加減目が疲れてくる。
しかし身体は不思議と疲れない。どれだけ歩いても、足はすらすらと軽い。
「・・・・・?」
またしばらく歩くと、細い道の上に一つの提燈が立っていた。
たったそれだけだが。
しかし変化は喜ばしい。ここまで周りの景色は、下方に森が見えるだけだった。
その酸漿色の光に手を伸ばした。
「!」
身体が驚きに跳ねた。
その提灯は小さい電灯のようになっており、上方に提燈、下方に支える棒という構成なのだが、それを触ろうと手を伸ばした瞬間、“それは”勢いよく
跳ね、僕から一歩遠ざかった。
片足で移動するように。
僕はそれをまた一歩で追いかけると、また提灯も本体を揺らしながら一歩遠ざかる。
「・・・・・・・・」
ロボットか何か・・・、なのだろうか。いやでも、この簡素な構成ではたしてそんな複雑なことができるのか。
追いかけている内に、もうすっかり慣れてきてしまった。
今はもう、一緒に歩いているような様子だ。というかその先を行くような態度はむしろ、僕をどこかに導いている様でさえもあった。
「・・・なぁ、こっちに何かあるのか?」
提灯はもちろん答えてはくれない。ただ、一歩前方に跳ね進むだけだ。
僕は苦いため息を吐き、諦めて着いていくことにした。どうせ何をする事も無かったのだし。
Act 1: 光彩の都
「・・・・何だ、これ・・・」
あまりの驚きに、間抜けな声が漏れる。いや、仕方が無いだろう。
あれからずっと歩いていた簡素な道は段々と広い道に出て、そして今すごく賑やかな道に出た。
賑やか、というのはすごくいい事なのだが、その賑やかを埋める面子に絶句する他ない。
「・・・・」
人間らしきものが、明らかに“少ない”。
大通りに、たくさんの者たちが一方のむきにしたがって、皆移動している。ニュージーランドの羊の大群を思い出させる景色だ。牧羊犬はもちろんいないが。
しばらく立ち呆け、目の前を右から左へ過ぎていく者たちを目で送っていく。
在る者は顔面だけが兎の形をし、体は人間の形をして、少し膨らんだ胸まである。
そしてまた在る者は、背丈が三十センチ程しか無い、頭に手拭いを巻いた二足歩行の蛙。
その誰もが大小様々な荷物を担ぎ、忙しなく“移動”していた。
「・・・・_!」
提灯に突かれて、促される。自分も、このなかに入れと言っているのだろうか。
それをためらうと、なおも強く突かれたので、仕方が無く目の前の大群の中に一歩踏み出した。
僕がその中に踏み入ると、提灯は僕の頭に乗っかった。しかしそのままの形ではなく、いつのまにかそれは、手持ちの提燈に変化していた。
「・・・・おい、どうすんだよこれから・・」
提灯に小さな声で問いかけても、やはり返事は無い。それどころか、もう頭に乗ったままピクリとも動かない。
諦めて歩いていくと、両側に建物が並んできた。日本の古い町並みのような景色。いや、なんだかそれよりも派手なような・・。
朱塗りの壁に、真っ黒な瓦屋根。のれんが掛かっていたり、彼岸花をあしらった木の看板のようなものが吊り下げられていたりした。
相変わらず行列はぞろぞろと、一定の速度で前進していく。
ふと隣を見ると、全く人間そのものの形をした女性が歩いている。綺麗な女性だ。
そうして見ていると、目が合った。
「!」
にこ、と彼女は気さくな笑顔で笑い、“首”を滑らかに上方に伸ばした。あまりに滑らかな動きで、何故か見入った。
普通にしていると、もう身体しか見えない・・。
僕は前を向いた。
なるほど、ろくろ首か。初めて見た。・・いや、当たり前だろ・・・・。
そんな風にあれこれ頭で自問自答していると、今まで全く動かなかった頭の上の提燈が、頭上で二度跳ねた。
「・・・・?」
何だと思い、反射的に上を見上げれば、目の前にはこのすべての者たちの流れを収めるように、一層大きな建物が建っていた。
黒い威圧的な高い塀に、横に広い中国の王朝の建物の様な雰囲気の・・。
城、なのか・・・・?
近づけばよくわかるが、横に広かった。
皆は真っ直ぐ、その建物の塀に大きく開かれた門の内に直進している。
・・・・・。
「・・・・何だこれ・・・・・?」
Act.2 紅眼の...
「・・・・・・・」
大きく、悠然と構えるその門の中に、僕たちは飲み込まれていく。怪物の、口の中に自ら望んで飛び込む様に。
そして今、このどこまでも続くかの様な、薄暗い灰色の食道の中を進んでいる。
行列は遥か後ろにも続いているようで、蒸すような温度は一向に下がろうとはしない。
「・・・・・・?」
それから少し進むと、一つの分岐の様な箇所があった。灰色の道は二手に別れており、その境には四人の者たちが居た。
人、かはよくわからない。隣のろくろ首の様な者も居るようだし。
またその分岐は二手にはわかれているものの、皆、明らかに左手に進んでいる。四人の遣いはそれを目で素早く仕分けし、奥に進めているようだ。
「・・・・・・・」
そして自分たちの番が来た。仕分けの基準がいまいちわからないので、きっと、怪しい者などを右に進ませるのだろうと思った。
右隣のろくろ首の彼女は、一歩先に左手に入った。その瞬間、少し微笑みかけられた。
自分もそれに応じ、その先に足を踏み入れようとした。
しかし、____。
「おい。そこのお前、止まれ」
「・・・え___?」
四人のうちの一人。肌が浅黒い、見るからに恐ろしそうな風貌の男に引き止められた。右目横に何か鋭い物で引き裂かれた様な傷跡があり、彼が勇ましい戦士だという事を、無意識に感じさせた。
「な、何ですか?」
「__こちらに来い」
そう強く言われ、仕方が無く人の波をかき分け、分岐前に抜けた。
四人の疑わしげな視線にとらわれる。それだけでは無く、左手に簡単に抜けていく者たちの好奇の視線を浴びせられた。
先程のろくろ首の彼女の微笑みが、何だかすごく恋しくなった。
「お前の頭頂に乗っているそれを、よく見せろ」
「・・・?これ、ですか」
恐る恐る頭の上に手を伸ばし、それに手を触れる。しかし思ったよりも普通に触れることが出来、取っ手を持ち、それを彼らに渡す。
・・・・・・。
彼らは慎重にそれを点検し、注意深く内側にまで目を通した。
そして、
「右手に進め。道なりに真っ直ぐ進めば、紅い大きな扉がある。そこにこの提燈を置いて待て」
そう先程の彼に単調に告げられ、背を押された。
「・・え___」
尚、困惑し反対側に立っていると、彼らに鬱陶しげに睨まれたので、諦めて進むことにした。
通路は先程と何ら変わりはなく、ただ奥へ奥へと伸びている。自分しか進む者の居ないこの通路は、本当に怪物の食道、のようだった。
孤独感、というか。
随分寂しげだった。
提灯は自分の手に握られており、それだけが、この先の得体のしれぬ恐怖に打ち勝つ、唯一のよすがの様であった。
「つづく」
薫る世界に僕一人。