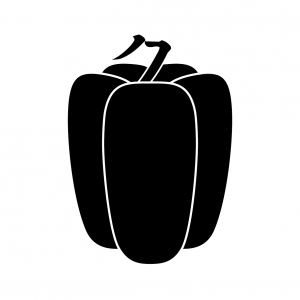ペイン
ひどく暑いある夏の日。麦わら帽子をかぶった一人の少年が元気よく走っている。しかし、何かに躓き、盛大にこけてしまった。こけてからの少年は全く動かない。まさか、死んだ?と思ったが、どうやら生きているようだ。
「……うう」
少年から小さく弱々しい声が漏れたと思った瞬間、インフレーションが起き、元気な泣き声に変わった。どうやら「痛い」という旨を彼なりに表現しているようだ。すると、その声を聞きつけた母親らしき人物が彼のそばに寄ってきた。余談だが、この女性、かなり色っぽい。
「大丈夫?」
「痛いよぉ!」
少年は被害者面をして己の右膝を母親に見せる。多少の出血はあるものの、泣き叫ぶまでにはいかないほどの傷。全くもって、子どもはオーバーリアクションである。しかし、母親は慈母の精神で少年にささやく。
「魔法の言葉、かけてあげる」
「魔法の言葉?」
「うん。イタイのイタイのとんでいけー」
薄暗い世界。混沌とした魑魅魍魎的な雰囲気が漂うだだっ広い世界。そこに、とある者がどこからともなく飛ばされてきた。ズサァァーと、なかなかの制動距離である。普通の人間なら、かなり痛がるダメージであろう。その者はゆっくり立ち上がり第一声をこう放った。
「嘘でしょ」
その者はなおも一人で話し始める。
「いやいや。嘘でしょ。……うん。そうだよ。嘘だよね、嘘」
そう言うと、その者は「えい」と言ってどこかへジャンプして消えた。これからさき「この者」が結構な頻度で登場するので、わかりやすいように「ゴボウ」と呼ぶことにする。なぜ「ゴボウ」なのかと言われても、特に理由がないので追求しないで欲しい。
「どう?」
「まだ痛いよぉ!」
ヘイ、少年よ。本当はそんなに痛くないのだろう?な?言ってみろよ。しかし、母親は流石である。
「そう。じゃぁ……イタイのイタイのとーんでいけーっ」
薄暗い世界。混沌とした百鬼夜行的な雰囲気が漂う漠々とした世界。そこへ、またゴボウが吹っ飛ばされてきた。ザサァァーとさっき以上の制動距離である。もう常人なら、痛すぎて帰りたくなるくらいだ。ゴボウはゆっくり立ち上がった。
「っ痛っ……なんでよ……ねぇ、なんでなの」
ぶつくさと何かに対して文句を言っている様子である。
「……よぉし。わかった。ハッキリさせよう」
ゴボウは助走をつけ、再びどこかへジャンプをし、消えた。
「……まだ痛いよぉ」
「まだ?よぉし、じゃぁ……イタイのイタイのイタイのイタイのとぉーんでいけぇー」
薄暗い世界。混沌とし(略)。ゴボウが落ち込んだ様子でゆっくりと現れた。そして、近くにあったショッキングピンク色のベンチに勢いよく座り、深いため息をついた。
「呼んだのお前じゃないか。ええ?呼んだのお前じゃないか。それで行ったら飛んでけって……あいつ頭おかしい。だったら最初から呼ばないでよ」
ベンチの背もたれにすべての身を預け、ぐでーんとするゴボウ。目をつぶり、聞こえないくらいの声量でなにやら呟いている。おそらくではあるが「なんで」と何度も呟いている様子である。しかし、ゴボウはいきなり目を開けた。
「そうだ」
ゴボウは何かを思いつき、立ち上がった。
閑静な住宅街の片隅に、小さな公園がある。その公園にはブランコに乗ったあの少年しかいなかった。お前には友達がいないのか?と思い、よく見てみると、彼の右膝にはカサブタがある。昨日の怪我でできたものだろう。そして、なぜかカサブタのまわりがほんの少し赤い。一人で楽しそうにブランコで遊んでいた少年だったが、何かに気付いたようだ。公園の隣の道には、あの色っぽい女性がいた。少年に向かって手を振っている。女性が着ている赤いTシャツの隙間からチラリと見える生脇(ナマワキ)をよく見ると、ムダ毛がほんの少し生えている。こういうのは高純度の興奮材料となる。そんな女性に向かって少年は「ママ」と叫び、ブランコから飛び降り、「ママ」へ走っていった。少年は「ママ」に抱きついた。
時間的には夕暮れだが、この国の季節ではまだ明るい時間帯。例の少年と「ママ」が手をつないで歩いていた。楽しそうに会話をしている。「ママ」の着ている赤いTシャツにうっすらと脇汗が染みている。トテモイイ。そんな「ママ」は何かに気付いた。
「あれ、カサブタのところなんか赤いわね」
「だって痒いんだもん」
右膝を掻く少年。確かに、さっきから掻いていた。あえて言わなかった(文にしなかった)が、そこそこの頻度で掻いていた。
「掻いちゃだめよ」
「なんで?」
少年の右膝は掻きすぎのせいか、少し出血している。少年よ、こういうことだ。
「ほらだって……血、出てるじゃない」
「えー。だって痒」
ポリポリ。
「ダメッ」
右膝を掻こうとする少年の手を掴む「ママ」。
「わかった?」
「はーい」
「クッソォー」
ゴボウは付けていたチョビヒゲを剥ぎ取り、地面へ叩きつけた。
「あと少しだったのにっ!」
鼻息が荒いゴボウ。虚しく横たわったチョビヒゲがなんとも言えない。
「クソクソクソ。わざわざ変装して、いい所まで近づけたのに。あの女め。余計な事をしやがって。本当に旦那の子かわからないくせに。クソッ」
コラコラ。ゴボウはいささか、口が悪いようだ。
「だが、今回はいい所までいった。もう一度行けば、もしかしたら、イケるかも知れない。ふふふ」
ショッキングピンク色のベンチに座りながら、ニヤニヤしているゴボウ。そして、地面に落ちていたチョビヒゲを拾う、が粘着面同士がくっつき、長座体前屈のようになってしまっていた。
「ちっ。めんどくさい」
ゴボウは文句を言いながらも繊細な手つきで、長座体前屈をゆっくり解除する。うまくいったようで、すぐにチョビヒゲを、名称がわからない鼻と上唇の間に貼るやいなや、笑い声を発しながらどこかへ走っていった。
「そんなに痒いの?」
「うん」
困った様子の「ママ」は少し考えて、ある結論を導き出した。
「じゃぁ、そこ、叩きなさい」
「叩くの?」
「掻くよりかはマシだと思うよ。とりあえずカサブタは無理にとったら傷が残りそうだから、掻かないで」
「はーい」
少年はカサブタをまた掻こうとしたが、「ママ」の言うとおり、叩いてみた。思った以上に痒みを緩和できたので、少年はご満悦のようだ。
「どう?」
「うん!これなら大丈夫!」
薄暗い世界。混沌とした阿鼻叫喚的な雰囲気が漂う悶々とした世界。目を凝らして見てみると、何者かがうつ伏せで倒れている。……ゴボウだ。さらに、目を凝らして見てみると……泣いている。ゴボウは泣いているようだ。
「……違う……。叩くのは違うんだよ……」
ゴボウのそばには、また長座体前屈になったチョビヒゲが横たわっていた。
「こう、爪でガッっと痒いところをボリボリ掻いて欲しかったの……」
見た目は五十代、調子が悪いと六十代にも見えるゴボウが泣いている。
「やっぱり『痒み』は向いてないのかな……精神的ショックが『痛み』より強い……はぁ」
仰向けになるゴボウ。眼前には、死屍累々の『空』のようなものが蠢いている。ゴボウの目にはもう涙はない。すると、ゴボウはどこかで聞いたことがあるようなメロディの演歌を歌いだした。何もない空間にゴボウの歌声が響く。
二曲目に突入した。仰向けのままのゴボウは自分なりに精神を落ち着かせているようだ。すると、目をつぶっているゴボウは何かに気付いた。
「ん?……あのガキの傷……化膿してきてるわ」
そういうと。ゴボウは起き上がった。
「これは……最後のチャンス」
ゴボウの表情は狂気に満ちていた。
「あの化膿、うまくいけば最高の『痛み』になるかも知れない」
ゴボウは立ち上がり、笑っている
「さぁ、小僧。『痛み』を感じなさい。そして、その先にある」
ゴボウの言葉は急に詰まり、少し驚いた表情をしている。
「……『痛み』の先ってなに?……そもそも私はなぜこうも『痛み』に執着するの?」
自問自答するゴボウ。だが、考えれば考えるほど彼女の思考は混乱する。
「痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い」
膝から崩れ落ちるゴボウ、その顔には一切の表情は感じられない。すると、ゴボウはゆっくりと消えていった。
鼻息すら白くなる冬のある日。子ども達は元気に校庭でドッジボールをしている。その最中、突き指をした少年がいた。
「大丈夫?」
「うん、ちょっと痛いけど」
どこかで『痛み』が生まれた。
そして、どこかで『痛み』が消えた、多分。
ペイン