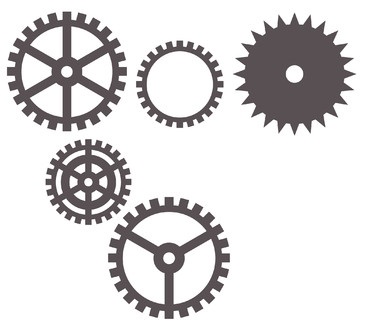
AMU
人生には様々な生き方がある。
小さいころは「スポーツ選手」とか「ケーキ屋さん」とか夢を持っていた―――のに。
今は夢なんてない。
というか高校生の私にとってはそれが普通だった。
だってもう、運命は決まっているのだから。
努力したって報われない。頑張ったって評価されない。
そんなのは知っている。
でも。だからこそ。
叶えられない夢に媚びてもいいんじゃないかな?
それで気持ちが少しでも楽になるのであれば…
ここに一人、運命が決まっている少女がいた。
その子は不思議な力を持った不思議な女の子。
―――でも、その子はそれを知らない。
知るはずもない。
男の子は見ていた。彼女の姿を、、、いつも。
いつかその子に見てもらえるように。
その子のそばにいられるように。
ずっと…
一生…
そして、男の子の夢は―――叶う。
序章
『ミャー…ミャー…』
「どうしたの?捨てられちゃったの?」
降りしきる雨の中、女の子は傘をさして子猫とお話をしていた。
泥だらけの子猫と自分が似ていたから無意識に話しかけていたのかもしれない。
その当時の彼女の気持ちは、誰も知らない。
知るはずもない。
「私も一緒なの…仲間だね」
女の子は子猫にニコッと微笑みかけた。その表情はどこか寂しげに見えて、どんよりとした雨が、彼女の周りには美しい絵のように栄える。
子猫はわからないといった表情で鈴を鳴らし、首を傾げる。だが、鳴きはしなかった。その必要性を感じなかったから。
雨は女の子の心の中の泥にゆっくりと染み込んでいく。
「…そろそろ帰らなきゃ」
女の子はそういって立ち上がった。子猫はそんな彼女をじっと見つめている。
雨水は猫が入っている段ボールに染み渡っていく。
「これ…私のお気に入りの傘…あげるっ!!」
女の子は子猫に雨が直接当たらないように傘を足元にそっと置き、その屋根にした。
それでも子猫はただ彼女を見つめている。女の子はさっきとは違う笑顔を子猫に向けた。
「じゃあねっ…!」
女の子はそのまま雨の中を走り去って行った。
その後ろ姿はどこか自信に満ち溢れているようにも見える。子猫は彼女の背中から目を離さなかった。
やがて見えなくなり、子猫はチリーンと再び鈴を鳴らす。
『ミーシャ様、お迎えにあがりました』
1人の紳士的な男がひっそりと現れ、子猫にお辞儀をする。
『ミャーオー…』
それに答えるように、小さく鳴いた声にはさまざまな感情が交差にしているように思える。
子猫は心の中で微笑んだ。
―見つけた。
高校2年生にもなればその高校にもいい加減慣れる。
友達も1人2人はできるし、先生とも最低限の会話もできるようになるし、勉強とか、習慣とか、人は慣れだというが、私もその通りだと思う。
高校生活にもそれなりに最低限にクリアしなくてはならないことがあり、1つとして挙げれば教師とのコミュニケーションである。
高校生活においてそれは絶対不可欠であり、その条件をクリアしたとき、私たちは薔薇色のような未来を約束される。
…と言うと教師の存在を過大評価しすぎになってしまうが。
勿論、私もこれらの最低限の条件はクリアしている。
「先生ーっ!おはようございましたーっ!」
『それを言うならおはようございます、だろ~っ。ったく、お前の日本語はいつもどこかおかしいよな~っ』
そう指摘しながら笑って職員室のほうへ去っていったのは現代文の先生。
彼の授業は本当に退屈で声も籠っているので子守唄にしか聞こえないのだが、個人で話すとそれなりに面白いので嫌いじゃない。
私、森永あむは、そんな先生の姿を満面の笑みで見送ってから、教室へ向かった。
私が通う『隼高校』は世界でも注目される超一流の進学校。
うちの高校は世界でも研究されていて未だかつて発見されていなかった『DaLE』という不老不死になれる絶対的細胞を見事発見し、ものすごく高い評価をされ、今年の立派な賞をいくつも獲得したという名誉ある高校である。今ではその細胞を人間の体の中に取り入れて不老不死を可能にしようというプロジェクトが進んでいる。本当に超エリートが集まっているすごい学校。
まあ、私はそんなにすごくないから関係ないけど。
私のクラスは学年でも一番低い『Ⅱ-Ⅶ』さまざまなタイプの不思議な人が集まるとても面白いクラス。本当かどうかは愚問だが、Ⅶ組の生徒は皆超能力者、予言者、霊媒師、魔法使い、戦士、など普通では考えられないような人間ばかりいるらしい。
うちの学校は超特進科、特進科、普通科、スポーツ科、医療看護科、特殊科、とさまざまな学部が存在するが、一目でわかるとおり、私は一番身に覚えのない特殊科に入っている。
―でも、時々思う。
どうして私みたいな超普通な女子高校生がこの学部なのか、と。
―そんなものは明白だったのだ。
彼女が気付いてないだけで、彼女は存在それ自体が偉大だった。
もはや彼女こそが、次期神の座に相応しかった。
≪自習 10:30~14:30≫
教室に入り、ふと目に入り込んできたのは黒板にデカデカと書かれた雑な字だった。
10:30~14:30まで自習…?ってか14:30って下校時間じゃん私!!
うちのクラスだけは『フリースクール』ならぬ『フリークラス』というもので、自分で授業時間のカリキュラムを作るのである。そのうえで、好きな時間に学校の来ても可能だが、2時間以上登校しなければならないという条件がある。
2時間だけなら無意味な気もするのだが…。暇つぶしとしてはちょうどいい時間なので、全然文句とかそういうのはない。
ちなみに今の時刻は12:30。
あむはクラスメイトと少しだけ挨拶を交わし、気分転換がてらに屋上へ向かった。
気分転換がてら、のつもりだった。
× × ×
どの学校にも、ビルにも屋上というものは存在する。
勿論この学校にも。そして、屋上はだれの物でもない。強いていうなれば、この学校の持ち主である校長のものだとは思うが、実際のところはわからないというのが現状である。
というかもう考え出すときりがないし面倒くさいので皆のもの、ということにしよう。
だから、私があれこれ言うべきものではないのだが。
つまり何が言いたいのかというと、今この屋上には私ともう1人、
小さな子どもがいる。
~悪党とその仲間たち~変!?
私はこの世の中で大人が一番苦手だが、それと同じくらい子供も苦手だ。
うるさくて、わがままで、自分勝手で、泣き虫で、見ているだけでイライラしてくる。でも、今までの過去を振り返ってみると私にもそのようなわがままな時期はあったのかと思う。いや、確実にあっただろう。なければ人間ではない。
しかし、そんな苦手物質が半径10m以内に存在しているのだから堪ったもんじゃない。
「こ、こんなところでなにをやっているのかな~?お嬢っ…」
後ろ姿からは男の子か女の子か判別が不可能だった。でもスカートズボン履いているし、多分、というか確実に女の子だろう。もし男の子がスカートなんて履いていたら驚くしかない。まあパッと見たところ7歳くらいに見えるし、男がスカートを履いても許されるこの時代、わからなくもないのだが。
とりあえず私の中では女ってことにしておこう。
そんな私の声が耳に入らなかったのか、彼女は空を見上げたまま振り向きもしない。
少しだけ距離を縮めてさっきと同じことを問いかけてみる。
「こんなところで何しているの~?」
すると彼女はハッとしたかのように肩をビクつかせ、ゆっくりと振り向いた。その瞬間吹いた風があむの髪をなびく。
それとは別に綺麗になびいたクリーム色のふわふわした髪が、あむを虜にした。
「…」
『…』
しばらく見つめ合った…と思う。
というか彼女がどこを見ているのか、今の状況では正直わからなかった。きっと私の顔を見ているのだと信じたいけど…。
なぜそんな意味不明な言動をするのかというとそれは…仮面を被っているから。
今小学生の中で大人気アニメ『地獄戦争』のミクミの仮面を。
「…」
しばらく硬直していた。予想外の展開に。まさかミクミの仮面を被っているとは思うはずもなく、思考が混乱する。なぜ仮面を被っている?
…というか、なんでここにこんな小さな子どもがいるの?
厳重に警備されているはずのこの高校に侵入者とも言えるべきこの子をどういった経緯で入れたのか不思議で仕方なかった。
この子がこちらに振り向いた瞬間、色々なことを考えていた。
その中に「今日の晩御飯は何かな?」も加わっていたのは言うまでもない。
『トモエ』
振り向いた直後にその子が発したのは、その台詞だった。透き通った綺麗な声が耳をいじめる。心臓の鼓動が変に緊張という気持ちを表すかのように音を奏でる。
トモエ?…誰かの名前?だとすれば誰の?
『ミナヅキ トモエ』
少し考えたらすぐわかることであった。彼女が発したのはきっと彼女自身の名前なのだろう。トモエ、ということはやはり私の予想通り女の子か。は~すっきりしたっ!
『ボクの名前は水無月叶萌。以後、お見知りおきを。』
その口調は幼い子どもを感じさせない独特のオーラを醸し出していた。聞けば聞くほど美しいその神々しい声に、小さいながら貫録を感じる。
しっかりしすぎでしょ…
叶萌の第一印象はまさにそれだった。
「私の名前は森永あむ。よろしくね」
気づいたら無意識に、自分の名前を口にしていた。
っていうか、『ボク』ってことはやっぱり男の子?
最近の親は男でも女の子っぽい名前付けるっていうし…アヤとかユイとか…
あ~もう顔見たいっ!
もどかしい感じが私の好奇心をいじめる。知りたいって思えば思うほど仮面を取って知りたいって思ってしまう。
でも、それに関して触れていけないってことはなんとなく勘で察した。
それを取ったらこの子の正体が完全にわかってしまうということ。
そしてそれはこの世の終わりだということ。
だから自然と自分の名前を口にしていたんだと思う。この子と何かを共有したくて。
しばらく見つめ合っていると、何の前触れもなく叶萌は言葉を発した。そしてその言葉に、私は再び硬直することになる。
『あむ。君は想像もつかないくらいすごい力を備えている。この世界で一番、誰も真似することのできない、強力な素晴らしい力を。』
そう言った叶萌の顔は私の方を見ているけど、本当に見ているかはわからない。ただミクミの気持ち悪いくらい大きな目がこちらを直視していることだけはわかった。
…というか力って何?
私が世界で一番強力な素晴らしい力を持っているって?学校で行われる体力テストで学年最下位の私が?
人違いなのかと思った。
この子…何を言っているの?
「力…?」
心の中で思っていたことを思わず口に出してしまう。人間は何を信じられない時、無意識にその言葉を発するという特性がある。今の現象はまさにそれだ。
『君の力を求めて死の国から多数の悪党がやってくることだろう。でも、きっと大丈夫。君なら守ることが出来る。自分自身を、自分の過去を――…』
全身に熱がこもった。今まで味わったことのないような不思議な感覚に苛まれる。
死の国…?悪党?どうしてそんな人たちが私の力を求めてやってくるの?この子は何を言っているの?それに一番気がかりなのは…
「私の過去…?」
もう何を言っているのか全然理解できなくて脳が疲れてくる。
というかまず、子どものくせに私より大人口調なのが許せない。…ものすごいどうでもいい自分勝手な意見なのだが。
知らない間に叶萌がゆっくり私の方へ近づいてきていた。そして、私の背後へとまわり、制服のショートパンツをギュッとつかんだ。
意味不明な行動に素直に混乱する。すると叶萌は私の脚に顔をうずめるようにして言った。
『ボク、君が気に入った。だからずっとそばにいる。』
「…え!?」
叶萌のそんな意味不明な発言にも驚きを隠せず、混乱状態に陥った。
私のことを気に入ってくれるのは勿論嬉しいけど、けどずっとそばにいるって何!?
まさか婚約宣言!?私がこんな小さな顔も知らない変な子と婚約!?
頭の中でおかしな想像をしてしまったが、少し落ち着いてみることにしよう。
ずっとそばにいるって叶萌は言ったけど、実際いずれは離れてしまう。それがこの世界においての運命であり、日常である。人間、ずっと一緒にいるなんて不可能な話だ。
だから最初は困ったけどすぐにニコッと微笑みかけて、
「うん、一緒にいようねっ」
と、素性も知れない子に宣言してしまったのだ。
『―みっけ』
それがすべての始まりでありすべての終わりだということも知らずに…
叶萌はギュッとしてから離れようとはしない。ショートパンツ越しからでも感じられるクリーム色の柔らかい髪の毛があたってくすぐったい。
「いい加減離れてもいいんじゃないかな?」
正直さっき言ったことを後悔しながらそう提案すると、さっきよりも強い力で握り、叶萌はたった二文字で拒否、ということを表した。
『ダメ』
だから子ども嫌いなのである。わがままで自分勝手で、本当に疲れる生き物だ。
私はわざとらしくはぁ…とため息を吐いて、叶萌の頭を両手で密着を避けるように押さえつけた。
「もう離れてっ…!」
強く押してもなかなか離れようとはしない叶萌。本当はここで諦めてもよかったのだが、心の中にある変なプライドがそれを許さず、私は思い切り全身の力を両手に集めた。
―その時。
ピカーーーーーーーーンッ!
私の両手が青く光り、気づいた時には叶萌は10mほど先に吹き飛ばされていた。
「なに…これ…?」
何が起こったのか理解できなくて、混乱した。しかし、そんな私を誰も待ってくれはしない。
『神の光…その名も雷光。保護完了♪』
『なんか…案外ちょろいな』
気づいたら私は、知らない男女に両手をロープ状の縄で縛られていた。てか、宙に浮いている!?何がどうなっているの!?
突然の出来事が並んで言葉が見つからない。それと同時に押し寄せてくる恐怖心が私の中でどんどん大きくなっていく。
「え…あなたたちはっ…?」
おびえた声でそう聞いていた。
真っ黒のドレスに包まれている長い黒髪が印象的なツインテールの少女と、真っ黒の戦士服を着ているフワッとした黒髪の少年。2人ともどこか似ていて、どこか違っていた。
私が二人の正体を訪ねると、少女のほうがフッと微笑んで大きな瞳でこちらに顔を向けた。
『うちの名前は足弥三砂(あしや みさ)!!魔王様に頼まれてあんたを捕まえに来たのよ♪感謝しなさいっ!』
魔王…?何?何の話?
ハキハキとしたクリアな声で早口に喋る三砂はとても満足そうな小悪魔的笑みを浮かべた。例えるならば何かの対戦ゲームで勝った時に誰もが見せる、勝ち誇ったようなそんな嬉しそうな笑み。
不思議と魅力的に感じる。
しかし、それとは正反対に少年は呆れてものも言えない、というような表情を浮かべていた。
「おい、三砂!むやみに名乗るな!魔王のこともそう簡単に口にするなよっ!少しは考えろ、馬鹿女!」
かなりお怒りの様子。きっと三砂が何かいけないこと言ったからだろう。しかし、気の強い三砂もそんなすぐにはひるまない。
『何よ!別にいいじゃない、どうせこの子は魔王のところで魔力を失ってまた一から人生をやり直すんだから!しかも、この計画がバレるのもどうせ時間の問題よっ!!』
『だからって言う必要性ねーだろ!』
まるで犬猿の仲だと、あむはつくづく思った。
2人はお互いを睨み合って、どちらも負ける気はさらさらないといった表情である。
その間にロープをほどこうと思ったが、あまりのきつさと動かせば動かすほど縛りが強くなるため、諦めることしかできなかった。
『ま、馬鹿秋人は置いといてっ。さっさと着いてきなさい。あんたは今から生贄になるのよ。』
さっきの茶番は終わったのか、三砂が再びニヤッとさっきとは違う笑みを浮かべた。
「生け…にえ?」
何の話か理解しようがなかった。私が…?誰の?
『そうよ、あんたは今から魔王様のための生贄になるの。人間だって自分のためになら動物を感情もなく殺すでしょ?そんなものよ。』
そう言った三砂の瞳はどこか虚ろに見えた。何かを思い出しているかのような、寂しい濁った瞳。怖いはずなのに今の彼女にそう思うことが出来なかった。同情という感情が生まれたから。
『…ってあいつはっ…!?』
いきなり秋人が声を上げて、三砂がハッとした。同時に私の体もビクつく。
2人の視線の先の方に目を向けると…叶萌?
2人は叶萌を見て硬直していた。どうしてなのだろうか。そんな疑問が少し考えればすぐにわかるというのに。
叶萌はただこちらを見上げている。ミクミの唇が少し歪んだ気がした。
『やばいっ…くるっ…!』
秋人がそう言った瞬間、目の前が真っ赤な炎に包まれた。
『あっちぃーぜ…侑!お前ちょっと激しすぎだろ!馬鹿か!』
『貴様以上の馬鹿などこの世のどこを探しても存在しないから安心しろ』
何が起こったのか全く理解できなかった。というか理解を働く暇がなかった。分かる範囲で説明するならば、私の隣にはさっきの男女ではなく、長身の男2人が立っていて厳密に言うとその中の1人の男性に抱きかかられているということだけである。
『怪我はしていないか?』
眼鏡越しにその人は問いかけてくる。まるで何もかも見透かしているかのような瞳でこちらを直視している。私は何も言わずに、ただゆっくりと頷いた。
するとその人は表情を変えないまま下を見て、
『叶萌、あとは頼んだぞ』
叶萌目がけて私のことを…投げた。
「ひゃぁああああっ!!」
宙をまるで落下するボールのように投げられた私を小さな叶萌が軽々しく、と言ったらあれだけど、何事もないように捕まえる。今は笑顔なのだろうか、叶萌がこちらを見下げてくる。
「ごめんねっ、重いよねっ!」
私は慌てて叶萌の腕の中から飛び出るようにして足をバタつかせ、脱出した。
『もっと大事に扱えよな~貴重品なんだから、一応』
『不器用なお前に言われる筋合いはない』
眼鏡の男とは対照的に、うに頭のような金髪男はよく喋る。
『お前なぁっ…!』
何か気に障ったのか、金髪男は眼鏡の男につっかかろうとした。そんなのは気にも留めず表情を変えた男は、表面を向き、ダーツのような小さい矢を手に数本持った。
『来るぞ』
2人は背後から襲いかかろうとした男女を難なくかわし、4人は向かい合った。
「何が始まるの…?」
あむは唖然と宙に浮かぶ世にも珍しい人間と、空を見上げた。
『またお前らかよ。魔王のくそじじいは相変わらず元気か?』
語尾に(笑)が付くんじゃないかってほど2人を挑発するような態度を取る金髪男、そしてその挑発に簡単に三砂が乗った。
『魔王様って呼びなさいっ!私たちにはあんたと悠長に話している時間はないのっ。ほら秋人、行くわよっ!』
『おうっ!!』
男女は空へと瞬時に飛び上がり、2人目がけて急速に落下してきた。
『『サイクロン・ブーストッ!!』』
風邪を身にまとった男女はお互いに重なりあい、攻撃を試みる。しかし、2人はその攻撃をなんなくかわす。意味不明な現実に目を疑った。
『じゃあ…俺から行くぜっ!!』
長身の金髪男はニヤッと悪魔的、否、天使的笑みを浮かべ、背中から剣を取出し、慣れた手つきで宙に八の字に激しく回転させ始めた。―すると。なんの変哲もない黒々した大きな剣から突然炎が発生した。
あむは熱くないのかな、とのんきに心配する。
『ファイアー・ジェ・ルリータッ!!』
激しく燃え上がる炎をまとったその剣と男は、男女目がけて振り落とされる。空の上に炎の海を見た気がした。…炎の海?
剣は少女の漆黒なドレスに触れ、あっという間に太ももまで焦げ消えた。攻撃は…外したみたいだ。
『あ~ん、またドレスが焦げちゃったじゃない!あんた、許さないわよっ!』
三砂は目つきを変え、頭に付けていたジュエリーのついた細長い髪飾りを外し、手に取った。地上からはよくわからないけど、秋人も同じようなものを頭に付けているように見えた。
『ベール・クトゥーナ』
目で追うことが出来なかった。一秒前まで確かに少女の手の中にあったはずの髪飾りが金髪男の胸に的中していた。否、ギリギリで止めたのであろう、胸を左手がカバーしていたようで突き刺さることはなかった。その代り、左手のど真ん中に命中していた。ダーツならばダブルブルと言ったところだろう。
『チッ、外したか』
『いってぇえええええっ!!』
金髪男はそれを抜き取ろうと試みているが激しい痛みでなかなか抜き取れず、激しく体を動かしている。しかし、右手に持っている剣を離そうとはしない。剣でその髪飾りを弾けばよかったのにと思いつつも、見上げる。
髪飾りは自然と左手から抜き取られ、三砂の手元へと戻っていった。まるで磁石のように。
『まじあのくそ女許さねぇっ!』
『あんたを…殺してあげるっ!♪』
2人が互いを睨み合った―その時。
~♪♪♪~
秋人の、携帯のような電子機器が音を奏でた。そそくさとでる秋人。
『こちらHS27。ご用件は?』
相手の声を聞いた瞬間か元からそうだったのかはわからないが、とりあえず秋人の顔色が真っ青になっていくのは分かった。
『―はい、承知しました。ただいま参ります。』
ピッ
『誰だったのよ?』
一時中断と言わんばかりに金髪男などお構いなしと秋人のほうに体を向け、問いかける三砂。
すると秋人は少し震えた声で答えた。
『魔王様からだ』
その単語を聞いた瞬間、三砂の顔色もまた真っ青になっていく。
この中でその理由を知らないのはただ一人、あむだけである。
『行きましょう』
そして、男女は何事もなかったように、視界から消えた。消え失せた。抹消した。…目の前の事実を疑った。
『くっそ!あの野郎ども、逃げやがって!』
2人の突然の退散に納得がいかないのか、金髪男は何やらおこり気味。眼鏡の男はそんなのには見向きもせず、上空から私と叶萌の近くまでゆっくりと降りてきた。先ほどまで所有していたダーツのような小さい矢はなく、代わりに真っ白なカバーの本を手に持っていた。
…いつどこから取り出したのだろうか。
服装からしてその四六判の本を収納できる場所は見当たらない。少しばかり興味がわいたが、さすがに点検するわけにもいかないのでやめた。
だって、気持ち悪いでしょ?
『叶萌、ありがとうな』
何に対してのお礼の言葉なのか少し考えたが、多分私も関わっていることなのだろうと思う。そう言って眼鏡の男は手に持っていた本を読み始めた。叶萌はそんな男をただただ見上げている。今はどんな表情をしているのだろう。無意識にそう考えていた。
しばらくして頭が冷えていたのか、上空から金髪男が降りてきて、こちらへやってきた。よく見ると彼の左手には先ほど髪飾りが刺さってできていたはずの傷がない。…どうして?
そんな彼の黄金に光る瞳に思わずうっとりしそうになる、がしかし異常に眉間にしわを寄せているので直視することが出来ない。
眼鏡の男同様叶萌に用があるのかと思っていたら、金髪男は私の目の前まで来て、
『―お前』
先ほどより深く眉間にしわを寄せた。目をそらしたくてもそうさせてくれないほど、私の体は硬直している。考えなくても、感じる。
私は冷静を装い、不思議そうに男を見た。
『お前、森永あむ、だな?』
確定している上で聞いてきたのにはやはり疑いを感じているからなのだろうか。なぜ私の名前を知っているのか疑問に感じたが、ここで嘘を吐く必要なんてまるでないので小さく頷くと、読書中の侑の体が一瞬反応した気がした。なぜ確信がないのかというと、それはこの男の目を直視しているからである。
すると金髪男は何か確信を得たかのように口を開いた。
『そうか…オレは神志路天磨(かみしろ てんま)。お前を“死の国”の魔王、ダラキアから守るため、“生の国”から来たオレたちは使者だ。』
何のSF小説の設定なのか理解できなかった。天磨の言っている意味がよくわからなかった。
死の国?
ダラキア?
生の国?
使者?
この人…頭おかしいんじゃないの?
おかしいのは私の方だというのに。
だからなのだろうか。鋭い黄金の瞳の天磨の顔を見て自然と無意識に口が動いた。
「****の指輪…」
―私は今夢を見ているのだろうか。何かを呟いた瞬間、ポンッという効果音とともに、目の前に少年が現れた。私よりも小さい、中学生くらいの少年。先ほどまで見上げられていた黄金の瞳はなく、少年の金髪と真っ青で綺麗な快晴が広がるばかりである。
少年の顔は少し幼くなった天磨のように見えた。
「…」
ふと我に返る。この子…誰?
『なんだ…これ…』
皆硬直している。でも多分一番驚いているのは私だろう。
私今さっきなんて言った…?
思い出せない…
『なんだよこれぇええええええええっ!』
天磨の叫び声はきっと天国の神様の耳にも入ったことだろう。
お昼寝中なら申し訳ないものだ。
天磨のような少年は自分の手や身体を見て信じられない、というような表情で目を見開いている。
目の前の光景にこれはやはり夢なのではないかと現実逃避をしていると、侑がこっちを向いた。
『自分は入江侑(いりえ あつむ)という者だ。』
「え、今さら?」
思ったことを思わず口にしてしまった。
~天無梨莉湖とその仲間たち~変!?
誰にでも寿命というものがある。
日本人女性の平均寿命は約86歳と聞くが、私は絶対そんな長生きはしないと思う。
たとえばボールペンのインクの寿命は約1年、シャープペンシルの芯の寿命は約1週間。だがどうだろう、シャープペンシルの芯は最後まで使い切ることはできない。どんなに短くても約1㎝が余って捨ててしまうだろう。そう、私はそのシャープペンシルの芯のように頑張れば生きられるのにあえて若くして命を絶ちたい。できれば死に方は安楽死で…
―なんて現実逃避はやめにしよう。
でも、叶萌が今言ったことを簡単に信じることなんてできるだろうか?
「ああ、そうですか。」なんて容易には言えない。いや、言える人はいるかもしれない、でも私には不可能だ。
だって、“私が神様のお気に入られているから魔王に命を狙われていて、様々な敵が私の秘力を求めて襲おうとするから、それを阻止すべく、天磨と侑が*生の国*からやってきた”などという漫画や小説に出てきそうな、そんな内容。
大体、神様とか魔王とか簡単に言ってくれているけど、私にはそれすら意味不明なんだからね、なんて心の中で指摘してみる。
生の国…そんなの地理では習わなかったぞ?そんな国、どこにあるの?
疑問から疑問が生まれ、再び疑問が浮かぶ。人間の思考回路というのは本当にすごいとは思うが、それ以上に疲れる。
―話を終えたのか、先ほどまで座っていた叶萌はピョンとうさぎのように跳ね、立ち上がった。なんてかわいい動作なのだろう。
『ボクは部屋に戻ってやることがある。退散させてもらいます。』
「あっ、ちょっと待って!」
聞きたいことがまだ山ほどあったというのに、仮面の子どもは素早く消え失せた。というか叶萌、私のそばにずっといるんじゃなかったっけ…?と思っていると、天磨が私に近づいてきた。
『てめぇ、早くこの魔法解けよ、あぁっ!?』
これっていうのは言われなくてもわかる。私が一番よくわかっていて、彼にとても謝罪では済まされないくらい有りえないことをやってしまった。これとは、あれだ。
「ま、魔法!?えと、すみませんっ、私もどうしてこうなったのかはさっぱりで…」
目の前にいる金髪少年に深々と頭を下げる。何て言ったのかはわからないけど、自分のせいでこの少年、否、男性に迷惑をかけてしまったことに罪悪感を覚える。
『それは変貌の魔法だ』
困惑していると、叶萌がいなくなって初めて、侑が口を開いた。とっさに侑の方を見るが、ずっと変わらず四六判の本を読んでいる。そこには何が記されているのだろう…?
「魔法…?」
非常識な言葉を聞いたのはこれで2回目である。なにそれ、魔法なんてあるわけないのに。そう思っていると、侑は本を開いたまま、こちらを向いた。
『貴女が使ったのは変貌の魔法。それもこのタイプは、人の容姿を過去の姿に戻す、という極めて難しい魔法だ。しかし、その解き方はどの本にも記されていない…。特にこのタイプの魔法は簡単に取得できるものではない。叶萌でも2年はかかった』
よくわからなかったけど、とりあえずすごいと思った。
『っつーことは、オレはずっとこのままなのか!?っざけんなよ…』
天磨がそう一人で頭を抱えているのを見て、本当に申し訳ないと思ったのと同時に、どうして自分がそんな魔法を使ったのか、使えたのかが不思議で仕方なかった。
なんで…?
「どうしてそんなすごい魔法を私が…?」
『貴女は特別だ。叶萌が認めた特別な人間なのだ』
侑がそう断言した。侑はさっきから叶萌の名を何度も繰り返し口にする。
叶萌って…そんなにすごいの?
「あのっ…~♪♪♪~
思い切って叶萌のことについて聞こうとしたら、誰かの携帯のような電子機器音が鳴った。天磨が腕に付けている時計のようなものを見る。そしてハッと驚き、侑を向いた。
『うわ、やっべ!もう夜になるじゃねーかよっ!早くしねーと神に怒られる!行くぞ、侑!』
『自分は指図されるのが嫌いだ、非常に』
ふと二人のやり取りと見ようと視線を向けたが、2人ともどこかへ消えていた。抹消されていた。さっき叶萌のように。…夜?空を見上げても美しい快晴が広がるばかりである。
「うん、きっと夢だ!幻だ!」
リアルな夢を見たのだと自分に言い聞かせて、私は屋上から出て行った。
―梨莉湖は一部始終をその目でしっかりと見ていた。
“叶萌みーっけた♪”
その表情はやがて、笑顔に変わった。
× × ×
あれから3日ほど経ったけど、特に前の生活とは変わらず、普通の毎日を過ごしている。
やっぱり悪い夢だったんだねっ!あれから何も起こってないし、うん。
しかし、その3日間は奴らがことを始める前の準備期程度だったということ、そして日常的な毎日は今日で終わりを告げることを、―この時、あむは知らなかった。
知る由もなかった。
そんな3日目の朝。
あむはいつも通り制服に着替えて、家を出た。…しかし、今日の学校はいつも通りではないことをこの子はまだ知らない。確実にその時は迫っているのというのに。
いつも通り学校に着いて、すれ違う未来の日本を担う天才たちをたたえながら教室へと向かい、適当にクラスの子と話して昼寝をする。
いつもはこの通りにあむの学校での時間が始まるのだが、ちょっと違った。
…というかかなり。
教室に入るまではいつも通りであった、その日常も少しずつ崩れていく。このことにあむはまだ気づいていない。そしていつも通りに過ごす予定だった今日という日が、これからという日が、この日を栄にもう戻ってこないことを彼女は明日、知ることになる。
―事件は意外とすぐに起きた。今のところまだ誰も知らない。
この学校に…
「爆弾」が仕掛けられているということに。
事件は教室に入ってからすぐ起きた。
~♪♪♪~
あむが教室に入ると、まるでそれを察知したかのようにタイミング良く教室の電話が鳴った。いつもなら学級委員である無問(むとい)さんが取るのだが、あいにくというべきか、周りを見渡しても無問さんの姿は見えない。あむは一番近くにいた責任からか、仕方なく電話を取った。
―これが全ての始まりだということも知らずに。
「もしもし…Ⅱ-Ⅶの森永あむです。用件をお願いします。」
あむは言い慣れたかのように言葉を並べていく。教室の電話に外部からは掛けられないよう厳重に警備されているので、職員室からだというのは確信できる。しかし、電話先の相手は何も言わずに黙っている。
あむは不思議に思って、聞き返してみた。
「あの…ご用件はなんでしょうか?」
何かがおかしいと思い、少し疑うような口調で聞いた。すると相手は小さな声で、普通では聞こえないくらい静かな声で呟いた。
≪この学校に爆弾を仕掛けた≫
その声はクラスの話し声などかき消してしまうほど大きく聞こえ、その言葉を理解したとき、私の体全体の脈がどんどん速くなっていくのが分かった。
私は『バトル』系のアニメは好きだが、『戦隊』系のアニメは好きじゃない。自分のために戦っているバトルに対し、戦隊モノは人を助けるためと言っておきながら、人を傷つけ、悲しませているからだ。
誰に許可を取って巨大化しているのか、町を破壊したお前たちが全てを弁償するのか、と私は幼いころ戦隊モノのテレビを見ながらいつも思っていた。今ではその理由も概ね理解できているが、まだ幼かった私にとってそれは不快で仕方なかった。
でも結果的にそのような人々がいることで悪党を撃退することが可能で、助かっている人はたくさんいる。だから、私にはわからなかった。
何が正義で、何が悪なのかを…
この時、爆弾を仕掛けたというこの人にこの状況は利益のあることで、この学校が無くなることで助かる人がたくさんいるのかと思うと、
「…」
私は何も言えなかった。
そして“はい、わかりました”と納得するべきなのか、混乱するべきなのか、判断することが出来なかった。
普通の人間ならば迷わず後者を選ぶだろう。私も後者を選んだ。
人間として、最低限の条件をクリアしたかったから。
「えっ、そ、それはどういうっ!?」
≪静かにしろ。もし仮に騒ぎでもしたら今すぐ爆弾のスイッチを押すぞ≫
混乱すると、殺意が湧いたようなドスの利いた声そう命令され、背筋が一気に凍った。
今の状況が全く理解できない。
…爆弾!?
警備が完璧に整っているこの学校にどうやってそんなものを持ち込むことが出来るというのか。まず外部の人間が不可能だとすると…内部の人間?しかし、何のために?
世界的に注目されているこの超進学校が破壊され、日本を担う高校生たちが皆殺しされたとすれば、全世界は絶望し、未来には生けなくなるだろう。
でも正直私にはそんなこと、どうでもよかった。今を生きられていればそれでいい。
―しかし。学校となればスケールがかなり大きい。3000人以上いるこの学校の人々の未来を私が自分勝手に決めてはいけない。私には皆を救う義務がある、皆を救う責任がある。
そう思うことが自分勝手だというのに。
「どこに…隠したのですか?」
そう警戒しつつ聞いたはずなのに、相手の答えは違った。
≪制限時間は2時間。では、健闘を祈る。≫
健闘を祈るなら初めからこんなことするなよ、と思っていると、相手は一方的に電話を切った。
その瞬間、
ビィィイイイィイイィイイイッ!!!!
まるでクイズ番組で問題を間違えた時に鳴るような、あの不快な効果音がクラス中に響いた。
時計を見ると10:00ぴったり。ということは12:00までに爆弾を見つけなければ…
―この学校は終わる。
多分今さっきの音はゲーム開始の合図だったと思われる。クラスは一瞬静けさに包まれたが、またすぐに賑やかさを取り戻した。
辺りを見回してみるが、この教室に爆弾を隠せるような場所などあるだろうか。掃除道具入れなどこの教室には存在しないし、ロッカーもない。意味もなく見渡しているとふと、窓側の一番端の席に座っている男子と目があった。あれは確か…名前が思い出せない。クラスメイトだというのに。
彼は私のことを睨みつけるようにして見つめてくる。金髪に近い茶色の短髪に赤いメッシュがあり、とても個性的である。私は少し怖くなって目をそらした。そしてとりあえず教室を出ようと、教室のドアを開けた。
どこへ行けばいいのか、どこを探せばいいのか、それすらわからない。
校舎全体?体育館?プール館?情報があまりにも少なすぎて選択に躊躇する。
とりあえず校舎全体を探してみよう。気づけば、私は走り出していた。
―幼き少女は親指を赤ちゃんのように咥えながら、走り去る彼女を見てニヤリと笑った。
が、その顔は歪むことはない。
“叶萌はリリのもの…”
少年はそんな少女を見てため息を吐き、青年はそんな2人を温かく見守っていた。
× × ×
私は今、何故か2年校舎の7階にいる。ここはⅡ-ⅠからⅡ-Ⅲ、所謂超特進科と特進科に入っている未来を担う人々が勉学には励んでいる階、いわば私みたいな一般人がどんな理由があれども来ることを許されない空間だ。
…だか、私は来ていた。適当に走っていて気づいたらここに来ていたのだ。自分でも不思議なくらいである。
授業の邪魔にならないように静かに、忍者の如く教室の前を通る。ふと顔を上げるとそこには見覚えのあるような後ろ姿を発見した。
―あれ、今渡り廊下を通って右曲がったあのクリーム色のふわふわした髪の毛が特徴的な子ってまさか…?
私は思わず走ってはいけいけない廊下を走っていた。あの子なら何か知っているはず、そんな根拠のない自信だけを持って追いかけた。
あの子のように渡り廊下を通って右に曲がると、私は途端に急ブレーキした。
「え…?」
そこは行き止まりであり、一面真っ白な壁であった。よく見てみると下の方に1mほどの小さな子どもが入れることが可能なくらい小さなエレベーターらしき乗り物のドアがあり、扉が開いてある状態であった。
「これは…?」
予測不可能な出来事に一瞬混乱する。この乗り物は上の階へと続いているのだろうか。でも私が知っている限り、この学校の最上階はこの階だったような…あの子はこれに乗ったのだろうか。
『何をしているの?』
全身が凍っていくのが分かった。怖いくらい綺麗で落ち着いているそこ声の持ち主が今、私の背後に立っている。もし振り向いたら、私はどうなってしまうのだろうか…そんなことも考えずに、とっさに振り向いていた。
再び会った小さき仮面の子ども。
―叶萌。
「どうしてあなたがこんなところに…?」
やはりミクミの仮面を被っている。そんな不気味なキャラクターのどこは好きなのだろうか。私には子どもの心情が理解できない。そんなどうでもいいことを思いながら、私は叶萌に問いかけた。しかし、違う答えが返ってくる。
『それはこっちの台詞だ、森永あむ』
仮面を被っているため、どんな表情をしているのか読むことが不可能だ。
驚いているのか、喜んでいるのか、悲しんでいるのか、怒っているのか。
きっと何も思っていないのだろう。そう感じさせるくらい落ち着いた声の叶萌は、私を見上げたまま微動だにしない。叶萌の腕には何故か六法全書よりも分厚い本が握られている。とは言っても六法全書がどれくらいの厚さなのかは知らないけど。
「じ、実は…」
私はすべて話した。叶萌なら力になってくれると思って。
『ふぅ~ん、なるほどね』
話し終わると、叶萌は理解したかのように頷いた。ミクミの不気味な笑みがこちらを向き、何かを探っているように思える。でも私は嘘なんかついていない、真実を語った。
『それで君はその爆弾を見つけようとここ周辺を歩き、探していたわけだ。よりによってこの階を。』
叶萌はわざとらしく語尾を強めた。体がそれに反応して、ピクッと動く。どんな表情をしているのかはわからないけど、叶萌はこちらを見上げている。ただひとつわかるとすれば、ミクミが不気味な笑みを浮かべていることだけだった。
『まあいい。今からその爆弾を探しに行く。ボクのものを破壊しようとするやつは絶対に許さない。』
ボクの物、という言葉に違和感に覚えたが、そこにはあえて触れなかった。すると叶萌は分厚い本を両手で投げ、左手を指鳴らしした。
その瞬間…ポンッ!!
投げた分厚い本は消え、なんと…
『ふぅ~お呼びっすか、仮面小僧っ!』
陽気な中学生くらいの金髪男否、金髪少年と、
『叶萌にそんな口の利き方をするな、無礼だぞ』
凛とした読書好きの眼鏡の男が現れた。
「えっ、な、なんで!?」
いきなりのことで状況が把握できない。これも魔法なの…?
思わず大声を出すと、私の存在に気づいた金髪少年と眼鏡の男はこちらを向いて目を見開いた。正確に言うとこちらを向いたのは2人で、目を見開いたのは金髪少年ただ一人なのだが。
『なんでこいつかこの階にいんだよ!?おい叶萌!!お前が勝手に許可したのか!?』
静かな廊下に絶叫が響き渡る。
どうしてこんなにも怒るのか、私にはそれが理解できなかった。確かにここは世界から注目されている素晴らしい生徒が集う階だ。でも私がここに来たのには理由がはっきりとあって、しかもその人々の邪魔をしているわけじゃない。むしろ応援していると言っても過言ではない。そんな私が何故怒られないといけないのか。
実際に自分が怒られているわけでもないのに、あむは天磨に対して無性に腹が立っていた。その時、その胸の中に何かの芽が出た感覚を、彼女はまだ気づいていない。
叶萌に怒鳴る天磨に、尽かさず侑がフォローを入れる。
『きっと何か理由があるのだろう。叶萌、訳を聞こう。』
侑は珍しく四六判の本を閉じ、叶萌のほうを向いた。
『実は…』
叶萌が言いかけた瞬間―…
ドォオオオォオオォオオオオオンッッ……
前方でものすごく巨大な爆発音が鳴った。全身の血流が止まったかのように血の気が引いて、額からがジワリと汗をかく。
…もしや!?
私は音のした方へ全力で走っていった。どうしよう…私のせいで皆が…そう考えるだけで胸が破壊されていくような気分だった。
―がしかし。そんな心配する気持ちもつかの間で、てっきりさっきの爆発音は例の爆弾のものだと思っていていたが、それは研究生たちが実験で失敗したための爆発音だった。
今彼らは、人間と全く同じ細胞を作り出す研究をしているらしい。ぶっちゃけ、『DaLE』を発見したのだからそれは意味のない研究だとは思ったが、無いよりはあったほうが確実にいいだろう。もしこの実験に成功すれば、世の中の障がい者やガン、植物人間など、どのような深刻な病を患わっている人でも100%に治すことが可能になるらしい。
そんな細胞を造り出すのは不可能に近いことだが、彼らなら可能にするだろう。
私は安心しきってホッと肩の力を抜き、叶萌たちのほうへ戻った。
「良かった…大丈夫だった」
そう言って笑った私のところへ天磨が歩み寄ってきた。私が意味不明なことを言ってしまったばかりに体が小さくなってしまった天磨。そんな背丈の少年に思いっきり睨まれてもちっとも怖くない。むしろ可愛いとすら思えた。
『叶萌からすべて聞いた。今この学校に爆弾が仕掛けられているそうだな。場所はどこか概ねわかっているのか?』
その声は思ったよりも落ち着いていて、少しびっくりした。慌てて返事をする。
「いやっ、聞いてないの。多分校舎内じゃないかと予想はしているんだけど…」
『校舎内な、わかった』
いつもと違って冷静な天磨を不思議に思いつつ瞬きをした瞬間、私は1人になった。
「…あれ?」
まるで見違えたかのように静まり返った廊下。
何の気配も感じさせないその空間は、この世に私以外の誰もないような感覚がして、不安が募っていく。
「叶萌…?天磨…?侑…?」
3人の名前を呼んでみるも、当然返事が返ってくるはずもない。
何かがおかしい。あむはそう直感した。
爆破まで残り、1時間20分。
× × ×
―『生の国』にて。
ここは空と宇宙の狭間に存在する選ばれし人間のみ入国を許される神の領域、生の国。そこに、ある一人の少年が呼び出された。
『…失礼いたします。神様、お呼びでしょうか?』
彼の額にはじわりと汗が浮かんでいる。自分が何をしでかしたのか、心当たりが全くなく何のために呼ばれたのか意図が理解できなくて、口から心臓が飛び出そうなくらいすごい勢いが今の彼にはあった。
真っ白な霧包まれている神の姿は遥か彼方に存在し、彼がいる位置からその神々しい姿を拝見することはできるはずもない。太陽の光が差し込むエデンの園には爬虫類や哺乳類をはじめとする、様々な動物がその身を癒しにやってきている。まさに楽園のような空間。
巨大な雲の上に身をのせているあのお方こそが神。この世で一番の正義で真実。究極の存在。
『…これを彼女に渡してくれ』
ハーブのような美しい声が彼の耳に入り込んでくる。神の声を聴いたのはこれが初めてだった―…
× × ×
あれから30分経ったが、爆弾は見つからない。大体こんな巨大な校舎のある一室を特定し、爆弾を発見するなど、普通に考えれば無謀なことである。
どこ…どこにあるの…?
あむは焦りを感じていた。一人になってしまった今では、誰かと協力して―だなんてことは到底できたものではない。
…叶萌たちはどこへ行ったの?
突然いなくなってしまった3人の行方など知るはずもなく、あむはただひたすら左右を見ながら、時々教室の中を確認しながら走っていた。
気づけば自分の教室のある階に行きつき、そこで違和感を覚えた。ざわつく気持ちを抑えながら教室の前を通ると…絶句した。
「どうして誰もいないの…?」
『オレが消した』
ハッとして声がした方を振り返る。そこには消えたはずの天磨と侑の姿があった。よく見てみると叶萌は侑の腕の中で眠っているのか、お姫様抱っこされていた。やはり仮面がつけられているので、目を閉じているのかは確認できないが。
―消したって、どういうこと…?どうしてそんなことする必要があるの?なんて聞く前にそれを察したかのようにして天磨は静かに、割と落ち着いた声で答えた。
『別にこの世から消したわけわけじゃねーよ。ただ爆弾探しの邪魔になるだろうと思って一時的に消した、ただそれだけのことだ。勿論、爆弾が見つかれば元の状態に戻るぜ。見つかれば、な。』
大切なことなので二度言いました、と言わんばかりに天磨は最後のところを強調して風に二度繰り返し言った。平然としているその姿に苛立ちを感じ、彼の言っていることに納得はできなかったけど、ここでもめている場合ではないと気持ちを切り替えた。それに早く爆弾を見つけ出して、安心したかった。
―残り、45分。
× × ×
『何か少しでもヒントとかもらわなかったのか?』
あれから10分。体育館やプール館を探し回ったが結局なんの手がかりも得られないままで、さすがの天磨たちも焦りを見せ始めていた。
もし、時間内に爆弾を見つけ出すことが出来なければ―…
想像するだけで口から心臓が出てきそうだ。
どうしよう…
どうしよう…
天磨の問いに、私は少し怯えたような声で答えた。
「何も…。健闘を祈るって言われてすぐに切られちゃったから…」
何の役にも立てないやつだと思われるのが怖くて、必然的に俯いていた。すると、2人はその言葉に反応を見せ、お互いに見つめ合い、ため息を吐いた。私は不思議に思って顔を上げると、2人はまるで呼吸を合わせたかのように同じタイミングでこの状況をつくりだした犯人の名を口にした。
『『天無たちの仕業だな』』
2人のその言葉に、侑の腕の中で気持ちよさそうに指をくわえて眠っていた(と思われる)叶萌が飛び起きた。
『梨莉湖!?梨莉湖が来ているのか!?』
慌てたように私に抱きついてきた叶萌の体は小刻みに震えており、私は無意識にギュッと優しく抱きしめていた。その時、左手の中指がチクリと痛みを感じた気がした。
リリコ…?誰、それ。
過去の記憶を辿ってもそのような名前の人間と接していた思いではなく、この状況についていけていない私はため息をついている天磨と侑や、何かに怯えている叶萌にどう接していいのか分からない。
―その時だった。
『よぉ』
そのどこか聞き覚えがあるような声に反応して振り返ると、そこには180㎝くらいの長身の男が立っていた。この人まさか…まさかなんて可能性を否定する気持ちなんて強制的に確実にこの人は今日会ったことのある人物だった。
私のことを見下げる鋭い瞳が視線逃せようとはしない。
ものすごい威圧感をそこから感じた。教室で睨まれていた時よりもはるかに殺気が満ち溢れているようである。殺されるのではないかと、正直不安になった。でも、不安にすらなる余裕もなかった。
赤い紅蓮の瞳が、私のことを直視して一言。
『お前が森永あむ。いや、“神の子”アイムか。』
人間は時々嘘を吐く。
周りに合わせて思ってもいないことを言ってみたり、不味いのに美味しいと言ってみたり、下手なのに上手だと言ってみたり、不細工なのに可愛いと言ってみたり、嘘なのに本当だと言ってみたり。この世の中は嘘であふれていて、人間は永遠にその束縛から逃れることはできない。
嘘つきは泥棒の始まりだというが、これもまた嘘。
もしそれが真実だというならば、世界中の人間が刑務所送りとなるだろう。事実、逮捕する警察官もまた少なからず嘘は吐くのでこの人たちも。
―だから私は少し戸惑った。ものすごく真剣な顔で嘘を吐いたこの赤メッシュに。どうしてこんなにも堂々と嘘を吐けるのか、それが不思議で仕方なかった。
「神の子…アイム?」
その男が言ったところで耳に強く残った言葉をリピートする。勿論、思い当たらない言葉である。
どうして皆同じように私の知らない言葉を並べるのか、私には到底理解できるようなことではなかった。
『なんでてめぇがいんだよ…』
天磨がこちらを睨みつけている。きっとこの赤メッシュのことを睨んでいるのだろう。私は前後、どちらに目を向ければいいのか迷った。この2人は知り合いなのだろうか。天磨の口調からしてそうとしか思えない。
そんな天磨を赤メッシュは目をぱちくりさせ不思議そうに見ていたが、すべてのことの理解が出来たのか、腹を抱えて爆笑し始めた。
『アハハッハッハ!!天磨、なんだそのしょうもねー身体はっ!まさかこの女に変貌の魔法でも掛けられたのか!?その面よく似合っているぜ!アーッハッハッハ!』
天磨の姿を見て、笑いが止まらない様子の赤メッシュ。恐る恐る天磨のほうを見てみると、怒り寸前といったような感じでプルプル震えていた。とりあえず変な口出しはしないでおこうと思った。ツボに入ったのか赤メッシュがその豪快な笑いを止めようとはしない。廊下に響いて耳に障ると思っていると、
『杏莉、うるさいよ。梨莉湖が起きちゃうじゃないか』
教室の中から声が聞こえてきた。慌てて中に入ってみると、窓側後列の席に知らない男の子が座っていた。そしてその腕の中には小さな女の子が指をくわえて眠っている。
リリコ…もしかしてあの子が叶萌の怯えている原因なの?私のことを強く抱きしめている叶萌の身体はブルブルと震えている。見た感じだけだと大人しくて可愛らしそうな女の子だけど…叶萌が怖がっている?
梨莉湖って何者…?そんなことより私はもっとも大事なことを忘れていた。
―残り、15分。
少女はふいに目をパチッと開き、辺りを見回した。そして私が今抱きしめているものに目を輝かせたかのように強い視線を送った。それを察知したのか、叶萌の震えが止まる。少女は勢いよくその男の子の腕から飛び出ると、こちらへ全力で疾走してきた。なんて危ない子なんだと思った瞬間、私の腕の中から叶萌が消えた。
…あれ?
目の前で起こった光景が速過ぎて何が起こったのか意味が分からなかった。
今のは…?
なんてさっきのことについて考える暇もない。遠くにいたはずの男の子が、何故か私の目と鼻の先にいるのだから。
『ふーん、悪くねーじゃん』
私の顔を覗き込むようにして見てくる男の子。その距離たった数㎝。
赤面した、こんな近くに人間の顔があったことなど今まで一度もなかったから。緊張なのか驚きなのか、どちらは定かではないが、胸の鼓動が高鳴る。
彼が機嫌良さそうに私を見ている中、杏莉が口を出す。
『おい、涼多。俺たちの目的はそいつの観賞じゃあないんだぞ。』
すると涼多はさきほどの表情を一変させ、舌打ちをして私からゆっくりと離れた。その衝動なのか、自然と一歩後ろに下がった。
この人たちの目的…?
そんなことを考えている矢先、私はもっと重要なことをようやく今思い出した。
…爆弾!!
とっさに教室の時計に目をやると…時刻は11時50分。
―残り、10分。
最悪なシチュエーションが脳裏に浮かぶ。
どうすればいいのかもうわからない。背筋が凍った、というか全身が凍った。
爆弾がある場所も発見できず、気づいたら爆発―なんてこともあり得るのである。
そんなの…残酷すぎる。
私の疑い目は杏莉たちに向けられる。そしてその勘は当たっていた。
『俺らが爆弾を仕掛けた。』
杏莉がボソッと吐いた言葉がまるで大音量で音楽を聴いている時みたいに鼓膜に響き、それと同時に憎悪感が私の中に生まれる。
どこに爆弾を仕掛けたの?どうして?なんのために?
頭の中に無数の疑問が浮かび、気持ち悪い。
「なんでそんなことっ…!!」
そうヒステリックに叫んでみるが、杏莉の耳には入らなかったらしくゆっくりと歩き始めた。
『すぐ見つかるだろうと思っていたんだけどな~』
教室の中央前列の席で足を止め、呆れとため息の混じった声で言葉を吐く。その余裕そうな態度に私の中の憎悪感は深まっていくばかりである。
『この中だ』
杏莉が指差した机、それは紛れもなく…
「え、私の机?」
紛れもなく私の机だった。
あれっ、一応確認してなかったっけ?と今更のように小一時間前の記憶を呼び覚ますが、“そのような記憶はございません”と脳が瞬時に信号を出す。
まさか私の机の中に爆弾が仕掛けられているだなんて想像もしなかったものだから、驚きでものも言えず、同時に憎悪感は一切消え、反省した。
ふと天磨のほうを向くと、呆れているのか、いつも異常に眉間にしわを寄せて私のことを睨みつけている。すぐに目をそらし、慌てて自分の机の方へ小走りで向かい、中をのぞいてみる。
…なんか入ってる?
何も入っていないはずの机の中には、黒い箱のような、物体が入っていた。
「これは…」
震えた手でその物体を取出し、机の上に置く。その物体はやはり爆弾箱のようで、タイマーが乱雑に黒いガムテープで巻きつけられ、時間のみ表示されている。―残り、7分30秒。
どうしよう…どうやって止めればいいの?よく殺人ドラマとかで出てくる爆弾には赤と青のコードがあるが、これにはそれがないのでどう停止させればいいのか思いつかない。
呆然と減っていく制限時間を見つめていると、天磨たちが不思議に思ったのか、こちらへ来た。
『7分!?嘘だろ…!?』
どうして人間は現実を受け止められない時、「「嘘でしょ」」や「「信じられない」」と言った言葉で現実逃避を試みようとするのだろうか。何を発したとしても現実は現実だというのに。否定的になどならずに、すべてを受け入れてしまえばいいのに。
とか、一番の現実逃避人間が言ってみる。
ようはさっき天磨が言うべき言葉は「「嘘だろ」」ではなく、「「へーそうなんだ」」のほうが正しいのだと、私はそう言いたいのである。
でも、こんな状況でそんなことをのんきに言えるわけがない。言えるはずがない。仮に言ったとしたら、その人は将来変質者と化すだろう。
―なんて、こんな状況でのんきなことをふと考えながら、私は表示されている制限時間を眺めていた。今の私はおかしい。なんでこんなに冷静でいられるのか、不思議で仕方ない。
『早く爆弾を止めねーとっ!』
最初に作業に取り掛かったのは天磨だった。箱に顔を近づかせ―そして呟く。
『レジュール・ティラロ』
そう呪文と唱え、箱にゆっくりと息を吹きかけた。―その瞬間、黒かった箱が…消えた。いや、消えたわけではないのかもしれない。なぜなら、そこにはタイマーと、コードの集合体のような物体が残っていたからである。まるで、箱だけが消えたような…そんな感覚だった。
「どうなったの…?」
『レジュール・ティラロ、透明魔法だ。今はそれを説明している時間はねーけどな』
天磨はそう言って目を凝らしながら爆弾の周りをじっくり眺めていた。その行動に不思議と違和感を覚える。…何をしているのだろう?
それにレジュール・ティラロという魔法、どこかで聞いた覚えは…ない。
『―おい、杏莉。』
何かに気づいたのか、爆弾を見たまま杏莉を呼ぶ。そのドスの利いた声は、怒りを抑えているような低さで、近くにいた私は呼ばれてもいないのに心臓が一瞬止まるかと思った。
『何の魔法を使った?』
声が教室に響き渡る。一瞬で、この空間が殺気に包まれた。天磨の問いに、杏莉がキョトンとした表情でこちらを見ながら答える。
『ん、囚われの魔法だけど…それがどうかしたか?』
『それ…禁止魔法じゃねぇかっ!!』
天磨が大声で怒鳴る。その表情には殺気が満ち溢れていて、私は息をのんだ。辺りがシンと静まり、重たい空気の中、杏莉が再び口を開いて言い訳をした。
『か、神が“アイムがいるから問題ない”っつって、俺もまだ取得したばかりで嬉しくって…だから囚われの魔法を…使った。』
『一度唱えたらどんな手を使っても解けねー魔法だぞ!?お前も正気じゃねーが神は何を考えてんだ…?もし時間内に止められなかったらここは…』
天磨の言葉に、最悪のシナリオを頭の中で描いて、鳥肌が立ち、下腹部のほうが重くなる。こんな危機的状況におかされたことなど一度もないのでどうすればいいのか分からない。…一度も?
そうえば、叶萌と梨莉湖ちゃんはどこへ行ってしまったのだろうか。もしここに叶萌がいたとしたら…あの子は何を発し、どう行動するのだろう。
2人のことを心配しながら、どんよりとした重い空気の中、私は重たい口を開いた。
「でもっ…爆弾を止めないと…止めなきゃいけないんだよ…」
堪えきれない何かを堪えながら精一杯声を出した。天磨と目が合う。私は今どんな顔をしているのだろうか、天磨とても苦しそうな笑顔を向けた。
「ったりめーだ…!」
人間は危機に瀕したとき、自身の持っている本当の力を発揮するのだという。
例を挙げるとすれば、とある男がいるとしよう。貧弱で、歩いているだけで転びそうなひ弱な男である。しかし、そんな男も、心から大切にしている友達ががれきに埋まってしまったとき、死ぬ気で助けようと全力で振り絞ぼれば、そのがれきを持ち上げ、助け出すことが可能…らしい。
なんでこんな話をするかというと…
―目の前にいる彼もそれ同様だったからである。
「でも…どうすれば…」
制限時間は残り、3分。3分後には…ううん、余計なことは考えないでおこう。今は、今は爆弾を阻止することだけを考えよう。そう決心した矢先、
『やはりお前を頼るしかない。』
天磨は私を見てそう言った。
「…は?」
唐突で何がなんなのか理解が出来ない。耳を疑った。
今この人…何て言った?私を…頼る?こんな見たこともないような爆弾装置の阻止を私に…頼んだの?
さきほどの決心は一瞬で消え去り、私の頭に答えがパッと浮かんだ。
「私が…?いや、無理!無理無理無理!絶対無理!私になんかできるわけないよっ!!」
断固拒絶する私に天磨それでも落ち着いて口を開く。
『大丈夫だ、お前ならできる。お前が―“神の子”アイム、ならば』
さっきから皆が口にする“アイム”という単語。
どんな意味があるの?
どこの国の言語?
世界史をろくに勉強していない私には知る由もない。あるはずがない。
ただ一つ確信できることとすればそれは…私がその“アイム”ではないという事実だけだった。
「神の子…?アイムって何なの…?」
私が問うた瞬間、爆弾が目覚まし時計のような不快音を奏でだした。
「何これ!?一体何が起きているの!?もう分からないよっ!!」
両耳を塞いでそう叫び、その場で崩れ落ちた。制限時間はあと1分半に迫っていた。
多分その不快音は爆発する準備を始めるための合図なのかもしれない。
恐怖で縮みこむ私に、天磨がそっと駆け寄ってきて、背中を撫でた。
『大丈夫だ。自分を信じろ、森永あむ。』
天磨の優しくも力強い、何かを思い出させるような声に、私の胸が熱く痛んだ。―自分のことを今まで一度も信じたことのない人間に、そんなことを言っても意味がないというのに。
「私に…できるわけないっ…」
私の消極的な声が、教室に響いた。
『少しは…力になろうとは思わないのか。』
天魔の低い声と、背中に添えている手の重みが、胸に、全身に、重圧かかった。重力にさからっているような、そんな感覚。口にあふれ出てくる胃液を飲み込む。
「って…だって…だって…っ」
声が震えているのが喉を通じて全身に伝わる。怖かった、人に反論するのが。でも。嘘はつきたくなかった、この人だけには。
「だって!!訳が分からないよ!いきなり私の目の前に現れて“私を守る”だの“使者”だの“魔法”だの!!挙句には“爆弾の阻止”を任せられて!!私は普通の人間なの!!17年間ずっと普通に生きてきた!それなのにいきなり何よ!こんなのできるわけないじゃないっ!!」
私の気持ちが言葉となって口から排出された。ずっと心の中に堪っていたものが出て行ったような、すっきりしたような気分である。全部無くなったわけではないけど。
『はぁ…』
背中から手が離れ、軽くなったのと同時にそこだけ妙に冷たく感じた。今天磨…ため息ついた?
彼は立ち上がると、顔を上げた私を蔑むような目で見た。その瞳に感情はない。
『そうかよ。じゃあお前に頼らねー…いざというときにやってくれると思っていたがここまで臆病だったとはな。失望した。…使えねー女だ。』
その言葉が胸にとげが刺さったみたいに深く貫く。使えない女…その言葉が引っ掛かった。
不快音だけが鳴り響く教室で、―しばらく2人の間に沈黙が生まれる。
何も言えなかった。本当に、口が開かなかった。
『とりあえず、時間がねー。やれるだけのことはやる。』
天磨がそう努力の意を決す。とその直後、挑発なのだろうか、突然涼多が口を出した。
『無理だって~。だって囚われの魔法だよ?解けるわけがないじゃないか。1分後にはこの学校も…ボンッだよ。ふははっ』
いつの間にか涼多が教卓の上に偉そうに座っていた。何故そんなにも気楽でいられるのか、あむにはそれが理解できない。脱出不可能のこの空間で、自分たちも巻き添えをくらうのに。何故そんなにも落ち着いているのか、理解できなかった。
そして杏莉も何かを誤魔化すかのようにハハハと笑った。
『悪いな。俺がこんなことをしてしまったばかりにお前らを地の果てに送ることになっちまって。』
『ぶっ殺すぞ』
天磨が杏莉をギロッと睨みつける。
―とその瞬間、不快音の速度が急速に上がり、咄嗟にタイマーを見て、私は気づいてしまった。
「やばいよっ!もう10秒しかないっ!!」
「んだと!?」
制限時間―残り7秒。
と表示されたそのタイマーは私の血の気を引かせていく。
もう死を受け入れるしかないのだろうか。
そうすれば楽になれるのだろうか。
今を生きればそれでいい私にとって、死など、怖くない。
…
―今日で、この世界ともお別れになる。楽しいようで、今思い返せば何もなかったつまらない毎日にも別れを告げる。それは悲しいようで、嬉しいようで、もうよくわからない。
きっと嬉しいことだろう。
きっと…そう、だろう。
「…だ」
だけどやっぱり…
「いやだぁあああああああああああああああああああああああああ!!!!」
―その瞬間、神の子の叫びにより、全人類の動作が…止まった。
何の前触れもなく、時間が、停止した。
しかし、そんなことが起こったということなどこの中で知る者はいない。…いや、一人を除いて。
天磨は目を見開き、瞬きもしないまま爆弾の方に目を向けた。
『と、止まっ…てる…』
何が止まったというのか。あむにはそれが理解できない。天磨の視線の先の物を見ると、目を疑った。タイマーは4秒で確かに止まっていた。
助かったという安堵よりはなんで?という疑問の方が大きい。
何が起こったの…?
ここは…どこなの?
変な疑問が浮かぶ。それもそのはず、さきほどの空間とは明らかに変わっているのだ。別次元にいるような、不安になるような、そんな何もない、そんな無の空間だった。
「どうして…」
目の前には天磨がいる…天磨しかいない。タイマーも確かにここにある。ならば他の皆はどこへ…?
辺りを見回しても何も見えない。ただ不思議な空間が続いているだけである。
『こ、これは…』
その言った後、天磨が何かを呟いた。
―すると。
グサッ…
「っ…」
胸に何かが刺さった。刀のような、刃物のような、そんな冷たい何かが。
私の熱い胸を、深く、貫いた。
「だっ…れっ…?」
背後に何かの気配を感じる。私の後ろに誰かがいたのだろうか。
振り向くとそこには―…
『…っむ!』
―貴方は一体誰なの…?
『…チッ』
―視界がぼやけてよく見えない…。
『…もう駄目だっ!時間がねぇっ!!』
えっ?その言葉に私はハッと目を見開いた。
『伏せろっ!!』
「へっ…?」
ぼーっとしている私に天磨は慌てて抱きつく。
『このノロマめっ!!』
天磨が叫んだ瞬間、地鳴りが始まった。
「なにっこれっ…!!」
『爆弾が爆発するぞっ!!』
―そして、天魔の腕の中で、私はそのまま気絶した。
『…で』
―ここはどこ?
『…おいで』
―貴方は誰なの?
『あむ、こっちへおいで』
私のことを優しく包み込んでくれる貴方は一体誰なの?
『僕が君を守ってあげる』
私のことを包んでくれるその光は暖かくて、でもどこか冷たかった。
―私のことを守って…
1人にしないで…
1人ぼっちはいやだよ…
『…い』
「ずっと私を守って…1人にしないで…」
少女は一粒の涙を流した。その涙はどんなものよりも美しく、輝かしかった。
―そして少年は決意する、
“絶対に君を1人にしない。僕が一生守ってみせる”
と。
少女は笑顔を見せた。その笑顔はどんなものよりも美しく、愛らしかった。
―少年は少女を強く抱きしめた。
バチンッ
痛っ…今右の頬が何か強い衝撃を受けた。
今のは何?何が当たったの…?眠たいのに起こさないでよ…良い夢を見ていたのに…起きたら絶対怒ってやる…
バカ…
『っ…』
私の目の前にいるのは誰?視界がぼやけてよく見えない。再び頬に何かが当たる。
…これは?
『…むっ!あむっ!起きろよ!おい!!』
私を呼ぶのは誰…?
――お母さん?
「お母さんっ!!」
私はその人に思いきり抱きついた。
「お母さん…お母さん…お母さん…」
その温もりをもっと味わいたくて、強く、強く、必死に抱き締めた。
『もう大丈夫…ずっとそばにいるから…』
抱き締め返してくれたその温もりは全身に伝わり、私を安心させた。
―大好きだよ。
私はゆっくりと目を閉じて眠りについた。
もっと素敵な夢が見られそう…。
× × ×
目を開くとそこには…知らない天井が存在した。
ここは…どこなんだろう?
ふかふかしたベッドとシーツが気持ちよくて、再び目を閉じようとしたところでふと思い出した。
…爆弾っ!!
ハッとして勢いよく身体を起こした瞬間―…
「っ…ぃたっ…」
全身に激痛が走った。今まで体験したことないくらいの激しい痛みに涙ぐんでしまう。
辺りを見回してみるが、真っ白な壁と、その壁とほぼ同化している扉以外は何もなかった。多分、保健室だろう。それにしても、無駄に広い空間である。
…皆は?無事なの?
「っ…」
考えたくても脳がそれを許可せず、頭痛がして、思い出そうとすると胸がむかむかして気持ちが悪い。
―すると、突然扉が開いた。
そこにいたのは…
『あむ…っ!』
そう叫んで、その子は走って私に飛びついてきた。それでもその子の表情は分かるはずもない。多分喜んでくれている…のだと思う。
その子に続いて、次々と人が入ってくる。最初に杏莉、次に涼多(の腕には眠っている梨莉湖)、侑、そして…天磨。
私はそこでふと視線をそらした。
『大丈夫か…?悪かったな、あんなことして。』
杏莉が申し訳ないといった声で声を掛けてくる。反省しているのだろうか?そう思っていると、次に涼多が口を開いた。
『本当にごめんね~?あれ爆発するタイプの爆弾じゃなくて、パーティとかで使う用の爆弾だったんだよね!お遊びのつもりで仕掛けたけど、あむちゃんに痛い思いさせちゃったよね?』
フハハと元気のない笑い声で涼多がそう説明した。…ということは、あの爆弾は何でもないただのおもちゃだったってこと…?そう思うと、あんなに必死になっていた自分が恥ずかしい。今思い返せば、だから杏莉たちは笑って気楽そうにいたんだ。…そうすると、同様に冷静だった侑もそれを知っていたということ…?
もう何が何だかわからなくなってしまったが、何はともあれ、皆無事で良かったと、あむはつくづく思った。
「大丈夫だよっ!」
謝る2人に、私は飛びっきりの作り笑いをした。するとそれが気に食わなかったのか、天磨が舌打ちをした。
『お前、…もうちょっと痩せろよな。この身体で眠っているお前を抱えるのがどれだけきついか少しは考えておけ。』
怒り気味にそう命令してきた天磨の言葉に、身体がどんどん熱くなっていくのが分かる。それに関しては明白な理由があった。
「て、天磨が…ここまで運んでくれたの?」
多少疑いつつもそう聞くと、天磨は腕を組みながら『おう』と返答した。その返答に私の心臓はチクリと痛み、鼓動が速くなっていくのが分かる。とても嫌な感覚。
「…私、帰る」
そう言って、私に抱きついてその子を外し、これもまた真っ白な純白ベッドから出た。その時激しいめまいが襲ってきたが、我慢して扉の方へと足を進めた。天磨が尽かさず止めに入る。
『…っおい!その身体じゃ無理だっ!ゆっくり休め!』
そう言葉を掛けてくれた天磨にイラッとして、私は気に留めずにその空間から出た。
扉が閉まり、ふと視線を上げるとそこには―…
『―…っ』
「っは!!っはぁ…はぁ…っ…」
今のはまさか…知っているはずなのに思い出せない。私に何か言いかけた言葉は一体…?
気が付くと、そこは私の部屋だった。安心したのと同時に、全部夢だったんだと、自分に言い聞かせて、必死にないことにしようとした。再びベッドに横になる。そのあとはモヤモヤして、よく眠れなかった。
× × ×
いつもは家を9時頃に出るのだが、この日は何故か早起きして7時に出た。私の今までの登校時間として、こんなに早く家を出たのは初めての出来事で、自分でも少し不思議に思う。
学校に着くと、教室がいつもより騒がしい感じがして、少し違和感を覚える。ふと、窓側の一番端の席に目を向けた。そこには…勿論だが杏莉の姿はなく、音楽を聴きながら腕に顔を埋めている真っ黒の髪をした男の子が座っているだけであった。それではあの時見たのは…そうか。
そう確信を思って、私は近くのクラスメイトに軽く挨拶をして、自分の席に着いた。
このあと、その確信がもろく消え去ることも知らずに…。
しばらくすると、担任の早志田(はやしだ)が教室に入ってきた。赤色の眼鏡とリーゼントがアンマッチで毎回不快に思う。早志田は私の姿に気づいたのか、笑顔で話しかけてきた。
『おっ、珍しいな。森永がこんな早く登校するなんて。』
嬉しそうな表情を見せる早志田に苦笑いする私。この先生…本当に慣れない。
頬杖をついてそっぽを向いていると、突然教室の外で声がした。
『―おい。早くしろよ。』
…ん?今の高低さのない中性的で、少し癖のある声って…
『おっ、すまんな~。もう少し待ってくれ』
早志田は笑いながら廊下にいる誰かに向かって謝った。
―もしかして、転校生…?
そして私の予感は見事に的中した。…しなくてよかったのに。
『―今日はⅦ組新たな仲間が入ってくる。仲良くしてやれよー。では、入ってきてくれ。』
早志田の合図で半開きだった教室のドアが全開になり、転校生が入ってくる。
1、2、3、4、…5人。
それらの顔を見た瞬間、私は絶句した。
そしてそれと同時に、私のいつも通りは、終わりを、告げた。
AMU


