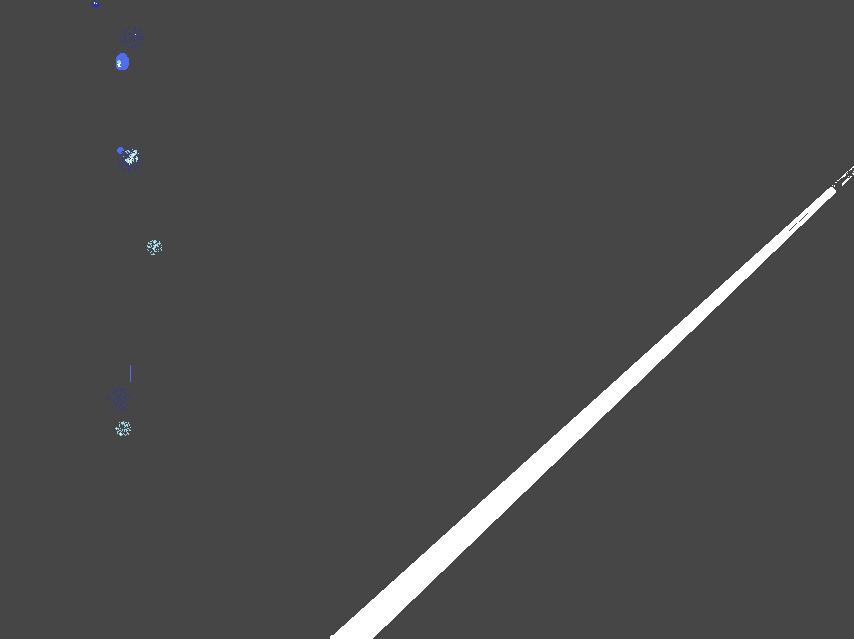
彼
『彼』1
『彼』のことを、日紅は「巫哉」と呼んだ。犀は「月夜」と呼んだ。たまに日紅のところに来る自称「彼の友人」は「太郎」と呼んだ。また別の自称「彼の友人2」は「多良」と呼んだ。また更に別の自称「彼の友人3」は……。
つまり、『彼』には沢山の名があった。
「はァ?あれはあいつらが勝手にそう呼んでるだけだ。俺にはちゃんと俺の名がある。大体あいつらは俺の友人なんかじゃねぇ」
一見すれば十三、四に見える幼さを残した容貌でも、『彼』はその実四千年以上の長きを生きる、ヒトとは一線を画した身だ。
どことなく獣の印象をあたえる釣りあがった目尻。その瞳は燃え上がるような紅。髪の色が光を弾く銀だから、瞳の色が余計に目立つ。肩までのぼさぼさの髪に大きな瞳、ルネッサンスの絵画にでも描かれていそうなほど端正な顔立ちなのに、口を開けば一転して罵詈雑言の数々がぽんぽんと飛び出してくる。
『彼』が着ているのは、どこかで安売りされていそうな、なんだかよくわからない英語が書いてあるTシャツだ。外見に不釣り合いなそれは、小さい頃に日紅が『彼』にプレゼントしたものだ。ちなみに小さい頃の日紅には『買う』という思いつきがなく単に父親のタンスから目についたものを引っ張り出し(日紅は「ちゃんと似合うものを選んだの!」と主張しているが)渡しただけである。
文句を言いつつもなぜ『彼』がそれをずっと着ているのか甚だ疑問ではあるが、日紅は「巫哉の趣味って変わってるなぁ」ですませている。
「じゃぁ、巫哉。あなたの本当の名前は何て言うの?」
「知るか。てめぇで考えろ」
でもその言葉遣いの悪さも、慣れてしまえばなんてことはない。
日紅は窓枠に肘をかけたまま、ふふと笑った。
日紅は別に今更『彼』の本名など気にならない。日紅にとっての「巫哉」は「巫哉」であり、目の前にいる『彼』に違いはないのだ。「巫哉」も「月夜」も「太郎」も「多良」も同じ『彼』。『彼』が『彼』としてここにいるのなら、日紅はそれで満足なのだ。
「…何笑ってんだ」
「ううん。巫哉はかわいいなぁと思って」
「………」
睨まれるのなんて、もう慣れたものだ。
「ねぇ巫哉、部屋の中に来なよ。もうすぐ冬だよ。外は寒いでしょ」
もう肌寒い季節だ。流石に日紅も、夜にずっと窓を開けっ放しにして『彼』と話をするほど元気じゃない。途端さらりと肉付きの薄い肌の上を夜風が撫ぜて、日紅はぶるりと身震いした。
けれど『彼』はっと鼻で嗤って言った。
「寒い訳あるか。貧弱なヒトでもあるまいし」
「巫哉はそうかもしれないけど、あたしは貧弱なヒトなの!このまま窓開けて話してたんじゃ風邪引くかもー…あ、やっぱり巫哉そこにいて!今日は犀が来るって言ってたから、って、どうして素直に入ってくるのよ!犀が来るんだってば!あたしじゃ巫哉みたいに空を飛べないし、こっそり犀を連れてこれないんだから!あ、こらっ、巫哉!だからっ、窓を閉めないの!」
ご丁寧に内側から鍵まで閉められた窓を見て、日紅は溜息をついた。
二階にある日紅の部屋は樹齢五百年だとか言う大木の太い枝が大接近している。ギリギリとアウト、どちらだと言われたら限りなくアウトに近いだろう。それはお隣さんの木なのだが、樹齢五百年だけあってかなり大きい。思わず肯けるほどの幹の太さもさながら、何より、高い。車庫付き二階建ておまけに屋根裏まである日紅の家が目じゃないくらい高い。おかげさまで日紅の家の日照条件は残念なことになってはいるが、立ち並ぶ家々の合間に一本、にょっきりと頭を覗かせている樹木はそれは人の目を引くだろう。渾名は勿論‘のっぽさま’だ。その五百年生きたのっぽさまも『彼』に言わせれば「まだまだヒヨっ子」なのだそうだ。しかし日紅に言わせれば『彼』のほうがよっぽど精神的にはお子ちゃまだ。
その大木の、日紅の部屋に一番近い、太い枝。そこに、いつも『彼』はいた。
だから、日紅は学校から帰ってくると真っ先に自らの部屋の窓を大きく開け放つ。するとむすりとした顔の『彼』がそこいるのだ。それはもう日紅の日課。何の疑問を持つこともなく、物心つくときはもう一緒にいた『彼』は既に日紅にとって家族とも言える存在になっていた。
「もう!巫哉!」
日紅は窓に片手をついて軽く『彼』を睨んだ。
「どうしてそういうことするの?こんな夜じゃあたしが下に行って犀を迎えになんていけないでしょ?ほら!犀がもう来てたらどうするの?ちょっとひとっとび行ってきてよ」
「…なんであいつが来るんだよ」
「別に今日に限ったことでもないでしょ。今更文句いわなーい。ほら、行って!」
日紅はぽいと『彼』を窓から押し出した。『彼』と入れ替わりにひやりとする風が入ってきて黄色のカーテンと日紅の髪をふわりと撫ぜた。
「…ケッ」
犀を連れて来いと追い出された窓の外、『彼』はぷいと日紅から顔を背ける。
「俺はあいつなんか連れてこねぇからな」
「どうして」
「嫌いだからだ!」
「ホントは好きなくせに」
「はぁ?好きじゃねぇよあんなきもいヤツ!」
「はいはい。じゃあちゃんと犀連れてきてね。じゃないと絶交だから」
『彼』の鼻先で、日紅は無情にも窓を閉じた。
「…ケッ…」
ご丁寧にシャッとカーテンまで閉める日紅に『彼』は心なしか寂しそうに口を尖らせて呟く。
「おーーーーい、月夜ぉーっ」
がさがさと風に騒ぐ葉音に乗って足元の方から聞こえてくる声に、『彼』の片眉がびんとあがる。
『彼』にとって、一番聞きたくないやつの声だ。
そのまま無視をしようかとも思ったが、その途端にぽんと日紅の顔が頭に浮かんだ。
あいつは怒ると手がつけられないからな…。
『彼』はしぶしぶ振り返った。
樹齢五百年の例の木の根元にそれは、いた。
グレーのロングコートを着込んで、少し着膨れした手を『彼』に向かって振っている。ツンツン頭の、それ。
「ここだよ。早く来いよ」
「…………」
『彼』はふわりと犀に向かって飛んだ。
勢い余ったふりをして繰り出した回し蹴りは難なくかわされ、「最近格闘技にはまっている」犀から逆に人間とは思えない速さでアッパーを食らった。
その攻撃に、『彼』は今度こそ‘勢い余って’どさりと地に沈んだ。無言で悶絶する。
「なにしてんだよ月夜。早く連れてけよ」
「…」
『彼』は無言でがっと犀の襟首を掴みあげると再び飛翔した。
「!?」
ふわりと犀の体が持ち上がる。
「うっそぉ!?」
当然のことながら、犀の首がぎゅっと絞まった。びりり、といや~~~な音もした。
「ちょ、待て月夜!俺、体重50あるんだけど!?」
犀が必死で『彼』を見上げても『彼』は知らんぷりだ。その目は据わっている。ま、まずい、と犀は思った。
ビリリッ、ブツッと音が追い討ちをかける。このままじゃ、日紅の部屋につく前に御陀仏だ。
たらりと嫌な汗が犀の背を伝う。
「ちょっと!」
バン!と、いきなり日紅の部屋の窓が開く。
「あんまりうるさいと皆起きちゃうでしょ!?なんでそう静かにできな、…って、キャァアアアアアーーーーーーッ!犀ッ!」
下を見た日紅は絶叫した。
「日紅!?」
日紅の部屋のドアが激しくダンダンダンと叩かれる。
日紅はさっと青くなった。
「どうしたの、日紅!何かあったの!?」
「な、なんでもないのお姉ちゃん!」
日紅はやっと部屋まで運ばれてきた犀を見た。
『彼』は運んできたものの、犀を部屋に入れようとはしない。
その間にも、ビッ、ビリリとーーー…。
ああ願わくば買ったばかりと犀が自慢していたコートの強度が防弾チョッキも真っ青のものであるか、のっぽさまの枝がクッションのように落下した犀の体を受け止めてー…って我ながらありえないー!日紅の思考は一瞬現実を逃避した。
「あ、あああたしぃっ!あって欲しくない現実、じゃない夢、夢を今見てっ!大声上げちゃったのぉ!なんでもないから、大丈夫!」
「…そうなの?本当に大丈夫?そっち、行こうか?」
「いやいやいやいやいや!本当大丈夫だから!お姉ちゃんはもう寝て、すぐ寝て、早く寝て!」
日紅は訝しむ姉の部屋のドアが閉まる音を聞くと、はっと我に返りすぐさま犀に手を差し伸べた。けれど、その手が犀に触れる一瞬前に『彼』はいきなり、犀の襟首を掴んでいた手をぱっと離した。
「おわーーーッ!?」
「犀!」
犀は咄嗟にぐわしっと『彼』の足に掴まる。
「巫哉!」
「何すんだよ月夜!殺す気か!?」
「死ね」
「ちょっと巫哉冗談でもそういうこと言わないの!ほら犀、掴まって」
かくして、やっと収拾のついた部屋の中で、日紅はぱたんと窓を閉めると息をついた。
日に日に、『彼』の犀に対する扱いが酷くなってきているのは気のせいではないだろう。
「…ごめんね、犀。その服、弁償するわ」
真っ赤になった首もとと襟元の破れが激しかった戦いの痕を物語る。
「何で日紅が月夜のやったことを弁償する必要があるんだよ。こいつにさせればいい」
「何言ってるのよ犀。巫哉に弁償できるわけないでしょう?お金持ってないんだし」
「別に金じゃなくてもいい」
犀がちらりと横目で『彼』を見ると、『彼』はしたり顔で言った。
「じゃあ体か」
「は!?」
日紅は目を剥いたが、犀はにやりと笑った。
「そうだな。じゃァ体で返してもらおうか」
「な、ちょ、ちょっと待ってよ犀!や、やっぱりあたしが一番単純かつ円満な方法で返すわ。はいお金」
日紅は犀にそっと千円札を握らせた。
「日紅!そいつに物を与えるとこの世の終わりまでついてきてウザいからヤメロ」
「別におまえについていくわけじゃねぇよ」
「犀!巫哉!喧嘩しないでよーーーーッ!」
日紅は再び叫んだ。
途端にドアがドンドンと叩かれる。
姉だ!まずい!
三人は顔を見合わせた。
…そしていつもどおり夜は明けてゆくのである。
『彼』2
「ヨ」
ある日、のっそりと大きい体を茶色の毛で包まれている、たとえて言うならば四肢のないマンモスのような生き物が日紅の部屋に入ってきた。窓から。
その日犀はいなくて、『彼』と日紅の二人だけだった。
変な訪問者がなれなれしく入ってきても、二人は驚かなかった。
「遊びに来たぞ青更。その人間だな?噂の」
「こんにちは。あたしは日紅。あなたは?」
「ワシは…大樹だ」
「あなたはどのくらい生きているの?」
日紅は慣れたように聞き返す。ヒトかヒトじゃないかなんて、ずっと『彼』と一緒にいた日紅からすれば細事だ。空気がそこにあるのと同じように、それが妖であるということは彼女にとっては単なる一つの事実でしかないのだ。当たり前に受け入れる。
「ワシか?ワシは…ヒトなどいなかった昔からだ。よろしくな、譲ちゃん」
そう言うと、大樹はのそのそと日紅に近づいてきた。
「ふんふん。おぬしが青更の、か」
「…え、あたしが、巫哉の…何?」
『彼』がすっと日紅と大樹の間に手を出した。大樹の歩みが止まる。
「あんまり近づくんじゃねぇ。てめぇはきたねぇんだよ」
「ちょ、バカ巫哉っ!失礼でしょ!」
「はははは、よいよい。ワシは気にしとらんよ譲ちゃん。…さて、どうやらわしはお邪魔虫みたいだから退散するよ。青更、うまくやれよ。ヒトの命は短く終わりがあるからな。もたもたするなよ。それと…祝言の際にはちゃんとワシも呼べよ」
顔(らしき部分)の毛がもそっと動いた。それが日紅にはなぜか大樹がにやっと笑ったかのように見えた。
『彼』の額にびしばしと青筋が浮かんだ。
「さっさと行け!このくたばりぞこないが!」
大樹は、ははははと笑いながら、ぴよんと窓から出て行った。窓枠より大きい体なのに、どうやって窓から出て行ったのかは彼のみぞ知る、だ。
そう言えば口がないのにどうやって喋っていたのだろう。目もなかった。あの長い毛の下に隠れてでもいるのだろうか。日紅は詮無いことを考えていた。
そしてちらりと『彼』を見た。
「…祝言って何」
「知るか」
とにかく不機嫌な顔で『彼』は言った。
『彼』3
「ねぇねぇ犀。巫哉の本名、って何だと思う?」
日紅が犀を覗き込む。犀はそれに軽く笑って、自分の机の上に弁当を広げ始めた。
「月夜、の?」
犀は牛乳にストローを差し込みながら答えた。
日紅と犀は小学校5年生の時に知り合った。それから日紅が犀に『彼』を紹介したので、『彼』と犀の付き合いは日紅よりも浅い。
「あたしは気がついたら巫哉って呼んでたの。きっとあたしが思いつきで勝手に呼び始めたんだろうけど、変な名前だよね、ミコヤって」
日紅はくすくすと笑う。
「ミコヤ、みこやー…うーん何かの略かなぁ?なんでこんなわけわかんない名前にしたんだろう?」
「おまえのことだからその時やってたアニメの主人公とかじゃないの?」
「そんなアニメなかったよー」
「思い出したら教えろよ?俺も気になる」
「ん。犀はなんで月夜なの?」
「俺は、あいつと出会ったのが月夜だったから、月夜」
「…なんでツキヨでツクヨになるのよ」
「…古事記に月夜見命って出てくるだろ?」
犀は一瞬詰まった後に小さい声でぼそぼそ言った。
「うん?」
「あいつに会った時、何かそれが思い浮かんだんだよ。あーくそっ!」
犀は照れ隠しなのかひとりで叫んで頭をぐしゃぐしゃとかきむしった。
日紅は思った。そうだ、犀は昔っから古文に興味津々だった。ツクヨミノミコトが日紅にはなんなのかよくわからない。でも確か古事記は日本の神様がいっぱい出てくる本だった気がする。八岐大蛇を倒したのは須佐乃袁尊だおまえそれくらいは覚えておけといつか犀に教わったことがあった。
スサノヲノミコトは神様だっけ?じゃあミコトつながりでツクヨミノミコトも神様?
ん?じゃあ犀は巫哉に初めて会った時神様みたいに綺麗だと思ったのかなぁ。
月光の下では『彼』の銀髪はさぞ神秘的で美しかろう。闇を弾く白銀の光に強い意志が燈った紅の瞳を見てしまえば犀がそう思ってしまったとしても全く不思議ではない。
不思議ではない、が。
「…犀」
「…何」
「あんたって意外とロマンティストだったのね」
「…言うな」
日紅の止めに犀はがくっと机に突っ伏した。
「なんでいきなりそんなこと言いだしたんだよ日紅」
犀が腕の囲いの間からもごもごと声を出した。
「ん?」
「気になるの?月夜の本名」
「興味本位で。まさか本当に『太郎』とかだったりして!」
「それは、ありうるな」
犀も顔をあげ、二人は笑いあった。
「来年はーーー…」
ふと、日紅が呟いた。
「あたし達、もう16だね」
「そうだな?」
犀が頬杖をつきながら返す。
「…嫌だなぁ、大きくなるの」
「何故?俺は早く大きくなりたいよ。背ももっと伸ばしたいし」
「170もあるくせに何言ってるの!背伸ばしたいのはこっちだよ~…。犀は伸びすぎ。ちょっと縮め。そしてその分あたしに頂戴。あ、その牛乳も頂戴」
日紅はひょいと犀の牛乳を取ると、ごくごくとあっというまに全部飲み干した。
「…俺の金で買ったんだけど」
「気にしない気にしない。ハゲるよ?」
「……男にハゲは禁句だぞ」
ちなみに犀の父、悟36歳は既に生え際が危ない。
「そうなの?でも巫哉はハゲないね?もうとっくにおじいちゃんな歳なのにねーーー」
「おじいちゃんどころか生まれ変わって死んでもおつりがくるぐらいだけどな。」
犀はふっと笑うと、日紅の頭をぐしゃぐしゃと撫ぜた。
「ちょ、な、何するの!?牛乳の恨み!?」
「そ。俺の背が伸びなくなったら日紅のせいな。目指せ200だから」
「200!?ありえない。てか、責任転換はよくないと思うよ」
「そういえばさ、日紅」
「ン?何」
「月夜ってさ、おまえが今みたいに学校に来てるとき、なにしてんの?」
「さぁ?あたしに巫哉のプライベートにまで干渉する権利ありませんからね。どっかのおネェちゃんとウハウハしてんじゃないの?」
「…おまえ、それが女子中学生の言うことか?」
「んじゃあ、犀は巫哉が何をしていると思うの?」
「俺か?俺は、そうだな…」
犀は、ふと日紅の肩越しの窓の外を見た。
目を細めて、強く、まるで射るように。
『彼』は思わずぎくりとした。
気づかれた?いや、そんな、まさか。
今、『彼』は誰にも、妖にすら視えないように姿を消しているのだ。ましてやヒトごときに気づかれるわけがない。
だがそれでも、その視線は的確に自分を見ている気がしてならない。
『彼』はどうしようもない居心地の悪さを感じてふわりと飛び上がった。
『彼』4
学校よりも、日紅のうちの隣に立っている木よりも更に高く高く飛翔すると、『彼』はぐるりと周りを見回した。
狭い町。人家は見果てぬように続くがその実ここがどれだけ狭いのか、彼にはわかる。
ヒトは地に足をつけ、土から生まれたものを食べ、陽光をその身に浴びなければ生きてはいけない。一生のうちに関わる他人も、土地も、ひとつ所に縛られるのが運命。弱い身、狭い視界。
『彼』はずっと、ここにいた。ここにこの町ができるずっとずっと前から。時に眠り、時に起き、そして日紅と出逢った。
「巫哉」
と、日紅は『彼』のことを呼ぶ。
その声は『彼』に温かく届く。それは日紅のこころだ。なんともくすぐったく思いながらも、『彼』は日紅を突き放せずにいる。
長く生きてきたけれど、ヒトの前に『彼』が姿を見せたのは、日紅が初めてだった。
あれはどれくらい前だったかーーー…などと考えるのもバカらしいほど、『彼』にとって日紅との出会いはほんの数日前の出来事と一緒だ。
「おぅい、黄泉よォーーー」
ふいに、ぐふぐふという妙な笑い声とともに、『彼』の目の前に拳大の丸い玉が現れた。
その玉は光の加減によって青にも赤にも見える。
『彼』は一瞥もせずに、まるで蝿でも叩き落すかのようにその玉をばちりと叩いた。
「な、何するんだ黄泉ーーーーッ!」
「うるせぇ。黙れ」
「機嫌が悪いな黄泉。ははァ…さてはおぬし」
『彼』の鋭い爪が空を切って唸った。玉は間一髪でそれを避ける。
「なななな何すんだ黄泉!今の当たってたら死んでたぞ!」
「てめぇはしぶといから、そう簡単に死ぬか」
「相変わらず短気だな!…まだ何も言ってないのに…」
「てめぇの言うことは予想が出来る。大体、俺は機嫌が悪いわけじゃねぇ」
「例の女子に振られたか?」
再び『彼』の鋭い爪が唸った。今度こそ、玉の一部がひゅうと飛んでキランッとお星様になった。
「……………んな……………」
既に球状でなくなった「もと」玉はあまりのことに絶句し、ぶるぶると震えだした。
「うるせぇ」
「こ…っ、このっ、覚えていろよ黄泉ッ!」
すうっと玉の姿が掻き消えると、『彼』はフンと鼻を鳴らした。
どいつもこいつも。俺がヒトの前に姿を現したのがそんなにおかしいか。
…いや、違うと『彼』は思う。あれは『彼』が姿を現したのではない。日紅が『彼』を見つけてしまったのだ。『彼』は別に日紅を何か特別な存在だと見て、姿を見せたのではない。なのに妖(あやかし)たちは勘違いをしている。
『彼』が日紅を特別なヒトだと見込んで、自ら姿を現したのだと。そして喜ぶ。よかった、よかったなと。いくら『彼』が違うといっても全く聞く耳を持たない。短く限りのある命を持つ日紅を見ようと我先に『彼』に会いに来る。
それでも、『彼』は日紅と一緒にいるのが嫌なわけではなかった。
けれど、あいつはーーーー…。
『彼』はむっと眉を顰めた。
犀、という、あいつ。
日紅が今よりも少し小さかった頃、あいつをいきなり連れてきた。『彼』は出て行きたくなかったが、日紅があまりにも『彼』のことを呼ぶので、しぶしぶ姿を現した。すると日紅はにっこり笑ってあいつのことを『彼』に紹介するのだ。
『彼』は犀のことが嫌いだった。出会ったその時から。
犀は『彼』のことを「月夜」と呼んだ。
けれど、『彼』はわかる。犀も『彼』のことを快く思ってはいないことを。その呼び声は『彼』に犀のこころとして突き刺さる。
別に、それはいいのだ。『彼』も犀に好かれようと思ってはいないから。
日紅は単純に、「二人はいつも仲いいねぇ」などと言っているが、不食の理を無視してでもこのクソ、喰ってやろうかと思ったことも一度や二度ではない。
勿論、犀も同じことを考えているようで、たまに据わった目で、『彼』を食い殺す勢いで見てくる。
『彼』は犀が嫌いだ。理由はよくわからない。でもとにかく嫌いだ。生理的に嫌いというのとはまた違う気もするが、嫌いだ。
犀も『彼』を嫌いだ。何故犀が自分を嫌がるのか、『彼』はわかりそうでわからなかった。
けれど、犀はわかっていた。自分が『彼』を嫌う理由も、『彼』が自分を嫌う理由も。
『彼』がその理由に気づくのは、それから2年の後のこと。
『彼』とあたしとあなたと1
日紅は、『彼』を好きで犀も好きだった。
『彼』は、日紅のことは嫌いじゃなく犀のことは嫌いだった。
犀は、日紅のことは好きで、『彼』のことは嫌っていた。
日紅は、わかっていなかった。
『彼』も、わかっていなかった。
犀。彼が一人だけ、全てを理解していた。
中学2年のときから、さらに2年。
ぬるま湯のような緩慢な時を経て、最初に変わったのは、日紅。
「ねぇねぇ日紅ちゃん」
うとうとしかけたところに声をかけられて、日紅はゆっくりと顔を上げる。日紅の中学校時代肩までしかなかった髪は、今やふわふわと弧を描いて背の半ばまでを覆っている。
目の前には、女の子。首をかしげて、日紅を覗き込んでいる。
ええと・・・と、日紅は眠りかけの頭を起こす。
「隣のクラスの桜ちゃん?」
「うん、そう」
桜は嬉しそうに笑った。かわいいな、と日紅は思った。
「で、ね、日紅ちゃん」
さらさらなセミロングの髪を揺らして、桜は心なしか、日紅に顔を寄せた。
何か秘密のハナシなのかな、と日紅は思った。でもなんであたし?確か日紅は桜と交流はあまりなかった筈だ。
「日紅ちゃんって、木下くんと付き合ってるの?」
木下?って、誰。日紅は一瞬考え込んだが、ああ、と間の抜けた声を出す。
「犀?」
「そう。木下犀くん。ね、付き合ってるの?」
桜は笑顔を顔に貼り付けたまま、真剣に聞いてくる。
日紅は思わず笑いそうになった。つきあってる?あたしと犀が?まさか。
変な誤解をされないためにも、ここではっきりと言うべきだ。
「違うよ。あたしと犀は気の合うってだけの、友達。別に付き合ってなんかいないよ?」
そう言うと、桜はとても嬉しそうに笑うのだ。
「よかった!」
あぁ、これはもうーーーー…。日紅は思った。まったく、いいわね色男は。
「じゃぁ、じゃあ日紅ちゃん。あのね、犀くんのー…」
「俺が何?」
桜と日紅は同時に目を見張った。一瞬の間のあと、桜の顔がぼっと赤くなる。
日紅は桜の後ろに、うんざりするほど見慣れた顔を見つけた。
「犀」
「今、俺の話してた?」
あっこらそこはわかってても黙ってなさいよ!日紅は思った。
「あ、ぁああぁの、日紅ちゃんっ、もう戻るねっ!またねっ」
そう叫んで、桜はばたばたと日紅のクラスを出て行った。
「…すっかりプレイボーイね、犀。お姉ちゃん悲しいわ」
「誰がお姉ちゃんだ、誰が」
「モテモテで羨ましい限りで」
「あの子になんて聞かれた?」
「あたしは遍く女の子のミ・カ・タ。そうぺらぺらと喋らないデース」
「ふぅん…」
まあ、大体察しはつくけど、と犀は呟いた。
「ねえ犀、あんた付き合ってるコ、いるの?」
一応桜ちゃんのためにリサーチしといてあげよう、と日紅は犀を見上げた。
「いると思うか?」
「全然」
「……。じゃあ俺も聞くけれど、おまえ好きな男いるの?」
「?付き合ってる男、じゃなくて?」
「おまえと誰かが付き合ってたら流石にわかるさ。おまえが俺に隠し事できる気しないし。で、いるの?」
「…いると思う?」
「全く」
「………」
仕返しかこれは。
「あ、日紅、もうひとつ聞いていいか?」
「嫌」
「さっきさ」
「ムシかい」
「さっき、おまえ青山と何話してた?」
「はい?」
日紅はぽかんと口を開けた。
「青山、ってあの青山くんかしら。うちの級長の」
「そう、その‘顔がよくて背が高くて頭もよくておまけにスポーツ万能だなんてキャーーッなんてステキなのv’って女子が騒いでた青山くん」
「あぁ、あの‘顔がよくて背が高くて頭もよくておまけにスポーツ万能だなんてクソーーッ一つも欠点がないぜ’って男子が騒いでた青山くん」
「……男子の内情に詳しくないか?」
「そっちこそ、女子に内通しているようで」
「で、その青山になんていわれた?」
「別に、何も。あ、でもリプト○のレモンティーくれたわ」
「リ、リプト○のレモンティ~!?」
「は?な、何をそんなに慌ててんの?リプト○のレモンティーってそんなに希少価値のあるものだっけ?」
犀は例の缶が日紅の手のひらに収まっているのを見て取ると、いきなりそれをむんずと掴んで、一気に飲み干してしまった。
「あーーーーーーーっ!なんてことをおおおおおお!バカ犀!ばか!あんた本当は青山くんの人気知らないんでしょ!?これだって欲しがる女の子いっぱいいるんだからね!」
日紅が憤慨して犀をどつくが、犀は真剣な顔で言った。
「日紅。今日から一緒に帰ろう。朝も迎えに行く。いいか、青山は、あいつは顔だけの男だ。他はいいところなんてひとッつもない」
「はぁ?」
「伝説を作れ、日紅」
「な、一体何のことなのよおおおおーーーーーッ!」
『彼』とあたしとあなたと2
「考えすぎじゃない?」
日紅は呆れて言ったが、犀は渋い顔だ。
「いや、間違いない。日紅、おまえは青山に狙われた。あのリプト○のレモンティーがその証拠だ」
学校の帰り道。結局、日紅は犀と二人で帰っている。
犀の家は反対方向なのだからと日紅が渋ったが、いつになくハイテンションの犀に押し切られる形になってしまった。
暗い道を、ふたり、てくてくと歩きながら帰る。
「リプトンのレモンティーが何だって?」
「青山は狙うと決めた女には必ずリプトンのレモンティーを渡す。それが宣戦布告。本人にも、周りにもな」
ま、確かに、わかりやすくはある、わ、よね…。
あの爽やかな人がやるだけで何事も好意的にとらえてしまうのが悲しいかな、凡庸な一女子の運命なんです。日紅は心の中で誰かに弁解した。
「でもなんであたし!?偶然じゃないの?まともに考えて、ありえないというかなんと言うか…」
「青山だって人間だ。たまには毛色の変わったのもいいかと思うときもあるだろうよ」
「…」
「あ、嘘です。ゴメンナサイ。口が滑りまし、だっ…!?」
どすんと日紅の拳が犀の鳩尾にめりこむ。
「お、おまッ…モロにぃっ!」
「おほほほほほほほごめんなさいねぇ?毛色が変わってて」
日紅はしゃがみこんで身悶えする犀に見向きもせずにざかざかと先へ進んだ。曲がり角を曲がったところで、犀の焦った声だけが日紅の背中に追いつく。
「おい!日紅!」
日紅は完全無視をして進む。
「青山が出たらどうするんだ!」
「出るかボケ!」
思わず怒鳴り返して振り返れば犀がいた。
足の速いやつめ…日紅はちっと舌打ちをする。
「先に行くなっての」
「青山くんは出ないわよ。あんたじゃないんだから」
「いや、出るかもしれない。どうやってやるのかは知らないが、あいつは狙った女は必ず落とす。伝説を作るぞ、日紅。青山に落ちなかった唯一の女、山下日紅として」
「…」
大袈裟な、と日紅は思ったが、溜息をつくだけにとどめた。
「それとも、まさかもう手遅れか?青山にホの字か?」
「好きな人なんていないって言ったでしょ。ま、青山くんなら考えないでもないけど」
何しろ学校中のプリンスだ。
「…ふぅん」
隣で犀が鼻で唸った。
空気が変わった気がして、日紅はどきりとする。
「…」
なぜか、日紅は汗がじわりと滲むのを感じた。
犀が次に何を言うのか、そのくちびるの動きを、必要以上に意識する。
「月夜…」
「ぇ…?」
蚊の鳴くような声が日紅の薄く開いた口から漏れる。
犀はそれを一瞥すると、視線を前に戻して、言った。
「月夜のこと、どう思う」
「どう、って」
日紅はもごもごと口ごもった。答えが出てこないのではない。日紅は何かに圧されている。それに追われて、声が日紅の奥のほうへ逃げ込む。隠れてしまう。だから、声が出ない。それは所謂プレッシャーというものかもしれない。
それを与えているのは、間違いなく犀。
「す、好きよ」
「ふぅん」
犀がまた唸るように答える。
日紅は困惑していた。犀が、変。何かおかしい。ここにいる犀は、日紅の知っている犀ではないような気がする。
「犀…?」
犀を見上げても、犀と目線が交わらない。犀は前だけ見て、歩いてる。
なにを見てるの?犀…。
日紅は悲しい。犀と見ているものが変わってしまった。考えていることが変わってしまった。昔とは違う。一緒に笑い合っていたころはこんな遠いものを見てはいなかった。
いつから距離が開いてしまったんだろう。肩が触れ合うほど隣にいるのに、犀がこんなにも遠い。
「おまえ、何も気づいてないの?」
「ぇ…」
「日紅」
犀は日紅の名を呼んで、それからゆっくりと日紅を見た。犀の目が夜闇と共に日紅を映した。
犀は瞳に黒い光を湛えて言った。
「わかってないよな、おまえ。なんにも」
『彼』とあたしとあなたと3
家に帰ってきて、自分の部屋に入っても、日紅は大木に面する窓を開けなかった。
制服を脱ごうともしないまま、ベットの上に転がる。
模様のない無機質なクリーム色の天井。日が陰ってきて薄暗くなっている日紅の部屋。黄色のカーテンから斜陽が射す。
日紅の口から無意識に軽い溜息が漏れる。
おかしい、犀。
あたしが、わかってない、って、どういうこと?
日紅はごろんと寝返りをうった。
「日紅」
「!」
いきなり目の前に『彼』の顔が現れて、日紅の悲鳴は喉に張り付く。
「どうしたんだよ、今日は。具合でも悪ぃのか?」
どうして窓を開けなかったのだと、『彼』はそう言う。
「…ねぇ、巫哉」
日紅は『彼』の頭に手を伸ばしながら言った。
「…何だ」
日紅に頭を撫でられて、不機嫌そうにしながらも『彼』は大人しく返事をする。
「背、ちっちゃいね」
ビシッ。
瞬時に『彼』の額に青筋が走る。当然ながら日紅の手はいささか乱暴に振り払われた。
『彼』の外見は出合ったその時から、13、4の少年の姿だ。それは今までも、そしてこれからも決して変わることはないだろう。日紅が老いて死ぬその瞬間も、きっと『彼』は実年齢に比例することない幼い外見のままなのだ。
『彼』は時間に囚われない不死の身だ。『彼』の時間は未来に向かって進むこともないし、過去に戻ることもない。ヒトとは似て非なるもの。
でもこうしてヒトである日紅の傍にいてくれる、それが日紅は嬉しい。
どうして一緒にいるかとか、難しいことはどうでもいいのだ。
いつまでも変わらないものを見ていると、ヒトは不意にそれに疑問を抱くことがある。常に移ろう時の流れに添わないものなどないのだと。なのにどうしてその身は老いぬのか。なぜ朽ちないのか。
それはきっと逆も然りだろう。時を刻まない『彼』は、まわりのすべてのものが移ろい行くことに疑問を抱いた筈だ。それはもしかしたら、疑問ではなく存在意義を押し潰す程の恐怖だったかもしれない。唯一無二の存在。この広い世界中、溢れるほどある命の中で、たったひとつだけ終わらない命。その孤独は如何ばかりか。しかしそれを圧してでも『彼』は日紅とともにいてくれる。それが、日紅にはとてもとても嬉しいのだ。
「ずっと、変わらないね巫哉は」
「悪ぃか」
「全然。でも、ねぇ、巫哉。あたしもういくつになったんだっけ?」
「17だろ」
こともなげに『彼』は言う。
「じゅう…なな…17かぁ…」
月日は無慈悲だ。一瞬の合間に過ぎていく。その一瞬で日紅や、犀や、ヒトが感じたものなど一瞥もしない。ただ流れてゆく。
「嫌だなぁ…」
日紅はクッションに顔をうずめた。
変わってゆくのは、怖い。
「ずっと、ずっと、今のままがいいのに。もしかしたら、明日、あたしが事故で死ぬかもしれない。犀が、何かの事件に巻き込まれて殺されちゃうかもしれない。そうしたらもう、変わってしまうでしょ?あたしを取り巻く何もかもが。大人になんかなりたくない。ずっとこのままで、いたい…」
犀も変わる。背が、伸びた。200とまでは行かないけれど、183もある。人当たりもよく、仲のいい友達もたくさんいる。日紅のことなんか、今日明日に忘れてしまっても不思議はない。
実際に、明日犀が日紅を忘れるなんてないことは日紅にもわかっている。でも、「絶対」なんて誰が言い切れるというのだろう。明日の保証を誰がしてくれるというのか。未来を知る術はないというのに。
怖い。
『彼』は、戸惑ったように日紅を見ていたが、躊躇いがちに手を伸ばすと、震える日紅のその肩にそっと手を置いた。
ゆっくり、不器用な手つきで日紅の頭を撫でもしてくれる。
「もう、寝ろ」
まだ闇も浅く、寝るには少し早い時間だったが、日紅はその声につられたように、じきに寝息を立て始めた。
『彼』とあたしとあなたと4
日紅(ひべに)の寝顔を見ながら、『彼』は想う。
日紅の、変化を恐れる気持ち。その気持ちを、『彼』は身を切られるほどよくわかっている。
『彼』にとって日紅は、人生のほんの一瞬を共にするしかできないもの。
時は、泣きたくなる位の速さで進む。子供から大人へ、大人から老人へ、そして死が訪れ、また命は廻(めぐ)る。日紅もすぐに老い、死んでいく。『彼』が日紅を見送るのは定められた未来。逆はあり得ない。そしてそれは決して遠いさきの話ではない。
そうすれば、『彼』はもう独りだ。
日紅と出会うまでの4千年余り、『彼』は孤独をたった独りで生きてきた。すべてのものに傍観者であり続けたそれは別に苦でもなんでもなかったし、自分がまさかヒトと馴れ合う日が来るだろうなんて予想だにしなかった。
例えば。
今日紅が死んで、『彼』を知る者が犀しかいなくなったのならば、『彼』は間違いなくすぐ眠りにつくだろう。
目覚めたときには犀(せい)はいない。ヒトの命は本当に短い。日紅を知っているものはもう誰もいないだろう。日紅の家もきっともうここにはない。『彼』が居座るこの枝も、この大木も、日紅が好んで買ってきたこのカーテンも、日紅の太陽のような笑顔も、その笑い声も、日紅と、犀と、『彼』とふざけあっていた思い出さえ、もう微塵もないのだ。
それを見たときに、『彼』はどうするのだろう。
死を持っている身は幸せだ。終わりがあると知っていれば楽だろう。終わりがあるということは始まりがあるということ。ヒトだけでなく、妖にも寿命はあり、死は舞い降りる。ただそれがヒトよりほんの少し長いだけのこと。生と死は生けとし逝ける遍(あまね)く全てのものへ平等だ。例外はひとつ。『彼』のこの身だけ。
延々と流れる時の中、『彼』はひとりで立ち尽くすしかないのだ。変化のない『彼』は命を持つものと一緒に生きることはできない。循環する命を見送り身守るのが定め。
ヒトは幸せだ。
死ぬことの出来ない『彼』には、終わりという言葉はない。ヒトの世には転生という言葉があるが、それもない。もしも、『彼』が死ぬとしたら、その時は消滅。完全なる無だ。
4千年の末(のち)、『彼』は日紅に逢った。けれどこれ以上生きて、生きて、生きて。一体何があるというのか。もう4千年生きたら再び日紅に逢えるというのなら、『彼』は喜んで眠りにつくだろう。けれどそんな保証を一体誰がしてくれるというのか。
何もかもを持っていて全て奪われるのと、最初から何も持っていないのは、一体どちらが苦しいのだろう。
日紅との別れ、それはいつか必ず来る。今日か?明日か。40年くらい先よと日紅は笑うが、そんなの『彼』にとっては今日明日も同じこと。
『彼』はやりきれない思いで日紅を見る。
いつか。…いつか、日紅と同じくらい、いやそれ以上のヒトが現れるだろうか。そうして、『彼』に手を差し伸べてくれるのだろうか。
だとしたら、それはいつ?何千年、何億年先のこと?不確かな未来を当てにして生きられるほど、『彼』は強くない。
だからといって、死ねもしない。
「…日紅…」
日紅よりも、『彼』の方が時の移ろいを恐れていた。
頼むから何処にも行くなと、離れなければならない日は必ず来るのだから、どうかその時が来るのが一秒でも長引くように…。
『彼』はそれだけをいつも身が切れるほど願っている。
『彼』とあたしとあなたと5
朝。犀(せい)は日紅(ひべに)を迎えに来た。
くしゃくしゃの制服で出てきた日紅を見て、犀が笑う。
少しふざけあって、二人で歩き出す。
日紅は犀を見れない。犀が怖いのかもしれないとふと思って、途端におかしくなる。犀が怖いわけない。だって、今までずっと一緒にいた。今更怖いわけがない。
でも、日紅は犀の顔を見れない。目を、見れない。
いつも通りに笑っているように見える、犀。
いつも通りに笑っているように見える、日紅。
犀は、こんな風に笑う人だったろうか。何かを隠して笑っているような。本当におかしくて笑っているのではないと、何かに気をとられているのだろうなと、わかるような。
でもそれは日紅も同じだろう。二人して笑いながら普通を装って話してるのはきっと、気まずくなりたくないから。傍から見ればこの上もなく違和感があるに違いない。
何かが変わった。いや、変わりそうなのだ。犀は変えたいと思っている。でも、日紅はいやだ。このままがいい。
でも、じゃあ、どうしよう?
日紅は変な風に息をついた。
そして、意識せずに言ってしまう。
「犀」
「何?」
「あのさ…。犀。もしかして、何か悩み事とか、あるの?」
日紅は言ってからしまったと思った。何が「しまった」なのかは自分でもわからなかったが、言わなければよかったと日紅は眉を下げた。
案の定、犀の歩みが止まる。
日紅は隣を見れない。犀にあわせて、歩みを止めて、その様子を前を向いたまま伺う。
「日紅」
「っ…せ…」
ぽつりと犀が日紅の名を呼んだ。なにも日紅は悪くないのにごめんなさいと謝ってしまいそうになる。強く、日紅は唇を噛み締めた。
「やっぱりおまえなんにもわかってない」
何と尋ねる前に、犀が日紅の手をとった。そのまま、いきなり走り出す。
「ちょ、せ…!」
日紅はすぐに息が切れた。止まってと言おうとしても、苦しくて喋れない。
日紅の足が縺(もつ)れる。でも犀に手を引かれているから走るしかない。
走って、走って、走って。
やっと、犀の足が止まった。日紅はげほげほと咳き込んだ。苦しい。苦しい。涙が出てきてぱたぱたと落ちた。
立ったままではいられなくて、日紅はくたりと座り込んだ。
犀が何か喋っている。でも日紅にはそれを言葉として認識できるだけの余裕がなかった。酸素がなくて、頭ががんがんと痛む。
そのまま、日紅は倒れこんだ。
『彼』とあたしとあなたと6
「日紅(ひべに)ちゃん、貧血だって?大丈夫?」
桜が心配そうに起き上がった日紅の顔を覗き込んだ。
大丈夫全然心配ないよと日紅は笑いながら答える。
気がついたら日紅は保健室のベットにいた。犀(せい)が抱えてきたのだとナイスバディな保健室の先生は笑って言った。
…なんなのよ、もう。犀のバカ。あほ。ぼけ。おたんこなす。
「で、ね、日紅ちゃん、あのねぇ?」
頬を染めて日紅を見る桜の用件は大体わかる気がした。
「山下さん」
教室に戻ってきた日紅に、青山が真っ先に声をかけた。
「もう大丈夫なの?もう少し休んでいた方が、いいんじゃないのかな」
心配げに日紅を見る青山は、まさに王子様。
「こいつはそんじょそこらのヤツと違ってひときわ丈夫だから平気だ」
日紅と青山の間に割り込んでくるこいつは、さながら玉子様。
「…なんなのよ、タマゴ」
「は?卵?何で俺が卵?」
「青山くんと比較して」
「……酷くね?」
「全く」
あんたの今朝の仕打ちに比べたら!日紅はフンと鼻を鳴らした。
「あ、で、山下さん、よかったらこれ」
いけない青山くんもいるんだった。おしとやかに、おしとやかに。既に手遅れなことを心の中で呟きながら、はいと日紅が青山に手渡されたのは、ノート。
「?」
「山下さんがいなかった授業分のノート、とってあるから」
よかったら使ってね、と言って光を振りまきながら青山は去っていった。
おおう神様。思わずその背を拝んでいる日紅の頭を例の青山のノートでぺしりと犀が叩く。
「ぺ様も負けるわね」
「え、俺のこと?」
「あんたはぺはぺでも、かとちゃんぺ~よ」
「酷!」
そう言って笑う犀はいつもと全く一緒。
日紅は内心ほっと息をついた。
「ねぇ犀。ちょっと、話あるんだけど」
「ん。ここじゃまずい?」
「ん~…ちょっと」
「じゃ、弁当もってこい。屋上行こう」
犀は日紅の頭をぽんと叩いた。
『彼』とあたしとあなたと7
「で、何?」
日紅(ひべに)が卵焼きをつっついたところで、犀(せい)がそう切り出した。
「うーん、とね?犀、あんた付き合ってるコいないのよねぇ?」
「…いないけど」
「じゃあ好きなコは?」
「………」
急に犀が黙った。
日紅は焦った。まさか…いる?
「いるよ。好きなヤツ」
日紅の心を読んだかのように犀が言う。その視線は彼の足もとに注がれていた。
「嘘ォ!?」
どうしようと日紅は予想外の展開に驚いた。
日紅の考えでは、(なんの根拠もないのだが)当然いないといわれて、じゃあ隣のクラスの桜ちゃんなんてどうと進める予定だったのにー…。
とりあえず!
「誰!?」
「同じクラスのヤツ」
日紅と犀は同じクラスだ。
と、いうことはうちのクラスの女子…!?
寝耳に水とはこういうことだ。
なんということだ。なんで言ってくれなかったのだろう!それよりいつから!?高校で犀とはクラスがずっと一緒なのだ。
日紅は犀ととても仲が良いと思っていた。それは日紅の勘違いではないと思うし、犀だって日紅のこと仲がいい女友達だと思ってくれていると、当然のようにそう思っていた。
ずっと、一緒にいたのに!
「席は!?」
日紅は犀に詰め寄った。
「俺とは遠い。確か前から2番目」
「前から2番目!」
ドンピシャ!と日紅は叫んだ。
「嘩楠(かなん)さんね!?」
嘩楠百合(かなんゆり)と言えば、顔よし頭よし財力よしの、三拍子そろった学校のプリンセスだ。プリンスは言わずと知れたあの青山である。
その二人と同じクラスになったから日紅は「今年のクラスは凄いぜ…じゅるり」と涎を拭いていたくらいなのだ。
奇(く)しくも、噂の嘩楠となんと日紅は隣の席どうしだ。だから嘩楠が噂と一寸違(いっすんたが)わぬ人だというのもようく知っている。
桜ちゃん、ごめん見込みないわ、と日紅は頭の中で謝る。桜は確かに可愛らしいとは思うが、嘩楠とは比べようがない。はっきり言って月と何とやらだ。
犀が好きになったのも、嘩楠さんなら十分納得だ。
「……」
犀は一人で百面相する日紅をじっとみていた。そして、溜息をつく。
「違う」
「え?違うの?でも二列目はあと男しかーー…はっ!ま、ままままましゃか犀、あんたそういう趣」
「落ち着け。嘩楠以外が男だったらおまえは男か?」
「は?んなワケないでしょ。ちゃんと胸あるしいらん脂肪もぷくぷくおナカについてるわよ」
「どれ?お、本当だ」
「ギャーーーーーーーーーーーーッ!」
ガゴッと日紅の拳と犀の頬骨がぶつかって凄い音を立てた。
「ーーーーッ痛(つ)ぅ…」
「何すんの!嫁入り前の女の子のお腹を触るなんてセクハラよセクハラ!訴えられても文句言えないレベルなんだからね!?」
「安心しろ。嫁の貰い手がなくなったら俺が貰ってやるから」
「そこまで落ちぶれちゃいないわようっ!」
「ま、おまえを貰おうなんていう男は一生出てくるわけないけどな」
「はい!?」
日紅の眉がピンと上がった。
「犀!またそうい」
「俺が出てこさせやしないから」
「ー…は」
「日紅。おまえのそれってわざと?気づいているんだろ。なんでそんな知らない振りするの?」
「な、なにが…」
「月夜(つくよ)を、好き?」
「え、そ、それは勿論好きだけど…」
「じゃあ、俺は?」
犀が日紅を見ている。視線を痛いほど感じる。日紅が視線をずらす。興奮して近づきすぎた犀の影が、自分の膝にかかっているのが見える。
「な、なに言ってるの、犀。犀のいいたいこと、わからない」
「おまえが好きだ」
無意識のうちに犀の膝にのせていた日紅の手を、そっと、犀の手が覆う。日紅は思わずびくっと体を震わせた。
だめ!違う、だめ。自然にしなきゃ。だってこんなのなんともないでしょう。普通、そういつものことなんだから、動揺するな!
重なった犀の手に、ゆっくりと力が加わる。それは振り払われるのを恐れるような、でも何か伝えたい感情があって、それが溢れてくるようなー…だめ、考えちゃダメ!
はやく、へんじをしなきゃ。
自分がなぜそう考えるのかわからないまま、日紅は笑った。唇は震えていた。
「あたしも好きよ」
「違う。はぐらかすな。顔上げろよ。俺を見て言え、日紅!」
隠しきれない苛立ちを含ませて犀が言う。
だめ。顔なんて上げられない。犀の目を見てはいけない。それを見てしまったら、何かが崩れる気がする。
「日紅!」
日紅は唇を噛んだ。そして、ゆっくりと顔を上げる。思ったより近いところにある犀の顔。その目が、あった。
「好きだ」
どくんと日紅の心臓が波打った。それは決して、犀のその言葉を聞いたからではない。犀の目。その瞳を見たから。その瞳の奥にあるものを、日紅は確かに見た。そして自分の瞼の奥も。
言葉にできない、その感情を。
「お前のことが、ずっと、ずっと好きだった。他の何にも代え難いくらいに好きなんだ、日紅。俺と月夜、どっちが好き?比べるのなら、どっちが上?俺はもう耐えられない。こんなに、お前を好きなのに。月夜と同じなんて冗談じゃない。俺はおまえの中に、俺だけがいてほしいと思う。ちゃんと俺を見て、日紅。自分のことからも、現実からも、目を逸らすなよ…」
『彼』とあたしとあなたと8
気がつけば、日紅(ひべに)はたった一人で屋上にいた。犀(せい)はいない。
食べかけの日紅の弁当が、そのままある。
「おまえ、本当に気づいていなかったの?」
犀の声が頭を巡る。
「今まで、本当に、気づかなかったの?」
日紅は頭を抱えて座り込んだ。
ぽつりと呟く。
だから大人になるのが嫌だったのに。
気づいていなかった。わかっていなかった。知らなかった。
でも本当は、きっとわかっていた。
日紅はそんなに鈍くない。思い当たることなんて、山ほどあった。
日紅自身が、ただそれに頑(かたく)なに目を向けていなかっただけ。
犀は『彼』のことをとてもとても気にする。
日紅がクラスの男子と話をしていれば割り込んでくるし、いつも日紅に優しい。とてもとても優しい。
それがただの優しさなのかと首を傾げる心を日紅は今まで押し込めてきた。犀はとっても優しいから。皆と同じようにあたしにも優しくしてくれるだけ。それだけ。特別扱いしているように見えるのも、小学校からの付き合いだから。ただそれだけのこと。別に変に思うこと、なにもない。
「あのね、日紅ちゃん。私ねぇ、木下君のこと、好きなんだぁ?」
その、言葉を聞いたとき、日紅は眩暈がした。
にこりと日紅を覗き込んでくる桜の瞳が、どろりと醜悪に歪められている気がした。
実際は、そんなことない。にっこりとかわいらしく笑う桜。ただ、桜は犀と仲がいい女友達の協力を仰ごうとしているだけ。勿論多少の牽制が入っているかもしれないが、それは、仕方がないだろう。下心が溢れているように見えてしまうのはー…それは、日紅の問題だ。自分が、犀のことを好きな子にとって邪魔でしかないということは重々承知だった。
だって、自分が逆の立場で、好きな人の近くにこんなに仲のいい女の子がいたら絶対不安だ。
犀は、高校に入って人気が出た。
何度か告白もされているようだったが、なぜか今まで「犀と一番仲のいい女」として嫌がらせを受けることも、そんな日紅と仲良くなって犀に近づこうと言う女も、いなかった。
「ね?だから日紅ちゃんに協力して欲しいの。日紅ちゃん、木下くんと仲よさそうだったから。好きな人とか、聞きだしてもらえないかなぁ?」
だから、日紅は油断していたのかもしれない。
ずっと、このままでいられると。日紅と犀と『彼』。三人で、このまま仲良くやっていけると。何も変わらないまま、のんびりと過ごしていけると。そんな、勘違いをしていたから。だからーーー…。
不変なんて、そんなの、あるわけがないのに。
邪魔ものと分かっていながらも、それでも犀から離れないのは自分のため。だってあたしは小学校から犀とずっと一緒だもの。後から来て彼が好きだなんだのといって引き離そうとするのはおかしい。あたしも犀のこと好きだから。犀だってそんなこと絶対望まない。恋愛じゃないよ。そんなのじゃない。だから、もう少しだけそばに居させて。
いつか、犀の隣には日紅じゃない人が寄り添っていくだろう。微笑みあって、手と手をとって支えあえる人が。
大丈夫、それはわかってるんだ。
ただ、ただ…それまでの、ほんの少しの間だけでいい、一緒に居させて。何も考えずに3人で笑っているだけでいい、あたしの日常を奪わないで…。
なんて高慢で、独善的で、汚いこころ。
…くるしい。
何も変わっていないように見える日常も少しずつ変化している。
日紅はその全てに耳を塞いだ。目を瞑った。何も気づかないフリをしていた。
日紅の足元は大きく崩れかかっている。それは決して止まらない。日紅が変わらない限り。
何もかもが日紅の手からすり抜けてしまう。
ほら、答えなんて、こんなにもすぐそばにあるものなんだ。
日紅のなか。
考えないようとしている頭の中、心の底で、ずるい計算して、何も知らないって顔で、ずっと、ずっと、犀を傷つけ続けてた。
一緒にいるか、離れるか。
きっと、犀は明日には笑ってくれる。
日紅が気にしないように、また、いつもみたいに笑ってくれる。
でも、それじゃ、だめなんだ。
離れることを犀は望まないだろう。日紅だって嫌だ。でも、犀のこころにちゃんと正面から向かうには、だらだらと甘えるだけじゃダメなんだ。
ちゃんと日紅が自分の心と向き合って、答えを出さなきゃいけない。
日紅は空を見上げた。
あおいあおい空だった。
どこまでもひろがるそら。
明日も、変わらずそれはそこにあって、好きとか嫌いとか苦しいとか楽しいとか、いろんな感情を全部その腕に抱えて上からこの世界を包んでいるんだろう。
日紅は泣いた。
日紅から見えないところに犀がまだいたことも全く気づかずに声を上げて咽び泣き続けた。
もうこどものままじゃいられない
『彼』とおまえとおれと1
「巫哉(みこや)。あたし、犀(せい)が好きかもしれない」
ピンク色のかわいらしいベットの上に日紅(ひべに)はクッションを抱えて両足を折り曲げて座っていた。
今日、帰ってきてから、日紅はまた窓を開けなかった。
『彼』は窓の外でやきもきしていた。『彼』は時の流れに縛られない。形あるものにも、この世の条理にも縛られない。こんな窓など越えて日紅の前に姿を現すのは簡単だし、日紅が学校にいる時のように日紅に悟られないよう寄り添うこともできる。
でも、『彼』はそのどれもしなかった。日紅の様子を透視(すかしみ)することもせずただ窓の外で日紅を待った。なぜか、『彼』にとって日紅が自らの意思でこの窓を開けてくれなければ、そうしなければいけないような気がしたのだ。
そして、望み通り窓は開いた。夜半のことだ。
部屋の電気は消されていた。これも、いつものことだ。『彼』と日紅と犀が三人で密会するときは夜半。電気がついていると両親や姉に怪しまれるからだ。だから、いつもは小さいスタンドライトをつけていた。
今日、そのスタンドライトはついていなかった。
「なんだよ、こんな夜遅くに起こすなよ」
いつもどおり軽口をたたきながら『彼』は窓枠に手をかけて部屋に入った。
部屋が真っ暗なのは『彼』にはどうでもいいことだ。夜目が効くとかいう問題ではなく、『彼』には見ようとすればそこにあるものがなんでも見えたから。
「巫哉」
そう言われて日紅を見た。
『彼』は、その瞬間、その身が凍ったように感じた。
日紅の目。
なにかー…なにか、違う?
日紅の瞳は静かだった。日紅の口が開く。『彼』は確かに恐怖を感じた。やめろ、言うな!それは直感だった。
クッションを抱えたまま日紅はぽつりと言った。
「巫哉、あたし犀が好きかもしれない」
「………………………………………」
『彼』は日紅の言葉を胸の内で反芻(はんすう)した。
日紅が、犀を、好き。
それは別に普通のことだろう。好きでなければ夜半にわざわざ自らの家に招いて人外のものと一緒に遊ぶなんて酔狂な真似をするはずがない。
けれど、日紅が言った「すき」には違う意味があるのだろう。でなければ、今更「かも」なんて曖昧な言葉は使うまい。
「そうか」
『彼』は早口でそう言った。自分が今どのような顔をしているのか想像するのを恐ろしいと思った。
その表情と考えていることが、必ずしも連動するわけではない。『彼』は表情を表に出す必要がない。本来、ヒトがそうするのは周りに自分とは違う他人がいることが前提であり、それはコミュニケーションのツールに他ならない。ただ、『彼』は違う。もともと、他の生き物との交流を図らなくてもいい身であった『彼』はまず、自らにヒトの言う心に近いものがあったのも驚きであった。
日紅と出逢って、ヒトと限りなく近く振舞うようになった。
日紅に異形の者として怖がられるのではないかという恐れから。
それに、慣れすぎたのか。
自らの面の皮一枚思うがままにならぬとは。
共に笑い、怒った。地に足をつけて歩くことを覚えた。触れた血肉の通う肌は温かいということを知った。
日紅に逢ってから、『彼』はいろいろな感情を学んだ。それは良いものだけでなく、『彼』から奪うものも多くあった。
「あたし、ずっと、ずっと、失うのが怖くて犀を傷つけていたの。ばかみたい。まだなんにもしてないのに、悪い結果だけ考えて、諦めてたの。おいしそうなケーキが目の前にあるとするでしょ?あれを食べたらおなかが痛くなるかもしれない、だから捨てようって。ずっとそう思ってたの。ホント、バカだよね」
日紅の目線はクッションを抱えている手元に降りていた。照れくさいのか足をもじもじと動かしながら一人で喋る。
「あ、あたしいきなりなんだよって話だよね!巫哉わけわかんないよね!ごめんね!あの、今日、犀にね、…好きだって言われたの。友達で、って意味じゃないよ!あたしも好き、って言ったら違うって怒られた。はぐらかすな、って。・・・あたし、わかってたんだ、きっと。犀があたしのこと好きでいてくれるってこと。でも、あたしが臆病すぎて、もしかしたらずっとこのまま楽しくやっていけるんじゃないかって、思ってたんだ。けどね考えるまでもなく、あたし、犀のこと好きみたい。まだ、戸惑いも大きいけど、あたしがバカで犀を傷つけてきた分」
日紅がふっと顔をあげて『彼』を見た。瞬間声が止まった。驚きで睫毛が震えた。
「みこ、や?」
茫然とその名を呼ぶと同時に『彼』の姿がふっと日紅の眼前から消えた。
今まで、『彼』が日紅の前でこんな風に掻き消えたことはなかった。
「巫哉?」
真っ暗な部屋の中、もう一度日紅はつぶやいた。
消える寸前、無表情の『彼』の右目からひとすじ涙が、流れていた。
『彼』とおまえとおれと2
犀(せい)は、本当のところ、日紅(ひべに)がどう出るか全く想像がつかなかった。
考えることは一つだけ。家に帰り母が自分を呼ぶ声にも気づかず、傍目には怒っているとも思われそうなしかめっ面で自分のベッドにどさりと倒れ込んだ。
そもそも、こんな急に気持ちを伝える予定ではなかったのだ。
犀は、日紅が考えていることはすべてわかっているつもりでいた。日紅がわかりやすいと言うことを差し引いても、伊達にずっと一緒にいるわけでもないし、ずっと見ていたわけでもない。
実は知り合う前から犀は日紅が好きだった。大勢の友達に囲まれて話をしていても、日紅が近くにいれば常に意識せずにいられなかった。話しかける切っ掛けになればとやけに大きな声でバカ笑いしてみたりもした。知り合うまでの一年間、犀はそんなささやかな主張をしていたのだが当然ながら日紅には全く伝わらなかった。
隣の席になってから、やっとおはようが言えるようになった。小学校5年生の春のことだ。そこからじりじりと距離を詰め、周りからも仲良くなってきたねと言われるようになったある日、犀は知ることになる。日紅の秘密を。
その瞬間を、犀は一生忘れることはないだろう。
日紅に真夜中に呼び出され、犀の気持ちは弾んでいた。親の目を盗んで家を出て、電灯の疎(まば)らな夜の道を走るのも十一歳の犀には冒険のようでその鼓動と足を速くさせた。
家の屋根にも隠れないのっぽさまが見えてくる。日紅の家に夜行くのは初めてだ。月明かりが紅潮した頬を照らす。はやく、はやくー…。青暗い闇夜の中、日紅の家だけが明るく光って見える気がした。
「せーくん!ここ、ここ!!」
のっぽ様の前で歩調を緩めた時、控え目な声がした。きょろきょろと見回すとのっぽさまの陰に日紅がいた。学校には決して着てこない日紅のやわらかいタオル地のワンピースを見て犀はとっさに目を背けた。ね、寝巻だ…。
「よかったぁ来てくれて。あのね、あのね、うわーなにからはなそうっ?えへへ」
「その俺にだけ話したいことって、なに?」
緊張を隠そうとついぶっきらぼうな口調になってしまう。それでも、犀にだけ、という言葉に心が震えた。自然と口元がゆるむ。
「みーこーやー」
「?日紅」
「あれ?巫哉ーみこやーみこやーみこやー」
「どうしたの?日紅?」
きょろきょろとあたりを見回しながらミコヤとしきりに言う日紅に犀は首をかしげた。
「巫哉!いじわるしないで。出てきて。お願い」
日紅が言い終わるとすっと日紅の後ろに影が差した。それは人だとは思うが陰になって姿は見えない。犀は知らず息を呑んだ。怖い。
足が逃げを打つ。だめだ。日紅がいる。あんなに近くに。危ない、日紅を残してはいけない!犀の中で恐怖よりも日紅を想う心が勝った。
震える足を叱咤してずかずかと日紅に近づくと驚く日紅の腕を掴んで自分の後ろに回した。もしかしたらそれは、全く意味のないことなのかもしれない。目の前に対峙するものは、全く得体が知れなくただ本能が怖い逃げろと告げてくるようなもの。犀がひとり日紅の盾になったぐらいではどうにもならない存在なのかもしれない。でもー…。犀は瞳を閉じて歯を食いしばった。どうか、神様。俺はいいから日紅を助けてくれ。お願いだ俺はどうなってもいいから!
「せーくん?どうしたの?」
場違いなのんびりした声が響く。日紅はこのとてつもないものに気づいていないのだろうか?だったら尚更犀が守ってやらなければ。
犀は覚悟を決めて相手をねめつけた。そして、驚きに声を失う。
風が吹いた。ざわざわと大木が枝を騒がせる。雲が晴れ、月光が一部の隙もないその男の顔を照らした。
犀より幾分か高い背、陶器のような肌、漆黒の髪、つりあがった眦(まなじり)。その瞳も漆黒だ。燃えるような苛烈な視線で犀を射抜いている。
月夜見命(ツクヨミノミコト)。犀は確信した。こいつは夜の神だ。
きっと、日紅を連れに来たんだ。
「巫哉!」
日紅が嬉しそうに言った。なんと、男に向かっていこうとするではないか!
「日紅!だめだ!」
犀は自分を通り過ぎようとした日紅を後ろから抱きしめた。必死だった。日紅が連れて行かれてしまう。犀の頭にあるのはそれだけだった。
「いっちゃだめだ!」
「日紅」
『彼』がはじめて口を開いた。犀はぞわっと鳥肌が立った。と思ったら腕の中から日紅が消えていた。目の前に『彼』がいた。一瞬のうちにこんなに近くまで来れるなんてやっぱりこいつは月夜見命だ!
「やめろ、日紅を離せえ!」
犀が必死でその足に蹴りを入れたり殴ったりしていたら上からため息が聞こえた。と同時に腕を掴まれてほおリ投げられた。あ、と思った時には地面に落ちていた。強かに手の平と腹をぶつけて涙が滲んだ。
「せーくん!巫哉!やめてなんでこんなことするの!せーくん!」
『彼』に抱えあげられた日紅はその腕から逃れようともがいた。犀に手を伸ばす日紅に『彼』はしれっと言った。
「先に手ェだしてきたのはあのクソ餓鬼だ」
「だからって巫哉のほうが背も高いし力も強いし年上だしなんでいつもそんなにおとなげないの!巫哉のばかぁ!せっかくあたしが巫哉は一緒に遊んでくれる友達もいないし紹介してあげようって思って連れてきたのに!ふたりとも仲良くしてほしかったのに!ばか、もう、きらいっきらいきらいきらい離せばかーーーーっ」
日紅は『彼』を抓ったり引っ張ったり暴れながらえぐえぐと泣きだした。それでも『彼』は手を離さなかった。
そうして、犀の腫れた手首と青痣になった腹とともに、最悪な初対面は過ぎたのである。
『彼』とおまえとおれと3
『彼』のことは好きじゃない。
人格のことだけで言ったら、別に好きでも嫌いでもない。
ただひとつ、犀(せい)には譲れないものがあって、それはきっと、『彼』も同じように譲れないのだろうと思う。
それを半分にもできないし、他の誰かに渡すなんて絶対に考えられない。
だからと犀は思う。眠れない夜。次の日の朝の日紅の答えをいくつも想像しながら。
だから月夜(つくよ)、お前には渡さない。
「おはよ」
日紅(ひべに)が犀の肩をぽんと叩いた。犀は考え事をしていたので驚き、声をかけたのが日紅だと確認すると胸をなでおろした。
「驚かせるなよ。おはよう」
「ん?別に大きい声出してなくない?いこっ」
犀と日紅は並んで歩きだす。いつもの光景だ。
ただ、今日は昨日までと違う筈だ。昨日、犀は日紅に積年の気持ちを伝えたのだ。日紅は犀の気持ち、自分の気持ちと向き合わされてさぞ混乱しているに違いないと犀は思っていた。
こうして一時間以上前からいつもの待ち合わせ場所で待っていたのも、正直混乱した日紅に無視されるのを恐れていたから。なのに。
犀の頭の中は疑問でいっぱいだ。日紅が至って普通の態度なのもわからない。緊張している様子もない。どういうことだ?日紅と下らない会話をしている間も頭の中はぐるぐるといろいろなことを考えてしまう。会話の内容は犀の頭をどんどん通り過ぎていく。
そして、犀は一つの考えに辿りついて固まった。
今まで考えもしなかったけれど。まさか、日紅は犀の告白をなかったことにするつもりではないだろうか。それなら態度が変わらないのも頷ける。今まで犀が考えていたのは日紅が犀のことを意識して今までのように接してくれなくなること、断られた時のこと、それだけだった。
かっと頭に血が上ってそれと同時に胸に痛みが走る。
犀だって、簡単に日紅に好きと告げたわけではない。言った後のこともずっと、ずっと沢山悩んで考えてきた。八年間の片思いだ。大きな意味が詰まった告白だった。
日紅が恋に関して幼い考えなのはわかっている。でもその無邪気さが、わかってはいても、犀の心を傷つけた。
犀の足が意識せず止まる。
「犀?」
訝(いぶか)しんだ様に日紅が立ち止まるのをぼんやりと認識して、犀は自分が立ち竦んでいたことを知った。
「なに、どうしたの?」
にこりと笑って犀の顔を覗き込む日紅が憎かった。ここで犀が日紅に詰め寄ったらどうなるだろう。好きという気持ちは綺麗なだけのものじゃないことを犀は知っている。そのどろどろしたものを今ここで日紅にぶつけたらどうなるだろう。日紅の泣き顔ですら自分のものにしたいと言ったら、日紅はどうするだろう。
その一方で、今犀の態度がおかしくなったら日紅が困惑するだろうとも考えていた。だけどもう犀は笑えなかった。
「犀」
犀がおかしいことに気付いた日紅の手がそっと犀の手を握った。犀は日紅の考えが読めなくて目線をあげた。目の前に、視線を伏せた日紅がいた。困ってるような顔。それを見た途端、犀は思った。もう、だめかもしれない。日紅は犀に何かを言おうとしている。その瞳を伏せたままで。
「犀、ごめんね」
犀は目の前が暗くなった。恋についてまだ何もわかっていない日紅に答えを出せというのは無理かもしれないと、犀は半分断られるかもしれないと覚悟していた。だが、予想はしていてもやっぱり堪えた。
しかし、日紅はさらに言葉をつづけた。
「ほんとに、ごめん!なんか、昨日から考えてて、あたしのなかではもう決まってて、だからなんか犀もわかってるって気でいつもどおりにしてたけど良く考えたらあたしなんにも言ってなかったよね!?だから、えっと…」
日紅はそこで顔をあげた。ちらりと犀を見てまた視線を落とす。その頬は真っ赤に染まっていた。
「こ、れからよろしくお願いします」
『彼』とおまえとおれと4
「ほんっっっっっ………とうに、おまえは紛らわしい!」
「だから、ごめんって!謝ってるじゃんか!犀のばか!心狭い!」
「狭くない!あーくそ、ドキドキした分を返してくれ~…死ぬかと思った…」
「大げさな」
「大げさじゃない」
「…ばか」
「でもそんなバカが好きってことでアーユーオッケ~~?」
「意味わかんないっ!」
「わかるだろ。答えろよ」
「………………」
「日紅(ひべに)。俺だっておまえのこと全部が全部わかってるわけじゃない。言葉で言わなきゃ伝わらないものもある。俺は、お前の口から、ちゃんと聞きたいから」
「………………………せいのことが、すき」
「ハイ、よくできました~」
「あっ!やめてよ!せっかくおだんごがんばったんだから!崩さないで!」
「ははっ、今俺空飛べる!」
「何言ってんの、バカ…」
「いや、嘘じゃない。今ならマジで何でもできそうな気がする。あ~俺今マジで幸せ~」
「はいはい。じゃあ帰りは飛んで帰ろうね」
「先に帰るなよー今日どこか寄って帰ろう」
「そーだな~~モンブランとーシュークリーム!」
「謹んでおごらせて頂きます女王様」
「当然よ!おーっほっほっほ…って何やらせるのよ!」
「いって!俺のせいじゃないだろ?」
「犀のせい!」
「うおおなんかいきなり寒く…?」
「ギャグで言ったんじゃないわ!」
「…?あ!やっべ予鈴だ!日紅走るぞ!」
「待って!こないだみたいな全力疾走はもうしないからね!?あたしあれでひどい目にあったんだから!男と女のリーチ考えてね!」
「それは…悪かった!それも含めて今日おごるわ。急ぐぞ!」
顔を見合わせて走っていく、犀と日紅の手はしっかりと繋がれていた。
だん!と犀は机に手のひらを叩きつけた。
机の持ち主は、ゆっくりと目を落としていた参考書から顔をあげる。
「青山」
犀の声が教室のささやかな喧騒のなか低く響く。
「こういうことだから、諦めてもらうぞ」
犀の腕の中には、顔を真っ赤に火照らせた日紅がもがいていた。
それを見て、青山はにこっと完璧な笑顔で言った。
「嫌がってるよ?」
「嫌がってない!」
日紅ではなく犀がむすりとした顔で言い返す。
日紅はなるべく教室や人前では付き合うことになったと言えど態度を変えたくないのに、犀が青山の前で日紅を抱き込むから恥ずかしくて青山の目も見れない。
「山下さん」
青山が日紅を見た。今日もきらきらしている。日紅はいまだに信じられないのだ。この学校のプリンス青山が日紅のことを好きだなんて。第一何にも確かなことを言われていないのに犀がこうして青山のところに来ているのも勘違いだったらと思うと輪をかけて恥ずかしい。
「山下さんは木下の事をどう思ってるの?」
日紅は覚悟を決めた。もし本当に青山が日紅を想っていてくれているのであれば、曖昧な態度は青山に対して失礼だ。日紅の勘違いだったら日紅一人が笑われるだけで済む話だ。
「青山くん。あたし、犀が好きなの。今でも青山くんがあたしのことを?好き?だなんて信じられないけど、犀と付き合うことになったから、ごめんなさい」
「というわけだ」
犀が日紅と青山の間に割って入った。
「まぁ、やっと二人が付きあったってことでとりあえず、おめでとう、かな」
やっと?って何。と日紅が思った時、犀が低い声で言った。
「青山。俺はこいつのことが本当に好きだから、軽い気持ちで手を出しているんなら辞めてくれ」
青山はそれにはにこっと笑うだけで答えなかった。
暫(しばら)く青山と犀は無言の攻防をしていたが、犀がふいっと顔をそらして日紅の腕をとった。
「戻ろう。日紅」
「あ、うん」
日紅は青山を気にしながら犀に腕を引かれるまま続こうとした。
「木下さん」
日紅に青山が声をかけた。
犀に引っぱられながらも日紅は振り返った。
「僕の名前も、清(せい)って言うんだ。これから名前で呼んでよ、日紅」
青山清は、にっこりと完璧な笑顔で微笑んだ。
『彼』とおまえとおれと5
青山の席から離れた二人をクラスメイトがわっと取り囲んだ。
「木下!おまえついにやったじゃん!」
「遅ぇよやっと言えたのかよ~お前何年かかってんだよ!」
「いつくっつくかって俺らマジでやきもきしてたんだからな?」
「おまえマジでおごれよ!」
「おめでとう!ほんともー二人ともじれったいんだからぁ~」
ぽかんとしてついていけない日紅(ひべに)をよそに犀(せい)はもみくちゃにされてあちこち殴られたり叩かれたりしている。
青山が『やっとくっついた』と言うわけである。日紅に焦れた段々大胆になっていく犀の行動は誰の目にも明らかだったようだ。
「やめろって!日紅が驚くだろうが!散れ!」
「うわ、こいつ彼女できた途端威張り散らしやがって!」
「敵だ敵!女紹介しろ!」
「日紅ちゃん見てよこの俺様。こんなやつやめて俺にしない?」
「は?ぶっとばすぞ」
「そうだよーやっと片思いが実ったんだからみんなで祝ってあげなきゃ」
人垣の向こう、教室のドアごしに誰かが輪に入るわけでもなくこっちを見ていた。
「…あ」
日紅ははっとした。
日紅と目があったと思った途端にその人は踵を返す。
クラスメイトにいじられているのは主に犀だ。日紅は人をかき分けてその人影を負った。
「待って」
教室を出て見回す。いた。階段を降りようとしている女の子に日紅は駆け寄った。
「待って、桜ちゃん」
桜は振り返った。まるで日紅が追いかけてくるのが最初からわかっていたかのように。
「桜ちゃん。あたし」
「木下君の事好きなの?」
淡く微笑む桜は視線を日紅に合わせたまま言った。
犀のこと。
本当のところ、日紅は自分の好きが犀の好きと同じではないとわかっていた。
つい先日まで、友情の好きも、愛情の好きも、なにも見ようとしなかった日紅だから、まだ愛情の大きさとかそんなことなんて何にもわからない。胸を張って犀の事が恋愛の意味で好きかと言われれば戸惑ってしまうだろう。
「好き」
でもその言葉はすんなりと日紅の口から出てきた。
あまりにも当たり前のように出てきたので日紅の方が少し驚く。それからその言葉はゆっくりと日紅の心に染みた。
うん。そうだ。あたしは犀が好き。その隣にあたし以外の女の子がいて欲しくないと思うくらいには犀の事が好きなんだ。
「そっか。あーあ」
桜がにこっと笑って言った。
「残念だなぁ。なんか木下君は日紅ちゃんの事好きなのはバレバレだったから、日紅ちゃんが気付かなきゃどうにかなると思ったんだけどなー。牽制(けんせい)かけたのが、徒(あだ)になっちゃったな~あはは、は…」
桜のその瞳からぽろりと涙がこぼれた。
「さく」
「謝らないで!…絶対謝らないで。わたしを惨(みじ)めにさせないで。謝ることない。日紅ちゃんは、誰かに謝らなきゃいけないような気持ちで木下くんと付き合った訳じゃないでしょ?じゃあ謝らないで」
ぼろぼろと涙をこぼす桜を日紅はそっと抱き寄せた。
言葉にしていないのに、どうして言おうとしたことがわかったのか。
桜ちゃん。
うん。あたしは誰かに謝るようなそんな気持ちで犀と付き合おうと思ったわけじゃない。友達がら一歩踏み出す覚悟を決めたのは日紅自身だ。
犀は本当に優しくて、他人の事を想いやれるいい男だから、日紅よりももっとずっといい人なんて沢山いるんだろう。でも日紅だって離れたくない。犀と一緒にいたい。これから先もずっと。
多分、きっと、こうして泣いているのは桜だけじゃないだろう。今までも、この先も、こうして日紅は心を痛めて泣く女の子たちに何もしてやれない。犀の隣を譲ることなくそんなことを考えるのは高慢だろうか。
日紅も桜と一緒に泣いていた。
悲しまないで。
『彼』とおまえとおれと6
「日紅(ひべに)。日紅の夢はなぁに?」
今にも眠りそうな微睡(まどろ)みの中、声が響く。
「ずっと一緒にいること」
日紅は毛布に顔を埋めながら答えた。
母親の膝の上、小学校6年生になったばかりとはいえまだ幼い日紅は甘えるようにきゅっと抱きつく。
「あらあら。それはママとかしら?」
「ママもだけど、あたし、せーくんと巫哉と一緒にいたい」
「本当に仲がいいわね、あなた達。今度はミコヤくんも連れてきてね?話はたくさん出るけど私一回も会ったことないんだからね、日紅」
「ん…巫哉がいいって言ったらね」
「そうね。日紅のお婿さん候補だから絶対連れてきてね。ママおめかしして待ってるから。でも犀くん以上に日紅のこと想ってくれてるかしらね~?」
「巫哉は優しいよ。日紅がなくしたもの持ってきてくれたり、泣いてるときれいな所に連れて行ってくれたりするもん。意地悪だけど…」
「ふふ。日紅には二人もナイトがついているのね。幸せ者ねー日紅」
「うん二人とも大好き!あたし、大きくなったらおっきーい家を買うの。そこで、三人で一緒に暮らすの。美味しいもの食べて、いっぱい一緒にあそんで、ちゃんとお店屋さんもするの。お花屋さんもやって、おっきくなるまでずーっと一緒で、おっきくなってからもずーっと一緒なの」
「ずーっと一緒なの?」
「うん!死んじゃう時までずっと一緒にいるの。巫哉は長生きだから、巫哉にあたしとせーくんのお墓をつくってもらうの。それで幽霊になって出てきて時々遊ぶの」
「それが日紅の夢?」
「うん…」
日紅の母親は日紅のふわふわの癖っ毛を優しく撫でつけた。
「きっと叶うわ」
ケーキ屋に寄った帰り道、日紅と犀はもう大分暗くなっている公園に寄った。
「犀さま御馳走様でした」
ブランコに座った日紅が、同じように横の滑り台のスロープに座った犀に手をあわせる。
「いえいえ日紅さんの胸に肥料を与えたと思えば安いものです」
「せ~い~く~ん~?」
「あ、それともお腹かな?」
「こらっ!」
日紅は足元の砂を掴むと犀目掛けて投げつけた。
「おわっ!ペッ!口に入っただろ!すぐ手が出る癖やめろよなー」
犀は立ちあがって口を拭うと日紅に歩み寄ってその頭を軽く小突いた。
「痛!脳震蘯(のうしんとう)だわ慰謝料」
「今のはただのスキンシップです~」
カシャンとブランコが軋んだ。日紅はブランコごと犀に抱きしめられていた。日紅は赤くなった。
「慰謝料とられるんならこれくらいじゃまだ甘いか?ん?」
「…参りました」
に、と犀は笑った。どうやら日紅だけではなく犀も少し照れているようだった。耳が少し赤くなっている。
「日紅」
「なぁに?」
「月夜(つくよ)とあんまり仲良くすんなよ」
「やだ」
「やだ、っておまえなぁ…つーか即答かよ」
「やなものはヤ。大体理由がわからない」
「…日紅さん。質問です。あなたは誰の彼女ですか?」
「木下犀さんです」
「正解です。その木下犀くんはやきもち焼き~です。だから彼女の山下日紅さんに他の男と仲良くしてほしくないそうです」
「…ってあははやだ犀、巫哉だよ!?巫哉にまで嫉妬するの?もう家族なのに!弟みたいなもんだし」
「その爆笑で日紅にとって月夜が対象外だってのは十分わかったが、まぁ俺もつい昨日までは同じこと言われてただろうし、おまえがそうでも月夜の方はどうかわからないだろ?」
「巫哉なんてもっとあたしのこと対象外だって!だって考えても見てよ!巫哉あんなちっちゃいのに4000年は生きてるお爺ちゃんなんだよ?ありえないよー。それに見た目中学生だし。あたしが手を出したら犯罪よ~」
「…」
犀ははぁとため息をついた。
「とりあえずあんまりべたべた触んなよ」
「はーい」
『彼』とおまえとおれと7
「じゃあ、またね」
「おう。また明日な」
にこっと笑って犀(せい)は言った。日紅(ひべに)の家の前。また明日と言っても犀は日紅の手を離そうとしない。
「犀?」
何か言いたいことがあるのかと日紅が少し戸惑った声で返す。
「日紅。俺、おまえのことマジで好き。大事にしてやりたい。ずっと一緒にいたい。俺が守ってやりたい。全部全部俺のものだったらいいと思ってる」
「な…ん………ぁ」
日紅は犀にまっすぐ見つめられて思わず顔を逸らした。顔に段々と熱が篭(こも)る。
「そ…う言うことは直接本人に言わないでください」
「ははっ。直接本人に言わないで誰に言うんだよ。ほら、こっち向けって」
犀は日紅の熱くなった頬に手をあてて自分の方に向けた。日紅の視線が居心地悪そうに彷徨(さまよ)う。
「せい…」
「ん、なに…?」
犀が日紅に一歩近づく。犀の顔が目と鼻の先にあって、日紅の声が自然と囁き声になる。犀の掠(かす)れた声が日紅を包む。
「ち、か、くない?」
思わず顔を押しのけようと日紅が目の前の顎に触れたその指を、犀の手が掴んだ。
犀の眼差しが燃えるように日紅を射る。
犀の顔がすっと近づいた。
あ…キス…。
日紅はぎゅっと目を閉じた。日紅の気持ちは、まだ犀とキスしたいとか、そこまでの感情になっていたわけではない。日紅は一緒にいるただそれだけで満足だけれども、犀と日紅自身の気持ちにずれがあるということもわかっている。だから、犀の気持ちは、できる限り大切にしたい。
「ーーーー………」
一瞬の空白が開いた。息がかかる距離にいる犀の顔はそれ以上動かない。
もしかして、あたし、勘違いした!?日紅が先走って瞳を閉じたから、犀は戸惑っているのかもしれないと考えたら羞恥で顔がカッと熱くなった。日紅は慌てて目を開けようとした。その瞳が開く前に犀が動いた。
日紅の髪がふわりと犀の頬に当たる。日紅は犀の熱を全身で感じた。犀の腕が日紅を締め付ける。日紅は犀に抱きしめられていた。強く。
「犀」
「無理、しなくていいから」
ぼそりと日紅の耳元で犀が言う。
「おまえにそんな顔させたかったわけじゃない。ごめん」
日紅の胸がずきりと痛んだ。謝らなくていいのに。犀は優しすぎる。自分よりも、いつも日紅を優先してくれる。それは犀の優しさで、日紅は嬉しいと思う反面どこかじれったい。
もっと、日紅に頼ってくれればいいのに。この先、犀は辛いことや苦しいことがあっても日紅には全くそんな顔を見せず笑って隠そうとするのだろう。守られているだけなんて、日紅はそんなことを望んでいるわけじゃないのに。
犀が日紅の事を大事にしていてくれているのと同じように日紅も犀を大事にしたいと思っているのに。たとえそれで傷つくことになってもいいのに。
犀ひとりで背負わないで。
日紅は口を開いたが、言葉は出てこなかった。かわりに左目からひとすじ涙が流れた。日紅を胸に抱きしめていた犀はそれに気付かなかった。
日紅は否定の代わりに犀に顔を押しつけて首を振った。
「俺、ちょっと嬉しすぎて、てかおまえが…可愛すぎてちょっと突っ走りすぎたわ」
「はい、そこまで~」
突然間延びした声が二人に割り込んだ。
犀がぱっと顔をあげる。日紅は聞こえてきた声にさっと赤くなった。
そういえば、すっかり忘れていたけれど、ここは…!!
「家の前でいちゃつかないでくれるかな~?ホレ、犀くん、送りオオカミになるには我が家にはまだ父も母もわたしもいますので一人暮らしをしてからにしてくださいね~?父さんもう少しで帰ってくるしね。そんな熱烈な歓迎したら血圧あがって倒れちゃうわよ」
「あ、あああああの、はいっ!」
二人は慌てて離れた。どこから見られていたんだろう、と考えるとますます顔が赤くなってくるのだった。
『彼』とおまえとおれと8
「じゃ、犀(せい)っ!また明日ね!」
「おうっまたな!」
裏返った声と一緒に慌てながら帰る犀を見送っていると、日紅(ひべに)の肩にぽんと手が置かれた。
「……お姉ちゃん」
日紅の赤い顔を見て、姉は鬼の首をとったようににたりと笑った。
「ふーん?ほーついにそういうことになりましたか。いつからなの?」
「今日だよっ!もうっ!」
日紅は姉の手を振り払ってずかずかと玄関に向かった。
「やっと犀くんの苦労が報われたわね。わたしあんたが恋愛なんて一切興味ありませんってぽけっとした顔でいるからぱっと出の変な男に引っ掛かったらどうしようって思ってたんだからね。そんなことになったらけなげな犀くんが不憫で不憫で…杞憂(きゆう)で終わってよかったわー」
日紅はぴたりと足をとめた。
クラスメイトといい、姉といい。
「…何でみんな知ってるの?」
「ん?犀くんがあんたを好きだってこと?そんなの、見てりゃわかるわよ」
「わかんないよ!」
「そもそも仲いい友達だなんて浮かれてんのはあんたぐらいだっつーの。いーい?夢見てるお子ちゃまな歳でもないんだから、男女の友情は一生だなんて思ってたら痛い目あうわよ」
「もうお姉ちゃんうるさい!」
「はれて犀くんと付き合うことになったんだから、あんたミコヤくんのことはどうするの?」
「犀の話でしょ?なんで巫哉が出てくるの。どうもしないよ。いつもどおり」
「だっかっら、あんたはおこちゃまだって言うの、よ!」
「痛い!」
姉はばしんと日紅のおでこを叩いた。
「男女の友情なんてもんはね、成り立たないようにできてんのよ。男と女ってどうがんばっても違うものだから、意識しちゃうの。成り立っているように見えてるのは、どっちかが気持ちを隠しているからよ」
「極論だよ!」
「一般論よ。現に、あんたがずっと友達としてうまくいってるって思っていた犀くんも、あんたのこと女として見てたじゃない」
日紅はぐっと言葉に詰まった。それは、つい先日まで日紅がずっと心の奥底で意識しないようにしていたことだった。
日紅はそこから踏み出す覚悟をしたけれども。
男女の友情が成立しないだなんて、それがこの世のもう定められてしまった条理だとしたらそんなの…悲しすぎる。
「ミコヤくんには犀くんと付き合うってもうそのこと言ったの?」
「付き合うとはいってないけど、巫哉には何でも話してるから…それっぽいことは言った…」
はーと姉はため息をついた。
「いい?ちゃんと、あんたの口から言いなさいよ?それが誠意ってやつなんだから」
「お姉ちゃん巫哉は別にあたしの事なんとも思ってないよ」
「うるさい。いいから言う通りにしなさい」
むすりと黙った日紅を横目で見て、姉ははぁとまたため息をついて、その頭にぽんと手をおいた。
「まぁ、本人がなにも言ってないのにわたしがあれこれ言うことじゃないかもしれないけど。知らないってことが免罪符にならないこともあるし、日紅に後悔してほしくないからさ」
「…意味わかんない。……お姉ちゃんなんて、巫哉のことなんにも知らない癖に」
「そりゃあね。でも話聞いてる限り…ま、いっか。ほら、着替えてきな」
ぽんと日紅の背中を押して姉は台所に行ってしまった。
日紅はそのまま玄関で立ち尽くしていた。
ぐるぐると色々な思いが頭を回る。
お姉ちゃん。巫哉。桜ちゃん。犀。青山くん。
…巫哉。
巫哉にあいたい。巫哉にあってまたあの生意気そうな顔で、どうしたんだと、優しくって意地っ張りな巫哉にそう言ってもらったら、安心できる気がする。巫哉は日紅を裏切らない。巫哉だけは。
だって、『彼』は変わらないから。犀は常に前を向き進んでゆく。日紅だって変わる決心をした。でも、それに恐れや不安がないわけでは、決してない。変化は怖い。それに付随する終わりが怖い。始まりと終わりはひとつだ。切り離して考えられるものではない。だから日紅は恐れる。変化を。
だから日紅は求める。『彼』を。
会ったら、巫哉に抱きついて、慌てる顔を見て、それを指さして笑って。
日紅は2階に続く階段を駆け上がった。はやく、はやく。一瞬犀の顔がよぎったが、日紅の心にある大きな不安には勝てなかった。犀も、姉も、巫哉のことを気にするのがわからない。巫哉は日紅にとって男だとか女だとか、そんなもので区切れるものではないのだ。4000年以上を生きる人外のものという認識ですらない。巫哉は巫哉。たったひとり、日紅にとってかけがえのない相手なのだ。
勢いよく日紅は部屋の窓を開けた。
「巫哉!」
しかし窓の外に求める『彼』の姿はなかった。でも、日紅の声を聞けば出てきてくれるはずだ。
はやく会いたい。はやくー…日紅の気ばかり急(せ)ぐ。
暫く待った。
日紅はそこできょとんとした。巫哉がいない。そんなことはないはずだ。今まで、一度たりともそんなことはなかったのだから。
「巫哉?」
相も変わらず窓の外は薄暗闇を映している。
どこかに出かけているのかもしれない。ぱたんと寂しく窓を閉じて日紅はのそのそと制服を着替え始めた。
今、そばにいて欲しいのにな…。巫哉。
巫哉1
暗闇。見間違えようのない銀の髪。俯(うつむ)いている絹のような髪の向こうから苛烈な紅い瞳が刺すようにただ、こっちを見る。
「ーーーーーー!」
日紅(ひべに)は『彼』に向かって何かを言った。
自分でも何を言ったのか聞き取れなかった。
「おはよ」
「ん…おはよ」
「最近元気ねぇじゃん。どした?」
それは日紅(ひべに)と犀が付き合って1週間が過ぎてからの事。付き合ったその日から日を追うごとに日紅の元気はなくなり落ち込みは深くなっていた。
そんな日紅を見て、犀はやはり時期尚早(じきしょうそう)だったかと少し早まった自分を悔いた。自分が限界だったとはいえ、日紅の逃げ道をなくすように気持ちを押しつけて選択を迫ってしまった。もっと日紅に合わせてやることもできたのじゃないかと考えたが、どうやら原因はそれとは違うことらしい。
「……………みこ、やが…」
そう言った途端、堪え切れなかったかのように日紅の瞳から涙が溢れた。
犀は驚いて日紅を覆い隠すように抱きしめた。今は登校途中で、同じ学校の子や、出勤途中のサラリーマンなんかも通る。泣き顔を見られたくないのではないかと思ったのだ。
でも日紅は周りの事など目にははいっていない様子で、犀の制服を皺になるくらい強く握って嗚咽を漏らした。日紅の姿に犀は『彼』に怒りを感じた。なにがあったかは与(あずか)り知らぬところだが、日紅をこんなに泣かせやがって!次会ったら殴ってやる。決意も新たに犀は日紅の肩を抱いた。
「日紅、ちょっと座って行こうぜ?な」
日紅は無言で肯(うなず)いた。
犀は日紅をベンチに座らせ自らも横に座ると、日紅の涙を拭いながら落ち着くまで辛抱強く待った。
「…ごめん、ね。がっこ…」
しゃくりあげながら日紅が言う。
「謝んなって。毎日ゾンビみたいな顔色したお前に会うぐらいだったら遅刻ぐらい。あ、でも俺ハンカチは持ってないけど。次から常備しとくよ」
「ありがとう…」
日紅は笑うことなく瞳を伏せたまま頷(うなず)いた。
「で、どうした?月夜(つくよ)がおまえになんかしたのか?」
日紅は首を振った。
「犀。巫哉、いなくなっちゃった…」
小さな声で日紅は言ってまた涙を零した。
「なに?」
犀は耳を疑った。
「………それは、違うだろ」
犀は強く言った。確信があった。『彼』が日紅を置いて姿を消すことなどあろうはずがないのだ。
「あいつ、いつもなんかふらふらしてんじゃん。どっか出かけてんじゃないの?」
「あたしも最初はそうかも、って思ってたけど…だって変!もう一週間だもん。巫哉がいないなんておかしいよ。今までいなかったことなんてなかったんだもん」
日紅はばらばらと涙を零しながら駄々っ子のように首を振った。
「どうしよう…犀、どうしよう!?誘拐とか監禁だったら!今巫哉どうなってるの!?どこにいるの!?どうしよう助けに行ってあげなきゃ。も、もしもこのまま会えなくなったら」
「落ち着けって!月夜は絶対におまえを置いてどこかに行ったりしない。そうだろ?日紅」
言いながら、何で『彼』のことを自分の口からわざわざ日紅に伝えなければならないのかと、犀は『彼』に無性に腹が立った。
先に日紅に出会ったのは『彼』だということもわかっているし、その分のふたりの結びつきが強いのも悔しいが分かっている。けれど、事実だけじゃ我儘(わがまま)な感情は納得してくれない。
しかしこんな状態の日紅にその感情をぶつけるなんて大人げないことは絶対にするまいと、日紅に悟られないように犀は気持ちを落ち着かせる。
「………………」
日紅は俯いたまま、唇を震わせた。
日紅も、何の根拠もなく取り乱しているわけではない。『彼』を最後に見たとき、日紅の見間違えでさえなければ『彼』は…涙を流していた。ほんの一瞬だったし、最初はまさかそんなことあるわけないと気のせいだと思っていたのだが、その時から『彼』の姿が消えたことを思えば、もしかしたら本当に『彼』は泣いていたのかもしれない。
それを犀に伝えようか迷って、でも言葉にできずに日紅は別のことを口にする。
「犀。あたし、夢を見るの。まっ暗闇の中に一人で巫哉が座っていて、近くに行こうとするんだけど近づけなくて。巫哉の紅い目が、暗闇の中でもじっとこっち見てるのがわかって。巫哉はあたしのとこに近づけるんだけどあたしから来てほしいって思ってる。あたしを待ってる」
犀は日紅の髪を撫でながら頷いた。
その一方で思う。赤い目?なんじゃそりゃ。あいつが兎ってタマでもあるまいし。泣きすぎて目が赤いなんてオチか?
「日紅。どうして夢の中の月夜の目は赤かったんだ?」
落ち着かせるつもりでなんの気なしに犀は話を振った。
わからない、と返ってくる答えは予測できていた。だが。
それを聞いて、日紅はゆっくりと犀を見上げた。犀の質問を自分の中でゆっくり噛み砕いているようだ。
「夢の中じゃなくたって巫哉の目は紅いじゃない、犀」
ははっとそれを聞いて犀は笑った。一瞬後にはっとした。日紅はどうみても冗談を言っているような雰囲気はない。
「赤い?月夜の、目が?」
「…紅、よね?」
「いや、月夜は黒髪黒眼だろ?」
巫哉2
泣き腫らした目で、のろのろと日紅(ひべに)は着替えた。
『彼』がいなくなってからもう2週間が過ぎていた。
探そうにも手はなく、結局日紅は『彼』のことを心配しながらもいつもの日常を繰り返すしかないのだ。それがどうにももどかしくて、日紅は自分が嫌になる。
『彼』は日紅にとってとてもとても大事な人で、いなくなるなんて絶対に考えられない。
そのはずなのに、なぜ日紅は眠れて、ご飯も食べれて、こうしていつもと同じ時間にいつもと同じように制服を着て、学校に行っているのだろうか。頭の中はやるせなさと疑問でいっぱなのに、また今日もこうして友達に笑顔を向けている。笑える自分が信じられなかった。でも心と裏腹に顔は笑みを形どる。
『彼』のいない日常に、慣れてしまいたくなんてないのに。
たすけて、と日紅は時折心でつぶやいた。
誰に向かうでもなく、それはぽつりと日紅のお腹の奥に落ちる。
助けて欲しいのは、『彼』のほうかもしれない。日紅なんて、ただ『彼』の事を心配しているだけで、別に命の危険があるわけでもない。けれど胸は苦しく涙は枯れなかった。『彼』のいない窓を見るのが苦しかった。それに慣れてきてしまっている自分が憎かった。
巫哉(みこや)。
巫哉。
巫哉。
いま、どこにいるの?
『彼』がいなくなってちょうど3週が過ぎた夜、日紅は熱を出した。
うなされて、朦朧としながら見る夢は『彼』のことばかりだった。
犀(せい)と、日紅と、『彼』と3人で笑いあっていた中学校の頃。
転んだ日紅をよく抱き起してくれた幼稚園の頃。
月光の下(もと)で一際輝く白銀(しろがね)の髪。
生意気そうな釣り上った瞳。
ぶっきらぼうで、だけどその掌は他の誰よりも日紅のことを思ってくれていると知っていた。
いつだって、『彼』は日紅に優しかった。
『日紅』
日紅は薄く眼を開いた。
開けられたカーテンから月光が日紅の顔を照らす。
「待ってる」
言ったときは無意識だった。耳で聞いて、心で噛みしめたら、その言葉はすとんと胸に落ち着いた。
そうだ。『彼』は待っているのだ。日紅を。
布団から床に足をつけた。立ち上がるとふらりとよろけた。でも行かなければならないのだ。『彼』が日紅を待っているのなら。
熱に浮かされたせいか定かではない頭で、日紅はゆっくり歩き出した。
巫哉3
「待て」
日紅はそれが最初、空耳だと思った。
「ヒベニ、待て」
「痛!」
思わず日紅は呻いた。左耳をいきなり何かで挟まれたと思った直後、薄皮を剥がされたような痛みが走った。
足元がふらついて日紅はそのままその場に座り込んだ。
「止まれと言うに聞かぬお主が悪い」
後ろから声がして、蹲った日紅の目の前に草履をはいた足と黒い着物の裾(すそ)が見えた。
「しかしお主予想以上に旨いな。もう少し齧っても死なぬな?」
「え何いたいいたいいたい離して!」
がしっと日紅は目や鼻のあたりを押さえつけられて再び耳を固いもので挟まれた。そして強く耳を引っ張られた。いや引っ張られるなんて生易しいものではなく、引きちぎろうとされたと言うほうが正しい。
日紅はあまりの痛みに訳も分からず目の前のものを両手で突き飛ばした。離れるときに、ぬるりとしたものが耳を掠めた。
日紅は耳を手のひらで覆いながらきっと顔をあげた。そして言葉を失った。
目の前にいたのは、闇よりも深い色の着物を着た、目を疑うほどの美人だった。
左右対称の顔もさることながら、その無駄のない引き締まった体つきも芸術品のように美しい。動作の一つ一つが軌跡を描いているかのように秀美で端麗だ。
男形であることがまた壮絶な色香を漂わせている。
「なんだ。二つもあるのに一つぐらい寄越(よこ)してもいいだろうが」
目の前のものはぺろりと唇についた赤いものを舐めた。
あれは日紅の血だ。日紅の耳を食べて旨いだ何だのと言っているということは、間違いなく妖(あやかし)でしかも人食いの類いだ。ヒトに対して魅力的な外見はヒトを捕食しやすくするためのものだ。日紅は今になって夜中に外に出てきたことを後悔した。逃げなければ!
日紅は踵(きびす)を返した。しかし即座に腕を取られる。
「待てと言うに。あやつに会いに行くのではないのか?」
「…あやつ?」
思ったより真剣な声に、日紅は耳を両手で覆ったままそのものと向き合った。
「む。お主、体がどこか悪いのか」
「そんなこといいから。あやつって?」
日紅は相手の瞳を覗き込んだ。底が見えない暗い瞳。けれども今は怖いと思わなかった。その答えのほうが気になった。
「自らの名を持たぬものだ」
『彼』だ!
日紅は思わず叫びそうになった。
「ねぇ巫哉(みこや)はどこにいるの!?いまなにをしてるの!?なんで戻ってこないの?あたしのことが嫌いになっちゃったの?それとも怪我してるの?それで戻ってこれないとか?ねぇどうなってるの!?巫哉は無事なの?」
日紅は妖の襟元をつかんでぎゅっと握りしめた。その手は震えていた。
「ヒベニ、お主はあやつを選ばなかったのだろう」
「…なに、選ぶって」
「お前が選んだのは人間の小僧だろう。ならば戻るがいい。ヒトはヒトの中で生きるのが幸せだ」
日紅はカッとした。
どうしてみんな、選ぶの、選ばないのと言うのだろう。日紅は、ただ、ただ3人で一緒にいたいだけなのに!
誰かを選んだら誰かを選べないなんて、そんなことあるはずがない!
「巫哉には会う。それはあなたには関係ない!」
日紅は掴まれていた腕を強引に振り払った。
「ヒトはヒトの中で生きるのが幸せ?そんなの、誰が決めたのよ!あたしは、巫哉にあえて幸せだった。それは巫哉が妖だったからじゃない。巫哉が、巫哉だったからよ!妖だヒトだなんて、そんなので差別するなんて違う!あたしは、犀が人間じゃなくても好きだし、巫哉が人間でも好きよ!そんなことで、あたしの幸せを勝手に決めないで!」
日紅は溢れる涙を拭いもせずに叫んだ。
「お主の心には自由がある」
妖は、そんな日紅を嘲(あざけ)るでもなくそういった。
「だから、あやつを見つけることができたのかも知れぬな。だが、ヒベニ。生まれ持ったものは、抗えぬのだ。いくら嫌がろうとも、変えられぬものもある。そのことをわたしは言っているのだ。お主は純粋で美しい。それを失うのは惜しい。あやつのことは忘れるのだ。ヒトの理で生きろ」
「…あなたは、なぜ、そんなことをあたしに言うの?わざわざ…」
「ふん…。悠久の古より知る者のために、一つぐらい何かしてやるのも良いと思っただけだ」
「あなたは、巫哉のことがすきなのね」
「すき、か。人間の感情は分からん。だが、直(すぐ)な瞳を持つヒトよ。お主のことも失うには惜しいと思う」
「…巫哉のためじゃないの?あたしが巫哉に会いたいと思うのは巫哉のためにならないの?あなたが止めるってことは、そういうことなの?」
「そうだ」
「なぜ」
「わたしから言うことはできない。ただ、あやつの考えていることはわかる。会えばお主は必ず後悔する。あやつも同様だ」
「…………」
日紅はじっと黙った。日紅が『彼』に会うことは、果たしてお互いが後悔するようなことなのだろうか。しかしこの妖が悪意でこんなことを言っているとは考えられなかった。
日紅は迷った。後悔する事とはなんだろう。悪いことなのか、だとしたらそれは何なのか。
どうしたらいいのだろう。日紅は、一体どうすれば。
わからなくなって日紅は立ち尽くす。
『日紅』
はっ、とした。じわりと胸の奥が熱くなる。
呼んでいる。『彼』が。
そうだ。日紅を待っている。暗闇の中、たったひとりで。
「…行かなきゃ」
「これだけ言っても分からんか」
妖がやれやれとでも言うように、日紅に向かって手を伸ばした。
「あ!?う…」
日紅の喉に、一瞬で妖の陶器のような指が巻きつく。
「…は、…ぁ…」
ぎりりと締められて日紅は声も出せない。
「帰れ。何度も言うが、お主らのためだ。それとも足の一本でも千切れば大人しく諦めるか?」
言葉の通りに、日紅の喉を絞めていない方の腕で日紅の右腿をつかむ。じわりと強い力がかかり、多分指先が肉に食い込んでいるのだろうが、日紅は息がつまってそれすら認識できないほど朦朧としていた。
その脳裏では蹲る『彼』がぶれて瞬いていた。
…巫哉。
一瞬、日紅の意識は飛んだ。
気がつけば、日紅はぐらぐらと揺れる頭で、変わらず暗い道端にいた。
右肩がやけに熱く、なにか暖かい水で濡れているような気もする。
ず…ずる…と日紅の耳の近くで音がする。
その水を触った手を見て、日紅は焦点の合わない目のまま、口を開いた。
「ねぇ」
「…なんだ」
耳の横で囁くような声がする。
「なまえ、なんていうの」
「名?わたしのか?」
笑ったような気配がして、日紅の体がぐらりと揺れた。下腹部に固い腕を感じて、日紅は自分が妖に抱えられているとぼんやりと思った。
「聞いてどうする」
「聞きたい。ただ」
「ウロ」
またふっと一瞬日紅の意識が飛ぶ。
「あやつはそう呼んでいた」
すぐに焼けるように熱い首元と、ずるりという水音が意識を呼び戻す。
日紅は唇だけで笑みを作った。
虚(ウロ)。ひねくれている『彼』が言いそうな名だ。
「ウロ。あたしは帰らない」
水音が止まる。
「あたしを食べてもいい。でも帰らない。だって巫哉があたしを待ってるから。心配してくれてありがとう。あたしには妖の理はわからないから、あなたが何を心配しているかはわからない。でも、巫哉があたしを待っているのなら、あたしは行かなきゃならない」
「…ヒベニ。その、まっすぐな純粋さこそが、お主が大切に思うものを失うことになると、心得ておけ」
すっと日紅を抱える腕がなくなった。
そのままへたりと日紅は座り込んだ。
「行け。お主の為でなく、あやつのために。愚かなヒトよ」
巫哉4
肩から流れ出る血は止まったようだった。腕を伝う滴がない。
ずいぶん深く齧られたようだったのに、もしかしたらウロが何かしてくれたのかもしれない。
日紅(ひべに)はじんと痺れる頭で考えた。
齧ってみたり、その直後に治してみたり、本当に妖(あやかし)は気まぐれなものだ。
日紅を放したっきり、ウロの声がしなくなった。言いたいことを言って、満足していなくなったのかもしれない。それを確認するために首を巡らすことさえ億劫(おっくう)だと思う自分を日紅は自覚していた。
このままここで眠れたら、どんなに楽だろう。
でも『彼』に会えるまでは。
ぐっと日紅は膝に力を入れた。鉛の塊を引きずるように重かった。
どれくらいの時間をかけたのか、ようよう立ち上がって、一歩踏み出そうとして、日紅は前のめりに倒れた。
だめだ。動けない。今日紅は一体どこにいるのだろう。家に戻ろうにも戻れない。そもそも『彼』はどこにいるのかさえわかっていないのに。
自分の無力さにじわりと目尻が熱くなったが、日紅は必死にこらえた。
今泣きたくない。いま、こんなことで泣きたくない。だってまだ日紅は何もできていない。巫哉を探し当てることも、なにも。
「そのようになってまで行く必要があるのか」
ふいに声がした。ウロだ。もういなくなったと思っていた日紅は驚いた。では、日紅が無様に地面に這い蹲(つくば)る一部始終を見ていたのか。けれどそれに対して恥ずかしいだとか思う気持ちももはや薄れていた。日紅が思うのはひとつだけ。
ただ、巫哉のそばにいきたい。
「ヒトは面倒だ」
日紅はふわりと体が浮いた気がした。重力や、自分の体重といった日紅を地面に押しつけていたものがすべてなくなったかのような不思議な感覚だった。ウロの声は、すぐそばで聞こえた。
「喰うのは容易(たやす)いが、生かすのは面倒だ。ほんの少し、力を籠めただけで死ぬ。ヒベニ、永久(とわ)の命が欲しくはないか。そうすれば、あいつとも共にいることができる」
どうしてウロがそんなことを聞くのだろうと思いながら、日紅は迷わず首を振った。
「いらない。あたしは、すぐに傷ついて血を流すヒトでいい。あたしはあたしのまま、巫哉は巫哉のままでも一緒にいれるよ、ウロ」
「ふん」
ウロは鼻で嗤(わら)った。
日紅だって『彼』より短い命に狼狽(うろた)えないわけじゃない。
でも、ずっと一緒にいたいというのは多分、日紅のわがままなのだ。あの天邪鬼(あまのじゃく)な態度でも、『彼』に好かれているのは分かっている。少なくとも嫌われてはいないだろう。だけど、永くを生きる『彼』を日紅の生に縛り付けることはできないと思う。
日紅が命を終えた時、『彼』は確かに悲しんでくれるだろう。けれど、悠久を一緒に生きたいと思うには日紅はまだまだ役不足だ。『彼』の世界は日紅の知らない事も多くて、きっと日紅よりも大事に思う人が沢山いる筈だ。それをちょっと寂しいとも思うけれど、嬉しい気持ちの方が大きい。
『彼』の世界が日紅中心で回っているなんて自惚れたこと、考えるわけがない。
「ヒトはいつの世もかく愚かだ」
ウロが呟いたその言葉には、なぜか悲しみが混ざっている気が、した。
ああ、ウロは…。
日紅の体に重力がゆっくりと戻ってきた。頬に暖かい風を感じた。
ウロの気配が遠ざかる。今度こそ、去っていく。
「あなたは虚(ウロ)なんかじゃないよ」
だって、こんなにも優しいんだから…。
日紅は囁くようにそう言った。
暫(しばら)く静寂が下りた。りりり、と鈴を転がすような微かな虫の音を日紅の耳は拾った。
ゆっくりと目を開けて、その時初めて、日紅は長い間目を閉じていたことに気がついた。
手の下にじゃりっとした砂が刺さった。辺りを見渡すと、錆びれた遊具、滑り台…公園だ。どうやら日紅の家の近くにある公園に日紅はいるようだった。小さいころからよく遊びに来ていたところだ。
いつのまにか、こんなところまで来ていたのだろうか。ウロと話していた時、日紅は確かにアスファルトで舗装された道にいたと思っていたのに。
なんとなく、きょろきょろとあたりを見回して、日紅は息をのんだ。
日紅から十足余りも離れた先に、『彼』が、いた。
巫哉5
『彼』は、隣にある木の幹に手を当て、その背よりもはるか高い空を見上げていた。
「巫哉(みこや)…!」
日紅の瞳から涙が溢れた。
言いたいことはたくさんあった気がしたが、もはやなにも言葉にできず日紅はただ感情の赴くまま『彼』に駆け寄ろうとした。
「日紅(ひべに)」
けれど、静かな声が日紅の足を止めた。近づくことを許さない拒絶がその声にこめられているように思えた。
『彼』は相変わらず空を見上げ、日紅を見ようとしない。
凪いだ『彼』の気持ちと昂った日紅の気持ち、その感情のずれに日紅は戸惑う。
風がふたりの間をとうと吹き抜けた。『彼』の髪が風に弄(なぶ)られて千々に浮いた。
ふいに日紅は犀(せい)が『彼』の髪も瞳も黒いと言っていたのを思い出した。けれど目の前にいる『彼』はどう見ても白銀の髪だ。
「…犀が、巫哉の髪の色が黒いって、いってた」
『彼』に言いたいことは別にあると思ったが、日紅が口にしたのはそんな言葉だった。
「だろうな」
驚くかと思った『彼』は予想に反し淡々とそう言った。
「目も、黒だって」
「ああ。あいつの目も髪も黒いから」
『彼』の口元が歪んだ。まるで嘲笑(わら)っているようだった。
「あいつ、って犀のこと?今は、巫哉の話だよ?」
「そうだな」
日紅は困惑した。今まで、『彼』にこんな突き放されたような言い方なんてされたことはなかった。
「…あたしには、巫哉の髪も、目も、その…黒には見えないんだけど…」
「俺の色は見てるヤツの生来の色を映す」
日紅は一瞬ぽかんと呆気にとられた。
今のは、一体どういう意味だろうか。
見ているヒトの生来の色を映す?犀は生まれつきの日本人で、髪も目も黒いから、『彼』の髪も目も黒く見える、ってこと?
つまり見てる人によって『彼』の髪も目も肌の色さえも違って見えると、そう言っているのだろうか。
「でもあたし、目紅くないし髪だってそんな綺麗な銀色じゃないよ…」
「それは」
日紅は心臓を鷲掴みにされたかのような錯覚を覚えた。『彼』がふいに日紅を見たのだ。
紅い瞳のなかに日紅が映る。
「俺の色だからだ」
『彼』はすっと日紅に向かって歩いてきた。
日紅はなぜか後ずさった。
「巫哉」
日紅はどくどくと鳴る心臓を押さえながら言った。
「なに、考えてるの…?」
『彼』は日紅の2歩手前で立ち止まった。
今まで日紅はただの一回も『彼』のことを怖いなどと思ったことはなかった。
口がいくら悪くても、態度がそっけなくても、日紅のことを大事に思ってくれているのが分かっていたから。
けれど、今、『彼』が怖い。いや、恐ろしいのは『彼』のことだけだろうか。日紅の気付いていないところで何かが起こっているのではないだろうか。
『彼』も、犀も。日紅が立ち止まっているうちにどれだけ遠くにいってしまったのか。
目の前で『彼』が顔を顰(しか)めた。
「会ったのか」
「え?」
「あいつ」
『彼』は苛立たしげに日紅の肩を指した。
「印つけやがって…ふざけんな」
「あ、えっと、ウロのこと?でもウロは巫哉の事心配してきたんだよ!傷口も治してくれたみたいだし、怒らないで!」
「だからおまえは甘いんだよ!妖(あやかし)をヒトと同じに見るなって何度言った!?首に虚(ウロ)の印が付いてる。それがどういうことかわかってんのか!」
「…どういう、ことなの」
「それは虚の食物って目印だ。それが付いている限り、おまえがどこにいても虚にはわかる。遅かれ早かれ喰い殺される」
日紅は咄嗟に首元を押さえた。押さえたところが一瞬カッと熱くなって冷えた。
「解いた。もう二度と会うな」
『彼』の声は確かに怒りがあった。自分に対してか、ウロに対してか、それとも、日紅に怒っているのか。
ウロが自分を食べようと目印をつけていたということを『彼』から聞かされても、日紅にはなぜかしっくりとこなかった。熱で頭が回らないのもあるのだろうが、日紅はどうしてもウロのことを怖いとは思えなかった。
それが、『彼』の言う甘いってことなのだろうが。
でも怒っている『彼』は日紅の知っている『彼』で、日紅は少し安心した。
「巫哉…かえってきて」
ぼんやりと日紅は呟いた。
そうだ。それが言いたかったのだ。
「どうして出ていっちゃったの?あたしのことが嫌いになったの…」
「嫌い…」
『彼』が日紅の言葉を反芻(はんすう)した。
「いつも言ってる。俺はおまえが大嫌いだ」
違う。日紅は思った。そんな表向きの言葉でごまかして欲しくないのに。
「あたしはすき」
結局いつもの応報になってしまうのを日紅は悔いた。だがこの言葉以外に日紅が『彼』へ向ける言葉はないのだ。
けれど、今回はいつもとは違った。『彼』はバカにしたように笑うでもなく、すっと無表情になった。
日紅は震えた。また『彼』が日紅の手の届かないところにいってしまいそうで。
「巫哉、言って!あたしにいやなところがあるなら言って!なおすから」
「犀のことが好きなんだな、日紅。何に代えてもいいぐらい」
日紅の質問とずれたことを『彼』は言う。
日紅は戸惑いながらも頷いた。
『彼』はそれを瞳に焼き付けた。『彼』の顔には何の表情も浮かんでいなかった。
「なら、俺の真名を思い出せ」
びゅうと強い風が吹いた。日紅は咄嗟に『彼』に抱きついた。『彼』がそのままどこかへ消えてしまいそうで。
『彼』の腕がほんの一瞬、日紅を抱きしめ返したような気がしたが、風がやんだ時には日紅は自分の部屋にいた。
うそ…。今までのは、全部夢?
茫然としていたが、日紅ははっとして肩を見た。寝巻の半身が暗闇に黒く塗れていた。夢じゃない!
『彼』は真名を思い出せと言っていた。思い出すということは、日紅が前に聞いているということ。
「思いだしたら、戻ってきてくれるの、巫哉…」
何も返さない夜闇に、そう日紅は呟いた。
巫哉6
今にも泣き出しそうな曇天に強く風が荒れていた。
下方に大きく広がるグラウンドは先日の雨がまだ乾いていないようで、空気もじっとりと重く水気を含んでいる。
学校の屋上で濡れた手すりに肘をかけながら日紅(ひべに)は考えていた。
『彼』の真名(まな)、それは何なのだろうか。
『彼』は日紅に思い出せと言った。では日紅が『彼』を呼ぶ巫哉というものが真名ではないのだろう。犀(せい)は『彼』のことを月夜(つくよ)と呼ぶが、犀自身も言っているようにそれは便宜上の問題で勝手につけた名のようだし、これもまた真名ではないだろう。
今まで日紅が会った妖(あやかし)も『彼』のことを太郎やら葉月やら梅やら好きに言っているが、どれもこれも『彼』の真名とは思えない。
いくら考えても、日紅は『彼』のことを巫哉としか呼んだことがなく、他の名前など一切浮かばなかった。
日紅は天を仰いで溜息を吐きだした。
手詰まりだった。いくら考えてもわからないものはわからないのだ。
一体どうすればいいのだろう。
もし、本当に『彼』の真名を知っている者がいるとするならば。たったひとりだけ、日紅には心当たりがあった。
「わたしの印を消されたな?お主を見つけるのに手間がかかってしまったぞ」
日紅はその声に大きく反応した。
「ウロ!どこ!?」
きょろきょろとあたりを見回したが漆黒の麗人の姿は見えない。
「いるんでしょ!?どこにいるの?」
「隣だ」
日紅は左右を見たが何も見えなかった。がらんとした広い屋上が広がっているだけだった。
ただし声はしっかりと日紅の左横から聞こえた。
「えーと…ウロ?」
「日の神が地を照らしている間、わたしはヒトの目には映らぬ」
「でも、いるんだよね!?ウロ!」
日紅は叫んだ。
「巫哉の真名を教えて!知ってるんでしょう!」
「知らぬ」
「だからはや、…え…?」
日紅は茫然と呟いた。
「嘘!知ってるんでしょ?意地悪しないで教えてよ!お願い!」
「何故わたしが嘘など言う必要がある。あいつの真名など知る必要もないから、知らぬ」
虚ははっきりと言った。
「…」
望みの綱も断たれてしまった。
もしや、『彼』はただ日紅と顔を合わせたくがないために真名を思い出せ、なんて無理難題を言ったのではないかという気さえしてくる。
「泣くな」
「ないてない。雨降ってきたんじゃない?」
「齧(かじ)るぞ」
どんな脅しだ、と思いつつも日紅は目尻をこすった。
ここのところ、情緒不安定なのか我ながらよく泣いていると日紅は思った。
犀は日紅を心配しつつも、『彼』のことで頭がいっぱいなのが不満なのか最近は少し怒っている。
日紅も犀には悪いとは思うのだが、『彼』のことをそのままになんてできない。
けれど犀はそのような様子で頼ることもできず、真名に辿り着く糸口すら見えず、日紅は途方に暮れていた。
「わたしは知らぬ。が、お主は知っているのではないか、ヒベニ」
日紅は首を振った。
「お主以外にあやつが教えると思えない」
「そんなことないよ…。あたしは、ウロにだったら巫哉は言ってるんだと思ってた」
こんなことを言い合っていても水掛け論にしかならない。日紅はため息をついた。結局、誰も知らないのか。
しかし虚は強く言った。
「いや、知っている筈だ」
日紅は黙り込んだ。
そうなのだろうか。日紅は知っている?『彼』の真名を。けれどどれだけ頭を絞ろうと思いだせなかった。
何かの拍子に思い出すかもしれないが、果たしてそれはいつになるのだろう。
タッと日紅の鼻先に滴が当たった。間をおかずそれは滝のような土砂降りになった。
「おい、ヒベニ。また身体を悪くするぞ」
「…うん」
虚にそう催促されたが日紅は動かなかった。水はすぐに制服の奥の奥にまで滲みた。
日紅は虚の声が聞こえる左をじっと見て、不意に拳を突き出した。
掌は空中の何かにぶつかって止まった。
「何をする」
「触れないと思った」
日紅はぱっと顔をあげて笑ったがそれはすぐに歪(いびつ)に歪んだ。
日紅はそれを隠すように勢いよく両腕を突き出して虚に抱きついた。
涙は空の滴と共に日紅の頬を伝い頤(おとがい)を流れた。
虚はきっと呆れた顔をしているか、無表情か。少なくとも驚いてはいる筈だ。けれど今日紅には虚以外に縋れる相手がいなかった。引き剥がされないように日紅は虚にまわした腕に強く力を込めた。
しかし予想に反して虚は動こうとしなければ喋りもしなかった。
暫(しばら)くしてから日紅は恐る恐る虚の顔があるはずのところを見上げた。
「気が済んだか」
やっと虚は口を開いた。
「うん…」
大雨は降ったときのようにあっというまに止んでいた。日紅が身じろぎするたびに足元の水たまりが耳触りのいい音を立てた。
遠くでチャイムの音が聞こえた。授業の始まる5分前を知らせる予鈴だ。
日紅は虚をもう一度ぎゅっと強く抱きしめた。
「ウロ!」
「なんだ」
「ありがとう!大好き!」
衒(てら)いなくそう言って、日紅はにこりとわらった。
「ウロ、あたしが死ぬときに身体をあげる」
日紅はすっと虚から離れた。
本人は否定するかもしれないが、虚は優しい。その優しさを日紅は一方的に受け取るだけだ。初めて会った時も、そして今日も。
虚に日紅がしてあげられることは何だろうと考えて、それしか思い浮かばなかった。
もともと日紅を食べようとしていた虚だ、わざわざ日紅から許可を出してもらわなくともいいかもしれないが、きっと虚はもう本気で日紅を食べる気はないと日紅は直感で思った。
「妖に向かって自らそのようなことを言うなど…愚かだ。ヒベニ」
「オロカでいいよ。でも今すぐはあげられない。あたし寿命が来るまで生きるつもりだから、その時まで待ってね」
我ながら都合がいい話かと思ったが、虚はなにも応えずに去ってしまった。
水滴が制服のスカートからぴちょんと垂れた。
『彼』は怒るだろう。たぶん、ものすごく。日紅が死んだあとに死体がないとわかったら家族や、犀は悲しむだろうか…。
日紅はそう思ったが後悔はしていなかった。
またチャイムが聞こえた。今度は本鈴だ。
日紅はいろいろな考えを振り切るように、滑る中履きを持て余しながら急いで階段を駆け降りた。
巫哉7
日の光もささず、時の流れもない感覚。自らを形どる体の感覚さえ忘れそうなどろりとした安寧と虚無を漂うことが、すなわち『彼』にとっては眠るということだった。
ヒトの形をとってその歴史を見守ることが『彼』にとっての起きていると同義ならば、この経てきた4000年は圧倒的に眠っていることが多かった。
その、ながいながい4000年の中の今より瞬きするようなほんの少し前、『彼』は日紅に見つかった。
そう、まさしく見つかったというのがしっくりくる出会いだった。
『彼』はその時眠っていた。いつものようにゆらゆらと波間を漂うような感覚に身を任せていたら、なんといきなり自分ではないものに鼻と呼ばれる部分を挟まれた。
『!?』
『彼』の意識は一瞬で覚醒した。
眠っている『彼』に触るなど、この世の何にもできる訳がないのだ。眠っている時は『彼』の実体も霞のように何にも見えないはずで…ましてや触るなどできようはずがない。けれど目を開けた『彼』は再び驚いた。
目の前で『彼』の鼻を掴んで目を丸くしているのはなんと、人間の幼子だった。格のある神ならまだしも、人間が意図的に姿を消し、しかも眠っている『彼』を見つけるとは!
さっと視たが、妖(あやかし)の類でも、物凄い霊力を持っているわけでも、守護霊の霊力(ちから)が強大というわけでもない。本当に、ただの人間の小娘だった。尚更解(なおさらげ)せない。何が起こった?『彼』は一瞬、自らがただのヒトに成り下がったような気さえした。
「ねんね?」
幼子はくりくりした目を動かして、拙(つたな)くそう言った。
寝ているのかと尋ねているのだろうということはわかったが、『彼』は返事ができなかった。
「ここねー、さむいよ。かぜ、ひいちゃうよ」
そう言うと幼子は鼻水をすする真似をした。
『風邪なんかひくかよ』
『彼』はようやくそう言ったが、自分でも間の抜けている返事だと思った。
しかし幼子はそれに対して何も反応しない。ただぱちぱちと目を瞬(しばた)かせながら見ているだけだ。
『つーかいい加減手離せくそガキ頭から喰うぞ』
そう言ってもやはり何の反応もなかった。手も離そうとしない。このくらいのヒトの子なら怯えて泣くものだが…そう考えた時にやっと『彼』は気がついた。声を出していなかった。ヒトは口から声を出し、顔の横についている耳というもので音を聞きとるのだった。
「―…あー…あ…声、これで聞こえるか?」
声が聞こえた途端、幼子は驚いてきょろきょろとあたりを見回した。
なにをやってるんだ、こいつは?
「おい?」
「よんだ?」
幼子は後ろを見ながら言った。本当になんだこいつは。『彼』には今まで、ヒトとの関わりがごく少ないと言えど何度かあった。それでもここまで理解できないヒトに会うのは初めてだった。何故目の前にいる『彼』と話をするのに後ろを見るのか。
「おい、どこ見てる。俺はてめぇのケツと話す趣味はねぇぞ」
『彼』は幼子の頭をがっしりと掴むと自分の方に向けさせた。
幼子は、じっと見詰めたまま、なんと今度は『彼』の上唇をぐいと掴んで引っ張った。
「この野郎…」
鼻と唇を引っ張られた間抜けな格好のまま、『彼』は唸った。
「おにーちゃんがいったの?でもこのくち、うごいてないよー?どうやってしゃべってるの?」
拳骨で幼子の頭を小突いて、『彼』は腕を払った。
声は聞こえるけれど、『彼』の口が動いていないと、だから他にヒトがいて自分を呼んでいるのだと思ったということらしい。そうだ、ヒトは言葉を発するのに唇を動かすのだった。『彼』は思った。久方ぶりに起きたせいで、ヒトに疑われないような擬態の仕方すらすっかり忘れているようだ。
いや、『彼』は起きたのではない。起こされたのだ。信じられないが、どうやらこの目の前のヒトの子供によって。
『彼』はじっと幼子を視た。しかしいくら視ても、なんの変哲もない普通の子供だ。
ただの偶然か。
そう結論付けて『彼』はまた眠ろうとした。偶然と片付けるにはどうも納得できなかったが、考えてもわからないものは仕方がない。ヒトはどんな不思議で不可解な事も納得させる言葉を持っている。偶然、いい言葉だ。眠ろう。
「ねーねー」
しかしそれを高い声が邪魔をする。
「何だ。まだいたのか。さっさとどっかいけ」
今度はきちんと唇を動かして『彼』は応えた。
言うか言わないかのうちに幼子はべたっと『彼』のお腹に抱きついた。
「何がしてぇんだてめぇは!」
「ひべにね、こうしててあげる」
「はぁ!?頼んでねぇよ!」
「そしたら、おにーちゃんさむくないよ」
幼子は『彼』の顔を覗き込んでにっこり笑った。
『彼』はもう幼子をほおっておくことにした。ヒトの子は飽きやすいものだ。そしたら勝手にどこかへいくだろう。
「おにーちゃん、あったかい?」
「あああったかいあったかい」
『彼』は適当に答えた。
「えへへ。ひべに、やくにたった?」
「たったたった」
「じゃあ、ありがとうございます、は?」
「は?」
「かんしゃしたら、ありがとうございますっていうんだよ!」
「……………。アリガトウゴザイマス」
「おにーちゃん!ちゃんときもちをこめていいましょう!ってせんせいにいわれるよ!」
ヒベニと言うらしい幼子は頬をぷくっと膨らませると『彼』の鼻先に人差し指を突き出した。
しかし勢いがありすぎてヒベニの指はそのままぶすりと『彼』の鼻の穴に入った。
「ぅおい!」
「ほら、もういっかい!」
「あ…ありがとうございます…」
鼻にヒベニの指を生やした間抜けな格好のまま、『彼』は言った。
「どういたしましてー」
ヒベニは満足したようににこにこと笑って言った。
それから引き抜いた指を汚いとばかりに『彼』に擦りつけている。
なんて餓鬼だ。図々しいにも程がある。大体人間同士でもいきなり初対面のヤツの鼻の穴に指を突きさすか?『彼』は唸(うな)った。そんな挨拶、聞いたこともないし見たこともない。
「あ、そういうことかー」
また唐突にヒベニは言った。どういうことだ、『彼』は思ったが十中八九、ろくでもないことなのは明らかだ。
「やましたひべにです!おにーちゃんのおなまえはなんですか」
名前?名前なんて…と頭に浮かぶうちに、ぼんやりと『彼』は自らの名を口にしていた。
それは、ヒベニの勢いに押されたからなのか。
はっとして口を噤(つぐ)んだときにはもう遅い。
…言ってしまった。ヒトの子ごときに…。自らの迂闊(うかつ)さに肝が冷えたが、しかしヒベニはこてんと首を傾げると言った。
「み、こ、や?」
『彼』は思わず笑った。よりにもよってそこを聞き取るとは。確かに『彼』の真名は人に比べるとかなり長く幼子なら全て覚えれずとも仕方ないが、たった三文字、しかもどこをどう切り貼りしたのか。
『彼』はそれで気が緩んだのか、もう一度、ゆっくり自らの真名を幼子に説いた。
どうしてその時、そんなことをしたのか、『彼』自身にもよくわからないのだ。一度目に呟いたのはうっかりだったが、二度目は『彼』の意思だ。
どうせこんな幼子には聞き取ることもできまいと思ったのか、それとも別の理由があるのかはわからないが、その時、『彼』がこの世に存在してこの方、誰にも知られず、一度も呼ばれることのなかった名を『彼』は確かにヒベニに教えた。
『彼』が予想していた通り、ヒベニは首を傾げたまま、もう一度言った。
「みこや」
「そうだ。俺の名はミコヤ、だ」
『彼』は言った。それから笑った。楽しい気分だった。ずっと『彼』の名を知る者などいなかったのに、それを妖(あやかし)でもなく、神でもなく、ヒトの子に伝えたということがなぜか物凄く面白いことのように感じたのだった。
「ヒベニ」
「なに?」
せっかく起きたのだ。延々と途方もなく長くを生きなければいけないこの身。目の前のヒトの、一生に関わるぐらいなら良い暇つぶしにはなるだろう。
それにこのガキの神経の図太さ、図々しさ、見ていて飽きない。どんな人間になるのかを見てやるのも一興。
「みこやびろ~ん」
ヒベニは『彼』の顔をもみくちゃにしながら好き勝手やっている。
「おい。喰うぞ!」
「えーやだーひべにおいしく…」
いきなりヒベニが黙った。じっと、『彼』の目を見ている。
「なんだよ」
「めのいろ、かわってきてる」
「目?」
『彼』ははっとした。
「なにから、なにに」
「くろ、から、えっと…ちゅーりっぷの、あか。きれい。あ!かみもだよ。かみもからすのくろから、しらが!」
「こんのくそガキ白髪じゃねぇよ!銀だ!ヒトと一緒にするな!」
「えーでもしろだもんしらがだもん。そういうんだよ。みこやおにーちゃんじゃなくておじーちゃんだったんだね」
とりあえずヒベニを小突いてから、『彼』は自らの髪に手を触れた。
「変わってきてるって言ったな。どれくらい変わってる?」
「はんぶんぐらい」
「半分…」
瞳の緋に、髪の銀。それは、誰も視ることのできない『彼』本来の色。
『彼』の真名を知ったからか。いや、正確には知ったのではなく、「聞いた」。だからこうして触れあっていても何も起きない。
『彼』はフンと鼻を鳴らした。名を知られたから、姿も偽れないのか。妖や神にとって真名は魂そのものだとはいえ、誰が決めたのか、よくできている。
「ぜんぶしらがになっちゃった」
「おまえ、俺が怖くねぇのか」
今更のように『彼』は聞いた。普通のヒトが瞬く間に髪や瞳の色が変化することなど、あるわけがないのだ。しかも目の色は血のような赤。髪も一遍の曇りもない銀だ。ヒベニは白髪と言ったが、ヒトのそれとは明らかに違うはずである。
「みこやのこと、ひべにすきだよ」
「はァ!?」
怖くないかと聞いたのに、何故好きだなんて発言になるのか。つくづくヒベニの思考回路にはついていけないと『彼』は思った。
大体、すきとは。会って間もないこんな怪しいモノを信用するなんて、よくこの歳になるまで生きていられたものだ。
「だから、こわくなんて、ないよ」
ヒベニが少し間をおいて言ったその言葉に、『彼』は虚を突かれた。
すき、だからこわくない?
「てめぇ、バカだな」
『彼』は憎まれ口をたたいたが、何故だか動揺していた。
好きだから、怖くない。
その言葉は、『彼』の心に小石のように沈んでいった。
日紅がだんだん大きくなって、一緒にいる月日を重ねて行くうちに、『彼』の胸に沈む言葉も増えて行った。それは時に、言葉だけではなく、日紅の表情や、態度だったりもした。
けれど、今、それが積もり積もっていっぱいになってしまった。
『彼』は、苦しい。もう自覚している、苦しいと。これ以上はもう、一粒でさえ乗せることができない。その積もったものを全て捨ててしまえれば楽になれるのだけれど、そうはできない自分もわかっている。
「苦しい」なんて、まるで、ヒトみたいに。
そうだ。あたしは、小さかったけれど、本気で、心をこめて伝えたかったんだ。
巫哉は、怖くないかと問いながら、別のことを気にしているみたいだった。
だから、あたしは、巫哉にそのときの精一杯で伝えたかった。
『彼』が何を考えているかは分からないけれど、誰かに好かれていること、愛されていることは、その人の力になるんじゃないかと、とても嬉しいことだから喜んでくれるんじゃないかと、小さな頭で考えたんだ。
巫哉、その気持ちは今でも変わっていないよ。
夢は続く。日紅の忘れている日紅の過去。小さな日紅は強引に巫哉を家に連れて行こうと必死だ。
『彼』の真名を日紅は知った。ちゃんと聞いた。忘れないように。
日紅はふと不安になる。
これは夢よね?自分が夢の中にいるとわかる、夢。明晰夢(めいせきむ)というものだ。けれど、日紅の意識はそのまま、夢の中でよくあるような意識の混濁や倦怠感がないままに存在する。
まるで、日紅の過去に今の日紅がそのままタイムスリップでもして、覗いてるかのような現実感。
「日紅朝よー」
なんとも緊張感のない声がどこからか聞こえる。
お姉ちゃんだ。朝なのだ。起きなきゃ、でも。
目の前にはむすりとした『彼』が小さい日紅を抱えたまま、家に向かっている。
巫哉。
あたしは巫哉の言うとおり、本当の名を知ったよ。
これで、全部、上手くいくんだよね?もとに、戻れるんだよね。仲が良かった、あたしたちに。
夢が遠ざかる。無邪気で幼い日紅の笑顔と、『彼』が風景と共に急速に白み滲んでいく。
この、理由のない不安も、みんな…。
巫哉8
「よしっ」
鏡の中の日紅(ひべに)は笑う。制服も、アイロンのかけたてでシワ一つない。髪はちゃんと櫛で整えた。『彼』がいつも入ってくる窓も掃除した。部屋も綺麗。準備はバッチリだ。
「いってきまーす!」
「いってらっしゃい!気をつけてねー!」
母親の元気な声に送られて、日紅は踏み出す。朝の透き通るようなにおいが日紅を包む。
顔を出したばかりの太陽が世界に明暗をつくる。その影ですら、朝は明るい。
今日、『彼』を迎えに行くんだ。
「犀(せい)。おはよっ」
「日紅」
犀が微妙な顔で振り向いた。
犀と日紅は、気持ちがすれ違ったままだった。『彼』のことを気にかける日紅。それを気にいらない犀。つい昨日まで、お互いぎくしゃくしてぎこちないままだったのに、今日の日紅の態度が普通だったから犀は戸惑っているようだった。
「あのね、あたし考えたの」
犀を促して歩きながら日紅は切りだした。
「や、待って。先に俺に言わせて」
それを犀が遮った。日紅は不思議そうな顔をして犀を見上げた。
「ごめん」
犀はそこで唇を一瞬噛みしめる。
「わかってるんだ。おまえとさ、月夜(つくよ)が仲がいいなんてことはさ。いなくなった月夜をお前が心配するのも分かる。でもさ、やっぱり、なんていうか…俺よりも、あいつの方が会ったのも早くて、その分俺の知らないなんか、繋がりっていうかさ、そんなのが大きいんじゃないかっておも、思っ、て…。…だーーーーーー!」
いきなり犀が頭を掻き毟って日紅は驚いた。
「ちょ、日紅、とりあえず俺の顔見ないで!前向いてて、ほらはやく!」
犀が無理矢理日紅の顔を前に向ける。日紅はとりあえず従ったが、前を向く前に見てしまった。顔を背けている犀の顔がゆでダコよりも赤くなっていることを。
思わず、ふ、と日紅は笑ってしまったが犀はそれどころじゃないようだ。
「おまえに嫌われたくないから今から正直に言う!だから絶対こっちみんなよ!?」
声を出すと笑い声が漏れてしまいそうで、日紅は口元を覆ったまま無言で頷いた。
「俺、月夜に嫉妬した。あいつ今どこにいるかもわからない状態だって言うのに。確かに日紅の言ってた通りあいつの力でどうにもならないことに巻き込まれてるのかもしれないのに。いなくなってもう一月とかになるだろ?日紅がそこまで気にする事かとか俺が彼氏なのにとか思ったら、なんか気持ちが納得いかないのが大きくて。でも非常事態みたいなもんだから、俺がそんな子供っぽいことにこだわってるわけにもいかないし、何より…おまえに嫌われたくない」
そう言いきって、犀はまたひとりで悶え始めた。
それを見て日紅は堪え切れずに笑ってしまった。
「笑うなよ!あー俺情けねぇ~…」
「あはは、でも、そんな犀の素直なとこ好きだよ」
日紅は犀に小突かれる。
「今のどこが情けなかったの?犀が優しい人だって再認識したんだけど」
「情けないだろ!?嫉妬したとか、嫌われたくないとか!女々しすぎる!」
「全然そんなことないよ。言ってくれた方が、嬉しい。ありがとう犀」
「…ん」
照れ隠しなのか、犀はしかめっ面で口を手で覆った。しかし顔の赤みはひかないままだったので、さらに日紅の微笑を誘った。
「あたしもごめんね。なんか、巫哉もいないし、犀ともあんなだったから、どうしていいかわからなくて避けるみたいなこともしちゃって」
「いや、それはもとはといえば俺が悪いから」
「じゃあ、二人とも悪かったってことで、仲直り、ね?」
「ああ」
「…ね、犀。巫哉(みこや)のことだけど、心配しなくて大丈夫。今日迎えに行ってくる」
「いるとこ、わかったのか?」
「ん…てかさ、犀が巫哉のことで怒っているみたいだったから言ったら犀不機嫌にしちゃうかなと思って言えなかったんだけど、この前巫哉に会ってね…」
「ん」
犀がむすりとする。
「俺が嫉妬するのはもう反射みたいなものだと思ってくれ。隠し事されるより、言ってくれた方がいい。あいつにはどうしても対抗意識が出る。で?」
「この前あたしが熱出したの覚えてる?その時に巫哉に会えて。公園にいたんだけど。巫哉の真名(まな)を思い出したら、帰ってきてくれるって」
「真名、真実の名ねぇ…。てか熱出したときに公園?月夜に会った?どうやって?」
「それはウロが…って、問題はそこじゃないの!」
「俺にとってはそこだよ。おまえ無茶するなよ!?」
「してない、してないからっ!」
虚(ウロ)に齧られた事を言ったら外出禁止令を出されそうだと日紅は思った。
「真名思いだしたら帰ってくるって…そんなことで家出したのかよあいつは。子供か」
「まぁ帰ってくるとは言ってないんだけど、ただ思い出せって。でも帰ってきてくれると思う」
「へぇ。思い出せたってことか?教えろよ。帰ってきたらからかってやろう」
「 」
「…日紅?」
「あれ、聞こえた?」
「いや、おまえ口パクだったよ今」
「おかしいな。 。え、言えてないよね?なんで?あたしちゃんと言ってるんだよ? 。ダメ?」
「ダメみたいだ…紙に書いたらどうだ?」
「携帯で打ってみる…あれ?」
「どうした?」
「わかんなくなる…打とうとすると…名前が。ええ?打つ直前はわかってるんだけど、打とうとするともうわかんないの…どういうこと?」
「あーまぁそうだろうなとは思ったけど。言うのも駄目、書くのも駄目、あとは読唇術ぐらいか…たぶんダメなんだろうけど」
「どくしんじゅつ?」
「唇の動きで何しゃべってるかあてること。多分月夜の名前は、本人から直接聞かないとだめなんだよ。よく神や妖怪なんてものは真実の名前が弱点にあたるようなことも聞くし、そう簡単には伝えられないようになってんだろ」
「そう、なんだ…流石(さすが)犀」
納得いくような、いかないような。日紅は首を傾げた。
「なあ…日紅。月夜がいなくなったのって、俺らがつき合った日か?」
「ん?そうだよ」
「俺も、おまえに言ってないことがある」
「…え?なに?」
「付き合った日、俺月夜に会った」
それは、日紅が『彼』の涙をみた、次の日の話。
巫哉9
ぼんやりと、していた。
今まで「ぼんやり」などした事などなかったが、きっとその時の状況を表すのはこの言葉が一番適切なのだろうと『彼』は思った。
気がつけば、時が流れていた。太陽は真上だ。『彼』は日紅の家の隣にある木の枝にいた。いつもの『彼』ならば、家を出る日紅に姿を消してついて行くのが常であるのに、それすら気がつかなかったようだ。
いつのまに、『彼』はこんなところにいたのだろうか。夜、様子のおかしかった日紅の話を聞いていたはずだ。それが、なぜ。日紅は、日紅はどこだろうか。
横を見た。窓。日紅(ひべに)の部屋の窓だ。そこから中を覗く。がらんとした部屋。かわいらしい人形も、机も、色褪せただ無機質な物の羅列としか映らない。そこに、あるべき人がいないから。
日紅。
ふらりと『彼』は動きだす。
その胸の奥で日紅の声が、ふと蘇(よみがえ)る。
「巫哉(みこや)あたし犀が、好き」
そうだ。昨夜(ゆうべ)、光のない部屋で、日紅は妙なことを言っていた。犀(せい)が好きだと。友情の意味ではないと。
好き。
わからない。言っているその意味が。それを『彼』に言うことで、日紅が伝えようとしたことが果たして何なのか。わからない。
わからない、ヒトの言う「好き」がどういうことなのか。妖(あやかし)である『彼』には。
何かが壊れそうに痛んだが、それが何かも、なぜ痛むのかも、ヒトではない『彼』にはわからない。
ふらりふらりと彷徨って、気がつけば日紅を追ったのか学校にいた。ヒトの子は大きくなるまでコンクリートの建物に詰め込まれて学を得る。『彼』はそれを全くくだらないと考えていた。一日中じっと紙と向き合うなど、命の無駄でしかない。それより、森に出、走り回り、土を耕し、太陽の光を浴び、花を愛でた方が余程実りがあろうと言うもの。ヒトは限りある短い命をどれだけ無駄にしていることか。
「月夜(つくよ)。いるんだろ?」
声がした。『彼』の心が一気に現実に戻った。一番、聞きたくない声。
がらんとした学校の屋上、フェンスの前に犀がいた。腕を組んでフェンスにもたれかかっている。
「出てこいよ。おまえから俺は見えるかもしれないけど、俺からおまえは見えないから」
日紅は側にいないようだった。
犀が、『彼』とふたりきりで話す事など初めてだった。そもそもそんな必要もなかった。
それが、なぜ。
ちりりと『彼』の心が騒ぐ。
「日紅と付き合った」
静かに犀が落とした言葉が、『彼』のまわりに波紋を広げて絡みつく。
耳障りな声だ。五月蠅い、うるさい。
「…やっぱりいたのか」
犀が、軽くため息をついて言った。
『彼』は、『彼』自身でも意識しないうちに、犀の前に姿を現してしまったようだった。
「月夜、おまえ日紅のことどう思ってんの。正直に言え。一応言っとくけど、はぐらかしたりしたらぶっとばすから」
はっ、と『彼』は笑った。虚勢を虚勢だと気づかぬまま、『彼』は口を開く。
「なに言ってやがるてめぇ。俺は…」
『彼』の声はそこで途切れた。犀は笑いもせずにじっと『彼』の返事を待っている。まるで、もう『彼』の選ぶ返事を知っているかのような、達観した表情だった。
しかし、『彼』はわからなかった。
いつものように、「日紅のことなど嫌いだ」と返せばいい。たったそれだけのことなのに、何故か、声が胸に詰まっているように、言葉が出てこない。
「…俺、は」
声の出し方を忘れたわけじゃない。なのに、なぜたった一言が出てこないのか。
「嫌い、だ」
ようよう絞り出した言葉にも、犀は無反応だった。
暫(しばら)く、無言の時間が流れた。
「日紅は、俺のことが好きだ」
どれくらいたったのか。そう唐突に犀は言った。
その言葉に『彼』が何か感じるよりも早く、犀は続けた。
「俺も日紅のことが好きだ。ずっと好きだった。だれにも渡したくないくらい好きだ。」
聞きたくない。『彼』は唸った。
ぐわりと明るい青空が歪む。『彼』と犀。世界中で、息づいている時間が今ここしかないように、その他の景色は時間が止まったように色褪せて感じる。
犀はまっすぐに『彼』を見ていた。『彼』は視線を逸らす。
「お互いに好きだから、付き合うことになった。俺は日紅を大事にする。絶対に悲しませたりしない。映画に行ったりとか、デートしたりとか、二人で一緒に勉強して、一緒に水族館とかにも行って。沢山思い出を作って、あいつ意地っ張りだからもしかしたら喧嘩する事もあるかもしれないけど、絶対に仲直りする。それで、もう少ししたら、結婚して、子供もできて、これ以上ないってぐらいの幸せな家族になる。」
やめろ!
「でも日紅のことを『嫌い』なお前には、関係ないか」
突き放すように犀は言った。幸せな話をしている筈なのに、犀の顔に笑顔はなかった。犀は『彼』の態度に苛立っているようだったが、それが具体的に何かは『彼』にはわからなかった。
「…おまえ、今の自分の顔鏡で見てみるといいよ。じゃあな」
顔?
犀は言うだけ言うとそのまま屋上から出て行ってしまった。後に残ったのはただ戸惑うだけの『彼』だ。
犀が言った、顔とは何だ。
顔と言っても、彼はヒトのように考えていることと表情が必ずしも連動するわけではない。今の『彼』は、いつものように不機嫌な顔を崩していないその筈だ。
『彼』は屋上のドアに自らの面を映してみた。
むすりとした銀髪紅瞳の年若い子供が映る。『彼』だ。なにも、変わっていない。ただ変わっていないはずなのに、なぜかずっと見ているのが不快で、『彼』はすぐに背を向けた。
ずきりずきりと痛んだそれは、どこだ。『彼』の身体か、それとも心などと言うものか。
ずっとずっと側にいて大切にしてきた日紅は、犀という唯一無二の相手を見つけた。
いままで『彼』に向けられてきた日紅の、眩しいくらいのあの笑顔は全て犀のものになった。
日紅は犀と結婚しそして、犀の子供を産むのだ。
それは決して『彼』が与えることのできない、命の温もりだ。
日紅の子も大きくなり、また誰か相手を見つけ、子供ができる。日紅の命が連綿と続いて行く。それをずっと側にいて見守ることができたら、それは、どんなに幸せなことだろうか。
『彼』は秘かに微笑んだ。優しい笑みだった。それからゆっくり地から足を離し、風にのった。
頬で風を受けるのが「心地いい」。それを『彼』に教えてくれたのも、日紅だった。
いままでごちゃごちゃと思考が乱れていたのが不思議なぐらい、『彼』の心は落ちついていた。
それ、を自分で認めることはできないのだ。それを認めれば、多くを望むようになる。そうすればきっと、正しい何かを歪めてしまう。そんなことは、『彼』の望むところではないし、日紅も悲しむだろう。それは絶対にしてはならない。『彼』は何でも望むことを叶えられるからこそ、地球の理(ことわり)を歪めてはいけないのだ。
『彼』の笑みは崩れなかった。
日紅の命が紡がれてゆく、それを見守るのは確かにこの上もない幸せだろう。また不死の『彼』にしかできないことでもある。
けれど、それを思ったときに、気づいてしまった。
たとえ日紅の子がいても、そこに日紅がいないのなら、何の意味もないと。
そう考えた自分に、驚き、また同時に納得もした。
そうか。だから、そうだったのか、と。
色とりどりの家の屋根は眼下に過ぎてゆく。日は高く上り、空を飛べもしないヒトは地に足をつけて立ち、陽を見上げてはその眩(まばゆ)さに目を眇(すが)める。
やはり、ヒトと長くいすぎたのだ、と『彼』は思う。
ヒトは、生きている。生きるために他の命を殺して生きる。
生きて行くということはそういうことだ。ひとつの命を生かすために千も万も億も他の命が失われている。それは単なる弱肉強食。ヒトすら死ねば他のものが生きて行く上での糧になる。
『彼』は、ひとつの命を大切に想ってしまった。例え他の命がいくつ犠牲になろうとも、たったひとつ、その命だけが愛おしい。
それを願うのは、ヒトと同じだ。ヒトは無力だからいい。願いは手が届かないから美しい。ただ『彼』は違う。願ったことを、現実にする力を持っている。それは、「いけないこと」だ。
「悪いこと」をしてはいけないのだ。
日紅に、怒られてしまうから。
腹も減らず、眠ることもなく、息もしない『彼』は、日紅に会って、ヒトの真似をするようになった。最初は日紅に強制されて、逆らうのが面倒くさかったから。そして、それは段々―…日紅と同じヒトではないことで怯えさせて嫌われたくないという思いに変わっていった。
地に足をつけて、歩くということ。足の裏に力を入れ、土を踏む。いのちの芽吹きを感じながら、ぐっと体重をかけ、前に進む。歩いた分だけ、自らの軌跡が後ろにはるか長く長く棚引く。
表情。笑うと言うこと。楽しいという感情を他者に伝えるために顔に浮かべる。笑顔を浮かべてみせると、日紅が笑うから。笑顔は嬉しいのだと日紅は言う。楽しいときは笑ってと、そう言う。だから『彼』は笑う。日紅のために。
息をするということ。体の中に地や光の暖かさを吸い込む。それは『彼』のなかをぐるりとめぐり、いのちの息吹(いぶき)をしみこませる。それを吸って、吐いて、自らも命の輪廻に宿る。身体を血が巡り、温かみが通う。ヒトのように。
けれど、いくら真似をして近づいても、『彼』はヒトじゃない。日紅とは違う。日紅もいくら妖と関わったところで、日紅が妖になるわけじゃない。日紅はヒトのまま、『彼』は妖のまま、そこには絶対の隔たりがある。
もし、などと考えることは愚かなことだ。いくら考えても現実に起こりはしないのだから。けれど、今だけは。
ひとつひとつ、日紅に近づいていって。
ひとつひとつ、何かを得ていく。
得たその分、持っていた何かを失って。
また、俺は手に入れる。
押さえきれぬ感情は滔(とう)々と溢れ零れる。それを拭う手も持たぬまま、『彼』はただ独り待つ。いっそ来なければいいと願いながら。
巫哉
とろりと優しい光に包まれた満月が、夜空に浮かんでいる。
夜の冷えた空気が日紅の上記した頬を包んで心地が良かった。
「巫哉!」
『彼』は相も変わらず、古ぼけた公園の、木の根元にいた。丁度月光が煌めき『彼』の姿を凛と浮かび上がらせる。遠くからでもその姿がよく見えて、日紅は駆け寄った。
「ぶ!?」
その勢いで『彼』に飛びつこうとした日紅はびたん、と何かにぶつかった。
「にゃにこれ…」
「てめぇはそのやたら飛びつく癖どーにかしろ」
『彼』のあきれ顔が目の前に見える。見えるのだが、日紅の身体は何か透明な板のようなものに遮られて『彼』に近づくことができない。日紅は空中に張り付いている自らの身体を引き剥がした。『彼』から見た日紅はさぞや面白い顔をしていたに違いない。
「ぷほっ!なによー巫哉にしかしてないからいいじゃない!なによこれ、この、見えない…板!?こんなのに妖(あやかし)の力使うなんて卑怯なんだからね!」
「俺にしかしてないことの何がいいのかわからねぇし、卑怯でもねぇ。俺に飛びつこうとするてめぇが悪い」
「わるくなーい!だって久しぶりだし…てゆーかあたしにそんな口きいていのかな~巫哉くん!」
「なんだ」
日紅はにやりと笑った。
「ふっふっふっふー…」
「何だよ」
「あたし、ちゃーんと思いだしたよ!巫哉の本名」
『彼』は瞠目(どうもく)した。それを見た日紅はしてやったりと笑う。
きっと『彼』は、日紅が本当に真名を思い出す事などできるわけないと思って、こんな無理難題を吹っ掛けたに違いない。幼いころに一度教えてもらったきりの名前だ。普通なら、絶対に思い出せないものだ。それを偶然夢で見たなどと随分虫のいい話ではあるが。
「…またあいつか」
「ウロ?ぶっぶーウロに教えてもらおうとしたけど、知らないって教えてくれなかったよ。自力ですー」
「教えてくれないも何も、あいつが俺の名を知るわけねぇからな。ただ、あいつはおまえの中にもともとある記憶を、引きずり出す事はできるんだよ」
「あ、そしたらやっぱり夢に見たのってウロのおかげなの?流石に都合良すぎかなーって思ってたんだけど」
「序(つい)でにこの前てめぇをここまで運んだのもあいつだ」
日紅が熱のある体で『彼』を探して朦朧(もうろう)と彷徨(さまよ)い、虚(うろ)に初めて会った時のことを言っているのだ。
「そうなんだ…。やっぱり、ウロ優しい。今度ちゃんとお礼言わなきゃ」
「…憶えてればな」
「そこまで記憶力悪くないから大丈夫!」
『彼』が微かに笑った。それを見た日紅も、笑う。
「ふふ。巫哉笑った!」
「何だよ俺だって笑うよ。悪ぃか」
「ううん、嬉しい!やっぱり巫哉とずっと会ってないって変な感じ。いつも一緒にいたから。いきなりいなくなっちゃって、心配したんだからね!?誘拐とか病気とか事件に巻き込まれてたらどうしようって」
「事件?病気?誘拐?この、俺が?ははっ」
『彼』は目を丸くして、それから笑った。満面の笑みだった。日紅は虚を突かれてぽかんとしてしまった。
暫く呆けていた日紅は、我にかえると、泣き笑いの顔で両手を広げて『彼』に突進した。
「巫哉ぁ~!」
「うお!?」
びたん!
案の定壁に阻まれたが、それでも日紅はぐしぐしと泣き続けた。
「もう巫哉ぁ~本当に本当に本当に心配したんだからね!探してもどこにもいないし、もしかして、このまま帰ってこないつもりじゃないかって、本当に…」
「わかった、悪かった。俺が悪かったから、泣きやめよ」
「やだっ!やだやだっ」
安堵が一気に溢れ出て日紅は子供のように暫く泣き続けた。
「もう巫哉ひどい!ひどい!あたしがどんなに心配したか、知らないからそんなにいつもどおりな顔していれるんだよ!」
「だから、悪かったって」
「じゃあこれからはもう勝手にどっかいかないでね!絶対だよ、絶対!家出する時は一言言ってからどっかいくんだよ!」
「…おまえ、顔ぶっさいくだぞ」
「泣いてるから仕方ないでしょ!?泣かせてるのはどこの誰よ!?もう巫哉なんて、巫哉なんてぇ…!」
「怒ると余計ブスになるぞ」
「うるさーいっ!もう なんて、知らないんだからっ!」
今度虚を突かれたように黙るのは『彼』の方だった。
「え…あれ、違ってた…?」
「…いや、あってる。確かに俺の真名(まな)だ」
思わず問い返した日紅に『彼』は静かに返した。
「でも、おまえはミコヤでいい」
「あ、うんわかった…巫哉」
『彼』はじっと日紅を見た。いつもそんなに『彼』に見られることがなかった日紅は思わず見つめ返した。
『彼』の顔は、喋らなければ精巧な人形のようだった。寸分違わず左右対称の顔。月の光を編んで作ったような銀の髪。炎のように輝く瞳。眼下に厚く影を落とす睫。高くすっと伸びた鼻梁に、引き結ばれているかたちのよい唇。肌は白磁、瞳は宝石、なんともまぁ、女泣かせの男がいたものだ。『彼』が人間でなくて本当に良かったと日紅は独りごちた。昔日紅が犀(せい)から教わった「傾国の美姫」というのは、こう言う容貌の人を言うのだろう。それは戦争も起こる。
「巫哉人間じゃなくてよかったねぇ」
『彼』は息を呑んだ。日紅はそれに気づかずへらりと笑う。
「……………何故」
「だって、悔しいけど!巫哉ありえないぐらい美人だもん。人間だったらきっととりあいだよ!絶対大変なことになってたよ」
「じゃあおまえも、妖じゃなくてよかったな。おまえみたいなのは、すぐに悪い奴に騙されて喰われて終わりだ」
言い終ってから、『彼』はまた笑った。
日紅は首を傾げた。あの仏頂面(ぶっちょうづら)な『彼』が、今日はよく笑う…。
「巫哉今日ご機嫌だねぇ?」
「そうかもな」
日紅は『彼』が肯定したことにも驚いた。いつもなら絶対にそんなことは言わないのに。
「巫哉熱あるの?なんか素直…」
「ねぇよ」
日紅が伸ばした手は、『彼』に触れることなくぺたりと壁に遮られる。
「ねぇ帰ろ?ここ寒いよ」
「おまえ、ここがどこか憶えてるか」
『彼』は日紅から顔を逸らした。どうやらまだ帰る気はないらしい。
「巫哉を初めて見つけたとこでしょ」
日紅は自分の言葉が無視されたことに少しむくれて答える。
「酷かったよ、あの時のおまえ。視(み)たんならわかるよな?」
「…返す言葉もございません」
幼い日紅は『彼』の鼻を掴み、腹に頭突きをし、唇を引っ張り、耳を捻る…やりたい放題だった。
「しつこく俺にじゃれつくし、突拍子もないことをいきなり言いだすし」
「う、ご、ごめん…でも子供の頃の話を持ち出すのはずるいと思う!今はもうそんなことしないし!」
「どうだかな」
フンと鼻を鳴らして『彼』は笑った。
「そうやってばかにして~!」
「してねぇよ」
「してる!」
「してない」
『彼』は静かな声で言った。そこには揄(からか)いも嘲(あざけ)りも含まれていなかった。
すっと月の光が陰った。雲が射したようだ。夜の公園は、月の光がなければただの闇。街灯の光も奥の二人を照らす事はない。
「だから俺は、ヒトの成長が早いってことを、忘れていた。ずっと」
「巫哉、なに…」
日紅は笑おうと唇をつりあげたが、それは途中で儚く消えた。『彼』が、余りにも寂しそうに笑っているから。
『彼』は視線を日紅に戻した。わかっているのだろうか、『彼』は。自分がどんな顔をして笑っているのか。夜の闇ですら隠しきれないほどの感情。
「俺には瞬きするほどの間なのに。おまえは違う」
「巫哉。巫哉?」
日紅は『彼』に手を伸ばす。けれどやはり見えない壁に遮られる。日紅は少しでも『彼』に近づこうと、空に両手を着き顔を寄せる。
「俺がいくら望んでも、お前と共に歩むことはできない。おまえも、俺と同じ時間を過ごすことはできない」
「そんなことないよ!命の長さが違うってことを言いたいの?あたしのほうが早く死んでしまうけれど、でも、それまでずっと一緒にいれるじゃない。共に歩めないなんて悲しいことを言わないで!」
「じゃあ、お前が死んだら俺はどうすればいい?日紅」
日紅は動揺した。なんだか、『彼』が今日は違う。いつもと違う。日紅が死んだらどうしたらいい、なんて、これじゃあ、まるで…。
まるで『彼』が日紅のことを、好きみたいだ。
一瞬浮かんだ考えを振り切るかのように、日紅は首を振った。自分で自分の考えに恥じる。そんなことあり得ない!
「巫哉にはみんながいるじゃない。あたしが死ぬのをヤだなって思ってくれるんだったら不謹慎かもだけど、それはやっぱり嬉しい。でも、死んじゃうのは仕方がないよ。そりゃあたしだって死ぬのは怖いし、ずっと犀や巫哉といれたらいいなって思うけれども、自分ではどうしようもないことだもん」
「死ぬのが怖いなら、一緒に生きるか」
「え、どういう…」
「不死の身体にしてやろうか」
日紅は息を飲んだ。『彼』はまっすぐに日紅を見ている。冗談を言っているような雰囲気ではない。
「…いらない」
考えるより早く言葉が出た。それは以前、虚に問いかけられたものと同じものだった。その時と違いなく、日紅は顔をあげ、『彼』の目を見て言った。
「あたしは、人間として生まれたから、人間として死にたい。永遠の寿命なんてなくていい。傷つかないからだなんて欲しくない。あたしはあたしでいい。全く違う存在でも、お互い認め合えて、ただ寄り添って生きていけたら、それはこれ以上ない幸せだと思う…」
『彼』は日紅から目を逸らさなかった。日紅の答えを、問いかける前から『彼』は知っていた。日紅はそんなものに心動かされるヒトではない。それでも口に出したのは、自らの為だった。日紅の揺るがない心を、日紅の口から聞きたかったのだ。
覚悟は決まった。いや、ずっと決まっていた。
『彼』はずっと無為(むい)に生きてきた。生きる意味も知らず、死ぬこともできず、ただヒトや動物の生を眺めてきた。四千年、四千年だ。目的もなく生きるには、途方もなく長い時間だった。
日紅と出会って、初めて『彼』は流れゆく時を惜しんだ。そしてこれからも必然として続く果てしない生を憎んだ。
『彼』は見えない壁にかじりついている日紅に一歩寄った。
「俺は死ねない。死ぬことができない。自らこの身を傷つけ殺めることもできない」
「う、ん…」
「けれど、たったひとつだけ、俺の命を終わらせることができる方法がある」
日紅は『彼』を見た。『彼』は、何を、何を言おうとしているのだろう。
ど、くんと日紅の心臓が脈打った。
『彼』が顔を寄せてくる。見えない壁越し、目と鼻の先に『彼』の顔がある。
「俺の真名を知るものが、ただ俺に触れればいい」
日紅は一瞬でその意味を悟り、震えた。慌てて『彼』から離れようと手をついた壁が、日紅がぶつかっても今までびくともしなかった壁が、ほろりと光と化して崩れた。
そのまま日紅はつんのめったように『彼』の腕の中へ倒れこんだ。
冷たい『彼』の腕。紛れもなく、今日紅は『彼』に触れていた。
「いやーーーーーーーーーーーーーーー!離して、離して、離して!」
日紅は混乱して暴れた。それをおさえて『彼』は日紅の背に腕をまわし抱きしめる。
「もう遅い」
残酷な言葉が『彼』の唇からおちた。日紅はわけがわからないまま、『彼』を見上げた。いつの間にか溢れ出た涙で日紅の顔はぐしゃぐしゃだった。
「巫哉、巫哉…嘘だよね?あたしをからかってるんだよね?あたしが触っても巫哉、ほら、生きてる、もんね?嘘でしょ?そんなことないよね?」
『彼』は肯定も否定もせずにただ笑っていた。日紅は現実についていけなくて震えながら首を振った。
「嘘、嘘、嘘!嘘だ、巫哉は死なないんだよ、そうでしょ、そうといってよ!巫哉の馬鹿!ばか!お願いだから何か言っ」
日紅の声が途切れた。『彼』の腕がきつく日紅を抱きしめる。
なに、え、いま、え…?
『彼』の顔がゆっくりと離れた。重なった唇は、冷たいのにどこか熱い…。
「おまえのことなんか、嫌いだ」
いつも聞いていたその言葉。けれど裏腹に『彼』の唇から頬笑みは消えない。その指が、茫然とする日紅の涙を拭う仕草も優しい。
「ああ、こうなるのか」
落ちついた『彼』の目線を追って日紅は息がとまった。日紅の頬に触れていた指先が、消えていた。空気にとけるように、静かにゆるゆると『彼』は消えていた。
「巫哉!」
日紅は掠れ声で叫んだ。夢ならいい、これが。日紅は願った。だってついさっきまで、いつものように笑い合っていたのだ。
日紅に真名を思い出させたのは、こうするため?真名を思い出したら『彼』が帰ってきてくれると、日紅は必死で考えていたのに。
あの時は既に決めていたのか。ならば一体いつから『彼』はこうすることを決めていたのだろう。
姿を消す前、日紅の部屋で『彼』が見せた涙。あれはやはり、見間違いなどではなかったのか。
もっと、『彼』の心に寄り添ってあげればよかった。『彼』の話を沢山聞いてあげればよかった。あの『彼』が涙したのだ。それほどの理由があったのだ。バカだった。途方もなく、愚かだった。こんなことになるまで気がつかないなんて、救いようがない。
時間が戻れば、といくら願っても、そんなことは起ころう筈もなかった。日紅はただ激しく後悔した。
『彼』はそんな日紅をじっと見つめていた。
「どうしたら止まるの、巫哉!」
日紅の溢れる涙を、『彼』は消える指先で優しくなぞった。
「止まらない」
「止まらないわけない!どう、どうすればいいの、あたしは!」
「俺のそばにいてくれ」
日紅はしゃくりあげた。
「いる、いるから…いるから、消えないで巫哉…」
「俺が、消えるまで、側にいて」
「…ばかぁあっ!」
日紅は泣きながら蹲った。もう立っていられなかった。
『彼』も、日紅と一緒にしゃがみこむ。
「犀がいるだろ」
「犀!?犀と巫哉は、違うでしょ!犀も巫哉もいなきゃ、だめなの!巫哉!」
「日紅…」
『彼』の優しい声。それは日紅がからかい半分でずっと『彼』に求めていたこと。笑顔も、優しさも。でもこんなの、全然嬉しくない!
なにもいらない、何も望まない。だから、いかないで、巫哉!
お願い、神様、巫哉を連れて行かないで…。
日紅は『彼』に飛びついた。ぎゅっと力を入れて抱きしめる。どこにも行かないように。
日紅が大人になって、おばぁちゃんになって、布団の中でしわくちゃな顔で笑う。その側には絶対にむすっとした表情の『彼』がいてくれる。そう信じていた。
日紅より先に『彼』がいなくなるなんて、考えたこともなかった、のに。
「日紅、俺にはもう、おまえを抱きしめ返す腕もない」
ぽつりと『彼』が零す。
「あたしが、巫哉の分も離さないでいてあげるから!消えないでよ…お願い…」
『彼』は抱きしめる代わりに日紅のつむじにそっと頬を寄せた。
愛おしい。
日紅に伝えることはない。けれど、それは心からの真実だった。
日紅と離れている間、沢山のことを考えた。もしも、『彼』が日紅と同じヒトであったなら。日紅と逢い、結婚し、子供ができて家族になる。いずれ老い、眠るように死を受け入れる。その側には日紅が、子が、孫たちがいるのだ。幸せだ。それはこれ以上望むべくもない、幸せだ。
『彼』が生きてきたのは、長い長い時間だった。産まれた意味を何度も考えた。終わりある命を持つものは、子孫を残すために産まれ死んでゆく。自らの家族に包まれて生きるのは、どんなにか幸せだろう。脈絡と続く命。死ねば輪廻の輪にのり、再び世に産まれ落ちる。産まれ、死に、また生まれ、死ぬ。命は尽きず廻る。
では、死なない命は、どうしたらいいのだ。
家族の温かみも知らず、自分と同じような生き物もいない。『彼』は常に独りだったし、それを疑問に思うこともなかった。今までは。
だが、やっと知ったのだ。『彼』が産まれたその意味を。日紅は『彼』を『巫哉』と呼ぶ。優しく暖かい声で。『彼』は終(つい)に名を得た。『彼』だけの名を。
終わりはすぐ傍まできていた。そこがどこなのか、自分がどうなるのかは『彼』にすらわからない。消えるとはどういうことだろう。肉体が消えたら、『彼』のこの気持ちはどうなるのだろう。一緒に消えてしまうのか。それはきっと誰にもわからないこと。
日紅の泣き声すらもう聞こえない。けれど絶対に泣いているとわかる。泣くな。
『彼』は酷いことをした。日紅に自らの命を終わらせた。
けれど、『彼』は幸せだった。産まれてから一番幸せであった。
もしかしたら、ずっと『彼』は死にたがっていたのかもしれない。死ねない『彼』の命を、終わらせてくれるモノが現れるのを、ずっと待ち望んでいたのかもしれない。それが日紅で、良かった。本当に、よかった。日紅に逢えて、よかった。
だから俺は、ちゃんと俺として、おまえの幸せを願って、いるから…。
「巫哉!」
どこだ、日紅。どこにいる。
目も見えない。耳も聞こえない。感覚もない。
ちゃんといるか?俺のそばに。俺が幸せだったと、お前と廻り逢えて本当に幸せだったと、伝わっているか。
日紅と過ごした時間は、短かったけれども、眩しく美しく輝いていた。
日紅と会って、はじめて俺は俺を知った。
日紅。
自分の心の在処も知らない俺だけど、確かにおまえを慈しめた。
もしも…俺が、生まれ変われるのならば。また、おまえと会いたい。そのために、一億年待っても良い。どれだけでも待つ。妖でなくて良い。ヒトでなくて良い。地に咲く花でも良い。
違う存在でも、たとえ命の長さが違っても、寄り添って生きていけたら、それはこの上ない、幸せだ。そうだろう、日紅。
だから、また、俺を見つけろよ。
秋の夜の、涼しさの中で。古ぼけた公園の、痩せた木の根元で。
何度でも、俺を探して。
「巫哉、巫哉、巫哉!嫌だよ、巫哉!」
…日紅。
俺の名を、呼んで。お前だけが呼ぶ、俺の名を。
_
「いってきまーす!」
日紅(ひべに)の元気な声が聞こえる。
「昨日やってた宿題持ったの?」
「もったー!」
日紅は後ろを振り返りつつ答えている。
その笑顔は明るい。太陽のように、きらきらと輝いたままだ。
家を出るのが、少し遅くなってしまったようだ。日紅は少し早足で歩く。
「ヒベニ」
いつもの道。光を反射して眩しい屋根。心地よく冷えた空気。
日紅はスキップでもしそうな勢いで、真っすぐ続く白く塗装された道を歩く。
「ヒベニ」
ふいに明るい朝には相応しくない、全身黒づくめの着物を着た男が道の端に現れた。けれど、日紅は彼の姿も、かけられた声も、まるで気がつかぬように、急ぎ足でせわしなくその横を通り過ぎる。
そして男など一瞥(いちべつ)もせずに、そのまま去ってゆく。
男はじっとその後ろ姿を見ていた。その間通りかかったサラリーマンや学生が、ぎょっとしたように男を凝視するのをまるで気にもかけず。
日紅が見えなくなってから、男はゆっくりとヒトに見えぬよう姿を消した。
わかってはいた。
もう、日紅が男を見ることはない。ウロと、その名を呼ぶこともない。虚だけではなく、日紅の瞳は二度と妖(あやかし)を映す事はない。当然、声も聞こえるはずなどないのに。
日紅は、奇妙なヒトだった。本当に。妖と関わるヒト。日紅と同じヒトを喰らうと知っても、日紅は虚を優しいと言った。
足の横を小さな妖がころころと転がってゆく。右を見ればいいところに来たと、日紅の家の隣にある大木がざわめいた。
最近、ここ一帯にいる妖が言うことはひとつだ。
「…なんだ」
用件は分かっていたが、虚はあえて尋ねた。
「花を」
やはり内容は一つだ。
「大樹(たいじゅ)お主は動けただろう。なぜわたしに頼む」
「もう動けぬ」
大樹はそっけなく言った。そうかと虚は頷く。命の終わりは誰にでも来る。そう、誰にでも。
「どの花だ」
「ワシの花を」
「命を縮めるぞ」
「構わんよ。勿体ぶる程のものでもない」
はらりと虚の足元に薄桃色の花が落ちてきた。
「嬢ちゃんの優しい色だ。青更(せいふ)にこれ以上な花はあるまい」
「では預かる」
虚はそれを拾った。懐にしまう。
「ワシはな、黒いの。昔、嬢ちゃんと青更に会いに行ったことがあってな。その時に祝言(しゅうげん)には呼べと言ったのだ。あれは、あながち狂言でもなかったのだが」
大樹は独り言のように、ぽつりと零した。
「よかったなぁ!ツミ!」
「よかったよかった!太郎!」
「わーっ!?」
「にぎゃっ!?」
虚は足元で踊っている妖どもを蹴散らした。
「食人鬼!こらなにをする!」
「大樹の花を持ってきた」
「それにしても我らをよけて通ればよいであろう!」
「そうだそうだ!せっかくの祝い事を…」
ぶつぶつ言う猫の妖を尻目に虚は公園に足を踏み入れた。
古ぼけた遊具。奥へと進む。
一番奥に、木があった。その根元は、花で溢れかえっている。
見ている間にも、はらりはらりと花が降り積もる。
その上に、虚は大樹から預かった花を置いた。花は喜ぶように綻(ほころ)んだ。
「お主とヒベニの祝言を大樹が見たがっていた」
『彼』はもういない。そんなこと、ここで言っても詮無いことだ。わかってはいたが、虚の口をついて言葉は落ちた。随分、ヒトに毒されてしまったようだ。虚も、ここにくる妖たちも。
『彼』は長い時間を生きてきた。故に『彼』の事を知らぬ妖はいなかった。
誰にともなく、ここに花を飾るのが、『彼』への餞別となっていた。ヒトは大切な人が死ぬと、墓を作り花を飾る。
所詮(しょせん)ヒトの真似ごと。しかし、ヒトと逢(あ)った妖には相応(ふさわ)しかろう。
風もないのに花弁は揺れる。歌うように、楽しげに。まるで、『彼』に日紅が寄り添っているかのように。
「馬鹿者が」
虚は呟く。
愚かだ。『彼』は自らが消えるのと同時に、日紅と犀(せい)から『彼』の記憶を消したのだ。妖と関わりすぎてしまった日紅が、もう面倒なことに巻き込まれないよう、ご丁寧に二度と妖を見ることも、声を聞くこともできなくしてしまった。
そんなことを…あの太陽のような娘が喜ぶとでも思っているのだろうか。
「よかったなー楠美(くすみ)!」
「いやあよかった!よかった!」
そこかしこで妖が宴会を繰り広げている。公園はいつになく賑やかだ。勿論ヒトの目には映らないが。
妖は『彼』が消えたことを喜ぶ。死ねない『彼』がただ一人、真名(まな)を明かしてもいいと思える相手に出会ったことにただ喜ぶ。妖とヒトは生きる道が違う。本来交わってはいけないものだ。いくら心を添わせても一緒に生きていくことはできない。
「おい、食人鬼。次は俺の番だどいてくれ」
ぬっと人型の細長いものが横から顔を出した。虚は横にずれた。妖は握っていた蒲公英(たんぽぽ)をそっと添えると両手を合わせた。
「…なんだそれは。何をしている」
「食人鬼、知らぬのか。ヒトはこうして手を合わせる。いなくなった者の幸せを願うのだ」
「願うだけか。無意味だな」
「ヒトは意味のないことが好きなんだろう」
がくんがくんと妖は首を振った。頷いているつもりらしい。人型に慣れてはいないようだ。
「そういえば、食人鬼、おまえなぜあのヒトの子を食べぬのだ。おまえの印が付いているぞ。食べぬなら印を消してくれ。旨そうだ」
「ヒベニはわたしのものだ」
「ならなぜ喰わない。遊ぶにしても長すぎじゃないか」
「ヒベニが寿命で死ぬときに喰う。そう約束した」
「なに」
妖は虚をみた。
「寿命とは、気の長い話だ」
「お主は短気だからな。ヒトの寿命など、あっという間だ。その間ぐらい生かしてやってもいいだろう」
「俺より気の短い奴が何を言う。印はひとつしかつけられないのに…おまえ、そうやってあの娘を守っているのか」
風が吹いた。虚は答えない。さわさわと花が揺れる。雲間から光が差す。花弁はなおも降り積もる。
「梢」
「三郎」
「宵闇」
「尊人」
「水流」
様々な妖が口々に『彼』の名を呼んでいく。いろいろな花が折り重なる。けれど答える声はない。
『彼』の望む名を呼ぶものはもう、いないから。
彼
こんにちは。50まいです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
これで、三人の物語は終わりです。
感想をくださった方、何より本当に、このお話を読んでくださったことに心から感謝をしたいです。
ありがとうございました。
以下だらだら後がきです。
書いている時に頂いた感想で多かったのが、「犀頑張れ!でも3人とも悲しい思いをして欲しくない!」「『彼』かっこいい!でもみんな幸せになって」と、3人ともの幸せを願って頂けるものでした。
嬉しい半面、『彼』というお話は、最初からラストを決めて書いていたので、みなさんの感想を頂けば頂くほど、筆が重くなっていく…。ありがたいことに更新のたびに感想をくださった方がいらっしゃったのですが、『彼』を大変気にいって下さり、更新を楽しみにして頂けているようで…でもラストがこんな終わりなので、大丈夫かなぁと思いながらも…書いてしまいました。私が『彼』をリアルタイムで書いていた時と同じ年齢の方です。その方からは何と言って頂けるのでしょう。苦情でしょうかね。ドキドキ。どんな感想も宝物ですから。でも読んでいる方から顰蹙かう終わりだろうなぁとは、自覚しています。
幸せにしてあげられなくてごめんなさい。本当に。
これはわたしが中学校のころに書いた小説でした。
そもそもの書くきっかけは、「これ以上ないくらい悲しい話って何なのかな」というものでした。
考えた末に、好きな人に殺される、ことが一番悲しいことなんじゃないのかなと思って、3話の短編で考えていました。
「『彼』とあたしとあなたと」と、「『彼』とおまえとおれと」と、「『彼』」の3編ですね。
題名は結構気に入っています。しかし予定は未定とはよく言ったもの、書いていくうちに、アララなんだか大分長くなってきたぞ?と焦り始め…。
わたしはどうも物語を長編にしてしまう癖があるようなので、できるだけ短く!そしてちゃんと終わらせる!と自己暗示をかけながら書いていました。
それでこの長さ…もちろん削れるところも多々あるのですが、もし改稿するのなら増えることは必至です。
あと、この小説は沢山の新しいことに挑戦したものでした。
まず3人称での語り。これ難しかったですね~!わたしの基本スタイルが一人称ですから。ただ一人称だと、気持ちが伝わりやすいというメリットはありますが、独りからの視点になっちゃうんですよねどうしても。三人称のように、同じ場面で違う人物からの視点ということができないのが…。でも書きやすいのは一人称でしたやっぱり。
次に普通じゃない表現、比喩と言うか、隠喩を沢山盛り込みました。漢字も意識して別の漢字を遣ったり…。絶対に普段の自分じゃ使わないような表現を沢山いれて。「おいおい誤字あるよ」と言われるレベルのものも沢山入れました。「ここ文章間違ってんぜ」「違うんですわざとなんですぅ」というやりとりはいまのところ起こっていないようですが。表現の幅はひろがった…かな?大分頭を捻りました。
話のほとんどは、最初から決まったものでした。日紅が犀を選ぶのも、『彼』が死ぬのも。でも青山くんと虚は予定外でした。こんな、出てくる予定じゃ、なかったんですけど…!特に虚は本当にいきなり出てきましたねぇ。齧られるのはごめんですが、なんだかんだ優しいところが好きです。青山君は意味深なところで出演が終わりましたけど…ええ、彼には本編で全く生かせなかった実は霊感が強いという設定を別のところで遺憾なく発揮して頂きましょうかね。
わたしは隠喩?トリック?が好きなので、全部読んだ後にもう一回読んで頂けると面白いところがあったり、するかもしれませんね。近いところだと『巫哉』の章で「ウロにありがとうっていおー♪」と日紅が言うのに『彼』が「憶えてればな」とかえすところ。覚えるの誤字じゃないんですこれ。『彼』は日紅の記憶を消す事前提で言ってますから…。「(おまえが明日も虚のこと、この会話も)憶えてればな」という意味です。細かすぎて、わかんないですかね?まぁそんな小さなものを少しずつ折り込んであります。気になる人は、読み返して頂けると面白いかも。
『彼』
不器用な人でしたね。あヒトじゃないか。妖としてほぼ無感情でいた中、日紅に出会い、沢山のものを知って行く。エピソードとして入れてませんが、日紅が「巫哉肌冷たい」というから心臓動かして血液も巡らせてるんですこの人。あと、加減を知らない力が日紅を壊さないように、「痛み」も感じるようにしてる。凄い!とっても私にはまねできません。身体をまねて行って、感情も出てくるようになって。笑う、怒る、沢山の表情を真似していたら、いつのまにか自分の顔になっていた。それで、日紅が犀好きって話されてからやっと自分の気持ちに気づく。遅い!正確には犀と話した時だけれど。しかも初恋。『彼』はいろんな感情がぐちゃぐちゃしてて一概には言えませんが、これで『彼』は幸せだったんです。言っちゃいけませんが、日紅が『彼』を選んでいたら、当然あんなことしませんでしたよ。日紅を不老不死にするか、『彼』が日紅と共に死ぬか、二人がどうするかはわかりませんが、あの決断は日紅に犀がいたからこそのものだったと思います。でも日紅は犀を選ばなくても、『彼』を選ぶことはないでしょう。完全に恋愛対象外、兄弟のようなものでしたからね。ただ他に二人が幸せに生きる道は、絶対にあったと思います。
ちなみに。本当にちなみにですが。『彼』が死ぬシーン、私、号泣。我ながらドン引き…。他で書いている「戦国御伽草子」の誰かさんが死ぬシーンではただ黙々と書いていたのに…この差。うう、『彼』かわいそうだよー。『彼』が男型で産まれてきたのも、日紅と逢うからでした。なんで日紅は二人いないんだ。本当に。なんで『彼』はヒトじゃないんだ。なんでハッピーエンドになれないんだ…。いや書いてるの私なんですけど。
日紅
純粋無垢。暖かい腕の中でぬくぬくとしていたいと思ってた子。変化を恐れて、恋愛面で超お子ちゃま。でも女はやっぱり強いね。犀に告白されてからがはやかった。ちゃんと現実を受け入れようと頑張ってました。警戒心皆無なので、犀は苦労しそうです。日紅っていう名前はお気に入りです。なんかかわいい。
犀
き、嫌われっこ、でした…。一人だけ、犀に優しい感想を書いてくださった方がいたのですが、残りは見事に『彼』派でした。しかも最初の原案だと酷くて、初めての恋に戸惑ってる『彼』に向かって、「おまえ、正直邪魔」とのたまいます。休む暇なく「つーかアヤカシってなんだよ。四千年生きるって?ハッうさんくせぇ」と攻撃の手を緩めない!そして恋愛に目覚めたばかりの恋敵を滅多打ちに追い詰めます。このままだと犀が超顰蹙かいそうでかわいそうでやめました。でももともと恋って盲目なものですよね。綺麗なところもきたないところも併せ持つものだと思います。書いているうちに犀の性格も丸くなってきたので、ちょっといい人になって、今の話になりました。
書いているうちに、何度も何度も、「幸せな短編を書いてあげたい」「パラレルストーリーでいいから幸せに…!」と思いましたけど、それは、やっぱり、違うんですよね。彼らの物語はもうこれしかないんです。人生が一度きりしかないように。いくら選択が間違っていても、後から悔やんでも、未来から過去はかえられない。あしたを見ていくしかないんです。幸せな短編書くとしたら、やっぱり、過去の話かなぁ。パラレルストーリーは以上の理由で自主的には書かないと思います。リクエストぐらいかな…。
…なんて長々書いていると終わりませんね。とりあえず、ここまでとしておきます。後から何か付け足すかもしれないですけど。
感想や、ひとこと、「どうして『彼』死んじゃったのーばかー」でも何でも頂けると嬉しいです。お待ちしております。
勉強不足で稚拙な乱文ですが、本当に、本当に、読んで頂いてありがとうございました。
50まい


