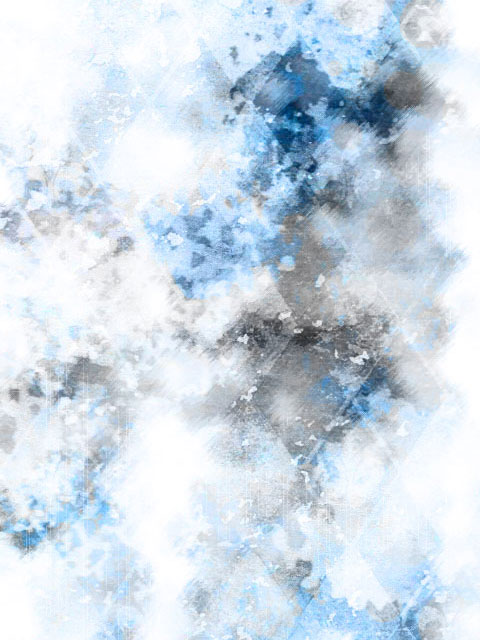
同級生
あの同級生を特別恐ろしいと感じたことは無いが、どういうことか私は彼女を視界に入れる度に、人では無いものを見てしまったような気持ちの悪さを覚える。
よく聞くような苗字と当たり障りのない名前の彼女は、私の斜め前の座席でそれなりに授業を受けている。その痩せた背中、黒々とした髪の毛、彼女の要素全てが、他の女子高生とはまったく違うそれに思える。たまに目が合ったりしたならばその日は一日中、居心地の悪い気分が続く。
幸か不幸か、接点はほとんど無い。同じ組になってから、二言三言業務連絡のようなやり取りをしたことがあるだけだ。彼女の異常性を確立し得る何かを知っているわけでもないのに、自分でも可笑しいとは思う。けれども同時に、私以外は誰も彼女に対してそんな考えを持ったりしないというのも、可笑しいと思う。口にはしないけれど。
表情が乏しいのは彼女の特徴のひとつとして挙げられる。とは言え、友好的な級友が気まぐれのように話しかけてくれば取り留めの無い会
話で対応するくらいの社交性はあるようだ。その如何にも巧妙な生き方も、私にしてみれば気味の悪いものである。
だからこそ、今こうしてぼろ雑巾のように転がっている彼女の姿というのは不謹慎ながらある意味私を安心させた。
なんでもないようなある夕方、下校しようと図書室から教室へ戻ってきたら偶然と必然が重なったような奇妙な光景が広がっていた。
詰まるところ、彼女が全身にかすり傷や痣を乗せて、床に倒れ付していた。何があったのかなど見当もつかず、だけどそれを放っておけるほど図太くもなかったので、そっと彼女の顔を覗き見る。彼女は私の存在に気づくと、笑った。
切れた唇に痛々しく血が滲むのも気にせず、彼女の口元が緩やかに弧を描いた。その瞳は淀んでいるように見えて、そこで初めて彼女を怖いと思った。どうしたの、と本来ならば私が言うべき台詞を彼女が吐く。赤い舌が唇の隙間から覗いた。やっとの思いで、何も、と呟けば、ふぅんとまるで拘泥しないような答えが返ってくる。
まるでぼろ雑巾だった。誰に何故やられたの、とか、訊けばいいのだろうけれども、それすらどうでもいいと思えるほど、彼女の有様から目が離せなくなっていた。
彼女は傷つければ傷つく、普通の人間であるという確証がそこにあるはずだった。しかし彼女は今、私を床から見上げて、笑っている。何よりもまずその事実が痛烈に私の意識を捕らえて離さなかった。
私の名前を呼んだ彼女の、声が目が口が身体が今や全てが恐ろしく思えて、私は咄嗟に彼女の腹を蹴り飛ばしていた。拍子抜けするほど軽々と彼女は傷つき、それでもなお、私をあざ笑うかのように私を呼ぶ。
その場に立ち尽くしながらも、混乱する脳内を鎮めようとするが、彼女の掠れ声がそれを阻む。今まで感じてきた不信感が、ぞわぞわと全身を駆け巡り、警報を鳴らす。おかしい。変だ。彼女は何だ。
床の上でくの字になっていた彼女が、ゆっくりと体制を変え、仰向けの状態で天井を見つめていた。その顔からもう笑みは消えていて、代わりにあったのは、深海のように底が見えない無表情。
瞬きと瞬きの隙間で、彼女の正体を見た。
同級生


