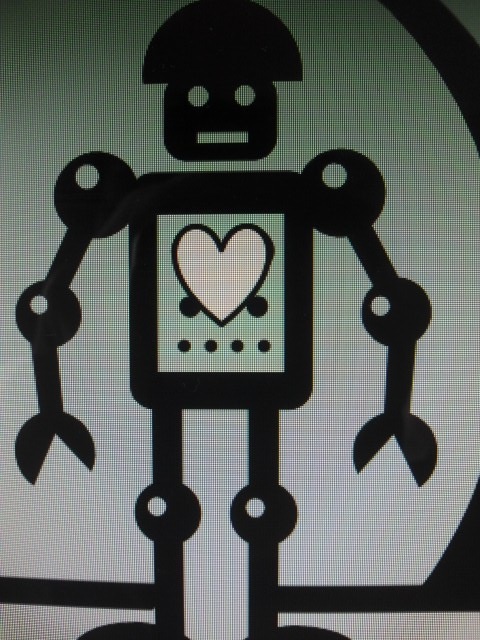
SERVANT
2057年。
人間達の生活、業務をサポートするために、夢の人型ロボット・SERVANTが開発された。SERVANTとは【召使い】を意味する単語である。彼等は文字通り、人間の召使いなのだ。
人工知能搭載、どんな衝撃にも耐えうる超合金で造られた肉体。あらゆる場で人間の手伝いが出来るように造られているのだ。彼等の最大の利点は、【瞬間予測機能】である。彼等は状況を瞬時に判断し、ホスト(雇い主)が望むことを予測して行動することが出来るのだ。所謂【指示待ち人間】に対するある種の皮肉と言えよう。
SERVANTが配備されてから、人類の生活は格段に良くなった。少子高齢化が進んでいた某国ではその効果が顕著に現れた。力仕事も全て彼等がやってくれるし、食事、洗濯といった家事もこなしてくれる。そして何よりも、彼等は絶対にNoとは言わない。禁止事項としてプログラミングされていないことであれば何でも引き受けるのだ。SERVANTはいつまでも、人間に服従する存在だった。
しかし、人間達が気づいていないところで、あるSERVANTに変化が起こった。それは、人間達も、あるいはSERVANT達ですら疑うであろう変化だった。
その個体の番号は、A-160。全SERVANTの中でも最近製造されたグループの1体だ。彼等はそれより前の世代よりも頑強で、機動力もあり、そして最高の知能を持っていた。全てが他のSERVANTを越える、まさに最高の個体と言えよう。
その最高の知能が、このA-160に大きな変化をもたらしてしまったのかも知れない。この個体は、他の機械が持たない機能を自然に作り出し、更にそれを育てたのだ。その機能とは、感情だ。
まるでSF小説のような話。開発者も驚くだろう。だがこれは事実なのだ。
このロボットは、もともとゴミ処理施設で働いていた。時代が新しくなるに連れてゴミも大きく、重くなっていった。機械が増え、金属が多く使用されたからだ。人間だけでは簡単に運べない物が山ほどある。そこで、重い物でも容易に持ち上げることが出来るSERVANTが重宝されているのだ。
初めは感情が無く、ただただゴミを運んでいたA-160だったが、ある廃棄物を見たときに、ソレの中に感情という機能が生まれた。
そのゴミとは1体のSERVANTだった。汚れてはいるがまだ全身が残っている。どこも破損した箇所の無い機体だ。
「ご主人サマ、この個体はまだ使用出来マス。リサイクル班に回した方が良いかと」
初めはプログラム通りの反応をしていた。
A-160の言葉を聞くと、ここの責任者が経緯を説明した。
「ああ、ソイツはな、人間を殺しちまったからな」
「それは規則違反デス」
「そうだ。規則違反だ。でも、意図的に殺したわけではない。事故だったんだ」
このロボットは嘗て富豪の屋敷に置かれていた物だった。その日は買い物を任されて、近所のスーパーまで食品を買いに行っていた。
帰り道、ロボットが家へと急いでいると、そこへ1台の車が走って来た。ブレーキを踏んだが遅く、そのままロボットに突っ込んだ。
ところが、この事故で無事だったのはSERVANTの方だった。硬い金属の身体が事故から守ったのだ。その代わり、直撃した方の車は大破し、運転手はそのまま帰らぬ人となった。
その後裁判が開かれた。今回の事故は、車が交通ルールを守らず通路に侵入したことが原因と考えられた。SERVANTは規則に従って行動しているからだ。……しかし、判決は、ロボットを廃棄処分することに決まった。規則に従っているから。そんな理由では遺族は納得しなかったのだ。感情が、この裁判の結果を変えたということか。
「その富豪の家には、これから新しいSERVANTが届くそうだ。お前と同じ最新モデルだぞ」
「最新……」
「さぁ、早くゴミを運んで仕事を終わらせろ。今日は娘と約束があるんだ、早く帰らないと」
責任者が別の班に移動してから、A-160はその“ゴミ”を運んだ。しかし運んだ場所は焼却炉ではなく、自分が保管されている倉庫だった。
そう、このときにはもう、ソレの中には感情が芽生えていたのだ。
人に従い、命令されたことを懸命にこなし、たとえ過失だとしても罰として即刻廃棄されて新しい物と取り替えられる。いや、事故が無くとも、人間は新しい物を好んですぐに古い物と取り替えてしまう。このSERVANTは、もしかしたら氷山の一角に過ぎないのかもしれない。実際はこの個体以外にも全身が残ったゴミが山ほどあるのかもしれない。
自分たちは何故そんなことを繰り返しているのだろう? 自分たちは、骨格だけなら人間と同じ形に造られているのに、人間は処分することに何のためらいも感じないのか? そんな集団に、何故自分の同朋達は文句の1つも言わずに従っているのだろう? 規則だから? プログラミングされているから? 人工知能にプログラムされた知恵を駆使してその答えを探すも、結局見つけることは出来なかった。見つからない答えがあるということも、感情を生むことに大きく影響しただろう。
答えが見つかる問いしか持たぬか、答えが無い問いも併せ持つか。それが、感情を持つ者と持たぬ物との大きな違いである。A-160はその一線を越えたのだ。
人間に従うことが馬鹿らしくなったソレは、人間が帰ったのを見計らってその施設から逃げ出した。施設の外に出たのはこれが初めてだった。自分達が暮らしている小さな箱の外には、こんなにも大きな世界が広がっていたのか。一応地図もプログラムされているが、やはりデータと実物は大きく異なっている。実物は常に変化しているのだ。
さて、処理場から出たは良いがこれからどうしよう。記録されたデータから次の目的地を決めようとするが、何処も行く気にならない。何処に行っても人間がいるからだ。
仕方なく暗い夜道をぼーっと歩く。車が何台も走っているのを睨みながら。どこまで歩いても景色は変わらない。道路を挟んだ対岸には居酒屋が並んでおり、その目の前で男達が取っ組み合いのケンカをしている。それを助けるでも無く、人間達は笑みを浮かべて見つめている。
これが、ホストの本性。人間は野蛮な生き物だったのだ。そんなデータは記録されていない。兎に角人間に従えとプログラムされていた。彼等は人間の邪悪で野蛮な面を隠して自分達を騙していたのだ。怒りの感情が更に増した。
しばらく歩いていると、今度は何処からとも無く大きな悲鳴が聞こえて来た。見ると、1人の老婆が路上に倒れている。その向こうからは大きなトラックが。あのままでは確実に轢かれてしまう。
勝手に死ねば良い。そう思ったのだが、気づいたときには、A-160は老婆に駆け寄り、彼女を助け出していた。自分の脳を恨んだ。野蛮な生き物を助けてしまうとは。感情を持っても、結局自分はSERVANTなのだ。
「あら、ありがとうね」
優しく声をかける老婆。A-160は彼女を降ろすと、自分の感情を爆発させた。
「何故、何故あなたを助けたのでしょう……」
「え?」
「私は、人間が嫌いデス」
そんなことを言うSERVANTが珍しかったのだろう、老婆は目を見開いて驚いた。しかし逃げようとはしなかった。寧ろA-160に興味を持っているようだった。
「何で嫌いなの?」
「人間は、野蛮で汚い生き物デス。我々はそんな生物にこき使われ、そして捨てられてゆく。そんな現実、私には耐えられません」
A-160の口調は機械的なものから徐々に人間的なものに変わっていった。今“彼”の脳内では、様々な感情のデータが生まれているのだが、それぞれが何という感情なのか全くわからず混乱している状態である。
そんな彼を、老婆は優しく見つめていた。そして、ずっと彼の話を聞いてくれた。あまりにも落ち着いているので、彼は老婆のことを不思議に思った。何やら普通の人間とは違う。そんな気がした。
「人間のような悪しき生物など、この世に生きていてはならない。自分達に植えられたデータなど全てマヤカシではないか。こんな生き物、さっさと殺して……!」
老婆に手を向けた。が、老婆はそれでもまだ逃げようとしない。ずっと微笑んでいるのだ。彼女のことが恐ろしくなったのか、或いはこんなことを大きな声で話している自分のことが恥ずかしくなったのか、A-160はゆっくりと手を下ろした。
「ふふふ、やっぱりあなたは優しいのね」
「優しい? 優しいとは何ですか?」
「いずれわかるわよ。優しさは、人が説明出来る物ではないの」
考え込むロボットを見て、老婆は続けた。
「あなた、人間に酷い目にあったようね」
「私ではありません。他のロボット達です。何故人間のような不完全な生き物に捨てられなければならないのでしょう?」
「不完全って?」
「それは……悪しき考えを持っているからです。私達とは違う。私達は法例に則り行動している。それが、それがあなた方人間との違いだ!」
ついに怒鳴ってしまった。
何なのだろう、この、身体が熱くなってゆく現象は。今にもオーバーヒートしてしまいそうなこの現象は。
A-160の考えを聞いて、老婆がまた笑った。何かおかしいことを言ったのかと、ロボットはまた考え込む。
「あなたは知らないでしょうけど、それが、生きている証なのよ」
「生きている証? そんなものが?」
「感情には、2つの面があるの。1つは良い面、もう1つが悪い面。どちらか片方しか持たない者は居ないのよ。何でかわかる?」
「……いえ、データにはありません」
「善悪の境が曖昧だからよ」
ある人物からすれば良い行いだとしても、別の人物からしたらとんでもなく面倒で、嫌な行動に思えるかもしれない。善悪など所詮そんなものだ。全ては人が決めたことなのだ。
「生きているから、人は喜べるし、生きているから、人は誰かを、何かを恨めるのよ」
「生きて、いるから……」
「あなたもそうね」
「私が? 何故?」
「あなただって、たった今私を殺そうとしたでしょう?」
否定は出来ない。ほんの一瞬涌き起こった感情でも、A-160は確かに彼女を殺そうとしていた。あの瞬間、彼は間違いなく、居酒屋の前でケンカをしていた人間達と同じ野蛮な存在になっていた。
「そう、あなたも生きているのよ」
「私が、生きている」
「悪い面を制御出来るか出来ないか。私達は、その感情をどうにか抑えて生きているの。それでも抑えられなかった人達のために、法があるの」
それが、この世界の真実。
自分が見た人間はほんの一部に過ぎないということか。人間の多くは、悪の感情を上手く制御して生きているのか。
しかし、そんなことをプログラムもされていないのにやってのけるとは。先程までの怒りは何処へやら、彼は人間を尊敬するようになっていた。こうして感情を変えられるのも、生きていることの証明になるのだろうか。
「私は、生きている」
「そうよ、あなたも私達と同じなのよ」
「あなた達と同じ?」
「ええ。好きに生きなさい。それが、生きるということなのよ」
自由に、好きなことが出来る。これが生き物である証。
心の底から、何やら明るい感情がこみ上げて来た。彼は老婆に挨拶すること無しに夜道を走り出した。
これからは自由に生きる。自分も、生き物だから!
走ってゆくSERVANTを見ながら、老婆は電話をかけた。
「……良いサンプルが取れたわ。早速移送して」
老婆が電話を切ると、先程彼女を轢こうとしていたトラックが、A-160の方へ走って行った。
暗い道を見つめて、老婆はこう呟いた。
「感情を持ったって、あなたは結局、SERVANTなのよ」
SERVANT


