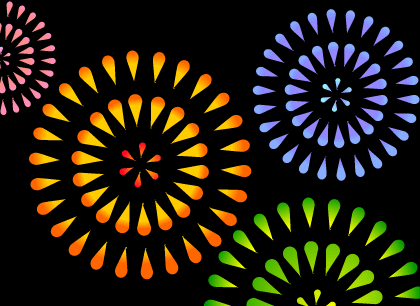
神様による合縁奇縁な恋結び!?
二日に一話更新
一期一会の出会い
「ねえ菜那城。あなたは人の役に立つ、助ける神様になりさい。そうすることできっとあなたが困ったとき、助けてくれる人たちができるわ」
「うん!」
手足もまだ短い少女は、それでも元気いっぱいに振り回してうなづいた。
それを愛おしそうに見つめる少女の母親おぼしき女性は、そっと頭をなでる。その頭にはぴんっとした耳が二つ付いていた。
「わたしはできなかったけれど、あなたならできる気がするの。黄金色の髪を持ち、先祖から続く狐火の力を誰よりも強く持つあなたなら……」
「お母様、私、早く大きくなって人を助けるわ!」
「ええ、お願いね。きっと大きくなったらあなたは美人さんになるわよー! 私とあの人の子供なんだから」
そういって母親は我が子をこれでもかというほど強く抱きしめた。
その抱擁が最後の母の温もりになるとは、その時の少女は夢にも思わなかったのであった。
ミーンッ、ミンミンッ……ミーンミーン。
その日は8月上旬の暑い日だった。
セミの鳴き声が嫌でも耳にまとわりつく。森のにおいが鼻先をなで、かすかに吹く風さえモワッとしていて温かい。
そんな暑い日差しの中、古風が漂う大きな神社の社の前に1人の少女、杏璃が立っていた。
彼女の額からは汗が流れ、その汗をぬぐいながら手をあわせた。真っ黒な髪が時々吹く熱風によって揺れる。
杏璃はそっと瞼をおろし
「―――君へ想いが届きますように……あっ! いや今のは違くて、恋とかじゃなくてね!? その、ちょっと会いたいなーって…………ん? 恋なのかな、これ……」
誰もいな場所で誰かに弁解するように照れた顔で悶々と言い訳を述べる。そして、そっと胸に手を当ててうなづく。傍から見たら珍妙な光景だ。
しかし自分が可笑しな行動をとっていることに張本人が気づくこともなく、それから杏璃は炎天下の中ずっと手を合わせ立っていたのであった。
その光景を遠くの木の上から見ていた者がいた。
その木は並大抵の者が登れるような木ではなく、とてもとても高い大イチョウの木だ。しかしその者は、何食わぬ顔で中央付近に腰を下ろしている。
「さっきから何分ああしてるつもりなの? こんな暑いのに苦労なことだわ」
言葉はあきれたようなふいんきが出ているが、言葉とは裏腹にその者の瞳には心配そうな色が出ていた。
灼熱な太陽の下、その者はおかしなことに汗の1滴も流れてなく、奇妙なほど白い肌だった。
遠く薄れる意識の中、杏璃の頭の中には思いをよせるあの人の顔が回っていた。
「あっ ――君、お願いっ待って!」
杏璃は思いを寄せる少年を追いかけ手を伸ばす。しかし少年は暗闇へと消えてしまう。
「お願い……待って…………!」
そこで意識は途切れ暗闇の中に杏璃は飲まれていった。
ふかふかとした触感、この何とも言えないお日様をたくさん浴びたようなにおい。
「ぐふふっふふっ……えへへー」
杏璃は夢と現実のはざまにいるのか珍妙な声を漏らした。
「いい匂い……幸せだなあ~」
眼を開けた途端、天使の羽のようなふっくら枕に思いっきり抱きついた。
「なんなの、このフカフカ感っ! 清潔に選択された洗剤と太陽の匂い、崩れていない完璧な枕の90度、45度のライン。枕愛好家の、この私が普段使ってる枕より素敵かもっ!」
あまりのフカフカ加減に涙を流すように感動した。今頃になって本当に自分が枕が大好きなのに気づく。
目の前の枕に気を取られすぎていたせいか、まったく周りは見えておらず、頭上から聞こえた鈴のような声にびくりと肩を揺らした。
「おはよー。そんなに琥珀が洗濯した枕が気に入ったの? なんだったらあげようか、それ」
のんびりとした口調を聞いて、夢の世界から抜け出し、はっきりしない意識を集中させながら杏璃は起き上がった。
「くれるなら是非とも頂きたい代物ですけど……いいんですか?」
のびのびと手を上に伸ばしながら釣られてフレンドリーに返す。少しずつ鮮明になっていく意識の中、杏璃はあたりを見渡した。
「あれ、ここどこ……あたしの部屋じゃない? じゃあなんで私は寝てるの……?」
杏璃は見慣れない布団の上に寝ていた。記憶という名のピースが、頭の中に一つずつ埋まっていく。
「…………っ!」
最後の一つのピースがはまった瞬間、ぱっと目を見開いた
(そうだ! あたしは神社の前で倒れたんだ!)
自分がここに寝ているわけを思い出し、もう一度辺りを見渡す。出会ったことのない枕を拝められたのも、のんびり口調で誰かと会話したのも事実なのだ。
急いで身なりを正して正座をすると、目の前の者に座っているのんびり声の張本人を見た。
「私の神社の前で倒れていたから運こんだの。ちょっとした貧血と熱中症よ。寝てれば治るわ」
体勢を整えたがいまいち状況把握に欠けている杏璃に、のんびり声の張本人は笑って答えてあげた。
「そうなんですか、ありがとうございます!」
杏璃は、はっとして頭を下げる。この素早さは父直伝だ。
助けてもらったらまず礼っ! と、父に昔から耳にタコができるほど言われてきのだ。
「いえいえ、人として当たり前のことをしたまでだから。いや……私の場合は人に入るのかな?」
うーんと首をかしげてぶつぶつと呟く自分を助けてくれた恩人に、杏璃は心からの笑顔を向けた。
「助けてくださり、本当にありがとございました。恥ずかしながら、ちょっと強く願い事をしてたため、辺りが見えてなくて……」
えへへと照れ笑いを浮かべる。それにもう一人の少女もそうだったのと優しく笑った。
それをきっかけに二人は初対面という心の壁が崩れたような気がした。歳が近いためか、同性のためか、もう緊張はあまりない。
「私は杏璃って言います。小林 杏璃(こばやし あんり)」
枕愛好家である杏璃はぺこりと頭を下げた。それに巫女服姿ののんびり声の少女もふんわりと笑顔を作る。
「私は菜那城(ななしろ)っていうのよ。親からこの神社を任されて神主をやっているの」
神主ということは既に神社の責任者の立場になっているということである。自分が今いる和室もきっとその神社の一角なのだろう。
「へーすごいですね! 私と同い年くらいなのに勤務してるなんて!」
尊敬の念を込めて杏璃は菜那城を見つめた。
それまでは良かったのだ。今思えば、なぜ早く気付かなかったのだろうかと思うし、あのまま気づかずにスルーしていればよかったとも思う。
しかし、菜那城をまじまじと見つめてしまった瞬間から、時すでに遅かったのだ。
まだ夢の中にいるのではないかと思った。少女は目の前の者の顔を見た瞬間、いや、頭にある『物』を見た瞬間硬直した。
「私があなたと同い年? それは違うわ。私は今年で116歳で…………」」
菜那城が話しかけるが、むなしくその声は少女の耳を通り抜けて行く。
そして少女は再度、今まで寝ていた、ふかふか枕に向かって倒れていった。
(まだ夢の中にいたなんて思わなかったな。さっ、元の世界に戻らなきゃ)
現実逃避の方向に目を向けながら目を閉じた。その姿は眠ったというよりは、気絶したようだった。
しかし、それも無理はない。なにせ、
「えっ! 杏璃ちゃん!?」
驚き声をあげて心配する者の頭の上には、キツネのような耳が生えたていたのだから。
この瞬間から、少女の現実的論理はきっと奪われてしまったに違いない。
神様は正直者
「ああっ! 倒れちゃった……まだ貧血気味だったのかなー?」
目の前で後ろへ見事きれいに眠っていく姿を、いや気絶していく姿を見て首をかしげる。
(どうしたんだろう?)
杏璃の隣に座っていた菜那城はもう1度少女に布団をかけなおしてやった
「ねーなんでだろう琥珀? やっぱり貧血かな。それともほかの何かかな」
自分のせいで気絶したとは全く思わず菜那城は頭を抱えた。そして後ろで壁に寄りかかりながら立っていた青年に問いかける。青年は腕を組みながら目を閉じていて、一見寝ているように見えた。だが億通(おくつう)そうにゆっくりとまぶたを上げて菜那城を見た。
「はあ? そんなこと知らねーよ」
短く傲慢な声が返ってきた。
「知らないってそんな無責任な……どうしよう。このまま、まだ寝せておけばいいのかな?」
投げ出すような答えに菜那城は少しむっとし、心配するような瞳で杏璃を見つめる。そんなつぶやきに琥珀は仕方なく近づいて杏璃の様子を見た。
「これ、気絶してんな……なんでまた気絶したんだ。そんな化け物でも見たわけじゃあるまいし……まあ、まだ寝かせとけ。起きたら甘いものでも作ってやるからあげろ」
青白い顔をした杏璃に的確な判断をし、用は澄んだように琥珀は部屋から出て行こうとした。しかし菜那城は琥珀の言葉を聞き逃さなかった。
「甘いお菓子作ってくれるの!?」
瞳を輝かせて詰め寄る。それをめんどくさそうに押しのけてびしっと言い放った。
「お菓子はあそこで寝転んでる病人のために作るんだ。お前に作ってやるなんて言ってない!」
「えー!!」
しなしなと耳が悲しげに垂れていくのがよくわかった。拗ねたように菜那城は杏璃の隣へ戻っていく。その時ふと、琥珀は違和感を覚えた。
「ん? 耳が垂れていく…………って、お前耳でてるぞ!!」
目を開き琥珀が声を上げた。
「ったく、また厄介ごとを増やしやがって……」
琥珀は自分の頭を指差しながら、深いため息をつく。
(え……? そんな馬鹿な、あれほど注意してたんだから……)
恐る恐る耳が出ているといわれた菜那城は自分の頭をさわってみた。。すると、そこには頭の上で気持ちによって動く自分の耳があった。
「あああー!」
杏璃が気絶したのは自分の耳を見たせいだと知り、失敗したことに気づいた菜那城はそれからしばらく琥珀と反省会に暮れた。
ここは菜那城神社。
古くから建っている大きな神社で建築400年以上にわたる。古風がただよい掃除の手なども行き届いていた。山の中に建っていて参拝者は1日30人程と少ないが、夏には大きな夏祭りが開かれ1月1日の正月には多くの人々が訪れる。
だが菜那城神社には神主がいなく巫女さんもいない無人だった。けれど神社はまるで人がいるように毎日きっちり掃除がされている。普通だったら気味悪がられるところだが祟りなんておこったことは一度もないし、昔からあるなじみの深い神社のなので、不思議だなあの一言で片付いていた。
そんな菜那城神社にまつられているのが狐だ。そしてもちろん、ここを守り管理するのが狐の神様、菜那城なのであった。
「んっん~」
太陽が沈み始める夕方の頃、少女はまだ暖かな匂いのするふかふかの枕から顔をあげ背伸びをした。そして先ほどのことを思い出し注意深く目を開ける。
(まさか本当に狐耳人間がいるなんてことはないよね……? きっとはあれはコスプレかなんかで)
菜那城にもう一度会って確かめようと探すが、そこには誰もいなっかった。
「……あれ、もしかして今までのは全部私の夢? まあ、この神社に誰かいるとこ見たことないし……」
一人で悶々と呟く。頬をつねってみるがしっかり痛みは感じるからいちよ今は現実なようだ。
「結局さっきの会話は私の頭の中で繰り広げられた夢だったの……?」
実際に自分は知らない部屋で枕にすがりついて寝ていたわけだが起きたのは今で、先ほどのは夢の中で起きたと仮設すると筋が通った。そうすると菜那城は自分の中で考えた創作人物となる。
「きっと誰かが運んでくれたんだろうな。菜那城さんじゃなくて……耳がついてる人なんているはずないもんね!」
そう一人で納得づけるとなんだか悲しくなった。
(もう少しだけ、おしゃべりしたかったな)
あの人懐っこそうな瞳が懐かしく思えた。自分の創作した人物とはいえ美しい子だった。その時目の前の障子に影が映った。
(私を助けてくれた人かな?)
首をかしげて障子に手を伸ばすと、杏璃が開ける前にゆっくりと開いた。障子をつかんで開く手は手はしわくちゃだ。さぁーと血が引いていくような感じがした。
(えっ、これっておばあさん? でもこんな骨ばってるものなの)
ブルっと鳥肌が立つほどその手は細く気味が悪かった。そっと開かれていく障子から次に醜い脚と長い髪が見える。乱暴にとかされたような髪はお世辞でも清潔とは言えなかった。冷や汗が額に浮かぶ。
(悪霊退散! これって絶対人じゃない!)
伝わってくる嫌な空気に杏璃は自分と同じ人間ではないことを悟った。先ほど現実だと頬をつねって確かめてしまったせいで、これもまた夢だとはのんきに構えてられない。むしろ先ほどのほうがよかった。これじゃあ天国と地獄の差だ。
「い、いやっ!」
怖いあまり腰が抜け、杏璃は座ったまま一生懸命後ろに下がった。背中を壁につけると壁が異様に冷たい。目の前の何かはいきなり狂ったように障子を乱暴に開いた。
「きゃああっー!!」
怖さのあまり固く目をつぶって腕を振りました。
「杏璃ちゃん?」
――ぴょこっと顔を出したのは目を丸くした菜那城だった。もう不気味な姿はない。
(え? 彼女って私の夢の中の人物じゃないの?)
へなへなと緩まっていく緊張とは別に、ふとあることに気づいた。先ほどは座っていたため上半身しか見えなかったが、今は立っている菜那城を見てみると自分とは違う神秘さがただよっている。
キャラメルとクリームを混せたようなキツネ色の髪を腰まで下し、目はルビーのように赤い。そして肌は純白だ。神社の巫女さんが着ているような着物風の衣装にはとてもよく似合っている。少し釣り目な感じだがくりっとした大きな目をしていて人懐っこそうな笑顔が目を引いた。
今はまだ可愛らしいにとどまるが、二十歳を超えたら美しい娘になるのではないかと期待させるような容姿だ。
「どうしたの、そんな丸い目をして……ああ、意地悪をしようとしてた髪垂れ女は蹴り飛ばしといたから安心して! まだ気分は悪い?」
元気に寄ってきた菜那城に杏璃はしばし呆然とした。今わかることは二つ。これは夢でなく、菜那城も自分が作った創作人物などではないこと。そして何か不気味なものを蹴り飛ばしたと爆弾発言を菜那城がしたこと。
「か、髪垂れ女……?」
自分の声が情けなく震えていることに気づいた。
「ええ、長い髪で執拗にまきついてくるという厄介な妖怪よ。よくここに来る人間に悪さをするの。驚いた?」
「そりゃあもちろん」
まだ先ほどのこと思い出すと寒気がする。しかし菜那城はけろっとした顔でお饅頭のようなものを渡してきた。
「琥珀が作った白あん饅頭よ。中は真っ白な雪のような白あん、外は甘さ控えめな茶皮」
甘い匂いに誘われて一つ手に取ってみる。口に入れてみると、ほろりと崩れあんの甘さが広がった。
「おいしい……」
凍りついた心を溶かすように、杏璃は自然と微笑んでいた。それに満足げに笑って菜那城も一気に二つ、お饅頭を口に頬張る。そのリスのような口に杏璃はつい忍び笑いが漏れた。
「えっなに!? 私何かおかしい?」
お饅頭を飲みこみ、もう一つと手を伸ばしていた菜那城はその手を止めてくすくすと笑う杏璃を不思議そうに見つめた。けれど益々笑いは大きくなっていく。
「ふっふふ。だって菜那城さん、リスみたいだから」
「そうかしら? まあ、琥珀にはそんなに口に物を詰めるなとかよく噛んで飲み込めとか言われるけど……」
うーんと悩む菜那城を杏璃は穏やかな目で見つめた。話すが手は止めず、やはりむしゃむしゃと菜那城はお饅頭をほおばった。それを眺めているだけでおなか一杯になってしまった杏璃は、菜那城に一つ、真面目な顔で質問した。
「菜々城さん、先ほど私が眼にした耳は本物ですか?」
今はもう影もない菜那城の頭上を見る。その話を切り出した途端、菜那城はお饅頭を食べる手を止めた。
「あっあれは、コスプレっていうやつよ! ほら、耳をつけたくなる時ってあるじゃない!? そういう感じ!?」
明らかに共同不信となった菜那城に杏璃は眼を細めて見極めようとする。
「だから本物なんてことはないのよ! そう、この世界に妖怪なんていないしー!」
目を泳がせながら話す菜那城を杏璃はもういいというように、止めた。
きっと目の前にいる彼女はどこまでも正直な人間なのだと思う。自分に正直で他人に正直。それは時として悪く出てしまうが、今の杏璃にとって菜那城の正直さはすごくいいものに思えた。
「菜々城さん、もういいです。お饅頭おいしかったです。ありがとうございました。また今度お礼に来ますね」
急な会話のおわりに菜那城は、え?と聞き返すが、杏璃は納得したような笑みを浮かべお礼を深くすると部屋から出て行こうとした。別れにしては素っ気なさすぎるが、これ以上菜那城の領土に入ってはいけない気がした。
「――杏璃ちゃん……もし私が狐の妖怪とかだったら怖い…………?」
障子に手をかけたとき、ぽそりと小さな声で菜那城が聞いてきた。それに杏璃は心からの思いを込めて
「怖くなんてありませんよ! むしろ菜那城さんみたいな可愛らしい方が、かっこいい狐の妖怪さんだったら嬉しいほどです!」
と笑顔で言った。それに菜那城は眼を見張るように開いた後、今にも泣きそうな笑顔を漏らした。
聞いた話によると菜那城は50年ほど前からこの神社の神様をやっているらしい。その前は親が神様をやっていたらしい。神様に代交代があると知り、杏璃は少し驚いた。
それからもう菜那城はしっぽや耳を隠すことなく、杏璃もその毛並みの良さに歓喜してモフモフさせてもらった。
「狐の毛並みってすごいんですね! すっごくサラサラ……」
まだ手に残る感触に浸っていると、褒められて照れたような菜那城はそんなことないと首を振った。
「琥珀のほうが白くて素敵よ。あれほどの毛並みはきっとそうそういないでしょうね……」
まるで夢を見るように菜那城は呟いた。それに杏璃は首をひねる。
「琥珀さんってどんな方なのですか? 確かさっき、お饅頭を作ってくれたのが琥珀さんとか言ってましたよね?」
「ええ、そうよ。琥珀は料理が上手でいつも家事全般をこなしてくれるの。いわば家族みたいな? それでね……」
その時障子が開いた。一瞬先ほどの髪垂れ女かと体を強張らせたが、どうやら違うらしい。
シンプルだが素人の杏璃にも上品な布だと分かる着物、さらさらと流れる銀髪。障子から現れた男に杏璃は目を奪われた。
「あなたは……?」
「いいところに来たね! これが琥珀。彼は狼なの。母の代からこの神社に努めてもらってるわ」
笑って紹介する菜那城に杏璃は呆然と整った顔の男を見つめた。
初恋の君
「杏璃ちゃん? おーい」
しばらく呆然と琥珀を眺めていた杏璃は、はっと菜那城の声で我に返る。自分が琥珀に見とれていたのだと認識すると顔が赤くなった。
(なんで……私には――君がいるのに琥珀さんを……もしかして私って面食い!?)
穴があったら入りたい気持ちに駆られていると、琥珀がじっとこちらを見つめている、というより睨んでいた。
「なんだ、元気になったんだったらさっさと子供は家に帰れ」
氷のように冷たい声に杏璃はぽっかりと口を開けた。助けてもらった身なので反論はできないがあまりの言い様だ。さきほどあんなにおいしいお饅頭を作ってくれた同一人物とは思えない。外見だけに騙されるなと自分に言い聞かせていると、菜那城は誤解を解くように手を振った。
「杏璃ちゃん、今のは暗くならないうちに帰れって意味なのよ。ごめんね、琥珀は口が悪いから」
「違う、そのままの意味だ」
不器用だなーと笑う菜那城に琥珀は即答する。杏璃はどちらが本当なのか分からなかったが気持ち的に菜那城の考えで受け取ることにした。
「あの、先ほどのお饅頭ありがとうございました。とてもおいしかったです」
「……ふん」
冷たい態度に少しだけ苦手意識を抱きつつ、空のお皿を見て思い出したように告げた。それに琥珀はそっぽを向く。やはりただ冷たいだけの人なんじゃないか。そう思っていると琥珀は背を向けて部屋から出て行く。その背を眺めつつ、杏璃は嫌われてしまったかもしれないと少しだけ悲しく思った。
その時確かに聞こえたのだ。小さいが確かに琥珀の声が。
「そんなに気に入ったのなら土産に持って帰るといい。あとで言え」
口調はぶっきらぼうだが優しい言葉に杏璃は眼を見開いた。菜那城は琥珀の態度にくすりと笑う。そんな菜那城をぽかりと殴りつつも琥珀は去って行った。
「琥珀は本当に不器用だから、あまり他人にはその優しさが伝わらないの。でも杏璃ちゃんの言葉に喜んでいたわね」
「そうなんですか……私には全然わかりませんでしたが、琥珀さんっていい人なんですね」
自分の考えを新たに考え直すと、菜那城は向日葵が咲くような明るい笑顔で笑った。
「杏璃ちゃんならきっとわかってくれると思ったわ。ありがとう」
「いや、礼を言われるほどのことは……」
お礼を言われることを言った覚えはないのに菜那城は嬉しそうに礼を言う。なぜだかその瞬間だけ子供のような菜那城が琥珀のお姉さんのように思えた。それから話を変えるように菜那城は杏璃に問いかけた。
「お昼の時、倒れるほど真剣に願っていた願いことはなんっだったの? 話したくないなら無理に話さなくていいけど、杏璃ちゃんがよかったら話してくれない……? 私はあなたの力になりたいの」
いきなりの質問と切実な眼差しに杏璃は喉を詰まらせた。
「えっ…………それは」
絶対に誰にも話さないと決め、固く結んだ紐が簡単にほどけそうになる。どこまでも正直でまっすぐな菜那城はきっと誠実に聞いてくれるだろう。
(私の願い……菜那城さんになら話してもいいかもしれない)
なぜだか出会って間もない菜那城に話してもいい気がした。いまだ誰にも話したことのない願いだ。もしかしたら逆に会って間もなく、何も知らない者同士だからこそ話せるのか。
「少し長くなりますが聞いてくれますか?」
「もちろん」
短くうなづくと二人は部屋に座りなおし杏璃は小さく、だがしっかりとした声で語り始めた。
雨の湿気が重たく背中に圧し掛かる。雨上がり、真っ赤に染まった夕日を見つめながら杏璃はため息をついた。
「はあ……また失敗しちゃった。いつになったら失敗しないで吹けるようになるんだろう……」
6月の半ば。じめじめする梅雨の中、気持ちも一緒に沈み込み、家への帰る気力もなく杏璃は校庭のベンチに座っていた。
(まただ……)
心の中でまたしても深いため息をつく。これほどため息をついてくると幸福が逃げるだけでなく不幸が寄ってきそうだ。
杏璃は先ほどまで音楽が流れていた部屋を見た。少し前まで自分が部活動に励んでいた場所だ。自分の入っている吹奏楽部は全国クラスという有名なこともあって練習がとても厳しい。楽器を奏でるだけでなく基礎のランニングはもちろん、腹筋背筋、ペットボトルを使っての肺活量の鍛え。そんじょそこらの運動部より運動しているはずだ。文化部と言っても吹奏楽部という名の運動部だった。
それに加え、今の時期は3年最後の大会が近いということもあり空気がピリピリしていた。吹奏楽部は総全132人、その中大会に出るれるのは50人という少ない人数であって3年生全員に2年生から5人選ばれる仕組みになっている。
厳しい選抜の末、2年生の中の1人に杏璃は選らばれた。しかし喜んでいたのもつかの間、杏璃は最初の合同練習から失敗しまくり今ではメンバーチェンジもささやかれている。
「――っもうやだ! やだよ……」
右手に持ったフルートに涙が落ちる。悲しくて悔しくて、きつくきつく手が痛くなるほど握りしめた。
(練習だって人一倍やっているつもりなのに、なんで私だけっ)
時が経つごとにどんどん上手くなっていく同僚、先輩たちからの期待、選ばれなかった者の陰口。いろいろなものが杏璃の心をつぶそうとする。
心の中で不満を吐き出すと、また涙が出てきた。ぐしゃぐしゃになった顔を手でおおいながら声を殺して泣く。
そんな時バシッ! と大きな音がした。
「――っ!? 何の音?」
いきなり響いた音にはっとして顔を上げる。今まで気づきもしなかったグランドには1人の少年が立っていた。
少年は大きく足を振りかざしてバシッと無人のゴールにサッカーボールを打ち込む。
(下校時刻はとっくに過ぎているから誰もいないはずなんだけど)
自分のことを棚に上げつつ、首をかしげてベンチを立ちグランドのフェンスへ寄ってみた。目を細めてそちらを見る。
(…………もしかして、あれは柴田君!?)
少年の正体に杏璃は眼を疑った。杏璃と一つ違ったクラスの柴田 結斗(しばた ゆいと)だった。
すらりとした173㎝の身長に、少しくせっ毛のふんわりとした首まである髪。その体格はサッカーで鍛えられたのか細身でありながらたくましかった。
女子の中ではもっぱらのイケメン男子とささやかれファンの子も多いい。最近ではサッカー部の時期エースとまでいわれ注目されていた。だからと言って舞い上がるのではなく、その性格は誠実で明るく、子供のように無邪気に笑う顔はいつもクラスの中心にあった。
しかしいつも笑顔の柴田が珍しく真剣な顔つきになっているのに気が付いた。
(何をしてるの? 練習かな……?)
時も忘れて、ただ夢中になってボールを蹴る柴田を見続ける。するといつの間にか涙は止まっていた。
グランドの中で1人、額から流れる汗をぬぐいながら何本もサッカーボールを蹴りシュートの練習をしている。その光景を見ていると、優しく吹く風が柴田を優しく包み込んでいるように見え、真っ赤な太陽が応援しているように思えてきた。
(あんなに頑張って……汗だってかいてるし息だって荒い。あそこまでしなくても彼は上手いのに)
目の前の光景に杏璃は眉を寄せた。どうしても柴田がここまでして練習に励む理由がわからない。しかし何かが引っかかった。
(いや……違う。柴田君はあそこまで頑張ったからこそ上手いんだ)
頭を強く殴られたような衝撃を受けた。サッカーがうまい彼のことを羨ましがっていた先ほどまでの自分が恥ずかしくなる。柴田の一番すごいところはきっと自分に甘えず励めるところだ。
(私は頑張れていただろうか。甘えてはいなかったか)
杏璃は握りしめていたフルートを見つめた。先ほどの零れ落ちた涙はどこかへ消えている。
厳しい選抜で選ばれたとき、あまりにも嬉しすぎて自分の努力にうぬぼれ、家での練習が厳かになっていた。
(私はできなかった。柴田君ってすごいな。エースだって騒がれていたのに、それに甘えず一生懸命練習してる。私ができないことを柴田君はしている……でも、私もできるんじゃないだろうか? やらないだけで、やれるんじゃないんだろうか?)
自分に問いただすと、心のもやもやがすーと晴れていくのを感じた。
(私もやってみよう)
瞳の奥の何かがきらめく。杏璃は握りしめていたフルートを再度見つめ口元へと運んだ。
「すっ」
息を吸い込み杏璃はメロディを紡ぎはじめた。音が校庭中に響きわたり、そよ風が流れ、今にも花々達が歌いだしそうだ。先ほどの風も太陽も杏璃に味方してくれているように思えた。
流れ出る旋律に身を任せていると大地が共鳴し、心も一緒に動き始めた。
――しかし
「ブビッ」
っとフルートから変な音がでて、世界は一瞬にして崩れ去った。また先ほどと同じ景色に戻る。
(はあ、まだまだか……)
変な音を出したフルートを見つめながら杏璃はため息をついた。だが少しだけ先ほどと違った何かの違和感を覚えた。そう、世界は先ほどよりもきらめいている。
それを感じ取り感動に身を浸していると子供のような無邪気な笑い声が耳に届いた。
「ふっ、あははははっ」
(――なっ!)
一瞬驚き、状況を理解してから頬をふくらませる。
(私がいくら下手だからってなんなのよ。人のことを笑うなんて!!)
声のした方を睨(にら)みつけると、そこには練習の足を止めた柴田がこちらを向いて笑っていた。そしてこちらの視線に気づいたのか笑顔のまま近づいてくる
「うわわわわっ」
想いもしなかった事態に変な声をだし硬直する。先ほどの怒りはどこへやらすっ飛んで行った。
「ねえ、今のって吹部でいつも吹いているやつ?」
きれいな声だ。澄んでいて青い空を思わせる。
「う、うん」
いきなりの言葉にあたふたしながらうなづいた
「やっぱり! でも、なんだか今のはいつも聞いてるのと違うなって気がして」
(……え……っ! どうゆう意味よ、何が言いたいわけ?)
杏璃は「普段の吹奏楽部よりひどい演奏」と受け取り怒りが戻ってきた。しかしそれは違ったらしい。
「なんだか今のはとっても元気がよかった。俺はいつも聞いてるのよりそっちの方が好きだな」
春風が吹いたような優しい笑顔に杏璃の思考は一度停止した。頭の中を「好きだな」の言葉だけが回る。時間が経つにつれ、先ほどの言葉が頭に入ってきた。
「うぅ~!」
赤くなる頬をおさえ見られないように下を向いた。これが世に聞く女子を瞬殺にするという王子様スマイルなのだろうか。
「ん? どうしたんだ小林」
ずっと頬に手を当てながら黙り込んでいる杏璃を柴田は不思議そうに見つめた。それによって更に緊張が増す。
「あっいや、えっと……――ちょっとタイム! 見ないで」
グルグルとまわりだした視界にとっさに柴田に背を向けた。それから少し冷静になると自分が言った言葉に青ざめていく。きっと今頃柴田は自分をおかしなやつだと思っているだろう。誤解を解きたくて振り返ると柴田はおなかを抱えて笑いをかみしめていた。
「あははは。女に見るなって言われたの初めてだ。小林って面白いんだな。俺、仲良くなってみたい」
明るい笑顔と言葉に杏璃は胸が跳ねた気がした。そっと控(ひか)えめに柴田を見つめる。
「私なんかでよければいいけど……どうしよう? 仲良くなるって、まずは相手のことを知っていくことから始めるのかな?」
本気で悩む杏璃にまたしても柴田は笑い、うなづく。
「そうだな。じゃあ、その手に持ってる笛のこと教えてよ。綺麗で興味がある!」
「笛じゃなくてフルート。聞くならちょっと話が長くなるから座って聞く?」
気を使って今まで座っていたベンチを指さす。
「どんだけ熱狂的に話すんだよ。じゃあ、心行くまで話してください」
「なっ、聞きたいって言ったの柴田君じゃない!?」
「うそうそ、ごめん話して」
いたずらな顔で笑った柴田はベンチに腰を掛け杏璃に隣をすすめた。それに杏璃は仕方なくもフルートを褒められ興味を持ってくれたことに嬉しくなり、喜々として説明を始める。
その時はまだ気づかなかった。柴田へと抱いた感情、それは杏璃が初めて経験するものだ。
けれどそのことよりも今は柴田の笑顔を見ていたかった。
次回 第四話「秘密の時間」
神様による合縁奇縁な恋結び!?


