
遠い日の暖かな約束
~0.はじまり~
~~~~~
遠い日の記憶…
幼い私は誰かと手をつなぎ、暗く長い道を、ただ永遠と歩いてゆく。
先すら見えない闇の世界を、ただひたすらに歩き続ける。
その先に何があるのかすらわからないのに…ただ、歩き続ける。
幼き私は、そんなおかしな状況であるのにもかかわらず…満面の笑みをこぼしていた。
一寸の曇りのない、綺麗な笑顔だった。
その笑みは、繋いでいた手の先にいる人物に向けられていた。
腰の高さまで伸びる黒い髪をしたその人物の表情は、はっきりと見ることは出来ない。
顔の特徴すら伺えない程、周りの世界が暗いのだ。
そんな不確かな相手に、私は微笑みかけ、時に歯を出して笑っている。
手を繋ぎながら、永遠と暗闇の世界を歩く…
私自身、この記憶がいつのもので、何が起こったのか全く覚えていない。
しかし、その記憶を思い出すたびに感じる。
ただ、懐かしく…
ただ、恋しいと…
あの繋いだ手の先にある暖かさ…
指先を絡める、こそばゆさ…
説明が出来ない安心感を感じていたからこそ、私は笑っていられたのかもしれない。名もわからない黒髪の女性から、愛情という物を感じることができていたから…
しかし、そんな愛情を受ける事はもうないだろう。
この先、一生をかけても手に入れる事が出来ない。
そんな気がした。
~~~~~
~1.灰色の世界~

~~~~
深々と降る雨の中を、色とりどりの傘が歩いてゆく。
道端に咲く紫陽花が、鮮やかな傘の色を引き立てているように感じる。
でも、色鮮やかな傘とは違い、私の心は灰色一色だった。道端に咲く紫陽花ですら、今の私の心を潤すことはないだろう。
梅雨の時期、私は他の人とは違う憂鬱さを感じ、一日を過ごしている。梅雨は大地を濡らし大地に恵みを与えるというが、人間社会とっては洗濯物が乾かないことや沢山の不都合が生じる。そのため、世の人々は梅雨を憂鬱に感じ、先にある夏を恋しく思うのだろう。…もとい、そこで相合傘という行為をしている恋人同士を除いてだが。
私は在学している高校に向け歩みを進める。学校は街で一番高い丘の上にあり、登校時は長々と続く坂を登らなければならない。何故こんなところに学校を作ったのだろうか…それは、私がこの学校を志望した理由にあった。
私の通う学校は、よくいえばそれなりの品格のある学校で、街を一望できるよう、丘を丸ごと学校で買い取っているのだ。学校から見る景色は、それはもう絶景で、街だけではなく隣町に隣接する海すらその目で拝むことができるのだ。他にも、丘が丸ごと学校のため、校舎はもちろん各種スポーツの施設もあり、勉学以外に部活動にも力を入れている。また、ラウンジやテラスなどの施設も豊富にあり、志望者は女性が多く志望率もこの街一番の高さを誇っている。
ここにいる私もそれが理由でこの学校を志望した一人になる。
当初は別の学校を希望していたが、両親の強い勧めで気持ちが変わり受験することになった。
いざ受かってみると、思っていた以上に過ごしやすい印象を受けたが、結局はそれだけの存在だけであった。楽しみにしていた学校生活も、楽しく過ごせたのは最初の1週間だけ。それ以降、私ははずっと灰色の日々を1年間過ごした。「学校から見る夕焼けは、みなさんの心を癒し、明日への原動力となるでしょう。」入学式に理事長先生が言った言葉と実際の夕焼けは、私以外の生徒の心を掴んだであろう。
でも、その景色を私は見ることは出来ない。
幼少期、私は不慮の事故で目に怪我を負ってしまった。バスに乗ろうとした私の目に、会社員のおじさんが持っていたボールペンが当たり、角膜を損傷してしまったそうだ。私がかなり幼い時の出来事なので、私自身はその出来事を覚えていない。この話も、母から聞いたことだ。角膜を損傷してしまった私の視力は、著しく落ちてしまいほとんど見えない状態にまでなった。しかし、運良くドナーがすぐに見つかったため角膜移植に踏み切り、眼鏡をかけて何とか生活できる状態でになった。しかし、日によって目の調子が変わるので、見える日と見えない日がある。そんな目に、私は飽き飽きとしていた。見えていても目の痛みは消えないし、白目の部分が赤くなっているのを他の人に見られたくない。またある時は、太陽の日差しすら感じない暗闇の世界にいることもある。私の場合、見えたとしても夕方になれば目の疲労から夕焼けの光にすら痛みが生じるため、入学してから1年間、その夕日を見たことがない。
私の気持ちに沿うこともなく、私の目は気まぐれに状態を変える。
「あ、あいつ…」
「あぁ、あの赤目の…」
「本当怖いよね、いつ襲ってくるかわからないし…」
そして、私が見たくない物を見せつける自分の目に、悪意さえ感じてしまう。
~~~~
私のような角膜移植した人のほとんどが拒絶反応に悩んでいると思う。
拒絶反応は、白目の充血、目がかすみ、急な視力低下、目の周りが痛いという症状が体に出て、移植者を苦しめる。薬の服薬や目薬などで症状が緩和するが、私には当てはまることはなかった。どんな薬を試しても、症状が緩和することがないのだ。日常生活に多少の制限がつくものの、我慢できる範囲だったので、高校に入学するのを機に私は治療を辞めた。毎日の抗生剤の服用は忘れないし、それが大変だとは感じない。ただ、何度も何度も試薬を試しても、治らない痛みと目の色に諦めがついてしまった。治らないたびに、私の心は傷つき、心身共に疲弊していく。そんな生活は、もううんざりだ。
そうして辞めた治療後の私の生活は、前以上に人の目を気にする生活となった。「赤い目」を他の人に見られるたびに、怖がられ、恐れられ、私をよそ者扱いのように遠目で見る。そして、根も葉もない噂話を打ち立てて、私を罵る。彼らにとって、私は良い笑い話のネタでしかない。そんな噂話は、そもそも証拠に残らないため、イジメとして訴えることもできない。そんな私も、暴力を降られることではないため、気にしないようにしている。が、頭の中ではわかっていても、私の心はその度に傷つき、泣いている。この赤い目のことを話すこともできず、私は高校生活を日々傷つきながら過ごしているのだ。
~~~~
教室についた私は、まっすぐと自分の席に座る。私の席は窓際で、学校自慢の景色を一望できるポジションにいる。昔からくじ運だけは良く、幼少期はお祭りで一等を当てることが多かった。ただ、この席替えのくじ運は、私にとってありがた迷惑なものだった。見えない私にとって、この席は本当に嫌なことしか与えない。席だけではなく、学校自体が嫌な存在でしかない。
「おい、またきてるぞ」
「気味悪い目…」
「くる学校間違えてるよね~」
クラスに入る途端、私への非難が始まる。入学式から受け続けた言葉の暴力は、いつしか私の日常となった。今ではもうそれが生活の一部となっている。誰もが、私のことを化け物のように扱う。誰も私に合いの手すら差し出してもくれない。これが社会だと大人が言うのなら、私は潔く認める。だって、私は大人を知らないんだから…
しかし、今日は珍しくクラスの話題は私ではないことでも盛り上がった。
「今日くる転校生ってどんな子なんだろうね!」
「綺麗な女子なら良いよな~」
そう、この学校が出来て始めての転校生がくるのだ。ただでさえ、倍率の高い学校なので、転入試験となれば、もっと難しい試験であることは誰でもわかる。良く入試に失敗した人が転入を試みるが、大抵は転入試験前の課題で挫折する。入試を勝ち得た私たちですら難しい課題と試験らしい。それを勝ち、転入を決めた転入生にクラスはおろか全校生徒が盛り上がっている。私にしてみれば、本当にくだらないことだと思う。入りたくても入れない学校に、私たち以上に努力し、転入を勝ち得た人。ただ、それだけではないか。この学校の「設備に恵まれた過ごしやすい環境」というキャッチコピーと一緒。たかがそれだけのことだ。
盛り上がるクラスをよそに、私は窓のカーテンを閉め、眠りの世界に身を投じる…
~~~~
〜2.夢…その1…〜

〜〜〜〜〜
また、遠い日のような夢を見た…
今度の夢は、前回の真っ暗な世界とは打って変わり、山々の間を歩いている夢だった。木々が生い茂り、空は木と木の間から覗ける程度。太陽の光が暖かい木漏れ日となって道を照らしている。それは、ただの風景ではなく、一つの物語に出てきそうな神秘的なものだった。
麦わら帽子を被り、トレーニングウェアとトレッキングシューズを身に纏った人物は、神秘的な世界を歩く。そこには以前までともに歩いていた私の姿はなかった。そして、今歩いている人物が私ではないこともわかった。
…綺麗なブロンド色の髪と碧眼の女性だった。
その外国の女性と思われる人物は、白い杖を左右に振りながら歩み続ける。とてもゆっくりとした歩調で、周りの様子を伺いながら緩やかな斜面を進む。そんな様子は、まるで森に迷い込んだお姫様の様だった。そんなお姫様を、山の木々たちは優しく包み、彼女が目指す目的の場所へと導いて行く…
〜〜〜〜〜
〜3.出逢い〜
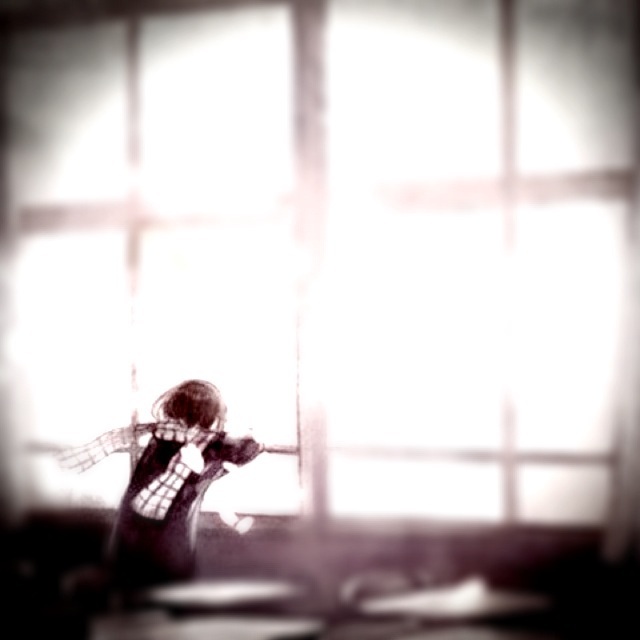
~~〜〜
…綺麗で暖かい夢の世界から、私は冷たく嫌な事に満ち溢れている世界に再び戻ってきた。元の世界に戻った私を、クラスはおろか先生すら冷たく迎えてくれた。つまり、私が目覚めたのは1時間目の授業中。良く寝てる事がばれなかったと、私は毎度驚いていた。おそらく、私には目のこともあるので、先生も気遣っているのだろう。でも、それはただのおせっかいでしかなかった。たしかに、私は普通の人に比べて疲れやすく、目の調子によって視力が変わる特殊な目をもっている。でも、調子がよければ見えるし、眼鏡があれば特に生活に障害になることはない。あるとしたら、クラスからの跡の残らない暴力。人には見えない、心の傷。枯れ果てた、私の感情。どうして、私は認められないのだろう…1人の人間として…
私も、1人の人間なのに…
少し弱いだけなのに…
ただ、それだけなのに…
1人の人として、扱われ、人として見て欲しい。私も、1人の人間だと認めて欲しい。私ことを…知って欲しい。そうすれば、きっと…わかってくれる。
…ちがう。
私に原因があるのだ。
先生も、みんなも、私に見られるのが嫌なのだ。
私の目に…
気味悪い、私の目に…
呪われた、私の赤い目に…
見られたくない。
こんな人を、わかろうとする人なんているのだろうか…
…いる訳がない。
この冷たい、灰色の世界では…
私は生きることができない…
1人の人として…
…なぜだか、今日はとても自虐的な日だ。ここまで考えることは普段はない。むしろ考えない様にしているはずなのに、なぜだろうか…
ふと、クラスの空気がいつもと違うことに気がついた。…みんなが、チラチラと私の方向を見ている。もちろん、その視線が私に向けられていないことはすぐにわかった。私は、静かに後ろを見た…
栗色で、腰まで伸びた髪…
白い肌を際立せる青い瞳…
傍にある白い杖…
そこにいたのは、夢で見た妖精のような女性だった…
「えっ…」
なぜ、ここに夢の中の人がいるんだ?そもそも、私の後ろには席などなかったはず…
寝ぼけた私の頭は、混乱しっぱなしだった。なぜなら、夢の中の人が、私の後ろにいる。普通なら、絶対にありえない。では、なぜなのだろうか…
「今も夢の中なのでは?」
…ちがう。枕にしていた私の腕が、ピリピリと痺れている。頬も圧迫され続けていたという感覚がある。
「寝ぼけた私の錯覚なのか?」
…普段こちらを見ないクラスメイトの視線が、私の方向に向く理由が見つからない。
…この人が、転入生。
これが行き着いた結論だった。
夢に出てきた人が、私の夢に出てきた…?これは、いわゆる予知夢というものだろうか?私はいそいそと辞書を引っ張る。
予知夢:未来のことを夢の中で見ることや、夢で見たことが現実となること。(Wikipedia参照)
…ちょっとちがう。なぜなら、私が見た夢は彼女が森の中を歩く夢であって、彼女と私が出会う夢ではなかった。これは予知夢と呼べないだろう…
「っ…!」
目ぼけた目で見ていたせいか、突然目に痛みが走った。あまりにも動揺したせいか、目の事もすっかり忘れてしまっていた。私は静かに辞書を机の中にしまい、目を休めるように閉じ、再び考えを巡らせる。
…。
私は遂に行き詰まってしまった。どう考えても、この答えを導き出すことが出来なかった。
私は、またゆっくりと後ろを見た。彼女の栗色の髪は、太陽の光に照らされ、一本一本が宝石のように輝いている。その髪だけに、大きな価値があるような美しさだった。白い肌を際立たせる青い目は、雲すらない青々とした空のように、私を包み込む。そこにあるのは、西洋のお人形と間違えてしまいそうな美しい女性だった。少女ではなく、女性。大人の女性が持つ、言葉では説明がつかない雰囲気が、そこにはあった。…ちょっと、過大に表現しすぎただろうか。私は恥ずかしくなり、前に向き直した。おそらく、今私の顔は赤々と熟したイチゴよりも赤くなっているに違いない。今まで、こんな風に人を見たことがなかった。他人は他人。自分は自分。自分の事しか考えていなかった私が、始めて人を羨み、見惚れた。それは、私にとって大きな衝撃だった。
赤く火照った顔を見られないよう、私は顔を机の上に組んだ腕の中にうずめ、再び夢の世界へと旅立った。
この後、私は彼女と話す事はおろか見る事もなく一日を終えた。
~~~~
〜4.痛み…〜

〜〜〜〜
学校から帰宅した私はまっすぐ自室へと向い、着替えることなくベッドに横になった。
あの後、眠りから覚めた時はすでに放課後で、クラスメイトの姿も後ろにいた転校生の姿はなかった。眠っている間に何があったかなど、私には知る術もなければその気もなかった。ただ、あの転校生に対し、よくわからない名残惜しさを感じていた。
これが寂しさというものだろうか…
今日は本当に普段と違った1日だった。学園創設初の転校生の存在、その転校生が女性の外国人だったこと、そして転校生の彼女が私の夢の中に出てきたこと。私には第六感というものはないが、流石に今日の出来事を見て今後の生活になんらかの変化が生じることが何と無くだが感じることができた。それがどんなことで何が起きるのかはもちろんのこと知るわけがない。良いことであるのか、それとも悪いことなのかさえも…。彼女には悪いが、今後の生活に変化が訪れるとするならば間違いなく彼女が関係していることが考えられる。彼女が私の夢の中に出て来たことが1番の理由だ。単なる予知夢なら、特に問題にすることはないが…たぶん、そんな単純なことではない。何と無くだが、そんな気がする。ただ今の情報量では、どうにもその答えを導き出すことはできそうにもなかった。
「痛い…」
そんなことをぼんやり考えているると、再び目が痛み出した。まるで夢や想像の世界から、苛立ちと不快感に満ちたこの世界へと引き戻したように…。私に夢や希望を持たせてはくれないかのように…。どうして、私だけこんな思いをしなければならないのだろうか…。こんな不快で、汚れている世界を私は見続けなければならないということなのだろうか。他の人は自分の理想や夢に向かって、頑張ることができる。人の汚いところや見たくないものから、目を逸らすこともできる。なぜ、私だけが現実から目を背けてはいけないのか…。なぜ、許してもらえないのだろうか…。
なぜ…
どうして…
その時、目から一筋の涙が頬を伝った。
「…ごめんなさい。」
私はいつも、宛先のない謝罪を口にしていた。謝れば、許してくれると思ったからだ。辛くて、悲しくて、情けなくて、誰かに助けて欲しくて…。…では、私は誰に許しを説いているのだろうか。神様?仏様?それとも嫌いな汚い世界に?
気づいて…
もう、私は十分苦しんでいるよ…?
これ以上苦しめて、この先の未来にいったい何があるの…?
毎晩同じことを考え、毎晩枕を濡らす私に、世界はいったい何を望んでいるのだろうか…
そして、いつも導き出されるひとつの疑問。
私は、何のために生きているの…?
そんな事を考えているうちに、すでに外が明るくなっていることに気がついた。また、寝ることができなかった。そう思い毛布を頭に覆い、眠りについた。今日も、枕は冷たかった。
〜〜〜〜
〜5.消失〜

〜〜〜〜
昨日の深々と降っていた雨は、今日になるとその痕跡すら残さず去っていた。その代わりにからりと乾いた、かつ熱々しい太陽の光が私の頬を照らす。…いや、こんがりと焼いているかのような暑さだ。空は雲一つない青々しく、太陽の光を遮る事なく広がっている。昨日とは違う理由でイライラな私の気分は、最悪の状態で学校へ向かっている。他の人にとってはただ暑さが鬱陶しいと感じるだろうが、私にとっては普段よりも眩しく世界が目に映る。目の負担は朝から最高潮なのだ。だから、イライラな気分になる。最悪の場合、強い偏頭痛が襲ってくるかもしれない。そう考えると本当に辛くて、家に帰りたくなるくらい悲しくなってくる。サングラスや日傘など対処を考えてはみたが、流石に学生の私がそんな事をするとその場で浮いている存在になることが目に見えている。そのため、私は一切の対処をしていない。自分の身体的負担をとるか、それとも精神的負担をとるか。いつも悩むが、最終的に身体的負担をとってしまう。なぜなら身体の傷は治っても、心の傷は治ることはないのだから…。
そんな心情が歩く歩幅を狭め、足取りを重くする。あぁ、家に帰りたい。学校行きたくないと思春期ならではの不登校児のような心境で心がいっぱいになる。…ほぼ毎日そう思う。今更ながら通信制の学校に行けば良かったと思う。人と関わるのは得意の方ではないが、それ以上に学校に行く事が苦痛でならない。それに、自分の目を見られ笑われる事もないだろう…。
本格的な偏頭痛の予兆から『本当にサボろうかな…』と、考えた時だった。遠くに茶髪ではない、明るい髪の色をした人物が目に入った。太陽の光に照らされ、一本一本が宝石のように輝き、白い肌を際立たせる空のような青い目。西洋の人形のような美しい大人の雰囲気をもつ女性。…それは、まさしくあの転校生だった。彼女は手に白い棒を持って歩いている。杖をつくような使い方ではなく、白い棒を左右に振りながら歩みを進めている。そのせいか周囲と彼女との間にはちょっとした空間ができていた。彼女の歩幅は狭く、一歩一歩をゆっくり時間をかけて進んでいた。まるで、彼女の周りにはゆっくりとした時間が流れているように…。気づけば、彼女と私の差が少しずつ近づいていた。さっきまでのせまき歩幅は、彼女に引き寄せられるように大きくなっていた。『い、いつの間にこんなに近くまできたんだ…』と思った時、自分の周りに多数の人影を感じた。彼女に近づいてしまったため、私はさっきまで離れていた学生の集団の中に入ってしまっていた。その途端、突然息が荒れ始めた。
く、くるしい…
私は歩くのを止め、道にの真ん中で止まる。周囲の目が一瞬で私に向けられた。
怖い…。
やめて…。
見ないで…。
私を見ないで…。
跳ね上がる心臓の音に、どんどんと荒れる始める呼吸。頭がクラクラし始め、だんだんと意識が薄れていくように感じられた。私は膝をつき、誰かに見られたくないがために地面にうずくまる。心拍も呼吸も乱れる中、遠くから誰かの声が聞こえてきた。
『だいじょうぶ…?』
初めて聞くその優しい言葉と共に、私の意識は暗闇の中へと消えていった…。
〜〜〜〜
〜6.夢…その2…〜

〜〜~〜〜
背の高いひまわりが僕の視界を埋め尽くすほどに広がっている。
皆が太陽の暖かなの恩恵を求めて、我を我をと一心に伸びているように見え、暖かな風が吹きひまわりは気持ち良さそうに体を揺らしている。空も海のように青々しく輝き、遠くの山まで見渡せるほどに快晴だった。
そんな景色の中に、なにやらうごめく物体が目についた。その物体は右へ行き左へ行きを何度も繰り返していた。よく見ると、その物体は麦わら帽子で、動いているのはその持ち主のようだった。その持ち主はよっぽど嬉しいのか、もしくはとても元気な人物なのだろう。そんな滑稽な動きをしばらく微笑ましく見ていたが、途端にその麦わら帽子は止まり、何かを見つけたのかどんどんとこちら側に近づいてくる。出てきた麦わら帽子の持ち主は、白いワンピースを身に纏った西洋に出てくるお人形のような容姿をした少女だった。その少女を抱き上げると、麦わら帽子から満面の笑みを浮かべた少女の顔が伺えた。
「________」
ぼんやりとだが、少女は何かを嬉しそうに話しているようだった。しかし、うまく聞き取ることが出来ず、私は少女の口の形をただ見ることしかできなかった。しかし、それでも少女は笑っていた。そんな姿をみている私も、不思議と胸が暖かな気持ちにみたされていく。
彼女と見る、この一面ひまわりの景色を、見れることに暖かな幸せを感じていた…。
〜〜〜〜〜
〜7.暮湖月 マリア〜

〜〜〜〜
…深い眠りから覚めた私の目の前には、無数の穴が規則的に並ぶ白い天井が広がっていた。そこが学校の保健室であることがわかるまでに、しばらく私は思考を凝らす必要があった。あの倒れた後、どうやってこの保健室にたどり着いたのかもわからなかった。あの時激しく乱れた呼吸は、既に落ち着いていてその不安感も既に消えていた。私は、いつまで惨めな思いをしなければならないのだろう…。ふと、隣に人影を感じ、顔を向けるとそこには…、あの転校生が座っていた。
「…起きましたか?」
彼女は西洋のお人形のようにお行儀良く座っている。その目は前に見た時よりも青く透き通っていて、私の心の奥を見つめているような目だった。
「びっくりしました。突然後ろで人が倒れたと大騒ぎになってましたし、沢山人が集まっている様子でしたので…。詳しくお話を聞くと、私のいるクラスの方だったので、すごく心配になってしまいまして…。お気分はいかがですか?」
…なんて、綺麗な声なんだろうか。私の耳にはその言葉よりも、透き通った美しい声しか届いていなかった。透明で、少しの濁りも許さない美しさが滲み出ているように感じ、ただその綺麗さに圧倒され、ときめきを感じていた。これぞ高貴な花と言わんばかりの美しさに、ただ見惚れるしがなかった。惚けていると、質問に対する応答がないため、彼女は首を傾け不安な表情をした。
「あの…大丈夫ですか…?」
「あ…、うん…。…ごめん。多分大丈夫…だと思う。」
恥ずかしい気持ちから、私はさっと彼女から視線をずらし、俯きながら答えた。久しぶりに人と話すためか、うまく言葉が出てこない。そもそも、声がうまく出せない。人は話すことをサボると、ここまで退化するのか。と、少しながら勉強になった。
ちゃんと伝わっただろうか…。
変な受け答えをして、彼女の気を悪くしてないか心配になった私は、ちょっとだけ顔を上げ彼女の様子を伺う。
彼女の顔には質問に対する回答が得られたことに喜びが笑顔となって滲み出ていた。その笑顔も、負担クラスの面々がする歯を出した品のない笑い方ではなく、太陽の優しい日照りのような品のある柔らかな微笑みで、それだけで私の心はドキドキと弾んだ。
「あの、1ーE組の方ですよね?」
「あ、あぁ。うん。でなくて、はい…。」
「自己紹介がまだでしたね。私は"暮湖月 マリア"と言います。えっと、父は日本人で母はアメリカ人のハーフですっ!あっ…。」
ですっ!って、声裏返ってるし(笑)
クスクスと笑う私を見て彼女は恥ずかしさを感じたのか、頬が少し赤くなっていた。
なんか、思っていたよりも可愛い子なんだろうな…。
「あっ、わ、私は…。」
と、続いて自己紹介をする。久々に話すと結構疲れる。そもそも、人と話すのはいつぶりだろうか。
彼女は、『これからよろしくお願いしますね。』と、優しく微笑んだ。私もほっと一息ついた。自分でもわからないくらい緊張していたのだろう。
しかし、私は小さな違和感を感じた。
ほんの少し、
本当に僅かだが、自分と彼女と視線が合わわない。
彼女の視線は私を見ているが、見ているものが私の目ではない。その目が見ているものは私よりも違うものを見ているように感じられた。いつもなら恥ずかしくて相手の目を見ることのできない私が、いつの間にか相手の目をしっかりと覗き込んでいた。
いったい、何を見ているのだろうか。
そう思った刹那、彼女は突然クスクスと笑い出した。
「ごめんなさい、あなたからの視線が強いものだから、恥ずかしくなって…。」
私は即座に目線をずらし顔を隠した。顔が一気に熱くなるのがすぐにわかった。
「ご、ごめんなさい…。」
私はなんて失礼なことを…。と、あたふたと動揺が隠せない。あまりの恥ずかしさと申し訳なさが混じり合い、いつしか私の目頭は熱くなっていた。もう、どうしたらいいかわからない…。そんな最中、不意に左腕が重くなった。少し困ったような顔をした彼女が、下を向いている私の腕を優しく掴んでいたのだ。
「ごめんなさい。あなたがそこまで気を悪くするとは思っていなかったの。私を堂々と見てくれたのがあなたが始めてで、とっても嬉しかったの。みんな、私を遠回しに見てヒソヒソと話すから気分が悪くて…。」
彼女は罰が悪そうに肩をすくめた。
あぁ、そうか。この子も気づいたのか。
あのクラスの異常性に。
あのクラスが作る、余所者に対する大きな壁の存在を。
私の所属するクラスは、中学からの内部進学者が多く在籍している。元々は外部進学生が多い学校なのだが、不幸にも今回のクラス替えで内部進学者が固まってしまったのだ。内部進学者たちは外部進学者を「余所者」と呼び、蔑む上にいじめの対象にしている。現に外部進学生へのいじめの犯人は、大半が内部進学者でいじめの内容も陰湿かつ悪質で教員も手をこまねいている状態だ。つまり、内部進学者たちにとって、外部進学生は忌み嫌う存在なのだ。私も、その忌み嫌われる外部進学生の1人だ。ちなみに、私以外に外部進学生はいない。私の場合は目の事と無口な性格から、気味が悪いとはじめの頃いじめられていたが、いじめても反応しないためか、今は無視されるようになった。
今、もしかすると彼女が標的になっているかもしれない。
それを考えた時、私の心は酷く痛んだ。
私にはわかる。…その痛みが。
心が重くなって、泣きたいくらい辛くて、息ができない程苦しい。言葉にはできないような痛みと苦しみが、私を苦しめる。
…そんな時だった、私はフッとある考えが浮かんだ。
彼女は、私の目をどう思っているのだろうか?
私は気づいた。いや、閃いたというのが正しいのかもしれない。目が合わないような気がしていたのは、これが原因ではないだろうか?私の目を見て、気持ち悪がらない人なんで殆どいないはずだ。きっと、転校生だから気を遣っているのだろう。しかし、いくつか腑に落ちない点もある。彼女はなぜ私と普通に会話し、笑っていられるんだろうか?転校生ほど、私を避ける人はいない。今までだって初対面の人は、大概驚いた表情をする。なぜ、彼女は違うのか…。
「あ、あの…。」
2人の間を流れていた長い沈黙を断ったのは彼女だった。彼女の表情は愛らしい笑窪があった顔から、次第にひどく緊張した面持ちの真面目な顔になった。そして、まるで重い口を開くかのようにゆっくりと口を開けた。
「やっぱり、変ですよね…。私って…。」
『えっ…』と私は驚いた。彼女が言っていることを理解することができなかっためだ。もしかして、私の考えていたことが伝わってしまったのではないかと、少し不安になりかけた。
「あっあの、な、なんのことでしょうか…?」
もちろん、聞かずにはいられなった。もし、伝わっていたとしたら失礼なことを考えていたとも思うし、土下座でもなんでも全身全霊で謝る。しかし、内心は違った。もしかすると彼女の視線の意味を知ることができるのではないかと考えたためだ。
彼女は『えっ』と驚いたした顔をした。そして、小さな深呼吸をし、彼女は話し始めた。
「実は私…目が見えないんです。」
ゆっくり、
ゆっくりと、彼女は語り始めた。
「小さい頃…、とある感染症にかかってしまって…。その治療で服薬した薬の副作用で…目が見えなくなりました。…もし、あなたが私の様子が変で、不快な思いをしているのなら…本当にごめんなさい。自己紹介の時に、皆さんに伝えれば良かったんですが…。やっぱり、怖くて…。自分で、自分の嫌なところを言うのが…。」
彼女は、深々と体を倒した。
膝には、小さな水滴が落ちている。
彼女は泣いている。
それに対して、私は何も言うことができなかった。どんな言葉をかければいいのか、すぐに頭に浮かばなかったからだ。
きっと彼女にとって、私がもじもじしていた長い時間は、ずっと気まずい思いをしていたのだろう。
彼女にかける言葉を考えている内に、私はあることに気が付いた。
私はいつまで現実から逃げているのだろうか。
コンプレックスというものは、どんな人にもあるはずだ。それが大きいものなのか、小さいものなのかは人によって変わってくる。目立つものもあれば、目立たないものあるだろう。私の場合は、大きく目立つものだった。
私は、なんて卑屈な人間なのだろう。
私は過去の事件から被害者ぶって、自分自身を甘やかしていたのだ。今まで、周りの人々は自分のことしか考えず、人のことを蹴落としてでも生きようとする醜い生き物だと考えていた。だから、私を誰も助けてはくれないのだろうと、そう思っていた。でも…、本当は私も彼らと同じ自分のことしか考えない『醜い』生き物だったのだ。自分が作り出した『被害者』の衣を着て、ただ可哀想な子を気取って演じていたのだ。
それに比べて、暮湖月と名乗る彼女は勇気を振り絞って自分の事を打ち明けた。そして、どうなるかもわからないこの先に起ころうとしている不安と戦っている。
見えない目で、
強く、
強く生きている。
なんて、強い人なんだろう。到底、彼女のように私は強くなれない。なぜなら、私にそこまで勇気を与えてくれるものはないのだから…。彼女のその強さは、勇気は、いったいどこにあるのだろうか…。
その時、ふいに以前まで見ていた夢を思い出した。黒い髪の長い女性。誰かの元へと山を登る美しい女性。麦わら帽子の少女と男性。どの夢も誰かのために、誰と共にいる。そして、とっても幸せそうにしていた。
もし、私の隣いる人が彼女だったならば…。
もう、やめよう。
下を向いて逃げてばかりではなく、
前を向いて、前に進まなくては。
「あ、あの!」
私は深呼吸をして、勇気を振り絞って彼女に伝えた。
”ともだちになりませんか?”
今日のこれ出来事は、私にとって勇気のある大きな一歩となった。今日のこの日を、私はずっと大切にしたい。これから始まる、2人の物語の原点なのだから…。
〜〜〜〜
遠い日の暖かな約束


