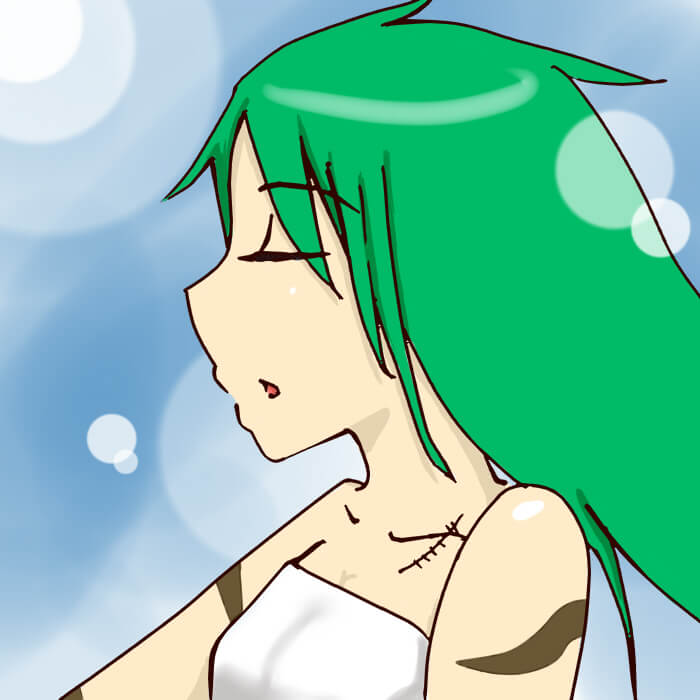
森住人-モリビト-
あるところに、みどりいろのひとみとかみのけの、きのせいれいがいました。
かのじょはにんげんにひどいことをされて、にんげんのことをきらっていました。
でも、ひとりぼっちなのは、さみしかった。
かのじょは、せんねんじゅにいのりました。
「わたしのことをわかってくれる、ともだちがほしい。」
すると、たちまちかのじょにともだちがふえて、まいにちわらってすごすことができたそうでした。
めでたし、めでたし。
――――――童話「森の住人」――――――
雲一つない、真っ青な空。
空の真ん中に浮かぶ太陽は、大地を照らしている。
照らしている。
うん、確かに照らしている。
そのせいで、こっちはむちゃくちゃ暑いんですが。
蒸し暑い。なんなんだこの暑さは。
干からびてしまいそう。
私はいま、森に在る一本の木の上で昼寝をしているところだ。
…こんな暑さじゃ、昼寝なんてしていらんない。
日陰だというのにもかかわらず、熱気が私を襲う。
暑い。
暑い…。
「だあぁああっ!!暑い!!もぅ限界!!無理無理!!!」
耐えきれなくなった私は、その身を勢いよく起こした。
しかし、私のいる場所は、木の枝の上。
―――グラッ
「あ、ちょ、おちるぅうう!!」
ただでさえバランスが悪い場所なのに、体勢を崩せば落ちるに決まってる。
とかなんとか考えてる内に、地面はすぐそこ。
物凄い音と共に、全身を強く打ちつけた。
「あだっ!!いったぁああっ!!!」
声なき声を上げてその場で呻く。
骨は折れてないと思うけど、思いのほか強く打ちつけたみたい。
ここ十数年と森の中で過ごしてきたけど、これだけ酷い落ち方をしたのは初めてだ…。
『まったく、お主と言う奴は…。』
私の乗っていた木のすぐ近くで、声がする。
顔を上げるが、そこには人の影は見当たらない。
いや、この声の主は人の声ではないので、人がいるはずない。
「うぅ…だって、この暑さだし、脳がいかれちゃうよ…。」
私は声のした木のほうにむけて、ボソボソ呟いた。
すると、それに答える声が、
『まぁ、まさに灼熱地獄と言ってもおかしくは無いがな。』
その木から帰って来た。
意味が分かりにくいと思うから、説明しよう。
まず、私はこの森に約12年間ほど住んでいる、ミドルナリット・ルナーティカ。
気軽に、ミドルと呼んでもらいたい。
次に、このしゃべっている木は、大地の神様とも言われている大木、【千年樹】。
実際に大木が喋っているところなんて、普通の人間では聞き取れない。
私はちょっと特別だから、こんな風に声が聞こえる。
何故かって?
私は、人間じゃない。
この国では珍しくはないけど、私は千年樹から生まれた精霊、木の精霊の【樹精霊】なんだ。
精霊独特の力で、命が宿るものと会話することができる。
だからこうして千年樹とも話す事が出来るんだ。
と、言うわけ。OK?
私は体を起した。
まだ、あちこちがズキズキ痛む。
「てか、なんでグリモワールはこんなに暑いのに平然としてられるの?」
『ふむ、我は大地の神じゃ。そう簡単になめられては困るのぅ。』
「私からしたら、神様に思えないんだけど…。」
『お主も神になるんじゃぞ?』
「はいはい、そうでしたー。」
グリモワール、というのは千年樹の本当の名前だ。
そっちの方が呼び方として呼びやすかったから、私はこっちの名前を使ってる。
ついでに。
グリモワールが死んだら、今度は私が千年樹になる。
【樹精霊】の最期は、本体が朽ちたら自分が次に本体になると決まっている。
…正直、嫌なんだけどね。
「…ん、汗臭いな…。」
この暑さで、全身汗だくのようだ。
汗で服が体に張り付いて、きもちわるい。
それに、とにかく、臭い。
近くの川で、水浴びでもしてこよう。
私は立ち上がり、川まで歩く。
足が重い。やっぱり当たり所が悪かったみたい…。
歩いて数分。
木々をかき分けていると、水の流れる音が聞こえてきた。
森に流れる一本の川。
透明で、太陽の光でキラキラ輝いている。
手を器の形にして水をすくい、口元まで寄せて啜る。
「んー!美味しい!潤う!」
ほどよい冷たさが、身体の体温を少し下げた。
私はブーツを脱ぎ捨てて、川の中に足を入れた。
ひんやりとした水温が足を包む。気持ちいい。
すると、
「誰だ。」
どこからか、声がした。
しかし、360度見渡しても、誰もいない。
まるで、頭の中から話しかけたような…。
「誰だと聞いてるんだ。」
次の瞬間、いきなり川が水しぶきを上げた。
水滴が目に入り、目をつむってしまう。
指で目をこすってどうにか目を開けると、目の前に男が立っていた。
青い瞳と髪。
コイツが話しかけて来たのか。
水の中から話しかけたのか?
それにしても、身体はあんまり濡れてないな…。
「…ミドル。ミドルナリット・ルナーティカ。」
とりあえず、名乗ってみるか。
「ミドル…?」
私の名前を聞いて、男の表情が少し変わった。
やっぱり、私の名前を知らない人は少ないらしい。
訳ありだしね。
「そう、ミドルだよ。」
「ふぅん…俺、アディダ・グランバード。【湖精霊】だ。」
【湖精霊】
なるほど。【湖精霊】という事は、何処かの湖の精霊と言う事か。
だから、水の中から話しかけられたし、あんまり濡れてないのか。
納得納得。
てか、この顔、何処かで見たいことあるなぁ。
いや、実際にこの男とあったことがあるわけではないけれど…。
誰かに似ている…。
「…なに人の顔ジロジロ見てんだ?」
不機嫌そうに、私の事を睨んできた。
うわ、目つき悪い…。
「いや…なんでもない。じゃあ、私はそろそろ御暇するよ。」
あんまり、人と関わりたくない。
私は川から上がって足をタオルでぬぐった。
ブーツを履いて、その場を去ろうとしたら、
「待て。」
手をひかれた。
関わりたくないのに…。
「…何?」
「お前、確か人間が嫌いなんだよな?」
「…そうだけど。」
人間が嫌いって知ってるんだったら、早く帰らせてほしいんだけど…。
「だったら、ちょっと俺から離れるな。」
「はぁ?」
意味が分からなかった。
人間が嫌いだったら俺から離れるな?
理解できない。
何を言ってるのこの男。
「…少ないけど、人間がこちらに来てる。お前目当てだろう。」
「…!!」
神経を集中させる。
確かに、微かだけど人間の気配が近づいてくるのが分かる。
これだけ気配を消せるのは、素人じゃない。
私は腰に下げている銃を取り出す。
すると、
「…Aquarium.」
男が呟いた。
次の瞬間、私の視界が青く染まった。
否、水で作られた壁が私を包み込んだのだ。
「なっ!ちょっとなにこれ!!」
私はその壁を叩いた。
しかし、壁は少し水面が揺れるだけで、壊れない。
思い切って、銃口をその壁に向ける。
「やめとけ、跳ね返ってくるだけだぞ。」
アディダは淡々とした口調で言う。
「人間が嫌いなら、ここは俺に任せろ。それはお前の身を守るための結界だ。安心しろ。」
そう言って、少しだけ此方を見てから前を向いた。
「…いるんだろ?隠れてないで出てきたらどうだ?」
森の中に向けて、少しだけ声を張り上げる。
すると、3人の男たちが木の陰から出て来た。
手に持っているのは、剣。
気配の消し方からして、素人ではない事が分かる。
しってる。コイツらは…、
「…そこの女をおいて、お前はどっか行ってろ。」
私を殺しに来た。
「全く、探したんだぞ?さっさとこっちに来い。」
あえて優しい口調で言ってくるけど、声に闇が混じっている。
私は全力で首を横に振った。
「嫌だっ!誰がお前たちなんかに!それに、お前らは一番知ってるだろう!?私は死なない事!!」
「お前は完全な不老不死ではない。人工なのだからな。俺達の力なら、お前を殺す事なんて簡単だ。」
不老不死。
それは、その名前通り、老いることも死ぬこともない存在。
コイツらは不老不死の研究者で、私はその実験体。
…私はこいつらに、不老不死にされてしまったのだ。
私は脱走して、その数日後に一部の研究所の研究員たちを皆殺しにした。
その日から、私は研究者たちには危険な存在と思われてるそうだ。
すると、アディダはその会話に割り込むかのように、口を挟んできた。
「ふーん。お前ら、コイツ殺しに来たの?」
「………。」
「俺もさ、一応精霊だから、同じ精霊を放っておくなんてこと出来ないんだよね。」
そう言いながら、右手を地面と水平に上げた。
「…じゃあ、まず、お前から逝け!!」
3人全員が剣を構えて、アディダに襲いかかってきた。
アディダは精霊とはいえ、無装備。
圧倒的に不利だ。
そう思った次の瞬間。
「Axe!!」
アディダが叫ぶと、何か巨大な物体が風を切る音がする。
音が終わった直後には、アディダの右手には巨大な斧が握られていた。
明らかに、普通の人間が持ち上げるにはキツイ大きさだ。
「そういうお前らが逝ってしまえ!!」
その斧を持ったまま、空中へ高々とジャンプする。
そして、斧を高々と振り上げた。
男たちは剣を盾の変わりに構える。
「爆・砕・斬!!」
重力の力で地面へ落ちていきながら、斧を渾身の力で叩きつける!!
―――――ドゴォッ!!!
物凄い騒音がする。
同時に、男たちから赤い液体が上がる。
地面は隕石が落ちたかのように抉れている。
男たちは、頭を割られていたり、首を切られていたり、もう生きていない。
「はぁ…弱かった。」
疲れたかのように、ため息交じりで言いながら斧を肩に担いだ。
アディダには、返り血がついてない。
いや、貴方が強いのでは?
「ん、ほら、もう良いぞ。」
アディダが指を鳴らすと、ぱちゃんと音を立てながら水の壁が崩れた。
「…あ、あのさ、なんで私を助けたの…?」
お礼を言う前に、疑問を突き付けてしまった。
でも、気になってしまった。
他人である私なんかを、なんで助けたの?
すると、少しだけ顔を赤くしてそっぽを向いて口を開いた。
「…殺すとか言われていて、助けねぇなんて思わねぇし。あと…助けることが、好きだから…。」
ちょっとだけ此方を向いて、口角を少し上げた。
「誰かを守りたいって、思ってるから…。」
その台詞で、ようやく思い出した。
どこかで見たことのあるこの顔。
性格まで、似てるなんて。
今は亡き、私の愛人に似ているんだ。
「ありがと、アディダ。」
私はにっこりほほ笑んだ。
「…おぅ!」
相手も照れくさそうに笑った。
ふいに、心の霧が晴れたような気がした。
森住人-モリビト-
「アディダ!いる?」
「ん?お、ミドルか。」
あの日から、私はアディダと友だちになって、こうして会う様になった。
アディダとは話が合うので、一緒にいて楽しい。
いや、なんか一緒にいて落ちつくと言うか。
ときめいてるというか…。
ん?まて?それって…。
アディダに恋してる?
「ないわぁああぁあぁぁぁあぁあぁああ!!」
「はぁあ!?いきなりなんだよ!叫びやがって!」
私の叫び声が、森の隅から隅まで行きわたった。


