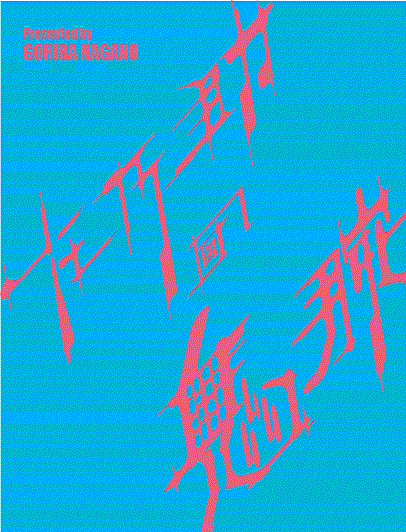
左乃助の鬼腕 序章2
「鬼虫か」
左吉はその名前を何度か村人の噂話で聞いたことがある。
死人の肉を喰らい、やがて大きな鬼になるのだとか。
死人に取り付きその者を操り鬼に変えてしまうのだといわれていた。
その鬼虫が左吉の身体が死肉になるのを待っているように揺らめいている。
「オレはおめぇの餌になんかならねぇぞ」
左吉は後退りして鬼虫と逆の壁に背をつけた。
左乃助の鬼腕 第2話 「鬼腕」
サラサラサラ
鬼虫はまるで「お前の考えなどお見通しだ」と言わんばかりにユラユラと左吉の様子を伺っている。
「バカにしやがって・・・バカにしやがっておまえにオレのなにがわかるおまえなんかに笑われてたまるけ」
勿論鬼虫は左吉の問いに答えることなくただ穴の隅で揺れているだけである。
「オレ一人消すのなんてたやすいっていいてぇのか」
ザザッザザッ
鬼虫の羽音が殺気をおびたような音に変わった。
「オレがなにをやったってぇんだ・・・オレなんかよりもっともっと悪い事をしているヤツなんて一杯いるべ」
左吉は涙声で訴え、壁を背にして立ち上がろうと試みるが、湿気を含んだ土が滑り、怪我をしていない左腕の力だけではうまく立ち上がれなかった。
ザザッザザッザザザ
鬼虫は奇怪な羽音をたて、激しく横揺れをしてまるで左吉を威嚇しているかのような動作を始めた。それは左吉の精神を恐慌に陥らせるには十分な圧力であった。
「あぁぁぁぁ!」
左吉は狂ったように叫びもがき、立ち上がろうとした。が、姿勢を崩し、骨折しているであろう右腕を激しく地面に打ち付けてしまった。
鈍痛の中左吉の意識が次第に遠くなっていった。薄らぐ意識の中、最後に覚えているのは、鬼虫がゆっくりと近づき自分の右腕を喰い始めた場面であった。
ガリガリガリ・・・ボキッ・・・ボリボリボリ
巨大な虫が少年の腕を喰らう乾いた音が闇の中に反響した。
何日間この穴蔵で気を失っていたことだろう。
ぼんやりと瞼を開くと、薄藍色のいびつな丸く切り取られた空が浮かんでいた。
「ここから出なきゃな」
それは悲壮感から出た言葉ではなく、もうそろそろ布団から出なければならない、程度の軽い口振りであった。
左吉は身体を起こすと難なく壁を上がってゆく。まるで水平の床を雑巾掛けでもするかのように。
地上に出ると左吉は鰯雲をみあげながら草むらに寝そべり、そこで初めて自分に起こった異変に気がついた。
あれだけ身体を打ち付け、激痛が全身を覆っていたのに、何故今はまるで痛みを感じないのか。何故あれだけ深い武者落としから軽々と抜け出せたのか。
「そうだ。オレの右腕」
その時、鬼虫に右手を喰われた記憶が蘇った。
ふっと自分の右腕を見た。
黒鉄色に光り、脈打ち動く右腕がそこにはあった。二の腕は異様に太く岩石のようで、隆起した血管だけが煉瓦色に染まり、上腕には昆虫の羽らしき物が付いている。
「なんなんだこれは・・・嘘だ・・・うそだ」
あのおぞましい鬼虫が我が腕を浸食しているではないか、しかもそれは何の違和感もなく自分の意志のまま動かすことが出来る。
「オレは化け物になっちまっただか」
寝そべったままその異様な腕を太陽にかざし、手をゆっくりと握りしめると、自然と涙が溢れ出た。
「おっかぁ」
それだけ言うと感情を吐き出すように左吉は立ち上がり、近くにあった椚の木に登った。 そこから自分の村を見下ろし、家族や村の人々に別れを告げ、身を潜めるように旅立たなければならない、と感情的に思った訳ではなく、そうせねば生きられぬ宿命を身体の中の一部分が感じ取っていた。
だが、木の上から見た光景は左吉を簡単には旅立たせてはくれなかった。
「村が燃えている」
西側に向いた斜面にある集落の谷側にある二軒の家から火柱があがり、数件上の農具小屋からは細い煙が天に揺れ上がっている。
「おっかぁ・・・おっとぉ」
椚の木から跳躍するとそのまま山の斜面を転がり、麓付近で体制を整えた左吉は村に向かい走った。
走った。
左吉は元々身軽な少年であったが、そこまでの動作は疾風のようであった。
「おっかぁ!おっとぉ!おにい」
村に着くと力の限り知った名前を叫び、中腹にある左吉の家に入ると繰り返し家族の名を叫び続けた。
静まりかえった狭い家からは、人の気配と言う物を感じることは出来なかった。
足の裏から板の間の冷たさだけが伝わる。
「左吉・・・左吉だか、そこにおるんは」
振り向くと五十がらみの男が泥だらけの顔で立っている。
「権助じぃ」
左吉は権助の元へゆっくりと歩みを進めた。
「左吉、その腕は・・・おめぇもあの化け物たちの仲間か」
権助は差し込む日差しに照らされた左吉の右腕をみて、震えながら庭へ逃げた。
「こっちへ来るな・・・化け物」
「違うんだこれは」
左吉は権助を追って庭へ出た。
ゴゴォォォ
不気味な音と黒い疾風の中、権助の姿は左吉の視界から消え去った。
ゴォォォゴォォ
左吉が音のする方へ視線を向けると、黒い壁が蠢いている。
ゴォォォ
壁ではない巨人だ・・・九尺はあろうかという黒い巨人が権助の頭を貪り喰っている。
サラサラサラサラ
武者落としの中で聞いたあの羽音が左吉の右腕から発せられると、上腕部の羽が大きく震えだした。
ゴォォォゴゴゴォォォ
巨人は羽音に気づいたのか、権助の残骸を投げ捨てると、左吉を見る、と同時に左吉を捕らえようと腕を振り下ろす、左吉は軽く土を蹴り、屋根に登る。
左吉が屋根に乗ってもまだ巨人の視線よりも低い。
「おめぇが村をこんな風にしただか」
巨人は大きく咆哮すると、家に体当たりを喰らわせて来た。
藁葺き屋根は大きく破損し左吉の足下を揺らした。
「おめぇ」
左吉も小さく吼えると、巨人の肩に飛び乗り、振り落とされぬよう耳を掴んだ。巨人は上半身を振るわせ、必死に左吉を落とそうと試みるが、左吉はその動きを利用して後頭部に回り込む。
カラカラカラカラ
左吉の右腕が異様な音をあげると、巨人の延髄を突き破っり首の骨をへし折る。
一瞬の出来事だった。巨人は脆く倒壊し、庭に突っ伏したまま動かなくなった。
倒れた巨人の顔を見ると妙に切なく優しい目をいしていた。
「これがオレの力か」
この力があれば何処ででも生きて行ける。
左吉の身体に粘りけのある黒ずんだ自信が芽生えたのはその時であった。
「オレはこの腕でなんでも出来るだ」
左吉は庭から綺麗に望むことが出来る富士山を見上げた。
左吉が見上げた富士は、四千メートル級の大富士と、二千メートル級の噴煙を吹き上げる小富士の双子山である。
そう、ここはもう一つの日本「ヤマタイ」である。
左乃助の鬼腕 序章2


