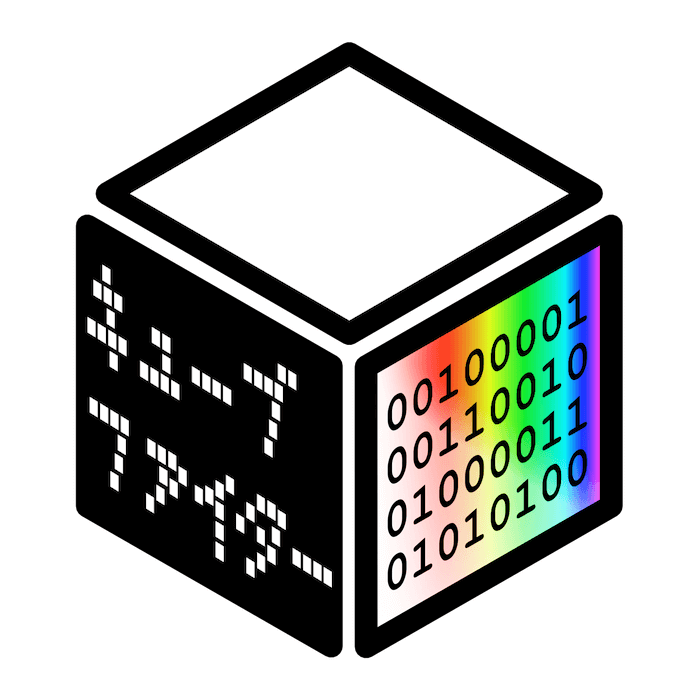
Z-C Session $02「エラー-->ナイトメア」Beta
※エンジニアリングオタ向け
イントロダクション
現在より遠い未来、地球のある場所に「ユニバース」と言う名前の都市群があった。その街は高度に都市化、電子化しており、その情報処理技術は非常に高度な域に達していた。電子技術は都市インフラをはじめ街の至る所で使われていた。
そのユニバースの情報処理技術を支えていたのが「キューブ」である。キューブは透明で立方体の形をした手のひらに収まるサイズのデジタル媒体であり、その中にはユーザーの脳の情報とリンクされたシステムが内包されていた。ユニバースの人々はこのキューブを使って日常生活の中であらゆる情報を処理していたのである。
キューブは過去にバレーのグル達がコンピュータ技術の粋を集めて作り出した究極のデジタル技術だった。が、しかし、情報技術というものは常に完璧ではない。当然のようにキューブについても悲喜こもごもの逸話が生まれてくる。
この物語には二人の主人公が出てくる。その二人とはヴォイス、そしてナックである。二人は家族であり、生みの親を失って養親の元に引き取られた過去を持つ。また二人はユニバースにあるキューブに関する知識を学ぶための学校「CSCH」の生徒でもある。
ヴォイスは冷静な眼差しを持ったCSCHの男子学生。その名は「論理」を意味する。ナックは奔放な性格を持った同じくCSCHの女子学生。その名は「直感」を意味する。二人は同い年で、年齢は今で言うと中学生くらいだろうか。ユニバースのとある街で、養親と共に暮らしている。——二人は覆しようもない運命的な出生を持っていた。
この物語では、そのヴォイスとナックの二人、そしてそのCSCHの仲間達と共に、主人公達の日常から始まる物語が時を進めていく。そしてその物語はいつしか、キューブの中に秘められた、ユニバースの人々の破滅と再生のシナリオへと辿っていくのだった。
用語説明
バイナリ:キューブのシステム上で動作するプログラムファイルのこと。キューブの機能はこれらのバイナリが協調して動作することによって実現される。
ルートネットワークシステム:キューブ技術における一種のインターネットにあたるもの。都市中心部に位置する電波塔であるミクセリタワー内にサーバーが置かれていて、各々の端末からそのサーバーへ接続することによって、キューブ同士のネットワークを構築している。
キーホール:キューブを端末(コンソール)に接続して利用する時のキューブの設置台。ちょうど四角の形をした穴が凹んだ形になっており、ここにキューブをセットして利用する。
登場人物説明
ヴィム:ナックやヴォイスたちのクラスメートで友達。「情報屋」と呼ばれるほど噂を調べ集めてはノートに書き込んでいる。性格・仕草は気分屋で軽いが、気が良く人当たりがいいので周囲との人間関係は良い。ノートとボールペンは常に持ち歩いている。
ショジュ:ナックの親友。いつもナックと一緒に行動している。引っ込み思案で自分を主張せず、多少弱気な性格だが、芯は強い。
サチコ:ヴォイスやナックたちの友達。がめつくてじゃじゃ馬な性格であるが、時々真を鋭く射ている発言をしたりする。
タイキ:ヴォイスたちのクラスメート。いたずら好きの性格で、幾らかの子分を従えるガキ大将的な立場。ヴォイスやナックたちとも時々関わりがある。
ノリオ:ヴォイスたちのクラスメート。タイキの子分的立場の友人。
Session $02 「エラー-->ナイトメア」
──苦しみの裏奥には、必ず誰かの悪意がある
その日、2時限目の授業としてヴォイスとナックたちは講堂で授業を受けていた。講堂はすり鉢状の階段方式になっており、先生がその一番下の皆の前で講壇に立って授業を行う形である。今日の『キューブ開発』の科目の授業はユニバース界の常識と言っても良いくらいキューブ技術には欠かせないあるバイナリの説明であった。担当の講師はシルバ先生。灰色の髪をした渋い言い回しの言葉を使う先生だ。
階段上の教室を取り囲む窓の外には青々とした木々が陰を作っているのが見える。窓からは鼻先をくすぐるような穏やかな風が入り込んできていた。先生が講義をしている黒板には今日の講義であつかう単元である「ソフトウェア開発」と言う言葉が白いチョークで書かれていた。ヴォイスはちびた鉛筆を筆箱から取り出すと、鼻先で支えて遊びながら、ボーッと、講義を聞いていた。
シルバ先生は指差し棒の先で右の手のひらを軽く二度叩くと、講堂の皆に向かって話をはじめる。
「今日の授業ではソフトウェアの『コンパイル』」について授業を行う。このCSCHに入学している皆なら知っていることかと思うが、私たちが日頃使っているコンピュータ、端末、電子機器には動作のために必ずプログラムというものが必要になる。プログラムというのは言うなればコンピュータへの命令を羅列したデータのようなもので、プログラムが組み込まれていなければキューブはただの硬化ガラスのかたまりに過ぎない。このキューブや電子機器を動作させるそのプログラムという物は最初からあるわけではなく、必ず誰かが作らなければいけないものだ。そしてそのプログラムを作ることを専門に職を持っている人のことを『開発者』という。この言葉は重要なので良く覚えておくように。」
そしてシルバ先生はヴォイスの方を振り向くと言った。
「でだ、昨日予習をしてくるように皆に言ったんだが、ヴォイス君、『コンパイル』とはなんだね。教科書の該当する部分を席から立って読んで答えなさい。」
「え、おれですか?」
いきなり当てられたヴォイスは少しの間困惑してから、横のナックを振り返る。
「ごめん、ナック、教科書貸して。俺今日持ってくるの忘れたんだよ」
隣で顎に手を当てながら神妙な目付きで講義を聞いていたナックだったが、ヴォイスから声をかけられると嗜めるように言った。
「あんた、教科書いつも忘れてばっかじゃない。だから学校の準備をするときはちゃんと確認しなさいって言ってるのに——まあ、いいわよ、貸してあげる。今度は忘れないようにしなさいよ」
ナックはヴォイスの前に教科書を差し出す。
事態を静観していた先生だったがヴォイスが教科書を手におずおずと立ち上がるところをみてもう一度聞いた。
「コンパイルとは何か、と言うのが問いだ。」
ヴォイスは教科書のページをまさぐる。
「えー、コンパイルによって処理の途中で中間ファイルが作成されるが……あ、これ違うか。もっと前か?コンパイル後にソフトウェアを実行しやすい形にファイル構成をまとめることをビルドと……、あ、これも違う……えーと、あれー。すみません、わかりません。」
先生はため息をついたのち、それを予期していたかのようにペンを揺らすと、
「そうか、ではナック君。コンパイルとは何か、説明してもらって良いかな」
先生は今度はナックを指名した。「ゴメン」と一言言ってヴォイスはナックに教科書を返してから席に座る。ナックはその教科書を手に席から立った。
「はい、ソフトウェアやアプリケーションなどキューブにとって必要なプログラムは、ソースコードをコンパイルすることによって作られます。ソースコードとは文字で書かれたソフトの一種の設計書のことであり、これを実際のソフトウェアのデータに変換することをコンパイルといいます。」
「即答と来た。素晴らしいね。さすがナック君だ。皆、拍手」
講堂の中に拍手がパラパラと鳴り響く。ナックは自慢顔でそれを受けた。
「コンパイルをするためのソフトウェアのことをコンパイラと言う。キューブの中にもコンパイラとしてzccというバイナリが含まれていることは二年生の皆は既に承知の上だと思う。——」
その後の先生の話をまとめるとこうだ——。キューブを使ってソフトウェアを開発する場合は大抵の場合においてzccが必要となる。zccはナックの言った通りソフトウェアの設計書に当たるソースコードというものを実際のプログラムデータであるバイナリに変換するために、キューブで利用できるコマンド(命令)の一つである。ちなみにzccという名前は正式名称であるZ Compiler Collectionの頭文字からとったものだ。一般の人が使うキューブにはzccは含まれていないが、CSCHではキューブ開発の授業があるため、生徒が持っているキューブにはzccやそれに関する各種のツールが既にインストールされている。
シルバ先生は話を続ける。──キューブは脳の情報とリンクされているわけだが、キューブ側から脳の情報にアクセスするためには高度な権限の認証が必要となる。キューブのzccをつかって脳の精神疾患を治すためには実際のところユニバースにおいて数台のみ設置されているzcc医療装置が利用されている。この機械は治療用にカスタマイズされたzccの実行ツールを装備するだけでなくルートネットワークシステムとリンクしてユーザーのキューブの認証情報をサーバーからダウンロードして認証を解除する機能を持っている。これはユニバースにおいては非常に限られた高度な権限だ。——
「実際のところzcc医療装置の利用には高度な知識と経験が必要であり——」
ここでキーンコーンカーンとチャイムが鳴った。
「もう時間か。今日はここまで。次回もちゃんと予習してこいよみんな。ヴォイスも教科書忘れるんじゃないぞ」
——鼻で遊んでいたちびた鉛筆を筆箱にしまうとヴォイスがナックのほうを見て言った。
「おまえすごいな、先生からいきなり指名されて教科書のどこが答えなのかすぐわかるなんて。」
ナックは自慢げに答える。
「私は教科書は学年のはじめに渡されたときに全部読み込んであるからね。そうすれば授業なんて復習みたいなもんよ。──学年トップを争う私をなめるんじゃないわよ。音楽さえなければ私は学校一の天才なんだから。あんたも少しぐらいは予習してきなさいよ。そうすれば教科書忘れたりなんてしないと思うわ。」
「説教はやめろよ、先生じゃあるまいし。ん?おっと、次は音楽の授業があったんだった〜。」
「えー!?音楽ぅ?」
ヴォイスの言うとおりヴォイスとナック達のクラスでは、3時間目の授業として音楽の授業があった。音楽の授業の場所はいつもどおりの音楽室。ヴォイス達が席に腰掛けていると、授業時間が始まるより少し前に、先生が教室に入ってきた。音楽のトゥッティ先生はドテッと太った中年の女性の先生で、厚縁の高級そうな眼鏡をかけていて、口紅も派手な赤を塗っている。トゥッティ先生は少々変わった語尾の話し方をする先生だった。ピアノの上に教科書などの教員道具を置くと、先生は授業のはじめにいつもの口上を述べた。
「では、皆さん音楽Ⅱの第32回目の授業を始めます。このCSCHはキューブの技術について学ぶ教育機関でありますが、一般の情報技術に関する学習内容意外にもその他必要な科目として様々な教養科目を学ぶことになってますの。音楽の教科もその中の一つであり、この科目はCSCHの中等課程における必須履修科目ですのね。──」
そのまま話が続いていったが、最後にトゥッティ先生が言った言葉に教室全体がざわめいた。
「今日は実技テストを行いますの。一人ずつ前に出て以前から練習している「約束の地へ」を私が合図するまで皆の前で歌ってください。このテストの結果は皆さんに配った評価用紙に聴いてる皆さんで評価を付けますので、くれぐれもまじめにやってくださいね。」
それを聞いてクラスは喧々囂々の状態になった。
「えーあたしには歌を歌うなんて無理よー!」
「私下手くそだからやだーー!」
「俺、今、風邪引いてんだけどな」
しかし喚いたところで授業内容が変わるわけでもなく、そんなこんなでテストが進んでいった。声変わりしている人、声が枯れている人、風邪を引いて声が出ない人、そこそこな人、やけにうまい人、声が大きい人、恥ずかしがってまともに歌えなかった人など、いろんな人が居たが、ヴォイスのテストも終わり(ヴォイスはそこそこの出来だった)、あのナックのテストが始まった。
——とは言っても結果は教室のみんなが最初から予想していたとおりだったのだが。
澄ました顔で現れたナックが教科書を両手で支えながら歌い始めると、その場は異様な雰囲気に包まれた。
——そう、ナックは大の「音痴」だったのである。
「いま、せか〜いじゅうのわがー、ひと〜つになっーてーーーきぼうーのみらいと、を、かなで〜るとーきー、いざいーかんえんぽうのとーもよ、ち〜きゅうの〜はてのーーやくそくのーーちまで(今世界中の輪がひとつになって、希望の未来を奏でるとき、いざ行かん遠方の友よ、地球の果ての約束の地まで)」
あまりの音痴さに顔を歪める同級生達。教室の中にはわざとか本気か耳を塞いでいる生徒まで居た。ナックの声が教室に響いている間気だるさのあまり誰も一言もしゃべらなかった。それでもナックは音痴な声で声を張り上げて歌い続ける。
「しゅーよーしゅくふーく〜あれー、われらのほこーりーにかけ〜て(主よ祝福あれ、我らの誇りに掛けて)」
しばらく鈍い表情で歌を聴き、所々汗をハンカチで拭っていたトゥッティ先生だったが、「はい、そこまでです」と合図すると歌は終わった。一礼したナックは自席に向かった。
ナックが席に着くまでの間、教室中に無言の時間が流れる——。トゥッティ先生のほうはしばし無言だったが、何かを飲み込むように口を開くと「それでは」と次の生徒を呼んだ。
ナックが遠くの席に着くと、ヴォイスの横に座っていた男子学生たちがぼやいた。
「なんかナックの歌い方ってアヒルが啼いてるみたいだよなー」
「あー、それ言えてる。声がブツブツ途切れてるって言うか、思いっきり音程外れてるし」
「ナックって美人だし勉強もあんなに出来るのに音痴なんてなー」
トゥッティ先生はしばらくピアノの縁を指で叩いていながら次の生徒視ていたが、一人ぼそっと呟いた。「──ふむ、声質は悪くないですのね。ただ喉の使い方が悪い。」
音楽の授業が終わるとき、友人のショジュと一緒に音楽室を出ようとしたナックのところに保健課の先生がやってきた。
「ナックさん、渡すのが遅れたんですけど。これ、覚えてますよね」
そう言って先生はナックにある資料を渡す。それを見てナックが声を上げた。
「ああー忘れてた!そうだったんだった。私、健康診断があったんだった!」
それはCSCHの生徒が一年に一回は受けなければいけない健康診断に関するプリントだった。
「明日はCSCHではなくこの地図で書かれたセンター前に集まってください」
CSCH では児童に対し定期的に健康診断が行われる。健康診断と言ってもかなり高度なもので、生徒はわざわざ病院に入院して人間ドックで検査を受けるのである。定期健康診断は生徒ごとに時期をずらして行われ、診断を受けている間は授業が免除される。(しかし休み明けには遅れを取り戻すための集中講座を受けなければいけない。)ナックは明日からこの健康診断期間に突入する予定だったのだ。
「あーいいなーナック、明日から授業免除だなんて。」
横からショジュがナックに声をかける。
「良くないよー。造影剤とか飲まされるんだよ。食事制限してさ。やってられないわよ。どうせ学校のレポートもたまっちゃうんだし。」
「わたしも早ければ良かったのにF班だからさ。ナックはB班なんでしょ。いいなあうらやましいなあ。——そっか明日はナックは直接病院に行かなきゃいけないんだね。じゃあ、わたしは朝は一人で登校するしかないか」
ショジュが残念そうに言うと、ナックは手を顔の前に立てて謝った。
「ゴメンねショジュ。ああ、家に帰ったらインターネットで病院のアクセス情報と地図、調べとかなきゃいけないな。」
そして二人は給食を食べるべく近くの食堂まで向かった。今回の健康診断がナックにたくさんの喜怒哀楽を与え、そしてとてつもない恐怖のどん底にまでナックを落とし込む発端になるとも知らずに──。
◆ ◆ ◆
そして健康診断の日。ナックは学校側から指定された病院まで向かった。ナック達が診断を受ける病院とは、ユニバースではかなり有名な施設である「高度技術医療センター」だった。高度技術医療センターは医療局が運営する公的施設であり、ユニバース中の最先端の医療技術が集中する高度な医療設備を備えたハイテク病院だ。当日いつもと同じくらいの時間に起きたナックは、別の行き先のバスに乗り、電車を乗り継いで1時間ほどでその医療センターについた。集合場所の病院正門付近までナックが来ると、聞いたことのある声が聞こえた。
「ナック〜、こっちよこっち〜!」
それは同学年のサリの声だった。サリとは選択授業で同じ科目をとっており、時々おしゃべりをする仲だった。
「おはよー、サリ」
見知った顔が居ることにナックはホッとした。CSCHで同じクラスの生徒もいくらかはいるはずだったが、周りに見慣れた顔が居なくて心配だったのだ。
まずナックをはじめとする生徒たちには健康診断中利用する泊まり込みの病室が紹介された。
「私が今回の健康診断期間中にB班を担当をすることになった看護師のエイドです。皆さん、よろしくね」
看護師の人の自己紹介に対して、集まった生徒たちは「よろしくお願いしまーす!」と挨拶した。
「では、皆さん、病室に泊まりこむために必要な確認事項を伝えますので、聞き逃さないようにしっかりと聞いてください──。」
そして食堂や浴室、トイレの位置が教えられた後、泊まり込み用品を生徒達は病室の棚に積み込んだ。準備を完了した生徒達は、今日は初日と言うこともあって早速班分けで呼ばれて健康診断を受けにいった。今日は脳のCT、MRI、血液検査を行う。後日には、尿検査、エックス線検査、内科診断、心音診断等の検査も行われる予定だった。
──脳のCTを撮りに行った後、今度はMRIをとりに地下階にある脳科学区画に行ったナックたち生徒だったが、途中でナックはある様子を目にした。ナック達生徒は検査の順番待ちで廊下に並んでいたのだが、その時廊下の奥の方で、二人の白衣の男が部屋から出てくるのを認めたのだった。どうもこの病院の医師ともう一人は医学生らしい。二人は廊下で立ち話をしている。ナックが耳をそばだてると、それはこの病院に設置されているzcc医療装置についてだった。
「──それにしても先生はzcc医療装置のことにはお詳しいようですね」
「いや、何分私はキューブおたくなものだから、そう言うメカには強いほうなのさ。私はキューブ技術が脳科学に大きな貢献をする可能性があると信じていてね。長年ここで研究をさせていただいているんだよ。」
「ええ、シープ先生のご活躍はいつも見聞しております。何と言ってもzccは精神医療の最先端技術ですものね。zccが精神医療に決定的な成果をもたらすであろうことは、私も信じております。」
「まあ、ここでは無駄話はよい。ではzcc医療装置がある部屋まで案内させてもらおうか。」
zcc医療装置——。ユニバースに数台しか存在しないという最先端の医療機器——。
(zcc医療装置か。私も見てみたいな。なんてったってキューブのことはなんでも知ってる私なんだもの。zcc医療装置だって見ておきたい。)
その時あるアイデアがナックの頭に思い浮かんだ——。先ほどの白衣の二人は廊下の奥へ歩き出している。
ちらちらと周りを伺い列から離れるナック。
「あれ、ナック、どこにいくの?」
サリが疑問げに聞くと、ナックは申し訳なさそうに言った
「ゴメン、サリ私ちょっとトイレ行ってくる。すぐ戻るからさ」
「え、ちょっと、ナック、まだ検査の途中よ。」
しかし、「シーッ」と口に指を当てたナックは訝しがるサリには構わずに、隠れがくれ廊下の奥に消えた二人の後を追った。ナックの行動が理解できなかったサリだったが、だからと言ってどうすることもできず、結局列からはぐれないように元の位置に戻った。──廊下を進んでいくナック。途中見つかりそうになったりもしたが、しかし壁に隠れたナックに二人は気付かなかった。
そして二人が着いた部屋の看板には確かに「zcc医療装置手術室」と言う標札があった。そう、そこがzcc医療装置の設置された手術室だったのだ。
部屋の入り口のドアの鍵を開け、部屋の中に先ほど廊下で話をしていた二人が入っていくが、幸か不幸か部屋のドアは開いたままで、ドアの隙間からは部屋の中が垣間見えた。ドアの向こうではヒツジ髪の老医師が研修医に装置の説明をしていた。
「患者には向こうの手術台に寝てもらう。とはいっても何も手術をするわけではなくて単にコンパイル中のアクシデントを避けるために安静にしてもらうためだ。そしてこれが虹彩認証装置。zccの利用にはキューブのシステムを脳と繋ぐFLポートへのアクセスが必要になる。虹彩認証装置はそのための認証鍵をルートネットワークサーバーからダウンロードするためのものだ。この装置はミクセリタワー側が提供している。」
老医師が説明すると研修医が驚いたような声を上げた。
「うわー、こんなの私は初めて視ました。これミクセリタワーのルートネットワークサーバーにもアクセスできるんですね。私も一度見てみたいとずっと思ってました。」
「まあ、世間でイメージされているような大した設備ではないがな。ただここにキューブ技術の一つのエッセンスが詰まっているといっても、それは過言ではないかも知らんが」
二人は長居するつもりはなかったらしい、しばらくして部屋の中から二人が出てくると、二人はそこで立ち話を始めた。——二人はドアの裏側に隠れていたナックには気付いていなかった。鍵を閉められる前に二人の視界の死角からナックはそろりそろりと二人に気付かれないように部屋の中に入っていく。
ナックが部屋の中に侵入した後に、ドアをまだ閉めていないことに気付いた医師がドアを閉めると、その医師は鍵を掛けた。ガチャリと鳴った鍵に一瞬ビクッとするナック。
(ま、鍵は中からあけられるから、大丈夫よね)
そう自分を落ち着かせて部屋の中を見回すナックだったが、そこにはやはりあのzcc医療装置——患者を乗せるための手術台と、zccを利用するための端末があった。そしてそのzcc医療装置とおぼしきマシンには、キューブをセットするためのキーホールが用意されていた。
ナックは手早く自分のキューブをzcc医療機器のキーホールにはめ込むと、近くの端末に向かってキーボードを叩き始めた。まずはヘルプを探し出してzcc医療機器の使い方を調べたナックだったが、ひと通り調べ終わると自慢げに言った。
「なんだ、zcc医療機器なんて言っても普通の端末にキーホール、虹彩認証装置、外部ディスクにカスタマイズされたzccツールがインストールしてあって、後はルートネットワーク機構から認証情報とソースコードをダウンロードして使うだけなのね。結構単純。」
そしてナックは気がついた。
「あれ、これって私のキューブにも使えるのか──。ならちょっと試してみよう。何事もまずは試してみなきゃわからないよね、実践あるのみ。」
ナックはそうつぶやくと、手始めにキューブルートネットワークのサーバーからヘルプにあったサウンド関係のソースコードを適当に選ぶと、それをダウンロードしてコンパイルしようと試みた。まずキューブにインストールされたコマンドでサーバーに接続、ソースコードを手元で操作しているキューブのローカル領域にダウンロードし、圧縮されているデータを解凍、そしてCSCHの授業で教えられたようにコードへの設定を行ったのちにコンパイルを試みた。
コンパイル後に行うバイナリのインストールのために認証を要求されたナックは端末の近くの虹彩認証装置で認証を済ませると、端末が表示した「脳内情報へのアクセス」に対する警告を了承して、コンパイルを開始する。そしてzccが動き始めた。──
画面にコンパイル状況が表示される——。端末には超高速のスクロールでコンパイル結果の出力文字列が滝のように流れて表示されていった。コンパイルの終了の表示とともにコンパイルされたソフトウェアのインストールが始まる。そのときだった。
バツッと電気ショックのようなものを受けてナックは床に倒れた。——
「いたた……何よ。」一瞬狼狽して起き上がるナックだったが、体を見てみても別にケガはしていない。
ナックは端末をのぞき込んだ。端末に表示されたコンパイル結果には「警告」が一件表示されていたが、エラーはなく、体も普通に動くし何事もないようだった。どうやらコンパイルは成功したらしい。しかしその時廊下から「ピピピピ……」と警報音が鳴り響いた。どうやら病院内のシステムがナックの端末の操作を察知したらしい。部屋の外は突然の警報に慌てて行ったり来たりするたくさんの病院関係者で騒がしくなった。
(見つかったらちょっとヤバいかな)
ドアに張り付いたナックは扉の近くのミラーウィンドウから廊下を見て、周りの動向を見計らいながら手術室を抜け出した。
(検査は…もう時間的に終わっちゃってるか。どうしよっかな、誰かに見つかったらなんで検査を受けてないのかって詰問されるだろうし、でも病室に戻るしかないよね。どうせ検査期間が終わるまでこの病院にいなきゃいけないんだし。)
相変わらず警報音が鳴り響いていたので、病院の廊下を壁などに身を隠しながら周りに見つからないように通り抜け、ナックは非常階段を使って地階に上がった。上階に行くためには遠くにある別の階段を使わなければいけない。途中幾度も病院関係者に見つかりそうになったが、ナックは素知らぬふりで横を通り抜けたりしてなんとかかわした。そして上に登る階段のすぐ近くに来た時、外に通じる開かれたドアから、外の街の音が流れ込んできた。──振り向いたナックは少しの間立ち止まっていたが、不思議な引力を感じて引き寄せられるようにドアから外に出ると、注ぐ五月の陽光のなかに出た。
外の空気を吸って、ナックはなんだか清々しい気分がしていた。窮屈な手術室から出て新鮮な空気を吸うと、こんなにも開放感があるのか、と——。しばらく病院の敷地内の森林公園を歩いた後に、門をくぐって町中に出ると、歩いているうちにそれまでうすうす感じていたあることに気がついた。
まず最初に外で鳴いている鳥の鳴き声のそれぞれの音の音階がわかる——鳥の鳴き声を聞いてドレミを諳んじられる——のだ。町中で流れる信号の音も、人のしゃべり声も、様々な物音、そしてもちろん街中に流れる流行のポップスなど、音の全てを音階としてとらえることができた。今まで感じたことのない感覚にナックは陶酔していた。うれしさに心なしかスキップしながら歩くナックを、街中の人はいささか不審そうに見ていたが、それでもナックはうれしくて、心躍るようだった。自分にもこんな感覚がわかるなんて──。心の中が軽やかな光の粒に満たされたようだった。
しかしナックが突然検査から居なくなったことで病院を含め周囲ではかなりな騒ぎになっていた。
実はナックがzcc医療装置を使った後、病院内の警備室に設置されている管理者用のモニター上にzcc医療装置が稼働しているとの表示があり、それで病院内の警報が鳴ったのだったが、その警報によってzcc医療装置手術室が無断利用されていたことが解り、検査の列からナックが居なくなったこともあって、大変な騒ぎになったのだ。
「ナックはトイレに行くって言ってたんだけど、全然帰ってこなくてさ」
病室にも戻っていないし、何か事故にでもあったのではないかという話になったので、警察にまで通報する事態に至ったのだった。しかししばらく街中を歩いた後に病院に戻っていたナックのほうはあっけらかんとしていた。
「いや、別に大したことじゃないよ。ちょっとzcc医療装置をいじってみただけ。ずっと前からいつか触ってみたいと思ってたのよ、zcc医療装置を。」
「えーでも、病院の装置を無断利用したのよ。ちょっとヤバイんじゃない?」
サリが心配そうに言ったが、ナックは全然気にしていなかった。
「え〜そんなの心配ないよー。それはそうとすごいんだよzcc医療装置って、──私ね、聞こえてる全ての音の音階がわかるの。zccでコンパイルしたから、絶対音感が身についたのよ。すごいじゃない?」
ナックの方は何も悪気は感じていなかったが、もちろん勝手に病院の設備を利用したことに厳重なお叱りを受け、病院から呼ばれた養親と共々頭を下げて謝った。しかしナックはその場の空気から仕方なく頭を下げただけで、本心では反省していなかった。そのせいもあってナックは担当の医師のシープ(ナックが手術室に入る前に医学生と話していたあの医師である)からzcc医療装置をつかった不注意なコンパイルの危険性について、看護師立ち会いのもと、診察室で面と向かって説教されることになった。——医師の話はこんなものだった。
キューブ技術の原型はバレーのグルによって開発されたもので、今は特許を持っているキュービック・テクノロジー社がその開発を続けている。それらの技術はその多くがまだ謎に包まれた物なのだが、当然人間が作る技術には不完全性が残る。それはzccでも同じ事で特に高度な知識を持っているユーザーでない限り常に正常なコンパイルを成功させる事ができるとは限らない。だから正常にコンパイルされなかったソフトがそのままバグに気付かれずにインストールされたりすると、今まで平常に動いていたソフトウェアが動かなくなってしまうようなことさえ起こるのである。だから不用意なコンパイル作業は危険なのだ。
しかし、注意を聞いてナックは不満がった。
「わかることがわかって、何がいけないんですか」
「──私は音階をとらえることができてうれしいんです。なんでそのことがそんなにいけないことなのかわかりません」
ナックの心には自分が街中で音を受けながら歩いたときの心地好い感覚がまだ残っていた。なぜこの感覚を否定されなければいけないのかが、ナックにはわからなかった。ふーんと口を尖らせるナックに対してシープは冷静に言った。
「ユニバースではFLポートを使ったキューブにおけるzccのコンパイルは医療用に限定されている。まあ、これは公には言えない話だが、実はzccを人間が新たな能力を身につけるために有用であるという事実は過去にキューブの開発を行ったグル達によって闇に葬り去られている。それはzccによる──新能力の開発、という利用法がこのユニバースの社会や、果ては人類の有り様にまで大きな影響を与えかねないという、そういうグルたちの懸念があったからだ。」
「──、そんな、そんなくだらない理由で、キューブの技術が隠蔽されたっていうんですか? そういう使い方が可能なのに?」
「君の言いたいことはもっともだ。現実に利用可能な技術が社会の既得権益維持のために封じられるようなことはあってはならない、そう私も思う。しかし、グルたちはどうしてもそうしなければいけなかった。なぜなら、この事実を認めてはこのユニバースの社会は成り立たないからだ。」
しばらくツーンとしているナックだったが、間を置いてシープが言った。
「音感のことについては何とも言えないが、しかし特にキューブを仲介にしてFLポートから脳の情報をコンパイルした場合、不用意に操作すれば脳に深刻な後遺症が残る可能性があるんだ。」
シープは手元のナックのカルテを見ながら言った。
「え、後遺症? でも私全然大丈夫だよ。ほら足も動くし手も動くし。指も足指の動作も問題ないじゃん」
ナックは足と手を動かしてみせた。しかしシープは落ち着いた口調で言った。
「元気そうなのはなによりだ。しかしナック君にはこれから経過観察のため入院時期を延長してもらう。これは君のご両親にも許可してもらっている。経過観察期間中は病院で寝泊まりをする以外は特別制限はない。外出もOKだし、CSCHにも毎日通ってよろしい。しかし毎日病院の検査を受けることだ。君がzccを使ったとなれば君の健康状態を調べるために様々な精密検査が必要だからね。これは君の身の安全のために必要なことなんだよ。」
「えーめんどくさいなぁ」ナックは不満顔をしたが、シープのその判断をどうしようもなかった。
ナックは最後まで不満がって、話が終わった後もふてくされながら病室に戻って行った。ナックはそのときに鳴ったパソコンの効果音すら音階をそらんじてみせた。看護士が去った後、シープは端末に表示されたログに目を移した。そこには「Warning:1」の文字が映っていた。そしてシープはつぶやく。「たしかにあれはミドララミシだったね……」
健康診断期間を終えたナックは、自身でコンパイルを使ったことの経過観察のために入院はしたままだったが、病院から通うと言うことで学校の授業に復帰した。しかし学校ではナックがコンパイルで絶対音感を身につけたらしいという噂が全校中に広まっていた。
「おい、ナックがセンターのzcc機器使って脳の情報のコンパイルをやったらしいぜ」
「ナックって規則とか全然気にしないけど、今回も校則違反よね、絶対大目玉食らうわ」
「なんかすっごい音感が身についたらしくてさ。どんな音でもドレミがわかるんだって、あの音痴のナックが──」
健康診断休暇の休み明けの初日にクラスに入ってきたナックの姿を見て、教室中がどよめいた。ささやき声が周りから聞こえる中、ショジュがナックに声を掛ける。
「あ、ナック、ナック〜。ねえ、大丈夫なの?ナックがzccを使ったってすごい噂になってるけど。大丈夫?体とかどこも痛くない?」
「ぜーんぜん大丈夫よ。全然問題ナシ。久しぶり、ショジュ。元気にしてた?」
周りにいたナックの友達たちも「よっ、ナック。元気だった?」とナックに声を掛けた。
「ねえ、ナック、コンパイルで絶対音感身につけたってほんと? みんなその噂で持ちきりなんだけど。」
「うん、今の私にわからないと音なんてひとつもないわ。ええと、たとえば——」
その時授業のはじまりの五分前を知らせるチャイムが鳴った。キーンコーンカーンコーンとチャイムが鳴り終わるとナックは言った。
「あのチャイムの音はファラソド、ファソラファ、だね。」
「へぇー、そんなことがわかるんだ」驚き唸る友人達。
「zccってすっごいよ。誰でも能力を身につけられるんだから。──」
その後周りのうわさ話の中、ナックは自慢げに学校の廊下を練り歩いた。もともとユニバースの「ナック」と言えば知らないものは居ないくらいの有名度だった(ここには後ほど説明がいるかも知れない)が、ナック当人もこの時はより得意顔で学校の中を歩いていた。
「聞いたか?CSCH切っての天才児兼超問題児のあのナックが今度はzccか。先生たちは何の懲罰も与えないのかね?」
「自分がユニバースのナックだからなんて舐めた態度してたら、後でどうなるか知らねえな。」
そしてやってきた音楽の授業。先週の続きで実技テスト第2週だったが、今回の題目では講堂でそれぞれの生徒がクラスメイトの前でやはり歌を歌うことになっていた。生徒達の皆が慣れない古文で歌詞が書かれた歌を苦心して無理矢理歌う中、ついにナックの番が回ってきた。
「ほら、ナックの番だよ。zccコンパイルの威力ってどんなもんだろう。そんなに変わるもんなのかな」
「あんだけ音痴のナックなんだから、そんなにうまく歌えるとは思えないけど。」
しばらくざわついていた生徒達だったが、静まりかえる講堂の中心で微かな笑みと共に舞台に立ったナックはすっーと息を吸うと、のびやかな声で歌い始めた。
"Komm, lie her Mai, und ma che die Bäu me wie der grün,──(コム リー バー マイ ウント マ ー ッ ヘ ディ ボーイ メ ヴィ ー ダー グリューン)"【春への憧れ『Sehnsucht nach dem Frühlinge』より】
ナックの声が教室中に響くとともに皆呆気にとられた。
前のアヒルが鳴いているようなブツブツの声と違って、今回のナックの声はなめらかでとても透きとおっていた。抑揚のある歌い回し、深みのある声、緩急自在のテンポ、声の伸びのビブラート、聴かせ所ではその声は講堂内に強く響いた。その歌声が響いている間は、誰一人として声を出さなかった。
その美しい声に同級生達は唖然とした。まるで夢を見ているような2分間の後、ナックの歌が終わった後は講堂中は大拍手の喝采だった。中には席から立ち上がって拍手をするものさえ居た。舞台のナックは深々とお辞儀をすると、まるで銀幕の中の歌い手のように颯爽した歩きで舞台を降りた。ヴォイスもそのナックを遠くから見つめながら、皆と同じように拍手を送っていた。
舞台から席に戻ったナックは横の席に座っていたヴォイスに話しかけた。
「ほら、私だってここまで出来るのよ。どんなもんよ、もう私に音痴なんて誰にも言わせないわ。」
「お前すごい上手くなったな。惚れ惚れしちまったよ。でもお前ほんとに大丈夫なのか? 俺もあの後先生に聞いたけどzccコンパイルって後遺症が残ったりするんだろ。そりゃ歌がうまくなって得意げになるのはいいけどさ、もう少し——」
しかしそこまでヴォイスが言うとナックは話を遮るように言った。
「はいはい、もう説教は十分よ。あのもじゃもじゃ頭【シープのこと】にも散々説教されたんだから。いいわよ、あんたは認めたがらないんでしょうけど。——」
もともとCSCH切っての天才でありなにより問題児として有名だったナックだったが、コンパイルによる比類なき音感を同級生に見せつけ、今回の一連の事件からナックはCSCHでさらに有名になった。
——ユニバースのある河原で
「音楽なんて怖くないわ。さらばミュージックコンプレックス。どんな歌でも一人勝ちよ!」「オーホッホッホ!オーホッホッホ!」
「あの姉ちゃん怖えー。一人で叫んでるよ」
◆ ◆ ◆
「ねえねえ、見てよこのポスター。あたしこれに出場することに決めたんだ」
後日、ナックはどこからかあるポスターを拾ってきた。それはユニバース全都市圏で開かれる声楽のコンクールのポスターだった。そのコンクールはユニバースでは名の知られたコンクールで、声楽を専攻するものなら誰もが参加する大会だった。自分もその音楽の歌のコンクールに出ることを決めたナックは、そのポスターを片手に周囲に触れ回れまわった。
「あ、知ってる。年に一回、都市中央ホールで開かれるコンクールだろ? 昔あたしのお姉ちゃんが出たらしいんだけどさ、姉ちゃん100人中78位だった。」
クラスメートの女子が受け答えるともう一人の女子が言った。
「——そうなんだ、でもさ、今のナックの音感なら入賞とかいけるんじゃない?」
「すっごいもんね、今のナックの歌声。」
ショジュが明るい声で言う。
「──私ナックの今の声を聴いたとき驚いちゃったもん。ホントにあのナック?って」
しかしナックはわざとらしく胸を張ると自慢げに言った。
「私入賞で終わるつもりないわ。絶対優勝してやるもん」
「また〜、そんなこと言って——」
相変わらずのナックの大言壮語にアセする友人たち。しかしナックは叫んだ
「宣言するわ。今年のユニバースの歌姫はこの私よ!目かっぽじってよく視てなさい!」
ナックのその言葉を聞いて仲間の一人が笑いながら言う。
「ナック、それ女の子の使う言葉じゃないよ。それに目はかっぽじれないし──」
しかしナックはその言葉にも耳を貸さずに心のなかで呟く。
(あー、私が歌姫!絶対にありえないと思っていたこのシチュエーション、神様ありがとう!)
一人ではしゃぎながら教室のドアから出る。
しばし沈黙の同級生たち。。。しかしショジュが身を乗り出して言った。
「ねえ、ナックを応援しようよ!あんなに張り切ってるんだから!」
ショジュの言葉に、
「いいねえ、俺応援行くよ。」ヴィムが提案に乗るとクラスの男子も騒ぎ始めた。
「なに、あのナックが歌姫としてステージに立つ?そりゃ見逃せねえな」
「さぞかし神々しい光景でしょう」
しばらく教室中がガヤガヤとざわめいていたが、サチコが腰に手を当てると宣言するように言った。
「いいわよ、私も行く。」
「またー、サチコはヴィムが行くから行くんでしょー。」
「うるさいわねー。」女子学生「あー(汗)」
「へぇ~、なんか面白そうじゃねえか。なら俺も行こうかな」
タイキが言うとノリオがアンニュく言う。
「親分、サチコさんが行くから行きたいんでしょ」
「うるせえ!こういうのは盛り上げた者勝ちなんだよ。」
タイキがノリオのこめかみに拳を当てると
「いた、痛いですよお、親分」ノリオは顔をしかめて痛がった。
そしてノリオの頭から手を離すと、タイキは机の上に足を載せて高らかに宣言した。
「ここに我々はナックのステージを、最高レベルの応援で盛り上げることを宣言する──!タイキの名において異論は一切許さん!」
その言葉にしばらくのあいだずっと教室中がどよめいた。
——しかし「恐怖」はじわじわと姿を現そうとしていた。
地区中央ホールでコンクール予選がひらかれ、ナックはその予選に出場した。ナックは周知の歌声で大喝采の中予選を勝ち抜けると、都市中央ホールで開催された都市決勝に出場。当日は担当を務めるカンの司会の元でコンクールが進んでいった。
「と言うわけで、今年も声楽コンクールが始まったわけですが、今年は期待の新星がたくさん目白押しなので、最後までどうぞ目を離さずにおつきあいください。」
「頑張れナックー!」
会場には「頑張れナック、俺達私たちは応援してるよ」と書かれた横断幕とともに友人たち、そしてヴォイスが応援に来ていた。コンサートホールのマナーも無視してメガホンを使ってまで徹底的に騒ぎ立てる。皆この状況に興奮していた。なにせ自分の友人が都市決勝のコンクールに出場しているのだ。お祭り気分でここぞとばかりに盛り上げる気だ。
──コンクール都市決勝は強豪揃いだった。予選は任意参加の開催なのでほとんど鐘二つレベルの人もたくさんいたのだが、しかし今回は鐘三つレベルと言っていい人もたくさん参加していた。そんな中でナックは舞台に立った。ナックが照明で明るく照らされたステージでマイクの前に立つと、ホールの中は仲間と観客の声援で沸き立った。
「では次はエントリーナンバー35番、ナック・シオラさんで『最後の楽園』。では、どうぞ」
ナックが息を吸い込むと、それまで騒がしかったホールは静まり返る。そしてナックの声が響き始めた。
"Ich verbringe Zeit im Sonnenlicht Landschaft. ──"《イッヒ ファボリング ツァイト テム ゾノンリフト ザンドシャフト》【ひだまりの中でゆるやかな時間を過ごす。】
詞を歌い始めるナック──。その歌声は順調にみえた。
"──Splash der Brunnen sind funkelnden, klaren, blauen Himmel, werden üppigen grünen, Vögel singen, in unserer Stadt zu loben. 《──プレッシュ デル ボーネンズ ゼンド フォンケンデゥン クラーレン ブラウン ヘメル ペーデン アッピデン ホーベル ズィンデン イン アンザーラー ズラッシュタ ズ ローベン》【噴水のしぶきはきらめいて、空は青く澄み、緑溢れ、鳥は歌い、私達の街を賛美する。】"Ja, das ist das letzte Paradies. die Stadt der Hoffnung, die Gott würde ewig so weitergehen…" 《ヤ ダス イツ ダス レツト パラディス ディスラシュト ダー ホフノング ディ ゴット フィウディ イウィジ ソ ウァイターギヒン》【そう、ここは最後の楽園。神が作りし永遠に栄えるはずの私達の希望の街。】
その時、ナックの歌声が急に止まった。無音の後にどよめく観客達。誰もが何が起こったのかわからなかったが、舞台の上のナックは歌声を詰まらせたまま動かない。司会のカンも何が起きたのかわからないまましばらく呆気にとられて困惑していた。
「皆様、落ち着いてください。なにかハプニングが起こったようです。会場の皆様はそのまましばらくお待ちください。」カンはナックの傍に走り寄ると、小さな声で状況に詰まっているナックに再び歌うよう指示した。しかしナックの額には冷や汗が滲んでいた。
——そしてその後間を置いて、ステージの脇に戻ったカンのフォローでタイミングを測って再び歌いだすナックだったが、しかし、途中までは歌えるもののやはり楽譜のさっき歌声が止まったところから、どうしてもその音、そしてその先を歌うことができなかった。
(──なんで、なんであの先を歌えないの? あそこだけ歌おうと思っても声が出ない、音が思い浮かばないの。)
「どうしたんだろナック。途中まではすごい上手く歌ってるのに、突然歌うのをやめるなんて。」応援に来ていた仲間の一人が言った。ヴォイスの視線は深刻な眼差しで遠くのナックを視ていた。
観客のざわめく声の中、一人舞台を降りるナック。その顔は引きつっていた。予想外のハプニングに会場の中はどよめいていた。
コンクールが終わるより早く、自分の身に異常を察知したナックは応援に来た仲間たちをほうったままバスを乗り継いで家に戻ろうとした。しかし、家にたどり着く前に早くじっとしていられなくなったナックは、街中を当てもなくさまよった。街はどこも夕焼けの黄昏にオレンジ色に染まっていた。
——しかし「エラー」はさらに顕著になっていく。
いくら思い浮かべてもナックはその音がわからなかった。そればかりではない、街中の「たちいりきんし」とひらがなで書かれた空き地への標識の最後の文字がナックにはどうしても読めなかった。そればかりか読もうと視線を合わせると頭の中でなにか音のようなものが鳴った。そしてそのあとも街中のあらゆる文字や、そして人の話し声や物音が、前とは違うざわめきと共に音に聞こえ、そしていっそう深くなっていく恐怖を感じたナックは病院へ戻る道へ向かった。
病院の中はいつもと変わらなかった。ナックは自分の表情が相剋なものだったとわかっていたが、異常を周りに察知されないように普通に振る舞い、しかし受付の事務員の挨拶を返すことも出来ないままそこを通り抜けて、自分の病室へ向かった。
しかし自分の病室にたどり着く前にナックのエラーは激化していった──。「キーンコーンカーンコーン(ファーラーソードー、ファーソーラーファー)」ふとチャイムの音とともに頭の中で階名をささやく男の子の声がしてナックが体を固まらせると、院内放送のメロディーとともにそれまで喧騒のように遠くで鳴り響いていた「音」が一気に頭の中になだれ込んできた──。ナックはよろめきながら病室に向かうが、もはやナックにとって病室までの廊下は絶壁の登山に等しかった。
——そして異変に気付いた周囲の人の声さえそれに聞こえる中、恐怖のあまりにナックは悲鳴を上げついに気絶した。——
…zccのキーホールにナックのキューブが載った。近くには手術台に寝かされた意識のないナック。心拍を示す電子表示のもと、そして近くで治療を行う医師の中には、シープの姿もあった。 ナックの治療のため端末にトップスピードでプログラムを打ち込むシープ。ナックはずっと手術台の上で昏睡していた……。
◆ ◆ ◆
ナックは心拍を監視していた脈拍計の電子音と、部屋の外から聞こえる鳥のさえずりの音で目を覚ました。あたりは五月の穏やかな日差しが床に日だまりをつくり、蛍光灯の明かりが部屋を薄暗く照らし出している。外からは澄んだ風がナックの頬を触った。少しの間ぼんやりとそんなことを感じていたナックだったが、ナックは頭を動かすと、今自分がベッドに寝ていて、体に点滴の針が指されていることに気付いた。——そうだ、私はあの時「音」と共に気絶したんだった、それから……。そして視線を動かした先に、ヴォイスが丸イスの上に座って寝息も立てないまま眠っているのを捉えた。
しばらく何も言わずにその顔を見ていたナックだったが、息を吸う音と共にヴォイスが目を覚ますと、ヴォイスもナックが目を覚ましていることに気付いた。
「ナック——?おい、目を覚ましたのか?おい、気付いたのか?」
ヴォイスはしばらく慌てふためいていたが、ナックのほうはまだ自分の状況がはっきり認識できていなかった。
「うん。ここ、病院、だよね。私、あの時気を失って——それから——」
「ああ、よかった、ナック〜!」
ナックが言い終わらないうちにヴォイスが声を上げると駆け寄ってベッドに寝ているナックに縋り付いた。
「——ちょっと!ヴォイス、何?なんなのよ! ちょっと、離れなさいよ!」
状況を理解できずに慌てふためいていたナックだったが、ヴォイスの頬が涙で濡れていることに気付いて、溜飲を下げた。ナックを離すとしばらくヴォイスはこぶしで涙を拭っていたが、ナックはその様子を見て一言、「ごめん、」と呟いた。
「俺たちがあとから病院に来たら、おまえ廊下で気を失って倒れてるんだもん。すぐ近くにいた看護師さん呼んで、手術室に運ばれたんだけど、先生は絶対助かるって、心配するなって言ってたけど、俺どうしても心配で、ホント、目を覚まして良かった。良かった〜。」
後は泣きじゃくって良く聞こえなかった。
しばらくヴォイスが泣いているのを視ていたナックだったが、部屋の外から声がした。
「おい、ナックが起きてるぞ! みんな、早く来い!」
二人の様子に気付いたヴィムが病室の外にいる仲間に伝えると、手に持っていた荷物を放り出してベッドに駆け寄ってきた。
「大丈夫なのか。もう大丈夫なのか、痛いところとか無いか?」
ヴィムが呼び掛けると、ナックは落ち着いた表情で答えた。
「うん、もう大丈夫。」
遠くから声がしたかと思うと、じき病室の外からも仲間達が駆け寄ってきた。
「ナック!」「ナック!目を覚ましたのか?」「まあ、ナックさんが目を覚ましたって?」
看護師のエイドも外から走り寄ってくる。
そしてヴィムはホッと胸をなで下ろすと呟いた。
「ああ、ほんとに良かったよ、目を覚ましてくれて。俺たちほんとどうしようかと思ったんだから——。あん時、声楽コンクールが終わったあとお前俺達と一緒に帰らなかったろ。病院に戻ったらちょうどお前廊下で倒れれて。ヴォイスが呼びかけても反応しなかったんだぞ。もう、ほんと、心配かけやがって。」
ナックのベッドの周りに集まると、仲間たちは皆安心したように言葉を交わした。
「俺、ナックの親御さんのところに伝えに行ってくる。待合室にいるはずだから」
そう言うと仲間の一人が部屋の外へかけ出した。
「脈拍、血圧、血糖、呼吸、体温、問題なしね。もう心配ないわ。」
エイドがそう言うとそれを聞いて仲間たちは皆ほっとしたようだった。
「ナックさん、何か言い忘れていることない?」
少しの間ナックはエイドのその言葉の意味がわからなかったが、ハッとすると一息飲み込んでから言った。
「ごめんなさい。私のせいで、皆んなに迷惑かけて──」
「わかってるならいいわ。親御さんたちにもきちんと自分の気持を伝えてね。私は今から先生のところに行ってナックさんが目を覚ましたことを知らせてきますから」
エイドは点滴用の袋の吊り下げ台を引きながら、病室の外に出ていった。
「ここじゃ手狭だから俺達もちょっと待合室の方に行っとくぜ。」
エイドと仲間たちが出ていったあと、病室にはナックとヴォイスが残された。ナックは目を伏せ、しばらく無言の二人だったが、
「あのさ、ヴォイス?──」
ナックが言いかけた時、その時部屋に入ってくる大きな声が聞こえた。
「ナック!」「無事か?ナック!目を覚ましたのか?」
外からの声に二人が顔を上げるとヴォイスとナックの両親が声を上げながら病室に駆け込んできた。
「父さん!母さん!」──
しばらくしてより意識がはっきりしてきたナックは、エイドの同伴のもとで歩けることを確認すると、診察室に呼ばれた。そこにはシープが端末の前の回転椅子に座って待っていた。おずおずとその前のイスに座ったナックだったが、シープは口を開くとこういった。
「目を覚ましたばかりで、聞きたくないこともたくさんあるだろうが、私は君にいろいろと説明しなければいけないことがあると思うんだね。そう、今回君が被った症状とその原因、そしてそれとzccコンパイルとの関係について話しておかなければいけないと思う。」
ナックは少しうつむくと無言のままシープの話を待った。
──シープの目の前の画面にはナックがコンパイルをしたときに残されたログが表示されていた。
シープの話はこういうものだった。
zccはキューブの効率的なコンパイルのためバレーのグルたちによって開発されたコンパイラの一つで、現在ユニバースで実用として使われているものはこれひとつである。ナックも以前学んだように、zccはキューブ技術を支える基幹技術とも言えるバイナリだ。zcc自体は綿密に確立された技術でありキューブ上だけで使う限りは単にソフトウェアを生み出すためのコンパイラにしか過ぎない。しかしzcc医療装置となると問題は変わってくる。zcc医療装置は被験者のFLポートから被験者の脳内の情報にまでアクセスするため、その安全性確保のために例えば虹彩認証装置などが配備されているわけだ。患者の脳の中の情報までアクセスするということはつまり脳の中の情報まで書き換えて動作するということであり、ケースに因っては脳内の情報を破壊するおそれがあるからだ。
ナックがコンパイルしたのはキューブのルートシステムに設置されていたサーバに保存されていたソースコードのうちの音楽関係のパッケージのソースコードと、ナック自身が日頃の生活の経験の中で無意識のうちにキューブに書きためてきたコードだったが、端末でコマンド操作をするときにがめつく手っ取り早く一括指定で操作したため、また、バージョンにずれのあるコードを一緒にコンパイルしたこともあって、明白なエラーこそでなかったものの、コンパイル時に「警告」が一件発生していた。それは「必要なファイルが見つかりません - 古いバージョンのソースコードを利用します - コンパイルで問題が発生しました - libtonlは外部関数を利用します。」と言うメッセージだった。
そしてインストール時の問題として、文字処理関連のバイナリファイルの一つを新たにコンパイルしたバイナリファイルの一つで置き換えていた。これらの問題によって音と文字の間の処理系に不適切なリンクが発生し、今回の現象を引き起こしていた。
たまたま今回ナックがコンパイルしたソースコードの性質上、最初は悪影響を現さなかったこのバグだったが、時間経過とともに悪質化して、あの体験と恐怖をうみだし、そして最終的にナックの意識を失わせるまでに至った。シープはナックの症状にコンパイル直後に診察した時点では危険性が見いだせなかったこと、そして悪質性の発現に時間経過が関わること(シープはコマンドが利用する設定ファイルの不要なバッファによって時間経過の後にその症状が発現すると考えているとナックに言った)がこれまでの経験になかったこと、そして今段階でも発現に時間経過が必要である理由はわかっていないことをナックに告げた。
本来ならキューブのバックアップシステムからシステムを復元すれば問題なかったのだが、ナックのバックアップシステムが独自の構造に改変されたものであったため、感覚ポートを利用した復元が不可能だった。なのでシープらは治療措置として中央サーバーのデータベースから(この時は緊急を要するためにアクセス権限の許可がおりていた)ナックのシステム内に書きためられていたオリジナルのコードをのぞくおなじパッケージ群の適切なバージョンのソースコードからコンパイルされたバイナリのデータをコピーし、それらを置き換えることで救急処置を完了させた。この時、ナックのシステムとデータベースからのソースコードを統合するためのコードはシープが即席で書いた。
「今の君には平常の音感覚が戻っているはずだよ」
その言葉とともに自分の感覚の平静さに気付いてほっとするナック。しかし肩を落として顔を曇らせると呟いた。
「私今度のコンクールでどうしたらいいんだろう……。絶対優勝するって思ってたのに」
その顔を見ながらシープは言った。
「それは君が決める問題だ。しばらくはうちの病院で安静にして、リハビリに励んでもらうことになる」
「リハビリ……ですか」
「ああ、今回のことで脳も体もある程度ダメージを受けているはずだ。それに完全に治ったと確認できるまで、しばらく経過観察をしておきたいのでね——」
シープによる診察が終わった後、ナックは暗い表情のまま診察室を去った。診察室の外ではヴォイス達が待っていた。
「行こうか、ナック……。湿気た面してないで、元気出せよ。」
ヴォイスが暗い表情のナックの声をかけると、
「うん。」
ナックは廊下をヴォイスたちの後に歩いて病室へ向かった。病室に向かう間、ナックは頭の中で一人呟いた。
(あの小さな男の子みたいな声、あれは何だったんだろ──)
ナックが部屋を出たあと、再び端末の画面に向かったシープは、そのなかの「nuqsa.c」とファイル名がかかれたソースコードをみて一人つぶやいた。
「このコード、とてもきれいな書き方をしたコードだ。これを彼女の無意識が……?」
リハビリに入ったナックは順調な回復を見せた。
リハビリ中のナックは周囲の配慮による大事をとって車いす生活となった。車いすを使うよう言われたときは困惑したナックだったが、zccの後遺症が身体制御に現れる心配が完全に拭えなかったため、しばらくのあいだ経過観察のため車椅子に乗ることになった。ナックは車いすの車輪を回しながら病院の建物内、そして敷地の中を時間をゆったりと過ごしながら周り、今はもう平常に戻った自らの感覚をたしかめるようにそのリハビリ生活を送った。──
ある日ナックは病院の敷地内にある森林公園に出かけた。この公園は病院が管理しているのだが、地域への病院設備の開放という目的から、一般の人も入れるようになっていた。その地区ではわりと知られた場所で、自然と触れ合えるとして週末は家族連れなどが散策に来ている様子が良く見られる場所だった。——梢の間ではユニバースだけに見られると言われている五月ゼミが軽やかな音で鳴いていた。敷地内の木陰道を車いすでゆっくりと辿っているナックだったが、
(あ、あれは……)
道の途中で良く見知った顔と出会った。小柄の背に太い縁の眼鏡。それはCSCHでも同じクラスに所属しているスコラだった。クラスメートで互いに面識があるスコラとナックだったが、堅そうなスコラとCSCHきっての問題児でもあるナックはあまり友達関係はなく、それまでほとんど話したことがなかった。そのときスコラはスケッチブックと鉛筆を手にもっていて、どうやら風景スケッチを行っているようだった。
「おはよ、スコラ、何描いてるの?」車いすの車輪を回しながら近寄ったナックがスコラに声を掛ける。
するとナックに気付いたスコラが答えた。
「あ、おはようございます。ええっと、ナックさん、でしたっけ? 今描いているのは五月ゼミですよ。ちょうど今頃の風物詩ですからね。ここのあたりは五月ゼミがたくさんいるんです。——ところで、ナックさんはなんでここにいらっしゃるんですか? 怪我で休んでるとは聞いてましたけど。」
「うん、ちょっとね。私今ここの病院に入院してるんだ。ちょっとしくじっちゃって。」
そう言うとナックは恥ずかしがるように笑った。
「スコラのほうはなんでこんなところでスケッチなんかしてるの?」
ナックの質問にスコラが答える。
「僕は絵を上達するためにいつもスケッチの練習をしているんです。こうやって街中を歩いて、良いなと思った構図やモチーフがあったらそれを描くのを習慣にしているんです。」
ナックの天才に対してクラス一の秀才と言われるスコラは、同時に絵を描くのが得意だと言うことでも有名だった。
「へぇー、そうなんだ。そういえばスコラって美術の授業でいっつもすごい絵描いてるよね。私なんか絵は全然下手だからどうやって描くのかわからないんだよね。どーしようもないくらい。前ヴォイスにウサギ見せてこれはサルかって言われたくらいだから──」
ナックが自分のこっ恥ずかしい話を暴露すると、スコラは木の上を見上げながら言った。
「絵をうまく描くためには、その対象物をよく見て、観察して描くんです。一見知っているように思っているものでも、人間って言うのは結構思いこみでものを見ているものです。いざ鉛筆を走らせようとするとどう描くのかわからないことがよくある。だから、よく見て、形とか色とか陰影とかを捉えながら、紙に写していく。それが絵を描くために必要なコツです。」
「へぇー。」ナックが唸る。
「僕はもともと不器用な方です。正直言って周りの人みたいにうまく物事をこなせない。だからこそ文章をじっくり読んだり、こうやってスケッチをしたり、そうやって例え少しずつでも自分の能力を高めていきたいと思ってるんです。才能はなくても地道に努力できる、それが僕が持ってる少しばかりの才能です。」
ナックにとって堅くて冷めた秀才児、のイメージのあったスコラの日常でのこの地道とも言える習慣をみて、このこころがけにナックは自分の今までの生き方を思いを馳せた。──こういう生き方で歩んでいる友人がここにいて、でも今のこの自分はどう進んでいけばいいのだろうか……
そして木の上のセミを観察しながら鉛筆を走らせるスコラを横に、目を閉じて周囲の音を聞き取るナック。風に揺れて梢のざわめく音、木々の間の五月ゼミの鳴き声、遠くからの鳥の声、街から流れてくる車の音、人の声、スコラの走らせる鉛筆が紙をこする音、 そして木々の隙間から漏れてくる太陽の光の揺らめき……
(もう音階には聞こえない……、でも……)
目を開いて木洩れ日を見つめるナック。そして再び目を閉じたとき、担当看護師のエイドの声が、ナックを探しに遠くから呼んで来ていることに気づいた。
「ナックさーん、昼食の時間ですよー!」
ナックは車椅子を回すと、エイドが走ってくるのを認めた。気づかないうちに食事の時間になっていたようだ。
「あ、もう昼食の時間みたい。私呼ばれているから帰るわ、スコラ。スケッチ頑張ってね。出来上がったら後でメールに添付して送ってよ」
「ああ、いいですよ。ナックさんもお大事に。また学校で会いましょう。」
そして二人は別れの挨拶をかわすとナックは病院へ戻っていった。
◆ ◆ ◆
そしてあのコンクールの全都市決勝(都市決勝よりさらに上のレベルで、最終選考である)が行われた次の日にナックはセンターを退院した。学校でも以前のように(音痴というほどのものは直っていたが)天才としてのナックに戻った彼女は再び日常の学校生活にだんだんと心をもどしていった。ナックの心はいつも通りに元気を取り戻しているかのように見えた。
しかし事件のほとぼりも冷めたある日、ショジュはナックの姿を探していた。授業が終わった後ナックと一緒に帰ろうと思ったショジュだったのだが、そのナックが見つからなかったのだ。友人に聞いてもナックを見かけたという話はなく、思い当たる限りのいろんな所を探しまわってようやくショジュがナックを見つけると、ナックはあの高度医療技術センターの病院近くの橋の中央で欄干に腕をかけ黄昏れていた。橋の向こうには黄色い太陽が真っ赤な夕焼け空の中に揺らいでいた。遠くをカラスが幾羽、飛んでいく。
「あの、ナック?」
遠い目で夕空を眺めるナックに、ショジュは心配になりながらも声をかけた。
「あ、ショジュ。」
ボッーっとしていたナックはショジュの声に気づいて振り返ると、抜けたような声で答える。その様子を見てショジュは一呼吸飲み込むとナックに言った。
「あの、どこか調子悪いの?学校終わって一緒に帰ろうと思ったら、居なかったから」
「うん、別に調子悪いわけじゃないんだけどさ。ただ、ちょっと考え事してたんだ。コンパイルした時のこと思い出すと、いろいろ複雑な心情になっちゃって。」
ナックは少し淋しいような笑みを浮かべて橋の下の川面を見つめた。
「複雑な心情って?」
ナックの言葉と表情に不安になったショジュが聞くと、ナックはとつとつと言った。
「調子に乗っちゃって不用意にコンパイルしてさ、あれだけ恐怖を味わったのに、それでも歌がうまく歌えた時のこと思い出すと物欲しくなっちゃうんだ。ほら、私ってさすごい音痴だったでしょ。それがコンプレックスだったから、音階を聞き取れるようになったときはすごい嬉しかった。それだけじゃなくて、音の心が解ったような気がしたのが、本当に嬉しかった。うん、強気に言うのなら私は全然後悔してないよ。でも、もっと地道に歩んでいく生き方もあることを知ったからさ。私は私だから、確かに周りとは違うかもしれないけど、それでも穏やかな気持ちっていうか、小さな喜びを大切にする気持ちっていうものをこれからも忘れたくないなって。ま、私のことだからどう変わっていくかはわかんないけどさ──。」
ナックの言葉にショジュは何かを言いたくて、でも何を言えばいいのかわからなくて、少しの間沈黙が流れたが、一つ大きく頷くとショジュは言った。
「うん、ナックはナックだよ。前聴いた時のナックの声、記憶に残ってる。すっごい心に響いた。前のナックがナックで、今のナックがナックなら、あの時のナックもナックなんだよ。あの声は紛れもなくナックの声なんだよ。自慢屋で、自由気ままで、でもどこか怖がりで、どこか女の子らしい──。あの声は、そのナックの心が生み出した他の誰でもないナックの声なんだよ!」
そしてショジュは持っていた通学用バッグの中から紙を取り出すと、それを見せた。
「ほら、これ、ナックがこの前作って見せてくれた楽譜。荒削りだけど、すごいいい旋律だと思う。これもナックの曲。ナックだからこそ作った曲なのよ。」
「ありがとう、ショジュ」
そう言うとナックは手の甲で涙を拭った。
「ありがとう、ショジュのおかげで元気でてきたよ。もう大丈夫。」
涙で濡れたナックが笑顔を見せると
「じゃ、一緒に帰ろ!」ショジュの言葉にナックがうなずき、二人は家路についた。
その時遠くではたまたまその場面を缶コーヒーを買い出しに来ていたシープが見ていた。シープは自分の過去を振り返る。
「──私にもいたな。あのような言葉をかけてくれた人が。」
その記憶の中では、楽器を机の上におき、楽譜を散らばらせて机に伏す若き日のシープとその肩に手をおく、その友人の姿があった。 ──
--> GO TO NEXT LEVEL
Z-C Session $02「エラー-->ナイトメア」Beta
参考文献:『音楽Ⅰ 改訂版 Tutti』教育出版株式会社


