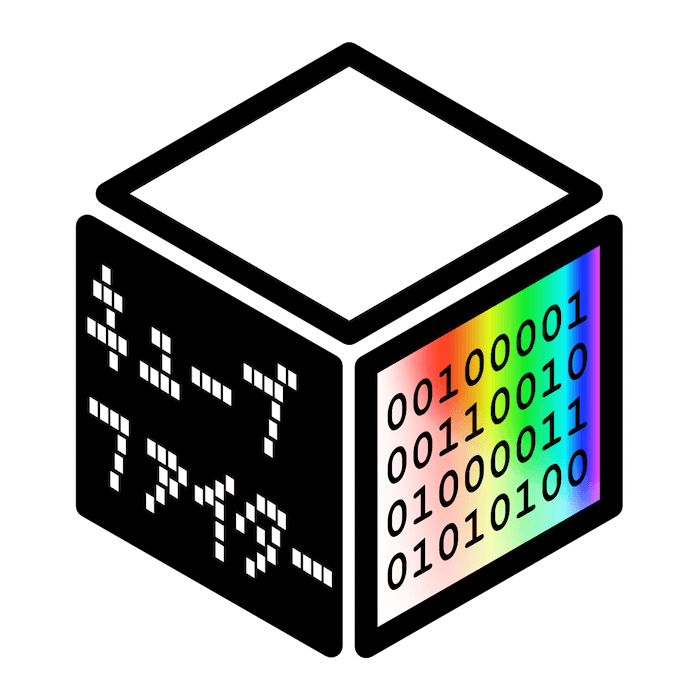
Z-C Session $01『微光』Beta
イントロダクション
現在より遠い未来、地球のある場所に「ユニバース」と言う名前の都市群があった。その街は高度に都市化、電子化しており、その情報処理技術は非常に高度な域に達していた。電子技術は都市インフラをはじめ街の至る所で使われていた。
そのユニバースの情報処理技術を支えていたのが「キューブ」である。キューブは透明で立方体の形をした手のひらに収まるサイズのデジタル媒体であり、その中にはユーザーの脳の情報と同期されたシステムが内包されていた。ユニバースの人々はこのキューブを使って日常生活の中であらゆる情報を処理していたのである。
キューブは過去にバレーのグル達がコンピュータ技術の粋を集めて作り出した究極のデジタル技術だった。が、しかし、情報技術というものは常に完璧ではない。当然のようにキューブについても悲喜こもごもの逸話が生まれてくる。
この物語には二人の主人公が出てくる。その二人とはヴォイス、そしてナックである。二人は家族であり、生みの親を失って養親の元に引き取られた過去を持つ。また二人はユニバースにあるキューブに関する知識を学ぶための学校「CSCH」の生徒でもある。
ヴォイスは冷静な眼差しを持ったCSCHの男子学生。その名は「論理」を意味する。ナックは奔放な性格を持った同じくCSCHの女子学生。その名は「直感」を意味する。二人は同い年で、年齢は今で言うと中学生くらいだろうか。ユニバースのとある街で、養親と共に暮らしている。——二人は覆しようもない運命的な出生を持っていた。
この物語では、そのヴォイスとナックの二人、そしてそのCSCHの仲間達と共に、主人公達の日常から始まる物語が時を進めていく。そしてその物語はいつしか、キューブの中に秘められた、ユニバースの人々の破滅と再生のシナリオへと辿っていくのだった。
用語説明
ミクセリタワー:ユニバースの都市部の中心にある最も高いタワー型の建築物。このタワーは同時に電波塔の役目を果たし、キューブのルートシステム及びネットワークの中枢をも担っている。
統括局:ユニバースの自治活動を行っている組織。清掃局などと似たような統括局という名前ではあるが、現実世界の言葉で言えば一種の政府にあたるユニバースの最高機関。
リンク:キューブのシステムとユーザーの脳の情報の同期設定のこと。またはシンク(同期)とも言う。シンクを行うとユーザーの脳の内容とキューブのシステムのデータが統合されて対応関係になる。
トランス:キューブにまつわる都市伝説のこと。人間の生命と直結しているキューブ及びその技術には不可思議な伝説が多々ある。その中でも特に有名なものは「キューブの七不思議」として一般に広く知られている。
Session $01『レジストネシス最終処分場』
——ユニバースの都市部に位置するある区画にて。
「よっこらせっと、」
ある日、ユニバースの清掃局員の〔コードネーム=〕コーチと〔コードネーム=〕スモークの二人組はミクセリタワーが遠くに見えるその収集区域でゴミの回収作業を行っていた。二人が今回回収作業を行っているこの通りは裏通りなのであまり人気はない。このあたりは都市化が非常に進んでいる地域だったが、それは綿密に計画された都市計画の結果でもあり、その近代的かつ衛生的に設置されたゴミ集積場に整然とゴミは捨てられていた。それを二人は回収しているのである。
あたりは既に昼下がりの陽気で二人の額にはじっとりと汗が滲んでいる。
実際の作業としては、コーチが車の後ろに立ち、スモークが掴み挙げたゴミ袋をコーチに渡してコーチが収集車のプレス機の中に放り込むという連係プレーでゴミを収集していっていた。ゴミを収集車に放り込むだけの仕事のコーチの方が楽だが、コーチは高齢で、かつ自分から仕事をするのを嫌がる傾向の性格だということを承知していたスモークは、文句も言わずに仕事をこなしていた。
(それにしても、全くこの辺りはゴミ捨てマナーがなっている)とスモークは思う。
そもそもユニバースのゴミ収集システムは近代化が進んでいる。資源ゴミは全て適切な方法でリサイクルされるし、その他のゴミの分別方式も確実。焼却場はダイオキシンを出さないよう高温でゴミを溶かす方式のものだ。確かに地域によっては所々衛生状況がいいとは言えない場所もあったが、大抵は統括局の言う「クリーンで安心」な衛生環境を築いていた。
——ゴミ置き場から引っ掴んだ最後に残っていたゴミ袋を、今度はスモークが自分でゴミ収集車のタンクに押し込むと、ゴミはすぐさま回転する歯に潰されてタンクの奥に見えなくなった。これで午前中の分は完了だ。
「うむ、ごくろうさん。これで午前中の分は片付いたな」コーチが声を掛けると、
「はい、ここいらで休憩にしましょうか」スモークが額の汗をぬぐって応えた。——
コーチとスモークは清掃局の公務員としてユニバースの街の清掃活動を担当している。もちろん以前はそれぞれ別のチームで働いていたのだが、最近になってこの二人でチームを組むこととなった。コーチは渋い面構えのいぶし銀風で、老齢であり定年前と言ったところか、かなりとげのある言い回しをする老人だ。一方のスモークは若手である。
休憩時間にはいると、スモークは住居の塀に寄っかかってタバコを吹かし始めた。三度の飯よりタバコが好き、というスモークの昼休みのいつもの習慣なのだ。コーチは朝出勤する前にコンビニで買ってきた弁当を開いて割り箸を割った。スモークがフーッと煙を吐くと、コーチに話しかけた。
「いやあ、参っちゃいましたよ。来週開く予定の親戚のホームパーティーに招かれましてね。なんでも子守要員が足りないとかで、それを頼まれましてね。子供の世話って大変でしょう。ほんとは断りたかったんですけど。うちの母親がどうしても行きなさいって言いましてね」
「嫌なら断ればええやないか」コーチはつっけんどんに答える。
「いや、でもうちの親の決定は絶対すっから。それに手伝ってくれたらタバコ一箱買ってくれるって言うんすよ。不当な取引ですけど、少しはマシになるかなと思って」
「ま、そんなら義務と思ってこなすことだな」
相変わらずのコーチの応対に不機嫌にもならずに、スモークはコーチに話しかける。そしてタバコの煙をフッーと吐くと、気付いたようにコーチにこう質問した。
「コーチっていっつもコンビニ弁当食べてますけど、結婚とかもうしてるんすか? 奥さんがいるなら愛妻弁当とかもってくるのかなとか思ったんすけど。」
コーチはいつも昼休みにはコンビニ弁当ばかり食べていた。日によって内容は様々だが、大抵は食べているのは幕の内弁当みたいなものだ。それとペットボトルのお茶。それはスモークにはいつも見慣れている風景だった。以前スモークは職場のコーチの仕事机の中にコーチの家族と思わしき写真が入っているのを見たことがある。別に盗み見たというわけではなく、コーチがいない時に必要な書類を探していて見つけたのだが、それは子供の幼稚園の卒園式の時に撮ったとおぼしき写真だった。その写真ではコーチはまだ若く、子供と一緒にそばには清楚な服装をした女性が映っていた。
「——知らん。」
スモークはどんな返答が来るのか期待していたが、コーチは即答でこう言った。
「知らんって、どういうことです?」
「わしはしがない一人もんや。わしの家族のことなんてしらんわい。愛妻弁当?そんな甘ったれたもん食えるかいな。わしはコンビニ弁当で十分や」
相変わらずコーチは弁当を割り箸でつついている。
「いやー、甘ったれたもんなんすか? 俺なんか結婚したらそういうもの奥さんが作ってくれたらうれしいなあ、とか思っちゃうほうなんすけど、そういうもんすかね。てか、えっと、コーチって一人で暮らしてるんですか。ご家族とは一緒じゃないんすか?」
「だから家族のことなんて知らん言っとるやろ。下らん話振って食事の邪魔をするんやない。」
二人はいつも休憩時間中にはとりとめのない会話をしていた。大抵スモークがタバコ片手に話を振ってコーチがあしらうタイプだったが、コーチの人格が悪くてそう言う態度をとるわけではないことを知っていたスモークは、それでも何かとコーチに話を振った。
そして今日もそうやっていろいろな話題を話していたのだが、そのうちに二人の話はキューブに関する話へと辿っていった。
「最近になって廃棄処分のキューブが送られることになっている最終処分場が満杯になりそうだとか言ってですね、新しい処分場を作る計画が上では持ち上がっているそうですよ。キューブも今世紀になってから普及してきましたけど、使用済みの廃棄処分しなければいけないキューブはたまりにたまってきていて、これからキューブ世代が老齢化してくるとなると、当然廃棄キューブも増えていく。結構上も頭悩ましているみたいです。」
「処分場?キューブたあ特殊なタイプの強化ガラスで出来とるんだとわしも聞いたことがあるが、ほなら溶かしてリサイクルしてまた使えばええやないか。わざわざ処分場に捨てて場所をとる必要もない。」
今回はコーチが珍しく話題に反応する。
「いや、それがキューブってのは一度リンク設定すると二度と壊せないんですよ。だからリサイクルも出来ないんです。」
「壊せない?んなもんあるか。使い終わったものはリサイクルする、太古の昔からの当たり前のことだろうが。ほないなおかしな話しがあるか。変な作り話して年寄りをからかうんやない。」
——リサイクルできない、と言うことは長年清掃活動に従事しているコーチの常識ではあり得ないことだった。コーチは割り箸を振って話を制したが、しかしスモークは話を続けた。
「作り話じゃないっすよ。それが、キューブというのはユーザーの脳と同期設定を行うとそれ以降全く物理的破壊を受けなくなると言う性質を持つんです。一説にはそれはキューブの仕様が作られたときに開発者の一人が細工をしてリンク時にキューブ内部に結合力を引き起こす『強い力』を発生させているからだとも言われているそうっすよ。とにかく、どうやっても、重機で押しつぶしても壊れない、それがキューブなんす。この話はキューブの七不思議って呼ばれているもののうちの一つなんですよ。」
そう、キューブはリンク設定後は物理的影響で壊れることはない。それは「キューブの常識」と現代人の間では当たり前に言われていることだったが、コーチは老齢なためキューブについての知識はあまりなく、そう言った話も初耳だった。
「さあ、休憩時間はそろそろ終わりにするか。下らん話しは終わりにしてはよ収集車乗れい。午後は西B地区の回収作業をせにゃならんからな。あそこはちっと骨が折れるぞ。」
コーチが収集車の運転席に乗り込むと、後からスモークも助手席に乗り込んだ。午後は別の地区のゴミ回収作業があるのだ。コーチはアクセルを踏むと車を発進させた。——
◆ ◆ ◆
それからいくらか経ったある日のことだった。コーチはその日仕事は休みで、近所にあるホームセンターまで日用品を買いに車で出かけていた。その途中でたまたまコーチ達とは別のチームが担当しているゴミ収集地域に入ったのだったが、そこはちょうどユニバースの都市群の中でも郊外の住宅用区画にあたるところで、閑静な住宅街が広がっていた。コーチはちょうど昼時になったので街角で車を止め、いつものようにコンビニ弁当をつつこうと弁当をビニール袋から取り出したのだが、食べ始めようとしたときに、サイドドアのガラスの向こうにちょっとした騒ぎを見つけた。
それは住宅街の中のとある一戸建てだったのだが、その玄関の前のところに清掃局のゴミ収集員が二人帽子を取って立っている。どうも彼らは勤務日程がコーチ達とは違って今がちょうどその就業時間らしい。顔から言って二人とも若手のゴミ収集員のようだ。そしてその玄関のドアは開け放たれており、しばらくコーチが車の中から様子を見ているとそのドアからは30才くらいだろうか、一人の女性が出てきた。その女性は手にトタンで出来た箱を持っていた。
——コーチはこの時はまだそれが何なのか知らなかったが、その女性が手に持っていた箱は使用済みのキューブを廃棄するときに使う箱だった。キューブはリンク設定をしているユーザーが死亡すると使用不可になるが、そのために使用済みのキューブは廃棄しなければならない。そのトタン箱はキューブの廃棄処分を担当する清掃局が用意したキューブの「棺」だった。——
と女性が姿を現したすぐ後に、その子供だろうか、まだ小学生くらいの幼い女の子が走ってきて玄関から姿を現し、母親が腕に持っているキューブの廃棄箱にすがって無理矢理奪いとろうとした。しかし女性はキューブをしっかり掴んで離さない。そしてその女の子に言った。
「やめて、〔コードネーム:〕マゼンタ!もうやめて! どうしてもこうするしかないの。お父さんのキューブはもう清掃局の人に引き渡すしかないの。」
しかし女の子のほうも引き下がらない。
「何で、キューブがあればお父さん生き返るかも知れないんだよ? それなのに何でお母さんはキューブを捨てようとするの?」
すると女性は一瞬息を飲んでから、その女の子へ言い含めるように言った。
「マゼンタ、キューブの伝説の中には根拠のないものもたくさんあるの。キューブがあってもお父さんは生き返らないのよ。いい?人は一度死んだら絶対に生き返らないの。それはキューブがあってもなくても同じなの。」
でも女の子のほうはなおも食いさがった。
「だって、前お兄ちゃんが言ってたもん!お兄ちゃんと病院で会ったとき言ってたもん。キューブの中にはリンクした人の命の元が入っているんだって。未来になったら死んだ人の心を生き返らせることが出来るようになるかも知れないって。ねえ、お母さん、そのキューブを捨てないで!絶対いつかお父さんをこの世に生き返らせる技術が出てくるって! なのに何でお母さんはその可能性まで捨てちゃうの?」
そして女の子は泣きじゃくった。しかし女性は聞かなかった。
「ダメなのよ。〔コードネーム:〕シアンが死んだときもそう思った。キューブさえあればいつかはシアンも生き返るかも知れないって。でも決まってることなの、使い終わったキューブは廃棄しなきゃいけない。それにどうやったって死んだ人間は生き返らないの……!シアンもお父さんももうわたしたちの傍には帰ってこない。もう、絶対に……絶対に会うことは出来ないのよ!——」
そう言い放つと女性も泣き崩れた。涙の雫がコンクリートの地面に落ちる。しばらく女の子と女性の嗚咽だけがその場に流れていたが、じき清掃員の一人が無言で促すと、女性もそれに応じてキューブは渡された。しらけた顔でその場に立つもう一人の清掃員の横で、箱を受け取った方の清掃員が女の子を言い聞かせるようになだめた。
「あのね、お兄さん達はこのキューブを持ち帰らなきゃいけないんだよ。これはお仕事なんだ。そしてこのキューブは別にゴミとして捨てられる訳じゃないんだ。お兄さん達がいる清掃局できちんと大切に保管するんだ。だから、もう泣くんじゃないよ。ね? 涙を拭ってお父さんとここできちんとお別れするんだよ。君が泣いたらお父さんが悲しむじゃないか」
それでも女の子は涙をこらえきれないようだった。清掃員から優しくなだめられても、まだ小さな肩が震えているのをコーチは遠くから眺めていた。
そのキューブは結局保管処分のために清掃車で運ばれた。近くで車の中から一部始終を見ていたコーチだったが、その時に若い清掃局員達が話していたある名前を耳に挟んだ。——その会話はこんなものだった。
「ま、俺たちは焼却場敷地内に設置された倉庫までこれを運ぶだけで、焼却しないでそのまま後は処分場まで別のやつらが運ぶんだけどさ、わざわざこんな石ころみたいなものを何でゴミ収集員の俺たちが回収しなきゃならないのかわかんねえよ。まったく上の考える担当業務なんて意味不明だよなあ。」
「まあ、それだけキューブをしっかり管理しとかなきゃいけないってことなんじゃないっすか。それにしても、中継したあとはレジストネシス最終処分場まで運ぶのに2日かかるって計算ですかね。まあ、俺的には丁寧に運んでもらわないとあの女の子に悪いなあなんて思うんすけど。」
「お前はお人好しだよなー。俺はトランスなんて信じねえし。死んだ人間が生き返る訳なんてねえだろ。一体どこの誰がそんなことを言いだしたのか。」
「えー俺なんかは結構オカルト的な話も興味あるんすけど。それにしてもレジストネシス最終処分場——キューブが最後に行き着く場所、か。一体どんなところなんでしょうかね。」
「何でも夢の島の地下にでっかい倉庫作ってるらしいぜ。あ、お前聞いたことあるか。上が廃棄キューブをここまで厳密に管理してんのは将来キューブのクラッキング方法が見つかったときにキューブから情報を抜き出して個人情報を入手するためだってよ。ま、そうでもなきゃキューブなんて埋め立てて廃棄しちまうよな——」
レジストネシス最終処分場——。ユニバースの全てのキューブが最後に行き着く場所——。この出来事から数日経って、勤務でまたスモークと顔を合わせたコーチはその施設について何か知っていないか聞いてみた。その話によると(「一般人が行くような場所じゃないっすよ。」とスモークは言っていた)その処分場はキューブ界では有名な施設で、清掃局の管轄下で運営されているらしい。破壊することの出来ないキューブを、安全に廃棄するために作られたのがその施設だった。
(キューブとやらがどうなっとるのかは知らんが、あの女の子の父親の命が内包されたものであるらしい。あのキューブがどない処理されたのかも気になるし、清掃局の管轄下なら、わしも関わりあることかも知らんからな。)
その話を聞いたコーチは、一人その処分場へと足を運ぶことに決めた。
◆ ◆ ◆
レジストネシス最終処分場はユニバース都市群の臨海部にある。もともとは遠浅の海だったものを干拓して出来上がった地区であるが、現在は港湾としての近未来的な都市群の風景が広がっている。ゴミ処分場である夢の島を例外にして臨海部は風光明媚なところでもあった。そしてその一角としてユニバース都市群で出たゴミが一手に集まる夢の島があり、さらにその地下にはレジストネシス最終処分場、つまり使用済みキューブが最後に行き着く処分場が建設されていたのだった。
——レジストネシス最終処分場へ向かうことを決めたコーチは、ゴミ収集の仕事のない休みの日に予定を組んで、朝早くから準備して家を出た。家からバス、間に電車、そして臨海部ではモノレールで移動して、最後に夢の島までは公務員としての特権を使ってゴミ収集船にのり海路で処分場へと向かった。
その処分場は通常の廃棄物が埋め立てられる「夢の島」の地下にあった。夢の島入り口で清掃局員証を提示して島内への立ち入りが許されたコーチは、キューブのほうの処分場であるレジストネシス最終処分場を目指して島の内部まで踏み込んだ——。
コーチが舗装のされていない島の地面を歩いていると、遠くに見える島のあちこちには白いビニールテープで覆われた丘のようになっているところや、ゴミが露出して散乱しているところなどがあり、春の霞んだ水色の空に海鳥達がワーワー鳴き交わしながら舞い飛んでいた。ゴミの山に近づくにつれて辺り一面に腐臭が漂い、海鳥たちがゴミの中から食べられるものを引っ張り出してついばんでいるのが見える。遠くに見える臨海部のビルやタワーをバックに海の上では船が盛んに行き交っていた。
島内に設置された標識を辿って島の奥まで足を進めると、その一角に大きな陥没地帯があった。正確には陥没しているわけではなく将来的に地下設備を建て増しして使うために用意された巨大な四角い穴である。周りのゴミの丘とはうって変わって、そこだけ視界が開けていた。
コーチは陥没した部分にはいるための坂を下った。赤茶けた土の壁に下げられた標識には、確かに「レジストネシス最終処分場入り口」と書いてある。そしてコーチは道のつながった先に、その最終処分場の入り口とおぼしき搬入口を見つけた。鉄の扉で閉ざされた隔壁の横には制服を着た警備員が二人立っている。一人は女性で、一人は男性の警備員のようだった。
——その時後ろからエンジン音が近づいてきて、清掃局のマークが付いたトラックがコーチの後ろで止まった。すると運転席から窓を開けて処分場関係者らしき男が顔を出し、コーチに呼び掛ける。
「ちょっと、ここトラックの通るところだから歩いてたりしたら危ないよー!」
一言言うと男はまた窓を閉め、トラックを発進させた。その走っていく先はさっきの処分場の搬入口だ。入り口前でトラックを止めると運転手はサイドドアを開けてトラックから降り、身分証明書のようなものを先ほどの搬入口で監視していた警備員に見せた。そして運転手と警備員たちは一緒にトラックの荷物を下ろし始めた。
荷物はあの住宅区画で見たのと同じ「キューブの棺」だった。きちんと並べられて荷積みされたそれらは棚ごと入り口前に下ろされる。そして警備員達によってカートに積み替えられ、入り口の鉄扉の前に配置された。
それをコーチは近くで見ていたが、コーチの存在に気付いた警備員のうち女性のほうが歩み寄ってくるのを認めたコーチは、その警備員がコーチに話しかけるのより先に自分の方からその警備員に声を掛けた。
「ちょっとすまんが、あなたたちはここの警備員かね」
「ええ、そうですが。」
警備員は応対する。コーチはさらに質問した。
「ちょっと処分場の中を見学させてもらいたいと思ってきたんだが、中にはいることは出来るかね。」
するとその女性警備員が言った。
「すみません、ここは関係者以外立ち入り禁止になっているんですよ。すみませんが、お引き返しください」
「ええ、ここは一般人の人の立ち入りは許可できないことになっているんです。申し訳ありませんが、おかえり願います。」
もう一人の男性のほうの警備員も声を重ねる。しかしコーチはなおも食いさがった。
「わしは清掃局に勤めとる清掃員でね。一般人ではなくて関係者なのだが。」
「はあ、そう言われても上の許可がないと立ち入りは許可できません」
コーチの意外な言葉に困惑する女性警備員。
「そうです。関係者以外は入れるなと上にも言われているもので」
男性警備員の方も加勢してやはりまだ了承しない。
しかしコーチは無言で胸の中をまさぐると、ある個人認証カードを胸ポケットから取り出し、最初の女性警備員の前に突きだした。そしてその警備員はそれを手にとって読む。
「え、ユニバース清掃局統括上級担当部長……?」
「そうだ。っていっても有効期限は12年前に切れてるがな。これで上の許可がとれた事にしてもらえんやろか。」
「元統括上級担当部長さんがなぜここに……。なぜそこまでここを調べたいのでしょうか。」
「ちょっと気になることがあってな。来てみたんや。」
女性警備員は少しの間考え込んだのちにもう一人の男性警備員に目で同意を求めたが、男性警備員が頷くのを見ると振り返ってコーチに言った。
「——そう言うことならご案内します、〔コードネーム:〕レオン、ここの見張りお願いね」
女性警備員がドアの横に歩み寄って扉を開けるための大きな赤いボタンを押すと、さっきの鉄扉が音を立てて開いた。ドアが開くと共に見えてきたその奥にはわずかな灯りの下、ずっと暗いトンネルが続いている。先に女性警備員が先導して中に入ったが、その警備員に「どうぞ」と声を掛けられると、コーチもその何かがかびたようなにおいのするトンネルの中へと足を踏み入れた。
トンネルの中に入ったときに、女性警備員は自己紹介をした。
「あ、自己紹介しておきますね。私は〔コードネーム:〕ロストと言ってレジストネシス最終処分場の警備をやっているものです。さっきの相方はレオン。どちらも今年の春からここに配属されて警備をやっています。」
話によるとロストとレオンは今年就職したばかりの完全な若手で、二人とも数ヶ月前にはまだ大学で講義を受けていたような新人の清掃局員とのことだった。ロストは公務員になりたくて公務員試験を受けて就職したのだが、その最初の配属先がレジストネシス最終処分場の警備の任だったと言うことだ。ちなみに二人はここでは警備だけではなくキューブの運び込みなどの雑務も担当している。そしてロストの紹介の後、コーチも自分の名前を告げた。
「わしは〔コードネーム:〕コーチ。まあ、名前はさっき名刺を見たからわかると思うが、今はユニバースのある区画で清掃局の清掃員をやっとるもんだ。まあ、よろしゅうたのむ。」
そしてロストの案内の元で、ロストとコーチの二人は処分場内部のトンネルへ足を進める。
歩きながら処分場についての情報をコーチはロストに聞いた。
ロストの話(といってもロストは若手なので、すべて仕事上のものとして上から周知される知識である)に依れば、この処分場はキューブが普及した頃に建設されたらしく、「一度リンクしたらユーザーが死亡しても壊れない」というキューブの最後に行き着く場所である。
「キューブの廃棄物が出てきた頃は、ハンマーとかプレス機とかで壊そうと試みた人がたくさんいたらしいんですけど、どれも歯が立たなかったんだそうです。」
話している二人が歩くトンネルの中の空気はひんやりとしていたが、それと同時にかなり湿気を含んでいた。また、トンネルは結構長く続いているようで、ロストが持っているライトが照らす先は暗く見える。ゆらゆらと揺れるライトが水気で塗れた壁を浮かび上がらせていた。
「ここは政府が管理する最終処分場だったと思うが、警備には君ら二人しかいないんか。かなり警備が薄いように思うんだが。」
コーチが聞くとロストが失笑して答えた。
「ここではキューブを管理しているわけですが、現状キューブという物は再利用の価値がないので、盗難などの被害に遭うことがまずないんです。再利用以外にもクラッキングと言って、キューブの内部の情報を不正解析しようと試みている輩が居るとも聞いたことがありますが、実際ユーザーが死亡したあとのキューブは全く外部からのアクセスに反応しないので、そう言ったクラッキングのような方法は今世紀中は通用しないとも言われています。だから政府もここの警備にあまり人員を掛けないのだと思います。一応夢の島への上陸許可は公務員でないと下りないわけですし。——まあ、わたしたちとしては、もうちょっと人手があった方がもっと仕事がはかどるわけですけど。」
トンネルを歩く間にコーチは、子供の頃空想科学雑誌で読んだウラニウムのことを口にした。
「こんな地下深くに保管されているとは、廃棄されるキューブというのは、放射能のようなものを出すのかな?」
「放射能?」
初めて聞く言葉におどろくロスト。
「使用済みのウラニウムは放射能という目に見えない光線を出す。それを浴びると人体に有害だそうだ。ま、あくまでも空想科学の話しだがな」
「いえ、キューブの近くにいてもそのようなことはありません。ただ、そこにあるだけです。」
「そこにあるだけ?」
コーチの疑問を残したまま入り口のトンネルを抜けると、そこは天井の高い広い空間になっていた。どこまでも金属製の棚が続いていて、そこに保管番号をつけられたキューブが所狭しと、しかし整然と並べられていた。
「廃棄物と言うにはえらいきちんと保管されてるじゃないか」
コーチが疑問を口にすると、ロストが答えた。
「ええ、昔からこう管理するようになっているそうです」
しばらく歩いていた二人だったが、コーチは周りを見渡しているうちにキューブが微光を発していることに気付いた。暗闇の中に並べられたキューブの中心あたりが、わずかに緑色を帯びた仄光をまとっている。
「なんや、こいつらうっすらと光っとるように見えるんやけど、これはなんや?」
コーチが聞くと、ロストは顔を曇らせた。
「ちょっと……気味悪いでしょう? キューブはリンク設定をすると内部に光を持つんです。それはキューブの内部信号のやりとりに使われている光信号が見えることに依るらしいんですが、それが利用者が亡くなってもキューブはわずかに光り続けるんです。」
「わしが今までテレビとかで見たときはそんなことなかったが」
「非常に微妙な光なので、日光の元とか、明るいところだと見えないんです。」
そしてロストは言葉を足した。
「それも見える人と見えない人がいて……。知ってます?、トランスって。」
「この前聞いた」
「トランスに依れば、この光はキューブがユーザーと同期したときのリンクを元に、その人の魂を吸い取って、自らの中に閉じこめてしまう……ことによって出るんだそうです。」
そして肩を奮わせてロストは恐れおののいた。
「君こんなところで働いていて気分沈まないのかね」
コーチが話を振ると、ロストは
「仕事ですから……。割り切ってます。」と答える。
「ほんとに?」
「ええ、もちろん!……」
しかし段階的に表情が暗くなっていくロスト。
「ほんとは事務関係に行きたかったのに就職早々にここが赴任になって……。家族とも恋人とも離れ、ああ、何で私はこんなところにいるんだーー(泣)」
「なるほどな。若手を置くような職務ではないな。」
そして、
「ん?あの隔壁は何だ。」
コーチはこのエリアの奥の方の一角に周りが縁で囲まれた隔壁を見つけた。そしてコーチはその隔壁へと足を進める。
「え、あの、その、……あ、あっちは……、いかないほうが……」
狼狽するロスト。
「何だ?」コーチはその糸目で振り返り際にロストを睨んだ。
「はい!あの場所はグル達のキューブが保管されている場所です。」
射すくめられたロストが答える。
「グル? なんだそりゃ。」
グルという言葉はユニバースでは常識なのでロストは一瞬その言葉に戸惑ったが、コーチに説明した。
「グル、つまりバレーのグルはキューブ技術を完成させた伝説の技術者チームのことです。今のキューブのシステムは全てそこから派生しています。しかしラボでの事故の時にグルの多くは死亡したり、意識不明になったりして、そのキューブがここに保管されてるんです。」
ラボの事故はキューブの歴史において非常に有名な史実だ。この事故は当時コンピュータ技術の粋を集めてキューブのシステムを初めて歴史に創出しようとしていたバレーのグル達の研究中に起こった事故で、この事故でグル達の多くは命を落とした。キューブユーザーの間では伝説ともなっている事件で、この事故に関しては現在も様々な憶測がネット上で飛び交っている。
「やけに厳重な隔壁じゃないか?」
コーチが疑問を呈する。
「ラボでの事故にはいろいろと嫌な噂がありまして、前例もなく対処に困った統括局があえて厳重に隔離保管しているそうです。……私もここは入ったことないんですよ。と言うより、近づきたくもないし……。」
「古いセキュリティーシステムだな。」
「キューブのシステムを開発した研究所で起こった事故ですから、キューブで隔離管理をするのは安全じゃないと言うことで、古い技術を使っているそうです。」
少し睨んだあと、胸ポケットから古いUSBメモリをとりだしたコーチは、隔壁のロック機構の接続端子にそれを挿し込んだ。そして少しの間の後、緑色の画面を表示して音を出すと、隔壁のロックが解除された。——ロストは何が起こっているのかわからないくらいに驚いた。——まさか、この隔壁のロックが解除できるなんて……。そして大きな音を立てて隔壁のドアが開くと、トンネルの奥は静寂の闇へと続いていた。
「どうした?案内せんか?」
(えーーー!汗)
縮こまるような気分で辺りを見回しながら足を進めるロストと淡々と足を進めるコーチ。トンネルの中は暗くて、手元のハンドライトの明かりだけで、二人はトンネルの中を進んでいった。
そして少しの後、二人は洞窟をそのまま掘ったような、天井と壁に岩盤が露出した小さな部屋に行き着いた。照明のスイッチを入れると、天井につけられたスポット光源が薄暗くそこを照らし出す。そこにはやはり両側の岩を削って設けた棚に、バレーのグル達のものとおぼしきキューブが置かれていた。初めて見るそのキューブ達に息を止めるロストと無言で視線を向けるコーチ。しばらく周りの様子を観察していた二人だったが、
「普通と何も変わらんな。」コーチが呟く。
「そうですね。グルのキューブだからどんなものかと思ってたけど、見た目は何も変わらないですね。でも……」
その場の凍えるような威圧感に肩をすくめるロスト。何か見えないオーラのようなものがその部屋に満ちているような気がした。
その時、コーチはある一つのキューブを見つける。
「これは?わずかも光っとらんじゃないか」
コーチが指したそのキューブは光が全くなかった。他のキューブはどれも微光を秘めていたが、そのキューブだけは光っていなかったのだ。コーチの指した先を見て気付いたようにロストが言った。
「これは……。そういえば、私が赴任したときに去っていったかなりお年を召した先輩の方が言ってました。一つだけこの中に光のないキューブがある、って。……そのキューブの持ち主のグルは、リンクを再設定したんだそうです。今は別のキューブを使っていて、だからリンクの切れたこのキューブは、全く光らないんだと。そのグルはそのキューブを手放すつもりはなかったそうなんですが、統括局が安全のために、他のグル達のキューブと共にここに保管することにしたんだそうです。」
——光を失い、ただ透明な立方体の水晶としてそこに存り続けるキューブを前に、二人はしばし佇む——。
そして見学を終えて処分場内のトンネルから外に出た二人は、(地階までロストがコーチの見送りをすると言うことで)今度は坂を登らずに開放式のエレベータに乗り、吹き上げるような風を受けながら地上へと上がっていった。地上の空気と太陽の元に戻った二人の後ろには夢の島の白い廃棄物の山が風に散り、白い海鳥たちがその上を舞っていた。
「同じ処分場なのに、全然違うんですよね。私まだしも上の勤務の方がよかったな……。あの、私が転任できそうな手がかり、なにかわかりましたか?」ロストがコーチに聞く。
「何もわからん」
唐突な言葉とそのショックにうなだれるロスト。
「さて、戻ったら昔の友人にちょっと連絡せにゃいかんな」
そしてコーチは帽子の先をつまむ。上がり行くエレベーターの上のその後ろ姿の奥には、白い積み上がったゴミの丘陵と、ゴミくずの舞う水色の空がどこまでも続いていた。
◆ ◆ ◆
……後日、ある家でこんな出来事があった。その家はコーチが前見たのと同じ清掃区画に建っていた家で、それまでそこに住む一家を支えていた父親が亡くなり、その家の娘の二人の姉妹がその死後の身辺整理のため、家の中の片付けを行っていた。
父の死を嘆き悲しむ妹にうって変わって、面倒なことはハヤく終わらせたいと清掃車の到着を待つ姉。そして「さっさと片付けてちょうだい」と言うその姉に、到着した新しい清掃局のチームが帽子をとって謹んで言った。
「今度から使用済みキューブの回収は行わないことになりました。」
「は?」
いきなりの言葉に唖然とする姉。その言葉を聞いて横にいたもうひとりの妹のほうが泣きやむ。
「じゃあ、どうすんのよこのキューブ。どうにも処分できないじゃないの」
いきり立つ姉に、その清掃局員はこう言った。
「これからは各家庭で保管していただくことになりました。」
「保管って、どうやって」
「保管のためにお使いいただく収納箱として、この箱を清掃局の方から提供させていただくことになりました。」
その清掃局員が姉に箱を差し出す。その箱は、キューブのように透明な、つつましくも清しい感じの箱だった。底には上等な布が敷いてあり、キューブを置けるようになっている。唖然とする姉に挨拶をすると清掃局員の二人は玄関から出て行った。
「何よ、キューブを保管するための箱って。こんな物とっといたって何の役にも立ちゃしないじゃないの。ああ、もういいわ。あんた、後片付けは任せるわよ」
そう言って姉のほうは腹を立てて家から出て行く。その後ろで、妹は清掃局員から渡されたキューブの箱を家の棚に飾り置き、そこにそっとキューブを入れて、「お父さん……」と故人を偲んだ。
◆ ◆ ◆
その後、ロストとレオンは上からの異動命令で最終処分場の任を解かれ、転任となった。二人は今でも異動命令を下達されたときの驚きが忘れられない。レジストネシス最終処分場での勤務にウンザリしていた二人はその時は子供のように手を取り合って喜んだ。そして今も清掃局のチームとして、コーチとスモークはユニバースのゴミ収集業務を行っている。——
ある日、都市住民の共同墓地にコーチの姿があった。共同墓地はこの区画に住むすべての都市住民にその権利を与えられる墓地であり、コーチが居を構えている区画にも設営されているものだ。そこで花を片手に珍しくスーツを着込んだ格好で現れたコーチは、ある一つの墓の前まで来ると、呟いた。
「お前が死んでからもう6年が経つんか……。時の流れるのは速いもんやな。別れた夫に墓参りなんかおこがましくされてもうれしくもないかも知れんが、まあ、許してくれや。」
コーチは懐のポケットからタバコを取り出すと、墓の前でそれを吸い始めた。それは生前に妻がこう言っていたことを思い出したからだった。その時コーチと妻は二人で出かけていたときだったのだが、妻は街角でタバコを吸う人を見て「ねえ、タバコを吸ってる人ってかっこいいじゃない。あなたも吸ってみてよ」と言っていたのだ。その時は「そないなもんわしは吸いたくもないわ」と邪険に拒否したコーチだったが、しかしコーチはその時の妻の残念そうな顔が忘れられなかった。
そしてタバコをしばらく吹かしていたコーチだったが、一度咳き込んで、こう呟いた。
「まずい……。ようあいつはいつもこないなもん吸ってられるもんやな——」
そして、墓の前に足を進めたコーチは、墓石の穴に挿してある花がまだ瑞々しさを保っていることに気がついた。どう考えてもコーチが前来たときに挿した花ではない。
「あいつ……、来てたんか。わしにはろくに連絡もよこさんくせに……。」
コーチの見上げる先には、今日もどこまでも青い空が続いていた。
--> GO TO NEXT LEVEL
Z-C Session $01『微光』Beta


