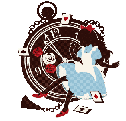
愛しのヤクザ
僕の3社目の勤務先はダイヤモンドをはじめとする宝石の輸入商社だったのですが、社長の思いつきで健康ランドの経営を始めたのです。その時の実体験を元にこの小説を書きました。ヤクザが登場する場面は、ほぼ事実に基づいています。また、その時の仲間達はそのままのキャラクターで出演しています。離ればなれになってしまった仲間達に僕の思いを贈ります。とはいえ、この物語はフィクションであることを申し添えておきます。
第一章 カーチェイス
遥かなる山並みは雲霞に煙り、緩やかな稜線がうっすらと幾重にも連なる。その背後に昂然と聳える急峻な峰々は雪に覆われ、どんよりとした灰色の空とくっきりと境をなし、その不動の地位を誇るかのようにあたりを睥睨(へいげい)していた。
そんな雄大な眺望に目もくれず、相沢の視線は前を走る車のテールランプに釘付けになっていた。峰峰に向かって真っ直ぐに伸びる道路は、車のスピードが増すに従い視界の中でがたがたと振動し、あたりの風景も瞬時に後方へと飛び去ってゆく。ふと、常緑樹に混じり黄色に染まった銀杏の樹が視界の片隅をよぎり、一瞬、秋の気配を捉えた。
既に制限速度を30キロもオーバーし、フロントガラス越しの風景に心を誘われることもなく、相沢は掌の汗を不快に感じながらアクセルを踏み続けた。追い越し車線を先行していた車は左の車線に入り、後続の二台の暴走車に道を譲る。その先は彼方まで直線が伸びていた。
相沢は、目の前を悠然と疾走するモスグリーンのジャガーのブレーキランプを見詰め、それが赤くなるたびに必死でブレーキを踏んだ。掌の汗はハンドルを濡らし、握り締める両手を滑らそうとたくらんでいる。その一瞬の悪魔と戦いながらハンドルにしがみつき、僅かな車間距離をこれでもかこれでもかと詰めてゆく。
若造がとろとろ走る相沢を一瞬のうちに抜き去り、まして追い越し際に嫌味な一瞥を投げかけた。しかもその車が若造には分不相応であったことが、彼をこのような暴走に駆り立てた訳ではない。
今日の相沢は、朝から普通ではなかった。他人の不幸まで背負い込んだような苦虫潰したような顔、眉間に寄せた深い縦皺、血走った目、どれをとっても、普段の彼を知っている人間が見たら、相当機嫌が悪いことは瞬時に分かったはずだ。
しかし、このカーチェイスを引き起こした心理をさらに掘り下げてゆくと、意外にその根は深く、相沢の人生を変えた一瞬、あの辞令を受け取った時から始まっており、ここ3年近く欝積されてきたものが、些細なことをきっかけに爆発したと言うことも出来る。
相沢は、大手スーパーに勤務して10年になる。3年前までは本社企画部販促課課長で、同期では出世頭であった。現場に出ることはあっても、それは企画部員としての仕事の延長であり、心の何処かで現場とは一線を画する心理が働いていたことは確かだ。
一生本社ということはあり得ないにしても、現場へ出る時はそれなりのポジションが用意されるものと勝手に思い込んでいた。何故なら、同期入社で本社に残れたのは相沢を含め数人であったし、これまでの実績からみてもそれが順当と思えたからである。
それが、今、何故こんなところに居るのか、それが相沢にとって納得出来ない。あの辞令は正に晴天の霹靂としか言いようがなかった。それを受け取った時、相沢は驚愕のあまり膝ががくがく震えた。本社から事業部への明らかな降格人事で、しかもそこにはこうあったからだ。「健康産業事業部課長を命ず」と。
この健康産業事業部は、会社が新規参入した事業で、風呂を中心とし、食事、喫茶、映画、リラクゼーション、アミュズメント等を提供する温泉娯楽施設の企画、運営、管理を実施する部門である。その企画が持ち上がった時、本部の誰もがお風呂屋さんにだけはなりたくないと心の中で恐れていた。
しかし、相沢は対岸の火事よろしく誰が選ばれるのか興味の対象でしかなく、まさか自分が矢面に立たされるなど思いもしなかった。唯一引っかかる点は一号店の候補が相沢の地元だったことだが、まさかそんなことはあるまいと高を括っていたのだ。
その辞令を受け取ってから、瞬く間に3年という月日が過ぎた。何にでも夢中になる性格のため、すっかりのめり込んでしまったが、ふと、冷静になれば、相沢はこんな仕事をするために大学で経済を学んだわけではと言う思いが頭をもたげ、憂鬱になる。
八王子健康ランドは16号線沿の郊外型スーパーに隣接して建てられた。竣工一週間前、オープンの実地訓練とオープンセレモニーが同時に行われることになり、昔の仲間がお客となって押し寄せると思うと、相沢は憂鬱で朝まで一睡もできなかった。
その日、一連のセレモニーが終わると、フル稼働を想定し、本部の社員やスーパーの幹部等を集めて宴会がとり行われた。最初、相沢は人目につかない裏方に位置した。勿論、誰にも見られたくないという思いもあったが、別の理由もあったのだ。
それはこの施設の問題点を実地で見る必要があったからだ。宴会場と厨房が離れすぎていること、そして洗い場が狭いことがネックとなって麻痺状態になることが予想された。この問題については何度も改善案をあげてきたのだが一顧だにされなかった。
宴会が始まってみれば案の定、引き上げた食器が裏の通路にうずたかく積まれ、宴会係は右往左往するばかりで収拾がつかない。宴会係りがまだ不慣れであるという点を差し引いても、出来上がった料理と空いた器を置く中継点と、新たな洗い場の設置が不可欠であることを思い知らされた。
相沢は汗だくで駆け回り、終いには宴会場まで出っ張って、指示を出し、食器を片付け、目立たぬどころの騒ぎではない。揶揄を含んだ元同僚の「おすっ」などという挨拶に答える余裕すらなく、ふと気がつくと宴会場には客は誰もおらず、食器の山をぼーっと眺めていた。
その翌朝、相沢は携帯を取り出し、ゼネコンの監督に電話を入れた。
「あれ、相沢さん、どうしたの、こんなに早く」
「例の中継所と新たな洗い場、以前僕がいっていた位置に作って下さい。大至急」
「でも統括事業本部長の了承は取り付けたの?」
「あんな奴にいくら言っても無駄です。事業本部長は無視。僕が責任取りますから、一週間、突貫工事でお願いします。オープンまで10日しかありません」
「俺、知らないぜ。統括事業本部長に何か言われたら、相沢課長の指示だと答えますけど、それでいい?」
「ええ、かまいません。兎に角、今日から始めて下さい。」
こうして、相沢は、山本統括事業本部長によって「上司を蔑(ないがし)ろにし、独断専行しがち」というレッテルを貼られるのであるが、当の本人は、ゼネコンの監督が匂わせていたのだが、子飼いの業者を工事に無理矢理入れマージンをもらっているという。
悩みはこれだけではない。本社ではあれほど熱い視線を投げかけていたレストラン事業部の石田京子が、宴会中、相沢に気付かぬ素振りをしていたのだ。これまで本社に週一で出かけるが、その度に、京子はにっこりと微笑みかけ、屈辱にまみれた心を癒してくれた。
あの態度は何なのだ?あのオープンセレモニーの当日、石塚調理長が、ズボンが汚れるからと前掛けを貸してくれた。現場の社員達からは似合うと褒められたが、普段背広姿を見慣れて入る京子には惨めな姿に映って嫌われたのか。或いは、惨めな姿を気の毒に思って、気付かぬ振りをしてくれたのか。
どうも、前者のような気がする。何故なら、あれ以来、本社で京子と出会っても、俯いて顔を合わせようとしない。今朝、起きた瞬間、京子のあの俯いた横顔が浮かんだ。困ったような顔で横を通り過ぎる京子の後姿をじっと見詰める自分がいた。
暗澹とした心に火をつけたのは、やはり、あのジャガーであった。追い抜かれる瞬間、若者の馬鹿にしたような視線にかっとなったのだ。もっとも、若者はサングラスをしており、馬鹿にしたような視線は相沢の勘違いに過ぎない。
今、スピードメーターは100キロの数値を示している。ブレーキランプを凝視し、距離を更に詰める。一瞬、ジャガーが唸り声を上げたと思うと、相沢の視界から消えた。視線を上げると、遥か彼方をゆうゆうと遠ざかってゆく。
慌ててアクセルを踏み込むが、1500ccのカリーナでは追いつくわけもなく、緩いカーブを曲がりきると既にその姿はない。相沢は緊張の糸がぷっつりと切れ、左の車線に移り、暴走前ののろのろ運転に戻った。へへへと自嘲気味に笑った。
高速道路でさえ120キロ以上出したことのない相沢が、一般道路で、ジャガーとカーチェイスするなどお笑い種である。そして、いよいよ現場が近付いてきた。15メートルを越す煙突が聳えている。いよいよあのことに向き合わねばならない。そう、あのことに。
相沢は、駐車場に車を停めた。暫く車の中で考え込んだ。深呼吸をし、一言呟いた。「まあ、いっか」
車を出ると、何事もなかったかのように歩き出した。ガードマンとにこにこと挨拶を交わし、裏口へ向かう。ふと、ため息を洩らした。一瞬、肩の力が抜けた。下っ腹に力を込め「よしっ」と声に出した。そうだ、この試練に耐えねばならない。
八王子健康ランドの入り口は、既に掃き清められ、『祝八王子祭り』の看板と垂れ幕で飾りつけられている。駐車場を振り返ると、山々が相沢の決意を称えているかのように、雲靄も晴れわたり清々しい姿を見せている。
おやっと思って駐車場の一角に視線を向けた。例のジャガーが駐車している。運転手はいない。隣のスーパーの開店まで2時間ある。ということは例の若者は健康ランドに来ているということだ。まさか、後をつけてきたのか。ひゃっとする思いを抱きながら、先ほどの決心を実行すべく、事務所の中に入っていった。
「おはよっす」
相沢の何時もの挨拶だ。向井支配人は机から顔を上げ、丁寧に「おはようございます」と笑顔で答える。その机に、それが、無造作に積み上げられている。相沢は迷うことなくその机に向かった。そして、その積み上げられた物を、むんずと掴み、さっと開いた。
すぐさま袖を通して羽織った。おもむろに、手拍子をとって声を張り上げた。
「へい、いらっしゃい、いらっしゃい」
向井支配人がにこやかに笑いながら応えた。
「課長、ハッピ着るのは明日からですよ。まあ、今日からってことにしてもかまわないけど。でも、いい男は、何着ても似合いますね。ハッピだって着こなしちゃうんだから。これで、八王子祭りもいやがうえにも盛り上がりますよ。」
そう言われてみれば、全員着用は明日からだった。一日勘違いしていたのだ。しかし、ハッピなんて着こなすも糞もあるものかと思った。こんな姿は石田京子には見せられない。まして向井支配人に似合うなどと言われてはよけい落ち込む。鵜飼則子に見せようと思った。徹夜明けでフロントにいるはずだ。
あのオープンセレモニーのおり、石塚調理長が前掛けを差し出した時、調理長との信頼関係を築くために、咄嗟にそれを腰に巻いた。現場の人間としての心意気を見せるためだ。でも、ハッピだけは着たくなかった。理由はいくらでも言い繕える。
向井支配人は系列の食品スーパーの店長を歴任してきたが、その実力を買われ本部の新規事業であるこの健康ランドの支配人に抜擢された。本部事業部の課長である相沢に一目も二目も置いて接するのだが、何故か相沢はこの向井支配人に頭が上がらない。
自分より職階が下の向井支配人の意向など無視しようが、誰も文句は言わない。しかし、何故か、今、相沢はハッピを着こんでいる。しかも一日前に、誰よりも率先して。背中に視線を感じて振り返ると、向井支配人が微笑みながら何度も頷いている。
相沢は一瞬にして心の葛藤の意味を理解した。相沢は向井支配人の期待に応えようと、自分のプライドと戦っていたのだ。そして、向井支配人は、今、初めて、相沢を本当の仲間と認めてくれた。胸にじーんときたが、向井にはお茶目に笑いかけただけだ。そしてドアを開けてフロントに出た。
鵜飼則子が眠そうな目を前方に向けて、ぼーっと立ちつくしている。則子は立ったまま眠る特技の持ち主だ。にこりとして相沢が話しかけた。
「どうだい、似合うだろう?」
鵜飼は、何度か瞬きして目覚めると相沢に焦点を合わせた。ようやく相沢を認めると、どうでもいいといった調子で答えた。
「まあね、でも、その色、センスがないわね。真っ青なんて。それに真っ赤な文字。ハッピはいなせなものなのに、まるでスーパーのバーゲンって感じ。まあ、しかたないか、元がスーパーなんだから」
相沢はハッピそのものを評価する則子の視線に安堵し、一回りも年下の流れ者に言い知れぬ親しみを覚えた。ましてハッピ作成にしつこく反対する相沢に一人同調してくれたことを思い出したのだ。と、急に則子がしゃきっと胸を張り声を張り上げた。
「いらっしゃいませ、こちらでキーをお受け取り下さい。入場料は1200円でございます」
見ると、ボーイッシュな女が下足キーを持ってカウンターに近付いて来る。相沢も気持ちを切り替えて、「いらっしゃいませ」と声をだしてお客を迎えた。則子が受付をしている間、その女は相沢を睨んでいる。不審に思ったがとりあえず笑顔を返した。すると女が、胸元からサングラスを取り出してくるくる回し始めた。
相沢はしばらくそのサングラスを何気なく見ていたが、突然、雷にでも打たれたように体が跳ねた。「やばー」と思っているうちに冷や汗が脇の下を伝う。謝るとか、どう繕うかなど思いも及ばず、顔面蒼白になってひたすら立ち尽くすのみである。
則子からロッカーキーを受け取ると、女は相沢に近付き、低く冷たい声を発した。
「さっきの人ね、まったく頭にきたわ。どんなに怖かったか分かる?あんなことしていると、いつか命落すわよ」
そして、相沢を頭の天辺からつま先まで眺め、続けた。
「いい年した男が、なによあれ。ハッピ着て、いらっしゃいませって頭下げている男がやることかよ」
この言葉は、相沢の心にぐさりと刺さり致命傷を負わせた。「いい年をした」も「ハッピ着て」も「頭をさげて」も、どれも相沢のプライドをずたずたに切り裂いた。その場に倒れ込まなかったことが不思議なくらいだ。相沢は呆然と立ち尽くした。女はその場を去ってロッカー室に消えた。則子がカウンター越に声をかけてきた。
「何かあったの、あの人と?でも、あんな美人とならどんな係わり合いでも、グーじゃない」
相沢はこの言葉を聞いていなかった。いや、聞こえなかったのだ。則子の口がぱくぱくと動くのを見ていただけだ。則子は見かねて、二階から降りてくる林田と林のハヤシコンビに向かって声を張り上げた。
「ねん、そこのハヤシコンビ、早く来て。本部の課長さんが落ち込んで、今にも死にそうよ。早く来て自尊心をくすぐってあげて」
林田と林は則子の声を聞くと、目を輝かせて階段を下りてきた。そしてぼーっとつっ立っている相沢を前にして、まず林田が則子に向かって第一声を発する。
「そのハヤシコンビは止めてよ。こんな奴といっしょくたに、しねえでもらいてえ。こいつとは、赤の他人なんだから。それよっか、課長、何かあったん?」
相沢がようやく自分を取り戻した。
「いや、その、何でもない……」
林田が視線を則子に向けると、則子は外人のように肩をすくませた。林田が言う。
「課長、何があったか知りませんが、元気出してくださいよ。こっちは課長だけが頼りなんだから、課長が落ち込んじゃあ、こっちは、屍(しかばね)になっちまう。」
林も林田に負けじと声を張り上げる。
「課長、どうしたんですか、その顔。世の不幸を一身に背負ったみたいな顔しちゃって。考えすぎない方がいいですって。考えたって何も良くはならないに決まってんだから、だったら考えない方がいいってことですよ」
二人は現地採用の社員である。年が近いこともあり、特に親しくしている。相沢も二人の陽気なお喋りに漸く気も落ち着いてきた。
「別に落ち込んでなんていないさ。今のお客、本当に厭みな奴なんだ。とにかく厭なお客っているじゃないか?あの女、あの年でジャガーなんて乗り回しているんだ。ここに来るとき、車でトラブったんだ。全く今時の若い者ときたら、何様のつもりなんだ。」
林田が怪訝な声を上げた。
「ジャガーだって?」
「うん、ジャガー。林田さん心当たりあるの?」
「いや、別に……」
その時、則子が相沢に声を掛けた。
「それはそうと、相沢さん。相沢さんがどう思ってるかは知らないけど、それとってもよく似合う」
相沢はハッピのことは忘れていた。則子は意地悪そうな視線を向け、にっと笑った。
第二章 肩代わり
既に20時を過ぎた。交渉は長引いている。相沢は事務所内で苛苛しながら向井支配人を待っていた。少し前、フロントの清水郁子が血相を変えて、向井を呼びに来た。また例の奴が来たのだ。ここ数日、地元のヤクザがマッチの売り込みに何度も訪れている。
名入りのマッチ。通常の価格の何倍もする。その小指のないセールスマンは町の有名人で、傷害事件を起こし服役していたが、つい最近出所したばかりだという。向井の話によると、その男は非常に紳士的で一見しただけではヤクザとは思えないのだそうだ。
これまでのところ、向井のご免なさい攻勢が功を奏し、何とか本部の通達をクリアーしている。そのご免なさい攻勢とは、「ご免なさい」を矢継ぎ早に繰り返し、脅迫の出鼻を挫き、相手の言葉を遮る手法である。これは向井が編み出し、自ら命名した。
本部の通達とは、ヤクザとは一切関係を持つなというもので、「全く本部なんて現場の苦労など分かっていない」などと、相沢は自分が本部の人間であることを忘れて思わず呟いたものだ。こうして身近に接してみて初めて、ヤクザの一人一人がノルマを課せられたセールスマンだということを理解した。今回のように名入りマッチという商品があり、市価より高いということに目をつぶれば、おつき合いしても良いのでは?と思ったりする。
実際に、向井は家にまで電話をかけてきたヤクザと、半年も先の正月用の門松を購入する約束をしたという。
「あの強面の人が、頼むよ、今年だけでもいいから、って言われたら断れないよ。今年だけで終わらないとは思うけど」
とは向井の言だが、売る商品があるというのは、まっとうなヤクザということになるのかもしれない。つまり原価率か低ければ低いほど、恐喝に近づくわけである。
暫くして、向井が戻ってきた。相沢はつかつかと向井に近付き声をかけた。
「ど、どうでした」
「まあ、今日が最後になるだろうね。どうしても金を取れないということを分からせたから。暫くは安心してられる」
「ああ、そう、良かった。本当にご苦労様です」
「でも、今日は焦っちゃったよ。あの紳士的な金子さんが、本性を見せたからね。さすがに、僕もぶるったね」
「どんなふうに、本性をみせたんですか?」
「それがね、僕達が良く行く飲み屋があるでしょう。そこに行くときには後ろに注意しろだってさ。びっくりしっちゃったよ。」
二人が健康ランドを抜け出し、時々行く近所の飲み屋のことだ。まさか、後ろからグサリなんていうことはないにしろ、その一言で精神的に追い詰められる。まさにヤクザ対策は気骨が折れる仕事である。相沢は暗澹とした思いに捕らわれた。
向井は、最初の一ヶ月が肝心とばかり、オープン以来ヤクザ対策のために毎日泊り込んでいる。向井は、ヤクザに対しては毅然とした態度さえとっていれば、いずれ諦めると言う。相沢には、あの「ごめんなさい」攻勢のどこが毅然としているのかよく分からないが、確かにその効果は出始めてきているのだ。
今日、相沢は、密かに決意していた。向井の負担を少しでも軽減してあげようと。それはある出来事を目の当たりにして、そうせざるを得ないと感じたのだ。それは、昨日の朝のことだ。相沢が出勤すると、向井は長椅子で眠っていた。大きな赤ら顔、その目の下には隈が浮き出ている。40の半ばを過ぎ、髪は半白髪で、この一ヶ月でその白髪が増えたような気がした。
そこに風呂場担当の岩井が例によって駆け込んできたのだ。刺青客の闖入である。向井は岩井の「支配人」という緊迫した呼びかけに、すぐさま反応し、かっと目を開くともう駆け出していた。寝起きのためか足がもつれ、出口でその太った体がこてんと転んだ。
起き上がり小法師のようにころりと立ち上がったのはいいが、運悪く清水郁子がドアを開けたのだ。向井はドアに顔をしこたまぶつけて尻餅をついた。「キャー、ご免なさい」と言う郁子を無視して、向井はまた走り出した。
相沢も後を追った。ロッカー室に入ると、半裸の刺青客に入場料の入った封筒を差し出し、ご免なさい攻勢をかけている向井の姿が目に飛び込んできた。その姿は陰惨を極めた。眼鏡の片方のレンズにひびが入り、鼻血は口元まで流れている。陰惨と滑稽は紙一重だ。
後から駆けつけた林は向井の顔を指差しながら声を上げて笑っている。相沢も何かおかしくて哀しくて、でも、込み上げる笑いを必死で抑えた。刺青客もさすがにすごむ気力を削がれたようだ。向井のその必死さを目の当たりにして、相沢は決心したのだ。本部も出先も糞もない。同じ目標を持つ仲間として、やるべきことをやろうと。
向井は支配人席で船を漕ぎはじめている。今時流行らない太目のクロ縁の眼鏡は、今朝、向井の奥さんが届けたものだ。その奥さんが美人なのには驚いたが、向井はスーパーに勤める前は腕っこきの証券マンで、飲む打つ買うのヤクザな生活をしていたと言う。正に人に歴史ありというわけである。
相沢は支配人の机に腰をかけ、向井の肩をゆすった。向井は目をぱちくりさせて相沢を見詰める。相沢がその決意を胸に話しかけた。
「支配人、今日は家に帰って下さい。支配人に倒れられたら元も子もないですから。それから、明日、明後日は暇になると思うので休んで下さい。副支配人も漸く一人前になってきたところですから、彼に任せてみるのもいいでしょう」
鎌田副支配人は柔道5段の猛者で、ガタイもでかい。それが採用の決め手になったが、いざオープンしてみればどこか頼りなく、今一である。そのことは向井も感じているはずだが、しばしの沈黙の後、向井は、にっこりと笑って答えた。
「課長のお言葉に甘えよう。ここ3週間、昔のつもりでやってきたけど、どうも調子が違う。年なんだろうね。昨日なんて、昼飯食って、ちょっとうとうとしていたと思ったら、もう夕方なんで吃驚したよ。兎に角、課長のせっかくのお言葉だから」
「是非そうして下さい。もう年なんだから無理はできませんよ。今日はこれから帰って、あの美人の奥さんと一杯やって下さい」
「美人だなんて…。でも、女房が聞いたら喜ぶ。伝えておくよ」
「それから、今日は僕の番じゃないけど、鎌田副支配人も帰ったし、僕が泊まることにします。それにハヤシコンビも来ると言っていますから」
「えっ、林が。しかし、林はタフだね。あいつ昨日も泊まらなかった?」
確かに林はタフなのである。体は小さく細いが、元フェザー級のボクサーで、ここに入る以前は24時間営業の激安雑貨店の店長だった。その前は本屋を開業して潰している。斜陽産業とは知らず投資してしまったと笑いながら話していた。まだ、借金があるらしい。
もう一人、コンビの片割れ、林田は有名なスチール家具メーカーの西関東支店の課長だったが、上司と喧嘩して辞め、ここに就職が決まるまでの6ヶ月間、出勤する振りをして、パチンコで稼いでいたというから凄い。林田は既婚者で子供が二人いる。
今日、この二人が泊まりを志願した魂胆は見え見えだった。鵜飼則子が深夜番なのである。二人は則子に何かとちょっかいを出しているようだ。その則子もそろそろ裏のフロントに入るはずである。
向井は、何だかんだと仕事を見つけ、結局帰り支度をして事務所に現れたのは22時を過ぎた頃だ。相沢はハヤシコンビとビールを飲み、向井の話題で盛り上がっていた。向井は椅子にどっかりと座ると話に加わった。
「そんなに、おかしかった?昨日の俺の顔。まったく人の気も知らないで、林は転げまわって笑っているし、相沢課長は笑いを噛み殺しているし。終いにはあの刺青までにやにやして引き上げていった」
林田が残念そうに顔で言った。
「俺も見たかったなー、支配人のその顔。しっかり脳裏に焼き付けて、時々取り出してはほくそえむの。本当に支配人は何をやっても絵になるんだから」
そこへ鵜飼則子が入り口から顔を出し、声をかけてきた。
「わー、いいな、男ばっか、ビール飲んで。私も飲みたい」
向井が答えた。
「フロント嬢が酒臭くてどうするの。コーラならいいよ。冷蔵庫にあるから飲んだら。少し休憩して」
則子も仲間に加わった。ハヤシコンビの目が一際輝く。則子は男達の関心の的だ。美人でスタイルがよく、しかも若い割りに妙に度胸が据わっているのである。相沢の目撃したシーンはまさにそんな則子の一面を垣間見るものであった。
それは一週間前のことだ。深夜、酔っ払いが入場してきた。則子は、泥酔と判断し入浴はご遠慮下さいと言ったらしい。酔っ払いはこれに激昂した。掴みかからんばかりに怒鳴り散らし、絡んだのだ。相沢は階段を下りる途中、則子の歯切れのいい啖呵を耳にした。
「おっさん、いい加減におし。女だと思って、甘く見るんじゃないよ。さあ、殴れるものなら、殴ってみな。えっ、どうしたのよ。早く殴りなよ。」
男に顔を近付けるだけ近付け、睨みつけ、そして続けた。
「ふん、どうしたのさ。さっきの元気はどこに行ったんだい。殴る勇気もないって言うんか?えー。それだったら、最初から絡んだりするんじゃないよ」
その時、相沢が駆けつけ、お客にひた謝りして事のなきをえたのだ。則子はお帰り頂くことになったそのお客に、けろっとして「またどうぞ」などと、にこにこして挨拶をしていた。
その後、則子が相沢に言った言葉がふるっている。近すぎる相手を殴るのは技術がいる。技術のある奴は、女の壊れそうな顔を殴るには勇気がいると言うのである。相沢は空手をやっていたから、その意味がよく分かる。
則子は24歳、和歌山県出身で、東京の片田舎で一人住まい。不思議な雰囲気を漂わせている。林田が、さっきから則子の過去を聞きだそうとしていた。
「本当のことを話せば楽になるんだから、早くゲロしなさいって。何で和歌山から逃げてきたん?和歌山の片田舎で居ずらくなるようなこと、しでかしたんじゃねえの?」
「逃げてきたなんて人聞きがわるい。何も理由なんてないわ。それに、私は貴方達が想像しているような不良でもなんでもないしー…」
今度は林だ。
「あやしいな、絶対何かある。もし東京に憧れたんなら、同じ水商売だし、原宿と六本木とかで働いて、そんで、あんなぼろアパートじゃなくって、洒落たマンションかなんかに住むってのが、田舎出の女の思考パターンだよ。」
「あら、何でぼろアパートって知っているの?」
こう切り返され、林は耳まで真っ赤になって困惑の表情だ。それに気付いた林田は林の頭を小突いた。
「この野郎、家までつけやがったな。きったねえ。抜け駆けしやがって」
「そんなことしてねえよ、つけるだなんて。俺はただ、住所録を調べて休みの日に行ってみただけだよ」
しゃあしゃあと本当のことを話す林に、林田は
「まったくこいつは、隅に置けないんだから。ちぃっちゃいなりして、すけべ心だけはでっかいんだ。それで前の奥さんも逃げ出したんだろう。子供も捨てて」
「そんなことねえよ。本屋潰して借金取りが押しかけて来たんで逃げ出したんだよ」
二人のやり取りをにやにやと聞いていた向井が割って入った。
「林田君。抜け駆けって言うけど、君には奥さんがいるだろう。少なくとも立候補出来るのは相沢課長と林君だ。君には関係ないと思うけど」
人差し指を左右に振り、チッチッチと舌を鳴らし、林田が答えた。
「支配人は古すぎます。時代は刻一刻と変化してんですから、支配人の時代のモラルを僕ら若人に押し付けようとしても無駄と言うものです。今の時代はですねえ、若い女が妻子ある重みのある男に体を投げ出す時代なんですよ。だからこうして財布の中に……」
と言いながら財布の中からコンドームを取り出して見せた。みな大笑いで、今度は林が林田の頭を小突いた。
「この体の何処に、その重みってやつがあるって言うんだ。何処にも見あたらねえよ。重みというより、単なるずうずうしさじゃねえの」
そこへ石塚調理長が入ってきた。石塚は仕事を終えると一風呂浴び必ず事務所に顔を出す。
林田の笑い声を聞きつけ、石塚が仲間に加わる。
「おい、おい、林田君。君はまた、すけべ話をしてるんだろう。調理場に来ては、すけべ話、風呂に入ればまた、すけべ話、ほかにないのかね、話題というものが」
林田が言い返す。
「何を仰いますか、調理長。僕の話を一番喜んでくれるのは調理長じゃないですか」
厨房の二番手、内村に言わせると、最近、調理長はサラリーマンのような言葉使いに凝っているらしい。内村は、調理長が仕入れ業者に「何々君」と君付けで呼ぶたびに、背筋がぞくぞくすると言う。
調理長は、体つきも何も、向井と正反対で、細身で上背があり、なかなかの二枚目で、鏡の中の自分に見惚れることがあるとぬけぬけと言う。向井とは同じ年で気が合うようだ。笑うと目が一本の線になってしまう。その笑顔を見せながら調理長が切り出した。
「話は変るけど、課長、あの山本統括事業本部長、何とかならない。週に一度来て、個室に篭って何しているか知らないけど、本部長用の昼飯を特別に作らせるっていうのは、おかしいよ。あの秘書みたいな女が取りに来るんだ。まだかって顔して。みんなと同じ仕出し弁当にしてくれないかな」
相沢は困惑顔で答えた。
「秘書じゃなくて、彼女は経理課長です。まあ、実質秘書みたいなもんですけど。でも、しかたないんですよ。あの人はレストランや喫茶の直轄事業の統括で、この事業部の部長も兼ねています。若いのに役員候補だそうです。確か支配人より2歳下ですよね」
向井もこの年下の上司が嫌いらしい。
「ここは本部じゃない。ばりばりの現場、しかも健康ランドだ。昼時、厨房は一番忙しいのに、何考えているのやら。でも、さすがに僕も言いずらい。でも、不思議だよね。あの個室で何をやっているんだろう」
林田がこともなげに結論を下す。
「やっぱり、あれじゃないですか。男が一人でやると言えば、マス。これしかないでしょう。でも、お似合いですよね、あの暗い顔して、マスかいている姿」
がはは、という笑い声でこの話はちょんとなったが、確かに不思議なのである。山本統括事業本部長の個室は本来フロント嬢の休憩所だったが、工事の途中で自分の個室に作り変えてしまった。鍵を掛けて誰も入れないようにしてある。
しかし、相沢はふかふかなソファーが運び込まれるのを見て、密かに合鍵を作らせた。仮眠所にはもてこいなのだ。フロントのそばなので何かあった場合、すぐ対処できる。向井にもそこで仮眠を取るよう勧めたが、さすがに怖いらしく使っていない。
この個室にはコピーファックス兼用機、応接、そして狭い部屋には不釣合いなほど豪華な机がでんとすえられていた。相沢も山本が何をしているのかちょっと内部を探ってみたのだ。しかし、机の引出から棚の扉まで全て鍵がかけられていた。
また、調理長の言った秘書こと、石田経理課長は、現地採用の社員だが、あれよあれよという間に山本に取り入り、経理課長のポストを射とめ、山本の後ろ盾をいいことに女帝のごとく振舞っている。相沢より二歳年上、二人の子持ちである。
「さて、休憩終了。京子ちゃんと代わるわね」
則子が立ち上がりフロントに消えると、向井と石塚も連れ立って帰っていった。林はパソコンのスイッチを入れて給与計算プログラムを立ち上げている。相沢と林田は暫く話していたが、それも飽きてそれぞれ夜の見回りに出かけた。
既に23時を過ぎ、日曜の深夜ということもあり、さすがに閑散としている。朝の4時まで開いている喫茶店では何人かの若者がビールを飲んでいるが、彼ら以外は皆、休憩室で寝静まっている。
隣のスーパーの社員達もしばしばここを利用する。家に帰らず健康ランドに泊まって、ゆっくり飲み、翌日出勤するのだ。スーパーの店長、片桐は単身赴任なので、しょっちゅう泊まる。その片桐はまだ来ていない。明日の売り出しの準備がまだ終わらないのだろう。
何が何やら分からぬまま、あたふたと時はすぎてゆく。降格人事の屈辱を感じる暇もないくらいの現実が目の前にあり、それを片付けるとまた別の現実が待ち受けている。唯一まだ体験していないのが本物のヤクザとの対決だ。
刺青客の対応は何度か経験したが、さほどの騒動にはならなかった。今日からの二日間、頼りの向井支配人がいない。鎌田副支配人はトラブルを避けて通ろうとしている。自分がしっかりしなければならない。
夜は深深と更けてゆき、不気味なほど静まり返っている。何事もなく過ぎることを心の中で念じながら、林田のいるであろうゲームセンターへと足を向けた。遠くで「いらっしゃいませ」という則子の声が響く。聞き耳を立てるが、その後の則子の声は聞こえてこない。不安が脳裏をかすめ、心臓の鼓動が内側からどきんと胸を打った。
第三章 鯨井組
いつの間に寝てしまったのか、相沢は机にうつ伏せ状態で、誰かに頬を突つかれ起された。顔を上げると則子がくすくすと笑っている。ふと、手元のノートパソコンの画面を見ると、報告書は1ページ半しか書かれていない。しまったと思ったが後の祭りである。
今日、本部で会議があり、そこで現況を発表しなければならない。電車の中で大筋だけでも書くしかないと思い、慌てて立ち上がると、則子がバッグの中から手鏡を出して相沢に向けた。相沢が覗き込むと、頬にくっきりとマルが描かれている。ワイシャツの袖のボタンだ。則子の微笑みの意味が分かった。二人して声をあげて笑った。笑い終え則子が言う。
「相沢さん、今日の3時ごろ、例の女性が来たわよ。今、休憩室で寝ている。今日はジャガーではなくてハーレーダビッドソンですって。でも、あの人に聞いたけど車で煽ったのは相沢さんだって言うじゃない。」
相沢は膨れっ面して押し黙った。聞かれてつい嘘を言ってしまったのだ。後悔したが、言ったものはどうしようもない。則子が続けた。
「でも、相沢さんのことも宣伝しておいてあげた。本部の偉い課長さんだって。彼女、へーって驚いていたわ。」
「別に、そんなこと言わなくてもいいのに。ところで何している人なの?いつも遊んでいるみたいだけど」
「そこまでは聞き出せなかったわ、いくら相沢さんのためとはいえ。それじゃ、私、帰るね。そうそう鎌田副支配人、今日、お休みしますって連絡入っていたわ。」
「えっ、それはないよ、あの野郎。しかし困ったなあ。今日、僕は本部に行かなければならないし、責任者が誰もいなくなってしまう」
そこにフロントの清水郁子が顔面を蒼白にして事務所に入ってきた。その顔を見て、相沢は容易ならざる事態が起きたことを悟った。心臓の鼓動が耳にまで聞こえてきそうだ。郁子が震える声で言った。
「課長ー、もんもんしょった人が、二人、フロアをうろうろしてるの。こわー。課長ー、早く行って、あれ、確か鯨井組よ、この辺の博徒」
「何故なんだー、向井支配人が休んだ初日にー」という相沢の心の叫びは向井に届いただろうか。それでも気を取り直し、うんと頷いて、足を前に運ぶ。膝が震えてうまく歩けない。丹田に力を入れようとするのだが、力は尻の穴から抜けてしまうようだ。
ドアから様子を窺うと、ヤクザ然とした男が二人、ダボシャツの下からこれ見よがしに刺青を顕にしフロント前のソファでふんぞり返っている。きょろきょろ辺りを見回し、責任者が現れるのを待っているのだ。
入り口前面の「刺青客お断り」の大きな看板が目に入らぬわけもなく、明らかに嫌がらせか、難癖をつけるのが目的である。何故、よりによって、今日なんだ。泣きたい気持ちだったが、女達の視線を感じて勇気を奮い起こした。逃げるわけにはいかないのだ。
相沢はドアを出ると、震える膝と格闘しながら、10メートルの距離をようやく歩き切り、二人の前に立った。立っているのが不思議なくらい両足に力が入っていない。二人がにこやかに笑いかける。相沢はその笑いに誘われるように声をかけた。
「どうも、おはようございます」
二人は声を揃え陽気に「おはようさん」と答えたが、これはこれから起そうとするひと悶着のための演出に過ぎない。前半の陽気な挨拶、打って変わって後半の怒鳴り声、この落差が大きければ大きいほど凄みを増すという彼らの一流の演出なのだ。
一人は丸顔のつるつる頭で、にこにことしているが、それはその落差を強調するためで、この顔に怒りを帯びれば相当凄そうである。もう一人は長髪で彫の深い二枚目で、ニヒルな顔に浮かぶ笑顔は瞬時に般若のごとく変わるだろう。
向井の編み出したご免なさい攻勢で済む相手ではない。さて、次に何と言おうか?相沢は、頭が真っ白になっていることに当惑していた。沈黙が続く。沈黙は彼らの思い描くシナリオにもないようで、困ったように顔を見合わせ、じれて長髪が誘いをいれる。
「どうだい、繁盛しているかい?」
「ええ、まあまあです……」
またしても沈黙だ。今度は坊主頭が聞く。
「大変だろう?」
「えっ?、ええ…まあ…」
会話が弾まないからといって、相沢が責められるべきではない。どう考えても会話が弾む相手でも状況でもない。二人は慣れない愛想笑いに疲れたようで、早く刺青に触れて欲しいらしく、ダボシャツに手をつっこんで更に見えるようにもろ肌を晒した。
相沢は何をなすべきか漸く思い出し、力なくため息を吐いた。そして恐る恐る自分で作ったマニュアル通り、
「実は、私としましても誠に申し上げにくいことなのですが…」
無駄な努力と知りつつ、ありったけの敬語をちりばめて話したのだ。
「あの看板に書かせて頂いている通り、お客様のように刺青をなさっていらっしゃる皆様には、ご入場をご遠慮頂くことになっております。誠に申し訳ございませんが、御退出頂けませんでしょうか?」
声は震えていない。よしよしと内心自分を褒めてやった。が、現実はそう甘くない。
「何だと、この野郎。もういっぺん抜かしやがれ」
「てめえ、この野郎、ふざけたことを言いやがって、出て行けだと」
待っていましたとばかり、耳をつんざくような怒鳴り声が響く。
二人の言葉は同時に吐かれたため、何を言っているのか判然としなかったが、だいたい似たような言葉だったのだろう。この怒鳴り声が合図だったとみえ、外で控えていた5人の仲間が入り口から一斉に雪崩れ込み、相沢を取り囲んだ。
7人のヤクザが噛み付かんばかりの顔で相沢を睨んでいる。相沢より小さいのは、はげ頭とニヒル野郎だけで、あとは皆ガタイがでかい。相沢は絶望のあまり目の前が真っ暗になった。膝のかくかくは大揺れで、冷や汗は両脇の下を濡らす。ちびらないだけましか。
坊主頭が大声でつっかえながらも、出て行けと言われた状況を皆に説明している。大きく頷く面々。聞き終えると、一斉に憤慨し、相沢ににじり寄る。怒声、罵声の嵐だ。坊主頭は小指のない両手を縦横無尽に振り回す。
よくみると、指なしは何人もおり、ない方の手をことさら見せるよう心掛けているようだ。相沢の目の前を指のない手が何本も蠢く。例のニヒル野郎は男達の輪から一歩引いて、だんまりを決め込み、腕を組み、相沢を睨みつけている。
しみじみと見ると、このニヒル野郎は、どこか知的な雰囲気を漂わせている。ジーンズ系でまとめれば芸術家タイプといってもよく、とてもヤクザには見えない。明らかに他の連中とは異なった人生を送ってきたことは確かだ。
相沢も無駄な努力とは分かっていたが、必死でマニュアルの言葉を思い出しながら対抗したが、相手は、はなから聞く耳など持ち合わせてはいない。終いには、だた押し黙り、神妙そうな顔を発言者に向けていた。不思議なことだが、恐怖をやり過すと妙に冷静になれるものなのである。或いは慣れというやつかもしれない。
相沢はさっきから皆より頭一つ出ているノッポの若者ヤクザに声援を送っていた。先輩諸氏が次々と怒鳴り散らす中、唇を震わせて出番を待つが、どうしてもタイミングが合わず、言葉を唾と共に飲み込んでいる。それ、今がチャンスだ。相沢の応援もむなしく、またしても坊主頭に出番をとられ舌打ちしている。
同じような罵声と怒声に辟易した相沢は一瞬の間隙に狙いをすまして大声を張り上げた。
「どうです、コーヒーブレイクにしませんか。そこの喫茶店でコーヒーでもどうぞ」
そう言うと、相沢は男達の間をすり抜け、どうぞとばかり腰を折って片手を喫茶店の方へ向けた。ニヒル男と坊主頭は互いに顔を見合わせ、自分達が舐められていること、もう少しドスを効かせなければならないことを瞬時に了解しあった。
他の連中も、互いに顔を見合わせ、首を傾げる者、憤慨する者、コーヒーブレークの意味を隣に聞く者、様々だが、相沢はかまわず先に立って喫茶店に入っていった。
「まあ、どうぞおかけ下さい。ハルさんコーヒー七つ。僕はコーラ。ビンでいいよ。」
ビンならぎゅっと握ればよい。二三本の指でコーヒーカップなど支えられるとは思えなかったのだ。きっと指が震えてコーヒーをぶちまけてしまうだろう。
ハルさんは喫茶店の元経営者だったが、店が潰れてここにパートで来るようになった。水商売が長いせいか落ち着いていて、はいはいと淡々と準備に入った。すると、ニヒル男が真ん中のテーブルの椅子に腰を落とし、ハルさんに言う。
「コーヒーは二つでいい」
坊主頭もそこに腰掛けたので、相沢もそのテーブルに着いた。五人のヤクザがそのテーブルを取り囲む。
「ちょっと失礼します、ご免なさい」
林田が、五人のヤクザの間をすり抜け前に出て、相沢の横に立った。ニヒル男が怒鳴る。
「テメエは何だってんだ。横からちょろちょろ出てきやがって」
「いえ、私もフロアーの責任者ですので、お話を拝聴しようと思いまして……」
立ち上がりながら坊主頭が、林田に向かって怒鳴り散らす。
「すっこんでろ、この野郎、一人でも話が通じねんだ、話がややっこしくなる……」
相沢が、まあまあと坊主頭の肩に手をやると、思いっきり払いのけられたが、それで気が済んだのか林田をひと睨みして腰を落した。
フロントに目をやると林がカウンター越にちょこんと手を上げた。どうやら奥の手の準備が整ったようだ。一息入れ、相沢はゆっくりと話し始めた。
「何度も申し上げている通りですねえ、これは会社の方針ですので、私としてもこれ以上のことは申し上げられないのですよ。私は一介のサラリーマンですから、上からの指示に従うより他ないのです」
ニヒル野郎が下から見上げるようにして睨み、重たげに口を開いた。
「おいおい、さっきから聞いていればテメエの言い分はそればっかりじゃねえか。他に言い草はねえのか?」
相沢はマニュアルの隅から隅まで思い浮かべたが、それ以外の記述などどこを探しても見あたらない。しかたなく「ええ」と答えた。ニヒル野郎が睨め付けながら言う。
「それじゃあ、例えばの話だ。指に彼女のイニシャルの刺青をしていたとしよう。それを絆創膏貼って入った。お前はそいつをつまみ出すのか?」
固唾を飲んで返事を待つヤクザ達の熱い視線に気付かないわけでもなく、何か引っ掛け臭いと思ったがついつい口が滑った。
「まあ、小さなイニシャルくらいなら」
取り囲む皆の目が一瞬輝いた。しまった、やっぱり引っ掛けだ、と後悔したが後の祭りだ。
ニヒル野郎が鷹揚に頷きながら、口を開いた。
「おうおう、そういうことだ。分かった、分かった。俺達も入場していいわけだ。絆創膏貼ってさえいれば、いいと、オメエはこう言うわけだ。なっ、そうだろう」
「そうは言っていません。小さなイニシャルぐらいなら、目をつぶると言ったんです」
「そうじゃねえだろう。オメエは絆創膏を貼って隠していれば刺青客を入れていてもいいといったんだ。そうだろう、そうじゃねえとは言わせねえぞ」
怒鳴り声とともにバンとテーブルを叩く。相沢と林田の体がピクンと浮いた。そして一斉に怒声の大合唱だ。ヤクザにとって話の内容などどうでも良いのだ。要は相手に恐怖心を抱かせること。早う金を包んで出せて言っている。一人一万、色を付けて10万か、などという思考が脳裏を掠める。
しかし、会社の方針で、それが出来ない以上、議論には負けられない。小さなイニシャルと刺青の違いなどというくだらない議論が続く。口角泡を飛ばしての遣り取りで相沢も次第に熱くなっていった。それで、ちょっと口が滑ったのだ。
「皆さんは、もんもんしょって、それを誇りにしているんでしょう。そんな絆創膏のお化けみたいな物を体に巻いて、風呂に入るのですか、えっ。ヤクザの誇りはどうなっているんです」
ニヒル野郎と坊主頭が血相を変えて立ち上がって怒鳴った。
「何だと、下でに出ていればいい気になりやがって。表に出ろ。この野郎、表に出ろってんだ」
坊主頭が手を取ろうとするが、相沢はさっと手を引いた。いよいよ正念場だ。もう少しの辛抱である。フロントで林がにやにやしながらVサイン。まさか、こんな場面で、おちょくっているわけではあるまい。もうすぐだという合図なのだ。
睨みすえるニヒル野郎。坊主頭は腕を取り立ち上がらせようとするが、相沢はその手を振り解き「暴力をふるうのですか?」と叫び睨みつける。互いに睨み合うこと数秒。ウーウーと短くサイレンの音。見ると、どっと入り口に制服の警官達が雪崩れ込んできた。相沢を取り囲んでいたヤクザ達も喚きながら入り口へと向かう。
その途端、相沢は緊張の糸がぷつんと音をたてて切れたのが分かった。体中から力が抜けてゆく。林田もそこにへたりこんだ。どんなにこの時を待っただろう。リーダ格の警官の怒鳴り声が響き渡った。
「おい、鯨井、鯨井はいるか。おい、鯨井」
見ると、警官とヤクザが小競り合いを演じている。手を出せば公務執行妨害で引っ張られる。だから罵声を浴びせ、胸をぶつけて警官などには負けないという姿勢を示すのだ。その罵声にかっとしたのか、一人の警官があのニヒル野郎をねじ伏せた。またリーダー格の警官の怒鳴り声が響く。
「おい、鯨井、いるのは分かっている。鯨井、出て来い」
と、外から上背のある精悍な男が入ってきた。のんびりした声で答えた。
「はい、はい、ここにいます、ここにいます」
鯨井組の組長らしい。思ったより若く、苦み走った良い男である。どうやら表で待機していたようだ。怒鳴っていた警官が、組長の肩に手を置き、何やら話している。組長は逆らいもせず、ハイ、ハイと答える。その様子を見て、子分達も小競り合いから睨み合いへ移り、収拾の方向へと向かった。そこへ、
「俺達には、人権ってもんが、ないのか?えー、人権ってもんが、ないのか?」
という叫び声。人権?相沢が振り返ると、あのニヒル野郎の声だ。一人だけ手錠を掛けられ、相沢を睨みすえ、再び叫ぶ。相沢が、人権だって?と訝しがっていると、あのノッポの若者ヤクザが目を輝かせ、それを真似て叫び始めた。
「俺達も人権ってもんが、ないもんかえー」
漸く出番が回ってきて、思い切り叫ぶことが出来たのだ。生き生きと何度も繰り返す。
「俺達も人権ってもんが、ないもんかえー」
しかし、言葉は意味を成さない。最後の「えー」は独立していないといけない。ニヒル野郎は苦りきった顔で、若者を睨んでいたが、ふと苦笑いを洩らした。
鯨井組長を乗せたパトカーがサイレンと共に去った。他の連中もぞろぞろと外に出てワゴン車に乗り込む。二台のパトカーが待機しており、どうやら事情聴取のため連行されるらしい。ニヒル野郎がワゴンに乗り込む寸前、相沢に向かって叫んだ。
「おい、テメエ、これから毎回毎回、警察を呼ぶのかよ。警察だって他にもっと仕事があるんだぞ。テメエ等の都合ばかり聞くとは限らねえからな。その時はどうするんだ。えっ、どうするんだよ」
その後、相沢は事情聴取され、当然会議に間に合うはずもない。こうした事情なのだから、本部も許してくれるだろう。事情聴取の合間を縫って電話をいれた。案の定、会議の主催者である小倉企画部長は何度も驚きの声をあげ、根掘り葉掘り聞き、結局、会議欠席を了承した。
警官からようやく解放されると、ハヤシコンビが近付いて来る。林田が話しかける。
「ご苦労さまでした。本当に大変でしたね」
ねぎらいの言葉にほっと胸を撫で下ろし、よろよろと歩いて、その場で力尽きたという様子で倒れ込む真似をすると、二人は大喜びで、大丈夫ですかなどと声を張り上げ、相沢をくすぐりながら介抱する真似をする。悪ふざけが終わると、安堵と言い知れぬ充足感に満たされ、相沢が、二人に向かって言った。
「助かった、本当に有難う。林田君が傍らにいてくれただけで、どんなに心強かったことか。それに林君の合図で、もうちょっとの辛抱だって分かったしね。でも怖かったなー。あんな怖い思い初めてだよ」
林がそれに応える。
「いやいや、どうして、課長もなかなか堂々としてましたよ。普段の課長からは、想像もできねえけど」
相沢が怒った顔をすると、
「今のは嘘、嘘ですよ。普段でも堂々としているよ、なあ、林田」
と林田に振る。
「ああ、堂々とし過ぎて危なっかしいなーと思うこともあるけどね。ちょっとくらい、可愛げを見せた方が出世すると思うけど。それはそうと、よくコーヒーブレイクなんて言葉が出ましたね、あんな按配なのに」
「いや、膝がガクガクして立ってるのがやっとだったから、とにかく座らないといけないと思って・・・」
林田もこれには笑って、相づちを打つ。
「俺も直立不動のつもりが、膝が笑っちゃて、ふらふらするんだもの、びっくりしたな。あんなこと初めてだ。でも、もうこれっきりにしたいよ、あんなこと」
相沢は則子がいないのに気付き、林に聞いた。林は、
「ああ、騒動が収まったら、おやすみって言って帰っていったよ、今日も則子は遅番だからな。でも、この喜びを則子と分かち合いたかったですね、課長」
と言って、相沢の顔を探るような目で見る。林は則子のことでは相沢をライバルとみなしている。
騒ぎも興奮も収まり、則子の言っていたショートカットの女が気になり探してみたが、施設はあまりにも大きく、とうとう会うことはなかった。車で煽ったことを謝ろうと思っていたのだが、会えなければ会えないで、どこかほっとする思いもある。
夕方になっても鎌田副支配人から連絡が入らず、相沢は今日も泊まることにした。そのことを林に言うと、林は、則子が今日も遅番だと知っており、かなり動揺したが、さすがに三日連続の泊まりは無理らしく、17時頃、林田としぶしぶ連れ立って帰っていった。
則子の出社する21時まであと2時間。今、相沢は来週まで繰り延べになった状況報告を書いている。1時間も割り当てられているのでかなりの分量だ。しかし、どうも気が散って筆が進まない。時計を何度も見上げた。則子の顔がちらちらと浮かぶ。
あの日、あの則子の啖呵を聞いてから、相沢はすっかり則子に参ってしまった。その場で惚れた。しばらくして、早番が明けて帰ろうとする則子を食事に誘った。どきどきしながら返事を待つ相沢に則子はにっこりと微笑んだ。
食事のあと家まで送った。肩を並べて歩きながら、そっと指に触れてみた。そして、そっと手を握ってみた。すると握り返してきた。恋人同士のように語らい歩いた。何度も微笑みあった。そしてアパートの前で立ち止まり、則子は相沢の正面に立った。手は握ったままだ。
「今日はごちそうさまでした」
則子は手を離そうとするが、相沢は離さない。相沢は少しずつ手を引いて体を寄せた。互いに見詰めあい、相沢が顔を近づけた。則子は受け入れて、目を閉じた。ほんの寸前だった。則子は相沢の胸を両手でぽんと押したのだ。
一瞬の後、相沢は走り去る則子の後姿を見詰めていた。則子が振り返り、微笑んで手を振る。相沢もそれに応えた。チャンスはまだまだあると高を括っていた。しかし、それから何度誘っても曖昧に受け流す。とはいえ、仕事場での態度は少しも変わらない。
相沢は、今日、何としても決着をつけるつもりである。あの日は、ことを急ぎすぎた。まずは心の内を告白すべきだったのだ。幸い今日は邪魔者の二人がいない。時計の針が21時を指した。相沢の胸が高鳴った。
第四章 パチプロ
則子が失踪してから一週間が過ぎた。鯨井組の騒動のあった晩、遅番の則子はとうとう相沢の前には現れなかった。寝過ごしたのだろうと軽く考え、何度も携帯に電話を入れたが留守電になったままだ。不安にかられて、深夜、アパートを訪ねたがドアは固く閉ざされ人の気配はない。
翌々日、非番を利用して林が訪ねると、則子は前日、アパートを引き払っていた。林は則子とメール交換をしていたので、連絡くれるようメッセージを送ったが何の反応もないという。林は失踪の原因が相沢にあるのではないかと勘ぐって何度も探りを入れてきた。
確かに相沢はデートに誘い、キスをしようとして拒まれたが、それが原因だとは思えない。それに、林のメッセージに応えないという事実は、二人には計り知れぬ則子なりの事情があったのだと結論するしかなかったのである。二人は目と目が合うと、どこでも、とほほと肩を落とし、うな垂れあった。林田もその傷心をもって仲間に加わろうとしてきたが、二人は林田を無視した。何故なら林田は妻帯者なのだからそんな資格はないし、恋心というよりやりたい一心だったからだ。
そんなある日の夕刻、山本統括事業本部長が個室から顔を出し、相沢を呼んだ。個室に入ると応接にでんと構えて、相沢にも座るよう顎で促す。相沢は厭な予感に捉われた。山本がてかてか光る額に皺を寄せ、唐突に切り出した。
「実は、林君のことなんだ。俺は前から言ってきたが、彼はどうもあの仕事には向いていないんじゃないか?本部の経理からもミスが多いと指摘されている。どうだろう、事務職からはずして、現場に出させたほうがいいんじゃないか」
山本統括事業本部長の遣り口は陰険だが確実である。まず負のレッテルを貼り、それを既成事実として周囲に認識させる。本部でもこれを確実にやっているし、根回しも済んでいるはずだ。真綿で首を締めるように邪魔者をねじ伏せるのである。
本部からの不満の声など聞いていない。確かに林はパソコンに慣れておらず、当初、ミスを犯したことはあったが、同じ間違いを繰り返すことはなかった。また、勘定科目を間違えて本部から指摘されることはあるが、それは慣れの問題である。
しかし、山本は、慣れるまで待てない、即刻だと言うのだ。この提案は二度目であることから、もう拒めないと覚悟を決めた。相沢はうな垂れて個室を出た。ちらりと林を見ると、いつものようにパソコンのキーを叩いている。
その隣で石田経理課長がぼんやり台帳を眺めている。部下などいないのだし、現金出納だけの課長職を置くというのもうなずけない。山本は石田に林の仕事を引き継がせろと言う。石田は、暇なものだから、山本に頼んで林の仕事を自分のものにしようと画策していたのだ。
林は総務の仕事だけやっているわけではない。暇さえあれば、どこでも、どんな仕事でも手伝う。この一月不眠不休で頑張ってきた。それが石田ときたら、現場に一切出ようとせず、日曜祝日は休み、山本の世話を焼くのが自分の仕事と勘違いしている。
その石田が、ごそごそとバッグから何かを取り出した。小さなビンだ。ちらりと上目遣いに相沢を見るが、何事もなかったように爪にマニュキュアを塗り始めた。相沢はため息をついた。向井に相談するしかない。相沢は居眠りする向井の肩を揺すった。
「まあ、そう悩むなよ。あいつはそんなこと気にする男じゃないから。俺から話すよ」
ほっと胸を撫で下ろし席に着いた。すると向井が大きな声で林に声をかけた。相沢は時間をかけてゆっくりと説得するものとばかり思っていたので焦って、止めるよう合図を送るが、既に大声で話は始まっていた。
「おい、林君。君の今までやっていた総務の仕事、全部経理課長に渡してくれ。君は副支配人候補ってことで、俺の補佐を頼むよ。まあ、今まで現場でやってきたことの延長みたいなことだけど、とにかく頼むよ」
一瞬、林は困惑した顔をしたが、向井が頭を下げているのをみて、即座に答えた。
「いいですよ、俺もこの仕事、向いてねえと思ってたところだから。本部から間違い指摘されるたんびに、落ち込んでるより、そっちのがいいや。何かせいせいしちゃった。ねえ、石田経理課長、教えっからこっちへ来いよ。ほれ、俺の膝の上に腰掛けて」
そんな下卑たジョークに反発するでもなく、石田は目を輝かせ、
「本当、嬉しいー。私、前からコンピューターに興味持ってたの」
と言うと、林の隣にちょこんと座って画面を覗き込んだ。向井が相沢に小声で言った。
「課長、林は分かっているんです。石田が林の仕事をやりたがっていたことも、統括事業本部長がそれを後押ししてることも。林は即座に了承したでしょう。あいつだって元店長経験者だ。俺の気持ちなど手に取るように分かる。そんなもんです」
これを聞いて、相沢は林に負けたと思った。林はこの数ヶ月、パソコンの研修を受け、プログラムの導入から実施まで手がけてきた。その仕事をあっさり人に譲るというのである。いつまでもプライドを捨てきれない相沢より、年は若いがよほど大人である。
清水郁子がフロントから顔を出し、ニヤニヤしながら相沢を呼んだ。お客さんだという。フロントに出ると、例のボーイッシュな女が待っていた。横に林田が佇み親しげに話している。林田は相沢に気付き話しかけた。
「課長も隅におけないですね。車で久美子を追い掛け回すとは。でも、後ろから追いかけて、何で久美子が美人だって分かったんです?」
「まさか、林田君のお友達?」
「情婦ですよ、ただのセックスフレンド、ねえ」
女は笑顔を見せ、肘で林田の腹を突いた。かなり本気だったらしく、林田はうーと唸ってうずくまっている。相沢は最初に謝ってしまおうと、ぺこりと頭を下げ、言った。
「あの節は、本当に申し訳ありませんでした。ちょっと苛苛してたもんですから。それに、まさか女だなんて思いもしなかったし」
林田が
「何が、あの節は、ですか、気取っちゃって」
と、ちゃちゃをいれようとしたが、またしても肘で打たれて顔をしかめた。女が言った。
「もういいですよ、あの時のことは、私も言いたいことは言ったし。フロントの女性に言わせると、私のその一言が、相沢さんをすっごく傷つけたって言っていたから、いずれ私の方から謝ろうと思っていたの。もっとも彼女辞めてしまったみたいね」
鵜飼則子は全てを知っていた。ハッピを着たくなかったことも、プライドを捨てきれない相沢の弱さも。じわっと目頭が熱くなり、切ない思いが胸を締め付けた。林田は相沢の様子に気付き、しんみりと言った。
「久美子、課長さんは、その彼女に惚れていたんだ。それがいなくなっちゃったもんで、もう、悲しんで、悲しんで、飯も喉に通らねんだ。見てる俺っちも辛くてさあ。まあ、時間が解決するのを待つっきゃねえ。」
しんみりとした顔のまま、何気ない風をよそおい、続けた。
「ところで、課長、俺もずっと気になっていたんだけど、といっても、まあ、林ほどじゃねえけど……いっぱつくれえ、やらしてもらったん?」
相沢は拳でボディをくれてやったが、林田はそれを避けて笑いながら逃げていった。林田の後姿を見詰めながら、女が言った。
「林田君、ちっとも変わらない。小さいときのまま。彼とは小学校から高校まで一緒。幼友達よ。そうそう、私、吉野久美子。よろしくね。ここ、もう三度目。これからも利用させてもらうわ」
相沢は怪訝な顔で久美子を見た。林田と同じ年であれば30歳。とてもそうは見えない。二十代前半くらいかと思っていた。突っ張ってはいるが、どこか幼さが残る顔立ちだ。久美子は相沢の不思議そうな顔に気付いたのか、笑みをうかべてた。
「もしかしたら、もっと若いと思っていたの?そうだったら嬉しい。でも、本当は30歳、もうオバンよ。そろそろ焦らないといけないって思いはじめたところ。相沢さんはお幾つ?」
「もう32歳だ。どうも女に縁がなくて。それより、いつも、あんなにスピード出しているの。追い付こうとおもったけど、とても無理だった」
「まあね、それっきり趣味がないから」
その時、後ろで怒鳴り声が響いた。振り向くと、林とお客が睨みあっている。怒鳴ったのはお客の方だ。相沢は会話を中断して二人に近付き、そのお客の横顔を見て、何度も問題を起こしている例の奴だと気付いた。相沢が話しかける。
「誰かと思ったら、また貴方ですか。何度、騒ぎを起せば気が済むんです。しまいには、出て行ってもらいますよ」
「何を言っているんだ。今回は、俺は悪くない。こいつがいきなり俺を突き飛ばしたんだ」
にこにこして林が答える。
「何が悪くないだ。悪さしようとしてたじゃねえか。酔っ払った振りして女にぶつかろうとしていた」
「俺はただ酔っ払って脚がふらついただけだ。そいつを、こいつが勘ぐってどついた。どう考えても割があわねえ。おい、兄ちゃんよ、やろうじゃねえか、えっ」
ここで間をあけると、低い声で続けた。
「おい、ちょっくら、外に出ようじゃねえか。ここでは他のお客さんにご迷惑がかかる」
ここで林がぷっつんした。
「何が、ここでは他のお客さんにご迷惑がかかる、だ。テレビドラマみてえな臭い台詞吐きやがって。テメエは、ここで何度人様に迷惑をかけてきた。一回や二回じゃねえだろう」
男はこれを聞いて、ふふふと不敵な笑みを浮かべ、ついて来なとばかり、肩を怒らせ歩き出した。林はその後を追おうとしたが、いつの間に来たのか、林田が林を羽交い絞めして押さえた。林はそれを振り解こうとするが、力では林田には勝てない。
男は振り向いて、二人の様子を見た。ふんと鼻を鳴らし、叫んだ。
「馬鹿野郎、風呂屋のサンスケがでかい面するなってんだ」
林は尚も抵抗するが、林田が事務所に無理矢理連れ込んだ。相沢は林の目に光るものを認めた。男は、またもふんと鼻を鳴らし、相沢の前を通り過ぎ、階段を上っていった。相沢がその後ろ姿を憎々しげに睨みすえる。
林はやはり悔しかったのだ。上司の理不尽で、これまで誇りをもってやってきた給与計算の仕事を諦めざるを得なかった。笑いながらその場をやり過し、現場に出た。そして、何度も女にぶつかって難癖をつけていたこの男に遭遇したのだ。
相沢と同じだ。プライドを傷付けられ、鬱憤はたまりにたまった。林と違うところは、それが相沢のは自尊心だったことだ。林の方は、自尊心ではなく誇りだ。仕事に対する誇りを傷つけられたのだ。相沢よりよほどこたえただろう。
相沢は、階段を上がってゆく男に向かって怒鳴った。
「おい、俺がさっき言った言葉が聞こえなかったのか?問題を起せば出ていってもらうと言ったはずだ。金は返す。今、出ていってもらおう。さあ、ロッカー室はこっちだ」
男は振り向くが降りてこようとはしない。相沢には林の悔しさが感染していた。引きずり下ろしてやろうと、階段を上がっていった。男は温厚そうな相沢が怒りを顕にしているのを見て、困惑の色をみせたが、まだ余裕の笑みをうかべている。
腕にそうとうの自信があるのだろう。それは相沢も一緒で、負ける気はしなかった。一歩一歩男に近付いていった。1メートルの距離で、ふと、相沢は自分がかなり不利な立場に立たされていることに気付いた。そこは階段途中である。
もし、男がつま先でちょっと蹴り上げれば相沢の顎にあたる。男が空手の有段者であれば、まず避けられないだろう。階段を一段上がる。男も一段上がる。優位を保っている。どうやら、相手はそうとう喧嘩慣れしている。参ったと思った。
と、突然、林田が下から駆け上がってきた。林田は、一目見て相沢の不利な点を見抜いたようだ。相沢と男の間に半身になって割って入った。そして言った。
「とっつあん、入場料は返してやっからよ、出ていってくれよ。とっつあんには世話になったけど、もう、俺だって我慢の限界だ。来るたんびに騒ぎを起している。さあ、出ていってくれよ」
林田は男を睨みつけているが、いつになく真剣な眼差しが、どこか寂しげに映る。男はまたしても、不敵な笑みを浮かべていたが、ふんと鼻先で笑った。「そうかい」と呟き、ふーと長い吐息をもらした。そしてゆっくりと階段を下りて行き、ロッカー室に消えた。
林田はじっとその後姿をみつめていたが、ふと、苦笑いを洩らし、重い口を開いた。
「あの人には随分世話になった。あの人はパチプロで、俺が稼げるようになったのは、あの人のお陰なんだ。でも、まあ、しょうがねえ。とっつあんも分かってくれたみてえだし。でも、林の奴、よっぽど悔しかったみてえだ。机につっぷして、くっくっくっって泣いていやがった。とっつあんと何かあったん?」
「いや、そうじゃない。事業本部長が、総務とコンピューターの仕事を石田経理課長にやらせろって言ってきた。それで悔しかったんだろう。つい、とっつあんに鬱憤を晴らしたんだと思う」
「何とまあ残酷なことを。あいつあんなに一生懸命やってきたのに。プログラマーになるなんて夢見てえなこと言ってた。まいったな、それは」
そこに、久美子が近付いてきて、相沢に言葉をかけてきた。
「相沢さんて、結構厳しいのね。誰だって酔っ払うことはあるわ。何もあんなに怒鳴らなくてもよかったじゃない」
どこか非難するような響きがある。くるりと背を向け更衣室へと消えた。当惑していると、林田が嬉しそうに声をかけてきた。
「課長、また振られちゃいましたね。まあ、彼女には彼女のなりの言い分ってもんが、あるんでしょう。今度会ったら、うまく説明しておきます。」
「彼女には彼女なりの言い分って?」
「課長は、久美子から何か聞きました?」
「何かって、何?二人の関係のこと?幼馴染とは聞いているけど」
「そうそう、幼馴染で、セックスフレンド。違う違う、そうじゃなくって、あいつの家のこと」
「いや、何も聞いていない。家が何かやっているの?」
「いえいえ、聞いていないなら、それはそれとして、いいんですが、まあ、あいつの家は地元の旧家で大地主ってとこです」
二人が事務所に戻ると、向井と林が深刻そうな顔をつき合わせて話し合っている。漏れ聞こえる向井の発言で、石田との仕事の分担と今後の仕事の内容を話しているようだ。当の石田はというと、5時を過ぎたのでもう家路についたということだ。
山本の個室も人の気配はなく、一緒に帰ったのかもしれない。まったく気楽な人達である。何の責任もなく、何の貢献もしない。もし、何もする気がないなら、何も口を出すな、と言いたいのだ。しかし、言える立場でないことは、分かりきっていた。
その日の夜、責任者を集めミーティングを開いた。明日から4日間、八王子祭りである。テキヤが全国から大挙して押しかけてくる。刺青をしょっている人々も多い。その入場を阻止すべく特別警戒態勢をとらねばならない。
鎌田副支配人が黒板に日程を書き、深夜番を書き込んでゆく。祭りの前後を含めて6日間、二人一組で泊り込む。相沢は一日おきに3日間泊まることになった。鎌田とのペアだ。肌は合わないが、こういう時には、何となく頼りになる男だ。兎に角、柔道五段、大男である。
第五章 覚醒剤
昨夜は、祭りの前日であることから危険と判断し、向井支配人とハヤシコンビの3人が泊まりこんだ。相沢も23時まで残り、帰りが遅くなったが、今朝、目覚めると普段より1時間も前である。やはり気になっていたのだ。三人は今頃どうしているだろう。
相沢はこの仕事に入って初めて宿直という体験をしたのだが、夜は人を不安にさせることを実感した。ましてやヤクザ対応していると尚更だ。しかし、東の空に暁が現れ始めると、不安は徐々に薄らぎ、安堵と平安が心の底から涌きあがってくる。
そして、太陽が顔を覗かせた時、何ともいえない躍動感と開放感が体を駆け巡る。原始人も同じように感じたに違いない。彼らの不安材料はヤクザではなく夜行性の肉食獣だった。そして相沢は、原始人もそうしたであろうように、太陽に両手を合わせるのだ。
車を停め、靄のかかる駐車場を横切り、事務所に入ってゆくと、向井支配人は机に突っ伏して寝ている。林田と林は机に座り話しこんでいたが、二人とも晴れやかな顔を相沢に向けた。どうやら、何も起こらなかったようだ。林が嬉しそうな声で言った。
「課長、おはようございます。何もなかったですよ。本当に良かった。ゆんべは、緊張しまくっていたけど、こうして何も起こらないとなると、ちょっと、肩透かしくったみてえで、がっくりしちゃいますよ」
林田も笑いながら合いの手を入れる。
「まったくだ、今日も泊まりてえくらいだ。今日は何か起こりそうな気もするし。なあ、林、気がつかねえか?今日の課長はなんとなく影が薄いというか、どこか寂しげで、俺達に別れを告げているような、そんな気がする。こういうのを胸騒ぎっていうのかな」
相沢も笑って答えた。
「自分達が終わったからって、随分勝手なこと言ってるけど、明日だってあるんだよ。僕は明日の方が危ないと思う。だってテキヤは、昨日今日は店の準備で忙しいけど、二日目は材料を運ぶだけだろう。その帰りにちょっくら暴れてみるか、なんてどっと押し寄せるんじゃないの」
「うーん、説得力ある。そう言われれば、そんな気がしないではない。でも課長は鎌田副支配人と組だから安心でしょう。なんたって、柔道五段。課長もうまくやっているんだから」
「馬鹿言え、僕が決めたんじゃなくて鎌田さんが勝手に決めたんじゃないか」
「そうでしたっけ、まあ、そんなことはどうでもいいけど、課長だって大学で空手やってたんだから、それなりに自信はあるんでしょう。ところで、課長は何段なん?」
「別に段なんか持っていないよ。最初の進級試験受けただけだから、覚えていないけど恐らく最初は三級じゃないかな」
「えーっ」と、大きな声をあげて、林田と林が顔を見合わせた。林が言う。
「空手4年もやってて、三級しか取れなかった人を、全面的に頼っていた俺達は何なんだ。この一月の間、感じていたあの安心感は虚構の上に成り立っていたなんて、あまりにも酷すぎる」
と、二人は泣くマネをして、林田が最後を締めくくる。
「これから、俺達は誰を頼りに生きていったらいいんだ」
朝の掛け合い漫才はこれでちょん。いつまでも付き合っている訳にはいかない。向井を起こそうと背中を向ける。その時、向井ががばっと起き上がった。目は血走っている。
「うわー、大変だ。あんなに刺青がはいってきちゃった」
と、叫んだ。驚いて見守る3人の視線に気付き、もじもじと照れ臭そうに言った。
「何だ、夢か、驚いた。次から次と刺青客が入ってくる夢を見ていたんだ」
思いは誰も同じである。皆、ことさら大きな声で笑いながらも、心から笑えなかった。
その日は昼も夜も何事もなく、3時の見回りが終わると、そうそうに個室に入ってソファに身を横たえた。遅番の清水郁子が起こしに来ないことを、そして早く夜が明けることを祈りつつ目を閉じた。
鎌田に起された。大きな顔が目の前にある。とうとう来たかと、一瞬不安が体中を駆け巡ったが、鎌田の笑顔を見て、ほっと胸を撫で下ろした。鎌田が口を開いた。
「今日は本部長の出勤日だから早く起きた方がいいですよ。早めに掃除させますから。そろそろ起きて下さい。」
鎌田は一人本部長に取り入っている。ここを仮眠所に使っていることも、いつかばらされるかもしれない。そんな不安もよぎったが、その時はその時である。フロントの更衣室を勝手に作り変えたことを、会社にばらしてやれ、と思った。
その日の帰り、久美子に出会った。とは言っても最初は久美子とは分からなかった。ハーレーが相沢の車の横にぴったりとついて並走していた。腹に響くエンジン音を聞きながら、ちらちらと視線を走らせた。ふと、鵜飼則子が言った言葉が蘇った。
「今日はジャガーではなくてハーレーダビッドソンですって。」
あっ、吉野久美子。相沢は走行車線を走るハーレーのライダーを見詰めた。その視線に気付きライダーのヘルメットが相沢の方に向いた。顔は見えないが、胸のふくらみから久美子に間違いない。右手でVサインを出し、すぐにアクセルをふかした。
ハーレーは相沢の車の前に位置を変え、暫く走っていた。しかし何を思ったか、久美子はお尻を上げ、後ろに突き出した。そして右手で尻をぺんぺんと叩いたのだ。そして一気に加速し、相沢の視界から消えた。
「なんだ、ありゃ。30女のすることか。」
相沢が呆然と呟いた。
翌日、相沢は出勤すると徹夜明けの林といつものように冗談を飛ばしあっていた。そこに清水郁子がコーヒーを三人分持ってきて仲間に加わる。経理の石田は早々に銀行回りにでかけ、2時間は戻ってこない。取引銀行は一行なのに何が銀行回りだか。
本部長がいれば一緒に行くが、今日は一人で羽を伸ばしにいくつもりのようだ。コンピューターにはすっかり飽きて、簡単な集計の操作を覚えて悦に入っているが、細かく面倒な作業だけは林に残され、今、林がコンピュータに向かう。そこに調理長が顔を出した。
「諸君、おはよう、元気かね。ところで、林君、君も切り替えが早いってみんなの噂だよ。鵜飼君が失踪してあれほど嘆いていた人間が、もう郁子君と出来てるってのは本当なのかね。うちの若いのも頑張っていたけど、林君に取られたって泣いていたよ。」
林と郁子は顔を見合わせ、困惑の表情だ。林が耳を真っ赤にして答えた。
「このあいだ、みんなでカラオケに行って、デュエット3曲歌ったくれえで、そんな噂立てられちゃうんだから、油断も隙もあったもんじゃねえや。」
郁子も顔を赤く染めて下を向いている。相沢はカラオケと聞いて嫉妬に駆られた。これだけ親しくしていながら一度も誘われていないのだ。みんな結構行っているらしい。相沢はことさら真面目腐って、仕事の話を持ち出した。
「調理長、例の新メニュウこと、考えて頂きました?」
調理長は、ぶっきらぼうな相沢の言葉に一瞬むっとして答えた。
「課長には、随分妥協させられてきたけど、今度の話はなかったことにしてもらいたいと思っている。」
林田からほぼ大丈夫という情報を得ていたのだが、調理長の厳しい表情に一瞬ひやりとして、昔のやり取りを思いだした。
調理長との最初の出会いの時だ。調理長は門弟を抱えて職を探していた。だからまさかあんなことで怒り出すとは思わなかったのだ。相沢は会席料理だけではなく、ラーメンや天麩羅蕎麦もやってもらいたいと言ったのだ。一瞬表情が強張り、調理長が言った。
「この話はなかったことにしてもらいましょう。」
こう言うとすっくと立ち上がって立ち去ってしまったのだ。相沢はその後何度も家に足を運び、頭を下げ、1年の契約にこぎつけた。勿論、今ではラーメンも天麩羅蕎麦も作ってもらっている。しかしこの新メニュウには納得がいかないのかもしれない。
不安そうに見詰める相沢に、調理長はにこっと例の目が線になるような笑顔を見せた。
「実はね、カツ丼は勘弁だけど、カツ重なら妥協しようと思っているんだ。でも、千円以下じゃだめだぞ。そこらの豚カツ屋なんて真似の出来ない豚カツを入れるんだから。」
相沢は林と顔を見合わせ頷きあった。カツ丼はやはり大衆食なのだ。こうした施設にはどうあっても必要だった。調理長が続ける。
「あの林田君も、すけべ話ばかりと思っていたら、結構うまいことを言うんだ。割烹で鰻重があるのと一緒で高級料理をだす健康ランドにカツ重がないのおかしいと言い張るんだ。あんまりしつこくて面倒だったから妥協することにしたよ。」
調理長にとってカツ丼もカツ重も同じである。ただ相沢達の熱意に合わせてくれている。厨房二番手の内村の苦虫を噛み潰したような顔が目に浮かぶ。内村は健康ランドなど最低だと思っているのは明らかだ。相沢は調理長に深々と頭を下げた。
その日の夕方、事件は起こった。風呂場担当の岩井が例のごとく事務所に駆け込んで来た。刺青男が騒いでいると言う。急いで行ってみると最近入社したばかりの上田が男に絡まれている。男の腕には大きな絆創膏が貼られている。そこに刺青を隠しているのだ。
相沢はつかつかと二人に近付き声をかけた。
「おい、上田、どうした。何か、お客様に失礼なことでもしたのか?もし、そうならちゃんと謝るんだ。おい、上田。何とか言ったらどうだ。」
上田は恐怖で体が硬直している。頭を下げようとしているらしいが、ぎしぎしと骨の擦れ合い音が聞こえそうだ。相沢に向かって何か言うのだが、声が震えて聞き取れない。しかたなく相沢がお客に話しかけた。
「誠に申し訳ございませんが、当店では絆創膏を貼ったままの入浴はご遠慮頂いております。お取りいただけませんでしょうか。」
中にはケロイドや傷を隠そうとする人もいるが、この客は明らかにヤクザまがいの人生を送ってきた顔である。パンチパーマに頬の傷、眼光鋭く、首には図太い金のネックレス。
ちんぴらの看板背負って歩いているみたいなものだ。男の目がきらりと光る。
「てめえ、俺を怒らせたいのか?俺は人に見られたくないから絆創膏を貼っている。それを見せろと言うのは、喧嘩を売っているのと同じことだぜ。やるか?あんっ。」
声に凄みを効かせ、相沢を睨みつける。相沢も負けてはいない。絆創膏の下には小さいにしろ刺青が隠されている。睨み合いは数秒続いた。男は、ふんと鼻をならし、
「やる気がねえのなら、風呂に入らせてもらおう。」
と言うと、風呂に向かって歩き出した。相沢は追いかけて、男の前に立ちはだかり、頭を下げた。そしてもう一度言った。
「申し訳ありません、絆創膏を貼ったままのご入場はご遠慮頂いております。」
男の顔が般若のよう歪んだ。男はとことんやる気なのだ。何故なら風呂に行くのにパンツをはいたままだからだ。フルチンですったもんだするのは、男にとってこれほど情けないことはない。この後、爆発するつもりで、パンツは脱がなかった。案の定、怒声が飛んだ。
「この野郎、とうとう俺を怒らせたな。こうなったらオメエも男だろう。覚悟はできているんだろう。ただで済むと思うな。」
男はロッカーに戻り着替え始めた。この時、林田が入り口から顔を覗かせ、合図を送ってきた。あと5分の辛抱というわけである。相沢は男が着替え終わるのを待った。上田はへたりこんだままだ。岩井は神妙な顔をして相沢の傍らに佇んでいる。
漸く着替え終え、男は上着のポケットから何やら取り出した。白い粉の入った袋だ。男は慎重に袋を破り、手の甲に大切そうに落としている。そして甲を鼻に近づけ、一気に白い粉を吸い込んだ。そして恍惚とした表情を浮かべている。
相沢と岩井は呆然と男の様子を見ていたが、顔を見合わせ、互いの身の不幸を哀れんだ。ほんまもんだ。ほんまもんのヤクザだ。相沢の膝ががくがくと波打つ。岩井は徐々に後退りして、相沢の視界の端から消えた。
男は不気味な笑いを浮かべて相沢に近づいて来る。胸のポケットに手をつっこみまさぐっている。何を出す気だ。相沢の額に脂汗が浮かぶ。男の手がさっと引き抜かれた。相沢は思わず、声を上げそうになった……あっ……ハンカチ。男は鼻をかんだ。
そのままハンカチをポケットにつっこみ、あらためて相沢を睨みすえる。そして一歩二歩肩を揺らして近づいた。拳が飛んだ。ぐっと奥歯を食いしばり衝撃に備えた。拳が触れたら大袈裟に仰け反って倒れてやろうと思っていたのだ。
しかし拳は相沢の一寸手前で止まっている。男がにやにやしながら言った。
「そうかい、そういうことかい。殴られて警察に突き出そうという魂胆だ。その手に乗るかよ。」
「いえいえ、そんな……」
怒声が飛ぶ。
「ざけんな、この野郎。顔にちゃんと書いてある。鯨井が言っていた。3分もしないうちにパトカーが駆けつけたってな。もう呼んでいるんだろう。」
図星を指され相沢が黙り込む。男はそれと察し、舌打ちして足早に出口に向かう。相沢は男の後を追う。フロントでは相沢を置去りにした岩井が林田に事情を話している。その二人を尻目に男はフロントで清算を済ませ、出口に向かった。
男は焦っているのかシューズボックスのキーがなかなか入らない。カチッと音がして、中から雪駄をとりだすと、それをつっかけて小走りに駆け出した。二人の警官がやってきたのはそれから一分と経っていない。
「どうしました。奴はまだ中ですか?」
そこで呆然と立ち尽くす相沢ら三人に声をかけてきた。林田はその警官と顔見知りらしくこれに答える。
「山ちゃん遅かったじゃないか。奴が出て行ってからほんの一分も経ってねえ。それよか、手柄立てるチャンスかもしれねえ。」
と言って例のクスリのことを告げた。二人の警官は色めき立ち、目を輝かせ、男を追って駐車場へと駆け出した。途中一人の警官がパトカーから小さな銀色のケースをつかみ出した。相沢も林も岩井も後を追うために裏口に回り、靴を履いて駆けた。大捕り物の現場に立ち会える、そんな興奮に駆られていたのだ。
三人が漸く駐車場に辿り着くと、警官たちは男の車をちょうど押さえたところだ。男がふて腐れながら車から降り立った。岩井が急に元気になり、お礼参りと言う言葉も忘れ、警官にクスリのありかを告げ口した。
山ちゃんと呼ばれた警官が興奮気味に言う。
「おい、こら、胸のポケットに入ってるものを出せ。隠そうたって、そうはいかん。分かっているんだ、早く出せ。」
良く見ると、山ちゃんは鯨井組の騒動の時、あのニヒル野郎をねじ伏せた警官である。男が惚けて煙草なぞ取り出すものだから、山ちゃんは胸倉をつかみ胸のポケットまさぐる。
「おいおい、暴力はいかんよ、暴力は。」
山ちゃんが応じる。
「何が暴力はいかんだ。暴力を生業にしてるくせしやがって。」
山ちゃんがようやく二センチ四方の包みを探り出した。そばに控えるもう一人の警官に包みを渡す。もう一人の警官は用意した銀色のケースを地面に置きながら、その包みを受け取る。ケースを開けようとした手が止まった。そしてじっと包みを見詰める。
「あのー、先輩……」
男がくっくっくと笑いを堪えている。山ちゃんが怪訝な顔で振り返る。
「先輩、袋に中央ドラッグストアって……」
男は辛抱堪らず大きな声をあげて笑い出した。そして尻のポケットからくちゃくちゃになった白いクスリ袋を取り出して山ちゃんの目の前にかざした。そして叫んだ。
「やいやい、ポリコー、ヤクザは風邪ひいても、風邪薬飲んじゃいけねえなんて言うんじゃねえだろうな。え、どうなんだ。飲み方だって色々あらあ。俺は鼻から吸い込むのが子供の頃からの癖なんだ。なんか文句あっか、はっー?はっー?」
山ちゃんの顔が怒りで真っ赤に染まる。男は尚も嵩にかかっていたぶる。
「なんだー、その顔は。えー、善良な市民に対して乱暴な態度とりやがって。名札を見せろ、この野郎。山科菊雄だな。な、な、なんだー、菊雄だ。鬼瓦みてえな顔して菊雄?こいつは、笑わせるぜ、がっはっはっはっは。可笑しくて腸ねん転起しそーだぜ。がっはっはっは。」
ここで山ちゃんが切れた。むんずと男の首を右手で鷲づかみにしたのだ。林田ともう一人の警官が必死で山ちゃんを引き離す。男が漸く逃れ、げーげー喉をならして逃げるように車に乗り込んだ。息を整え、エンジンを駆けると、窓を開けて言い放った。
「テメエの顔と名前は覚えたからな。このお返しはたっぷりとさせてもらう、覚えておけよ。いいか、良く聞け、背中に注意しろ、えー、菊ちゃんよ。」
二人に押さえられながら、山ちゃんが吼える。
「ああ、覚えておく。腕に自信がないなら、チャカでも何でも持って来い。受けてたってやらあ。」
男はにやりと笑ってアクセルをいっぱいに踏み込んだ。
山ちゃんがしゃがみ込んだ。そして涙を拭う。悔し涙だ。林が声を掛ける。
「ご免よ、山ちゃん。てっきりヤクだと思ってよ。まさか風邪薬だなんて。」
「林さん、そんなこといいんです。それよっか、くやしいな、あいつら。あいつら、いつだって俺たちを馬鹿にしやがる。」
林田が笑みをこぼし答える。
「山ちゃん、明日、また例の飲み屋で一杯やりますか。このあいだは奢ってもらったから、
今度はオレッチに奢らせて下さいよ。」
山ちゃんがゆっくりと顔を上げる。その顔に笑みが浮かぶ。誘いに乗ったのだ。相沢が慌てて割って入る。
「そうしろ、林田、交際費でいいから、奢ってさし上げろ。」
林田が人差し指を口の前で横に振り、ちっちっちと音をたてる。
「課長、こんな時、野暮なこと言わないでくださいよ。男と男が互いの傷を舐めあうのに、交際費はないでしょう。」
相沢は真っ赤になってうろたえたが、気を取り直し、笑いながら二人に話しかけた。
「はっはっは、まさにその通り。それより、山科さん、それと……?」
もう一人の警官が答える。
「石橋です。」
「石橋さんもどうそ、コーヒーを飲んでいって下さい。いつも、お世話になりっぱなしですし。」
感情の振幅の激しい人は、陰と陽が背中合わせだ。一瞬前の悔し涙さえ笑いの種にしてしまう。事務室では相沢や岩井の幾分興奮気味の笑いが響き渡る。殴られることなく終わったことに安堵する気持ちが心を高ぶらせているのだ。
その横で、真面目くさった顔でコーヒーをすする石橋は、イヤホンから流れる情報に神経を集中させている。相沢が気になって石橋に聞いた。
「そうやっていつも本部からの指示や情報を聞いているんですか?」
「ええ、心の休まる暇もありません。24時間続くのですから……」
「えっ24時間勤務なんですか?」
「ええ、それで次の日は休み。昼過ぎまで寝て、ごそごそ起き出してぼーっとしていると一日が終わっています。あれって思うと、またイヤホンに耳を傾けている自分がいます。」
山ちゃんも頷く。相沢はあの日のことを聞いてみたくなった。
「そういえば、山科さんは鯨井組がここで騒いだ時もいましたよね?」
「ええ、こいつとはコンビですから二人で来てました。」
「ああ、そういえば石橋さんも覚えてます。特に山科さんはあの長髪のニヒルな感じのヤクザをねじ伏せていましたから。」
山科が苦笑いして答えた。
「あの時はつい頭にきてしまって。帰ってから上司に散々絞られました。」
林田が合いの手を入れる。
「山ちゃんは、言葉より先に手が出ちゃう方だから、警察よりヤクザの方が向いてるんじゃない?」
「馬鹿言わんで下さい。それに、あいつの場合は特別なんです。3年前、駅前交番勤務の時、奴は駅前の工事現場で働いてて、それで知り合ったんです。奴の出身が親父と同じ和歌山なんで何となく気があってよく飲んだんですよ。名前は堤隆二」
「和歌山ですって?」
相沢と林田が同時に言った。
「それがなにか?」
「いえいえ、別に。」
と、これも二人同時に声を合わせる。山科が続ける。
「堤は、頭も切れるし、度胸もいいし、いい男だと思ったんですが、何時の間にか刺青入れて、鯨井のいい顔になっていました。まったくがっくりです。」
相沢と林田が視線を合わせ頷きあう。鵜飼則子が失踪したのは鯨井組の騒動の直後だ。則子は堤と和歌山で知り合いだった。そしてあの日、偶然、変わり果てた堤を見たのだ。そして失踪した。どんな事情があるのか分からないが、堤の出現が失踪の原因であることは間違いない。二人は山科の話に耳を傾ける振りをしながら全く別なことを考えていた。
二人にはどんな事情があったのか?則子は1年前に八王子に現れた。堤は3年前だ。もし則子が堤を追ってきたとするなら、刺青をし、ヤクザになった堤を見て失望し、関わりたくないと思い八王子を去った可能性もある。
別の可能性もしかりだ。たとえヤクザであろうと気持ちに変わりがなく、堤の胸に飛び込んだという可能性だ。山科が去ってから、林田と二人、あれこれ話し合った。推論を戦わせたところで、意味のないことは分かっていたのだが話は尽きない。
いつの間にか夕闇が迫っていた。山科との待ち合わせの時間だと言って林田が席を立つ。ドアに手をかけて、ふと、振り返った。そしてにやりとして言った。
「それじゃ、課長、遠慮なく交際費使わせて頂きま。」
第六章 テキヤNo1
いよいよ八王子祭りの最終日。今日をやり過せば、一段落である。皆、今日は絶対に来ないと確信をもって言う。何故なら、最終日なのだから、テキヤも後片付けを済ませ急いで家路につくはずだし、まして中心街から遠い健康ランドに泊まるはずかないからだ。
皆の意見に全幅の信頼を置いていたわけではないが、相沢もなんとなくそんな気がして、祭りの最後の夜が暮れる頃、鼻歌交じりで出勤し、向井と交代した。すでに出勤していた副支配人の鎌田が、林田が急遽泊まり番を申し出たと報告する。
今日は郁子の深夜勤務日である。林と郁子が出来ているという噂を聞いて以来、林田も郁子争奪戦に参加しており、厨房の丸山を含め三つ巴ということになる。林田はとにかく気が多く、しかもけっこう女にもてるのである。
相沢はこれまで何人もの友人に出会ったが、この種のタイプは初めてだった。相沢はけっしてガリ勉ではないし、友人もどちらかと言えばナンパな人間が多い。それでも女にスケベ話をしながら近づき、嫌われもせず、いつの間にか女の懐に入ってしまう特技を持つ林田のような男は皆無だった。
羨ましくもあり、だからといってすぐに真似のできるものでもない。しかし、相沢も林田の影響を受け、少しずつその人格が変りつつあったのだ。
先週のことである。本部に帰っての昼休み、社員食堂で昔の部下の女達と一緒に食事をした。相沢のヤクザに向こうを張っての武勇伝が洩れ伝わっており、誰もがその話を聞きたがった。相沢は面白おかしく話を脚色し皆を笑わせた。腹をかかえて笑いころげる女どもを見ているうちに、ついつい調子に乗ってきた。
林田がいつもやっているジョークの練習をしようと思いついたのだ。先日もこのジョークで喫茶店の新人ウエイトレスを笑わせ、以来気安く話せるようになった。ジョークは人と人との垣根を取り除くようだ。ようやく笑いがおさまり、一人の女子社員がおべんちゃらを言う。
「課長って、ぼーっとしているようでも、けっこうやる気になると凄いって聞いていましたけど、本当ですね」
よし、チャンス到来である。相沢はが待っていましたとばかり口を開いた。
「おー、いいこと言うじゃないか。ほら、ちゅーしてやっから、こっちさ来い」
いやーなどと黄色い声が食堂中に響いたが、臆することもなく相沢は続けた。
「ただのちゅーじゃないよ。ねっとりベロ入り」
ここで更なる笑い声を期待したが、シーンと静まり返った。しまったと思ったが後の祭りである。最年長のお局様が、「さて、そろそろ……」などと言いながら腰を浮かせ、続いて女どもが立ち上がった。
この話を林田に話すと大笑いで、曰く、感性豊かな女は卑猥な言葉の裏に秘められた人間臭さに感応するのだという。従って、自ら感性を磨き、相手がその手合いか否か見極められるようにならないといけないのだそうだ。大層なもの言いだが、ようするに気取っ女など、糞っ食らえということらしい。相沢もその意見には賛成である。
事務所で仕事を片付け、ふらふらと風呂場に入って行くと、上田が洗面台を磨いている。一昨日のショックからようやく立ち直ったようで、口笛なぞ吹いている。相沢が、よっと声を掛けると、元気良く挨拶した。
「課長、おはようございます。今日は日曜の晩だし、お客も少ないですねー。そういえば林田さんも言っていましたげど、今日は何事も起こらないと思いますよ。だって、誰だって仕事が終わったら一目散で家に帰りますもんね。こんな所に泊まるわけないですから」
少し違っているが、林田の言葉をそのまま繰り返して同意を求める。うんうんと頷いてそのまま階段を上がった。
今日は風呂場チーフの岩井が早番で帰ったので、上田も心細いのだ。まして、岩井は入ったばかりの上田に、研修だとか何とか言って、絆創膏の客の応対をさせた。上田は腰を抜かさんばかりの現実に遭遇したのだ。見ると、上田の後姿がどこか不安げだ。
大広間の中を覗くと副支配人の鎌田がウエイターよろしく注文品をお盆にのせて運んでいる。客は少なく、隅でお喋りに興じるオバちゃんたちを働かせるのが自分の仕事だというのに、何か勘違いしてんじゃねえか、と心の中で毒づいた。
そのことを何度も注意しているが、そのたびに現場を知らない相沢の弱点を突き、ましてオバちゃん連中は率先垂範を示さなければ付いてこないなどと反論する。ちょっと違うんじゃねんか実態は、と首を傾げた。
それから映画館に入った。映画は寝転びベッドに横になって鑑賞する。勿論、夜ともなるとここも男子専用の仮眠所に様変わりするのだが、林田に言わせると、一段高い女性専用スペースを覗くと、しばしば女性のあられもない下半身が映画の光に照らされ浮かびあがると言う。
今日こそと思い、相沢は横になってチャンスを窺った。林田はうつ伏せに寝るフリをして覗くのだそうだ。相沢は何度も寝返りをうつが、プライドが邪魔をしてうつ伏せの位置で首を上げることが出来ない。しかたなく、横眠りで目が白目になるほど視線を上げた。
歪んだ視覚がようやく一人の女を捉えた。
なんのことはない。女は白いタオルケットで足首まですっぽりとくるまり、太股なぞ見えやしない。ふと、女がしゃくり上げているのに気付いた。目一杯首を持ち上げてよく見ると、久美子である。
古い恋愛映画だが、それに感動しているのだ。ここぞと感動を煽り、涙を誘うテーマ曲。久美子がタオルケットを引っ張って、顔にあてがい涙を拭う。その拍子に、形の良いふくらはぎとそれに続く太股が顕になった。極彩色の光がその白い肌を染める。久美子がまたしてもしゃくり上げる。相沢はあまりの可愛さに思わず見惚れた。
久美子に気付かれぬよう映画館を抜け出した。そしてようやく思い当たった。林田が急遽泊まると言い出したのは久美子が泊まるからだ。郁子を狙っていると皆の前で言ってはいても、妻帯者の林田に勝ち目はない。単に場を盛り上げているだけなのかもしれない。
ゲームセンターに入って行くと、その林田が宇宙戦争ゲームのボックスの中で機械を操縦している。斜めに傾いた入り口を開け、相沢も中に入って画面に見入った。レーザー砲を発射しながら、レバーを操縦して相手の撃ちだす弾を避けるのだが、ついに被弾してボックスはがたがたと振動しながら墜落した。
「やられちゃいましたね、課長。いいところまでいったのに」
相沢が笑っていると、林田はいつになく無表情な顔で続けた。
「ところで、課長は明日何か予定あります?今晩の勤めが終わったら、暇ですか?」
いよいよ飲みに誘ってくれる気になったかと思い、相沢はすぐさま頷いた。
「ああ、暇、暇、暇を持て余している。全然予定ない」
それを聞いて、林田はちょっとがっかりした様子で言った。
「実は、今日、久美子がここに泊まるんですよ。久美子からお誘いがあったもんだから、嬉しくって急遽泊まり番して、明日二人して遊びに行こうと思っていたわけです、女房には内緒で…」
相沢はちょっと話が違うと思い怪訝な顔で聞いた。
「で?」
「俺は内心うきうきしてたわけですけど、久美子が課長も誘えっていうもんだから、なんか、こう、冷水を浴びせられたみたいで…」
相沢にしてみれば、林田の誘い方のほうがむしろ自分に冷水を浴びせているようで納得いかなかったし、思わずむっとしたが、林田はそれにも気付かず続けた。
「とはいえ…惚れた弱みであいつには逆らえないし、じゃあ、そういうことで、明日、ご一緒しましょう」
まさにとぼとぼといった表現がぴったりな歩きでその場を離れたが、ふと立ち止まり呟く。
「でも、俺、止めようかな、だってあのジャガーの助手席は絶対課長を座らせるだろうし、なんか、付け足しみてえで、俺、惨め。かといって、久しぶりにデートもしたいし…」
林田は揺れる心を持て余し、ハムレットよろしく悩んでいる。相沢は林田の落ち込みようを目のあたりにして、気の毒な気がして断るつもりになっていたが、林田の結論のほうが少し早かった。
「まあ、課長は独身だし、優先権を尊重すっか。ジャガーの中で恋の鞘当でもして遊びましょう、じゃあ、明日」
今度はきっぱりと歩き出した。林田は今日、深夜喫茶のマスターを引き受けてくれたのだ。相沢は林田の後姿に語りかけた。
「動機はどもかく、深夜喫茶を引き受けてくれて感謝してるよ、でも、恋路は別だ。僕も今日、久美子を可愛いと思ったんだ」
相沢の脳裏に久美子のむっちりとした太股が蘇る。果たして恋心と欲情はいっしょなのか否か。いつか林田に聞いてみようと思った。林田なら明確な答えを用意しているだろう。
その後、喫茶で久美子と林田がビールを飲みながら談笑しているのを見たが、何となく近づけず、遠くから眺めた。全ては明日だ。何かが始まろうとしているのか、或いは何も起こりはしないのか?全てが明日決まる。そう思ってその場を後にした。
事務所に戻り、書きかけのレポートを仕上げた。既に0時をまわり、皆の言った通り何事もなく時間は過ぎていった。しばらくして警官の山ちゃんと石橋が立ち寄り、二人とコーヒーを飲みながら談笑していた。
相沢はすっかり安心しきっていた。まして頼りがいのある警官二人がいることも、明日デートすることも相沢をうきうきとさせていた。喫茶店を抜け出して林田もやってきた。久美子はもう寝たのだろう。
警官二人を少しでも長居させようと、林田が冗談を連発する。笑いが部屋中に響く。にこにこと相沢も遅ればせながら笑い顔を作り、上の空で笑い声をあげた。平和な夜、明日はデート。なにもかも順調だった。
と、突然ドアが開いた。見ると血相を変えた上田が口をパクパクさせている。部屋の全員が上田を注視する。ようやく上田の口から声が響いた。
「課長、大変です。大勢で押しかけて来ました。モンモンしょってます」
相沢は血の気が失せるという感覚を初めて味わった。立ち上がりかけたが膝に力が入らない。それでも気力を振り絞り立ち上がった。そしてぽつりと聞いた。
「大勢で押しかけたって、何人くらいだ?全員がモンモンしょってるって?」
上田が、うろたえて答える。
「いえ、そうじゃなくて、大勢は大勢なんですが、モンモンしょってるのは一人だけです」
ふっと肩の荷がおりた。大勢で、しかも全員刺青入れていたら、まさに嫌がらせか殴り込みだ。そうでないと分かっただけでもめっけもんである。にわかに足に力が湧いてくる。
立ち上がろうとする山ちゃんと石橋を手で制し、上田と連れ立って事務所を出た。少し後に林田がついて来る。風呂場と事務所の連絡係である。
ロッカー室に入ってゆくと、なるほどあちこちに目つきの鋭い男達がたむろし、入ってきた相沢等を睨みすえる。どの男達も刺青はしていない。抵抗しつつも上田に背中を押されるものだから、男達の間を通り抜け問題の場所に到着した。
ザ・ヤクザといった顔つきの男が二人、二列のロッカーの入り口で相沢を待ち受けていた。一人が「野郎…」と口にした。と同時に、奥の方から大きな怒鳴り声が聞こえてきた。
「おい、今の失礼な男を呼んで来い。我慢にもほどがある。奴の態度はゆるせん。おい誰か、さっきの男を連れて来い」
上田は「ひー」と言ったきり、相沢の背広をひっつかんだまま背中に顔を押し付けている。あの失礼な男とは上田のことなのだ。二人の男の背後を覗くと、太った大男が背中にタオルを掛け、男達にマッサージをさせている。そのタオルの下から紛れもなく刺青が露出していた。
声を掛けようにも、二人の男が遮るように立っており、近づくことも出来ない。太った男が振り向いた。かっと目を見開き、またしても怒鳴り声をあげる。
「おい、お前だろう、そこのふんぞり返っている男の陰にいるのは。さっき失礼な態度をとったのは、お前だろう」
相沢は別にふんぞり返っているわけではなく、背中を押されるものだから胸を反らせて押し返しているだけなのだ。男が立ち上がった。のっしのっしと近づいてくる。その大きさに思わず相沢はたじろいだ。相沢も背は大きい方だが、その相沢が見上げるほどの大男なのだ。その大男は二人の男を掻き分け前に出た。そして再び怒鳴った。
「さっきから俺の顔をじろじろと見てやがって、俺に文句でもあるのか?えっ、何とか言え、この野郎。言いたいことがあるんだろう?はっきり言ったらどうなんだ」
上田の「ひー」という声が震えている。それほど迫力のあるドスの効いた怒鳴り声である。これが合図となって散り散りに佇んでいた男達が集まってきた。二人は完全に取り囲まれた。中から二番手らしき男が前にでて、低い声で言った。
「親分が怒っていなさるのも、ちゃんとした理由がある。そいつのせいだ。人をじろじろ見るなんて、だいたい失敬だろう。誰だって決していい気持はしないぜ、そうだろう?」
相沢は首を傾げた。どうも変だ、皆、妙に理屈っぽい。ましてヤクザにしては言葉が丁寧すぎるのだ。親分さんが怒鳴りながら相沢達に詰め寄る。
「俺の何が気に入らないのか知らないが、文句があるんなら、やってもいいんだぞ。やっか?やるんなら、相手になっぞ、えっ、どうなんだ、やんのか、やんねえのか?」
相手はこちらの失礼な態度に抗議していることを強調している。上田にしてみれば、タオルケットで隠した刺青を確認しようと思っただけなのだ。その行為を失礼だとか何とか言って、居直るつもりなのだろう。そうは問屋が卸すかと、相沢も覚悟を決めた。
親分さんは相沢に顔を近づけるだけ近づけ怒鳴り散らし、因縁をつけているのではなく接客態度の悪さに抗議しているのだと強調する。一方その脇で一人の若者が殺気立った顔で唸り声をあげている。その顔はまさに般若の面そっくりだ。二番手らしい男が、そいつを手で制しながら言った。
「こういうのを押さえるのも大変なんだ。血気に逸って何をしでかすか分かったもんじゃねえ。こいつは2年前、酔っ払いを半殺しにして、つい最近出所したばかりだ、おい、我慢しろ、我慢するんだ、バカ野郎、相手は素人だ」
二人の迫真の演技にみとれつつ、いや、そうもしていられないと慌てて相沢は頭を下げた。
「申し訳ございません。失礼があったみたいで、心からお詫びいたします」
と言った途端、親分さんの怒鳴り声だ。
「みたいで、とはなんだ、みたいでとは?こいつの失礼な行為は実際にあったんだ。みたいではなく、失礼な行為があったことを、と言い直せ」
随分言葉に神経質な人だとは思ったが、確かにその通りだと思い訂正した。
「分かりました、言い直します。大変失礼を致しまして申し訳ございませんでした。ですが、皆様も入り口の大きな看板を見てご承知とは思いますが、刺青のあるお客様はご入場出来ないことになっておりまして…」
ここで親分さんに話の腰を折られた。
「まてまて、なんでもかんでも一緒くたんにするな。それは別の問題だ。その前に、お前、言ったよな、失礼があったって。俺達、極道の世界じゃ、こういう場合は、きっちりと落とし前をつけなければ納まらない。ヤクザなら小指をばっさりとやれば済む。どうだ、お前もそうすっか?」
「滅相もございません。私はカタギです、ヤクザと同じと言う訳にはまいりません」
「馬鹿野郎、それが甘いって言っているんだ。お前の部下の行為は俺達の神聖な世界に土足で踏み込んだも同然なんだ」
「いえいえ違います。親分さんがたまたまお客さんとして入ってきた。うちの社員が親分さんの刺青を確認しようと目を凝らした。これは社員として当たり前のことです。失礼な態度と親分さんは思ったかもしれませんが、カタギの聖域に土足で入ってきたのは親分さんじゃありませんか?」
「お前は、大きな勘違いをしている。いいか、俺達は料金をきちっと払い、カタギとして入ってきた。カタギの聖域に土足で踏み込んだ訳じゃない。だけど俺達は見た目がカタギじゃない、まさにヤクザだ。そのヤクザと知っていながらこの男は失礼を働いた。つまり土足で俺達の聖域に踏み込んだと言うのはそういう訳だ」
おいおい、何だ何だ、この屁理屈は。相沢は頭が痛くなった。一瞬ひるんだ隙に、親分さんが決め付けた。
「つまりだ、カタギがヤクザに接する時の不文律、波風を立てないと言う不文律をカタギの方から破った。ってことは責任はお前達にある。従って、今晩は泊めてもらう。それを認めることがお前達の責任の取り方だ」
「冗談じゃありません。さっきも言ったとおり、玄関に二つも大きな看板があった。そこには刺青の方は入場できませんと書いてあったはずです。見なかったとは言わせませんよ」
相沢のもの言いに取り囲んでいた男達は激昂し、罵声を浴びせながらにじり寄る。例の若者は今にも飛び掛らんばかりの勢いだ。親分さんは皆を見回し、尋ねた。
「おい、そんな看板あったか?」
皆口々に気がつかなかったなどと白々しく口を揃える。なかには外人よろしく首をすくめ、両掌を上に向け小首を傾げる者までいる。「ヤクザには似合わねえー」と怒鳴ってやりたかった。だいたい縦横1メートルもある看板が目に入らぬはずがない。
「惚けるのもいい加減にして下さい。あれが目に入らないわけないじゃないですか。貴方達は目を何処につけているのですか」
ここで親分さんが切れた。館内じゅうに聞こえるような声を発した。
「舐めんのもいい加減にしろ、この野郎。こう見えてもこの世界じゃ、ちっとは知られた人間だ。お前みたいな若造に舐められてたまるか。」
ロッカー室の入り口に林田が顔をだし、目で警官を呼ぶかどうか聞いている。相沢は首を僅かに左右に振る。そして林田が背後に合図を送る。それを見ていた親分さんが冷ややかに言った。
「そうか、随分威勢がいいと思ったら、警察を呼んでいるな。もう事務所に来ているんだろう、どうりで落ち着いていると思ったぜ」
図星をさされて驚いたが、そんなことおくびにも出さずに、こう言った。
「とにかく、お引取り頂けませんか?会社の決まりです。刺青の方はお断りしておりますので、どうか、ご理解下さい」
警官がいると相手も理解したことだし、これで騒ぎは納まると思ったのだ。しかし、この分さんに限ってこうした常識は通らなかったのである。親分さんの怒鳴り声が相沢の甘い期待を切り裂いた。
「おい、警官、マッポ、ポリス、出てきやがれ。お前に文句がある。出て来い、隠れていねえで出て来やがれ。こらー聞こえねえのか、出手て来いってんだ」
突然唸り声を上げていた若者が相沢に殴りかかった。唸り声をあげていたのは演技ではなかったのだ。こいつは本気だと思った。咄嗟に顔を左にかわすとパンチが右の頬を掠めた。
親分さんは更に声を張り上げた。
「出てきやがれ、今、うちの舎弟が暴力を振るったぞ。いいチャンスじゃねえか、出てきて逮捕しろ。聞こえねえのか?」
これまで越えたことのない一線を越えたことは確かだった。肌が粟立った。それでも相沢は負けじと親分さんと睨みあう。緊張で胸の鼓動が聞こえてきそうだ。その時、「失礼しまーす」と繰り返しながら林田が子分どもを掻き分け掻き分け親分に近づいてくる。そして言葉をかけたのだ。
「親分さん、あっちでコーヒーを用意しますんで、どうぞ場所を変えて…、いわゆるコーヒーブレイクってやつです。へへへへ…」
手もみして、にこにこと佇む林田を見て、親分さんも行く気になったようだ。パンツ一丁で凄むのも調子がでないのだろう。「よし、行くか」と言う親分の一言で、みなぞろぞろとロッカーに戻って着替え始めた。相沢が林田に耳打ちする。
「子分はそっちで面倒見てくれ。喫茶店がいい。親分は例の個室に連れてゆく。一緒だとうるさい。それから一番若いのには気をつけたほうがいいぞ。さっき本気で殴りかかってきた。俺が空手3級の腕前じゃなかったら、避け切れなかったろう」
林田は肘で相沢の脇を突っつきながら言った。
「課長、もし課長が黒帯だったら、その冗談…、もっと落ち着いて言えたんじゃねえの」
言われてみて初めて気がついた。喉がからからに渇いて、ほとんど唾がなくなっている。相当緊張していたのであ。
テキヤNo2
林田が子分どもを喫茶店に連れ込んだ。相沢は親分さんを本部長の個室に案内する。ちらりと事務所を覗くと副支配人の鎌田が警官たちとなにやら話しこんでいる。部屋を覗いた相沢に気付いているはずなのに顔を向けようともしない。ちょっと意地悪がしたくなった。いつだって肝心な時にいないのだから。鎌田に声を掛けた。
「鎌田さん、コーヒー二つ持ってきてください」
初めて気付いた素振りで「は、はい」と答える。
個室に入ると、親分さんは応接にでんと腰掛け、目顔で座れと言っている。そこは俺の寝床だぞ、と思いながら腰を落とす。親分さんはにこっと笑って言う。
「ちらっと見たら、案の定警官を呼んでいるんじゃねえか。しらばっくれやがって」
「勘違いしないで下さい。別に呼んだわけじゃなくて、最初からいたんです。ここは警官立ち寄り所になっていますから、夜一度は来ます。別にしらばっくれていたわけじゃありません」
「ふん、国家権力に守られていい気なもんだぜ。警官が隣にいるから安心ってわけか。だけどよ、俺がその気になれば、お前の首根っこをポキって折るなんざ、あっと言う間だ。どうする、あいつらがこの部屋に来る前にそうしたら、どうする?」
思わず親分さんのグローブのような手に見入った。脅し文句だと分かっていても、一瞬恐怖がよぎる。ええいやけくそだ、とばかり口を開いた。
「出来るなら、やってみたらどうですか」
親分さんはしばらく睨んでいたが突如怒鳴った。
「人に厭な思いをさせておいて、その言い草は何だ。もんもんしょっているからって、人を見下した態度をとったり、軽蔑したりする権利がお前にあるのか、えっ、どうなんだ」
そこへ、鎌田がコーヒーを運んできた。両の手に一つづつ、コーヒー皿を指先でつまんで入ってくる。皿とカップがかちゃかちゃと音をたてている。手が震えているのだ。コーヒーはこぼれ放題でカップが皿に浮いているみたいだ。親分さんはにやりとして言う。
「お兄ちゃんよ、随分騒がしく入ってきたのはいいけど、両手ふさがってちゃ、砂糖を運んでくるわけにはいかなかったわけだ」
「い、い、今すぐお持ちします」
鎌田は、喫茶店に子分どもがうじゃうじゃいるので、事務所のコーヒーを持ってきたのだ。喫茶店からだったらお盆にひと揃えを載せて来られたのだし、醜態を見せずに済んだはずなのだ。
鎌田はシュガーポットをテーブルの上に置いて、逃げるように部屋を出た。
親分さんはスプーンに山盛り3杯ばかり砂糖をいれた。相沢は、コーヒーカップに手を伸ばし、おもむろに口元に運ぶ。震えていたら相手に見くびられる。腕の関節がぎくしゃくと音をたてているように感じたが、何とかやりおおせた。
「砂糖はいいのかい?」
「ええ、僕はブラック党ですから」
本当を言えば、砂糖なしのコーヒーなんて飲めたもんじゃない。でも、砂糖を入れようとすれば、スプーンの長い柄に震えが伝わりテーブルいっぱいに砂糖を撒き散らすに決まっている。鎌田を笑えるわけもない。親分さんがせせら笑う。ばれたかと思ったが、しらんぷりを決め込んで、もう一度、コヒーに手を伸ばす。親分がじっと見つめながら言う。
「俺はなあ、60年安保の時代の成れの果てなんだ。何度も豚箱に放り込まれた」
ずるずるとコーヒーをすすり、ゆっくりと喉に流し込む。そして腕を伸ばし慎重にカップをテーブルに置く。今度もうまくいったとほくそ笑む。ふと、聞き流していた親分の言葉が蘇り、「何だって、60年安保だって?お前、ヤクザだろう?」と心の中でつぶやき、まじまじとその顔を凝視した。
「そんな俺を雇う企業なんてありゃあしねえ。しかたなくこの商売に入った。刺青だって、いい場所取るためには有利だって勧めてくれる人がいて、気はすすまなかったけど、生きてゆくためにはしかたなかったんだ」
相沢が目をまん丸にして聞いた。
「親分さん、60年安保やってたってことは、大学卒ですか?」
「馬鹿野郎、大学卒業してたらもっといい商売やってる。中卒だ、悪いか?えっ、中卒だと言って、また俺を馬鹿にする気か?」
「いえいえ、そんな滅相もない……」
「お袋は背中を見て泣いたっけ。こんな男に育てたつもりはないって。だけどよー、これを入れなかったら食べていけなかった。そのお袋も、今じゃ贅沢させてもらって俺に感謝している。この刺青にはそういう過去があるんだ。お前みたいな若造には分からない歴史ってもんがあるんだ」
「勿論、人それぞれいろいろな事情があるのは分かっていますよ。でも、そういう事情をいちいち聞いていたら、こういう施設は刺青だらけになってしまうんです。きっぱりと一線を画してシャットアウトしないと食い物にされてしまうんです」
「何にー、食い物だ。俺が食い物にしに来たっていうのか?」
「そういう揚げ足取りは止めにしましょう。親分さんは、話せば分かる方だと思ったから、こうしてお話しているんですから」
話せば分かる人というおだてに乗ったのか、急にしんみりとした表情になった。
「そうだよな、俺たちみたいな善良なテキヤばかりじゃないからな。そうそう、この辺だと鯨井っていう博徒がいた。確かにあいつに食い物にされたら大変だ」
と言って、微笑みかけた。やっと真心が通じたなどとは思わなかったが、子供のような笑顔に思わず心が和んだ。親分さんが続ける。
「警察とは懇意にしておいた方がいいぞ。何かの時に役に立つ。俺だってしょっちゅう地元の警察には顔を出すんだ。それが、また、好きな奴が多くてよ、地方の地酒なんて持って行くと、昼間っから酒盛りだ」
「へー、そうなんですか」
「ああ、あいつらはけっこうストレスがたまっている。だから呑み助が多いのさ。たまには何か持って挨拶に行っているか?」
「ええ、たまには手みやげさげて挨拶には行きますよ。世話になることも多いですから」
これが親分の手だった。怒鳴り声がはじけた。
「何だと、今、何て言った。恥を知れ、この野郎、お前は公務員を酒で買収しているって言ったな?酒ってことはビール券も含まれる。つまり現ナマと一緒だ。それこそ贈賄じゃねえか。そんなことが許されると思っているのか。そんな野郎が、刺青は反社会的だと非難する。公務員を買収するのとどっちが反社会的だと言うんだ、答えろ、答えてみろ。贈賄、収賄が当たり前のように行われ、善良な市民を苦しめる。こんなことが許されていいと思っているのか?」
「???」
何だ何だ、相沢は頭が混乱してきた。まるでこっちが悪いことをしているような口振りだ。その言葉はほんの少しだけ痛いところ突いている。確かにビール券を持参して挨拶に行っているのだ。そんなこと口に出してはいないが、相手はお見通しなのだ。
突然もう一人、ヤクザがドアを開けて入ってきた。ぎょっとして見詰める相沢に名乗った。
「マルボウの中村だ。」
つかさず、親分さんに鋭い視線を投げかけた。
「氏家親分、舎弟から名前は聞いたよ。まあ、そう興奮しなさんな。血圧が上がるぜ。薬、飲んでいるんだろう、血圧を下げる薬」
苦みばしった顔を半分相沢に向け、
「あんた、もう出て行ってもいいよ、俺が話す」
と、顎で指図する。これが警官?相沢はマルボウという言葉を反芻した。暴力団員専門の警察官だ。どっちがヤクザか見まごうばかりなのである。パンチパーマに金のブレスレット、裸にすればたぶんネックレスも、長身の相沢が見上げるばかりの大男、しかも顎には傷痕まである。
「よろしいので…?」
相沢は遠慮がちに言った。早く出て行けと言わんばかりに、またしても顎で指図する。相沢は心のうちでほくそ笑み、深く頭を下げてドアを出た。
ドアの外から聞き耳をたてる。中村の凄む声が響く。なかなかやる、と思って頼もしく思っていたが、更に凄みのある声が覆いかぶさる。次は何を言っているのか聞き取れない。突然親分さんの怒声がドアを揺るがせた。
「貴様、それでも警官か?貴様は、そうやって有りもしない犯罪をでっち上げ、罪もない人間を陥れていたってことだ。そうやって、無実の人間を何人刑務所にぶっこんだ?えっ言ってみろ、言えってんだ、この野郎。事と次第によっちゃあ、マスコミにぶちまけてやる。声のでかい奴はみんな脅迫罪でぶっこんでやるだって?そんな理不尽があるか?もともと声のでかい俺は、それだけで刑務所にぶち込むってか?」
「バカ野郎、俺はただ、大声で人を脅せば脅迫罪にあたるって言っただけだ」
「いや貴様はその後でこうも付け加えたじゃねえか。俺に逆らえば痛い目にあうってな。ってことは、何の罪もない俺をその舌先三寸で罪に落そうってことだ」
「言いがかりはよせ、この野郎、そんなつもりで言ったわけじゃねえ」
このやりとりがしばらく続き、その後、急に声を落してぼそぼそという声、しばらくしてまたしても親分さんのどなり声、これが何度も繰り返えされた。そして声がやんだ。ドアに耳をあててみると、話してはいるらしいのだ。だが声は殆ど聞こえない。
マルボウの中村が「それはない、それはない」と応じている。ぼそぼそと言う親分の声。「あるわけないだろう」と答える中村。そして沈黙、せせら笑う親分。
突然、ドアが開き、中村が出てきて、困ったような顔をして相沢に聞いた。
「あんた、酒やビール券持って警察に行ったなんて、本当に言ったの?」
「いや、言ってません。あいつが勝手にそう言っているだけです」
「困るんだよな、そういうこと言ってもらうと」
「だから、言ってませんて」
「分かった、分かった、まったく嫌な野郎だ。ほんとか嘘かうちの署長のことも色々知っててよ、明日、挨拶に寄るなんて言いやがって、嘘に決まってるだろうが。ったく」
中村は一瞬肩を落としてドアの向こうに消えた。
ふと、喫茶店を見ると缶ビール片手に子分どもが思い思い、床に寝ころんだり、椅子にもたれたり、皆、だれた雰囲気で親分さんを待っている。中には絨毯の上で、ジャンパーを枕代わり本格的に寝ている奴もいる。
驚いたことに林田と例の二番手が円柱に寄りかかり談笑している。随分と親しげな様子である。林田が冗談でも言ったのか、二番手がげらげらと笑った。仲間に入れてもらおうと相沢が近づいてゆくと、林田が声をかけてきた。
「課長、駄目みたいよ。あの人、国家権力に噛みつくのが趣味なんだって。このあいだも名古屋の警察で朝までやったそうです」
二番手も苦笑いしながら口を添える。
「まあ、覚悟すんだな。あれ、朝までやる気だ。まいったなー、疲れているのに」
しばらくして、中村が出てきたが、その顔は泣く一歩手前だ。ドアの前で地団太踏んでいる。急いで近づくと、すがるような視線を向けて言う。
「どうだろ、泊めてやるわけにはいかんか?」
「だめですよ、そんなこと出来ませんて、頼みますよ」
嫌がる中村をもう一度頑張るよう説得し、ドアの向こうへ追いやった。どう考えても、親分さんの方が一枚も二枚も上手だ。敵うわけもない。だとすれば朝まで付き合うことになる。マルボウの中村と交代することも覚悟した。
どれほど時間が経ったのだろう。円柱の横で寝ころんでいる自分に気付いた。妙な音がするので、上を見上げると林田が柱に立ったまま寄りかかり鼾をかいている。一瞬、今という時が理解できなかったが、すぐに現実を思い出した。
見回すと、誰もが諦めてそこここで身体を休めている。鼾もあちこちから響いてきた。深夜喫茶はヤクザで埋め尽くされ、カウンターの奥でハルさんが何事もなかったように洗い物にせいをだしている。
と、マルボウの中村が個室のドアから顔を出した。きょろきょろして、ようやく相沢を見つけて手招きしている。
「相沢さんよ、ちょっと」
相沢がおもむろに立ち上がり、首を鳴らしながら近づいてゆくと、背広の裾をつかんで陰に連れて行く。そして小声で言う。
「あいつら、この3日、トラックの下で寝てたんだと。それがこの雨だろう、可哀そうだと思わないか。子分どもを畳の上で寝せてあげたいんだとよ。ここに泊まったなんて絶対に口外しないし、風呂は子分だけでも入らせてくれって言ってる。どうだろ、あんたの権限で泊めてはくれないだろうか」
「……」
「約束は絶対に守らせる。それは俺が誓わせた。間違いなく、あいつは信用できる」
ヤクザな容貌とは裏腹な人の良さがその眼(まなこ)に滲み出る。すがるような目つきで相沢の答えをまっている。腰をかがめて視線を相沢の高さに合わせている。相沢もこの二人のヤクザ者を信用することにした。
「わかりました、お二人を信用します」
「恩にきる」
しばらくして、親分さんが、中村の背中から顔を覗かせ、ばつの悪そうに笑った。そして、のろのろと寄ってくる子分どもに声をかけた。
「課長さんが、二階の小宴会場に寝床を用意してくれるそうだ。目立たねえように風呂に入ってから、そこで寝ろ。俺は先に寝ている」
子分どもは一目散でふろ場に駆け込んだ。相沢は親分さんを小宴会場に案内した。鎌田と林田がマットとタオルケットを準備していた。親分が声をかける。
「おい、敷くことはねえ。その辺に散ばしておいてくれ。後は自分たちでやる」
林田が応酬する。
「いえいえ、親分さん、客商売ですから、そんな訳にもまいりませんよ。最後までやらしてください」
人数分を敷いて、林田と鎌田が出ていった。親分が言う。
「お前にも、なかなか良い子分がいるじゃねえか」
「ええ、私もそう思っています」
「それはそうと、ずいぶん迷惑かけたな。明日は誰も見ていない時間に出て行く。泊まったなんて誰にも言わねえ。心配すんな。…もう、行ってくれ」
「風呂の件は申し訳ございませんでした。前例を作るわけにはいかなかったものですから」
「ああ、そうなると思って子分どもに濡れタオルを持ってこさせて体は拭いた。さっぱりしている。さあ、行ってくれ。もう、眠る」
相沢は、どうも、と言って部屋を後にした。
小一時間ほどして、見回りに出た。奥まった小宴会場は襖もぴったりと閉められ、静かに寝静まっている。親分さんも畳の上で寝たかったのだ。前例をつくってしまったことは悔やまれるが、向井支配人はわかってくれるはずだ。相沢の決断に、にこにこと相槌をうってくれるあの大きな顔を想像して、苦笑いを浮かべた。
おいっと、呼ぶ声がした。振り返ると、唸り声の若者が、人気のないバーのカウンターで缶ビールを飲んでいる。相沢はバーに入っていって若者の隣の椅子に腰かけた。若者が口を開く。
「さっきは悪かったな」
「ええ、本気なんでびっくりしました」
「馬鹿言え、本気ならはずさねえよ。どうも、俺はおめえみたいなエリートをみると虫酸が走るんだ」
「いや、エリートなんて、とんでもない。こんな風呂屋に回されたんですから、とてもエリートだなんて…」
相沢は会社でエリートの地位から落とされたことを言ったのだ。自分を卑下したつもりが、この若者にとって傲慢以外何ものでもなかった。
「エリートじゃねえか。こんなすっげえ建物で、バーがあって映画館があって、ゲームセンターまである。その責任者なんだから、エリート中のエリートじゃねえか。何がエリートじゃねえだ、この野郎」
若者は怒りを露わにし、さっと席を立った。
とぼとぼと事務所に戻った。林田は机に、鎌田は床に、それぞれマットを敷いて眠っていた。二人とも往復の鼾をかいている。ふと、若者の怒りの言葉を思い出して赤面した。何と馬鹿なことを言ってしまったのか。
二度と会うことのない人々。だけど互いに濃密な時間を共有した。何か運命的な出会いだったのではないかと思う。親分さんとあの若者に明日、声を掛けたいと心底思った。せめて見送ろう。そう決心して、郁子に6時に起こすよう頼んで、個室にはいった。
朝、郁子に起こされ、いの一番に連中のことを問うと、既に出ていったと言う。相沢はため息をつき、ゆっくりと立ち上がった。行ってみると小宴会場はもぬけの殻で、マットとタオルケットが部屋の片隅にきれいに積み上げられていた。
第八章 暴走族
疾走するジャガーも、さして車に興味のない相沢にとっては走る揺り籠以上のものではなく、ひたすら助手席で鼾をかいて眠っていた。親分さんの騒動がおさまったのは午前2時、相沢が眠りについたのは3時、睡眠時間はたった3時間である。
林田に手を引かれるようにして駐車場へ行くと、久美子は既にアクセルをふかせ、待っていた。当然後ろの席だろうと思いドアに手をかけると、林田が背中を押して助手席をすすめた。久美子との挨拶もそこそこに倒れるように席に着いたのだ。
久美子はバックミラーで林田の様子を窺う。相沢が寝付く寸前まで、林田は興奮をした様子で昨夜の事件について喋りまくっていた。それが、相沢が鼾をかきはじめた途端、むっつりと黙りこくり小一時間ほど外を眺めたままだ。久美子が問う。
「ねえ、何を考え込んでいるの?いつもの林田君じゃないみたい」
「そんなことねえよ。お喋りな林田君もいれば、物静かな林田君だっているんだ。久美子には見せてねえ、俺の一面だ」
「へー、この20年間一度も見たことのない林田君の一面を今見ているんだ、感激」
「そういうこと。俺はついついお前のこととなると真剣に考え込んじゃう。いっぺんもやらして貰ってもいねえのに、馬鹿みてえだ」
「何いってるのよ、馬鹿言わないで」
「いいか、久美子、言っておくが、この人に期待しても無駄だぞ。この人はエリートだ。ちょっくら間違えて風呂屋になんか紛れ込んできたけど、いつかは元のねぐらに帰ってゆく」
「そんなこと期待なんかしてない」
「いや、期待している。期待してるからこそ誘ったんじゃねえか。でも、この人は駄目だ。そんな高望みすんな。それよっか、俺と結婚しよう」
「林田君は私の親友の旦那さん。結婚できるわけないでしょう」
「離婚だってありえる」
「馬鹿言ってんじゃないの。そんなこと出来るわけないじゃない、子供のこと考えたら。あんなに可愛がっているくせに」
「分かったよ、冗談、冗談。だけど、俺の結婚は、久美子とあいつの策略に引っ掛かっただけだ。あの時、久美子が一緒だったら、あんな間違いは犯さなかった」
「何言ってるのよ。男女を結びつけるのは、縁、そう縁なのよ。それにあの時は、親友の三重ちゃんに頼まれたんだもの」
「俺は久美子が行くって言うから、上司の嫌味をくぐり抜け、有給休暇をとったんだぞ。久美子が行かないと知っていれば絶対行かなかった」
「でも、やっちゃったんじゃない」
「こりゃ、嫁入り前の女が、やったなんてぬかすんじゃねえ。そりゃ、俺も男だ。わいわいがやがやみんなで楽しく酒飲んで、ふと気がつけば三重と二人きり、浴衣姿が艶めかしく、まして、ましてだよ、ぽろんと乳を出されてみな、男なら、誰だって、ついつい吸いついちゃうもんなんだって」
「でも、やらない男だっていると思う」
「久美子は、まだそんなこと言っているんだから。生娘じゃあるまいし、そんな子供じみたこと言うなよ」
「あたしゃ、生娘だよ」
「えっ、今、何て言った、生娘?俺と離れてた大学時代、何やってたの?時代の風潮を感じなかったの?」
久美子が答えようとした時、相沢がもぞもぞと起き上がろうとした。シートベルトに引っ張られ、起き上がれず四苦八苦している。それを見て林田は背中をシートに倒した。久美子は今の会話を聞かれたのではないかと身を固くしていた。
相沢が大きなあくびをしながら口を開いた。
「林田君、俺、どのくらい寝ていたろう?」
「ええと、1時間半くらいかな、ねえ、久美子」
久美子はそれには答えず、運転しながらも相沢の様子を窺っている。
「そうか、1時間半、ようやく眠気がさめてきた。でも、林田君、昨日は、いや、今日か、また危ない所を助けてもらったね。あの場面で、林田君が現れてコーヒーブレイクにもっていかなかったら、あいつらにぼこぼこにされてた。久美子さん、この男は本当に頼りになるんだ。君はいい友達を持ってる」
「ふふ、それ、さっきも聞いたわ。でも、私もそう思っているの。この人、幼友達なんだけど、お兄さんみたいに感じることがあるもの」
「久美子、俺、お兄さんじゃいやだよ。せめて、セックスフレンドにしてくれよ」
相沢は大袈裟に笑って、この訳のわからない二人の関係に立ち入れぬもどかしさをもてあましたが、それでも、うきうきとした気分ではしゃいでいる自分を意識していた。
あたりに潮の匂いが漂い始めた。松林の向こうに海が見えてくると「おお」と男二人が同時にどよめく。そして海岸を左に見ながら疾走する。すでに海の家は閉じられ、サーファー達がうねりの強い波間に漂う姿がみられる。しばらく行くと海岸線は波に洗われる浜づたいの磯が続く。海に見ほれていた二人はいつの間にかイビキをかいて眠りこけている。久美子が目指すのはこの少し先の、いつも一人そこで一時海を眺める、人気のない小さな砂浜だった。
車は国道から離れ、海岸に続く道に入った。松林の前の高台に車を停め、久美子はまたしても眠りこける男どもを置き去りにして、人気のない砂浜を駆けた。ドアを思い切り閉めたのは相沢に目を覚ましてほしかったからだ。その思いは通じた。
相沢はふと目覚めた。窓越しに久美子が遠ざかって行くのが見える。心がざわめく。バックミラーで林田を窺うと往復のイビキをかいて熟睡している。意を決して外に出ると、久美子の残した足跡が海岸まで続いていた。相沢は歩きだした。坂を上りきると、久美子が浜辺に膝を抱えて座っているのが見える。潮風が久美子の前髪をなびかせた。
昨夜の久美子を思い出した。恋愛映画に涙する少女。そう、少女にしか見えなかった。瞳が濡れて、きらきらと光った。タオルケットを口にあてて声を押し殺した。それでも声は漏れ、しゃくりあげながら涙を拭う。
久美子は相沢が近づいてくるのに気付いている。でも、振り向こうともしない。相沢は久美子の横に腰をおろした。久美子の心の高鳴りが聞こえてきそうだった。相沢は林田と久美子のやりとりをすべて聞いていた。
「しかし、凄いスピードだったね。思わず足を踏ん張ってた。カーブだらけの海岸線を100キロで飛ばすなんて」
「あれでも、抑えたのよ、今日は。でも、カーブが多くなったのは、この付近に来てからだわ。足を踏ん張ってただけ?それとも私たちの会話を聞いてた?」
「どっちもだ」
「林田君に相沢さんを誘わせたのだから、私が相沢さんに興味がないと言ったら嘘になってしまう。でも、林田君が言うような期待なんか少しも持っていないわ。そうそう、林田君から、私の家のこと聞いてる?」
「大地主だって言っていた」
「ふーん、林田君はあのこと黙っていたんだ」
「あのことって?」
「父はあの辺の一帯の親分なの。吉野組って言うの。オープンしたての頃、うちの金子が出入りしたでしょう。名入れのマッチを売りに。でも、もう大丈夫、父に言ってあるから。手を出さないでって、周辺の親分さんたちにもよ」
「鯨井組ももう来ない?」
「ええ、駅前の飲み屋で飲んでても、後ろから襲われるなんてことないわ、安心して。それに鯨井なんてまだ駆け出しだもの」
相沢は予想だにしない話の展開に度肝を抜かれたが、心の動揺に気づかれまいと煙草をとりだした。ライターを点けようとするが、潮風が邪魔をする。カチンと音がして、見ると久美子がジッポを点火し、それを差し出していた。
煙草を大きく吸い込んだ。そして吐き出す。久美子は相沢から視線をはずし、水平線を見つめている。海鳥がカラスのような鳴き声をあげる。相沢は心の動揺を海鳥が笑っているように感じた。久美子が沈黙を破る。
「このパターンってすっごく多いの。打ち明けると、黙り込んで煙草に火をつけるの。煙草を持つ指が震えていた人もいたわ」
思わず自分の指先を見たが、震えてはいない。ふと、鎌田を思い出して思わず笑みが浮かぶ。久美子も微笑みながら相沢を見つめている。
「でも、それってよくわかる。テキヤといってもヤクザはヤクザ。サラリーマンやってる人が入れる世界じゃないもの。だから林田君がいっている期待なんか持つわけはないわ。ただ、なんて言うのかなぁ…」
久美子が言葉を探している。
「ただ…?」
「愛する心っていうか、それを大事にしたいなって。ふふ、でも、林田君には言っていないけど、私、婚約しているの。父の勧めで。だってしょうがないもの、家ってものが厳然と存在するんですもの」
相沢はこれを聞いて少し肩の荷がおりた。少し気になったので聞いた。
「婚約したって、やはり……」
しまったと思ったが後の祭りだ。やはりヤクザ?なんて馬鹿な質問だった。焦ってうろたえる相沢を見て、久美子が目をくりくりさせて答えた。
「そう、やはりヤクザ。ずっとうちにいる人で、お兄ちゃんって呼んでた。物静かで、読書家で、立派なテキヤ」
へーと言ったきり後が続かない。何か喋ろうとするのだが話題がでてこない。すると久美子が言った。
「相沢さん、バイク乗ったことある?」
「バイクかー、どうも剥き出しで走っているみたいで……」
「私も最初はそう思ってた。初めのうちは恐怖と闘いながら無理してスピードを上げていた。一瞬のミスは即死ですもの。でも、それは最初のうちだけ。しまいには恐怖が徐々に恍惚へと変わってゆくわ。」
「うーん、それって人にもよるんじゃないかな」
「ふふ、で、どうしてかなっていつも考えていた。その訳がようやく分かったの」
「どうしてなんだ?」
「しがらみを振り切るからよ。運命の赤い糸っていうけど、それ一本ではないし、まして赤ばかりでもないの。生まれる前から人々は沢山の糸、つまり縁で繋がっているんだと思う」
「つまり一瞬、スピードがそうした縁というしがらみを断ち切ってしまうというわけ?」
「そう、そこにいるのは孤高で純粋な魂だけの存在。いいえ、自分という個もけし飛んでしまう」
「でも、しがらみのない世界なんてありえない。人間はしがらみによって成り立っているみたいなところもある。僕の父と母のしがらみがなければ僕は存在していない」
「本当にそう思う。やっぱり結婚は人間関係の中で強い縁だと思う。どんなに愛していても縁がなければ結ばれない。でも、結ばれなくとも大切な縁だってあるかもしれない」
と言った途端、久美子は耳まで赤く染めた。久美子が泣いた映画は悲恋物語だった。自分の運命と重ね合わせているのだろう。愛おしさが胸元までせりあがる。とはいえ、相沢が映画の主人公になるわけにはいかない。ヤクザと婚約している女を奪う?馬鹿な。
ふと、視界の右端に林田が入り込んだ。相沢が言う。
「あれっ、林田があんなところで石投げてら。こっちに来ればいいのに。呼んであげよう」
「何いじけているのかしら、馬鹿みたい。もうちょっと放っておきましょう。そうそう、林田君と私って、男女関係という意味からいったら本当に縁がなかったと思う。林田君って、下品だってことを除けば、それなりにいい男だし、頭もいいし、ずっと一緒に遊んできたけど、そういう関係にはならなかった」
「うん、ありえる」
「林田君の部屋に遊びに行ったこともあった。もう少しでキスしそうになった。でも、私が避けたの。何故だか自分でも分からなかった。ある程度期待していったのに…」
「期待していたけど、覚悟が出来ていなかった?」
「ええ、その通り。林田君、吉野の家を継ぐ気はないって……、でも、一人娘が家を出るなんてできないもの。林田君はそれを期待してたみたいだけど……」
相沢は林田に嫉妬を覚えた。結ばれなくとも大切な縁だってある、とは林田のことを言っているのかもしれないと思ったのだ。少なくとも、それが相沢だとは一言も言ってはいない。相沢の思いを知ってか知らずか、久美子が言う。
「そろそろ、声をかけてあげようか、あんなに石を投げてたら肩がいかれちゃう。彼、甲子園には行けなかったけど、地区大会ではいいところまで行ったのよ、ピッチャーだったの」
こう言って、久美子が林田に声を張り上げた。相沢は、高校時代、サッカー部のキャプテンだったが地区予選で勝ち残ったためしもない。敗北感に打ちのめされた。にこにこと近寄ってくる林田が二倍にも三倍にも大きく見える。
「課長、そんな所にいたんですか、あれっ、久美子も一緒か、ちっとも気付かなかった」
そんなみえみえの言葉を吐くことに動じる林田ではないはずなのに、何故か恥じらいを見せた。そんな心の襞を覗かれまいと、林田はことさら大きな声で吠えた。
「久美子、車のキーくらい置いてけよ。残暑とはいえ、車の中は蒸し風呂だ。俺だって気きかせて、寝てるふりを決め込んでもよかったけど、あれじゃあ寝てられねえもの。クーラーかけてれば時間は稼げたはずだ。しかたなく、うぶな少年みたいに、石を投げるポーズをとるしかねえじゃねえか、まいったよ」
相沢と久美子は、傷付いた心さえジョークにしてしまう林田の強じんさに、思わずほほ笑みを交わした。相沢は、林田という男が、ほとほと一筋縄ではいかない人間であることを思い知らされたのである。
その日の帰り、夕食で飲んだビールが疲れた体を程よく酔わせ、二人の男はすっかり寝込んでしまった。従って、久美子が二台の暴走族の車に挟まれ、海岸に停車せざるを得なかった経緯など知るはずもない。
揺り起こされた二人は、久美子の必死の言葉を理解するのに多少時間を要した。とろとろ走る二台の車を追い越すと、それまでとはうって変わって爆音を響かせ追ってきたと言う。意図的にゆっくり走り、追い越させて難癖をつけるタカリの部類だろう。
林田が「俺に任せろ」と言って久美子の胸のサングラスを取ると車を出た。相沢も後に続く。ジャガーのライトは海に向けられている。月は雲間に隠れ、闇に慣れていない目には男達の姿もぼんやりとしか見えない。相沢が囁く。
「林田君、その濃いサングラスかけて、こんな真っ暗でも見えるの?」
「何にも見えねえ。真っ暗闇です。で、敵は何人です?」
「うーん四人みたいだ。おー、だんだんよく見えるようになった。みんな若い。見るからに暴走族。強そうなのは一人。後は足が細すぎる。けっ飛ばせば折れちゃいそうだ」
「よしきた、これからサングラスをとります」
「……?」
林田はゆっくりとサングラスをはずし、胸のポケットにねじ込む。ほの白く浮かぶ横顔は苦み走っている。ハリウッドのギャングスターみたいだ。相手はたじろいだ。女一人だと思っていたのに、出てきたのは頑丈そうな男二人、まして一人は胡散臭い。
しかし、相沢が強そうだと見込んだとおり、骨のありそうなその男が暴走族の誇りにかけて怒鳴った。
「その女に焼きを入れてやる。俺たちをコケにしやがって、その女を出せ、ふざけやがって。粋がると痛い目にあうぞ、この野郎」
林田が静かに応える。
「お嬢様は車の中でお化粧直ししていなさる。どうやらテメエ等、この辺の族じゃねえな。この辺の奴なら、このモスグリーンのジャガーの持ち主が誰なのか知らねえはずがねえ、謝るのなら今のうちだぞ。謝らねえと後で後悔することになる」
一瞬ひるんだが、その若者が叫ぶ。
「誰だか知らねえが、俺たちだって何のバックもなく族やってる訳じゃねえ。そんなクソ白々しい脅しが効くかよう」
林田の演出に何かわくわくさせるものがあり、ついつい調子に乗って相沢がこれを引き取る。
「笑わせるな。テメエ等みてえなガキを子分にするようなシケタ組なんざ、ヤクザとは言えないんだよ。おい、テメエ等のバックの名前を言ってみろ。えっ、駆け出しの鯨井組か、それとも鎌田組か?言ってみろ」
鯨井と聞いて若者が一瞬たじろいだ。相沢が調子に乗って嵩にかかる。
「そんなケチな組なんざ、こちとら目じゃねえんだよ。テメエ等みたいなジャコに粉をかけるサンシタ奴(やっこ)なんざ、指を詰めさせてやる」
と、小指を手前に曲げ、手の甲を相手に向けて振り回しながら怒鳴った。 かつて鯨井組に囲まれた情景を思い出しながらの迫真の演技である。これは効き目があった。若者が一歩後じさる。はあはあと息も荒く、ことの真偽を量りかねている。
それでも睨み続ける若者に業を煮やし「しょうがねえ」と言いつつ、背中の何かを掴むまねをして、ちらりと林田に目で合図する。林田は一瞬ぽかんとしたが、すぐ了解して相沢の後ろに回した手を押さえる。
「兄貴、そいつはいけません。なんせ、相手はガキですから。ましてお嬢様がいなさるし」
と言うと、若者を睨みすえ、静かに話しかけた。
「お兄ちゃんよ、もう許してやっから、さあ、もう、行け。ちなみにお嬢様とは、吉野組の組長さんの一人娘で、組長さんはそれは大事にお育てになってる。そのお嬢さんの身に何かあったら、それは大変なことになる。分かるな?指を詰めるなんて話じゃなくなっちまう」
若者の顔に今度こそ恐怖の色が浮かぶ。事実なのだから、林田の心にみじんの揺らぎもない。林田が続ける。
「そうそう覚えておけ、八王子ナンバーのモスグリーンのジャガー、この辺の族に知り合いがいたら、聞いておけ、いいな?」
既にブルっている3人の仲間が、威勢のいい若者にそれぞれ震え声を掛ける。「おい、行こうぜ」「ヤバいよ」などと言っている。威勢のいい若者も3人に引きづられるように車に戻ってゆく。キーという音と共に急発進して2台の車は闇の中に吸い込まれていった。
どちらともなく二人は声を上げて笑い始めた。こみ上げてくる可笑しさは止め処なく溢れ、腹を抱えて笑った。久美子が車の窓から身を乗り出し、やはり笑いながら二人に声を掛ける。
「あんた達、いつからうちの組員になったの?」
林田が笑いながら答える。
「俺はちっちゃい頃からお嬢様の家来だったじゃねえか。それよか、相沢さん、鯨井組はいいとして、鎌田組はないんじゃない。副支配人、今頃、クシャミしてんじゃねえの。思わず吹き出しそうになっちゃった」
「しかし、今まで経験したことがこんなところで役にたつとは思わなかった。いや、おかしい」
3人は笑い続けた。緊張感の後の弛緩した神経が可笑しさを倍加している。たまったストレスを吐き出すように、それは爆発した。ヤクザとの戦いに明け暮れた日の最後に、二人はヤクザの振りをして、暴走族の暴力から逃れたのである。笑わずにはいられなかった。
第九章 嵐の前
ようやく訪れた平安の日々。入れ墨を入れた人々も噂を聞いたのか殆ど来なくなった。入り口に置かれた2枚の大きな看板を見て、がっくりと肩を落とす子供連れがいた。うなだれる父親を不思議そうに見上げる子供には申し訳ないと思ったが、致し方ないことと心を鬼にする。
ヤクザさん達も久美子の父親の通達が効を奏したのか、ここ一月ほど姿を現さない。久美子はその後、ドライブの帰りに何度か泊まっていった。家は目と鼻の先なのだから泊まる必要などないのだ。
相沢は久美子が館内にいると思っただけで、苦しくやるせない思いに苛まれ、仕事も手に付かなくなる。相沢の熱い視線に気付くとそれをさらりとかわし、相沢がため息と共に諦めようと思えば、涼しげな眼差しを向け微笑む。
真綿で首を絞められるとはこのことかを思わず合点がゆく。久美子は相沢がそんな関係に慣れることを望んでいるようだ。何もなかったかのような昔に戻れと言いたいのか?相沢は深いため息とともに切なさを吐き出す日々が続く。
久美子はこの近辺では初めてというミストサウナが気に入っている。花の香りの熱い霧が降り注ぎ、長椅子に横たえられた男を知らぬと言う肉体がそぼ濡れる。相沢はその姿を想像するだけで下半身がぱんぱんに張っていた。
いくら修行を積んでも、煩悩から解放されず、思わず下半身を切り取ろうとした高僧の話を思い出す。男というものは死ぬまでその煩悩が付いて回るという。相沢はその煩悩が脳の半分以上占めていた10代はとうに過ぎているが、まだまだ男盛りである。
一度火がつけばそれなりの満足を得なければ治まらない。薄れゆく記憶をまさぐり、その滑らかな肌、唯一久美子と繋がりを持った唇の感覚を呼び覚ます。愛おしいという思いと突き上げるような欲望をもてあましていた。
あの日の帰り、久美子は林田を先に降ろした。道順からいってそれが当然なのだが、林田はどこか不満げに二人を見送った。走り出し、バックミラーに林田が写っている。振り返って見ると、林田が何やら叫んでいた。何を叫んでいるのか聞こえるわけもない。
八王子の街を見下ろす高台にジャガーは止まった。二人は車を降り、眼下に広がる夜景の美しさに感嘆の声を上げた。「ねー、綺麗でしょう」という久美子の言葉に頷きながら、相沢は大きく夜気を吸った。高まる気持ちにブレーキをかけるためである。
「あそこに野球場のライトが見えるだろう。その後ろ辺りに僕の家がある」
どの家もマッチ箱のように小さく、そこから灯りが漏れている。相沢が指さす方向を見詰めながら、
「何か、うらやましいなー、家族だけで、こじんまりとした家。でも、そこには普通の幸せがある」
とぽつんと言った久美子の言葉に相沢の心が揺れた。あの悲恋物語にしゃくりあげながら涙を流す乙女。そして普通の家庭に憧れながら、それでも因習に従おうと決心した健気な女。風の中を疾走し、死と隣り合わせの恍惚を友とする。男のように髪を刈り上げ、いったい何を表現しようとしているのか。
相沢は愛おしいという思いが急激に膨らんでゆくのを感じた。その感情を抑制しようとするのだが、それは膨らむばかりで如何ともしがたい。じっと久美子の横顔を見詰めた。
どれほどそうしていただろう。久美子はその相沢の熱い視線に耐えている。震える瞼が久美子の恐れと期待を物語っていた。
そしてついに乙女の心が勝った。伏し目がちに首を徐々に相沢に向ける。視線は落としたままだ。その震える瞼が徐々に開かれ、視線は相沢の目を捉えた。その刹那、相沢はその身体を強く引き寄せた。
暖かなぬくもりと、ドックンドックンという心臓の鼓動が相沢の胸に伝わってくる。唇を重ねる。相沢が久美子の下唇に舌を這わせた。「あっ」という声が漏れる。唇が僅かに開かれ、相沢を受け入れた。二人だけの恍惚の時間だけが流れた。
背中に回した掌で柔らかな脂肪をまさぐり、相沢の唇は柔らかな頬を、首筋を濡らした。次第に興奮が二人を包み、久美子の荒い息が相沢を刺激していた。右手がティーシャツの裾から差し込まれ、ブラジャーに覆われた豊かな乳房に触れた。
拒絶は唐突だった。久美子が相沢のその手を瞬間的に押さえたのだ。強い力だった。相沢もその刹那現実を思い出し、乳房を握った手を引いたのだ。重い現実だった。それを思い出したのだ。相沢が言った。
「ごめん、あまりに君が愛おしくて、耐えきれなくなった。婚約していることを忘れてしまった」
久美子は黙って言葉を探していた。一歩身を引くと相沢を見た。
「そんな風に言ってくれて有り難う。私がデートに誘って、ましてこの高台に車を停めたのも私。何も期待なんかしていないなんて言っておきながら、考えてみたら逆に誘っていたみたい。馬鹿だった、私…」
「いや、違うんだ。僕が我を忘れてしまった、僕が馬鹿だったんだ。昨日、君が映画を見て涙をながしているのを見た。本当に可愛いと思った。抱きしめたいと思った。君の横顔を見ていたら自分が押さえられなくなってしまったんだ。今日、君が言ったこと、確かに聞いのに、すっかり忘れてしまった」
久美子はじっと相沢を見詰めながら言った。
「だったら今の私を忘れないで。一生、覚えていて」
と言うと、車に乗り込みドアを開け、相沢に乗るよう促す。相沢が車に身体を入れると、久美子はまっすぐ前を向き、ハンドルを握っていた。相沢がシートベルトを装着し、シートに背を着ける。アクセルが踏み込まれた。
何か言わなければと思うのだが相沢の頭の中は真っ白だった。己の気持ちに正直に従っただけなのだが、久美子はそこまで期待していなかったのではないか?あの夜景を、二人だけの空間で、目に焼き付けておきたかっただけなのではないか?そんな不安が己を萎縮させていた。
林田以上に惨めな思いで車を見送った。とぼとぼと家に帰り、部屋で考えた。もしかしたら、これが最後かも知れない。もう会えないのではないかという思いは相沢を激しく責め苛み、一線を越えたことを後悔させた。
でも、何処が一線なのか?そんな一線などあるものか。でも、と考える。もしかしたら乳房を触らなかったら良かったのか?キスには迷いながらも応じたのだから。そこで止めておけば今まで通り会えたかもしれない。
どうどう巡りの思いは、突然の闖入者によって遮断された。妹の和美が突っ立っている。
「おい、驚かすなよ。部屋に入る時はノックぐらいしろよ」
「ちゃんとノックはしたわよ。それより、お兄ちゃん…それ何よ?はっはっはっは」
和美が相沢を指さし笑い出した。鏡を見ろと言う。手鏡を取り出し覗き込むと、口の周りが真っ赤になっている。久美子の口紅だった。
そう言えば、車を降りる段になっても、久美子は相沢を見ようとはしなかった。まっすぐ前を睨むように見ていた。なかなか降りようとしない相沢に業を煮やし、ドアロックを解除して降りるよう促したのだ。はやし立てる和美の言葉が相沢の心を更に暗くした。
久美子はしばらく姿を見せなかったが、一週間ほど前泊まりにきたのだ。何もなかったうに相沢に会釈し、ほほえみを送ってくれた。その時、喜びで胸が一杯になった。涙がにじんだ。また会えたことが嬉しくて飛び上がらんばかりだった。
その時、諦めようと決意した。あの温もりに接することは出来なくても、それでいいと思った。なのに、それから一月が過ぎ、相沢はその決意のことなど忘れてしまった。愛執が相沢の心に住み着いたのだ。それを断ち切らねば、苦しみがいつまでも続くことは分かっていた。
林田はそんな相沢の様子を見て、何度もあの晩の出来事を聞きただそうとする。何もなかったと言えば安心するのだが、疑惑を払拭できないようだった。しかたなく、久美子が婚約したことを打ち明けた。婚約した組長の娘に手出しするほど勇気はないと。
これを聞いて林田はようやく納得したのだが、婚約相手に焼き餅を焼くかと思えば、そうでもなく、婚約相手をよく知っているようで、「若頭なら大丈夫。良かった、良かった」と呟きながら何度も頷いていた。
人には根ほり葉ほり聞くくせに、あの時、二人を乗せた車に向かって何を叫んでいたかについては口をつぐんでにやにやするばかりだ。恐らく口には出来ないことを叫んでいたに相違なく、二度と聞くことはなかったが、どこか引っかかるものがあった。
いずれにせよ、相沢は苦く切ない思いを抱きながらも、仕事は毎日あるわけで、日々の仕事をこなしてゆくしかなかった。元々統括事業本部健康産業事業部の課長であり、ヤクザ対策がなければこれと言った仕事があるわけではないのだが、何かと忙しい。
林田は宴会誘致の営業だけでなく、宴会場の催し物に力を入れ始め、売れない歌手を呼んだり、カラオケ大会を企画し司会業にまで手をひろげている。深夜喫茶の担当は応募が全くなく、心苦しいとは思いながらも林に甘える日々が続いている。
林は深夜勤務明けの午前中にコンピューターの処理を終えて帰るが、その日の零時には出勤という激務が続いていた。林を休ませるために相沢、林田、昼間担当のハルさんが深夜喫茶担当を申し出て、何とかやりくりしているが、そろそろ限界が近づきつつあった。
そんなタイトな勤務ローテーションなど何処吹く風、9時5時勤務、日曜祝日休みの石田経理課長を、向井支配人が、林からコンピューターの仕事を引き継げ、と怒鳴りつけたのはつい先々週のことだ。。
その石田経理課長と厨房との関係が険悪になっている。石田は伝票を、厨房は仕入れを取り仕切る。両者の関係は信頼関係がまず前提になるのだが、その信頼関係が皆無なのだ。
その対立の裏でうごめく山本統括本部長の影。うんざりすることばかりだ。
鎌田副支配人は山本統括事業本部長に取り入り、向井支配人を出し抜こうと躍起になっている。山本の個室の鍵が替えられたのは鎌田副支配人の密告に違いなく、寝る場を失った相沢は二階の休憩室で仮眠する羽目に陥っている。
こうしてパートのおばさん達を巻き込む大騒動の下準備がゆっくりと入念に用意されていた。オープン当初の入れ墨、ヤクザ対策に忙殺され、それのみに神経を集中している間に、それに一切関わらなかった勢力が背後でうごめいていたのだ。
ぼんやり頬杖をつく相沢の肩を誰かが突っつく。居眠りしていたらしく、辺りを見回すと、隣の石田が個室の方を指さしている。その方向を見ると、個室から鎌田副支配人が顔を出し、相沢を見ていた。鎌田は振り返り最敬礼して個室を出ると、相沢に声を掛けた。
「事業本部長がお呼びです」
頷いて立ち上がり、すれ違いざま心の中で「クソッタレ」と呟く。鎌田副支配人はヤクザとの一件以来、相沢に敵意を抱いている。何故なら弱みを握られたと思っているからだ。相沢は鎌田の手が震えていたことなど誰にも話していない。
誰だってあんな場面で、しかもあんな風にコーヒーカップを持てば手先は震えるに決まっている。しかし、鎌谷は武道家としてのプライドがあるのだ。身勝手なプライドだ。自分は許せても、それを目撃した人間は許せないのだ。
個室に入ってゆくと山本統括事業本部長はソファにゆったりと腰を落として待っていた。顎で座れと指示する。山本は相沢が座るとおもむろに口を開いた。
「今、本部の方でも問題になっているんだが、どうも厨房の評判が思わしくないんだ。まあ、一部の意見を大げさにとらえているという批判もあるのだが、料理がまずくて食えないという人もいる。相沢君はどう思う?」
「私も料理の評判は気になって当初からアンケート用紙に目を通していますが、そういう反応はごく少数で、殆どのお客は大満足のところに丸をつけてます。特に、今度出したカツ重は好評で、売り上げ第一ですし絶賛されています」
「おいおい、別に、そんな単品をもって良し悪しなんて言ってるわけじゃない。まずくて食えないといっているお客がいることが問題なんだ。これを放っていれば、こうした施設では後々禍根を残すことになるのは目に見えている」
相沢は山本を睨みすえ言い放った。
「勿論、私もその少数を無視するわけではありません。何度も言わせてもらいますが、アンケートの統計によりますと大多数の人が料理には満足と答えています。問題はその少数意見をどう料理に生かすかという問題だと思うのです、違いますか?」
相沢は自分自身をつくづく可愛げない部下だと思う。しかし、そう仕向けたのは山本自身だと思っている。山本も反論を食らって頬が紅潮してきた。それでも年の功を見せつける。
「分かった、分かった。その問題はとりあえず君に任す。まあ、そのことはいい。それより、俺はこうした客商売のプロをもって自認している。その点、君より経験を積んでいるつもりだ。だから、ああゆう職人の狡さも汚さもよく知っている。そして今回の厨房は最悪だ」
こう言うと、タバコを取り出して火を点けた。いよいよ反撃に出ようというわけだ。
「奴らの関心事は、仕入れでどれだけ浮かすかだ。バックマージンなんて当たり前の世界だ。奴らは確実にそれをやってる。伝票をチェックするだけじゃ足りん。仕入れ商品のチェックが管理者の重要な仕事になる。君はそれをやったことがあるのか?」
自信をもって答えた。
「いいえ、ありません」
「だったら明日からでもそれをやりなさい。あいつらが何をやっているか、その目で確かめなさい。それがあんたの仕事だというのも忘れて、石田課長におんぶにだっこじゃしょうがないだろう」
じっと相沢を睨みすえる。
「ふっ、まあ、そんなレベルだから風呂屋にまわされたんだろうがな」
挑発するようなその言葉に思わず頭に血が上ったがじっと耐えた。分かりましたと答え、惨めな気持ちで個室を出た。まだ辞めるわけにはいかないのだ。それならじっと耐えるしかない。しかし、恐れていた事実にいよいよ直面することになった。
その事実とは蕎麦がまずいという事実だった。「どうだ?」とにこにこしながら問う調理長に思わず「旨いです」と答えたが、正直言うと違和感があった。さすがにアンケートにまずくて食えないとは書いていないが、その種の意見があったことは事実なのだ。しかし、あの調理長の笑顔を思い出すと何も言えなくなる。
相沢は調理場へ裏階段から上がっていった。そこは宴会が二件重なっており、戦争でも始まったかのような慌ただしさが繰り広げられている。調理長が怒鳴り、二番手が更に細かな指示を出す。下っ端は調理長の指示に「おーい」と声を揃え、位置を変え、手際よく料理を仕上げてゆく。その統制の取れた動きは見るものにある種の感動を与える。
その指示系統、指示直後に下準備に入る担当、次にそれが入れ替わる手順、そしてオーダー通りの順番に料理を仕上げてゆく記憶方法等々をじっと眺めていた。料理長に何遍聞いてもそれは相沢の理解の範囲を超えていた。
先ほどから石塚調理長は相沢の存在を気にかけており、一連の指示が終わる頃合いを見計らっている。二番手の内村がその様子に見付き、全面的に指示を出し始める。石塚は「手を緩めるな」と叫ぶと、相沢を振り返り相好を崩した。近づいて来るのを見て、相沢は慌てて言った。
「いや、いや、用事があるわけではないし、お忙しいのだったら仕事続けてください」
「いいんだ、もう何回もやっているメニューだからみんな身体で覚えている。二番手がいれば十分だ。ところで、向井さんは?」
「夜勤明けで、さっき帰りました。明日は休むよう、言っておきましたから」
「そうそう、たまには休ませないと。あの人はまじめ過ぎる」
そう言うと折り畳み椅子を二脚だしてきて、どっかりと座り込む。相沢が座るとタバコを取り出し勧める。喧噪の中、二人して煙をふーっと吹き出し、一息ついた。ふと、石塚の薄くなった頭が赤らんでいるのに気付いた。
「頭、どうしたんですか」
「ちょっとかぶれちゃって」
「大丈夫ですか?火傷ですか?」
「いやいやちょっと、叩きすぎたんだ」
「叩きすぎた?」
「養毛剤にブラシがついてて、それで頭を叩くと毛が生えるというから、必死で叩いていたらかぶれちゃった。何でもやり過ぎはいかん」
吹き出しそうになるのを堪え、薄くなりかけた髪をちらりと見た。
石塚はため息混じりに話し始めた。
「あの石田課長さんは、俺たちが不正をやっていると疑ってかかっている。肉の仕入れ先
を誰が決めたんだとか、どこにしまってあるのか見せろとか。課長、いいかい、俺は関東でも一応名の通った板前だ。だから仕入れは俺が納得のいくものじゃないと駄目なんだ。課長はそれでいいと言ったよね?」
「はい、料理に関しては全て調理長の納得がいくようにやって下さいとお願いしました」
「この世界に入って30年。食材の良し悪しを見る目がなければ旨い料理は作れない。親方にそうやって仕込まれてきた。勿論、仕入れ先との人間関係もある。でも、一度でも物で裏切れば、その業者との関係は成り立たない。鮮魚と肉はおたくの仕入れ業者じゃ駄目なんだ。俺たちは魚も肉もを触っただけでその鮮度が分かる。包丁を入れれば更にはっきりする」
「はー、そういうもんですか?」
「いいかい、これはいわゆる勘、あの第六勘の勘だ。職人のこの勘こそが日本文化の神髄だ。なにがバイヤーだ。横文字並べりゃ偉いと思っていやがる。課長のすきなマニュアルなんて、忍耐を知らず、微妙さを体得できない毛唐が平均点を取れればいいという思いで作ったもんだ。だけど、俺たちの目指すのは平均点より遙かに上なんだ」
相沢は石塚の毛唐と言う言葉に苦笑いを漏らしたが、彼の言う文化論にも多少頷けるような気がした。相沢は答えた。
「調理長、もう少し耐えて下さい。山本本部長はあの若さで取締役候補です。一課長の僕が出来ることなんて限られていますが、僕なりに努力をしています。もっと上の方にも訴えていこうと思っています」
「いやいや、課長、無理はするな。別に課長にどうにかして欲しいなんて、これっぽっちも考えていない。ちょっと愚痴を言いたかっただけだ。とにかく、課長は無理をするな。サラリーマンなんだから上手く立ち回れ。」
「はー、あの山本さんに対して上手く立ち回っていたら、人間性が歪むような気がしますし、もう手遅れです」
調理長は同感だというように苦笑いを浮かべた。
「いや遅いということはない。これからのこともある。課長はサラリーマンなんだから、長く勤めることを考えろ。俺たちはどこにでも行ける。1年契約にしてもらったのもそういう含みがあってのことだ」
「そんな寂しいこと言わないで下さい。来年も契約更新、何とかお願いします」
「課長、それは無理だ、歳だしな。こんな長丁場の勤めも初めてだし、体力の限界を感じ始めている。ところで、二番手の内村が不思議がってる。浅草の家から通えず、アパートを借りてまで、何でここに留まっているのか不思議がっている。昔の俺なら、不正を疑われていると感じただけで、さっさと辞めている」
それは相沢も同じことを感じていた。どうしたわけかここに引き寄せられる。居心地が良いのだ。何故なのか何度も考えた。そして相沢はある結論に達したのだ。人間関係であると。ここに集まった核となる人間達に惹きつけられているのだと。
調理長、支配人、林コンビそして相沢。5人は、かつて何処かで出会っているのではないか。そう前世で。そこで共通の目標のために働いた同志だったのではないか。相沢の本来の仕事は計数管理だ。何も現場に来てそれをやらなくとも、本社ビルの7階でパソコンに向かっていても誰も文句は言わない。それが毎日のこのこやって来る。皆に会いたくて。
にこにこして調理長が言う。
「それは二人に頼まれたからだ。課長と向井支配人が料理で勝負したいと俺を頼ってきた。その期待に何としても応えたいと思ったからだ。1年で何とか軌道に乗せるつもりだ。だけど、どうにも耐えられないという時が来るかも知れない。そんな時、俺は二人には絶対に迷惑をかけない形で辞める。」
「調理長、」
「まあ待て、これだけは言っておかなければならないんだ。この世界じゃよくあるんだが、店のものが出勤してきたら、厨房がもぬけの殻なんってことはよくある話だ。それだけは絶対にしない。後釜を据えるまで辞めない。だからその時は許して欲しいんだ。とにかく、石田課長さんの露骨な態度には辟易している」
「はー…」
「どうも山本さんのやり方は俺の流儀とは合わない。最初に出会った時からそれは感じていた」
ふと、悪代官を懲らしめる5人の侍を想像した。山本統括事業本部長は時代劇に出てくる悪代官にぴったりだし、山本事業本部長の後ろ盾となっている安藤常務はさしずめ悪代官を影で操る悪徳商人といった案配だ。まてよ、侍なんかじゃなくて、農民一揆をを起こした村の主導者だったりして…。
調理長の真剣な眼差しに気づき、妄想を振り払った。そして懇願した。
「今は耐えてください、お願いします。僕は絶対にあいつらには負けません」
「おいおい、勝ち負けをいっているんじゃない。世の中には、負けるが勝ちってこともあるんだ」
「何とかお願いします」
「分かったよ、分かったから、もうその頭を上げろよ。どうも弱い、向井さんと課長には…。とにかくだ…、向井さんと課長の二人のために、やれるだけやる。」
「有り難うございます」
相沢は深々と頭を下げた。
事務所に戻ると相沢はパソコンに向かった。ワードを立ち上げ、最初に「岡安専務殿」と書いた。統括事業本部は安藤常務の直轄であり、岡安専務は直接タッチしていない。しかし、今の現状を打開するには常務の上に訴えるしかないと思ったのだ。
専務は大学の先輩であり、何かと目を掛けてくれている。企画部時代、販促キャンペーンで全国行脚の出張のお供をしたこともある。しかし、専務に信じてもらえるだろうか?厨房が不正をしているという山本の宣伝は既に経営陣にまで浸透しているのではないか?
相沢が本部に赴くのは会議に出席するためで、月に一度だけ。これに対し、山本は月に一度直轄事業の各現場を回る以外はずっと本部だ。山本のやり方は陰湿だが確実だ。まずは潰したい相手に負のイメージのレッテルを貼る。それをあちこちで触れて回る。
相沢の「上司を蔑ろにし、独断専行しがち」というレッテルはすでに本部でも定着してしまっている。宴会場と厨房の間に洗い場と中継基地を山本の了解なしに作ったことは皆知っていた。それは山本が稟議に判を押さないので既成事実を作ったまでだし、まして、それを作らなければ現場は大混乱で、今日の成功はありえなかったのだ。
相沢は大きなため息をつき、書きかけの文章をゴミ箱に放りこんだ。専務に秘密のレポートを送ったことが知られれば、安藤常務と山本事業本部長の機嫌を損なうことにもなる。まして調理長は上手く立ち回れと言った。時期を待つしかないのかもしれない。
そこへ林が出勤してきた。目の縁にうっすらと隈ができている。早めに深夜喫茶担当を決めようと時給を上げた稟議に山本が判を押さない。「林にやらせておけばいいじゃないか」と言うのだ。林の過剰な勤務実態など素知らぬ振りだ。
「あれ、今日は休みじゃないの、深夜喫茶はハルさんじゃなかった?」
「そうなんだけど、月末まであと10日だから給料だけはやっておかねえと、みんなが困っちまう」
「でも、それは石田課長の仕事だろう。支配人が今月こそやれって、彼女に怒鳴ったてたじゃない」
「俺もそのつもりだったんだけど、あのアマ、やってねえんだ。あれ、今、いないの?」
「また銀行回りだ。本部長もいっしょだ」
「まったくあのアマ、本部長の恋人だと思ってやりたい放題だ。厭になっちまう。慣れない私がやるより、林さんがやった方が早い、なんてヌカしやがるんだ。来月からやるって言ってるけど、どうなるか分かったもんじゃねえ」
「今、何て言った?本部長の恋人って言わなかった?」
と相沢がすっとんきょうな声を上げる。
「あれっ、知らなかったの?恋人に決まってるよ。最初の頃、本部長のおごりで、みんなで飲みに行ったんだ。その時、石田がタバコをくわえて火を点けて本部長に渡したんだ。そんなこと、関係のない男女がするわけねえもの」
組織上、こういった施設の最高責任者と経理担当が男女の関係であってはまずい。しかし、それを告発するには、もっと確実な証拠が欲しいと思った。そう言うと、林はこともなげに言う。
「証拠ならあるよ。二人はいつも本部長の車で一緒に帰るんだ。みな知ってるよ。ここを出る時、ちょっと時間差を置くんだ。石田が先に出て、車の中で待ってるんだよ」
「それってたまたまなんじゃないの、帰り道がいっしょで、送って行ったのを誰かに見られたとか…」
「いいや、本部長が来るときはいつも一緒だよ。17時半出勤のハルさんがちょうど遭遇するんだ。石田はいつもシートを倒して隠れているんだって。ハルさんに言わせると、あんなことしたって、見えるにきまってるじゃねえか、こっちは立ってるんだもん、だって。笑っちゃったよ」
相沢はほくそ笑んだ。これは使えそうだと。二人を誰かにつけさせて、その証拠を握る必要があるのかもしれない。林田だったら上手くやってくれそうな気がする。明日、支配人に相談しようと思った。
林は眠そうな目をこすりこすりパソコンに数字を打ち込み始めた。林が今日の勤務を終えたのは今朝の7時。ということは数時間しか眠っていない。「ご苦労さん」と相沢は林の肩を揉んだ。林は気持ちよさそうにされるがまま目をつむる。
「気持ちよくってとろけそうだ。眠気が増してねむっちまうよ、課長。でも、もっとやって、気持ちいい」
その日、林はまだ正常な神経を保っていたのだ。
第十章 悪意
厨房との騒動を起こしたのは、やはり鎌田副支配人直轄の宴会場だった。それは料理に異物が混入していたという客からのクレームから始まった。これを聞きつけたウエイトレスの村田が騒ぎだし、鎌田に御注進に及んで抜き差しならない事態へと発展していった。
知らせを聞いた向井支配人が急遽駆けつけ、お客に対処した。お客はさほど怒ってはおらず、ことのなきを得たのだが、その異物である瀬戸物の欠片は、鎌田と村田が抗議のための証拠品として厨房へと持ち去った後だった。
急ぎ向井が駆けつけると、鎌田副支配人が大きな肩を怒らせ厨房の若手に向かって怒鳴り声をあげていた。
「こんな物が料理に入っていたぞ。一体全体、お前らはそれでもプロか?料理にこんな物が紛れ込んでも気付かないなんて、呆れてものも言えない。」
若手は後ろを振り返り、二番手の内村に助けを求める。遅番勤務で厨房に調理長はいない。内村は鎌田を無視してスポーツ紙を広げている。向井支配人は困惑気味に内村に声を掛けた。
「おい、内村さん、ちょと来て、見てくれないか。こんな物が料理に入っていたと言うんだ。髪の毛一本が命取りになると言っている調理長のことを思うと、俄には信じられないことだけど」
村田はその言い方にかちんと来たらしい。
「変な言い方。まるで誰かがわざと入れたって言ってるみたい」
向井はぎろりと村田を睨んで言った。
「いいか、料理が出来上がってお客に届くまでに何人の手を経てると思っているんだ。それにその距離は何十メートルもある。あの料理に関わった全ての人がミスをした可能性を疑わないといけない。途中で茶碗が割れることだってあるんだ」
村田は向井の剣幕に一瞬ひるんだ。今度は鎌田副支配人に視線を向けた。
「おい、鎌田。何でそれを厨房のミスと決めつけたんだ?」
鎌田の目が一瞬泳いだ。
「別に決めつけたという訳じゃなくて、料理の中から出てきたのだから、当然厨房がミスを犯したと思ったんです」
「お客は料理の中から出てきたなんて言ってなかったよ。皿の端にちょこんと載っていたって。ミスを犯したのは、厨房と料理を置いておく中継点、そこに関わった全ての人たちの可能性がある。そうだろう、上に立つ者は常に中立じゃなくちゃ」
村田がふて腐れたように言い放つ。
「そう言う支配人は、いつだって厨房の味方じゃない」
にやりと笑って向井が言う。
「ましてや村田さんは、厨房と一悶着あったのだから、そのことも考慮しなけりゃ」
村田はずっとオーダー係りをやっていた。次々とあがる注文をマイクで厨房に伝える役目で、村田本人はウエイトレスより一段上だと思っていたようだ。ミスが多いという厨房からのクレームでその役目を変えられた時は、そうとうショックだったらしい。最後までミスは厨房の方だと言い張っていた。
そこで内村がようやく重い腰をあげてやってきた。内村が鎌田からその破片を取り上げると、ちらりと見て、固唾を飲む若手に笑いかけた。
「おい、この割れ目を見ろよ。まるでガラスみたいに光ってる。そうとうの安物だ。恐らく百円ショップの瀬戸物だろう」
若手も笑いながら答える。
「ここにはこんな安物置いていないよねー、内村先輩。百円ショップの湯飲茶碗なら中継点にたくさん置いてあった、村田さん達のやつが。俺たちのは全員同じ形のステンレス製のマグカップ。店のものと紛れないし、洗えば誰が使ってもいい」
と言うと可笑しそうに笑った。内村がちらりと鎌田副支配人を見て言う。
「俺の言葉が信じられないのなら、ここの食器を揃えた瀬戸物担当の佐々木バイヤーに見てもらったらいい」
内村はこう言うと踵を返し、奥にひっこむとまた新聞を広げた。向井支配人はにやにやしながら鎌田と村田に視線を向けた。
「あのお客は料理をただにするという僕の申し出を断った。だからあのお客がわざと入れた可能性はない。この破片は少なくとも厨房で入った可能性も少ない。いったい何処で入ったのかなー」
と言うと、その破片を持って厨房を後にした。鎌田と村田は内村の一言を聞いてから、うんでもすんでもなく、向井が去ると、何事もなかったかのように仕事に戻ったという。
相沢がことの次第を聞いたのはその翌日だった。あからさまな悪意に慄然としたのだが、向井はむしろ面白がっていた。
「いいかい、課長、現場なんてこんなことしょっちゅうだ。特に女連中のいがみ合いは凄い。見ているこっちが冷や冷やする。妬み、嫉妬、恨み、憎しみ、全てのマイナスの感情が渦巻いている。しまいには、それを利用する汚い奴も出てくる」
「やはり山本本部長の差し金でしょうか?」
「それはどうかな、今回の件はどうも女の浅知恵臭い。本部長の歓心を買おうという鎌田が、その浅知恵に飛びついたってとこだろう。それより、当面の問題は調理長がこの件でどう出るかだ。きっと辞めるって言い出すと思う」
「ええ、僕もそう思います。でも何とか慰留してみます」
「そろそろ調理長の出勤時間だ。内村さんが調理長に昨夜の出来事をことさら大げさに聞かせていることだろう。あの人はここを辞めたがっているから」
「ええ、内村さんは調理長にはこんな現場は相応しくないと思っています」
その時、相沢の机の電話が鳴った。向井がにやっとして出るように促す。相沢が受話器を取り上げ耳に当てる。
「か、課長、ちょっと上ヘ…」
と言う調理長のうわずった声が響く。受話器を置くと向井が真剣な眼差しで言った。
「課長、任せるから、兎に角、慰留してください。お願いします」
相沢は頷いて厨房へ向かった。
厨房では調理長を中心にみなが集まっていた。本来であれば仕込みで忙しく立ち働いてる時間だ。調理長は感情を押し殺しているが、他の連中ときたらまるで仇にでも出会ったかのように相沢を睨んでいる。相沢が頭を下げながら言葉を発しようとした時だ。
「課長、今度という今度は、もう我慢の限界だ。俺もいろいろな所で働いてきたが、こんなのは初めてだ。ミスはどこにでもある。でも悪意はどこにでもあるってもんじゃない。この会社はレベルが低いよ」
思いのほか語気鋭く言い放った。いつもの目を線にして微笑む顔など見せるものかという強い意思を感じた。しかし、言ってることも、怒るのも当然なのである。
「調理長、本当に申し訳ございません。こんなこと、私も信じられないくらいです。でも、何とか今回は留まって下さい。お怒りはごもっともです。でも、どうか勘弁してやってください」
調理長はまだしも、他の若い連中の怒りはそうとうのものだ。一流料亭勤めであれば休む時間はたっぷりある。でも、ここではそうはいかない。のべつ幕なしに注文が入ってくる。彼らを納得させるには言葉では駄目だと観念した。
向井支配人はこう言ったことがある。「ここぞと思うとき。僕はあれをやるのに一瞬の躊躇もしない」と。あれか…、散々躊躇して一瞬で決意した。いきなり地べたに座り込んだ。土下座である。ごめんなさい攻勢に、土下座攻勢、全く向井さんには参る。
水撒きしたのであろう。コンクリートの床はまだ水が残っていた。スラックスが濡れて折り目はだいなしだ。でも声を張り上げた。
「調理長、申し訳ございませんでした。皆様にも厭な思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございません。でも、何とか、堪えて下さい。男相沢、何としても皆様の思いを重く受け止めて、今後、このようなことの無きよう奮闘する決意です。ですから、どうか怒りの矛先を納めて下さい」
唖然と見守る皆を前に、相沢は額を床にこすりつける。慌てたのは調理長だ。
「おい、課長、俺は課長に謝れなんて言っていない。おい、頭を上げろよ」
と言いながら、近づいてきて肘を持って立ち上がらせようとしている。相沢がそれに抗うものだから、調理長も諦めた。ふーと息を吐き、皆を振り向いて怒鳴った。
「どうする、本部のお偉い課長さんが土下座までして、堪えてくれと言っている。どうだ、やっぱり辞めるか、今日、この場で、きっぱり辞めるか?困っている課長を放っぽらかして去ろうと言うのか?おまえら、どうなんだ?」
親方にこう言われたら、弟子である連中が逆らえるはずもない。調理長はきっとして二番手に問う。
「どうする、内村?」
内村は一瞬で諦めた。
「残るしかないですね」
と言うと相沢に一瞥をくれた。一瞬、にやっとしたように見えた。調理長はこの一言を聞くと、叫んだ。
「さあ、急いで仕込みだ。遅れた分を取り戻すぞ」
例の「おーい」と聞こえるおかしな返事が厨房に響き、それぞれの位置に戻っていった。 相沢は胸をなで下ろし、立ち上がった。調理長にお礼を言おうと待っていたが、調理長は相沢を無視している。相沢べったりという厨房内の批判を気にしているのか。しかし、先ほどの内村の反応はそれを揶揄しているようにも思えた。
事務所に戻ってみると、ここでもひと騒動持ち上がっていた。そこには、鬼のような顔をして山本本部長が突っ立っている。両脇には向井支配人と石田経理課長、その前には林がうなだれたまま座っていた。
山本の顔は紅潮しており、林を怒鳴っていたことは明らかだ。向井がいつものように割って入ろうとした矢先だ。山本の唸るような声が響いた。
「貴様、どうやってこの責任を取るつもりなんだ。ええっ、どうするつもりだ。一度や二度じゃない、もう三度目だぞ。そのたんびに、本部で駆けずり回って、大目に見てやれと皆をなだめた。その俺の顔に泥を塗ったことになるんだぞ。えっ、どうする」
山本は伝票のようなものを手に持って、林を睨み付けている。林が辞めると言い出すのを待っているのだ。
と、ドアが開き、林田が入ってきて緊迫した雰囲気に気付いた。ごほん、とわざとらしい咳をすると、林の返事を今か今かと待つ山本に話しかけた。
「本部長、上で審査委員長の席を用意しておきました。もう、宴会場に上がってもらえませんか?」
大広間のカラオケ大会の席のことだ。これを山本が目を剥きだして怒鳴った。
「何で、今から上にいなけりゃならないんだ。まだ20分もあるじゃないか」
「いや、早く用意しておいた方がいいと思って」
山本は林田を無視して再び林を睨みすえる。相沢は林田の優しさに涙が滲んだ。自分の保身も顧みず、迫真の演技をする最高権力者にちゃちゃを入れたみたいなものだ。相沢が割って入った。
「本部長、いったいどうしたって言うんです?」
山本はこれを無視した。相沢は、一瞬血が頭に上ったが、再び冷静に声を発した。
「また林が入力を間違ったんですか?しょうがねえな」
ふと、山本が力を抜き答えた。
「まただよ、何回やっても同じミスを繰り返す。向いてねえんだよ、こうゆう仕事に」
「あれっ、その伝票は給与計算のじゃありません?おかしいな、給与計算は石田課長がやっていたはずだけど」
石田が焦って何か言おうとしたが、山本がそれを手で制し答えた。
「違うんだよ、それが。石田課長は教わってないんだとさ。林が譲りたくないもんで、教えねえんだ。ケツの穴が小いさいんだよ、男のくせに」
この時、林はとうとう堪えきれなくなった。その顔は今にも泣きそうだ。
「俺は、何度も教えたよ。石田課長、正直に言ってくれよ。この間だって、やってるか?って聞いたら、やってるやってる返事したじゃねえか。何で嘘言うんだよ」
石田が甲高い声を上げた。
「私、教わってなんかいないわ。そんな返事なんて、した覚えないもん」
向井も覚悟が出来たのだろう。林を応援する。
「林が何度も教えてるの見てきた。それでもやろうとしないから、先日、俺があんたにやるように指示したはずだ。何で嘘を言うんだ」
事の成り行きに一番驚いたのは山本だった。ついさっき石田から聞いた話とちょっと、いや、ちょっとどころか全然違う。石田を振り向いた。石田が叫んだ。
「みんなして話を合わせて、私に責任を押しつけようとしてるのよ、みんな仲間だから。あんな教えたかでは、覚えられないわよ、身体さわったり、すけべなことばっかり言って、肝心なことはちっとも教えてくれなかった」
この言葉を聞いた林の顔が見る見るうちに歪んだ。そして唸った。
「嘘こけ、このアマ、ふざけやがって、ぶっとばしてやる」
完全に切れたのである。唸りは続いている。ぶつぶつと口の中で何かを言いながらも言葉にならず、唸っている。そして立ち上がった。
林がじろりと山本を睨み付けた。そして一歩、また一歩と近づいてゆく。相沢は林の様子に尋常でないものを感じた。相沢は山本の前に割って入り、林の両肩をつかみ、振り返って石田に叫んだ。
「本当のことを言ってやれよ、石田さん。林が石田さんに懇切丁寧に教えてるのを俺も見ている。身体を触ったり、いつものおふざけなんて微塵も見せなかった。何故なら、林は仕事がきついから、この仕事を石田さんにやって欲しかったからだ」
林田も加わる。
「俺だって見ている。林は朝6時までの勤務なのに、あんたが出てくる9時まで待ってた。その後、何時間も教えてもらってたじゃねえか」
石田はその場をよろよろと離れ自分の席に戻ると、机に突っ伏してわっと泣き出した。山本本部長は既に自分の言い分に説得力のないことを自覚して一歩退いた。
「まあ、そのことはともかく、間違いは間違いだ。間違ったのだからみんなに謝れと言っただけだ。とにかく、今後は注意してくれ」
と言うと、手に持っていた書類を林の机に置くと個室へと戻っていった。相沢は林を無理やりミーティングスペースへ連れ込み座らせた。そして言った。
「いいか、林、落ち着け。落ち着くんだ。ここで問題を起こせば本も子もなくなるぞ。せっかく、一部上場企業の子会社へ就職できたってあんなに喜んでたじゃないか。兎に角、子供のことを考えろ」
林田も席についた。
「馬鹿なこと考えるな。ここはバックがでけえ会社だ。ここら辺の地場産業じゃ貰えねえぞ、こんな給料。あんな奴のためにそれを棒に振るつもりか?」
林はまだ何かに憑かれたようにぶつぶつと独り言をつぶやいている。おいっと林田が肩を揺すると、はっきりとした声でいった。
「あの野郎、ぶっとばしてやる」
相沢が低い声で言う。
「ぶっとばしたらどうなると思う。あいつは以前、部下にぶっとばされたことがある。その部下はどうなったか分かるか?訴訟を起こされそうになって示談金をそうとう取られたって噂だ。いいか、あいつは一筋縄ではいかん。それを覚えておけ」
一瞬、真剣な表情をしたが、またしても言い放つ。
「あいつに先に殴らせればいい。そうすれば俺も殴れる」
相沢と林田が顔を見合わせた。林田が林の肩をつかんで大きく揺する。
「おい、冷静になれって言ってるのが分からねえのか。まだ借金が残ってるって言ってたじゃねえか」
林はにやりとして答えた。
「そうだった、借金もあった。大丈夫、大丈夫。俺だってこれ以上経済的に逼迫できねえんだ。分かった、分かった、冷静になるよ」
その表情はさきほどよりだいぶ落ち着いてきている。林田が肩を押さえて言う。
「そうか、本当か、本当だな」
いつもの林の笑顔が戻った。林田が続けた。
「いやー、一時はてっきり狂ったかと思ったよ、びっくりしたなー。いいか、林、あいつだってサラリーマンなんだし、どっかに飛ばされちゃうかもしれない。だから一時のことだと思って、ここは堪えろ。いいな」
「ああ、だいぶ落ち着いてきた。だから心配すんな」
相沢と林田は顔を見合わせ、頷きあった。林は立ち上がると、
「さあ、間違ったとこ訂正しねえと、ハルさんの給料が俺より多くちゃ、案配悪いかんな」
と言って笑った。二人はほっと安堵し、その背を見つめた。
ほっとしたのもつかの間だった。給料計算をしていた林が「便所いってくんべえ」と立ち上がった。個室には向かわずフロントの方へ向かったので、相沢も油断した。数秒たって、事務所側の個室のドアから怒鳴り声が聞こえた。裏から回って個室に行ったのだ。
向井、相沢、林田が同時に立ち上がって駆けだした。個室のドアを開けると、般若みたいな顔で林が山本を怒鳴りつけていた。ただ怒鳴っているのではない、山本に自分の胸をぶつけているのだ。
「さあ、殴れよ、殴ってみれよ。俺が憎いんだろう。だったら殴りやがれ。男だろう、貴様。金玉つけてんのか」
先に殴らせようとしている。一瞬、相沢の心に悪意が走った。「山本、殴れ。殴って、林にぶちのめされろ」山本の顔は驚愕に彩られている。口元が歪み、わなわなと震えている。相沢が、心の中で「山本なぐってやれ、林のために」と叫んだ時だ。
向井が林を羽交い締めにして押さえた。林田も林の両手を握っている。それを見た途端、山本の怯えは止み、目が徐々に怒りを帯びてきた。押さえられた林に向かって、沸き上がる憎しみを込めて怒鳴りつけた。
「貴様なんて、首だ。首にしてやる。もう二度と就職できなくしてやる。この辺の企業に暴力を振るったって言いふらしてやる。貴様のような…。」
相沢がその怒鳴り声を遮った。
「さあ、これで終わり。私憤による喧嘩はこれでストップ。仕事優先。おい、林田、もう時間だろう、本部長を上にお連れしろ。カラオケの審査委員長がいなけりゃ、格好がつかない。本部長、蝶ネクタイを締めて、早く行ってください。仕事第一、仕事優先、おい、林田」
はい、はい、はいと林田が無理矢理山本を連れだした。林を見ると、目には涙を湛えている。向井がその羽交い締めした手の力を抜いた。林はしゃがみ込んだ。そして床を叩き始めた。拳で床を殴りつけている。その手が血に染まってゆく。叩きながら泣き喚いた。
「間違いは認めるよ。だけど、何もそこまで言うことはねえ。俺の存在価値をそこまで貶める必要はねえ。なんであの書類をわざわざ持って来るんだ。本部で訂正すればそれで済むじゃねえか。何度もそうやってきた。俺をそこまで責めることに何の意味があるんだ。本部本部って偉そうに言うんじゃねえ、馬鹿野郎」
泣き声は事務所いっぱいに広がる。向井も相沢も声を失った。
第十一章 乱交
林の退職は、心の一部が切り取られたような痛みを相沢に残した。戦列からいつのまにか消えた戦友を捜すように、広い施設を歩くたびにその影を求める自分に気付き、あらためて林がいないという現実に寂しさを覚えるのだった。
林はもう客としてさえこの施設に来ることはないだろう。この数ヶ月、針の筵に座るような辛い日々を送っていた。隣のスーパーへの就職の斡旋も拒絶した。ここは、林にとって思い出したくもない場所になってしまったのだ。
相沢は、林の優しさ、寛容さ、表裏がなく素直で正直な性格が好きだった。社会に出て初めて出会ったタイプの人間だ。しかし、その性格が過ぎたことがハンディとなった。そこにつけ込む人間は大勢いるのだ。
林の交代要員として深夜喫茶担当を急募した。時給を上げてようやく応募があった。完璧な夜型人間で、ぴったりの人選だった。しかし、現職を辞めるのに3週間かかり、週1日をハルさんに頼み、残る6日を相沢と林田が交互に受け持つこととなった。
相沢は週3日の深夜喫茶勤務になるが、むしろ心躍った。それは林がかつて、久美子が泊まる時、必ず深夜喫茶で時間を過ごすと言っていたからだ。お客が入ってこなければ、一発やらしてもらえたかもしんねえ、などと言って林田にこづかれていた。
相沢は、ここのとこと久美子に会う機会に恵まれなかったが、週3日となれば会えそうな気がしたのだ。相沢はもう二度と手を出すつもりはなかったが、心の整理がしたかった。あまりにも唐突な出会いと別れ。残滓のような中途半端な恋心が切なさを増幅させていた。
しかし、相沢の期待に反し、初日も二日目も久美子は現れなかった。三日目、そんな時に限って招かれざる客が訪れるものなのである。夜の1時を回った頃、一人の若者が喫茶に入ってきた。他にお客はいない。
相沢はその若者に見覚えがあった。どこかで会っている。そう思った。その若者も同じように感じたらしく、何度も小首を傾げていた。相沢が注文の生ビールと枝豆を運んで、テーブルに置く間も、若者は相沢見詰めている。だが思い出せないようだ。
若者がジョッキを口に運び、飲もうとした瞬間、思い出して「あれっ」と声を発し、相沢を指さした。そして立ち上がって言った。
「どっかで見たことがあると思っていたら、お前はあの時のヤクザじゃねえか。何でヤクザがこんな所でウエイターなんてやってんだよ」
相沢はにやにやしながら答えた。
「ウエイターじゃない、マスターって呼べ、マスターって。それにあの時、俺たちはヤクザなんて一言も言ってないぜ。お前等がヤクザだって勝手に思いこんだだけだ」
「何言ってやがる、この野郎、ふざけやがって、指だってちゃんとあるじゃねえか」
若者は騙されたことに腹をたてているようだが、あのことは失念しているらしい。思い出させる必要がある。
「ところで、ジャガーの持ち主については仲間に聞いてみたか?」
若者は怒りの顔に、ふと不安を滲ませ、ぷいと横を向いて答えた。
「ああ、聞いたよ…」
「じゃあ俺たちの言ったことが本当だって分かっただろう。だとしたら俺たちに感謝してしかるべきだ。もし、お嬢さんに手をだしていたら、君はこの世に存在しないか、或いは身体のどっかがなくなっていたはずだ」
「何も暴力を振るおうなんて思ってもいなかった。ただ脅してやろうと思っただけだ」
相沢が小首を傾げると。顔を引きつらせながら言った。
「脅すっていったって、ただお話し合いをして、何故僕らが怒っていたか、知ってもらおうと思っただけですよ。いやだなー、ところで、マ、マ、マスターはお嬢さんと、ど、どうゆうご関係なんですか?」
「まあ、お友達ってところかな、もっともあの後、喧嘩してしまったけどね」
「ああ、そうなんですか。ここに、よ、よく来るんで?」
「ああ…」
相沢は言葉を飲んだ。久美子がこっちにやって来るのが見えたからだ。既に帰り支度を整えている。いつ入店したのか気が付かなかった。若者に向かって言った。
「噂をすれば影だ。この店に今から来るつもりらしい」
若者は後ろを振り返り、慌てて顔を伏せた。咄嗟に立ち上がり隠れようとあちこちうろうろしていたが、諦めて相沢に言う。
「あの時のことは謝ろうと思ってます。あっち向いて隅の方でビール飲んでますから、適当な時に声を掛けてください」
ビールと枝豆を持って別の席に移った。
久美子が入り口に佇み笑顔を向けている。相沢もそれに応えた。久美子がゆっくりとした足取りで相沢に近づいて来る。二人はじっと見つめ合った。相沢の胸が苦しくなる。久美子がカウンターに席をとった。やはり愛してしまったようだ、ヤクザから奪ってしまおう、とちらりと思った。久美子が口を開いた。
「生ビールを二つ。相沢さん、よかったら乾杯してくれる?」
「えっ、何に?」
「私の結婚に。日取りが決まったの。全ての手配を終えたわ」
何も答えず、マグカップを二つつかんだ。深い悲しみとかすかな安堵、複雑な思いが相沢の頭を空白にしていた。
「相沢さん、ビール、ビール」
久美子の声に驚いて手元を見ると、ジョッキからビールが溢れている。かなり動揺していたのだ。でも、心を切り替えた。どこかほっとする気持ちがあるのは確かなのだ。ヤクザさんからその婚約者を奪うなど出来っこないのだから。
相沢は無理矢理笑顔をつくると、ジョッキを久美子に手渡した。そして言った。
「おめでとう、心から祝福するよ。本当にお目でとう」
そう言ってジョッキを合わせると微笑んだ。久美子も伏し目がちに笑顔で答えた。
「ずっと迷っていたの。でもあの時、決心したの」
そう言うと、言葉を詰まらせ、目を潤ませた。「あの時」とは、高台での一時のことだ。
あの一瞬一瞬の思い。二人の息づかい、言葉、夜景、全てが蘇る。久美子が、ふーっとため息をつき、話題を変えた。
「相沢さんの勤務日を林田君に教えてもらったの。だいぶ迷ったけど、今日、やっと決心し来たわ。あんな事があったのに、何もなかったみたいに接するのって、思ったより辛いね。そう出来ると思ってた私って、まだ子供だったんだわ。本当に馬鹿みたい」
相沢は俺もそうだと叫びたかった。しかし、笑顔で結婚を祝福した男のセリフではない。相沢はビールを一気に飲み干した。
「でも、私って、ずっと子供だったような気がする。いつだって現実から逃れようと夢ばかり追いかけていた。でも、林田君のあの一言は痛烈だった。彼、相沢さんに期待しても無駄だって言ったわ」
「ああ、僕も聞いていた…、何を言っているのか意味が分からなかった」
「私、男の人に家のことを隠したことないの。だから恋愛なんて始まりもしなかった。でも、相沢さんは違った。本当に嬉しかった。でも、そうなってみると、思いのほか苦しくて切なくて、死にそうになっちゃった」
「実を言うと、僕もそうだった」
にわかに久美子の目からはらはらと涙が落ちる。相沢はその涙をじっと見詰めていた。そして言った。
「僕なんて君が思っているような男じゃない。僕は狡くて臆病な人間だ。君は僕の心の奥底なんて見えない。見えないからそんな風に言うんだ。君は僕を過大評価しているだけなんだ」
「いいえ、違うわ。今まであんなふうにしてくれた人、いなかった。家に帰ってもその余韻が残っていてなかなか眠れなかった。何度も思い出して、一瞬、一瞬を思い出して、心に焼き付けて、幸せを噛みしめた。家のことも知ってて、婚約のことまで知ってて、それでも抱いてくれた。本当に嬉しかった」
「違う、それは違うんだ。ただ、僕は自制心がないだけなんだ。君があまりに可愛くって自分が押さえられなかった。ただそれだけだ」
「いいの、それでもいいのよ。私にとって忘れられない思い出ができたんですもの。でも、それ以上のことを相沢さんに望むのは酷だってことも分かっているの。だから、だから、延ばし延ばしにしてきた結婚の日取りを決めたわ。もう後には戻れない。後に戻るなんて、この世界では許されないから。だから…今日…お別れに来たの」
大粒の涙が頬をつたう。胸を震わせ、しゃくり上げながら、微笑もうとしている。その顔はただ歪んだだけだ。そして声は殆ど泣き声になっていた。
「それじゃあ、さようなら、忘れない、あなたのこと」
言い終わると、きっぱりと席を立った。くるりと背を向け歩き出した。相沢は堪えきれずに声を掛けた。
「久美子さん」
久美子の背中がぴくんと反応して、歩みを止めた。相沢は心を込め別れの言葉を贈った。
「俺も忘れない。君のことは一生忘れない。墓場まで持ってゆく」
振り返りもせず、肩を震わせて歩いてゆく。振り返らないと決めていたようだ。相沢はその後ろ姿をじっと見詰めた。
頬に一滴、涙がつたう。これで良かったのだという思いと、愛する者を失った悲しみが交互に訪れる。諦念という言葉が浮かんだ。諦めなければならないことは分かっていた。だとしたら、この辛さに堪えるしかないのだ。
くっくっくという声が聞こえた。声の方を見ると、若者の肩が上下に揺れている。若者が惨めな自分を笑っている。相沢はその悲しみを若者におもいっきりぶつけた。
「おい、何がおかしい、女に振られたのが、そんなにおかしいか、この野郎。笑うんじゃねえ」
若者が怒鳴り返した。
「笑ってなんていねえよ。こんなことで笑える奴なんている訳ねえよ」
振り返った若者の目には涙が溢れていた。もらい泣きしていたのだ。ふん、というように後ろを向くと、ビールを飲み干した。そしてガラス越しに去りゆく久美子を目で追っている。手の甲で涙を拭う。久美子の後姿がホールから消えた。
相沢は棚からウイスキーの瓶を取り出し、カウンターにグラスを二つ置くと、どくどくと注いだ。そして若者に声を掛けた。
「おい、若者、こっちに来いよ。ちょっと付き合ってくれ。飲まずにはいられない」
若者はカウンターの席につくと、おずおずと口を開いた。
「マスター、何て言ったらいいのか。あんまりにも可哀想で。マスターもそうだけど、あの女の心情を思うと…」
「何も言うな。同情の言葉も、慰みも、何も言うな。ただ飲めばいい。それより紹介し損ねて悪かった。あんまり急な出来事で、面食らっちまった。さあ、表の看板はずして来てくれ。今日はもう閉店休業だ」
「あの、俺、いや、僕、清水っていいます。若者じゃなくて清水って呼んでください」
「分かった、俺は相沢だ、よろしく。それじゃ、清水、看板頼む」
若者が立ち上がって外の看板をはずしにゆく。相沢はウイスキーを満たしたグラスを傾けた。ようやく飲み終えると熱い息を吐いた。頭がくらくらするが、まだ足りない。瓶を引き寄せ、グラスを満たす。今度は手首のスナップをきかせて喉に流し込んだ。
翌日、ずきずきという頭痛で目覚めた。目に映る天井のシミを見て、いつもの六畳の宿直室だと気付いた。辺りを見回し、薄明かりに浮かび上がった尻を見いだし、度肝を抜かれた。期待に胸を躍らせたが、すね毛が濃く男のものだと分かってうな垂れる。
記憶の糸をたぐり寄せ、その尻があの若者、清水のものだとすぐに合点がゆく。まさか、と思って尻の穴に意識を集中するが痛みはない。ふと、口の中がねばねばしているのに気付いた。まさか飲んだ?わーっと心の中で叫び、外に駆けだした。流しに行って蛇口をひねると水流を口に受け、がぶがぶと口をゆすいだ。
まさか、まさかと焦りながら記憶の糸を手繰るが何も思い出せない。むしろ思い出さない方が幸せなのかもしれないなどと考えながら、部屋に戻った。清水は尻をだして高いびきだ。ふと、その隣に小さな足が出ているのに気付いた。
布団から乱れた長い髪がこぼれている。布団をそっと剥がした。女だ。可愛い女の寝顔が目に飛び込んできた。よくよく見ると赤城君子だ。中途採用で本部の総務部に配属予定の事務員だった。一週間ほど前から研修に来ていたのだ。
その目がうっすらと開いた。その目が輝いてにこっと笑った。そして言ったのだ。
「課長、もう、起きてたの。清水君は?」
相沢が君子の隣を指さした。君子はすぐに気付いて、隣に寝ている清水の唇に長々とキスをする。すると清水が「うーん」と声を発して背中を向けた。
君子が半身を起こした。その瞬間、ぽろりと布団が落ちて形の良い乳房がぽろんと顔をだした。相沢が固唾を飲む。にーっと笑って、君子が微笑む。
「昨日は楽しかったー。課長ってすごいんだもの。何回も行っちゃった」
その時、がーんと後頭部を金槌で叩かれたような衝撃に見舞われた。何も覚えていないのだ。相沢はどうしたらもう一度お相手願えるか考えた。思い出せないのなら、やった意味がない、いや、やったことにならない。だからもう一度、と思うのだが、さて、さて。
いきなり抱きつくのも変だし、もう一発なんて林田みたいに言える訳もない。こんな場面でどう対処したらいいのかさっぱり分からない。立ちつくしている間に、清水が目覚めた。相沢の目の前が真っ暗になった。清水がごそごそと起き出して、
「あれっ、二人とももう起きてたんですか?はやいですね」
と言って大欠伸。ふと、何かを思いだしたらしく、慌てて聞いた。
「課長、本当にここで働いていいんですね。高校中退でもかまわないのですね?」
下半身をぱんぱんに張ったまま答えた。
「昨日、もし、そう言ったのなら、武士に二言はない、雇う。で、俺、どこが募集してるって言ってた?」
「風呂場担当って言ってました。女風呂覗き放題って。何か楽しそうな職場だなー。よし、ばりばり働くぞー。お袋、びっくりするだろうなー、俺が一流企業の社員になったなんて聞いたら」
「おいおい、ここは子会社だよ、一流企業っていうわけじゃない」
「どっちにしろ一緒ですよ、親会社だろうが子会社だろうが」
相沢は苦笑いして頷いた。酔っていても、仕事に関してはまともだったようだ。八王子祭りの後、上田が一身上の都合で辞めた。よっぽど恐ろしかったのだろう。それで募集をかけていたのだ。清水ならりっぱに勤めてくれるだろう。
その時、食堂で数人の女達の笑い声が聞こえた。相沢は焦って時計を見ると10時半である。早番のパートさん達の休憩時間である。おい、と二人に声をかけ、とりあえず君子を押入に入れて、慌てて店のお仕着せを着込んだ。
パートさん達の休み時間は15分。彼女たちが部屋を出たら、誰にも見つからずに抜け出せと君子に指示し、清水と一緒に宿直室を出た。宴会場担当のおばさんが二人に声をかけた。
「あれま、課長さん、また泊まりかい。あれ、いやだよー、課長。若い男を連れ込んじゃったりして、でも、なかなか可愛い子じゃない」
相沢も冗談で答えた。
「馬鹿言っているんじゃないの。男は趣味じゃない。こう見えても、女の方が好きなんだから」
「また、照れちゃって、顔が赤いよ」
夕べの酒が残っているのだから赤いに決まっている。なのに、戯れ言を真に受けて清水がやり返した。
「馬鹿野郎。そんなんじゃないわい」
肩を怒らせ歩いてゆく清水の後ろ姿をみて、相沢は目を覆った。店のお仕着である半ズボンの背中から君子の赤いスキャンティが垂れている。おばさんたちは顔を見合わせ、次いであきれ顔で相沢に視線を走らせる。ひそひそという声が後ろから聞こえた。
第十二章 茶そば
出会いと別れ、喜びと悲しみ、それらが交互にやってきて、そして去ってゆく。人生とはそんなもんだと分かっていても、失恋の悲しみの深さはそれなりに深く、やるせない思いは如何ともしがたい。そう、日々の忙しさだけが救いだった。
街でショーットカットの女を見かけるたびに心が高鳴り、久美子でないと分かってはいても、確認しないではいられない。林田はある程度事情を知っているのか、明るく話しかけてくる。気の抜けたように微笑む相沢の背中をきつく叩き「しっかりしてくださいよ、課長」と励ます。
赤城君子はあれ以来、顔を合わすたびにウインクで挨拶し、意味深な表情をするのだが、あの時に見たおっぱいしか思い出せず、肌を許しあったという感情は沸いてこない。まして久美子との鮮烈な別れと、その後の切なさが、口説こういう意欲を削ぐ。
清水はすぐに就職し、あっというまに先輩でチーフでもある岩井を子分にしてしまった。すっかりその気になって、先日も入れ墨客と一悶着起こした。今、林田が相手の心を傷つけずにお引き取り頂く接客法を特訓中だが、敬語が駄目で苦労しているらしい。
相沢は鎌田副支配人や村田のきな臭い動きを牽制しつつ、面倒な事態の到来を予感していた。とはいえ、事前に災いの芽は摘んで置かなくてはならない。蕎麦の問題である。林田が先ほどから思案していたが、諦めて言う。
「課長、悩んだって妙案なんて出ねえよ。結局、どんな言い方したって、それってまずいってこと?って聞かれるに決まってるもの。何をおっしゃる調理長、なんておべんちゃら言ったところで、後が続かねえ」
「うん、評判が今一とか、肌触りが云々とか、歯ごたえがどうのとか、どんな言い方したって蕎麦がまずいからってことになるからなー。そのまんまぶつけるか。よし、その線で行こう。林田君、一緒に厨房に来てくれ」
そう決意し二人は立ち上がった。山本統括事業本部長は蕎麦の評判が悪いことを以て全ての料理がまずいという方向へもってゆこうとしている。まずはそこを改善しなければ山本の思う壺に嵌ってしまう。そのことを言えば石塚調理長も山本に対して反発するだろうから、蕎麦に関する二人の意見に耳を傾けてくれるはずである。
石塚調理長の専門は会席料理で、関東でも大きな調理人組合の役員をしており、その世界では重鎮なのだ。従ってその料理にケチをつけるのはそれなりに勇気のいることなのである。しかし、相沢も林田も石塚の心意気に何度も接してきており、きっと分かってくれるはずだと思っている。
厨房に上がると、ちょうど昼飯の真っ最中で、みんな立ったままカレーをかけた丼飯にトンカツの切れ端を載せてかっ込んでいる。調理長が一番の早飯で、いかにも誇らしげな顔をして丼を置いた。二人に笑顔を見せると、
「おや、お二人さん、どうした、そんな神妙な顔をして」
と言って、折り畳み椅子を用意する。相沢が答えて言う。
「調理長に、お話がありまして…」
と言うと、いきなり動悸が相沢の胸を襲う。一瞬にして口の中がからからに乾いたような気がした。心やすく接しているが、一つの道を究めた人に対し、その道のことについて口を出すということ自体が恐れ多いのではないかという不安が鎌首をもたげた。
ちらりと林田を見て、肘でつついた。困惑顔で林田が口を開いた。
「いやー、調理長、そんなまじまじと見ないでください。こっちだって言いづらいことも言わなければならないことだってありますしー。そのー、何と言うか……」
どうも林田も極度の緊張に陥っているらしい。ふだん使い慣れていない丁寧語がそれを物語っている。相沢は課長としての責務を果たさなければならないという義務感に駆られ、林田と石塚の人間関係におんぶしようとしていた自分を恥じた。
「調理長、ちょっとお話があります。怒らないで聞いてください。どうか気を落ち着けてください」
そこまで言うと、石塚は手で相沢を制し、隣の座敷に二人を誘った。さっと立ちあがり、内村に何か耳打ちし、先に座敷に入って行った。二人して雁首揃えてその後に続く。二人が座ると石塚が厳かに口を開いた。
「さあ、話を伺おう。覚悟はできている。この日がいつか来ることは分かっていた。山本が考えていることは手に取るように分かる。俺を追い出し、自分の自由になる奴を入れたいんだ。そういう手合いと随分争ってきた。自分がやっているんだから、厨房だってやっているはずと思いこんでいる。だけど、俺はそんな不正などするような調理人じゃない」
そこまで一気に言うと二人をじっと見詰める。二人だけは分かっているはずだと言いたいのだ。二人は顔を見合わせ焦って同時に反論しようとした。またしても手で制し続ける。
「どこに行っても繰り返されるイタチごっこだ。味と経営は別物だとつくづく思う。味だけで勝負ができないものかといつも考えてきた。でも、最近、人間社会に生きていれば、そんなことは高望みだと思うようになった。俺もようやく大人になりかけているのかもしれない」
林田が息急き切って言葉を挟もうとする。
「調理長、調理長…」
「失礼します」
二番手の内村がお盆にお茶を載せて入ってきた。林田も押し黙るしかない。来るべき時を期待する内村は、威儀を正そうとするのだが、その嬉しさを隠しきれない。お茶をそれぞれの前に置くと、調理長の傍らに正座した。石塚が続ける。
「これだけは言い残して置きたかった。人の悪口になると思ってこれまで誰にも話さなかった。しかし、首になるのだから言わせてもらう」
林田が焦って言う。
「調理長、そうじゃなくって・・」
「黙って聞きなさい」
調理長の強い語調に林が圧倒され、調理長が続けた。
「山本は、最初、ある鮮魚と肉の業者を使うように言ってきた。勿論断った。何故なら品質に問題があったからだ。だが問題はどちらの業者もおたくの仕入れ業者リストに名前が載っていないことだ」
こう言うと、石塚はどうだ参ったかとばかり二人を見詰める。確かに臭い話だ。しかし、今は、そんなことより、調理長の誤解を解くことの方が優先された。相沢が叫んだ。
「調理長、そうじゃないんです。今日、話したかったのは蕎麦のことです。あの緑色した…」
言葉が出ず、横にいる林田を促す。
「茶そば、茶そば」
林田の合いの手に答えて、相沢が続ける。
「そう、あの茶そばの件なんです」
石塚はぽかんと口を開いて、細い目をまん丸にしている。冷静な内村は、来るべき時が来たわけでないことに気付き、心の中で舌打ちしている様子だ。調理長が聞く。
「蕎麦だって。蕎麦がどうした?今度は、まさか蕎麦にミミズが入っていたなんて言うんじゃないだろうな?」
林田が顔色を窺いながら、恐る恐る言葉を選んで言う。
「実は…、私はそうは思わないのですけど、一部の客の中には、蕎麦がまずいと言う人がいるのです。その何て言うか、歯ごたえっていうか、どうもぱさぱさしてて、しっとりとした蕎麦の肌触りがないって言うんです」
怪訝な顔をして二人を見詰めていた調理長が、がくんと肩を落とし大きなため息をつく。そして一言。
「なんだ、そんなことか…」
急に力が抜けて、もう何も言いたくないといった案配だ。力なく笑って、内村に話しかける。
「おい、内村、俺たちの蕎麦が旨くないってよ。どうする、もっと安い蕎麦に変えるか?味の分からない奴に何を出しても同じだ。どうする?」
うんざりしたように内村が答える。
「だから言ったじゃありませんか。この辺で本格的な8割蕎麦なんて出してもしょうがないって。あれは懐石で腹八分目のお客にちょこっと食べてもらうから美味しいんですよ。まして高いのに課長に言われたからって分量を増やしたりするから赤字もいいとこです」
相沢も思いだした。お客からもっと大盛りにして欲しいという要望があり、調理長にその旨伝えたのだ。調理長は困惑顔でこう答えたものだ「これってちょっと高いんだ。でも、まあ、いっか」
林田が目を輝かせ聞いた。
「その8割蕎麦って、どういうもんなんです?」
内村が調理長に代わって答える。
「あんたらがふだん食べてるのは、蕎麦粉3割、うどん粉7割の蕎麦だ。あんたら、蕎麦の歯ごたえだ、肌触りだと言うけど、俺に言わせれば、あんなのうどん粉の歯ごたえ、肌触りにすぎない」
林田の目の輝きが増した。まったく分かり易い人間だ。内村が続ける。
「8割蕎麦は、歯ごたえ、肌触りが、江戸っ子の心意気にぴったりだった。でも8割蕎麦麦なんて庶民には高値の華で幻の蕎麦って言われていた。だから、うどん粉に慣れたこの辺のお客にはもったいないって思っていたんだ」
うんうんと聞いていた林田は、さっきまでうな垂れていたことなどすっかり忘れている。
「そうじゃないかと思っていましたよ。あんなに旨くて綺麗な料理を作る人達がまずい蕎麦を出すはずがないって。やっぱりだよ。よし、これで行こう。江戸庶民には高値の華、それが今じゃ八王子健康ランドの名物蕎麦、どうです、このコピー。電通だって思いつかない絶妙なヒーリング。いいなこれ。早速作んねえと」
相沢が何と言おうと、勝手にポスターを作り壁にべたべたと貼っている林田のことだ、もうすっかり頭の中にデザインが浮かんでいるのだろう。相沢はほっと肩の荷を降ろしたのだが、石塚の態度に不安を感じた。明らかに最後通告を待ち望んでいる。
相沢はいつもふて腐れたような態度の内村と話がしたいと思った。その機会はその日のうちに訪れた。帰りしな、石塚が事務所に降りてきて、相沢を酒にさそったのだ。今日のことは水に流そうという配慮だ。林田は夜勤明けで帰った後だった。
厨房のメンバーは15人だが、その日一緒に飲んだのは調理長を含めて7人で、残りは遅番のため22時までの勤務だ。みな羽目をはずして騒いでいるようでも、やはり親方の目を意識しているのがわかる。師と弟子達なのである。
内村は調理長の傍らを離れず、ウイスキーをちびちびとやりながらも、調理長がタバコを取り出すとさっとライターで火を点ける。カラオケに興じる若手の歌に手拍子するわけでも、合いの手をいれるわけでもない。
二軒目のカラオケボックスで、石塚調理長はだいぶ機嫌がよかったのかピッチも早かった。ソファーに寄りかかり船を漕ぎだした。しまいには本格的な眠りに入り、鼾をかいている。内村がぽつんと言った。
「おやっさんは疲れているんです。料理屋なんて忙しい時間帯は決まってますから、それ以外はけっこう暇で休めるんですよ。でも、ここは違う。おやっさんがもう十年若けりゃと思います。もう45歳ですから」
「ええ、分かります。無理をしているのは」
「それに家族と離れてアパート暮らしでしょう。疲れなんて取れるわけないですよ」
しみじみとした口調に親方を思いやる心を感じた。相沢は気になることをずばり聞いてみた。
「内村さんや三番手の荒井さんを含め、メンバー全員がここにいることは反対みたいですねえ」
「ええ、おやっさんが1年だけ我慢してくれって言うから、我慢しているだけです。まして次が決まってますから。新装開店の店です」
相沢はがくっと肩を落とした。契約更新はしないと言うのは本心だった。何とかなると考えていたのは甘かったのだ。
「それじゃあ、また腕のいい調理長を探さないと」
「その点は安心してください。私の兄弟子に当たる方が一家を構えてます。おやっさんはその方に話を繋いでいますから。その方も腕はいいですから、私より3歳年上です」
ほっとしたものの、一抹の寂しさが相沢を襲う。その寂しさを吹っ切るように内村のグラスにどぼどぼっとウイスキーを注いだ。
「相沢さん、俺、そんなに飲んじゃまずいっすから」
と言ったものの、すぐにグラスに手を伸ばし口に運んだ。若手がちらちらと内村をみている。
一人が「やばー」と言うのが聞こえた。内村を見ると既に飲み干して、自分でグラスにどぼどぼと注いでいる。厭な予感がした。
やはり大虎だった。調理長が寝込んでいる隙に羽目をはずしたいのだ。首に腕を回され、さっきから相沢は内村の愚痴を聞かされ続けている。
「あのアマ、石田だ、石田。あいつ、何とかならないのかー、えー。忙しいときに来て、冷蔵庫を開けさせて、伝票をひらひらさせて、何処にあるなんて聞きやがる。見せてやるよ、そんなに信用できないのなら。でも、暇な時間、夜9時以降とか、朝8時半前とかにやってくれって申し入れたら、私には家族がいますから、そんな時間には無理ですって言いやがる。課長だろうー、石田のアマは…」
石田から山本に行ったり来たりしながら悪態は続く。その間「こらー、歌え」などと若手を怒鳴り、「それでよー、どこまで話したっけか?」などとうっぷんを吐き出すのに余念がない。相沢もしこたま飲まされて半分眠りながら話を聞く。
「あのアマ何か企んでいる。副支配人や村田とひそひそやりやがって、気分が悪くてしょうがねえ。そうそう、相沢さんに言っておくけど、相沢さんも標的になってるよ」
「標的?」
「そう標的。大広間の厨房寄りのウエイトレスから聞いた話だ。山本は相沢さんを地方のスーパーに飛ばしてやるって息巻いていたそうだよ。そのウエイトレスは山本のおごりで村田や石田と一緒に飲んだって言ってた」
一挙に酔いが冷め、ひやりとする感覚が背筋を降りてゆく。山本はそれだけの影響力を持っている。ここでの成功はこれまで以上に安藤常務と山本事業本部長の立場を強くした。山本は現在名古屋で候補地を物色中で、鼻息が荒い。
「クソー」と歯がみして目の前を睨み付けた。睨み付けられた若手が声を掛ける。
「課長、どうしたんっすか、そんな般若みたいな顔して」
「般若、どれどれ…」
内村が首に回していた腕を解き、相沢の頬を両手で挟んで顔を自分に向けさせた。
「本当だ、般若だ、般若。そう、時には、そんな顔でことに立ち向かうことも必要だ。なー、課長。よーし、飲むぞー、今日はとことん飲むぞー」
困惑顔の若手を尻目に、備え付けの受話器を取り、何本目か分からないがウイスキーのボトルを注文している。その目がちらりと横になって鼾をかく調理長に注がれた。
その日、相沢は宿直室に泊まった。ふらつく足で部屋に入り、布団も放り投げるように敷いて、ばたんと横になった。一瞬にして深い眠りへと入った。
翌朝早く、外の食堂に二人の男女が入ってきた。清水と君子だった。誰もいないことをいいことに、最初はじゃれ合う程度だったのだが、二人は次第に本気になっていった。清水が君子の首筋に唇を這わせ、その手で乳房をまさぐると、君子は堪えきれず呻くような声を発した。
喘ぎながら清水の手を取ると下へ導き、椅子から腰を浮かせて前につきだした。スカートの下で清水の手がうごめく。それを眼下に見ているだけで、じっとりと湿っていくのが分かる。二人は時間がないことが気になっていた。
早めに済ませればいいと、ようやく決意し、宿直室にもつれるように歩いていった。襖を開けると、二人ははっと息を飲んだ。相沢が鼾をかいて眠っている。清水が困ったように聞いた。
「どうする、また三人で…」
とは言ったものの、君子を独り占めしたいという気持ちの方が強かった。君子は君子で、なかなか二回目を言ってこない相沢に腹を立てており、まして、もう時間がないことで焦っていた。
「いいわよ、相沢さん疲れているみたい。ここんとこ、いつもそう。そっとしておきましょう。ここが駄目なら、更衣室しかないわ。うわー、みんなが来るまであと30分しかない」
と言うと、君子は清水の手を引いてその場から駆けだしていた。
こうして相沢は二度目のチャンスを、そしてあのめくるめくような官能の世界、最初で最後となった乱交の記憶を思い出すきっかけさえ、失ったのである
第十三章 反撃
降って沸いたチャンスを最大限に活かそうと、相沢は社長をはじめとする役員を前に熱弁を振るった。相沢は蓄積したアンケートデータをもとに、現在の成功の要因が宴会場における幅広い品揃えと安価に設定した会席料理であり、ひいては陰の存在であるの厨房の果たした役割がいかに大きいかを強調した。
この会議は、社長がどういうわけか現場の社員の意見を聞きたいということで、今日の運びとなった。社長は頷いたりしながら熱心に聞いてくれたが、他の役員達はどこか上の空で、安藤常務などは目をつむり、腕を組んだまま微動だにしない。
山本統括事業本部長は苦虫をかみ殺したような顔で、時々、相沢に睨むような視線を浴びせている。頼みの岡安専務は最初にちらりと一瞥しただけで、あとは正面を向いたままだ。かつての親密さなどお首にもださない。
今、相沢が話している内容は、山本事業本部長が社内で宣伝してきたこととまるっきり正反対のはずだ。「さて」と間合いを取り、まずいと評判だった蕎麦にも触れ、8割蕎麦に対する認識のなさを詫び、今後はそれを宣伝材料とする旨述べた。
1時間近い現況説明が終わり、最初に口を開いたのは安藤常務だ。相沢は緊張して身構えた。
「まあ、相沢君の意見は十分に拝聴した。確かに相沢君の言うとおり、健康ランドの常識を破った高級料理という山本統括事業本部長の発想はすばらしかったと思う。相沢君のレポートは、今後の参考にさせてもらおう。総務部の方へ提出しておいてくれたまえ」
こう言うと、社長を振り仰ぎ続けた。
「さて、次の出店計画について、山本統括事業本部長から報告があります。さあ、相沢君、もう下がっていいよ」
山本統括事業本部長の発想という言葉に思わず絶句した。そもそも山本は事業計画には参画していない。それは相沢を中心とした出店準備室がとりまとめたのだ。山本はそれを承認したに過ぎない。やられたという思いが相沢をぶちのめした。レポートを鞄に詰め込み、晴れ舞台を惨めな思いで退出した。
とぼとぼと歩いて古巣の企画部に向かった。惨めな思いを誰かにぶつけたかった。このままでは帰れない。今日のレポートは、山本統括事業本部長が本社で根回している厨房の不評を覆すことに力点を置いたため、相沢の主張は茶そばに言及するなど、枝葉末節に拘泥しているという印象を与えたに違いなかった。山本の嘘に反論することを主眼にしたからだ。しかし、常務は、山本が1号店を軌道に乗せ、既に次の目標に突き進んでいると締めくくったのだ。
今朝、林田にレポートを見せた。読み進むに従い目を輝かせた。興奮して相沢を激励した。よく決意したと。安藤常務と山本統括事業本部長に逆らうことがサラリーマンにとって危険な試みであることを知っていたからだ。しかし、全ては徒労に終わってしまった。
企画部に入ってゆくと元上司の小倉企画部長が笑顔で迎えた。そして応接室にさそったのだ。はじめてのことである。いつもなら、部長席の前の応接セットに座るのが常であったのだ。席に着くなり小倉が問う。
「どうだった、会議のほうは?」
「あんまり芳しくありませんでした」
「まあ、あの会議のことはあまり気にすることはない。それより、だいぶ落ち着いてきたみたいじゃないか」
「ええ、ようやく変お客が少なくなってきました。勿論皆無というわけにはいきませんが、最初に比べたら天国みたいなものです」
「そうか、それは良かった。しかし、厨房の腕が悪いって噂は本当なのか」
この言葉を聞いて相沢はぷっつんしてしまった。全てはそこから始まっているのだ。その噂にどれほど心を痛めたであろう。会議での鬱憤を晴らすかのように、言葉が奔流のように流れて止まらなくなった。
林の退職の経緯、石田の仕事ぶりや山本とのあやしい関係、瀬戸物混入事件、そして山本が厨房に押し付けようとした鮮魚と肉の業者が、会社の仕入れ業者でなかったこと。そして肝心なこと、山本が何にもやっていないことをぶちまけた。
小倉は苦笑いを浮かべながら言った。
「分かった分かった、そう興奮するな。正義感の強い相沢君が怒るのは無理はない。その林君には気の毒なことをした。でも、その石田課長と統括事業本部長が日に2回も銀行回りに出掛けるというのは本当の話なのかい」
「ええ、本当です。午前中は1時間、午後は2時間かかってます」
ふーんと考え込んでいたが、にこりと笑顔をつくると、こう言った。
「まあ、そうかりかりせず、冷静になることだ。何かが見えてくるかもしれん。まあ、僕達は君に期待しているよ。頑張ってくれたまえ」
東京から快速に乗った。相沢は小倉部長の言葉を繰り返し反芻していた。小倉は言った。
「僕達は期待している」と「僕達」とは小倉と誰のことなのか?単に会社の仲間?いや、もしかしたら専務ではないか。
「何かが見えてくる」という言葉も気になる。山本の身辺を探れという意味かも知れない。甘い期待が相沢の心をうきうきさせたが、敢えてそれを否定した。何故なら、期待した分、落胆も大きいからだ。
しかし、会社の仕入れ業者でない鮮魚と肉の業者を厨房に薦めたことに何の反応がないのはどういう訳だ。などと思案している間に、深い眠りに陥っていた。
事務所に戻ると隣接するスーパーの片桐店長が向井と話していた。片桐は「よっ」と挨拶し、相沢に席を返し、隣に移った。そして言った。
「今日の晴れの舞台、上手くやったか?」
相沢は両肩をちょこっと持ち上げて惚けてみせた。向井がにこにこしながら言う。
「しかし思い切ったね、課長。最初に読んだときは思わずどきどきしちゃったよ。それで上の方の反応は?」
「全く無視されました。期待した専務はただ聞いていただけ。終わったら、常務が次の議題があるからもういいよという調子で会議室を追い出されました」
「山本さんはどうだった?」
「それこそこんな顔してましたよ」
山本がよくやる下から睨め付けるような顔を真似た。片桐は笑いながら言った。
「その顔よく似てるよ。山本さんの表情見ているとヤクザ映画の見すぎじゃないかと思うことがある。ところで、今も向井さんと話していたんだけど、山本さんは銀行回りが好きみたいだね」
相沢はおやっと思った。小倉部長も同じことに興味を持った。
「誰に聞きました?」
「勿論、向井さんからだよ」
向井が反論する。
「よく言うよ、片桐さんが山本の銀行回りは本当か?って聞いたんじゃないか」
相沢は心の中でにんまりと頷いた。どうやら小倉部長から片桐に電話が入った。銀行回りのことを確かめろと。何かある。そう確信した
厨房へ上がってゆくと、林田と石塚調理長が何やら話し込んでいる。相沢に気付くと、二人は目配せして座敷に誘った。3人は憂鬱な顔で額を寄せ合った。今日の結果は電話で林田に話してあったのだ。石塚が言う。
「課長、よくやった。でも、自分の立場も考えろ。今後は、何もなかったように山本に話しかけろ。それがサラリーマンってもんだ。いいな、そうしろ。ただ、どうしても我慢出来ないというなら、就職は俺に任せてくれ。こう見えても人脈には自信がある」
「有り難うございます。ご心配をおかけます。でもご安心下さい。僕は負けません。あいつ等に何としても一矢報いてやります。辞めるとしてもそれが成就できてからです。それまでは何としても、どこに飛ばされようと居残ります」
「偉い、課長、それが肝心だ。サラリーマンなんて浮き沈みあってこそ成長する。復讐心を賞賛するわけではないけど、いつか見返してやるという思いは大切だ」
林田も嬉しそうに同調する。
「課長は、この世の終わりみてえな声だすもんで、ちょっと心配しちゃったよ。でも今の言葉聞いて安心した。俺も手伝うから、何とかしましょう」
「ああ、分かってますって、今日は初戦を開いたと思っている。まずは、あいつ等の鼻先にカウンターパンチを食らわせてやった。よし、やるぞ、エイエイオー」
相沢は最後の言葉を、拳を突き上げながら言ったのだ。二人は顔を見合わせ笑った。林田が言う。
「なんですか、いきなり。こっちは心配していたっていうのに」
石塚は別の反応を示した。
「いいんだ、いいんだ。から元気でも、しょげているより、ずっとましだ。それより、ここのところいろんな噂が飛び交ってる。もうすぐ厨房が代わるとか、鎌田が近い内に支配人昇格だとか、敵は本部だけじゃなく、店でも山本色を作るのに必死だ。いよいよ決戦が近づいてきているってことだ」
林田がうーんと唸った。
「敵は鉄砲も大砲も持っているってえのに、こっちは厨房の包丁だけってな案配ですね。手も足もでねえ。なにか対抗手段はないですかね?」
調理長が笑いながら言う。
「肉弾戦なら包丁持ってる方が強い。でも情報戦では包丁は何の役にも立たない。奴らはやりたい放題だ。うちの連中もそうとうかりかり来ている」
「そりゃそうでしょう。今度の厨房のオーダー係り、鎌田副支配人がやってるでしょう。あの人も管理職だってのに何考えているんだ。管理職ならもっとやることがあるはずなのに。いや、いや、そんなことどうでもいいけど、鎌田の嫌みは相当ひどいって話ですね?」
「ああ、俺がいるときは普通にオーダーを入れてるけど、いない時なんか、ひどいらしい」
相沢が頷きながら言った。
「辞めるのを待っているんです。みんなが怒って辞表を叩きつけるのを期待しているんですよ。調理長、絶対に挑発にのっては駄目ですよ」
「ああ、俺は腹を括ってる。問題は若い連中だ。特に三番手の荒井がいつ爆発するか心配なんだ。よく言って聞かせてるけど、あいつは怒ると怖い」
「あのおとなしい荒井さんが爆発する?」
相沢がすっとんきょうな声をあげた。調理長がにやにやしながら答えた。
「あいつは本来であれば二番手でもおかしくない腕を持っているし、それなりの修行も積んでる、でも、あいつは一度抜けているんだ。5年ほど、遊んだ」
林田が聞く。
「遊んだって、何して遊んでたんです?」
石塚は二人を見ながらにやにやしている。言っていいものか迷っている。凝視する二人に促され、まあいいかといった具合で口を開いた。
「君たちの嫌いなヤクザ。組に入っていたんだ。奴だけ長髪を許してるのは、当時、髪も眉毛も剃ってたから人相を変えさせている。組から逃げてきた。頼られたら、昔の可愛い弟子だ、断る訳にはいかない」
二人は意外な話に顔を見合わせ、あの荒井さんが…と絶句した。石塚が慌てて付け足した。
「そうそう、君たちがもう一つ嫌ってる入れ墨はしてないから安心して」
その言葉を聞いた瞬間、相沢の脳裏に閃きが走った。口を開け、じっと一点を見つめる。林田が怪訝そうに聞く。
「課長、何、思いついたん?その顔は何か閃いて、それを、どうやらかすか考えているって顔だ」
罠だった。罠を思いついたのだ。敵が乗ってくれば一挙に挽回できるかもしれない。憎々しげな眼差しを送ってきた山本の鼻を明かすことが出来る。実に良いアイデアだった。石塚と林田を交互に見て、相沢が口を開いた。
「情報戦に勝てるアイデアを思いつきました。ちょっと聞いてくれますか。汚い手だけど、相手はもっと汚い。それだったら、おあいこだと思うんです」
二人の目が輝いた。林田が答える。
「汚いって、結構じゃないですか。やられる前にやる。男同士の争いに汚いも糞もあるもんですか」
相沢が声を低めて二人に説明する。
「実はですね、荒井さんより、内村さんの方がよっぽどヤクザっぽいでしょう。だったら内村さんを元ヤクザにしたらいいじゃないですか。内村さん、この間聞いたら、いつも長袖なのは冷房が駄目っていうでしょう。調理服も七分袖だし、いかにも入れ墨を隠しているみたいじゃないですか」
石塚が付け加える。
「あいつは潔癖性だから、商売女は駄目だし、他人が入った風呂には絶対入らない。つまり、あいつは自分の背中を誰にも見せたことがないってことだ」
林田が意地悪そうに言う。
「奴らと同じように噂を流す。それを山本が鬼の首でも取ったみてえに本部で問題にする。見物ですねえ。そして、山本に引導を渡すのは課長」
頷きながら相沢が答える。
「ああ、山本は絶対に乗ってくる。鎌田の嫌みにじっと堪えている厨房に対して苛々しているはずだ。絶対に乗ってくる。それと、もう一つ、林田さんにお願いがあります」
相沢は本部長と石田の関係の決定的な証拠が欲しかった。そのことを言うと、林田は二つ返事で引き受けた。小倉部長が最もほしがっている情報だ。それには証拠写真がなくてはならない。それも含めて頼んだ。汚いと思うが仕方がない。
三人は残忍な笑みを浮かべ、低く笑った。そしてその笑い声は次第に大きくなっていった。悪巧みほど、男達を魅了するものはない。善悪より勝ち負けである。
噂は瞬く間に広がった。フロント嬢と付き合っている厨房の若手が寝物語にうっかり秘密をしゃべってしまった。組から追われている人間が厨房にいることを。ウエイトレスと付き合っているもう一人の若手は、その元ヤクザが入れ墨までしていることを漏らしてしまったのだ。噂が広まらないなずがない。
誰でも、人には言えない秘密を心許せる友人に話したくなるものなのだ。問題はその友人にも心許せる友人がいると言うことだ。或いは、根っから秘密を保てない性格の者もいる。噂とはこうして広まるのである。
あれ以来、内村は外股で肩を揺すって歩いている。むっつりはそのままだが、東映ヤクザ路線の俳優よろしく、顔に凄みが増した。最初の変化は、オーダー係りに徹している管理職、副支配人の鎌田に現れた。
あれほど厨房を苛立たせた副支配人の嫌みが皆無となり、おもねるような声音に変わったという。村田はお礼参りが怖いのか敵意を含んだ視線を厨房に向けなくなった。しかし、この副支配人と村田の二人の変化は、一時を堪え忍ぶ仮の姿だ。その巻き返しには余程自信があるらしい。
そんなある日、山本が相沢をその個室に呼んだ。部屋に入ってゆくと、山本はソファーに腰掛け、最近始めたパイプの煙をくゆらせている。座れとは言わない。立ったまま待っていると、口をへの字に曲げたまま口を開いた。
「相沢君は、ここのところ変な噂がたっているのを聞いているかね?」
「いいえ、噂というと、どんな噂ですか?」
山本は大げさに驚いて見せて、この実情に疎い現場の管理者を見下した。
「おい、おい、君は何のためにわざわざ現場に来ているんだ。何のための管理者なんだ。料理が旨いかどうか味見するためだなんて思っているんじゃないだろうな」
この嫌味にはかちんときたが、ぐっと堪える。山本が勝ち誇ったよう顔を満足げに歪めた。片桐が言っていた、東映ヤクザ路線の顔とはこのことかと合点がゆく。
「いいか、驚くな、厨房の二番手の内村は入れ墨をしている」
こう言うとじっと相沢の目を覗き込む。相沢は驚愕の表情を浮かべるとともに、次に苦渋に満ちた顔を作る。それを知っていながら、今まで隠していたという表情なのだが、どこまで山本がそれを読みとったのかさっぱり分からない。
山本が引導をわたすような表情で言った。
「君の役目は内村の入れ墨を確認することだ。確認出来たら、苦渋の選択だが、厨房を全員入れ替える必要がある。いいか、俺たちはオープン以来、入れ墨対策にやっきになってきた。ところが、その内部に入れ墨者がいたとなればどうなる。責任は重大だ、分かるな?相沢」
「はい、分かりました」
うなだれて個室をでると、ぺろりと舌をだした。小躍りして向井の机の前まで行った。向井は目配せして石田の存在に気付かせる。相沢はすぐに気付いて、がくっとうな垂れる姿勢に戻した。石田は銀行回りに出掛ける準備に余念がなく、小躍りした相沢には気付いていない。
個室が開かれ、山本が事務所にいる石田に目配せしている。山本は余程機嫌が良いと見えて、珍しく事務所に声を掛けた。
「ちょっと銀行回りしてくる」
向井と相沢が複雑な顔をして、もう参りましたとばかりに声を掛ける。
「いってらっしゃいませ」
石田がぷりぷり尻を振って出ていくと、ようやく安心して相沢が話し始める。
「いよいよ、引っかかってきました。あと一押しです。次の段階に移りましょう」
次の段階とは、村田に内村の入れ墨をちらりと見せるのだ。勿論入れ墨はシート状になった貼るタイプのものだ。村田がそれを目撃し、山本にご注進に及べば嘘はすっかり真実に変貌する。
そして、翌日、昼過ぎ、午後2時、村田は厨房の奥で休む内村のちょっとまくし上げた右腕から現れた紛れもない濃い青色をした文様を目撃する。そしてあたふたと、その場を後にした。その後ろ姿を見て、内村がにやりと笑った。
第十四章 再会
ウエイトレスの村田が内村の入れ墨を目撃してから一週間が過ぎようとしているが、事業本部、健康産業事業部、そして本社からも、これと言った動きは伝わってこない。一方、健康ランドにおいては、これまでにないほどの平穏な日々が続いていた。
そんなある日の午後、相沢は館内放送で最寄りの館内電話にでるように呼びかけられた。マッサージ室のオーナーと話していた相沢は、部屋の隅にある受話器を取った。石田の声が響く。
「課長ですか?本社企画部の小倉部長からです」
その声に疑わしげな響きがある。小倉部長が直接電話してきたのは初めてのことで、まして小倉は山本統括事業本部長と出世争いのデットヒートを演じている。山本が寝物語に小倉のことを話していたとしてもおかしくはない。小倉が押し殺したような声で言う。
「相沢君か?どうもそっちの旗色が悪くなってきた。あのことは知っているのか。厨房の内村っていう奴が入れ墨をしているという話を」
「小倉部長、どこでその話がでたのですか?」
「役員会で安藤常務が暴露したらしい。せっかく、こっちが相沢君の言うことも一理あると思った矢先、相手は反撃に転じた。どんなに腕が良くて信頼に足る人間でも、会社の方針を無視するようではこのまま放置出来ないという結論に達したようだ」
相沢は笑いを押し殺して答えた。
「しかし、安藤常務の言っていることが本当だという保証はないんじゃありませんか?」
「だから、石塚調理長を呼んで、確かめた上で解雇を言い渡すこととなった」
「しかし、調理長があくまでも否定したらどうするつもりなのです?」
「それはないと思う。何故なら、鎌田副支配人が内村の入れ墨を目撃したのだから、否定
は出来ないと思う。山本に言わせれば、鎌田副支配人は館内でも相当人望があって、ヤク
ザ対策でも陣頭に立って指揮した柔道5段の猛者だというじゃないか。その鎌田が石塚調
理長と対決してもよいと言っているらしい」
予想を上回る早さで事態は大きく動き出していたのだ。しかも内村の入れ墨を目撃した
のが村田ではなく鎌田ということになっている。恐らくウエイトレスの村田では役不足と思ったのだろう。
相沢は迷っていた。小倉部長は紛れもなく相沢の味方である。真実を話して安心させて
やりたい。しかし、敵を騙すにはまず味方から、ということもある。相沢の沈黙に小倉は動揺したようだ。
「おい、相沢君、君は知っていて黙っていたわけじゃないだろうな。そうだとしたら、どうなるか分かっているのか。もし知っていたとしたら、君も同罪だと安藤常務が言っていたそうだ」
どうやらその口振りから小倉部長のバックにいたのはやはり岡安専務だったのだ。柔和な岡安の笑顔が脳裏に浮かぶ。胸が熱くなる。しかし、心を鬼にして答えた。
「確かに山本事業本部長に呼ばれて、そのことを確認するよう指示されました。まだ確認
は取れていませんが、確かめた上で本当のことを報告するつもりです」
「じゃあ、知らなかったんだな、まだ確かめていないのだな?」
「ええ、まだ確かめてはいません」
「それを聞いて安心した。実は専務もそのことを心配していた。常務は厳しい人だから言
ったことは必ず実行する。しかし、ここだけの話だが、もし、知っていたとしても、知らなかったと言い張ればいい」
これを聞いて目頭が熱くなった。
「ご忠告、ありがとうございます。でも、私を信用してください。私は決して人の期待を裏切るような人間ではありません」
ふと、直接の上司を裏切ろうとしていることを思い出し付け加えた。
「まあ、それは人にもよりますが…、ところで一つ聞いてもいいですか?」
「何だ?」
「部長は片桐店長に山本さんの銀行回りの件を確認させましたでしょう?私が部長に話し
たその日にです。つまり、施設の責任者がそこの経理課長と男女の仲であっては不都合だ
とお思いなのでしょう?」
一瞬の沈黙の後、答えた。
「基本的には恋愛は個人の問題だから会社は干渉しない。しかし、もしそうであったとし
たら、間違いを未然に防ぐためにもどちらかを異動させるべきだろうね」
「でも、もし就業時間中にホテルへ連れ出していたとしたら、どうです?」
小倉は即座に答えた。
「そんなことは許されることじゃない。会社に知られれば即刻首が飛ぶ」
「調べましょうか?」
やはり沈黙だ。今度は長い。じっと待った。小倉の口が開いた。
「やめときなさい。そこまでやることはないでしょう」
この言葉を聞いた時、相沢はどこかほっとする自分を意識した。人は時に悪魔的な誘惑に駆られ思い悩む。しかし、そのこと自体で責めを負うことはない。責めを負うのは最後の一線を越えた時のみである。小倉は相沢よりましな人間だということだ。
林田が撮ってきた写真には、ホテルから出てくる車のフロントガラス越しに、紛れもなくあの二人の顔が写っていた。その生々しさに思わず息を飲んだ。人間は浅ましい。しかし、自分のしたことも同様に浅ましいと感じた。小倉も同じ感性を持っていたのだ。
「小倉部長」
「何だ」
「石塚調理長を呼び出すのは誰ですか、それと一人だけですか、つまり内村さんは呼ばないのですか?」
「呼び出しをかけるのは総務部課長の山田君だ。それから内村さんは呼ぶわけにはいかな
い、その意味はわかるね。兎に角、石塚さん一人呼ぶ手はずになっている」
「では、入れ墨を入れていなければ、内村さんが本社に行って問題ないですね」
「勿論だ、入れ墨を入れていないと証明できるわけだしね」
「分かりました。もし、内村さんが入れ墨をしていないと分かったら、私は内村さんと同行いたします」
一瞬の間があった。
「ふふふ、だいぶ自信がありそうだな。分かった、そうしてくれ」
小倉はどうやら相沢の意図をある程度理解したようだ。小倉が思わず漏らした含み笑いはそのことを物語っていた。以心伝心とはこのことを言うのであろう。
電話を切ると、相沢は本部の山本に電話を入れた。山本は出張中だったが、シナリオ通
り、伝言を秘書に残した。こう伝言した。「確認しました。内村の背中には何もありませんでした」と。
山本が内村の入れ墨の件を確かめろと言ったのは、相沢が真実を隠蔽していたことを証
拠立てるためだ。確認し、入れ墨はなかったと伝言したことがその証拠となる。山本はそのメモを相沢の背信行為の証拠として大事に取っておくだろう。
事務所に戻ると石田が話しかけてきた。
「小倉部長さんが電話かけてくるなんて珍しいわね。何かあったの?」
「ああ、ここに来る前は企画部にいた。以前の仕事についての問い合わせだ」
「あら、そうなの。ねえ、ねえ、それよりこの間、林さんを街で見かけたの。よれよれのジャンパーを着て歩ってた。まだ就職していないみたい」
石田は林の失業について何の責任も感じていない様子だ。相沢は信じられない思いでため息をつく。
「うちのパパの会社で経理を募集しているんですって、林さんに紹介してあげようかと思って」
相沢は答えなかった。石田の夫は地場産業の工場で経理の仕事をしているという噂は聞いていた。しかし、不倫関係を知られた男を本気で紹介するだろうか。いや、林がいくら求職で焦っていたとしても、石田に頭を下げるとは思えない。
「少しは悪いことをしたと思っているわけだ」
石田の顔が見る見るうちに朱に染まる。怒りをあらわにして言った。
「何が悪いって言うの、私が何をしたって言うのよ。まるで自分だけが正しいみたいなアンタの態度は頭にくるわ。いつか罰があたるわよ。ふん、今に見てらっしゃい」
ぷりぷりと尻を振って事務所から出ていった。二階の鎌田副支配人のところへ行くのだ。二階の反支配人グループは確実に勢力を伸ばしている。何故なら施設のトップがそのバックにいるのだから。
ふと、石田のバックが机の上にあるのに気付いた。事務所には誰もいない。バックの中
にキーホルダーがある。その中に個室の鍵もある。山本が不在の折り、石田が鍵を使って
部屋に入るのを何度か見ている。もしかしたら、机の鍵も持っているのではないか。そんな気がした。あの部屋に何か胡散臭いものを感じていた。
バッグに手を伸ばそうとしたその時、キーというドアが開く音がしたので、慌てて振り向いた。清水だった。ほっと胸をなで下ろした。
「課長、どうしたんですか、鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔をして」
「ああ、ちょっと考え事していたんで、ちょっとびっくりしただけだ。」
「それはそうと…」
いつになく真剣な表情だ。まして言いよどむなど清水らしくもない。
「どうしたんだ?」
「実は……君子のことなんですけど。課長はその後君子と付き合っているんですか?」
「いいや、俺はそっち方面はあまり得意じゃないし、清水と付き合っているって林田から聞いたから、諦めたんだ。もし、やったことを少しでも覚えていたら、もっと積極的に出
られたと思うけど」
清水はこの言葉を聞いて安心したらしく、下を向いて笑いを堪えている。ようやく笑いが治まるとにやにやしながら言った。
「そうですよねー、覚えていないんじゃ、やったことにはなりませんからねー」
そこへ林田がカラオケ大会の審査を終え戻ってきた。そしてさっそく冗談を飛ばす。
「あれっ、マズイところに出くわしちまったなー。お二人きりでしみじみと愛を語らってたとこだったんでしょう。人の恋路の邪魔する奴は、ってこともあるし、上でもうちょと
向井支配人と話してくるか」
清水が、がくっと肩を落とし反論する。
「先輩、その冗談、とっくに終わってますよ。お願いしますからもう止めてください。考えただけで気色悪くて背筋がぞくぞくしてきますから」
「分かった、分かった。女ともやってるみてえだから、両刀使いってわけだ。だけど、課長は、愛するお前を裏切らねえと思うからいいけど、あの女はやめにしておいた方がいいぞ。誰とでも寝る女なんて女房にも恋人にも向かねえ」
清水はこの一言を聞いて一瞬怒りの表情を見せた。しかし、すぐに肩を落とし、頷いた。
「そんなこと言われなくとも分かってます。でも、何つうか、胸が苦しくって、切ないというか…、分かるでしょう?林田さんだって経験あるでしょう?」
「馬鹿野郎、お前の数十倍数百倍経験している。でも、諦めることだって時には必要なんだ。辛くとも諦める。これが男の美学っつうもんだ。それに何が高鳴る心だ。それは心なんてもんじゃねえ。キンタマだ」
「キ、キンタマ?」
「そう、キンタマ。いいか、そこから十発も抜いてみて、それでも心が高鳴るんなら本物だ。そん時は俺も応援してやる。そうだ、今日あたり行ってみっか、ファッションマッサージへ。本番もあり、どうする」
元気のいい声が響く。
「ごっつぁんっす」
困惑顔で林田が答える。
「そうくるか。最もまだ初月給もらってないからな、それはそれでしょうがねえ。課長、どうです、一緒に、奢りの割り勘で?」
「そう言われても…」とは答えたものの、相沢の心は決まっていた。「是非ご一緒に」だ。
今日は無性に女を抱きたかった。君子のことでは欲望を発散したというより、逆に貯め込んでいるとしか思えなかったし、久美子のことでも鬱積した思いが心の底に澱んでいた。だから息せき切って答えた。
「でも、今日は暇だし、やることもないから付き合ってもいいよ」
「あれー珍しいな、課長がそんな所に付き合ってくれるなんて。よし、今日は三人で行きましょう。たまには羽目をはずさねえと、人生の機微にふれることも出来ねえ。そう、商売女との機微、分かりますか?」
「いや、教えてくれ、その機微ってやつを」
「それじゃあ、教えてさしあげます。例えばストリップ。そこに入ったらスケベ心がストリッパーへの思いやりになる。顔が綺麗でも、見惚れて『綺麗だ』なんて呟いちゃいけません。俺の関心はただただあんたの下半身だけという顔をしなければなりません。そのスケベ心をストリッパーが笑う。こうしてストリッパーはお客と五分と五分になれる、わかりますか?」
「まあ、何となく」
「ファッションマッサージでも同じです。私はお金を払うことでしか、女と交渉が持てません、情けない男ですってな顔でお金を払うんです。こういう顔をすると、女も、しょうがねえ、一発でも二発でもやらしてやるか、お金ももらってることだし、って気になるわけです。」
「ほーなるほど、うーん、そういうことか、なるほど」
相沢が何度も頷く。それを横目に林田の舌は滑らかだ。
「君みたいな子が何故こんなことしているの、なんておためごかしのセリフを吐いちゃいけません。だって、相手はそんな人間的な触れあいなんて求めていねえもの」
その日、三人は一杯引っかけて林田の行きつけの店に繰り出した。相沢は酔って血行が
が良くなっているせいか、どきどきという胸の鼓動を感じながら店の門をくぐった。ひさびさのことで緊張しているのかもしれない。
待合室でもウイスキーのダブルを注文した。しかし、あの夜のことを思い出した。覚え
ていなければやったことにはならない。運ばれたグラスをちびりちびりとやりながら、林
田がおすすめの源氏名「いすず」の順番を待った。
待つこと15分、最初に清水がそして林田が消えた。林田は振り返りつつ微笑んだ。その微笑みの真意など気付かず、相沢は照れ笑いを返した。そして相沢だけが残された。胸の鼓動が高まって、下半身がむくむくと起きあがる。
そしてとうとう相沢の順番がやってきた。案内された部屋に一歩足を踏み入れる。薄いカーテン越しにスタイルの良いシルエットが浮かび上がった時、ほっと安堵のため息を漏らす。かって10センチもあるハイヒールに騙された。足の短い女だった。
カーテンが開かれ、「どうぞ」という声を聞いた。相沢は気恥ずかしく視線を合わせられず、俯いていた。その視線は、女のそのまっすぐに伸びた脚、黒のふりふりの付いたパンティ、締まったウエスト、ブラジャーからこぼれた乳房、と這うように上っていった。さぞかし、やにさがった顔をしているだろうと自分でも思った。
目と目があった。お互いあっという声をあげた。女は鵜飼則子だった。
第十五章 悲しき性(さが)
通された部屋は十畳ほどあり、隣の湯殿は本物かどうか分からないが、大理石らしき床板が敷き詰められ、ピンク色のジャグジー風呂は二人で入るには大きすぎるほどで、相沢にとっては初めての高級感溢れる店だった。
ベッドは真新しいシーツに変えられているとはいえ、先ほどまで別の男がいたことは確かで、商売用とはいえ則子の喘ぎ声がこの空間に響いていたはずである。健康ランドにいた則子と目の前の則子の落差に、相沢は戸惑いを感じて、以前の関係をとりもどせずにいる。
則子はベッド近くに置かれたソファーに脚を組んで座り、そっぽを向いたままタバコをくゆらせている。薄い眉毛、色濃く引かれたアイシャドウ、妙に照明を反射する口紅、どれも相沢にとって初めて見る則子だった。
はーとため息をつく。気詰まりは如何ともしがたく、かつての上司である自分が、元部下を金で買うなんて許されることではないなどと、屁理屈が頭の中を駆けめぐる。林田の教えを思い出したが、こんな場面でどう応用したものかさっぱり分からない。
そして林田が個室に消えてゆく刹那、相沢に見せた笑みの意味をようやく悟った。最初から計画していたのだ。相沢の相手に則子を選んだのは林田だった。何故そんなことをしたのか、後で問いただしてやると息巻いてみたものの、緊迫した空気を変えるほどの元気も勇気も沸いてこない。
よし、いっそのこと、今日は諦めようと思った。そして言った。
「招かれざる客みたいだな。やはり元上司が…」
と言って言葉に詰まった。何を言おうとしているのだ?元部下を買う訳にはいかない、なんて言えるわけがなかった。軽口の癖は治りそうもない。せめてきっぱりと立ち去ろうと思った。そして立ち上がったその時、
「それ…」
と言って則子が指差した。指の先、自分の下の方を見ると夏用のスラックスの前がぱんぱんに張って山のようになっている。咄嗟に横を向いて隠したが、今更遅い。意志とは裏腹な肉体が恨めしい。
恐る恐る則子を見た。ふん、とばかりに鼻を鳴らし、またしてもそっぽを向いた。プライドがずたずたになった。軽蔑されたまま立ち去るわけにはいかない。どうしたらいいか逡巡した。そして則子がちらりと相沢に挑むような視線を向けたのだ。二人の視線は絡み合い、時に火花を散らした。
そして蔑むような視線が再び下半身に向けられた時、理性がぶっ飛んだ。その刹那、相沢は我を忘れて則子に襲いかかった。欲望をむき出しにして覆い被さった。両手首を押さえ、勃起したそれを柔らかな腹に押しつける。怒りがその欲望の底にあった。
「客に向かって、その態度はないだろう」一瞬、心に浮かんだ罵声がこれである。接客業の悲しい性だろうか?
則子は則子で必死に抵抗する。手首を振り解こうとめちゃくちゃに動かした。そして、
「やめて、課長、お願い、やめて」
と、悲しげな声を上げたのだ。則子は自分のその台詞に唖然とした。まるで生娘ではないか。毎日何人もの男をくわえ込んでいるというのに。どうしよう。しかし、始めてしまったからには続けるしかない。演技を、である。
相沢は抵抗する則子のなまめかしさに欲情をがそそられた。ブラジャーをはずし、その乳首に吸い付いた。則子は尚も抵抗を続けた、でも、そろそろ・・・、うーん、もういいかと思った。だから「あっ…」と切なそうな声をあげ抵抗をゆるめてゆく。そして、
「か、課長…駄目、駄目…ああ・・・」
と次第に喘ぎ声を上げ始める。欲望がじわじわと沸き上がる。演技がかえって欲望を誘ったのである。終いには相沢の首に手をまわし、自ら唇を求めた。
ことが終わり、相沢は虚脱したようにベッドに横たわっている。則子は鏡台の前に座り、ほつれた髪を整えていた。則子は相沢に惹かれてはいたが、これまでの自分の人生を思えば最初から別の世界の人間だと感じていた。だから相沢の誘いをやり過ごしたのだ。
でも、体が一つになった時に感じた喜びはひとしおで、自ら張り巡らせた垣根を飛び越えられたと感じた。なのに、ことが終わって相沢が吐いた一言が則子に冷水を浴びせることになる。「ご免、つい、かっとなっちゃって」と言ったのだ。
拒む素振りはしたが、本心ではない。抱いて欲しかった。それが「つい、かっとなって」襲ったということか。むかっ腹が立った。愛おしくて抱いたのではないと言っているようなものだ。その怒りの感情が単なる言いがかりに過ぎないのは分かっていたが、則子は臭い芝居をしてしまった自分がやはり許せなかったのだ。
相沢は無理矢理犯したと思いこんで、自責の念にかられているらしい。ふと、林田とのやり取りを思い出した。一ヶ月ほど前のことだ。今日と同じように驚きの対面となった。でも、則子はふて腐れたりはしなかった。
そして、林田も緊張していた。だから、林田らしからぬことを言ったのだ。
「則子、だめだよ、こんな商売してちゃー」
則子は笑いながら答えた。
「そんなこと言うなら、やらしてあげない」
林田がにーっと笑った。その顔が可愛かった。
「ごめん、ごめん、つい緊張しちまって、おためごかしなこと言っちまった」
「しょうがないよ、突然の再会だし」
「まったく、思いもしない突然の再会だ。でも、会いたかったー、本当に会いたかったんだ。則子が消えちまってからというもの、気張っても気張っても、元気のゲの字も出なかった」
と言うと、則子の手をとった。暖かくて柔らかな手だった。そしてすっと引き寄せられ、抱きしめられた。「会いたかった」と何度もくりかえし、そのたびにぎゅっと力を込めるのだった。
則子の心も体も次第に溶けてゆく。林田のぬくもりが胸から体全体へと広がって行き、今日の疲れを癒してくれる。ずっと、そうしていたかったが、時間も気になった。林田は値段の安いショートのお客だ。でもサービスしてやろうと思った。
体を少し離し、指先で林田の顎を上に向け、唇を近づけた。林田が驚いて言った。
「キスは大事な人に取って置くんじゃ・・」
体はゆるしても、キスは恋人のために取っておくという商売女の唯一のプライドのことを言っている。ふふっと笑って、則子は林田の唇を塞いだ。
その後、林田は豹変し、もう一回、もう一回とねだり、最後には土下座して頼んだ。それでも時間内に終わったのだ。ふっふ、と思い出し笑いを漏らした。それなのに何故、今日はこんなことになったのか?やはり相沢にこんな姿を見られたくなかったのか?
相沢はのそのそと立ち上がり、着替え始めた。その姿を鏡ごしに則子がじっと見詰める。どう対応したものか迷っていた。互いの欲情が果てるまで絡み合ったのだから、気心が通じてもよさそうなのに、二人の心は離れたままだ。
相沢が着替え終わり、立ったまま何か言おうとしている。則子の心は揺れた。「外で会いたい」という言葉を期待する自分に舌打ちした。一瞬、食事したり、ドライブしたりするシーンを思い浮かべた。普通の恋人みたいに。しかし、そんな思いとは別なところから言葉が出たのである。
「相沢さん……、もう来ないで」
相沢がじっと見詰める。則子の心情を推し量るように。則子も毅然とした表情を保持している。「分かった」と呟くように言って、踵(きびす)を返した。ドアに手を掛け、一瞬、動きを止めた。則子の鼓動が動きを早めた。しかし、相沢は後ろも振り向かずドアから消えたのだった。
則子は短くため息をついた。相沢とはもう二度と会うことはない。一抹の寂しさはあったものの、これで何もかも、ふっ切れたと思った。
林田と清水が待合室で待っていた。林田が相沢の顔を見て言った。
「だいぶ抵抗されたみたいですね」
「えっ、ど、どうして分かったの?」
「だって、顔、引っかかれてますよ」
相沢が慌てて顔に手をやって血の滲んだ傷を探し当てる。そう言われればひりひりしていた。急に林田に腹がたってきた。
「林田君、ひどいじゃないか、何もかも知っていて、ここに連れてきたな」
林田がにこにこして、
「何を怒ったふりしてるんですか、良かったくせに、おい、清水行くぞ」
と軽く受け流し、出口に向かう。
外に出ると林田は清水の肩を抱き、なにやら話している。追いつくと、林田の声が聞こえてきた。
「俺も、愛の真理に気づいたのは、つい最近なんだ。動物王国って知ってるだろう、ムツゴロウさんがやっているやつ?」
「ええ、何度か見たことがあります」
「面白かったのは、ムツゴロウさんが、犬のチンポコをイタズラしたんだ。すると、犬はどうなったと思う?」
「さあ、どうなったんです?」
「それが、人間様と一緒で、ムツゴロウさんに必死ですがりついたり、顔を舐めたり、しっぽを振り続けるんだ。見ていて身につまされるほど、やりたい一心の男とそっくりだった」
「そして?」
「ムツゴロウさんは、その犬を行かせてあげたんだ、つまり、抜いてやった。その後、ことを終えたその犬の態度が面白いんだ」
「いったい?」
「人間様と一緒さ。背中を向けて、ムツゴロウさんが少しでも触ろうものなら、うるさそうに邪険にして、逃げ回っていやがった。掌を返すってのは、ああいうことだろうな」
「つまり人間も同じということですか?」
「そういうこと。何発やった後でも、愛おしいと思えれば、それは愛、それほどでもねえと思えば、欲情ってことだ。おい、今日は何発やったんだよ?」
二人は肩を組んで、押し問答を繰り返している。相沢はぼんやり則子のことを思った。今、自分は則子をどう思っているだろう。やはり、愛おしい。でも、愛とは違うような気がする。
今日、相沢は則子と会えたことが嬉しかった。帰り際、則子が何故あんな風な態度にでたのか理解に苦しんだが、二人は狂おしいほどに燃えたのは確かなのだ。
「何故、僕の前から消えた?」
「何も言わないで、この一瞬一瞬を大切にしましょう」
喘ぎながらの一言が蘇る。相沢にとって忘れられない一時だったのだ。突然、大きな笑い声が響いた。林田が振り返って怒鳴った。
「課長、こいつ3発しかやってねえのに、やっぱり君子のことは勘違いでしただって。まったく若いのにだらしがねえ。俺だったら5発はやらねえと、本当の愛かどうかなんて、分かんねえけどな。とにかく、君子のことは諦めるそうです。あんな女、ろくでもねえからな」
相沢は素直な気持ちでこれに答えた。
「そうかな、いい子だと思うけど」
「そんなこと言って、まさか、やらしてもらったんじゃねえんでしょうね」
清水が顔を引きつらせ笑いながら言う。
「それが、課長ったら、笑っちゃいますよ。あんなにがんがんやって、俺なんか出る幕ないくらいだったのに、課長、酒飲みすぎてて、やった記憶をなくしちゃっているんだもだから、やったことにならないって、嘆いていいるんですもん、ガッハッハ」
もう辛抱たまらず歩きながら笑い転げている。憮然とした相沢と、呆然とした林田が、互いに顔を見合わせた。目をまん丸にして林田がぼそっと言った。
「今、な、何て言った。課長と清水と君子の3人でやったみたいなこと言わなかったか?俺の聞き違いじゃなければ、そう聞こえたけど」
清水がこともなげに答えた。
「ええ、宿直室で大乱交しちゃいました、3人で」
林田が叫ぶ。
「何てこった!あの女、佐々木ともやってるし、今井とも…、その上…」
動揺して言葉が続かない。ようやく口を開いた。
「課長ー、何でそんないいことやるのに俺を呼んでくれなかったん?俺は則子を諦めて、金髪のスエーデン女で我慢したっていうのに、随分と冷てえじゃねえか」
「林田君は、その晩、いなかったんだから誘えるわけがないよ。それより、もしかして、林田君は君子に振られたんじゃないの?」
清水がそうだそうだと合いの手をいれる。憮然として林田が答えた。
「振られてなんかいねえよ、ケツ触ったら、バシって頬を張られただけだ」
相沢と清水は腹を抱えて笑った。清水が笑いながら言った。
「偉そうに誰とでもやる女は女房にも恋人にも向かないなんて言ってて、結局、自分もやりたかったんじゃないですか、先輩こそ旦那にも恋人にも向かないですよ」
二人は笑い続けた。何とも言えぬ爽快な笑いだった。林田もつられて笑っている。目的を達した男達の満足感がそこにあった。
ようやく笑い終えると相沢が聞いた。
「そういえば、則子はあの鯨井組の堤と知り合いだったのかな?」
「いや、俺も気になって聞いたけど、否定してた。だけど、則子の言うことなんて分かったもんじゃねえ。俺は知り合いだったと睨んでいる」
「そいつに言われて、あんな所で働かされいるんだろうか?」
「いや、それはない。あいつは目標を持ってる。小さくてもいいから自分の店が持ちたいなんて抜かしてたけど、あれは本心だと思う。もう二千万貯めたって言ってたから」
ふーんと頷いた。確かに則子は強い意志の持っている。もう一つ気になることを聞いた。
「でも、やっぱり俺とは会いたくなかったんじゃないかな?」
「ええ、だと思ったから、会わせたんですよ。則子は目標を持ってる。でも心の何処かに疚しさを持ってた。疚しさを取り除くにはきっつい現実に直面するのが一番」
「俺と会うことか?」
「ええ、そうです。疚しさをもっている限り、成功なんておぼつかない。そんな疚しさなんて捨ててしまえばいいんです」
「そういうものかな」
「ええ、そういうものです」
林田の横顔をちらりと見た。その顔にどこか哲学的な雰囲気を漂わせていた。
翌日、出勤して事務所のドアを開けると、向井支配人が立ち上がって相沢を迎え、ちらりと視線を石田の方に動かし、注意を促す。そして口をこわばらせ、決められた台詞を話し出す。
「相沢課長、先ほど石塚調理長が来て、いよいよ最後通告らしいってこぼしていた。総務部に呼び出されたらしい」
相沢もちらちら石田を盗み見て答える。
「本当ですか、呼び出されたって、いつですか?」
「明日の午後一番で来るよう言われたとのことだ。とうとうその時がきたか」
二人して深刻そうに額を寄せ、考え込んでいる。
石田はパソコンに向かい、ようやく覚えたエクセルの表作りに余念がないという素振りで聞き耳を立てていた。明日の呼び出しのことは、山本からとうに耳打ちされている。そしてこうも言われたのだ。「いいか、正念場だ。どんなことでもいい、あいつ等の動きを逐一知らせろ」と。あと一歩である。鎌田が支配人、そして石田が副支配人になる日まで。紺のブレザーに身を包み、颯爽と館内を闊歩する自分を想像して、にたついた。
相沢が厨房にあがると、石塚調理長が手を挙げ、折り畳み椅子を用意して自分も座る。既に注文が入り始め、内村が大声で指示を出し始めた。オーダー係りの鎌田副支配人が二人をちらちら見ているものだから、石塚は完全にあがっている。
大枠のセリフは決められていた。でも石塚調理長は最初の出だしはアドリブでやると言っていたのに、そのアドリブが出てこない。緊張しまくっている。石塚がようやく最初の一言を思いついた。
「あれだねー、なんと言うか、天高く馬肥ゆる秋っていうけど、本当に空が高いって感じだねー」
なんだよ、散々考えて天気の話かよ、と思ったが、合わせるしかない。
「本当です。春もいいけど、この季節も何とも言えず気持ちいいですよね」
どうも話がぎくしゃくして不自然だ。これからが肝心なのだ。声の音量を上げた。
「でも、とうとう呼び出しがかかったみたいじゃないですか」
どぎまぎしながらも石塚が大声で答える。
「そうなんだ、明日の午後1時半。本社に呼ばれている。向井さんが言ってたけど、課長も一緒に行ってくれるそうじゃないか。助かるよ」
「ええ、入れ墨のことは謝るしかと思います。僕も一緒に謝ります。誰にだって若気の至りってこともありますし、可愛い弟子のことですから、黙認したと言うしかありません」
「そうだな、謝るしかないか」
聞こえたのか聞こえなかったのか分からないが、鎌田がオーダーを読み上げる。もし、聞こえていたのなら、相当な役者だ。相沢は、決められたセリフを終え、話もいつものように弾まないものだから、しかたなく厨房を後にした。
厨房がごった返す昼すぎ、次のオーダー係りに代わったら、向井支配人が同じようなセリフを繰り返す。夜は林田の担当だ。明日に備えて万全の体制が整えられていた。まさに相沢たちにとっても、明日が正念場なのだ。
第十六章 逆転
相沢と石塚が総務部のフロアに入ってゆくと、山田課長が立ち上がり、急ぎ近づいて来る。応接室の前に立ち二人の方を見て「相沢課長、調理長、どうぞこちらへ」と声を掛けてきた。山田は相沢より年上なので、その慇懃な態度に不審を覚えた。
相沢は既に来ているはずの鎌田の姿をフロアーに探したがどこにも見あたらない。応接
に入ってソファーに座るが、山田は一礼して部屋を去った。どうも様子がおかしい。山田は本来であれば冷徹な死刑執行人に徹していなくてはならないはずなのに終始穏やかな顔
を崩さなかった。
相沢は応接室を出て、総務部の奥を覗いた。山田課長は電話をする部長の前に立って、その話を聞いている。部長の声は遠くて聞こえないが、誰かを怒鳴りつけている様子だ。
一体全体、何が起きたのか。まさか罠が露見したのか?応接に帰って石塚に話しかける。
「様子が変です。今、総務部長が誰かを怒鳴りつけていましたが、あんな風な総務部長を見たのは初めてです。もしかして相手が山本統括事業本部長だったりして」
「山田総務課長はどうしてる?」
「怒鳴っている部長の前に佇んでいました」
「ってことは、その可能性大だ。山本と鎌田副支配人が総務部に来なくては話しにならない。だから、総務部長が呼び出しをかけているんじゃないか。それが来ないってことは、どうやらばれたみたいだな」
「やはりそうお思いになりますか。でも、どうしてばれたんでしょう?」
「分からん、いずれにせよ、こっちはどう転んでも傷がつくことはない。成り行きにまかせよう」
そこへ山田が困惑顔で入ってきた。二人は山田の口が開くのをじっと待った。
「相沢君、困ったと言うべきなのか、それとも君の主張が正しかったと言うべきか。実は、山本統括事業本部長が今朝、謝りの電話を僕にしてきた。内村さんの話は勘違いだったと言うんです。今更遅いと思います、こうしてお二人に来てもらったのですから」
「なんですって。全くひどいは話だ。で、山本統括事業本部長は、どのようにおっしゃっていたんですか?」
「それが、念のためと思って鎌田さんにもう一度話を聞いたんだそうです。すると以前の話と少し食い違う。不審に思って厳しく問いつめたところ、嘘だと白状したと言っていました。でも眉唾ものですよ、どう考えても」
「さきほど総務部長が怒鳴ってましたけど、あれ、相手は誰ですか、もしかしたら山本さんですか?」
「ええ、私は山本さんに、直接お二方に説明してくださいと何度もお願いしていたのですが、らちが明きません。ですから部長にお願いして電話してもらったのです。それでも、急用が出来たとかなんとか言って来ようとはしません。いくらなんでも、そんな失礼な話はありませんよ。いったいどういうことなんでしょう」
調理長が口を挟む。
「まったく人を馬鹿にした話だ。入れ墨がどうのこうのと言ってるとは聞いていたが、こっちはとんと心当たりがない。今日はその証拠をみせてやろうと、内村も連れてきた。外で待たせてある。店は忙しいっていうのに、いったい何を考えているんだ」
「ええ、おっしゃる通りです。まことに申し訳ございません」
「まあ、あんたに謝れなんて言ってないけど」
と言って、相沢にウインクする。
山田がしてやったりといった顔で相沢に言う。
「先ほど安藤常務にも電話を入れて事情を話しておきましたが、かんかんに怒っていました。常務も山本さんの話を信じて役員会であんな発言をしわけです。大恥をかかされたことになりますから、山本さんもただでは済まされません」
相沢は山田にお礼を言って、フロアーを後にした。まずは山本をつかまえて話をしたかった。相沢は歩きながら石塚に話しかけた。
「僕は山本をつかまえて言いたいことを言ってやります。そうしなければ気持ちがおさまりませんから。調理長は内村さんのいる喫茶店に先に行って待っていてください。言いたいこと言ったらすぐに行きますから」
「分かった、内村もじりじりして待っているはずだ。行ってあげないと。でも、ちょっとがっかりだな、内村の背中を見せてやりたかったよ。山本が目を剥いて驚く顔がみたかった、残念」
「そうそう、厨房に電話を入れてみてください。みんな僕らに協力して演技してくれていましたが、今日、調理長と内村さんが出掛けて、ほっとして、ついぽろっとしゃべったということも考えられるでしょう。それを誰かに聞かれて、その誰かが山本に電話した」
「うん、あり得る。みんな今日で終わりだと言って喜んでた。嘘をつき通すのも辛い。ついほっとして、ぽろり、と言うことも考えられる」
「本当、調理長はセリフ棒読みだし」
「馬鹿言え、課長こそ、時々噛んでたくせに」
エレベータが8階に止まった。外に出ると隣のエレベーターの前に安藤常務が立っていた。いつもなら大きな声で話しかけてくるのだが、ちらりと一瞥しただけで全く無視の態度だ。恐らく山本と何かしら打ち合わせをしたのだ。
相沢も挨拶もせず統括事業本部の部屋に向かった。部屋に入ってゆくと受付の桜庭が立ち上がり、声を掛けてきた。
「あれ、課長、いらしてたんですか。今日は、部長室は千客万来です。今、部長室に鎌田副支配人が入ってます。その前は安藤常務。課長も入りますか?」
「ああ、その予定だ。秘書の内田さんに都合を聞いてくれ」
桜庭はすぐに内線を入れ、しばらくして受話器を置くと言った。
「副支配人が出てきたら、中に入って下さい」
ふと、レストラン事業部の石田京子がこちらを見ているのに気付いた。相沢が視線をむけると、一瞬、はっとして下を向いてしまったが、しばらくしてまた相沢に視線を向けてにっこりと微笑んだ。相沢も微笑み返した。勇気凛々、やったるぞーと心の中で叫んだ。
10分を過ぎた頃、ドアが開き鎌田が出てきた。ドアを開けたまま深く腰を折って挨拶している。相沢が近づいてゆくと下を向いたまま、ちょこっと頭を下げてすれちがった。
ドアを開け「失礼します」と声を掛けて中に入った。山本は相沢に一瞥を与えたが、忙しく出掛ける準備に余念がない。大きな鞄に書類を詰め込み、抽出(ひきだし)を開けて中をがさごそと探っている。相沢のことは全く無視である。
ようやく準備が整うと、どっかりと椅子に腰掛けた。そして初めて相沢に気付いたような顔をして口を開いた。
「おやまあ、相沢課長さまのお出ましかい。風呂の掃除でもしてりゃあいいのに、本部に何の用かね」
「用事を作ったのはそっちではありませんか。石塚調理長に同行して来たんです。それなのに肝心な方がお二人とも来ていない。どうしたんですか、首を宣告する手はずは整っていたんでしょう?」
「まったく、お主も役者やのう。てっきり本当のことかとおもったよ。あやうくお前の罠に嵌るところだった。かつてヤクザだっただと、若気のいたりで入れ墨をしただと、ふざけやがって、ぜんぶ嘘じゃないか」
「えっ、何のことですか?さっぱり分かりませんが」
山本は顔を一瞬のうちに充血させた。そして怒鳴った。
「ふざけるな、お前のおかげで俺は大恥をかいた。安藤常務もだ。これで終わると思うな。いいか、良く聞け。常務が俺の上司である限り、これからも俺はお前の上司だ。いいか、覚えておけよ、この仇は絶対にとる」
「部長、部長はいつも本質を見誤るタイプの人間ですよね。内村さんのことも、家庭用のシンクであの大量の食器を処理できると思ったことも、20メートルある厨房と宴会場に中継点がいらないと言ったこともみんな見誤っていました」
山本は白目が飛び出すのではと思えるほど目を剥きだして怒りに燃える。
「だから、部長って、お笑いぐさですよ、みんなの。最後まで、内村さんが入れ墨していると頑張ってくれたら、山本部長らしくて、お笑いぐさでよかったのに、残念です」
山本は怒鳴る寸前だった。しかし、しばらく下を向いて何かぶつぶつと呟いていた。そして顔を上げたときには薄笑いを浮かべ、相沢に哀れむような眼差しを向けた。
「とうとう牙を剥きだしたってわけだ。それがお前の本性だってことは常務も俺もとっくに分かっていた。常務に逆らったキャンペーン会議の後だ、常務が言った。相沢を新事業の課長にすると。そして潰せと指示した。さっきも、常務はお前を力でねじ伏せてやるとおっしゃっていた。覚悟しろよ」
こう言って立ち上がると、相沢を指さし睨み付けながらその手を上下にゆする。相沢も負けじと睨み返し、一歩前に出る。思った通り、山本は後じさりして、ふんと鼻を鳴らして、歩き出した。小さな背に大きなバッグを肩から提げて歩いてゆく。
部屋を出ると、受付の桜庭が緊張した面もちで相沢を見ている。どうやら怒鳴り声が聞こえたようだ。鎌田は隅の応接セットに腰掛け、両手で顔を覆っている。相沢はその前に腰掛け話しかけた。
「鎌田さん、これからも山本さんに付いて行くつもりですか。もう、あいつは終わってますよ。総務部長に怒鳴られていました。総務部長は社長の最も信任の厚い人です。この会社を背負ってゆく人と言われてます」
鎌田はしばらくじっとしていたが、両手を顔から離し、相沢を見詰めた。
「山本さんは、村田が見たのに、僕が見たって証言させようとしたんですよ。納得できませんでした。今日は本当に心臓が破裂しそうだったんです。いまさら課長や支配人に顔向けできませんが、本当に申し訳ございませんでした。」
「支配人は寛容な方ですよ。恨みを翌日まで持ち越さないことが施設運営の鍵だって言っ
てました。今みたいに素直に謝れば、許してくれます。僕がそう断言します」
「そう言って頂けると、少しは気持ちが軽くなりました。分かりました、そうします。課長からもお口添え願います」
「ええ、勿論させていただきます。それから、この後、このビルの前にあるブルボンという喫茶店に行って、調理長にも頭を下げてください。それと、今日のことはどうしてばれたんですか?」
「そのことですけど、実は今日、厨房の若い二人がトイレで内村さんのこと話していたそうです。それを大の個室に入っていたウエイターが聞いて、村田にご注進したんです。山本さんがそのことを常務に連絡すると、常務がすぐ駆けつけてきて、部長と先ほどまで怒鳴合いです」
「何か特別なことは言っていませんでしたか?」
「課長のことを散々に言っていました。あいつは何をしでかすか分かったもんじゃない。だから証拠を隠滅しろって指示していました」
「何ですって、証拠を隠滅するですって?」
「ええ、出来るだけ早く処分しろと言っていました。だから今日、山本さんは八王子に出掛けたんです」
相沢はすぐに思いついた。あの個室だ。あの個室にある何かを処分しようと言うのだ。相沢は山本の後を追うことにした。何としても阻止する。鞄を奪うしかない。そこまで思い詰めた。相沢が廊下を曲がった時、小倉企画部長にばったり会ってしまった。
「相沢君聞いたよ、山田君から。良かったじゃないか、今、専務にお話申し上げてきたところだ。専務が、相沢君を連れてきなさいというので、探していたところだ。ちょうどよかった」
ウワーンと泣きたくなった。しかし、断ると角が立つ。山本が証拠を隠滅しようとしていることを話したとしても、鞄を奪う計画を二人が承認するはずもない。10分やそこらの遅れは高速で飛ばせばなんとかなる。そう思い専務室に同行した。
しかし、予想外に岡安専務は機嫌が良く、だらだらと話が続き、専務室を出たときは既に40分を過ぎていた。しかたなく喫茶店に急いだ。店に入ってゆくと、鎌田副支配人が調理長の前で首をうなだれている。相沢を見ると、調理長が声を掛けてきた。
「課長、今、こいつが謝ってきたんだ。内村は許さんと言っているが、俺はもういいと思っている。こうして謝ってきたんだから」
相沢はぜいぜい言いながら答えた。
「ええ、そうして下さい。向井さんもきっとそう言うと思います。それより大変なことになりました。山本はやっぱりあの個室で何かやっていたみたいです。きっと不正です。それを処分しに健康ランドに行きました。どうしましょう?」
「向井さんに電話しろ、それが一番早い。そこで押さえるしかない」
「でもどうやって押さえるんですか」
二人見つめ合い、それぞれ思考を巡らせていたが、最後は首を傾げた。相沢は向井が山本の行く手を遮り、鞄を渡せと怒鳴っている図を思い浮かべたが、そんなこと出来るはずなどない。それでも、電話だけはしなくてはならない。
携帯を取り出し、ボタンをプッシュする。携帯に出たのは林田の声だ。息せき切って事情を話すと、林田はしばしの沈黙の後、きっぱりと「何とかします」と答えて電話を切った。相沢は携帯を見詰めて考えた。林田はいやにあっさりと、自信ありげに答えた。何とかすると。じっと見詰める三人に視線を向けた。
「林田君が何とかしますって言っていました。だけど、いったい、何を、どう、何とかするつもりなんでしょう?」
三人は一様に首を傾げた。
第十七章 転勤
林田は受話器を置くと考え込んだ。社会人の常識の範囲では、何を、どう処理したらよいのか全く何も思いつかない。同じような鞄を用意して隙をみてすり替える?隣の品薄の靴売り場の隅っこに鞄が置いてあったが、同じ物が偶然あるとは思えない。
さて、どうする。向井は出掛けていて自分一人で何とかしなければならない。林田は事務機器メーカーに勤めていた。だから内装工事とスティール家具の専門家でもあった。従って山本の個室も、机の鍵も開けるのはわけもない。
林田はジェムクリップを机から取りだし、個室に向かった。数分で個室のドアが開いた。中に入って流れる汗を拭った。山本が到着するまでの時間は後30分ほどだ。もう一つの関門がそこにでんと置いてある。机である。
その机に取りかかった。じっとりと汗がわき出る。疚しさが邪魔をしているのか、指先が震えている。自分を叱咤し指の感覚に全神経を集中させる。固い感覚が指先に伝わってきた。これを回せば鍵が開く。そっと回した。かちっと音がして鍵は開いた。
恐る恐る一番下の抽出を開けて覗き込んだ。林田は「あれー」という叫び声をあげた。中には林田の技を越えるものが、またしてもでんと納まっていた。手提げ金庫である。ダイヤルを右にいくつ、左にいくつと回して鍵を開けやつだ。
林田は手提げ金庫を机から取りだし、絨毯の上に置いた。しばらく眺めていたが、よし、と言ってダイヤルに手を伸ばした。金庫に耳を押し当て、ダイヤルをそっと回してゆく。音がするはずだと耳を澄ましたが、いくら回しても音など聞こえない。
ふと、後ろに人の気配を感じた。どぎまぎしながらゆっくりと首を回す。白いソックスが目に入った。うわーと悲鳴を上げて立ち上がった。そして突然の侵入者と向かい合った。相手は向井であった。
向井は悲しげな視線を投げかけている。信頼する部下が泥棒を働く現場を押さえてしまったのだ。これほど不幸なことはない。向井の胸は悲しみで押しつぶされそうだった。言葉もでない。林田はその深刻そうな顔を見て、思わずからかいたくなった。
「てへへ、つい出来心で」
向井の顔は更に悲しみに沈んだ。何故、こんな深刻な場面でジョークなんだと自分を叱責し、林田は頭を拳でごつんと叩き、すぐさま説明にかかる。
「違うんです、支配人。支配人が出掛けている間に、課長から電話があったんです。山本が証拠隠滅のためにこっちに向かったって。その証拠が個室にあるはずだと言うんです。
で、この個室を開けて、机も開けたんですが、最後に出てきたのがこいつです」
恨めしげに手提げ金庫に視線を向ける。向井はこの言葉を聞いてほっと胸を撫で下ろしている。そしてようやく口を開くことができたのだ。
「いやー、びっくりした。本当に心臓が止まるかと思ったよ。あの真っ正直な林田君が、まさかって。で、証拠隠滅って言うけど、証拠って何なの?」
「そんなこと俺には分からねえよ。とにかく、常務が山本に早く処分しろって言ったそうです。そんでもって課長が電話かけてよこしたわけです」
「それが、あれか」
と投げ出された金庫を指差した。
「それが、あれでも、あれが、それでも、かまわねえけど、金庫なんてダイヤル知らなければ開けようがねえよ。支配人、そんなことより、山本の野郎が、ここに到着するまで25分しかありません。早くこの金庫を開けなければ」
「よし、俺に任せろ」
向井は手提げ金庫を持って事務所に戻り、自分の席にそれを置いて机の中をまさぐる。あったと言って取り出したのは聴診器である。
「支配人、いいもん持ってましたね」
「ああ、この間、林田君が業者を呼んでガラクタ市を開いたじゃないか。その時、買ったんだ。こんなにすぐ役立つとは」
と言って金庫に聴診器を当て、ダイヤルを回し始める。まるで専門家みたいで、林田もしばらく見ていたが、ダイヤルの回し方がぞんざいだ。林田が聞いた。
「支配人、右にいくつ、左にいくつ、って回すのはご存じですよね?」
「いや、知らない、なにそれ?テレビなんかで見たことあるけどカチって音がすればいいんじゃないの、違うの」
「支配人、どいてどいて」
うろ覚えだがいたずら程度に金庫の鍵をいじったことはある。向井に代わり聴診器をして金庫に向かい合った。林田は全神経を聴覚に集中させゆっくりとダイヤルを回す。かすかに音がするはずなのだ。額に玉の汗が浮かぶのが分かる。
そろそろ銀行回りから石田が帰って来る頃だ。向井も何度も後ろを振り返り、石田の影に怯えはじめた。極度の緊張はしばしば人に無意味な行動を取らせるものなのである。向井は机の上にある佐川急便の伝票に勢いよく住所スタンプを押し始めた。
パタンパタンとその音が響き、神経を張りつめていた林田がうんざりしたような顔で向井を見詰める。その視線にようやく気付いた向井は、自分の行動の意味を計りかね、じっと住所スタンプを見詰める。
「支配人、何やっているんですか?今、そんなことしたって始まんないじゃないですか」
「すまんすまん、妙に緊張しちゃって、あれっ」
向井の指差す方向を見ると、ガラス越しに石田の茶髪がゆれている。林田は手提げ金庫を個室に戻そうと立ち上がったが、すでに事務所のドアが軋んだ。金庫を林田の机の下に放り込み、二人は石田を迎えるための姿勢を整えた。
石田が事務所に入ってゆくと、妙ににこやかな二人と向かい合った。普段なら無視する二人が笑って、お帰りなさいと声を揃えて挨拶する。石田はすぐに了解した。いよいよ本社で決定が下されたのだ。厨房は首になり、支配人は更迭、そして自分たちの権力は盤石
なものになったのだ。
席に着くと向井が声を掛けてきた。
「石田課長、ちょっと話があるんだけど、ここではちょっと話しづらいから喫茶に行きましょう。銀行回りでお疲れでしょうから、アイスコーヒーでも」
一挙に優位な立場にたって興奮気味ではあるが、石田は気を落ち着けることにした。コーヒーは喫茶店で週刊誌を読みながら二杯も飲んできたが、向井の哀れな顔を見ればむげには断れない。深いため息とともに立ち上がった。
二人が事務所を出ると、林田は金庫を個室に運び元あった場所に戻した。鍵をかけ、何食わぬ顔で事務所に戻った。林田はまた新たなアイデアを考えなければならなくなった。もう時間もなく、石田という邪魔が入った。
金庫を開けるのを諦めるとなれば、残る手段は強奪しかない。林田は一瞬手錠をかけられる自分の姿を想像し、ぶるっと震えた。完全犯罪でなければならない。ふと、清水の顔が浮かんだ。清水は遅番だからアパートにいるはずである。林田は携帯を取り出した。
山本は思ったより早く到着した。いそいそと石田が個室にお茶を運んで行った。向井と林田はその後ろ姿を見て固唾を飲んだ。個室に忍び込んだ痕跡が残っていないか不安だったのだ。しばらくたったが、二人は籠もったままだ。
林田が「どうやら大丈夫みたいですね」と言って向井を見た。向井も大きく頷いたが、その目が大きく見開かれた。振り返るとドアが開き、石田が出てきたのだ。その顔は青ざめ失望の色は隠せない。山本から事の次第を聞いたのだ。
お盆を胸に抱き、よたよたと歩いて来る。そして不安そうに見詰める二人を見つけると、きっと睨み付けた。二人はその形相に息を飲んだ。石田が叫んだ。
「あんた達、よくも騙してくれたわね。おかげで何もかもめちゃくちゃだわ。いい、部長も言っていたけど、絶対にこのお礼はするそうよ。お前達がこの会社にいる限り、絶対に浮かび上がらせない。お前達には未来はない。覚えておくことね」
石田は途中から山本そのものの言い方になっていた。そして山本が出てきてまだ口汚く罵る石田の肩に手をやった。そして言う。
「おいおい、もうその辺にしておけ。こいつらには言葉ではなく、現実でもって分からせてやる。この俺に逆らえばどういうことになるかをよ。お前達には残念だろうが、すんでのところで罠には嵌らなかった。いいか、レースは始まったばかりだ」
こう言い残すと、事務所を後にした。左肩にバッグを吊して歩いてゆく。二人は尚も唇を震わせ面罵する石田を無視して、山本が事務所のドアから消えるのを待った。そして消えた瞬間、石田を押しのけ事務所を出た。出た途端走り出す。駐車場の見える二階の社員食堂まで一気に駆け上がった。そして駐車場を見下ろした。向井が震える声で聞いた。
「こんなことをして本当にいいんだろうか」
「支配人、もうそんなことは言いっこなし。賽は投げられちまったんですから」
山本が歩いて行く。黒塗りのベンツまで50メートル。清水の姿が見えない。いったいどこにいるのだ。ふたりはやきもきして、清水の登場を待った。
それは疾風のごとく現れた。フルヘルメットで黒の革の上下に黒のブーツ。出で立ちは決まっているのだが、オートバイはスーパーカブに毛が生えたようなおんぼろでナンバープレートははずされている。どこで助走を付けたのか分からないが、山本の後ろから音もなく近づいてゆく。
滑るように背後から接近して、直前で清水の手が伸びた。山本の左肩にかけたショルダーのバンドを左手でつかみ、山本の右側を走り抜けた。その直後いきなり爆音が響いてオートバイは加速した。
山本は一回転したが鞄はしっかり持っていた。しばらくオートバイと一緒に走ったが、転びそうになってその手を離した。清水のオートバイは農道に出るとあっという間に遠ざかり民家の家並みの中に消えた。
山本は唖然として立ち尽くしている。二階の窓から見詰める二人はごくりと生唾を飲み込む。山本がどう出るか。警察に連絡した場合も考慮した。結論はしらを切る。それしかない。そう三人で確認しあった。さて、山本はどう出るか。
二人とも無言である。山本も立ち尽くしたままだ。と、山本が歩き出した。とぼとぼとベンツに向かう。電話するとしたら、その場でするはずだ。山本の後ろ姿をじっと見詰める。しかし、ベルトに吊した携帯を取り出そうとはしない。
山本はベンツに乗り込むと30分もハンドルに覆い被さりうっぷしている。そしてようやく起きあがると、エンジンをかけ、走り出した。国道に向かった。
二人はふーと深い息を吐いて、その場にへたり込んだ。山本はとうとうどこへも携帯をかけなかった。
相沢が事務所に到着したのは、それから30分後だ。個室から声が漏れており、覗くと向井と林田、そして清水の三人がまだ五時前だというのにビールを飲んで気炎をあげている。相沢の顔を見ると、林田は机に並べられた缶ビールを取り上げ叫んだ。
「課長、乾杯しましょう、石田を追い出しました。ヒステリーを起こして叫びまくるもんで、ウララっちゅうモーテルの名前を言って、旦那に言いつけるぞって言ったら、目ん玉、ひん剥いて驚いていましたっけ。いやー、その顔、見せたかったなー、課長に」
「それで、どうなった?この様子だとやけ酒じゃないってことくらい俺にも分かる。つまり、成功したってことですか?」
向井が手招きしている。向井の横に腰掛けると、いきなり相沢の首に腕を回し、囁くような声で言った。
「山本の鞄を強奪した。清水を使って。警察に届けるかと思って不安だったけど、山本は届けなかった。ベンツの中で30分も考え込んでいたが、どこへともなく消えた」
強奪という言葉を聞いて驚いて向井の顔をまじまじと見詰めた。向井はにこにこ笑いながら言った。
「お礼をいうなら林田君に言えよ。俺はただおたおたしてただけだ」
林田に聞いた。
「強奪っていうけど、どうやって強奪したんですか」
三人がくちを揃えて「しー」と言って唇に人差し指を立てた。林田が清水に声をかけた。
「おい、清水」
今度は清水が隣に座り、相沢の首に腕を回し、耳元で囁く。
「俺、昔、ひったくりやったことありまして、けっこう上手かったんです。オートバイは道に乗り捨てて、鞄の中身だけ頂いてこれはゴミ捨て場に置いておきました。そして、部長の机の上に置いてあるのがその中身と言うわけです。ちなみに、逮捕歴はありません」
相沢は振り向いてそれを見た。段ボール箱が机に置いてある。相沢は立ち上がり、それに近づいた。段ボール箱には佐川急便の宛名シールが貼られている。向井が声をかけてきた。
「山本が警察に通報できない訳が分かったよ。その中身は台帳だ。いわゆる裏帳簿。山本さんは直轄事業の責任者だ。業務上横領の罪にも問われかねない。直轄事業のレストラン、喫茶、エステ、映画館等々の裏帳簿だ。それを善意の第三者が道で拾って、今日、親切にも佐川急便で本社経理にお送り申し上げるという手はずになってる」
相沢はこみ上げる興奮と感動で身体が震え、「きゃっほー」っと心の中で叫んだ。そして
声に出して皆に言った。
「やっぱり乾杯だ。向井支配人、林田君、清水君、本当に有り難う。今日の事は一生忘れられない。人生最高の記念日だ。さあ、乾杯しましょう」
四人で声を揃えた。そして、一気にビールを空けた。相沢はやはり我慢できなかった。だから叫んだ。
「きゃっほー」
数日後、山本直轄事業本部長は解雇された。安藤常務は山本が最後までその名前を出さず、首は免れたものの6月の株主総会で更迭されることになったらしい。こうして、相沢は全面勝利し、オープン以来の確執の種は取り除かれ、どたばた劇はフィナーレを迎えることになった。
奥多摩の峰峰が雪ですっぽりと覆われる頃、相沢は本社に呼ばれた。店は何もかも順調に推移しており、相沢は名古屋のプロジェクトの主要メンバーとして本格的に参画しなければならない時期に来ていた。
ここで知り合い、共に辛酸を嘗め、喜びを分かち合った人々と別れるのは非常に辛いものがあったが、サラリーマンである以上、それは仕方のないことなのだ。いよいよという思いで本社総務部にやってきた。
山田は例によって応接に相沢を迎え入れ、以前と同じように季節はずれの異動の話をしようと、にやにやと相沢を見詰めている。健康産業事業部への異動もこんな状況で内示があったのだ。しかし、今度は辞令らしきものを手にしている。そしてその口が開かれた。
「とりあえず、これを見てください。話はそれからにいたしましょう」
と言って辞令をテーブルに置いた。その辞令を手に取り、じっと見入った。開いた口が塞がらなかった。そこにはこうあったのだ。
「香港店総括課長を命ず」
最終章 彼方に
彼方の峰峰は既に雪に覆われ、澄み切った晩秋の空にくっきりとその雄姿を見せている。まるで天上の神々が下界の人間の営みを優しく見詰めているかのようだ。かつて毎日通った国道を、相沢は車を走らせている。
銀杏の樹が右手に見え、すぐに後ろに走り去る。それは黄色に色づき秋の深まりを感じさせた。そこは5年前、相沢が久美子と初めて出会った場所なのだ。そう、ここからあのモスグリーンのジャガーを追ったのだ。その同じ道を、今日、彼女の弔いのために走る。
吉野久美子。享年35歳。吉野組組長。久美子は夫である吉野林蔵が急死したため組の跡目を継いだ。翌年10月、甲州街道において、愛車ジャガーが中央分離帯に激突して即死。彼女の血液から多量のアルコールが検出されている。それは夫の死から1年後のできごとであった。
相沢の目から涙が一滴流れた。この不幸な女の一生を哀れんだわけではない。彼女に最も似つかわしくない人生を選ばせた運命を思えば、確かに哀れな人生である。しかし、幸不幸の総量は本人にしか分からない。他人がとやかく言うべきではないのだから。
相沢の涙は大切な人を失った哀惜の涙なのだ。胸が押し潰されそうな痛みを感じていた。生きていればこそ、久美子が夢想したおとぎ話の通り、人と人とを結ぶ糸によって久美子と繋がっていると感じることができたのだ。その糸がぷっつりと切れてしまった。
今度こそ、久美子は本当に別の世界に行ってしまった。それは単に相沢一人の感傷に過ぎないことも分かっていた。5年という歳月は、久美子にとって初めての男との、愛も憎しみも含めて夫婦という特殊な人間関係を形作る月日だったのだから、相沢とのたわいない思い出など心の片隅に追いやってしまっただろう。
相沢が香港から帰国したのは1年前で、古巣の企画部次長に返り咲いた。結婚は3年前のことだ。あの石井京子と結ばれた。京子は安藤常務の姪だった。健康産業事業部に飛ばされて態度が急変したことも頷ける。常務に諭されたのだ。相沢はやめておけと。
常務が辞めさせられた直後、京子は辞職したのだが、送別会があり、相沢も出席して事情を知った。京子が正直に常務の姪だと打ち明けたのだ。あの内村の入れ墨の件で本社に呼ばれた日、にっこりと微笑んでくれた理由も分かった。相沢が窮地に立たされていると
聞いていたからだ。相沢は京子の携帯のナンバーを聞いて、翌日デートに誘ったのだった。
林田から電話があったのは昨日のことだ。林田は2年前健康ランドを辞め、地元で事務機屋を始めた。健康ランドの営業を通じて企業の総務関係者とのコネクションを培っていたのだ。林田は相沢の送別会の翌日みたいな雰囲気で話しかけてきた。
「課長ですか、おっと次長さんか。実は今月の16日、久美子が死んじゃったんです。自動車事故で。それで明日、八王子で告別式です。もし、時間があったら一緒に行こうと思って…」
あまりの衝撃に相沢は言葉を失った。長い沈黙に林田が苛立った。
「課長、久美子の告別式どうします?用事でもあるんですか?」
相沢がようやく答えた。
「勿論、行くよ。ごめん、ちょっとショック受けちゃって」
「良かった、久美子も喜ぶよ。でも驚いたねー、やっぱり二人は仲良かったから、旦那があの世から呼んだんだと思う。だって、旦那が死んでからちょうど1年目だもの」
「二人は仲良かったの?」
「ああ、いつまで経っても、まあ、子供がいなかったせいもあるけど、まるで恋人同士みてえだった。その旦那が心臓病で死んじまって可哀想だった。だいぶ前から心臓の発作に苦しんでいたらしいんだけど、誰にも言わずに病院にも行かなかったらしい」
久美子は旦那の死後、伸ばしていた髪を切り、かつてのショートカットに戻したと言う。
まるで旦那に操を立てたみてえだと林田は言った。その時、相沢は久美子の幻影を見ていた。様々な場面で表情を変えながら目の前で微笑んでいる。涙が溢れた。
健康ランドに着くと林田と清水が待っていた。清水は照れながらマネージャーという名刺を差し出した。物腰が客商売のそれになっており、紳士然として元暴走族だったという雰囲気は微塵もない。
本社の次長に挨拶とばかりと現れた支配人は相沢の知らない人間だった。向井は相沢の代わりに新天地名古屋でその経験を存分に発揮しているはずだ。石塚調理長は浅草の高級料亭の調理長に納まっている。
ひとしきり懐かしい昔話に花をさかせ、頃合いをみて腰をあげた。3人は相沢の車で告別式に向かう。相沢は運転しながら二人の会話に耳を傾け、割って入っては声を上げて笑い、そして一人物思いに耽った。
八王子の泉岳寺に着いて、3人は声をあげ、その異常さに驚いた。そこはまさにヤクザの世界だ。それははじめから分かっていたはずなのに、その規模は想像を遙かに越えていた。寺の駐車場は警官とヤクザがごった煮みたいになって車の整理に追われている。
ヤクザの親分とおぼしき人物とそれを取り巻く子分達。黒の喪服の群れが艶やかに微笑む女組長、久美子の面影を偲び、そしてそれぞれの思いに耽る。数奇な運命に翻弄された女に対する思いは一つであろう。
愛した旦那の後を追うように、ただ一人、夜を疾走し、そして死んだ。愛車、ジャガーとともに。マスコミが飛びつかないはずはない。それ以前から、久美子はマスコミの餌食にされていた。美人でインテリの女組長として。
カメラの放列が相沢達を迎えた。たまたま相沢達と並んで歩く恰幅の良い紳士に向かってシャッターの音が一斉にしかも数秒続いた。清水がかっとなってカメラマン達を怒鳴りつけた。
「てめえら、誰に断って写真撮っているんだ」
この声とともに、またしてもシャッターの音が鳴り響いた。数週間後の写真雑誌にその親分の身内として紹介されようとは、清水は思いもしなかった。
久美子の遺影を遠くから眺めた。読経の響く境内に一般参列者用のお焼香台が5台置かれている。長い列の最後尾から見ると髪を長く伸ばした、見覚えのない久美子が微笑んでいる。その写真は結婚直後のものらしい。
相沢は心の中で話しかけた。久美子、久しぶりだな。林田から聞いたよ。旦那と愛し合っていたそうじゃないか。よかったな。また好きだった旦那に会えるじゃないか。でも、もう一度、この世で会いたかった。
二人とも結婚していて、街でばったり会ったらいいな、なんて想像していたんだ。立ち話して別れるだけだとは思うけど、そんなふうにして会いたかった。もし、あの世があるって言うなら、そこで会おう。微笑み合って握手しよう。
焼香を済ませると、相沢達は足早に境内を抜け、裏の出口に向かった。マスコミに写真を撮られるなんてまっぴらだったからだ。3人は黙り込み俯いて歩いた。しばらくして林田が口を開いた。
「旦那が死んでから、あいつと飲んだことあるんだ。夜中だけど。そん時、相沢さんの話題がでたよ」
「へー、どんな?」
何でもないふうに装っていたが、胸の動悸が激しく息苦しいほどだった。
「いや、久美子が聞いたんだ、相沢さんどうしてるって?だから結婚して、香港から戻って、そんでもって出世したって言ったんだ。ただ、それだけ」
「彼女は、何か言ってた?」
「いや、ただ黙ってお酒飲んでいたよ。今度、相沢さんを呼ぶから一緒に飲もうかって言ったけど、返事しなかった。きっと、そうしてって言いたかったんじゃねえか、今から思うと」
相沢もそう思いたかった。林田に誘われれば相沢は飛んできただろう。それをしなかった林田を恨んだ。ふと、あの時の情景が浮かんだ。林田の叫ぶ姿がバックミラーに映されていた。相沢は振り向いてじっとその姿を見詰めたのだ。
「林田君、3人でデートした帰り、最初に林田君を降ろした。その時、僕と久美子が乗った車に向かって何か叫んでいただろう。いったい何を叫んでいたんだ?」
「そんなことあったけ?忘れちまったなあ。まあ、今更しらばくれてもしょうがねえか。今日は久美子の告別式だし、ばらしちまうか」
というとにやりとして言った。
「俺は久美子の心が手に取るように分かるんだ。だから、あの日、久美子が何を期待して
いたか分かっていた。最初はそれを何とか阻止しようと思っていた。だけど、なんだか久美子が哀れに思えて、最後には応援したくなっちまった。だから二人の乗った車に向かってさけんだんだ。久美子、やってもらえよーて」
これを聞いて相沢は何故か涙が滲んだ。林田が何か言おうとして言いよどんだ。しかし、もう一度、意を決したように口を開いた。
「こんな日に、こんなこと聞くのは不謹慎だけど、あの日、俺、眠れなくて苛々して女房に当たっちまった。まったく情けねえ人間だ。でも、今でも気になっているんだけど……、結局あの日、やったん?」
涙に潤ませた目を拭い、相沢は笑顔をむけて答えた。
「いや、やらなかった。やろうとしたけど、拒否された」
黙って聞いていた清水がすっとんきょうな声をあげた。
「えー、やってなかったの。あの日、久美子さんが、あの喫茶店で『抱いてくれてありがとう』って言ったから、てっきりやったとばかり思って、林田さんにそう言ったんだ、ねえ先輩」
林田が清水の頭をひっぱたいた。
「馬鹿野郎、全然ちがうじゃねえか、お前の言ったこと。この5年間思い違いして過ごし
てきたってことだ」
清水が小さくなってバツが悪そうな顔で相沢をちらりと見た。林田が続ける。
「やっぱりなー、あいつらしい。でも、思い切って聞いて良かった。本当に良かった。心が晴れた。全くあいつは意気地のねえ奴だったから」
相沢ははたと歩みを止めた。遠くに見覚えのある顔を見いだしたのだ。寺の境内の裏に臨時駐車場が用意されていた。そこに相沢は堤の姿を見いだしたのだ。あの長髪と彫りの深い顔はよく覚えていた。健康ランドに乗り込んできたヤクザだ。
堤は車の横に立っていたが、一方のドアからサングラスをかけた女が降り立つと、先に歩き出した。女は少し急いで堤に追いつくと、並んで歩く。相沢はその女をじっと見詰めた。サングラスをしているが、その女は間違いなく鵜飼則子だった。
林田も気付いたようだ。立ち止まって見詰める相沢を振り返り、声をかけてきた。
「相沢さんも気付いたか。あの二人、俺の睨んだ通り、やっぱり関係していたってわけだ。
則子の奴、惚けやがって。でも、則子にも会えるなんて、嬉しいね、ねえ、相沢さん。きっと久美子の取り計らいだ」
相沢はこの偶然が偶然とは思えなかった。やはり久美子の言っていた糸は存在するのだ。そして縁のある人々はその糸によって引き寄せられる。こうして則子と会えるなんてこれほどの喜びはない。たとえ、その別れがぎくしゃくしていたとしても。
堤と則子が相沢達に気付いたのはだいぶ近づいてきてからだ。始めに則子が相沢を認め、小声で堤に囁いた。堤は顔をしかめて三人を睨みすえ、そしてそっぽを向いた。則子は俯き、ゆっくりと歩いてくる。
相沢も歩みを緩めた。話をしたかったのだ。俯いていた則子が顔を上げて背筋を伸ばした。サングラスに隠された瞳は二人を捉えているはずだ。黒のドレスはやはり素人とは思えず、水商売が身に染みついている。
則子がサングラスをはずした。すれ違う寸前だ。林田が歩みを止め微笑む。則子も立ち止まった。その目は林田にのみ向けられている。相沢をまったく無視していた。則子がにやりと笑い、堤に話しかけた。
「あんた、何かと縁のあった方達なんだから、挨拶したら」
堤は二人を睨み付け、すこしだけ頭を下げて言った。
「どうも、その節は…」
林田がにこやかに答える。
「いえ、いえ、こちらこそ…不調法で」
堤は、先に行っていると言い残し歩き出した。後ろ姿を見やりながら則子が言う。
「鯨井が組を解散して、今、あの人右翼やってるの、ほら、バスに乗って、がなっているやつ。そっちの方がヤクザより向いていたみたい」
林田がへーと言って話題を変えた。
「それはそうと、またべっぴんさんになったね。ところで、今、どこにいるんだ」
「立川に店を出してるの。小料理屋、安くしとくから飲みに来て。これ、名刺。そこに住所が書いてあるから」
「ああ、行く」
則子が何か思い出したような表情を浮かべた。
「そうそう、堤のことで嘘言っちゃたけど、ごめんね。別に隠すつもりはなかったけど、何であんた達が知っているのか不思議で、つい本当のこと言えなかった」
「そんな昔のことで謝られたって、もうそんなこと覚えていねえよ。それよっか、今度、本当に飲みにゆくよ」
「そうして」
則子は最後まで相沢を無視し、林田に別れを告げた。じっと見詰める相沢の横を通り過ぎて行く。相沢は振り返りその後ろ姿に見入った。林田が則子に声をかけた。
「こんど、3人で行くから。俺と林と、それから課長さんと」
則子の歩みが止まった。すこしたって、ゆっくりと振り向いた。その視線は相沢に注がれている。そして笑みを浮かべた。相沢もそれに応えた。その微笑みは二人の心のわだかまりを溶かしていった。則子が踵を返し歩き始める。
3人は遠ざかる則子の後ろ姿をじっと見ていた。清水が口を開いた。
「いいな、二人は。俺なんて、久美子さんは、後ろ向いてて声しか聞かなかったし、則子さんは噂でしか知らない。もうちょっと早く健康ランドに就職していたら、二人と知り合えたのに」
林田が言った。
「清水、縁っていうやつがあってな、縁のある人どうし糸で結ばれているんだってさ。そいつが引き合うのさ。清水が俺たちと縁があるってことは、久美子や則子とも縁があるってことだ。来世では恋人になってるかもしれねえ」
「先輩、来世まで待てません。今度その店に行く時、俺も連れてってください、お願いします」
相沢は林田が自分と同じ考えを持っているのに驚いた。来世も本当にあるような気がして
きた。縁といえば、もう一人、林がこの場にいないことが寂しかった。
「ところで、林はどうしてるの?」
「元気でやってるよ。赤ちゃん本舗に就職して今じゃ店長だ。そうだ、おい、清水、3人じゃなくてお前を入れて4人で飲みに行こう。林には、あの日のひったくりの話はまだしてねえんだ。その話をしてやってくれ」
「例のはなしですね。山本が泣いていたことや、金をやる、金をやるから、これだけは勘弁してくれって叫んだことでしょう」
相沢が立ち止まり二人に声を掛けた。
「それじゃあ、とりあえず、今日は3人だけで飲みますか。まだ早いけど」
「相沢さん、車でしょ、車どうするの」
「今日は健康ランドに泊まる。車置いて、近場の飲み屋にくりだせばいい」
3人は互いの顔を見合わせて頷きあった。
今日は思い出に乾杯しよう。そして、忘れていた大切な人々に乾杯しよう。心優しき人々、人の痛みを我がことのように感じる人々。またいつか会える。生きている限り何処かで会える。いや、あの世だって本当にあって、そこで会えるかも知れない。相沢は夕焼けに染まる黄金色に映える峰峰を眺めながらそう思った。輝きに満ち、神々しくそびえ立つ峰峰に向かった歩きはじめた。あの彼方にその世界があるような気がしていた。
愛しのヤクザ


