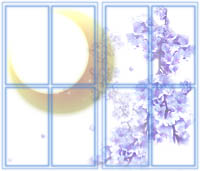きつねの話―提灯
実話半分、伝聞半分のお話です。昔はこんな話が結構あったそうです。
母方の祖父は、幼い頃に亡くなったので顔すら殆ど覚えていない。
母の実家は、高野に続く山道沿いに開けた村のうち、一番奥まった処にあった。逆に言えば、高野から下りて来ると、最初に出合う、集落らしい集落と言える。
あれは、祖父の葬儀だっただろうか。白装束の親類たちが白頭巾をかぶり、棺の周囲を時計回りに回っていた。自分が住む海辺の町では見た事のない光景だったのだろう。それだけは鮮明に覚えている。菩提寺の住職も高野から来たと言う、真言宗だった。
その頃はそんな田舎でもさすがにもう土葬はすたれていて、そんな筈はないと母は笑って否定するが、私の記憶にある祖父の遺体をおさめた棺は樽型の、昔ながらの座棺だ。多分、記憶の中で、後年テレビの時代劇やらで見た田舎の葬儀の光景と混乱しているのだろう。
祖父は、若い頃、海軍に居て、戦艦の厨房で料理を作っていた。そのお蔭で、世界を見る機会があり、片田舎の人にしては開明な性格だったようだ。戦後は山奥の村にまで「進駐軍」がやって来たと言うが、当時村で唯一の旅館を営んでいた祖父が海軍時代に磨いた腕をふるって洋食を出し、米兵に「こんな料理は和歌山でも食べた事がない」と言わしめたそうだ。何度も聞かされた、母の自慢である。
そんな祖父の話だから、嘘とも思えないと母が言う。
祖父は何度かきつねに出合っている。
一度目は、少年の頃。
山肌に張り付くように広がる村の、その斜面が下りて行き着く先に、川があった。川は山に暮らす少年たちの唯一の遊び場だった。祖父も毎日のように坂道を下り、川へ遊びに出掛けただろう。
川魚を獲り、大人の背丈の倍はある岩から川へ飛び込む。川の流れに逆らって、誰が一番速く泳げるかを仲間同士で競う。そんな他愛ない遊びで半日以上は楽しめた。
ふと気づくと、音が消えていた。
高市の周りには、もう仲間が居なかった。山の日の入りは早い。日が傾いたかと思えば、あっと言う間に暗闇が迫って来る。高市も山の子供だからそれは十分承知していたが、脱ぎ捨てておいた藁草履が片方見つからず、家路を走って行く仲間に遅れた。
どれほど風のない日でも、山には音があった。木々のこすれる音。鳥の鳴く声。川のせせらぎ。だが、その時、確かにそのどれもが消えたのだった。
意味もなく胸騒ぎがし、一刻も早くここから立ち去らなければならない焦りを感じた。だが、失くした草履は見つからず、何よりも自分の足が自分のものでないように、意志とは別に全く動かなかった。
川向うに、ぼおっと灯りが一つともった。
人がいる、と思った瞬間、高市の視線の先、真っ黒なシルエットとなった山肌に夥しい数の提灯の灯が一斉に掲げられた。
同時に、どこにそれだけ居たのかと思うほどがやがやと人に似た声が上がった。
数十。
もっとか。
だが、意味のない音が聞こえるだけで、一体何を話しているのかさっぱりわからない。
まるで、これから村の祭でも始まるように陽気にはずんでさえいるように聞こえる。もちろん、今夜、村に祭などないし、人の声に似てはいるが、あれが人ではない事を高市は知っている。
提灯の数は見る間に増えて行き、山を照らし始める。
見てはいけない。
高市はきつく目を瞑り、無数の提灯が浮かび上がらせた彼らの顔を目にするのだけは必死で避けた。
ゆらゆらと揺れる提灯の明りはきつく閉じた瞼をも照らしていたが、揺れながら山を上って行くのを高市は感じた。それにつれ、その人外の声も小さくなり、やがて聞こえなくなった。
そして、提灯も、消えた。
どうやって家に帰りついたのか、高市は覚えがなかった。気がつけば、高熱にうなりながら床の中に居た。
高熱は三日三晩続いたそうだ。
「目閉じる前にちらっとだけ見てしもたんやが、あれは間違いのう、きつねやった。そやさけ、あんな熱出てもたんだわ」
祖父は、幼い母によくその話をしたそうだ。
きつねの話―提灯