
世界は竜龍と共に 1
大陸サンガイア――南部を人間、西部を白魔族、北部を黒魔族、そして東部をドラゴンが治める4つの国と、その中央に位置する聖域から成る広大な大陸。
物語は人間の国フェニール北部、森の中の小さな町ネストから始まる。
夏から秋へと移ろうある晩から、彼女の人生は大きく変わることとなる。
1. 呪われた町と新たな神 Ⅰ
1.1. 新月の邂逅
若い女が夜闇を駆ける。月の無い獣道をなりふりかまわず死に物狂いで走っている。
彼女の背後に舞うは翼人。ヒトである。しかし、人間ではない。血を糧に魔術を用い、他の生物の血肉を啜る残虐な種族。人は彼らを『悪魔』と呼ぶ。
森の中を走る内に、開けた場所へ出た。清らかな水をたたえた小さな湖の畔に白い石を組んで作られた祠がある。その祠の前の石畳に、足をもつれさせた彼女が転倒した。彼女が抱えていたバスケットからまだ青く臭う薬草が散らばる。恐怖にひきつった顔を後ろに向けると、翼人が地面に降り立ち、翼をたたむところであった。
『翼をたたむ』という表現には語弊がある。彼らの翼は背より血を噴出させ、魔の術により固めたものだ。正確に言えば『翼の形を成していた血を体内に戻した』のである。
「やっぱり。」
悪魔の男はおびえる彼女に近づきながら言う。
「僕好みの可愛い娘だ。ほら、もっとちゃんと顔を見せてよ。」
「嫌っ!」
とっさに薬草をつかみ、男に投げつける。もちろんそれしきで男の歩みが止まるわけがない。
「いいねぇ。そそるよ。その整った顔が苦痛に歪むのを早く見たいなぁ・・・」
男の服は変色して固まりかけているが、まだ新しい血によって薄暗い星明りの下で不気味にてかっている。すでに今晩、他の獲物を狩った後なのだろう。悪魔は一晩に1リットルも血を吸えば腹が満たされる。ゆえに今、男が彼女を襲うのは生理的な理由ではなく、ただ殺人の快楽を貪りたいという理由からである。幼子が蟻を踏み潰して遊ぶ、男は殺人をそれくらいにしか思っていない。
「やめて・・・来ないでっ!」
「そうそう!もっと僕を怖がれ、泣き叫べ!最後にはちゃんと殺してあげるからさぁ!」
再び立ち上がり、逃げようとする彼女の髪を掴み、地面に押さえつける。男は右手に絡まる白銀色の細い髪をうっとりと眺めた。
「綺麗な髪・・・何て言うんだっけ?天の川色?きっと血の紅が映えるんだろうなぁ・・・!」
発達した八重歯がなめらかな首の皮膚にあてがわれた。必死の抵抗も、助けを求める声も全てねじ伏せられ、彼女は狂おしいまでの恐怖にさいなまれる。自宅で心配しているであろう両親の顔が脳裏に浮かぶ。嗚呼、ごめんなさい、お父さん、お母さん。言いつけを聞かなかったばかりにこんな最期を迎える娘をどうか許して。涙が止めどなく頬を伝う。
「あのぉ」
あまりにも間抜けな声に、唖然とした男は一旦少女の首筋から顔を上げた。いつの間にか祠の上に長髪の男がしゃがんでいた。どうやら彼はこんなタイミングで男に話しかけているようだ。
「あ?」
「俺はここらに住んでいるはずのある方を探しているわけだが、誰か見かけなかったか?」
男は自分の下で同じく唖然と彼を見ている彼女を見た。
「いやいや、女じゃなくて男なんだが。」
「いや・・・」
「そうか・・・。おっかしーなぁ・・・」
彼は困ったな、と頭を掻く。悪魔である自分を恐れないどころか、こちらの状況を全く気にした様子のない彼に、男は苛立ちを覚えた。
「おい、用が済んだんならさっさと失せな。僕はこれからディナーの3品目を喰うところなんだから。」
舌なめずりした男に彼女は再び怯え、無駄な抵抗を再開した。対して彼は男の言っている意味が分からなかったのか、首をかしげている。
「・・・まさか僕が黒魔族だって気づいてないの?殺されたいわけ?」
凄む男に気圧されもせず、彼は眉間にしわを寄せる。
「3品目?そんなに飲めないだろ。無駄な殺生は止めろよ。」
「おいおい、黒魔族は殺生を至上の快楽にする生き物だぞ?」
男はまずこのうるさい長髪を始末して、それからじっくり女をいたぶることに決めた。彼女を結界に閉じ込め、腰に挿していた短剣を構える。
「殺生は黒魔族の快楽ねぇ・・・。それならさ、」
彼も立ち上がる。と、同時に背から血が噴き出した。
「俺がアンタを殺っても、文句は言えないわけだ。」
彼女は怯えた目で彼を見つめた。彼の長い髪は返り血を浴びる前から赤かったようだ。そして徐々に血溜まりを大きくしている男に向けられる瞳も、血のような紅色だ。背に生やした赤黒い翼は彼も悪魔であることを象徴している。
「こんな新月の夜に、何で女の子が一人でうろついているわけ?悪魔に襲われて当然じゃないか。」
手を差し伸べるも、彼女は後ずさる。術者が斃されたために結界は消えて、逃げられるようになった。
「あなたも悪魔でしょ?何故私を助けるの?」
獲物を横取りしたかっただけかもしれない。恐る恐る問いかけた。問いかけたが、彼が何と答えようが信用する気は微塵もない。隙を見て逃げ出そうと思っていた。
「う~ん・・・悪魔にもいろいろいるってことかな?」
彼は適当に答えて何気なく足もとに落ちていたバスケットから残っている薬草を摘み上げ、臭ってみる。が、すぐにむせこんで薬草を放り投げた。
「ゲホッ!からし草!?なんでこんな幻覚作用のある薬草を・・・」
その瞬間、世界が傾いた。いくらからし草に幻覚作用があるからと言って、軽く臭っただけで目がくらむわけがない。彼女に突き倒されたのだと気付いたころには、彼の体は湖に着水していた。冷たい水が全身を包む。驚きからしばらく動けずにいた彼だが、すぐ体勢を立て直して岸まで泳ぎ着いた。
そこに彼女の姿はすでになかった。上半身だけ水上に上がった彼は、意識の無い男と、散らばったからし草を交互に眺め、ため息をついた。
「礼ぐらい言えよな、まったく・・・」
1.2. 旅人
白い石畳みに映える血痕。しかし、そこに死体は無かった。
昨夜、悪魔に襲われながらも奇跡の生還を果たした彼女の証言から、男たちは手に銃を持って町の守り神を祀る神殿に悪魔の死体の捜索へ来ていた。万が一、悪魔にまだ息があったならば、皆で止めをさそうと思っていたのだ。しかし、死体は無い。考えられる理由は2つだ。
「悪魔を殺したっていう男が死体を始末したか、でなかったら・・・」
悪魔が自力で逃げ隠れた、ということになる。後者の場合、かなり忌々しき事態である。深手を負い、怒った悪魔が町の人間を襲うかもしれない。
「その男はどんな人だったんだい?サージちゃん。」
「暗くて顔はよく見えませんでした。ただ、肩よりも長い赤い長髪で・・・紅の瞳をしていました。それと・・・」
「それと?」
流星色と呼ばれる青みがかった白銀色の髪を後ろで一つ結びにした彼女、サージは翡翠色の瞳を伏せた。
「たぶん・・・その人も悪魔です。」
どよめきが広がる。町の人間は勇敢な旅人が彼女を救ってくれたと思っていたのだ。
「本当か?」「悪魔同士の縄張り争いだったのか?」「この町にも悪魔が・・・」
サージは記憶を探る。彼を湖に突き落としたとき、何か違和感を持ったのだ。からし草を臭う彼の背後に近寄り、思いっきり駆け寄って彼の背中を突き飛ばした。その背には不気味な蝙蝠のような翼が1対、2対・・・?
「お父さん、私、昨晩初めて悪魔を見たけど、悪魔には翼が2対あるものなの?」
「え?」
傍にいたサージの父は目を丸くする。サージの父はこの町唯一の医師で、様々な生物の骨格を知っていた。父はしばらく腕を組んで考え込み、ゆっくり語り始める。
「皆さん、もしかすると悪魔ではないかも知れませんよ。サージを救った旅人は。」
皆の視線がサージの父に集まる。
「悪魔は1対の翼を持ちます。これは背の皮下にある翼専用の血袋から血を噴出させて形成するのですが、1対分だけでもかなり多量の血を要します。2対も形成すれば重度の貧血に陥って意識を保ってなどいられない。サージが見た旅人の翼が2対あったならば、彼は悪魔ではなく、もとより翼を2対持つ生物・・・例えば、妖精やドラゴンが人間に化けていたものだったと考えられます。」
人間に化けた魔獣が人間社会で生活するという事例は多々ある。しかし、人間を怖がる妖精やプライドの高いドラゴンがそんなことをしたという話はあまり聞いた事が無い。可能性の低い説ではある。
「本当に翼は2対だったのかい?両腕が翼に見えただけなんじゃないのかい?」
「そう言われると・・・」
星明りしかない夜闇の中での出来事だったので、サージは自分の記憶に確信がもてなかった。黙り込んでしまった娘の肩に優しく手を置き、サージの父は町の人に弁明する。
「彼女も怖い思いをして記憶が錯綜しているのでしょう。町の治安にかかわる重要な事ですが、少しだけ、サージに時間をあげてください。」
必死に記憶を辿ろうとするサージの肩は震えていた。助けてくれた旅人の事より、首筋にかかる生暖かい吐息の感覚や死への恐怖の方が鮮明に思い出されてそれ以上思い出したくなくなるのだ。
「あぁ、すまないね、サージちゃん。今日はゆっくり休むといい。また後日、話を聞かせてもらうよ。いいね?」
サージは小さくうなずいた。
サージと父が戻ったのは昼前だった。家には2つの扉があり、片方は診療所、もう片方は自宅への玄関となっている。自宅の玄関のノッカーを叩くと、エプロン姿のサージの母が迎えた。
「ずいぶんとかかったのね。大丈夫?サージ」
顔色のすぐれない娘の肩を抱くように押して、家の中に入れる。父は靴に着いた泥をふき取りながら捜索の結果を妻に伝えた。
「死体が見つからなかった。悪魔が生きているかも知れない。」
「まぁ・・・」
「サージを助けてくれた旅人が死体を処理したというならいいんだけどね、旅人の正体も分からないし、用心をしておいた方がいい。」
ダイニングへのドアに手をかけた母が振り返る。
「なら、悪魔がどうなったか教えてもらわなくてはね。」
父は眉間にしわを寄せた。話が通じていないと感じたのだ。
「だから、旅人の行方も分からないんだよ、ポーラ。」
口を開きかけて、サージの母は肩をすぼめ、ドアを開けた。入って左手、カウンター越しにキッチンが見える。タイルの敷き詰められたダイニングの真ん中にはカウンターに寄せる形でテーブルが据えられており、母が手織りした麻のテーブルクロスの上に小さい白い花が生けられた花瓶が置かれている。3脚ある椅子の一つには客人が座っていた。母が勧めた紅茶を口元に運びかけたところで、入室者に気づいて止まっている。サージと父も彼を見て固まった。
「赤い長髪に、紅色の瞳、年齢は20代で身長180センチ強の男・・・って、この人よね?」
母がサージから聞いた旅人の特徴を確認する。椅子に座っていたのはまさに昨夜サージを救った男に間違いなかった。思わずサージは後ずさりする。
「な・・・何故あなたが私の家に・・・!?」
彼はティーカップを受け皿の上に戻し、隣の椅子に置いてあったバスケットを持ち上げた。サージがからし草を入れていたものである。
「一緒に落としただろ?俺を湖に落としたときに。届けに来たわけ。」
両親は娘を見た。サージはいくら相手が悪魔だと思ったからとはいえ、命の恩人を湖に突き落とした事までは言っていなかったのだ。顔を真っ赤にしてバスケットを奪い取る。
「そ、そういう意味じゃなくてっ!どうやって私の家を突き止めたの?」
この質問に対しては、別に尾行したわけではない。朝、町に来てみたら何やら騒がしかったので、近くにいたおばさんに理由を聞き、ついでに家の場所を教えてもらったのだ、と説明をする。それでもサージと父は彼が悪魔かもしれないので警戒を緩めない。
「旅人さん、サージを襲った悪魔の死体が見つからなかったらしいですが、悪魔はどうなったのですか?」
旅人の翼の事を聞いていないので、母は全く警戒などせずにお菓子なんか進めている。彼は遠慮もせずにクッキーを一つ摘まんで口に放り込む。
「祭壇っぽかったし、あそこに放っとくのもどうかと思って森の中に移動させましたよ。」
「死んだ・・・のですね?」
「飛行核を潰したから、親切な誰かが回復魔法でも使わない限り生きては無いでしょう。」
飛行核が何かは分からないが、母は安堵した。しかし、人間にしては悪魔に詳しすぎる。父が妻を引き寄せて自分の背に隠すようにしながら問う。
「よく悪魔の事を知っているね。君も・・・悪魔だからかい?」
「え!?」
説明を求める母を無視して、父娘は紅茶を啜る彼を疑り深く見つめる。紅い視線を向けられ、3人は廊下へ1歩下がった。
「そうですよ。」
あっさりと認めた。むしろ隠す必要がどこにあるのかとでも言いたそうな態度である。さらに後ずさりした親子を見て、彼はため息をつく。
「人間ってのは俺たちの事を本当に知らないんだな・・・。何か誤解しているみたいだけど、俺たちは人間を見かけたら手当たり次第殺すような野蛮な種族じゃない。そりゃ昨日のあいつみたいに殺しが大好きなクレイジーな奴もいなくはないが、あれは異端ってわけ。俺もあそこまでの奴は初めて見たよ。」
それでも信じてくれそうにない様子を見て、諦めたように立ち上がる。
「ふん・・・。まぁいい。とりあえず、それは返したからな。それと、紅茶と菓子をありがとう。俺はおいとまさせてもらいましょうか。」
横の椅子に置いてあった皮をなめした鞄を背負い、帰り支度を始める。壁を伝うようにして3人は玄関への道を譲った。3人の態度を気にした様子もなく、普通に家を出て行こうとする旅人の背に、サージは勇気を振り絞って声をかけた。
「あ・・・あのっ・・・」
廊下の端と端で、2人は見つめあう。
「どうも・・・ありがとうございました。」
これには少々面食らった旅人は、やがて穏やかに微笑み、手を振りながら無言で出て行った。
自室で本を読んでいたサージは肌寒さに窓の外を見た。季節は夏から秋へ移りつつあり、日中はまだ暑いものの、夕方頃には涼しいを通り越して冷たい風が吹くようになった。時計に目をやると、現在17:44。そろそろ部屋の明かりをつけなくては字が読みづらくなってきた。部屋の入口まで行き、ライトのスイッチを押す。と、つま先にゴツゴツしたものが当たった。昼前に旅人が持ってきたバスケットだ。乾燥させた蔓を編んで作られたそれは、そういえば昨晩旅人と共に湖へ落ちた。内側の水分を拭き取っておかなくてはカビが生えてしまう。サージはタオル片手に床に胡坐をかき、その上にバスケットを置いた。
「ん?」
バスケットの中に小さく折りたたまれた紙が入っている。見覚えのないその紙を開くと、丁寧な字で手紙が書いてある。
流星色のお嬢さんへ
昨日も言ったと思うが、俺はこの町にいるという噂の知人を探しているわけだ。
しばらくはあの祭壇を拠点に情報収集をするつもりだ。西の空が赤くなってから
東の空が白み始めるまでの間はあの祭壇にいる。あと、昼飯時にもいると思う。
それと、アンタの髪は飛んでるとすごく目立つ。あんなの格好の餌食だ。
夜に出歩く時は黒めのフードを被れよ。出歩かないのが一番なわけだが。
湖に突き落とされた男より
そして紙の下の端には殴り書きでこんなことが書かれている。
追伸
からし草は効かなくなる。木のことは木こりに、魚のことは漁師に聞くと良い。
1. 呪われた町と新たな神 Ⅱ
1.3. 不治の呪い
翌日は休日で、サージは隣町の大学へ行かず、看護師の母と一緒に父の手伝いをしていた。医学部に通っているとはいえ、まだ学生なので医療行為を行う資格は持っていないが、彼女の住む町ネストでは現在、そんなことを言っていられないほど医療の心得を持つものが必要とされていた。
自宅に併設された診療所では患者を収容しきれず、町の体育館の床にシートを張って、その上に並べられたマットに患者が寝かされている。皆、身体のどこかに黒く丸い痣がある。この痣が徐々に大きくなり、激痛を与える病がネストでは流行っていた。
「タフタ!ミーシャの薬が切れたみたい!早く!」
妻に呼ばれて駆けつけると、巻毛の女性がもだえ苦しんでいる。2人かかりで彼女の腕を押さえつけ、注射を施す。しばらくして、ミーシャは激しくせき込みながらも再び眠りについた。打ったのは強い幻覚作用のあるからし草を煮詰めて作った鎮痛剤、つまるところの麻薬である。普通の鎮痛剤ではもはや痛みを和らげることはできなくなっており、最後の手段として用いていた。知り合いや大学病院の医師に聞きまわったが、病の正体も原因も治療方法もまったく分からず、しかも今のところ治癒した人は1人もいない。こうして脳を溶かす麻薬で薬漬けにして、なるべく苦しまないようにしながら衰弱死するのを待つしか手だてがなくなっていた。
「薬の量を増やしても効かなくなってきた。」
何もしてやれない悔しさから、サージの父は少し乱暴に椅子に腰を下ろした。しかし、すぐまた他の患者のうめき声が聞こえて立ち上がる。
「一体何なの?この病は・・・」
先月最初の患者が発見されてから日に日に患者数は増え、新たな感染症なのではという噂も出始めていた。そんな中での一昨夜の悪魔の出現。町の人間の不安は非常に強くなっている。
「病気ではないのかも知れないね。」
鎮痛剤を小瓶に注ぎながら、サージの母が呟く。
「ポーラ・・・君も、呪い・・・だと思うんだね?」
父は数日前から気づいていた。これが人間の医学で何とかできる『病』ではなく、『呪い』である事に。しかし、自分が生まれ育った町が呪われているなどと信じたくなかったのだ。
「呪い?」
「あぁ。呪いだよ、サージ。人間の科学が通用しない、白魔族や悪魔の業だ。」
大陸の南部に住む人間は、太古の時代より北の悪魔や東の魔物から身を守るために科学を進歩させてきた。身を守る衣服、外敵を倒す武器、人口を支える農業、法制度、建築学、医学など、生き残るためにあらゆる世界の仕組みを学んできた。しかし、人間にまだ学べていない仕組みがある。魔法だ。人間は魔力を体内にため込むことがほとんどできないため、研究対象が身近にいない魔法の分野はほとんどされていない。人間と同盟関係を結ぶ白魔族は多くの魔法の知識を持つが、魔法の使えない人間に教えても無駄と、相手にしてくれないのだ。
「白魔族にお願いして呪いを解いてもらえないの?州都に行けば魔導師がいるんじゃないかな」
魔法でしか解決できない問題を解決する対価に謝礼を受け取り、生活する出稼ぎ白魔族の事を魔導師と呼ぶ。ネストのような小さな町にはいないが、都市部にはたくさんいて、事務所を持っていたりもする。
「実力のある魔導師にお願いするには大金が必要だ。この町の財力では難しい。」
「でも、それじゃあ・・・」
いつか近いうちに町は滅びる。どうすればいいのかも分からず、3人は黙り込む。また、うめき声が聞こえた。
1.4. 黒い蛇
「夜中に出歩くなって書いただろうが。」
黒いフードをかぶって祠へ来たサージは声の主を探した。ランタンの置かれた手作りと思われる木のテーブルの近くには羽虫がふわふわ飛んでいるだけで、旅人の姿が無い。
「おい、聞いてるのか?」
バシャバシャという音を立てながら、湖から男が上がってきた。サージは持ってきた懐中電灯の光をそちらへ向ける。
「あっ!!」
旅人の姿を照らしてすぐに、顔を背け、身体を反転させる。彼は服を着ていなかった。
「何で裸なのよっ!」
「そりゃぁ、水浴びするときは服脱ぐだろ。誰かさんに突き落とされないかぎりは。」
この男、かなり根に持つタイプのようだ。わざと衣擦れの音を大げさにさせて怒りを表現している。
「しつこいなぁ・・・悪かった。ごめんなさい。」
「心がこもってない。」
「キャッ!!」
ズボンだけを身に着けた旅人が急にサージの右腕を掴み、自分の方を向かせる。とっさに振り払おうとしたサージだが、ランタンに照らされた自分の肘を見てギョッとした。まだ小さいものの、先ほどまで体育館で見てきた痣と同じものが右肘に出来ていたのだ。左手で患部を押さえ、力なく地面に膝をついた。そして死への恐怖から全身が震えだし、両手で自分の肩を抱いた。
「そんな・・・そんなっ・・・」
「一昨日こけた時にできた擦り傷から入ったんだな。」
サージは涙ぐんだ目で旅人を睨み付ける。他人事のような態度に腹が立ったのだ。
「あなたは・・・この病を知っているの?まさかあなたが・・・」
「おいおい、勝手に人を犯人扱いすんなよ。それに、それが『病』じゃないって思ったから俺に会いに来たわけだろ?」
彼はテーブルの横の椅子にかけていたベルトを取りに行く。ベルトには短刀がつけられている。彼が短刀を鞘から引き抜いても、サージは怯えずに座り込んだまま黙って震えていた。
「そうそう、昨日アンタらにした話、嘘だ。」
短刀で自分の右の人差し指の先を小さく切り、血を出す。
「俺はある男を探している。その男の魔力を探してウロウロしてたら、あの体育館へたどり着いた。で、体育館の入口に貼ってあった張り紙からアンタの家に行きついたわけ。」
サージは顔を上げた。
「魔力?じゃあこの呪いは・・・」
「あぁ、多分俺が探している男の呪いだ。何があったか知らないが、この町に相当な恨みを持ったんだろうな。」
ランタンの明かりに照らされた旅人の首筋と左胸には古い創傷の跡があった。
「・・・その傷も、その人に関係があるの?」
旅人は一瞬胸の傷を見て、笑った。憂いをおびた瞳で。
「人の心配してる場合か。さ、肘を見せて。」
突き出された右肘が明るくなるようランタンの位置を調整し、次いで人差し指で痣を囲うように丸く血を付ける。集中するために長い深呼吸を一つ。緊張感が漂ってきた。
「よし、右手で左肩、左手で右手首を掴んでなるべく肘を動かさないように。いいか?これから呪文を唱えて、ちょっと肘に切り傷を付ける。少々痛むかも知れないが、我慢してろよ。」
今度は自分の右腕の肘から手首にかけて短刀で浅く傷をつける旅人に、不安そうな顔を向ける。傷口から血がにじみ出てきた。
「大丈夫、すぐに終わる。いくぞ。」
生唾を飲み込み、うなずく。旅人はブツブツと呪文を唱え終えるとサージの肘に浅く切りつけた。途端に肘の皮膚と肉との間で何かが蠢くような痛みが彼女を襲う。歯を食いしばり、言われた通りできるだけ肘を動かさないようにしていると、急に痛みが消えると同時に肘の傷口から黒い蛇のようなものが飛び出した。蛇は旅人の腕の傷に飛びつき、その中へ入ろうとうねる。旅人は顔をひきつらせながらブツブツと他の呪文を唱え続ける。頭を傷口に食い込ませた蛇はしばらくもがいていたが、じきに力なくぶら下がった。ふぅ、と息をついた旅人は左手で蛇を摘まみ出す。全長5センチほどの小さな黒い蛇は、もう動かない。
「よし、終了。ちょろいもんだな。」
サージはこのセリフを皮肉と取っていいかどうか迷った。そんな彼女を余所に、旅人は蛇をころころと丸めてパクリと食べてしまった。
「ちょっ!食べて平気なの?」
「もうヒトを呪う力は残ってない、ただの魔力の塊だ。呪いを解くのに使った魔力を少しでも補ってもらおうってわけ。」
右腕に包帯を巻き、さらにサージの肘に付けた自分の血を拭う。黒い痣は消えていた。サージは旅人に満面の笑みを見せた。
「ありがとう!あなたには2回も助けてもらってしまったわ。何かお礼ができたらいいんだけど・・・」
旅人はサージから視線をそらした。実のところ、彼女の笑った顔があまりに可憐で、恥ずかしくなったのだ。ランタンの明かりが当たらなくなり、丁度サージから顔が見えなくなっていたので気づかれずに済んだようだが。
「・・・この呪いについて調べれば何か手がかりになるかもしれない。ってわけで、他の人間の呪いも見たい。」
彼の言わんとしていることは伝わった。町の人間が悪魔である彼を怖がらないよう、サージに間を取り繕ってほしいのだろう。サージは立ち上がる。
「わかった。それじゃあ早く残りの服も着て、荷物もまとめて。」
「は?まさか今から行くのか?」
目をぱちくりさせる旅人。
「善は急げって言うでしょ?」
悪戯そうな笑顔もまた旅人の心をくすぐる。
「じゃあ、荷物は置いていく。どうせここに戻ってくるし・・・」
「こんな寒い所で寝泊まりしてたらそのうち風邪ひいちゃうもの!家に空いてる部屋があるから、そこに泊まればいいよ。」
予想だにしない提案に、旅人はたじろいだ。先ほどまでの警戒心はどこにいってしまったのだろうか?
「・・・良いのか?悪魔と一つ屋根の下、なんておっかないだろ?」
「あなたなら、平気。そんな気がする。」
旅人は口元に笑みを浮かべながら頭を掻いた。ずいぶんと信頼されてしまったものだ。
「そりゃどうも。流星色のお嬢さん。」
手紙を読んだ時から思っていたが、大して歳の離れていない(と思われる)彼が自分のことを『お嬢さん』と称するのはなんだか可笑しかった。そういえば、まだ互いに自己紹介していなかった。
「私、サージ。あなたは?」
旅人も自己紹介をしていなかったことに気付いたようで、そういえば、と手を打った。
「俺はリップルだ。」
1. 呪われた町と新たな神 Ⅲ
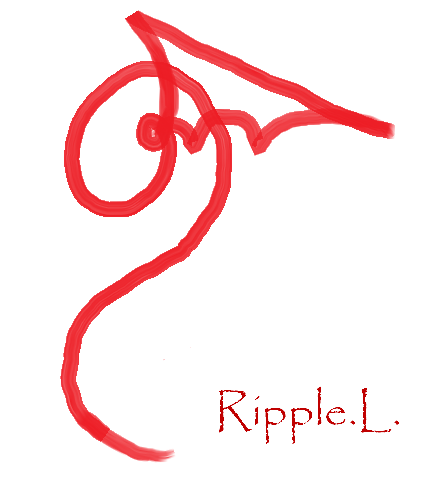
1.5. 貧血
結局、明け方頃までリップルは体育館で呪いを解き続けるはめになった。最後の一人から取り出した黒い蛇を口に入れ、ドカッと椅子に落ちるようにして腰かける。
「ふぇ~!疲れたぁ。」
黒い蛇を喰らうことで多少は魔力を回復してきたが、収支は赤字である。数回ならまだしも、50回弱も赤字を重ねればさすがに若干の魔力不足を感じざるを得ない。そして何よりも眠い。ぐったりと背もたれに寄り掛かるリップルに、サージと両親が近づく。そのままの体勢で、紅い視線だけ親子に向ける。
「本当にありがとう。感謝してもしきれないほどだ。」
サージの父が深々と頭を下げる。母とサージもそれを見習う。意識を取り戻した患者たちと、夜中に呼び出されたその家族、体育館にいる全ての人間が口々に感謝の言葉を述べる。
「んにゃ、いいって事よ。俺も情報収集させてもらったわけだし。ふあ~・・・っ」
欠伸をしながらだらしなく伸びをするリップルの顔を見て、サージがくすくす笑う。
「目の下に隈ができてる。お疲れ様。」
「アンタもな。」
サージは慌てて目の下を指で隠した。その様子をニマリと見つめてから、姿勢を正して町の人に視線を移す。
「ネストの皆さん、俺はある男を探してこの町へ旅して来ました。イデア、という名の男に心当たりはありませんか?多分、足が不自由な、銀色の髪をした老人なんですが。」
皆、互いに顔を見合わせる。収穫はなさそうな予感だ。
「ん~・・・、わかりました。ここにいない人にも訊ねてみてください。何か思い出せたら、俺はしばらくタフタ医師の家に居候させてもらうことになっているんで、知らせに来てください。よろしくお願いします。」
町の人たちは了承した。話が終わると、短く髭を生やした山男と呼ぶべき体格の男が進み出る。曰く、ネストの町長だとか。町にはびこる呪いを解いてくれる悪魔が現れたと聞いて、やってきたのだ。
「イデアという方の情報提供はもちろんですが、他に是非とも我々にお礼をさせて下さい。ささやかですが、明日・・・もう今日ですが、晩に宴を開きます。」
イメージ通りの野太い声で提案する。この町長が開く宴となると、何だか熊丸々1頭とかが料理に出されそうでちょっと怖いな、とリップルは勝手に苦笑いした。
「別にそこまでしていただかなくても・・・!」
「遠慮せずに、お好きな食べ物でも飲み物でもおっしゃって下さい。用意させていただきます。」
あまり拒むのも申し訳ないと思い、リップルは頭を掻いた。
「そうですか・・・?う~ん・・・好きな食べ物ねぇ・・・」
両親と話をしているサージをちらりと見る。ふと、少しおどかしてやろうかという悪戯心を抱き、すっと立ち上がる。彼女を抱きすくめて、『若い女の生血』とか言えば人間の抱く悪魔像っぽいかな、なんて考えていた。
が、しかし、その冗談は実行に移す前に失敗した。急に目が眩み、倒れることは免れたものの、体育館の床に膝をついてしまった。貧血の症状だ。
「リップルさん!?」「リップル!」
周囲のざわめきもエコーがかかったように耳の中で反響して聞こえる。背中に誰かの手の温もりを感じた瞬間、沸き起こった強い吸血願望にリップルは歯を食いしばる。普段なら近くにいる獣や人間を襲って血をいただくところだが、信頼関係を築いてイデアの情報を得ようという時に町の人間を襲うわけにはいかない。やはり無理をしてはいけないな、なんて冷静な反省を抱きながら、意識が暗い靄に包まれていく。
断片 1
いやだよ、おとうさん、やめて
いたい いたいよ、おとうさん
なぐらないで、けらないで、おねがい
わたしのだいすきなおとうさん
わたしのだいすきなおかあさんをぶたないで
いやだ、いやだよ、おとうさん
いつものやさしいおとうさんにもどって
いいこにするから いうこときくから
いたいよ、おとうさん、くるしいよ、おとうさん
おとうさん おとうさん おとうさん おとうさん
おとうさんなんて、××じゃえばいいのに・・・
1.6. 未知への恐怖
目が覚めた。冷たい汗が体を伝う。自分が誰なのかさえもわからないほど頭が混乱していた。右手首を額の上に乗せてまぶしい照明の光を遮る。右手首に銀色のブレスレットがつけてあった。表面には『Ripple.L.』の文字と、炎を逆さまにしたような紋章が刻まれている。
「リ・・・ップル・・・える・・・」
読み上げたところで自分の事を思い出した。たしか、ネストの人間の呪いを解いて、宴に招待されて、それから、それから・・・。そこで記憶が飛んでいる。状況を理解しようと上半身を起こした。ここはカーテンに仕切られたベッドの上で、どうやらここは病院のようだ。左肘の内側にチューブが繋がれた針が刺さっている。さらにチューブの反対側は金属製の柱にぶら下げられた透明な袋に繋がっている。袋の中の見慣れた赤黒い液体は恐らく血だ。
「あ!リップル!気が付いた?」
カーテンの隙間からサージが見える。彼女はカーテンを勢いよく開け、ベッドに駆け寄ってくる。リップルは血の入った袋に視線を戻す。
「これは?」
「ん?あ、輸血のこと?リップル、昨日の朝体育館で倒れたでしょ?検査してみたら重度の貧血だったから、輸血したんだ。」
「ゆけつ・・・?」
サージは目を丸くして、輸血をしている理由ではなく、輸血そのものについての質問だったとは、と驚いた。人間が当たり前のように用いる科学技術は、悪魔や白魔族にとっては馴染みのない代物なのだ。
「えーっと、怪我とかで血が足りなくなった人に、他の人からもらった血をこうやって投与するの。」
「血をもらうって・・・金で血を売るような奴がいるのか?」
サージは困って苦笑いした。
「何でお金の話になるのよ・・・。有志で無償で提供してもらうの。自分の血で助かる人がいるのならって。」
「ん~・・・、なら何で慢性的に血が足りてない俺たちには提供してくれないんだ?」
「それは・・・」
そこまで言って、言葉に詰まる。これを言ったらリップルは機嫌を損ねるかもしれない。だが、思いついた理由はただ一つ。
「多分・・・怖いから。」
ふん、とリップルは鼻を鳴らす。やはり癪に障ったようだ。
「何で人間は白魔族ばっか頼って俺たちを怖がるんだか・・・。」
「知らないからだよ。」
リップルと出会ってから分かったことだが、サージたち人間は悪魔の事をあまりにも知らなすぎた。襲われた人間の恐怖体験や、悪魔と敵対関係にある白魔族から得られる悪いイメージばかりが伝わり、悪魔は危険な者たちで、こうやって話をしたり、助け合ったりできる相手だとは思ってもみなかった。
「人間は悪魔の事をほとんど知らない。だから怖いんだよ。でも、リップルと会って、怖がってばかりないで、貴方たちの事をもっと知りたいと思った。」
紅い視線と翡翠色の視線が絡み合う。リップルはこの時ようやく、何故新月の夜にこの娘を助けようと思ったのか理由が分かった。彼女の流星色の髪と、色は違うが優しさの中に強い意志をのぞかせる眼差しは似ているのだ。あの女に・・・。
「・・・でもこれ、いいな。」
「え?」
サージから視線を外すために、リップルは輸血のパックを見上げた。
「人間を襲わなくても血がもらえる。この技術が広まれば、俺たちは人間ともっと仲良くなれると思うわけ。そうだろ?」
そうだね、と、彼女に似た眼差しが笑う。心を掻きむしる記憶がこれ以上蘇らぬよう、リップルも無理に笑った。
1. 呪われた町と新たな神 Ⅳ
1.7. 宴
リップルが倒れたために延期になっていた宴は、結局1日遅れで、彼が目覚めた日の夜に催されることになった。夕暮れの道をサージと両親に連れられて会場へ向かう。
「リップルさんは何歳なの?」
サージの母が唐突に聞いた。
「え?・・・23ですが・・・?」
ああ、良かった、と3人は微笑みあう。意味が分からず、リップルは説明を求めてサージを見た。普段薄くしか化粧をしないサージだが、今日は橙色の口紅を挿している。リップルは慌てて視線を外す。
「町長がお酒を用意したから、そういえば飲める歳なのかな?って心配してたの。」
「飲める歳・・・?」
「人間の法律では20歳未満の未成年は飲酒を禁じられているんだよ。」
サージの父の説明にも、リップルは首をかしげて一応の相槌だけ返した。悪魔の社会では未成年の飲酒禁止というルールが無い。そもそも歳による『成年』という概念が無く、自分で獲物を狩って血を飲めるようになれば何歳であろうが大人の一員となるのだ。
「そもそも俺は酒ってのを飲んだことが無いんだが・・・。そんなに旨いものなわけ?」
「私は苦手かなぁ。」
と、言っていたのは嘘だったのだろうか?リップルは葡萄酒(リップル曰く『渋い酒』)を飲みながら同年代の友達にからむサージの様子を、宴の主賓席から呆れながら眺める。橙色の提灯の明かりの赤みを差し引いても、サージの顔は真っ赤だ。酔いやすい、という意味の『苦手』なんだ、と自分を納得させる。
「楽しんでいるかい?リップル君。」
サージの父が果物の盛り合わせが乗った皿をリップルの前に置く。彼の顔も娘ほどではないが赤い。酒に弱い家系なのだろう。
「ええ。フェニール地方の果物は皆おいしいですね。流石は名産。」
フェニール地方、というのは人間が多く住む大陸南部の名称だ。温帯から熱帯の気候を持ち、果物をはじめ農産物が豊富に採れる。
「ネストはフェニールでも北の方だから、生産量は少ないんだ。今夜は君のために町長がかき集めてくれた。」
「そりゃぁ、ありがたい。」
町の中心にあるこの広場に飾り付けられた提灯は、よく見ると作物の形をしてる。豊穣を感謝する祭りのようだ。
「この飾りも今回のために?」
「いやぁ!違うよ!」
サージの父もそこそこ酔っているようだ。普段からは考えられないハイテンションでからんでくる。サージの酒癖の悪さは父親譲りのようだ。
「この町では毎年これくらいの時期に町の守り神に1年の幸を感謝する祭りが行われていたんだ。これはその時用の飾りさ!」
「行われていた・・・。今はやってないわけですね。」
サージの父に付き合って、ビール(リップル曰く『シュワシュワする苦い酒』)を一口飲む。飲み干してから質問に答えようとしていたサージの父は、後ろから娘に体当たりを喰らってビールを自分の服にこぼしてしまった。
「おっと!やってくれたね、サージ。ちょっと待ってて、タオルをもらってくる!」
父親が退場すると、サージはリップルの肩に寄り掛かってきた。酒のせいで体温が高くなっている。
「リップル、祭りの話ぃ?」
「ああ。今はやってないのか?」
明日酔いが醒めてから思い出して後悔しないだろうか?と心配するリップルを他所に、サージは彼の膝の上に座った。
「できないのよ。今、私たちが乗ってるステージ、何でしょうか~?」
宴の催されている広場の中央には、リップルの席と料理や飲み物の机が置かれている直径20メートルはある円形のステージがある。リップルは足元を見て、年輪を発見した。
「切り株・・・?切られる前はそうとう大きかったんじゃないか?」
「正~解~!ゼクウの大木!枝が鳥の巣みたいに広がってて、だからこの町は『ネスト』って名前なのっ!でも、去年、切っちゃった。」
ゼクウというのは大陸東部に多く生える木だ。5000年以上生きるともいわれる大木で、神聖な力が宿るとされている。
「何故?」
飲まずにやってられるか、と言わんばかりにサージはウィスキー(リップル曰く『ツンとする酒』)ベースのカクテルをあおる。
「電波障害の原因になるから~とか何とか!本当はこの木に住んでいた龍が怖くなって追っ払いたかっただけ!ひっどい話らよねぇ~!」
酔ったサージの話を分かりやすくまとめると、こうだ。ネストではゼクウに住む龍を昔から守り神として崇めて来た。しかし、近代化にしたがって信仰が薄くなり、龍は危険だと考える町民が増えた。そこで、神木であったゼクウの大樹を切り倒してしまった。
「だ~か~ら!祭る神様がいなくなっちゃったから、お祭りはもうしないの!終わり!おしまい!」
やけくそ気味に話を終わらせたサージは勝手にリップルの杯(まだビールが入っている)に葡萄酒を注ぎ、氷をごろごろと追加する。
「その追い出された龍はどうなったわ・・・んぐっ!」
サージがビールと葡萄酒の混ざった杯を無理やり口に押し付ける。飲まないと質問をさせてくれそうにない。リップルは案の定あまりおいしくない混合物を頑張って飲む。
「知らな~い!木を切るときに怒って襲ってきた龍を町長さんたちが銃で森の方へ追い払ってたけど、どうなったんだろうね~?綺麗な龍だったのに、酷いことをするもんだよ。」
「あの町長だとやりかねないな・・・って、おい!」
急に彼女が顔を近づけて来たので、リップルは慌てて彼女の肩をつかみ、それ以上近づかないようにしなくてはならなかった。気にせずサージは自分の唇を指さした。
「こんな色の、綺麗な龍だったの。祭りの時には提灯の光に鱗をきらめかせて・・・幻想的だった。どこ行っちゃったのかなぁ?橙龍・・・」
肉料理の机の向こうからドッと大きな笑い声が起こった。
「キスしろー!」「止めろー!」「奪っちゃえ~!サージ!」
やんやする声に背中を押されて、サージは瞼を閉じる。リップルの手がサージの肩を放した。
1.8. 漆黒の龍
上空で光が炸裂した。花火ではない。会場の人々は皆、突然の爆発に悲鳴を上げながら地面に伏せる。光の正体は空を見ればわかった。
「龍だ!」
夜闇にまぎれそうな漆黒の龍が咆哮している。龍の口に光が集まり、広場に向かって放出された。
ドーーーンッ!
先ほどと同様に、広場を覆う透明な膜が龍の攻撃を防ぐ。左腕を天に掲げられたリップルが結界を張っているのだ。右手でサージ守りながら、第3波も防ぐ。龍はらちが明かないと察したようで、龍の言葉で呪文を詠唱し始めた。
「広場から逃げろ!早く!」
サージを両親の方へ走らせ、リップルはグッと膝を曲げる。彼の背に赤黒い翼が現れる。しかし、新月の夜にサージが見たときとは異なり、翼は1対だけだ。走りながら横目でリップルの翼を確認し、サージはやはり見間違えだったんだ、と思った。
リップルは地面を強く蹴り、上空へ飛び上がって、龍の呪文詠唱を短刀で斬りつけることで中断させた。龍は怒って噛みついて来た。それをひらりと避けて短刀を払う。龍の腹から黒い液体が吹き出し、リップルの身体を染めた。耳をつんざく叫びが広場にこだまする。
「ギャアァアアアアア!!!」
しかし、浅く入ったその攻撃はさらに龍を怒らせることになった。龍は体勢を立て直して目にも止まらぬ速さでリップルに体当たりを仕掛けて来た。避けきれず短刀を盾にして防御するが、勢いを殺しきれずに後方へ押される。このままでは広場横の電波塔に背中から叩き付けられてしまう。
「ちっ・・・!」
リップルが力むと、翼の下に、赤い翼がもう1対生じた。それは血を噴出させて形成されたものではなく、骨格のある蝙蝠のような翼だった。
「翼が2対の悪魔・・・!?」
すっかり酔いが醒めたサージの父は建物の影からリップルの翼を見て驚きの声を上げる。翼が増えたことで少しスピードが弱まった。龍の顎の上へ逃れ、赤く光る目玉の前で叫ぶ。
「目を覚ませ!イデア!」
龍の動きが止まる。広場の様子をうかがっていた町の人は耳を疑った。イデア――たしかにリップルは龍のことをそう呼んだ。我に返った龍は、ゆっくり高度を落とし、ゼクウの切り株の上へ降り立った。一息ついたリップルが翼をたたんで龍の頭から滑り降りる。
町の人が恐る恐る広場へ戻り始める。両親の制止を振り払い、サージが切り株の上へ駆け上がった。龍と見つめあったまま、リップルは短刀を腰のベルトへ戻す。
「そうだよ、サージ。こいつが俺が探していた男、イデアだ。」
低く唸ってサージを威嚇するイデアに手のひらを見せ、大丈夫だと落ち着かせる。
「まさか・・・この龍はネストに住んでいた橙龍なの?」
「橙龍だったもの、だ。もう死んでいる。町の人間に殺されて、恨んで呪いを発生させたわけだな。」
町長に視線が集まる。町長は顎の髭を撫でながら、バツが悪そうに頷いた。
「ゼクウを切った日、龍が怒って暴れた。放っておけば町を襲うと思った。だから、銃で森へ追い立てて祠で倒した。」
人間の言葉がわかるらしい。龍は町長に今にもとびかかりそうだ。何か喋っている。
「・・・生き埋めにしたのか?」
リップルの言葉に町長は驚く。そのことは共に龍を追い立てた数人しか知らないはずだ。
「なぜそれを・・・」
「祠の裏で、くぼみに落ちた。上から岩が降ってきた。体が挟まれ、動けない。骨が砕ける。肉が千切れる。臓物がつぶれる。痛い。苦しい。今まで町を悪魔や厄災から守ってやっていたのに。恨んでやる、呪ってやる。我が苦しみを思い知らせてやる・・・」
リップルはリップルで龍の言葉が分かるようだ。恨みを言うにしたがって龍から黒いオーラが広がり、近くに散らばっている食べ物が腐敗していく。リップルの体に着いた血がぐつぐつと蒸発し、皮膚に黒い痣を刻んだ。オーラはサージの元へも広がり、見る見る彼女の全身を呪いが蝕んでいく。
「呪いだ!」
皆、一斉に広場から離れる。しかし、サージは動かない。
「どうすれば!」
痛みに耐えながら叫んだ。リップルが振り返る。
「どうすれば、その龍を救えるの?」
町を守ってくれていた龍を、町の人間が自己中心的な考えで殺めてしまった。その償いをしようというのだ。サージの決意を目の当たりにして、リップルは再び2対の翼を広げる。
「祭りをやるぞ。俺は祠へコイツの身体を解放しに行く。その間に祭りの準備をするんだ。」
龍を伴って、リップルは夜空へ飛び立った。
1. 呪われた町と新たな神 Ⅴ
1.9. 祭
日付けが変わってしばらく経った。龍が広場を襲撃してからの2時間ほど、町は上を下への大騒ぎだった。龍を恐れる町の人の気持ちは変わらない。だが、サージが呪われ、唯一呪いを解けるリップルも呪いを受けた。龍を救わなくては、サージが助からない。人質をとられた形の人間は、リップルの言うとおり祭りの準備を急ぐ。
ゼクウの切り株の前に白い布で覆った祭壇が据えられ、その上にゼクウの葉付きの枝を乗せる。祭壇の両脇に提灯を立てて橙色の灯りをともす。そこから少し離れた場所で、サージは椅子にぐったりと座っていた。サージの母が彼女に白い衣を纏わせ、橙龍を象った金の冠をかぶせる。サージはこの祭りの巫女であった。サージの母の家系は代々、祭りの巫女を務めてきた。流星色の髪が、橙龍の銀色のたてがみと似ているからだ。
「何故、龍はこんな事を・・・。サージが一番あの龍を心配していたのに。」
肌の大部分が黒い呪いに侵された痛々しい娘の姿に心が痛む。気づけば着付けをしながらぼやいていた。
「お母さん・・・私・・・今なら・・・分かるよ・・・橙龍の・・・気持ち・・・。痛くて・・・苦しくて・・・悔しくて・・・・・・。こんな・・・辛い思いを・・・抱いたまま・・・死んでも・・・死にきれなかったんだ・・・。」
うわごとのように呟く。全身が燃えるように痛むが、意識ははっきりしていた。懐かしい祭りの会場が出来上がっていく光景を穏やかに見守っていられる自分がいた。
「龍が戻って来たぞぉ!」
地上からライトを当てられて夜空に照らし出された龍は、先ほどと姿が変わっていた。黒いもやだけで形成されていた龍の身体は、今度はちゃんと実体がある。一部が白骨化した腐敗が進む身体は、強烈な異臭を放ちながらゼクウの切り株に降り立った。傍にリップルの姿は無い。
「サージ・・・」
「大丈夫。できる・・・」
サージは立ち上がり、ふらつきながら祭壇へたどり着いた。ゼクウの枝を震える両手で掲げ、龍に深くお辞儀する。そして神へ捧げる言葉を奏上する。
「 我らが鎮守の守り神
太陽の化身の赤き龍よ
闇を照らす灯火の龍よ
地を治め
水を湛え
天を照らせよ
橙の龍 」
龍は細く長く吠え、祠の方へ飛び戻った。
リップルは祠にいた。龍を閉じ込めていた祠の裏の一枚岩が移動していて、その上に胡坐をかいている。涼しい顔をしているが、かなり汗をかいている。彼もまた、痛みに耐えているのだろう。
「あれ?祭りは広場でやるんじゃなかったのか?」
「第一部はね。〆の第二部はこっちに場所を移すんだ。」
サージの父が娘を負ぶり直しながら答える。そして湖の少し上で浮遊する龍を横目に見ながら囁く。
「祭りをすればサージや君の呪いが解けるのかい?」
サージは移動中に発熱しはじめ、自分で歩けなくなっていた。祭りの第一部は終わったというのに、症状は悪化の一途をたどっている。
「解けないですよ。」
さらっと言ってのけるリップル。面食らってサージの父は何も言えない。
「この祭りは俺たちの呪いを解くためのものじゃない。あんな姿になってしまったイデアを浄化し、葬るためのものです。イデアはこの町の守り神だった。ヒトに正しい葬り方があるように、神には神の正しい葬り方があるわけ。正式な手順を踏まずに生き埋めなんかにするから、死にきれなかった神に呪われたんですよ、この町は。」
ここでイデアが歌い始めた。祭りの第二部の始まる合図だ。ぐったりとしていたサージが急にむくっと頭を起こし、父親の背から降りる。歌に操られるようにサージは祠の前の祭壇まで進み、持ってきたゼクウの枝を左右に振る。
「 我らが鎮守の守り神
太陽の化身の赤き龍よ
闇を照らす灯火の龍よ
地を治め
水を湛え
天を照らせよ
橙の龍 」
広場で奏上されたものと同じ言葉が繰り返される。繰り返す度に龍は祭壇へ近づき、8回目が終わったところでサージの手からゼクウの葉を1枚食べた。その瞬間、急激な上昇気流が祠周辺から巻き起こり、湖の水が輝きながら浮き上がった。
「おぉ!」
町の人たちは思わず声を上げた。闇に染まっていた龍の身体が、淡い光を放つ橙色に変わったのだ。まさしくサージが付けている口紅と同じ、美しい橙龍である。龍から発せられる黄金色の光が周囲の水滴に散乱され、闇夜を幻想的な空間に染めた。
「クリュリュリュ~」
リップルが通訳せずとも、サージには龍の言っていることが分かった。龍の呪いを受けた身は、龍の言葉を解すようだ。
「御心安らかに眠りたまうよう、かしこくかしこく、申し上げ奉る。」
体が、口が勝手に動く。それでも、操られているわけではない。自然とそうすべきだと分かり、そうしようと思い、そうなった、そんな不思議な感覚にサージはもはや痛みを忘れていた。『願いは聞き届けられた』という声が聞こえた気がした。安堵したサージの身体から力が抜け、祭壇にもたれるように気を失った。
一方、龍の身体は透明になり始めた。満ち足りた穏やかな表情でサージから離れ、湖の中央へ移動する。紫色の澄んだ瞳が岩の上のリップルをとらえる。思い出したように彼に何か語り掛ける。
「え?俺が?」
少し困った様子のリップルに、さらに言葉を投げかける。頭を掻いて、しばし唸ったリップルは仕方ない、と右腕を差し出した。龍はその手に頭の先で触れる。龍からリップルへ、何かが移った。最後に2・3言葉を交わし、龍は湖の上で光の粒となって消えた。骨と鱗が水滴とともに湖へ落ち、湖の水がうっすらと輝く。
「ゆっくり眠れよ。イデア。」
岩の上のリップルは、その様子を寂しそうな表情で見届ける。
リップルは岩から飛び降り、祭壇に倒れたサージの元へ駆け寄った。龍は浄化されたというのに、2人の呪いは解かれていない。娘を腕に抱きながらすがるようにサージの父がリップルを見上げる。母も傍らで真っ青な顔をリップルに向けていた。サージの呼吸が弱くなってきている。
「リップル君!サージが・・・!」
頷いて、リップルは湖の岸まで走って水を両手に汲んできた。それを飲ませようと口に流し込むが、弱弱しくむせ込んで受け付けない。舌打ちをして再び水を汲みに行き、サージの前でしゃがんだ。一瞬迷って、
「失礼しますっ!」
と早口に断ってから水を自分の口に含み、そのまま口移しで与える。両親の目の前で娘の唇を奪うのはかなり気まずいが、今はそんな事を言ってられる場合じゃない、と自分に言い聞かせながら。今度こそサージは水を飲み込んだ。とたんに全身の黒い痣が消えていく。
「サージ!」
「うっ・・・・・・お父・・・さん・・・?」
胸をなでおろしたリップルは、サージの父と目が合う前にまた湖まで走って行って自分の呪いを解く。あまりにも彼が慌てているのが面白く、それまで黙っていた町の人たちはそろって大笑いした。呪いが解けた町に、新しい太陽が光を注ぐ。
1.10. 新たな神
早朝。町の人々はすっかり荒れてしまった広場の片付けに追われていた。そんな中、すっかり体調が良くなったサージは一人で祠まで戻ってきていた。手にはシャベルと小さなゼクウの苗を持っている。龍が生き埋めにされていた部分は石畳が砕け、土が露出していて、そこをシャベルで耕した。最後に小さな穴を掘り、ゼクウの苗をそっと植える。
「もう大丈夫なのか?」
いつかのように突然湖の方からリップルの声がした。恐る恐る声の方を見ると、今日は裸ではなく、岩場に腰かけ靴を脱いで足を水に浸けている。サージはほっとした。
「うん。リップル、こんな所にいたんだ。」
曰く、昨晩消費した魔力を湖で回復しているとのこと。イデアの魔力が水に溶け込み、何の変哲もなかった湖は魔力の泉へと変わっていた。
「私にキスしたのが恥ずかしくて顔を見せられないんじゃないかって皆が言ってるよ。」
「なっ・・・別に!うわっ!」
急に立ち上がって足を滑らせたリップルは湖へ落ちた。熱で水が蒸発するのではないかというくらい顔を赤くしたリップルの顔が水面に浮かぶと、サージはたまらず笑い始めた。彼女の頬も赤みを帯びていて、照れ隠しの笑みでもあったようだ。
「その・・・すまなかった・・・。今思えば他に方法もあったが、俺も慌てていたわけで・・・。」
「私が怒ってると思うわけ?」
しゃがんだ膝の上で頬杖をつきながら、サージはリップルの口癖を真似てみる。立ち泳ぎをしながら、リップルはサージを見つめる。服装は祭りの時のままで、金色の冠が彼女の流星色の髪の美しさを引き立てている。
「・・・怒ってない。と、思う。けど・・・」
お茶を濁し、水中に口を入れてぶくぶく泡を立てる。
「けど?」
「それって・・・、いや、その・・・・・・ゴホンッ!」
結局最後まで言わずにサージの傍の岸まで泳ぎ着き、水から上がって服を絞る。魔力は回復したが、秋口の着衣泳ですっかり体が冷えてしまった。顔は熱いままだが。
リップルを茶化すのもこれくらいにしておいてあげようと思い、サージは湖へ視線を落とす。ほのかに輝きを放つ清らかな水。この下に町を守ってくれていた龍が眠っている。自分が龍を葬ったとはまだ信じられない。
「リップルのお知り合いだったんだね、あの龍。綺麗な神様だった・・・。」
長い髪を根元から絞って地面を水浸しにしていくリップルには、サージの背中が寂しそうに見えた。
「・・・神がいなくなって、この町は平気なのかな?悪魔が町の人を襲うようになったのも、龍が守ってくれなくなったからなんだと思う。中途半端な覚悟で神を屠ってしまったこの町は、これから龍が遠ざけてくれていた色んな災難に立ち向かっていかなくちゃならないんだよね。」
「生きるって、そういうことだろ。」
「・・・そうなのかもね。」
生まれたての頃は親が守ってくれる。成長するに伴い反抗期を経て自立していき、最後には一人立ちして自分の家庭を作っていく。ネストは反抗期を終え、今日から一人立ちをすることになった。最初は苦労するだろうが、きっとやっていけるだろう。
「でもま、よっぽど困ったことが起こったら助けになるよう、イデアは後継者を立てたわけだし、なんとかなるさ。」
「後継者?」
聞いてないぞ、とサージはリップルを見上げる。上目遣いの視線をかわし、リップルは翼を広げた。明るいところで見ると、赤黒い上の翼と赤い下の翼の違いがよくわかる。
「こっちは悪魔の翼だ。飛行核に貯めた血を放出して作る。」
上の翼だけを羽ばたかせながらサージの方へ歩く。説明が終わると上の翼をたたみ、今度は下の翼を羽ばたかせる。近づくと、その翼の骨がある部分は鱗に覆われていることが分かる。
「でも、こっちは違う。」
四つん這いになり、ググッと全身に力が入った。途端にリップルの身体の輪郭がぼやけ、長く伸びて再び実体がはっきりした。
サージの前に赤いたてがみの橙龍が姿を現す。目を丸くして硬直するサージに、龍はヒトの言葉で話しかける。
『これは龍の翼。母から賜った神聖な翼だ。』
龍と悪魔の間に生まれたために、リップルは2対の翼をもっていた。龍の世界では混血を、悪魔の世界では2対の翼を忌み嫌う風習があるが、両親からの大切な贈り物をリップルはどちらも誇りに思っている。
『先代、イデアの意思を引き継ぎ、我リップルがネストの鎮守となる。・・・なんてな。神サマなんて、性に合わないけどな。』
ようやく頭の処理速度が追いついたサージは恐る恐る立ち上がり、右手を龍の胴へ伸ばした。柔らかな日差しと湖の光に照らされて美しく輝く鱗に触れてみたくなったのだ。引き寄せられるように近づいていたが、途中で我に返って龍の紅い瞳を見上げる。
「触っても・・・いいかな?」
『どうぞ。』
思ったよりも鱗は薄い。薄くて滑らかだが、とても固そうだ。次いで、鱗にかかる艶やかなたてがみを撫でる。触り心地がよく、いつまでもこうしていたいほどだ。
『俺のこっちの正体は他の人間には言うなよ。町の自立に悪影響だ。』
サージはネストを守る橙龍の巫女である。そのため、リップルは彼女にだけは教えておこうと思った。
「私とリップルだけの秘密?」
『そういうわけ。』
「そっか・・・。」
終いに龍の胴に顔をうずめて目を閉じた。リップルは腹を地面につけて座り、サージが満足するまで宝石のような鱗に触れさせてやった。
リップルとサージが出会って3日。つまり新暦251年9月8日午前6時11分。
大陸南部フェニール地方北部の町 ネストでの出来事である。
≪1章 完≫
世界は竜龍と共に 1
町の呪いは解かれ、人知れず新たな神が誕生した。
平穏を取り戻したかのように見えたこの町が、大いなる災いに呑まれるのはしばし後の話である。
今はただ、神と巫女の静かな時を見守ることとしよう。

