
路地裏のパンダ
某電子歌姫様の楽曲からイメージ。たぶん長くなります。
1~5⇒シュン視点。
6~7⇒マオ視点。
8~10⇒シュン視点。
11~12⇒マオ視点。
1.『いい子』の条件

僕は『いい子』でいなくちゃいけない。
右向け右の前倣え。列からはみ出た子は悪い子だ。ワガママな厄介者扱いをされてしまう悪い子だ。
この街は『廃材街(ハイザイガイ)』と呼ばれる街で、文字通り廃材で出来上がった街だ。鉄骨むき出しのビルに解体途中の建物。そこら中にあるゴミ、鉄屑、錆び付いた機械。
街はそんな物に囲まれてもなんとか成り立っていた。
街の中心地にはお金持ちや資産家、あとはずる賢さでのし上がった人間達が住む『富裕街(フユウガイ)』と呼ばれる街がある。文字通り富裕層の人間が住む街だ。
その富裕街を囲むように出来上がっているのが『貧困街(ヒンコンガイ)』。富裕街とは対照的に貧しい人間達が蔓延っている。貧困街はまるでドーナツのような形状になっている。ドーナツの穴の部分は富裕街になっていて、それを中心に外へと広がる。富裕街に近いほど裕福な人間が住んでおり、外側にいけばいくほど貧しい人間が増えていく。
僕の家は貧困街にあって、ボロボロでお世辞にも住みやすいとは言えない。でもママと二人で住むには丁度いい大きさだった。それに雨風がしのげる屋根と壁があるだけまだマシだ。それらが無い、決して家とは呼べない場所に住んでいる人もこの貧困街にはたくさんいるから。
ママは僕をどうしても学校へ行かせたがった。正直、僕はどうでも良かったけどママが『行きなさい』と言ったから行った。貧困街に学校は無い。ママは男の人達と仲良くするお仕事をいっぱいして、お金を稼いで、唯一富裕街にだけある学校へ通わせてくれた。物凄くたくさんお金がかかるみたいだけど、でもママは頑張って払ってくれていた。
だから僕も無駄にはできなくて、言われた通りに学校へ行っていた。
学校はお金持ちの子ばかりで僕はあまり好きじゃない。
でも勉強は自然とできた。勉強ができれば先生は褒めてくれる。先生が褒めてくれるとママは喜んだ。だから僕は頑張って勉強をした。
友達とは適当に仲良くしていた。とびきり仲良しの子が居る訳でも無いけど、なんとなくみんなの輪の中に入っていれば目立たずに済んだから。黙ってただ笑ってればなんとかなるから。だからずっとそうしていた。
ある日、同じクラスの子が妙なことを言い出した。
「ねえ、なんで人を殺しちゃいけないの?」
みんなポカンとしていた。なんでそんな話になったのか、僕は今になっても思い出せない。
「悪いことだからに決まってるじゃない。悪いことはしちゃいけないってパパとママに教わらなかったの?」
高飛車な二つ結びの女の子が鼻で笑って言った。
「じゃあなんで人殺しは悪いことなの?」
「世界のルールで決まっているからだよ」
「なら、もし人殺しが悪いことじゃ無かったら、その時は人殺しをしてもいいってこと」
屁理屈の言い合いみたいになってしまったけれど、確かにと僕は思った。例えばこの世の中での一番悪いことが盗み食いだったとしたら――。そうしたら人殺しはそこまで重い罪にならなくて、今よりも簡単に人の命を奪うことができたかもしれない。
「でも僕、ずっと前に聞いちゃったんだ。貧困街の人間だったら一人くらい殺してもわからない、って。怖そうな大人の人が話してたんだ」
『貧困街』という言葉に耳がぴくっとした。でも僕はみんなの輪の中でじっと黙っている。
「本当に? どこで聞いたの?」
「貧困街の近くの路地だよ。嘘じゃないってば。シャカイのチツジョ?が変わる訳じゃ無いしって言ってた」
「じゃあ大人は人殺しをしてもいいってこと?」
「そんな訳無いよ。大人だって悪いことをしたら逮捕されるじゃないか」
うーんと唸りを上げて一人が名案でもひらめいたかのように声を上げた。
「そうだ! 先生に聞いてみようよ! そうしたら答えがわかるかもしれないよ?」
そうだそうだと口を揃えてみんなは嬉しそうにはしゃいだ。先生は丁度用事があったのか、教室の中に入ってきた。
あっと言う間に先生は僕達に囲まれた。不思議そうな顔をしながらも笑顔は絶やさない。
「ねえ先生、どうして人殺しはしちゃいけないの?」
最初、先生は驚いて目を見開いた。その後に吹き出すように笑って言った。
「どうしたの急に?変なこと聞くのね」
するとみんな思い思いにさっきまで話していたことを我先にと話始めた。しかも怒鳴るような大きな声で。途端に辺りが騒がしくなる。でも僕はだんまりを決め込んでいた。うるさいのは先生に迷惑をかける悪い子だから。
「待って、みんな静かに!」
みんながぴたっと口を閉じる。先生は一息ついて口を開き始めた。
「人の命を奪ってしまうのは悪いこと、それはみんなわかるわよね? 何故それが悪いことになるのか――それは人の大切な物を奪ってしまうからよ。自分達がもし同じことをされたらって考えてみて。自分が痛くて辛いことをされたら嫌よね?パパやママに会えなくなっちゃうのは?一生美味しいものが食べられなくなっちゃうのは?」
みんな口々に嫌だと呟く。僕もママに会えなくなるのは嫌だな……。
「自分がされたくない事を人にするのは良いこととは言えないわよね。だから人を殺すのも同じこと。この世界で犯罪になると決まっているのよ」
みんな「そっかあ」と感嘆の声を漏らす。でも僕はなんだか納得できなかった。何か引っかかると言うか、なんと言うか。
だって、それが理由なら――。
僕は廊下に出ていく先生を追いかけ、その背中に声をかけ呼び止めた。
「どうしたの? シュン君。まだ何か聞きたいことがあったのかしら」
先生は柔らかい笑顔をくれた。いつも通り、優しい先生だ。
「先生、じゃあ――――」
僕は先生を見上げた。
「自分が殺されてもいいと思ったら、人を殺してもいいってこと?」
先生は何も言わず、ただじっと僕を見ていた。
2.ほんの少しの冒険

失敗した。先生を困らせた、僕は悪い子だ。もしママにこのことを話されたら、僕はまた怒られてしまう。
でも間違ったことは言っていないと思うんだ。さっきの先生の言葉は裏を返せば『自分が嫌なことをされても構わないというなら他人にもしていい』という結論に辿り着く気がしたから。そういう訳で無いのならその理由が知りたかった。
でも先生は『早く教室に戻りなさい』と言うだけで何も答えてはくれなかった。その時の先生の表情は、いつもの優しい先生では無かった。
だから今僕は目の前に居る彼らを殺しても構わないんじゃないかと、今そのことを考えている。
僕はいつもひっそりとご飯を食べていた。ママが買ってくれる小さなパン、それがいつものお昼ご飯だ。みんなはお弁当を持っていたりしたけど僕はこれで十分。でもそれを見られたくないからとか、後ろめたいからという理由で隠れて食べていた訳じゃ無い。教室でご飯を食べていると、決まっていじめっ子が僕を呼び出しに来るからだ。だからできるだけ場所を変えて、そして目立たない所でご飯を食べていた。
今日は非常階段でこっそりとパンを食べていたけれど、残念ながら見つかってしまった。
「よお、シュン。今日もマズそうな飯食ってんな。飯なんていいから屋上で一緒に遊ぼうぜ」
僕を囲む数人の男の子。屋上で一緒に遊ぼうと言うのは、屋上で僕をリンチしたいのだけど如何かな、という意味だ。当然ながら僕は渋った。
「……嫌だ。ご飯……食べてるし」
そんなことを言っても有無を言わさず連れて行かれるのは知っていた。腕を引っ張られ、まるで隠すように囲まれる。
ママが買ってくれたパンは手からこぼれ落ち、誰かに踏まれて潰れてしまっていた。それを視界に入れながら僕は言われるがままに屋上へと連れていかれた。
みんなは僕を殴ったり、蹴ったり、言葉の暴力で僕を詰ったり。それを見て笑ったり、唾を吐いたり。僕は黙ってそれに耐えている。だって反抗したら貧困街の人間だとバラされてしまうから。それを知っているのはここに居る数人の男の子と、多分、先生だけだ。
屋上には誰も居ない。みんなの足や腕の隙間から真っ青な空が見えた。なんでこんなにも平和なのに、富裕街の人達は幸せなのに、僕だけがこんなに辛い思いをしなければならないんだろうといつも思う。だからあの先生への質問は間違っていなかったと思ってやまない。
だってそうでしょう?自分の身は自分で守らなければいけないから。みんなに殺されてもいいと思ったら、僕はこの目の前で腹を蹴る男の子を殺してもいいんじゃないかって。でもそんなことをしたらママが怒るから……だからじっと我慢している。
暫くすると予鈴の音楽が鳴った。あと5分でお昼休みは終わる。僕をいじめるのにも飽きたのか、さっきまでいた数人の男の子は走り去って行った。僕は衣服の乱れを直し、切れた唇から滲んだ血を拭った。殴られた腹が少し痛んだ。お腹をさすりながら僕は屋上を後にする。この不条理な青空を眺めながら。
ママは僕に偉い人になって欲しいようだった。
例えばお医者さんとか、学者とか、政治家やお金持ち。だから富裕街の学校に無理をしてでも僕を通わせていた。
みんなが車やバスで帰る中、僕は一人とぼとぼと帰り道を歩いていた。
富裕街と貧困街の境目には看板や境界線がある訳では無いけれど、綺麗にくっきりと街並みが分かれている。富裕街の人間は貧困街の近くに住むのを嫌がり、貧困街の人間は富裕街の近くに住むのをステータスにしている。境界線付近には民家は少なく廃屋や廃材置き場なんかが立ち並ぶ。
それらを横目に通り過ぎ、富裕街にほど近い貧困外の奥の奥にある小さな家。僕はそこでママと二人で住んでいる。パパは居ない。昔ママに聞いたら『どこで何をしているのかわからない』と言われた。多分誰が父親なのかもわからないんじゃないかと思う。ママは色んな男の人と仲良しだから。
「ただいま」
返事は無かった。ママは外に出ているみたいだ。僕は洗面所に向かって鏡を見た。口に小さな切り傷が一つ、顎に青痣が一つ、肩とお腹も痣ができていた。お昼にいじめられたせいでシャツが汚れていた。
僕が通う学校には一応制服があってブレザーにショートパンツ、シャツという格好だった。ブレザーとパンツは1着ずつしか無い。シャツは2着しか無い。だから汚すとママは凄く怒る。「新しい物を買うお金なんか無い」って。シャツは汚れたらすぐに洗濯をしないと乾かない。僕はシャツを脱いで洗面台に水を張った。
じゃぶじゃぶと溢れる水を眺めていると玄関で物音がした。それからすぐにママの声がする。僕は水を止めて声のする方へ走って行った。
「ママ、おかえり……なさい」
ママは一人じゃなかった。男の人の二人で帰って来ていた。多分『お客さん』だ。
「あんた、帰ってたの?」
「おい、ガキが居るのか?」
「構わないわよ。すぐ追い出すから」
するとママは僕の方へ歩いてくる。
「シュン、とりあえずこれ着て外行きな。客が来てんだからわかるだろ。ほら、とっとと出てきな」
僕に上着と時計を渡すとママは背中を押した。
「10時になるまで待ちな。その前に帰ってきたらお仕置きだからね」
僕はお客さんの前で靴を履く。お客さんは背広を着た背の高い男の人だった。ちょっと怖そうな、そんな感じがした。
「おいガキ、これで美味いもんでも食いな。今日は追い出して悪かったな」
お客さんは僕の手のひらにお札を握らせた。多分これなら美味しいものどころかかなりいい物が食べれる。僕は困惑してお客さんを見て、すぐにママを見た。
「ちょっと、ガキにそんな大金……!」
「いいのさ、構わねえよ。きちんとお前にも金は払うから安心しな」
ママはちょっと困ったようだったけどすぐに僕の頭を掴んだ。
「ほら、礼言いな!」
僕は言われた通りに頭を下げてお礼を言う。お客さんはこれまでたくさん来たけれど、こんなにお金をくれたのはこの人が初めてだった。
「ありがとうございます」
僕はお金を握りしめて外に出た。
こういうことはよくある事で、ママがお客さんと仲良くしている間は外に追い出されることが多かった。
でもママはそれでいっぱいお金を貰っているからしょうがない。僕が生きていられるのも、ママがお仕事できるのも、学校へ行けるのも、富裕街の近くに住めるのも、全部ママのお仕事のおかげだから。
こういう時は大体近くの公園で遊んだり、眠ったりして時間を潰していた。でも今日はかなり時間がある。空は日が傾き始めていた。
なんだか不思議と遠くへ行きたくなった。よくわからないけれど、少しだけ知らない場所に行ってみたくなった。何かあってもこれだけのお金があればなんとかなるだろうし。
僕はちょっとだけ冒険をしてみることにした。
3.歌うアンドロイド

暗い路地は気持ちを不安にさせる。貧困街は外側に行けば行くほど人通りは少なくなる。
僕の家の近くは昼間は人が多かったりするけど、それでも富裕街に比べたら少ない方だ。貧困街は治安が悪い。外に出たら何が起こるかわからないからだ。盗みもあれば殺人も起こる。自分が巻き込まれても言い訳ができないのがこの街だ。
僕も制服を着ている時はあまり出歩かないようにしている。富裕街の人間だと思われて誘拐されたりしたら困るから。
出来るだけ辺りを警戒しながら、帰り道がわかるように目印を探しながら歩いた。貧困街の街並みはさほど変わらずどこも廃材が転がったような場所が続く。立ち止まってきょろきょろと辺りを見渡すと、路地に猫が一匹ぽつんと佇んでいた。少し近づけば、猫は颯爽と身を翻して闇に消えていった。
月明かりがビルの隙間から差し込む。僕はママが渡してくれた小さな時計を見た。まだ時間はある。
「どうしようかな……。お腹、減ったなぁ……」
廃材街の真ん中辺りまで来たのだろうか。この辺だともうまともなお店はやっていない。仕方なく富裕街に戻ろうとした時、何かが耳を掠めた。
「……誰か、歌ってるのかな?」
小さく歌声が聞こえた。それはとても綺麗で、微かにしか聞こえないけれどそれがわかる。僕は歌声を探すようにして路地を縫っていった。
段々と建物が少なくなっていき廃材ばかりが立ち並び草木も増えていく。寂れたその場所に、ぽっかりと穴が空いたように不思議な空間が存在していた。
廃材、鉄パイプ、錆びた車輪、それと不用品が山のように積まれている。その先に廃墟があった。窓ガラスが割れ壁もない場所もあって、半壊状態の建造物。何年も人が使ってないのがわかる程荒れていて、草木や蔦が絡んでいた。その建造物とは対照的に響く美しい歌声――。奇妙な空気が流れていた。
僕はそっと廃墟の中を覗いて見た。――――誰も居ないみたいだ。なら、これは誰が歌っているんだろう。
「お邪魔します……」
凄く小さな声で囁いて中に入ってみた。歌声は止まない。何の歌かわからないけれど、すごく落ち着く曲だ。廃墟の中は結構広くて天井も高かった。きっと2階部分が抜け落ちて吹き抜けみたくなっているからだと思う。空からは月光が差し込んでいて、凄く幻想的な雰囲気が漂っていた。
そして、僕は見つけた。歌声の正体を。
月明かりに照らされたそれはとても綺麗で、美しかった。その姿にはちょっとびっくりしたけれど。
「君が、歌ってたの?」
いつの間にか止んでしまった歌を惜しむように僕は問いかけた。
「……貴方は?」
「僕はシュン。君の歌声が聞こえてきて、ここに迷い込んじゃったんだ」
「では、マオ様のお知り合いという訳では無いのですね?」
「マオ様?」
「私の主人の名前です。今は留守にしていますが」
「ご主人様?君の?」
「そうです。こんな私を拾ってくださった優しい方です」
こんな私と卑下するのも無理は無いと思った。彼女には体が無かったから。頭だけが小さな棚のような物の上に乗っていて、それで歌っていたのだ。勿論彼女は人間では無い。首の辺りからケーブルや集積回路が見えた。きっと機械なんだと思う。
「凄く綺麗な歌声だからびっくりしたよ」
「ありがとうございます」
「お話もできるんだね」
「首だけでも人工知能は備わっていますから。会話ができるようにしてくださったのもマオ様なんです」
「君のご主人様は凄い人なんだね」
「ええ。素晴らしい方です。とても感謝していますわ」
彼女に名前があるのかはわからない。けれど会話をする相手はいるようだった。
彼女は頭だけでもすごく綺麗で美人だった。真っ黒な髪を垂らし、長い睫毛をぱちぱちさせながら僕と話をしてくれた。作り物だから当然綺麗にはできるんだろうけど、でもやっぱり人間のように見えるほど精巧な作りでどこか見とれてしまう。
口には出して言えないけど、少しママに似ていた。ママも綺麗な黒髪で目鼻立ちはくっきりとしている。美人だからああいう仕事ができるんだろうし。僕もママと同じ黒髪だ。真っ黒な髪は今じゃ珍しくなっていて、ママはそれも商売道具にしているようだった。
「誰だ?」
僕は体をびくつかせて後ろを振り返った。そこには――――。
「迷子か、それとも俺に用があるのか?」
そこには、血まみれの少年が立っていた。
4.貧困街4番地の屋台にて

多分、僕と同じくらいの年であろう少年は、顔や腕や服に血液と思われる赤い液体が飛び散っていた。けれど頭の先から足の先までどっぷりと浴びたような感じではなく、例えるのも嫌だけれど、まるで返り血を浴びたような――。
「お帰りなさいませ、マオ様」
「お前が呼んだのか?」
「いいえ」
黒髪の喋る頭は彼と会話を始めた。どうやら『マオ様』の正体は目の前の彼らしい。僕はてっきりもっと大人の男の人かと思っていた。だって彼女がとても敬っているように思えたから。けれど正体は僕とおんなじ子どもだ。けれど彼がこの喋る頭を作ったとしたら、それは尊敬に値する。
「じゃあ迷子か」
「そういう訳では無いようですけれど」
「じゃあ客か?」
「そういう訳でも無いようです」
少年は手に金属バットを持っていた。それにも血液らしきものが飛び散っていた。格好はボロボロになったタンクトップを一枚、それに膝丈のパンツ。どちらも綺麗とは言えなかった。
バットをそこらへんに放り投げ、少年は顔の血をぐいっと拭う。
「用が無いなら帰れ。ここはお前みたいなヤツの来るところじゃない。それ、富裕街の学校のだろ」
少年は僕のズボンを指差して言った。僕は家を出るときにズボンは制服のままで、上はママが適当に渡したパーカーを着ていた。富裕街の学校のこと、知ってるんだ…。
彼は気にする風でも無く、離れた場所にある蛇口を捻った。水がばしゃばしゃと音を立てて地面に落ちていく。それをすくって顔を洗い始めた。赤茶色の水が透明な水に混ざり合っていく。
「学校へは行ってるけど、住んでるのは貧困街だよ。生まれも貧困街だし、学校はママが無理に通わせてるだけだし」
「行きたくないならやめればいい」
彼は簡単に口にする。そう、やめればいい。逃げ出せばいい。あの家もママも置いて飛び出せばいい。でもそれはできないし、するつもりもない。だって――。
「行きたくないけど……ママに嫌われたくないから……」
彼は気にくわないような顔をしていた。と言ってもほぼ無表情だったけれど。一瞥するその顔立ちは、浴びたであろう血が洗い流されはっきりと僕の目に飛び込んできた。
白金と呼べる程白く輝いた髪の毛。髪型はおかっぱで、前髪はまっすぐ切り揃えられていた。何より驚いたのはその顔で、目の周りが真っ黒だった。黒と言っても絵の具を塗ったような黒では無く、クマのような色素沈着してしまったかのような黒。見とれてしまった訳では無いけれど顔を凝視していたら、不意に僕のお腹の虫が鳴いた。
「お前、腹減ってるのか?」
ぎゅるぎゅると音を立てるお腹を抱え赤面してしまう。僕は小さく頷くしか無かった。
「お、お金は貰ったからあるんだ。でもお店とかわからなくて…」
少年は隅にある木箱の中をごそごそと探り、適当に見繕った服を着始めた。
「おい、オヤジ来てるか?」
「半径500メートル以内には居るかと。南東の方角が最短ルートになります」
「わかった。お前、名前は?」
少年が僕を見る。
「シュン。君は――」
「マオでいい。行くぞ、飯が食いたいんだろ?」
首だけになった機械が言ってたから彼の名前はわかっていたけれど、僕が尋ねるよりも先に言葉を投げられてしまった。
マオは汚い寸足らずのズボンのポケットに手を突っ込みながら僕の前を歩いた。
マオが何故血まみれだったのか、何故金属バットを持っていたのか、それは聞いてはいけないことのような気がして口には出せなかった。でも気になるからタイミングを見計らって聞いてみようとは思っている。
路地を歩きながらマオはたまに立ち止まって鼻をきかせる。すんすんと鳴らし方角を定めているようだった。匂いがするのだろうかと僕もやってみたけれど、廃材街特有の腐ったような匂いしかしなかった。
暫く歩いていると遠くに湯気が立ち込める屋台が見えた。きっとこれを探していたんだろう。
「お、居た居た」
近くまで行けば美味しそうな匂いが鼻をくすぐる。生まれた時から貧困街に住んでいたけれど、こんなにも外側で屋台を見るのは珍しい。僕の家の近くでも屋台はそうそう見ない。
「らっしゃい。おう、久しぶりだなガキんちょ。よく見つけてきたな」
暖簾を揺らせば屋台のおじさんが笑顔で出迎えてくれた。マオは無愛想に黙って席に座る。僕も同じように隣に座った。
「また鼻きかせて来たのか?」
「オヤジのトコのラーメンの匂いはすぐわかる」
「相変わらずすげえガキだな!今日はツレも居るのか。なんでも好きなもん食ってきな」
屋台のオジサンは人の良さそうな雰囲気だったけれど額の真ん中から右頬にかけて大きな傷があった。この貧困街では顔に傷を負ったり、病気で体が不自由だったりする人は珍しくない。驚くことは無かったけど何か理由があるのかな、と思った。
「シュン、何が食いたい」
不意に問われたけれど何が美味しいのか、何があるのかがわからない。
「マオと一緒でいい。何が美味しいかわからないから、同じのを食べるよ」
「……そうか。オヤジ、ラーメンとチャーハン2つずつ」
するとオジサンは返事をして調理をし始めた。
「ここの食いモンは何でも美味いから安心しろ。お前の口にも合うはずだ」
僕もなんだかそんな気がした。現にこうして匂いを嗅いでいるだけで涎が滴りそうだった。
視界が煙るくらいの湯気が立ち込める。透き通ったスープに麺が泳ぐ。上には卵とメンマ、凄く美味しそうだ。チャーハンも香ばしい匂いがしてすぐにでも頬張りたい。僕はごくりと喉を鳴らした。
「冷めないうちに食っちまいな。とびきり美味いから覚悟しろよ」
オジサンがそう言うとマオはお構いなしに割り箸を割ってラーメンをすすり始めた。
「い、いただきます」
僕も堪らず箸を握る。麺を口に入れて驚く程の美味しさに箸は止まらなかった。熱いのも構わずに食べてしまう。こんなに美味しい食事は初めてかもしれない。お腹が減っていたせいもあってか生きてきた中で一番美味しいくらいの食事だ。
僕は食事の時も綺麗に食べるように言いつけられてきた。食事は育ちが出やすい、とママに言われた。だから学校で食事をする時には綺麗に食べるように躾けられてきた。
けれど今、隣に居るマオの食べ方は最悪だった。本当に笑っちゃうくらい。ガツガツ、ズルズル、食器もカチャカチャ鳴らしながら食べる。たまに口から溢れるし。でも、これが普通なのかなと思った。僕が富裕街の学校に通わず、ママもそれを望まず、ただ普通に貧困街で暮らしていたらマオと同じだったのかもしれない。
「そもそも、お前なんでこんな所に来たんだ。家はこんな外側じゃないだろ」
『外側』と言うのは貧困街での特殊な呼び方だ。廃材街は富裕街を中心に外に行くほど貧しい者が住み、治安が悪くなる。
「家は1番地。ママがお客さん家に連れてきて、邪魔になっちゃうから出てきたんだ」
「それで4番地まで来るかよ。お前帰れるのか?」
「うん。ちゃんと覚えてきたから大丈夫」
「覚えてきたって……」
「僕、人一倍記憶力が良いんだ」
僕の特技、取り柄と言ってもいいかもしれない。昔から記憶力だけは良かった。それに気づいてママも学校に入れようと思い立ったに違いない。
教科書は一度読めば大体覚えられる。3回読めば確実に丸暗記できる。だからここまでの道もしっかりと頭に叩き込めば忘れることは無かった。路地が多い廃材街も僕の脳みそならなんとかなった。
「大体一度通った道なら覚えられるんだ。変な言い方だけど、忘れることが出来ないんだ。記憶したことはずっと蓄積されていって、古いものから徐々に消えていく。変な脳みそなんだ」
するとマオは口をもぐもぐ動かしながら冷めた表情で言った。
「お前、あんまりそれ言いふらすなよ」
「……なんで?」
「そのうち痛い目見る。お前の特技は黙っとけ」
それだけ言ってマオはおおきなゲップをした。
5.月明かりの帰り道

ご飯のお代はマオが支払ってくれた。僕はママのお客さんから貰ったお金があるからいいと言ったけれど、マオはどこから貰ってきたのかわからないグシャグシャのお札をオジサンに出していた。
『その金は何かあった時の為に取っておけ』
そう言ってくれたから、僕は大事に家のどこかに隠しておこうと思った。
帰り道は一人でも大丈夫そうだったけどマオが一緒に行くと言ったから二人で僕の家まで帰ることにした。僕の家がどの辺りか知りたいというのと、本当に一回来ただけの道を戻れるのか知りたいのが理由だったみたいだ。
「マオはなんであんなにお金持ってたの?誰かから貰ったの?」
マオは歯に何か詰まっているのか爪でシーシーしながら言う。
「仕事してる。メシ食える程度の金は貰えるから。でもあんまり腹減らねぇから大してメシに金は使わないけどな」
「仕事って?どんな仕事?」
マオは少し間をおいて口を開いた。
「人に言えねぇような仕事」
その言葉にドクンと心臓が鳴った。それって、それってもしかして――。
「さ、さっき、血まみれだったのも……その仕事のせい……?」
聞きづらかったけれど、どうしても気になってしまった。するとマオは僕の顔を見る。無表情なせいか睨んでるようにも見えて怖い。
「そうだけど……お前勘違いしてるだろ」
「えっ?何を?」
「あれ、返り血じゃない」
「…………は?」
「だから、あれは返り血じゃないって言ってんだよ」
つまり、マオを初めて見た時に血まみれだったのは、誰かの血を浴びてああなったのでは無いということで…。
「えっ?誰か殴ってきたか、それか殺してきたから返り血を浴びたんじゃないの?」
「だから違うって」
「じゃあなんであんなに血まみれになってたの!?誰か殴るか殺すかしなければあんなに真っ赤になる訳無いじゃないか!」
なんでか僕はムキになってしまう。だって、それを想像して怖くて仕方なかったのだから。
「あれ、俺の血」
「は?」
「頭怪我した。逆に殴られて血まみれになった」
「えっ?えっ?じゃあバットの血は?」
「飛び散ったかなんかしたんだろ。ああ、もういいや。全部説明する」
マオは面倒くさそうに頭を掻いた。家までの道のりはまだ遠いから、マオの話は十分聞けるだろう。
「俺の仕事は人に言えないようなことが多くて、大体富裕街の裏側に住んでる危ない仕事やってる奴らからの依頼が多い。人づてに俺の噂を聞いて頼まれることも多いし、俺の知り合いが仲介して仕事を持ってきたり。
今回のは運び屋の仕事で頼まれたモノを運ぶだけだった。中身は知らない。見るなって言われたからな。ただそれが少し厄介だった。
モノってのが人のモノだったからだ。つまり、盗みをしてそれを依頼者に届けるってヤツで……でも何回か同じような仕事はしてたから大丈夫だろうと思って引き受けた。
それで盗みをした時にヘマして見つかった。バットは毎回持ってるけど、間に合わなかった。頭思いっきり殴られて、ぶっ倒れて――そうだ、その時にバットが手から離れて血がモロにかかったんだ。
それでなんとか撒いて血まみれで逃げてきた。そこでお前と会った」
淡々と作業的に話す。その姿に本当に何度もそういうことをしてきたんだと実感する。マオの話の中には自分の感情が出てこない。焦ったとか、ヤバイと思ったとか、だからマオにとっては本当に仕事でしか無いんだと思った。
「怪我は平気なの?頭、殴られたんでしょ?」
僕がそう問いかけると、マオは無言できょとんとしていた。
「――ああ。血も止まったし少し切れただけだろ。頭痒いけどなんとも無い。いつもの事だし」
でも心配だった。いつかもっと危ない事になって、酷い怪我をするかもしれない。けれど止められないのが現実だった。
多分、マオには両親がいない。存在しているのかどうかはわからないけれど、確実に一緒に住んで生活を支えてもらうような人はいないのだと思う。あの廃墟を見ればわかる。マオはあそこに住んでいるんだ。
「あんまり危ないことはしちゃダメだよ……。僕が、言えるようなことじゃないけど。」
するとまたマオはきょとんとしていた。パンダのような目が僕を見つめる。
「…………お前、変だよな」
「ええっ!?」
「うん、変だよ。今まで色んなヤツ見てきたけど、お前みたいな変なヤツに会ったの初めてだ」
「そ、そんな……」
変な意味では無いと思うけれど、でもマオは表情が無いから不安になる。僕って変なのかな?だから、いじめられたりしちゃうのかな……。
「ここか?お前んち」
「うん。あの奥のボロボロの」
月明かりの中を二人でただ歩けば、家への道のりはあっと言う間だった。僕は遠目で家を指差しマオに教えてあげる。
「じゃあ」
帰ろうとしたマオを呼び止める。これでさよならしちゃうのは、なんだか虚しかったから。
「ねぇマオ、またあそこに行ってもいい?」
あそこって言うのは勿論マオの家で。またあの首だけの女の子にも会いたかったし、またマオと話もしたかった。
「……別にいいけど、もうその服着て来るのはやめろよ。4番地に富裕街の人間が来てると勘違いされたら何されるかわからないからな」
マオが言ったのは僕の制服のことだろう。確かに富裕街の人間だと勘違いされたら殺されるかもわからない。
「わかった。ありがとう。じゃあ、またね」
「またな、シュン」
マオは手をぷらぷらさせて踵を返して行った。
マオは月明かりに照らされて、なんだか格好良かった。ポケットに手を突っ込んで背中を丸めて歩く。
なんだか、初めてトモダチができたような気分だった。
***
6.パンダの憂鬱

世界は真っ黒だ。
綺麗な物なんて一つもありゃしない。汚い物だらけだ。欲に業にそれに塗れる人間に、全てが汚染された腐敗物質だらけの世界。こんな世界で息なんてできやしない。
けれどその腐った世界の底辺のそのまた底辺で生きてる俺は、一体何なのだろうか。生きる価値も無いクソッタレだ。
気を紛らわしてくれるのは注射器だった。
もう何本目かわからない注射器を手に取る。仕事の依頼者から貰った薬を吸い込ませ、空気を出すためにピストンを少しだけ押す。地面に数滴染みができた。それを腕に打つ。薬が全部体内に入っていくのを確認して注射器を抜く。それを捨てる場所は決まっている。罪悪感を感じるから穴を掘って、そこに毎回放り投げている。上には布を被せて自分の目から遠ざけるようにしている。誰に見られる訳でも無いし、誰かに咎められる訳でも無いのに、隠したくなるのは後ろめたさを感じているからだ。穴に投げられた注射器の数は日に日に増えていく。この穴いっぱいになった時、俺は死ぬんだろうと思っている。願掛けなんて大層なことはしていないけれどただなんとなく穴に埋めたいからそうしてる。それだけだ。
咳が止まらなかった。最近は投与後に咳き込むことが多くなった。不眠はずっとだし、吐き気はほぼ毎回。下痢はたまにある。咳き込みながらうずくまって、なんとも言えない幸福感に身を委ねていたらすぐ傍に人の気配がした。
「おーおー、今日も随分とキメこんでんなぁ。体に無理はさせちゃいけねぇよ?」
咳き込みながらも答える。また来やがった……。大した仕事も持ってこねぇくせに……。
「何の用だ……」
煙草を咥えたひょろっとした男が俺を見下す。色の付いたサングラスに七三に分けた髪をぺったりと撫で付けて、薄い顔に不敵な笑みを浮かべる。俺はコイツが大っ嫌いだ。
「お前の大好きなクスリの為に仕事持ってきてやったんだよ、クソガキ」
ほら、すぐに悪態つきやがる。地獄に落ちちまえ。
「うげぇっほっっ……おぇっ……」
ダメだ、吐き気まできやがった。胃に何にも入れて無い筈なのに、嗚咽が止まらない。結局吐き出したのは胃液だけだ。
「きたねぇな……。ま、こんだけ打ち込めばしょうがねぇか」
穴に捨てられた注射器の山を見て男が笑った。途端に悪寒が襲う。禁断症状も末期だ。すぐに反応が出やがる。ガチガチと歯を鳴らしながら俺は口を動かした。
「……出てけ」
男は気に食わぬ顔で俺をさらに見下す。そしてしゃがんで可能な限り目線を合わせ、煙草の煙を目一杯吸い込み俺の顔に吐き出す。――今すぐ頭ぶん殴ってやろうか!
「お前の大事なオピウムのタネ持ってきてやったんだよ、感謝しやがれ。あといくらも残ってねぇだろ、あ?」
図星だ。男の言うオピウムというのは俺が打つクスリのことで、そのタネってのは仕事。つまりは仕事の報酬がクスリってことだ。息を荒げながらも俺は去勢を張る。
「金ならある……。てめぇから貰わなくても売人から買えるんだよ、カス――」
「――――口の利き方には気を付けろよクソガキ。ぶっ飛んでる頭でよく聞きやがれ、いいな?」
男は俺の髪を掴んでグラグラと揺らす。やめろ――カス……。てめぇの自慢の革靴ゲロまみれにしてやろうか――。
「富裕街5番地2-33。青い屋根が目印のでかい構えの家だ。あの辺には青い屋根は珍しいからすぐわかる筈だ。そこの家の2階の金庫にお目当てのブツがある。今のところ報告じゃお目当てのモノしか入ってないようだが、わからなかったら全部かっさらってこい。いいな?」
「ブツは……ぐぇほっ……ブツは一体なんなんだよ……がはっ……」
「お前は知らなくていい。報酬はオピウム3本でいいな?」
注射器3本分?足りねぇよカス……。
「6本だ――じゃなきゃ下りる。盗みが絡んでんだ……しかも富裕街の一般宅だろ?倍じゃなきゃやらねぇ……」
少し間を空けて男は俺の頭を地面に向かって突き放した。
「クソガキが……!必ず6本やる、その代わりヘマすんなよ!いいな!」
煙草を吐き捨てて男は去って行った。
――富裕街5番地2-33、青い屋根、2階の金庫――――。
朦朧とする頭の中で男に言われた情報を叩き込む。そしてゆっくりと目を閉じた。
何時間、いや、何分経ったのだろうか。長い時間のように思えたがほんの数分のような気がする。
「お目覚めですか、マオ様」
寝転がる俺に背後から声をかけるのは喋る生首。俺が近くのスクラップ広場から拾ってきて直してやった。この家の住人であり、唯一の話し相手でもある。
「俺が目を閉じてからどのくらい経った」
「3分と52秒です。少々早いお目覚めのように思えますわ。もう少しお休みになってはいかかでしょう?」
俺は体を起こした。人工知能の割には気が利く。不眠も日に日に拍車がかる。これじゃクマも消えない訳だ。
「もういい…。仕事に行く。留守は頼んだぞ」
「お気を付けて」
俺は金属バットを手にして富裕街へと足を向けた。目指すのは富裕街5番地2-33―――。
7.黒に混じる白

手には金属バット。どっかで拾ったネックウォーマーで鼻まですっぽりと覆う。これも拾った黒の色褪せたヨレヨレのキャップ、そいつを深々と被る。黒を身につければ夜に塗れる。多少なり気は強くなる。これがいつもの俺の作業着。仕事をする上での制服だ。
富裕街5番地にこんな格好で行けばすぐに捕まる。けれど夜ならば話は別だ。富裕街と言えど夜の外出は禁物。大抵は車で外に出るか、人手が多いのは歓楽街付近だけだ。
遠くで狼が遠吠えをするのが聞こえた。
富裕街5番地2-33、青い屋根、2階の金庫。
それが目指すべき場所だ。今日の仕事は簡単では無い。その場所にそびえ立つ立派な豪邸を見てふと頭を過ぎる。
こんなことをいつまで続ける気なんだろうか――――。
けれどどうしようも無い宿命か、運命か、それとも義務か。それが自分に伸し掛っているのがわかる。この仕事をしなければ生きていけない。生きる術を失って路頭に迷うだけだ。何より俺には『オピウムの種』が必要不可欠になっている。アレが無いとダメな体になってしまった。
この仕事は、生きる為の手段なんだ。ある種病気のようになってしまったコレと共に生きていくための――――。
ヘマをした。
荒い息と共に駆け抜けた。路地裏を縫うように、ひたすらに。
「あそこだ!居たぞ!」
「まだガキじゃねえか!」
「構うか!アレを取られたら俺たちだってどうなるか……!撃て!」
確かに聞こえた。『撃て』と――――。相手は銃を持ってる。流石に金属バッドでは勝ち目が無い。ちらと後方に視線を投げた瞬間、聞き覚えのあるあの渇いた音が響き渡った。
「外してる場合か!狙って撃ちやがれ!」
「五月蝿ぇっ!!!」
家の警備の人間であろう二人の男が声を張る。
必死で走った。必死で逃げた。今回ばかりはヤバいと心底思った。息が弾む。いつ撃たれても、命中してもおかしくない。
そう思った矢先だった――。
「!!!」
頭を強く拳がかすめるような感覚に似ていた。頭が前に傾く。
「当たったか!?」
「いや、掠っただけだ!」
頭の右側を銃弾が掠めたせいで血が出てきた。痛ぇ……くそ……。
傷口は熱く、燃えるように痛かった。真っ赤な液体が視界を遮る。それを服の袖で拭った。すると急に視界が揺らいだ。まずい――――。
「やっと捕まえたぞ、このクソガキ!」
首根っこを掴まれたと思ったら脳みそが揺らぐくらいの衝撃が走った。頭を殴られたらしい。さっきとは比べ物にならない血が飛ぶ。
「さ、盗んだもん返しやがれ!」
呼吸が小刻みになる。渡してたまるか……これが無いと報酬が貰えねぇんだよ……。
「あ? 死んだのか?」
ぐったりとした俺を見てもう一人の男が覗き込む。そこを――金属バットで思い切り殴ってやった。
必死で走った。
盗んだ例のモノは服の中に隠した。それを抱えて走った。
富裕街から貧困街への路地は絶対にアイツ等よりも俺の方が知っている。それには自信があった。
何度も通った道だ。迷う訳がない。
富裕街五番地からねぐらにしている場所までは結構な距離がある。けれど廃材街に入ればなんていう事はない。
廃材街五番地辺りまで来れば治安は極端に悪くなり、まともな人間ならまず近付かない。その程近くに、俺は住んでいる。
住んでいる、というのは正しい表現かわからない。適当な雨風を凌げるような廃屋を見つけたから、そこを寝床にしているだけだ。
生きるのに最低限必要な物があればいい。水は運良く引いてあって、それを使っている。
近くに廃材の山もあって、富裕街からの廃棄物はそこに辿り着く。その廃材の中から適当に物を作って遊んでいた。機械いじりは嫌いじゃない。
ガラクタの中から人形の頭とロボットの声帯を見つけて、それで頭だけのアンドロイドを作ってやった。まあ、番犬みたいなものだ。
今日は先客が居た。それも見た事のないガキだ。
俺に会いに来る奴なんてものは限られていて、いつも仕事を紹介しに来る『ネズミ』と勝手に俺が呼んでいる男か、それに関係してる誰かだ。
どっかで見たことがあると思えば、あれだ、富裕街唯一の学校。そこの制服着てやがる。でも金持ちそうには見えない。
それに金持ちはこんな辺鄙な土地には来ないだろう。制服以外はくたびれてるようだから、まあ廃材街一番地辺りのギリギリ金持ちってとこか。
どこか怯えているような気がした。無理も無い、同じ年の頃のガキが目の前で血まみれで立っているのだから。
話を聞けば予想した通り、富裕街にほど近い所に住んで、貧乏な癖に高い金を払って見栄を張ってるだけだった。
名前はシュンというらしい。
何も知らない初めて会ったガキと飯を一緒に食った。いつも世話になってる屋台のオヤジもよくしてくれた。
シュンの母親はどうやら体を売ってるようだった。一言しか聞いてないからわからないけれど、多分そうだ。俺のカンが外れてなければ。
貧困街の人間が学費を払うなんてことは無理に等しい。
簡単に、且つ大金が手に入るような仕事をしなければ不可能だ。そういう仕事は大抵まともな仕事では無い――――。
シュンも例外では無いだろう。
然しなんでこんなガキが一人でのこのこと4番地まで来たのか。一人で帰れるのかと聞けば、コイツは人一倍記憶力が良いらしい。けれどそれがいつか命取りになるような気がして俺は忠告だけしておいた。
シュンはまた4番地まで来たいと言った。
親が仕事をしている時、コイツはきっと追い出されるのだろう。正直、勝手にすればいいと思った。来たいなら来ればいいし、そうでなければ来なければいい。
取り敢えずその富裕街の制服を着てくるのだけはやめろと言った。
貧困街で学校の制服は目立ちすぎる。
するとシュンはやけに嬉しそうな顔で返事をした。
「またな、シュン」
そう言って手を振る。らしくないなと思った。
8.かみかくし

それから僕は何度かマオの家とは呼び難い住処に遊びに行くようになった。
ママに追い出される日がそれから何度かあったから、必ず着替えてから出向くようにした。
マオが居ることもあれば居ないこともあったけれど、居ない時はあの頭だけの人形とお話をしていた。彼女には名前が無い。けれど僕は楽しかった。言えない事に関しては必ず『それはマオ様に伺って下さい』と言ってくれたから、気兼ねなく何でも話せた。
マオは『言えない仕事』をしているせいかたまにボロボロになって帰って来ることもあったけど、初めて会った時のように血まみれなんてことはもう無かった。
マオとは何度も話をしたけれど笑うことも、気を使うことも無かった。けれど僕にはそれが心地よくて、凄く楽しかった。
例え学校でいじめられても、暴力を振るわれても、マオと話すことだけを楽しみにしていれば気が紛れた。
僕が少し気になったのはマオの腕にある無数のポツポツだった。
針で刺したような跡だと思っていたけれど、暫くしてその正体を知ることになる。
それはいつも通り貧困街4番地のマオの住処に行った時のことだった。
その日はいつもに増して帰りが遅くて、僕は廃墟の中をウロウロとしていた。頭だけの人形と話すのも飽きてしまって、ただ歩き回っていた。
マオの家はかろうじて屋根と壁があって、窓ガラスなんかはほぼ抜け落ちていた。マオが寝床にしているであろう部屋だけ段ボールや廃材で風が入らないように工夫がしてあった。
其処に拾ってきたようなボロボロのベッドと、これまたボロボロのテーブルがある。そのテーブルに頭だけの人形は乗っていた。
それからその近くに木箱があって、そこにマオがいつも使っている物が乱雑に入れてあった。
金属バットはいつもそこから取り出していたし、あとはヘルメットとか、コートとか、何に使うかわからない物も少し入っていた。
僕が気づいてしまったのは、その近くに敷いてある布だった。
落ちているのかと思ってそれをめくってみると、そこには穴が空いていて、その穴の中にはおびただしい数の注射器が入っていた。
「ひっ!」
驚いてそんな声が出てしまい、僕は尻餅をついた。
「ご覧になられましたか?」
そう問いかけたのは頭だけの人形だった。
「こ、これは? マオが入れたの?」
「ええ」
「マオの腕にある傷って、まさかコレじゃないよね!?」
何故だか僕は必死だった。信じたくない。もし何か打っているとしても、治療薬であって欲しい――――。
「何の薬なの……?」
「オピウムと呼ばれる物です」
「オピウム?」
僕が安心したのは彼女が『嘘をつく』ということを知らなかった事だった。僕が尋ねたことには何の裏もかかずに返してくれる。きっとマオも口止めなんかするような性格では無いし、そういったことも命令して無かったのだろう。
オピウムという単語は初めて聞いた。聞きなれない言葉だ。
「強い陶酔感を味わえる麻薬の一種です。マオ様は以前から服用されており、報酬の殆どをオピウムに使っていらっしゃいます」
「麻薬って……そんな物マオは使ってるの!?」
「ええ。もうマオ様のお体はオピウム無しでは生活できない程になっています。禁断症状も日に日に酷くなる一方で――――」
「君はそれを止めないの!?」
つい声を荒げてしまった。僕はマオにそんなことをして欲しくないと思うし、どうにかオピウムを使うのをやめて欲しいと思う。
でもそんな権利なんてものはどこにも無い――――。
「お気遣いはしていますし、お言葉もかけています。けれど副作用や禁断症状に苦しむマオ様を見ると私は止めることができないのです」
「禁断症状って?」
彼女には表情が無い。けれどどこか憂いを感じた。悲しみとか、そういう類のもの。マオはそういうことも教え込んだのだのかわからないけれど。
「投与後は酷い咳が出ます。あとは不眠、嘔吐、下痢が殆どです」
それほどになってもマオはオピウムを止めない……いや、止められないんだ。
実際に目の当たりにしていないし、禁断症状や副作用が一体どういう物なのかすら理解していない僕にはきっとわからない。おそらく見たらゾッとするんだろう。そしてきっと、安易に止めろとは言えないのかもしれない。
「今日は――――帰るね」
「気分を害されましたか?」
「いや、なんだかマオに会える気分じゃないんだ。また来るよ、じゃあね」
そう言って僕はその場を後にした。
人体に影響のある薬が出回っているのは少し聞いたことがあった。
ママのお仕事の相手が話しているのをこっそり聞いたこともあったし、貧困街で話している人を見たこともある。けれど実際に見たのは初めてだった。
子ども一人入れるくらいの穴にぎっしりと埋められた注射器は不気味だった。それをマオが使っているかと思うと、尚更ゾッとした。
マオが何故オピウムを使うようになったのかはわからない。でも、できれば止めてほしい。
けれど僕にそれを言う権利はあるんだろうか。言ったところで何か手伝えるのだろうか。
僕の胸の中ではどうしようも無い感情が渦巻いていた。
富裕街で奇妙な事件が起きたのは、それから暫くした頃だった。
最初は噂程度だったけれど、段々と確信になっていき、ついには先生の口から忠告がされた。
それは下校の時のホームルームの時間だった。
「今日は皆さんに大事なお話があります。とても大切なお話なので静かに聞いてくださいね」
みんな元気に返事をした。僕は黙って聞いていた。
「最近、富裕街で皆さんくらいの年齢のお友達が行方不明になる事件が起こっています。いいですか?知らない人に声をかけられても絶対について行かないように。悪い人は平気で嘘をついて、皆さんを誘拐しようとします。例えば『ママが事故にあったので病院に一緒に行きましょう』とか、『道がわからないから一緒に案内して欲しい』など、困った振りをする人もたくさん居ます。そういう場合は必ず大人の人を呼ぶか、お家に帰って誰かと相談した上で判断しましょう」
また元気な返事。僕も同じように小さく返事をした。
様々な噂が飛び交っていた。
神隠しにあったとか、行方不明になったとか、殺されてしまったんでは無いかとか。けれど僕は貧困街で聞いた噂がずっと頭に残っていた。
それは学校の帰り道、細い路地を歩いている時のことだった。
石ころを蹴りながら歩いていると隣の通りにスーツ姿の男が二人立っているのが見えた。石ころを追っていた目線を上げて、物陰に隠れてそっと二人の会話に耳を傾けた。
「いい金のなる木を見つけたもんだな」
白いスーツと黒いスーツ。黒いスーツの方が喋って、白いスーツが気味の悪い笑い声を漏らす。
「いやぁ、さすがウチの親分っすよ」
「でも狙いどころがいいもんだな。富裕街のガキなんて」
顔まではわからない。声は……今まで聞いたことが無い気がする。ママのお客さんでもこの声の主はいなかったと思う。
「まさかガキの臓器があんだけ高値で売れるとはな」
その一言に息を飲んだ。――――ガキの臓器?
「富裕街のガキ攫って、それをまた富裕街の人間に売るなんて誰も考えやしねぇよ」
「しかも金持ち連中は自分のガキの為ならいくらでも金を積むんだから、こんな美味しい商売ないっすよ」
白いスーツがケタケタと笑った。
気づかれない内に僕はその場をそっと離れた。でも心臓がバクバクと脈打って仕方なかった。
先生が言っていたのは本当だったんだ……! しかも被害にあった子どもはみんな攫われて、行方不明なんかじゃない! みんな殺されてるんだ!!!
あいつ等の話が本当ならば攫われた子ども達は内臓だけ取られて、売られている。それを求めているのは他でもない、富裕街の人達なんだ。
正直、ゾッとした。
きっと臓器を買っている人達は何も知らない。自分の子どもを救うために安心して提供されたものだと思っているんだ。
どうしよう、どうしよう、どうしよう。とんでもないことを聞いてしまった。
何もできないのはわかっているけれど、僕は怖くなって家までの道のりを走って帰った。
9.彼女の証言

家に帰るとママがご飯の支度をしていた。いい匂いが家の外まで漂っていた。
ママが料理をしているのは凄く珍しい。お仕事が無いのと、機嫌がいい時の証拠だ。
「ただいま」
玄関の扉を開けても何も応答が無い。ぺたぺたと歩いて台所まで行くと、そこにはいつもより少しだけ豪華な食事が待っていた。
「おかえり」
『おかえり』と言われたのが大分久しぶりに思える。やっぱり今日はママの機嫌がいいみたいだ!そのテーブルに広げられた食事を見ればわかる。
「これ、どうしたの?」
僕が目を丸くしているとママがにっこりと笑った。
「臨時収入が入ったからシュンの好きなもの作ってやったのさ」
「りんじしゅうにゅう?」
「いいから、手洗っといで。すぐご飯にするよ」
「はーい」
僕は小走りで洗面台へ向かった。やった……やった!ママが優しい!しかもハンバーグ!小さいけど、お肉だ!やった、やった!
その日の夕ご飯は今まで一番楽しいご飯だったように思えた。
ほっぺたについたご飯粒もママは笑って取ってくれた。凄く、凄く楽しかった。
僕はその夜どうしてもママと一緒に眠りたくてワガママを言った。いつもは機嫌が悪くて何かブツブツ言いながらも布団に入れてくれるけど、この日は優しく微笑んで「おいで」って言ってくれた。
昼間に見たスーツ姿の男たちがどうしても頭から離れなくて、怖くて仕方が無かった。でもずっとママが隣に居てくれたから少し気が紛れた。
ママはたまに怖かったり僕を叩いたりするけれど、でもやっぱりママはママだから。どんなことがあっても僕はママが大好きだと思う。
あの注射針の山を見て以来、僕はマオに会っていなかった。
何度か足を運んでいたのだけどマオはあの場所には居なくて、頭だけの人形と少し話をする程度だった。彼女曰く『最近は忙しい』らしい。
前に言っていた『仕事』が忙しいのだろうか。そんなことを思っていた。
久しぶりにまた足を運んだけれどやっぱりマオは居なくて、僕は渋々帰ることにした。
行きも帰りも通る道は必ず違う道を選んで通った。貧困街は何が起こるかわからないし、あのスーツの男たちを見てからなんだか怖くなってしまったから。
けれどその日もマオはいなくて会うことは叶わなかった。
色々と僕なりに考えたけれど、やっぱり僕はあの注射器をこれ以上増やしたくないと思う。マオが壊れていくのを見たくない。もっと一緒に話したり、遊んだりしたい。
マオは自分の感情を表情には出さないけれど、僕はそれが好きだった。不思議と安心する。
僕の周りには感情的になる人が多いからかもしれない。学校で僕をいじめる子達も、ママもそうだ。
だからマオは一緒に居ても怖くないし、ビクビクすることも無い。だから安心するのかもしれない。
帰り道、日はもうとっぷりと暮れていた。
ママに戻って来いと言われた時間には十分間に合いそうだ。今日もまた違う道を選んで帰ることにした。いつもよりは細い、入り組んだ路地。もうこの辺りの路地は殆ど把握しているかもしれない。そのくらい僕はマオの家との間を行ったり来たりしていた。
途中、一際薄暗い路地に入った。街灯が無く、月明かりがなんとか差し込む程度で、酷く不気味な路地だった。気持ちが悪いと思いながらも僕の足取りは少しずつ早くなっていた。
すると急に体に衝撃が走った。
「うわっ!」
突然細い路地から飛び出した女の子がぶつかってきた。その衝撃で僕は女の子と一緒に倒れ込んでしまった。
「だ、大丈夫!?」
慌ててその子の体を心配すると、よく見れば僕も通う富裕街の学校の制服を着ている。
ゆるくウェーブのかかった綺麗なブロンドだった。真ん丸な目はこれでもかというくらい大きく見開かれ、潤んでいる。
「た、助けてっ! 怖い人達が追いかけてくるの!」
「怖い人達?」
訳がわからないまま話を聞いていたけれどすぐ近くから足音がして、僕は彼女の口を手のひらで覆って適当な物陰に隠れた。
まだ現状を把握していないけれどなんとなく危険なことはわかる。けれど彼女が呻くものだから僕は必死で手に力を込めた。
「静かにっ! 見つかったらどうなるかわからないだろ!」
すると彼女はなんとか声を出すのをやめ、荒い息を必死で抑えようとしていた。
路地の廃材とゴミ箱の影に潜んで、僕はそっと様子を伺った。鼓動が早鐘を打つ。この足音――――きっと革靴を履いている。それも上等の。
「すいません、見失いました」
「メスのガキ一匹だろ? 何やってやがる」
「すいません、兄貴」
「まあいい、そう遠くは行ってないはずだ。すぐ見つかるだろう」
男が二人。この間の二人とは違う。子どもを一人取り逃がしたというのに随分と落ち着いているように感じた。多分、慣れてるのかもしれない。
グレーのスーツと、黒のスーツ。この間の二人とは違う、上物の服と靴に見えた。顔は――駄目だ、ここから見ようとしたらバレてしまう。
「まあ、逃がしたとしてもなんとかなるだろ。あのガキの素性ぐらいすぐに調べられる」
彼女がビクッと体を震わせた。彼女はきっとアイツ等の顔も見てしまったのかもしれない。そうしたら口封じの為に――。
もうそれ以上は考えないことにした。
ライターの音がする。『アニキ』と呼ばれた黒のスーツの男が煙草を吸い始めた。少し匂いが鼻をつく。
「仕方ねぇ、行くか。来い、ヘビ」
「はい」
革靴の足音が遠ざかる。はっきりと聞こえなくなったのを耳にしてから、僕は口を抑えていた手を離し大きく息をついた。
僕の隣の女の子はまだガタガタと震えていて、僕も手が震えて血の気が引いていた。まだ心臓がドキドキしている……それは彼女もきっと同じなんだろう。
「大丈夫……?」
彼女は僕と目を合わせないまま何処か一点を見つめて何度も頷いた。ブロンドの髪がふわふわと揺れる。
「どうしてアイツ等に追われてたの? 一体何があったの? しかも君、富裕街の人間だろ? なんでこんな所に……」
「なんで、知ってるの? あなた、貧困街の人じゃないの?」
「その……制服が、富裕街の学校のだろ? 一度見たことだけあるんだ」
怪しまれないように適当に答えた。同じ学校に通っていることがもしバレてしまったら、色々と不都合があるから僕はできるだけそれを隠したかった。
「私もここに来たくて来たわけじゃない……」
「じゃあ、なんで――」
すると彼女は目を潤ませながら、少しずつ言葉を繋いでいく。恐怖と緊張からか口にするのも憚るのかもしれない。
「面白いものがあるって、見せてくれるって言われて――」
僕は信じられなかった。そんな子ども騙しみたいな手でのこのこついて行ったのだろうか?学校でも言っていたから彼女も絶対に先生に忠告されていた筈だ。
「それでアイツ等について行ったの!?」
「違うの! あの人たちは知らない! “あの子”について行ったらそこに居て――!!!」
「“あの子”?」
「帰り道で会ったの……。おうちの近くに居て、少しだけお話して、一緒に遊んで、そうしたら『面白いものが家にあるから遊びに行こう』って言われたの。おうちは貧困街って言ってた。でも私怖くて、それに最近私の通っている学校で生徒が行方不明になる事件も多くて先生に言われたばっかりだったから――。でも“その子”が『自分は貧困街の人間だから大丈夫だ』って言って、『何かあったら助けてやる』って言ってくれたの。それで一緒にここまで来たら――」
「アイツ等が居たんだね?」
彼女は頷いた。そしてぽろぽろと涙を零した。
僕は「大丈夫だよ」と言って指で涙を拭ってあげた。僕も凄く怖かったんだ。きっとこの子はもっと怖かったに違い無い。
「すごく、すっごく怖かったの……。気づいたらもうその子はいなくなってて、あの二人の男の人が話しかけてきて。『おじさん達と一緒に遊びに行こう』って言われて、声が出せないように捕まえられたから手に噛み付いて、それで必死に逃げてきたの。きっと私、騙されたんだと思う。“あの子”が怖い人達の所へ連れて行って、富裕街の子を攫ってるんだって思ったの」
「“あの子”って、君と同じくらいの年だったの?」
彼女は頷いた。どうやら気分は少し落ち着いたようだった。
子どもを使っておびき出して誘拐する手筈だったのか――ならこんなにも簡単に誘拐できるのも頷ける。他の子たちも同じような手口でやられたんだろうか――。
「身長も、年齢も同じくらいだった。あんまり笑ったりしない子で、でも私の知らないことたくさん知ってて楽しかったの。でも服もボロボロで痩せてたから、きっとあの怖い人達にお金を貰ってあんなことをしてたんじゃないかと思って」
ならばやっぱり貧困街の生活ができない子なんだろうか。でも親が無理矢理そういう仕事をさせていることもあるし――。
「見せてくれるって言った物もね、凄いのよ。喋る機械のお人形があるって言ってて、それも自分で作ったって言うの!」
――――僕は、心臓が止まりそうになった。
頭の中で警鐘が鳴る。言葉も出ない。口が、体が、麻痺してしまったように動かなくなった。
「ねぇ……その子の顔とか、特徴は何か、無かった――?」
やっと絞り出した言葉だった。
「そうね……でも凄く変な子だったわ。金髪で――でも私みたいな綺麗なブロンドじゃなくて、真っ白に近い髪色で。ぶっきらぼうな喋り方だった。あ、あと――――」
僕は、信じたくなかった。
「目の周りが真っ黒になるくらいのクマができてたわ」
10.生きるという正義

僕はその晩彼女を家まで送って行った。
貧困街の地理は圧倒的に僕の方が詳しい。まだ近くに居るかもしれないスーツの男達に遭遇する危険もあったから一緒についていくことにした。
彼女にはついでにスーツの男二人の特徴も聞いておいた。
兄貴と呼ばれた黒のスーツの男はぺったりと撫で付けた髪を七三に分けていると言っていた。細いつり目の男で、彼女が噛み付いたのはこっちの男らしい。
ヘビと呼ばれたグレーのスーツの男は余り喋ることは無かったようで、表情一つ崩さずに兄貴の言うことを聞いていたらしい。きっと子分なんだろう。
翌日、僕は彼女を探そうと学校で集合写真を探していた。
先生の机の後ろの本棚に入学式の全クラスの集合写真があるのを知っていたから、誰もいない時にそれをこっそりと覗いた。
Dクラスの子だった。綺麗なブロンドは昨日見たままで、クラスメイトの中でも一際輝いているように見えた。
数日後、彼女が行方不明になったという話を聞いた。
家に着いた時に彼女は「ありがとう」と言ってくれた。真ん丸な瞳と、綺麗なブロンドを思い出すと、なんだか虚しくなった。
僕はマオに会わなければならない。マオと話をしなければならない。
それはある種の使命感にも似ていて、この暫く会わなかった期間を酷く悔やんだ。
マオと会うことを避けていた僕への報いだ。もっと早く知っていれば、何か出来たのかもしれない。
マオは奴らに加担している。それが分かった今、僕にはやらなければいけないことが出来た。
話を聞いて、説得しなければ。そう思った。
その日はママも家に居たけれど、遊びに行くと言って許可を貰った。
長時間出かけることなんて無いからママに止められるかもしれないと不安に思ったけれど、どうやら男の人も来るみたいだからママにとっては好都合だったみたいだ。
いつも通り適当な道を選んでマオの家まで歩くことにした。今日も空は晴れ渡っていた。真っ青な空が路地に差し込む。太陽が眩しかった。
この恨みたい程に青い空を僕はいつも眺めていた。いじめっ子達に叩いたり、蹴られたりしながら、ぼんやりと空を見ていた。
僕が怒ったり泣いたりすればする程、いじめっ子達は決まって喜ぶから。だからもう黙って無感情にやられる事にした。
その度に空を見た。なんであんなに青いのだろうと、なんであんなに晴れ渡っているのだろうとずっと思いながら。
マオの住処は外に草が生い茂っていて、天気が良いせいか今日は一際青々しく見えた。
緩やかな風に靡いて凄く爽やかだった。
廃墟に近づくとうめき声が聞こえた。マオだ――何かあったのかもしれない。そう思うと言おうと思っていたことや、伝えようと思っていた事を全て忘れて自然と駆け出していた。
「マオっ!」
けれど目の前には僕が想像する以上の現実があった。目の当たりにした瞬間、これがオピウムの副作用なんだとすぐに理解した。
マオの横には注射器が転がっている。また、打ったんだ――。
マオは咳き込みながらお腹を抱え込んで横たわっていた。すぐ側に吐いた跡が残っているから、何度か嘔吐を繰り返しているようだった。
「マオ様、シュン様がいらっしゃいました」
マオは僕を視界に捉えた。
「マオ、大丈夫?」
僕はマオの体をさすった。気休めにしかならないだろうけど、何かしてあげたかった。
それでもマオは何度も吐いた。寒そうでずっと震えている。
「がはっ! おぇ……、くそ、来るんじゃねぇよ……。見せもんじゃねぇぞ……」
「マオ、もうやめよう? お願いだよ、もうオピウムなんて体を蝕むだけだよ!」
「うるせぇっ!!! 触んなっ!!!」
マオは僕の手を振り払い、外の水道までよろよろと歩いて行った。
落ち着くまで少し離れていようと思った。あれじゃまともに話ができる状態じゃない……。
「ねえ……あれが毎日続いてるの……?」
「ええ」
頭だけの人形は返事をした。心無しか悲しそうだった。
暫くしてやっとマオは落ち着いたようで廃墟の中に戻ってきた。
頭はびしょびしょに濡れていた。頭から水を被っていたんだろうか、それで副作用が止まるのだろうか。
「もう大丈夫なの?」
「なんで知ってた」
僕の問いかけには応えてくれなかった。マオが言うのは僕がオピウムの事に関して知っていたことだろう。
マオはちらと頭だけの人形を見た。
「お前か」
「申し訳ございません、マオ様」
「別に構わない。隠すつもりも無かったからな」
マオは転がっていた注射器を拾った。そしてあの穴に放り込む。また一つ注射器が増えて、マオの体は確実に壊れていっている。
マオの姿を見て僕は凄く怖くなった。これがオピウムを使った成れの果てなのだと、現実を突きつけられて体が震えた――。
「ねえマオ、それを止めることはできないの?」
「無理だ。オピウム無しじゃ生きていけない体になった。今更止めることなんてできやしない」
「でも、どうにかできるかもしれないし……。そうだ! 僕がいっぱい勉強して薬を作るよ! 副作用と禁断症状を止めれる治療薬!」
するとマオは溜め息をついた。
「じゃあお前が薬を作るまで俺はオピウムをやってていいんだな?」
「それは……」
「お前がその薬を作るまで何年、何十年かかるんだ。そんなもの出来上がる前に俺は死んでるよ」
「お願いだよマオ! やめよう? このままじゃ君が壊れちゃう!」
「そんなこと解りきってる」
「じゃあなんで!!!」
するとマオは僕の胸ぐらを掴んだ。
「お前に止める権利は無い」
僕は言葉が出なかった。悔しくて涙が出そうになった。
そうだ、僕には止める権利なんて無い。マオの苦痛も味わうことができなければ、感じることもできない――。
そうして口を開いて出た言葉は、酷く最低なものだった。
「そんなくだらない物の為に、人殺しの手伝いをしてるの?」
震える唇をどうにか動かして吐いた言葉がそれだった。
マオは無言だった。どうか嘘であって欲しいと思っていた。あの女の子の言葉は勘違いで、偶々似たような子が居ただけだって。
けれどマオが返した言葉は残酷な物だった。
「見たのか?」
胸を刺されたみたいに痛くて、息が詰まりそうだった。マオの言葉は肯定を意味してる。
「ブロンドの女の子、覚えてる?」
「――途中で逃げたガキか」
ああ、本当にマオは手を貸してたんだ。本当なんだ――――。
「逃げた後に僕が助けた。スーツの男が二人居て、そいつらから逃げる為に二人で隠れた」
マオは溜め息をついて手を離した。
「ここの所、富裕街の子どもが行方不明になる事件が多いって先生が言ってた。ねえ、全部マオが関わってるなんてこと無いよね?」
マオは何も言わなかった。
「マオ、お願いだよ……やめよう? あんな奴らに手を貸して、子どもを攫うなんてそんな――――」
「お前に何がわかる」
え――――? 僕は目を見開いて、喋るのを止めた。今マオはなんて――――。
「知ったような口をきくな」
「マオ、何言って――」
「俺は生きる為に割の良い仕事をしてるだけだ。
俺は今までずっと一人で生きてきた。気付いた時には捨てられていて、一人だった。盗みをして、死んだ奴から物を剥ぎ取って、そうやって生き延びてきた。お前は自分で何かしたことがあるのか? お前には親がいる、メシも食える、家もある、学校にも行ける。けど俺には何も無い。この身体一つで生きてきた。生きる為の手段として奴等に手を貸してるだけだ。それの何が悪い」
マオの言葉はナイフだった。とても凶暴に突き刺さる。
「俺はどんなに汚いことだってする。犯罪でも、何でも、それが生きる手段だからだ。善悪の問題じゃない。俺が生きる術はそれしかない。生きていく為にはそんなこと考えている余裕は無いんだ。お前は恵まれてる、でも俺は違う。お前が俺の生活を保証してくれるのか? メシを食わせてくれるのか? 生かしてくれるのか? 違うだろう。
良いことか悪いことかなんて誰が決めることでも無い。第三者が勝手に善悪を付けるだけだろう。それはお前が判断することじゃない」
刺さったナイフは抜けなかった。
見えない血液が流れたまま、僕はそこに立ちすくむことしか出来なかった。
***
11.カニバリズムの恩恵

その話は数週間前に突然舞い込んで来た。
あのいつもの目つきの悪い俺が『ネズミ』と呼んでいる男、そいつが俺を“呼び出した”。
珍しくそんなことなんてしたことも無かったのに。
近くの廃材の山から適当なガラクタを引っ張って、俺の住処まで持ってきた時だった。ネズミに負けず劣らずの目つきの悪い男がご丁寧に出迎えてくれた。
「お前が“パンダ”か?」
そいつが口を開いた。俺は廃材を放り投げて返事をする。
「誰の紹介だ?」
男は表情を崩さない。俺が今まで会ったことの無いタイプの人間だ。
「“ネズミ”でわかるか?」
「ああ、やっぱりアイツの紹介か」
「違う、兄貴からの呼び出しだ。富裕街のアジトまでついて来い」
急に腹が減った。確か林檎がどっかにあった筈だ。俺は手下の男を尻目に林檎を引っ張り出して齧り付いた。
不味い。カラカラで美味くもなんともない、けれど腹が膨れれば十分だ。
手下の男は煙草に火をつけた。一筋の糸のような煙が空に向かって伸びていく。
「美味い話がある」
「美味い話にゃ大抵裏がある」
「その通りだ。裏はあるけど美味いには越したことないだろ」
案外話のわかるヤツなのかもしれない、と思った。ネズミや今まで会ってきた奴らとは違う。アイツ等は自分の都合を押し付けて、相手を強引に捻じ曲げて、強制的に都合のいい返事をひねり出すことに長けている。交渉だとか話なんてできたもんじゃない。
「オピウムは?」
「3本は確実だとよ。ご希望なら上乗せもできる。それに現金もオマケでつけるとよ」
こんな話は今まで聞いたことが無い。どれだけのリスク背負わせようってんだ。
「どんだけヤバい仕事だよ……」
「ヤバいかヤバく無いかは話を聞いてお前が判断しな。今回ばかりは降りてもいいって言われてる。ひとまずついて来たらどうだ? もう守る物も捨てる物もねぇ身だろ」
それを言われて俺はヤツの後ろをついて行くことに決めた。
シュンとは暫く顔を合わせていなかった。
何度かウチに来ていたことは知っていた。あの頭だけの人形が俺に必ず伝えた。
「本日17時頃、シュン様がいらっしゃいました。お一人でした。また来ると言っていました」
「本日18時頃、シュン様がいらっしゃいました。お一人でした。また来ると言っていました」
「本日、シュン様はいらっしゃいませんでした」
「本日もシュン様はいらっしゃいませんでした」
少し仕事が立て込んでいたせいもあった。オピウムを稼がなくては――体が追いつかない。
金とオピウムの為に危ない仕事をする毎日で、家に帰っている暇も無かった。
やっとゆっくりできるかと思えばこの有様だ。なんで富裕街なんかに行かなきゃならないんだ。あんな掃き溜めみたいな場所、御免だってのに――――。
連れてこられたのは富裕街は2番地、裏通りの建物だった。
2番地と言えば一等地に近いけれど裏通りはそういう奴らしか居ない腐った街だ。そんな場所に堂々と居座っているんだから、この街も相当腐ってやがる。
上等な赤煉瓦の建物だった。その二階に案内された。
「ご苦労だったな、ヘビ」
男の名前はヘビと言うらしい。ネズミとヘビとは物騒な組み合わせだ。
「座れ、俺にとってもお前にとっても大事な話だ」
革張りのソファに促され腰を下ろした。ヘビはドアの前に立ち、ネズミは俺の向かいに座り煙草をふかした。
やけに高級感が漂う部屋だった。俺が住んでいる廃墟とは比べ物にならない。
「ガキを攫う手助けをするだけだ。簡単だろう」
煙が当たる。不愉快だ。
「それだけじゃ仕事の内容が読めない」
するとネズミは笑った。そう、裏の人間ってのはこういう反応が普通だ。振り返ってヘビの様子を見れば、相変わらず無表情で突っ立っていた。
「今ガキの臓器が裏で売買されてる。しかもとんでもねぇ高値でだ。なんでこんな事が今更って話もあるけど、発端は極々小さなことでよ。富裕街のどこぞのガキが難病にかかったんだよ。方法は内蔵の入れ替えだけだ。でも今現在ガキの臓器移植ってのは違法でよ、当然ながら売る方も買う方も法に触れるんだよ。それでも金の有り余ってる人間ってのは我が子をどんな汚い手を使ってでも救いたいってもんさ。泣けるだろ?」
ネズミは話を続けた。
「そこで目を付けたのは医者だ。秘密裏にガキの親に話つけて、その親が金を積んで、裏で臓器移植をするって魂胆さ。これがまぁ旨いビジネスになってよ、医者も富裕街の人間も表沙汰にならないように金を積んでもみ消してる。それで美味い汁を吸うのが俺達だ。医者が臓器を仕入れる先なんて言うのは正規のルートじゃ有り得ない。頼られるのは俺達だ。しかもコッチは強請(ゆすり)もできるオプション付きさ。久々にいい商売見つけたってもんだ」
相変わらず汚い人間共だ。そんな事普通の人間なら考えつかないだろうに。ガキの内臓売りさばいて喜んでんだ、悪魔か何かだろう。
「ガキの臓器って言っても、貧困街で何を食ってるかわからないようなモンじゃ駄目だ」
「富裕街のガキか?」
ネズミはニタリと笑う。気色が悪い。
「共食いとは知らずに奴らは平気で金を出す、とんでもねぇ世界だよ。けど富裕街のガキを攫って殺すには手間もかかればリスクが高い。
そこで――――お前の出番だ」
そういうことか……くだらねぇ。確かにガキをおびき出すにはガキが一番だ。警戒もされない。
もしもの場合になっても処分が楽だ。俺を殺せば済む。目撃者はほぼゼロに近い。成程――よく考えたもんだな。
「報酬は?」
「かなり割の良い仕事だからお前にもいつもの倍近く出せる。オピウム10本まで出そう。必要ならオピウムを減らして現金でもいい。金ならオピウム10本分まで出してやる」
目先の欲に目が眩む――とはこういう事か。
俺もコイツ等となんら変わらない。悪魔に魂を売る下等な生き物でしか無い――――。
仕事は楽だった。今までやってきた何よりも、どの仕事よりも簡単だった。呆気ないくらいに。
最初にどこまで連れてくるかを話して、適当なガキを見つけて連れてくるだけだ。
信用させる為に少し話をして、遊んだ時もあった。そうして必ずこの言葉を言えばガキはついて来た。
『貧困街に行ってみないか?』
これは富裕街のガキには魔法の言葉だったようで、俺が様子を説明すればどのガキも目を輝かせていた。
貧困街は何も恐ろしいだけでは無い。そこを話さずにガキが知らなそうなことだけを喋れば、恐怖よりも好奇心の方が勝つ。
そうなったガキを所定の場所まで連れて行く。
そこからは奴らがどうにかしていた。その先の事は知らない。危ない橋は渡りたくない、首を突っ込むだけ危険が増すだけだ。
それで報酬はいつもの倍以上。アイツ等じゃないけれど、本当にこんなにうまい話は無かった。
注射器の数は日に日に増えていった。
止める奴もいなければ止める気も無い。穴は埋まっていく。薄汚れた注射器で少しずつ、少しずつ、体を蝕むように――――。
何回か仕事をして、富裕街の人間の中で噂が流れ始めた。
『富裕街の子どもが人攫いにあっている』
当然だ。
神隠しに近い。目撃者も居なければ行方もわからず、それからどうなっているのかさえ誰も知らない。
そんな時だった。あるガキに逃げられたのは。
金色の長い髪を緩く巻いて、シュンと同じ学校の制服を着て一人で歩いていた。
良さそうなガキだ、そう思って声をかけた。
最初は警戒していたけれど、話せばなんとか打ち解けて、例のごとく事前に示された場所まで連れて行った。
その日は報酬を貰う為に近くで待っていた。
暫く経ってから、ネズミとヘビが二人で戻って来た。少し気が立っているように見えた。
「しくじった」と言っていた。どうやらあのガキに逃げられたらしい。ネズミは手を摩っていて、どうやら怪我をしたらしい。
粗方あのガキに噛まれでもしたんだろう。ざまぁみやがれ。
その日の報酬は貰えなかった。結果的には失敗だから当然か。
けれど文句を言って食ってかかったら殴られた。まぁ、こんなもんだろう。俺の生き方なんてものは。
そのすぐ後だったと思う、シュンがやって来たのは。タイミングが悪く俺がブッ飛んでる最中だった。
胃の中の物は全部口から出てきて、震えも止まらない、咳も震えも止まらない。そんな壊れた俺を、シュンは見つめていた。
アイツは何を思って俺を見てたんだろうか。
こんなぶっ壊れた俺を、どう思ってたんだろうか。
シュンが口を開いたかと思えば「薬をやめろ」と言ってきた。やめられるならばとっくにやめている。
もうそんな体じゃない。文字通り俺は『壊れて』いるんだ。
その上甘えたようなくだらないことを言いやがったから、正論をぶつけて追い払った。
もう、シュンはここへは来ないだろう。
もう、来なくていい。――――来るべきじゃない。
12.アンドロイドの涙
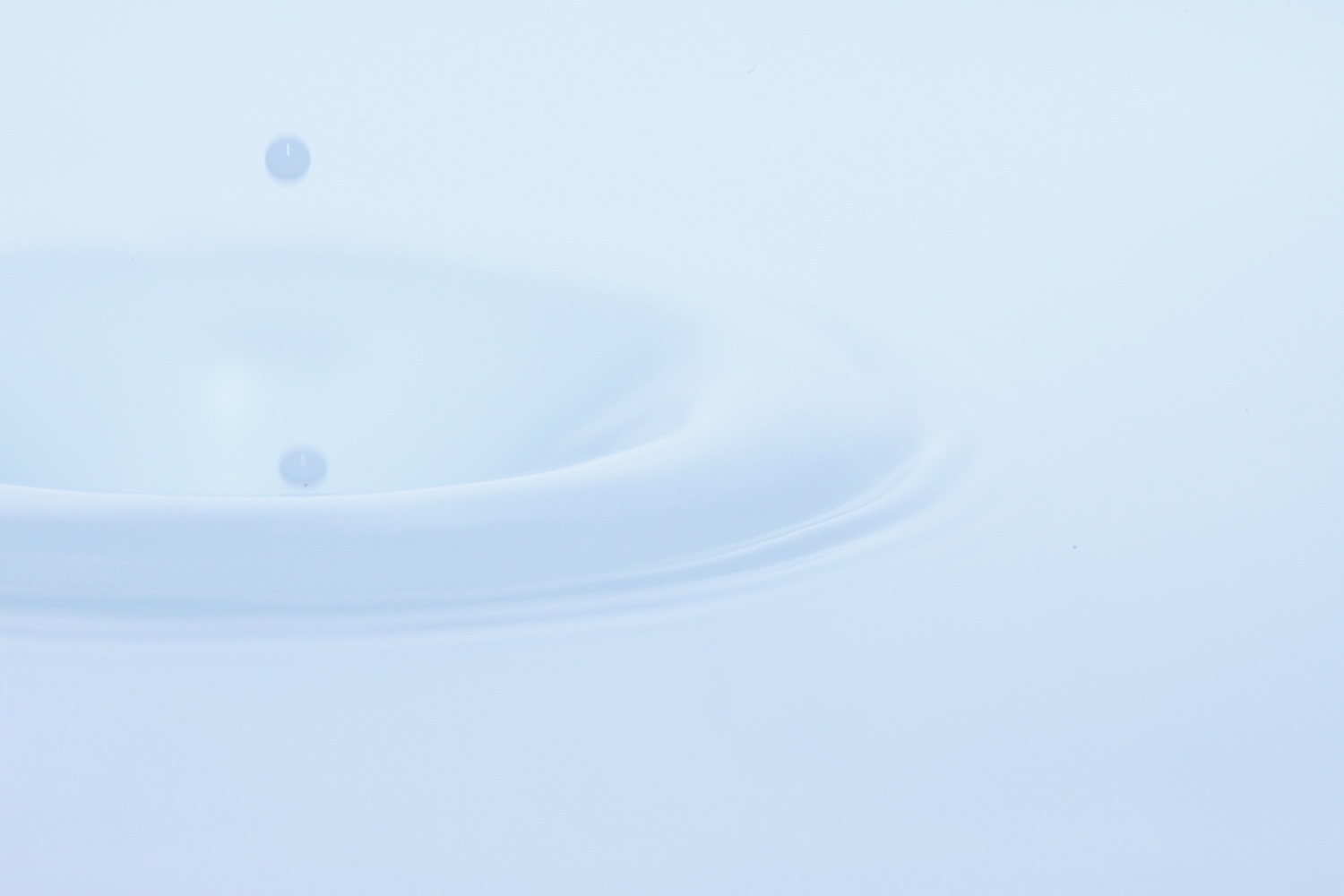
シュンが来なくなって一週間が経っていた。
あれからオピウムの数は減らした。どうにも我慢できない時にだけ打った。
屋台の親父に期待もしないで治療薬があるか聞いてみた。帰って来た答えが意外とまともな物で驚いた。
大分前の話になるらしいけれど、貧困街を渡り歩いている時に一人のジャンキーに会ったらしい。
そいつは屋台に飯を食いに来たようで、けれどどう見ても酷い中毒者だったらしい。話を聞けばそいつは医者で、どうにか自分自身で依存症から抜け出すために薬を作ってるようだったと。確か貧困街8番地辺りだったと思うと親父は言っていた。
中毒症状を緩和する薬だったらこの辺りにも存在するのかもしれない。
ダメ元で闇医者に片っ端から声をかけてみようかと思う。金なら今は少しくらいならある。
あれからシュンを見なくなったけれども、心残りだったことが一つあった。
それはあの金髪のガキとシュンが一緒に居たということだった。本人が言ってたんだ、事実だろう。
下手したらネズミとヘビの顔も見ているかも知れない。それにあの記憶力の良さなら絶対に今でも覚えている――――。
もしシュンが奴等に見られていたとしたら、殺される可能性も高い――。
けれどすぐに頭の隅からかき消した。
あいつがどうなろうと俺の知ったことじゃない。
今まで盗みを働いたヤツも、半殺しにしてきたヤツも、攫ったガキも、どうなろうと知ったことがない、そうやってきたんだ。
今更人の後先を考えることなんて無い。
ガキが逃げた一件から仕事はパタリと来なくなった。
向こうも下手に動けなくなったんだろう。それか――あのガキの始末をしてるかどっちかだ。
俺はその間適当に仕事を探して働いて、貧困街の遠くに行って廃材をかき集めたりなんかしてた。
久しぶりに落ち着いた時間が流れていた。
太陽が暖かくて、適当に廃材を使ってガラクタを作って、気ままに過ごすなんてどれくらいぶりだろうか。飯を食えるぐらいの金は手元にあった。
ガキの誘拐の手伝いが想像以上にいい仕事だったせいもある。
シュンのせいでは無いけれど、オピウムは控えるようにした。
屋台のオヤジの話を聞いて裏通りの闇医者を探しに行った。結局は見つからなかったけれど、安定剤は見つかった。
これも貧困街の外れに住んでいる闇医者から買った物で信用性には欠けたけれども、使ってみればある程度は軽減された。
気休めにしかならないけれど使ってみる価値はあると思って使っている。
数日経った頃に珍しくネズミがやって来た。
相変わらず趣味の悪いサングラスに髪型、遠目からでもすぐにわかる。
「ほとぼりが冷めたか?」
ネズミは煙草を咥えたまま言葉を発さない。話さないのなら何の為に来た、と聞きたい。面倒だからそのままにしておく。
「お前に聞きたいことがある」
「あのブロンドのガキなら知らない」
「そのガキのことならもういい。もう身柄は拘束してる。あとは殺すだけだ」
捕まったのか……。誰かが一度救った命もこうやって奪われていく。無情な世界だ、この街は。
「そのガキが妙でよ、富裕街のガキが貧困街から一人で逃げるなんて無理な話だろう。それで話を聞けば『同じ年くらいの男の子に助けて貰った』って言う訳だ。
パンダ……貴様じゃねぇだろうな?」
下らない――――。俺があのガキを助けて何の得になるって言うんだ。
「ふざけるな。俺はあの後お前らと顔を合わせただろう。それにあのガキを助ける理由なんて俺には無い」
「そらぁ安心した。悪かったな、疑って」
けれどネズミの口振りはどこか全てわかっていた風だった。カマかけようとしたのか――駄目だ、読めない。
「ガキの言うことだから信用性に欠けるが、貧困街の人間には違いなさそうだった。道の案内しただけで迷いもせずに家までたどり着いたそうだ。ガキでそれだけの事ができるなんて話は聞いたことがねぇ……。廃材街を熟知してるか、相当記憶力が良いかなんかだろう」
「それで俺にカマかけたって訳か」
「人聞きの悪いこと言うなよ」
ネズミはおどけてみせたが腹が立つだけだ。バットで頭を殴ってやりたい。
「お前ぐらいの歳で裏稼業やってるガキなんていねぇよな?」
「聞いたことねぇな。小さい仕事やってるヤツなら居ても、この街を熟知してるガキなんて居ない」
「なら偶々居合わせただけか……」
そこで電話のベルが鳴った。富裕層の奴らが持っている携帯電話だ。ネズミも例外では無く持っている。
「俺だ。……それらしいガキを見たかもしれない? わかった、すぐ行く」
短い通話だった。けれどそれで大体の内容は見えた。
「ガキを探す必要があるのか?」
余計な事を聞いたかも知れない。口を開いた後で気付いた。
「俺とヘビの顔を見てるかもしれない――殺す必要がある。仕事に支障が出ればお前も迷惑だろ」
ネズミは地面に煙草を放り、それを足で踏み潰した。俺の庭に煙草なんざ捨てるんじゃねぇ。
「次に来る時は仕事持って来れるかもしれねぇな。せいぜいオピウムに縋って待ってな」
ネズミはそれだけ言い残して去って行った。
シュンの母親は身売りをしている。それで金を稼いでる筈だ。
もし客としてネズミと関係のある人間が来ていたら――――シュンが殺されるのも時間の問題だ。
「お帰りなさいませ、マオ様」
「……」
俺は喋る頭部の機械を見た。コイツをもう少し有能にしてやろうと思ってパーツを拾って来たけれど、このままの方が幸せなのかも知れない。
既にコイツは頭が良い。
「どうされましたか?」
コイツは何を見てるのか。感情は無いにせよプログラムで判断はできている筈だ。
「お前を改造してやろうと思って廃材を拾って来た」
「まぁ、それは有難うございます。如何様に改造して下さるのですか?」
「お前はどうなりたい」
「私……ですか?」
表情は勿論無い。けれど戸惑っているようだった。感情が芽生えた――いや、そんな筈は無い。
「マオ様、私はこのままで十分です。マオ様が改造を、より良いシステムをお望みならばして下さい。私の望みはマオ様の望みです」
「作ったのは俺だ。けれどもうお前の中には“お前”が出来てる」
目の前の頭は少しだけ黙って、ゆっくりと口を開いた。
「マオ様、少し変わられましたね」
「?」
変わった? どこが、何が。俺は俺のままだ。何も変わってなんかいない。
「シュン様は無事でしょうか?」
「――――聞いてたのか?」
「申し訳御座いません」
「別に、聞かれて困るような話じゃない」
コイツは、シュンを心配しているのか? 俺の知らない間に大分頭が良くなっているようだ。
「時間の問題だろうな。アイツが見つかるか見つからないか」
「シュン様は優しい方です」
「だから何だ」
「シュン様はいつでもマオ様のご心配をされていました」
「知るか」
「お体の心配を。日々の心配をしていらっしゃいました」
ふと、思い出した。最初に会った時も、アイツは俺の心配をしていた。
俺は『心配』という感情がわからない。他人の身を案じて何になる。人を気にかけて何になる。何も見返りなんて無いだろう。
「マオ様、私のプログラムでは明確な答えははじき出されません。私には感情も無いので笑顔も、涙も、表現できません。けれどシュン様が私に下さった言葉の全ては、マオ様が作って下さった人口知識の中に全て刻み込んでいます」
「だから何だ。お前は何が言いたい! 俺に何をして欲しい! 指図する気か!」
「ですからマオ様、私のプログラムでは――――っ!!!」
金属バットで俺は、自分で作った機械の頭を吹っ飛ばした。
ノイズのような機械音を漏らしながらソイツは壁に打ち付けられた。
コードがゆっくりと弧を描いて、しなって、揺らいで、俺の目の前を過ぎる。
顔の半分が陥没し、オイルが漏れ出した。それは図らずとも目尻に溢れ、まるで涙を流しているようだった。
ソイツは横に転がって目を開けたまま、スピーカーが壊れたような音を出し続けていた。
それはいつの間にか止まって、うんともすんとも言わなくなった。
いつだって一人だった。コイツがいなくても何も変わらない。また一人に戻るだけだ。五月蝿いのがいなくなって好都合だ。
俺は何がしたいんだろうか。このままオピウムに塗れて、生きて、どうしようっていうんだ。
今まで生きることに執着してきたけれど、それがなんだっていうんだ。
生きて、何になる。生きて、何をする。
俺は何なんだ。何がしたくてここまで生きてきたんだ。
部屋の隅に座って、壁に寄りかかって。バットは自然と手から離れ、ゆっくりと転がり動きを止めた。
今まで歩いてきた景色を振り返って見れば、そこに何があるのか見えなくなった。
俺の後ろには何も無い。俺の背中には何も無い。
視線を戻せばその先にも何も無い。真っ白だ、何も無い。敷かれたレールがある訳でも無い。
俺は、何なんだ――――――。
そこで急に禁断症状が襲う。
目の前がクラクラして吐き気が腹の底から沸き上がる。手足が震える。
俺は体を引きずりながらオピウムを探した。これはヤバイやつだ。止まらない。安定剤では抑えきれない。
朦朧とする意識の中でアイツの言葉が頭を過ぎった。
シュンはオピウムを『くだらない物』と言った。
確かにな――そうだ、とんでもなく下らない物だ。それに溺れる俺は、心底くだらない人間だ。
オピウムを打って、呼吸を整える。視界がクリアになって、震えも止まってきた。
陶酔感が通り過ぎて、俺は決心をした。立ち上がってバットを握り締めた。
「お前の言葉に従う訳じゃないからな」
転がった機械の塊に届かない言葉を投げて、俺は歩き出した。
13.
またつまらない毎日が始まった。
非常階段の端っこで蹴られたり、殴られたり、罵られたり。暴言を浴びて小さくなって嵐が過ぎ去るのを待つ日々。
マオと遊んでた毎日は、こんなことをされても平気だった。こんなの屁でも無かった。
また夜にマオの所へ遊びに行こうと思えば案外早く終わったりした。
体を小さく丸めながら考えていたのはマオの言葉だった。僕の頭の中を行ったり来たり。何度も、何度も巡っていた。マオの言う言葉に間違いは無い。正論だ。何も否定できる部分なんてこれっぽちっも無い。けれどそれが無性に悲しくて虚しかった。
僕には家がある。保証はされていないけれど、それなりの安全と安心もある。必要最低限の食事も用意されている。
僕の事を殴ったり、叩いたり、罵ったりするけれど、大事なママがいる。
マオにはそれらが無い。安全も安心も無くて、その中で生きている。
マオの言う事は何も間違ってはいない。僕は当然のことを言われているまでだ。
もしかしたら僕はとんでもなく酷いことをマオに言ったんじゃないだろうか、そんなことが頭を掠めるようになっていた。
あのブロンドの女の子を学校で見ることは無かった。
僕が送っていったあの日から、彼女は家の中で安全に暮らしているんだろう。
そうじゃない可能性の方が大きいけれど、そんなことは考えたくなかったから無事でいるのだと想像していた。
マオに会うことはもう無いのかもしれない。
これから一生。もう一度も顔も合わせずに二人で大人になって、どこか知らない場所でお互いに生きていくのかもしれない。
でも、それは凄く淋しいなと思った。
けれど僕はマオに合わせる顔がない。また会っても喧嘩をするだけだと思った。マオがオピウムを断ち切らない限り、僕は彼を否定し続けるだろう。
そんなことをぐるぐると考えながら家までの道のりを歩く毎日。
もうすぐママが待っている家に着く、そう思ってふと顔を上げると家の前に男が一人立っているのが見えた。
僕はすぐに近くの物陰に身を潜めた。何故だかわからないけど、パッと見てその男がママのお客さんには見えなかったこと、それと何か危険信号みたいなものを感じたからだった。
顔を合わせてはいけない、そんな気がした。
夕日が傾いて男を赤く照らす。スーツを着た男は家のドアをノックしている。気だるそうに出てきたのはママだった。二人の会話が小さく聞き取れる。
「この家にガキが一匹居るだろ。出せ」
その一言に心臓が跳ねた。咄嗟に物陰から少し出していた首を引っ込める。
男は明らかに『僕』を探している……! 僕がこの家に居ることを知っている……!
「ガキ? あんたに何か関係あるのかい、そのガキってのが」
ママは臆することなく煙草を吸いながら言った。
「どうだっていいだろ、そんなことは。兎に角出せって言ってんだ、クソ女」
「生憎今は留守にしてるよ」
「どこに行ってる」
「さぁ、あたしが知ってる訳無いだろ。こっちは体売ってんだよ。子どもに悪影響だからいっつも外で遊ばせてんのさ」
「行き場所くらい知ってんだろ」
「知るかい、そんなこと。あの子がどこで遊ぼうが何しようが帰ってくれば問題無いんだよ。出直しな」
男は不満そうな顔をしたけれど埒が明かないことがわかったのか
「――――また来る」
そう言い残して立ち去った。
通り過ぎる瞬間、僕はその姿を目に焼き付けた。
見覚えのある黒いスーツ。顔までは見えないけれど、右手にはしっかりと包帯が巻かれているのが見えた。
ブロンドの女の子が言っていた言葉を思い出す。
彼女は確かに男の手に噛み付いたと言っていた。それがどちらの手かは分からない。
けれどあの声、あのスーツ、あの靴音――――絶対にあの時に見た男だ。
一瞬にして察した僕は全身を震え上がらせ、寒気さえ感じた。
あの男は僕を探しているあの男は僕を探している僕を探している僕を探している僕を探している――――!!!!
心臓は早鐘を打って止まらなかった。そして確信した。
僕は、いつかあの男に殺される。
男が完全に立ち去って確実に足音すら聞こえなくなったのを確認して、僕はゆっくりと路地裏から這い出た。
凄く怖くて、どうしてもママの側に行きたくなった。
路地裏のパンダ
アイディアを頂いた楽曲、及び作者様の他楽曲⇒ttp://www.nicovideo.jp/mylist/12682175
アイディアを頂いた楽曲の作者様HP⇒ttp://reissuerecords.net/diary.html
※不適切でしたら御手数ですがご一報下さいませ。


