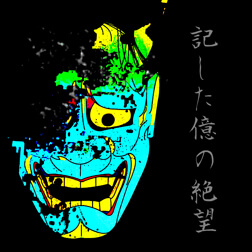
記した億の絶望
注意:性行為の場面は書かれていませんが、それを強く匂わせる描写、その他に生理、流産、など気分を害しやすいグロめの表現が多々あります。苦手な方は絶対に読まないでください。あらかじめ誤解のないように書きますが、私はあくまで物語として書いているので、これら全てが現実で起きても良いとは一切思っていません。
序章
一番古い記憶は、当時下腹に襲いかかった激痛を否応無しに思い出させた。腹を押さえ、熱くなった体を低く屈ませれば、熱を持つ何かがどろりと股から垂れた。鉄臭い、強い異臭が鼻を突き、己の体から流れ出ている物が血であると理解できた。夥しい量の血が流れ出るのを、ただただ苦痛で朦朧とした頭で眺めるしかなかった。
生理的な涙が冷や汗と混じり合いながら顔を濡らす頃には、硬めの異物がぼとりと地に落ちたのが目に入った。何だろうと意識もぎりぎり保っていた状態でさらに前屈みになり、そこにある物を見つめると、なんだか奇妙な物体であった事を良く覚えている。小石のように小さいそれは、二つの玉が連なっているように見える。そのうちの一回り小さい玉には四つの根が生えているようだった。その四つの根のさらに中央に位置する管は、未だに股へ続いている。何かに酷く似ている、と脳裏に一瞬浮かんだ考えは、意識とともに消え去った。
ーーー『胎児』ーーー
今思い返せばあれは、未熟で正しく生まれ落ちる事も出来なかったややこであったのは解る。それが自分の腹から流れ出る以前の記憶がない以上、相手の男は誰であったのかは定かではない。ましてや、ややを作る行為が同意の元なのか、それとも無理矢理であったのかは更なる謎にしかなりえなかった。ーーー後者なのであろう、とは思っているが。想い合っている者同士での行為ならば相手も女の顔を見に来るだろうに。それが出来ぬのならば、その殿方は何らかの事情で会えない、もしくは死しているか。いや、やはり現実的ではないだろう。どんな事情があるにせよ、小汚い、齢十にしかならない女児に色恋沙汰で手を出す酔狂な物好きはこの世にいない。手短に弱く、性欲の捌け口として成り立ち、幼くとも性が女である者を選んだのならば、まだ理解出来るというものだ。まあ最も、このご時世ならば肉欲を銜え込む『穴』さえあれば、女も男も関係なかっただろうが。
あれから幾年も過ぎ去った今、ふと己の最古の記憶に思考を巡らせる事態を招いたこの状況に苛立が収まらない。別に過去はどうでも良いのだ。どんなに汚れていて、不幸せな出来事が最初の記憶として脳に刻まれていたとしても、この記憶は己の数少ない幼少期の出来事。今の私を作り上げた基盤と言っても良い。他人とは違う生い立ちであったとしても、痛みを知り、生きる事に執着出来たのは、他でもないこの時の出来事のおかげだ。当時刹那に浮かんだ死の恐怖も、流れ出た胎児による苦痛がなければ決して味わう事もなかったはずである。周りとくらべりゃあ我が強く、男の顔を立てるなんざまっぴら御免だと唾を吐き捨てるような下品な女になったのは認める。が、生きて行く事に貪欲な性分である以上、世間の常識とやらは只の煩わしい雑音でしかなかった。私の決めた生き方だ。陰口は言われようとも、邪魔だけは誰にもさせない。
一般的に死の話題は縁起が悪いと嫌悪感を持つ人々で溢れかえってるが、その分彼らは無知のまま、傲慢にのらりくらりと自分勝手に生きるのであろう、と勝手に推測する。時がいかに価値の有る物かも解らず、老いて死を目前と控えた瞬間、ああ、あの時あれをすれば良かった、これをすれば良かったと後悔を募らせ、胸に不安と絶望を抱えながらきっと逝くのだ。実際どこのどいつがそんな事を考えながらあの世へ旅立とうと、私には関係ない。むしろ無様に恐怖で震え上がる姿を想像するだけで、あまりの滑稽さに笑えてくる。笑いたい、けれど、目の前の女がそうさせてはくれない。
床に臥せっているのは、痩せこけた妙齢の女。肉も付ければ見れない事もない顔なのだろうが、如何せん、骨と皮だけの躯は弱々しい笑みと供に不気味に写る。だというのに、下腹だけはぽっこりと突き出ていた。ややこが、いるのだ。腹は普通の出産まじかの妊婦のよりはだいぶ小さい、が、 小さいなりにおのが存在を主張している。 十月十日もそろそろ経つ。貧相な躯にこじんまりと収まっているものの、もうすぐ生まれるのは確かだろう。
「菊、お菊。京介様は本当にのんびりな方ですね。もうすぐややが生まれる時期なのに、まだ帰ってこないんですもの。きっとまた迷子になられているのね。」
ふふふ、仕方のない人、と弱々しくもすべてを許すような慈愛に満ちた微笑みで私に語りかける。話している間も、骨と皮しかないその手で、布団越しに優しくややのいる腹を撫でていた。まだ子を産んでいないというのに、その顔はすでに母親のそれであった。
面倒くさい事になった、と心の中で舌打ちをしる。どう考えても、この女は子を無事産み落とせるような躯をしていない。子供とともに果てるか、奇跡が起きて子だけ命をつなげて生きてゆくか。どちらにせよ女、椿は、我が子を抱く事は疎か、顔が見れる事すら危うい。共に果てるのならばまだ、二つの遺体を同じ墓に入れるぐらいはしてやれる。けれど、ややが残ればそれを育てる手立ては私しかいない。そうなればそのややを生かす責任は一気に私にのしかかる。いっその事、私が昔経験したときのように、ややが流れれば良いと何度思った事か。そうすれば多少の痛みが伴っても、椿は生きられる。戻らぬ京介の事なんか忘れて、一から夢をやり直す事も可能なはずだ。
誰かの嫁になって子供を産みたいという椿の純粋な願いは、歪な形で成し遂げられようとしている。唆して婚姻も結ばず、ただ快楽を得る躯だけの関係をあの男は望んだ。愛している、親が反対して今は一緒になれない、ややが出来れば親も俺たちの結婚をきっと認めてくれる、そうすれば俺と夫婦(めおと)になってくれ、と嘘で塗り潰された甘い言葉を、椿は今でも信じている。
ボンクラの京介が戻るのを期待して、否、確信して健気に帰りを待っている椿を見る都度に、苛立から来る吐き気を覚えた。そもそもややが出来たのはあの男の誤算だ。椿を石女(うまずめ)と思い込んで手を出したのだから。定期的でないにしろ、椿には忌み日が来たというのに。もっとも、忌み日がくれば床からは出られない程の鈍痛に襲われる椿は、端から見ればいつものように病気で倒れているようにしか見えないのは確かだが。しかし、椿は石女だと認めた事は一度もない。大方椿にはそっちの知識が備わっていないとでも勘違いしていたのだろう。実際夜枷の知識は皆無だった。気づきもしないで椿の腹の中へ種を本能のまま奴は吐き続けた。椿も椿で子供欲しさと、知識の少なさでその行為を止めようともしなかった。その結果が、この様だ。死期を迎える命が私の目の前に横たわっている。
こんなになっても疑いもせず彼奴の嘘を信じ込みやがって。あの腐れ野郎が戻ってくるかよ。やるだけやって女を捨てるのが野郎の十八番なんだ。面倒事が嫌いなあの男に、期待するだけ無駄だ。だいたい奴が旅好きな方向音痴だという言い訳を鵜呑みにする椿も大概大馬鹿者だ。彼奴は知っていたはずなんだ。椿は元々躯が弱い。産んだ後もそうだが、女自身に一番負担が掛かるのは産まれるまでの期間。女がその時望むのは相手方の存在、支えである。それを、懐妊の知らせを聞いた途端に次の旅の準備を始めやがって。ややに珍しい物をたんまり見せたい、この一言を言い訳に早々と足し去った。隣に椿が見送りに立ってなけりゃあ、八つ裂きにしていたのに。今でもあの忌々しい背中が頭から離れない。今もし奴が顔を見せにきたら、きっと奴に襲いかかって嬲り殺すだろう。それ程までに京介への憎悪は膨らんでいた。
第一章
山羊の乳を含んだ布を優しくややの口へとあてがう。母の乳を味わった事のない男の子(おのこ)を見て、言いようもない虚しさを覚えた。
この子は母を知らずに生きてゆく。
椿は死んだ。息子をこの世に送り込んだ直後、入れ替わるように息を引き取ってあの世へ去って逝った。呆れる程の微笑を残して。息を引き取る前に、我が子を抱かせてやりたかったが、間に合わなかった。生きている事を限りなく主張するかのように泣き叫ぶややを、椿の胸元へ乗せる頃にはすでに躯の熱がさがり始めていた。先ほど分娩の際に触れていた肌は熱かったというのに。こうも呆気なく去られるとは。事実、ややの顔も見れないかもしれない、とは思っていた。しかしいざ現実になると、遣る瀬ない気持ちになる。せめて我が子を抱いて、名前を呼んで、愛して、長くない人生に悔やんで、理不尽な世界を憎んで、泣き叫んで、未来のある私を羨んで、生きる資格のない私を罵倒して、泣き喚いて、諦めて、覚悟をして、もう一度我が子を呼んで愛して……母親として、死んで欲しかった。
私にややは育てきれないと、愛しきれないと証明して欲しかった。いくら死後、子の面倒を見るのが私でも、決して超える事の出来ない親子の絆を見せつけて欲しかった。欲しかった。欲しかったのは私だ。親子という絆を欲したのは、誰でもない、私自身だ。娘としても、親としても。
親が居ないのは幼少の時より明らかだった。でなければあの幼さで孕む事など出来ないであろう。私は、決して護られる存在ではなかったという事だ。もし荒れ地に放り出され、野犬に襲われ喰われてしまっても、誰にも気に留められない存在。それが私だ。ならばせめて、人の親になり、一心に愛し愛されたかった。私には貴方しかいないと、貴方には私しかいないと。けれど、病弱な椿でさえ十九で初潮を迎えた事を知った時、優に五つは彼女より年上であろう私は、石女である事を悟った。悟った以前に、きっと知っていた。けれど、認めたくはなかった。母になれる可能性を捨てたくなかった。病弱な椿と同様、きっと不摂生な生活で発育が悪いだけなんだと。けれど無理だったのだ、最初から。私にはどんなに望んでも人の親にはなれないし、求められる事もない。あるのは己で護ってきたこの身と、護る為に築き上げた山姥のような野蛮な性格。人生で私の傍に寄る奇特な奴は椿だけだった。その椿さえもう居ないけれど。代わりにこの腕に残されたのは浄も不浄も知らぬ小さな命。お前は私を望むだろうか。本当の母を知らずに生き、私に護られる事を望むのだろうか。血の繋がりのない私でも、お前を、幸せに……。
もっともっとと乳をねだる為にぐずりはじめる正春で我に返ると、はらはらと何年も前に枯れたはずの涙が頬を濡らしていた事に気づいた。
記した億の絶望
中途半端に終わってますが、ここまで読んで頂き本当にありがとうございます。一発目からシリアスでグロい物になってしまいましたが、これからも『記した億の絶望』を更新しながら色々なジャンルの小説に挑戦したいと思います。よろしくお願いします。


