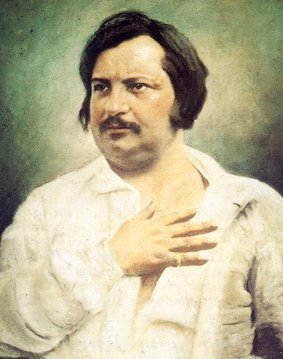東海道線にて
東海道線にて
「海は綺麗だなあ!」
Nは思わず電車の中だというのに大声で叫んでしまった。彼は東海道線の車中にいるのである。
Nは都内の大学生で、いつも長期の休みになると青春18切符を使って郷里の熊本まで鈍行で長旅をしているのだった。いま電車は神奈川県内をいくらか通り過ぎて鄙びた景色を車窓から見せるようになり、いよいよ夏の海が緑の隙間から姿を覗かせはじめていた。
「あれ? 急に電車が止まったぞ?」
Nが異変に気付くと、乗客たちも同様に気付き、ざわつき始めた。
「お客様にお知らせいたします」
車掌が車内放送を始めた。なにやら線路にトラブルが発生したため、停車して安全の確認を行っているとのことだった。
「弱ったなあ、五時半までには大阪に着いていたいのになあ」
彼は大阪からフェリーに乗って別府まで行く。その便が七時半なのだ。大阪から港までも電車を何本か乗り継がねばならないし、大阪では家族へのお土産も買っておきたい。電車が遅れてしまうと、大変なことになってしまう。最悪船に乗れなくなってしまうのだ。
「早く動けばいいのになあ……」
しかし電車は動かなかった。たっぷり三十分待っても動かなかった。
「これはお土産は無理かな」
これだけ動かないと、半ば開き直ったような気持ちになり、Nは本でも読むことにした。網棚に置いていた馬鹿でかいリュックを苦労して下ろし、乱雑に詰め込まれた荷物から本を探していると、いつの間にかボックス席の向かいに女子中学生が乗り込んでいることに気付いた。真面目そうな子供で、少し日焼けしていたが、服装からみても大人しい性格なのではないかと推測できた。昔の西洋人の子供が着ていそうな、上品な白のワンピースである。もしかしたら親類のお下がりなのかもしれない。小さくつつましく席に座り、川端康成の『伊豆の踊り子』を読んでいる。
「可愛いなあ……」
さすがにNは小声でつぶやいた。Nは女子中学生が好きなのだった。何より小動物のように気が小さいところが良い。高校生たちは若さを一番満喫していて、若さが実は人間の何よりも得がたい財産なのだということに無自覚的に気付いているがゆえに大人たちをバカにしている気配すらあるし、逆に小学生だと幼すぎて大人を怖がるという意識が少ない子供が多い。だがその中間に位置する中学生は、未だ自らの若さの価値を知らないままで、なおかつ大人たちを警戒する必要を感じ始めている。彼女らにとって大人とは得体の知れない恐れるべき敵なのである。こういう中学生に出会ったときにNがとる行動は決まっていた。
「やあ、困ったことになりましたね。こうなったら本でも読むしかないよねえ」
少女が、びくり、と全身を震わせた。Nはたまらなく愛おしい気持ちでいっぱいになった。
「お、『伊豆の踊り子』だね。俺も中学生のころ読んだけど、もう内容はさっぱり覚えてないなあ。どんな話だっけ?」
えっと、と少女は言いかけたが、結局押し黙ってしまった。彼女の内面に今どれだけ荒々しい葛藤が生まれているのかを思いやると、Nは不意に勃起してしまう自分を感じるのであった。
「あ、君もまだ読んでいる途中だよね。まだどんな話かわからないか」
少女はゆっくりと頷いた。
「ところで君は中学生だよね?」
少女は本格的に困ったような様子になった。目をきょろきょろとさせている。
「いいよね中学生は。まだまだ未来がある! 俺も中学生のころは色々な夢を持っていたなあ。今は夢かなって、東京の大学に通っているけどね! 君の夢もきっとかなうから、今から精一杯努力するといいよ。もしかして君は、小説家志望なのかな? 中学生なのに、そんな難しい本を読んでいるんだもんなあ」
ところがここでNの困ったことには、通路を挟んだ向かい側のボックス席の中年夫婦がNと少女のやり取りをじっと疑わしげに睨み始めたのである。しかしNはこうした事態にはある意味慣れていた。
「あ、これはどうもすいません! ちょっと声のボリュームを落とすことにしますね! いまどき珍しい勉強家の中学生に出会ったものですから、ついね。ところでいつまで動かないんでしょうねえ、この電車は。ここはどこですか、大磯あたりですかね?」
いきなり話しかけられて虚を衝かれた中年夫婦は、気まずそうに雑誌や新聞を眺め始めた。これくらいの危機は、Nにとっては全くどうということはなかったのだ。
「ところで話は戻るけど」Nが言った。「川端康成が好きなのかな、君は? そうだとしたら申し訳ないんだけど、俺は川端があまり好きじゃなくてね。なんでかっていうと、何かこう、ポーンと放り出されるような気がするんだよね。物語の結末を楽しみに、真剣に読んでいたのに、読み終わってみると、その読書の真剣さのみが置き去りにされて、ポーンとね、放り出されるんだ。まだ君はそれを読み終わってないからわからないだろうし、俺もその話の内容は全く忘れてしまったから確たることは言えないんだけど、おそらく君も、ポーンと放り出される気がするよ。ポーンとね。そういえば川端康成がノーベル賞を取ったとき、弟子とも言える存在だった三島由紀夫と実は賞を争っていたんだという話があるよね。それについて俺は、あの時三島がノーベル賞を取っておくべきだったと思うんだ。そうすれば三島が死ぬことはなかったんじゃないかと、俺は疑っているんだ。もちろんだからといって三島の文学的名誉に傷がつくわけじゃあない。ノーベル賞なんていったって、選考委員たちが絶対に正しい判断をするとは限らないよ。しかし、三島にしてみれば川端程度の作家に自分が劣っていると世界的にみなされてしまったことによるモチベーションの低下は、やはりかなりあったと思うんだ。それがなければあそこまで性急な死に三島が至ることは、もしかしたらなかったのではと思わずにはいられないんだなあ。あ、ごめんね、君は川端が好きなんだよね。俺だって決して川端を悪い作家だというつもりはないんだが……やはり、ポーンと放り出されるのが、どうも苦手でね」
事実、Nはポーンと放り出された。電車が動く見込みが全く立たず、乗客みんなに降りてもらうことになったそうなのだ。どうもかなり大きなトラブルが線路上で起こったらしく、その日一日は運行できそうにもないのだった。幸い駅はもうすぐそこで、歩くのに苦労はしなさそうだった。少女と一緒に並んで駅を目指しながら、Nは訊いた。
「もうお昼になっちゃったね。いやはや参ったよねえ。何があったのかな? テロだろうか? あっ! もしかして三島由紀夫が地獄から復活したのかもしれないよね! それにしても、これからどうしようかなあ。そうだ、一緒にご飯でも食べにいかないか? おごってあげるよ」
「すみません、家、すぐそこですから」
そう言って少女は走って行った。確かに駅から見えるところに彼女の家はあって、ドアを開けて中に入るところまでNは見届けた程だった。
さて、乗客たちはみなタクシーやバスなどの代替交通手段を探しに奔走し、そのうちの半数はもう手立てを見つけたようだった。N一人が東京のアパートに帰るでもなく、ましてや大阪まで行けるわけでもなく、炎天下に取り残された。この時ばかりはNは川端康成の小説にリアリティを感じざるを得なかったのであった。
(ちなみにその後Nがせっかくだからと現地でとった海が見える宿において聞いたテレビニュースによると、本当に線路トラブルはテロのせいだったらしい。新進気鋭のアナキストグループの犯行声明文も一部読まれ、Nは民宿で、「いまどき粋な青年たちがいるものだ!」と快哉めいた叫びを叫んだ)
東海道線にて