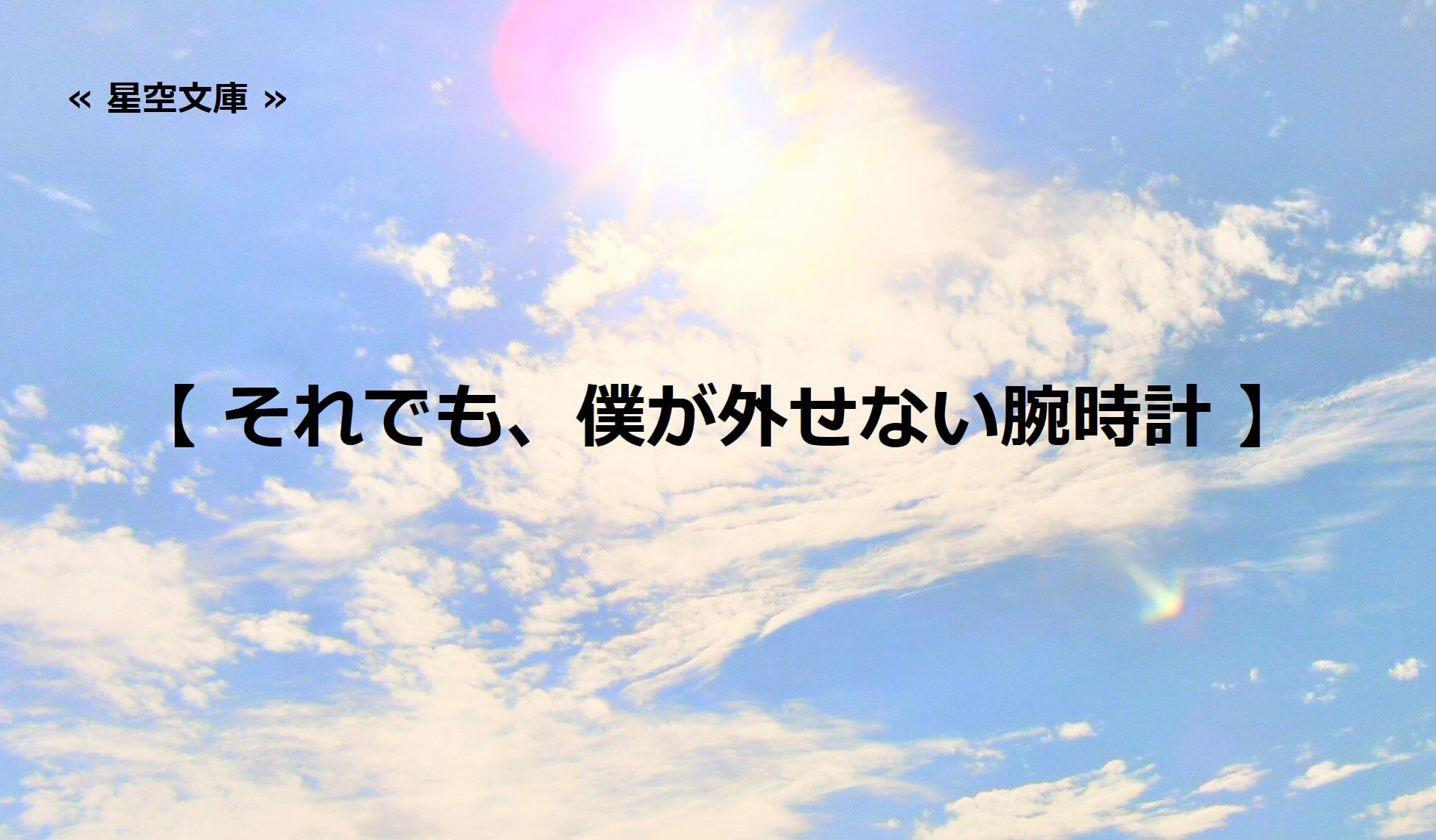
それでも、僕が外せない腕時計
1 いつもの夢
あの事故が起きた翌日の朝刊で、犯人の名前を知った。
…正直、僕は犯人が捕まっても捕まらなくてもどうでも良かった…。
紙面に丸で囲まれた彼女の顔が微かに笑っていて、不思議な気分になった事を今でも覚えてる…。
僕は決して忘れないよ。
忘れちゃいけないんだ、きっと…。
あの日何も出来なくて悔しくて悲しくて泣いた事を。
僕は決して忘れないよ。
君が好きだった桔梗の花を。
君が最期に見せてくれたあの笑顔を…僕は忘れない。
* * *
これは夢だ… 分かってる。
でも…。
高3の帰り道、セーラー服を着た長い髪が良く似合う朝美は恥ずかしげに頬を赤く染め、形の良い小さな唇が動き出す。
「あのね私…笑わないでよ…」
「何んだよ?」
「真っ白なウェディングドレス着て二十五歳までには結婚したいな…」
僕は立ち止まり目を瞑った。
「何してるの?」
「想像してんの。朝美がドレス着てるトコ」
「で、どうだった?」
にんまりとした顔を近づけて来る朝美にドキッとしながら「ん…微妙…」とふざけて言うと「ヒッドーイ…」と頬を膨らませムスッとした顔の朝美は「どうせ私は身長低いからドレス何て似合いませんよー!」と僕の肩をバシバシ叩き、僕は「悪かった。悪かった」と笑い合った。
ふと振り返ると朝美は居なく「朝美、朝美…」と僕はもう一度振り返ると地面の真っ赤な血を見つけ…。
「ハァッハァッハァー…」
いつもこんな夢で目が覚める…。
涙で濡れた頬を僕は両手で覆った。
後悔してんのかな…。
本当はあの時、ちゃんと朝美のウェディング姿想像出来てたんだ。
「絶対似合うと思うよ」って言ってあげれば良かったな…。
2 あれから4年
あれから4年が過ぎ、高校卒業後直ぐ僕は広告会社に就職した…。
そんなある日の社員食堂で…。
僕がカレー定食を食べていると遅れて長い髪を一本に束ねた後輩の志穂が「やっと見つけた…。待ってて下さいねって言ったじゃないですか…」と頬を膨らませやってきた。
「あぁ悪い。忘れてた…」
志穂は「もう…」と言いながら僕の隣に座りサラダ定食を食べ始めた。
ムスッとした志穂の顔を見ながら僕は話題を変えようと、言った。
「どう? 慣れた?」
「えぇ、まぁ何とか」
「そう…」
「前から気になってたんですけど、滝さんていくつ何ですか?」
「23…」
「えっ」
「何?」
「いや、同い年何だなーと思って。でも同い年なのに何で先輩?」
「俺は高校卒業してから直ぐ入社したからじゃない?」
志穂は「あぁ、そっか…。私は大学卒業してから入社したからか…。でも…」と言いかけて僕を見た。
「年上に見えるって?」
「いや、そんな事は。ただ、落ち着いてるなと思って」
「そうでもないさ…」
「そうですか? 大学の男子達ってもっとうるさかったですよ」
「そっ。俺がオヤジくさいって事?」
僕は笑いながら皮肉った。
「そんな事言ってませんよ」
「同い年だと分かったんだし敬語は使わなくていいよ」
志穂は「そうですか?」と笑み、ハッと何かを思い出したようだった。
「今何時ですか?」
「さぁ?」と僕は敬語抜けしない志穂を笑った。
「さぁ? ってケータイ持ってないんですか?」
「デスクに置いて来た。そっちこそ自分のケータイ見ろよ」
「えっ! それがですね、さっき落としちゃって…。でも社内だからすぐ見つかるとは思うんですけどね…。それより、時間教えて下さいよ」
「俺も分からないんだよ」
「だったら腕についてる物は飾りなんですか?」
「あぁ、これ? …そうかもな」
確かに僕の腕には場違いな茶革ベルトの小さなアナログ時計がある。
志穂は「もうー。そうやっていつも私をいじめて…。見せてもらいますよ」と強行手段とばかりに僕の腕を掴み時計を覗いた。
「ん…止まってる…」
「だから俺も分からないって言っただろ」
「じゃ、止まってるなら止まってるって早く言って下さいよ…」
「悪かった、悪かった」
「じゃ、今日終わったら付き合って下さい」
「何処に?」
「内緒です」
不敵な笑みの志穂。
* * *
「で、何でビアガーデン何だよ」
「だって女の子一人じゃ行きづらくて」
「だからって…」
「まぁまぁ気にせずに」
ほとんど一方的に志穂は喋り続け、僕はその話に「うんうん」と相槌を打ち続けた。
何の事はない話だったけど、会社で見る志穂の姿と少しだけ違っていて、アルコールのせいも多分合って、話し方が朝美と似ていて、目の前に居るのが志穂なのか朝美なのかぼやけて来た頃、トントンと机を叩かれ我に返ると志穂がじっと僕を見つめて居た。
「何?」
「ちゃんと聞いてます?」
僕は「うん、聞いてる聞いてる。飲みすぎるなよ」とジョッキ6杯目を飲み終えた志穂に言うと「分かってますよ」と束ねて居た髪をほどき、真っ赤な顔がこちらを見つめた。
「あのっ!」
「ん?」
「今度何処か行きません? やっと車の免許取ったんです私」
「車…、デートのお誘い?」
「そんなんじゃないですよ。ただいつも助けてもらってるし…」とはにかみ真っ赤な顔が更に赤くなった。
「バスじゃダメ?」
「ダメです。私の運転疑ってるんですか?」
「ばれた?」
「ヒドーイ」とむくれる志穂。
「冗談。今度な」
「ホントに?」と笑む志穂。
「あぁ…」と言いつつ少しだけ戸惑っていた。
それに気づいたらしく志穂はテーブルに頬杖をつくと僕の顔を覗きながら「嫌ですか?」と呟く。
「そんな事無いよ。車に酔いやすい体質だから酔い止め飲んどかないとなーと思って」
「そうなんだ…」
「そろそろ帰らないか?」
「そう、だね…」
3 桔梗の花
翌日、空が夕日色から闇に染まった頃。
僕は会社帰りに花屋で桔梗の花束を買い自宅行きとは反対のバスに乗った。
数十分が過ぎバスから降りると横断歩道の少し手前にある電信柱の前でしゃがみ込み桔梗を立て掛けた。
何度も目の前を行き交うヘッドライト。
あの日真っ赤に染まった地面も今は跡形もない…。
憎いより、悔しかった。
あの日一緒に居た僕は生き残り朝美が死んだ。
死んだんだ…。
僕は朝美の腕時計を撫でながら泣いて居た。
* * *
子供のように、大声で泣いてやりたかった。
でもそんなこと出来なかった。
なぜだろう?
大人になったからなのか?
それとも、ただ恥ずかしいからなのか?
恥ずかしかったら、こんな所で泣かないか…
* * *
突然「滝さん?」と呼ばれ、振り返ると少し離れた所に志穂がいた。
「やっぱり…」と口の端を持ち上げ近づいて来ると僕の頬に伝う涙に気づいたのか「ごめんなさい」と呟いた。
僕は鼻をすすり、涙を拭った。
「何で謝るんだよ」
「見られたくなかったのかなと思って…」
僕は立ち上がり「ありがとう」と呟くと、志穂は桔梗を一瞥し、察したように話を変えてきた。
「あの…」
「ん?」
「…私のアパートこの辺何です」
「へーそうなんだ…」
「寄って行きませんか?」
「…悪い、今日は遠慮しとくよ。そういえば、ケータイ見つかった?」
「はい誰かが拾って受付に届けてくれたみたいで」
「そう、良かったな」
「うん…」
僕は志穂の顔を見ながら言った。
「明日会社あるんだから遅刻すんなよ」
「しませんよ」と志穂は苦笑し、別れた。
4 円佳センセ
志穂と別れ、買い物をしてアパートに帰ると「やっと帰って来た。よっサラリーマン」と部屋の前で待ち構えていたのは、セミロングが良く似合う円佳だった。
「何してんの…?」
「待ってたの。一緒にワイン飲もうと思ってね…。寒かったんだからね」
「じゃ待たなきゃいいじゃん」
鍵を開けながら厭味を言う。
「相変わらず可愛くないわね…」
円佳にワインボトルで軽く小突かれ、僕は軽く口の端を持ち上げ「どうぞ」と円佳をリビングに通した…。
ワインを開け、グラスにそそぐまどか。
テーブルを挟み対面して座った僕らは軽く近況報告しながらワインを飲んでいると、急に真剣な顔になった円佳が言った。
「さっきね、寄って来たんだ…。あの桔梗、和紀でしょ」
「あぁ」
「お墓行って来たら?」
「いいよ。俺は」
「そう…。何でカウンセリング来ないの? 私じゃ不満なの?」
「そんな事ないですよ円佳センセ」
「またそうやってちゃかす…」
円佳は朝美の友人で、今年から新米ではあるが精神科医であり、僕は数回円佳のカウンセリングを受けていた。が、最近仕事にかまけて行かなくなった。
それでも一月に一度、円佳は僕の顔を見に来てくれた…。
円佳には感謝してる。
でも…。
「治ったよ。俺は」
「ウソ…」
「ウソじゃないさ」
僕はワインを一口飲んだ。
「和紀なら直ったフリぐらい簡単でしょ」
じっと円佳に見つめられ、僕は観念した。
「…バレたか」
「当たり前でしょ! 今でも朝美の夢見るの?」
「うん、まぁ…」
「朝美が死んだのは和紀のせいじゃないんだよ」
「分かってるよ。分かってるさ…」
これ以上円佳と目を合わせていたくなくて「自分では治ったと思ってる…。円佳には感謝してる。バスにすら乗る事を怖がっていた俺をバスに乗れるようにしてくれた。それだけで充分だよ」と立ち上がりキッチンに向かいながら続けた。
「それに衝動的に自殺したくなるのはカウンセリングを受けたからって直ぐ治るもんじゃないんだろ?」と冷蔵庫を開け中を覗いていると「そうかも知れないけど、私は和紀にッ」と言いかけてやめた事が気になり振り返ると円佳は泣いていた。
「何で円佳が泣いてんだよ」
「だって…」
僕は「だから泣き上戸は嫌なんだよ」と円佳が泣き上戸じゃない事も知っているのに愚痴り「悪かった…」と円佳を抱き寄せ少しだけ消毒の匂いがする髪を撫でていると「うん…。まだ外せないんだね。朝美の腕時計…」と呟いた。
僕は苦笑いし「うん…まぁ…」と返した。
朝美が死んでから、僕は自分に似合わないと分かっていて、いつも朝美が付けていた小さな腕時計を付ける事にした。
朝美が生きていた事を忘れない為じゃなく、朝美が死んだ事を忘れない為に僕は朝美の腕時計を付ける事にした。
円佳の涙を拭ってやりベッドに座らせた。
「ねぇ、和紀。もう、いいんじゃない? もう、充分だと思うよ。これからは自分の為に生きなよ」
円佳はジッと腕時計を見ながら言い、僕は「どう何だろうな…」とはぐらかしてみた。
「気になる娘いないの?」
「気になる娘ねぇ…」
一瞬浮かんだのは…。
「…ねぇ、しよう…」
言われ僕はジッと円佳を見つめ返事は返さず円佳をベッドに押し倒し小さな唇にキスをした。「ハァ」「ンッ」と息切れしながら舌を絡め合い、ワインで赤いのか、恥ずかしくて赤いのか、真っ赤な顔の円佳の服を脱がして行くと、右腕に包帯を巻いていた。
「どうしたの?」
「あぁ、今日病院でカルテ書いてたら上からダンボール落ちて来ちゃって。打ち身だしたいした怪我じゃないんだけどさ…」
「痛いの?」
「うん、まぁ…」
僕は両手で円佳の右腕の包帯の上から優しく掴み「フゥー」と縦に息を吐くと、円佳はじっと僕を見つめ「うん、もう痛くないよ」と言い僕は手を離した。
「相変わらずすごい『力』だね」
「何の役にも立たないよ」
「役に立ってるよ。ありがとう」
言うと円佳の方から舌を絡めて来た。
僕は円佳の形の良い胸を揉んでいると「和紀、愛してる…」と囁く声が聞こえた。
分かってるんだろ?
俺は性欲で円佳を抱いてるって。
円佳を愛してるかどうかで、抱いてるんじゃないって…。
円佳を抱くのはこれが初めてじゃない。
朝美が交通事故で死んで一緒に泣いてくれたのは円佳だけだった。
お互い慰める為に身体を重ねたのが始まりだった。
朝美への裏切りだと分かっていた。
でも寂しさを埋めてくれたのは朝美と雰囲気の似てる円佳だけだった…。
円佳を抱き続け、疲れ果てた円佳は眠ってしまった。
ほどけた円佳の包帯を見つめながら僕も眠っていた。
5 夢…高3の冬
これは夢だ…分かってる…。
高3の冬、あの日僕は車の免許を取ったばかりで浮かれていた。
隣には朝美を乗せドライブ中、急に隣を走っていたトラックが蛇行し始めトラックが横転。
ひどい爆音。
僕の車はぶつかられた勢いで何度も回転し電柱にぶつかりようやく車は止まった。
目を開けると目の前に電信柱があり車体が酷い潰れ方をしてるのが分かった。
「朝美はッ…」
隣の朝美を見ると頭や顔面、腹部からも血を流し潰れた車体に挟まれていた。
「朝美! 朝美!」
痛々しい朝美の体を揺すると目を開いた朝美は「ハァハァ、ンッ、痛い、痛いよ」と呻くような喘ぐような声で、のたうちまわりたいのに挟まれていて身動きが取れない状態だった。
痛み、苦しみ、泣く、朝美…。
真っ赤に染まりつつある、朝美…。
僕は朝美を両手で包むように抱きしめ、朝美の温もりを感じながら大きく息を吸いスゥーーと細く長い息を吐き『力』を使った。
「ごめん、俺こんな事しかしてやれない…」
僕は泣いていた。
喘ぐような朝美の息遣いがゆっくり無くなって行ったのが分かった。
「ありがとう、もう痛くないよ…」
「うん…でも、もう少しだけ…」
僕の服が朝美の血で染まっていくのが分かった。
「うん…泣いてるの?」
「痛いだけだよ…」
「私にも和紀と同じ『力』があればな…」
「こんな『力』あったって何の役にも立たねぇよ。傷を治したんじゃない、忘れさせただけなんだし…」
「それでも良い、最期にちゃんと和紀と喋れる」
「最期って何だよ!」
僕は抱き締めるのをやめ、朝美を見た。
「痛みが無くても分かるよ、もう私、そんなに時間無いと思う」
「時間無い何て言うなよ!」
「さっきからね、眠いの…」
「何言って…」
虚ろな目で朝美は僕を見つめていた。
「だから最期にちゃんと言いたいの。ありがとう、痛みを忘れさせてくれて。今までありがとう。大好きだよ」
言った後ゆっくり目を閉じた。
「何自分だけ好き放題言って…」
穏やかで、優しく口の端を持ち上げ笑んだまま動かなくなった朝美。
僕は無力な自分を責めながら泣き続けた。
そんな事しか僕には出来なかった…。
* * *
朝、目が覚め僕の腕枕に眠るのは裸で幸せそうな顔の円佳だった。
何でそんなに幸せそうな顔してんだよ…。
僕は円佳を抱き寄せ、壊れてしまいそうな小さな身体をギュッと抱きしめ、額をくっつけ合った。
「ん…痛いよ…どうしたの?」
寝起きの円佳と目が合い、僕が口を開く前に円佳が言った。
「ごめんね…」
「何が?」
「泣いてるよ…」
円佳に頬を触られ「ほらっ」と湿った指先を見せられた。
「ホントだ…」
呟くと円佳の舌先が僕の頬を舐めた。
「しょっぱい…。また悲しい夢でも見てたの?」と逆に円佳に頭ごと抱き締められた。
「どうなんでしょうかね、円佳センセ」
僕は目の前にある形の良い円佳の乳首をカプッとした。
「ンッ、何してんのよ」
「円佳先生のいやらしい声が聞きたくて…」
「もーバカ…」
6 癒えない傷
昼休みになり、僕は会社の屋上に行きコンビニで買って来た弁当を食べていると「ご一緒していいですか?」と隣に志穂がやって来た。いつものお喋りな志穂は無言のまま数分が経過した。
「どうかした?」
志穂は食べながら遠慮がちに言った。
「あのっ」
「ん?」
「失礼なのは分かってるんだけど、昨日の横断歩道で誰か知り合い亡くなったの?」
「あぁ」
「そうなんだ…もしかして彼女? 朝美さんっていう女子高生?」
「あぁ…お前は超能力者か?」
「違いますよ」
「分かってるよ。調べたのか?」
無言になる志穂。僕は微かに口の端を持ち上げ「分かってるんだ。もう四年たったし、忘れた方が良いんだって事ぐらい。でもさ…」遮るように「ごめんなさい!」と志穂は頭を下げた。
「え? 何が?」
「あの事故起こしたの、私の兄なんです」
それを聞いて僕は一瞬志穂を睨み、怯える志穂は視線を反らせた。
「ごめん…。そっか、志穂の…」
「本当にごめんなさい…」
「志穂に謝れても…」
「でも…あの日兄はッ」
「もういいって…」
「不眠の中それでもトラックに乗らなきゃいけなくてッ」
「もういいって言ってんだろ! もういいんだ…頼むからやめてくれ、聞きたくないんだ…」
俯き僕は志穂に泣き顔を見られたくなくて手で覆った。
「本当にごめんなさい…」
呟き志穂は行ってしまった。
もし死後の世界があるなら僕は朝美に会えるだろうか…。
そんな事考えながら、涙でぼやけた視界の中、緑のフェンスに向かって歩いていた。
一歩、一歩、歩む足。
朝美に会えるんじゃないかと期待してる自分がそこにいた。
ねぇ、朝美今行くよ…。
突然ケータイが鳴り出し、僕は我に返り涙をぬぐい通話ボタンを押した。
「はい」
「円佳だけど」
「分かってるよ」
「和紀の部屋にピアス忘れて来ちゃった見たいなんだけど捨てずに取って置いてね」
「捨てないよ」
病院内のアナウンスだけが無情に聞こえて来た。
「…何かあった?」
「いや、たいした事じゃ無いよ」
「何?」
「…ちょっと屋上から飛び降りそびれた…」
「…」
再びアナウンスが鮮明に聞こえ出し無言の円佳に「聞いてる?」と言おうとすると「馬鹿じゃないの!」とスピーカーが音割れする程の音量で叫ばれ耳がキーンとなった。
「今どこ?」
「会社の屋上」
「直ぐ中に入りなさい!」
「大丈夫だって」
「良いから!」
強い口調で言われ、受話器から鼻を啜る音が聞こえ出し、僕は急いで弁当を畳み屋内に入った。
「中に入ったよ。大丈夫だから泣くなよ…」
「バカ…」
「ごめん…」
いつも円佳を泣かせてばかりだな…。
僕は屋上入口に通じる階段に座った。
ひんやりとしていて高ぶっていた感情が冷えて行った。
「ねぇ、何があったの?」
「会社の後輩に、朝美を死なせた人の妹がいた」
「そっか…」
「で、謝られた。謝られても朝美は死んだのに…って思ってたら急に朝美に会いたくなって…」
「うん」
「いつの間にか足がフェンスに向かってた。でも、もう大丈夫だから…」
「うん。分かった…」
そのあと言葉が続かなくなり僕は「そういえばピアスって何処に置いたか覚えてる?」と話題を変えると「うん、たぶんテーブルに置いたんだと思うけど」と円佳は話を合わせてくれた。
他愛もない話をして、気持ちを落ち着かせデスクに戻ろうと廊下を歩いていると自動販売機横の長椅子に座り俯く志穂を見つけ僕は隣に座った。
一瞥し僕だと認識した志穂は顔を上げ、口を開いた。
「あの…私…」
泣いたのだろうか、志穂の目が赤かった。
「さっきは悪かった。志穂が責任を感じる事じゃ無いよ」
「でも…」
「先輩に楯突く気か?」
僕は志穂の髪をクシャクシャッとした。
「何するんですかー」と手グシで直す志穂。
「俺は誰かを責めたい分けじゃないんだ。誰かを責めた所で朝美はかえって来ない分けだし、志穂が責任を感じる事じゃないよ。だから…いつもみたいに笑ってくれないかな…」
「うん…」
志穂はじっと潤んだ瞳でこちらを見つめ、ぎこちない笑みを作った。
「変な顔…」
「ヒドーイ」
「昼飯食べれた?」
「ううん」
「俺も」
言うと志穂は口の端を持ち上げた。
誰かを恨んだり、責めたい分けじゃない。
責めるとしたらあの時何も出来なかった自分だけ…。
* * *
アパートに帰り、部屋の鍵を開けるとリビングの明かりに照らされ玄関に円佳の靴を見つけた。
ん? あぁ…。
今朝、僕は円佳に合鍵を渡して先に出社し、円佳に鍵を預けた事を思い出した。
やっぱり来たんだ…。
中に入ると、膝を抱えた円佳がベッドに座っていた。
「ただいま…」
「バカじゃないの…」
じっと僕を見つめる円佳の瞳が潤み出した。
「大丈夫だって言ったろ…悪かったよ…」
僕は円佳を抱きしめた。
「もうしないから…」
「絶対?」
「ん…たぶん」
「たぶんって何よ!」
ムッとした円佳は僕の腕を振りほどき立ち上がると微かに笑み、言った。
「顔見て安心したから帰るね」
「え?」
「新米ドクターは大変なんだよ。カルテは書かなきゃいけないし、雑務はあるし、和紀の事ばかり構ってなんていられないんだらかね!」
「そっか…。いつも心配ばかりかけて、ごめんなさい」
「うん…」
「今度電話するよ」
「うん、じゃ…」
円佳の後ろ姿を見送った。
7 数日後
数日後、僕は朝美が好きだった桔梗の花束を持って墓参りに行く事にした。
そこは墓しかない、静かな場所だった。
墓は墓、ただそれだけの存在のはずなのに『朝美』と彫られた文字を見て、急に泣けて来た。
墓石に語りかけても返事なんて返って来ないと知ってるのに、それでも話しかけて居た。
少しは朝美が死んだ事を受け入れられたのかな…。
僕の苦しかった気持ちが少しだけ軽くなった気がした。
帰り道僕はケータイの通話ボタンを押した…。
※ この話には2つのエンディングがあります。お好きな方を読んでください。
・『円佳』に電話した場合→ Aへ
・『志穂』に電話した場合→ Bへ
エンディングA :円佳
「はい…」
円佳に電話をすると、もれなく病院のアナウンスが聞こえて来る。
「俺、和紀だけど…」
「うん。どうしたの?」
「今時間ある?」
「んー。良いよ。手短になら」
「あのさ、俺の事好き?」
「…うん」
「こんな俺でも好き?」
「…うん」
「さっき朝美の墓参り行って来た」
「そう…」
「今直ぐは朝美の腕時計外せないかもしれないけど、それでも良いなら俺と、付き合って下さい…」
「…自分勝手、自己中、最低…」
罵りながら受話器から鼻を啜る音が耳に響いて来た。
「分かってる。それでも円佳にそばにいて欲しいんだ…」
「バカ…」
「朝美にはもう伝えて来たんだ。円佳が好きになったって」
「バーカ、朝美、実はすごいやきもちやきなんだよ。そんな事言ったら朝美怒るじゃん」
「良いよ。それでも円佳が好きだって伝えるから…」
「バーカ…」
受話器から伝わる円佳の鼻を啜る音をどうやったら止められるんだろう…。
今はそんな事で頭がいっぱいだった…。
- end -
エンディングB :志穂
墓参りの帰り道、僕はずっと気になっていた事を確かめる為に志穂に電話をすることにした。
「はい…」
「今大丈夫?」
「うん。大丈夫…」
少しだけ声が暗い気がした。
「ここ何日か会社休んでるけど、カゼだって?」
「うん」
「大丈夫?」
「うん…」
「もし、俺と顔合わせずらいなら…」
「そんなんじゃないんです。本当にただのカゼで…」
「そっか。で、いつデートする?」
「え?」
「だからドライブ連れて行ってくれるんだろう?」
「唐突すぎません?」
「そうかな…」
「何かあったんですか?」
「うん…。初めて…朝美の墓参りに行って来た」
「初めて?」
「うん、初めて…。何も無くて静かで朝美らしいなって思って、で、気になる娘がいるって伝えて来た。会社の後輩で、朝美を死なせた人の妹だって。まぁ、墓石に喋りかけたって返事なんて返って来ないのに、どうして喋り掛けるんだろうな…」
「どうしてかな…」
「志穂が俺の事どう思ってるか分からないけど、俺は志穂が好きだよ」
「私が好き? 冗談ですか? 私は滝さんが好きだった人を…」
「あのさ、前も言ったと思うけど志穂が悪い分けじゃ無いし、もし俺の心の何処かで志穂の事も憎んでるとしても、好きだから許せるって事もあると思うんだ…」
電話の向こうで鼻をすする音が聞こえて来た。
「いや、あるだろ。好きでやめられない事って、例えば性癖とか」
「私と性癖を一緒にしないで下さい!」
「そうそう、いつもの志穂だ。…俺志穂のそういう所が好きだよ」
「そういう所って言われても分からないけど、私も滝さんが好きです。ずっと、ずっと好きでした」と震える声で返って来た。
「うん。知ってた」
「もー滝さんのそういう所が、嫌いです」と志穂は皮肉った。
- end -
それでも、僕が外せない腕時計


