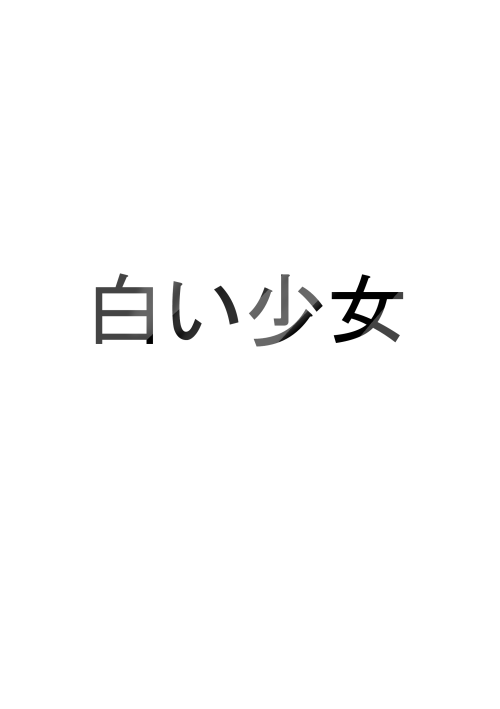
白い少女
始めまして、五月と申します。
星空文庫に作品を投稿するのは始めてになります。
数年前に書いた作品で、なんとも拙い作品ではありますが、読んでもらえれば幸いです。
白い少女
いつものように暇を持て余している最中だった。
ふと通りかかった自然公園。
枯れ木が道にそって等間隔に立ち並び、その枯れ木の直ぐ傍にあるベンチに一人の少女が座っていた。
彼女はぽつんと取りとめもなくそこにいるように思えた。
暇を持て余した同士だとでも思ってしまったのか。
他にもベンチは沢山あったのに、俺はわざわざ少女が使っているそのベンチに足を運んだ。
平然と近寄って、すとんと腰を下ろす。
彼女はそんな俺を見て、なんだろうとこちらに顔を向けるんだと思った。
だが彼女は俺に見向きもせず、それどころかどこを見ているのか分からない瞳で顔を前に向けたままだった。
興味があるのは、俺だけのようだ。
俺は木枯らしが吹くその公園で、しばらく少女の隣に座っていた。
少女もそこを動く様子は見せず、俺達の事を奇妙に思いつつ通りすぎる人や俺達など視界にないし、どうでもいいと自分の道だけを進む人々を一日中見送った。
寂しい青を広げていた空も、次第に朱色に変わり、大地を赤く染めた。
これだけ時間が経っても少女は俺に見向きもしない。
少女は俺に気づいていないのではなく、気づいていて、どうでもいいのだろう。
空気が肌寒いから、寒いに変わった。
マフラーをするには少し早いのかもしれないが、俺は首にそれがぐるぐる巻きだった。
そんな俺がいつまでも動かずにこの寒空の下ベンチに座っていたのだ。
体はとうに凍えていた。
隣の少女をちらりと見る。
この少女も俺より先にここにいて、全く動いていない。瞬きはしているので、死んでいる訳ではないようだ。
こげ茶色のコートを着て、赤いびらびらしたスカートを穿いて、薄茶色のブーツを履いていて。
けれど、存在は白い。
雪のように次第に消えてなくなるのではないかと。
そんな事を考えた。
話しかけてみようかとも思った。
けれど、隣でこうして会話はないけれどお互いの存在は確信しているこの状態が心地よいものに思えて。
声をかけるのをやめた。
夕日が沈み始めると、俺はすくっとベンチから立ち上がる。
まだ動きそうにない少女を残し、その場を去った。
奇妙な体験はしたけれど、今日も良い歌詞は浮かんでこなかった。
メロディも浮かばない。
今日いた公園は木枯らしが音楽に聞こえ、落ち葉が囁いているように感じる場所だったがこちらがそれに満足していた。
そうじゃない。
俺は自分の思いとメロディを伝えたい側だった。
でも、人の思いに届く歌を作るのは難しい。
素直に思いを書いて、それを歌って。皆に認められている音楽家が羨ましい。
俺は黒い手袋をしている自分の両手を見つめた。
この両手には、まだ何もない。
気分転換にと普段行かない道を通り、あの公園を見つけた。
知らない景色を見るのは好きだった。
自分の世界が広がる気がするし、知らない景色を知るという事がとても楽しい事だった。
そんな事を考えながら帰り道を歩き、普段より遅く家に帰宅した。
誰もいない家の扉を開けて、壁にあるスイッチを押して電気をつける。そして玄関から真っ直ぐ進んだ所にある自分の部屋に入ると、窓際にぽつんと存在するギターが真っ先に目に入った。
自分の音を奏でることのないギター。
「お前は、俺に買われて不幸だったかな」
翌日。
俺はまたも暇を持て余して外を歩いていた。
以前なら目的地はなかった。
ただなんとなくそこらへんを歩き回って日が暮れた頃には家に帰宅する。そんな毎日だった。
歩いていれば自然と詩が浮かぶだろうかとこの日課を始めて何年になるだろう。
思いついたものを綴っても。自分の好きなメロディで歌っても。
それを認めてくれる人はいなかった。
在り来たりなのか。詩が共感できないのか。俺の歌声が駄目なのか。原因はなんだろう。
すべてだろうか。
そんな事を考えても無駄で、次第にそれを考えるのはやめにした。
そうしていると、ふと歌詞が浮かばなくなった。
メロディも刻めなくなり俺の声は歌を歌うことをやめてしまった。
こうなるまではどんなくだらない歌詞もメロディも頭に自然と浮かんできたのに。
今では全くその姿を見せない。
だからこうして暇を潰しに、またこの自然公園へとやって来た。
昨日と同じように公園内の一本道を通って、あのベンチを目指した。
あの少女がいるかはもちろん分からない。
ただ、いて欲しいと思う自分がいる事にこの頃はまだ気づいていなかった。
ベンチに辿りつくと、少女はぽつんと膝を折ってベンチに座っていた。
今日はスカートではなくズボンだった。
コートとブーツは健在のようだ。
今日もまた平然と俺は彼女の隣に座る。
すると、昨日は見向きもしなかった少女が俺の瞳を覗いてきた。
「え・・・・・・」
昨日のように無視なのだろうと思っていた俺は思わず声を洩らす。
「・・・・・・昨日も来てたね」
じきに発せられたのは、そんな言葉。
か細い声だった。
「・・・・・・やっぱり、気づいてた」
心の底でほっとしている自分がいて、首を傾げた。
俺の心境とは裏腹に、少女は俺の顔を見上げながら言葉を続ける。
「最初は誰かが来たって思って、でも知らない人だったから話しかけようか迷って。あなたも話しかけて来なかったからいいかなって」
「…………まあ、うん」
話しかけるのを躊躇していたということか。
「今日も来たから、今度は話しかけて見ようと思って」
「知らない人に変わりはないけどな」
俺が無意識にそう言うと、彼女は首を傾げた。
「昨日見てるから、知らない人じゃないよ?」
「…………」
そういう基準なのか。
その少女は、存在が白い。
これは勝手な俺のイメージで。
ただ、心が真っ白で綺麗なような気がしてた。
話してみると、イメージと違い無口という訳ではなく、むしろよく喋る子だった。
「この季節になると、わたしよくここに来るの」
「ふぅん……」
俺は少女の話に耳は傾けていたが、あまりよい返事が浮かばず適当に返していた。
それでも少女はただ聞いてくれていればいいのか俺の相槌など構わず話を進める。
彼女は数年前までこの公園に毎日通っていたらしい。
けれどある事を切欠に「毎日」ではなくなった。
それは単に、引越しをしてこの公園から家が離れてしまったからだそうだ。
こっちでの友達とも遊ぶ事はなくなり、新しい生活が始まった。
その変化を、彼女は望まなかった。
「わたし、知らない景色を見るのは好きだけど、この公園は大好きだったの」
友達も変わって欲しい訳ではなかったし、このままでいいとさえ思っていた。
「そこに住み続ければ、そこは「知らない景色」じゃなくなるわ。そして、時が経ってこの公園のほうが知らない景色になるのよ」
それが嫌で、この季節にだけは毎年通い始めるらしい。
どうしてこの季節なのかと俺は尋ねた。
「今の季節のこの公園が、一番好きだから」
その答えは、意外だった。
枯れ葉が舞い、木々が枯れてしまっているこの物悲しい季節のこの公園が一番好きだと言うのだから。
普通だったら春とか夏とか緑が生い茂る季節のほうが清々しいし、好きな人が多いんじゃないかと思う。彼女はその逆だった。
「どうしてこの季節の公園が一番好きなんだ? 殺風景なのに」
「引っ越ししたのが、この季節だから」
毎日通っていた公園。
それは日常にある当然で、ここに通えなくなる日が来るとは思っていなかったから引っ越しすると分かってからここが大切だった事に気がついた。
「分かってくれなくていいよ。人からすれば、わたしの大切なものなんてくだらないもの」
「別に、くだらないなんて思ってない」
俺の大切が、人によっては価値のないものだったように。
それは誰だって抱く「どうでもいい」という感情であり。
そう言われると辛いけど、それを否定する権利は自分にはない事を俺も彼女も知っていた。
「でも、引越ししたのがこの季節ならそれは、辛くないか……?」
引っ越しした事をやはり後悔するのではないだろうか。
こうして通うほど、ここが好きだと言うのだから。
「最初はちょっと寂しかったけど、今ではそうでもない。むしろ、ここに来れる事がうれしいの」
そう微笑んで言う彼女は、本当に白かった。
「あなたは?」
「ん?」
自分の話がある程度終わると、彼女は俺をじっと見つめて訪ねてきた。
「あなたはどうしてここに来たの?」
「――……。迷って」
「迷子……?」
「違う」
普通はそっちに行くか。
俺は軽くため息をついた後、重い口を開いた。
「……ギターが好きなんだ。でも、もうこの手はその音を奏でられない」
「どうして?」
彼女の無垢な瞳は、話したくない過去でさえも、話したくなるほど透明で綺麗だった。
「……辛かったんだ。認められない事が。それで、気づいたら歌を創れなくなってた。歌詞もメロディも浮かばない。歌おうとする声さえもでない」
正直、諦めていた。
自分には無理なんだと。
結局、これが自分の限界で実力なのだと。
「どうにもならない事って、あるだろ? お前も、引っ越しを止める事なんてできなかった」
彼女はそれを認めるように黙った。
そしてしばらくすると、
「難しい事は分からないわ。……でも、あなたはそれでいいの?」
「――――」
そう言われて、声が詰まった。
諦めていた。
自分にはもう歌は創れない。
これが自分の限界で実力。
そう思うしかなかったから。
今更、そんな言葉。
「わたしは、引っ越しは止められなかったけど、嫌だから。ここに来れなくなるのは嫌だから、今こうして来てるの」
凛とした声で少女は言う。
その瞳は「あなたは?」と問うていた。
――俺は?
「俺は……」
息が詰まる。
……いや。
もっと前から詰まってたんだ。
歌うのをやめた時から、俺の時間は止まっていた。
隣を見ると、一人の少女は微笑んでいた。
「わたしはここにいたいからここに来たの。あなたも、歌いたいなら歌えばいいんだよ」
その言葉を、俺は待っていたのだろうか。
認められないという事は必要とされていない事で。
誰も、俺の歌など求めていないんだと、そう思おうとしていた。
ただ、逃げていただけなんだ。
「単純な事だ……そうだよ。歌いたいなら、歌えばいいんだ」
そう呟く俺に、少女はもう一度笑顔をくれた。
それは、この殺風景な公園をどこまでも美しく見せていた。
あれから、季節は変わった。
あの自然公園にいた彼女は、もういない。
「あれ? あそこで誰か歌ってる」
「私、あの人テレビで見た事あるよ? ここ数年全然見なかったけど」
木枯らしは去って、木々は緑に体を覆う。
空は暖かな青を広げ、白い雲は泳ぐように流れる。
季節は変わった。
彼女はもういない。
けれど俺はここで歌おう。
彼女がまた来るその日、こうしてここで出会えるように。
白い少女
『白い少女』、読んで下さりありがとうございました。


