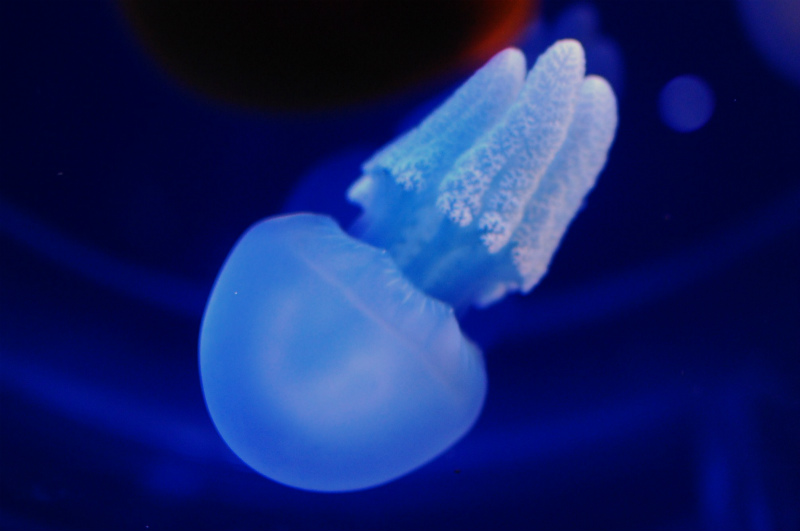
神様の質量
SCENE 1
左手と右手を交互に見る。右手を動かそうと試みるが指一本動かせない。このままぶくぶくと沈んでいくのだろうか、体中の血という血が地面に流れ出している感覚がする。地面が徐々に生暖かい生を獲得し、自分の身体は鉛のように重たく冷たくなっていくように感じた。そんな中でも左手だけが、唯一、人間らしい温かさを残していた。それが人間的な温かみの域にあるのか、それとも左手以外が氷点下の域に達しているから相対的にあたたかいのか、判別はつかなかった。分かっているのはまずこれだけだった。右手もそうやって温かくしたい。必死で動かそうとする。どうやって身体が動いているのかよくわからなくなっていた。自分自身の筋肉を曲げ伸ばそうとしても、太い金属でできたバネのように、固く縮んだままだった。うでの筋肉のどれもが使い物になってない。せめて顔ぐらいは動かそうとしてみる。動かない。身体はどうやらもう固まってしまったらしい。もはや残されているのは見ることだけだったが、それも視界がだんだん古いテレビの砂嵐のようになってきた。そしてそのまま暗く暗く沈んでいく。自分に体はあっただろうか。さっきまでいったい何をしていたのだろうか。全部忘れてしまった。
SCENE 0 + 2
夢から覚めたかのように、ふいに自分の意識が鮮明になった。
ずいぶんと気の遠くなるような時間が過ぎた気がする。僕は土手に座り込んで、なんだか少し早く感じる雲の流れをぼんやりと眺めていた。もこもこと内側から外側へ潜り出てくる入道雲は、まるでひとつの生物であるかのようにうねうねと西から東へのたうっていた。それはまるで早回しのビデオを見ているみたいだった。座り込んでいる土手に生えた草花の匂いが忘れた頃に主張してくる。早回しに時が流れたら、このにおいはどんな風に感じるのだろうか、そんなことをぼんやりと思っていた。
「ここにおったんや。ちょっとだけ探したよ」
麦わら帽子をかぶった女の子が、少しだけ息を切らして僕の後ろに立っていた。手にはペットボトルを二本、小さな手で危なげにもっている。麦茶だろうか、ラベルは剥がされていて、中の茶色の液体が揺れるたび太陽をキラキラと散らしていた。彼女は僕の隣に座り込むと、もっていたペットボトルのもう一本を僕に渡してきた。それを当たり前のように受けとって、口いっぱいに麦茶を含む。口から食道へとくだっていく冷たい感覚がなんとも心地よく、自分が思っていたより喉が乾いていたことに気付き、あまりにも今更ながら今の季節が夏だということを思い出した。
「もう隅のは全部刈り終わったし、あとはおじいちゃんに任せたらええね」
「うん、ちぃと間はお休みや」
彼女の一言で今まで自分が何をしていたのかを思い出した。今日は稲刈りを一家総出でやっていたんだ。とはいえ、歴史の教科書で出てくるような昔のように全てを手作業でやらなくちゃいけないというわけじゃない。僕達が手作業で刈り取るのは機械が入らない田んぼの角や小さな隙間になっているところだけだ。残りのほとんどは機械がやってくれる。大きな牛のような稲刈り機が、お米をたくさんつけてしなだれている稲をバクバクと食べつくす光景を今まで何度も見てきた。おじいは僕が中学校に行くようになったら操縦させると言っていた。大きなエンジン音をたてながら動きまわるアレを、自分が動かすんだと思うと、少しだけ憧れた。
土手の向こうの、僕の家の田んぼでは、おじいとおとうが、稲刈り機を使って次々と田んぼを丸裸にしていた。その様子をおかあが見守っている。おかあの足元に敷いてあるビニールシートにはおにぎりやペットボトルに入ったお茶がいっぱい置かれていた。
「ねえ、ハル、お宮さんに涼みにいかへん?」
彼女はなぜか恥ずかしそうにはにかみながら、僕の手を握った。どちらの手も土に汚れて綺麗とは言いがたい。普段土を触ってないもんだから手も少し荒れていた。かさかさとした感触と、彼女の手の温かさが、なんだかちぐはぐな感じだった。僕は軽くうなづいて、引っ張る彼女の手におとなしくついていった。
今おじいたちがいる田んぼのすぐ近くに神社がある。普段はお宮さんと言っていて、新年のお参りや、お祭りの時など、行事があるごとに部落で集まっている。特に近づかないようにと言われたことはないけど、神社で遊んだりしたことはなかった。
彼女の手に引かれるがままに、僕は田んぼを両脇に抱えた土手を登っていく。おかあがこっちの様子に気づいて、あんまり遠くいったらあかんよ、と口元に両手を添えて大きな声を出している。それに僕と彼女でうなづきながら、神社の石段まで歩いて行く。といっても土手を登れば道路を挟んですぐそこにある。いくらもしないうちに石段にまでたどり着いた。
石段を登ろうとすると、彼女は足を止め、僕と向かい合うようにしてお宮さんに背を向けた。
「どうしたん、お宮さんのぼらんの」
「ねえ、ハル。おじいちゃんからお宮さんに住んどる神様の話聞いたことある?」
「ううん、ない」
「うそー。それやったらウチが教えたげるわ」
僕とおじいはそれほど話をしなかったし、だいたいうちの家族はみんな寡黙で用事があるとき以外はめったに会話をしなかった。晩ご飯を食べるときもおかあと僕だけしかほとんどしゃべってない。二人だけがおしゃべりのように思っていたけど、近所の人と比べたら僕もおかあもあまりしゃべる方じゃない。
だから、おじいから神社の話なんて聞いたことがなかった。あれこれ考えているうちに彼女が喋り始めた。
「ここの神さんはな、生まれつき目が見えへん人やったんやて。知ってた?」
「ううん、知らんかった」
「そんでな……今からハルに質問するね」
「うん」
彼女はぶっきらぼうに会話を切り出すので、僕もおとなしく彼女の問いにそなえる。
「目の見えないここの神さんは、お参りに来た人たちをどうやって知ってると思う?」
神様だったらどんなことでも知ってるんじゃないの、という考えが浮かんだけれど、それは彼女が望む答えじゃないと思い、まじめに考えてみる。
「ええと、話し声とか?」
「それやったらあんたみたいに無口なんはどないするん」
「確かにそうやね。そんで正解は?」
そう言うと彼女は眉を寄せながらフウ、とため息をついた。
「諦め早いなー、もっと考えなあかんよ」
「ごめん」
「謝らんでもええけど……まあ引き伸ばしてもしゃあないか」
そういうと彼女は、少しだけ飛び跳ねて地面を踏んづけた。小石や土がこすれ合ってジャリジャリという音がした。
「足音や。右足、つぎは左足って感じで、石段を登る音でここの神さんはお参りに来る人を聞き分けてるんよ。ここの石段って白い石がいっぱい敷いてあって登ってるとすごいうるさいやろ。これは音を出してお参りにきましたよーってむこうに教えたげるためなんやって」
確かに神社の石段には大きく切り取った石の上に砂利石が敷いてあり、踏むとジャリジャリと大きな音がする。小さな頃はわざと踏んで遊んでいたりしたけど、その理由について深く考えたりしたことはなかった。
「そんなこと全然知らんかった」
「ウチなんかおばあちゃんに何回も聞かされたのに、『神様に来ましたよって知らせてあげなさい』って。たぶんハルだってお参りするとき片足でケンケンしたらあかんって言われてると思うよ」
「そうだったかな。まあうち、家族であんまり話さへんから」
「ふーん、まあそれはええよ。そんでな、今日はハルに一緒にやってほしいことがあってここに誘ったんよ」
そういって少し恥ずかしそうにする。その仕草の理由がわからず少し不思議に思った。
「うん、何?」
「……今からやるおまじないを、一緒にやってほしいんよ」
そういって彼女は少しだけ深く息を吸った。
「さっきお参りするとき神様は足音で聞き分けてるって言ったやろ? あれはな、正確に言うと右足の音、左足の音を交互に鳴らすことで一人の人間として認めてもらってるんよ」
「右足、左足でひとりの人間?」
「そう。そんでな、こっから先はウチが考えたおまじないなんやけど」
「うん」
「ウチとハルで、それぞれ違う足でケンケンするんよ。それで、そのまんまお宮さんの鳥居をくぐって、お参りするんよ」
「え、でも……それってあかんのんじゃないん?」
「ううん、これは、ずっと一緒にいるっていうおまじないなんよ。だから全然悪いことなんかじゃないよ」
彼女の話し方は、少し焦っていたように感じた。
「例えば、ウチが左足、ハルが右足で立って、そのまま鳥居くぐるやろ、そしたら、神様はウチら二人を『ひとつの魂』として認めてくれるんよ。そしたら、どんなに離れ離れでも、魂がひとつなんやから、ずっと一緒。そうやろ?」
「でも、途中で足ついたらどないするん?」
「そん時は、一緒にごめんなさいって神様に謝ろ」
「謝るって、そんな簡単に言わんといてな」
「……」
彼女は、そのあと少しだけ地面を眺めて、静かな間をひとつ空けた。
「……ハル、これ、全然ふざけてやるつもりじゃないんよ」
「どういうこと?」
「ウチらもう中学校三年生やんか? そろそろ、高校に行くかとか、ちゃんと決めなあかんやん。ハルは、頭いいから他所の偏差値高い高校行くつもりなんやろ?」
「うん、一応そのつもりやけど……」
「ウチな、ハルとずっと一緒におりたいんよ。まだ将来のことなんも考えてへんし、ハルが行きたいって言ってる高校にウチも行きたい。でもな、ウチ阿呆やからもしかしたら頑張っても無理かもしれへん。やから、神様にちょっと助けてもらうんよ」
「だから、ずっと一緒にいるおまじない?」
「うん、あかんかな……?」
僕は彼女の想いについて、単純に嬉しく思っていた。生まれてから今までの間、ずっと一緒だった僕達は、今でも十分深い絆で結ばれていると思う。でも、このおまじないで彼女の不安が少しでも軽くなるのだとしたら、拒む理由なんてこれっぽっちもない。神様も、これくらいのいたずら、許してくれるに違いない。
僕は少しだけ、空を見る。さっきまでせわしなく動いていた雲が、ゆっくりと漂うように、見えた。
「ええよ」
彼女は、これ以上ない笑顔を僕に向けた。
僕たちは手をつないで、少しずつ石段を登っていく。一段上がるごとにけっこうな体力を使う。夏の暑さがまだまだ抜け切らない初秋、汗もだんだんと染みてきた。手についていた土が汗に溶けて泥になる。せめて手を洗ってくればよかった。そう謝ると彼女は笑って、私も一緒だからと一歩飛び跳ねて石段を登った。子供一人分の体重がのった片足は、石段の砂利を力強く踏みつけ、バチバチと弾けるような音を周囲に響かせた。
僕はこの時間がずいぶんと長く感じられた。いつもは何気なく上がってしまう石段も、やたらと大きく見えた。一心不乱に石段をひとつひとつ登っていく。途中に生えているコヤスノキにもたれかかって休憩し、お互いに励まし合いながら一段一段登っていく。僕は一段登るごとに掛け声をだしている彼女の姿を横目で見ながら、手を握っている左手を少しだけ強めて、こんな時間がこの先ずっと続けばいいと強く願った。
SCENE 2.1
ガコン、ゴトンと単調で無機質な音がたくさんの人を西へと運んでいる。スーツを来た人、親子連れ、僕と同じように大きなリュックを膝に置いて座っている人、重たそうに背負ったまま立ち続けている人。
それぞれに違った目的地があり、それぞれに違ったやりたいこと、しなければならないことがある。特に急ぐ必要もなく、本を読んだり、音楽を聴いたり、何もせずぼーっとしたりしている人や、もっと早く走れと言わんばかりに時計をチラチラと覗いている人もいる。それでもこの電車は、誰をえこひいきするわけでもなく、無数に走るダイヤラインの一本に几帳面に沿わせながら、皆をつかの間の運命共同体ように扱い、一緒に平等に運んでいく。
僕は同じ車両の人たちを眺めるのをやめ、読もうとして開いたまま膝に伏せていた小説に目をやった。ついでに腕に巻かれている腕時計にも目をやる。午後一時。下宿をしている京都を離れもう二時間も経っている。
ずいぶんと希薄な記憶が僕の二時間を埋めていた。特に急ぎの用でこの電車に乗っているわけじゃない。ただぼんやりと無為に風景を眺め続けることに、心の中の何者も咎めることはなかった。
そういえば、大学一回生だった頃は、こんな風に電車に揺られながら優雅に読書をするだなんてことはできなかった。というのも、数年前までこの路線を走っていたのはいつから走っているのかも分からないほど色あせた橙色の古い車両だったので、常にガタガタと強く揺れていた。昨年の年末に実家に帰ろうとしたときに乗った車両がその電車の最後の運転だったらしく停車駅ごとに並んだ多くのカメラにその姿を収められながら、ガタガタとゆっくりとしたスピードでその役目を終えた。
今では車両は一新され、ダイヤが少し早くなったし、揺れも気になるほどではなくなった。とはいえ田舎であることにかわりなく、相変わらず一両か二両編成で走らせているのであった。
そんなわけで快適に読書ができるようになったので、京都から帰省する際にはこうして本を読みながら時間を潰すこともできる。けれども、以前の車両に乗った時に感じていた「僕は生まれ故郷に帰ってきたんだ」という感覚は少し希釈されたような気がした。
距離としてはさほど離れてはいない実家と京都市ではあるけれど、ローカル線を乗り継いでの帰路は片道四時間もかかるため、あまり気軽に帰れるといった感じではなく、今回のようにお盆時か、年末年始ぐらいにしか帰ろうという気にはならない。
そういったわけで年に二回ほどしか実家には帰っていない。そうやって大きな間隔を空けて故郷を見ると、田舎とはいえ変化があるのだということに気付く。昼間の商店街の無機質に地面に伸びるシャッターが今までよりも増えていたり、子供の頃遊んでいた山が切り崩されて赤茶色の地面がむき出しになっていたり、近所の田んぼに稲ではなくコスモスの苗が植えられていたり(なんでも、村おこしの一貫として使われていない田んぼをコスモス畑にしているのだそうだ)、どれも他人から見ればささいな変化だけれど、そのささいな(僕にとっては大きな)違いは、慣れ親しんだかつての景色に知らないものが紛れ込んでいる妙な違和感を感じさせた。
そういった一連の思いを馳せる度に、うまく説明できないぐらい自分でもよくわかっていないことだけれど、僕は忘れ物をしてしまったような感覚に陥る。
なくなっていくのは決して僕のせいではない。たとえ良い解釈で言えばスローライフと呼ばれる、めまぐるしい技術発展から見放されてしまった田舎といえど、時の流れによる変化にはどうしても抗えない。近所に立つ巨大なスーパーを、みんな便利がって利用するから、商店街は太刀打ち出来ず目を塞ぐようにして鉄のカーテンを店の前に引き下ろす。そんな摂理のような力関係が否が応でもかつて見た景色を変えていく。
でも、心はそうは思っておらず、この「かつての消滅」とも言える変化に、まるで自分が直接関わっているかのような感じ方をしてしまう。というのも、「かつての景色を忘れている」ということをはっきりと自覚してしまうからだ。目に見えていないと、耳に聞こえていないと僕は、思い出せても「なくなったそれ自体」を思うことはできない。中学生の時に頻繁に出入りしたあの店のシャッターの向こう側が、どんなであったか正確に描くことはできない。確かに僕は「かつて」を忘れてしまっているのだ。実家に帰ってきてそう感じるたび、それを悲しく思う。そしてその悲しさも、次に帰ってくるときには多分忘れてしまっている。
そうやってわずかな悲しみをぷちぷちとつぶしながら、僕の故郷はいつの間にやらすっかりかたちを変えてしまうんだろう。
電車の窓を次から次へスライドしていく景色をぼんやりと眺めながら、そんなことを考えていた。
SCENE 1.50≒3.? ( or1.50+3.?)
僕はまだ、電車に乗っていた。
無理もない、京都から僕の実家まで、鈍行で3時間以上もかかるのだ。少し居眠りをした程度で、過ぎ去ってくれるほどの短さではない。それでも、帰宅ラッシュを避けるために日が沈む前に乗った車両の外を見てみると、赤い日差しも消えようとしている。乗客も、沈む太陽を追いかけるように頭を垂れてつかれた顔をしている。僕はせっかく眠りから覚めたのだからと、今どのあたりなのかを確かめようとする。しばらくして車内アナウンスが流れる。もう兵庫県に入っているらしい。何十回、何百回と言ってきたことがよくわかる、感情の削げ落ちた声が電車の乗り継ぎについてぼそぼそと伝えている。この駅で降りるであろう人たちが、スーツケースや小さなバックを持って入り口に集まっていく。僕の隣に座り込んでいた男の人も、せわしなく身支度をして立ち上がろうとしてた。速度を緩め続けていた電車が鋭い金属的な悲鳴をあげながらゆっくりと停車した。ドアが開くのと同時に、何かに背中を押されているかのようにして人々が飛び出していく。隣の男もいつの間にかいなくなっている。この新快速の座席は、2席セットで進行方向を向くタイプであり、僕は窓際に座っていた。もちろん通路側には空席ができている。とはいいながらも日も落ちようとしている今はかなり混雑する時間帯であり、わずかでも足を休める時間を獲得しようと、新たに乗り込む人、あるいはさっきからずっと立っていた人がすぐにでもこの空席を埋めてしまうに違いない。
けれども、ホーム側だけいっせいに開かれていたドアが閉まり、次の駅へと人を運ぶためにゆっくり発進しはじめた今にいたっても、僕の隣には誰も座らず、まるでもう席は全て埋まってしまったかのように、周囲の人間は疲れた顔をしてつり革にぶら下がっていた。
ふいに、妙な罪悪感に襲われる。自分の席だけ空いていて、誰も座らないというのは、心当たりがまったくなくとも自分に原因があるのではないかと思われて仕方がない。しかしながらいくら現状を確かめてみても、自分に何かしらの落ち度があるとは思えない。だから他の原因があるのかもしれない。それでも、「自分の隣だけ埋まらない」というこの状況に、どうしても自分が関与しているようにしか思えないほどには、自意識が強く僕に訴えかけていて、いくら考えても答えがでないので、座らないのならば仕方ないと自分を必死に説得し、目の前の状況から逃げるように眼を閉じ再び眠ることに専念しようとした。
「あの、すいません、ちょっといいですか」
とても近い距離で声がした。自分では無いかもしれないが、とりあえず声のした方に眼を開けながら顔を向ける。
女性が、僕の隣の席に座っていた。そして、その顔は僕の方を向いており、向かい合うように互いに互いの顔を見ていた。ということは「この声の発し手」は間違いなく自分を受け取り手として見ているはずで、僕はそれに応える責任があるはずだった。恐る恐る反応を返した。
「えっと、なんでしょうか?」
「お願いがあるんです」
間髪入れない応答だった。相手の女性は学生だろうか、少なくとも大学生である自分よりは若くみえる。しかし働いていると言われても違和感はない程度の年齢だとは思う。理系大学の宿命とはいえ、普段からあまり女性と接触のない生活を送っている自分には、このような近距離で女性に見つめられることはかなりの緊張だった。それでもこれだけまっすぐに見られてはっきりと物申されている以上、こちらも誠実にものを返さなくてはならない。そんな気がする。頭皮からじとりとした汗が湧き出る感触がする。なぜだか「慎重になれ、慎重に」と心の中で繰り返しながら、恐る恐る会話を開始した。
「なんでしょうか、もしかして、僕が知らないうちに何かご迷惑を…?」
「あ、違うんです。むしろ迷惑なのはこちらの方で、なんと説明していいやら。でも、どうしてもお願いしたくて」
「はあ、それでその、お願いというのはどういったものでしょうか」
「それはですね、えーと、あ、その前にちょっと聞きたいことがあるんです。今、三宮ですよね。あなたはこれからどちらまで行かれるんでしょうか?」
「え? あー、僕は姫路よりもっと西側に行きます。ですから、少なくとも終点である姫路駅までは乗りますよ」
「そうなんだ! あ、ごめんなさい。今のは失礼でしたね」
「いえいえお気になさらず。それで、ご用件というのは」
「簡潔に言います。姫路駅まで私と手をつないでいてください」
怒涛のやり取りだった。と思う。少なくとも僕の中では。考える余地があまりに短くて、言われるがままに答えてしまったが、あんまりにもこの女性は怪しい。人の行き先を聞いた上で、その間手をつなぐように要求してきた。その目的は全く検討がつかないが、なんだか詐欺まがいのことをされているような気になっていた。
「手、ですか……」
「なんか、変質者みたい、というか変質者ですよね、ごめんなさい。でも、他にどう言ったらいいのやら……」
「なにか、事情がおありなのですか?」
「事情という程のものではないのですが……」
そういいながら少しの間彼女はうつむき、やがて意を決したのか強い眼差しでこちらを見据えた上で、話し始めた。
「昔、死に別れてしまった恋人に、似ているんです」
「それは、僕が、ということですか?」
「そうです。あなたには迷惑でしかないことなんですが、あまりにもそっくりで、声をかけずにはいられなくて。でも、声をかけて、姿を見ただけでは、なんというか、あなたが恋人の幽霊のように見えてしまうから、別人だということを、確かめたかったんです。本当に、自分でもおかしな話だとおもいますし、意味の分からないことだともおもいます。でも、ここで行動しなくては、私はずっと今日のことを引きずり続けると思って、迷惑だと承知のうえで今あなたにお話しているのです」
「ちょっと待ってください。話はわかりました」
こちらが話し手になることで無理やり会話に間を挟み込む。そして少しの間考え、会話を続けた。
「あのですね、話を聞いていると、なんというか、少しばかり違和感というか、ひっかかるところがあって」
「……それはなんですか?」
「というのも、君は僕のことを亡くなられた恋人に似ていると言ってはいます。ですが、なんというか、君を前にして言い難いことですが、やっぱり僕は君の恋人ではなかったのです。それは、今までの記憶だとか、僕自身の確信だとか、そういったところでしかありませんが。それははっきりとしておきたくて」
「それはわかってます。でも、」
「それでも、君が手を繋ぎたい、話をしたいというのは、君が僕のことをその恋人に見立てているからでしょう。なんというか、きつい物言いになってしまいますが、僕自身ではない誰かのために、自分の身体を使われるというのは、なんとなく良い気分にはなれませんし、これは大きなお世話かもしれませんが、君のためにもよくないことじゃないかと」
「私がかつての思いを引きずっていて、あなたにすがろうとしている、ということは分かっているつもりです。ですが一応私も、恋人本人がまだ生きてるんじゃないかと思い込むことができない程度には現実的な心をもっているとおもいます。そして、あなたに触りたいと思うこの気持ちを解消することが、後で耐え難い空虚を招くことも知っています。あなたに対してすごく罪悪感も覚えます。それでも私は、そういった気持も含めて、あなたの隣に座って、お話したいと思ったのです。これもまた、勝手な話になりますが、自分のこういった気持ちに嘘はつけません」
「うーん、なんというか、僕もはっきりと言ってしまえば、君のような女性と話をしたり、触れたりすることに対して、不快感があるわけではないんです。むしろそれは下心としては喜ばしい部類に入るものでしょう。それでもなお、こうして抵抗感を示しているのは、僕の中の良識だったり、常識だったりする感覚が、『亡くなった方と似ている人とをかぶらせる』という行為は、する側、される側、どちらにとっても良いものではないと訴えてくるからです。なんというか、初対面の人にこんな説教腰に話すのは失礼だとは十分分かっているんですが、それでもこうして誠実に自分の気持ちを伝えてくださる方に対しては、素直に自分の考えを述べた方が良いと思って、こうして伝えているのです」
「あなたのおっしゃっていることはよく分かりますし、その通りだと私も思います。でもなんといいますか、理屈や理性でわかっていても、どうにもできない感情の部分というのがあって、それが私の中ではいっそう強くて、なんともしがたいといいますか……。ただ、間違いないと思えることは、今こうしてあなたとお話できて、良かったと思っているということです。やっぱりあなたは私の知っている彼ではなくて、他の誰かであって、もうしばらくお話していたら、なんとなく今まで引きずっていた気持ちとかも、すっきりしそうな気がして……。とにかく、今の私自身に後悔とかそういった感情はないということは確かです」
「うーん、そういった気持ちを理解できないというわけではないんですが……」
そのとき、彼女の口元が崩れるようにして緩み、重く沈んだ空気を無視するかのように彼女の吐息が軽やかに宙に舞った。笑っていたのだ。こらえきれずにふふ、と。
そんな様子を憮然と見ていた僕を見て、彼女は取り付くように口を走らせた。
「あ、ごめんなさい。これは、なんというか、あなたを馬鹿にして笑っているわけじゃないんです」
「え……ああ、はい」
生返事をした僕はその時、彼女が笑った理由について必死に考えていた。自分のこれまでの言動から、特にさきほどまでの会話の中から、強く関連していそうなものを探しだそうとしていた。当然の話だが、最初に見当がつかなかった時点で見つけることは困難で、だからこそ僕は思考の渦に巻き込まれ我を忘れた。
「なんというか、ちぐはぐですよね。さっきから私たちの会話。あなたは、ずっと正しいことを言ってくれてるのに、私が子供の駄々のようにそれを認めようとしなくて、なんか頭悪いですよね、私」
「うーん、そんなことは無いんじゃないでしょうか。むしろ、駄々をこねているのは私の方ですよ」
「え? それはどういうことですか?」
「だってほら、君は自分が手を繋ぎたいという気持ちを伝えてくれてるのに、僕はその気持を無視しようとしているんですから。ほんとは、気持ちや感情というのは、理由がなくて当然のものなんです。でも、僕の中ではどうしても理性がありのままを受け入れる、気持ちを疑いなく肯定するということが難しくて、必死で抗っているんです。それこそ、子供の駄々というものです。感情が正しいということは、覆せないことですから」
僕がそう言い終えたあと、彼女は眉間に皺を寄せたあと、申し訳無さそうな顔をしてこちらを見ていた。たぶん、僕の言葉がよくわからなかったのだろう。
「つまり、君は正しいということなんです」
僕は息を吐く。さっきからの会話でつかれてしまったのか、それとも安心してしまったのか。どちらにせよ、何かしらの緊張の糸が緩み、肩がだらりと下がったから、息がもれたのだ。
「じゃあ、手をつないでくれるんですね」
「まあ、姫路までまだ30分くらいありますから、その間に僕の疑問をなんとか解消したいと思います」
僕は右手を差し出した。
自分でいきなり切り出して、怒涛の勢いで説得していた彼女は、躊躇しながら僕の右手を左手で握った。
死んだ誰かに自分が似ているのだという。ドッペルゲンガーは出会うと死ぬんだったか。じゃあ、あの世で出会ったらどうなるんだと、あまりにも不謹慎なことを考えていた。その人と死に別れた女性とこうして横並びに手をつないでいるというのに。好奇心というものに、善悪の価値基準はない。面白いか面白くないか、まずそこから始まる。だから仕方ないじゃないか。そう思いながら僕は自分自身の思考をむやみに否定することなく、緊張して汗がにじみだした手を意識する。
「僕、汗っかきなんで不快だったらすぐ離してもらっていいですよ」
「その時は、ベビーパウダーを塗ってあげますよ」
彼女の目は僕を見据えていた。じっと見つめていた。そこに一体何を見ているのだろう。死んだ彼を見ているんだろうか、そこは避けられないだろう。それでも、少しぐらい僕自身を見てもらわないと寂しいと思った。初対面の相手で、恐らくはこの電車に乗っている間の関係であるはずなのに、僕はその先のことについて本能的に考えていた。人が社会的な動物である限り、こういった過剰な自意識はきっと拭い切ることはできないのだろうな。そう思いながら僕はようやくまともに隣の女性の顔を見た。綺麗な女性だと思った。
SCENE 0.99…≒1.0
窪みへと向かう僕の直進は、ゆっくりとしていて、だからこそ確実性を帯びていた。
この駅にこの新快速の車両は停車しない。各駅停車の電車を待つ人はまばらだった。多くはない。到着時間までには幾分かの余裕がある。少なくとも、もうすぐこの駅を過ぎ去る、新快速の車両をやり過ごす必要がある。
向かって左側から金属の擦れる鈍い音がする。その音がそれなりの速さでこちらに近づいている。しかし、その音には、そして音を響かせながら近づいてくるソレには、極力注意を向けないようにする。気が変わってしまわないように。人は窮地に立てば、なんにでもすがる。溺れたならば藁だってつかむし、藁がなければ飛沫だってつかむだろう。だから僕はその藁も飛沫も、ひいては自分が溺れゆこうとしていることすら、意に留めない。
ゆっくりと自分にせまる「窪み」を、2メートル足らずの距離を隔てた先にある暗がりを、ただじっと見つめ続ける。暗がりに吸い込まれてゆく自分をイメージする。向かおうという意識をなるべく持たず、ゆっくりと引き寄せられる。自らの歩みを自ら客観視していた。だからこそ焦りや恐怖はなく、ぼんやりとしたぬるい虚脱感を全身に積もらせながら点字ブロックの凹凸を踏み越えることが出来た。
右足を一歩踏み出す。地面の感触を、重力からの垂直効力を十分に感じる。もう一歩進めば、暗闇。僕は、左足を引きずるように前へ進めた。
当然のことながら、次の一歩を支える足場は用意されておらず、身体はより低い場所に落ち着こうと僕をせかした。ホームの椅子や気だるそうに携帯を見ながら暇を潰している人たちの顔がぐるんとゆらぎながら識別不可能な背景になる。線路に引かれたレールが首元を締めあげられたかのような悲鳴をあげながらこちらに接近している。その音をどこか遠くで聴いているような心地で、茶色く光る地面を見つめていた。
突然、がくん、と身体がこわばり、回転しながら消滅していた景色が鮮明になった。ホームの人たちはみな僕のことを凝視していた。時間が止まったかのように人の姿は変化せず、自分だけが時間の波に抵抗できないでいた。
続いて僕の身体は後ろ側に引っ張られ、ホームの地面にたたきつけられた。フードポケットに入れていた携帯電話が飛び出してしまい、回転しながら地面へとぶつかり、衝撃に耐えられず電池パックを吐き出していた。
自分の身にいったい何が起きたのか分からず、ただ石の冷たさを肌で感じながら少しずつ思考を取り戻そうとしていた。呼吸を整え、周囲を見渡すと、自分の目の前にひとりの男性が立っていることに気がついた。
「何をしようとした」
男性は明らかに怒りのこもった口調で僕に対して問いかけた。スーツを着たその姿から会社員であることが分かる。見た目から年齢は若いとはいえず40代後半といったところが妥当だと思えた。
彼の問いかけは僕の返答を待たない。
「やっていいことと悪いことがあるだろう。どれだけ俺らが迷惑すると思ってんだよ。おい、聞いているのか。」
僕は、自分に向かって落下してきている言葉に何ひとつ反応を示すことが出来ないでいた。呑気なことを言うようだが、もし、生き物を身体と魂に分かつことができるならば、この時、僕の魂は間違いなくこの身体のどこにも存在していなかった。ただ絶えず耳に入り込む怒りの言葉を、押し寄せる情報のひとつとして淡々と処理し続けていた。
それからしばらくの間、その男性を中心に様々な人に何かを言われた(それらのほとんどは直接的なものではなく、仲間内での囁き合いやつぶやくような独り言であった)。もちろん、その全てが僕に対しての怒りや僕自身をけなすものであったが、詳しくは記憶していない。その間僕はただ茫然と地面に座り込み、10分後に各駅停車の車両が到着し、その場に居た者たちがせわしなく車内に乗り込んで初めて立ちあがった。
コンビニでペットボトルのお茶を買い、自宅への帰路をたどりながら、さきほどの出来事について考えていた。
男性の言葉は不可解であった。見ず知らずの自分に対し、なぜ怒りをもって接することができるのか。彼が良い人間で、彼自身に何一つの利益がなくともそうやって人をしかることができるのだと考えるのは簡単だが、それでは納得のいかない違和感があった。
僕が思うに、彼は目の前で起ころうとする「死」に恐怖していたのだ。ひとりの人間が死に、魂(あればの話だが)がひとつ消え去ってしまうことに対し、本能から来る恐怖を感じていたのだ。人が恐怖を感じるとき、それを怒りという異なる感情でもって抑圧するという解消方法はありがちな心理行動ではある。僕からすればそう考える方が妥当であるように思われた。
それに、多くの人間は黙って見ているか安全圏内から野次を飛ばすことをその場の行動として選択しているのだ。さきほど述べたような「良い人間」が果たして人間社会において本当に「良い」のかどうかは甚だ疑問だ。
それにしても全く気分がそがれてしまった。これから自分はどうすべきなのか、もう一度考え直す必要性が生じてしまった。かといってこれ以上だらだらと平坦に生きる自分には心底嫌気がさしていた。どこかで区切りをつける必要がどうしてもある。そう考えているうち、このまま自宅に帰ることになんとなく気がひけてしまい、住宅街から少し抜けたとこにある、人通りの少ない公園に足を運ばせていた。
この公園は、周辺の人々の生活圏から少しだけ離れているせいで、公園としての機能をあまり満たせずにいる。利用するものがあまりいないため、管理が徹底されなくなり、およそ寂れた公園としての風格を掲げようとしていた。
この公園に独りで来るような人間は、あまりいい精神状態とはいえないだろうな。
そのように僕は思った。
公園には、およそ公園らしいものが互いに邪魔しないように配置されていたが、それらを眺めていると、そのどれもが形容しがたい退廃的な感情を僕の心に呼び起こさせた。
木陰のようになっている公園の端にベンチがあったのでそこに腰をかけてみる。木製のそのベンチは少し朽ちているようで、何人もの人間が座るには少し不安を感じる危うさが感じられた。おそらく3人座ればこのベンチは痛んでしまうのではないだろうか。2人であればおそらく大丈夫。なんとなく僕はそう思った。
公園という公共空間でありながら、この空間は僕ひとりによって占有されていた。少し風がきついらしく、木々がこすれ合うさわさわという音や、地面に落ちた葉や、誰かがここで捨てたのであろうゴミが、弱弱しく転がっている音があたりを埋め尽くしていた。
そういった音を耳にしながら、僕はiPodをズボンのポケットから取り出し、音楽を聴くことにした。再生ボタンを押すと、軽快なラグタイムの曲が耳元で転がり始める。その音楽は、部屋に配置された家具のように自然で、さきほどまで僕がぼんやり聞いていた木々や葉やゴミが奏でる音たちのように生活の一部の音として表現されている。
自分が今、どんな感情を抱いているのか、よくわからない。
人が自ら命を絶つ時、絶望が満ち足りた状態でなければならないのだろうか。
深い悲しみの中に呑まれ、生きる希望の一切を失い、死という選択が常に目の前にまとわりつき続ける。
そんな状態でないと、人は自殺してはならないのだろうか。
少なくとも、僕の心はそのような激情の中にあったわけではない。悲しいことや空しいこと、深い絶望を経験したとは思うが、それが自分の中の許容量を超えたとは思わない。
人は、死というものを重く見過ぎているように思う。あんなに気さくに性行為を繰り返して、「出来て」から結婚するだなんて風潮も受け入れられ、ポンポンと生産され(もしくは中絶され)ている「生」の裏で、これほどに死に対しての禁忌を貼り付けているのは、どうも良いことのようには思えない。もっとフランクに、気さくに死んでもいいんじゃないかと僕は思う。
だから、僕は、買い物に行くように死のうと思った。感情というよりは気分に近い軽さだった。
しかし、生きて帰ってきてしまった現実を顧みるに、やはりそれでは死に対して失礼だとでもいうのだろうか。それとも単に僕自身の精神がいかれてしまっているだけなんだろうか。
考えても、答えは出ない。それは己のよく知るところだった。こんなことはそれこそ「こんなこと」になるまで考え続けた。それでもいっぱしの答えのようなものの片鱗すら現れないということは、きっとそういうことなのだろう。そして、僕の頭が足りていないという結論には至ることはできない。
考えているうちに、きい、という悲しげな音をたてて、座っていたベンチがきしんだ。
背中や臀部に伝わる振動が僕の耳に雑音を取り入れさせた。
女性だった。歳は比較的若く、僕より年下、もしくは同世代のように思われた。少なくとも高校生か大学生をやっていそうな年齢だ。こちらを見ている、口を開いている。声は聞こえず、耳には不思議なリズムのピアノが流れ込み続けている。ベンチ上で相対する女性の声が聞こえない。その瞬間、イヤホンから聞こえるピアノの旋律は、家具ではなくノイズとなり、音楽としてではない不本意な主張をし始める。
僕は聴衆として音楽を冒涜するわけにもいかず、音楽の再生をやめ、イヤホンをはずし、iPodにくるくるとイヤホンを巻きつけた。
目の前の女性はその一連の動作の間、言葉を発することをせず、ただ僕の作業が終わるのを待っているように見えた。
「この公園にはよく来るんですか?」
社交性の高そうな笑みを浮かべ、彼女は僕に話しかけてくる。その根拠のない積極性に当惑しながら、この問いかけに対して反応を示すべきか否か吟味したうえで、口を開くことにした。
「この近くの者だけど、ここにはあんまり来ない。寂れた公園だなぁとは思っていたけど」
「そうなんですか。じゃあ、今日はなんでここへ?」
僕と友好関係を結ぶという目的以外で、このようなやり取りを行う必要があるとは思えない僕は、彼女の真意をつかみ損ねていた。なぜ彼女はここに座り、ここに座っていた僕に話しかけ、このように僕を知ろうとしているのか、考えるのも億劫になったので、思った通りに答えることにした。どの道この女性と自分は何ひとつ関係性など持ち合わせていないのだ。
「なんでって、ひとりでここに来るくらいなんだから、きっとあまり普通とはいえない人間なんですよ。理由なんてないよ」
「それって私も普通じゃないってことになりますよ。」
「違うの?」
「そんなの私には分かりません」
「まあ、人気のない公園で男性に話しかけてくるぐらいだから、あんまり普通とはいえないんじゃないかなぁ」
「せっかくさびしそうにしてる人に話しかけたのに、そのあしらい方は関心しませんね」
「さびしそうにしてる人は、さびしい自分に酔っているんだから、放っておくのが最善なんだよ」
「でも、あなたはそのままにしてたら自殺とかしそうですよね」
「失礼な決め付けだな、やっぱり君は普通じゃないよ」
「だって顔に書いてありますよ。『ああ死にたいなぁ』って」
「まぁ、正解っちゃ正解だから、その失礼な物言いに関しては多めにみることにするよ」
「あらら、本当に死のうとしてたんですか。あ、それとももう未遂で終わっちゃったとか?」
「かっこ悪くて悪かったな」
「謙遜しなくていいですよ。十分かっこいいですから」
そうやって笑いをこらえるようにする。僕はそろそろこの会話に嫌気がさしてきていた。しかし、その裏で楽しくもある。自分の素生を知らない、無害な人間と会話をするのは、いろいろと気遣う必要がないからだ。
話題を変えるために、少し間をあけてから話しかける。
「ところで、君はここで何をしているんだ? まさか君も死のうとしたとか?」
「まさか。偶然ここを通りかかったらさびしそうにしている同世代の人間がいたもんで、気になっただけですよ」
そのあと、彼女は暮れゆく陽光を、見送るかのように3拍、眺めた。そして、その陽光を浴びるかのように、間もなく失われる光のかけらを集めるようにして身体の向きを変えた。
僕と彼女の間に鋭い光が介在し、彼女の体の輪郭が若干ぼやける。現実との区別がつかなくなるほどに、彼女は存在感を失いながらうつろいでゆくように見えた。
そうやってありもしない妄想を頭の中で繰り広げている差分、ぼんやりしているのは間違いなく彼女ではなく僕であった。
「名前、聞かせてもらえますか?」
彼女は、話しかけるに十分な拍数を得たと思ったのであろう、僕の口が開くのを待たずして問いかけた。
「僕の名前は―――」
ノイズで聴こえなくなった。自分自身の声が還ってこない。映りの悪いテレビのように目の前が鋭くひんまがっていく。雑音が耳に押し込まれていく。声が入ってこない。視覚能力もほとんど機能していない。三半規管がとたんに不十分になる。僕は大きくふらつきながら、必死に正気を保とうとした。目の前の女性に、悟られないよう、少しずつ、呼吸を整える。
悟られないように、というのはたぶん、僕の気持ちだけであって、きっと感づかれているに違いない。でもそこは大した問題じゃない。僕がそうしようとすることに意味があるのであってその結果に対した意味はない。
視界が良好になりゆく。耳が風の音をようやく聴いた。
彼女はこちらを見ていたが、ベンチからは立ちあがっていた。もう時間なんだろうか。それとも、救急車でも呼ぼうとしたのか。
「大丈夫」
やっとのことで声が出る。声帯がうまく機能しない。反応がにぶい。一拍遅れで口が開く。音ズレのような気分の悪さを感じる。
「少し心配しました。でも、申し訳ないんですが、そろそろ」
彼女は時間を気にしている。表情は読めない。見えない。帰りたいのだろうか。
「もう帰らなきゃいけない時間?」
「はい」
「家はどこらへんなの?」
ゆっくりと手をあげる。僕は空間を上へとスライドしていく指を眺めていた。浮かんでいく腕は、地面と平行の位置で停滞し、指はゆっくりと下へと降ろされた。
「ここです」
「この公園に住んでいるの?」
「ちょっと前まで住んでたんですが、今日はここに帰らないといけないんです」
「どういうこと? 良く分からない」
「ゆっくりと帰るんです。それにしても、風がきついですね」
「もう帰るの?」
「はい。それでは」
そうやって彼女は、公園から飛ぶように出て行った。
公園に帰る。というのはどうやら違ったらしい。まさか、地球上の裏か、とも思ったが、馬鹿馬鹿しいのでそれ以上考えるのはよした。
「そりゃあ、見ず知らずの人間に家は教えたくないわな」
口にだすことで、落ち着きを取り戻そうとした。
ベンチから立ち上がると、ギシ、という音がした。
風が背中にぶつかってははじけていく。公園の入り口へ、僕を押し出そうとしている。
風にも勝てない、僕はゆっくりと家へと帰った。帰宅の途中で葉っぱを踏んだ。まだ木から取れたばかりなのだろう。乾燥した音はせず、無音のまま僕の靴に踏まれていた。
ベッドに入ると恐ろしいぐらいに温かみがあった。生きた心地というものが熱したナイフのように僕の肉を残酷に焼き切る。苦痛に顔を歪めることが出来ればまだいいのだが、自分の脳内で繰り広げられる、つまりは意識的に僕が生み出した痛みであるため、結局は自虐的快楽へと帰結させる以外の終着点はない。我ながら恐ろしい人間である。いや、むしろこれは一般化されうることだろう。
人間は誰しも、こういった「自分に対する残酷さ」を持っていて、その身をあえて焼いてしまおうとする。それらは自分自身を殺すことなどないというのに。どんな人間だって、自分勝手な自分の呪縛から逃れることなんてできない。生きている限り、それはずっとずっと闇に落下し続ける。
これも全ては悦楽あるがゆえ、である。僕たちはどんな痛みだってそこに快楽を呼び起こすことができる。小さな私たちの夢は嘘だったみたいにはじけ、その刺激で僕は全身で震える。
神様の質量


