
赤い渚に浮かぶ月
キャラクターFILE (順次更新します!)
No/1 カリム(16、7くらい?)
淡い色の長い髪と、蒼い瞳を持つ少年。
元、退魔組織”白亜の塔”の上級天使。
現在、人生について悩み中。
今一番知りたいこと:彼女の気持ち。
座右の銘:弱みを見せるは負けると同じ。
No.2 アシェル(12くらい?)
燃えるような赤い髪と、緑色の瞳。
身長は、大人の肘から手の先までくらい。
背中に、溶かした金属のような色の羽を持つ。
元”白亜の塔”所属の天使で、現在は妖精姿で活躍中。
主張したいこと:カリムは自分の物!
今一番知りたいこと:男女別、自尊心の持たせ方。
座右の銘:男は女に言い負かされてなんぼ、女は男に甘えられてなんぼ。
No.3 イリィ(15才)
銀色のお下げ髪と、紫の瞳の少女。
海辺の寒村に、育ての母と二人暮らし。
現在、トラブル抱え中。
今一番知りたいこと:人に嫌われない方法。
座右の銘:ふつつか者ですが、精一杯がんばります!
№4 フェグダ(20+α才)
日焼けした肌に、明るいはしばみ色の髪、若い木の実のような茶緑色の大きな瞳。
白亜の塔所属の天使で、 現在あちこち放浪中。
今一番知りたいこと:貧乏クジと当りクジの違いについて。
座右の銘:悪運も実力のうち・・・多分。
No.11 ジーロ(10才)
鳶色の短い髪と、焦茶色の瞳の男の子。
とってもイリィを慕っている。
兄とは恋敵のつもり。
序
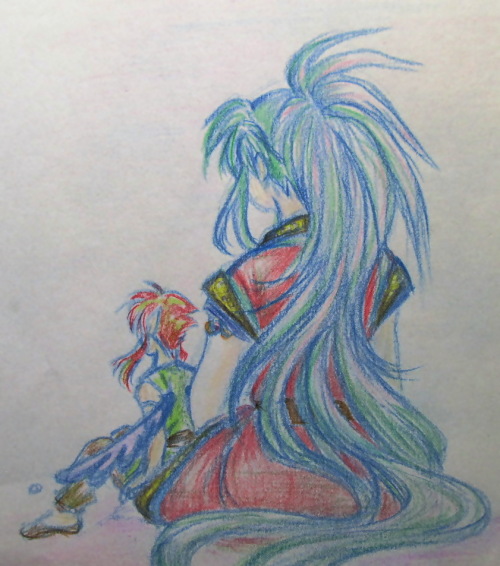
真新しい瓦礫と舞い上がる土煙に埋め尽くされてなお、真っ白なその広間で。
彼は、大切なその人をしっかりと抱きとめた。
満身創痍になり果てた身体を、今にも解き放たれようとしている命ごと。
そんな彼自身も。
大きく引き裂かれた傷口から、絶えることなく溢れ出す鮮血。流れ出ていく力と熱。
それでも彼はまだ、その足で立っていた。
大切な人の命の重みを、その全身で確かめようとしているように。
「そ奴を殺せ! でなくばこちらに引き渡せ! 即刻にだ!」
二人を遠巻きにして、無数の刃が取り囲む。
(うるさいな)
武器は既にこの手に無く、戦う力などありはしない。
誰の目にも、それは一目瞭然なことだろう。
そんな者に対して、これほど厳重な布陣が必要だとは、何と滑稽なことだろう。
「従わぬのなら、諸共に処断することになるぞ!」
それがどうした。今更、何が惜しいものか。
自然に、口元に笑みが浮かぶ。
諦めのためでも、自棄のそれでもない、心からの笑みが。
とうの昔に、滅んでいたはずの命だった。
でなければ、かつてのあの日に、共に終えるはずの命だった。
それでもこれまで、自分の意に反してでも生にしがみつき、醜く足掻き続けたのは、お前らのためでも、お前らの語る”世界”を救うためでも、ましてや崇高な使命とやらのためでもない。
大切な人が。もしも彼女がまだこの世界に存在しているのなら、その可能性が僅かにでも残されているのなら、守らないわけにはいかなかった。
ただそれだけ。
俺にとって、世界とはそれだけのもの。
けれど今、この瞬間。
求め続けた者は、この腕の中に存在する。
消えていこうとする命とともに。
そのほんの僅かな時すらも許さないというならば。
この世界には、意味がない。
留まる理由など、ありはしない。
ああ、ようやく。
ようやく、あの優しい闇の中に眠ることができる。
この時をどれだけ待ち望んだことだろう・・・・・・。
「何だ、それ!」
背後でガラリと瓦礫が崩れる音。倒れていた者が、手足を突っ張って身を起こそうとする気配。
「何が可笑しい! 何で諦めてんだよ!」
掠れた怒鳴り声に、目一杯の怒気を込めて。
「何やってんだ君は! ずっとずっと探していた人にやっと会えたんだろ! これからじゃないか! 何もかも! なのに、もういいだって!? ここで終わっていいだって!? それで幸せだなんて、馬鹿じゃないのか!? そんなの納得できるか! 絶対に、僕は認めないからなっっっ!!!」
うるさい奴。
馬鹿はお前の方だろうが。一人で熱くなりやがって。
任務で無理やり組まされたこの数ヶ月、そりが合ったことなど一度だって無かったはずだ。
いつもいつも、人に逆らってばかりで、文句だけ一人前のくせしやがって。
こんな時にまで。
「本当に、僕は、君が嫌いだよ」
それには全く同感だ。
嫌いな奴のために、本気になって怒っている場合じゃないだろう。このままでは確実に巻き添えを食うくらいは解るだろうに、ったく、どれだけ馬鹿なんだか。
「だから、嫌いな奴が何を考えてようが知ったこっちゃない! 僕は僕の好きなようにする。たった今、そう決めた!」
ゆらりと、あの馬鹿が立ち上がる。
踏み締められた瓦礫の小片が、乾いた音を立てて砕ける。
何をする気だ!?
取り囲んでいる騎士団の連中よりも、遥かにただならぬものを全身から立ち上らせて。
更に膨れ上がる不穏な空気に、動くはずがない身体が緊張し、全身が粟立つ。
「せーのっ! どりゃあああっっっ!」
完全にヤケクソじみた掛け声、と同時に。
(な!?)
足元の地面が消失し、強烈な浮遊感が襲う。
瓦礫に埋め尽くされた真っ白な空間が、急速に遠ざかって行く。
落下しているのか? 何処をどうやって、何処に向かって?
最後に目に入ったのは。
慌てふためいて駆け寄る騎士団の連中を背に「ザマミロ」と嘲笑う、あの馬鹿の憎ったらしい顔だった。
第1話 歌う天使の神殿

天使は恋をしないなんて、誰が言ったんだろう?
そんなフレーズが浮かんだのは、足元を気にしながらも、通い慣れてしまった坂道をリズムよく登っていた時だ。
(うん、いいかも。恋の歌を歌う天使様って、春のお祭りにピッタリ! メロディにしたら、ル・ル・ラ・・・、んー、ルルール・ラー? それとも・・・・・・)
「イーリィーっ!」
「きゃあ!」
歌の創作に夢中になっていたところを、いきなり背後から飛びつかれて、イリィと呼ばれた少女は思わず大きな悲鳴を上げる。
「わ、ビックリしたあ! ハハハッ!」
白いエプロンごしに腰に回されたのは、小麦色に日焼けした悪戯っ子の手。
鳶色の短い髪と焦茶色の瞳を持つ、いかにもやんちゃそうな男の子が、すぐ傍からイリィを見上げて笑いかけている。
「ビックリしたのはこっちです! ジーロってば、いきなり何するのよ!」
「ええー? オレちゃんと声かけたじゃんか! あ、そっか。まーた夢見ながら歩いてたんだー! そっかー!」
「そんな、いつもボーッとしてるみたいに言わないで! 私はただ、歌の歌詞を、その・・・・・・」
反論が小声になるのは、それはそれで気恥ずかしいものがあるからで。
「うんうん分かってるって! そんなテレることないじゃん! オレとイリィの仲なんだしさ」
「どんな理屈よ、それ・・・・・・」
ニカッと笑ったジーロの顔いっぱいに、元気な白い歯がこぼれる。そんな屈託ない顔をされては、何でも許してしまいたい気分になってしまう。
(もしジーロみたいに元気な弟がいたら、きっと、毎日楽しいだろうな・・・・・・)
ジーロが言いたかったのはもっと違う意味なのだが、それには一向に気付かず、イリィは少しだけ口元を綻ばせる。
「でもジーロ、あなたどうしてこんなところに居るの?」
「そりゃあ、イリィが丘を上がってくのが見えたからさ! きっと廃墟に行くんだろうなって!」
「ええ? 私そんなに目立ってた?」
イリィは、不安げにキョロキョロと辺りを見回す。
「大丈夫! オレ、イリィ見つけるの得意だもん! それに他のヤツに見つかるようなドジは踏まねーって。廃墟に遊びに行ってるなんてバレたら、すっげー怒られるもんな!」
「・・・・・・それもだけど、私と一緒にいるところも・・・・・・」
ふと顔を伏せるイリィに、何を誤解したものか。
「うん! アイツにだけはぜってー見られない!」
「・・・・・・あいつ?」
「あっ! 何でもない何でもない!」
小首を傾げるイリィに、ジーロは慌ててぶんぶんぶんっと子犬のように勢いよく首を振った。
「だけど、あそこは廃墟じゃなくて、神殿よ?」
「えー? 廃墟じゃん? みんなそう言ってるよ?」
イリィが行こうとしていたそこは、村を見下ろす丘の上にある白い石造りの建造物の名残で、実際、天井も壁も崩れ放題の荒れ放題ではあるのだが。
「みんなが言ってても! えーと、ほら、気分の問題よ。その方がステキだもの」
力説するイリィにしても、あれが本当に神殿だったのかなんて知らないし、いくつかある噂話の内どれが正しいかは、今となっては多分誰にも判らない。
ただ、村の大人たちは、探検好きの子供たちに、こんな風にクギを刺す。
『あそこで遊んではいけないよ』
『あそこは大昔に天使が飛び去ったところって言う話だ』
『怖い魔物に連れて行かれてしまうよ』
『誰も、足を踏み入れてはいけないんだよ』
脆くなった壁が崩れると危ないからとか、迷路のような通路の隙間に入り込んだら探しようがないとか、理由は大体想像がつくのだが。それで「ハイそうですか」と素直に言うことを聞くのは小さな子供くらいのものだ。
ただしイリィくらいの年齢の少年少女になると、別のジンクスを気にして足を向けなくなるので、一人静かに過ごすには好都合な場所なのだ。
それに。
(あそこには歌う天使様がいらっしゃるのだもの)
神殿の最奥にある、砂に埋もれかけた小さなホール。その中央には、十人くらいが余裕で立って歌える程の円形の舞台があって、その舞台を取り囲むようにして大人の背丈の倍ほどの高さの柱が五本立っている。
その五本のうちで一番高いもの、つまり唯一崩れずに天辺まで残った柱の上部には、少女の姿の彫像が舞台を見守るように腰かけている。
ひび割れたり欠けたりして形の細部は失われてしまっているが、微笑を浮かべた目元や微かに開かれた口元は、長い年月を経た今でも優美で穏やかな雰囲気を漂わせている。
(あの像に出会った瞬間のことは、今でも覚えてる・・・・・・)
幼い頃に、村の子供たちと探検に行って、まるで魅かれるようにホールに入った。そして、少女像を見上げた時の、不思議な感動を。
一目で判った。
彼女は天使に違いない。
そして、ずっとずっと、歌を歌い続けている。
彼女の最愛の人のために。
けれど、勇んで報告しに帰ったイリィに、お母さんは呆れた顔を向けた。
『ああ、あの像のことだね。だけど翼も無いのに、どうして天使だと判るんだい? それにね、天使だったら、恋の歌なんか歌わないよ。天使は人々に等しく慈悲を垂れるものだから、たった一人に恋したりなんかしないんだよ。さあ、もうあんな危ない所に行ってはダメよ。今度言いつけを破ったら、きつーくお仕置きするからね』
信じてくれないのなら、それでもいい。
だって、私はちゃんと、知っている。
私だけの、天使様。
あそこは私だけの特別な場所。
私の歌を、いつも、あの少女だけが静かに聞いてくれた。
ジーロが来てくれるようになるまでは。
「イリィってば、廃墟・・・・・・じゃなくて、神殿で歌の練習するんだろ?」
「ええ、そうだけど」
今更取り繕っても無駄なので、イリィは正直に認める。
「オレも行っていい? イリィの歌聞くのちょー好きなんだ! 春祭りの歌って言やアレだろ、ほら、”愛しい花”とかさ!」
「何言ってるのよ。それは恋人に捧げる歌よ?」
「えーいーじゃん! オレら恋人みたいなもんだしさ!」
「五つも年下のくせに何言ってるのかしらね、おマセさん!」
「何でさ! ロッゾの親父なんて、八つも年上のカミさんゲットしたんだぜ!」
「・・・・・・それは大人の話なの! それに、ジーロにはマリエッタがいるじゃない」
「マリィぃぃぃー? じょーだんだろー? 二つも年下のくせにえらそうぶって、すっげナマイキなんだぞアイツ」
途端にジーロは、鼻に皺が寄るほど顔をしかめる。
「お似合いだと思うけど?」
「やーめーろー! ってかオレはイリィ一筋なんだぞ!」
臆面も無くハッキリ言ってしまうところが子供である。
「はいはい。ありがと」
そんな風に話しながら歩いていたせいだろう。程なく急な坂道は緩い勾配に変わり、目の前に廃墟もしくは神殿の佇まいが現れ始める。
元は壮麗だったのだろうが、崩れて歪になった建物を、高い壁がぐるりと取り囲んでいる。
正門に向かうなら、道なりにもう少し登って行かなくてはならないが、ホールに直行するなら、手前の壁の破れ目から入るのが近道だ。
銀色のおさげ髪や長いスカートを引っ掛けることなく、慣れた様子で壁の隙間に滑り込んだイリィの後に、身軽なジーロが続く。
外観の割に幅のある通路を進んで、時々壁の間を抜けて近道して。辿り着いたのは神殿の最奥、高い天井を持つ広々とした空間だ。ここだけは天井が抜けも壁が破れもせずに、明り取りの窓から差し込む光を受けて厳かな雰囲気に満ちている。
「わあ・・・・・・!」
何度か来たことのあるジーロでさえ、つい感嘆の声を上げてしまうほどだ。
イリィは床を覆い尽くす細かい砂を踏みしめながら円形の舞台まで進み、いつものように少女像に向かって挨拶するように微笑みかける。
少女像が微笑み返してくれているような気がする時は、とても自然に見上げることが出来る。
思う存分声を上げて歌うという、普段は出来ないような行為さえ、ごく当たり前のことのように。
心の奥底から湧き上がってくる音に全てを委ねて、イリィは紫の瞳を緩く閉ざし、静謐な空気を身体一杯に取り入れる。
歌を紡ぐ前の一瞬の静寂。
それはイリィが一番好きな瞬間だ。
おやすみ わたしの 愛しい子
輝く面に 祈りを重ね
歌う天使の まなざしに
導かれしは 夢の通い路
まばゆき炎が おまえを照らす
白き腕に 抱かれつ
今ひとときは 安らぎて
おやすみ わたしの 愛しい子
何故だろう。
口をついて溢れ出したのは子守唄。
ずいぶん長いこと忘れていた、懐かしくて、ちょっと切ないメロディ。
(ああ、そうだったんだ・・・・・・)
今初めて、解った気がする。
天使が歌っているのはきっと、子守唄。
愛しい人に捧げる安息の歌だ。
(これは、私の声を借りた、天使の歌・・・・・・)
その時だ。
どさっと、派手に何かを放り出したような音が、ホール中に大きく響き渡った。
「痛っー・・・・・・ったくあのバカ! どこに放り出しやがる!」
何かではなく、誰かと言うべきだったようだ。
どこか高い所から砂地に落下したと思しきその人物は、少し掠れたテナーの声でそんなことを呻いた。
(綺麗な響き・・・・・・)
歌の上手い下手以前に、通りの良い声質というものがある。
この状況でノンキなこと極まりないが、思いがけずイリィの耳に入ってきたのは、正にそういう声だった。
もし、イリィが一人だけでいたのなら、しばらくこのまま呆けていたかも知れない。が、
「イ、イリィ・・・・・・」
「あ・・・・・・」
動揺を抑えきれない声で名を呼び名がら、腕に捕まって来た子供の手に、イリィはハッと我に返る。
ボーッとしている場合ではなかった。
最初に気にするべきだが、イリィの知っている者に、こんな声の持ち主はいない。
いや、もっとそれ以前に、台詞の内容は悪態以外の何物でもない。
ジーロの手に自分の手を重ねたイリィは、声のした方へ恐る恐る首を巡らせる。
「・・・・・・!」
舞い上がる砂煙の向こうに、頭を振りつつゆっくり起き上がろうとする人影が見えて、イリィは再び言葉を失った。
それは、幻想的な光景だった。
明り取りの窓から差し込む光に輝く砂粒がゆっくりと晴れるに従って、その人物の姿がだんだんと鮮明になっていく。
頭上で一つに束ねられた長い髪は月光のように淡く、スラリとした腕は闇さえ弾くのではないかと思えるような白磁色。
少し伏せられた横顔に、凛とした切れ長の瞳。
細身の身体を覆う袖の無い緋色の長衣は、絵本に出てくる異国の王子様のよう。
「ん・・・・・・ここ、どこ?」
また、声が聞こえた。
けれどそれは、先刻聞こえたものとは別の、もっと高い声だった。
小さな男の子っぽくもあり、同時に女の子っぽくもありながら、幼子特有の舌足らずさは全く無い。
それよりも不思議なのは、イリィの聞き間違いでなければだが、その声が異国風の少年とほとんど同じ位置から発せられたということだ。
「あ・・・・・・!」
イリィが注視していると、少年の胸元で、何かがピョコンと頭を上げた。
少年の腕に庇われるような恰好の、小さな子供・・・・・・ではない!
赤い髪をした小さな頭に、人形のように細くて小さな手足。
大人の肘から指先くらいまでくらいしかない、小さな小さな身体。
しかも、髪の間に覗く耳の先はピンと尖っているし、背中には金属のような光沢を放つ一対の翼まである!
(もしかして、妖精さん!?)
そう言えば。
イリィとジーロが立っているのは、舞台を挟んでホールの入り口側。少年らが現れたのは、奥側だ。
他の出入り口が塞がっていて使えないのは判っているから、彼らが普通に歩いてここに来た、なんてことは有り得ない。だだっ広いホールの中で、隠れられる場所も知れている。
魔法か何かでいきなりこの場所に現れたとでも考えない限り、彼らがここにいる説明がつかない。
ドキリと、イリィの心臓が跳ね上がる。
腕を掴んでいるジーロが、ゴクリと唾を飲み込んだ気配。
その時。
俯いていた少年がゆるく頭を振って、イリィの方へと顔を上げる。
今まで髪に隠れていた、白く整った顔立ちが顕わになる。
怜悧に輝く蒼い瞳が、真っ直ぐイリィに向けられる。
幻想的で儚いとさえ見えた細身の少年が、その瞬間、言い知れぬ存在感を放つ。
目を、逸らせない。
足が竦んで動けない。
声を上げることもかなわない。
(ダメ! ジーロだけは逃がさなくちゃ・・・・・・!)
イリィはなけなしの気力を振り絞って、腕を掴んだままのジーロの手を外すと、庇うように後ろへさがらせた。
そんなイリィに向かって、少年がおもむろに口を開く。
「お前、天使か?」
「・・・・・・・・・はい?」
あまりにも有り得ない問いかけに、イリィの頭は真っ白になった。
聞き間違いでなければ「天使か」とか、何とか・・・・・・。
「違うのか?」
訝しげに問われて、イリィはようやく、ぶんぶんぶんと勢い良く首を振って否定する。
(何言っているんだろう、彼は?)
銀色の髪と紫の瞳というイリィの外見こそ珍しいが、それ以外は何の変哲も取り柄もない田舎娘そのものだという自覚はある。
だからそれは、イリィが質されなければならない問いではないはずだ、絶対に。
天使というなら、そう。精一杯努力して着飾った少女達よりずっっと綺麗なこの少年の方が、よほど天使に相応しいではないか。
背中に白い翼を隠していないとしたら、その方が驚きなくらいだ。
赤い髪の妖精さんと一緒に、「おとぎの国から来ました」と自己紹介される方がずっとマシ、いや、いっそ現実的に思える。
「ああもう、いきなり脅かしてどうするのさ! 相手はフツーの女の子だってのに!」
妙に張り詰めた空気を破ったのは、赤い髪の妖精さんだった。
妖精さんはするりと少年の腕を抜けると、ふんわり優雅な軌跡を描いて、イリィの目の前に飛んできた。
翼があるのだから飛べるのは当然なのだろうが、翼を鳥のように羽ばたかせるわけでもなく、フワリと空に浮かんで、プカプカとイリィの眼前に静止していたりする。
良く見れば不思議な金属色をしたその翼は、妖精さんの背中から生えているのではなく、背中近くの空間に浮かんでいるだけだった。
「こんにちは」
完全に及び腰のイリィに向かって、妖精さんはくりくりした緑の瞳で、人懐っこく笑ってみせた。少し身を屈めて覗き込むような仕草はとても愛嬌があって、妖精であるということを忘れさえすれば、少年よりも格段に親しみやすい感じがする。
「ボクはアシェル。で、あっちの目つき悪くて無愛想なのがカリム。キミは?」
「あ、イリィ。イリーナって言いま・・・す・・・」
反射的に答えてしまってから「いけない!」と思うが、もう遅い。
”妖精に不用意に名前を告げてはいけない”というのは、おとぎ話では常識中の常識なのに!
「そう、イリィちゃんっていうの。可愛い名前だね」
その笑顔に、悪意があるようには見えなくても。
「で、一緒にいた小さい子は誰?」
「え、ええと・・・さあ・・・?」
ジーロの名前を出すのは、さすがに思いとどまった。
目だけ動かして辺りを見回せば、ジーロの姿はどこにもなくなっている。要領よく逃げ出すのに成功したようだ。
(良かった・・・・・・)
自分一人なら、何かあったとしてもまだ気が楽だ。
「ふーん? まあ、いいけど」
一瞬思案するように入り口の方に目をやってから、妖精さんは再びイリィに瞳を向ける。
「ねえ、もし良かったら、ちょっと聞きたいことがあるんだけど」
「あ、はい・・・・・・」
またしても反射的にうなずいてから、「忙しいのゴメンね」と逃げ出してしまえば良かったのではないかと思い至って、イリィは内心ガックリとうなだれる。何をやっているんだろう、本当に。
もしかしたら自分で自覚している以上に、パニック状態なのかも知れない。
だが”妖精に嘘がバレれば余計に酷い目にあわされる”というのもまた、常識中の常識なわけで。
イリィが心中オタオタし通しなのを知ってか知らずか、妖精さんはニコニコしたまま可愛く首を傾げると、
「ああ、良かった! ダメって言われたら、どうやって説得しようかって思っちゃった!」
胸元に持って来た両手の指を、何だか難しい形に組みながら。もしかしてもしかすると「何かの術を使っちゃうよ」の意思表示的に。
「・・・・・・お前だって、人の事言えないだろ」
そっぽを向いた少年が、呆れたようにぼそりと呟く。
何気なく少年に目を移したイリィは、再びドキリとして目を見開いた。
少年の纏う濃い緋色の長衣には、まるで獣が爪を振り下ろしたかのような無残な傷が、いく条も走っていた。
でも、どんな大きな獣だったら、こんな爪跡をつけられるのだろう? 山の稜線の迫るこの村でも、そんな獣の話など、今まで聞いたことがない。
(って、そんなことにしてる場合じゃないよね? ど、どうしよう・・・・・・!?)
その時、少年を凝視したままのイリィの前に、すっと妖精さんが割って入った。
ひらりとした緑のチュニックが、イリィの鼻先に触れそうな近さだ。
「ねえ、ボクの話聞いてる?」
無視されて思いっきり気分を害した、と言いたげな顔。
「あの、でも、彼、怪我してるんじゃないですか? 手当とか、薬とか、その・・・・・・」
妖精さんの機嫌が気にならないわけではないが、優先順位としてはそっちが先なはず。
なけなしの勇気を振り絞って、イリィは意見を口にしてみる。消え入りそうな声でだが。
「え? ああ、あれだったら、いーのいーの!」
イリィの言わんとしていることを理解した妖精さんは、チラリと少年を振り返ってから、パタパタと手を振って見せる。
「俺がどうしたって?」
話題になっていると気付いたらしい当人は、いかにも面倒くさそうに立ち上がると、バタバタと乱暴かつ盛大に服に付いた砂を払い落とした。
それはどう見ても、怪我人の挙動ではない。
「ね?」と、妖精さんが振り向いて笑う。
イリィはほっとすると同時に、それならそれで、どうしてそんなにズタボロな恰好でいるのか聞いてみたい衝動に駆られる。
なにしろ、そんな風に汚れたり傷ついてさえいなければ、一目で高価だと判るような出で立ちだし、少年の髪や腕を飾る装身具にしてもかなり立派なものなのだ。
本当に、天使様なのか、異国の王子様なのか、身分の高い騎士様なのか。
くどいようだが、どうして妖精さんと一緒なのか。
(アシェル、それに、カリム・・・・・・)
イリィは響きを確かめるように、二つの名前を心に唱える。
(あなたたちは、どこから、どうやって来たの? ここに。私の目の前に・・・・・・?)
怖いと思う気持ちが無くなったわけではない。が、イリィの心の中でゆっくりと好奇心が首をもたげ始めていた。
第2話 謁見

「ねえ、イリィ、ちょっとこっち」
不意に、妖精さんがイリィの袖をつんと引っ張る。
明るい雰囲気から一転、妙に深刻な面持ちで。
「え、あの・・・・・・?」
何だかとても逆らい難い雰囲気。
戸惑うイリィに有無を言わせずホールの壁際まで連れて行くと、妖精さんはひそりと耳元に口を寄せた。
「一目ぼれ?」
「はい?」
「はい? じゃないの! さっきからずっとカリムのこと見てるでしょ。カリムのことがキニナルの?」
「まさかっ!」
妖精さんの言わんとすることにようやく察しがついて、イリィは大きく首を振る。
「あ、耳まで赤い」
え、と思わず両耳に手をやったイリィに、妖精さんは”ほら見ろ”とばかりにジト目を向けた。
「それは、あの、だって、ほら、いきなり妖精さん連れた異国人の男の子が現れたら、気になるに決まってるでしょ。その・・・・・・好きとか言う前に・・・・・・」
しどろもどろの説明だったが、妖精さんはうーんと首を傾げる。
「まーソレもそっか・・・・・・」
「でしょ! それに、見た途端に好きになるなんて、そんなお話みたいなこと、本当にあるわけが・・・・・・」
「それ違う!」
畳み掛けようとした途端。最後まで言わせずに、妖精さんはイリィの鼻先にビシッと小さな人差し指を突きつけた。
「いーい? 人を好きになるのに、時間とか理由とか言い訳とか、そんなの一切関係ないの! どんなにどんなにどんなにどんなにっ好きにならない理由がいっぱいあってもっ、そんなの全部ぜーんぶすっ飛んでっちゃうもんなのっ!!!」
「そ、そう・・・・・・?」
「そうなの! 間違いなく!」
とても反論出来そうにない勢いで、妖精さんは力説する。
「だけど!」
「あ、はい!」
「カリムはボクのだから! イリィがどんなに好きになってもムダなんだからね! そこのところ、よーく肝に銘じておくようにっ!」
こくこくこく。
何を宣言されたのか考えるより先に、迫力に気圧された身体が勝手に頷いている。
小さな妖精さんがどーんと巨大化して見えたのは・・・・・・果たして本当に目の錯覚だろうか。
「ん、よろしい。くれぐれも心するように」
そんなイリィの様子を確認して満足げに腕を組むと、妖精さんは重々しくのたまった。
何とか解放されたイリィは、深い深い息をつく。
なるほど、ホールの隅に誘われた理由は判ったが、何と言うか、この程度離れたくらいでは当の本人に丸聞こえなのではないだろうか。
妖精さんも、はたとそれに気付いたようで、心持ち探るように少年の方を振り返る。
が、話の渦中である少年は全く興味ナシといった風情で、柱を背もたれ代わりに舞台に座って、完全にくつろぎモードだ。
ホッとしたような、拍子抜けしたような・・・・・・。
何気なく目を戻したイリィと妖精さんは、どちらからともなく、互いに笑顔を見せた。
「・・・・・・あの、聞いてもいいですか?」
「別に畏まらなくていいよ。で、何?」
言いたいことを言い終えて満足したのか、妖精さんは思いのほか素直に返事をしてくれた。
「お二人は、どうやってここに来たんですか?」
イリィはようやく、本当にようやく、聞きたくてウズウズし通しだった質問を口にした。
「それがねえ、よく判んないんだよね」
「判らない、の?」
はぐらかされたのかと思ったが、妖精さんは本当に困惑顔だった。
「何かね、気がついたらどこか遠くからキレイな子守唄が聞こえてきて、それが急に近くなったと思ったら、ここにポーイって投げ出されてたんだよねー」
「歌! 聴いてたの? やだどーしよっ! ハズカシっ!」
「あ、やっぱりアレ、イリィちゃんだったんだ。ってか、何? 引っかかるとこ、そこなんだ?」
「その、だって私、ジーロ以外の誰かに歌を聴かれたことなくって・・・・・・」
「ええ? 何で? あんなに上手に歌えるに? もったいないなあ」
上手かどうかはさて置いて。
「・・・・・・私、ここでしか歌えないから・・・・・・」
「歌え、ないの? 歌わないのじゃなくて?」
「ええ、そう。ここ以外で歌おうとすると、声が全然出なくなるから・・・・・・」
こんなことを言って信じてもらえるかは判らないが、本当なのだから仕方がない。
「明後日は春分のお祭りで、村のみんなは準備や歌の練習で忙しいのに、私一人こんなだから・・・・・・」
「春分のお祭りっていうと、歌って踊って恋人にコクハクしちゃったりなんかするアレだよね?」
他にも豊作祈願など色々と重要ポイントはあるのだが、イリィのような少年少女に重要なポイントは、正にそこのところだ。
「まあ、歌ナシでも、イリィみたいに可愛かったら問題ない気もするんだけどなー」
「・・・・・・はい!?」
「何ビックリ目してんのさ? 綺麗な髪だねーとか、神秘的な瞳だねーとか、そーゆうキメ台詞よく言われるでしょ?」
「・・・・・・珍しい、とは言われます」
ほめ言葉なんてとんでもない。
こんな紫色の瞳なんか、変えられるものなら変えてしまいたいし、この銀色の髪だって村の慣わしで仕方なく伸ばしてお下げにしているだけで、出来ることならバッサリ切ってしまいたい。
だがそれを妖精さんや少年に言ったところで、理解してもらえるかどうか分からない。
二人のような外見も珍しいには違いないが、そもそも異国人と妖精さんなのだから、違っていて当たり前だ。
肩を落としたイリィは、気付かれぬよう内心でため息をつく。
(・・・・・・それでも、この二人には、私の見た目なんか珍しくも何ともない、のかな?)
考え込むイリィをよそに「えー、こんなに可愛い子前にして、見る目ないなーここの連中ー」とか何とかひとしきり呟いてから。
「あ、じゃあさ、好きな人連れてここ来ればいいんじゃない?」
目を輝かせた妖精さんは、いかにも名案と言いたげに無邪気な質問を繰り出してくる。
好きな人がいないなどと言えば、また要らぬツッコミを受けそうだし。
「・・・・・・それがダメで。村ではここは一応、神聖な禁域ってことになってて、本当は来ちゃいけないって言われてるし、それに”天使が飛び去りし地”って伝説があって、好きな人と来たら別れることになるってジンクスもあって、それから・・・・・・?」
「・・・・・・・・・・・・」
妖精さんは、下を向いて押し黙っている。
「・・・・・・あ!」
その理由に思い当たって、イリィは思わず硬直した。
(どうしよう・・・・・・何かフォローは・・・・・・)
焦ったところで、すぐに名案が浮かぶわけではない。
ところが妖精さんは、なかなか不屈な精神の持ち主だった。
「・・・・・・大丈夫! ボクとカリムの仲は、そんなちっぽけなジンクスくらいで引き裂かれたりなんかしないんだからっっっ!」
がばっと天井を見上げて、握りこぶしで宣言する。
「そっ、そうよねっ!」
「もちろん!」
「あ、あははははは・・・・・・」
「ふ、フフフフフフ・・・・・・」
またしても、顔を見合わせて笑ってしまう。
こんな他愛ない話で誰かと盛り上がるのは、イリィにはとても久しぶりなことだ。
何だか、親友が戻って来たみたいに錯覚してしまいそうになる。
「てかさ、今更だけど、ここ何? 何てとこ?」
「・・・・・・」
それは確かに、今更な疑問ではあった。
「要するに、ここは普段、滅多に人が来る場所じゃないんだね」
村のことや遺跡について、知る限りの言い伝えを並べた後のこと。
妖精さんは、思い出したように少年の方を振り返る。
「じゃあ、アレ、何だと思う?」
「四、五人ってところだな」
いきなり話を振られたのにも関わらず、少年は至極あっさりと応じた。
「あの、それって、まさか?」
ある可能性に思い至って、イリィはさあっと顔色を変える。
「うん。あのジーロって子が、大人に報せて連れて来たんだろうね。よそ者が来たぞーっ、とか何とか?」
そして妖精さんは、イリィの顔をじっと見た。
「さあ、どーしよっか?」
大きな街道から外れた辺鄙で小さな村のこと。
ジーロがどんな風に説明したかは分からないが、異国人の来訪というだけでも村を挙げての大事件だというのに、その来訪者が妖精さんと一緒に遺跡に突然現れたとなると、これはもう、村始まって以来の天変地異だ。
それに、ああ見えてジーロは、十歳の子供にしてはしっかりしている方だ。悪戯で済む事柄かどうかの分別だってある。そんなジーロが必死に主張すれば、大人だって真剣に耳を傾けざるを得なかっただろう。
どうしてそんなところに行ったのかを追及されては困るので、それなりに言い訳はしただろうが、来訪者の特徴に関してジーロに嘘をつかなければならない理由はない。
「あの、隠れた方が良くないですか?」
不安そうな面持ちで、イリィは至極当たり前に思える提案をした。
崩れかけてはいても、神殿にはそれなりに奥行きと広さがあるし、こっそ隠れてしまえば、ちょっとやそっとで見つかりはしないだろう。
大人達だって、あまり長居して捜索したりはしないだろうし。
「うーん。どうかなー。ボク達が隠れちゃったら、今度はイリィちゃん達が怒られるんじゃない?」
鋭い指摘だ。
勝手に禁域に入って騒動を起こしたということになれば大変だ。怒られる程度で済めば良い方。下手をすれば、普段からしょっちゅう出入りしていることまでバレてしまうかも知れない。
「どうしよう! そんなことになったら、もう歌いに来れなくなっちゃうかも・・・・・・」
掟破りで一番割を食うのは、逃げ出せばそれで解決のよそ者よりもむしろ、今後もその掟に縛られて生活していかなければならない共同体の一員の方である。
青い顔をして俯くイリィを気遣うように覗き込んだ妖精さんは、「どうする?」と言うように少年に視線を送る。
「まあ、考えようによっては、出向く手間が省けたかもな」
少年はおもむろに立ち上がると何を思ったか、パチンと音をさせて両腕に嵌めていた籠手を外し、ポイッと無造作に砂の上へと投げ落とした。続いて両手の指に嵌めていた指輪を。結い上げた髪を束ねていた、凝った細工の髪留めを、何の躊躇もなく次々と投げ捨てる。
そんな様子をイリィはハラハラしながら見ている。ホールの入り口から見れば舞台を挟んで反対側になるので、上から砂を被せて隠さずとも見つかりはしないだろうが、それでも小さな指輪などは落ちた拍子に深く埋まってしまうかも知れない。
もちろん、イリィのハラハラなど少年が気にするはずもなく。淡い色の長い髪が波を打って広がるのに、一瞬わずらわしそうな目を向けてから、今度は幅の広いベルトのバックルを外す。途端に、引き裂き傷だらけの緋色の長衣は、押さえを失ってバサリと落下する。それは舞台の上で、貴賓席を彩る敷物のように広がった。
黒の上下に飾り帯という身軽な出で立ちとなった少年は、やはりくつろいだ格好で、長衣の上に腰を下ろす。
袖の短いチュニックも、長衣と同じような位置が裂かれていたが、それは少年の白磁色の肌を一層引き立てていて、あの長衣姿を見ていなければそういうデザインなのだとあっさり納得してしまっただろう。
むしろ、豪奢で異国風なイメージが軽減された以上に、神秘的な雰囲気が増したのではないだろうか。彼は明らかに、身を飾ることで地位を主張しなければならないような人間とは、一線を画す存在だ。
「それで、お前はどうする?」
「・・・・・・!」
思わず見とれてしまっていたイリィは、その問いかけで我に返った。
「えっと、私、えっと・・・・・・」
少年が聞いたのは「自分と一緒に居る所を見られてもいいのか、隠れてやり過ごすか」ということに違いなく、そんな場合ではないのだが、心配されたみたいでちょっと嬉しかったりもして・・・・・・。
普段の自分らしくない浮かれた妄想を追い払って、イリィは頭を現実に切り替える。
このホールの中は遺跡の他の場所よりは瓦礫の少ない方だが、人一人が隠れられそうな大きさの瓦礫もいくつかは存在する。
一番隠れやすそうで、一番舞台に近い瓦礫の陰に、イリィは素早く移動する。
それを見届けてから、少年は妖精さんを招くように手を伸ばす。
「アシェル」
「うん!」
呼ばれた妖精さんは、躊躇無く少年に向かって飛んだ。
(!?)
妖精さんも一緒に隠れるのだとばかり思っていたイリィは、驚いて目を瞠る。
だが少年は、真っ直ぐに飛び込んで行った妖精さんをその腕で受け止めて、しっかりと視線を交わしてから、自分の傍らにそっと下ろした。
そして二人は、謁見者の控えるホールの入口に目を向けた。
程なく、イリィの耳にも数人の大人が遺跡の通路を進んでくる足音が聞こえてきた。
が、彼らの足運びはだんだんと緩慢なものになり、ついにはホールの入り口を前に動かなくなってしまった。と、思いきや、何やら囁き合うような揉めているような、妙な気配が伝わってくる。
普段は廃墟だ何だと顧みもしないくせに、いざとなると禁域の言い伝えを恐れているのだろうか。
「そこにおられる方々。遠慮は要らぬ、入られよ!」
まさか、そんな風に声をかけられるとは思ってもみなかっただろう。
息を飲む気配とともに、ざわめきはピタリと治まって、ややあって数人の村男がおっかなびっくり連れ立って、入り口から姿を現した。
だが彼らは十歩も進まない内に、舞台に端座する少年と、更にその傍らにピタリと寄り添う妖精さんの姿を見るや、大きく息を呑んで立ち止まる。
彼らが息をすることを思い出す程度に驚く時間を与えてから、少年は鷹揚に口を開いた。
「貴公をこの地の村長殿とお見受けするが」
声を張り上げるでも威圧するでもなく、ごく普通に話しかけただけ。
にもかかかわらず、団子に固まっている男たちの誰一人として、しわぶき一つ立てることが出来ないでいる。
(村長、には見えないわね。お世辞にも)
団子の先頭にいる恰幅のいい年配男が、一応、去年代替わりした村長なのだが、それを知っているイリィは思わず吹き出しそうになる。もしかすると少年もまさか本当に村長が居るとは期待していなかったのではないだろうか。
村長の後ろで牧草用のフォークや鎌を抱え持っている三人にしても、普段は村で一二を争う屈強自慢なのだが、それが威厳も貫録も無い村長を盾にするように縮こまっている様子は、情けないことこの上ない。
「貴公らを騒がせたこと、まことに心苦しく思う」
彼らの反応を特に待たず、少年は軽く目を伏せる程度に黙礼する。
「そ、そんな滅相もない! 申し遅れましたが、わ、私が村長のオーリーでございます。異国の尊きお方とお見受けいたしますが、その・・・・・・」
村長も、相手が下手に出たことで何とか体裁と本来の目的を思い出したようだが。
「大変失礼ながら、この地は代々の禁足の聖地でございまして・・・・・・もしお許し願えますならば、ご来訪の理由などを承りたく存じますが・・・・・・」
普段の横柄さはどこへやら。今すぐにでも平伏してしまいかねない雰囲気だ。
「我は、訳あって故国より難を逃れて参った。氏素性を明かすことは、貴公らにとっても都合が悪かろう故、許されよ」
意訳すれば「そんなの秘密だ追及は許さん」と突っ撥ねられたようなものだが、もちろん異論は上がらない。
「これなるは、我が友にして守護である」
少年は、すぐ隣に立つ妖精さんに視線を向けた。
村長が一番問いたくて、どうしても口に出来なかった事柄が、それ。
「これがおらねば、我はこうして難を逃れること叶わなかったであろう」
妖精さんは艶やかな笑みで少年を見上げてから、村人らの遠慮がちな視線を悠然と受け止める。先刻までイリィと話していた人懐っこい妖精さんとは別人のようだ。
ゆっくりと村長に目を戻した少年は、凛とした声で宣言する。
「約束しよう。我と貴公らとの間に諍いなき限り、我ら両名、貴公らとこの地に仇なすことはない」
それは言葉通りの意味であると同時に、手出ししようものなら容赦しないとの宣告でもある。
「そ、それは、はい、もちろんでございます、はい!」
背筋をびしっと伸ばして応える村長に、カリムは満足げに頷いてみせる。
「禁足の地を汚したことは申し訳なく思う。何か礼が出来ればよいが、今はそれも難しい有様」
少年が装飾品の類を外したのはそういうことだったのかと、イリィは納得する。
「そ、それにございますれば、不肖ながら我が家へお越し下さいませんでしょうか。あばら家ではございますが、ここよりは幾分おくつろぎいただけるかと存じますが」
村長としては、他の村人の手前もあっては、やはりいい格好すべきところだ。
だたし声が上ずってしまっているあたり、自分の発言に動揺しまくっているのが丸分かりだ。見ていて何だか「よく頑張ったね」と褒めてあげたくなる気分。
「ご厚情痛み入る。なれど、我が友にはこの地の空気が馴染みやすい。それに先の通り、我らにはあまり関わらぬが貴公らの益と心得る。数日のことと黙認いただけまいか」
やんわりと断られて、村長は明らかにホッとした。
「は、それは、その、どうぞご存分にご滞在下さいませ。ご入用の物がございますれば、どうぞ何なりとお申し付けを」
深々と頭を垂れた村長に倣い、背後の男たちがぎこちなく頭を下げる。
(何だか、歌劇を見ているみたい・・・・・・)
相手役はダメダメだが、少年は最初から最後までその場の雰囲気を支配し、名乗らない言い訳をさらりと納得させ、互いに争わない約定を取り付けた。
対面した瞬間から、両者の立ち位置は既に決まっていたのだ。
「その方ら」
放って置けばいつまでも平身低頭していそうな村人を、高音の声がピシリと打つ。
その声の主が、少年の傍らの妖精さんだと判って、村人らはギクリと身を固くする。
「謁見は終わりだ。退席を許す」
意訳するまでもなく「さっさと出て行け」ということだ。
妖精さんにきっぱりと告げられて、緊張も限界の村人たちは、謝辞もそこそこに急いで退出しようとした。
幸いにも、イリィの存在は忘れ去られているようだ。もしかしたらジーロは、ここにイリィが居ることまでは言わなかったのかも知れない。
イリィはようやくホッとして、肩の力を抜く。
だが、その時だ。
「みんな待ってよ! イリィは? お前らイリィをどうしたんだよ!?」
決死の覚悟の体で叫びながら、ホールに駆け込んで来たのは。
「ジーロ、どうして・・・・・・!」
イリィは、身体の芯が冷えてギュッと縮こまるような気がした。
第3話 傷ついた瞳

「何をしに来た、ジーロ! 何と無礼な・・・・・・!」
突然の闖入者に跳び上がった村長は、普段からは想像できないような反射神経を見せて、自分の脇をすり抜ける寸前のジーロの腕を捕まえるのに成功した。
村長らを呼びに走ったジーロは、村で待っていろと言い渡されただろうに、こっそり後について戻って来て今までのやり取りを窺っていたのだろう。
「こら何すんだよ! 放せよバカ村長!」
掴まれた腕を振り解こうとして、ジーロは激しく抵抗した。
そんな両者の背後で。
「ここに来ているのか?」
「あの、不吉の娘が・・・・・」
「しっ! それを口にしては・・・・・・」
村男らのひそめた声が、イリィにはとても大きなざわめきに聞こえる。
少年とと妖精さんに、それが聞こえているかどうかは判らない。だが、村男らがイリィの名を聞いた時のただならぬ雰囲気は、きっと伝わってしまっただろう。
イリィはギュッと固く目を瞑る。
身体の真ん中が冷たく重くなっていく。
村人たちは、イリィを嫌い、のけ者にする。
村の不吉であるから、と。
(そんなこと、知れれたくなかったのに・・・・・・)
絶望的な気分で、イリィは両手で顔を覆う。
(ジーロってば、もう、どうして・・・・・・)
八つ当たりしたい衝動に駆られるが、ジーロに悪気が無かったことは判っている。むしろ、イリィを助けたい一心で、村まで助けを呼びに走ったであろうことも。
だが、ジーロの思いとは裏腹に、その行動は完全に裏目に出てしまっている。
「貴公が探すは、あの者か」
その時、少年の声が、ピシリとその場のざわめきを打ち払った。
彼はきっと、イリィを指差しているはず。
少年にも妖精さんにも、イリィを庇う理由はない。そもそもイリィの問題は、村の中の問題なのだ。先刻の約定通り二人が村人との諍いを避けたいのなら、下手にイリィと関わりを持つよりも、とっとと放り出して村長の裁量に委ねるべきなのだ。
でも、そうなれば。
村長らは、イリィが遺跡に出入りしていたことを咎めるだろうか。
煩わしそうに追い立てるだろうか。
それとも、いつものように無視するだけか・・・。
イリィは、のろのろと顔を覆っていた手を下ろし、閉じていた目を無理やり開く。目の前は暗いまま。
それでもふらりと立ち上がったのは、彼らの前で見苦しい真似はしたくないと思う、意地のようなものかも知れない。
だが。
「あれもまた、我の助けになりし者。あの者が遣わされたは、大いなる御手の導きであろう」
イリィははっとして、顔を上げる。
目の前に、笑顔のアシェルがいた。誘うように、優雅に手を差し伸ばしながら。
村人の視線の集まる中。針が突き刺さるように感じる、そんな場面の真ん中で。
イリィの心から冷たい恐怖が追い出されて、温かい嬉しさが込み上げてくる。
「されど、知らぬここととはいえ、あの者に禁を破らせたは我らの落ち度。我に免じて、此度のこと咎めだてなきよう望む」
命令でこそなかったが、はっきりとそう告げられては、彼らに否やのあろうはずもない。
「は、はっ! まことに、数々のご無礼、平に平にっ・・・・・・!」
「すでに許すと言ったはず。これ以上、主の心を騒がせることを、我は望まぬ」
妖精さんが、緑色の瞳を細めて平身低頭する村人らを一瞥する。。
「主の平安こそ我が望み。ゆめ、違えるまいぞ」
口調こそ柔らかいものだったが、その目は全く笑っていない。妖精さんの念押しは、ある意味脅しと大差ない。
村長らは辞意もそこそこに、やってきたときと比較にならない速さで、ホールから退出して行った。
「さて、と」
妖精さんは腰に手を当てると、取り残されたままもうひとつ状況を理解していなさそうなジーロと、まだ動悸が収まらず胸を押さえて肩で息をしているイリィを振り返った。
「イリィ、イリィ! 大丈夫だった!? あいつらに何かされなかった!?」
我に返ったジーロは、子犬のようにイリィに飛びつくや、開口一番まくし立てる。
「・・・・・・あの、違うから。それに、この人たちはそんなんじゃなくって」
「あのねえ、ジーロ! もうちょっと状況考えて行動しなよね! キミのせいでイリィが困ることになったんだからね!」
「るせーな、何だよお前・・・・・・うっ・・・・・・」
いつものように啖呵を切ろうとした途端、相手が妖精さんだったと思い直したか、さすがのやんちゃ坊主も威勢をなくす。
「・・・・・・あれ、俺、名前言ったっけ?」
「てか、イリィちゃんが呼んでた」
「え、私が、いつ!?」
「あ、気付いてなかったんだ」
「はい、全然・・・・・・」
「まあ、それはともかくさ、」
こほん、と妖精さんは一つ咳払いする。
「二人とも、一度戻った方がいいんじゃないかな。二人していつまでも戻って来ないってなったら、それこそ心配されるんじゃないの?」
「・・・・・・ここにいては、お邪魔ですか?」
「ええっ! 何言ってんのさイリィ、こんな得体の知れない・・・・・・」
「ジーロってば!」
「うぐ! ・・・・・・てか、イリィが残るんだったらオレも残る! こんなトコにイリィを置いてなんか帰れるもんか!」
「ジーロ君ってば、見事な騎士様っぷりだねえ。そりゃあ? 先刻のあいつらの態度じゃあ、一人でノコノコ帰ったら叱られちゃうの確定だもんねえ?」
「そ、それはその・・・・・・別にそれだけってワケじゃ・・・・・・」
しどろもどろなジーロの様子を面白そうに見やってから、妖精さんはふと、真面目な顔つきになる。
「けど、あまり親御さんを心配させるもんじゃないよ。それにさ、もし怒られそうになったら、ボク達が怖かったからだって言い訳しなよ」
妖精さんにウィンクされて、ジーロは少しホッとした顔を見せる。
やはり怒られるのは嫌だったのだろう。
「イリィちゃんも。口裏合わせは必要なんじゃない? それにね、」
「はい? ・・・・・・!」
ひらりとイリィに近付くや、妖精さんはその頬にキスする、ように唇を寄せた。
「あーずっこい! ボクだって、まだイリィにキスしたことないのにさ!」
「ジ、ジーロってば!」
「はいはい、ごちそう様!」
妖精さんは素早くバックステップで離れると、赤面する二人に悪戯っぽく笑ってみせた。
(また明日おいでよ。話したいことも色々あるしさ!)
あの一瞬で、妖精さんがイリィに囁いた言葉。
明日の、約束。
イリィとしては、まだここを離れたくないというのが正直な気持ちだったが、自分が帰ると言わなければジーロが一人で帰るはずもない。
「わかりました。あの・・・・・・さっきは、ありがとうございました」
妖精さんと、それから舞台に腰かけたまま三人のやりとりなど興味なさげにしていた少年にも聞こえるように。
返って来たのは「ああ」という、至極簡単な返事だけ。なのに、イリィはちょっとドギマギしてしまう。
「さ、帰ろう、ジーロ、早く早く!」
「え、あ、何、何でそんな急いで歩くのさ?」
「い、いいからっ!」
「じゃーねー、気を付けてー!」
ドギマギしてしまったことを妖精さんに気付かれれば、せっかくの友好関係にヒビが入ってしまいかねない。
イリィは出来るだけ普通の笑顔で手を振って振ってから、ジーロの手を引っ張りつつ、神殿を後にした。
イリィとジーロが帰路に就いたのをしっかりと見届けてから、アシェルはやれやれと息をつく。
「ほんっと、何だかなー」
次から次へとドタバタ続きで、落ち着いて考える暇も無かったが、自分の置かれた状況がさっぱり判らないのはアシェルも同じ。と言うか、切羽詰まっていて打ち合わせが必要なのはむしろこっちの方だ。
(ってか、ツッコミどころがあり過ぎだよ。一体どこから手を付けていいんだか。やっと二人きりになれたってのにさ・・・・・・二人っきり!?)
自分の鼓動が急に跳ね上がった気がして、アシェルは胸に両手を当てる。
(うわ、どーしよ? ってか落ち着けボク! ちょっと冷静になろうよ、今それどころじゃないんだから!)
その時だ。
背後で、どさっと何かが倒れる音。
「カリム!」
慌てて振り向いたアシェルが目にしたのは、力を失った手足を投げ出すように、横向きに倒れ伏したカリムの姿だ。
白い舞台の上に広げられていた長衣の緋色が不吉なほど鮮やかに、アシェルの瞳に焼きついた。
慌てて駆け寄ったアシェルの眼前、カリムは倒れ伏したまま、ピクリとも動こうとはしなかった。
淡い色の髪をかき上げるようにして触れた頬は、ヒヤリと冷たい。
閉ざし切らない瞼の下、僅かに覗く瞳が、光すら届かぬ深淵を思わせる。
それでも、胸に耳を押し当ててみれば、ゆっくりとした鼓動が感じられて、アシェルは小さく息をつく。
”あの時”の傷は完全に塞がっていて、見た目には何の痕跡もない。だが、負ったダメージからは、まだ回復し切れていないのだ。
(せめて・・・・・・ここに薬酒があれば・・・・・・)
アシェルは自分の両手をぎゅっと強く握り締める。
そう。この手にはまだ”あの時”の感覚が残っている。
『やあ、おはよう! キミには久しぶりになるのかな。ボクのこと、覚えてる?』
”あの時”。
何年もの時を経て。
驚きに歪む綺麗な顔を、正面から見据えた。
『ねえ、もっと嬉しそうな顔をしたら? これは感動の再会ってヤツなんだからさ。懐かしい懐かしい、キミが殺したトモダチとの、ね』
そこで笑おうと思っていた。
『ボクの望みがわかるかな? もちろん、わかるよね。そのためにわざわざ、こんな力を手に入れてまで戻って来たんだからさ』
無邪気に。あでやかに。残酷に。
『ボクにはね、必要なんだよ、どうしても。ねえ、キミの命をボクにちょうだい! いいでしょう? だって、キミはボクを殺すことで、今まで生きて来れたんだからさ』
刃のような、宣告を。
『・・・・・・アシェル・・・・・・』
苦しげに搾り出された声が、それでもハッキリと、その名前を呼んだ・・・・・・。
だが、伏せられた瞳が再び開かれた時、その蒼い瞳からも、全身からも、一切の表情が消えていた。
それはつい先刻。
アシェルとカリムがこの地で目覚める、ほんの直前にあった出来事・・・・・・。
不意に、カリムの睫が微かに震え、アシェルはハッと我に返る。
一度強く瞼を閉ざし、小さく眉根を寄せてから、カリムは薄く目を開けた。
深く蒼い瞳の中に、アシェルの小さな姿が浮かぶ。
その一瞬で、カリムの顔から造り物めいた硬質さが消えた。
「・・・・・・どれくらい寝てた?」
「五分くらいかな。ってか、寝てたんじゃないでしょ。気を失って倒れてたって言うんだよ。無防備に、格好悪く!」
「容赦ないな。相変わらず」
「そりゃーね。で、どう? どれくらい大丈夫じゃない?」
「・・・・・・そういう時は大丈夫かって聞くものだろ、普通」
「そんな風に聞いたら大丈夫って答えるでしょフツー。どー見たって大丈夫じゃない人に、ンなこと聞くほどバカじゃないし!」
どうだと言わんばかりにふんぞり返ってみたものの、アシェルの顔はすぐにまた心配げに翳る。
「キミってばホント、意地っ張りだよね。調子悪いなら悪いで、もうちょっとそれらしくすればいいものを、ヘンに格好つけちゃってさ。まさか、ボクに隠し通せるなんて甘いコト考えてたわけじゃないよね?」
カリムが本調子だったのなら、いきなり中空に投げ出されたとしても、無様に地面に転がるようなヘマはしなかっただろう。
その場に部外者二人が居合わせたところで、そんな者には目もくれず、さっさと立ち去ってしまえばいいだけのことだった。
自分の状態があまり芳しいものではないと自覚していたからこそ、カリムは当分の居場所を確保するために村人相手に交渉もしたし、アシェルの存在を隠すことなく周知させた。
「まったく、ボクが連中をとっとと追い返してなかったら、一体どうするつもりだったのさ?」
「・・・・・・その時は、その時だ」
自分の感覚を確かめるように、目の前にかざした手を握ったり開いたりしてから、カリムは身体を起こそうとする素振りを見せる。
「もう少し寝てたら。どうせ他に誰もいないし、今のところ差し迫った危険はなさそうだし」
頭の方向から見下ろすアシェルを、カリムは少し驚いたように見返した。
「何? どうかした?」
「いや・・・・・・ずっと前も、そんな風に見下ろしてたよな、お前」
「うん。何度もね」
「・・・・・・そうだったか?」
「うん。何度も!」
それは、カリムがカリムとして、アシェルがアシェルとして、目覚めたばかりだった頃のこと。
”力”を制御する訓練の毎日だったアシェルは、何の気なしに息抜きに出た先で、派手な爆発現場に遭遇した。
アシェルと同じく訓練を受けていたらしい少年は、ガタガタにめくれ上がった訓練場の床の上に、大きく四肢を投げ出して転がっていた。
『・・・・・・何だよ、お前?』
それが彼の第一声。
失敗の直後だろうに、悪びれた様子など微塵も無く。
好奇心に駆られて見下ろすアシェルを、彼は実に堂々と見上げ、自分から問いかけた。
『・・・・・・キミこそ、こんなトコに転がって何してるのさ?』
それは、少し意地悪な質問だったかも知れない。
『見て判んねーのかよ』
彼が”力”を制御し切れず暴発させたのは、見れば誰でも判ること。
『天井見ながらお前と話してるに決まってるだろ』
不敵に笑う、蒼い瞳・・・・・・。
カリムとアシェルは、そんな風にして出会った。
その後アシェルは、勝手に出歩いたことをこっ酷く叱られ、”訓練期間が終わるまでは二度と会いに行くな”と散々言い含められたけれど。
結果的に、アシェルはその言いつけを無視した。
カリムが何かを派手に破壊するのは茶飯事で、そんな時は周りの小うるさい連中もバタバタと慌しくしていたから、その隙をぬって会いに行くのは簡単だった。
そうして二言三言、他愛無い言葉を交わして、見つかっては逃げ戻って。今度会ったら何を話そうかとワクワクしながら考えて・・・・・・。
そんな日常がその先も続くのだと、疑いも無く信じていた頃。
そしていつか、自分達の”力”でもって世界の人々を幸せに出来るのだと、無邪気に信じていた頃。
カリムにとって、それは”ずっと前”の、過去のこと。
けれど、深い闇の中に閉ざされていたアシェルには、一夜の眠りに着く前の、昨日のことと変わらない。
ほんの一瞬、ほんの些細なきっかけで、世界はガラリと様相を変える。
優しかった世界は瞬時にして幻と消え去り、真実は残酷な刃となって、手にする者の心を抉る。
それを手にしてしまった時、アシェル全てを破壊し終わらせる事を望んだ。
カリムもろとも、滅びる道を。
だがカリムは、アシェルとは違うものを望んだ。
それゆえに、カリムは一人生き延び、その後もあの場所で戦い続け、アシェルはそんなカリムを激しく憎んだ。
閉ざされた闇の中・・・・・・再び目覚めるその時まで。
ボクとキミの間に何があったかなんて、語りきれるものじゃない。
時の流れは容赦なく。時を戻す術は無く。
アシェルは変わった。外見も、何もかも。取り返しがつかないほどに。
カリムも、そう、背格好こそ以前と大差無いが、短く切り揃えられていた髪は、流れるほどに長く伸びた。二人を隔てる時の流れそのもののように。
アシェルはカリムの左腕に目を落とす。短い袖の間から覗いているのは、細い金細工のアームレット。
護符でも何でもなく、どこか素朴な印象さえあるそれは、身に着けていた装備や装身具だけでなく、自分の”力”の源ですら何の躊躇いもなく手放したカリムが、たった一つ手元に残した物だ。
そんなところにさえ、アシェルの知らないカリムの物語がある。
悲しみも、憎しみも、愛しさも、真実も。
ボクの全ては、キミが持ってる。
だけど、キミの全てを持っていたのは・・・・・・。
何もかも終わらせる。今度こそ。
そのためだけに、アシェルは”あの時”、カリムの前に立った。
それがどんな形であれ。
全てが始まった、あの場所で。
なのに・・・・・・。
「ねえ、ボクたち、まだ生きてるんだよね。・・・・・・どうしてかな?」
第4話 夕凪ぎ

『あーあーあー、ちょっとフェグダ! これ聞こえてる? ちゃんと? やった! ようやく繋がったー!』
いつにも増してテンションの高い声に、フェグダは通信珠を持つ手を目いっぱい身体から遠ざける。
通りかかる者がいれば確実に振り向かれるレベルだが、幸いなことに今夜のねぐらを乞うた教会の中庭には、フェグダの他に人影は無かった。
「何だクミルか。どうかしたのかよ? 」
『何だとはご挨拶ね! このあたしが折角、超重大激レア情報教えたげよーと思ったのに、いいわけ? そんな態度でさ!』
「ほーお。お前の激レア情報ってーと、アレだ、上司のスキャンダルが発覚したか、でなきゃ例のカップルが破局したとかか?」
『あの堅物上司にスキャンダルが発覚したら、それこそ大スクープ間違いナシだけど・・・・・・じゃなくて! まったくノンキな放蕩天使様よね! てかそもそも、あんたが天使様だってのが悪い冗談なんだけどさ』
クミル言うところの”天使”とは、神話や宗教説話に登場する神の使いのことではない。
この大陸には、魔物討滅を旗印に掲げ、あらゆる国家も宗教的枠組みも超えて存在する、一大軍事組織が存在する。
その組織は、本拠地とする都の白く輝く尖塔連なる威容を以って、”白亜の塔”と呼ばれている。
組織の主力となる天軍六軍に所属し、最強の退魔法具たる”羽根”を扱える者のことを、神の僕になぞらえて天使と呼ぶのだ。
もっとも最近では、羽根を扱える者の数が減少傾向だということで、天軍六軍に所属しているだけでも便宜上天使を名乗ることが許されるようになりはしたが。
『悪かったな、こんなんが天使なんか名乗ってて! てか、イヤミ言いたいだけなら切るぞ』
『ふーん、いーのかなー? 本当にー?』
クミルは通信班所属で、天軍各隊への指令や報告が仕事だ。その合間の暇つぶしに、時々こうして雑談がてら情報を教えてくれたりする。そのほとんどが、使い道の無いムダ知識であったとしても、現地駐留部隊所属という肩書きだけは大仰だが実態は地方をフラフラほっつき歩いているフェグダにとっては、結構重要な情報源であり、天軍の本拠地である聖都との唯一のつながりだ。
幼馴染みの気安さがあるとはいえ、無下にしてしまっていいはずもない。
「スミマセン俺が悪うございました、で、何があったんだ?」
『・・・・・・ま、いーけど。ところであんた、この二日間転移門も通信珠もぜーんぜん通じなくなってたって、気付いてた?』
「あ!?」
『やっぱりねー。そーじゃないかとは、最初の一言でわかったけどサ。こっちはすっごい大変だったってのに、もう・・・・・・』
「・・・・・・それは別にオレのせいじゃないと思うんだが」
文句だかグチだかのはけ口にされかけて、フェグダは指でカリカリと頬を掻く。
「つまり、慰めて欲しかったのか?」
『そんなんじゃないわよ何考えてるのよこのおバカ! これってば白亜の塔始まって以来の一大事なんだから、ちょっとは察しなさいっての!』
いや、何百年という歴史ある白亜の塔きっての大事件と言えば、普通は、魔物と大規模戦争に突入したという五〇〇年前の伝説のことを言うだろう。
『そんな大昔の本当にあったかどうかも判んないよーな話なんかどーでもいーわよ。それより、ね、何があったか気にならない?』
「いや、ええと、まあ、少しは・・・・・・」
『あーじれったいっ! じゃあそれが災厄の天使様に関わることかもしれないって言ったら?』
「そうかよ。へーえ」
『まーた気のないフリしちゃって! あんたがこのネタに食いつかないはずないって、ちゃーんとお見通しなんだからね。どーする? ほら? 正直に言ってごらん?』
「・・・・・・はいはい、お願いします是非ともお教え下さいませクミル様!」
『はい良く出来ました! っても、実はまだ噂の段階なんだけどね・・・・・・』
クミルの話を強調表現抜きで要約すると、二日前の午後、白亜宮内で天軍第一軍に緊急招集がかかった直後から通信珠が完全に沈黙してしまい、それと同じ系統の技術による転移門までが使用不能に陥ったのだという。
それは確かに、ただ事ではない。
『でしょ? おかげで連絡しようにも一々伝令走らせないといけなかったし! 通信班はもちろん、管理部各班や、手の空いている駐留部隊まで片っ端から駆り出されて、広っろい白亜宮の中、延々走り回らされることになったんだから!』
もっともそれは完全に内部でのみ処理されて、対外的にはいつも通りの平静を取り繕っていたというのだから、さすが権威ある組織と言うべきか。
『唐突に通信珠が復活したのがつい先刻よ。そしたら直後に各地の門番に向けて”この二日の間に門を潜った者について報告せよ。可能であれば拘束せよ”って指令が下ったってわけ』
「つまり、使用不能になる前か、その間にってことか!?」
それは転移門を通常でない手段で用いた者があったことを示唆している。
もっとハッキリ言うなら、脱走者の可能性を。
「まあ、脱走天使の一人や二人、毎年この時期にゃ珍しくもないか・・・・・・」
『脱走天使なんか珍しくもない、ね。あんたにしてみれば、どうせその程度のことなんでしょうよ。世界一ノンキな天使様だもんね』
「だから、そんな突っかかることか?」
『これだから・・・・・・。あのね、脱走天使ってのはね、不可能を夢見る馬鹿の代名詞みたいなものよ!』
この世界には、様々な魔物が跳梁跋扈する。同様に、魔物に対抗する手段もまた、少なからず存在する。
退魔の能力を持つ人間、あるいは一族しかり。破魔の力を宿した武器や法具しかり。
そんな中で最強の退魔法具と位置づけられているのは、”羽根”と呼ばれる人智の及ばぬ神秘の力を宿す”物質”である。
羽根について確認されているのは、あらゆる魔物に対抗する力となり得ることと、その力を行使するには絶対の条件が存在すること。
その条件とは、羽根の所有者たる人間のみが、その強大なる力を行使することが出来ること。
羽根は、自ら選んだ人間の元にのみ出現し、人間の側がどれほど望もうと、あるいはどれほど拒絶しようと、一切の選択権は与えられていないこと。
羽根を扱うことの出来る人間が死んだ場合、羽根もまた、ともに消滅してしまうこと。
羽根は何時いかなる時に、何処へ、どんな人間の元へ出現するか、皆目予測が出来ないこと。老若男女、身分の貴賤、人種、信仰心、職業、罪の有無等、一切斟酌されないこと。
白亜の塔は大陸中の国々と協定を交わし、羽根使いが現れるや迅速に召集する権利を有している。
故に、羽根に選ばれて天使となり、世界の為に奉仕すること。それは、崇高にして名誉あることとされている。
昨日まで全く顧みられなかった者が、一躍神の御使いとして歓呼を以て称えられることもあるだろう。
だが裏を返せば、それまでごく普通に暮らしていた人間が、羽根使いであると認定された途端、今までの暮らしや家族友人の全てから切り離され、魔物と対峙する運命を突き付けられることでもある。彼らは羽根が損なわれない限り、離塔は許されない。それは”命ある限り白亜の塔を離れることは叶わず、二度と故郷には戻れない”のと同義である。
羽根を持たない仮称天使が、使命に燃えてか生活の為かの事情はともかく、自主的に天軍に身を置き、いざとなれば天軍を離れて別の人生を選ぶことも可能であるのとは、根本的に違うのだ。
となれば、故郷に家族や恋人や心残りな事情を残して来た者などは、特に毎年春の祭りの頃には、つい出来心に走りたくなるのも無理からぬことだろう。
ただし、脱走を考えるまでなら多かれ少なかれ誰もが一度は思い描きもするだろうが、実際に決意し決行するとなると、これはハッキリ別問題だ。
『だけど、思い出してもみなさいよ! あんたが放蕩三昧してたこの五年の間に、このあたしが、天使が脱走に成功したって話を一回でもしたことあった?』
「・・・・・・そう言や、覚えが無いような」
『当たり前よ。成功例なんて無いんだもの』
「そう、なのか!?」
『そーなの! ちょっと考えれば判ることよ。脱走自体も相当難しいけど、運よく逃げ出せたとして、その後捕まらないでいられるなんて有り得ないじゃない。羽根の気配は隠しようがないんだから、天使狩りに捕縛されて連れ戻されるのがオチよ』
天使狩りとは穏やかではないが、それは天軍内での揶揄を込めた呼び名であって、彼らの普段の任務は大陸全土を回って新人の羽根使いを探し出すことである。
「ちょっと待てよ! お前、最初に言わなかったか? その件に、災厄の天使が関わってるって?」
『そう、そこなのよ! 先刻判ったばっかの最新情報なんだけどね、第一軍が緊急招集される直前に、災厄の天使様と星焔(セイエン)の天使様が任地から帰還されているはずなのよ。正に、転移門を使ってね! その時偶然、白亜宮内に居合わせたっていうハウスキーパー(衛生管理班)の子が教えてくれたから、確かだと思うわ!』
「・・・・・・」
『大体、下っ端天使の立ち入りが制限される宮殿内での事件だもの。上級天使が全然関わっていないって方が、おかしいっちゃおかしいのよね。しかもそれ以来、お二人に関する仕事が来てないって、衣装部屋(主塔装備管理班)の子が言ってたから、信憑性は高いと思うのね』
相変わらずスパイ顔負けの情報収集能力だが、真に驚くべきは、それが単に好奇心とおしゃべり本能故の、女同士の噂話のレベルで遂行されているという点だろう。
「・・・・・・いや、だけど、まさか、上級天使が脱走したってか? しかも、よりにもよって災厄の天使が、だ!?」
『お二人で手に手を取って逃避行・・・・・・うっわあロマンチック!』
「何の妄想だよ・・・・・・てか、有り得ねーだろ、そんなの」
上級天使が脱走するという行為もだが、災厄の天使はもちろん、星焔の天使という最近上級に列っせられたばかりの新人も、一五、六の少年という話ではなかったか。
「これが雪華の天使ならともかく、わからん・・・・・・てか、わかりたくねぇ・・・・・・」
『雪華様がオトコとなんてダメよ絶対!』
「いや、それもどーかと・・・・・・」
『いーのよ、あんたなんかに理解出来るなんて、これっぽっちも期待ないから』
「それは良かった! だが冗談抜きで。転移門を使って脱走なんて、それこそ無理が有り過ぎだろ? どこに行こうと、門の出口には門番が貼り付いてんだ、それでバレないはずがない・・・・・・」
『だから、噂だってば、あくまでも。え? あ、ちょっと待って・・・・・・』
続いて、通信珠の向こうでクミルが誰かと話す気配。
「おい?」
『・・・・・・あ、ゴメン、仕事入っちゃった! これから”転移門のシステムに干渉しそうな遺跡や聖所を片っ端から調べろ”って、地方軍と天使狩りの全部隊に緊急連絡しなきゃなのよ! 忙しくなるから、これで切るわ! じゃね!』
「おーい?」
だが、バタバタとした余韻を残して、一方的に通信は切られた。
途端に、フェグダの周りがシーンと静まり返ったのは・・・・・・多分、錯覚だろう。
「ったく、中途半端な・・・・・・」
クミルにも、シュミを兼ねているとはいえ、忙しい任務の合間に情報をくれたわけだから、感謝するべきなのかもしれないとは思う。だが。
「いや、何も脱走説に拘るこたねーんだよな。ただのアクシデントって可能性もあるんだから」
もっとも、どんなアクシデントが起こり得るのかなど、想像しようも無かったのだが。
「ンなもん、考えたって判るわきゃないっか。で、転移門のシステムに干渉しそうな遺跡だ? 漠然とし過ぎだろ! この国限定でもどんだけあるよ? 何百、いや何千? ・・・・・・て、俺には関係ないハナシか」
頭を一振りして、フェグダは通信珠を荷物の中にしまい込み、腰かけていたオブジェの縁から立ち上がって大きく伸びをする。
春祭り前夜とあって、教会の中も心持ち慌ただしい。下手に用事を言いつけられない内に、さっさとあてがわれた部屋へ退散するのが正解かも知れない。
「災厄の天使か・・・・・・ここしばらく忘れてたってのにな・・・・・・」
歩き出しながら、フェグダはポツリと呟いた。
「ねえ、ボクたち、まだ生きてるんだよね。・・・・・・どうしてかな?」
アシェルが呟いた途端、カリムはガバッと半身を起こした。
「どうしたのさ?」
何が起こったのか掴み切れず、アシェルはキョトンと目を瞬かせる。
「・・・・・・嫌なこと思い出した」
あぐら座になったカリムは、アシェルの視線から逃れるように、ふいと顔を背ける。
「んー?」
回り込んだアシェルが横から強引に覗き込むと、カリムは実に不機嫌そうな、不本意そうな、外見相応に子供っぽい顔でふてくされていた。
「・・・・・・あ、ひょっとして、」
あることに思い当たり、アシェルはわざとニッコリ笑う。
「キミのトモダチが関係してるでしょ。あの時一緒にいた彼が何かして・・・・・・」
「そんなんじゃない! あれはただの大バカヤローだ!」
実に分かり易い、素直な反応だ。
「そーなんだー?」
「当たり前だ。・・・・・・この世で一番ってくらい嫌いなヤツを助けるためにテメーの命張るよーな奴が、バカじゃなけりゃ、何だってんだ!」
「ふぅーん?」
カリムにそんな顔をさせるとは、彼もなかなかいい性格の持ち主のようだ。
(ひょっとして、似たもの同士?)
アシェルから見れば、カリムだって他人のことは言えないと思う。本人にその自覚が無かったとしても。
「・・・・・・あの馬鹿、勝手に転移門を開いて、俺たちを突き落としやがった」
ぼそりと、だが固い声でカリムが呟く。
「転移門を、勝手に!? ・・・・・・それって、簡単に出来ることじゃないよね?」
その意味するところに思い当たって、アシェルの顔からもニヨニヨ笑いが消える。
転移門とは、白亜の塔と呼ばれる織によって管理運用されている一種の交通システムで、大陸全土を網羅し、一瞬にして目的地に移動することを可能にしている。
その仕組みは、魔道によるものとも、錬金術によるものだとも、古代の超科学によるものだとも言われているが、実際のところは塔に属する者の間でさえ”昔から存在する便利な技術である”という以上のことは知らされていない。ひょっとすれば技術部の連中でさえ、確かな原理を把握出来ているかどうか、怪しいものである。
ただし乱暴を承知で言えば、仕組みなど解らずとも確実に運用出来さえすれば、それで別段問題があるわけでもない。
が、個人の一存で何の準備もなく突発的に操作するとなると、話は全く違ってくる。
転移門の操作は決して容易くなどないし、長年にわたってかなり日常的な頻度で転移門を利用していたカリムでさえ、そんなことは不可能だろう(そもそもやろうと思ったことも無いが)。
「感心することないぞ。あの馬鹿がロクに扱えもしないものに放り込んだりするから、俺たちは転移門の中に二日も閉じ込められた挙句、こんな出口でもない場所に投げ出されたんだからな。ったく、あのまま出られなくなってたらシャレにならん」
「二日? ああ、春祭りの日から逆算したらそうなるのか・・・・・・」
転移門の中に、時間の感覚というものは存在しない。つまり、カリムとアシェルには一瞬でしかなかった間に、外界では二日が経過していたことになる。
「ねえ、ひょっとして年単位でズレてるって可能性も、無いとは言えないんじゃない?」
それがどれだけ未来だろうと、もしくは過去だろうと、二人の状況を考えれば願ったりなのだが。
「いくら何でも希望的楽観主義的推測過ぎるだろ。可能性は除外は出来なくとも、最初からアテにするわけにはいかないな」
「そだね。けど、彼がいなかったら、ボク達は今、ここでこんな風にしていられなかったのも確かだよね?」
「・・・・・・」
転移門の出入り口は通常、教会などの施設の奥で管理されており、当然のことながら組織の関係者が常駐で警護している。
まさか転移先がこんなうち捨てられた廃墟だとは、放り込まれた方にしても、門を管理する側にしても、想定外もいいところだ。
だからこそ白亜の塔に敵対した者と逆らった者が、即座の追撃を受けずにのんきにしていられるという、アシェルの指摘はもっともだ。
「しかも、それだけじゃないよね。あの時死にかけてたボクが、何のイカサマもなしに助かるなんて、万に一つもあり得ない。ボクのこの小っちゃな姿はさ、その代償じゃないのかな? キミがそのくらいで済んだのは、ボクらが負っていたダメージの差っていうより、干渉した力の質の問題じゃないのかな・・・・・・」
言いながらアシェルは、淡い色に変じたカリムの髪の一房を手にとって弄ぶ。
「只者じゃないよね、彼・・・・・・」
一般人から見れば”只者ではない”の範疇に入るカリムやアシェルから見たとしても。
「・・・・・・だから、極め付きの大馬鹿だっての。余計なことばっかしやがって」
「こだわるね、ホントに」
カリム言うところの”あの馬鹿”が何者でどんな”力”を持っていようと、あからさまに反逆者の逃亡を手助けしたとあっては、何の咎めも受けないで済むはずがない。
だが、カリムは小さく舌打ちすると、考えを追い払うように、頭を一振りした。
事が起こってしまった後で、目の前に居るわけでもない奴を相手にいくら文句を言ったところで、何が出来るわけもない。今一番考えなければならないのは、自分達の置かれた状況の確認と、これからどうするかということだ。
「それにしても静かだよね・・・・・・追っ手、来るかな・・・」
「来るだろうな、間違いなく」
ぽつりと呟いたアシェルに、カリムは当然そうに断言した。
予想外のアクシデントのせいで、一時的に行方をくらませてはいても、やはり時間稼ぎでしかないだろう。
白亜の塔は逃亡者を許さない。
ましてや、表沙汰に出来ないような都合の悪い内部事情を、これでもかというくらい熟知している者を、何の手も打たず放置するなど絶対に有り得ない。
「いつかは見つかっちゃうにしても、ここで騒ぎになるようなことは、あんまりやりたくないよね。この村の人たち、いい人だったもの。カリムのあんな超が付くほど直球なハッタリ話を、あっっっさり信じて受け入れちゃうくらい。ホーント、問答無用で出てけーって言われるとか、ボコボコにしてやるってなってたら、大変だったよねー」
カリムにしてみれば、何の算段も無かったわけではないのだが、状況によってはそちら側に転ぶ可能性も無くはなかった。
「その時は、受けて立つに決まってる」
「キミが? そんなにヘロヘロになってて、羽根も無いのに?」
「ンなもん無くたって、俺がそうそう負けるわけないだろ」
「魔物や、塔の追っ手が相手でも?」
「当たり前だ」
「どうだかなー。今のキミとだったら、ボクのが強いと思うよ。絶対!」
「・・・・・・そりゃあ頼もしいな」
「うん! それで、塔の追っ手なんかギュウギュウにノしちゃって、”許して下さいお願いします”って謝ってきたところで、樽一杯くらい薬酒を持って来させるんだ。そしたらカリムもすぐに元気になれるしね!」
途端にカリムは、本気で嫌そうな顔でそっぽを向く。
「・・・・・・あれは嫌いだ。不味い」
「そーゆう問題じゃないでしょ。だってあれが無いとこの先キミは・・・・・・」
「・・・・・・」
黙り込んだカリムの顔から、すうっと感情の色が消える。
冴え冴えとして冷酷にさえ見えるそれは、自分の心を閉ざすことに慣れてしまった者の顔に他ならない。
アシェルは、キリリと心臓を引き絞られるような痛みを覚えた。
カリムが今までどんな風に生きてきたのか、それだけで十分伺い知れる。それをさせてしまったのは、塔の連中であり、そして・・・・・・。
不意に。
アシェルはカリムの腕に引き寄せられ、抱きしめられた。
「・・・・・・カリム!?」
しっかりと、だが振り解こうと思えば出来なくはないくらいの強さで。
カリムの鼓動が、アシェルの身体に伝わって響く。
アシェルの位置からでは、カリムの表情はよく見えないが、ひどく真剣な様子であることだけはわかる。
「その時は、全部、お前にやる」
すぐ傍にいるからこそ聞こえるくらいの声で、だが、一言一句はっきりと。
「あれは、本当のことだろう?」
再会したあの時、”アシェルが生きるためにはカリムの命が必要”だと告げた、あの言葉は・・・・・・。
「だったら、構わない」
「カリム・・・・・・」
アシェルは目の前に流れ落ちる、淡い色の髪をそっと撫でた。
隔てられていた時間を何よりも語りかけている、長い髪。
(そうだったね。キミは、彼女に会うために生きてきたんだものね。彼女のためだけに、必死に生き延びようとしていたんだものね、あんな所で。・・・・・・だけど、彼女はもうどこにもいない。キミがどんなに望んだって、ボクは彼女にはなれないし、代わりにさえ、なれない)
長い間求め続けてきた大切な人が、もうこの世界には存在しないのだと知って、カリムは生きる目的を失った。
この世界に執着する理由もなくなった。
遠い”あの日”。離宮が炎に包まれ崩壊したあの日、カリムと共に果てることを望んだアシェルと同じように。
(ボクらにとって、”死”は救いのもう一つの名前。だけどあの日、キミはボクの望みを拒絶し、ボクを一人死なせてしまった。その罪悪感があったから、キミは自ら”救い”を選べなかった。今になってもまだ・・・・・・。それでキミは、立ち止まってしまったんだね。進む方向も、進むべきかどうかすら、見失って・・・・・・)
「ねえ、カリム」
アシェルは少し躊躇ってから、腕に力を込めて抱擁から抜け出すと、カリムの耳元に小さな顔を寄せた。
「もしもボクが、イリィを助けてあげてって言ったら、キミ、どうする?」
第5話 朝靄
久しぶりに、その夢を見た。
白く優美な柱に囲まれた、開放的でありながらどこか威圧的な空気の漂う空間。一度だけ、入ったことのあるその場所は、白亜宮の外縁に位置する一般謁見用の大広間だ。
フェグダはそこで、美しく磨かれた床に膝をついて控えている。高揚と不安がないまぜになった心を抑えながら。
ようやく、対面を果たせる。
幼い頃よりずっと、想像し続けてきた相手と。
その人物は、聖都で要職にあるとだけ聞かされていた。一介の者がおいそれと会える立場の人間ではないのだと。
フェグダは羽根使いとして白亜の塔の天使に加えられたことで、ようやく対面を許された。この時をどれだけ待ち望んだことだろう。
自分自身の鼓動が、耳をつんざくほどにも大きく響く。
そんなフェグダの前に、一人の男が現れる。黒を基調にした長衣を纏い、一段高い所に立ったまま、跪くフェグダを睥睨する。そのフードの奥から覗く目を見た瞬間、ぞくりと冷たいものがフェグダの背筋を駆け上がる。
心の中だけでなく、世界の全てが急速に色を失い冷えて行く感覚。
自分が何を言ったのか、男が何か一言でも返したのか、あまりよく覚えてはいない。
すぐにでもこの場を駆け去ってしまいたい衝動と、凍りついたまま指先さえ動かすことの出来ない焦りの間で、どす黒い憤りが湧き上がる。
目の前に存在する男に対して。否、愚かにも甘い夢を抱き続けていた自分自身に対して。
不意に。冷たい重圧がふっと軽くなった気がして、フェグダは睨み付けていた床の模様から視線を上げた。
男が、どこか高い所を見上げている。
その視線を追った先。
等間隔に並ぶ柱ごしに仰ぎ見た隣接する建物の外回廊に、一人の少年の姿があった。
遠目ではあったが、フェグダとそう変わらない年頃だったろう。
有り得ないくらい白い肌に、整った顔立ち。その身を包む、鮮やかな緋色の装束。黒曜石のように陽光を弾く長い髪を頭上で一つにきりりと束ね、傲然と頭を上げ前だけを見据え、自信に満ち溢れた足取りで歩を進めていく。
背後にかしずく従者どもや、慌てて左右に退き平伏する者どもに、一瞥さえくれることなく。
少年が進むにつれ、その背に負ったものが顕わになってくる。少年の背丈ほどもあるような、大振りの曲刀が。
羽根使いであるフェグダには、それが並外れて強大な羽根の力を具現したものだと判った。
だが、秀麗過ぎる出で立ちよりも、凶悪そのものな武器よりも、圧倒的で鮮烈だったのは・・・・・・氷の刃のように冴え冴えとした眼差しだった。
何も映さず、何も留めることなく。
あれは、一切の他者を寄せ付けない、孤高の冷徹さ。救いや加護を求めてはならない、断罪の剣そのものだった。
少年が現れてから回廊の奥に見えなくなるまで、おそらく一〇秒も無かっただろう。たったそれだけの僅かな時間。、
だが、あの瞬間目にした少年の姿は、フェグダの心の中に今もハッキリと焼きついている。
あの男が少年に向けた、自分には決して向けられることのない真摯な眼差しとともに・・・・・・・。
この世界には、比べることさえ愚かしい、絶対的な差というものが存在する。
あの日フェグダは、自分がいかに価値の無いただのガキでしかないことを、嫌と言うほど思い知らされた。
フェグダが辺境勤務に配置替えされたのは、その謁見から程なくのことだった。
その理由は、今もって不明だ。
(ったく、何て夢見だよ・・・・・・)
苦いものを振り払うように、フェグダは井戸から汲み上げたばかりの冷水で、乱暴に顔を洗う。
(あれからもう五年になるのか・・・・・・。塔のお偉いだか何だか知らねーが、あんなのが俺の親父だなんて、絶対に有りえない。じーさんの思い違いだ。そうに決まってる。あんな奴が誰に感心を持っていようと俺には関係無いし、どうだっていいんだ、下らない。そんな些細な理由で、他人のことを気にするなんて、馬鹿らし過ぎる・・・・・・)
一夜を借りた教会の裏庭。
いつもは朝の遅いフェグダにしては、既に旅装も荷物も整えて、今すぐにでも出立出来る格好だ。が、使い込まれたタオルを握り締めたまま、フェグダは空を仰いだ。
あの少年の正体を知るのに、大した時間はかからなかった。
白亜の塔には、上級の位を与えられた、十人にも満たない特別な天使がいる。
”日輪の天使”や”暁虹(ギョウコウ)の天使”などの称号を戴き、並の羽根使いなど足元にも及ばない強大な力を自在に操ることの出来る、稀有なる存在が。
天軍の先頭に立つ彼らの活躍は塔の公式発表として宣伝され、彼らを題材とした歌劇は旅芸人らによって大陸各地へと伝えられ上演される。そして時には、神の使者として敬愛され崇められるのだ。
市井の人々が抱く天使様のイメージとは、フェグダのようなただの一兵卒ではなく、正に特別な彼らのことに他ならない。
少年は、そんな特別な存在の一人。”災厄”という呼び名で畏怖を集める上級天使だ。
あの日以来、フェグダは上級天使のことを調べ始めた。そうせずにはいられなかった。
だが、塔に所属するフェグダにさえ、大々的に宣伝される強く美しく華やかなイメージ以上のことは、ほとんど何も判らなかった。
それもそのはず。天使であっても主塔で側近くに務めるか任務で同行を許されるかした者でなければ、上級天使と間近に接する機会など無いに等しい。せいぜい年に一度の式典の折に遠くから眺めるのが関の山。知ろうとすればするほど、とんでもなく遠い世界の存在だと思い知らされるばかりだ。
その一方で、多分に脚色を含んだ噂話には事欠かなかった。
白亜宮の最上部で王侯貴族のような暮らしをしているとか、幼少の頃より特別に養育されるのだとか、塔の秘術で不老不死を得ているとか、聖人のように奇跡によって人を救う力があるとか。
あるいは、羽根使いを対象にした資格審査が毎年秘密裏に行われているとか、魔物千匹を倒せば誰でも資格が与えられるのだとか、闇の闘技大会で上級天使を倒した者が新たに成り替わるのだとか・・・・・・。
そんな中でも一際異彩を放っていたのは、やはり災厄の天使に関する噂だ。
常識で考えれば塔が虎の子の上級天使に不吉な名をつけるはずはなく、災厄あるいは凶兆というのは通称である。それでも不吉な名を冠されるには、やはりそれだけの理由があった。
どこまで本当なのかは知らないが、味方であろうと一切顧みられることなく平気で見殺しにされるとか、従者など捨石同然に扱われるので随行して無事生還出来ればかなりの幸運なのだとか、魔物討滅のためには街一つ破壊し尽くすことも厭わないとか、およそ天使についての評判だとは思えない逸話は枚挙に暇がない。そんな悪評のある者がよく何事も無く天使を名乗っていられるものだと感心したくなるほどだ。
もちろん、そんな噂が天軍外で囁かれることは無い。
それでもあの日から五年が過ぎ去った。辺境部隊に配属されたことで聖都を離れたフェグダは、クミルから時々聞かされる話以上には新しい情報を仕入れる機会もほとんど無くなり、他にやらなければならないこともあって、災厄の天使の名はあの男の存在と共にいつしか頭の片隅へと追いやられてしまっていた、はずだった。
(なのに・・・・・・よりによって逃亡だと? あの災厄の天使がか?)
上級天使に関する噂の大部分が眉唾なのだとしても、全てが根も葉も無いわけではない。例えば、本塔管理官として長年仕えていたという門番のオヤジから聞いた、「強大な力を誇る上級天使が塔に服従しているのは、塔の秘術なくしてはそう長くはいられないからだ」という、あの話。
羽根の力を引き出すには羽根使いの精神力、ひいては生命力が必要不可欠なのだが、その理が上級下級に関わらず不変であるのなら、強い力を引き出すには相応の代償を課すことに他ならない。
フェグダの羽根使いとしての実感としても、そこには一抹の信憑性が潜んでいるように思える。
(だとすれば上級天使が、しかもあの災厄の天使が脱走したかも知れないなんてハナシ、デマかデタラメのどっちかなんじゃないか?)
至高の存在である自身の全てと引き換えにしてでも手にしたいものが、あの冷徹な眼差しを持つ天使の中にあるなどと、一体どうして信じられるのか。
(あるわきゃねえ。あの目の中には、きっと何者も存在しやしない・・・・・・)
フェグダは思い出したように、既に乾きかけた顔を、手にしたタオルでゴシゴシと擦った。
その日、いつも以上に早起きして超特急で家の用事を済ませたイリィは、朝食もそこそこに家を飛び出した。
お母さんはそんなイリィの様子を不思議がったが、お祭りの準備があるからという言い訳に納得してくれたようだった。
そして、イリィが勇んで向かった先は当然、アシェルとカリムが居るはずの遺跡である。
「あの、おはよ・・・・・・!」
はやる心を抑えつつ、ホールの入り口からそおーっと覗きこんで声をかけた瞬間。
「おっはよイリィちゃん!」
「きゃあっ!」
胸の辺りをどーんと勢い良く強襲されたイリィは、危うくひっくり返りそうになってたたらを踏んで、偶然肩に触れた壁を支えにして何とか転倒を免れた。
「どしたのイリィちゃん、こんな朝早く?」
悪びれもせず至近距離から見上げているのは、赤い髪の妖精さん。イリィに遠慮ない体当たりをかました張本人だ。
「お、おはよ、アシェル」
ばくばく言う心臓を宥めすかしながらアシェルに挨拶を返したイリィは、もう一人の姿を探してホールの奥に目を凝らした。が、そこに人影らしきものはない。
「今、ちょっとガッカリしなかった?」
「そ、そんなことないっ!」
「ふうーん?」
「本当! 絶対ほんと!」
疑わしそうな目を向けるアシェルに焦ったイリィは、大急ぎで違う話題を探す。
「あ、そだ! 食べ物とか服とか持って来てみたんだけど・・・・・・」
「ええっそうなの? 見せて見せてっ!」
途端にアシェルは、緑色の瞳をキラキラと輝かせる。
コロコロと表情を変えるアシェルは、見ていて可愛いと言うか、妙に憎めないものがある。
イリィは家から大事に両手に抱えて来たものを差し出そうとして、けれど今その位置におさまっているのは他ならぬアシェルであって・・・・・・。
「あ、あれ?」
ぶつかられた拍子に、どこかに飛んで行ってしまったらしい。
慌てて周りを見回したイリィは、自分の斜め後ろにぽってりと転がったバスケットを発見する。大き目のナフキンでしっかり包んであったので、中身が散乱する事態は避けられたようだ。
「良かった」
イリィがバスケットに手を伸ばすよりも、イリィの肩ごしにそれを目にしたアシェルが飛び出す方が早かった。
「これだね! わーあ、かわいい!」
素早くナフキンを解いたアシェルが真っ先に取り出したのは、イリィが散々迷った末に思い切って持って来ることにした、レモン色の古いブラウスだった。
「それ、私が小さい頃に着てた物なんだけど、もしかしたらアシェルに似合うかもって思って・・・・・・」
だがイリィが危惧した通り、いくら子供サイズといえども、子供よりもっと小さなアシェルにとってはダブダブのドレスサイズだ。
「ありがとうイリィちゃん!」
それでもアシェルは本当に嬉しそうに、ブラウスを胸に当ててながら、ダンスのステップを踏むように宙でクルリとターンしてポーズを決める。
古着にそこまで喜ばれると、何だかかえって悪いような気になってくる。
「ところでさ、今日はジーロは一緒じゃないの?」
「え? ええと・・・」
急にジーロの話を振られて、イリィは少し視線をさ迷わせる。
「今朝はまだ見かけてないけど・・・」
そもそも、いつもジーロの方が呼びもしないのについて来るのであって、イリィから誘いに行ったことなど一度もない。
が、大体のことは想像出来る。昨日の騒ぎのせいで両親に叱られた挙句、外出禁止のお仕置きを言い渡されて、今頃はふて腐れていることだろう。
「イリィちゃんは? 叱られたりしなかった?」
ようやくイリィは、アシェルが昨日の件を心配してくれていることに気がついた。
「私は大丈夫。お母さんには黙ってたから」
昨日の一件を正直に言ったが最後。お母さんは心配のあまり、イリィを家に閉じ込めてしまいかねない。
「あーなるほど。バレないで済むなら、それに越したことないもんね」
事情を知らないアシェルは別段気にした様子もなく、イリィに同意するようにうなづいた。
「あ、それとね、これ・・・・・・」
それ以上突っ込まれても困るので、イリィは違う方向に話を振る。
「お菓子を、その、焼いてみたんだけど・・・・・・」
「ええっ! そうなの? 見せて見せて!」
キラキラおめめで期待しているところ申し訳ないが、単に練った小麦粉に刻んだドライフルーツを混ぜて焼いただけの、簡単な焼き菓子だ。
焦がさないようにかまどの前で真剣に見張った甲斐あって、焼き加減だけは悪くないと思うのだが。あまりにも素朴すぎて「何コレ本当にお菓子なの?」とか言われてしまったらどうしようなどと、今頃になって心配しつつ、イリィは小さな包みを開ける。
「わああ! 美味しそーう! 嬉しいなー! あ・・・・・・と」
アシェルは味見するかどうか迷うように焼き菓子の上で手をひらひらさせたが、ふと何かに思い当たったように、小さな手を引っ込める。
「あの、どうかした?」
やっぱり不味そうと思われたのかと、イリィは再び不安に襲われる。
「カリム・・・・・・早く帰って来ないかなぁ」
「あ・・・・・・」
この場にカリムがいないことを、アシェルも気にしているのだ。
「あ、そだ! 食べ物だったらそこにもあるよ。イリィちゃんもどう?」
アシェルが指差したのは、昨日イリィが隠れるのに使った大振りの岩のある方向だ。見ると岩の平らな面をテーブル代わりにして、上等のパンや肉やハチミツ漬けの果物などが、きちんと綺麗に並べられている。どうやら村長の家の、祭り用のご馳走の一部のようだ。これに先に気がついていたら、イリィ自作の焼き菓子など、到底披露出来ないような。
「昨日、あれから、お供えみたいに持って来られちゃってさ。何かボクたち、神様扱いされちゃってるみたいだよ? カリムはぶどう酒が美味いって喜んでたけどね。ねえ、一緒に食べていかない?」
「え、でも・・・・・・」
綺麗に並んだままだということは、ほとんど手付かずなのではないだろうか。いくら美味しそうだからと言って、それをイリィが貰ってしまうのは、あまりにも申し訳なさ過ぎる。
「それで、その、カリムはどうしたの?」
イリィはやっと、当初からの疑問を口にする。
「さあ? そこらを見回って来るって先刻出てったきり。イリィちゃんこそ、来る途中見なかった?」
「ごめんなさい、全然気が付かなかった・・・・・・」
そもそもイリィは、二人とも遺跡の中に居ると思って、わき目も振らずに道を登って来たのだ。もし遺跡の近くに誰かがいたとしても、あれでは気付きすらしなかったかも知れない。
「まあ、遠くには行ってないだろうし、放って置いたってそのうち帰ってくるでしょ・・・・・・」
元気なアシェルにしては、何だか少し・・・・・・。
「あの、カリムさんと何かあった?」
好奇心に負けたイリィは、恐る恐るその質問を口にする。
「えっと、何でかな?」
不意の問いかけに、アシェルは思わず目を見開く。
「だって、声がちょっと、元気なさそうだったから」
イリィはすぐに、違ってたらゴメンと付け加えた。
(そういえばイリィちゃんって、人の声には敏感だったっけ。おっとりしてそうで、意外に嘘やハッタリの通じないタイプかも?)
僅かに思案してから、アシェルは心持ち真面目モードになって、イリィに向き直った。
「ねえ、ちょっと相談したいコトがあるんだけど、聞いてくれる?」
「ええっ私なんかに? 相談って何を・・・・・・」
「・・・・・・あのね。イリィちゃんくらいの女の子に相談って言ったら、恋の悩みに決まってるでしょ」
当然のごとく答えたアシェルだったが。
「えええええっ!」
「ええっ? そこ驚くとこ!?」
イリィときたら、本気でオロオロしている。
(あーあ。ここにも一人、問題児がいたか・・・・・・)
アシェルは今度こそ、大きなため息をついた。
「ああ? っかしーなー。道、間違えたか?」
街道へ出る道順は、フェグダが教会を辞す時にしっかりと聞いたはずなのだが。
路地をいくつか折れた先は、整然とした石畳の街道ではなく、石の間に雑草の生えだしたような海際へと続く旧街道だ。
「まあ、アレだ。整備の行き届いた街道だろうが、海沿いの脇道だろうが、次の街まで続いているには違いないけどな」
ただちょっと、街道ほどには歩きやすくなくて、便乗させてくれそうな乗合馬車が通る可能性が格段に低くて、ぐるりと岬を回る分大幅に回り道になるだろうことくらいなもので・・・・・・。
「たまには気分を変えて面倒なコトをしてみるのも一興だし、ついでに昨日の酔っぱらいのオッサンが言ってたショボい遺跡とやらに寄り道するのも悪くないよな! 遺跡探しでここまで来たって目的を忘れるトコだったぜ。災厄の天使とか関係なく。そう、それだけ。単にそれだけのことだ。クミルのアホな妄想を真に受けたとか、そーゆーのじゃないぞ、断じて!」
誰に問われたわけでもないのに、言い訳じみたことを呟いてしまっているのも、きっと、気のせいだ。
(それに・・・・・・無断で転移門を通ったヤツがいたとして、それがホントのホントに災厄の天使と関係があったとしてもだぞ? 俺が行き当たりバッタリに歩いて偶然かち合う確率なんて、石投げて星に当たるより低いんじゃねーの? それこそが正しい真っ当な常識ってもんだよな!)
運だけで何とかなるほど、人生甘いものじゃない。それはよーく解っている。
だが、もしも。
もしもそこで思いがけない何かに行き当たることがあるとすれば、それはこの上ない悪運か、でなければ限りなく作為に近い偶然か、それこそ人智を超えた存在のタチの悪い悪戯のせいに違いない。
幸運を信じる程、フェグダはもう幼いこどもではない。
が、悪運は時と場所を選ばずに不意打ちを食らわせてくるからこそ、この世界は侮れないのだ。
第6話 波紋

イリィがバスケットを抱えてわき目も振らずに丘を駆け登って遺跡に辿り着いた、その少し前。
カリムは一人遺跡の外へ出ると、早朝の冷たい空気を吸い込んだ。
潮の香を含む風が、無造作に束ねた髪を穏やかに揺らしながら吹き抜けていく。まるで地を這う者どもに、春の到来を知らしめようとでもするように。
あれから一晩休むことで、大分支障なく動けるようになりはしたが、実のところそれだけ回復したというより、その状態に慣れてきたという方が正しかったりする。
痛みや疲労感とは少し違う。腕を持ち上げるなど普段何気なく出来るはずの動作に、いちいち”腕を上げろ”と意識するような、そんなもどかしい感覚だ。重装歩兵用の装備一式を、がっつり身に着けて動いているカンジとでも言のが近いだろうか。気分的に。
(まあ、あれだけのダメージ食らってこの程度で済んでるならマシな方か。別に今回が初めてでもないしな)とは、アシェルに知れればどんな顔をされるか予想出来るので、絶対に言わない。
それよりも、昨夜ほどくつろいで休めたのは、カリムには初めてのことだったかも知れない。
何しろこれまで居た場所ときたら、自室だろうが街中だろうが関係なく、呪符やら結界やらが大盤振る舞いに張り巡らされていて、常に苛立たされっぱなしだったのだ。
まったくあれは、イヤガラセとしか思えない。そこまで徹底しなければならないとは、一体何を隠匿しているのやら、だ。
とにかくそんな場所に比べれば、今のこの平穏は、どれほどかけがえのないものか。少しくらいの不調など、全く大したことではない。
小高い丘の上に、その遺跡は鎮座している。遺跡の後背に当たる東側は、なだらかに山の稜線へと続き、正面にに当たる西側には緑の牧草地が広がっている。牧草地を下って行けば、畑地の中にぽつりぽつりと民家の屋根が点在している。細長い平地に沿った、細長い形の村だ。
遺跡から村までは、精々低い雑木が生える程度の斜面だが、それでもある程度の起伏があるために、村の全景を見渡すことは出来ない。それはとりもなおさず、村から遺跡を見上げたとしても、屋根部分が白い岩のように見える程度のものだろう。
村の方からは、祭りの前のそわそわした雰囲気が伝わってくる。家の中では既に人々が忙しく動いているのだろうし、広場になった辺りには飾り付けられた櫓のようなものが建てられているのが見える。餌を求める家畜の蹄の音さえもが、心なしか浮かれているように思え得る。
そこにあるのは、ごくありふれた平和な光景だ。
だが・・・・・・と思いかけて、カリムは苦笑する。
一見当たり前のような風景に潜む魔を炙り出し殲滅することが、これまでのカリムの常だった。塔以外の景色を見る時は、何らかの任務を帯びてであると決まっていた。
なのに今は、塔の外に在りながら、誰に何を求められているわけでもない。そう考えれば、何だか妙な気分だ。
村の向こうは、おそらく崖にでもなっているのだろう、急にぶつりと切れ込んでいて、陽光を反射して青くきらめく海が浮かぶように広がっている・・・・・・。
昨日の村人らの言葉や風体から大体想像はしていたが、やはりここはロアーナ国の南部と思って間違いないだろう。
大陸西南端の、海に突き出た大きな半島に位置する、温暖で豊かな国だ。王の直轄領と十五貴族の自治領から成っており、半島の付け根に当たる北部が交通の要衝で交易が盛んであるのに対し、南部は主に豊かな農村地帯として知られている。半島の西側は、海に面してはいても浜や港に適した地形はそれほど多くない。
かつては古代帝国の版図であったとも言われ、国土全体に名も知れぬ神々の遺跡が多数点在しており、土着の伝説も数多い。
そんな土地柄であるからこそ、唯一神の信奉者が多数を占めている一方で、農耕の神や戦いの守護神など古来からの土地神も共存しているような懐の深さがある。村人から見れば、貴族も異国人も妖精も魔物も、自分達とは違う存在だという意味では同列なのかも知れない。
とまあ、その程度の予備知識があったからこそ、村人との交渉にも余裕を持って対応出来たのだが。
カリムは改めて、背後の遺跡を振り仰ぐ。
今は崩れかけているものの、元はなだらかな曲線を描いていただろう白い壁面が、丘の斜面に沿うように延びている。
壁沿いには2メートル幅くらいの白い砂地が、整地された小道のように続いている。その様子は、石畳だろうが壁だろうがものともせずに生い茂るはずの雑草が、遺跡を畏れて避けているような印象で、ガタガタになってしまった壁よりもよほどしっかりと聖域の範囲を主張している。
神殿の建築時に何か特別な技術が使われたのでなければ、遺跡に残された僅かな力がそんな風に作用しているのだろう。
だが、それだけだ。
白い砂地からしっとりと朝露を含んだ下草の上へと境界を越えて足を踏み出してみても、素足に感じる感覚以外、これと言っておかしなものはない。
そのまま壁に沿って白い道を辿って行くと、遺跡の正面入り口と思われる門があり、さらに進んで丘の勾配が強くなる辺りで壁は裏手へと切れ込んで、山の斜面にぶつかって終わっていた。その唐突感は、当初からの設計ではなく後世に何らかの事情でそうなったのかも知れないが、今となっては知りようもないことだ。
それよりも重要なのは、もしも敵が現れた場合、どう備えておくかということだ。相手が人間であれば、遺跡の裏手に回り込むようなことは出来そうにないが、天軍や魔物はその限りではない。もしも裏手に何らかの気配を感じたならば、それが難敵である可能性は限りなく高い。
もっとも、少々派手なことをやらかしたところで村人が巻き添えになることは無いだろうから、いっそ裏手から攻め込まれる方が対処しやすいかも知れないが。
(いや、今更だがな。俺たちがここに留まっていること自体・・・・・・)
頭を一振りし、来た方へと踵を返そうとしたところで、カリムは不意に微かな気配を感じて立ち止まった。
(水の・・・・・・?)
水音と言うより気配に近いような微かな音を頼りに、壁の割れ目の一つに身体を滑り込ませると、その先は10メートル四方程の部屋に通じており、四角く区切られた床の中央からふつふつと小さなさ泉が湧き出していた。
(砂の遺跡に、湧き水・・・・・・ね)
これも遺跡の力が何らかの作用を及ぼしていると見るべきだろうが、危険なものは感じられない。危険ではないことが、イコール好ましいであるとは限らないが。
ためしに泉の縁にかがんで片手を浸してみると、雪解け直後の氷水のような冷たさだった。
そんな痛みを覚える程の冷水に、カリムは豪快にも頭をざばっと突っ込んだ。
キンとした冷たさが快い。どこかシャッキリしない感覚を覚ますにはちょうどいい。
水から上げた頭を振ると、水滴が盛大に舞い散って、たちまち全身ビショ濡れになる。
(アシェルが見れば何と言うかな)
何気なくそんなことを考えて、カリムは少し目を伏せる。
湧き出る水の波紋と、カリムが作った無数の波紋が重なり合い、漣となって水面を揺らす。
きっかけは、ほんの些細なことだった。
持って来られた酒や料理などの”お供え”と一緒に、男性用の衣服の一揃いがあった。
村人と対面した時のカリムのあの格好では、そのくらいの気は遣われても、まあ当然ではあるだろう。
だがそれは特別な儀式や行事などに用いるような上等の正装で、横方向に貫禄のある村長本人ではなく、その身内の誰かの晴れ着用にとあつらえられた物らしかった。
カリムはそれを着ることに、抵抗を覚えた。
確かに、自分が今まで身に着けていた物がかなり高価な部類であることは理解している。だがカリムがそれを纏うには、相応の意味があった。
丈の長い上衣に使われていた服地は、丈夫な素材をさらにしっかりと織り上げた特別製で、ちょっとやそっとの武器では簡単に貫けないような代物だったし、縫い取られた紋章や装飾めいた防具には護符の意味がある。
色は何だっていいのだが、やはり濃い物の方がある種の汚れが目立たたない。それで見た目が派手になるのは、これはもう、諦めるしかない。
とにかくそれはカリムにとって、任務に当たる上で必要な物だった。
それは塔を離れた今となっても、戦うことを念頭に置く以上、汚したり破いたりに気を遣わなければならないような身を飾るだけが目的の衣装を纏うことには、どうしても納得がいかないのだ。そんな風に不承不承で袖を通すのは、その衣装を着るはずだった者に対しても、その服を仕立てた職人に対しても申し訳ないだろう。
出来れば農作業用の古着を譲ってくれと頼みたいところだが、昨日のあの演技の後では、そういう我がままを言う訳にもいかない。
それならいっそ、少しばかり痛んでいるとしても、元のままでいた方がマシ。
だが、アシェルはそうは考えなかった。
『何言ってんのさ、それでいいワケないじゃない! この衣装はね、村長さんの好意の表れなんだから無下にしないで、ちゃんと受け取りましたって身に着けるのが礼儀ってもんだよ! なのにそんなの要らないって言っちゃったら、村長さんはカリム用にもーっと高価なのを新調しなくちゃって思うに決まってるでしょ! それに、そもそも装備品なら乱暴に扱っていいなんて考え方が間違ってるよ。作り手はね、どんな用途で着るにしたって、着る人に喜んでもらえるよう一生懸命作るものなの! それは贈り手も一緒! そこんとこ、よーく考えなよね!』
そういう発想は、カリムにとっては新鮮なものだった。驚きと言ってもいい。思わず称賛の声を上げてしまうほどに。
『アシェルは服に詳しいんだな』
だがアシェルは、カリムのその一言に、思いきりムッとした顔をした。
『まったくもう、キミってヒトは・・・・・・』
不機嫌に黙り込んだアシェルは、それ以上何を言ってもツンとしたままで、カリムは困惑する以外なかった。
一体何が気に障ったのか。いくら考えても解らない。
そんなわけで、カリムの現在の出で立ちは礼服の内着に当たるクリーム色の上下で、それが最大限の譲歩だったりするのだが、アシェルの反応はクール過ぎるままだった。
だがそれ以上に解らないのは、やはり昨日のあの一言だ。
『もしもボクが、イリィを助けてあげてって言ったら、キミ、どうする?』
もちろん、カリムは即座に何故かと問うた。
だが、アシェルはただ、笑ってみせただけだった。
あの娘のの様子や村人の態度を見ていれば、両者の間に何らかの事情があるだろうことは、カリムにだって察しがつく。
アシェルはあの娘のことが気に入ったようだし、色々と同情的だ。
が、それがアシェルが助けを頼む理由になるとは思えない。
(大体、何をどうすれば助けることになるんだ?)
あの娘が何者かに狙われてでもいると言うのなら話は簡単だ。そういう状況なら、いくらだってシミュレート出来るし、対策だって立てられる。
だがアシェルが言うのは、どうもそういうことではない気がする。
(アシェルのことが大切だ)
強く、強く、そう思う。
アシェルはいつだって、どんな闇の底でだって、カリムを見つけて手を差し伸べてくれる。
それなのに、カリムはアシェルに何も出来ないどころか、いつもひどく傷つけるようなことばかりしてしまう。
もう二度と、アシェルを傷つけるようなマネはしたくない。アシェルのためになるのなら、何だってしようと思うし、今の自分になら出来るはずなのに。
どうすればいいのか。
こんなに近くにいると言うのに、その程度のことすらままならない自分がもどかしくてたまらない。
カリムは今までずっと、何も見ないように、考えないようにしてきたから。
だから今になって、そのツケが回ってきている・・・・・・。
湧き出る水が生み出す波紋が、僅かに差し込む陽光を反射し、静かに燃える炎のように室内を満たしていく。
あやなす光と、影。
水の湧き出すささやかな音は、次第に空間全体に響く旋律と化し、溢れ出す旋律は意味を持つ音の羅列へと変化していく。
(・・・・・・そりゃあそうだよ。君はただの”力”の器。強大な力の為の、形の綺麗なだけの容れ物)
(出やがったか)
それはカリムにとって、ものすごく聞き覚えのある声だ。
(だから君の中には、力以外のものが満ちることはない。心も時も留まらず、ただ風のように行き過ぎるだけ。そんなものに、他人の何が解るというの)
泉の水面に、ゆらゆらと反射し折り重なる光と影。その陰影が、徐々に一つの像を結び始める。よく見知った者の姿を。
(煩いぞ!)
カリムの瞳に、鋭いものが過る。
ビシッ!
弾かれた水面が激しく波打ち、結びかけていた像がぐにゃりと揺らぐ。
(酷いなあ)
だが、それは一瞬のこと。
湧き出す水が乱れた流れを押し流し、水面から天井へ壁面へと次々に跳ね返った光の陰影は、再びゆるゆると人影を浮かび上がらせる。
(いきなり攻撃するなんて、恩人に対してあんまりじゃないですか? 本当の事を言ったのが、そんなに気に障りましたか?)
どこか間延びした、本音とも冗談ともつかない喋り方。記憶の中のあの馬鹿のものと、それは寸分違わない。
(何が酷いものか。ここはお前の支配する呪術空間だ。この程度の波風など、イヤガラセにもなりやしない)
苛立ちを隠そうともせず、カリムは目の前の幻影を睨み付ける。
(体大、助けてくれなどと誰が頼んだ。勝手に手前の独善を押しつけやがって。恩人だと? 冗談じゃない! お前が幻でなかったら、この手で斬り刻んでやれたものを!)
(怖いなあ)
とは全く思っていない顔で、あの馬鹿の幻が笑う。
(それを言うなら、お互い様ではありませんか? 自分勝手な都合で災いを振りまいて歩くヒトに、文句を言われる筋合いなんてありませんよ)
(ああ?)
(トボけるつもりですか? 君がイリィさんを利用して村人に取り入った件についてですよ)
追い詰められた目をしながら、どこにも縋る先を見出せないでいた少女。気紛れで差し出した手を、信じられないものを見る目で見つめていた少女。
(困っていそうだったから、手ェ貸してやった。それが気に入らないってか)
(自分がではなく、”大いなる御手”なんかのせいにして、ね)
それは一般的には唯一神そのもののを指す言葉であるが、神々を信じる者には主神あるいは一番信奉する神を指す。それを持ち出すことによって、イリィとの出会いだけでなくカリムとアシェルの来訪さえも、人知を超えた存在の導きによるものだと示唆出来る。
(君が村長と交わした約束にしても、同じことでしょう。彼らの平穏主義をいいことに、わざと手の内を隠したまま約定を交わしましたよね)
見るからに只人ではないカリムを前にした瞬間、村人の顔に浮かんだものは、触らぬ神に祟りなしの事なかれ主義。
(あいつらは見知らぬ脅威を排斥するための労力とメリットを秤にかけ、争いで村に被害が出ることよりも、黙認しても面目が立つような言い訳を欲した。なのに俺だけを糾弾するか)
少なくともカリムは嘘など言ってはいない。最低限のことしか語らなかっただけ。それで彼らが何を想像するかは、彼らの自由というものだ。
(ふうん。わざと誤解させるよう仕向けておいて、開き直りますか。では聞きますけど、君は村に仇なさないと言っておきながら、天軍の到来や魔物の襲来を予期している。君自身が災いの種であることを自覚していながら、敢えて約定を交わした。それは卑怯ではないんですか)
カリムが約束したのは、カリム自身が村に敵対行為をしないこと。
だが、天軍は遠からずカリムを探し当て追捕にかかるだろう。それに対してカリムが応戦するならば、村に災禍が及ばないはずがない。
それでも天軍だけならまだマシだ。彼らは少なくとも村に被害が及ぶような手段を、積極的には選択しないだろうから。
しかし魔物の方はそうはいかない。
彼らは天軍ほど躍起になってカリムを探してはいないだろう。が、カリムはこれまでに相当、彼らの恨みを買っている。こんな辺境の地に単独で居ると知れようものなら、見過ごされるはずがない。
しかも魔物は人間に遠慮するどころか、嬉々として殺戮に走るなり、便利な手駒として使おうとするに決まっている。
どう転んだとしても、カリムはこの地に争いを呼び込むことになる。
(それでも君は、”大いなる御手”とやらのせいにするつもり? 自分には関係ないと、知らんふりするつもりなの?)
(・・・・・・)
(まあ、どうでもいいことだよね。君に関わることで他人がどうなったって。君は今までずっとそうしてきたんだから。何も考えることなく、権力の言いなりで力を振るうだけの、空虚な器でしかないんだから。君の心なんてただの虚像だ。君の抱く感情なんて、ほんの一時吹き過ぎる風のようなもの。通り過ぎてしまえば、後には何も残りはしない。だったら、ねえ、君の価値は、一体どこにあるんだい? この村を災厄に巻き込んで許されるだけの価値が、君のどこにあると?)
(・・・・・・それが言いたくて、こんなまどろっこしい真似をしやがったのか。ったく、いい加減にしろよ。この程度の揺さぶりで、俺がどうにか出来るとでも?)
その瞬間、ざわりと空気が不穏に蠢く。水面に全く変化の無いまま、幻像だけが波打つように大きくブレる。
(茶番には飽き飽きだ。今更教えられなくとも、俺が何者かくらい、俺が一番知っている。それをあの馬鹿の姿でいつまでもごちゃごちゃと。本当に目障りだ。お前こそ、さっさと正体を晒したらどうだ? それとも他者の姿を借りてしか喋れないような腰抜けか? だったらお前には、心を止めるほどの価値すら無いな)
(・・・・・・)
(どうする? このまま一戦交えるとしても、俺は一向に構わないが?)
苛烈に光る蒼い瞳が、幻像だけでなく空間の隅々までをも薙ぎ払う刃のように細められた。
第7話 幻影
「やっぱり女の子はこうでなくっちゃね!」
「あの、もうこれくらいでいいんじゃないかって・・・・・・」
「何言ってるのさ。こーんなツヤツヤで、こーんなすべすべの綺麗な髪なんだよ! 手入れもしないで放っとくなんて、もったいなさすぎ!」
「ええと、してないなんてことは・・・・・・」
「そんなんじゃダメ。全然足りない。ボクがお手本してあげるから、黙ってじっとする!」
遺跡のホールのど真ん中。
舞台の上に立ったアシェルは、往生際が悪くそわそわしているイリィの頭を両手で押さえてまっすぐにさせる。
ベッド程の高さしかない舞台のすぐ脇に足を投げ出して座らされたイリィは、いつもはお下げにしている長い銀色の髪を解かれて、アシェルにくしげずられている真っ最中。
「明日はお祭りなんでしょ! 思いっきり綺麗にしなくっちゃ!」
「だって、私はお祭りには・・・・・・」
ウキウキ明るいアシェルに反して、イリィの声は沈みがち。
「行くかどうかはイリィの自由! けど着飾りもお祝いもしないなんて、間違ってるよ、絶対! 誰が何と言おうと、イリィちゃんは可愛いんだから!」
「・・・・・・」
言い返す言葉を飲み込んで黙り込むイリィに、アシェルはコッソリと息をつく。
今使っている櫛や鏡だって、「アシェルに必要かと思って持って来ました」などとイリィは言うのだ。
アシェルのことを完全に女の子だと思ってるのは、まあ、無理ないとして。女の子にはこういうアイテムが必要だと判っているのは、いいとして。
それは正真正銘年頃な女の子であるイリィ自身にも必要で、普段から持ち歩くべきものなのだという認識が欠落してところに、大きな問題がある。
この分では、お化粧なんてしたことないとか言われても、全然不思議じゃないという気がする。
(ったく、カリムといい、イリィといい、どーしてこー自分をもっと評価しないかなー)
周りの環境が悪かったのは仕方ないとしても、そんなものは自分自身が認めなければいいだけのことなのに。
(そこのところがまるで解ってないんだから。ボクみたいになってから開き直ったって、遅いのに・・・・・・)
時々、自分に向けられるカリムの眼差しが、ひどく辛く感じられる。
アシェルの向こう側の、存在しない者に向けられる眼差しが・・・・・・。
そう。
カリムはずっと、”彼女”を愛し続けてくれた。
求め、探し続けてくれた。
だけどキミは、”彼女”の名前はおろか、本当の気持ちさえ知らない。
”彼女”は、”彼”の前ではいつも、気丈に振る舞い続けていた。
そうしていないと、失ってしまう。だから”彼女”は”彼”の前で、誰よりも明るく鮮やかに笑えた。
(キミがボクの中に見ているのは、失われた”彼女”の幻でしかない。それはキミのせいじゃないけど、時々キミを責めてしまいたくなる。ボクって嫌なヤツだな、ホント。それでも未だに強がりばっかり言っちゃうんだから、進歩なさ過ぎ・・・・・・)
「ねえ、アシェル、ええと・・・どうかした?」
いつの間にか手を止めていたアシェルに、イリィは出来るだけ頭を動かさないよう気をつけながら視線だけで振り返る。
「・・・・・・あー、何でもない何でもない。うん。すごく綺麗にサラサラ! いいカンジ!」
梳き終わった髪を手に取りながら、アシェルは満足そうに笑ってみせる。
「良かった。それじゃ、もう・・・・・・」
「うん。あとは結い上げるだけ! ねえ、やってみたい髪型とかあったら今のうちだよ?」
「・・・・・・」
これは当分解放してもらえそうにないと、諦めるしかないイリィだった。
カリムの剣呑な瞳に睨まれて、”あの馬鹿”の姿を真似た”何か”は、困ったような顔をする。
(ちょっと待って下さいよ? 僕は友好的に話しかけたつもりなんですけど、どうしてこんなことになってるんでしょうか?)
(充分友好的だろう? お前に少しでも敵意があったなら、俺は一瞬だって、こんな茶番に付き合ってなどいなかったさ)
(ああ、なるほど。・・・・・・ではここは、聞いておくべきところですね。どうして僕が彼じゃないと判ったんですか?)
(判るも何も、)
言葉を切って、カリムは肩をすくめる。理由ならいくらだって並べ立てることは出来るが。
(お前自身が認めてるくせに、今更何を言えって?)
(あ、そっか! こういう時はまずトボけて見せるのがセオリーなんですね! では改めて、何の根拠があって僕が君の知ってる彼でないなんて言いがかりをつけるんですか!)
トボけ切った顔をしながらトボけた理屈で押し通すあたり、どこからどう見てもあの馬鹿そのものなのだが。
(だから、違うだろ)
冷やかな視線を受けて、そいつは考え込む仕草をする。
(何をそんなに怒って・・・・・・もしかしてこの形が気に入らなかったとか? だったら別の形でも構いませんよ。でも君にとって彼以上に好ましい形っていったら・・・・・・?)
(変な言い方はやめろ!)
ゆらりと輪郭を崩し始めたそいつに向かって、カリムは素早く一喝する。
(それに他のヤツだったらいいって問題じゃない。何をしたってお前は俺の知っているヤツじゃない。何の理由があってそんな真似をする? 姿が無いなら、無いままでいいだろうが)
(仕方がありません。形だけが無いわけではありませんから)
再びあの馬鹿の姿になったそいつは、へらりと笑って頭を掻く。
(・・・・・・)
思わず聞き流してしまいそうなほどあっけらかんとした台詞の中に、無視出来ない言葉を聞き取って、カリムはしばし沈思する。
(ええと、納得してくれましたか?)
(まずはお前の正体、話はそれからだ)
(あれ? その察しがついたから、喧嘩を振ったんじゃないんですか?)
(それは、白状する気が無いって意味か?)
(僕に興味があるんですか? 嬉しいなあ)
(知るか!)
一向に進展しないやりとりの不毛さに、カリムは短く吐き捨てる。これ以上問い詰めたところで、実のある答えは引き出せそうにない。
(だったら何でわざわざ出て来た。俺に用でもあるのか?)
(え? 用ですかぁー?)
あの馬鹿が喧嘩を売って来る時の、わざと間延びした喋り方。
(やっぱムカつく。叩っ斬るか)
(そんなこと、出来るんですかぁ?)
(当然だろ。こんな術を破るくらい、わけも無い)
(ま、この程度の術、破ったって自慢にもならないでしょうけどねー。やりたいならどうぞ? でも、天軍や魔物が相手だったらどうなんでしょうねー)
(・・・・・・何が言いたい)
(そのままの意味ですよ。僕の庭で物騒な事を考えるのがどんなヤツかと思ったら、実は単に威勢がいいだけの、見かけ倒しの器でしかなかったなんてね)
(何だと!)
(おや? 力を持たない力の器に、何が出来るって言うんですか?)
(持たないんじゃない。そんなものは必要無い)
(ああ、自分から放棄したんでしたっけ? そもそも力なんて・・・・・・”羽根”なんてものが無ければ、塔の連中にいいようにされることもなかったんだしね)
(・・・・・・!)
(甘いですね。君は戦う者じゃなかったんですか? 戦う者が戦う力を放棄して、どうやって敵に立ち向かうつもりですか。それとも最初から無いのかな、勝つつもりなんて、これっぽっちも?)
(・・・・・・だからって負けてやるつもりなど無い!)
(じゃあ聞きますけど、君にとって”負けない”とは何です? 敵に屈服しないってことですか? だけどそれは”勝ち”とは違いますよね。勝ちを手放した者に、戦う者としての価値はあるのかな? 戦う者ではない君は、一体何者で、どんな価値が残されているんですか?)
(そんなもの!)
人の価値とは他者が決めるものだ。
自分自身がどう思っていようと、自分以外の者にとってそれは何の意味も無く、従ってそれが斟酌されることは皆無と言っていい。
圧倒的多数の他者に己の価値を主張したいのなら、それだけの力と地位を手に入れるしかない。
いや、それを手に入れたと思っていてさえ、きっかけ一つで気付かされることになるのだ。
それは単なる幻想でしかなかったのだ、と。
価値とは他者が決めるもの。そして、実体を持たない相対的なもの。
常に量られているのだ。自分ではない者の机上で。
自分に出来ることがあるとすれば、それは、願うことくらいなものだ。
自分の大切な者にとって、自分が無価値ではない事を。
(そんなもの、たった一人のためにだけ在れば、それでいい)
自分が何者だろうと、どうでもいいのだ、そんなことは。
たった一人、アシェルのために、自分にはまだ出来ることがあるのだと。望むのはそれだけだ。
そして、それだけのことが、この世界で一番難しい。
(だったら、君の大切な人は、否応も無く見せ付けられるわけですね。君が天軍だか魔物だかの手で滅びる様を、目の前で)
(そうなる前に、譲り渡すことくらいは出来る。他の誰にも、やるつもりはない)
僅かに残された力と命は、アシェルのためにだけ、使おうと決めている。
それしか出来ないというのも情けない話だが、せめてそれだけは貫き通してみせる。
それすらも出来ないようでは、価値どころか、意味さえ無くなる。アシェルに苦しみを与えてまでカリムが今ここにいる、その意味さえもが丸ごと、全部。
(あれがそんなに大切なの? あんな小さな、消えかけの魔が・・・・・・)
いつ吹き消されるとも知れない、儚いともし火。
小さな姿になることで何とか安定しているものの、それがいつまで保つかなど、全くわからない。
それでも、この世界で存在し続けていてくれた。戻って来てくれた。
他のどこでもない、ただ、カリムだけの元へ。
(大切だ。何よりも)
簡単に消してしまうなど、絶対にさせない。
アシェルは、カリムがようやく見つけた、たった一つの大切なものなのだから。
(それこそ今更じゃないんですか? 君はかつて、アシェルさんを容赦なく切り捨てている。ただ、自分の望みを叶えたいがためにね)
本当のことだ。
遠いあの日、カリムの腕の中に崩れ落ちたアシェル。
その光景を思い起こす度、体の芯が冷たくなる。
だがそれは、思い起こしたその瞬間に湧き上がる感情というだけのこと。
あの時、あの瞬間、自分が何を思い考えたのか。それはとうにカリムの中から零れ落ちていて、もう二度と戻ることはない。
確かなことは、アシェルを手にかけたのが、間違いなくカリム自身だったということ。
そして、もう一つ。
(・・・・・・カリムとアシェルにとって、”死”とは”救い”そのもののこと。それは、今でも変わらない。だからアシェルが望むなら、カリムは残された”力”の全てを与えて果てることが出来る。アシェルさえ望むなら、カリムはアシェルをこの手で解放してやることが出来る。今度こそ、きっと)
大切な者のためなら、何だって、どんなことだってやれる。
(ああ、お前の言う通り。俺は、俺の望み意外のことには何の興味も無いし、誰がどうなろうと知ったことではない。利用出来るか出来ないか、その程度の意味しか無い。今までも、これからも)
人々の願いなど、どうでもいい。自分の望みを叶えるための手段という以上の意味など無い。多くの者どもが天使だ何だと無邪気に崇め奉っているものの、それが本当の正体だ。
(どうだ、これで満足か)
事実のみを告げる、淡々とした声。感情も熱も無い深淵色の瞳が、静寂だけを映す。
(奇遇ですね。僕もそうです)
静寂をぶち破ったのは、緊張感のカケラも無い声だ。
(あれ、どうかしましたか? 額なんか押さえちゃって?)
(別に・・・・・・)
その応えに若干疲労感が滲んでいたとしても、仕方がないと思う。
(おかしいなぁ。僕がそういうものだと、予想してなかったわけじゃないでしょう? だからこそ君は、彼には絶対にしない話を、僕に話してくれたんじゃないんですか?)
(・・・・・・)
指摘されて、カリムは成程と思う。どれほど追及されたとしても、あの馬鹿を相手にこんなとこをぶちまける自分というのは想像出来ない。それ以前に、こんな話の展開になることからして有り得ないシチュエーションだ。
人は他者の中に、自分の見たいものを見る。そうして理解したつもりになる。
あの馬鹿もまた、カリムの中に自分の見たい物だけを見て、それにそぐわない部分を否定していた。知ったようなことをずけずけと口にしながら、その実、あれは何も解ってなどいなかった。
だから、カリムが何かを訴えたとしても、決して届きはしないだろう。
(すっげ違和感・・・・・・あの馬鹿の口からそんなセリフを聞く日が来ようとは・・・・・・)
苦笑する瞳に、いつもの蒼い光が戻る。
(さあ? 君が知らないだけで、案外解ってくれるかも知れませんよ? 君が彼に、解らないヤツでいて欲しいと思うのは自由ですけどね)
(・・・・・・勝手な解釈はやめろ)
(とか言ってますけど、まだ僕の話を聞いてくれてるじゃないですか。ということは、君にとって僕は無価値じゃないってことですよね?)
(それ以前に、お前が何者かも知らずに、ノコノコ引き下がれるかよ)
(興味ないです)
(あ?)
(僕が何者かなんて、そんなことはどうでもいいです。どうしても気になるのなら、君が勝手に解釈してくれれば、それで構いません)
(・・・・・・こういう心理攻撃は、タチの悪い魔物の得意技だよな)
相手の弱みを掌握した上で、容赦なく襲い掛かる。物理的にはもちろん、精神的にもだ。
完全な悪意を持ってなされる攻撃には一片の慈悲も無く、少しでも隙を見せようものなら、記憶を捏造し精神を破壊しにかかる。
そういう意味では、この相手にカリムを”攻撃”しようとする意図は無いらしい。
(別に魔物じゃなくたって弱点を突くのは、戦術としてはフツーでしょう。その点、君は防壁が薄いようだし? 信仰心や忠誠心といったものは、下手な術よりずっと強固な盾となりうるのにね)
(ふん。冗談じゃない)
使命を遂行することに対する使命感。選ばれた者としての揺るぎない自信。白亜の塔に対する絶対の忠誠。それらは塔に帰属する者が、最初に誓約することでもある。
幼い頃より専門の教育を受けてきた上級天使などは、まさにその典型だと言えるだろう。
(誓約護法に頼るなんざ真っ平御免だ。そんなことより、顔を見に来ただけにしては、仕掛けに手が込み過ぎてやしないか? そうまでして、俺を見極めたがるのは何故だ)
術に触れた時から、漠然と感じていた違和感。
この術は、カリムを量るために心を揺らすよう干渉しているだけではないか。目の前であの馬鹿の姿を取るものは、術者の自我を反映してのものではなく、カリム自身の潜在意識から構築された影なのではないか。
幻の向こうに術者が存在しないのなら、こいつはカリムが知り得たことや推論出来たこと以上の何かを語ることも、問うことも出来ない。
目的を果たすためだけに存在する幻影。
その目的は・・・・・・。
(お前が何だろうと、俺は災厄の火種でしかないのだろう。ぐちぐち嫌味並べてないで、ただ一言「邪魔だ立ち去れ」と締め出す方がずっと簡単だ。なのに、何故そうしない?)
(それが出来たら苦労しないんですけどねー。残念ながら、僕にはそこまで他者に干渉する力はありません。第一、君はもう約定を交わしているじゃないですか。その時点で君たちもまた、この地に守られるべき者になってるんだから)
(なっ!?)
約定とはもちろん、昨日村長と交わしたそれのことなのだろうが。
(誰がそんなことまで期待するかよ! 俺はただ、俺たちの事は放って置けって言っただけだ!)
(なんて、今更言われてもねー。契約は契約ですからねー)
約束とは、一番原初から存在する、一番身近な呪的契約だ。カリムが村人と交わした約束は、この地に根ざすものにとっても、同等、いやそれ以上の意味を持つ。
あるものの”存在”が物質レベルから高次にシフトすればするほど、契約に縛られる度合いは増す。
この地の住人が交わした約束に縛られる者の正体と言えば、それは一つしかない。
(お互い、諦めるしかないですねー。そこで提案なんですけど・・・・・・)
その時、ちりりとした何かが、カリムの感覚に触れた。
泉の術によるものではない。
遺跡の外部からの、何か・・・・・・。
(!?)
(おや、残念。邪魔が入りましたか・・・・・・)
途端に、さあっと波が引くように、泉の水が消滅した。
湧き出す水の奏でる旋律も、波立つ水面に反射していた光も、光の中に浮かんでいた影も。
一瞬にして何もかもが跡形も無く消え去り、四角く区切られた床で、乾いた砂がさらりと音を立てて崩れた。
全てが、夢幻のように。
いや。
床に膝をついて水面に触れていた格好のカリムは、顔を洗った時そのままのずぶ濡れ状態だった。
眼前の前髪から冷たい雫がぱたりと落ちて、白い砂の上に濃淡を描き出す。
気がついたら砂だらけというのも嫌な話だが、これはこれで、頭を冷やせと言われているようで面白くない。
わざわざ相手の術に応じてやったというのに、失礼にも程がある。
カリムの周りでビシビシビシッと破裂音が響き、壁の一部が弾け飛ぶ。
「何で俺が、あの馬鹿の顔をしたヤツに好き放題言われなきゃならない! てか、それもこれもあれもどれも、全部あの馬鹿が元凶じゃねーかよ。今度会ったら絶対、微塵に刻んでやる。いや、その程度で済むと思うな!」
理屈で納得したからと言って、感情までが納得出来るとは限らない。その目論見を実行する日が、決して来ることはないのだとしても。
(その前に、あれをどうするか・・・・・・)
術が消える直前に感じたチリチリした気配。
それは、無視出来ないような何者かが近付く気配だ。
この地の守護が、カリムに念押ししたくなるのも解る。
(そうだな。お前がこの地の守護だと言うなら、念押ししに来たくなるのも解らなくもない。これ以上何があろうと、お前にはもう見守る以上の事は出来ないだろうからな)
カリムは、図らずも入った時より大きくなった壁の隙間から、遺跡の外へと身を翻した。
第8話 紋章
「できたー完成ー! どうどうどう? いいカンジになったでしょ!」
ふんだんに編み込みを入れて丁寧に結い上げられた髪は、イリィが今までに見たことがないほど---自分自身は当然として、街の少女や歌劇の女優にだって負けないくらいの---豪華な仕上がりになっていた。
アシェルは手先が器用な上に、手自体も小さいので、細かい作業も抜かりが無い。
「うん、ボクって髪結いで商売しても食べて行けるかも。お人形さん遊びの成果が、こーんなトコで役に立つとはねー」
などと満足げに何度も頷いているアシェルだが、その小さい体ゆえに、結われる側のイリィもじっとしているだけとはいかず、どこそこを持てだの押さえろだの、アシェルの命令一下、バッチリ協力させられた。お陰で終始万歳状態だった腕がだるい。
鏡の中の芸術作品は、そんな二人の努力の結晶である。
「ねえ、感想は?」
「・・・・・・すごい、お姫様みたい・・・・・・髪だけは」
「何言ってんの! イリィが可愛いから似合うんだって!」
と、いくら自分が言ったところで納得しないんだろうなーと、アシェルは小さくため息をつく。
「・・・・・・そう言えばさ、イリーナって、おとぎ話のお姫様の名前だったよね」
「え? それ、知らない・・・・・そうなの?」
「うん。寒い国のお姫様! 赤い大きなお花が見たいってお願いするの。雪と氷で出来たお花じゃなくて、本物のお花」
「・・・・・・」
「そだ、折角だし、お姫様みたいにもっと飾ろう! いい物があるしね! 手伝って、イリィ!」
いいことを思いついたとばかり顔を輝かせたアシェルは、イリィの手を引っ張って舞台の反対側へと連れて行く。
「うん、この辺り!」
「ここって確か・・・・・・?」
「そ、カリムが色々放り出したとこ!」
「でも・・・・・・埋まっちゃってる?」
昨日は砂の上に落としただけだったのに、後で上から砂を被せて隠しでもしたのだろうか。何も知らなければ、さらさらした砂山に埋まっている物があるなんて思わなかっただろう。
「だーいじょーぶ!」
言うやアシェルは、そこに何があるのか見えているのではと思うほど迷いなく両手を突っ込むと、狙い違わず幅広のベルトを掴み出し、ポイと脇に投げ捨てた。
その何気ない仕草のわりには、どさりと重量感のある音が響く。
(アシェルって、意外に力持ち?)
気になったイリィが傍によって触ってみると、表面全体に綺麗な打ち出し模様を施されたベルトは、分厚い皮を重ねた丈夫な造りになっていて、その分しっかりとした重量がある。
にもかかわらず、裏面にまで達するほどの無残な切り裂き傷が数条走り、その内の一つはもう少しでベルトを上下に両断する寸前だった。
ぞくりと、イリィの背筋に冷たいものが走る。
「そんなのどーでもいーから、こっち手伝って!」
その間にアシェルは、小さな身体には一抱えもあるような金属製の籠手をどかし、別の何かを掘り出しにかかっている。
「そっちと、あっちと、そこ・・・・・・探してみてよ」
アシェルは適当に、イリィの近くの砂地を指す。言われた通りに手探りすると、すぐにコロリと硬いものが指先に触れる。摘み上げてみると、それは銀色の指輪だった。
カリムの白い指を飾っていたにしては少し角ばった武骨なフォルム。それでも全体に精緻な彫り込み模様が施されているのが美しい。真ん中の部分には、何かの紋章だろうか。
羽根の一枚一枚まで細かく刻み込まれた三対の翼。中央を貫く炎のような三叉の矛。翼と矛が交わる中心に、交差する二つの三日月。
そう言えば、あのベルトにも籠手にも同じ紋章が刻まれている。
(これに似たの、どこかで見たことがあるかも・・・・・・?)
これほど優美で精緻な紋章であれば一度見たら忘れないだろうから、多分、気のせい。でなければ、ちょっと似ている程度のものだったかも知れない
「あ、あった!」
その時、アシェルが嬉々として振り返って、イリィは現実に引き戻された。
ほら、とアシェルがかざして見せたのは髪留めだ。緩やかに広げられた銀色の翼の中央に、炎のような赤い貴石が嵌め込まれている。
「わあ! きれい・・・・・・」
「でしょ! これ、イリィにもきっと似合うよ。ねえ、つけてみよーよ!」
「そんな! おそれ多すぎっ! もったいない!」
こんな見事な装飾品なんて、イリィのような田舎娘には、一生に一度でも目に出来ただけで大ラッキー。そんなものを身に着けるなど、考えるだけでもガクブルものだ。
慌てて否定したイリィだが、アシェルはにやーっと、いかにも楽しそうな笑顔で応じる。
「そんなことないって! 絶対似合う! 保障する!」
「え、だって、ちょっと待って!」
「ダーメ待たない! こら、動かないの!」
「きゃああ!」
「あーっ! 折角の髪型を台無しにする気っ!」
イリィがジタバタ足掻こうが、アシェルに勝てるはずもなく。
大騒ぎの末、結局その髪留めは、結い上げられたイリィの髪の中央に無事収まった。
「ふっふっふっ。どんなもんだい!」
満足そうに笑うアシェルにつられたのと、大騒ぎし過ぎたのとで、イリィもつい、声を立てて笑ってしまう。
どうしよう。
楽しい。
楽しくて楽しくて、こんな時間がずっと続けばいいと願ってしまいたくなる。
大好きなお母さんの待つ家に、帰りたいとは思えなくなってしまいそうになる。
「・・・・・・あれ?」
ひとしきり勝ち誇った後で、アシェルはふと、先刻の砂地に目を戻した。
何がアシェルの目に留まったのか、同じように覗き込んでみても、イリィにはさっぱり判らない。
だが、再び砂地に降り立ったアシェルはすぐに、ガラス製らしいキラキラとした小瓶を掘り当てた。
「・・・・・・!」
イリィの見ている前で、小瓶を握り締めるアシェルの両手が小刻み震え、その表情には明らかな怒気が滲む。
「あーのーバーカーはーっ!!! っとに、っとにっ とにっ!!!」
「ア、アシェル?」
一体何がどうしたのか。
イリィにはさっぱり解らない。
ただ何となく察しがついたのは、ただならぬアシェルの怒りが、どうやらカリムに向けられているらしいということだけだ。
ところが、次の瞬間。
いからせていた肩から力を抜いてイリィに向き直ったアシェルからは、綺麗さっぱり跡形もなく、怒りの色が消え去っていた。
「ねえイリィ。キミ、何するのが好き?」
「はい?」
先刻と変わらないニコニコ顔であるのだが、その口調には、とてつもなく不穏な響きがあるような。
「あ、歌だよね。そだ! 一緒に歌お、歌!」
「え、え、え、何!?」
何の脈絡なのか、やっぱりイリィには理解不可能な展開だ。
「ねえ、恋人だったヤローを思いっきりののしって別れる歌って、何かない?」
満面の笑顔で、さらりと言ってのけるアシェル。怖い。怖すぎる。
「え、えっとぉ・・・・・・」
ひょっとして、これが遺跡の呪いというものだろうか・・・・・・?
イリィは、何をどう言いつくろおうかと、真っ白になりかける頭を必死になって巡らせた。
イリィが登って来たのと同じ道を辿って現れたのは、一五歳から一八歳くらいの、いかにもその方面でやんちゃそうな三人組だった。
彼らは遺跡手前の岩の上に日向ぼっこよろしく悠然と座るカリムに気付き、一瞬ギョッとした表情になるが、そこはそれ、気を取り直すのも早かった。
リーダーらしき少年を真ん中に、三人きれいに横並びになると、示し合わせたように足を開いて肩を怒らせて”オレたちゃ無敵だ”ポーズを作ると。
「おい、お前か! 昨日ウチの弟が世話になったってーのは!」
「お貴族様だかよーせーだか知らねーが、イキナリやって来てスキ放題かよ!」
「しかも、村長たちまで手玉に取ってだまくらかすとは許せねえ!」
「オレたちの村に手出しすりゃどうなるか!」
「よーっく味わわせてやるから覚悟しろ!」
「だがオレたちにも情けはある!」
「今すぐ尻尾巻いて逃げるんなら見逃してやってもいいぞ!」
口上の内容はありきたりだが、息の合った台詞分担は見事なものだ。
この手の連中は街中では別段珍しくも何ともないが、こういうノンビリした村にも居るものなんだなと、カリムは変なところで感心する。
もしかしたら彼らのようなのが居るから、人の少ない寒村でも、それなりに活気があると言えるのかも知れない。と、目の敵にされるのが自分でなければ、もっと単純に面白がっていられたのだが。
(ったく、面倒なことだ)
内心、カリムは大きく息をつく。
カリムらのことは、おそらく昨日の内には、村中の知るところとなっているはずだ。
だが村には村特有のルールというものがあって、興味の対象と認定されれば嫌でも遠巻きの村人に囲まれることになるだろうし、触らぬ神に祟りなし認定されたなら、その輪はずっと遠くなる。
現状、おそらく後者だと思っていたのだが、無謀な若者という人種は、その限りではない。
彼らは彼らだけの理屈で判断し、彼らの信じる力を絶対だと思い込み、それが高じればルールなど無用とばかりに簡単に踏み越える。
そんな奴らはどこにでも、それこそ天軍の中にだって居たりするし、そういう奴の鼻っぱしらをへし折ってやるのに何の躊躇いも覚えはしないが、相手が平和協定を交わした村の住人となると、話が少々ややこしい。
何しろ、ルールに訴えてお引き取り願うなんてことは、最初からやるだけムダだ。
しかも彼らの信じる腕力という尺度に照らし合わせれば、農村生活で体格のいい彼らに比べてカリムの見かけときたら、力仕事どころか外で日に焼けることにすら縁がなさそうな生っ白くて非力な存在そのものだ。
彼らが実力行使を躊躇する要素は、どこを探しても全く無い。
先手必勝と行きたくてもカリムの方から手を出すわけにはいかない、というのはまだしも、圧倒的に勝ち過ぎれば他の村人にも無用な警戒心を抱かれかねないし、速攻で出来るだけダメージを与えないよう気を遣えば、攻撃を食らった方は自分が何をされたか判らず、結局二度手間になったりする。
先手は相手に取らせて、ゆっくり動作で判り易く、あまりダメージは与え過ぎないよう注意しつつ、三人同時に相手する。
本当に、面倒以外の何物でもない。
(これがもう少し手加減の要らない相手なら、八つ当たりのし甲斐もあるんだが)
一瞬あのバカの顔を思い出しかけて、カリムは急いでそれを振り払う。
さて、何と挑発してやるのが良いか・・・。
その時、風に流れて聞こえてきた少女の朗らかな笑い声に、三人が一斉に遺跡の方へ目を向けた。
途端に彼らを取り巻く空気の温度が、目に見えて上昇する。
なるほど、これは非常に分かりやすい反応だ。
「何だお前ら。女一人に手も出せないで、徒党を組んで、そのザマか」
これ見よがしにバカにされるよりも、鼻先で笑われるよりも、にこやかに断言される方がよほど頭にくるものらしい。
しかも、自分達が完全に見下していた相手になど。
全身にゴオーっと紅蓮の炎を燃え上がらせた愚連隊三人は、「やっちまえ」の掛け声とともに、後先考えずにカリム目掛けて飛び掛った。
「ハアッ ハアッ ハアッ・・・・・・に、にーちゃんたち、ちがう、ごかい・・・・・・あれ?」
黒ブチ模様の小犬と一緒に、息咳きって道を駆け上がって来たジーロがそこで目にしたものは、うーだかぎゅーだか変なうめき声を上げながら重なり合って伸びている実の兄とその友人二人。
「お前、こいつらに何吹き込んだ?」
それに大した興味も無さそうに岩の玉座に悠然と座る、昨日の少年の姿だった。
「ねえ、これ、にーちゃんがやったの?」
ぐてーっと伸びている三人組とカリムを見比べながら、ジーロはおずおずと口を開く。
「さて、ね。そいつらが勝手に転んだんじゃないか」
もちろん、そんなはずが無いのは一目瞭然。
「・・・・・・にーちゃんって、本当にどっかの王子様か神様だったりする、んですか?」
しごく真剣な表情で、ジーロはカリムを見上げている。
「大人たちに、何か言われでもしたか?」
「うん・・・・・・遺跡の神様のことは誰にも言っちゃいけないって。それから、神様がいる間は遺跡に近付いちゃいけないって」
(なるほど、賢明な判断だ)
村人の共通見解としては、相手がどこぞの逃亡貴族とするよりも、神様の類であると示し合わせた方が後々都合がいいだろう。
来訪者を奉っておけば、上手くすれば将来褒美が貰えるかも知れないし、来訪者が領主の敵だったりした場合でも言い訳が立ちやすい。どちらに転んでも損のない対処法だと、カリムは思う。
「だが、お前はそうは思わないわけだ」
「うーん。良く分からないや」
眉間に皺を寄せながら、ジーロは正直に白状する。
「そうか。実は俺もよく知らない」
「えーっ、そうなの?」
まさかそんな風にあっさり言われるとは思いもよらなかったジーロは、意表をつかれて大きく目を見開いた。
「・・・・・・でも、にーちゃん、強いんだよね」
「ん?」
「こいつ、トルナードってゆーんだ。オレの犬!」
「威勢のいい名前だな」
「うん、かっけーだろ! だけどこいつ、ちょっとバカでさ。誰にでも平気で吠えかかって行ったりするんだ。自分より大きい犬や牛や狐なんかにもね」
言いながらジーロは、初対面であるはずのカリムの足元で神妙な様子で伏せをしている犬の、大きな黒ブチの入った背中を撫でてやる。
「ねえ、にーちゃんだったら、イリィのこと、助けられる?」
「!?」
カリムは思わず、真剣な眼差しを向ける少年の顔を見直した。
「イリィはさ、みんなに怖がられてるけど、オレもちょっと前まで怖いって思ってたけど、本当はすっごく優しいんだ。前にこいつが迷子になって、もしかしたら遺跡の中にいるんじゃないかって思って、オレ、一人で探しに行ったんだけど、そしたらオレ、自分がどこにいるのか判らなくなって・・・・・・そん時イリィの歌が聞こえてきてさ。イリィはオレのこと、ちゃんと外まで連れて行ってくれたんだ。それに、こいつのことも一緒に探してくれたんだ。それなのに、みんな、イリィに冷たいし。こいつだって、イリィのこと怖がるし。ヒドいよ・・・・・・」
「怖い? あの娘が?」
「うん。そう」
「それでどうして、他所者の俺が何とか出来ると思うんだ?」
「だって、にーちゃんは強いし、いい奴っぽいし、イリィのことも怖がったりしないし。オレもイリィ怖くないけど、ガキの話なんか、誰も聞いちゃくれないし。でもこなままじゃ何かヤなんだ・・・・・・」
うつむくジーロの手を、トルナードがそっと舐める。手の甲の真新しい刷り傷は、部屋で大人しくしてなさいという言いつけを無視して窓から脱走してきた時に、うっかり擦って出来たものだ。
「だが、それを他所者に頼むということは、変化を望むってことなんだぞ?」
「へんか?」
「そう。良くも悪くも。お前は、あの娘がどうなったらいいと思うんだ?」
「どうなったらって、それは、その、オレのお嫁さん! とか?」
「ッハハハハハ!」
「わ、笑うなよ! ガキだと思ってバカにすんな!」
「ハハハ。いや、そういうつもりゃない。いい答えだと思っただけだ。下手に親切ぶるより、ずっといい」
「うう・・・・・・」
「だが、さすがにそういう膳立ては出来ないな」
「んーやっぱりかー。仕方ない、それは自分でドリョクするよ。何たって今日はオレのが絶対、にーちゃんよりポイント稼いでるしなっ! あ、あっちで伸びてるオレのにーちゃんの方な。・・・・・・あのさ、オレのにーちゃんもさ、ホントはイリィのこと好きなんだぞ。オレがイリィとデートしたって言ったら、いっつもフキゲンになって、オレのことどついたりするんだぜ!」
つまりは、どつかれようが何しようが、自称デートの度に自慢しているということで。
「ほーお。それで余計なことまで喋ったか」
昨日のカリムと村長達のことまで。
「あー、えっと、それはそのー・・・・・・ゴメン、にーちゃん!」
がばっと頭を下げる潔いジーロである。
「いーけどな、別に」
「やたっ! ・・・・・・それはそうと、なかなか起きないなあ、オレのにーちゃん」
「そうだな。そろそろ起こすか」
カリムは、自分の足元で伏せをしたままの黒ブチ犬に視線をやる。
わん!
心得たとばかり跳び起きたトルナードは、伸びたままの三人組の周りをわんわん吠えながら駆け回り、それでダメならとむき出しの手や顔を遠慮なく舐め倒す。
ボンヤリ頭の少年らは、いきなり強襲してきたむにゅむにゅ怪獣に驚いて、奇声を上げて無暗に手足をバタつかせ、それが仲間にバシバシと当たってさらに変な風に絡まっている。
「ワハハハハ! 見たか! ゲンコのカタキだ!」
思いっきり腹を抱えて笑うジーロは、横暴な兄に、日頃のうっぷんが溜まっていたらしい。兄弟とはそういうものだが。
「いい犬だな。小さいなりに、主人を一生懸命守ろうとしてる。だろ?」
「ああ、うん。そう」
言われてジーロは、得意げに鼻の下をこすった。
ただちょっと、自分の力量というものを判っていなくて、逆にジーロが世話を焼かなきゃならなくなるだけで。
「誰かを守るのに、強い力ってのは、絶対に必要なものではないよな」
「ええ? だって、強くなくちゃ、何にも出来ないじゃないか!」
「そうだな。強くないとな」
「? うん。そーだよ」
「あの娘のことは、俺に出来るだけは、何とかしてみる。お前の他にも、同じことを言った奴がいるからな」
「ホント? それ、誰?」
「俺の連れ。昨日会ったろ」
「あの妖精さん!?」
「俺よりずっといい奴だ。仲良くなってくれると嬉しい」
「うん、そーするよ。ありがとうにーちゃん。あ、そだ。オレはジーロ! にーちゃんは・・・・・・そか、言ったらダメなんだっけ・・・・・・」
「カリム。でも内緒な」
「うん!」
内緒を共有する時の嬉しそうなこそばゆそうな顔で、ジーロは白い歯を見せた。
その暫く後。
子犬に散々いいようにされた三人は、げんなりと疲れた様子で並んで草地に座り込む。
「・・・・・・なんでジーロがここに居るんだ? てか、オレたち何でこんなコトに・・・・・・」
「しっかりしてよにーちゃんたち! ボロ負けして気イ失ってたんだよ。覚えてねーの?」
「・・・・・・お前、どっちの味方なんだよ!」
「そりゃモチロン、オレのことどつかない方!」
「・・・・・・」
昏倒する直前のカリムとの顛末を思い出したらしい少年らは、一応根性を見せるべく立ち上がろうとしたが、結局すぐに地面と仲良くする羽目になる。戦意は完全に喪失したようだ。
その様子を見ていたカリムは、さて、とジーロに視線を移す。
「頼んで悪いが、ちょっとぶどう酒を取って来てくれないか」
カリムに遺跡を指して頼まれ、ジーロは少し迷った素振りを見せたが。
「うん、わかった!」
何事か察するものがあったらしく、一つ大きく頷くと、遺跡に向かって駆け出した。トルナードが一度カリムを窺ってから、すぐにその後を追う。
ジーロはすぐに戻るつもりだろうが、アシェルとイリィが黙って帰すとは考えられないから、しばらくは戻って来れないだろう。いや、捕まりっ放しになるかも知れない。
酒が欲しいというのは半分以上本心なのだが、まあ、それは仕方がない。
ジーロが立ち去って格好をつけねばならない相手がいなくなったことで、少年らは実にすんなりと大人しく降参した。思った通り、力関係さえハッキリすれば、却って素直で扱い易い。
「それで、お前らに聞きたいことがあるんだが」
「ははっ! 何なりと!」
・・・・・・少し効果が強過ぎたかも知れない。
第9話 不穏の影
「あれー? えらくゆっくりだったねー。よっぽど楽しいことでもあったのかなー?」
遺跡のホールに戻ったカリムに対する、アシェルの第一声がそれ。
しかも、口調に反して目が全く笑っていない。
おかしいとは思ったのだ。
カリムが外から戻って来たことくらい気配を読めるアシェルにはすぐに判ったはずなのに、何の反応も示されなかった、その時点で。
ホールに入ってからでさえ、不意打ちされた格好のイリィが驚いて歌を中断し、そのせいでアシェルと一緒にダンスの練習中だった---と言うか、一方的に振り回されているように見えた---ジーロがステップをトチッて止まるまで、アシェルは振り返ろうともしなかった。
今朝のことが尾を引いているとは、いくら何でも思えなかったし・・・・・・。
助けを求めるような視線を向けてくるジーロから、歌を聞かれたことに照れているのか顔を紅くして両手で口元を覆っているイリィに目を移した時・・・・・・カリムはイリィの結い上げられた髪におさまっている銀色の髪留めに気が付いた。
(なるほど、そーゆうコトか・・・・・・)
自分の髪留めがそこにあるということは、砂中に埋めた装備品が掘り返されてしまったということで、ついでにそれと一緒に埋めておいた小瓶がアシェルに発見されてしまったということになるわけで・・・・・・アシェルが怒るとすれば、原因は多分それ。
とっとと処分しておかなかったのは失敗だったが、さりとて簡単に処分できるような代物ではなかったし、まさかそんな理由で掘り返されるとは思ってもみなかったし・・・・・・この件に関しては後で釈明を考えた方が良さそうだ。
カリムは知る由もなかったが、「別れてやる!」の歌はさすがにマズいと思ったイリィの提案で、「春分祭で恋人をゲットしようダンス」の練習とあい成ったのだ。
何も知らずに入って来たジーロがダンスの相手役に抜擢されて散々振り回され、四苦八苦する羽目になったのは、トバッチリ以外の何物でもない。
ふと、お供え物に目をやれば、案の定、そこに置いてあったはずの酒器一式が消えている。腹立ち紛れに隠されてしまったらしい。
「で、後ろのその連中、何?」
初めて目にする実物の妖精さんに思いっきり不審の目を向けられて、ホールの入り口でおっかなびっくり固まっていた三人組が、見ていてハッキリわかるほどビクッと身を竦ませた。
「え・・・・・・コリオにレノにエリオット? どうしてここに・・・・・・?」
かなり小声で驚くイリィに、アシェルは「知り合い?」と囁き返す。
「ボクの兄ちゃんたち」
と、イリィの代わりにあっさりと答えたのはジーロで、そんな必要は無いはずなのに、二人につられて囁き声だ。
「外に居たんで連れて来た」
カリムもまた簡潔過ぎる説明で片付けると、放っておけばそのままジリジリと後退して逃げ出してしまいかねない三人に、早く入って来るよう視線で命令する。
「いや、その、さっきも言いましたけどー、ここ”恋人と来ると別れる”ってジンクスがあってですねー」
という少年らの往生際の悪い主張は、
「ンなもん、まだ付き合ってもないのに、関係あるか」
無情にも、一言でバッサリと斬り捨てられる。
退路を断たれた三人は、大げさなほど絶望的な雰囲気を漂わせながら、ホールに足を踏み入れた。
「こいつらも一緒に歌を聞きたいって言うんだが、どうだろうか?」
途端に、唐突にして単刀直入なカリムの発言に、「ええっ!?」という驚きの声を上げた者、上げなかったが内心で叫んだ者、「オレたち何も聞いてないっスよ」という抗議を飲み込んだ者の視線が集中する。
「一緒に歌って踊って遊びたいっての? まあ、ボクはどっちでも」
一番にそう言ったのは、カリムの台詞が突拍子もないものだとは全く思わなかったアシェルだった。
ただし、場を取り持とうとか助け舟を出そうとする様子は微塵もなく、完全に他人事発言だ。
「え、ええと・・・・・・ごメーワクなんでわ?」
恐る恐るの体で上がった声は、キッパリと無視された。
三人組に、発言権は認められていない。
「無理なことか?」
と、重ねて問われたイリィは、未だに驚天動地ポーズのまま微動だにしていない。
カリムに歌って欲しいとお願いされたこともだが、幼なじみ三人組登場の衝撃からも、まだ全然立ち直っていない有様だ。
肝心のイリィがこの調子では、この場は硬直状態突入が決定したようなもの。
その時、ジーロが舞台を飛び降りて、ててっとカリムの前に走り寄った。
「ねえ、にーちゃん、それってイリィ助けてって言ったのとカンケーある?」
近寄ってコソリと囁く辺り、なかなか察しがいいし、機転も利く。
「物は試し程度には」
「分かった。任せて!」
ニッと歯を見せて笑ってから、てててっと舞台に駆け戻ったジーロは、相変わらず固まったままのイリィにピョンと抱きついた。
「あっ! あのヤロ、チョーシ乗りやがって!」
思わず前のめりになった三人は、至近距離からの眼光に牽制されて、一様にウッと押し黙る。
「ねえ、イリィ! オレももっとイリィの歌、聞きたいな! それにさ、これってお祭りみたいじゃね? だったらきっと楽しいって!」
「え・・・・・・? ええ・・・・・・そう、かな・・・・・・」
「そうそう! きっとそう!」
「でも、その・・・・・・」
拗ねた様子でそっぽを向いていたアシェルは、視線を感じてイリィにだけ表情が見えるよう振り返ると、
「ボクも気晴らし賛成。別れる歌でも全然おっけ!」
悪戯っぽい顔で、どこまで本気なのか判らない事をさらりと言う。
「それはちょっと・・・・・・」
「だよねー。でもこのままイリィが帰っちゃったりなんかしたら、その後ボク達大喧嘩しちゃうかもねー」
「だから、それはちょっと・・・・・・」
脅しとしか思えない台詞を笑顔で言わないでほしいと、切実に願うイリィなのだが。
「ほら、イリィ、セキニンじゅーだい! にーちゃんたちの仲はイリィ次第だってさ。何ならこのまま別れてもらう?」
どういう仲なのかなどまるで考えていないジーロは、おそらく自分の爆弾発言に気付いていない。
「そんなこと言われたって・・・・・・」
このままでは、何だかとんでもない方にどんどん話が進んで行く気がする。多分、気のせいではなく。
ちなみに、先刻から額に手をやっているカリムにも、舞台でのヒソヒソ話は丸聞こえだと思われる。
「ああもう、わかりました、やってみます!」
「やったー! イリィ歌ってくれるってー!」
途端にパチパチパチーっと、拍手付きで盛り上げにかかるジーロに慌てたイリィは。
「待って待ってちょっと待って! ・・・・・・ええと、その、ね・・・・・・?」
何事か耳打ちされたジーロは、再び伝令役になってカリムの元に走り寄る。
「あのさ、イリィが言うには、注目されてるとハズカシイから、みんなあっち向いててくれないかって」
今度は兄たちにも普通に聞こえる声で。思いっきり得意げな態度なのは、まあ、ご愛嬌だ。
「だとさ」
ジーロに対して口々に不満を表明しようとしていた少年らは、口を開く前にカリムに睨まれて、渋々の体でノロノロと舞台に背を向ける。
が、首を変な風に傾けつつ、横目でしっかり舞台に注目している彼らの微妙な緊張感は、後ろを向くくらいではどうにもならない。舞台上のイリィも、居心地悪そうなままでいる。
いくら「気にするな」と命じてみたところで、こればっかりは言われて出来るものではないだろうし。
カリムは何か無いかと周りを見回し、お供えの食べ物に目を向けた。どうせ酒があるわけでなし、アシェルと二人で食べきれるわけでなし。
「お前ら、あれ、食ってろ」
「・・・・・・!?」
言われて喜ぶかと思いきや、少年らは互いにそわそわした視線を交わし合う。
「ホントにいーのか?」
「ココはいちおー遠慮とかしねーと?」
「だよなー?」
「や、でも親分の命令だし・・・」
まさかそんなオイシイことを言いつけられるとは思ってもみなかったということらしい。
「お前ら、言われたことはさっさとやれ!」
カリムに苛々とした目で睨みつけけられ、三人はまたもやビクッと飛び上がる。
何か言う度どうしてこういちいち面倒くさいのか。もちろん彼らはカリムの従者でも部下でもないのだから、打てば響くように従わないからと言って、怒る筋合いなど全くない。それはよーく分かっている。分かっては、いるのだが。
こんな場合、機嫌の良い時のアシェルなら、自分から首を突っ込んでいいように場を仕切ってくれるだろうが、それを今は期待出来ない。そのことがまた、カリムの苛立ちに拍車をかけている。
だが、さすがにカリムの怒気に気付いた三人は、そそくさと岩のテーブルまで移動し、そこに並んでいる上等のご馳走を前にして思わずおおーっと歓声を上げる。
単純と言うか、何と言うか。この様子なら、お預けと言ってもそう長く待てなさそうだ。
「ちょっと待って。コレはダメ!」
それまで口を挟まず状況を横目で見ていたアシェルが、素早くテーブルに向かうや、置かれていたバスケットを掴み上げると、食べ物に手を伸ばしかけたままの姿勢で止まった三人に向け「お邪魔しましたー」とニッコリ笑顔を見せて、そのままフワリと後退する。
「ジーロも、食べて来ていいよ」
わざと二人の前を通り過ぎ様、ジーロにだけ声をかけたアシェルは、カリムのことはキッチリ無視してイリィの方に戻って行った。
「大丈夫か、にーちゃん。一体何やったんだよ?」
ジーロに心配そうに見上げられては、カリムも苦笑するしかない。
「まあ、誰にでも譲れないものはあるってことかな」
「あーソレ知ってるぞ。オトナのジジョウってヤツだよね!」
「いいから、お前も行って来いよ。あの様子だとすぐに食い尽くされるぞ」
「うん、そーする!」
実は先刻からご馳走を気にしていたジーロは、急いで兄たちの方に駆けて行くと、押し合いへし合いに混じって自分の取り分を確保しにかかる。兄弟だろうが友人だろうが、そこは仁義無き戦いだ。
(さて、と。俺も邪魔者の一人、だよな)
彼らの様子を見届けてから、カリムは入り口近くの壁際に寄ると、軽く背を預けて目を閉じる。
ここからなら全体を把握しやすいという判断だ。
何だか調子を崩されっぱなしだが、やるべきことを見失うわけにはいかない。
妙なドタバタの末、とりあえず聴衆の注目から開放されたイリィは、ドキドキしながらも覚悟を決めた。
だが。
「どうしよう。何歌ったらいいのかな・・・・・・」
深刻な顔で困ったように囁くイリィに、
「じゃあさ、さっき歌ってたのにしたら? 楽しい歌だし、もう練習済みだしね」
バスケットの持ち手をしっかり握り締めたままのアシェルが囁き返した。
程なくして、ホールに明るい花祭りの旋律が響き渡る。
ジーロを遺跡に行かせてからカリムが少年らに質問したのは、もちろんイリィについてだ。
彼らのような連中は、余計な事にもいちいち首を突っ込むのが本能のようなもので、おしゃべり好きな女性たちほどではないにしろ、身の回りのムダ情報には意外と精通していたりする。
ただしそれを役に立てようとは夢にも思わないところが、ムダ情報たるゆえんなのだが、興味ある女の子のこととなると話も変わる。
そして、彼らの証言をまとめると、だいたいこんな事情のようだ。
イリィは村外れの小屋で母親と二人暮らしをしている。
母親は遠方の街からの出戻りで、その時一緒に連れていたのが赤ん坊のイリィだった。
村の子供たちは目立つ外見のイリィをからかう時もあったが、肩を並べて読み書きを習ったり、そこらじゅう駆け回って遊んだり、一緒になって悪戯をして叱られたりした幼馴染み同士だ。
ところが二年くらい前のある日を境に、その事件は起こるようになった。
やはり幼馴染みだった少女がイリィと口喧嘩をした直後、転んで怪我を負った。もっとも本人が大騒ぎするほど大したものではなかったし、誰もが単なる偶然としか思っていなかった。
だがそれは、確かに災厄の始まりだった。
イリィを苛めた者、無視した者、うっかりぶつかった者、単に挨拶を交わした者・・・・・・少しでもイリィに関わった者が、次々と災難に見舞われるようになった。
そして災難の程度も、転んだりぶつけたりという些細なものから、ついには何の前触れもなく突然ぽっきり腕が折れたり、今まで元気だった者が突然高熱で倒れたり、家が火事に見舞われたり、一家の家畜が揃って病気になったりと、次第にエスカレートしていった。
ただしそれは、イリィの前では起こらない。
イリィと接して別れた直後など、絶対にイリィが見ていないところで起こる。
しかも、その事をイリィに告げようとした者は、急に声が出なくなくなったり、身体が金縛り状態になったりした。
聖職者か誰か、この手のトラブルに詳しそうな相手に相談するため街に行こうとした者などは、危うく崖から海へ転落しそうになった。
だからイリィ自身は、そんなことが起こっているとは知りようもないだろうし、村人以外にこの状況を知る者はいない。
村人は何となくにしろ、この事態を招いたのはイリィでないだろう、とは承知していた。
それでも、村人はイリィを避けるようになった。イリィに接しさえしなければ、不可解な災難には遭わないように思えた。
最初の頃こそ訳が分からず、自分が何か悪いことをしたのかと一生懸命謝ったり、誰彼かまわず話しかけたりしていたイリィも、やがて諦めたように村人から遠ざかった。
病弱な母親と二人暮らしのイリィの為に、村人は食料や必需品などの援助は続けていたが、それは災厄を広げないための行為に他ならない。
村人は最低限しか、イリィ母子には関わらない。
イリィは村人に、関わりを求めない。
そうしている限り、彼らは互いに平和でいられる。
この村の平穏は、そんな微妙なバランスの上に、辛うじて成り立っている。
ただ不思議なことに、最近のことではあるが、ジーロだけはイリィと親しく接しても平気でいる。
その理由は誰にも分からなかったし、このままずっとジーロが無事でい続けられるかどうかも分からない。
村人、特にジーロの両親は気が気ではなく、かと言ってあまり強引なことをして逆に災いを呼び込んでは元も子もない。せいぜいが事あるごとにジーロに外出禁止を言い渡すくらいのもので、親の気も知らないジーロはとっくに脱走慣れしてしまっている。
たったこの程度のことを説明するのに、彼らは彼らなりに精一杯まわりくどい言葉を選び、身振り手振りのジェスチャーゲームを繰り広げ、さらにはカリムの推測にイエスノーで答えるという経過を経てやっとという有様だった。
それは取りも直さず、彼らが本気で災難を恐れている証拠でもあるのだがまどろこしいことこの上なく、カリムはこの時点でいい加減、いや、相当うんざり来ていた。だいたいカリムは魔物退治が専門であって、探索班のような地道な調査は向いていない。
『つまり、お前らも見て見ぬふりか・・・・・・』
カリムとしては単なる事実確認のつもりだったのだが、それは言われた者にとっては非難に聞こえたらしい。
『オレたちは!』
『その、』
『困ってないか、陰ながら見守ったりとか・・・・・・』
『他所者が苛めに来やしないか見張る、とか・・・・・・』
『やってるぞ、いろいろ、これでも・・・・・・』
だが、言い募る彼らが一様にうつむき加減だったのは、それが自己満足に過ぎないことを自覚しているからに違いない。
(さて、どうしたものか・・・・・・)
少年らの話が本当なら、何らかの呪的要因が絡んでいる可能性は否定出来ない。
だが、いくらそのつもりで探してみても、イリィに対しても、この村に対しても、そんなものが仕掛けられているようには視えない。
カリムとて自分の探査能力を万能だと思っているわけではないし、魔術理論に精通しているわけでもない。と言うかぶっちゃけてしまえば、カリムは魔術的なものを発見するのが得意なのではなく、そういうものが大嫌いで逆に無視することが出来ない性質なのだ。いじめられっ子がいじめっ子の気配に敏感だとか、ニンジン嫌いの子がシチューの中の細かい欠片まで発見して除けるとか、まさにそういうレベルで。
いくら何でも人間に危害が及ぶような呪術が施されていれば、見逃す方が難しいのではないだろうか。
では、可能性は二つ。
一つは単純に、仕掛けられている術がカリムの探査能力を超えるほど高度である場合。
ここでネックになるのは、術者にそれだけの動機があるのかあということだ。高度な術が仕掛けられるには、そうしなければならないだけの理由が必要であって、それがイリィや村に存在するのかというと、首を傾げたくなるなるのが正直なところだ。
れでも何らかの事情があったとして、高度な術がかけられていると仮定した場合、何とかしろと言われたところでカリムのスキルで太刀打ち出来るものではない。諸手を上げて降参するだけ。
(それとも・・・・・・?)
滅多に無いことではあるが、術との相性の問題である場合も考えられなくはない。
現にこの地の守護の術が、カリムの防壁を突破出来ることは、先刻で経験済みである。
が、守護的性格のものが守護対象に害意を持つとは考え難い。術が不本意な形で絡まったなどと言われても、やはりやれることなど無いような気がする。
もう一つは、本当は呪術など何もなく、単に誤解の積み重ねである可能性。
この誤解というのは意外と侮り難く、実は一般から持ち込まれる怪異の申し立てのほとんどがそうであり、塔に奏上される以前の初期調査の段階で大半が”怪異とは無関係”判定されてハネられるほどなのだ。
では、呪術など存在しなかったとして、それなら事は簡単かというと、実はそうとも言い切れない。
例えば適当な原因を示して、これで怪異は無くなりましたと宣言すれば、当面の事態は治まるだろう。が、イリィが孤立することになった本当の原因を何とかしない限り、何か些細な災難をきっかけに、事態が再燃する可能性は非常に高い。
しかも、イリィが恐怖の対象ではなくなってしまえば、村人の対応は、今度はハッキリと排斥の方向に向かいかねない。恐怖心を抱かれている事自体が、排斥から身を守る最後の盾でもあるのだから。
そんな思案をしていた矢先。
遺跡の方から、風に乗って明るい歌声が聞こえて来た。アシェルとジーロを前に、イリィが歌っているのだろう。問題は多々あるにしろ、今はその程度には平穏なのだ。
だとすれば、他所者でしかない自分の介入は、果たして許されることなのだろうか。
均衡を崩してしまうことで、僅かに残された平穏さえも奪ってしまう結果になりはしないだろうか。
事態を悪化させる可能性の方が大きいのなら、正直、関わらない選択をする方がマシかも知れない。見て見ぬふりをすることが実は最善だったという事例など、この世界にはいくらでも存在するのだから。
それとも、均衡はもう崩れかけているのだろうか。水面に広がる波紋のように、石はすでに投じられてしまったのだろうか。
カリムとアシェルの来訪によって。
(我ながら、往生際が悪いよな)
何もしないうちから怖気ていてどうすると言うのか。
アシェルが望むのなら、それを叶えるのは当然のこと。それが、アシェルに近付く唯一の方法だ。
(歌、か・・・・・・)
確かイリィは、遺跡でだけしか歌うことが出来ないと言っていなかったか。
そして、村人の中で唯一、ジーロだけが遺跡でイリィの歌を聞いている。
ここに何かヒントになるようなものはないだろうか?
(いや、いくら何でも短絡か。その程度のことなら、こいつらだって思いつかないはずがないし・・・・・・)
その時、手持ち無沙汰にされた少年らのヒソヒソ声が声が耳に入った。
『・・・・・・そう言やジーロのヤツ、遅せーなー』
『遺跡だろ? よく平気で行くよなー」
『あの遺跡、恋人と行くと別れるってジンクスがあるのになー』
成程、そういうことなら、イリィと同年代の少年少女が近付かないのは道理である。一緒には行かなくとも、現地でうっかり鉢合わせしてしまえば、当人達にとってはシャレにならないだろうから。
それなら、試してみてもいいかも知れない。
歌を聞くくらいならアシェルやジーロが経験済みなのだから危険ということはないだろうし、何も起こらないならそれで可能性を一つ潰せる。
『お前ら、ちょっとカオ貸せ』
即断即決即実行。一体何事かと腰の引けまくっている三人を一睨みで従えると、カリムは遺跡へ取って返した。
草の上で行儀よくお座りしてご主人様のお帰りを待っていた子犬が、カリムや少年らが通り過ぎるのを尻尾を振って見送った。
イリィの歌が、ホール中を満たしていく。
芽吹きの季節を讃える歌を紡ぎ出す声は清らかで美しく、ゲージュツなどにはあまり興味がなさそうなヤローどもですら、肉を大口で頬張ったまま、飲み込むのを忘れて聞き惚れている程だ。
もしかすると稽古次第では、大きな劇場の舞台の歌い手も夢ではないかも知れない。
だが、普通だ。
呪術的な要素どころか、力らしきものの片鱗すら、全くどこにも感じられない。
それはカリムの予測の範疇であり、それが証明されたに過ぎない。
なのに、少し落胆した気分になるのは何故だろう。
落胆しているということは、何かが腑に落ちないということだ。
折しも、イリィはラストのパートを歌い切り、延びのある歌声はホールの隅々にまで響き渡りながら、その幕を閉じようとしている。
響きの余韻が溶け去るのを待ってから、カリムは閉ざしていた目を開けて舞台の方を見た。
だが、まるでそれが合図であったかのように。
グワッと、空気が大きく震えた。
第10話 呪歌
夢を、見ているみたい。
ジーロがいて、コリオがいて、レノがいて、エリオットがいて。
お姫様みたいに、アシェルに髪を飾ってもらって。
歌って欲しいとカリムさんにお願いされて。
皆の前で、私は今、歌っている。
歌を聞きたいって言われた時はビックリして、恥ずかしくて、絶対無理っやめてーって思ったけど、でも、村のみんなに陰から見られる時みたいな凍りつくような怖さじゃなかった。
ドキドキして、ゾクゾクして、フワフワする感じ・・・・・・なんて言ったら、何だそれって笑われちゃいそうだけど。
ジーロに「歌って」ってお願いされる時も、ほっこりしてくすぐったいけど、それとも少し違った感じ。
誰かにお願い事をされるのは、ちょっと嬉しい。自分がちゃんと認められているみたいで。
カリムさんにとっては、ただの気まぐれなんだろうけど、それでも私には・・・・・・。
こんな瞬間が来るなんて昨日までは、ううん、さっきのさっきまで、夢にも思ってなかった。
アシェルとカリムさんに会ったあの時から、夢のようなことばかりが次々起こる。
ずっと、こんな時間が続けばいいのに・・・・・・。
だけど、それは無理。
何度もリピートしたとしても、歌はじきに終わってしまう。
歌声なんて、すぐに風に吹き消されて無くなってしまう。
誰かと一緒にいる時間は、あっと言う間に過ぎてしまう。
それに、ここにいるのは数日だけだって、カリムさんは言ってた。
明日まで? 明後日まで? もう少し後?
だけど時間はすぐに駆け去って、アシェルとカリムさんは、どこかにいなくなってしまう。私には決して手の届かない、遠い遠いところに。
そうしたら。
戻って来る。また、いつもの日々が。
コリオもレノもエリオットも、カリムさんに連れて来られただけなんだから、二度とこんな風に過ごすことなんて無い。それにジーロだって、いつまでも一緒にいてくれるわけじゃない。
そうしたら、私はまた一人。
いいえ。昨日までよりも、もっともっと一人になる。
ああ、でも、お母さんがいる。
私には、お母さんがいてくれる。
いつも私を心配してくれて、大切なイリィって言ってくれる、大好きな、たった一人の私の家族。
だから、平気。大丈夫。
一人になっても、ちゃんと笑える。
ここでだって、暮らしていける。
だけど。
この歌が、ずっと終わらなければいいのに。
今この瞬間が、永遠に続けばいいのに。
このまま時間が止まってしまえばいいのに。
そんなこと、考えてはダメ。
願ってはダメ。
でも・・・・・・。
歌は、終わる。
ジーロやコリオやレノやエリオットが、夢から覚めたように、また食べ物に手を伸ばす。
こっそりカリムさんの方を気にしていたアシェルが、思い出したみたいにそっぽを向き直す。
歌を聞いてくれていたカリムさんが、顔を上げて瞳を開く。
イヤだ!
お願いだからもう少し!
もう少しだけ、このままで!
歌が余韻を残して消え去った直後、ホールの空気が激しく身震いした。
突如としてホールの真ん中に高密度の気圧の塊が出現したかのような、波動の爆風が吹き荒れた。
(何だと!?)
身体よりもむしろ、感覚という感覚全てに、見えない拳で殴りつけられたような衝撃が走る。
少しでも気を抜けばたちまち持っていかれそうになる意識を、ほとんど意地だけで繋ぎとめ、背にしていた壁を支えに体勢を立て直すと。
カリムは、あまりにも馴染みのあり過ぎる波動の源を凝視した。
イリィが立っている。
糸に絡め取られて倒れる事を許されない操り人形のような、奇妙で危ういバランスで。
ぼんやりと虚ろな表情の中、僅かに動かされる口からは、声ならぬ声が溢れ続けている。
それは、歌。
先刻までの澄んだ歌声とは似ても似つかない、空気そのものが震え奏でる呪文のような、低い旋律の子守唄。
幻のような羽根のイメージが、イリィの姿と重なって視える。
呪歌が翼となって広がるように。
いや、幻などではない。
きっとすぐ近くに、確かに”羽根”は存在していて、急速に力を具現させようとしている。
目的もなく闇雲に、ただ、高圧の波動という形で、その力を誇示ようとしている。
イリィの生命力を代償にして。
そんなイリィのそのすぐ傍には、頭を抱えてうずくまるアシェルの姿がある・・・・・・・。
事態を把握した時には、カリムは既に目標を見定め、床を蹴って飛び出していた。
吹き荒れる波動に逆らい、その中心に立つイリィに向かって一気に距離を詰めると、鳩尾に掌底を当てて正確な一撃を放つ。
ショックでイリィの呼吸が一瞬止まり、紡ぎ手を失った旋律がプツリと途切れる。と同時に、波動の奔流は、嘘のように雲散霧消した。
糸を解かれた人形のようにくたりと崩れ落ちるイリィの身体を、カリムは腕を伸ばして受け止める。
が、うまく堪えきれずに、そのまま床に膝をつく格好になる。
大きく息を吐いたカリムの額に、汗が玉を作っていた。
(・・・・・・たく、大した仕事じゃないんだがな)
初心者の暴走を止めるくらい、羽根使いであれば出来て当然の、ごく基本的なことだというのに。
自嘲するように呟いてから、その場にイリィを横たえたカリムは、すぐさま傍に倒れているはずのアシェルを探した。
至近距離から羽根の波動を受けたアシェルは、舞台から砂の上に転げ落ちた格好のまま、完全に気を失っている。
アシェルが波動を受けていたのはごく短時間だったが、何しろ距離が近すぎた。しかも警戒すらしていなかった状態で、とっさに防御することも出来なかった。
羽根の波動は、今のアシェルにはとても危険だというのに。
カリムはざわめく鼓動を抑えて、ぐったりしたアシェルを出来るだけそっと抱き起こすと、血の気の引いた頬を包み込みように手を添えた。
「アシェル、大丈夫かアシェル!」
その瞬間、アシェルの瞳がカッと見開かれ、放たれた灼熱の光がカリムを捉えた。
「っ!」
カリムの喉を、ガッと重い衝撃が襲う。
甲冑のように硬質な黒い腕の先、節くれだった長い指を持つ巨きな手が、カリムの喉を押しつぶしながら万力の強さで締め上げている。
骨が軋むよりも先に、空気を絶たれた肺が悲鳴を上げ、頭の奥がじんと痺れる。
暗転しかける視界の端に、刃物のような鋭さを持つ五本の爪が閃いた。
ずぶり
肋骨を砕き、胸膜を突き破り、肺を切り裂いて、凶刃と化した爪先が狙うのは、カリムの心臓部。
心臓そのものではなく、それと同化して存在する、カリムの命の源であるもの。
”炎の結晶”と、それは呼ばれる。
普通の者には見ることも出来ず、傷つけることはおろか触ることも出来ないが、視ることの出来る者の”眼”には、高次元のエネルギーを更に極限まで凝縮させたような、炎の塊のように感じられる。
白亜の塔の所有する数ある魔道技術の中でも最高峰のものであり、それを授けられるのは羽根使いの中でも厳しい条件をクリアしたほんの一握りの者だけだ。
”炎の結晶”を身の内に抱えるが故の多大なる恩恵と、決して軽くはないリスク。
そのリスクを制して自らの力に変えることこそが、上級天使の第一条件である。
だが、万能であるかのような結晶も、時には脆く砕け散る。
例えば、生命力を高次元の魔道力に変換し発現する”羽根”の力によって。
あるいは、高位の魔物が有する魔力によって。
高位、高次とは、世界に及ぼす影響の深度のこと。どんなに大きな力でも、空の高み、水の深みに届かなければ意味がないように、何層にも重なった世界にも、次元の高み、空間の深みに似た概念が存在する。
高位の魔力をまとうアシェルの爪は、結晶に影響を及ぼす次元に十分到達出来る。
無慈悲なまでに正確に、カリムの内の結晶を目掛けて刃を突き立てていくアシェルの顔には、ただ、冥い虚無が広がるのみ。
(ごめん、アシェル)
これは、カリムの失態だ。
この事態が予測不可能だったとしても。そしてアシェルがどんなに怒っていたとしても。すぐに庇えるくらい近くに連れてくるなり、遺跡の外で待っているよう説得するなりすべきだったのだ。
羽根の波動は、それが攻撃の意図を持って放たれたのではなくとも、アシェルには凶器となってしまう。
どんなにその気配を封じ込めていようと、今のアシェルが魔物の力を持っていることは変えようのない事実なのだから。
強過ぎる波動を受けて、アシェルは意識を失った。そして制御を失い解き放たれた魔物の力は、所有者であるアシェルが最も必要とするもの、カリムの結晶へと狙いを定めたのだ。
(羽根を捨てておいて良かった)
咄嗟に自分の羽根の気配を探り、近くには存在しないことを確かめて、最初にカリムの頭に浮かんだのはそれだった。
でなければ攻撃を予測してしまった時点で、羽根はアシェルの身体を引き裂いてしまっただろう。カリムの意思に関係なく。
そのことに心底ほっとして、カリムは自ら目を閉じる。
遠いあの日。
燃え落ちようとする離宮の中で、カリムはアシェルの結晶を破壊した。
だが、その力は最後の最後で及び切らず、ほんの小さな欠片を残してしまった。
カリムはアシェルを解放出来ていなかったばかりか、長い間アシェルを辛い夢の中に眠らせてしまうことになった。
『この手でキミを殺さない限り、ボクの苦しみは終わらない!』
それは、再会したアシェルが、カリムに向けて叫んだ言葉。
憎まれて当然だ。
恨まれて当然だ。
だが、本当にカリムを憎み恨むのなら、そのまま放って置けばよかったのだ。
求めるものを決して得ることの出来ない世界の中で苦しみもがく様を、ただ、あざ笑っていればよかったのだ。
あの言葉は、白い闇の底にカリムを見つけ、救いに来てくれたアシェルの、覚悟の言葉だ。
カリムのためだけに、魔物の力すら取り込んで、アシェルはこの世界に留まってくれていた。
小さな欠片となってしまったアシェルの結晶を元に戻すことは不可能だが、カリムの結晶を破壊して内包されていた力を吸収するなら、アシェルは元の姿にだって戻れるだろうし、魔力を抑えたまま人間の中で生きていくことだって出来るはずだ。
イリィが羽根と関係があると判った以上、この地で暮らしていくのは難しいかも知れないが、アシェルならきっとどこでだって、誰とでも、上手くやっていくだろう。
安らぎを求めることなど、許されないと知っている。自分のしてきたことを思えば、何もかも投げ捨てて楽になるなど、決して望んではならない。だが、こんな命でもアシェルの役に立つのなら。
(もう、いいだろう?)
冷たく優しい真っ暗な闇に、全てを委ねてしまっても。
きつく眼を閉ざしてさえ刺すように眩しかった光が消え、ゾワゾワとざわめき騒ぐ音が引き、闇が、ゆっくりと頭をもたげる。
遠い幻の中、真っ白い閃光に飲み込まれて消えた、黒い影と同じ、黒い闇。
あの場所に行きたくて、だが、どんなに手をのばしてみても辿り着くことの出来なかった、遠く深い、懐かしい場所。
今なら、届くだろうか。
決して消えることのない古傷を刻む、この手の先に・・・・・・。
ひらり。
闇との間を隔てるように。
伸ばした手の先に触れられそうなほどすぐ傍に。
凍てつく夜に踊る極光のような、淡い虹色の裾を翻して。
立ち去ろうとしていたはずの後ろ姿が、一転、優雅なダンスターンをキメて振り返る。
夕焼けのような、朝焼けのような、暖かい光を背にして立つ、一人の女性。
その表情はおぼろげだが、口元に笑みを浮かべていることだけは解る。どこか痛みをこらえるような、それでも誰かの為に精一杯咲き誇ろうとする花のような、鮮やかな微笑みを。
”彼女”の口元が微かに動いて。紡がれた言葉が、風の中に溶けていく。
(何故?)
素直な驚きに、拡散しかけていた意識が引き寄せられ、鮮明になる。
(何故、ここで、現れる?)
あまりにも微かな、それでいて、狂おしいほどに懐かしい、淡い幻。
たった一人の、大切な人・・・・・・。
(貴女はアシェルの中に在るはずなのに・・・・・・これはアシェルのためになるはずなのに・・・・・・何故・・・・・・?)
笑顔を、見たいと思った。
曇りも憂いも無い、心からの笑顔を。
たとえ、それを向けられるのが、他の誰かであったとしても。
ただ、幸せで、世界のどこかにいてくれさえすれば、それだけで。
なのに、時を渡り、姿を変え、どんな制約さえも飛び越えて、こんなにも近くにいてくれた。
(・・・・・ああ、そうだな。これは、お前の意思じゃない)
今、カリムの結晶を壊そうとしてるのは、ただ暴走しただけの魔物の力。
アシェルがこの行動を選択しているわけではない。
(だったらきっと、お前は怒る)
このままカリムが委ねてしまったら。意識を取り戻したアシェルは激怒する。深く、傷つきながら。
たとえそれがアシェルのためだったとしても、知らない間にいなくなることは、アシェルにとってはこの上ない裏切りとなるはずだから。
(俺は、お前にやると約束した。お前が決めた”その時”に、お前自身の手によって)
それが今でないのは、残念ではあるけれど。
カリムはアシェルを抱く腕に力込めると、その小さな額に自分の額を押し当て、波動を送り込む。静かに、穏やかに。
アシェルの意を離れてその身体を支配している魔物の力を、宥め、眠らせるために。
永い永い永劫の時間、そうしていたような気がする。
だが実際は、爪による一撃がカリムの結晶に到達しようとするまでの、ほんの刹那の間のこと。
アシェルの、見開かれていた瞳から灼熱が消え、瞼がゆっくり閉ざされる。
黒い甲冑のような腕から力が抜けて、砂地の上にパタリと落ちる。
静寂に満たされていた空間に、じわじわと音が戻り始める。
本当に、耳障りだ。
一番の耳障りは、ゼイゼイヒューヒューと空気を求めて咳き込み足掻く、自分自身が発する音。
採光窓からホールに差し込むごく淡い光さえ、砂漠の灼熱のようにギラついて見える。
戻って来たのだ。喧騒の現実へと。
(何をやってるんだろうな、俺は・・・・・・)
カリムは激しく肩を上下させながら、腕で乱暴に口元を拭う。
遺跡のすぐ外で、小犬が激しく吠え立てている。だが、吠え声がそれ以上近付いて来ることはない。
普段は無謀に見えるほどやんちゃな子犬であっても、どんなに主人を心配しようとも、遺跡に立ち入ることを生き物としての本能が拒絶しているのだ。持って生まれた”格”の差は、そう簡単には越えられないものだから。
もっとも、あまり心配する必要はないだろう。羽根の力は、そのように命じられない限り、人間を標的にするものではない。彼の主人であるジーロも、三人組の少年達も、単なるショックで昏倒してしまっているだけだ。
彼らはじきに目を覚ます。
それまでに、やっておかなければならないことがある。
(愚図愚図するな、確りしろ! ”カリム”に弱さは必要ない!)
第11話 特別ということ
ぼんやりと霞んだ景色がだんだん晴れて行って、最初に目に映ったのは、高い丸天井を背にして穏やかに見下ろしている一人ぼっちの天使像。
五本の柱が舞台を囲んで立っていたのだから、像も最初は五人だったはず。
なのに今は、一本だけ残された柱の上で、たった一人だけ取り残されて。それなのにあんなにも穏やかな笑みを浮かべて。
見上げる者を優しく包み込みながら、誰かを、愛しい誰かを想って歌い続けている、気高い孤高の天使像。
その微笑みに誘われるように手を伸ばそうとした、その時。
「目が覚めたか?」
聞き覚えのある、だけど少し低く掠れたような少年の声。
その方向へ首を傾げると、天使像を戴く柱に背を預けて立つカリムの後ろ姿が見えた。
夢の続きのような穏やかに明るい光の中で、ゆるく束ねられた長い髪が真珠色の光を弾いて揺れている。
淡い色の服よりもさらに透き通るような、彫像めいた白い横顔。
首元に巻かれた深緑のストールが、光の中に溶けてしまいそうな姿を、辛うじて現実に引き止めているかのよう。
アシェルが釘を刺したくなるのも、解る気がする。
好きかどうか以前に、どうしても目を逸らすことの出来ない存在が、この世界にはあるのだから。
彼は何者で、どこから来たのか。
聞いてみたいと思う反面、何故だろう、それを知るのはとても怖い事のような気がする・・・・・・。
「気分はどうだ?」
再び、静かな口調で問われて、ようやくイリィはハッとして目を瞬いた。
先刻も声を掛けられたのに、返事もしないでついボーッとしてしまっていた。その間何を考えていたのか知られたはずはないというのに、何だか急に顔がかっかと火照ってくる。
けれど幸いと言うか何と言うか、カリムは柱を背にした格好のまま、振り向く素振りも見せなかった。
「あ、えっと、私・・・・・・」
そう言えば、どうしてこんな所で横になっているのだろう?
どうしてこんな所で眠ってしまっていたんだろう?
上手く目覚め切れていない時のような妙なフワフワ感が、今もまだ続いている。
「・・・・・・んん!?」
身体を起こそうとた途端、鳩尾の辺りに鈍い痛みが走る。けれどそれはほんの一瞬で消えてしまったので、気のせいだったのかも知れない。
ただ、ズキリとした妙に生々しい感覚に、これは夢の続きではなくちゃんと現実の世界なのだと、ハッキリと告げられた気がしたのは確か。
お腹に手を当てながら恐る恐る身を起こし、座り直して見回すと、ここは間違いなく遺跡の舞台の上。さらに言うなら、ダンスの練習に邪魔だからと畳んでおいたはずの緋色の上衣が広げ直されていて、その上に寝かされていたっぽい。
すぐ左側には、気を失ったように眠っているアシェルがいて、レモン色のブラウスが掛け布代わりに掛けられている。
「えっと、私・・・・・・みんなの前で歌っていて、それから・・・・・・?」
一生懸命思い出そうとしてみても、どうしても思い出せない。
多分、あまりにも緊張し過ぎて気を失うか何かしてしまった、ということではないだろうか。
アシェルまで眠っているのは・・・・・・イリィに付いている内に、自分も眠くなってしまったから、とか・・・・・・。
「あの、ごめんなさい。私、また何か、迷惑なことしちゃったんですよね・・・・・・」
せっかく、イリィの唯一の取り得の歌を聞きたいと言ってくれたのに。
それからふと、辺りが静かであることに気がついた。
「ええと、ジーロやコリオたちは?」
「あいつらなら、先に帰した」
「そう・・・・・・そうですよね・・・・・・」
コリオもレノもエリオットも、本当に久しぶりに顔を合わせた。
久しぶりなのに、三人とも以前の悪戯っ子のまま、全然何も変わっていなくて。
あのまま、また、友達に戻れそうな気がするくらい・・・・・・。
でもあの三人は、別にイリィに用があったわけではない。カリムに強引に連れて来られただけ。
だからイリィが倒れてしまった後は、やれやれと帰って行ったのだろう。ジーロを連れて。
「あいつらがどうかしたか?」
「ううん、何でもない・・・・・・」
期待してはいけないことだ。
期待しなければ、どうってことはない。
「だよな。お前が気にする必要などない」
「・・・・・・?」
「お前は、あんな奴らとは”違う”のだから」
「・・・・・・え!?」
小さな子どもを諭すような静かで優しい口調でありながら、きっぱりと告げられたその言葉に、イリィの心が激しくざわつく。まるで夜の岩場に砕ける波のよう。
柱を背にし、イリィに顔を向けぬまま、カリムはゆっくりと口を開く。
「お前のことは、大体、あいつらから聞いた」
「!」
その瞬間、イリィはビクリと肩を震わせ、身を竦める。
「あいつらが言うには、お前に関わると災難に遭うのだそうだ」
そんなイリィに構うことなく、カリムは言葉を続ける。ごく静かな声で、至極当たり前のことを告げるように。
「怪我をしたり病気になったり」
(やめて・・・・・・)
「家が燃えたとも言っていたな」
(知らない! そんなの知らない!)
心の中で叫びながらも、イリィの内に過去の記憶が頭をもたげる。
そうだ。
本当は。
自分に関する不吉な噂を、全く知らなかったわけではない。村人がよそよそしくなり始めた頃、そんな話はどこからともなく耳に入って来た。
人の不幸を望むつもりは全く無いのだと、どんなに訴えかけてみても、その場限りの作り笑顔をされたり、キッパリと無視されたり、そ知らぬ顔でさっさと立ち去られたり。そして何よりも、彼らの目の中に、怯えの色が浮かんでいることに気がついてしまった時・・・・・・イリィは弁解することを諦めた。彼らに期待することを止めた。
「不幸な災難は、何でもかんでも他人のせい、か」
「・・・・・・」
「少しでも”自分たちと違う”者を見つければ、平気で非難し攻撃する。ちょっと下手に出てやれば勘違いして、いくらでもつけ上がる。まったく始末に終えやしない」
「・・・・・・え?」
イリィは思わず、伏せていた目を上げる。
関わった者を不幸にしてしまうという事実を内緒にしていたイリィのことを、カリムは不快に感じているのだと思っていた。それなのに、何だか話の風向きが違う気がする。
「ただの人間とは、憐れな生き物だな」
けれどその声からは、哀れみも蔑みも、伺えはしない。ただし、同じ人間としてではなく、高みから卑小な下界を見下ろす者の言葉で、カリムはハッキリと、その言葉を口にした。
イリィに、同意を求めるように。
「何を、言って・・・・・・?」
心臓がドキドキと、怖いくらいに大きな鼓動を響かせる。
聞いてはいけない。
心のどこかが、激しく警鐘を鳴らしている。
「そんな連中のどこに、自分の心を偽ってまで優しく慈悲を垂れてやる価値がある?」
それは、問う者はもちろん、問われる者もまた高みの存在であることを前提にしてしか、発することの出来ない問いかけだった。そして、問われているのは、他ならぬイリィ自身だ。
「だって、あなたにはそうでも・・・・・・私は、ただの村娘で・・・・・・見かけはちょっと変わってるかもだけど、それで何か特別ってワケじゃないし、どっちかって言ったら何にも出来ない方で、みんなのお荷物になっちゃてるのは本当だし、だから、我慢出来ることは我慢しなきゃならなくて・・・・・・でもいつか、村のために何か役に立てたら、みんなはきっとまた認めてくれるようになって、それで・・・・・・」
「何故下を向く? お前はここの村人ども、いや、下賎な人間どもとは違う」
ダメだ! 聞いてはいけない!
心が悲鳴のように叫んでも。
耳を塞ぐ手をすり抜けて、運命を宣告する言葉は容赦なく、イリィの中に流れ込む。
「お前は、大いなる御手に選ばれた”力”を持つ存在なのに」
「・・・・・・!」
一瞬にして目の前の見知った景色が全て崩れて行くような、そんな錯覚がイリィを襲った。
「まさか自分で気付いていない訳ではないだろう? 気付いていなかったのなら、それは周りの連中の所為だな。お前の”力”を妬んで、卑小な者のように誤解させたのなら」
「あの・・・・・・何を、言ってるんですか!? 力なんて知らない。そんなもの、私には、これっぽっちも・・・・・・」
「呪歌使い」
「・・・・・・!?」
初めて耳にする響きに、知らずイリィは瞠目する。
「お前の歌には”力”がある。特に子守唄。あれを歌うお前には、魔物を殲滅させるくらいの強い力が秘められている。そうだな。使い方次第では、人間を操るくらい簡単だ」
「・・・・・・私の、歌・・・・・・?」
「そう。見物だろうな。今まで自分らとは”違う”と見下していた者どもが、一転、救いを求めてお前の足元に平伏す様は」
「そんな・・・・・・私はそんなの望んでない! 私に力なんて、あるはずない!」
「ふうん? それならこの先ずっと、非力な小娘を演じ続けるつもりか? 一生、こんな小さな村の中で?」
「・・・・・・!」
「村を一歩出れば、色んな街があるし、色んな国がある。お前と同じような容姿の奴どころか、もっと奇抜なのさえ珍しくも何ともない。お前ほどの力があれば、どこでだって好きなように暮らしていける」
「やめて・・・・・・」
「誰に遠慮することなく、思う存分、好きな歌を歌って暮らせる」
「やめて・・・・・・!」
「何故? それが”力ある者”の、当然の権利だろう?」
この期に及んでも、カリムの口調ははごく静かで、語りかけるその声はとても優しかった。
このまま頷いてしまえたら、どんなに楽になれるだろう。
「やめて! そんなの欲しくない! 私は、私は・・・・・・!」
だが、誘惑を振り払うように、イリィは必死に声を上げた。
「ならば、お前は何を望む?」
「ここで、この村で! お母さんと、みんなと、仲良く幸せに暮らすこと! それだけでいいのに、それなのに、どうして・・・・・・」
「本当にそうか?」
「人に言うことを聞かせる力なんて、そんなの要らない! 無理やり人を振り向かせたって、それじゃ一人ぼっちなのと何も変わらない! そんなの違う! 絶対に違う!」
「ではこのままでいて、幸せか? このままお前一人が我慢していれば、いつかは全てが良くなるとでも?」
「やめて! やめて! やめて!」
「お前は、全然悪くない。村人とは違うとこも、力が使えることも。悪いのは・・・・・・」
「聞きたくないっ!」
その瞬間、イリィは立ち上がっていた。
ようやく、彼女をここに縫いとめていた力を振り払うのに成功したかのように。
「どうして! あなたにそんな事が解るんですかっ! あなたとは昨日会ったばかりで、お話だってほんのちょっとしかしてなくて、それなのに私のことが解るだなんて、そんな事あるはずないでしょ!? 私が・・・・・・私が悪いことなんて、そんなのいっぱいあるに決まってますっ!」
叫ぶや、イリィはそのままホールを飛び出した。
これまで小さく立ち竦んでいたのが嘘のように、一目散に、振り返りもせず。
イリィの姿を静かに見送って。
「そうか。悪いのは自分、か・・・・・・」
カリムはそっと、一人ごちる。
「う・・・・・・ん・・・・・・」
その時、微かな吐息とともに、アシェルが身じろぎして睫を揺らせた。
「・・・・・・今の・・・・・・イリィ?」
まだ虚ろな意識の中で、アシェルは小さく呟いた。
少女の、激昂する声が聞こえた。
いつも穏やかで、優しくて、辛いことを全部自分の中にしまい込んで、人に見せまいとしていたイリィが、はじめて見せた身の内の激情。
そうか。
イリィはようやく、自分の中に押し込めていた感情を吐き出すことが出来たのだ。
「・・・・・・だけどその役、ボクがやるつもりだたんだけどな。思いっきりハラ立つよーな台詞、考えてるとこだったのに」
半ば夢うつつの声で、アシェルは近くにいるだろうカリムに向けて話しかける。
「それは悪いことをしたな」
思った通り、すぐ近くから応えが聞こえた。
「そうだよ。憎まれ役なんかより、素直にイリィの憧れの人をやってれば良かったのにさ」
「優しく慰め役に徹しろとでも? 向かないと思うぞ、俺は」
(そりゃまあ・・・・・・それ以前に、目の前でイチャつかれるのはオモシロくないけどね・・・・・・)
妙にぼうっとする頭を振りつつ、霞む目を擦ろうとして何気なく右手を上げたアシェルは、自分の手の奇妙な感触にハッと目を見開いた。
黒い光沢を持つ鎧のような腕。奇怪に長く伸びた指先には、鋭い刃物のように凶悪な爪。
砂埃の絶えないこの場所で、たった今磨いたばかりのような光沢を放つ、それ。
「・・・・・・そっか、イリィだね」
思い出した。
アシェルが気を失う前、イリィは歌を歌っていた。いつもより真摯に、精一杯。歌うことで、どんどん心を研ぎ澄ませていった。
もしかしたら、何か強い願いを歌に託して。
おそらく、そんなイリィの”呼びかけ”に反応し、さほど遠くないどこかで所有者を待ち望んでいた羽根は、嬉々として力を解放した。
だが、それはアシェルにとっては完全なる不意打ちで、羽根の波動にさらされて意識をなくした自分は、支配されてしまったのだ。自分の中の、魔物の衝動に。
そうなった自分が取った行動は、ただ一つ。
アシェルは腕を元に戻すと、柱に背を預けて立ったままのカリムを見上げた。
「何してるのさ、そんな所で」
「別に、何でも・・・・・・」
素っ気無い上に、妙に歯切れの悪い返事だ。
そんなカリムの肩から首にかけて、ストールのようにゆるく巻かれている絹布には見覚えがある。差し入れの服に着替える前に自前で使っていた、奇跡的に大きな破損を免れた薄絹の帯だ。
ファッション的にはなかなか似合っているのだが、カリムは理由も無くそういうことをするような性格ではない。
「ねえ、こっち向きなよ。そんな風に立ってられたら、話しにくいでしょ」
「・・・・・・ああ」
だが、カリムは一向に動こうとしない。
「ボクの言うことが聞けないっての?」
「・・・・・・」
「何かやましいことでもあるのかなー?」
追及の声が、段々怒気を増してゆく。
そう、アシェルは怒っていたのだ。気を失うよりもっと以前から。ただ、大勢の手前もあって、自制していただけで。
白ーい目で睨み続けてたっぷり一分以上も経過した頃、カリムは渋々の体で、横顔を僅かにアシェルに向けた。
「ほら、とっととこっち来る!」
「・・・・・・」
黙っているカリムに業を煮やしたアシェルは、すっくと立ち上がると、柱ごしに絹帯に手を伸ばす。
だが、素早く身を引いたカリムによって、すんでのところでアシェルの手は空を切った。
「と、見せかけて!」
そのままフワリと宙に舞ったアシェルは、頭上からカリム目掛けて急降下をかける。
「!」
どしゃ!
「アシェル、それ、卑怯・・・・・・」
カリムが避ければ、アシェル自身が地面に激突しかねないような、無謀な突撃を仕掛けるのは。
ぶつかられた勢いで背中から砂地に転がったカリムは、腕の中のアシェルに恨めしそうな目を向ける。
「だーまーれ! 最初から素直に言うこときかないからそーなるの! 前にも言ったけど、ボクの方が強いんだから逆らったってムダなの!」
アシェルはカリムの腕の中から強引に抜け出して、胸の上にちょこんと馬乗りになるや、躊躇なく首元をゆったりと覆う絹帯に手をかけた。
「やっぱり!」
絹帯が緩んであらわになったカリムの喉には、締めつけられた名残の赤い痣がくっきりと浮かんでいる。
それに、血に染まった上衣の胸元は、小さな裂け目が穿たれていて、それはちょうど魔物化した時のアシェルの手の大きさと符合する。
(我ながら的確な攻撃だね・・・・・・)
傷口に指を這わせて確かめたアシェルは、詰めていた息を吐き出した。
「・・・・・・これだから白っぽい服は困るんだよな。ちょっとしたことでも大げさに見える」
往生際悪くそっぽを向いたまま、カリムはそんなことを口にする。
「あのねえ、そんなド下手な対応で、ボクを誤魔化せると思ったわけ?」
全く呆れた話だ。いくら取り繕ったところで、アシェルの魔物化した手をどうにも出来ない以上、バレないわけがないというのに。
「・・・・・・誤魔化されてくれればいいな、くらいには」
それでも怪我を負わせたことまでは、知られずに済むに越したことはない、と言いたいらしい。
アシェルの手に付着したはずの血を綺麗に拭ったのも、きっと同じ理由でだ。
「ったく。もっとちゃんと避けてくれないと、安心して暴走出来ないんだけどね!」
「ちゃんと避けたろ。こうして無事でいるんだから。ほら、自分で言ってただろ。お前の方が俺より強いんだって」
「うっわ、そー来るかなっ!」
これでもかというくらい”怒”マークを顔に貼り付けて、アシェルは思いっきりカリムを睨みつける。
「そう怒るなって。こんなのどうって事ない。どうせすぐ消えて無くなるんだし」
カリムが言う通り。
出血は既に止まっていて、乾いた血が紅玉のように傷口を覆っている。
服に染み込んだ血の跡も、パキパキと結晶状に固まり始めていて、端から徐々に昇華して消えていきつつある。
喉の赤痣もまた、見る間にじわりと小さく薄くなっていく。
本当にもう少し経てば、そこに傷があったことなど完全に判らなくなってしまうだろう。
服に引っ掛けたような小さな裂け目を刻んだ以外、何の痕跡も残すことなく。
この回復能力もまた、炎の結晶のもたらす恩恵の一つだ。
「だから何さ!」
アシェルはカリムの目の前に、掌を上にした右手を突き出した。
「はい! ボクから取ったヤツ、返して!」
砂の中から見つけて懐に入れたはずの、紋章入りのガラスの小瓶が無くなっている。
アシェルが気を失っていた間に、カリムが取り返したのに違いない。
その紋章を見た時、正直、少し驚いた。”矛に三対の翼”は同じでも、その中央に配されているのは”光条を放つ星”だ。”交差する月”がカリムの紋章だとすれば、その小瓶はカリムの物ではないことになる。
だが、とりあえず今一番重要なのは、その中身だ。
「キミ、薬酒持ってたんだね。なのに・・・・・・ったく、何考えてんのさ!」
思えば昨日、アシェルが薬酒に言及した時も、カリムの態度は明らかにおかしかった。
”炎の結晶”と同化した命を持つ者にとって、薬酒は必要不可欠だというのに。
第12話 炎の結晶
何もかもまっさらで目覚めた、白い部屋。白い空間。どこまでも白い、閉ざされた世界・・・・・・。
そこにいた者は皆、同じようなフード付きの装束をまとい、同じ目的の為に、いつ何時でも同じように立ち働き続けていた。
そして、そこにいた誰もが同じように、恭しくへりくだった態度で、この自分に接した。
『素晴らしい命です』
だからそいつも、そんな者の中の一人だったはずだ。
『炎の結晶と同化できるのは、本当に選ばれた者だけです。数少ない羽根使いの中でも、真に特別な存在なのですよ』
そう。真っ白に閉ざされた小さな世界の中で、自分は特別な存在だった。
『ただの羽根使いなど、所詮は人間と変わりません。羽根に命を注ぎ過ぎれば、それだけで死んでしまう。怪我でも、飢えでも、病気でも、呆気なく簡単に死んでしまう、か弱く憐れな存在でしかありません』
おかしなことを言う。羽根使いですらない彼らもまた、ただの人間でしかない者達だというのに。
『ですが炎の結晶と同化した命は違います。人間にとっては致命傷のような怪我を負ったとしても、たちどころに回復出来ます。当然、病を得ることもありません。それに年を取ることも、加齢によって肉体が崩れ衰えることもなくなるんですよ。つまり、死を恐れる必要が無い。どうです? 素晴らしいと思いませんか?』
目深に被ったフードの下の表情は窺い知れなかったが、うっとりと夢見るような響きを持つその声は、妙に耳の奥を揺さぶった。
『炎の結晶とは・・・・・・そうですね、たとえて言うなら精巧な機械のようなものです。数々の優れた性能が備わっている一方で、燃料となるものがが無ければ機能しません。炎の結晶が機能するのに必要なのは”炎の雫”。薬酒という名で供される飲み物のことですよ』
あの声の内に潜むのは、羨望だったのか、それとも自尊心であったのか。
『薬酒を常に取り入れる事によって、結晶は膨大なエネルギーを蓄積出来ます。エネルギーを蓄積すればするほど、長時間フルパワーで羽根の力を発揮することが可能となりますし、肉体に回復力を供給することを始め、様々な恩恵を得ることが出来るというわけです』
炎の結晶と同化する者を造り出すという、高度な魔道技術を思いのままに出来るが故の。
『羽根、炎の結晶、炎の雫。この三者は互いに共存し、拮抗し、はじめてその機能を存分に発揮出来る。それでこそ、命は最高にして完璧となるのです』
完璧でないはずの人間の手によって、完璧なる者を生み出し制御する事に対する自信、優越心。
彼らは自らを”真理の番人”と称していた。
「ねえ、どうして薬酒を捨てちゃったりするのさ! それって絶食するのと同じなんだよ? って、キミが一番良く知ってるハズだよね!」
「・・・・・・捨てたんじゃなくて、隠しておいただけなんだが」
激怒するアシェルに対し、カリムはどこまでも暢気に応じる。
「いざって時に使えないんじゃ、捨てたのと一緒でしょ! しかもボクに内緒で!」
「いや、それは、つい・・・・・・余計な事ばっかやる馬鹿に腹が立ってだな・・・・・・」
やはり、あの”光条を放つ星”の紋章の持ち主は、カリム言うところの”あの馬鹿”で間違いなさそうだ。
「誰のかなんて、今はどーでもいいでしょ! てか、そもそもカレは何でキミに薬酒をくれたワケ? キミが自分の分を持ってないって知ってたからじゃないの?」
アシェルは不信感満載の目で、カリムを見下ろす。
「それは・・・・・・お前と再会したあの時、俺たちは任務帰りだったって、それだけだ」
「じゃあ、キミの分はとっくに使い済みで、それを知ってたカレが気を利かせてくれたってコト?」
「まあ、そんなトコ」
「本当に? それだけ? あの混乱の中でわざわざ?」
任務時に携行することが常の薬酒の瓶は、もしも多大なダメージを受けてしまった時や、数日に渡って塔と連絡が取れないような状況に陥った場合に備えての命綱だ。
それを人に譲ることが、どういうことなのか。
ついに上級天使として任務に出ることの無かったアシェルだが、それくらいのことは想像出来る。
「・・・・・・それじゃあ、そういうコトにしといてあげてもいいケドさ。変な意地張って捨てちゃって、その後どうするつもりだったのさ?」
「どうって・・・・・・」
「ハッキリ言うけどね、キミの結晶、もう大概エネルギー切れになってるでしょ」
アシェルの目には、カリムの不調は明白だ。その理由もまた、明白だ。
必要なものが不足すればどうなるか。当然、結晶は機能しなくなる。そうなれば”力”を発揮出来ないどころの問題ではない。
「言うまでもないけど、動けなくなってから飲もうったって手遅れなんだからね。怪我してから鎧着ても遅いのと一緒で! だからほら、早く出す!」
「大げさだって。常に自分の状態を把握するのは基本中の基本、だろ? 俺だったらそんなすぐにどうにかなったりしないし、怪我だってちゃんと治ったろ? このままでもまだ十分戦える」
「だーかーら! キミの大丈夫ほど信用出来ないものはないってゆーの!」
「ヒドい言われ様だな」
アシェルは大きなため息をつくと、胡坐座になって腕組みをする。
「何がそんなに気に入らないワケ?」
「不味いから」
「殴るよ?」
「じゃあ聞くが、好き嫌いに理由なんて要るか?」
好き嫌いと聞いて、アシェルは思わず視線を泳がせる。
「・・・・・・ええと・・・・・・ニンジンとか、カブの酢漬けとか?」
「そうそう。内臓肉のパイとか。見かけだけは美味そうなのに、アレはねーよなアレは」
「それを言うなら塩漬け魚の包み揚げだよ。香ばしい匂いでユーワクしときながら、あの強烈なしょっぱさは裏切りだよ!」
「聖夜祭のプディングなんかもそーだよな」
「えー、あれは美味しいでしょー?」」
「ああ? 嘘だろ? あんな香料キツくてだだ甘いののどこがいいんだよ?」
「あれはあれでクセになる味なんだけどなーって、そーじゃないでしょ! 嫌いな食べ物は食べなきゃそれでいいけど、薬酒の代わりなんて無いんだから、意味が全然違うでしょ!」
「そーかあ? 似たようなものだと思うがな」
「似てません! ・・・・・・ねえ、ハッキリ言えば? 副作用が嫌なんでしょ」
「・・・・・・」
慇懃に手を取って導きながら、その番人は語り続ける。
『・・・・・・一つだけ、注意しなければならない事があります。ただの人間にとって、薬酒は強すぎる麻薬のようなものです。もしも怪我や病気に苦しんでいる人間をどれほど哀れに思っても、決して薬酒を分け与えてはいけません。与えたら最後、その人間は回復の代償に心を食われ、薬酒を求めて動くだけの屍のようになってしまいますからね』
『・・・・・・!』
『おや、怖がらせてしまいましたか? 大丈夫、あなたが心配する必要はありませんよ。結晶を持つ者には、そんな危険は全くありませんからね。むしろ怒りや恐怖や不安といった余計な感情を洗い流してくれる、とても便利なものですよ』
『・・・・・・それは、何も感じなくなるってこと? それとも記憶がなくなるってこと?』
『大丈夫、感情も記憶も、無くなったりはしませんよ。ただ、過去に感じた事が曖昧になる、それだけのことです』
『・・・・・・それだけの、こと?』
『そうですね。例えばあなたが、何かとても怖い目に遭ったとします。怖い事は、早く忘れてしまいたい。これが人間であれば、忘れたい事ほどなかなか忘れられずに苦しむものです。薬酒はね、それを消し去ってくれるんですよ。どんなに怖い事も辛い事も、少しずつ曖昧になっていって、やがて解放されるのです。忘れたなんて自覚もないくらい、ごく自然にね』
『・・・・・・それじゃあボクは、もう既に何かを忘れてて、忘れた事さえ忘れてて、思い出せないだけなのかな?』
『それは、誰にもわかりません。忘れるとは、そういう事ですからね。だからと言って、それで何か困ったことがありますか? 無いでしょう?』
『・・・・・・それは、本当にいいことなの?』
『もちろんですとも! 戦闘経験は蓄積しつつも、トラウマのような精神的ダメージに悩まされる事なく、常にベストの状態で強大な力を発揮して戦える。あなたのような”戦う者”にとって、こんな理想的なものはない。そう、思いませんか?』
『・・・・・・でも、それは、あの土人形とどう違うの?』
訓練の相手としてあてがわれる土人形。命令されたことのみを忠実に実行する以外、自らの意思は持たず、呪力核を破壊しない限り何度でも立ち上がる、あのゴーレムと。
『もちろん、全然違います。ほら、彼らをご覧なさい。ゴーレムはそんな穏やかな表情をする事など出来はしません。あなたにもすぐに解りますよ』
『・・・・・・』
『おや、気に入りませんか? それでは一つ、いい事を教えてさしあげましょう。それはね・・・・・・』
薬酒は経験した出来事を洗い流すものではない。ただ、その経験をした瞬間に何を思い感じたかを、静かに消し去って行く。
だが人間とは、体験したことをその瞬間の感情と共に記憶するものではないだろうか。時と共に具体的な記憶は薄れたとしても、楽しかった、あるいは怖かったという感情は、後生覚えているものではないだろうか。
伝え聞いたり調べたりして得た情報以上に自身の体験が意味を持つのは、それを体験した時の感情の起伏が同時に記憶されるから。だとすれば、感情を伴わない記憶は、単なる記録でしかない。
ただの記録は、知識の海の中に埋没し、情報の渦に呑まれてしまう。簡単に、容赦なく。
アシェルは覚えている。
アシェルになる以前のことも、アシェルになってからのことも。
あの日、薬酒に頼らない方法を選んだアシェルには。
けれど、カリムは思い出を持たない。
カリムになる以前のことはもちろん、それ以後のことですら。
塔に降り、薬酒の力を借りて戦い続けることを選んだ時に、それは決した。
「ねえ、薬酒を要らないって言うのなら、知ってるよね、他にも方法があるってこと! 結晶の色を変えてしまえばいいんだよ! ボクみたいに・・・・・・!」
さらに言葉を続けようとした、その時。
一瞬で視界の中のカリムが消えて、代わりに高い天井を見上げる格好になり、アシェルはパチクリと目を瞬かせた。
何の前触れも無しにいきなりカリムが上体を起こしたせいで、その上に乗っかっていたアシェルは、カリムの膝の上にコロンと背中からひっくり返ってしまったのだ。
「何すんのさっ!」
事態を理解し憤慨するアシェルに、カリムは悪戯っぽく笑ってみせる。
「お前があんまり深刻な顔してるんで、つい」
「ついじゃないっ! ったく、ヒトがマジ心配してるってのに、キミってば、もう!」
「それなんだがな。見てくれはこんなでも、俺はガキでも悲劇のヒロインでもないんだぞ。薬酒の特性は知ってる。知っていて、それを選んだ。今更グダグダ言う気は無いよ」
「・・・・・・じゃあ?」
「俺はね、今、すごく幸せなんだと思うぞ」
「・・・・・・はい!?」
思いがけない告白で、アシェルは不覚にも言葉に詰まる。
「塔から飛び出せて無茶苦茶せいせいしたし、これから何やったって自由だし、何よりお前がいるもんな」
「ちょっっっ! もう、真顔で何言ってんのさ!」
「だから、忘れてしまいたくないな」
「だったら!」
「それに、俺の不器用さは良ーく知ってるだろ?」
今でこそそれなりにコントロール出来るようになったものの、訓練時代のカリムは毎日のように力を暴発させていた。
「考えてもみろよ。ここで力の質を変えたりしたら、慣れるのにどれだけかかるか知れたものじゃない。この期に及んで役立たずになんてなりたかねーよ。ハッキリ言って」
「・・・・・・」
「だから、こうしないか? もう絶対捨てたりしない。必要だと判断した時はちゃんと使う。それまでは、俺のスキにさせとく。な?」
「・・・・・・ホントに? ちゃんと使う? 約束出来る?」
「ああ」
(・・・・・・だったらどうして、そんな風に笑うのさ? 嘘つき・・・・・・キミはいつも、いつだって・・・・・・)
アシェルはふいとカリムの膝から砂地に降りると、背を向けたままでビッとホールの奥を指差す。
「・・・・・・あーもう! やってらんない! お酒ちょーだいお酒! ボク今すっごく飲みたい気分!」
そっちが、ぶどう酒の隠し場所。
「許してあげる」とは絶対に言いたくなかったから、その代わりに。
「ありがとう」
「だから、許すなんて言ってないからっ!」
「ああ」
アシェルの背後で、砂を払って立ち上がったカリムが、指差した方向に離れていく気配がした。
わざと反対方向を向いたままで舞台の上に戻ったアシェルは、膝を抱えて座り込む。
(どうして、あんなこと言っちゃったんだろ・・・・・・)
実のところ、エネルギー切れを心配しなければならないのは、カリムに限ったことではない。
結晶の欠片に残った僅かな力を、小さな身体になることで辛うじて維持しているアシェルもまた、今のままではそう長く動いてはいられない。
”カリムを殺すこと”を条件に契約を交わしたアシェルは、それが成就されない限り、魔物としても中途半端だ。
カリムは躊躇いもせず、自分の命を使えと言う。それが自分の望みだから、と。
だけど。
どんな手段を取っても良いのなら、一緒に生きられる方法がある。
炎の結晶を黒い炎で満たし、名実ともに黒翼の天使になればいい。余程の事情が無い限り黒翼同士の争いは禁忌だから、アシェルの条件は変更される可能性がある。
それより何より、黒翼には薬酒など必要ないし、想いを食われることもない。もしかしたら、”カリム”になる以前の記憶を取り戻すことだって出来るかも知れない。
アシェルがかつて選んだのと同じように。
(だけど、解ってる。キミは絶対に、それを選ばない。あの時ですら、選ばなかったんだもの・・・・・・)
あの白い部屋が連なる離宮が、世界の全てだった頃・・・・・・。
大勢の番人たちに囲まれて、どんなに大切に扱われても、それでもボクは一人だった。
誰とも違う。同じにはなれない。どんなに何かを訴えても、誰も解ってなんてくれない。誰にも理解を求めちゃいけない。だってボクは特別だから。理解を求めたところで、それは誰にも解らないこと。
そんなボクの前に、ある日突然現れた、ボクと同じ存在。それがカリム。
キミだけは解ってくれたね。ボクの痛みも、辛さも、怖さも。だって、ボクたちは特別で、同じだったから。
キミと一緒にだったら、ボクはどこにだって行けるし、どんなことだってやれると思えた。世界だって救えちゃうくらい、強くなれる気がしてた。
だけど、ボクは気付いてた。
いつも決して弱音を吐こうとはせず、どんな時でも強気の笑顔を見せながら、キミは心の中では、全てから解放されることを切望してた。
気付いてしまったからこそ、それでもずっと一緒にいてほしくて。ボクはキミに会いに行っては、とりとめのない夢の話をし続けた。
気付いていたからこそ、番人どもがボク達に対して行った手酷い裏切りを知った時、一緒に死の世界に眠ることが幸せなのだと信じた。
でも、それは間違ってた。
ボクと同じ存在でありながら、同じ事実を知りながら、そしてあれほど解放を望んでいながら、キミが選んだのは生き続けることだった。
アシェルを否定してでも、生き続けることだった。
もしもカリムが塔を捨てて生き続けることを望むなら、あの時こそ黒い炎を受け入れているはずだったんだ。
その後だって、きっと、機会は何度もあったはず。
それでもキミは、黒い炎を選ばなかった。
だから再会した時だって、キミは天使としてボクと相対した。
だけど、今のボクにはもう少しだけ、あの時見えなかったものが見える。
”アシェル”になる前の事を思い出したボクは、いつの間にか、キミと”彼”とを混同してた。
ボクを否定したキミと、ボクを置き去りにして戻って来なかった”彼”を。
まさかキミが本当に”彼”だったなんて。
”カリム”になる以前の全てを奪われているはずのキミが、それでもずっと探し続けてくれたなんて。
”彼”にとっての”彼女”を。
アシェルになる前の、ボクのことを。
それが、キミが生き続けることを選んだ理由だったなんて。
それを知った時、どんなに嬉しかったか。
そして、どんなに悲しかったか。
キミは今、ボクのために出来ることは何でもやろうと考えているね。
ボクが”彼女”だったことを知ってしまったから。そして、ボクの中には今も”彼女”が存在していると思っているから。
キミの一番は、アシェルではなくて、アシェルになる前の”彼女”だから。
だけどアシェルは、”彼女”とは違う。
いくらアシェルに”彼女”の記憶があったとしても。
かつて”彼女”として生きていたのだとしても。
キミが想い描く”彼女”は、黒い炎を望む存在ではないよね。
美しい世界の中で、何があっても気丈に笑う。きっとそれが、キミの大好きな”彼女”だよね。
アシェルは、カリムのためなら何だって出来る。世界を破滅させることさえ厭わない。
黒い炎を受け入れるとは、つまり、そういうことだから。
キミには出来ないよね。ボクのために、世界を滅ぼすなんてことは、絶対に。
『おや、気分を害されましたか? でしたらお詫びに、いいことを教えてさしあげましょう。炎の結晶は薬酒を求め、薬酒は代償として想いを必要とする。でも本当はね、自分で代償を払う必要なんて、これっぽっちもないんですよ。ただ、そういうことにしておく方が、連中には都合が良いというだけのこと。・・・・・・ほら、これが見えますか? 綺麗な黒でしょう?』
目深に被ったフードの奥で。血のように赤い唇の端を引き上げて、そいつはニイーッと笑みを浮かべた。
あれは番人の中の、誰か、だったはず。
怒りに身を委ねたアシェルの炎に飲み込まれ、消えて行った、あの場に居た大勢の中の、誰か・・・・・・。
不意にぞくりと背筋を震わせたアシェルは、知らずカリムの背中を追うように視線を巡らせ・・・・・・砂の上に落ちているそれに気が付いて。
「あーっっっ!!!」
悲鳴のように一声叫ぶや、アシェルは放たれた矢のように一直線に駆け寄った。
第13話 告白
自分でもよくわからない切羽詰った感情に突き動かされて神殿を飛び出したイリィは、わき目もふらずに飛ぶような早さで、村への道を下っていた。
ひどく嫌な気分だ。
心が黒い靄で覆われたような、自分がひどく惨めであるような。
あの神殿はイリィの大好きな、とっておきの場所だった。
この坂道は何度も、数え切れないくらい何度何度もも往復した、窪みや石の一つ一つさえ熟知しているほどの、通い慣れた道だ。
いつもならどんな嫌な事があっても、神殿で歌いさえすれば少し気分が軽くなる。神殿を後にする時は、後ろ髪を引かれる気持ちを断ち切るのに、かなりの思い切りが必要で。だから、こんなに急いで駆け下るなんてことはしない。
なのに今は、一刻も早く、あの場を離れてしまいたい。
何も無かったのだと、忘れてしまいたい。
だって、そんなことはありえない。
あってはいけない。
自分が神様や天使様や妖精さんのように、”ただの人間”とは違うだなんて、そんなの絶対にあるわけない。
夢だ。夢に決まってる。
あれはきっと、この村を逃げ出したいと思うイリィの弱さが見せた、一時の夢。
自分は価値のある者だと、村のみんなに受け入れられてもいい存在なのだと思い込みたかった、バカな自分が見た、儚い夢。
だけど、もし・・・・・・カリムに面と向かって問いかけられていたら。あの蒼い瞳に見据えられ、手を差し伸べられでもしていたら。
あんな風に拒否することが出来ただろうか。声を上げることが出来ただろうか。
だってそれは、イリィが心のどこかで思い描き続けてきた願いでもあったから。
でも、イリィにとっての現実は、この村での生活にある。
現実を見失なわない内に、どこかに迷って行ってしまわない内に早く、誰かに会いたい。
だけど、今、村の誰かに会ってしまったら・・・・・・。
いつ転んでもおかしくないほど機械的に回転していたイリィの足が、途端にひどく重いものに変わる。
今、村の誰かに会ってしまったら、もう、ダメかも知れない。
心にぽっかりと空いた、大きな穴。
気が付かないフリをして、目を逸らし続けてきた暗い穴の中に、今度こそ落ち込んで、出て来られなくなってしまうかも知れない。
(お母さん!)
それがイリィの、助けを求めるべき、たった一人の大切な人。
顔を見たい。
その腕の中に飛び込みたい。
今、すぐに。
だって、そうでないと・・・・・・。
イリィは一度立ち止まってから、小さく一歩を踏み出した。
村の外周へ続く道を外れ、お母さんの待つ家へ真っ直ぐ向かう方向へと。
その時だ。
「待って! イリィ!」
不意にそんな声が聞こえて。
意表をつかれて凍りつきかけたイリィは、慌てて足を前に出すことに全意識を集中する。
今はダメだ。
心が一杯いっぱいで、これ以上何か言われることに耐えられそうにない。
「待って! お願いだから、イリィ!」
けれど。懇願する声に、ひどく真剣な気配を感じて。
イリィは今度こそ足を止めると、恐る恐る、声の方を振り返る。
「・・・・・・コリオ?」
イリィが道を外れようとしなければ向かうはずだった村の方向から、息せき切って駆け上って来たのは。
そして、そのままドドドッとすぐ近くまで走り寄ると、コリオは思いつめたような顔で、両手に握りこぶしを作って、両足を踏ん張って、そしてイリィのことを真っ直ぐ見据えて。
「その、あー、えっとだな・・・・・・」
勢いに任せてやって来たまでは良かったのだが、いざ会ってどうするかまでは、あまり考えていなかったらしい。
何を言いたいのか、言いたくないのか。妙にもじもじと歯切れ悪い。
「・・・・・・あの、コリオ。今日はありがとう。お話できて嬉しかった。じゃあね」
イリィは精一杯の笑顔を作ってそれだけ言うと、さっさと踵を返そうとした。
(お前の能力なら、人を従わせることも簡単・・・・・・)
先刻のカリムの声が、脳裏に蘇る。
コリオが何を言いたいかはともかく、無理して何かを言ってほしいわけではないのだ。
特に、今は。
「ええっと、じゃ、なくてだな、聞いてくれイリィ!」
ぎゅっと目を閉じ思いっきり顔を上気させて、ありったけの声で、コリオは叫んだ。
遺跡のホールでイリィの歌を聞いている内、何故か急にクラクラして眠ってしまったコリオらが、むにゃむにゃ言いながら目覚めた時。
舞台の上ではあろうことか、他所者の少年が、ぐったりと眠っているイリィのことを、優しく抱きしめていたのだった。
『お、お前、何やってんだよっ!』
あまりのことに跳ね起きたコリオは、矢も盾もたまらず、舞台に駆け寄ろうとする。
ちなみにそれは、コリオらよりも一足先に起きたジーロが「砂地に寝かせたままでは可愛そうだ」と主張したことで、それならとカリムが、アシェルの隣に寝かせてやろうとイリィを抱えて運び上げた、ちょうどその瞬間だったのだが。
ついでに言い出しっぺのジーロも、しっかりカリムの横にいたのだが。
残念ながら、頭に血が上ったコリオの目には、そんな外野は一切入っていなかった。
だが、舞台まであと数歩というところで、コリオの足は急停止した。
イリィの身体を敷物の上にそっと横たえてコリオに向き直った少年の、胸の辺りが赤い色に染まっている。
『どうした?』
凍りつくように立ち止まったコリオの視線を辿った少年は、さも面倒臭そうな顔で、ああ、と一つ頷いた。
『・・・・・・そこの石で切っただけだ。見かけほどじゃない』
ジーロにしたのと同じ言い訳を、カリムはもう一度繰り返す。
だが、コリオはジーロのように「にーちゃんって意外とドジなんだなー」と笑って済ませはしなかった。
『・・・・・・やっぱり、それもアレのせい、なのか!?』
イリィに関わった者が被る災難。
しかも、認めるのは悔しいが、コリオらよりもよほど強くて身分もあって、村で神様扱いと決まったようなこの少年までもが、災難には勝てないのだとしたら・・・・・・。
『それは、やっぱり、妖精か魔物みたいなのが、イリィに憑いてるってことなのか? あの時代遅れで馬鹿馬鹿しい教訓話は、本当に本当のことなのか・・・・・・?』
”この世界には人間ならぬ存在がいて、ごく稀に、好ましい人間に所有の印を付けることがある。そして、不用意に印を入れられた者に近付けば、災難という制裁が降される。印を付けられた者に、手を触れてはならない。迫害してはならない。そうして大事に扱う限り、人間ならぬ存在の手によって、村は加護を受けられる”
それなのに、いつの間にかジーロはイリィと友達になっていた。
最近は災難の噂も聞かなくなっていたし、あれは何かの偶然だったのではないか。
大体、年寄りの語るもっともらしい話に振り回されるなどナンセンスだ・・・・・・。
だが、実際はそんな単純なものではなかったのかも知れない。
たとえばジーロは子供過ぎてお目こぼしにあっていただけで、昔語りは真実を伝えていたのかも知れない。
『だったら、どうだと言うんだ?』
『・・・・・・なん、だって?』
少年の声に、コリオは蒼白な顔を上げた。
『そんなもの、ちょっと力のあるガキ大将が、相手の気持ちなどまるで無視して好き勝手に主張してるようなもんだろ。これくらいでビビって女と話も出来ないとはな』
『そんなものって、相手は人外なんだぞ!? 人外相手に、俺なんかがどうやったら敵うってんだよ!』
『そのくらい自分で考えろ。だが、たかが人間に姿も見せられない、ちょっと怪我させて悦に入るのが精々の小物相手にそのザマでは、とっとと尻尾巻いて逃げ出すのが正解だな』
『なっ!? お前は余所者だから! そんな簡単に言えるんだ!』
『それなら、いくら生傷作ってもメゲないお前の弟には、永久に敵わないだろうな』
『・・・・・・!』
反論出来ないでいるコリオから、少年はふいと、いかにもどうでも良さそうに目を離した。
『この娘は、気が付くまで見ててやる。悔しかったら、自分がどうしたいか、よーく考えてみるんだな。もっとも、その調子で怖気たままでいるのなら、この娘はあっと言う間に手の届かない所に行ってしまうかも知れないが・・・・・・』
イリィに向けられる少年の目が、意味ありげに細められた。だが、その時のコリオは、何も言えずに遺跡を後にするしかなかった。そうするしかないと、思ってしまった。
だが。
「ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんっ!」
大声で連呼し続けるコリオに、イリィは驚いて、踏み出しかけていた足を止めた。
「ど、どうしちゃったの、コリオ?」
「今までごめん! ホントごめん! 俺、前にイリィの事を街の誰か偉いヤツに聞いてもらおうと思って、そんで崖から足滑らして落ちそうになって、死ぬかもしれないって思ったら、怖くなって・・・・・・。それからずっと、イリィのことを避けてた。遠くから見守るって言い訳しながら、肝心のこと、見て見ぬフリしてたんだ! ホントにごめん!」
「・・・・・・」
「だけど俺は、怪我しただけで、落っこちても死んでもねーし。村の奴らだって、怪我や病気は治ったし、火事の時だってみんな無事に助かってたし、実は何も大したことなんて無かったんだよな。もっともっと、根性入れれば、ちょっとした災難なんて、何でも無かったんだよな! だから、その、俺達の事、許せないのは仕方ないけどさ、俺、もっとがんばるから! 相手が人外だろーが魔物だろーが、ちゃんとイリィのこと守るから、だから、俺と! つきあってくれませんかっ!」
「・・・・・・・・・・・・え?」
そこでカーッと真っ赤になったコリオは、極度の緊張に耐え切れず、今度は自分が背中を向ける。
「あ、その! 返事は今度聞くからっ! だからそのっ、あんな余所者ヤローになんか、ついてくんじゃねーぞ! 絶対!」
言うが早いか脱兎の如く、コリオはあさっての方向へ駆け出した。
直後にどどっと派手に転ぶ音が聞こえたが。
「・・・・・・今のは違うからっ! 何でもないからっ!」
恐らくは、怪我などしてないと言いたいのだろう。
すぐにまた地響きを立てんばかりに駆け出す足音が響いたから、実際無事なのには違いないだろうが。
「・・・・・・・・・・・・はい?」
コリオが消えた方向を眺めながら、イリィはしばし、ポカンと立ち尽くした。
「・・・・・・そーやってあのコ達けしかけたワケ?」
自分が気を失っていた間の事を一通り聞き終えたアシェルは、その様子を想像して目を丸くする。
「大体、キミの怪我はイリィのせいってワケじゃないでしょ?」
キッカケになったと言えなくはないが、少なくとも例の”災難”とは関係ない。
「まあ、恋する男にはそのくらいで丁度いいかと」
もちろん、誤解していると知っていてわざと否定しなかったカリムは、しれっとしてそう応える。
「だけどジーロには面白くなかったんじゃないの? お兄ちゃんは恋敵なワケでしょ?」
「同じリングで戦ってこそ男だって言ったら、負けるはずないって息巻いてたぞ」
「うっわ策士だなーっ! てか、よくそんな事ヌケヌケと言えるよねー。人事だと思ってさー」
面白半分、呆れた半分で見上げるアシェルに。
「人事だからに決まってるだろ」
杯をゆっくりと傾けながら、至って素っ気なく、カリムは応じる。
「まあ、それはそーだろーけど・・・・・・その洞察力の何十分の一かでも、どうして自分の方に向けられないかなー」
後半は完全に口の中で。
なみなみとぶどう酒が満たされた杯を両手で抱え込みながら、アシェルはやれやれとひとりごちる。
「それで、イリィは今どうしてるワケ?」
「そいつと別れてから、まだ同じ場所でヘタり込んでる」
「えー? 何言われたんだろ。ねーねー、ひょっとして、コクハクとか?」
「そこまで判るか。ストーカーの趣味は無い」
アシェルがイリィに付けた髪留めが目印になって、カリムにはイリィの状態がおおよそ把握出来る。
と言ってもせいぜい、イリィがどこにいるかとか、周りで羽根や魔的な力などの力が働いていれば判るという程度だが。
「何その微妙な便利さは。てか、何でそんなアイテム持ち歩いてたのさ?」
「そこは使いよう、かな」
「ふーん? 具体的な使い道を聞いてみたいもんだねー」
などと、並んでノンキに杯を交わす二人である。
(不思議だな)
つい先刻までの重苦しさが嘘のようだ。
(これもイリィのおかげ、なのかな)
アシェルは傍らに置かれたバスケットに目を向けた。
悲鳴の如き大声を上げながらアシェルが飛び出した先には、イリィが持って来たあのバスケットが横倒しになって転がっていた。
自分のベッドになりそうなほどの大きさのバスケットに両手をかけて引き起こしたアシェルは、砂上に点々と転がっている焼き菓子を見て、がっくりと肩を落とす。
『あーあ。せっかく・・・・・・』
アシェルは唇を噛みながらナフキンを広げ直すと、落ちている菓子をひとつ残らず丁寧に拾い集めて、再び舞台に戻って来た。
『それ、どうしたんだ?』
ぶどう酒の瓶と酒器を見つけて戻ったカリムが、不思議そうに尋ねる。
『イリィが作って持ってきてくれたの。みんなで一緒に食べようと思ってたのにな・・・・・・』
沈んだ声のまま、アシェルは菓子を一つ取ると、手で払ったり息を吹きかけたりしながら砂を払ってみる。
が、キメの細かい砂は、完全には取れてくれない。
『いいや!』
思い切ってパクッとかじると、香ばしさや微かな甘さと同時に、じゃりっと砂の歯ざわりがした。
『うん! おいしい!』
構わず一つを食べ切ったアシェルは次の菓子に手を伸ばすと、同じように砂を払って、さあ食べてやるぞと決意も新たにじっと睨みつける。
『すごい気合だな』
ノンキな声に見返すと、図らずもカリムと目が合った。
『何だよ、バカにするんならすれば』
『してないしてない』
宥めるようにやんわりとした仕草で、カリムは両手を上げて見せた。
表情を悟らせない術を心得ているカリムだが、別に嘘ではなさそうだ。
『だってさ、折角イリィが焼いてくれたんだもん。ちゃんと美味しく食べなくちゃ』
『それで、美味いのか?』
『すっごく美味しいよ!』
一生懸命作ってくれたものが、美味しくないはずがないのだ。
力一杯断言してから、アシェルは手にした菓子に目を戻す。
『ふうん?』
と、横から手を伸ばしたカリムは、菓子の山から一つを摘み上げると、おざなりに砂を払って無造作に口の中に放り込んだ。
『・・・・・・どう?』
『・・・・・・美味い、と思う』
答えながらもカリムは、神妙な顔で眉根を寄せている。
『あははっ!』
こらえきれずに笑い出したアシェルに、何がそんなに可笑しいのかと言いたげな困惑顔のカリム。その顔がまた可笑しくてたまらない。
ひとしきり笑ってから、アシェルは手にしていた菓子をほおばった。
じゃりじゃりするのは同じなのに、さっきよりもずっと美味しく感じるのが、何だか不思議だ。
(そっか。カリムと一緒にお菓子食べるのって、初めてだったんだ)
それだけのことで、菓子職人の作った甘くて綺麗なお菓子を前にするより、ずっとふんわりした気分になる。
イリィやジーロと賑やかに食べられなかったのは残念だけど、これはこれで悪くない。
『砂、か・・・・・・』
呟いて視線をさ迷わせたカリムは、首を傾げているアシェルに気付いて、いつもの悪戯っぽい笑顔を向けた。
『・・・・・・なあ、外に行かないか?』
『え? 何、突然?』
『お前、ここに来てからまだ外行ってなかったろ? 景色が綺麗だし、海も見えるぞ』
『え、海!?』
『そう。この辺りの海は深いから、くっきりと青い色をしているんだ』
『・・・・・・』
『それともイヤか?』
『・・・・・・イヤ、じゃないケド』
『なら決まりだ!』
カリムは焼き菓子を乗せたナフキンを手早く包み直すと、傍らに置きっ放しにしていた酒器と一緒にバスケットに放り込み、空いている方の腕でヒョイとアシェルを抱き上げた。
『ちょっと、カリムってば!』
『天気もいいし、ピクニック日和ってヤツだ。実は外行った時、いいとこ見つけといたんだ』
そうしてアシェルは今、遺跡の屋根の上に、カリムと並んで座っている。
ぶどう酒の杯を手に、焼き菓子を食べながら。
目の前には、放牧に良さそうな新緑に萌える草原。眼下には赤茶の屋根が連なるのどかな村。
そして、明るい青空を映したような、どこまでも続く蒼い海。
白い部屋しか知らなかったアシェルが、初めて目にする外の風景。
そして、アシェルになるずっと以前に諦めた、自由な景色。
「すごくキレイ・・・・・・」
アシェルが滅ぼしてもいいと思った、この世界は。
「ところでさ」
「ん?」
「先刻、何かに気付いてたよね? そろそろ教えてくれないかな?」
カリムというヤツは、何の理由も無くロマンチックなシチュエーションを思いつくほど器用な性格では、決してないのである。
第14話 仮初の夢
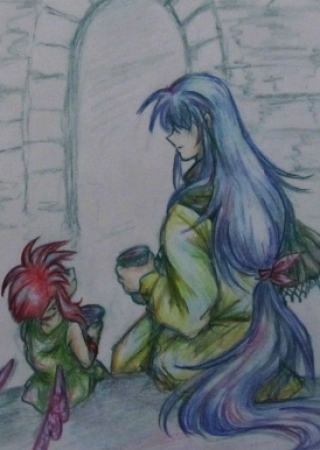
「気付いたこと・・・?」
アシェルに問われて、カリムは少し思案顔をする。
「美味くもないモンを酒って名で呼んじゃいけない」
「マジメなカオして、いの一番に言うコトがソレ!?」
呆れたように腰に手を当てて、アシェルはカリムの周りを一周する。
遺跡の回廊部分の屋根の上。壁柱が近接している分、他よりいくらか頑丈なはずだが、それでも所々屋根が抜け落ちたりガタガタになっていたりするから油断は出来ない。
もっとも、飛べるアシェルに足場の心配はあまり要らない。
「真理だと思うがな」
のんびりとくつろいだ様子のカリムが手にした杯の中で、赤い酒が揺れている。
「はいはい、キミの薬酒嫌いはよーくわかりました!」
やれやれと芝居がかった仕草で、アシェルは緩く首を振る。
「まったく、そんな調子だから、イリィの羽根に気が付かなかったりするんだよ」
「・・・・・・それって、俺だけのせいなのか?」
「ふふん! 言った者勝ちだよ。ま、確かにボクもアレにはビックリだったけどねっ」
「そもそも本人が自覚してなかったくらいだしな」
先刻のイリィとのやりとりを思い出しつつ、カリムは応じる。
「それはそうと、今、あの娘の羽根の気配を感じるか?」
「ううん、全然!」
あっけらかんと即答するアシェルに、「だよな」とカリムは頷いた。
イリィが子守唄を歌い始めた瞬間、羽根の気配は唐突に出現し、旋律が止むと同時に再び綺麗さっぱはり掻き消えた。
それを目撃した後でさえ、どんなに眼を凝らして視ても、イリィの内には羽根の気配の片鱗さえ感じられなかった。その消え去り方は、羽根使いが自分の羽根を秘匿するというレベルを軽く超えている。
「思えば、最初にここに投げ出された時に感じた気配、アレは気のせいじゃなかったんだな」
「天使かって開口一番に聞いてたっけね。でもさ、イリィが羽根を持ってるワケじゃなくって、どっか他にあるのと偶然共鳴してるだけだったら、わからなくはない、カモ?」
「新人指導ならまだしも、俺は新人発掘の方は専門外なんだが・・・・・・そういう事ってあるものなのか?」
「それは、ボクにも何とも・・・・・・てか、新人指導? キミが?」
ツッコミを受けたカリムが、しまったという顔でそっぽを向く。
「なんてお気の毒な・・・・・・」
スパルタ指導される新人の様子を想像してだろう、伏目になったアシェルは、口の中で何やらゴニョゴニョ唱えながら胸の前で両手を組む。
「それとも意外に向いてたりして?」
アシェルの頭の中では、どんなシミュレートがなされているのか。
「あーそれはさて置きだな、」
こほん、と一つ咳払いして、カリムは話を元に戻す。
「羽根がどこにあるかは置くとしても、あの娘の生命の力を吸い上げて発現していることに変わりないんだよな」
「やっぱ本人に自覚ナシってのが一番の問題だよね。てか、イリィにはそのこと、ちゃんと言った?」
「一応、歌に注意するようには。羽根の話はまだ全然」
「ええ? 何で?」
「そりゃあ、天使云々の話を、天使を放棄した者の口から聞けば、どうしたってマイナスイメージにしかならないだろ」
それを聞いた途端、アシェルの顔に陰が差す。
「それはそーかも知れないケドさ。塔出てせいせいしたって言うヒトが、そんなコト考えるんだ・・・・・・」
アシェルにしてみれば、塔の連中をどれほどボロクソに貶したところで、貶し過ぎるという事はない。
それだけの仕打ちを、彼らはしたのだ。
「確かに俺達にはいい所じゃなかったがな。それでも羽根使いにとって、塔に全く価値が無いとまでは言えないと思う」
不完全な羽根使いほど危なっかしいものはない。本人にとっても、周りにとっても。
羽根が羽根使いの生命力を必要とする以上、そして暴走の危険が常に付きまとう以上、羽根使い同士が集い助け合える場所はどうしたって必要だ。
それに、魔物は天敵である羽根使いに容赦しない。イリィのように無自覚な者が襲われでもしたらひとたまりもないだろうし、その災禍はイリィの大切なもの全てに及ぶ。
イリィが何らかの形で羽根と関わっている限り、このまま村で平和に暮らすという選択肢は有り得ない。
何よりも、いくらカリムやアシェルが望んだところで、ずっとイリィの傍に居て見守り続けるなど不可能だ。
「・・・・・・」
「同意しろとは言わない。俺みたいに割り切る方がおかしいんだ」
何でもないことのように、さばけた口調でカリムは言う。
「・・・・・・あーあ、羽根の発現を阻止するとか封じるとか捨てちゃうとか、出来たらなぁー」
「それが出来れば苦労しないよな」
カリムが羽根を手放せたのは、特殊事情による例外中の例外で、普通はどんなにがんばったところで、羽根を拒否することなど出来はしない。
「そーだよねえ。村にいたいなら歌っちゃいけないって、クギ刺すのがせいぜいかぁ」
「心から望むことを抑えられるものならな」
「歌うことが? みんなと仲良く暮らすよりも?」
「本人は違うと言うかも知れんが、俺にはそう見える。たとえあの娘がこの先村人らと幸せに暮らせるようになったとしても・・・・・・やりたいと望むことを我慢して圧し込め続けていれば、いずれ、何かが壊れる。今度こそ、最も不幸な形で」
「・・・・・・」
「いっそのこと、無理してトラブルを解決するよりも、とっととここから連れ出してやる方が、よほどあの娘の為なのかも知れない」
それはカリムの、偽らざる本音だったのだが。
「それはダメ」
アシェルは笑顔で、キッパリと断言した。
「今のままじゃあ、イリィは永遠に故郷を失ってしまうでしょ。だから、それはダメ」
「だが・・・・・・」
どちらが幸せなのだろうか。帰りたい故郷があるのと、無いのとでは。
「何?」
「いや・・・・・・」
(それを決めるのは俺じゃない)
結局カリムは、酒と一緒に、続く言葉を飲み込んだ。
カリムの記憶は、白亜の塔が所有する離宮の、眩しいほど白い部屋で目覚めたところから始まる。
だからカリムが故郷と呼べる場所は、白亜の塔をおいて他には無い。
だが。
白い光の中に消える無数の影と、それに向けて伸ばした、大きな古傷を刻む腕。
そして、夕日のように暖かい光を背にして微笑む人・・・・・・。
時折浮かぶ僅かな夢の断片が、ただの幻でないのだとすれば、それはきっと、自分が永遠に失くしてしまったもの。帰ることの叶わなかったところ。
それだけが、自分であったものの全て。
上級天使の第一条件は、”炎の結晶”と同化した命を持つことだ。
羽根使いとなって塔に招聘された者は、最初に必ず審査を受ける。この審査で選別され、専門の教育と訓練を施された者だけが、”炎の洗礼”へと臨み、”炎の結晶”と同化し得てはじめて、上級天使を名乗ることを許される。
上級天使となる者は、スタートの時点から、一般の天使とは全く異なる道を歩むのだ。
だが、あの幻が見せる光景は、その知識とは矛盾する。
あの幻を信じるなら、自分は結晶を得る前にも天使をしていた。そこにはきっと、大切な人がいた。その頃の自分は、今とは全く違った外見をしていた・・・・・・。
最初は、そんなことがあるはずないと自分に言い聞かせていた。
もちろん、合理的な説明だって可能だ。
炎の洗礼は過酷なものだという。選び抜かれた羽根使いにとってさえ、全てが洗礼に耐え切れるわけではないのだと。
自分もまた、そんな適応し切れなかった者の一人だったのだ、と。
新たな羽根使いの数が年を追う毎に減少して行き、必然的に上級天使候補となれる者が数年に一人現れるかどうかという現状を考慮すれば、ほんの少しでも可能性のある者に対し、最大限の技術を投じて望みを繋ごうとするのは必然の流れであっただろう。
どんな経緯があったにせよ、カリムは結晶を得て、離宮の深奥で目を覚ました。
目を覚ましこそしたものの、無理を重ねて生まれただろうカリムは、様々な面で常に不安定だった。
番人どもは結晶の万能性を説くが、カリムの実感としては、結晶の本質は調和の力だ。強大な力の源である羽根と、莫大なるエネルギーの源である炎の雫、それを扱う人間の意志。時に相乗し、時に相反する、それぞれの力を調和させることこそが炎の結晶の本質であり、表面に現れる様々な”恩恵”とやらは副次的なものにすぎない。
その根幹を成す結晶の力が不安定であれば、その影響は随所に及ぶ。
度を越して高過ぎる感応能力も、裏を返せば魔道の術から受ける干渉を上手く受け流すことが出来ないからだし、薬酒の不安や恐怖といったマイナスの感情を取り除いて精神の安定をさせるはずの作用は、逆に混乱を助長する一因となった。
忘れるということは、それは無かったことと同じだ。ならば普通は、”忘れた”ことを”忘れた”と認識することは無い。
だが、何かがおかしいと認識してしまえる程の不自然な記憶の歪みが、逆にカリムに疑念を抱かせ、ついには辿り着いてしまうことになる。
塔の連中がこれまで積み重ねてきた所業や、塔の本質がどんなものであるかという事に。
それでも。
遠いあの日。離宮が燃え落ちたあの夜。
アシェルを手にかける判断を下したのは、誰でもない、自分自身。
時を同じくして、別の手段で”真実”に辿り着き、それ故に全てを憎み、破壊し、そして”カリム”から解放してくれようとした、たった一人の友達を。
”カリム”にとって、一番大切だった者を。
最後の最後で、自分は捨てることが出来なかったから。
幻の中の彼女が、この世界のどこかに存在するかもしれないという、万に一つも無い可能性に縋りついてしまったから。
アシェルと共に死の世界に行くことを選べなかった時、自分に残された道はたった一つ。この手で楽にしてあげること、それだけがアシェルの心を救う唯一の方法なのだと・・・・・・。
だが、いくら言い訳を重ねたところで、本音のところはどうだったのか?
その後自分はどうしたか?
彼女を探すために塔を離れることもなく、黒い炎を受け入れて記憶を取り戻す可能性に賭けもせずに。
自分は塔の側と契約を交わした。
与えられた力も、容姿も、上級天使という地位も、望んだはずのないものだったが。自分の望みの為に、”カリム”の力を利用した。
自分の望み以外はどうでもよかったから、塔も薬酒も羽根も任務も、課された全てを受け入れた。
そうやって、命じられるままに、何も考えることなく。
カリムが上級天使となったことに、大儀などありはしない。
魔物を憎んだことすら、あったのかどうか。
魔物は天使の敵であり、天使とは魔物を討滅するものである。ただ、それだけのこと。
(全く、番人どもも大したことはない。あんなに偉そうに威張っていながら、やることが中途半端すぎだ)
どうせなら最初から、彼らにとって必要な能力以外のもの全て取り上げておけば良かったのだ。それこそ、何も思わず考えない土人形と同じように。
そうすれば、余計なことを思い患う事もなかった。不完全な想いに囚われてアシェルを傷つけることもなかった。
だが、そんな考えが単なる八つ当たりだとも解っている。
(何故、判らなかったのだろう。アシェルは、俺に一番近い存在だったはずなのに。俺のことを命がけで気にかけてくれるような者など、他に居るはずがなかったのに。何を奪われ損ねられたとしても、それだけは間違えてはいけなかったのに)
そう。どんな理由があろうとも、間違えてはいけないことはある。
(知っている。自分がどんな者であるのかは)
黒い炎を受け入れるまでもなく、一番大切だと思う者より自分の望みを優先させ、手を下すことの出来る者なのだと。
それを肯定して、今まで生きて来たということを。
だからこそ。
薬酒を飲めば、僅かなりとも時間稼ぎは出来るだろう。
黒い炎を受け入れるなら、それこそ塔に戦いを挑むことすら出来るだろう。
ただし、それを自分の為に行うことは断じて出来ないし、してはならない。
それは大切な人に対してだけでなく、カリムが天使として刃を振るった者たちへの、それでいながら記憶にも留めておけなかった者たちへの、この上ない裏切りだから。
『やはり君だったな・・・・・・』
全てを悟った瞳で、そいつは静かにカリムを見た。
『命じられて来たんだろう? 何を置いても、この結晶だけは持ち帰れと』
そいつが自らの胸に当てた指の間に視えるのは、心臓と同化して揺らめく炎の結晶の静かな光。そいつが上級天使である、確かな証。
その輝きの中にほんの僅かに陰りが視えた。たった一筋であっても、決して元に戻す事の出来ない、黒い炎の片鱗が。
『だが、壊してほしい・・・・・・』
そいつのことは、大して知らなかった。興味も無かった。
だからその時、そいつが何を想って行動していたのか皆目解らなかったし、解る必要など無かった。
命令に逆らってまで、願いを聞いてやる義理も無かった。
『いつか、君にも解る時が来るかもしれないな・・・・・・。だが、願っているよ。そんな日が永劫に来なければ良いとね・・・・・・』
何を気にすることがある。一瞬にして傍らを通り過ぎて行った者のことなどを。
上級天使が塔を離れ、薬酒を断たれれば、いずれ肉体は限界を迎え、朽ちてゆく。
だが、炎の結晶は。
魂を封じ込めた、”力の源”は・・・・・・。
「どうしたのさ? ボーッとしちゃって?」
不意に後ろから首筋に抱きつかれて、とっさに握り締めた杯の中で、半分ほど残った酒が大きく波打つ。
「アシェル・・・・・・」
背中に感じる、小さな温もり。
俺は今、幸せだ。
とうに失ったはずの者が、こうして傍に居てくれる。
それ以上の幸せが、この世界にあるはずがない。
だから、忘れてしまうのは怖い。
俺が、幸せに値しない存在だということを。
「何でもない。で、お前はどうするのがいいと思うんだ?」
カリムの背中に張り付いたまま、アシェルはぴょこんと肩口から顔を覗かせる。
「そりゃあ、まず何がどうなってるのか確かめないとね。やっぱさ、これって魔物絡みだったりすると思う?」
「羽根と来れば、魔物ってか?」
「そう考えるのがセオリーってもんじゃない?」
「いくら魔物でも、あんなに気配が無い羽根使いを発見出来るものなのか?」
「やっぱそこだよねー。・・・・・・けど、魔物には眷属が多いから、今までにも気配を発したことがあるんなら、絶対無いとは言い切れないよ?」
「俺が魔物なら、見つけてすぐにさっさと襲撃するけどな。その方がよほど手っ取り早いし、村の一つ潰すのに躊躇いはしないだろ?」
魔物にとって、羽根使いは憎悪の対象だ。羽根使いらしき者がいたならば、本物だろうと単なる勘違いだろうと確認する必要もない。可能性は、潰せばいい。
「うん、それは同感」
なるほど、とアシェルは難しい顔で深く頷く。
「だとしたら何だろう? ただの誤解ってだけじゃないっぽいんだけどなー」
「チビの守護印のこともあるしな・・・・・・」
「・・・・・・ジーロに? 何それ?」
アシェルはキョトンと目を瞬かせて、カリムを見返す。
「だから、胸のあたりにチカチカしたのが。それに、羽根騒ぎの後は、あの三人組にも・・・・・・」
「そんなのあったの!?」
「・・・・・・」
「・・・・・・」
しばしの沈黙の後、カリムはがっくりとうなだれる。
「フンだ! どーせボクには判りませんでしたよ!」
拗ねた声で、アシェルはすとんと、カリムの背中から滑り降りる。
「いや、そういう意味でなく・・・・・・」
当然のことだが、罠のような高度なものでない限り、術の存在に気付き易いのはより強く影響を受ける者の方である。
集中しなければ判らない程度のそれを、カリムは自分には影響が無い故に魔物に対する護符の類と推測したのだが、アシェルが全く気が付かなかったということは、それはアシェルにとって何ら意味を持たないものだということだ。
「ってことは、目印だったのか」
一口に目印と言っても、相手に存在や所有権を誇示するような目立つものもあれば、特定の者に対してのみ意味を持つものも、印を付けた者にのみ判ればいいものもある。
ジーロらに付けられた印は、おそらくは後者だ。
「それ、イリィの羽根で付いたのかな?」
カリムの背中にもたれたまま、アシェルは腕組して首を傾げる。
「いや。あの発現の仕方では、それは無理だ」
「断言するね」
「いくら何でも、そこまで間違えやしないさ」
至近距離であれだけ無遠慮に力を見せ付けられれば、嫌でも解る。あれは単なる暴走、でなければ羽根の自己主張だ。
たとえ羽根に術を成す能力があったとしても、相応の動機が無ければ術は形にならないものだ。
「じゃあ、遺跡に入ったから? 昨日の村長さんたちにもキラキラって見えた?」
「その時は、気にしてなかった」
「あ、そ。じゃあ、カリムが気にするまでも無いレベルだったわけか・・・・・・」
「あまり買い被り過ぎるな」
ここにきて感応能力の低下を痛切に実感しているカリムである。視えていた時は煩わしいだけだった能力も、いざ精度が出せないとなると、不便なこと甚だしい。勝手な話だが。
「不完全な羽根使いに、何か悪い力に、何だかわかんない力かぁ・・・・・・こんがらがりそー」
アシェルは一度肩を竦めてから、ひょいとバスケットの中の砂付き焼き菓子に手を伸ばし、つまみ上げたそれをじっと見つめる。
「ねえ、こういうのはどうかな? あの子達が倒れた拍子に、ここの砂をウッカリ吸い込んじゃった、とか?」
目の前に広がる緑や青の風景の中に、これほどさらさらした白い砂は存在しない。遺跡だけが、切り離されたように、白い砂の中に埋もれている。
「ものは試しって言うじゃない? 村の人達にコレ食べさせてみてさ、カリムにチカチカが見えれば・・・・・・」
勇んで自説を披露していたアシェルは、そこで急に視線を落とした。
「だからどうだって話だよね。キミにも視えるかどうかってくらいささやかな力、証明出来たところで意味無いかも・・・・・・」
「それは印を付けたものの力の程度によるだろうが・・・・・・遺跡に在る何かは、お前にも視えないんだよな?」
「キミに視えないんじゃ、ボクに視えなくて当然でしょ」
「いや、俺だって何でもかんでも視えるわけじゃ・・・・・・」
言いかけて、カリムははっと瞠目する。
「当然のこと。視えて当然。視えなくて、当然・・・・・・視えなくて当然の力・・・・・・」
そしてカリムは、一度瞳を閉じてから、アシェルの顔を見直した。
「もしかしたら、間違っていたのかも知れない。いや、正しかったと言うべきか・・・・・・?」
「はい?」
「なあ。もしも、お前と俺とに視えなくても不思議じゃない力が存在するとしたら?」
「何それ、冗談!?」
ここは笑うところだろうかと一瞬悩んだアシェルは、自分を見ている真剣そのものな蒼い瞳に行き当たった。
「・・・・・・じゃ、ないんだ。偶然じゃなく必然でってこと?」
「たとえば、俺と似た性質の力があったとしたら、それは区別出来ると思うか?」
言われてアシェルは、大きな緑の瞳を、さらに大きく見開いた。
「じゃあ、何? わかんない力の正体は、カリムと同質のものだって言いたいワケ? でもそれってズバリ、炎の結晶の力ってことでしょ?」
「そうなるか?」
「なるよ! てか、言ってるイミ解ってる? 結晶は塔の専売特許なんだよ! だったらボクたちは、今でも塔の手の内ってことじゃない!」
「いっそその方が、話が簡単だったかもな」
「・・・・・・違うの?」
「炎の結晶と一口に言っても、誰かの命と同化した時点で個性が出てくる。他の上級天使のものなら、区別出来ないってことはない」
「でも、気のせいだとは思わないんだね?」
「ああ。それがずっと引っかかってた。俺の感覚が鈍っていると考える方が、可能性としちゃ高いわけだし。だが、結晶かどうかはともかく同質の力が存在すると考えた場合、いいことが二つ、悪いことが一つある」
「それは?」
「感覚の精度を確認も修正も出来ないなら、考えても無駄だろ。それならいっそ、自分の感覚が正しい方に賭ける方が建設的だ。ついでに疑問のいくつかにも間単に説明がつく」
「ええ、そーなのかな? ・・・・・・いーのかなそれで?」
真顔で断言されればつい頷いてしまいそうになるが、よく考えればそれはあまりにも都合の良すぎる論理展開というものだ。
「まあ、そこは後で突っ込むとして、悪いことの方は?」
「その仮定が正しかった場合、ここの平穏な状態は、崩壊する寸前かも知れない」
「何それっ!」
思わず立ち上がったアシェルが、カリムの瞳を正面から見据える。
「だから、そのままの意味だよ」
どこまでも落ち着き払ったまま、カリムはアシェルの視線を真っ向から受け止める。
「だったらイリィはどうなるの!?」
「それはあの娘次第だろ。俺たちが出来ることなんてたかが知れている」
「そんな・・・・・・」
「だが、まあ、意外と大丈夫なんじゃないか。ああ見えて、あの娘、か弱いだけじゃなさそうだ」
「ええ? それって根拠があって言ってる? 適当に誤魔化すのナシだからね!」
「そうだな・・・・・・あの娘は、人の名を呼ぶことに全く躊躇いがないから。なんてのは理由ならないか?」
第15話 もう一つの出会い
(何だったんだろう、さっきの、コリオは・・・・・・)
村に続く坂道にへたり込んだまま、イリィはぼうっと空を見上げていた。
頭の中がぐるぐるして、のどかな青空までぐるぐるしている気分。
いつからか一人、また一人と、イリィを無視して遠ざけるようになった村人達。
その中でもコリオは、大分後の方まで、一緒に居てくれた、ような気がする。
けれどある日足に大怪我をして、家までお見舞いに行ったけれど会わせてはもらえなくて・・・・・・それ以来、コリオとは話をしなくなってしまった。
ただ時折、コリオの視線を感じることはあった。偶然出くわした時などに、何か言いたそうな目でイリィを見ては、結局視線を落として行ってしまう、みたいなことが。
でも、それだけ。
それだけでは、何も解らない。コリオが、どんな気持ちだったかなんて。
なのにどうして突然、神殿にまで歌を聞きに来たり、あんな風に謝ったり、しかも、あろうことか、あろうことか・・・・・・。
(あれって、まさか、もしかして、ひょっとして、ええと、その・・・・・・コクハク?)
思った途端、かああっと顔が熱く火照るのを感じて、イリィは両手で頬を押さえた。
一体、何がどうして、そんなことになったのか。
『お前は全然悪くない・・・・・・』
その時不意に、カリムの声が脳裏をよぎった。
あの後カリムは、何を言おうとしていたのだろう。
きついことを言われたとは思う。
けれどカリムは事情を知ってからもイリィのことを心配してくれたし、神殿までコリオ達を連れてきてくれたし、何よりイリィの為に行動しようとしてくれた。
コリオが話しかけてきたのは、きっと、カリムがきっかけになったのに違いない。
それなのにイリィは、言われたことに腹を立ててしまって、話しの途中で怒鳴って飛び出して来てしまった。
何を叫んだのか、良く覚えていないけれど、自分に対して一生懸命になってくれた人に、きっと酷いことを言ってしまった。
(戻らなくちゃ。戻って、謝らなくちゃ)
今更ノコノコ謝りに行くのはすごく気が引けることだけど、カリムとアシェルはいつまでここにいるか判らない。ぐずぐずしていたら、永遠にその機会を失ってしまうかも知れない。
(戻らなくちゃ、今すぐ!)
ギュっと拳を握って決意を固め、イリィはすっくと立ち上がる。
そして神殿に続く道を再び上ろうとした、まさにその時。
「やあ、こんにちは。可愛いお嬢さん!」
驚くほどすぐ近くで、全く聞き覚えの無い声がした。
それよりも少し前。
「そりゃまあ確かに”風光明媚な海沿いの一本道”には違いないけどな・・・・・・」
呟いてフェグダは、もう何度目かになるため息をついた。
街から街へと続く街道を逸れ、海沿いの村に向かう小道に入ったまでは良かったが、その小道はだんだん崖沿いへと追いやられ、ついには断崖絶壁を掘り広げたような代物へと変わっていった。
それでも一応、小さな荷馬車が通れる程度の道幅は確保されており、馬車同士がすれ違えるような待避所だって設けられてはいるのだが、少しでも天気が荒れれば簡単に通行困難になりそうだ。
だが、フェグダがこうして歩いていても、荷馬車どころか道行く人影すら全くお目にかかることがない。これは余程の用事でもない限り、街道を外れた村を訪れる者などいないということだろう。
「ところで、もうそろそろ着いても良さそうなものなんだがなぁ」
街で聞いた事前情報では、歩きでも昼頃までには村に着けるだろうとのことだったが、先の”風光明媚”情報の発信元と同一人物でもあるだけに、どこまで当てにしていいものか判断に迷うところである。
が、断崖絶壁は突然途切れ、ゆるやかな起伏の草地が目の前に広がった。
草地の先は、手入れされた畑地。そこから丘の上の方に向かっては、若葉色の牧草地。
そして畑地の間を道なりに上って行くと、ゆるい三角の屋根の連なりが見えてきた。
「おお! やったぜ!」
胸の前でぐっと拳を握ってから、フェグダは大きく深呼吸する。
同じ海風の香りでも、断崖絶壁を横目にしながら嗅ぐのと、開けた草地にいるのとでは大違いだ。
そうやって一息ついたところで。
「さーて、例の遺跡とやらはいずこ?」
村を見下ろす丘に建っているという情報を頼りに、額に手をかざしつつ目を凝らしてみると、なるほど、それらしい辺りにそれらしい白っぽい石造りが見つかった。
「・・・・・・アレ、だよな?」
歩を進めるにつれて徐々に形を現し始めたその建造物は、遺跡という名に恥じないくらい十分風雨に晒された佇まいだ。
しかも平和な風景に馴染みまくっている辺り、塔の転移門に影響を及ぼせるような雰囲気はおろか、秘法や秘術が隠されていることを期待させるような独特の迫力とは全く無縁な、至極あっけらかんとした印象だ。
いや、見だけで判断するのは早計だと判ってはいるが、それにしても、各地の遺跡巡りをしてきた経験から言わせて貰えば、今目にしているあれは、天気のいい日に彼女を誘ってピクニックデートとか、子供同士で秘密基地ごっことか、そんな用途にこそピッタリしっくり来るような気がする。
「・・・・・・そりゃ、そーだよなー。世の中そんなもんだよなー。一発目でビンゴなんて偶然、そーそーあるわけねーもんなー」
拍子抜けしたような、どこかホッとしたような・・・・・・。
妙にもやっとした感情を吹っ切るように、フェグダはもう一度大きく伸びをする。
「まあ、せっかくここまで来たんだから、後で見に行くくらいはするとして、」
太陽はまだ中天高い。
来た道を戻るにしろ、村を抜けて次の街に向かうにしろ、遺跡見物に少々時間を取ったところで十分余裕はありそうだ。
「けど、まずはやっぱりアレだよなー」
折しも丁度お昼時。
村の方からは祭り前の浮かれた雰囲気と、それより何より窯でパンやパイを焼くような香ばしい匂いが漂って来る。
「旅の醍醐味は美味いメシと甘ーい出会い! 回り道して苦労して、このまま素通りはないよなー」
ここはひとつ、滅多に訪れることがないだろう旅人が歓迎されることを期待しても、悪くないのではないだろうか。それとも。
「まさか目が合った途端、村人総出で追っ払われる、なんてこた、ねーだろーな?」
街ではそんな物騒な噂は聞かなかったし、雰囲気的にも悪くないとは思うのだが、村には村独特の共同体ルールが存在するもので、こればかりはいつも出たトコ勝負である。
「歓迎されるなら、明日の祭りは村にお世話になるのがお得、歓迎が期待出来ないならとっとと次の街に行って楽しむのがお得。この見極めが肝心だ」
フェグダは今までの経験則総動員で、真剣に思案を始める。
「そうだなー。村に入る前に誰かに会えれば、事情が判っていいんだがなー。出来ればカワイイお嬢さんとか、ナイスバディなお姉さんとか、清純可憐な美少女とか・・・・・・ん?」
そんな呆れた妄想を神様が聞き届けて下さったわけではないだろうが、フェグダが歩を進めるその先で、ほっそりとした人影がすっくと立ち上がった。
「おおお!?」
それは、こんな田舎どころか大きな街でだって早々お目にかかれないような、とびきりの美少女だった。
結い上げられた髪は、この地方では珍しくも美しい銀の絹糸。ドレープの効いたスカートをパタパタはたく仕草も愛らしい。
「やった、ラッキ!」
とは、フェグダでなくとも思うはずである。多分。
足早に歩み寄ってから、出来るだけ脅かさないよう、なおかつ馴れ馴れしくない程度に愛想良く、最上級の紳士笑顔でもって、フェグダは少女に呼びかけた。
「やあ、こんにちは。可愛いお嬢さん!」
歩いて四、五歩という至近距離から不意に聞こえたその声に、イリィの心臓は口から飛び出しそうなほど大きく跳ね上がった。
(だ、誰!?)
動揺しまくって、振り向くことすらままならないイリィは、頭の中でその声を繰り返す。
とりあえず、無邪気で、ノンキで、楽しいことばかりを考えているような、悪意のカケラも混じらない声だ。
感じからして、年齢は二十歳前後くらいの青年なのだろうか。
そして、かなり注意しなければ判らない程度ではあるが、少し変わったイントネーションがある。
街まで行けば、地方なまりや外国なまりで喋る声を耳にすることもあるのだが、それとも少し違う気がする。
もしかすると、イリィの想像もつかないような遠いところから来た人、ということだろうか?
好奇心を覚えたことで硬直から立ち直ったイリィは、恐る恐る振り返る。
そうして目に入った人物は、思った通り、いかにも異国の旅人然とした格好の青年だった。
日焼けした肌に、明るいはしばみ色の髪。前髪に隠れ気味の大きな瞳は、若い木の実のような茶緑色。顔立ちだけならカリムやコリオと同年代くらいに見えないこともないが、声の印象が間違っていなければ、単に童顔なだけかも知れない。
髪の間に見え隠れする三角形の耳飾りが、何かの護符のようで印象的だ。そして何より決定的なのが、見慣れない綺麗な幾何学模様が刺繍された膝丈の旅用マント。
彼の印象を一言で表すなら、見渡す限りの広い草原、ではないだろうか。
「ゴメンゴメン。脅かすつもりはなかったんだけどね」
振り返ったまま黙っているイリィに申し訳なさそうな目を向けて、青年はそう口にする。
「い、いえ、私こそ、ごめんなさい」
無遠慮に観察してしまったことに頭を下げてから、イリィは恐る恐る口を開く。
「あの、旅人さんですよね。この村に御用がおありなんですか?」
「あ、そんなかしこまらなくていいからさ。俺、フェグダっての。君は?」
やはり変わった響きの名前だなと、イリィは思う。
「あ、あの、イリィです、けど・・・・・・」
「イリィちゃんかー。いい名前だねー。それにとっても美人だしー」
「え、あ、え・・・?」
面と向かって美人だとか言われてしまったイリィは、何と応じていいのかわからずに上ずった声を上げる。
「ねえ、俺さー、見ての通りの全然怪しくない旅人なんだけど、良かったら村を案内してくれないかなー?」
彼は気軽に言ったのだろうが、その一言はイリィの高揚しはじめた気分を冷ますのに十分だった。
「・・・・・・それは、やめた方がいいと思います」
「うわあーっ! 俺のどこが不審人物っ!? こー見えても俺、結構イイ奴だし、色々役に立つ特技とかもあるんだけど」
陽気な調子で重ねて売り込みをかけてくるあたり、すんなりとは諦めてくれなさそうだ。
「いえ、そうじゃなくて。気を悪くされたなら謝ります。ただ、私が案内しない方が・・・・・・あなたのためなんです」
「ええと? どういうことかな?」
それは聞かれて当然だろう。が、いくら悪い人ではなさそうでも、初対面でほいほい話せることでもない。
「・・・・・・村に入って真っ直ぐ行けば広場に出ます。そこに村長か誰かがいるはずですから、そちらで聞いていただいた方がいいと思います。では、私は用がありますので、これで」
早口で説明してから出来るだけ丁寧に一礼して、イリィは素早く身を翻した。
「ちょ、ちょっと待ってよ、ねえ?」
カワイイ女の子と仲良くなろう計画が初っ端から挫折しかけて慌てたフェグダは、歩き出そうとするイリィに向かって、とっさに大きく腕を伸ばす。
その時、フェグダのマントの間から何かが滑り落ちた。
チャリーン!
不意に上がったカン高い音に、イリィとフェグダの目が集中する。
岩に当たって大きく跳ね上がった銀色の丸い物体は、そのままイリィの足元まで転がって来て、クルクル回ってから草の中で止まった。
フェグダが追いかけて手を伸ばすよりも、イリィが拾い上げる方が早い。それは親指と人差し指で丸を作ったくらいの大きさの、銀色のメダルだった。
刻まれた飾り文字は、どうやらフェグダと書いてあるようだ。
何気なく裏返したイリィは、思わず目を見開いた。
そこに現れたのは三叉の矛に二対の翼の紋章。
「あの、これ・・・・・・?」
綺麗な細工だ、というだけではない。これと似たものを、イリィはつい今しがた目にしたばかりだ。
「拾ってくれてありがとう! 大事なお守りなんだよコレ。ったくこんなとこで鎖が切れるなんて、どーしたんだろーなホント」
フェグダは乱暴にならない程度に素早くイリィの手からメダルを掴み上げると、ササッと服の隠しにしまい込み、あははと笑いながら頭を掻く。
「・・・・・・?」
なおも不思議そうに見ているイリィに、フェグダの笑顔が少し引きつる。
「や、全然大したもんじゃないんだって。ええと、ちょっと待ってね!」
気まずい雰囲気を払拭すべく、フェグダは素早く荷物を下ろすと、じゃらじゃらと音の鳴る皮袋を取り出した。
貨幣が入った財布にしては、やけに大きい。
と、中から出て来たのは、ピカピカ光るコイン大のペンダントだった。
フェグダのメダルを見てしまった後では、シンプルを通り越して素朴過ぎる矛と翼のデザインが施されている。
「あ、それ知ってます! 天使様のお守りですね」
露店などで気軽に買える天使の守護印入りのアクセサリーは、家族や友達や恋人へのプレゼントとしてはポピュラーな物だ。
「でも、どうしてこんなにたくさん?」
「これはさ、路銀稼ぎ用なんだよね」
護符ペンダント売りはフェグダの数ある副業の内の一つだ。
「ほら、中央に太陽のが”日輪の天使”で、武運長久無病息災にご利益があるんだ。虹が幸運全般の”暁虹の天使”。美人になれますようにっていう”雪華の天使”も人気だけど、もう十分美人なイリィちゃんには必要ないかな」
「・・・・・・」
フェグダは手の上にペンダントを並べながら、商売用の抑揚をつけた節回しで印の意味を説明していく。
「イリィちゃんに似合うのは・・・・・・」
「いえ、私、お金なんてありませんから」
「もちろんプレゼントだって! お近づきにってことでさ!」
「いえ、それこそ悪いです!」
下心が皆無とは言えないフェグダの提案は、即座に辞退されてしまう。
「遠慮しなくてもいいって! ・・・・・・あ、でも、そんな上等な髪飾りをプレゼントしてくれる彼氏がいるんじゃ、こんな安物はお呼びじゃないっか」
自分で言ってから、フェグダは内心舌打ちして肩を落とす。気付かなければ良かった。
「あ!」
言われたイリィもまた、慌てて自分の頭に手を伸ばす。そこには赤い石の髪留め。アシェルに結ってもらって、そのまま借りっ放しだったことを、今の今まですっかり忘れ去っていた。
「これは、借り物だから、返さないといけないものだから・・・・・・」
「ああ、明日はお祭りだからね」
その意味を勝手に解釈したフェグダは、嬉しそうにニッコリ笑う。
「だったら、俺がプレゼントしても問題ないよね」
「え、だって、そんなわけには・・・・・・!」
慌てて身を引こうとしたイリィだったが、その目が吸い寄せられるように、ペンダントの一つに釘付けになった。
向かい合う三日月の印。
不意に、イリィの胸がドキリとする。
ペンダントのデフォルメされまくったデザインとはギャップがありすぎて、すぐにはピンと来なかったのだが、これをもっともっと、フェグダのメダルのものよりもさらに精緻で優美な紋章にすれば・・・・・・。
「あの、これ・・・・・・!」
「ああ、”災厄の天使”の印な」
応じるフェグダの声は、先刻の営業トークとは打って変わって素っ気無い。だが、イリィは気にしてはいなかった。
「災厄の、天使様・・・・・・?」
それは、イリィが初めて耳にする天使の称号だった。
第16話 災厄の天使
「ええと、災厄って言いました?」
細い三日月が交差するデザインのペンダントを見つめたまま、イリィは首を傾げる。
「天使様なのに?」
護符売りと言う商売がら、この手の質問はよく耳にする。
世間一般には半ば伝説的な存在である上級天使の知名度は、その在位期間と実績に左右される、とは限らない。
彼らの活躍を実際に見聞きする機会なんてものは、相当に稀だからだ。
それよりももっと重要な要素。それはズバリ、天使を題材にした歌劇の演目の流行廃りである。
”日輪の天使”や”暁虹の天使”などは在位期間も長く、主役脇役含めて登場する歌劇作品が多いために、知名度もまたダントツである。
だがそれ以外となると、題材にされている演目にどれだけ人気があるかが勝負であって、”災厄”や”雪華”などは、アクションシーンやロマンスシーンの効果もあって、この数年で人気上昇中だ。
ただし、劇場が常設されているような大きな街に比べて、たまに興業が巡回するだけの地方では、新作よりも定番が好まれるといった傾向もある。
イリィの発した疑問は、初めてその名を聞いた地方出身者の客なら、大抵が抱くものである。
そして、訳知り顔をした客の誰かが決まってこう答えたものだ。
「聞いたことないかな、”我、悪鬼魔物の災厄たらん”って歌劇の台詞」
芝居がかった節回しで謡い上げるべき台詞部分を、だがフェグダは殊更平坦に棒読みした。
「縁起悪そうな名前が逆にウケて、魔除けや悪縁避けなんかにそこそこ人気があったりするね」
イリィの耳にも、フェグダの説明は素っ気ないものだった。先刻の営業トークと比べるまでもなく。
「お芝居でしたら、子どもの頃に何度か観たことはありますけど、最近は町に行くこともないし・・・・・・」
その時のことを思い出してか、一瞬うっとりした表情を見せたイリィだったが、すぐに寂しそうな顔になる。
「ああ、そりゃ仕方ないよな。気軽にホイホイ観に行けるもんでもないし」
こういう村では、普通そんなものだろう。勝手に納得して、フェグダはうんうんと頷いてみせる。
「それよかさ、」
「あの、フェグダさんは、災厄の天使様がどんなお方かご存知ですか?」
違う話題を振ろうと口を開きかけたフェグダは、意を決するように問いかけてきたイリィに、おやと目を丸くする。
「あー、そうだなー。ざっくり言えば、長髪の美形。ド派手な衣装で、得物は三日月みたいなデカい曲刀。天使にしちゃインパクトのある方だよな。でもって、人間なんか取るに足らないって見下してるタイプ」
後半などは、結構私情が入っている。
興味深そうに見つめられるのは満更ではないが、よりによって災厄の天使の話題であるところが、何ともフクザツな心境だ。
「フェグダさんはもしかして、災厄の天使様に会ったことがあるんですか!?」
これまたストレート過ぎるツッコミだ。
普段のイリィであれば、話題を変えたそうなフェグダの声色を読んで、それ以上の発言は差し控えただろう。が、今はどうしても、聞いておきたかったのだ。
「え、あ、まさか! 役者にならあるけどさ。本物は文字通り、雲の上のお方だろ?」
ここは即座に笑い飛ばさねばならないところだったのだが。真剣そのものなイリィに、フェグダはどうも気圧され気味だ。
「色んな所へ行く旅人さんでも、ですか」
「そうそう。いくら旅人やってるったって、行き当たりばったりに出くわすもんじゃないからな」
「そうですか・・・・・・そうですよね・・・・・・」
シュンと俯くイリィに、つい不用意な態度を見せてしまったことをフェグダは猛烈に後悔した。いくら面白い話題ではなかったとはいえ、あれではまるでライバルに対する嫉妬のようではないか。
しかもこんなことで、女の子をがっかりさせてしまうとは・・・・・・。
いつもなら、この程度の質問くらいどうにでもはぐらかせるはずなのに、全くどうかしているとしか言いようがない。
「・・・・・フェグダさんのメダルの模様は、翼が二対でしたよね。それにも意味があるんですか?」
反省中だったフェグダは、その台詞を聞いた瞬間、思わずはっと息を飲む。それから、
「無い無い無い! それきっと見間違い!」
ぶんぶんぶんと、勢いよく首を振って否定する。
「え、でも・・・・・・?」
「まあ、普通のよりちょっとだけ造りがいいってのは認めるけどさ、」
笑顔を作りつつ、フェグダは一生懸命言い訳を探す。何しろ、証拠をお見せするわけにはいかない。
「そだ! それともイリィちゃんもしかして、他でも見たことある、とか?」
それは単なる苦し紛れの反論だったのだが。
「え、えっと・・・・・・」
口ごもるイリィを、フェグダはしげしげと見つめた。
二対翼は天軍の羽根使い、三対翼は上級天使にのみ許される印で、一般に出回っているのはデフォルメされたものだけだ。
貴族や聖職者ならいざ知らず、一般にはその存在すらほとんど知られてはいないだろう。災厄の天使の名すら知らないような村の住人など、論外も論外だ。
「ここだけの話だけどな、」
フェグダは誤魔化し笑いを引っ込めると、声をひそめてイリィにそっと耳打ちする。
「もし、もしも、どっかでそんなの見ても、絶対に手を出すんじゃないぞ。二対翼や三対翼の印を勝手に造ったり持ってたりしたら、偽称罪や不敬罪で捕まっても文句言えねーから。これホント!」
「!」
「ま、そんなわけだからさ」
この話題はここで終了。
イリィが握り締めている一つを除いて、フェグダは慣れた素早さでペンダントを袋にしまう。
「で、どう? やっぱり案内役、頼めないかなあ?」
「あの、用事があるのは本当なんです。それに、私が行かない方がいいのも本当なんです」
「ふーん。何か事情がありそうだね。良かったら、俺が力になろうか?」
「それは結構です」
親身に言ったつもりなのに、即座にキッパリと断られてしまった。本当に取りつく島もない。
「そっか。じゃあ、あと一個だけ。イリィちゃん、あの遺跡に詳しい人、誰か知らない?」
「遺跡、ですか?」
その瞬間、イリィの顔に驚きが広がった。
「ええと、あんな所、崩れてるし、何も無いし、行っても面白くないですよ?」
「でもイリィちゃん、そっちに行こうとしてなかったっけ?」
フェグダが声をかける直前、イリィが歩き出そうとしていたのは、遺跡に続く上り道だった。
「あ、あそこは聖域なんです。勝手に他所の人を案内したら、怒られてしまいます」
イリィはしどろもどろになりながら、とっさに思いついた理由を口にする。
「そこを何とか! 外から見るだけでもいいからさ」
対するフェグダは、これでもかの拝み倒しポーズだ。
「本当に、その、困るんです。ええと、村長に許可してもらってからでないと・・・・・」
「うーん、そりゃあ、カワイイ女の子を困らせるのは不本意だけど、オレもあんまノンビリしてらんないからなー」
ここぞとばかりの二枚目スマイルで、フェグダはイリィの瞳を覗き込んだ。正真正銘、ここがフェグダの正念場だ。
(カワイイ女の子!)
それが自分に向けられた台詞かと思うと、色んな意味でめまいを起こしそうになるが、イリィは辛うじて耐え抜いた。
と同時に、一つの考えが閃いた。迷っている暇はない。こうなったら実行あるのみ。
「お願い・・・・・・」
イリィは両手を胸元で組んで、潤んだ瞳でフェグダの顔をじっと見返す。
「困らせないで下さい、ね?」
ひと呼んで、カワイコブリッコ大作戦!
年頃のお姉さんが彼氏に対して演技して見せる、アレ。
まさか自分がそのようなマネをする日が来ようとは思ってもみなかったが、深く考えてはいけない。
気分的には、まさに捨て身。ハズカシさのあまり顔は真っ赤に上気するし、普段やりつけないだけに動作などカチンコチンでぎこちない。
はっきり言って、色気には程遠い。だが。
(うぐっ! か、可愛すぎるっ。このたどたどしさがたまらんっ!)
・・・・・・どうやら努力の甲斐はあったようである。
名残惜しそうに何度も何度も手を振りながら村に向かうフェグダの姿を、精一杯のお愛想スマイルで見送って、イリィはようやく深い深いため息をついた。
何だかこれで、一生分の勇気と根性と度胸と愛想を使い果たした気がする。
が、いつまでも脱力してはいられない。
念の為にと、イリィは村の外周に沿って延びる家畜用の小道を少し進んでから遺跡の方へ向きを変えて、所々岩肌の覗く草地を登り始める。あまり足場が良いとは言えないが、牧草地の中では地面が固くて上りやすいルートで、しかも村からは家や植え込みが邪魔をして目立たない。
子供の頃にはみんなで競争しながら上ったものだが、まさかこの年齢になって再び使うとは思ってもみなかった。スカートの裾をからげつつ、イリィは一心不乱に登っていく。
フェグダという名の旅人は、少なくとも悪い人ではないように思える。
それでも、どうしても、何かが気になる。
たとえば、あの紋章のこと。
フェグダのメダルには、確かに二対の翼が刻まれていた。
そして、カリムの持ち物には三対の翼と向かい合う月が。イリィがフェグダからもらったペンダントの図柄と似た、けれどずっと精緻なで綺麗な”災厄の天使”の紋章があしらわれていた。
”災厄の天使”。それは、カリムのことなのだろうか?
初めて会った時、その背に翼が無いことの方が不思議だと思った。
でも、本当にそんなことがあるのだろうか?
カリムは村長に対して、逃避行の最中であること、誰にも喋らずにいてほしいことを約束していた。
だとしたら、一体何があったというのだろう?
(私、カリムさんのことも、アシェルのことも、何も知らない・・・・・・)
けれど、二人が何者であっても、どんな事情を抱えていても、イリィにとってはもう、大事な存在だ。二人のためにならないことは、したくない。
二対翼のメダルを持つフェグダは、そのことをイリィに隠そうとした。彼は悪い人ではないのかも知れないけれど、誰に対してもそうなのかは、残念ながら判らない。
イリィを遠巻きにする村人たちにしたって、決して悪い人たちではなのだから。
これが取り越し苦労なら構わない。それでも謎の旅人の来訪を知らせることは、きっとカリムとアシェルのためになるはずだ。
だから、一刻も早く!
騒ぐ心のままに、イリィは坂道を駆け上がった。
息せき切って神殿に辿り着いたイリィは、すぐには中に入らずに、壁の前で深呼吸を繰り返す。
二人は中にいるだろうか?
怒鳴って飛び出して行ったイリィのことを、怒ってはいないだろうか?
怖気そうになる自分を叱咤して、イリィは壁の破れ目に手をかけた。
「あの、アシェ・・・・・・」
からり。
ホールに向かってイリィが呼びかけたのと同時に、背後で小石が滑るような音が響いて、
「あ、マズ・・・・・・」
慌てたような声が小さく聞こえた。
「・・・・・・!?」
驚いて振り返ったイリィの前に、
「あ、ごめん。脅かすつもりじゃなかったんだけどね、ホントに」
片手で頭をかきかき、照れ笑いで姿を現したのは、ついさっき別れたばかりの人物。
「フェグダさん、どうして・・・・・・!?」
「いやー、イリィちゃんが深刻なカオしてたからさー、やっぱちょっと気になって、つい」
「そんな・・・・・・酷いじゃないですか! 黙って後をつけるなんて!」
「そりゃあ、後をつける時に大騒ぎするヤツはいないよなあ」
もちろん、そういうことを問題にしているのではないのだが。
悪びれた様子もなく、はっはっはーと笑ってから、フェグダはふっと真顔になった。
「でもそっかー。何かあるんじゃなくて、誰かいるんだねー」
「フェグダさん!」
「てかさ、大きい声出せば、中のヤツが気付いて逃げるって思ってる? それはちょーっと甘いんだなー」
ここでフェグダはニヤリと笑う。先刻のような人好きのする笑顔ではない。茶緑色の瞳が好戦的に光る。
「まあ見てなよ」
「!」
その瞬間、スウッと、空気の色が変わったような気がした。
フェグダを中心にして、不可視の矢が四方八方に放たれ、何もかもを突き抜けて進んでいく。
それは、現実には決して有り得ない、幻。だというのに、その光の矢はイリィの身体にもぶつかって、パチッと弾けて火花を散らす。
「なに、これ!?」
「あ? まさか、これが視えて・・・・・・!?」
驚いて飛び退るイリィの、その過剰とも言える反応に、フェグダは一瞬気を取られた。
その刹那。
フェグダの目の前で、鳥が大きく翼を広げた。
「!!?」
それが幻覚の類ではなく、翻った長い髪なのだと気付いた時には、フェグダの身体は前のめりに傾いでいた。腹に重い衝撃。せりあがる苦い胃液。ぼやける視界。
だが、気が遠くなるより先に、今度は右腕をぐいと後ろにひねり上げられ、背中に一撃を食らったのと同時に、左半身が地面に強かに打ちつけられる。
飛びそうになった意識が、その衝撃で無理やり引き戻される。
「他愛のない」
頭上から降って来たのは、呟くような声だ。
つまらなそうでも、馬鹿にするわけでもなく、ただ単に事実を口にしただけのような、短い言葉。
「・・・・・・ぶざけろよ・・・・・・馬鹿にする価値もないってか!」
声を絞り出すのに、かなりの努力が必要だった。しかも自分のものだとは思えないほど、ひどくざらざらした声だった。
だが、激しい痛みよりも苦痛よりも、侮られたという怒りが先に立った。
フェグダはぎりりと歯を食いしばりながら首を捻ると、自分の背中を踏みつけにしながら腕をねじり上げている者の顔を視界の端に捉えた。
「!?」
端正な白い面に、冷たい氷そのもののような蒼い眼差し。
それは五年前のあの日、謁見の間から垣間見た少年と、寸分違わぬ同じ顔。
「・・・・・・災厄・・・・・・双月の天使!?」
フェグダを見下ろす少年の瞳が、すっと剣呑な光を帯びた。
反射的に身を竦め、尚且つぎゅっと硬く目を瞑っていたイリィは、その直後に何が起こったのか、全く目にしていなかった。
ただ、ちりちりと全身にまとわりついてくるような空気がズバッとなぎ払われて、それと同時に、誰かがイリィの腕を力強く引っ張った。
「イリィ、こっちこっち!」
「・・・・・・え? アシェル!?」
はっとして目を開ければ、そこには小さな両手をイリィの左腕に回したアシェルが、励ますようにニッコリと笑っていた。
「さ、今のうちに行こ! カリムがアイツの気を引いてる隙に!」
「でも・・・・・・」
アシェルが引っ張るのと反対の方を振り向けば、ぺしゃんと地面に腹這いになったフェグダと、それを容赦なく押さえつけているカリムの姿があった。
靴の踵で踏みつけにされたフェグダが、世にも哀れなうめき声を上げる。
その時一瞬、カリムの蒼い瞳がイリィを見た、ような気がした。
「大丈夫、アレはカリムに任せておけば!」
アシェルは自分の事のように得意げに胸を張る。
「だからボク達は邪魔にならない所に行ってようよ、ね!」
「は、はい・・・・・・」
アシェルの大きな緑の瞳にウインクされ、イリィは腕を引かれるまま、足早にその場を後にした。
(まったく、余計なことをしてくれる)
羽根使いの青年が放ったのは、周囲に潜む者を炙り出すための探索魔道で、例えるならドアを思いっきり蹴破る類の挑発的なものだった。退魔や魔道に関わる者であれば、反射的に身構えるだろうが、普通の人間であれば特にどういうこともない代物だ。
青年には知りようもないことだが、イリィは無自覚に羽根と同調してしまう不安定な状態にある。思慮の無い術に身の危険を感じてしまったらどうなるか。
一度は何とか暴走を阻止出来たとは言え、次も運良く運ぶとは限らない。
遠ざかっていくアシェルとイリィの気配を感覚の隅で追いつつ、カリムは改めて踏みつけにしている羽根使いの青年を見下ろすと、
(にしても、本当に変なヤツだな)
彼の存在に気付いてからもう何度目かになる感想を、再度心の中でつぶやいた。
第17話 錯綜
フェグダがイリィを追って遺跡に現れるより、少し前のこと。
「ようやくお出ましか」
遺跡の屋根の上で、カリムは村の方向を見下ろしていた。
そいつが泉の術中にあったカリムの警戒網に引っかかってから、実際に姿を確認するまで、結構な時間が経過している。
「ふーん、あれが例の羽根使いか・・・・・・」
カリムの横で、アシェルもまた興味深そうに瞳を細める。
「一人、だよな」
「うん。他には誰もいないっぽいね」
「のんきだよな」
「うん。緊張感のカケラも無いね。気配だだ漏れだし」
あえて探す必要もないくらい、そいつの気配は目立ちに目立っていた。
「あれ・・・・・・天使狩りだと思う?」
「もしそうなら、酷い冗談だ」
彼が羽根使いであることは間違いないのだが、その様子は影の精鋭部隊と目される天使狩りどころか、およそ任務行動中の天使とは思えないものだった。
「じゃあ、何だと思うわけ?」
「・・・・・・迷子?」
しばし目を泳がせてから、しごく真面目な顔でカリムは言った。
「ま、冗談は置くとして、」
「あ、冗談だったんだ、何だ・・・・・・」
「あ?」
「ううん、気にしないで続けて!」
「・・・・・・まず解らないのは、あれが何で一人でノンキに出歩いてるかってことだよな」
羽根使いが任務に出る場合、必ず複数、少なくとも二人以上での行動が義務付けられている。この規定は所属する隊や任務の内容に関係なく適応されるし、見習いだベテランだといった区別もない。ただし、これは羽根の特性を考慮した規定なので、同じように天使と呼ばれていても、羽根使いでない者には適用されない。
「もし何か事情で仲間とはぐれたとしても、普通は仲間との合流を最優先にする、はずなんだが・・・・・・」
カリムがどれほど眼を凝らしても、彼の周囲にはそれらいい者など、誰一人として見当たらない。それだけでも十分不可解だと言うのに、この羽根使いときたら、物見遊山のようにノンビリ歩いて来たかと思えば、ナンパかというような軽いノリで出会ったばかりの女の子(つまりイリィだが)に話しかけてみたりする。
かと言って、任務以外で天使が勝手に出歩くなど、それこそ認められるはずもない。
「うーん、わっかんないなー。てか今更なんだけどさ、イリィに渡したあの目印に、会話が聞こえるような魔法の一つも組み込んでおけば良かったんじゃないかなー。そしたらあの二人が今何喋ってるかわかるのに」
「そんなの鬱陶しい機能は今まで必要無かったんでね。それに聞こえたところで、初対面で部外者の女の子相手に重要事項をペラペラ話す馬鹿はいないだろ」
「馬鹿だったら?」
全く容赦のないアシェルの反論に、カリムは一瞬絶句する。
「・・・・・・それは、考えてなかったな」
相手が聞けば大憤慨しそうな台詞だが、実際、真面目にその可能性を考慮に入れたくなるほど、変に見えるのだから仕方がない。
「でもまあ、彼が追っ手じゃないなら、ちょっと気が楽かな」
「さあ。それはどうだろうな」
「何で?」
「天使狩りの連中は効率主義だ。厄介な相手ではあるが、やり過ごしさえすれば、あいつらは長居しないでさっさと次に移動する。むしろ何をするか判らない奴の方が、予測が立たない分厄介だ。侮って馬鹿を見たくはないだろう?」
「もしかして天軍の天使じゃないってことは・・・・・・有り得ないっかぁ」
自分の思い付きを、アシェルは自分で否定する。こうもはっきりと羽根の気配をまとった者が、新人スカウトの目に留まらないでいられるとは考えにくい。
「少なくとも、身分証は本物のようだ」
天軍の発行するメダル型の身分証には、いくつかの法印が組み込まれているので、その気になれば少々離れていても判別することは難しくない。
「ホント、キミってばいい眼してるよねー」
「それがどこまで当てになるかは判らないが」
本物を持っている者が、必ず本物であるとは限らない。真贋というものは、最終的には自分自身で判断するしかない。
「ねえねえねえ、だったら囮って可能性は? 変な奴だなーってボクらが油断して出てったところを、遠巻きに隠れてる追討軍が一気に突撃! とかさ?」
冗談めかしたアシェルの発言に、
「俺なら待ち伏せに軍団は使わないけどな。上級の誰かを使った方が、機動性が高いし応用も利く」
ごく当然のようにカリムが応じる。
情報が徹底的に不足している以上、最悪の事態はいつだって起こりうる。
ただし、その作戦を実行するには、塔の側に二人が高確率でこの付近に潜んでいるという情報が必要だ。
カリムとアシェルがこの遺跡に着いて一日足らずだが、塔にはプラス二日の余裕があったんだし、その間にいくらでも打つ手はあったはずだ。
例えば手っ取り早いところで、転移門を開いた張本人である”あの馬鹿”に、門の出口を白状させることだろう。”あの馬鹿”にはシラを切りとおす義理など無いのだし、返答を拒否すれば反逆罪確定なのだから、むしろさっさと白状して塔への恭順を表明するべきだ。カリムなら、きっと、そう判断する。
が、よりによって、相手は”あの馬鹿”だ。
(アレにせめて自分の立場を考えて立ち回るくらいの利口さがあれば、俺も苦労しなかったよな・・・・・・)
”あの馬鹿”が上級天使の末席に着いて二ヶ月ほど。任務でしか顔を合わせない奴のことを、カリムがよく知ろうはずもない。なのに残念ながら、自分の保身に走る”あの馬鹿”ほど想像出来ないものはない。
それよりは、技官に不眠不休で転移門の軌跡を解析させるとか、カリムも気付かないような技術で持ち物に細工されていたとか言われる方が、まだ可能性が高い気がする。
「それか、下手な鉄砲方式に各地に手配書を回して、天軍だけでなく猫の手まで動員して、最優先マークで探索に当たらせる、とかな」
「じゃあ、あれは猫の手の見本なわけか」
もしも天軍がこっちの位置を正確には掴んでいないのなら、それで一応の説明はつく。もっとも、それはあまりにも楽観的過ぎる見通しなのだが。
「でなければ、探索には全く関わってなくて、全く偶然ここに来たか・・・・・・」
「偶然ー? まーたご都合主義なことを」
「可能性だけなら、ゼロじゃない」
「ま、ね。それにしても、これってお酒片手にノンビリ交わす会話じゃないよねえ・・・・・・てか、どうしたのさ? 何で笑ってんの?」
「俺が? まさか!」
「笑ってたよ?」
「・・・・・・何でもない!」
カリムは残った酒を一気にあおると、タンッと空になった杯を置く。
それから背の中ほどでゆるく縛っていた髪を解いて、何かを振り払うように大きく頭を一振りし、今度はキリリと頭上で一つに結わえ直す。
「あのさ、まさか自分から出てって、あの囮かも知れない変なのの相手をしようっての?」
少し驚いて、アシェルは大きな瞳をさらに丸くする。
「隠れてやり過ごさないんだ?」
「確かにその方が賢明だろうな」
あっさりとカリムは同意する。
相手が何者だろうと、見つかりさえしなければ何も問題は無いわけだし、わざわざ自分からここにいると教える必要など、全く無い。
だが、この状況でカリムが無視を決め込んでしまえば、イリィを矢面に立たせることになりかねない。
たとえ相手にその気がなかろうと、羽根を所持しているというだけでも、不安定なイリィを大きく揺さぶってしまう危険がある。いや、そいつとイリィが顔を合わせていなかったとしても、この村に足を踏み入れた時点で、既に均衡が危うくなりかけている。
「考えてみれば、俺には逃げ隠れするスキルなんて無いんだよな」
心配げに見上げるアシェルに、カリムは悪戯っぽく笑って見せた。蒼い瞳に、不敵な光を宿しながら。
「・・・・・・まあ、コソコソするキミってのも想像つかないんだけどさ、大丈夫なの? 羽根使い相手に羽根なしで」
「手加減要らなくて楽だよな」
羽根は根本的に所有者の身を最優先で守ろうとするから、本気で蹴り飛ばそうが投げ飛ばそうが、やり過ぎて倒してしまう心配は要らない。
「だからっていきなりバッサリいったりしないよね? ・・・・・・ちなみに、論戦になった場合のスキルの方は?」
「これから磨くさ。せめて俺に恨み持ってる奴じゃなきゃいいよな。知らない間に買いまくってる自信があると、こういう時は厄介だ」
「だからそれ、面白がって言うセリフじゃないから。てか、そんな自信持たなくていいから」
どこまでが強がりで、どこまでが本気なのか、判断に困るアシェルである。
「でも! それならフル装備しろとは言わないけどさ、靴くらいは履きなよね」
「・・・・・・」
アシェルの指摘に、カリムは目を丸くする。
「何だったら、印のところに×でも付けとく?」
自分がどんな顔をしたのか考えて苦笑すると、カリムはアシェルに手を伸ばし、その綺麗な紅い髪をくしゃりと撫でた。
「・・・・・・災厄・・・・・・双月の天使!?」
苦労して首を捻ってカリムを見上げながら、羽根使いの青年は呟いた。
痛みに歪んでいた顔が、その一瞬だけは完全に驚きの色に染まる。そんな表情の中に僅かな狼狽を見てとって、カリムは興味深げに目を細める。
それにしても、”双月”とは、久々に耳にした。他人がどう呼ぼうと興味がなかったので気にも留めずに放っておいたら、いつの間にやら融通の利かない番人どもの間でさえ”災厄”や”凶兆”で通るようになっていた。
正式な方の称号は、今ではせいぜい報告書類か、堅苦しい儀式の時くらいにしか使われていないのではないだろうか。
(こんな反応を見せるってことは、俺に用が無いわけじゃなさそうだな)
見下ろすカリムを、挑むような茶緑色の瞳が睨み返す。
冷たい光を宿した蒼い瞳が見下ろしている。
その瞬間、頭の中に電気が流れた気がした。何故ならそれはフェグダの記憶の中、遠くで一瞬すれ違ったあの少年と、全く同じものだったからだ。
(ちょい待てよ? 同じ、過ぎる!?)
当時のフェグダが同い年くらいだろうと思った少年は、今この時、完全に年下であるように見える。五年前の記憶の中から、そっくりそのまま飛び出してでも来たかのように。
いや、よくよく見れば。あの時の少年の髪は、これほど長くはなかったし、こんなふよふよした色ではなく、黒鳥のような漆黒だったはずだ。いや、髪を切ろうが伸ばそうが本人の自由だが、色違いの方はどうなのか?
あまりにも同じ過ぎるところ、あまりにも違いすぎるところ。
(上級天使は不老不死・・・・・・)
噂に聞いた言葉が、頭の中に蘇る。
(こいつは、本当に災厄の天使なのか? もしかしたらソックリさんの兄弟だとか・・・・・・!?)
どう判断するべきか。正直、フェグダは混乱していた。
ただ一つ確かなのは、五年前にはフェグダを掠りもせずに通り過ぎたそいつの双眸が、その同じ冴え冴えとした眼差しが、今はしっかりと自分に向けられているということだ。
「痛ってええぇぇぇ!」
ガツンと踵で小突かれた拍子に、忘れていた痛みが蘇ってきて、フェグダは再び地面に突っ伏した。
いや、痛いなんてもんじゃない。ねじ切られそうな右腕も、容赦なく踏みつけにされている背中も、一瞬でも忘れていられたたことが不思議ほどの激痛を訴えている。
相手は自分よりずっとヤワな体型で、それほど力を入れている素振りすら無い。なのに、何故だか全く振りほどくことも跳ね除けることも出来ない。
人を見かけで判断してはいけないのは承知しているが、それ以前に腕力勝負で負けるのは酷く屈辱的な気分だ。などとノンキなことを言っている場合ではない。
これはかなり、本気でヤバい状況だ。
「すいません、降参です! 俺が悪うございました! お願いします放して・・・げほ・・・!」
まずはダメ元で訴えてみる。
まさかあっさり応じてくれるはずはないだろうが、相手が油断したスキに、何とかして反撃を・・・・・・。と考えたところでいきなり、腕を捻っていた力が消失し、同時に背中にかけられていた重圧が退いて、フェグダは唐突に自由になった。
「・・・・・・あ!?」
腹這いの亀のまま呆然とするフェグダを他所に、そいつはクルリと背を向けて、スタスタと歩き去ろうとする。
「お、おい、ちょっと待てよ・・・!」
痛む右腕を庇いながら、フェグダは慌てて身体を起こす。
言うだけ言ってはみたものの、まさかこんなにあっさり解放されるとは予想外。いや、むしろ心外だ。これでは解放されたというより打ち捨てられたみたいではないか。
しかも何事もなかったかのように無防備に背を向けられるのは、いくら何でも人をなめ過ぎではないか。
「おいって!」
つい、捻られていた右腕の方を伸ばしてしまい、フェグダは痛テテと顔をしかめる。
と、そいつはふっと足を止め、ほんの僅かだけ首を巡らせてこっちを見る。たったそれだけのことで、ぞくりと背筋に冷たいものが走る。
「あー、そのだなー・・・・・・」
言いよどんだ途端、そいつはとっとと視線を戻して歩き出す。
「おわっ! だからその、待てってば! 待って下さい! お願いします!!」
遺跡の壁際まで行ったそいつは、いかにもかったるそうにため息をつくと、
「旅人風情に興味はない。用があるなら勝手に喋れ」
今度は視線を向けもせずに言い放つ。
(ムカつくヤローだ)
フェグダは、ぎゅっと音が聞こえるのではないかと思うほど、両手の拳を強く握り締める。
だが、ここで引いてはただのムカつき損だ。何か、何でもいいから話しかけて、とにかく何か喋らせて、相手の正体を確かめなければ。
「じゃ、じゃあ・・・俺のことを何であっさり解放した? そのまま腕を折るなり縛り上げるなり、いくらでも出来たはずだろーが!」
我ながら子供じみた下らないことを聞いてしまった、という気はする。
話のとっかかりにしても、もう少しマシなセリフが・・・・・・思いつかなかったのだから仕方がない。が、
「・・・・・・お前、そういう趣味なのか?」
「違う! 断じて違う!!!」
聞かれた意味に気付いたフェグダは、即座に、顔を真っ赤にして否定する。
解っている。見え透いた挑発だ。ムカつくことはムカつくが、そんなものにほいほい乗っかるほどフェグダはもうガキではない。
「そーじゃなくて! 俺がそんなに取るに足らない存在に見えるのかって聞いてンだよ!」
「言った通りだ」
「!」
興味ない。フェグダが何を言おうと、何をしようと、何を思おうと。
挑発する気も、気にかける価値さえも。
その瞬間、頭の中で、何かがブチ切れた音がした。
「・・・・・・お前は、双月の天使なのか!?」
形だけのへりくだりさえ完全にかなぐり捨てて、渾身の力を視線に込めて、単刀直入に、一番の疑問を相手にぶつける。
背を向けたまま振り向こうとさえしない、そいつの表情は判らなない。
細い背中だ。両腕で締め上げれば、簡単にへし折れるのではないかと思うほど。そのくせ居丈高で、尊大で、傲慢極まりない貴族のように自分の優位を微塵も疑わず、他者を見下すことが当たり前。
そいつのまとう雰囲気は、災厄の天使の噂と重なる。宣伝向きに華やかに彩られた歌劇の主人公としてではない、天軍内で囁かれる数々の噂。
強大な力をその身に有しながら、味方を顧みることは一切ない。味方を犠牲にすることすら厭わない。魔物のみならず、居合わせた者全てにとっての災厄そのもの。
こいつが件の天使であるという確証はない。だが、違うと断定するのはもっと難しい。
握り締めたままの拳に、じっとりとした汗が滲む。
と、不意にそいつが動いた。
「あ、おい!」
問いかけを無視して歩み去るつもりなのかと思いきや、そいつは腹立たしくも優雅な挙動で半壊した遺跡の壁に腰を下ろすと、そこからフェグダを睥睨する。
冷たく光る蒼い瞳が、面白がるように細められる。
「それを聞いてどうする?」
「あ・・・・・・?」
「仮に俺がその天使だとして、お前に何の関係がある?」
「関係は・・・・・・無い。だが!」
そいつが興味を失う前に、フェグダは急いで付け加える。
「言いたいことなら山ほどある! まずは・・・・・・」
何から喋ればいいのか、考える余裕など無かった。思いついたことを、そのままぶつけるのみ。
「その・・・・・・噂を聞いた。双月の天使が白亜の塔から姿を消したせいで、天使狩りに動員がかかった、と。それはつまり、上級天使が脱走したってことじゃねーか。これが黙っていられるか!?」
そうだ。クミルからその話を聞いた瞬間、自分の内に湧き上がったもの。いても立ってもいられないほどの、それは怒りではなかったか。
「関係あるかだって? ンなもん、どうだっていい! 上級天使が脱走なんて前代未聞だ! それはこの上ない裏切り行為じゃないか! 塔の天使、いや、天使を崇める世界の全てに対しての裏切りじゃないか! だってそうだろ? 上級天使がどんな贅沢三昧しようと、無慈悲な事をしようと、それでも崇められるし威張っていられるのは、魔物を倒す力があるからだろ? 上級天使でもなきゃ倒せないような、強力な魔物から世界を守れるからだ! なのに、脱走だって? 何でそんなことが出来る? 言い分があるなら言ってみやがれ! 俺には聞く権利があるはずだ。世界中全ての人間にその権利があるはずだ! ってな・・・・・・」
叫んでいる内に、どうしようもなく高ぶっていた感情は、急速に冷めていった。
(それを聞いてどうするんだよ・・・・・・)
フェグダの中の冷静な部分が囁いている。
(そんなもの、聞いたところで何になる・・・・・・?)
第18話 凝る瘴気
「あの・・・・・・ごめんなさい!」
村に続く坂道を半分ほど下ったあたりで。走る足を緩めたイリィは、先導するように先を飛ぶアシェルの背に向かって、思いつめたような一言を口にした。
「私、あんなことになるなんて、全然思わなくて・・・・・・」
素性も知れない者を案内するつもりなどなかったし、人の良さそうに見えた旅人があんな訳の判らない力を持っていようとは思いもしなかった。
アシェルとカリムに迷惑をかけるつもりなど、これっぽっちもなかったのだ。
「・・・・・・本当に、ごめんなさい・・・・・・」
行き過ぎてしまった分を戻ったアシェルは、うつむくイリィの顔を覗き込むように見上げると、
「大丈夫、怒ってないよ。カリムもボクも」
「でも・・・」
「あれはイリィのせいじゃないって、ちゃんと解ってるよ。イリィはボク達に、危険だよって報せに来てくれたんだよね。だったら何も謝ることなんてないよ。でしょ?」
言い含めるようにゆっくりと語りかけながら、アシェルは柔らかく笑ってみせる。
「それにカリムだったら大丈夫! ああ見えても結構頼りになるんだから!」
話をカリムに持って行った途端、アシェルは自慢げに胸を張る。
「だからもう気にしないの。ね?」
「うん・・・・・・本当に、ごめんなさい」
「はい。よしよし」
アシェルはイリィの目線よりも少し上まで浮かび上がると、お姉さんが小さい子にするように、そっと頭に手を乗せた。
と、イリィの目から大粒の涙が零れ落ちた。
「あ、これは、違・・・・・・」
慌てて目を擦ろうとするイリィの手を、アシェルがそっと押しとどめる。
「すっごく怖かったよね。それでもイリィはとってもとってもがんばったんだもんね。だから、いいんだよ。思いっ切り泣いちゃっても」
「うん・・・・・・」
小さくうなづいたイリィは、素直に両手で顔を覆った。細い肩が、静かに震える。
そんなイリィの頭を、アシェルは優しく撫で続けた。
(ボクの方こそ、ごめん・・・・・・)
ややあって、顔を伏せたままのイリィの耳に届いた微かな声は、何故かそんな風に聞こえた気がした。
「世界に対してだと? それは大きく出たものだ」
その口ぶりは、いかにも面白い冗談を聞いたと言いたげだったが、無視されるかと思っていたフェグダは、まず応えがあったことにハッとする。
「では聞くが、お前は本気で世界なんてものを気にするのか? それともお前こそが世界だとでも?」
「違げーよ! てか、そんな思い上がった発想は、いかにも上級っぽいよな! けどな、どんなに上級天使が凄いって言っても、それはその他大勢扱いの下級天使の支えがあって、だからこそ威張ってられるんじゃねーか。それを・・・・・・」
(バカか、俺は・・・・・・)
苦いものが、フェグダの中にこみ上げる。
(言ったところで、どうせ届きはしないんだ。こいつは俺に、名乗りすら求めはしなかった。俺にどんな理由があろうと、こいつに取ってはまるで関心のない、下らないことでしかない)
「そうか? 俺には、お前自身が裏切られたと泣き喚いているようにしか聞こえないが」
「・・・・・・!」
今度こそ本当に、そいつはくっくと笑い声を上げた。
「無意味だな」
「何、だと?」
「世界だ何だと、そんな建前を聞くためにわざわざここまでやって来るとは、大概物好きな奴だよな」
「・・・・・・・」
「だが、そうではあるまい? なのに何故、ありきたりな言葉ばかりを並べ立てる。自らの言葉で語らぬ限り、どれほどの時と言葉を重ねたところで、得られるものなどありはしない。違うか?」
「!」
見透かされた、と思った。
こんな奴に!
よりにもよって、一番言われたくない奴に!
「お前なんかに何が解る! 簡単に放り出してしまえる奴なんかに! 名誉も地位も力も何もかも、人がうらやむ物を全て与えられながら、それがどんなに恵まれているのか考えもせず、当たり前だと勘違いしてるから、だからそんな真似が出来るんだろーが! それを、偉そうにっ! 知ったような口ぶりでっ!」
そうだ。解るはずがないのだ。
どんなに望んでも手に入らない苦さを知りもしない奴になど。
身体の奥底から湧き上がる、どす黒い怒り。だが。
(違う。そうじゃない・・・・・・)
フェグダに残された、ほんの僅かな冷静な部分が指摘する。
こんな怒りは見当違いだ。
たとえこいつが本当に災厄の天使本人だろうと、どんなに鼻持ちならない奴だろうと、どんなに気に食わない奴だろうと、自分が本当に怒りをぶつける相手は、こいつではなく別にいる。だからこれは、単なる八つ当たりなのだ。
(ある意味、判りやすい奴だよな・・・・・・)
一生懸命感情を制御しようと努める青年を前にして、カリムは至極冷静に考えていた。
当然のことながら、カリムには青年の抱える事情など知る由もない。
だが、喋りたい奴を喋らせること自体は、さほど難しいことではない。前置きや駆け引きの手間を省きたいのなら、相手を怒らせてタガを外してやることは有効な手段の一つだ。
盲目的に天使を崇拝するような部外者と違い、天使の大半は、災厄の天使に対して好意的な感情など持ってはいないだろうし、場合によっては恨みを買っていることもあるだろう。それを面と向かって言いに来るほど度胸のある奴は珍しいが、それに関しては別段思うこともない。
だからカリムにとっての関心事は、この青年が有益な情報を持っているかどうかであり、いかに手持ちの札を晒すことなくその情報を引き出せるかである。
(噂を聞いた、と言ったな)
災厄の天使逃亡の報を、追討命令という形ではなく、噂で知ったのだと。
(それに、わざわざ来たと指摘した時も、こいつは否定しなかった)
つまり、命令を受けて来たのではなく、彼自身の意思でここまで来たというわけだ。
天使狩りの連中が動いているのは解るとしても、躍起になって探しているだろうそいつらよりも早くここに辿り着いたのは、単なる偶然の悪戯か。それとも誰かの周到な作為なのか。
(とりあえず、あの娘から注意を逸らすって初期目標は達成したし、どうやらこれ以上の有益情報は期待出来そうにないし、ノンキに付き合ってやる意味も暇も無いし。こいつには、暫く行動不能になってもらおうか・・・・・・?)
無関心どころか、そんな物騒な思案をされているとは、青年は知る由もないだろう。
だが、カリムがあえて手を下さずとも、その手段はちょうど向こうからやって来るところだった。
不意に冷水をぶちまけられたような悪寒を感じて、フェグダは肩を大きく震わせた。
頭に上っていた血が、一気に引き戻された気分だ。
(何だ、このイヤな空気は・・・・・・?)
いつの間にか、あれほどノンキに晴れていた空がどんよりとくすんだ色に変わっている。揺れる草木がざわざわと騒がしい。にもかかわらず、風は温く澱んで、じっとりと身体にまとわりついているようだ。
肌の粟立ちを押さえようと深呼吸してみるものの、一向に効果はない。
「やれやれ。またも招かざる客のお出ましだ」
「おい、招かざるって俺のことかよ!?」
反射的に噛み付いたフェグダだが、そんな場合でないことは判っている。
ひたひたと押し寄せる暗灰色の霧が、すぐ近くにあるはずの灌木や岩を覆い隠していく。
「おい、何がどうなってる!?」
フェグダの両手は、無意識に腰の短刀の柄を探る。
それと時を同じくするように、フェグダの背後で、黒い影がゆらゆらと形を取り始める。それが大量の瘴気であることは、もう疑いようがなかった。
(馬鹿か俺は? こんな所で変なモノに巻き込まれてる場合じゃねーぞ!?)
そろりと周囲を伺ったフェグダは、すぐ近くに放り出されたままになっていた自分の荷袋を引っ掴むや、瘴気の薄そうな方へ向かって脱兎の如く駆け出した。
もちろん、そのまま逃走を決め込むつもりで。
(ふーん・・・・・・?)
あっという間に駆け去って行ったフェグダを、カリムは面白そうに見送った。
だが巻き上がった砂埃も治まらぬ内に、再びだだだーっと騒々しい足音が大きくなったと思いきや、羽虫の大群のような瘴気を引き連れたフェグダが、今度は右から左へと素晴らしい速さで駆け抜けて行った。
それから、大して間を置かず。
「・・・・・・なんで、俺にばっか、ついて来んだ、よ・・・・・・!」
ぜーぜーぜーと肩で大きく息をつきながら駆け戻ってきたフェグダは、恨みがましく吐き捨てる。
瘴気の塊は、フェグダ一人に狙いを定めて追いかけているのだった。
「やはり、そういうことか」
呟いたカリムに、フェグダがギッと怒気のこもった目を向けた。
「何だよ”やはり”って! お前、何か心当たりでもあンのかよ?」
意味ありげなニュアンスに、フェグダの眉がつり上がる。
「解らないのなら、言ってやっても構わないが」
「ンだと!?」
その台詞を意訳するなら、「俺に聞くってことは、解って当たり前のことが解らないって宣言するようなものだぞ? それを認めて頼むのなら、面倒だが説明してやってもいいぞ」ということになる。
当然、素直に「お願いします」とは言えない。間違っても言いたくない。が、意地を張っている場合ではないわけで・・・・・・。
フェグダは握りしめた両拳をブルブル震わせながら、少年と瘴気を見比べる。
だが、葛藤するフェグダの返答を待たず、少年はゆっくりと口を開く。
「フェグダ・ノル。第四軍、現地駐留部隊所属の二対翼」
「な!」
いきなり名乗ったはずもない本名と所属を言い当てられて、フェグダの顔に動揺が走る。それは、図星であると自分から白状してしまったようなものだ。
そんなフェグダに向かって、そいつはコイントスよろしく光るものを弾いて寄越す。
綺麗な放物線を描いて落ちてきたそれは、天軍の証である紋章入りのメダルだった。裏には凝った飾り文字で、フェグダの名と所属と経歴が記載されている。
「い、いつの間に!」
いや、それは聞くまでもない。出会い頭に一撃を食らった時の、ドサクサでに決まっている。
「お前、村の入り口で呪法結界に触っただろう」
「あ!?」
言われてフェグダは、村に入ろうとした時のことを思い出す。あの時、何の前触れもなく、メダルの鎖が切れて転がり落ちたことを。
「嘘だろ? あれがトラップだったってのかよ! て、ことはつまり・・・・・・」
「瘴気が狙うのは、そのトラップに掛かったマヌケだけだ」
「ンだとこの!」
言い返したいところだが、この場面では何を言っても負け惜しみにしかならない。
村や街の境界に悪霊(魔物や泥棒、疫病に犯罪者など、災厄の一切合切を含む)避けの呪いが施してあることは、別に珍しくも何ともないが、羽根使いにも有効なほど強力な呪いがかけられているなど、一体誰が予測できるのか。
と言うか、普通に暮らしている村人が根使いを敵視する理由などこれっぽっちも無いわけで、つまりこれは、かなりマズい事態ということになる。
「・・・・・・それで、どーすりゃコレを解除できる?」
不本意感をこれでもかと込めて、フェグダはその質問を口にする。
「それは解除条件次第だな」
「だから! それを知ってるなら、もったいぶらずにさっさと教えろ!」
トラップのような術の場合、簡単に感知されたり解除されたりすれば意味が無いため、術者はあの手この手で工夫を凝らす。何百何千通りもあるバリエーションの中から術の本質を見極め正確に対処するとなれば、多大な手間と労力が必要だ。ヒントがあるなら、それに越したことはない。
「それより呪を成就させてやったらどうだ?」
「呪を、成就だ・・・・・・?」
さらりとした口調の中に、そこはかとなく物騒な響き感じてしまうのは気のせいか?
「だから、”ケガをさせる”のが目的の呪なら、お前がちょっとケガしてみせれば、満足して消えるんじゃないか?」
「じゃないか? てか、ちょっと待て! ケガで済むって根拠があるのか? ケガどころじゃ済まなかったらどーしてくれンだよ!」
いや、済まない可能性の方が圧倒的に高い気がする。根拠は無くても、そういう気がする。
「だったら、あれを全部消し飛ばすか、追って来なくなるまでどこまでも走って逃げるか、飽きて離れるまで防御に徹して耐え忍ぶか、術の大本を探して解除させるか・・・・・・。俺としては、ここを離れて二度と戻って来ないことを勧めるがな」
「えらく行き当たりばったりな・・・・・・つまり、お前、具体的な対処方を知ってるワケじゃ・・・・・・?」
「さあ?」
完全に他人事モードの少年の応えに、フェグダはげっそりとうなだれる。
そうしている間にも、瘴気はどんどん濃度を増していき、フェグダの羽根の防壁に触れた部分が爆ぜて不可視の火花を散らす。
「・・・・・・ったく、とんだ災難だ。こんなの引き連れて村行った日にゃー、カワイイ子の出迎えにご馳走どころか、石投げられて追っ払われるの確定じゃねーか。仕方ねーから相手してやるよ!」
この期に及んで村でご馳走を諦めていないとは、ある意味見上げた根性だと言えなくもない。が、残念ながら、フェグダの台詞にすかさずツッコミを入れてやるほど、少年は親切ではなかった。
「っと! この野郎! ちょっとは仲良く団体で来やがれっ!」
瘴気と格闘すること暫し。
フェグダはすでに、威勢良く宣言してしまったことを後悔していた。
どんどん濃度を増していって形を取るかに見えた瘴気は、実際にはそれ以上凝ることはなく、幾重にも周りを取り囲んで漂っている。
下手に触れれば皮膚など簡単に溶け落ちてしまいかねない厄介な瘴気だが、羽根の防御結界をまとっているフェグダには大した脅威ではない。
その反面、短刀を振り回してのフェグダの攻撃も、羽虫の大群に徒手空拳で挑むようなもので、これまた大した有効打になっていない。
「こんなんじゃ、キリがねえ!」
だが、苛立ちの息を吐き出した瞬間、霧の中から延びた獣のように太く長い腕が、フェグダ目掛けて掴みかかった。
「おわっ!」
鎌を並べたように凶悪な鉤爪にかけられそうになりながら、咄嗟にかざした短刀でその一撃を受け流し、すかさず抜き放ったもう一本で爪の付け根をスパリと一刀両断する。
退魔法印を施された刀身が白炎のきらめきを放ち、じゅわりと音を立てて、腕の形を成していた瘴気の一部が蒸発して消える。
「っの! イキナリ何しやがる!」
短刀を握った両手を胸の前で交差させて構えながら、息を整えついでに悪態をつく。
と、今度は左後方の瘴気が凝ったかと思うや、再び獣の腕と化して、フェグダ目がけて襲い掛かった。
横っ飛びにかわしざま振るった短刀で、切り落とした獣の手首が、白炎に焼かれて消し飛んだ。効率は悪いが、霧のままでいられるよりは、攻撃が届きやすい分だけマシかも知れない。
だが、蒸発する瘴気に気を取られたフェグダに向かって、手首から先を失った腕が勢いもそのままに突進し、咄嗟に地面に身を投げたフェグダの真上を掠め過ぎた。
「っぶねー・・・、っと!」
すぐに跳ね起きたフェグダの眼前で、新たに繰り出された腕が地面にめり込むように潰れて四散した。地面を覆っていた下草がしなびて茶色く変色し、歪な円形の痕が残る。
「息つくヒマくらい寄越せってーの!」
「おい、お前!」
いきなり声をかけられたフェグダは、一瞬、注意を少年に向ける。
「危ないぞ」
「!」
あらぬ方向から襲い掛かった腕に対して、ほんの僅か、フェグダの反応が遅れた。
奇妙に捩れ曲がって伸びた腕が、振り上げられた短刀を掻い潜るや、フェグダの腹に食らい込む。と、見えた瞬間。
ぐわっ!
盛大な火花を散らして、腕を形作っていた瘴気の塊は、拡散する暇もなく根元近くまで一気に爆発消滅する。
他派手な衝撃のせいなのかどうか。爆ぜ残った瘴気は、フェグダから少し距離を開けたように見える。
「なるほどな」
高みの見物を決め込んでいた少年は、口にした台詞以上に素っ気ない顔で、ほんの少しだけ目を細める。
「何が、なるほど、だっ! わざとだろ、今、のっ!」
「要領悪過ぎ・・・っ・・・」
全く悪びれもせず呟かれた声に露骨なやれやれ感を読み取ったフェグダは、全力疾走直後なみに息を弾ませながらも、くわっと大きく牙を剥いた。
羽根を武器化させずに自前の短刀を振るっていたことからして、青年の得意は防御系だろうとは思ったが。
(攻撃型の障壁、か)
羽根の障壁を発現させている限り、瘴気の攻撃は青年には届かない。それどころか、攻撃してきた相手の力をごっそり浄化消滅させるほどの強いパワーを発揮する。それは魔道の術だけでなく、他者の羽根による攻撃に対しても十分に有効なのだろう。
(通りで、平気で挑発出来るわけだ)
カリムとの出会いがしら。いや、カリムの姿をまだ見ない内に、青年は探索の魔道を使った。
いくらイリィに気付かれた後だとはいえ、遺跡の中に潜んでいる者に対して、いきなり波動を放って探索をかけるという無謀かつ大胆な行為は、そうそう出来るものではない。
なにしろ青年がやったことは、みすみす自分の存在を喧伝するのみならず、相手が自分よりも強い力を有している可能性すら全く無視したものだったのだから。
だが、相手に反撃させることこそが目的だったのなら、その行為にも納得がいく。
青年の狙いは、相手の魔道攻撃を無効化することで、そこに生じる隙を突くことだ。思い切りよくその戦法を取ったのは、最強の法具である羽根の防壁を破れる敵など早々いないことに加え、大概の事態には対処出来る自信があったからだろう。
(まあ、怖いもの知らずではあるがな)
少なくとも、魔道的知覚の持ち主が魔道でしか反撃しないと決めてかかるのは間違いだ。
それに、こうして見ていればよく解る。障壁の能力は、決して万能などではない。
何よりも、障壁が羽根の具現である以上、使えば使うほど消耗することは避けられない。青年の戦法は、速攻で勝ちを決めることにこそ利点がある。
不定形の瘴気に対して、このまま打開策無しに強い発現を続ければ、時間とともに青年が不利になっていく。
しかも、瘴気は未だ、諦める素振りを見せない。
(それも不可解なことだよな)
魔気の色濃い瘴気へと、カリムは鋭い目を向ける。
青年が触れた呪術結界は、村の境界に沿って施されていたものだ。
仮にも羽根使いたる者が、何の危機感もなくスルーしたくらいだから、大本の呪法自体はごくありふれた、精々が村に出入りする存在を認識する程度の代物なのだろう。
だが結界に触れることでマークされた青年は、イリィに話しかけるのみならず、激しく怒らせたり恐怖させたりしたことで、術者に敵と認識された。そして、イリィが青年から離れることで、呪の発動条件を完全に満たした。
村人に対しては不幸の呪い程度でしかなかった呪が、これほど惜しみなく全力を投入しているのは、青年のイリィに対する態度が相当気に障ったか、それとも羽根使いであることが影響したのか。
それでも。
カリムから見れば、最強の退魔法具とされる羽根が必要なほど、この呪は強力なものではない。
青年の羽根がたまたま苦手とする状況であるからこそ、力が均衡しているように見えるのであって、彼がもう少し真面目に攻撃系の技を習得していたなら、あるいはカリムが忠告したようにとっとと逃げを決め込んでさえいれば、これほど苦戦する必要はなかっただろう。
(これが術者の限界なら、気に食わない事には目を瞑ってでも、羽根使いが村を出て行くまで息を潜めているべきだ。これでは、塔に敵対する術者として攻撃の口実を与えるだけだろうに。その程度の分別も持てないほど、あの娘に執着しているのか。それとも・・・・・・?)
この期に及んでも、村の付近に魔物や魔道師などの気配は読み取れない。番犬代わりに術を仕込んで、本人は不在である、というオチなら良いのだが。
(さて、そろそろ・・・・・・)
術者の正体を見極める必要があるとしても、ここでこれ以上粘ったところで、更なる状況の変化は期待出来ないだろう。
(村に向かったアシェルのことも心配だし、潮時か)
おもむろに、カリムは腕を持ち上げた。フェグダに狙いを定めるように、真っ直ぐに。
(ああもう! 何やってんですか君はっ!)
声がかかるのと同時に、カリムの全身を、覚えのある浮遊感が包み込んだ。
第19話 プリズム
水中を漂うような感覚を覚えながらも、周りに水は存在しない。カリムの身体は遺跡の壁に腰掛けたまま、どこかに移動したわけでもない。
ゆらめく水面をはさんだ向こうで、瘴気の腕を横っ飛びに避けようとする青年の動きが、コマ落としのようにゆっくりとしたものに変わる。
カリムと青年との間に垂直な壁のように存在する水面。それは、砂地と草地を区切る境界線に沿って遺跡全体を覆っていた。
(出やがったか)
視線を動かした先に、先刻の声の主は緊張感のないヘラヘラ笑いを浮かべて立っていた。
その足下に地面はない。カリムの視線の高さに合わせて、水中をプカプカと漂うように浮かんでいる。
(あれ? あまり驚いてくれませんね。あ! もしかして僕が止めに入るの、期待してました?)
(まさか。”ただの力の器”に、まだ用があるとは驚きだ)
(嫌だなあ。今朝のこと、ネに持ってるんですか?)
プイとカリムはそっぽを向く。
(全く、余計なことをしてくれる)
(それはだって、君が彼を攻撃しようとするからですよ)
(単に足止めしようとしただけだ)
(彼を囮にして、その隙にアシェルさんのところに行く気だったんでしょ。そんな軽はずみなことをして、彼の羽根が暴走したらどうするつもりですか)
(お前が心配しなくとも、奴のあの能力なら、暴走したところで大した影響は出ないはずだ)
当の本人以外には。
(・・・・・・っとに、情け容赦ありませんね)
(あんな瘴気より、羽根使いの方がよほど油断ならないからな)
(これは任務じゃないんですよ? そんなに頑なにならなくても・・・・・・)
(お前こそ、無駄口を叩きに出て来たのか? 茶飲み話がしたいだけなら、アシェルのところにでも行けばいいだろ)
(全くです。僕だって好き好んで君のところに来たくなんかありませんよ。だけど残念なことに、本当に本っ当に残念なことに。アシェルさんとはうまく道が繋がらなかったんだから、仕方ありません。あーあ、よりによってこーんな無愛想なのしか話し相手がいないなんて、僕は本当にツイてない・・・・・・)
(それは全く同感だ)
(おや、意見が合いました? 実は僕たち結構気が合・・・)
(ざけんな。こんな問答に意味があるとは思えない。俺を利用したいのなら、そのつもりで敬意を払え)
カリムはピシャリと、相手を遮る。
あの馬鹿と同じ顔。同じ声。同じような喋り方。無性に苛立ちを覚えるヘラヘラ笑い。
だが、あの馬鹿とは決定的に違う存在。
(それもそうですね。君はとっくに、僕の正体に気付いてるんだから)
特に気を悪くするでもなく、そいつはあっさりうなづいた。
(君の推測通り。僕はこの地の守護的存在の一部です。なんって格好つけてみても、今となってはどうにかこうにか気脈の調和を保つのが精一杯って体たらくなんですけどねーっ)
重々しい宣言から一転、調子よく振舞う時のあの馬鹿そっくりのテンションに、カリムは軽く眩暈を覚える。
(ったく、要らんトコばっか真似しやがって・・・・・・)
いや、解ってはいるのだ。
この姿、性格、喋り口調、その全て、守護的存在であることを自認する者がカリムの意識に同調するために、あの馬鹿のイメージとして認識させられているだけであることは。
そんなまどろこしい手段を用いなければならないほど、こいつ本来の容(カタチ)は微弱なものとなり果てている。自我という概念すら、残しているかどうかも怪しいほどに。
だが逆に言えば、それほどまでに純化された存在だからこそ、カリムの警戒心に弾かれることなく、意識に干渉することが可能だったのだ。
(で? まさか本気で、話し相手が欲しかったなどと言うつもりじゃないよな?)
(えー? それじゃダメなんですかー?)
同じ系統の術の場合、二度目以降は格段に成功率が高くなる。術者はそれを”道が繋がりやすくなる”とも表現する。しかも慣熟度が増す分だけ同調率も上がるので、カリムの違和感も随分と軽減されてきている。
しかしそれを考慮に入れたとしても、あまり余力のない守護者にとって、他者への干渉はかなりのパワーを浪費する為であることに変わりはない。
一度目は、多少の無理を押してでもカリムを見極める必要があっただろう。だが二度目は、何の得があるのか?
「まだ用があるとは驚きだ」というカリムの憎まれ口は、実はかなり本心に近い。
(まあ、実益を兼ねた好奇心とでも言いますか。それに、僕の話に付き合うことは、君にとっても損ではないと思いますよ。情報、要るでしょう?)
確かにその通りだが、それは質問に対する答えにはなっていない。
そっぽを向いたままのカリムに構わず、そいつは勝手に喋り始めた。
(いつからここにいるのか、どうしてこうしているのか。そんなことは僕にもわかりませんし、どうでもいいことです。ただ、僕はこういう存在である。それだけのことです)
カリムには想像もつかないほど昔から。それほど永い永い時間を、平穏に、ひっそりと、誰に知られることもなく。
そしてこの先もずっと、ゆるやかに、それは続くはずだった。
(ところが、つい最近、この地に禍々しいものが紛れ込んでしまったんですよ)
守護者にとっての”つい最近”が、どのくらいの時間を意味するのかは疑問だったが、問い質してみたところで、明確な答えは期待できないだろう。
(でもまあ、その時は大した脅威というわけでもなくて、そのうち何とかなるだろうって気楽に構えてたんですが、何がどう作用したんだか、この地に在るものと変に絡まってしまって、うまく排除できなくなっちゃったんですよね。困ったことに)
そいつは腕組みしながら、眉間に皺を寄せみせる。だが、その雰囲気からは、まるで危機感というものが感じられない。
(それならと、対抗するような力を持ってきて均衡させることを期待したんですけど、これがなかなか、思うようにはバランスしてくれなくて。気が付いたら、どっちも変な方向に膨らみはじめてしまって。ボクの能力は術を細かく把握するには向いてませんし。正直、どうしたものかと思ってたところだったんです)
(そこに、お前と似た力が通りかかった)
(そう! その通りです)
口を挟んだカリムに、我が意を得たりとばかり、そいつはにっこり笑ってみせる。
(僕とほとんど同質で、羽根なんていう余計なものがくっついてなくて。そんな都合のいい力なんて、滅多にありませんからね。それが向こうから手の届くところに落ちて来たんです。拾わない手はないでしょう?)
(それで、俺たちはここに引き寄せられたのか・・・・・・)
守護者による干渉が、あの馬鹿によってイレギュラーに開かれた転移門を、更に歪ませることになった。
あの馬鹿がどこに向けて出口を開いたにせよ、その意図とは違う場所に、カリムとアシェルは転がり落ちた。
ということは、塔の技術者がいくらがんばって解析を試みたとしても、外部からの干渉を特定しない限り、カリムとアシェルの行方を正確に割り出すことは不可能だ。
塔の連中は、さぞや焦ったことだろう。
図らずもカリムが羽根を捨てて来たことで、羽根の気配だけでその持ち主を特定出来るほど探査能力に長けた天使狩りでさえ、容易には辿れない状況になっている。
質より量の人海戦術か、それこそ悪運的偶然にでも頼らない限り・・・・・・。
(お前、俺たちを異空間から出す気なんか無かっただろ)
ただの確認事項であるかのように、サラリとカリムは問い質す。
(はい! 君たちがあっちの空間からこっちの世界に引き戻されたのは、ハッキリ言って手違いです)
応じる守護者にも、悪びれた様子など全くない。
(それにしても、よく判りましたね?)
(せっかく招き寄せた力だ。異空間でじっとしているのなら、その方が都合が良かっただろうからな)
守護者に必要だったのは、カリムの力のみであって、力の器に意味など無かった。
それだけを取れば、塔の連中がカリムを見るのと何ら変わるところはない。
だが、人間であるはずの連中が、他者の意思に何の興味も無いのとは違い、こいつには人の意志というものを認識することが出来なかった。その意味では、こいつは素直な反応をしただけであって、そういうものであることに罪悪感など持ちようがない。
遺跡に立ち入った少年らに付された印にしても、彼らにとって幸運のお守りになったのは単なる偶然であって、こいつから見ればチョロチョロ動き回る物が何かを知るための、ささやかな手がかり程度のものだったはずだ。
同じように、守護者の言う”禍々しい力が絡まったもの”や、”それに対抗しうる力を担っているもの”は、きっと、それぞれの力を背負わされた人間なのだ。
(まさかイリィさんがあんな風に羽根を使って道を繋ぐなんて、ホント、ビックリです。けど、まあ、そのおかげで君を通して周囲を見回すことが出来たわけですから、結果オーライというか、何が幸いするか判らないものですね。そうか。人間っていうのは、こんな風に物事を捉えていたんですね・・・・・・)
(・・・・・・それがいいことかどうかは知らないが)
(確かに、知らないでいる方が幸せだってこともありますからね。でもそれは、認識することが出来て初めて考えられることなワケだし、こうなることを事前に予測出来たとしても、やはり僕はこうしたでしょう。だから僕は、君に感謝すべきなんですよ)
(ノンキなことを。このまま、この地に力が集まり続ければどうなるか・・・・・・)
歪に膨らんだ力に対して、違う種類の力を加えることで強引にバランスを取ろうとすることは、自力で調和を図ることが出来なくなった守護が唯一選び得た非常手段に他ならない。それは同時に、最終手段にも等しい危険行為である。
しかもそれで得られる安定は、やがて来る破綻の時をほんの僅か先送りさせる程度のものでしかなく、新たに力が加われば加わるほど、その影響は拡大していく。
守護者自らこの地を滅ぼす要因になりかねないのだ。このままでは。
人間の思考を認識できるようになったからこそ、守護者は自らの運命を自覚した。
(ええ。きっと、そうなるでしょう。でも、それは仕方のないことです。僕はそういうものなんですから。何も君が気にする必要はない)
(誰が気にするかよ)
(ああ、それは良かった!)
言ってそいつは、ニカッと笑ってみせる。
『大丈夫! 笑えるうちは、何とかなります!』
無理やり貼り付けたのが丸分かりな笑い顔。
何度も。それこそ任務の度に。
『ほら、僕はちゃんと笑えている。だから、大丈夫。まだ大丈夫です』
目先の、ほんの些細なことに拘って、躓いて、悩んで、怒って、落ち込んで、泣いて、最後に笑う。
無理にでも。全然大丈夫ではなくても。
そしてまた繰り返すのだ。懲りずに、何度でも。
『いいんですよ。それが僕のポリシーなんですから!』
誰に何を言われようと、思った方へ、一直線に。
ったく、呆れてものも言えない。
そういう馬鹿だ、あれは。
それと全く同じ顔、同じ表情でありながら、こんなにも違って見える・・・・・・。
言うなれば、あの馬鹿のマヌケ面は矛盾した感情のごった煮から生まれたものだった。色んなものがない交ぜになりすぎて、もう笑ってみせるしかないという表情だった。
だが、たった一つ、そこに無かったもの。あの馬鹿が決して持ち合わせていないもの。
こいつの奥にあるのは、そのたった一つだ。
生にも死にも、何ら意味を持ち合わせない者のみが浮かべる、どこまでも平坦で色のない、穏やかさ・・・・・・。
(馬鹿らしい。何で俺がそんなことでイラつかなきゃならない)
自分が苛立ってしまったこと自体に苛立ちを覚えたカリムは、見るともなしに、青年の方に目を向けた。
紙一重で瘴気をかわし続ける青年の動きは、透明な泥の中を泳ぐように、おそろしく緩慢だ。
勝機は未だ掴めていない。が、諦めているわけでもない。
前方に大きく身体を投げ出して地面に転がりながら、四方に配る視線には、敵の攻撃を見極めようとする強い意志が見て取れる。
(いい顔してますよね、彼)
カリムの横、腕を伸ばしてギリギリ届くかどうかという位置に、一瞬で移動した守護者が並ぶ。
(誰に同意を求めている)
それに目をくれようともしないカリムを、全く意に介すことなく。
(一生懸命って、ああいうのを言うんでしょうね。君もそういうの、嫌いじゃないでしょ?)
何のつもりか、とんでもない決め付けだ。
(関係ない)
そう。カリムは他人を気にかけたりしない。どこの、どんな奴であろうと。
フェグダという名の青年にしても、もしかしたら以前に会ったことがあるのかも知れないし、何かしらの因縁があるのかも知れない。少なくとも、向こうにはそうなのだろう。
だとしても、どうでもいいことだ。自分にとっては。
(そんな風に諦めてないで、本人に直接聞いてみたらどうですか? 結構素直に答えてくれるかも?)
(それは無い)
(そうですか? 試してみないと分からないんじゃ?)
(言うつもりがあれば、もうとっくにぶちまけているはずだ)
先刻、カリムに怒りをぶつけた青年の顔は、言ったところでどうなるものでもない、それでも何かをぶつけないではいられない、そんな自分自身に憤っているようだった。
おそらく青年が見ているのは、カリム本人ではなく、災厄の天使という存在の持つポジションか、それともその向こうに投影される何かなのだろう。
(彼も色んなものに振り回されて、盛大に空回ってるカンジはありますけどね。見習うところも多々あると思いませんか?)
彼も、という言い方に込められた含みは、とりあえず無視して。
(見習う? あれのどこを?)
心底不思議そうに、問い返すカリムに。
(そうバカにしたものでもないと思いますよ。たとえば、瘴気を前にして自分が不利と見た瞬間、ソッコーで逃げ出そうとするところとか)
聞きようによっては強烈な嫌味になりかねない発言だが、その顔は真面目そのものだ。
(君も逃げ隠れするスキルが無いなんて開き直ってないで、今からでも心がけてみたらどうですか?)
(俺が? 何故?)
(だって、そういうものはこの先必要になりますよ? ほら、今は逃亡天使なんだし、少しはそのつもりでですね、)
(誰が逃亡天使だ。言っておくが、転移門に落ちたのはあの馬鹿のせいだからな。俺は、逃げる気なんて少しも無かった・・・・・・)
ふと、自分が言ったことに対して、何かが心にひっかかったような気がしたが、それは明確な形になる前にするりと通り過ぎてしまう。
(あの馬鹿ねぇ。誰の事も気にしないなんて言うくせに、彼のことは結構気にしてるじゃないですか?)
(そんなんじゃない。ここ最近、あれの面倒を押し付けられてたんで、仕方なく、だ)
(それだけじゃないでしょう? 君の評価基準に照らせば、彼は結構いいセン行くんじゃないですか?)
(ああ? どういう意味だ)
(だって君、つい考えてしまうでしょ。こいつは自分を殺せる奴かどうかって)
(何だそれは? 俺があの馬鹿に、そんなことを望んでいるとでも?)
(あ、自覚してなかったんですか)
(おい!)
(だからね、実際に君が何を望んでいるかはこの際置いといて、単に君が他人の何を評価するかって話ですよ。君が彼を気にするのは、彼には出来るはずだって思うからじゃないですか?)
(まさか)
(なのに彼は出来ないって言い張る。あろうことか、絶対やらないと公言してはばからない。それどころかあの時も、君たちを止めようとして大怪我を負いながら、意地でも助けようと奮闘した)
(・・・・・・)
(でも、それって不公平ですよね。君の方は、彼を殺すのなんか何でもないって考えてるのに。それが必要なら、絶対に躊躇するつもりなんかないのにね)
(当たり前だ。それが俺の任務だったんだ)
もしも、その時が来ていたら・・・・・・。
カリムが上級天使に加えられた当時、その総勢は八名だった。
あれから二人が欠け、二人が新たに加わった。公式には、そういうことになっている。
だがその中には、ほんの僅かの期間在籍しただけで称号を受けることなく去った者は、カウントされていない。
炎の結晶に適応する資格のない羽根使いに対し、塔の誇る魔道技術の全てを結集し、適応を試みる実験。
カリムになる以前の自分が巻き込まれたのは、それの初期の段階においてであったのだと思う。
炎の結晶への適合適性を補うものとして、塔の連中が考えたのは、羽根使いが死に瀕した際の生への執着を利用することだった。その方法にはある程度の成果が認められはしたが、彼らの目標は上級天使を造り出すことであり、いくら結晶と同化して目覚め、羽根を手にするところまで漕ぎ着けたとしても、利用出来るほどのレベルに及ばないのであれば失敗も同じだった。
真っ白な離宮で、カリムは目覚めた。
以前の記憶を喪い、全く異なった姿容を与えられ、何の理由も知らされず、ただ能力のみを求められて。
彼らの望むような結果を出せぬまま、連日繰り返される訓練と、調整の日々。
それでもあれは、技術が確立する前だったからこそ、与えられた時間だった。もちろん期限付きの、ではあったが。
もしも、あの場所でアシェルに会うことがなければ、自分が置かれた状況に抗する術もなく、ただ、終わっていたのかも知れない。誰にも知られず、名前も残らず、ガラクタのように打ち捨てられて、顧みられることもなく。
あの明るい緑色の瞳が、覗き込んで来ることが無かったら・・・・・・。
けれど、あの日。
『許セナイ 許セナイ 許セナイ・・・・・・』
真実を知って、自らもろとも、全てを葬り去ろうとしたアシェル。
それでもなお、生にしがみついた自分。
その選択をした時点で、カリムは、塔を責める資格を失った。
あの真っ白な離宮が、それに携わった多くの番人や施設や資料もろとも崩壊炎上したことで、上級天使を造り出す試みは大きな打撃を受け、中断を余儀なくされた。
だがそれも、ほんの一時的なこと。
カリムの知らないところで、実験は再開されていた。
そして彼らは、上級天使の候補者として、カリムの前に現れた。
第20話 深淵の畔に
「どう? ちょっとは落ち着いた?」
イリィの嗚咽がおさまってきたところを見計らって、アシェルはそっと声をかける。
「ええ、はい・・・・・・」
アシェルの声がきっかけとなって、イリィはおずおずと、顔を覆っていた両手を下ろした。
そんなイリィの顔を見るなり、アシェルは小さく苦笑すると、一体いつの間に用意したのか湿らせた布切れで、涙の筋の付いた頬を拭いにかかる。
「あの、アシェル、私自分で・・・・・・」
「いいのいいの、まっかせっなさいっ!」
ほんの短いつきあいではあるが、世話焼きアシェルに逆らっても無駄なことは、既に十分思い知らされている。イリィは、アシェルが自分の仕事に満足するまで大人しく待つことにする。
「うん、これで良し! どう、さっぱりした?」
「あ、ありがと、アシェル」
「どういたしまして!」
「・・・・・・」
「・・・・・・あれ? まだ何か心配事?」
何だかソワソワしているイリィに、アシェルはピョコンと首を傾げる。
「ええと・・・その・・・今誰かに見られたら、やっぱり判っちゃいますよね、泣いた後だって、思いっきり・・・・・・」
「それは、まあ・・・・・・目が赤いなーとか、瞼が腫れてるっぽいなー程度には」
「ああ、やっぱり・・・・・・どうしよう。お母さんに心配かけちゃう・・・・・・」
「いいんじゃない? 思いっきり甘えて帰れば?」
「でも・・・・・・私・・・・・・」
「心配、かけたくない?」
「だって、私のお母さんって、とっても心配性で・・・・・・こんな顔で帰ったら、ビックリしてどうにかなっちゃうかも・・・・・・」
そんな大げさなと笑われる覚悟で、小さな声でイリィが言う。
「そっかー。それは困ったなー」
だが、アシェルは真面目な顔で頷いたので、イリィは少し考える余裕が出来る。
「ああっ! でももうお昼過ぎっ! 私、今朝出て来たまま、家の用事全部放ったらかしっ! これ以上遅くなっても心配されちゃうし、どっ、どうしたらっ・・・・・・!」
途端に、忘れていた心配事を思い出してしまう。
「ま、まず落ち着こうよ、ねっ!」
パニック頭では、いい案が浮かぶはずもない。
「でも、ちょっと羨ましいかな。イリィちゃんには、そんなにも心配してくれるお母さんがいるんだね」
「あ! ごめんなさい、もしかしてアシェルには・・・・・・」
自分の都合に気を取られ過ぎたと、イリィはアシェルに申し訳無く思う。アシェルにだってきっと、色んな事情があるはずなのに。
「あ、気にしないで。ちょっとね、思い出しちゃっただけだから。ボクのお母さんのこと。もう、ずうっと前に別れたっきりだけどね・・・・・・」
「そう、なの・・・・・・」
「うん。そう!」
さっぱりした笑顔でアシェルは頷く。
「あの、聞いてもいい?」
少し躊躇ってから、イリィはおずおずと、遠慮がちな声をかける。
「何?」
「アシェルのお母さんってどんなカンジだったのかな、って」
「んー。わりとフツーだったかなー」
思案するように首を傾げたアシェルは、結局、素っ気ない答えを返す。
「普通の、妖精さん?」
イリィには妖精の親子関係はよく判らない。お話にだって、親子の妖精というのは、あまり登場しないのではないだろうか。
「あ、そっかー。そこからかー」
何が面白かったのか、ひとしきり声を上げて笑った後で、アシェルは悪戯っぽい緑の瞳をイリィに向けた。
「ね、教えてあげよっか、ボクのヒ・ミ・ツ!」
「え? えっと」
どう反応していいのか、判断に迷ったイリィだったが。
「どーしよーかなー。やめよっかなー」
などと上目使いに窺うアシェルが、どんな反応を期待しているのかは一目瞭然だ。
「聞きたい! 聞きたいです。すっごく!」
「そうー? ホントにー?」
「ホントに! とっても!」
両手を胸の前で組んでお願いポーズのイリィに、満足そうにアシェルは頷く。
「そんなにお願いするなら、トクベツに教えてあげる。ってか、ホントにホントにここだけの話なんだけどさー」
徐々に声をひそめて話すアシェルに、イリィは思わず身を乗り出す。
「人間だったの」
「・・・・・・はい?」
瞬間、イリィの目が点になる。
「だから、こんな風になる前はさ、ボクは人間だったんだ」
何でもないことのようにあっけらかんと言ってのけるアシェルだが、その告白はあっさり受け流していいような軽いものではないはずだ。
「そんな・・・・・・でも、どうして? 悪い魔法使いに捕まっちゃったの?」
「わあ、よく解ったねー!」
それが冗談なのか本当なのか、芝居かかった仕草で驚いてみせるアシェルからは伺えない。
「お話では、人を何か違う者に変えるのは、悪い魔法使いの仕業だけど・・・・・・」
「なるほどねー。おとぎ話の定番かー。そっかー。これって別に、特別なことじゃないのかー」
くすり、と小さくアシェルは笑う。それは少し、フクザツな笑みに見えた。
「ねえイリィ、そろそろ歩き出さない? 歩きながら、おとぎ話を聞かせてあげるよ」
「おとぎ話?」
「そう。一人の女の子が出てくる、あんまし大したことのない、わりとよくあるような、ほんのささいな話をね・・・・・・」
上級天使候補なる新人未満のヒヨコの面倒など、誰も好き好んで見たいとは思わないだろう。となれば、実戦訓練のサポート役のようないかにもかったるそうな仕事は、一番下っ端が押し付けられることになる。
そして同じ上級天使という身分であるなら、その序列は能力や実績以前に列せられた順、つまり一番経歴の浅いカリムが一番下っ端ということになる。
だが、そういう事情を考慮に入れたとしても、長期間に渡ってカリム一人がその役に任じられ続けたのは、やはり不自然と言っていいだろう。それこそ番人どもの中に、上級候補者の素性を秘匿しておきたいという思惑でも無い限り。そう考えれば、カリム以上の適任者はいないのだ。出自はもちろんのこと、任務に疑義を差し挟むことも無く、他者に漏らす心配も無かっただろうから。
もちろん、それは単なる推測だ。番人どもの真意について、カリムが問い質したことは一度として無いのだから。問い質したところで、正直な答えが得られるとも思えなかったが。
ともかく、つい最近に至るまで、新人候補の面倒はカリムの担当であったのだ。
だが。
彼らの顔を、カリムはほとんど覚えていない。彼らの名前も。何人くらいと出会ったのかも。
覚えていることと言えば。
上級天使になることが悲願なのだと、異口同音に彼らは言った。”全て承知”でここまで来たのだ、と。
そのように願うこと自体、彼らが炎の結晶の適合資格を満たしていない、不完全な者であることを意味していた。
そして、彼らは誰一人として、実践訓練の期間を乗り切ることが出来なかった。
どれほど強く願おうと、死に物狂いで努力しようと、手が届くことのない儚い望み。
なのに、一縷の望みに賭けようとする者は、後を絶たない。
上級天使という名の華やかな伝説など、虚飾の幻でしかないというのに。
あの時、もしも。
あの炎の中で、カリムがアシェルの手を取っていれば。カリムを含めた全てが破壊し尽くされていれば。
カリムという成功例が存在しなければ、実験は中止されただろうか。
それともやはり、手を変え品を変えて、試みは続行されただろうか。
おそらくは、後者だろう。
上級天使が必要とされる限り。魔道に携わる連中の探究欲がついえぬ限り。そして、彼らが羽根使いを単なる道具としか見ることがない限り。
それでも。
それでも、カリムに何の責任も無いと言えるだろうか。言い切れるのだろうか。
彼らを非難する資格を、自ら捨ててしまったカリムには。
あれは数ヶ月前、冬の初め頃だったか。
『はじめまして! 僕、アイルっていいます。でも本当の名前はアレクサンデルっていうんで、皇帝陛下って呼んでくれても全っ然OKですから!』
それは大胆にも、小さな子供でさえ知っているほど有名な、統一帝国を樹立した伝説の皇帝と同じ名だった。
しかも、それを告げた声は、どこまでも大真面目。その顔には満面の笑み。
『あれ? おかしいな。こう言うと大体みんな和んでくれるんだけど・・・・・・。あ、一応言っておきますけど、ウソでも冗談でもないですよ。もし信じられないんだったら、僕の親にでも聞いて下さいね! あ、でも、今どこにいるかまでは知りませんから、探して聞くのは大変でしょうけど』
仮にも上級天使たる者が、本名や素性について自発的に語るのは、珍しいことだった。
上級天使に至上の価値があると信じる者は、そうなる以前の自分を語るなど、決してしないものだから。
案の定、そいつは単なる候補者ではなく、最初から称号を授与された上級天使としてやって来たのだった。
が、その時カリムの頭を占めていたのは、もっと別の事だった。
(あれを見た瞬間、戦慄が走ったのを覚えている・・・・・・)
危うく襲い掛かりそうになった羽根を宥めるのには、一方ならない努力が必要だった。
そいつが何者であろうと、関わってはならないと、全ての感覚が警告していた。
それなのに、例によってお守りを命じられたばかりか、以降ずっと面倒を押し付けられることになる。
理由は、初任務の最中に知れた。
(あいつが力を振るった時・・・・・・清浄なはずの結晶の中に、闇の色が閃いた)
それがどれだけ特異なことかは考えるまでもない。
炎の結晶に少しでも闇の色が混じれば、闇の炎は結晶全体を侵食していく。
有り得ないのだ。
闇の色が入り込んだ結晶が、清浄であり続けるなど。しかも普段は全く判らないほど、闇がなりを潜めてしまうなど。
あいつがどんな経歴を持ち、どういった経緯でそうなったのかは知らない。知ろうとしたこともない。
だが、番人どもは承知していたはずだ。承知の上で、上級天使に任じたはずだ。対抗手段を有する監視役が常に目を光らせた状態で。
あれの特性を見極めるつもりだったのか。それとも使えるだけ使って、都合が悪くなれば処分するつもりだったのか。
(それなのにあの馬鹿ときたら!)
てんでマイペースに誰彼構わず同情しまくり、勝手な正義感を振りかざして命令無視で突っ走り、考えなしに口ごたえして逆らって、睨まれるようなことばりやる。どうしようもなく甘ちゃんで、どうしようもなく馬鹿なのだ。
それがどれほど危険な行為か、知ろうともしないで。
”不測の事態が起こった場合、どんなことをしても、結晶だけは持ち帰れ”
それは、上級天使に同行する者全てに課される使命だ。
羽根使いに限らない。随行を任じられる者は必ず、結晶を封じる術を習得している。
だが随従のみならず、上級天使同士が常に組んで行動させられるような、前例の無い編成の仕方。それは、もしもの場合、あの馬鹿の処断はカリムに任せられていたということだ。
通常では有り得ない結晶を持つ者に対して、通常の法術では太刀打ち出来ない可能性を想定して。
それは、逆も然りだ。
カリムが任務続行不可能な状況に陥った場合には、あいつもまた、決断しなければならなかったのだ。単なる心構えの話ではなく、当然の義務として。
あいつに出会う少し前から、その兆候は現れ始めていた。
ふとした拍子に、僅かに感じる軋みのようなものとして。
とは言え、それはごく些細なものに過ぎず、カリム付きの番人でさえ気付くのは難しかったのではないだろうか。
だが。
『・・・・・・ついにガタが来ましたか・・・・・・』
それは、すれ違いざまの一瞬のことだったが。
独り言のような小さな呟き。
しかし、カリムの耳に入ることを十分承知の上で、番人の長たるあの男は、確かにそう言った。
番人どもが期待したのは、カリムとあの馬鹿が仲良くタッグを組んで魔物退治に勤しむことではない。互いに監視し”適切に対処”することだ。
敵の殲滅よりも任務の完遂よりも、優先されることとして。
他の誰が気付かなくとも、どんなにお気楽能天気でも、あの馬鹿は気付いたはずだ。カリムがどんな状態であったかを。
いくら無関心を決め込んでいても、カリムにあの馬鹿のことが解ってしまったように。
任務に同道するとは、つまりそういうことなのだ。
『ねえたら! 任務の間はイヤでも顔を合わせてなきゃならないんだし、だったらいがみ合うだけ損じゃないですか。だったら仲良くしましょうよ。僕も精一杯努力しますから。イヤだけど。ねっ』
ったく、冗談じゃない。
『どうしてですか! そんな馬鹿な命令、クソっ食らえですよ! おかしいと思うことをおかしいって言うのの、どこが悪いってんですか! 自分の行動を自分で決められないなんて、どうかしてる! 自分の心ってのは、何の為にあると思ってんだ!?』
無茶苦茶な理屈で自分が正しいと言ってしまえる、その自信はどこから来るのか。
『この、ガンコ者の分からず屋! 君なんか大っキライですよ! とっとと転んでくたばっちまえ、だ!』
それでいい。お前に何かを期待したりはしない。俺はただ、与えられた責務を果たすだけ。最期の最期まで。
最期?
それは、いつのことだ?
動けなくなるのは、とても簡単。
薬酒を断つだけで、たったそれだけのことで、この身は簡単に力を失い朽ち果てる。
だが、本当の意味で死を迎えるとなると、それはとても難しい。
身体が滅びても炎の結晶を残す限り、新たな器が与えられるだけ。
そうでなければ、魔道の道具に利用されるだけ。
終わることのない、永遠の牢獄に囚われたまま。
『この結晶を壊してほしい・・・・・』
ずっと前に、そう望んだ奴がいた。
上級天使となるべくしてなった者でありながら。
カリムにとって、そいつはどうでもいいものの一つでしかなかった。
一度任務で同行した以外には、特に関わったこともなければ、すれ違いざま挨拶を交わすような間柄でもなかった。
誰かと親しくしようなどと思ったこともないカリムと違い、そいつは穏やかで慈愛に満ちて、誰にでも敬われ慕われる存在だった。
なのに何故、そんなカリムに願ったのか。そんなカリムだったから、願うことが出来たのか・・・・・・。
『いつか、君にも解る時が来るかもしれないな・・・・・・。だが、願っているよ。そんな日が永劫に来なければ良いとね・・・・・・』
安心しろ”蒼空”。そんな事にはなっていないから。
あの馬鹿にそれを望むくらいなら、俺は迷わず、魔物に引き裂かれる方を選ぶから。
俺は決して、他の誰かに委ねたりなどしないから・・・・・・。
(それで君は、蒼空の天使の願いを叶えてあげたんですね)
あの馬鹿そっくりの守護者の声に、カリムはゆっくりと目を瞬かせる。
どこにいる?
自分は今、どこに立っている?
(・・・・・・まさか。理由が無い)
(理由、ですか?)
(任務を受諾すれば、その時点で契約が成立しているんだぞ。契約違反が身に返ることくらい、俺たちには常識だろう)
人間であれば命令違反には罰則を課されるが、上級天使であるカリムにとっては、その程度のレベルで済まされる問題ではない。
人間のみならず、この世界のものは全て、物質界と精神界のバランスの中に存在するものだが、炎の結晶と同化したことで、ただの人間だった時よりも少し精神界寄りの高次にシフトした上級天使は、そう簡単に契約を反故にすることは出来ない。
契約を違えるという行為自体が、例えば小さい魔物であれば、この世界に存在するための力を根こそぎ消し飛ばされてしまうほどのダメージを被る行為に相当するのだから。
(有り得ないだろ。どうでもいい者のために、誰がそんな馬鹿を見るものか)
(だったら最初から、そんな任務なんか拒否しちゃえば良かったのに。少なくとも、二つ返事で引き受ける必要なんて、なかったはずですよ)
(何故?)
(はい?)
(何故、拒否しなければならない?)
(だって、イヤな任務とか、自分に向いてない任務とか、どう考えたって理不尽な任務とか、色々あるじゃないですか。それを・・・・・・)
(任務なんて、どれも同じ。どうでもいいことだ)
(同じですか? 本当に? 今でも?)
(しつこいぞ。何が言いたい)
(だったら、もし、仮にですよ? 今の君が今も塔にいるとして、あの時と同じような場面で同じことを命じられても、そう言うつもりですか?)
(ああ。塔にいるならそうだろう。俺が拒否したところで、その任務が無くなるわけじゃない。他の奴に振られるだけだ。それなら俺がやっても同じことだ)
(そうかなあ? ちょっと、違うんじゃないですか?)
(では、こう言えば満足か。大切な者すら手にかけられる奴に、それ以上に躊躇うことがあるとでも? その他大勢の命など、俺には何の価値もない。だったらどんな任務だろうと同じことだ。俺は”魔物”を討滅するだけ。それがどんな”魔物”であっても)
激昂して吐き出されたものでもなく、悲嘆にくれたものでもなく、まるで用意された台詞のようによどみなく。
深淵色の瞳に、何かを映すこともなく。
(でも、君の大切な人は、今はちゃんと君のすぐ近くにいる。以前の君ならともかく、今もそうであり続ける必要はあるんですか?)
(決まっている。あの日・・・・・・あいつを殺すつもりで結晶を砕いた。俺が、この手で。その事実は何があっても変わりはしない。絶対に)
(だってそれは、君は大切な人を解放するためだったんでしょう? 大切だったからこそ、やったことでしょう? だったら全然、意味が違う・・・・・・)
(黙れ。あいつを殺せていなかったのなら、なおさらだ。あいつを苦しませるだけ苦しませておいて、自分だけはのうのうと助かろうなどど。そんな、見下げ果てたものに、成り下がれと?)
(それでは、君の気は済んでも、アシェルさんのためにはなりませんよ)
(・・・・・・!)
(ねえ、君のその力、僕に譲りませんか?)
第21話 ごく他愛のないおとぎ話
むかしある町に、ひとりの女の子が、お母さんと一緒にくらしていました。
女の子のお母さんは、とてもきれいで、やさしくて、そして夢のようにキラキラしたドレスをつくるのがとっても上手なお針子さんでした。
お母さんがお仕事で作るドレスは、どこかのお金持ちのお姫様のためのもので、その女の子はドレスを着られるほど裕福な暮らしではありませんでしたが、大好きなお母さんと一緒にいるだけで、毎日がとても幸せでした。そしていつか大きくなったら、自分もお母さんのようなステキなお針子になるのだと信じていました。
ところがある日、立派な身なりをした人たちが女の子の家を訪ねて来ました。彼らはある国のご領主様の家来で、その女の子を探しに来たと言いました。
何でも、亡くなられた先代のご領主様には子供がなく、ご領主様の姉上様と弟君が跡継ぎの座をかけて大喧嘩、周りの者はとても迷惑をしていたのです。そんな時、実はご領主様には内緒の子供がいたことがわかったのです。その国の法律では、ご領主様の跡継ぎになるのは、姉上様でもなく弟君でもなく、どこかにいるというその子供です。
そう、それが、女の子だったのです。
女の子は、お母さんと別れるのがいやで泣きました。
でも、お母さんは女の子に言いました。
『泣かないで、いい子にしておいで。そうしたらお屋敷のみんながお前を好きになって、お前にやさしくしてくれるからね』
『いい子にしていたら、いつか迎えに来てくれる? お母さん』
お母さんは女の子の涙を拭いて、そっと微笑みかけました。
『幸せにね。私の可愛い子』
そうして、女の子はお屋敷に連れて行かれたのでした。
お屋敷の人は、女の子を大事にしましたが、それは、女の子が好きだったからではありません。
女の子を見つけ出して後見人になったことで、ご領主様の姉上様はお屋敷の主人になりました。
負けた弟君は、当然面白くありません。何とか女の子をさらおうとしたり、それがダメなら殺してしまおうとしたり、そうれはもう、色んなことを企んでは片っ端からやってみようとしたのです。
だから女の子は、大事に大事にお屋敷の中に閉じ込められたままでした。外に出ることも、お客様の前に出ることも、ドレスを着て舞踏会に出ることもなく、ペットの小鳥と猫とお話の本だけを友達にして。だって、いつ弟君の手下が来て女の子をさらってしまうか、でなければ殺してしまうか、わかりませんでしたから。
女の子は、ずっとずっと待ち続けていました。いつか、お母さんが迎えに来てくれることを信じて。
やがて、女の子が少女に成長した頃。
ついに迎えはやって来ました。
でもそれは、大好きなお母さんではなく、天使のお城のからの使者様でした。
使者様は、後見人の姉上様に言いました。
『この少女には特別な力があるのです。天使のお城に連れて行かなくてはなりません。少女を渡してくれるなら、その功により、あなたが正当な領主になることを認めてあげましょう』
もちろん、姉上様が嫌と言うはずはありません。
そして少女は、今度は天使のお城に連れて行かれたのでした。
それでも少女は、少し、わくわくしていました。
だって、長いこと閉じ込められていたお屋敷から、やっと出ることが出来たのです。
それに、天使様がいらっしゃるお城なら、そこはきっとステキなところに違いないと思ったからです。
でもそこは、少女が想像したのとは、全く違う場所、違う世界だったのです。
「・・・・・・特別な力・・・・・・あの、フェグダって人みたいな・・・・・・?」
アシェルの話を聞いていたイリィは、特別な力と聞いた途端に顔色を変えていた。
「うん。あれもそう」
羽根の力による防壁と、挑発目的の探索の波動。それは敵対とまではいかないが、決して友好的でも優しくもないものだ。
「・・・・・・あの時、私、たくさんの光が弾けるのが視えた。・・・・・・でも、あれは、普通は視えないもの、ですよね。視えていいものじゃないのに、私にはそれが視えて・・・・・・そのことだけで頭がいっぱいになって・・・・・・。私には特別な力があるんだって、カリムさんに言われた時はまさかって思ったのに、それは本当だったんだって・・・・・・だから・・・・・・怖かった・・・・・・」
イリィは両手で、ぎゅっと自分の肩を抱く。
「カリムさんは私の歌に力があると言ってた・・・・・・もし、私が歌うのをやめたら・・・・・・あれは、視えなくなる・・・・・・?」
怯えた紫の瞳が、縋るようにアシェルを見ている。
「力が怖い?」
問われたイリィは、黙って頷く。
「ねえ、イリィちゃん。何が特別かってのは、人それぞれだけどね。それは貴族のお姫様だったり、お金持ちだったり、頭の良さだったり、腕力だったり、美しさだったり、お料理上手だったり・・・・・・数え切れないくらい、色んな種類の力があるよね。ただ、ボクらの持ってる力は、人間の決まりごとの範囲をちょっとだけ越えていて、自分自身にも周りにも影響が大きくて、自分がちゃんとしてないと簡単に翻弄されちゃう・・・・・・」
「・・・・・・あの女の子も、怖かった?」
「・・・・・・そうだね。最初はよく解ってなかったかな。天使のお城は、それこそ特別な力を使う人ばっかりだったし、怖がってる暇なんてなかったかも。・・・・・・怖いって言うなら、ご領主様の子供ですって言われた時の方がずっと怖かったかもね」
それに。その力は彼女にとっては、大して特別ではなかった。屋敷の外にこそ連れ出してくれたものの、そこも結局は人間の作った決まりごとでがんじがらめで、その枠から逃れるには、彼女はあまりに無力過ぎたから。
だが、不安でいっぱいのイリィに向かって、それをそのまま伝える気にはなれなかった。
「ああ、でも悪い事ばっかりでもなかったかな。女の子はお城で、特別な人に出会えたわけだし」
「特別な人? 王子様? 天使様?」
パッと、イリィは顔を上げる。
イリィにとっては、知らない人との出会いそのものが、特別なことなのかも知れない。
「・・・・・・えーと、天使には違いないんだけど、あんまり王子とかそーゆーガラじゃなかったかなー」
天使と呼ばれる身になれば、他の天使は特別でも何でもなかったりする。
さらに夢を壊すようで申し訳ないが、アシェルの知る限り、王子様や騎士様に相当する連中に、ロクな奴はいなかったりもする。
「・・・・・・特別な人に会えて、女の子は幸せになった? 特別な力があって良かったって思った?」
「・・・・・・」
その答えは、多分まだ出ていない。だけど、はぐらかしてしまいたくもない。
「・・・・・・ある日突然、彼は彼女の前からいなくなって、彼女は彼を探し回るんだ。一生懸命探して、探して、探して・・・・・・。そうだね、誰だって、力は怖いよ。だってそれは、否応なく運命を変えるものなんだから。・・・・・・だけど、もし、もしも・・・・・・たった一度でいいから、特別で大切な人のために何かしてあげられるのなら、力があって良かったと思えるのかも知れないね・・・・・・」
「大切な人の・・・・・・」
「それは、イリィちゃんがこれから出会う誰かなのかも知れないし、今までずっと見守ってくれていた人なのかも知れない」
「私が一番大切なのは、お母さんです。今までずっと、見守ってくれて、私を大事にしてくれる人だから」
「うん」
「お母さんは・・・・・・私の本当のお母さんではないんです。本当のお母さんは、私が生まれたばかりの頃、私を置いてどこかへ行ってしまったって聞いてます・・・・・・」
「そう、なんだ」
おそらくそれは、秘密でも何でもない。村でただ一人、少しだけ違った外見を持つイリィは、誰かに問い質す以前に、そうと言われ続けてきたのだろう。
「だから、お母さんが私のたった一人のお母さんなの。ちょっとでも帰りが遅かったり、転んで擦り傷作ってたり、落ち込んで泣いてたりしたら、すっごくすっごく心配してくれるんです」
「いいお母さんなんだ。・・・・・・お母さんのこと、好き?」
「はい! 大好きです!」
「そっか。それじゃ、心配なんかかけたくないよね。大丈夫。涙のあとも、もうわかんないよ。だから、早く行ってあげよう?」
「はい!」
不安が完全に拭い去られたわけではないだろうが、それでもイリィはニコリと笑ってみせた。
(ごめんねイリィ・・・・・・ボクたちの存在は、間違いなくキミの運命を変えた・・・・・・)
アシェルは心の中で、そっとつぶやく。
『もしもボクが、イリィを助けてあげてって言ったら、キミ、どうする?』
それは昨日、アシェルがカリムに言った言葉・・・・・・。
本当は、誰でも良かったんだ。偶然出会ったのがイリィだったってだけで、イリィがどんな問題を抱えていようが、そんなことはボクにはどうでも良かったんだ。
だけど、ボクがあんなこと言わなければ、カリムはイリィに関わらなかった。イリィのことが気になったとしても、自分のすべきことではないと切り捨てて、顧みたりはしなかった。今までずっと、自分の気持ちを切り捨ててきたのと同じように。
ボクがあんなことを言わなければ、イリィだってボクたちに関わる理由も無くて、少なくとももうちょっとだけ、平穏な生活を続けられたはずなんだ。
でも、それじゃカリムは・・・・・・。
ボクじゃダメなんだ。
ボクの前ではカリムは、自分を許すことなんて出来ないから。
カリムがボクに望むのは断罪。そして終焉。
でも、ボクは。ボクの望みは・・・・・・。
(だから、イリィ。ボクに出来る事は何でもしてあげる。巻き込んでしまった代わりには到底ならないだろうけど。それでも・・・・・・)
(お前、一体どういうつもりだ)
見るもの全てを凍らせそうなほど冷ややかなカリムの視線を、そよ風のごとく受け流して。
(どうって、そのままの意味ですよ)
どこまでも穏やかに微笑みながら、あの馬鹿の声と顔をした守護者が応じる。
(だからですね、君の力を僕にくれれば、君の望みもアシェルさんの望みも、ついでに僕の望みも同時にまとめて叶えられて、万事上手くおさまるじゃないですか。我ながら、すっごく名案!)
(どこが名案だ馬鹿らしい)
(なんて言う前に、ちょっとは考えてみて下さいよ。炎の結晶と同化した命を持つ君は、身体が滅んでも魂は結晶の中で永遠に在り続ける。そんなのは、君の望む死ではない。なのに君は、肉体の維持に必要な薬酒を拒否している。いくら感情記憶を失くしたくないと言っても、それで動けなくなってしまっては本末転倒もいいところです。ねえ、どうして、そんな馬鹿なマネをするんです?)
微動だにせず、カリムはその言葉を聞いた。
(決まってます。君の身体が死ぬ時には、迷わず結晶を破壊してほしいっていう、アシェルさんに対しての意思表示です。アシェルさんの手にかかって完全に消滅することこそが、君の望みなんだから)
動く事が出来なかった。耳を塞ぐことが出来なかった。
(欠片ほどの結晶でようやく存在を保っているアシェルさんは、このままではいつ消滅してしまってもおかしくない状態です。だけど君を殺せば一人前の魔物として生きることが出来る。つまりアシェルさんには、君を殺す理由がある。それなのに、どうしてわざわざ意思表示をする必要があるんですか?)
見開いた眼が、宙を見据えながら何も映していない瞳が、ギラギラと乾いた光を宿す。
(その必要があるとすれば、それは、君が不安に思っているからです。アシェルさんはもう、君を壊してくれないのではないか、とね)
カリムの身体が微かに、本当に微かに震える。
(アシェルさんがどんな人なのかは、君が一番良く知っていますよね。そう、アシェルさんは君を犠牲にして生きようなんて、考える人じゃない。そもそもアシェルさんが魔物の力を手にしたのは、君の望みを知っていたからであって、そうでもしなければ君を殺すなんて出来なかったからです。だからこそ、君は恐れているのでしょう? 最期の最期で、アシェルさんは躊躇ってしまうのではないか、とね)
ただの言葉だ。関係ない者が勝手にほざく、ただの思いつきから出た言葉だ。
それなのに何故、こんなにも動揺してしまうのか。
図星だからだ。
守護者の指摘は正しいのだと、心が悟ってしまったから。
アシェルのために、何でもやろうと考えた。それは決して嘘ではない。
こんな命でも、アシェルの役に立つのなら、永らえてきた意味もある、と。
だが、それすらも、自分の望みでしかないのなら。
アシェルの望みではないのだとしたら。
では、一体どうすればいいのか。
自分に残されたものの中で、アシェルに必要とされるものはあるのだろうか。
(・・・・・・未だに俺は・・・・・・あいつより、自分の事ばかりを・・・・・・)
自分とは、そういう者。
誰かのためにと言い訳ばかり重ねながら、結局一番大切なのは自分だけ。
どこまでも、それだけ。
(永遠とは、それほど怖いものですか? でもね、いくら永遠とは言っても、身体を失ってしまえば、そう長い間意識を保っていられるものじゃない。百年、二百年もすれば、何もかもどうでもよくなりますよ。それはそれで、君という存在が消滅するのと変わらない。たとえ、結晶が塔の手に渡って、何らかの術の媒体に利用されるのだとしてもね。ああ、でも、再び肉体を与えられ蘇生されるって可能性もあるんでしたっけ? まあ、僕としては、どっちでも構いませんけどね)
どれほど意識から締め出そうとしても、消してしまうことの出来ない事実。
だがそれは、一番大切な者を前にしてなお、囚われ続けねばならないことなのか。
(だけど今の状況で結晶が残されたとして、それがすんなりと塔の手に渡るかは疑問ですけどね。場合によっては、天軍と魔物とで争奪戦になった挙句、この地は破壊され尽くされるでしょう。僕には素のままの結晶を利用することは出来ません。何とかして取り込めたとしても、結晶を欲する連中は僕の存在など物ともせずに、僕を破壊して結晶を奪っていくでしょう。ホント、迷惑極まりない話です)
カリムが聞いているのかいないのか、そんなことは大した問題ではないかのように、守護者はなおも語り続ける。
(ねえ。僕だったら、君を殺してあげられますよ。君の力を譲渡してくれさえすれば、君との繋がりを辿ってアシェルさんの意識に道を通すことも出来ます。守護の僕と意思の疎通がはかれるとなれば、アシェルさんはこの村で大事にされて、幸せに暮らすことが出来るでしょう。君がいなくなってもね。何だったら、アシェルさんの前では君の姿でいてあげますよ。僕はきっと、アシェルさんが理想とする君になってあげることが出来ます)
乾いた光を宿す瞳が、ゆるゆると守護者に向けられる。
(ね、悪い話ではないでしょう?)
第22話 それでも・・・

一体どんな理由があるのか。
それとも理由など、最初からありはしないのか。
ただ、目覚めた時には、それは既に心の内に存在していた。
ごく微かな囁き声は、この上なく冷たく、静かに、腕を広げて優しく誘う。
昏く深い、果ての向こうへ。
乾きに苦しむ者が水音へと手を伸ばさずにはいられないように、優しく差し伸べられる冥き御手から目を離すことなど出来はしない。
だが、それ以上、手を伸ばしてはならない。
決して、その手を求めてはならない。
何故なら、その手を取るべき時に、その手を拒んだのは俺自身。
大切なたった一人とともに眠ることより、幻の面影を追って生き永らえることを選んだのは。
だから、それ以外は何一つ、望んだりしないと誓った。
それ以外の何かのために、決して命を使わないと誓った。
いつか。
この世界のどこかに、幻の人を見出すその時まで。
さもなくば、抗うこともかなわぬほど圧倒的な敵の前に、ただ一つの願いごと粉砕され消滅するその瞬間まで。
いや、絶望的なまでに力の差を見せ付けられたとしても、絶対に負けたりしない。決して諦めたりしない。どれほど醜く足掻こうとも、きっと必ず生き残ってやる。
俺が負けるということは、俺が今まで犠牲にしたものには、簡単に諦めてしまえる程度の、たったそれだけの価値しかなかったのだと認めてしまうことなのだから。
カリムはゆっくり瞑目すると、一度大きく息を吐く。
あまり感情の振れ幅が大きいと、いつ記憶をごっそり持っていかれるかわかったものではない。忌々しいことに。
そうして静かに開かれた深淵のように蒼い瞳は、押さえ切れないギラギラとした乾きも、剣呑極まりない灼熱も、すっかり影を潜めていた。
(一つ、教えておいてやる。俺の全てはアシェルにやると、もうとっくに決めている。俺の意見など、差し挟む余地はない)
(それはひょっとして、僕の提案を拒否るって意味ですか?)
能天気極まりなかった守護者の表情が、その途端あからさまに曇る。
(アシェルさんにって、それは君が勝手に決めているだけでしょう? 君がそう言った時、アシェルさんは応じませんでしたよね? だったらその契約は成立していません。違いますか?)
(契約どうこうの話じゃない。ずっと前から、それは決まっていたことだ)
カリムは自分の右手に視線を落とす。
生っ白く細っこく、ほんの小さな傷痕すら刻むことのない手。
二度にわたって、アシェルを殺すための力を振るった手。
(でもそれは、アシェルさんを苦しみから解放したかったからで・・・・・・)
(それは後付けの理由だ。そういう綺麗な理由でもなければ、大切なものを殺せるはずがないという、都合のいい願望に過ぎない)
(でもそれじゃ、)
(黙れ。お前に何が解る。あの頃の記憶はもうとっくに無くなった。なのにどうして、何を根拠に言えるんだ)
(・・・・・・)
(それでも・・・・・・あいつが再び現れた時、湧き上がってきた感情・・・・・・あれだけはまだ、辛うじて残っている。あの記憶や感覚は、お前も共有出来るんだよな。だったらお前には、あの意味が解るか? 解るんなら教えてみろ)
(・・・・・・)
守護者は表情を消して、静かに押し黙っている。
(フン・・・・・・それで俺を演じられるとは、よくも豪語したものだ)
(君を、ではなくて、アシェルさんの理想とする君を、ですけど)
(だったらその格好は、俺の望むあの馬鹿だとでも言うつもりかよ)
(さあ。どう思います?)
(いい。興味ない)
(おやまぁ、バッサリと)
守護者は小さく苦笑する。
(・・・・・・俺には、アシェルを理解出来ているなんて言えないし、アシェルがどうしてあの娘のことを気にするのかも、未だによく解らない。だが、これだけは聞かなくとも解る。あいつの望む俺だ? そんなもの、あいつは決して求めない)
(それが、君の理由? だけど君自身は本当にそれでいいんですか? また、たった一人で取り残されることになっても? アシェルさんのいなくなったこの世界に?)
(あいつがそう決めたなら)
死を許されないことは残酷だ。死を求めるしかないことは悲しい。死しか与えてあげられるものがないことは、何よりも辛い。その全てを知っているアシェルが、それでも決めると言うのなら、どんなことであろうと、それはカリムが受け止めなければならないことだ。
(怖いくせに。声が震えていますよ)
(それの何が悪い)
(おや、開き直りましたか)
(・・・・・・アシェルの望む俺、か。そいつはさぞ、いけ好かない奴なんだろうな)
ふとカリムは、嗤うように口の端を上げる。
そいつはきっと、こんな風に怖れたりしないだろう。滑稽なほどに強がったりなどしないだろう。一時吹き荒れては跡形もなく消え去ってしまう感情に、惑い翻弄されることもないのだろう。
だとすれば、それは、これっぽちもカリムではない。
同じ物を見、同じことを知っていたとしても、同じ気持ちを抱くことがないのなら。
(どうしてもダメですか? 僕がこんなに頼んでも?)
(ああ)
(君のせいで、この地に災いが降りかかっても?)
(そうなった時は、俺ををこの地に引き寄せたお前の失態こそ問うべきだ。自分の行為を棚上げして責任を押し付けられるのは、ハッキリ言って迷惑だ)
(言ってくれますね。さすがは災厄の天使様だ。ですが、僕も守護として、あっさり「はいそうですか」って引き下がるワケにもいきません)
(ではどうする?)
守護者に向けられたカリムの目が、瞬時に鋭く細められる。
(あー、早まらないで下さいよ!)
途端に守護者は、おどけた調子でひょいと肩を竦め、物騒な視線から逃げ出すように数歩離れる。
(力勝負じゃ、僕に勝ち目なんてありません。そもそも君の承諾も無く力を奪い取るなんて不可能な話だし。かと言って、みすみす彼にかっさらわれるのもシャクに障りますけどね)
(誰に、何だと?)
(別に、何でも)
(・・・・・・)
(あ! そっか!)
いい事を思いついたとばかり、守護者はぽんっと両手を打って、笑顔を作る。
(つまり、アシェルさんの承諾を取り付けさえすれば、君は僕に力を譲っても構わないと、そういうことですよね?)
(・・・・・・お前、俺の話ちゃんと聞いてたか?)
(ええ、もちろん、確りと! アシェルさんが承諾しないだろうっていうのは、単に君の憶測であって、最終的に結論を下すのはアシェルさん自身なんですよね? だったらダメ元でも何でも、聞いてみる価値はありますよ!)
(・・・・・・意外と懲りない奴だな。どっから沸いて出るんだ、そのバイタリティは?)
むしろ呆れて、カリムは呻く。一人でキリキリしているのが、何だか馬鹿らしくなりそうだ。
(そりゃあもう! ダテに長年、のらくらと守護をやってませんから!)
(それにアシェルに聞くも何も、道がつながらないと言ってなかったか)
(代わりに君が聞いてくれたりは、)
(するか)
(やっぱり。まあ、がんばって、何か方法を考えますよ)
(だからって、あいつに何かしたら承知しないからな)
(わーかってますって!)
言いながら、守護者はびしいっと了解ポーズをキメる。
そんな守護者から、カリムはすいと目を逸らした。
(・・・・・・用が済んだんなら、さっさとこの術を解け)
(おや、何か気になることでも?)
(・・・・・・悪い予感というほどではないが、どうにも妙な感覚が、先刻から消えない)
(あの魔気を気にしてるんなら、多分大したことはないと思いますよ。以前にも見たことがありますから。それに、これは君の感覚の妨げになるような術じゃないし、ここで見極める方が時間もたっぷり使えて便利じゃないですか? だって君は元々、)
(もう一度言わせるつもりか?)
(はいはいはい、怖いなーもう・・・・・・あ!)
カリムの一瞥に、守護者はひょいと肩を竦めてから、思い出したように声を上げる。
(肝心のことを聞き忘れるところでした!)
(まだ何かあんのかよ)
うんざりした声で、カリムは応じる。
が、それにめげる相手ではない。
(はい! 君の名前、まだ聞いてませんでしたよね?)
売り言葉に買い言葉的成り行きで、瘴気を相手に奮闘するハメになったフェグダだが、勝算も無しにイキオイだけで見栄を張ったわけでは、勿論ない。
瘴気の凝った触手を避けるだけで精一杯、と見せかけて、次の一手を打つべく鋭意努力中。
名付けて! こんな瘴気なんざ呪術結界に取り込んで封じ固めてやるぜ作戦!
結界の頂点となるポイントの地面に剣先で呪印を刻み込むという下準備には少々手間がかかるのだが、術の効率と効果を考えれば、その程度のことは妥協すべきだろう。
もっとも、知能どころか本能だって有るかどうかという瘴気を相手に、気付かれないようコッソリ動く必要はハッキリ言って全く無い。それが必要な相手が居るとすれば、それはふんぞり返って傍観を決め込んでいるあのクソ生意気な少年に対してである。
(あの鼻持ちならない高ビー野郎! マヌケだの要領が悪いだの好き勝手言いやがって! 俺の華麗なるワザで一発逆転バッチリキメてあっと言わせてやるからな! 絶対! ついでに瘴気で泥団子作ってぶつけてやるっ!)
どちらかと言うと瘴気を封じた後の計画の方をより熱心に練り上げつつ、飛び込み前転の要領で瘴気の腕をかいくぐって顔を上げたフェグダは、その時はじめて、視界の端に捉えられるはずの少年の姿が消えていることに気がついた。
(な、なにーっ!?)
慌てて左右に目を走らせるも、あの目立つ姿はおろか、動くものの気配すら全く無い。
(あの野郎、どこ行きやがった!? 遺跡の中に逃げたのか?)
いや、たとえそうだったとしても、ノンキに詮索している場合では無い。
とっとと気持ちを切り替えて布石を完成させ、一刻も早く瘴気を封じてしまわねば。
だが、もしも上手くいかなかったら・・・・・・という考えが、ふっとフェグダの脳裏を過る。
(馬鹿か俺は! あんなヤツ、最初っからアテになんかしてなかっただろーが! それに、これがダメでも別の手がある!)
見ている限り、フェグダを取り囲む瘴気は遺跡方向に広がろうとはしていない。ということは、遺跡には結界になりうるような力が辛うじて生きている可能性が高い。いざとなれば、壁の破れ目に飛び込んで隠れれば、多少の時間稼ぎにはなるだろう。
(まあ、アレだ! あの野郎を瘴気の中に蹴り飛ばしてイヤガラセしてやれねーのが残念だがな・・・・・・っと、これであと一つ!)
最期のポイントに到達したフェグダは、瘴気を警戒しつつ、簡略型の魔道図形を可能な限りの速攻で刻み付ける。
(よっしゃ! これで準備おっけ!)
図形の完成と同時に、片膝立ちで身構えたフェグダは短刀を握ったままの左手で印を組み、結界を発動させるべく呪の詠唱を開始する。
それは、詳しい者が聞けば、古代帝国時代の名残を汲む魔道言語だと解るだろう、詩。古代魔術の系統では、そこそこ知られたものである。だが、その韻律を乗せる旋律は、風の唸り声を思わせるような、かなり独特な音だ。
大気に紡がれる不思議な韻律に反応して、地面に描かれた五つの簡略図形が、ぼうっと不可視の光を放ち始める。図形を浮かび上がらせた光は、すぐに火柱となって立ち上がり、隣り合った火柱同士が手を繋ぐように光の線を延ばして、複雑な文様を持つ五角形の魔法陣を形成する。
やがて魔法陣の中心に小さな渦が出現し、フェグダを包囲していた瘴気が、強風にさらわれる羽虫のように渦の中心方向へ引き寄せられ、渦の拡大とともに寄り集まりくっつき合う。その有様はまるで、見えない手で捏ね繰り回される粘土塊のよう。ハッキリ言って、かなり不気味。
(ま、まあいっか! そのまま全部捕まえろよーっ!)
順調に推移する術に、フェグダが安心しかけた、その時。
何の偶然か。光の網の中でもがいていた粘土塊の腕が、結界を構成する呪印の一角が描かれた地面を大きく薙ぎ払った。
瞬間、バシッと大きな火炎が舞って、呪印に触れた瘴気の腕にぽっかりと大穴が空く。
だが、半実体化するほど凝り固まった瘴気にピンポイント攻撃された呪印の方も、ただでは済まなかった。
(・・・・・・げ! 消えるな踏ん張れ!)
フェグダの期待虚しく、呪印から吹き上がっていた火柱がぐにゃりと歪んで掻き消える。図形の一角を欠いたことで、瘴気と呪文、内と外との力のせめぎ合いに耐え切れなくなった残り四角の火柱が、風に煽られたローソクの炎のように次々と虚しく吹き消される。
突然の結界の消滅に、一ケ所にぎゅうぎゅう詰めにされていた瘴気が、弾け飛ぶ羽虫となって、どばっとフェグダの眼前に広がる。
(!!!)
思わず、息を飲んだフェグダは。
その空白の分、次の行動に移るのが遅れる。
どしゃっ! がらがらがらっ!
「っ!?」
背後で何かをぶちまけたような不吉な音が、フェグダの空白を打ち砕いた。
「呪文!」
「な!?」
「グズグズすんな!」
有無を言わせぬ鋭い叱咤。と同時に銀色の尾を引いて、幾つもの礫が飛ぶ。
フェグダが呪文を再開するや、空中の礫の数個が反応して呪光を発し、瘴気全体を取り囲む五角形が構築される。
結界の形成を見て取ったフェグダは、呪文を次の段階へ移行させ、結界の強化と縮小を同時に行う。引き絞られる網の中で、瘴気は再び寄せ集めのアメーバ状へと変わり始める。ここまでは大体、先刻と同じなのだが。
(げ!)
フェグダの見ている前で、術の媒体として瘴気の周りに滞空していた礫の光が、急速に弱まり始める。
術式の為に描いた呪印と違い、礫自体に込められた魔力など、所詮は間に合わせでしかない。これではとても、結界の魔法に耐えられない。
(どうする!? もう保たねーぞコレ!)
その動揺を見透かしたように。
「うろたえんな! 呪文を続けろ!」
またしても叱責が飛び、それに呼応するようなタイミングで、地面からゆらりと呪炎が這い上がった。
先刻投じられたものの、空中では反応せずに地面に転がり散っていた礫が、術を引き継ぐように輝き出す。中空の光が完全に消え去るのと同時に、地面の布陣は完全に起動し、光の檻となって暴れる瘴気を囲い込む。
(やーれやれ。にしても、どんだけあンだよコレ・・・・・・)
フェグダは内心、げんなりと唸る。
これだけ圧し固めたというのに、瘴気の塊は未だ、巨象を呑み込めるほどの大きさがある。ここで結界が破られでもしたら、いくら羽根の防壁があると言っても、何らかのダメージは避けられないかも知れない。
(このまま結界を維持して、ギリギリまで動きを封じるとして・・・・・・泥団子にするにはもう一手間必要か?)
使える手段は無いかと、脳を高速回転させ始めた矢先。
「限界だな」
きっぱりと断じる声は、片膝をついて呪文を唱え続けているフェグダの、すぐ横の頭上から降ってきた。
咄嗟に振り仰ぐより早く、そいつはすいと横を通り過ぎてフェグダの前に割り込むと、そのままスタスタと瘴気に向かって歩を進める。
「・・・・・・!」
意表を突かれたフェグダは、不覚にも呆然と息を呑んだ。
だって、そうだろう。
そこに在るのは、頑丈な檻に入れられた見世物の珍獣などではない。いつまで保つか知れない不安定な魔術結界と、いつ結界を食い破って飛び出すか知れない半実体化したおぞましげな瘴気の塊だ。
そんなものに自分から近付こうなど、狂気の沙汰だ。
いや、そいつが普通でないだろうことは、大体察しがついている。
着飾って社交界のサロンで女の子を口説いているのが似合いそうな、ちょっと見栄えがする程度の長髪でか細い少年の姿でありながら、いくら隙を突かれたとは言え一瞬でフェグダを締め上げるような体術の持ち主であり、あまり認めたくはないが、その実力は計り知れない。
(だが、何でだ?)
フェグダが少しくらい手こずろうと、少年には全く関係無い話ではないか。
たとえ少年にとって、この瘴気がアリ程度の卑小な代物でしかなかったとしても、そんなことはわざわざ手を貸す理由にはならない。
(俺だったら、絶対にやらない・・・・・・)
これが、是非ともお近づきになりたいような美少女のピンチだとか、報酬を山と詰まれてならまだしも、今ここで少年が割って入るなど、フェグダの常識からは考えられないことだ。
それなのに、いかにも当然とばかりの落ち着き払った態度で、少年は歩調を全く緩めることなく、瘴気との距離を詰めていく。
(何考えてやがるんだ? 何の得があって、こんな・・・・・・)
ワケもなく混乱する。悪酔いのように眩暈を覚える。
なのに、信じがたいことに。心のどこかでは、納得してしまっている。理由も無く、安堵してしまっている。
そんな自分自身の認識のズレが、何だか無性に気持ち悪い。
少年は既に、結界に触れるほどの所まで進んでいる。
その眼前で。
何の前触れも無く、結界を構成する光壁が左右に開いた。
結界の一部が弾ける不気味な手ごたえに、フェグダの身に緊張が走る。
いや、それは大したトリックではない。少年が手にしている短刀の護符が、結界に干渉した結果だ。もちろん、意図的に。
(何やる気だ・・・・・・!?)
当然のことながら、光壁の綻びに向けて、瘴気の塊が雪崩をうって押し寄せる。
細い体躯があっと言う間に、瘴気の中に埋没する。
と、見えた瞬間、少年の姿がふわりと舞った。
大きく後ろに後退するのでも、高く飛び上がって逃れようとするのでもなく。
襲い来る瘴気の塊を踏み台にして、突出する触手スレスレの僅かに空いた空間を、何の躊躇いも無く、前へ。もっと前へと。
瘴気と接触した靴底からは、ジュッと灼けた煙が立ち昇る。
防御結界の類をまとっているのなら、普通、そんなことにはならない。
(まさか、生身のままで!?)
僅かでもその身に触れれば、皮膚などたちまち爛れ落ちてしまうほどの濃い瘴気の間隙をついて。
狙うは瘴気の塊の中心部分。
短刀の護法を発動させるには一番効率のいい、逆の言い方をすれば最奥にまで踏み込まねば到達することのできないポイントへ。
(そんな無謀な・・・・・・)
だが、フェグダがそう考えたのとほぼ同時に。
無謀なその一点目掛けて、渾身の一撃が叩き込まれる。
その瞬間、短刀から放たれた白光が、雷の速さで瘴気の内部から触手の隅々まで疾り抜け、完膚なまでに灼き尽くす。
おぞましげな闇色のアメーバは、のたうつ姿そのままに、完全に硬直した。
何もかもが静止したかに見えた時間を破って、フワリとトンボを切った少年は、邪魔だとばかり、奇怪なオブジェに軽く蹴りを入れる。大きさの比率を考えれば、大した衝撃になるとも見えなかったが。その一蹴りが合図となったのか、今まで瘴気の塊だった物体は、呆気なくボロボロと崩れ出し、その灰が地面に積もるより早く、思い出したように吹き抜けた風に散らされて消滅した。
ゆらゆらと立ち上っていた結界の名残の陽炎が力尽きたのは、その僅かに後のことだ。
後には、馬鹿みたいに晴れ渡った明るい風景の中で、やはりたった今瘴気を消し飛ばしたばかりとは思えないほど静かに佇む少年の姿があるだけだった。
片膝をついた姿勢で、詠唱の印を解かぬまま。フェグダはそいつの背中を睨みつけていた。
フェグダの意思に関係なく、一連の出来事が脳裏でリピートされる。
最初から最後まで、一挙手一投足の全てが焼きつくほど、優雅な動き。
それはつまり、瘴気に向けた少年の攻撃は、目で十分追える程度の速さでしかなかったということだ。
しかも、結界呪術と短刀による攻撃の組み合わせでもって。
それは単に、少年が手の内を明かさなかったというだけではない。
護法結界で身を守れるフェグダであれば、十分可能な攻撃方法を敢えて見せ付けたのだ。
「これくらい出来て当然だ」という高笑いが聞こえる気がする。
いや、方法がどうであれ、助かったのは事実なのだから、ここは感謝すべきなのだろうが・・・・・・・。どうにも素直に礼を言う気分ではない。むしろ酷くムシャクシャする。
(あの野郎にしてみりゃ、どーせ、ちょっとした余興のつもりなんだろーし。・・・・・・・・・・・・けど、このままスルーして、俺の了見が狭いって思われるのもシャクだし・・・・・・いや、でも・・・・・・)
ぐおおおと叫びたくなるような深刻な葛藤の末に、フェグダはありったけの自制心をかき集めると。
「お、おい! お前! その・・・・・・」
礼を言う、と続けるつもりが言葉に詰まる。
そんなフェグダの呼びかけに、少年は思い出したように、僅かに視線を動かすと。
「ああ、返すぞ」
「は!?」
次の瞬間、目の前の地面にぐっさりと短刀が突き刺さる。ぎょっと目を剥いて思わず飛び退きかけたフェグダは、そのまま派手にバランスを崩した。
思いの他、疲労が足にきていたらしい。
とっさに身体を支えようとした右手が、何の抵抗も無く地面に触れる。
「お、お前、いつの間に・・・・・・!」
見覚えがあるのも道理。
右手に握り締めていた短刀が無くなっていたことに、今の今まで全く気付かずにいたとは。不覚以外の何物でもない。
「ん? 待てよ?」
不意に、戦闘中に聞いたがしゃんという音が、不吉な予感と共に、フェグダの耳に蘇る。
「あ、あーっ! 俺の荷物! 俺の商売道具!」
改めて見回せば、銀色の礫と見えたものは、天使の紋章が彫り込まれたコイン型のペンダントで、それがどこから持ち出されたかは、もちろん言うまでもなくフェグダの荷袋の中からで。
戦闘中に脇にどけておいたはずのその荷袋はと言うと、派手にぶちまけられた中身の横に、しょんぼりと凹んで打ち捨てられていた。
第23話 つながり
(あーせーせーした。ったく、手間かけさせやがって)
感覚のノイズとなるものを綺麗さっぱり粉砕して、カリムは改めて眼下の村へと意識を向ける。
そうして一番に飛び込んで来たのは、遠く木立の向こう、村の外周に沿った小道を辿るアシェルとイリィの姿だった。
守護者の術中でも外の様子は問題無く感じ取れたし、二人が無事である事も判ってはいたが、やはり直に確認するとホッとする。
村の広場の辺りでは、祭りの準備に余念の無い村人たちが集まって賑やかに立ち動く気配がある。その内の誰かがこちらに向かって来るどころか、視線を向ける様子もない。ということは、遺跡付近での騒ぎに気付いた村人は一人としていないようだ。
(鈍いなんてものじゃない。この程度の瘴気の澱みなど、もう当たり前すぎて気にもならないか)
守護者の術に同調したせいでだろう。こと村の周囲に関しては、先刻までよりも鮮明に視えるようになった気がする。
人間が住む場所はどこでも大抵は、聖邪が入り混じって混沌としているものだが、ここの空気はそれにも増して、大きなボウルに清濁流し込んでかき回したような渦がそこここに視てとれる。
そこからはみ出した微かな魔気の澱みは、守護者も言った通り、今はまだバランスの範囲内ではある。だが、内包される力の密度がこうも高ければ、いずれ触発されるものも出始めるだろう。
何かが起こる。漠然とした不安にも似た、予感。
(だが、どうする?)
カリム自身がバランスする力の一角にされているのなら、不用意にアシェルやイリィのに合流するのは、あまり得策でないかも知れない。
それよりも今は、どこで何が起こっても対処できるよう注意を怠らぬこと、だろうか。
しかし仮に最悪の予感が的中するとしても、それは数分後のことなのか、数日先のことなのか。そもそもどの程度の介入が可能なのか・・・・・・。
(つくづく厄介だな・・・・・・)
カリムは内心ため息をつく。
と、その時。
「おい、お前! 無視すんなよな!」
大声で怒鳴ったのは、先刻から背後で商売道具がどうの要らん手助けがどうのと、ぶつくさ言い続けていた青年だ。
(意外に立ち直りが早いな)
もう少し放って置いて、弱らせておくべきだったか。
この青年の存在も、予定外な力の一角には違いない。
「ったく、どうしてくれるんだよ!」
ぶちまけられた荷物を見るなり、フェグダは立ち回りの疲労感もどこへやら。砂まみれになった所持品を荷袋に放り込み終えるなり、広範囲にばら撒かれたコイン型のペンダントを一つ一つ拾いにかかっていた。
「これだってな! 俺にとっちゃ、大事な売り物だったんだ!」
と、過去形で言わなければならないところが悲しい。
ほんの少し前まで天使のお守りだったそれらは、内包していたささやかな魔力を瞬時に強制放出するという想定外の使い方をされたせいで、どす黒く焼けただれたガラクタと化してしまっていた。
だが、売り物的にはガラクタでも、魔道に使われたものである以上、このまま放置する訳にはいかない。
あの切羽詰まった状況で、術の足しに使えそうなものを手っ取り早く調達した結果だというのは解るのだが、それにしてもだ。
「っとに、手ぇ貸すにしても、もう少しやりようってモンがあるだろーが・・・・・・」
ぶつぶつと不平を口にし続けるフェグダを、当の少年は横目で鬱陶しそうに見やる。
「誰が手を貸したって? ああ。お前がモタモタしてる間に、あの目障りなのを潰したことか」
「おい、どーゆーイミだそりゃ!」
いや、聞くまでもない。瘴気を消したのは単に自分の都合であって、フェグダを手助けをしたつもりは微塵もない、ということだ。
「じゃあ何か、俺の魔法は単なる便利アイテムかよ!?」
「邪魔だな。どっちかと言えば」
「・・・・・・・なっ!!!」
その瞬間、フェグダの目尻がキッと吊り上る。
利用したと言われる方がまだ許せるものを。
「何か言いたいことでもあるのか? 立ち去れという勧めを無視したのはお前だろうに」
とっさに反論の言葉も吐けないでいるフェグダに対して、少年の態度はにべもない。
それは「お前が瘴気を振り切ろうと、振り切れずに餌食になろうとどっちでもいい。双方とも自分の目の前からいなくなりさえすれば万事良し」という意味である。絶対、そうに違いない。
助けられた礼を言うべきかどうかというフェグダの葛藤は、完全に一人相撲だったというわけだ。
フェグダは両拳をきつく握り締め、ぶるぶると肩を震わせる。
「それに、結果的に助かったのなら何も問題無いと思うが」
「無いワケないだろ! 見ろ! お前のせいだぞこれは!」
言いながらフェグダは、片手に山盛りになった護符の成れの果てを、少年の眼前に突きつける。
「お代だよお代! お前が使った分、今すぐキッチリ払いやがれ!」
こんな低レベルな反論しか思いつかない自分自身も腹立たしいが、それでも蔑ろにされたと責めるようなプライドの無いマネだけは、絶対にしたくなかった。
もちろん、それをしおらしく聞く相手ではないと解ってはいたが。
「なら、そっちの水晶玉を投げつけていれば良かったか?」
「冗談じゃねー!」
フェグダはほとんど反射的に、ぶんぶんぶんと首を振る。
ぶちまけられた所持品の中でも一番に回収した手の平サイズの水晶玉は、当然のことながら、そんじょそこらの巷に転がっているシロモノではない。
フェグダが聖都を立った日に、幼馴染みのクミルから餞別として直々に手渡された通信珠だ。
オモチャのような護符とはケタ違いの魔力を保有しているだけに、魔法の媒体としては申し分ないが、それで壊れでもしたらどれほどの怒りを買うか知れたものではない。想像するだけで、背筋に冷たいものが滲む。
「一々煩いヤツだな。そもそもお前は人に文句を言える立場か? 風刃の一つも使えないくせに」
「まさか! 使えないワケねーだろ!」
風刃とは、塔に入った羽根使いが最初に習得する基本技の一つで、応用次第ではああいう不定形の相手に対する有効な手段にもなる。当然フェグダも、正式配属前にそれくらいはマスターしている。ただし、
「その、何だ・・・・・・ほんのちょっと条件がだな・・・・・・」
フェグダの強力な障壁は、羽根の力をごっそり必要とする。つまり、他の技を使うためには、障壁を解除しなければならない。同時使用は、限りなく不可能に近い。
「実戦で役に立たないなら、使えるとは言わないだろ」
事実であるだけに、その一言はかなり辛辣に聞こえる。
「るせっ! ・・・・・・俺にだって深ーい事情ってのがあるんだよっ!」
「ったく、コレだから上層部にコネのある奴は・・・・・・」
「なっ! あるワケねーだろ、そんなモン!」
そんな指摘を受けるとは思ってもみなかったフェグダは、つい過剰反応してしまい、直後に「しまった」という顔をする。
「な、何言ってやがる、そんなんで誰が誤魔化されるか!」
慌てて何とか取り繕い、こっそり少年の様子を伺うが、遠く眼下の村に目を向けたままの端正な横顔は、相変わらず何も語りはしない。
(分かり易っ! つか、図星かよ)
どんなニブいヤツが見たって一目瞭然な青年の狼狽えぶりに、カリムは内心やれやれと嘆息する。
いや、それらしいフシはあったのだ。
その気も無いのに降参したフリをしてスキを伺ってみたり、瘴気という明確な敵を前に迷わず逃走を試みたり、意地だけで独りよがりな戦い方をしてみたり。それらの行動は、軍団に属している者の行動原理とは相容れないものだ。
しかも青年の所属先とされている現地駐留部隊、第四軍と言えば、隊内の規律と結束力は実質上の主力部隊である第三軍と同等かそれ以だ。
隊の中では馴染めず一人浮いているタイプだが、それ以前に、第四軍の一員として行動したことがあるかどうかすら怪しい。
それに、これはカリムの主観に過ぎないことだが、もし自分が部隊長の立場だったら、羽根もろくに扱えない半人前を長期に放り出すという、色んな意味で危なっかしいマネが出来るだろうか?
たとえそれが青年と隊の為に最良であり、騎下全員の同意を得られたとしても。
いっそ、何らかの介入でもない限り・・・・・・。
それは事実を元に推論を重ねた結果辿り着いた答えというよりも、むしろ当てずっぽうに近いもので、ふと一言を漏らしたカリム自身、本当に当たるとは全く期待していなかったのだ。
(だが、それが事実となると、)
青年の知人か身内が塔の上層部に在籍しているというのなら、それはそれで新たな疑問が湧き上がる。
(コネで入るとしたら、普通は騎士団(第一軍)か貴族部隊(第二軍)だろ。どうしても単独任務に就きたいのなら何でも屋(第五軍)って選択肢も無くはない。なのに何故、よりにもよって第四軍なんだ? あそこは聖都が本拠地じゃないってだけで、任務のハードさで言うなら主力の第三軍と大差無いはずだが・・・・・・)
聖都の花形の第一軍、外交任務が主で直接戦闘の少ない第二軍は、天使本人にも望ましいが、塔の上層部に属する者にとっても何かとメリットがある。
通信や兵站など管理部門を担う第五軍も、実質的な利用価値は高い。
それに対して第三軍第四軍は、身体が資本の実働部隊だ。天軍としてメインの活動を担っているとはいえ、上層部からは労働階級としか見られていないのが実情だ。そういう上から目線な連中が、大事なコマになり得る身内を配属させるのに適しているとはとても言えない。
カリムが青年の身元について即座に言及しなかったのも、それがネックになったからだ。
(だがそうなると、一軍二軍に入れられなくて仕方なく、なんて理由はあり得ない)
それは青年の所持する宝珠を見ただけでも解る。
一見普通の通信珠っぽく装ってはいるが、そこに内包される魔力のケタが違い過ぎる。それくらいのパワーがあれば、使い方次第で転移門のシステムと独立して通信を繋げることも可能だろうし、相当大きな魔法の媒体にも転用可能だろう。
今のうちに壊しておこうかという思い付きを実行に移さなかったのは、下手に触ることで厄介な魔法を発動しかねないという危惧があったからだ。
(あんなものを仕込める立場となると、お飾りの名誉職なんかで満足するような手合いでは無いな・・・・・・)
宝珠にしてもだが、青年が古代帝国版図のみならず中原の呪術にも精通しているのなら、その人物もまた、魔道技術に精通していると見るのが自然だろう。
加えて軍団長に指示が可能で、通信その他諸々の面で第五軍にかなりの融通を利かせられる人物。
もしかすると、羽根使いを地位固めに利用する必要がなく、むしろ天軍から遠ざけて置きたいと思うような・・・・・・まやかしではない天使の実情を冷静に把握している人物・・・・・・。
(治世の輪、探求の徒、それに真理の番人・・・・・・)
塔の技術部門の中でも先進的な魔道体系に属する主要な派閥を連ねたところで、カリムは内心苦笑する。
(まあ、そんなのはどうでもいいことか)
青年の身内が何者であろうと、カリムにはもう関係のない話だ。
『どうしてそんな簡単に何もかも放り出せるんだよ! 名誉も地位も力も、人がうらやむ物は全て与えられておきながら!』
それは先刻、激昂した青年がカリムにぶつけた、偽ることのない本音。
この青年にしてみれば、彼が置かれた現状は、どこにも属さず誰からも認められていないように思えるのだろう。おそらく、彼自身が配属の理由を知らされていないせいで。
そんなヤツから見れば、上級天使は塔のみならず世界の誰もに認められる存在であり、青年が望むものを全て手にしている存在なのだろう。それをあっさり捨て去る者に、無意味であると知りつつも、怒りをぶつけずにはいられないほどに。
(一体何の皮肉だろうな・・・・・・)
カリムは青年の抱える事情など何も知らない。
それでも羽根使いでありながら、戦場に狩り出されることもなく、天使という身分を持って自由に旅をしていられること。それは上級天使のみならず、一般の羽根使いにさえ、願う事すら許されぬ夢。塔に入城した瞬間に、手放さざるを得なかったもの。
カリム自身、その立場を羨ましくないと言ってしまえば、それは嘘になるだろう。
だが青年にそう言ってみたところで、納得することはないだろうが。
『かと言って、みすみす彼にかっさらわれるのもシャクに障りますけどね』
ふと、守護者が漏らした言葉がカリムの脳裏を過る。
大した意味は無かったのかも知れない。単にカリムの注意を引くために言ったとも考えられる。
だが、額面通りに受け取るなら、それはカリムの脅威になり得る者の存在を示唆する言葉に他ならない。
(だからって、それがコイツってことは無いな。絶対)
単純に術者としての能力を言うなら、青年がカリムを圧倒すること自体は可能だろう。
半人前だろうが何だろうが青年が最強の法具と呼ばれる羽根の所有者であることには違いなく、しかも系統の異なる魔法を組み合わせて独自の術とするだけの術者であることも事実だ。
それでも。この青年が脅威であるとは、どうしても思えない。
その時。
草の中で、何かが鈍い光を弾いた。
それはカリムが、青年の袋の中から掴み出してバラ撒いた護符の一つ。呪術結界の発動範囲よりも少し外れて転がったせいで、ガラクタ化を免れた銀色の護符。
「・・・・・・!」
何気なく拾い上げたカリムは、そこに刻まれた簡略な紋章にハッとする。
広げた翼の中央に、空を駆ける矢羽根。
「蒼空の・・・・・・?」
それは、今はもう存在しない天使の紋章だった。
「ありがとう、アシェル。こんな所までわざわざ送って来てくれて」
村のかなり外れの方。小道の先に、申し訳程度の石積みの塀に囲まれた、小屋と呼んでもいいような小さな家が見える。
そこで立ち止まったイリィは、気配を察して振り返ったアシェルに向けて、静かに穏やかに笑ってみせた。
「それと、ごめんなさい。本当は、家にお招きしなきゃだけど、お母さんを驚かしちゃったら困るから。あの、アシェルが特別だからじゃなくて、初めての人はみんなそうだから・・・・・・」
「うん。ボクのことは構わなくていいよ。イリィってば、気を遣いすぎなんだから・・・」
「あと、これを、」
続けて何か言おうとしたアシェルを制して、両手で頭上を探ったイリィは、飾られていた髪留めを外し、髪を結い上げるのに使っていた小さな紐全てを取り去った。
ウェーブの余韻を残して、銀色の髪がさらりと流れる。
「返しますね。大事なものなのに、貸しててくれてありがとう」
イリィは、外したばかりの髪留めを大切そうに両手に載せて、アシェルの前に差し出した。
「あの・・・・・・今までとても楽しかったです。夢みたいに。だから、カリムさんにもありがとうって、伝えておいてもらえますか」
イリィは明るく笑っている。
その、どこか一生懸命な笑顔を、アシェルはじっと見つめる。
イリィの手の中で、広げた翼を模した台座に嵌め込まれた宝玉が、赤い光を弾いて光る。
「・・・・・・それでいいの? イリィ」
黙ってその様子を見守っていたアシェルは、イリィの顔を真っ直ぐに見ながら、静かに問う。
アシェルには、解った。
イリィは、別れを告げているのだと。アシェルとカリムが、イリィの知らない間に立ち去ってしまう前に。自分の方から。
(さっきから静かだと思ったら、そんなこと考えてたんだ。それ、ボクに返したら、さっさと走って行っちゃうつもりなんだね)
遠慮なく見つめるアシェルに、イリィは紫色の瞳を伏せる。
「・・・・・・カリムさんに、言われました。村を一歩出れば、色んな街や国があるんだって。そこには私と同じような人も、もっと変わった姿の人でも、珍しがられないでいるんだって。あの変な力を認めて、外に出さえすれば、それは叶うことだって。・・・・・・その時私は、そんなの全然望まないって怒鳴って逃げ出しちゃって・・・・・・カリムさんは、私に良かれと思って言ってくれたんだから、あんな風に怒鳴ることなかったって、後で反省して・・・・・・いえ、少し、違うかも知れません。だって、あの時、あれ以上聞いていたら、私、つい言っちゃったかも知れません。私を、外の世界へ連れて行ってくれませんかって。そう言いたい気持ちが、確かに私の中にあるんだって、分かっちゃったから。色んな所へ行って、色んな物を見て、思うままに歌って・・・・・・もちろん楽しいことばかりじゃないでしょうけど、それでも・・・・・・って」
小さく、イリィは笑う。楽しげな夢の話を語り終えた直後の顔で。
「私は、生んでくれた人にすら、要らないと言われた子供です。そんな私を大切だと言ってくれたのは、この世界でたった一人だけ。そのたった一人の母さんを置いて、裏切って。私一人だけがどこかに行って楽しく暮らせたとして、でもそれって、本当に幸せなことなのかなって考えたら・・・・・・。ダメですよね。やっぱりそれは、望んではいけないことなんです。私は、私のことを大切に想ってくれる人のために、ここにいるべきだと思うんです。もしもそれで、この先ずっと歌うことを諦めなければならなくても。いつか本当に一人ぼっちになってしまうとしても、やっぱり、私はそうするべきだと思うんです」
「・・・・・・そう」
『やりたいと望むことを我慢して圧し込め続けていれば、いずれ、何かが壊れる。今度こそ、最も不幸な形で』
(ねえ、カリム。キミはこれまで、大勢の人間と魔物を見てきたから。悲しいことだっていっぱい見てきたはずだから、そんな風に言いたくなるんだよね。でも、それじゃあ、大切な人のためなら何だって出来る、好きなことを諦めて構わないって覚悟を、キミは間違いだと言ってしまうの? ボクが決心したことも? ううん、それよりもキミ自身の生き方を、キミは否定してしまうつもりなの? 見ててよ。イリィをそんな結末には、ボクがさせないから! だから・・・・・・)
「イリィ」
アシェルは自分の小さな両手で、髪留めを載せたままのイリィの両手を、外側から包み込むようにしっかりと握りしめた。
「返してくれてありがとう」
いつもの能天気なまでに明るい顔で、ニコーッと笑ってイリィを見上げる。
「で、改めて。これはイリィが持ってて!」
「だ、ダメよ、そんなの!」
「ねえ、聞いて!」
驚き困惑して声を尖らせるイリィを、アシェルは持ち前の強引さで制すると、一転、小さな子供を諭す優しい顔になる。
「あのねイリィ、このままサヨナラしちゃっても、もう二度と会えなかったとしても、近くにいて力になってあげられなくても、それでもボクはイリィの味方でいるから。それだけは忘れないで欲しいから。その印に持っててよ。ホントにただ持ってるだけでいいから、ね!」
「でも・・・・・・」
「どうしても困るって言うなら、それはボクじゃなくて、カリムに返してあげて。明日でも、何日後でも、何年後でも、何十年後でもいいからさ!」
「だって・・・・・・」
「ボクがそうして欲しいんだ。ね、お願い!」
真剣なアシェルに、イリィは心底困った顔をする。
「ねえ、どうして? 私、色々してもらうばっかりで、アシェルに何もしてないのに・・・・・・」
「そんなことないよ。イリィは会ったばっかのボクたちのために、一生懸命になってくれたじゃない。アシェルのためにそんなにしてくれた人なんて、他にいないよ。それじゃダメ?」
「・・・・・・」
「ボクの気持ち、イリィなら解ってくれるよね?」
「・・・・・・でも、私なんかじゃなくっても、アシェルにはカリムさんがいるし、」
「うん。もちろんカリムはボクの一番だよ。だからって、他はどうでもいい、なんてことにはならないでしょ? イリィにはお母さんが一番。でも、心のトモダチがいたって、それは全然悪いことじゃないんだよ!」
「だって、そんな風に言われたら、期待しちゃうじゃないですか・・・・・・せっかく、諦めようって決めたのに、私・・・・・・」
「うん。いいじゃない」
「いいの? 本当に?」
「うん、本当に!」
「じゃあ、もう少しだけ。次に会う時まで」
「ありがとう!」
途端にアシェルはパッと明るい笑顔になる。
「じゃ、早く行ってあげて。お母さんが待ってるよ。それまでここで見ててあげるから」
イリィは小さく微笑んで、コクリと頷く。
「元気でイリィ!」
「ええ。アシェルも」
その言葉と同時に。名残を振り切ってパッと駆け出したイリィは、途中一度だけ振り返ってアシェルに手を振ってから、「ただいま」の声とともに小さな家の中へと駆け込んで行った。
イリィの姿が家の中に消え、バタンとドアが閉じる音が聞こえるまで、その場で手を振り続けていたアシェルは。
「さて、と?」
人差し指を頬に当てながら、可愛らしく小首を傾げる。
「もしかして、ボクってヤなヤツ、かな?」
あまりにも堂々と、いい加減なことを言った。
アシェルにしろカリムにしろ、何十年後どころか明日さえ、確かにこの世界に存在していると断言出来はしないのに。
「でもイリィのためにも、これでいいんだよね。ああでも言わないと、髪留めを持っててくれそうにないし、あげるなんて言ったらそれこそ完全拒否されそうだったし。それに、ボクが存在する限り味方でいるってのは、少なくとも嘘じゃないし・・・・・・」
一つ大きく頷いてからアシェルは、イリィの入って行った小さな家をまじまじと見る。
「うーん、どーしよっかなー?」
『言っておくが、変な天使の相手をするよりむしろ、あの娘の傍に居る方が危険かも知れないんだぞ』
『大丈夫、判ってます!』
『村には、』
『絶対近付きません!』
『くれぐれも、』
『気をつけます!』
『何か、』
『あったら即、キミを呼びつけます! 遠慮なく!』
とは、少し前に遺跡の屋根の上でカリムと交わした会話だったが。
「でも、このまま戻ったんじゃあ、何も解らずじまいなんだよねー。それに、イリィのお母さんがどんな人なのかも興味あるし・・・・・・」
都合のいいことに、村の周囲に巡らされた結界のトラップは、あの変な天使の青年が引き受けてくれている。
「まあ、魔物の結界なんて、このボクにとっちゃ全然大したコトないんだけど、ね・・・・・・」
アシェルの緑色の目が、一瞬、キラリと輝いた。
第24話 遠い面影
「これは・・・・・・」
拾い上げた護符を見つめながら、カリムは知らず、小さく呻いていた。
「ああ?」
その様子に気づいた青年は、すかさず大股で歩み寄る。
「何だ? 護符の成れの果てがどーしたよ・・・って無傷じゃねーか! やたっ! てか、俺ンだぞ! とっとと返せ!」
カリムは、騒がしく突きつけられた手の平の上に、素朴な護符のペンダントを落とし込みながら。
「何故こんなものを? その印の持ち主はもう存在しないのに」
自分では平静なつもりだったが、発した声は思いのほか硬かった。
「ンだよ何か文句あんのか!?」
反射的に喧嘩腰で言い返した青年は、カリムがそれ以上言い返さないと見るや、コホンと一つ咳払いして、改めて受け取った護符に目を落とした。
「あー蒼空の天使の印な。知らねーの? 去年の新作歌劇にも出てんだぜ? 魔物の軍団を相手にたった一人で奮戦して、町ごと大勢の人間を救ったはいいが、当の天使様は深く傷ついて天の国に羽根を休めに帰られました(空に向かって大仰なお祈りポーズ)ってヤツ。実際はともかく、おかげで護符の売上も上々ってワケだ。どーだ、納得したかよ」
いささか得意げに、青年は知識を披露する。
「実際はともかく?」
「そりゃまー俺だって、蒼空の天使がホントは殉職しちまってるってコトくらい知ってるさ。けど、それが何だってんだよ? 魔物の大群が誇張だったとしてもだぞ、宣伝劇ってなそーゆーモンだろ? 景気良く盛り上がる演目ならそれで観客は喜ぶし、当の天使様にしたって盛大に褒め称えられた方が浮かばれるんじゃねーの? それで輝かしくも華々しい過去の経歴が変わるワケじゃなし」
その方が商売繁盛で万々歳と続けたあたりで青年は、黙り込んでいるカリムの様子に「あ」と小さく声を上げる。
「いや、ほら、上級天使様方ってのはさ、俺みたいなヒラやフツーの人間にしてみりゃ、どっかの王様並に手の届かない存在だからさ・・・・・・その、茶化そうとかそういう気は全然なくってだな、あー、えーと・・・・・・」
そんな青年の言い訳を、カリムは半ば上の空で聞いた。
(どういうことだ?)
あれは二年近く前のこと。
蒼空の天使は塔を裏切り、カリムは天使狩りとともに追跡を命じられ、その任を果たした。
それは確かな事実であり、カリムに命じた上層部連中も他の上級天使らも、そのように認識しているはずだ。
だが、それがどのように公式発表されたかなど知ったことでは無かったし、どうでもいいことだったのだが。
新聞などのメディアが広く普及し始めた昨今でも、白亜の塔の武勇伝や天使の去就について一般人に知らされるのは、伝統的に歌劇の演目に依るところが大きい。そして当然、天使を題材にした演目を上演するには、塔の許可証が必要だ。
新たに就任した上級天使が新作劇で華々しく語られる一方で、除籍された天使を題材にした演目は上演リストから削除され、時とともに忘れ去られていくのがこれまでの常だった。
それなのにわざわざ、除籍になった天使が出てくる新作を発表する理由とは何なのか?
簡単なことだ。
上級天使が逃亡し追討されたなどという事件は、イメージ重視の塔にしてみれば、スキャンダルもいいところだ。そんな事実を承認したくはないし、可能であれば隠蔽してしまいたい。美談として脚色できるならそれに越したことは無い、というところだろう。
いかにもありそうなことだし、カリムが引っ掛かったのもそこではない。
『上級天使が脱走なんて前代未聞だ! それはこの上ない裏切り行為じゃないか!』
出会って早々カリムの挑発を受けた青年は、あの時確かに、そう怒鳴った。
つまり青年は本当に、蒼空の天使の経緯を知らない。
そして青年が所持している身分証の”五年前に第四軍配属”という記載が確かであるなら、”蒼空が逃亡天使である”事実を噂としてすら知らないのは、どういう訳なのか?
逆に言えば、”災厄の天使が逃亡したという噂”を、たった三日やそこらでどうやって知り得たのか?
(・・・・・・ま、俺の場合は城内で派手に暴れてるし、騎士団の連中って目撃者もいるわけだし、事件自体はは隠しようがないとして・・・・・・それでも外部に対しては、可能な限り緘口令が敷かれたはずだ。聖都外の部隊や転移門の門番に通達を出しすにしても、詳細まで説明されたかは怪しいものだ。噂、か・・・・・・)
青年が”噂”を聞いたのなら、それは通信珠を通してである可能性が高いが、その相手が誰であれ、内輪の噂話として話題にするにはあまりに危険過ぎるネタではないだろうか。
天軍に限らず、情報漏洩に対する軍規は厳しいのが普通だ。たとえ公然の秘密のようなものであっても、口にしたこと自体を処罰対象とされた実例はいくらでもある。
日常的に重要情報に接する通信班の連中の徹底ぶりは呆れるほどで、彼らの融通の利かなさときたら、平時ならまだしも緊急時には何度ブチ切れそうになったことか。
(だとしたら、こいつの情報源は何者だ? それとも、意図的に流された情報ってことは・・・・・・?)
その”噂”を聞いた時、青年がたまたまこの近くにいたことは、偶然だったかも知れない。
だが、その裏に作為的なものが一切無いと、断言してしまえるだろうか。
青年自身が与り知らぬところで、糸を引く者が存在してはいないだろうか。
だとしたら、それは。
その可能性がある者は・・・・・・。
ピシッ!
「!?」
不意に空を疾った、小さな石が爆ぜるような衝撃に、カリムの思考はそこで中断された。
アシェルと別れたイリィは、ドアの前で立ち止まって、一度大きく息を吐く。
(考えない! 考えない! 考えない!)
色んなことがあり過ぎて、頭の中がぐるぐるで。
アシェルに向かって「これからもお母さんと一緒にこの村でがんばります」宣言をしたはいいものの、両足は地面の上を漂っているようで、心の整理も何も出来ていなくて。
だから、まだ考えない。
今すぐこの手でトアを開けて家に飛び込んで、お母さんの顔を見てただいまを言って、用事を置いたままで遊びに行ったことを謝って、大急ぎで用事を済ませて夕食を作って、そうだ、明日のお祭りの準備もちょっとだけして、夜になったらお母さんにお休みを言って隣り合ったベッドに入って。明日、お母さんと二人だけで過ごすお祭りが終わったら、またいつもと変わらない日を何度も何度も繰り返す。
その頃には多分、この気持ちも落ち着いているはずだから。それからゆっくり考えればいい。きっと、それが正解。
さあ、歌を歌い始める瞬間のように、思いっきり大きく息を吸って、でもそれは歌うためじゃなくて。
家に入る魔法の言葉。普通の日に戻るための合図の言葉を、明るく微笑みながら唱えるために。
「ただいま、お母さん!」
少しぐらつき気味のドアを、注意しながらもパタンと大きく開け放って。満面に笑みをたたえたイリィは、そこにいるべき人に呼び掛けた。けれど。
ドアを開けてすぐの台所兼居間に、あるはずの姿は見えなかった。
「お母さん?」
イリィはさして広くない室内を見回しながら、一歩、二歩と踏み入れる。
「ねえ、お母さん、どこ?」
胸の中が黒いもやもやでいっぱいになる。鼓動が早鐘を打って全身に響き渡る。
一体どうしたんだろう。
お母さんが家にいないはずがないなのに。
病弱なお母さんは、最近では外に出たとしても、家の周囲を歩くらいだ。それなのに、何も言わないでどこかに行ってしまうはずがない。
それとも、気分が悪くなって寝込んでいたりするのだろうか?
煩いくらいにドキドキする胸の前で両手を組みながら、奥にある寝室を覗こうとテーブルを回り込んだイリィは。
「!!!」
目の前の床に倒れ伏しているお母さんの姿に、悲鳴を上げることすら出来ずに立ち竦んだ。
一方、アシェルは。
「ホント、イリィちゃんってばカワイイなー」
と、イリィの入って行ったつつましやかな家を眺めつつ、ピョコンと首を傾げていた。
その家は村の一番外れも外れ、村の境界に沿って張られた結界の辛うじて内側というところにある。
「あの子はさ、こう、守ってあげたくなるタイプだよね」
アシェルはその結界のすぐ外側から、そーっと人差し指を伸ばしてみる。
なるほど、災難除けの結界自体は普通の村ならよくあるレベルのものだ。これが弱すぎたり、逆に強力過ぎたりする村は何かしら問題アリな場合が多いそうだから、この村は至って普通ということになる。
問題は、その至って普通な結界に重なって、微弱ではあるが魔気を帯びた結界が存在することだ。
「実はイリィちゃんの隠れファンとか、けっこーいるんじゃないかなー。で、中には独り占めしたくなっちゃうヤツがいてもおかしくないよねー。それがおっとビックリ魔物だったり? だけどイリィちゃんは羽根と関係ありそうだから、退治されやしないかとビビッて近寄れなくて、でも他のヤツがイリィちゃんと仲良くするのは許せないからとりあえず結界で見張ってイヤガラセしちゃおう、てコトなのかなあ。だったら話はカンタンなんだけどなー」
天使とくれば魔物。
カリムはそれを敵対者という意味で捉えたのだろうが、恋愛トラブルだって負けず劣らず深刻だとアシェルは思う。特に想いが一方的だった場合は。
「それにしても器用だなー。結界を維持するのにギリギリピッタリな魔力で、魔除けの結界を邪魔しないようすっぽり被せているなんて。何て言うのかな、繊細なレース編みでカバーを作っちゃったみたいなもん? 器用通り越して職人芸だよ」
フウと感心したように息を吐いて、アシェルは伸ばしていた指先を引っ込める。
「だけど、何でこんなのが要るワケ? これ、攻撃の性質なんか無いし、他に高度な術が仕込んであるようには全っ然見えないし、まさか単にお邪魔虫探知機なだけってコトは無い、よね? それじゃ労力の割に実が無さ過ぎだし」
むう、とアシェルは眉根を寄せる。
気に入らない。どこがどうというわけではないが、何となく気に入らない。
「そりゃーね、魔物って言っても色々いるからなー。白亜の塔も白亜の塔だよ。十羽ひとからげで一緒くたにしちゃってさ! あいつらにはその方が都合がいいんだろーけど、ホント失礼な話だよねっ!」
例えば、塔に寄せられる魔物絡みの要請の中で、正真正銘魔物の仕業と確認されるものはどれくらいあるかというと、多分、一割にも満たないだろう。
魔物や魔族や魔獣といった生粋の魔性が滅多に存在しないから、というわけではない。
やむにやまれぬ事情でもない限り、彼らは好き好んで人間とトラブルを起こしたいとは思わないだけのことだ。
それはそうだろう。在り方こそ普通の生き物とは異なっているものの、魔物がこの世界に存在するものである以上、種族として存続し続けることが至上命題であることは少しも変わらない。要するに、彼らも生活がかかっているわけだ。
もちろん中には後先考えずに魔力を駆使して暴れるような例外もいるが、トラブルが常態化しているようなところでは退魔ギルドの目が光っている。
退魔ギルドの連中は塔と違って直接報酬制だから、チャンスがあればソッコー団体で営業に駆けつける。そうなると、基本無報酬ではあっても腰の重い塔の出る幕はない。
では他はというと、その八割方は魔物呼ばわりされただけの人間が原因であるケースだ。
行動に問題があるとか、身体的特徴や病気、タチの悪い魔道師、果ては政治的要因など。魔物というレッテルを貼られる要素は様々だ。
そして、そのようなトラブルの解決方法は、退治云々よりも、いかに周囲との折り合いを付けて調停に持ち込むかだったりする。
何にせよ、人間に害をなすものが圧倒的に人間であるというのは、非常に頷ける話ではないだろうか。
「そーすると犯人候補は・・・・・・どっかから手に入れた魔術アイテムの発動にウッカリ成功しちゃった村人とか? ほら、普段は大人しくて虫も殺さないカオしときながら、実はコンプレックス持ちで粘着質で、けどホントの自分はそんなじゃないぞーってプライドだけは変に高いハタ迷惑なヤツとか、いかにもそーゆーコトに興味持ちそーじゃない? ・・・・・・あ、でもそれだったら村人に限らないっか。結界張った本人が結界内にいるとは限らないわけだしさ。村に立ち寄っただけの旅人とか、街行った時に目を付けられてストーカーされちゃったとか、それから・・・・・・って、キリ無いし。そもそも犯人探しの役に立ってないし」
考えながら、アシェルは急にシュンとする。
「カリムだったら、ボクよりもっと色々読み取れるのかな。この程度の役にも立てないなんて、ボクって何でこう中途半端なんだろ・・・・・・って、ンなこと言ってる場合じゃないんだってば! こらアシェル、この程度で弱気になってどうすんの! いつまでもそんなんだったら、”力”を手に入れた意味が無いじゃない! そうだよ魔物のことは、ボクの方が詳しいんだからね絶対に!」
アシェルは両手握り拳で気合を入れて、心の中から弱気を追い払うと。
「そうだね。結界の術式を探ってみたら、もうちょっと何か判るかも! それにさ、少なくとも殺戮の魔物が関係なさそうなのはラッキーだよね。あれはまどろっこしいこと一切ナシで、実力行使一辺倒。こんな小さな村、一瞬で阿鼻叫喚だもんね」」
殺戮の魔物。それが最後の一割だ。
自らを省みず平気で姿を晒し、何も怖れず考えず殺戮本能を満たすためだけに存在するような、最も凶悪な魔物ども。
殺戮という明確な意図をもって、この世界に放たれたもの。
彼らに与えられた魔力の核は、非物質の世界に属する。故に、この世に強力な魔法具は数多あれど、核の深度にまで正確に到達し破壊出来る武器は、羽根使いの操る羽根のみと言われている。
彼らがどのようにして生みだされるのかを知らない天使はいない。だが、何のために生み出されるのかが語られることは、塔においてもほとんど無い。
「さあ、教えて」
アシェルは深く息を整えながら、今度は指先一本ではなく手の平全体を結界に近づけてみる。触れるか触れないかの、ギリギリのところまで。
「キミは誰? どこにいるの? 何がしたくてこれを作ったの?」
『・・・・・・魔物とは何か、あなたは知っていますか?』
いくら細身であるとはいえ、気を失ってぐったりした人間を運ぶのは、そう簡単なことではない。
倒れていたお母さんの身体を背中から抱きしめるようにして、手足をぶつけたりしないよう気を付けながらようやくのことでベッドに運び上げて横たわらせると、イリィは掛布の端から覗くカサカサと痩せた手を両手でギュッと握りしめた。
「ねえお母さん、どうしちゃったの? 何があったの?」
けれどそこには血の気の引いた青白い顔と、固く閉ざされた瞼があるばかり。
熱もなく、息を荒げることもなく。
イリィが慌てて駆け寄った時も、足を床に引きずりながら運んでいる間も、お母さんはうめき声を上げるどころか、眉をしかめることすらせず、まるで妖精に眠りの粉を振りかけられたかのように、ただ昏々と眠り続けている。
こんなことは初めてだ。
(ど、どうしよう? どうしたら・・・・・・)
このまま見守っていていいのだろうか。
誰かに助けを求めるべきだろうか。
(でも、誰に?)
イリィが助けを求めたとして、誰か来てくれるだろうか?
来てくれたとしても、お母さんのこの姿を見て、様子がおかしいと判ってもらえるだろうか?
『イリィ、お願いだよ。どこにも行かないで、お前のお母さんを一人にしないでちょうだいね。お母さんは、お前さえいてくれればそれで幸せなんだからね』
「・・・・・・これは私のせい? 私がこっそり、お母さんを悲しませるようなことをしてしまったから?」
けれど、応えは返らない。
そんなことないよと言ってくれる声は聞こえない。
イリィは握っていた手を片方放すと、ポケットの中のものをスカートの上から握りしめる。
アシェルから預かった、カリムさんの髪留め。
「・・・・・・待っててお母さん、すぐ戻るから!」
居てもたってもいられなくなったイリィは、お母さんの手を放して立ち上がると、出来るだけ静かに早足で寝室を飛び出し、それから遠慮なく入口のドアを大きく開け放って外へ駆け出した。
白亜の塔に連れて来られて。はじめて”私”は、これから魔物と戦うのだと聞かされた。
『魔物とは。我ら白亜の塔に属する者にとって真の敵たる魔物とは、人間が変じた魔性、ただそれのみを指す』
入城したての新人天使らの前で、天使長を名乗る初老の男は、大仰な身振りで謡うように語った。
『先にも教えた通り、魔物呼ばわりされる人間は往々にして存在する。だが、我らが敵はそのような易いものではない。唾棄すべき邪なる望みを叶えんがため、魔の盟主と契約を交わして身も心も売り渡し、自ら魔へと堕ちたる輩。そうして遂には殺戮の悪鬼と成り果てた、憎むべき人間の裏切り者。天使に与えられた羽根のみが、彼奴らの内の魔を滅し灰燼へと還し得る。銘記せよ。貴方ら羽根の使い手は崇高なる神の僕。尊き使命を託された、希望そのものなのだ』
それから男は滔々と並べたてた。
魔物がいかに悪逆非道であるのかを、それを滅する天使の華々しい活躍とともに、飽きもせず、延々と。
侮蔑。嫌悪。憎悪。高揚。陶酔。そんな感情を隠そうともせずに。
『魔物だって? どうして我々が、そんな卑しいものに煩わされねばならないんだ? あんなものは下級天使にでも相手をさせておけばいい。誇り高い我が隊では、そんな些事にかまける必要はない。神に選ばれたる高貴な血を持つ我々の使命は、この羽根の威光を以て、下賤なる者どもを導いてやることだ』
誇り高いとか、高貴とか、何とか。臆面もなく堂々と。
言っている本人は信じて疑わないが、これだけ空々しく響く単語も無いものだ。
隊長だか何だか知らないけれど、好きになれないタイプなのは間違いない。絶対に。
だけどこの人が嫌いだからと言って、この人の言うことが全て間違いだと決めつけていい理由にはならない。
けれど私が質問すれば「そんなことも判らないとは世間知らずだ」と言われてしまうだろう。
本当のことだ。
私にあるのは、誰かに聞くか読むかした知識だけ。
それは全て他人の考え、他人の体験。
私が直に見聞きし思ったことなんて、ただの一つもありはしない。
『魔物とは何か? 面白いことを聞くね』
よりにもよって白亜宮の中でそんな質問をされるとは、”彼”には予想外だったことだろう。
『そうでしょうか?』
私は挑みかかるように真っ直ぐに彼を見上げた。
幾度となく最前線で魔物と戦い生き残ってきたというその人の、大きな傷の疾る顔を。
本当は少し怖かった。それでも、知りたいと思う気持ちの方が強かった。
『どうしてそんなことに興味があるんだ?』
『何かおかしいですか?』
『少なくとも、俺のようなものにわざわざ問う理由くらいは、聞いてもかまわないかと思ってね』
『それは、だって、よく知りもしないものと戦うなんて出来ないからです』
『そう? 天使長殿から散々聞かされなかったか? 魔物の凶悪さや、魔物から人間を守る任務の尊さなんてのは。それだけでは、満足出来ない?』
『出来ないから、聞いているんです』
それは、彼の目にはどれだけ能天気なものに映ったことだろう。
『君の所の隊長殿には、もちろん聞いてみたんだろう?』
『そんなの気にする必要はないって、即答です』
ああ、と彼は頷いた。
『だろうね。俺だってそう言う。馬鹿なことを考えるヒマがあったらもっとしっかり鍛錬しろ、とね』
『どうしてですか!?』
けれど彼は隊長のように、下らない質問だと馬鹿にしたわけではなかった。
『魔物は人間にとって最悪の殺戮者だよ、間違いなく。君が戦うためには、それ以上のどんな理由が必要なんだ?』
『それは・・・・・・正直、分かりません。でも、今の私には魔物を憎むことが出来ない。だって、魔物は人間がなるのでしょう? 願いと引き換えに、魔物になっても構わないと覚悟した人間が。じゃあ、その願いってどんなものなんですか? 悪いこと? 勝手なこと? でもその中には、どうしても誰かに会いたいとか、どうしても誰かを助けたいとか、そんな風に考えた人がいないって、本当に断言してしまえるんですか!?』
『出来ないよ』
『!』
『それは本人でなければ知りようのないことだ。他人が何か言えるとすれば、願いを叶える方法が間違っていたと断ずるくらいだろう』
『じゃあ、その人にはどうしようもないことだったら? 追い詰められて、それしか方法がなくて、魔物になること選ぶしかなかったのなら・・・・・・』
『だからこそだ』
『!?』
『自分の身を滅ぼすほどの望み。それがどんなものかは分からなくても、何の望みも持たない人間なんていやしない。たった一つの何かを望む気持ちが理解出来ないと、自信を持って言い切れる人間などいるだろうか。だからこそ、魔物の声に耳を貸してはならない。善悪に関わらずたった一つの純粋で強烈な想いに共感してしまったら・・・・・・それは魔物と戦う者にとって、死を意味するんだよ』
『・・・・・・』
『付け加えるなら、どんな事情があろうと彼らは決断したんだ。願いと引き換えになら、自分の手で他者を滅ぼすことも厭わない、と。相手に罪があろうと無かろうと、生まれたばかりの赤子であろうと、よく見知った隣人であろうと。憎しみもなく、喜びもなく、何百人何千人でも無差別に。君の隊長の答えは、そういう意味ではとても正しい。そう思わないか?』
『・・・・・・』
何か言い返したいと思った。
でも、言い返せる言葉が無かった。
他人の経験に便乗しているだけの私には。
『俺も一つ聞いていいだろうか?』
握り拳を震わせて俯く私に、彼は静かに問いかけた。
『もしかして君は、魔物にならない理由の方こそ知りたいんじゃないか?』
『え!?』
『何となくだが、誰かに怒っているように見えたから・・・・・・いや、詮索が過ぎたな。すまない』
(思えばあの頃から、変にスルドイとこあったよね)
出会って間もない頃の、真剣だけど、どこか遠慮がちな会話。
何故だろう。
一つの価値観に凝り固まった塔の中で。それに異を唱えれば馬鹿にされるか、運が悪ければ処罰対象にもなりかねないようなあの空気の中で。キミだけには素直に思ったことを吐き出せた・・・・・・。
だけどあの時間はもう、キミの内からは喪われてしまっているんだね。
でもね。ボクは取り戻したよ。
決して諦めることのできない想いに囚われ続ける魔物には、救いの忘却は必要ないんだから。
「アシェル!」
「わっ!!!」
バタンとドアが開け放たれた音、と同時にイリィの切羽詰まった声が響いて。
強制的に現実に引き戻されたアシェルは、思いっきりバランスを崩しながらも、何とか地面に落下することだけは免れた。が、
「あ・・・・・・」
伸ばした右手にぐにゃりとした抵抗感。
「どーしよ・・・・・・」
アシェルの右手の先は、例の結界を突き抜けた向こう側にあった。
第25話 慟哭の歌
「あ・・・あれ・・・・・・?」
図らずも結界に腕をずっぽり突っ込んでしまったアシェルは、馬二頭分ほど飛び退がってから、恐る恐る周りを見回してみる。
が、特に何かの術が発動した気配も無く、結界は何事も無かったように依然としてそこにそのまま存在する。
「えええーっ! ここで無視するー?」
アシェルはむうと唸りつつ、自分の右手に目を落とす。
「変なカンジだったなー。ぷにゅーんってしてて、なんかこー失敗して水入れ過ぎたパン生地みたいな・・・・・・?」
「アシェル!」
「わっ! イリィ!?」
思いの他至近距離からの呼びかけに、アシェルは文字通り飛び上がった。
そう言えば結界にばかり気を取られていて、そもそもどうして手を突っ込っこむ羽目になったのかを見事に失念してしまっていた。
「アシェル、どうしよう、私、どうしたら・・・」
家からアシェルの居るここまで一気に走って来ただろうイリィは、足を止めるより先に口を開いた。
当然だが、イリィが結界に気付いている様子は全く無い。
「え、えーと、どうしたの? そんなに慌てて。忘れ物?」
「違うんです! あの・・・・・・お母さんが大変なの! 帰ったら床に倒れて、呼んでも揺すっても全然目を開けてくれなくて、だから、だから・・・・・・」
「大っ変! 早く何とかしなくちゃ!」
まだ何か言おうとしているイリィを遮って、アシェルはすぐそこにある小さな家に目を向けた。
「とにかく、まず様子を見に行った方がいいよね! ボクで分かればいいんだけど・・・イリィ?」
「来て、くれるの?」
問われたことの意味が掴めず、アシェルはキョトンとした瞳をイリィに向ける。
「え? だって困ってるんでしょ? だからボクを呼びにダッシュで来たんじゃないの? あ! そっか、ボクがお母さんに見つかったら心配されちゃうんだっけ。だったら、他の誰かを呼びに行った方がいいかなあ? お医者様とか、近所のおばさんとか、ええと、イリィがいいと思うコトがあったら言ってよ。手伝うからさ!」
「あ・・・・・・」
イリィが家を飛び出した時、用意していたセリフはこう。
「やっぱり髪留めは返します。お母さんと一緒にいるって決めたくせに、これを持ってるのは、全然決心出来てないって証拠だから。お母さんがこんなことになったのも、きっと私のせいなんです・・・・・・」
だけど、本当に言いたかったのはきっと、たった一言だけ。
「助けて!」と。
「ヤだなあ、また泣いてるの? 大丈夫! ボクもカリムもついてるからさ! てか、こーゆー時にカリムが役に立つかは分かんないケド・・・・・・でもイリィにはジーロって小さなナイトも、ちょっとハズしてるっぽいけどジーロのお兄ちゃんもついてるんだし、きっと何とかなるよ! だから元気出そうよ、ね?」
「な、泣いてませんっ!」
両目を両手でゴシゴシしながら言い返すイリィに、アシェルはにかっと笑ってみせる。
「うん。じゃあ行こっ!」
「はい!」
もうすっかり当たり前のようにイリィの手を取ると、アシェルは先に立って家に向かい始めた。
だが、イリィに背中を見せた途端に、その顔から笑みが消える。
今度は意識して結界に手を伸ばしたアシェルは、ぐにゃりとした抵抗を無視してそのまま強引に通過する。
(敵対はしないけど、余計な手出しは無用ってコト? それってやっぱりそーゆーコトなのかな・・・・・・。けど、もしボクの考えが当たってるなら、それこそボクが何とかしなくちゃ!)
イリィがついてきやすいように小道を辿って飛んだアシェルは、右手方向にある入り口扉に回り込むため、小屋の側面を通り過ぎようとした、その時。
「! イリィ伏せてっ!」
「!?」
バンッ!
大きな破壊音とともに、閉ざされていた木窓が内側から弾け飛び、砕けた木片が真横からアシェルを急襲する。
「な、何!? ・・・・・・アシェル!?」
ほんの一歩の差で木片の洗礼を免れたイリィは、そのまま呆然と立ち竦む。
「・・・・・・だ、だいじょーぶ」
地面に突き立った窓枠部分のすぐ後ろ側で声がした。
割れて尖った木片の直撃だけは躱したものの、疾り抜けた力に煽られ地面に転がったアシェルは、クラクラする頭を振りながら上体を起こした。
アシェルの上に積もった細かい木片が、土埃とともにパラパラと落下する。
「それより、逃げてイリィ、早く!」
「え!?」
根性でガバッと跳ね起きたアシェルは、状況を把握出来ないでいるイリィを背にして身構える。
あるはずのない光景を、イリィは、呆然と見ていた。
小道沿いの壁に取り付けられた木窓には、イリィが小さい頃に背伸びして描いた拙い花模様が微かに消え残っていた。
その木窓が、どこにもなくなっている。
そればかりか、壁には細かいひびが無数に走り、木窓があったところを中心にして大きな暗い穴がぱっくりと口を開けている。
暗い、冥い、穴。
どんなに目を凝らしても、穴の中は全然見えない。
でも、そんなのは変だ。
窓を閉め切っているわけでもない家の中が、こんなに真っ暗なはずがない。
こんな澱んだような臭いなど、するはずがない。
だって、あの穴の先には寝室があって、お母さんが眠っているはずなのに・・・・・・!
喉元までせり上がってきたものが、悲鳴となって空気を振るわせようとした矢先。
塗りつぶしたような闇の奥で、二つの赤い火が灯り、ふらふらと左右に揺れながら持ち上がった。
火の周りに僅かに見て取れるのは、痩せ細った獣が身構えてでもいるかのような歪な輪郭。二つの火は、灼けるように燃え上がる二つの眼だ。
「おマエが・・・おマエが・・・」
「!?」
低くカサカサしたような唸り声の中に、言葉のような音が混じる。よく注意しなければ聞き取れないような、拙い発音と喋り口調の。けれど、それに混じって微かに聞こえる、これは・・・・・・。
手足を突っ張り背中を高く持ち上げた格好で、そいつはギッとアシェルを睨みつけた。
「おマエがタブラかしたのかっ」
「え、もしかしてボクに言ってる!?」
問い質す間もあらばこそ。そいつは何の予備動作も無く、穿たれた穴の奥から一気に外に飛び出した。
「!」
咄嗟にアシェルは、イリィを押し退がらせつつ、その場から大きく距離を取る。
思った通り、そいつは迷わずアシェルを追って鋭角に進路を変えながら突進して来た。
その動きはまるで、大きく振り回した操り糸の先にぶら下がる人形のようだ。
「おマエ、あのコをトりアげるつもりだなっ」
「ちょ、待ってよ、ねえ!?」
そいつの突進を、アシェルは宙空でひらりと身を翻して躱す。ギリギリのところを掠めたそいつは、首を捻って灼熱の眼でアシェルを睨みつけながら着地する。
暗い穴の中から白日の下へ。
だがそれでも、全身に暗色の靄をまとっているそいつの姿は、あまり判然とはしない。
辛うじて見て取れるのは、そいつが枯れ木のように細い手足を持ち、針金のような灰色の髪を逆立てていること。
手足を踏ん張った獣の格好をしていながら、体つきは人間のそれであることだ。
その姿の歪さには、人の形をしたものを無理やり獣役の代用として使ったような、苛立ちや痛々しさといったものを含んでいるように思える。
そしてもう一つ、何よりアシェルの眼を引いたのは、そいつの額に刻まれた、闇色に脈動する不吉の刻印。
同じ闇に属する者にしか視ることの出来ない、闇の天使の所有印。
「そうか・・・・・・あなたは・・・・・・!」
「おマエっ、ユルさないっ」
アシェルを遮って叫ぶと同時に、そいつは両肩を持ち上げるや、またも生き物の動きを無視した跳躍で敵と定めたもの目がけて肉迫する。
が、ほんの僅か横に滑空しただけで、アシェルはその攻撃をやり過ごす。
さらに二度、三度と。
「オノレっ!」
「ムダだよ」
憤りの唸りを上げる相手に対し、アシェルは冷静に応じる。
実際、相手に生き物的な動きを期待しなければ、ごく単調な攻撃だ。動きだけがいくら素早かろうと、回避するのは難しくない。
跳んだり跳ねたりという”動き方”を知らないものが、魔力だけで動こうとすれば、正にこういうものになる。
だが、そればかりではない。
「あなたは絶対にボクに勝てない。あなただって解ってるんでしょ。ボクに言われるまでもなく」
同じように魔物の力を持っていたとしても、アシェルは人間が変じる魔物とは違う。
魔物の力を手に入れる以前から、アシェルはもう人間ではなかったから。
炎の結晶を闇の色に染めた、黒翼の天使なのだから。
確かに、魔力と魔力の真っ向勝負となれば、本来の力の大半を削ぎ落とされている今のアシェルが有利であるとは言い切れない。
だが、魔物でしかないものが黒翼の天使に対して僅かでも逆心を抱こうものなら、それだけで精神崩壊を起こしかねないほどのプレッシャーと戦わねばならない。
灼熱色の眼窩から黒い血を滴らせながら、なおも立ち向かって来ようとするそいつが、過大なプレッシャーを受けていることは間違いない。
おそらく、このような肉体を使う攻撃は、そいつにとっても不本意だろう。が、どれほど必死になろうとも、アシェルに対して魔物の力を直接ぶつけるような攻撃を仕掛けることは最初から不可能なのだ。
それでも。
魔に属するものの本能に逆らってまで、自らの意志でアシェルを敵と見做すなら。何よりプレッシャーを受けながらも、逆らうこと自体は可能だというのなら、この相手の正体は・・・・・・。
「本当にっ、もう止めようよっ! これ以上やったって、あなたが辛いだけなんだから!」
「ウルサいっ! このイヤしきモノおっ! デてイけっ! ココからイなくなれっ!」
「あーもう! ちょっとは聞く耳持ってよねっ!」
「ダマれダマれダマれっ!」
(困ったな・・・・・・今のボクじゃ無傷で圧倒するのは無理っぽいし、かと言って、ここでモタモタしてたらカリムが来ちゃうかも知れないし・・・・・・やっぱダメだ! こんなトコ見られたら、それこそどうなるか。たく、仕方ないなー)
アシェルは一つ頷くと、次の攻撃を予測し身構える。
「イなくなれっ! おマエなんかイなくなれえっ!」
吠えるなり、細い身体が跳ね上がる。
「あんま手荒にはしたくないんだけどさ、ちょっとくらいはガマンしてよねっ!」
アシェルの腕が、瞬時に黒曜石の光沢をまとう。
「お、かあ、さん・・・・・・?」
その時、耳に届いた小さな声に、アシェルは思わずそちらの方へと注意を向けた。
いや、気付いたのは相手も同じだったろう。が、魔物の力のみに頼って肉体を動かしているそいつは、一度動き始めてしまえば、多少注意が逸れたたところで動作に全く影響しない。
ほんの僅かの差。それがアシェルに、間合いを誤らせた。
「!」
鞭のように振り回された腕の一撃を掴み損ねたアシェルは、とっさに甲冑化させた両腕を交差して攻撃を受け流し、そのままぶつかって来ようとする相手の身体を回避する。が、
「わ、まずっ!」
自由落下するそいつの視線は、イリィをしっかりと捉えている。
アシェルがトンボを切る間に地面に降り立ったそいつは、今度はイリィ目がけて地を縫うように走り出した。
両者の者に割り込もうと、体勢を立て直したアシェルが飛ぶ。
が、間に合わない。
「逃げてイリィ、早くっ!」
だが、イリィは立ち尽くしたまま、自分に向かって来るものを凝視し続けている。
「おかあさん、なの・・・・・・?」
目前に迫るものに、イリィはそっと呼びかける。
枯れ木が魔力を得て動き出したと言われた方が納得してしまいそうな姿でも。
見る者を焼き尽くすような灼熱色の眼をしていても。
イリィが知っている優しい姿とは、全く似ても似つかなくても。
それでも、強風に喘ぐ木立のようなその唸り声の奥の奥に、聞きなれた声音が確かに存在する。
毎日毎日、一日も欠かすことなく、おはようからおやすみまでの言葉を交わし続けてきた、決して間違えるはずのない、たった一人の人の、声。
獲物に襲い掛かる獣のように見えたそいつは、イリィに覆いかぶさるような格好でピタリと動きを止めた。
イリィの身を案じてだろう、全身を覆い尽くしていた瘴気が幾分薄らいで、痩せた老女の輪郭が浮かび上がる。
「・・・・・・お母さん?」
「アア、ワタシのタイセツなコ。もうダイジョウブだよ。もうコワくないよ。ワタシがちゃんとマモってアげるからアンシンおし」
「・・・・・・私は大丈夫だよ。誰にも何もされてないよ。それにアシェルは私の友達だから、心配しなくても平気・・・・・・」
「アアアアア、カワイソウに! すっかりタブラかされてしまったんだね。でもダイジョウブだよ。あんなケガラワしいモノなんかスグにホロボしてアげるからね。おマエはナニもシンパイしなくていいんだよ。だからちょっとマっておいでね」
「何を、言っているの? アシェルは怖くなんかないよ。お母さんのことも心配してくれて・・・」
「アアアア、あああアアァァァ!」
「お母さん?」
「おマエがっ!」
イリィを胸に抱いたまま、そいつは有り得ない角度にまで首を捻って、頭上のアシェルを睨みつけた。
「おマエのセイだっ。おマエのセイでっ! どうしてそっとしてオいてくれないっ! どうしてこのコをトりアげようとするっ!」
「だから違うって言ってるのにっ!」
「ダマれ、このケガラわしいクロいアクマっ! おマエなどっ。おマエなどおぉぉっ!」
「!」
「キャアアッ!」
そいつは細い片腕にイリィを軽々抱え上がるや、再びアシェルに向き直った。
魔物の力を振り絞っての膂力であるが、力任せに振り回されるとは予想だにしていなかったイリィの口から、驚きと苦痛の悲鳴が上がる。
「ダメっ! イリィが潰れちゃう!」
迂闊に手を出すことが出来ず、アシェルは一旦高度を取って間合いをはかる。
そして。
「違うよねっ!」
アシェルは叫んだ。声を限りに。
「あなたはまだイリィを思いやれるし、イリィのためなら自分より強いものにだって立ち向かえる。だったら、あなたはまだ違うよねっ! だからもう止めて! 本当にイリィのことを思うなら・・・・・・っ!」
「ウルサいウルサいウルサいいぃっ! ダレであろうと、カワイいこのコをウバうなんてユルさないっ! ショウジキにコタえろ! おマエ、あのオンナのテシタだろうっ!」
「!?」
「あの女? それがあなたの理由?」
「ダマれダマれダマれっ! ウソをツくなっ! あのオンナ! ニクいニクいあのオンナ! このコをタイセツにマモってキたのはこのワタシだっ! イマさらダレにもワタすものかっ!」
「だからっ! それもっとちゃんと話してよっ!」
「イマサラ、イマサラ、イマサラあぁ、テバナしたりするものかあぁっ!」
「・・・・・・それは、誰? 誰のこと? それって・・・もしかして、私の・・・本当の・・・?」
もしかしたら、と。
一度も考えなかったわけではない。
ただ、考えないようにしていただけ。
この世界のどこかに、私の本当のお母さんがいるということ。
私を要らないと言った、見も知らないお母さんが・・・・・・。
一緒にいてくれるお母さんが嫌いなわけじゃない。本当のお母さんだから会いたいというわけでもない。
でも、出来るなら、一つだけ。聞いてみたいことは、ある。
”本当に、私は要らない子だったの?”と。
本当のお母さんがどんな人だったのか。
それは、私を育ててくれた人に聞くのが一番の早道。
ほんの一言。
ごく他愛のないことのように、さらりと、さり気なく。
でも、聞けなかった。
だってそれは、私のことを大切だと言ってくれるたった一人の人を、傷つけてしまうかも知れないから。
いいえ。それ以上に、確かめることが怖かった。
確かめないうちは、たとえ儚いものだしても希望は希望のまま、心の中に抱いていられる。万に一つの可能性を。
”本当のお母さんは、私を嫌っていたのではない”のだ、と。きっと、”何か事情があったはず”なのだ、と。
でも。
それを考え始めたら、何もかもを疑わなくてはならなくなる。
一緒にいてくれるたった一人の人さえも・・・・・・。
馬鹿みたいだ。そんな物語のようなことが、私にあるはずがない。
私はもう、そんな夢を見るほど子供じゃない。
けれど、一度心に浮かんでしまった疑いは、そう簡単に消せはしない。
自分でも忘れてしまうほど心の奥底に沈み込みながら、それでも埋み火となって消えることなく在り続け、そして、きっかけを待っていた。
小さなきっかけ一つでいい。
それだけで、全てを呑みつくす炎と化すには十分だ。
「嘘・・・・・・」
「!?」
「嘘、嘘、嘘・・・・・・」
「アア、どうしたの? ワタシのカワイいコ。あれはスグにケしてアげるから。ゼッタイにおカアさんがマモってアげるから・・・・・・」
「違うっ!」
「イリィ!?」
「私はあなたの本当の子供じゃないでしょう? ねえ、お母さんはどこにいるの? 私の本当のお母さんは、今もどこかで私を探しているんじゃないのっ!?」
「アア、アア、どうしてそんなコトをイうの! どうして、どうして・・・・・・」
「待ってイリィ! この人は今正気じゃないんだから、話を真に受けちゃダメ・・・・・・!」
イリィの変化に気付いたアシェルは、思わず手を伸ばす。
黒い光沢に覆われた、魔物の力を宿す手を。
「あああああぁぁぁぁぁあああああ!」
泣き声は悲鳴に、悲鳴は音階に。
それは、歌。
悲しみの歌。
怒りの歌。
イリィの心が、歌となって流れ出している。
歌は、力へと変換されていく。
「わっ!」
突然生じた衝撃の波に弾き飛ばされた勢いのまま、アシェルは地面に叩きつけられる。
「ったぁー! ・・・・・・どーしてこう何度も何度もっ・・・・・・!」
思わず毒づいたアシェルのすぐ傍に、どさっと大きな塊が投げ出された。
「!」
アシェルから見れば大きな塊でも、人間としては小さくか細い。
魔の力をまとっていなければ、ただの非力な女性でしかない人。
アシェルはハッとしてイリィの姿を探す。
居た! でも・・・・・・。
虚ろに目を見開き、力なく無防備な姿勢で迸る力の只中に立ち尽くしている銀色の髪の女の子。
いや、そうではない。力はイリィの内側から溢れ出している。
声ならぬ声。歌ならぬ歌。
イリィの紡ぐ、この世界のものとは異質な音が異界の力に変換され、天と地とを繋ぐ濁流のように溢れ出している。
「待ってイリィ! お願いだから!」
だが、アシェルの声は途中で空しく跳ね返された。
視えない断層の向こうのイリィには、誰の声も、どんな音も届かない。
シャリィィィ・・・・・・ン・・・・・・
どこかで何かが砕け散る音ならぬ音が、空間に響き渡った。
イリィの周りで渦を巻き始めた力の奔流の中に、キラキラとした無数の粒が出現し、縦横無尽に飛び回り始める。
「これは、羽根!?」
光の一つが、イリィに向かって伸ばそうとしていたアシェルの腕を掠め、甲冑のような皮膚にざんっと鋭い傷を刻む。
黒い天使のアシェルであっても、魔物を滅ぼすことの出来る羽根の力は侮れない。
明確な攻撃指示を与えられていない今でさえ、羽根は魔の気配に奮い立ち、少しでも近づくものがあれば即座に襲い掛かろうと身構えている。
だが、そんな中で、アシェルは顔を上げて真っ直ぐにイリィを見据える。
「ダメだよイリィっ! そんな風に暴走させたら、命なんてすぐに使い果たしちゃう! それに、」
旋風に混じる刃が、喜々としてアシェルに襲い掛かる。
上衣を引き裂き、皮膚を抉り取り、闇色の血をしぶかせる。
「それに、イリィにはいるじゃない! 本当のお母さんじゃなかったとしても、いてくれるじゃない!」
身体中に傷が増えていくのにも構わず、アシェルは精一杯声を張り上げる。
「イリィの為に、魔物になってもいいとまで想ってくれる人がっ!」
(ああ、そうか。そういうことだったんだ・・・・・・)
思いながら、アシェルはさらに言い募る。
「ボクにはいなかったよっ! ボクのお母さんは、魔物になってでもボクと一緒にいてあげようだなんて、思ってはくれなかった!」
人間は魔物になれる。
どうしても叶えられない望みを、それでも諦めることのできなかった人間が、自らの運命を引き換えにしてでも手に入れるための、最後の手段。
そうと知った時、何て悲しいことだろうと思った。
でも、同時に、何故だかすごく腹が立った。
そんな感情が、自分の内のどこにあったのかと思うくらいに。
だから、それ以上考えるのをやめた。
考えないでただ、心の奥に封印した。
だって、考えてしまったら・・・・・・その答えに行き当たらずにはいられなくなる。
”どうして、お母さんは迎えに来てくれなかったのか”。
もちろん、仕方がなかったからだ。
”私”の幸せを考えるなら、それが一番だと思ったから。
わかってた。わかってたけど。
それでも”私”は、思わずにはいられなかった。
あんな場所での幸せなんかより、一瞬でもお母さんと一緒にいられたら、その先にどんな破滅が待っていたとしても、絶対に後悔などしないのに。
それなのに・・・・・・。
イリィのお母さんは望んだのだ。魔物の力を。
本当のお母さんでもない人が、そうまでするほどイリィを大切に想っていた・・・・・・。
そんな推測は間違いであってほしいと、本気で思った。だから、ここに来るまでだって、違う可能性ばかり考えてた。
イリィのために? もちろん、そうだ。少なくとも、それだけは嘘ではない。
ああ、でもそれ以上に、ボク自身の気持ちのために。
だけど。
だからこそ。
「イリィは! その人のために生きるんじゃなかったのっ! だったらダメだよ! ちゃんと、向き合って話をしなくちゃ! じゃないと、きっと後悔する! ボクみたいになってからじゃ遅いんだよっ!」
「アシェル! しっかりしろ、アシェル!」
腕の中に抱きしめられ、揺さぶられる感覚に、アシェルはうっすらと目を開いた。
「・・・・・・カリム?」
「大丈夫か? まだどこか痛むか?」
「!」
焦点が合うかどうかの至近距離に、心配げに覗き込むカリムの顔。
何だろう。
頭の芯がぼうっと痺れて、変なカンジだ。
ああ、そうだ。何か言わなくちゃ。ええと、ええと・・・・・・。
「来るの遅い!」
一瞬目を丸くしたカリムだが。
その蒼い瞳に、安堵の笑みが広がった。
第26話 望むもの、望まれるもの
ねえ、イリィ。
どうして世界は、こんなにも簡単に壊れてしまうんだろうね。
白一色に埋め尽くされたあの離宮で。
全てが偽りだったと知ったあの日、目の前の世界は一変した。
それでもたった一人だけは、ボクを理解ってくれるはずだと・・・・・・。
でも、そのたった一人ですら、ボクを裏切り去って行った。
『・・・・・・必ず行くから・・・・・・やらなきゃならないことをやり終えたら、その時は、絶対に、お前の所に行くから・・・・・・』
その声は、微かで、途切れ途切れで、ボクの内の結晶が砕け散る音に重なって、かき消されて。
何だよ、それ。
そんなの、信じられるわけないじゃない。
ボクよりも大切なものがあるんでしょ。
そのためだったら、何だって出来るんでしょ。
だったら、キミがボクの所に戻って来るなんて、あるはずがないじゃない。
”彼”ですら、”私”の所に戻って来ることはなかったのに。
なのに、ボクはどうして、こんな冥い闇の中で、淋しい夢を見続けているんだろう・・・・・・。
「アシェル、大丈夫かアシェル!」
揺さぶられる感覚と同時に、繰り返し呼ばれる、ボクの名前。
「来るの遅いっ! って、あれ? 何でキミがここにいるの?」
カリムの腕の中で覚ましたアシェルは、思わず怒鳴りつけてしまってから、キョトンと首を傾げた。
だって、カリムがこんな所にいるはずがない。
魔物の眼を持たないカリムが、結界の外からアシェルやイリィの危機を知る術など無かったはずだから。
村を覆う結界は、本来そのためのものなのなのだ。
「さぁて、どう答えたものかな? この期に及んで、俺のことを呼ぼうともしなかった薄情なヤツに?」
「ううう・・・・・それはその、色々とワケが・・・・・・」
上目づかいに見上げると、いつもの悪戯っぽい瞳が見下ろしている。
憎ったらしい意地悪口調でも、全然そうは聞こえないから不思議。
悪態をつくことで「何でもないよ」ってフリをするのは、カリム流の思いやりだ。
「って、そんなこと言ってる場合じゃない!」
慌てて身を起こそうとしたアシェルに逆らわず、カリムは握っていた手を開く。
(あれ?)
カリムが握っていたのは、アシェルの手と言うより、両の腕で。それは、アシェルを介抱するにしては、ちょっと不自然な感じで。
嫌な予感とともに視線を落としたアシェルは、目にした自分自身の姿に、思わず肩を震わせる。
引き裂かれて、ボロボロになった衣服の下。黒く武骨な甲冑様の殻に覆われた、自分の腕と、身体。
魔物の力の具現である鎧。
(そっか、あの時・・・・・・)
暴走し襲い掛かる羽根に耐えかねて、とっさに魔力で防御した。そこまでは、覚えている。
だが、その後は・・・・・・。
「カリム、これ・・・・・・!」
ふと横に目を移したアシェルは、カリムの腕に赤く走る、鋭いもので切り裂いたような数条の傷に気付いてギョッとする。
それは、羽根によるものではないだろう。
羽根は基本的に、魔物以外を攻撃することはない。たとえ暴走していたとしても。いや、むしろ暴走状態だからこそ。羽根使いであるイリィが命じるか、イリィが攻撃を受けるかしない限り、カリムが標的になったはずはないのだ。
「もしかして、ボクが、また・・・・・・?」
魔物の力に支配されて、無意識の内にカリムのことを傷つけた。そうとしか考えられない。
何だか無性に泣きたい気分で、アシェルは俯く。
「なあ、アシェル。今、村ン中はどうなってると思う?」
「? 今そーゆう話してんじゃないでしょ!」
が、アシェルの反応など意に介さず、カリムは続ける。
「見境無い羽根のせいで、もの凄い大嵐だぞ。バラバラになった祭りの櫓とか、大工道具や農具なんかが飛ばされて来て、危ないの何の。ちょっとでも油断したら、たちまち傷だらけだぞ。村人は家に逃げ込んだだろうが、この分じゃ家ごと飛ばされたりしてな」
気遣っているつもりだろう、カリムは明るい調子でそんなことを言う。
「ふーん。キミって、そんなのも避けられないよなドジなんだ!」
返す言葉に、つい怒気が混じる。
変に気を遣われるくらいなら、いっそハッキリお前のせいだと言われた方が、どれだけ楽か。
「その程度のものだよ。お前の暴走なんて。俺からしたら、それくらい何でも無いことだ」
俯いたまま、アシェルはハッと目を見開く。
「言っただろ。俺はお前以外には殺されてやらない。もちろん、暴走した魔物の力になんか負けてやらない。絶対に、お前が知らない間にいなくなったりしない。だから、いいぞ。安心して、いくらでも暴走しろよ」
と、同時に。アシェルの上からフワリと、深緑色の布が降ってきた。
それはカリムがストール代わりに使っていた絹帯だ。
カリムはそのままアシェルの身体を包み込むように絹帯を巻き付け、余った端を腰の辺りでちょうちょ結びする。
「うわ、何か雑・・・・・・」
「大丈夫、お前は何でも似合うから」
見上げたアシェルに、カリムはニッと笑って見せる。
「だからもうしばらく防御を解かないでいろよ」
「え?」
「羽根の暴走が止まったわけじゃないからな。お前にもしものことがあったら困る」
「・・・・・・キミってばどーしてそーゆーコト真顔で言うかな」
「思ったことは思った時にハッキリ言うことにした」
「たくもう・・・・・・」
苦笑してから、アシェルはふと、カリムの腕に手を伸ばした。
「ちょっと待って! そんなこと言ってまた誤魔化すつもり? 傷が結晶化してないってどういうこと!? 再生の力が弱ってるんじゃないの!? 意地ばっかり張って薬酒を嫌がるから!」
騙されるもんかと、アシェルは再び目を吊り上げる。
「ああ、違う違う。そうじゃない! ここがそういう所だからだ」
「ここ? そう言えば、ここって、どこ? 何でこんなに静かなの? イリィは? あの人は・・・・・・!?」
改めてキョロキョロと見回したアシェルに、カリムが指し示した先。
草地も海も家もまるで見通しが利かないほど激しく渦巻く嵐の只中に、虚ろな瞳で立ち尽くしているイリィの姿が微かに垣間見える。
そして、イリィのすぐ傍の地面には、倒れ伏しながらも、イリィに向かって必死に手を伸ばそうとする女性の姿が。
それはアシシェルが気を失う前、最後に見たのと寸分変わらない光景だった。
本当に何も変わらない。
(何で? それって変! あ、でも・・・・・・?)
イリィの周りを激しく渦巻いているはずの羽根の動きは、そよ風に揺らめくように緩慢で、それはまるで現実の一場面を切り取った絵を見ているようだ。
完全に静止していはいないが、恐ろしくゆっくりにしか動かない、時間。
「何、これ・・・・・・どういうこと? もしかして、これも結界の作用とか?」
「少し違う」
混乱して声を上擦らせるアシェルに、どこまでも冷静な声が答える。
「強いて言うなら、空間の狭間みたいなものだ。時間の流れが外とズレて感じるが、それは感覚だけの問題で、肉体にまで作用するものじゃない。だから怪我をしても血は流れないし再生も進まない」
「どうしてそんなことが? てか、結界のせいじゃないなら、これって誰の能力? それとも作用? カリム、何か知ってるの?」
「えーとな、えらくお節介なのが居て、力を押し貸ししやがるからさ。実際、お前を助け出すのに便利だったし、遠慮なく利用してやった」
「先刻の、変な旅人羽根使いの彼のことじゃないよね。・・・・・・もしかして、会えたの? キミと同質の力の持ち主に?」
その問いに答える代わりに、カリムは僅かに微笑った。
それは肯定の意味に違いないのだが。
「ねえ、何があったの?」
カリムが纏う空気の色が、先刻までとは少し変わっている気がする。
どんなに隠そうとしても隠しきれないでいた切羽詰まった雰囲気が、ごく自然に影を潜めてしまったような。
「ま、その話は落ち着いてからゆっくりな。残念ながら、ここもそう長くは保たない。だから今の内に、お前に何があったか知りたいんだが・・・・・・聞いてもいいか?」
それを聞くことは、アシェルがカリムを呼ばなかった理由を聞くことでもある。
「無理はするな」との含みを読み取って、アシェルはふるふると首を振る。
「確かめたいことがあったんだ。どうしても、ボク自身で。でも・・・・・・ボクには何も出来なかったんだ。イリィを守ってあげることも、あの人を解ってあげることも・・・・・ボクだけじゃどうにもならない・・・・・・」
「そうか・・・・・・」
うなだれるアシェルの頭を、カリムはくしゃりと優しく撫でた。
「で、何があったんだ?」
「うん・・・・・・あれからボクは・・・・・・」
「魔物? あの老婆がか?」
アシェルにしてはかいつまんだ話を黙って聞いていたカリムだったが、話しがそこに及んだ途端、思わずといった様子で呟いた。
怪訝そうに眉根を寄せながら。
「だから、イリィのお母さんだってば。やつれてるから歳取って見えるけど、ホントはそれほどじゃないと思うよ」
すかさずアシェルが訂正を加える。
「いや、それはどっちでもいいんだが。魔物にしては、あまりにも気配が無さすぎる。あえて探せば、微妙に存在の芯がブレてる気もするが、それだって感受性の強い人間だったら有り得ないレベルじゃねーし。第一、羽根の標的になってねーし・・・・・・」
そう。羽根は魔物の気配に敏感だ。
羽根の本性が顕わになる暴走状態ではなおさらのこと、魔物と見れば、見境なく襲い掛かっているはずだ。
しかも、先刻のアシェルよりもよほどイリィに近い位置にいるにもかかわらず。羽根はそれ以上近寄るなと威嚇はしても、積極的に攻撃しようとはいていない。
もっとも、アシェルは魔物の力を使える以前に黒翼の天使でもあるので、単純には比べられない。だが、そうだとしても。
「ってことは、まさか・・・・・・」
「判った?」
「契約者、なのか?」
「そう。正解。どうしても叶えたい望みと引き換えに、魔物になることを承諾した人間。だけど、その願いが完了してないから、あの人はまだ人間のままで、魔物の力は単なる借り物。だから力を使っていない時には、本当にただの人間にしか見えないんだよ。契約者を見分けられるのは、魔物か、契約主である黒翼の天使だけ・・・・・・」
「・・・・・・」
「ビックリした?」
「いや・・・・・・まあ、そうだな。そう、初めて見た」
契約の魔物が元は人間であることは、カリムも知識としては知っている。契約主となるのが、黒翼の天使であることも。
だが、魔物に変じる前の契約者を目にする機会などは、これまで一度として無かったのだ。
「だろうね。塔は契約者には無関心だもんね」
アシェルの言う通り。白亜の塔は、魔物退治の要請を受けてはじめて、現地に天使を派遣する。
それは昨日今日の話ではなく、塔が組織された当時に各国との間で交わされた取り決めによるものだ。
どこの国からも、どこの組織からも中立を保つために、それは必要なことだったが、塔という組織の地位が確立した現在でも、その姿勢は全く変わっていない。天使が自ら魔物を探して歩くことも無ければ、契約者の段階で魔物の芽を摘み取ることも、人間が契約を結ぼうとすること自体を阻止することもない。
天使は魔物を滅するもの。
悲しい魔物を生み出さぬように、務めるものではない。
「この村を覆っている結界はね、あの人の契約主が張ったものなんだ。あの人が魔物になるのを邪魔されないよう、その存在を覆い隠すために。だって、せっかく契約して力を分け与えたってのに、魔物になる前に狩られるようなことになったら、丸っきりの大損だもん。契約者に付けられた契約印が魔物や黒翼の天使に視えるのは、”これはオレの所有物だぞ、誰も手を出すなよ”ってサインだからだよ」
「だが、どんなに覆い隠したとしても、すっと一緒に暮らしていれば、何かがおかしいことに気付く・・・・・・だからあの娘は歌えなかったのか? 母親がおかしいとは認めたくなくて、無意識に自分の力を抑えていた。そして否定しきれない事実を突き付けられたことで、そのタガが一気に外れてしまった。唯一の支えである母親に、裏切られたと分かったから」
「誤解なんだよ!」
即座にアシェルは大声を上げた。
「誤解なんだ。イリィのお母さんはきっと、イリィを守りたくて契約したんだ。イリィだってそれは解ってるはずだよ! ただちょっと、お母さんを信るのが怖くなっちゃったんだ。本当に大好きな人だから。だからこそ、信じ切れない自分がイヤで、悲しくて、不安で、どうしようもなくなっちゃったんだ・・・・・・」
「アシェル・・・・・・」
「イリィの周りで変なことが起こり始めたのは、二年くらい前からだったよね。だから、あの人が契約したのは、多分その頃だったと思うんだ。でも、これだけ経ってもまだ魔物になってないってことは、イリィのお母さんは本当に優しい人なんだよ。契約者はね、簡単に魔物になるような人間には声をかけないものなんだ。本当なら魔物になろうとなんか考えない人間を、手間暇かけてじっくりと魔物に変える。それが強い魔物を生み出す方法なんだ。だけどいくら手間隙かけるったって、いつまでもは待っていられない。結界は契約者の存在を隠すものだけど、同時に早く魔物になるよう促す仕掛けがしてあるんだ。イリィの周りに起こった異変だって、その仕掛けのせいに違いないよ。それでもイリィのお母さんは、まだ魔物になってないんだから!」
「それで、契約者を救う方法はあるのか?」
カリムが問うたのは、一番肝心なことだ。
「・・・・・・契約を解除できるかって意味なら、それは無理だよ。契約主は自分の配下となる魔物が欲しいんだ。願いを叶えるのは、人間の為なんかじゃない。魔物を作る為の、単なる手段。だから、契約に解除条件を付けるなんてことは、絶対に有り得ない」
泣き出しそうな顔で、アシェルはカリムを見上げた。
「ねえ、カリム。黒翼の天使は魔物を必要とする。それがどうしてだか知ってる?」
カリムの返事を待たず、すぐにアシェルは言葉を繋ぐ。
「魔物が集める、恐怖と悲しみに満ちた人間の魂こそが、闇色の結晶にとっての薬酒だから」
「・・・・・・!」
「そうだよ。だから黒翼の天使は、自らの記憶を代償とする薬酒を必要としない。他人の悲しみを代償に、ボクらは永遠を手にしている・・・・・・」
「・・・・・・」
(どう? それでもボクが大切だって言える? ボクを救う価値が、本当にあると思うの!?)
叫んでしまえば、きっと楽になれる。
だって、カリムの答えは解っている。
あれほど薬酒を嫌うカリムが、それでも天使であり続けた。そのこと自体が、何よりも明確な答えだ。
カリムは信じていたはずだ。カリムの求め続ける人が、他人を犠牲にするような選択をすることは決してない、と。
アシェルになる以前の記憶はあっても、アシェルが昔に戻ることは出来ない。決して、出来ない。
解っているのに。
最後の言葉を、口にすることが怖い。
カリムを、アシェルの世界そのものを失ってしまうことが、怖くてたまらない。
アシェルはギュッと目を瞑る。
固く、固く。
そうしたところで、何も感じずに済むわけではないのに。
「・・・・・・すまない、アシェル」
(イヤだ! やっぱり、聞きたくない!)
「それでも、俺は」
(耳! 耳を塞がなきゃ! 早く、早く!)
「お前がここにいてくれることが嬉しいよ」
(・・・・・・え?)
「お前にそれが必要だったのなら、それは間違いなく俺自身の望みだよ。それこそが、あの日、炎上する離宮の中で、俺が選んだものだったんだ・・・・・・」
「カリム?」
目を開ければ、そこに優しい笑顔があった。優しい、でもどこか泣いているような、穏やかな蒼い瞳がそこにあった。もちろん、本当に泣いてなどいなかったけれど。
あの時、どうしていれば良かったのか。
何が出来たのか。
それは、アシェルが眠りにつく前の、ほんの少しだけ過去のこと。
カリムにとっては、思い返すこともままならない、遠い過去のこと。
「だけど、あの二人は違うよね。イリィとお母さんは、まだ間に合うよね? イリィだったら、きっと解ってくれるよね?」
想いを振り切るように、アシェルは緑の瞳をカリムに向ける。
「あの二人に、ちゃんと話をさせてあげたい。誤解したまま傷つけ合うなんて、絶対にダメだよ。たとえ運命の結末が変わらないのだとしても、このままじゃダメなんだ。解ってるよ、それがボクのワガママでしかないってことくらい。イリィは羽根使いで、イリィのお母さんは魔物になる。それを変えることなんて出来やしない。だけど・・・・・・」
「そうだな。俺もそう思うよ。出来ることなら、助けてやりたい」
アシェルの瞳を真っ直ぐに見返して、カリムが微笑う。
「頼みがあるんだ」
微笑を浮かべたまま、静かにカリムが口を開く。
「その役、俺にやらせてほしい」
「ちょっと待ってよ!」
間髪入れずに、アシェルは声を荒げる。
「ちょっと待って! ボクはそんなつもりで言ったんじゃないよ! いくらキミでも、あんな暴走しまくった羽根を相手に羽根無しで・・・・・・ううん! 羽根があったとしても・・・・・・」
「だよな。俺の羽根は攻撃専門で、こんな場合にはハッキリ言って何の役にも立ちやしない」
「違うよ、そうじゃない、はぐらかさないで! 今のキミが、羽根の発現に耐えられるワケないじゃないか! それに、これはボクがやりたいことであって、キミに望むことじゃない! ボクがキミに望むことはたった一つだけだよ! 今も、昔も、ずっと、一つだけ。なのに、どうしてそんなことが言えるのさ! それともまさか、これで終わりにするつもりなの? ボクがモタモタしてたから、ボクじゃないものの手を借りて、それで・・・・・・」
「アシェル・・・・・・」
「ねえ、イリィだったらきっと大丈夫だよ! ちゃんと羽根を受け入れられるよ! 大切な人を消したりなんかしないよ!」
「そうだな。正気を取り戻せれば、あの娘ならきっと出来る。だから、呼び戻してやらないとな。羽根に命を削られる前に。それに、このままあの母親が近付いて行けば、羽根の威嚇はもっと強くなる。もしも反射的に魔物の力で防御してしまえば、その時は本当に羽根の標的となる。それは止めないといけないだろ?」
「だからって、どうしてキミが・・・・・・キミに何が出来るってのさ!」
「このまま黙って見ているよりは、ほんのちょっとマシなこと、かな」
「まだ解ってくれないの? どうして解ってくれないの!? キミはいつもそう! 自分のやりたいことばっかりで、ボクはいつも置いてきぼりで、ボクがどんな気持ちでいるかなんて、これっぽっちも知ろうとしないで! いつも、いつだって、ずっと前から、ちっとも変わらなくて・・・・・・!」
「そうだな。俺は今までずっと、お前に甘え続けてきたんだと思う。お前だったら解ってくれる、許してくれるって、多分、心のどこかで思っていたんだ。お前の為になりたいと言いながら、ワガママを通してきたのはずっと、俺の方だ。そうと解ってさえ、やっぱりまた同じことをしてしまう。きっと、何度でも。俺が存在する限り」
「そうだよっ! その通りだよっ! 解ってるよ、それがキミだってことくらい! ・・・・・・そうじゃなきゃ、キミじゃないってことくらい! そんなのとっくに知ってるんだから。知っててキミとこうしてるんだから! っとにナメないでよね!」
何を訴えたいのか、自分で解らなくなりそうだ。
ただただ感情のままに、思いついたことをぶつけるだけ。
子供みたいに。ワガママに。
それは、昔の私が決して言えなかった言葉。だけど今は。アシェルであれば。
だってアシェルは、昔の私とは違う。昔の私みたいに物分かりのいいフリなんか、絶対にしないから。
「なあ、アシェル。お前に聞いてほしいことがあるんだ。どうしても。これが終わったら。だから、」
「・・・・・・」
「お前が望まないのなら、やらない。お前に望みを強制しようとは思わない。だが、あの二人に話をさせてやりたいってのも、お前の望みなのだろう?」
「だけど・・・・・・」
「言っただろう。俺はお前のものだよ。契約を交わしていなくても。何の約束も無くたって。それだけはずっと変わらないよ。だから、お前が望むなら、このまま成り行きを見守るだけの傍観者であり続けても構わない。傍観するしか出来ない罪悪感を、共に背負っても構わない。でも、それを悲しいと思うのなら、」
むずがる子供のように、アシェルはゆるく首を振る。両手をしっかり握り締めながら。
「望んでくれるか、俺に?」
アシェルの肩が、小さく震える。
「・・・・・・似てると思ったんだ。最初は。誰かのために一生懸命なイリィは、どことなくだけど、キミみたいだって。だけど、ちょっと違ったみたい。イリィは昔の私に似てる。自分からは何も出来なくて、立ち竦んで泣いてるだけの私に・・・・・・。だからかな。イリィが泣くのを見るのは、心が痛い」
アシェルはカリムを見上げる代わりに、その腕をしっかり掴んだ。
「助けてあげて、カリム。イリィを、あの人を・・・・・・助けて、それからちゃんと戻って来ること。絶対に。じゃないと許してあげない。言い訳なんか、聞いてあげない。キミを殺すのは、他の誰かじゃない、このボクだけなんだから」
「ああ。ありがとう、アシェル」
「・・・・・・だからどうして、そこでお礼なんか言うかな」
「思ったことは、思った時に伝えておかないとな」
忘れてしまう前に。遠い彼方へ消え去ってしまう前に。
「この空間もそろそろ限界みたいだ。お前は絶対に動くんじゃないぞ。少なくとも羽根の暴走が治まるまでは」
「ふんだ! そんな約束してやんない! 心配だったら、さっさと片付けて戻って来ればいいんだよ!」
「ああ、それもそうか」
「そうだよ。ボクがキミに望むのはたった一つなんだから。今も昔も変わらない、たった一つなんだから・・・・・・!」
空間を隔てていた薄幕が少しずつ溶けて行き、凪いでいた空気が動き始める。
時間の感覚が、現実と同調し始める。
そよ風が、突風に、そして逆巻く暴風に。
カリムは、自分の腕を掴んでいるアシェルの手に、手の平を重ねてそっと解く。そして、風の吹きこまない石垣の土台の陰に、アシェルを座らせる。
そして一挙動で立ち上がったカリムは、羽根の生み出す波動の中に無造作に身を晒した。
結い上げられた淡い色の長い髪が、羽根の生み出す強風に煽られて激しく揺れる。
だが、真っ直ぐに目標を見据える蒼い瞳には、僅かの迷いも存在しない。
(ああ、キレイだな)
唐突に、アシェルはそんなことを思う。
しっかりと地を踏みしめて立つ凛々しい体躯、白く端正な面立ち。
見る者の目を釘付けにせずにはおかない、上級天使の名に相応しい少年の姿。
キレイだって言われるのは、キミは不本意なんだよね。その賛美は自分ではなく、その肉体の持ち主だった誰かが受けるはずのものだから。
だけど、そうじゃないんだよ。外見がどうこうじゃない。
昔からキミは、とても眩しかったよ。
そりゃあ、今みたいな美人だったとは、お世辞にだって言えなかったけどね。
そうじゃなくって、いつもいつもいつも、他人のために。自分が傷つこうが何しようが、無茶苦茶なくらい潔く立ち向かって行っちゃうキミは、本当に・・・・・・。
外見は全然違うのに。性格だって違うのに。そんなところだけはどうして、こんなにも変わってないんだろうね。
キミだって、世界が壊れる光景を、もしかしたら何度だって見ているはずなのにね。
どんなにキミを憎んでも、嫌うことさえ出来たとしても、無視して忘れてしまうことだけは、どうしても出来なかったよ。
ねえ、イリィ。
目の前の世界なんて、いとも簡単に砕け散ってしまう。
自分の心なんて、こんなにも簡単に見失ってしまう。
それでも。
どうしてかな。
世界を失ったはずの者こそが、より強くなることも出来るなんてね。
第27話 最高の奇跡
その昔。全てを創った全なる神とやらは、この世界を完全なものにするつもりなど無かったらしい。
長い時が過ぎ去って、不完全なものが好き勝手した挙句の果て。世界はあちこちガタガタで亀裂だらけ、いつ壊れても不思議はない。
だが、そこに棲み続けねばならないものは、そんな都合の悪い事実を認めるわけにはいかない。
世界はこうあるべきだという建前の元に、ごてごてと嘘を塗り重ねて、見たくないものを覆い隠して。
出来上がったのは偽りだらけの歪んだ世界だ。
そんな世界にどんな意味がある?
ほんの少しでも。
この世界に意味があるのだとすれば・・・・・・。
ピシッ!
ぎゃあぎゃあとわめき続けるフェグダを他所に遺跡の丘の上から村を眺め下ろしていたカリムの背後で、不意に何かが爆ぜたような音が響く。と同時に脳裏に飛び込んで来たのは、半ば壊れかけていた石像のヴィジョン。
遺跡の中央広間の五本の柱の内、折れ残った一本の頂に取り残されていた少女像。その中心部から放射状に亀裂が走ったと見るや、像は粉々に弾け飛び、内部に在ったものを顕わにする。
揺らめく炎の形に凝縮固定された、高次の力。
非物質の結晶は、一瞬だけ何かに抗するように瞬いて。
シャリィィィン・・・・・・
音ならぬ音を響かせながら、無数の火の粉と化して飛び散った。
響きの余韻は波動となり、幾重にも連なる空間の垣を飛び越えて、広く深く、どこまでも浸透してゆく。
暗転する世界の中。降り注ぐ炎の欠片、その一つ一つに、数多の虚像が映り込む。
知っている。
俺はかつて、これと同じ音を聞いている・・・・・・。
『・・・・・・そしてついに! 魔物は光の中に溶けて、消えていきました』
声が、聞こえる。
暗闇の向こうから押し寄せてくるのは、呪印の発するじりじりとした白い光。
『こうして、美しく甦った湖畔の国に帰った王子様とお姫様は、末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたし!・・・・・・あ、起きた?』
暴力的な光がすっと陰って、そこに上下逆さまのシルエットが浮かび上がる。
『大丈夫、じゃないっか。またハデに暴走させてたもんねー』
快活に話しかけて来たのは、明るい緑色の瞳の持ち主。
『これくらいいつものことだろ。・・・それにしても惜しかった。あともう少しで、この手で結晶核を壊してやったのに』
『ゴーレム相手に徒手空拳で3時間も粘ったんだって? キミ付きの番人達、ウンザリしてたよぉ。上級天使には体術なんて必要ない、羽根さえ使えれば立ってるだけで十分なのに、って』
『それはいくら何でも極端過ぎるだろ。・・・・・・で、何をブツブツ喋ってたんだ?』
『ん? ああ、キミが寝たまんまでタイクツだったから、昨日読んだお話でも聞かせてあげよっかなーって。どう、面白かった?』
『どう、と言われてもな・・・・・・』
辛うじて耳に入ったのは、話のラスト部分だけだ。
『ねーねーねー、幸せに暮らすってどんなだと思う?』
『・・・・・・あ?』
『ボクはねー、うんといっぱい魔法の勉強をしたり、剣の修業をしたりしながら、二人仲良く一緒に国中の魔物を退治して歩くんだと思うなっ! また魔物が出て悪いことをしたら、みんなが悲しい思いをするからね』
『・・・・・・』
『青い空の光を映して宝石みたいに輝く湖かあ。どんなのかなー。キレイかなー。いつか見てみたいな・・・・・・』
その時の俺は、どんなことを考えていたのか。どんな顔をしていたのか。
お前の言う通りだと同意したのか。
そんなものはお伽噺だと突っ撥ねたのか。
何か言おうとしたのか、しなかったのか。
一言でも発していたなら、手掛かりになったものを。
『あ! 番人こっち来る! あいつら仕事熱心過ぎだなんだよ、ったく、何が楽しくてやってんだろ? 少しはノンビリすりゃいいのにさ! じゃまたねっ!』
アシェルが慌ただしく立ち去った後も、カリムはついぞ無言のままだった。
薄ぼんやりと滲んだ視界の中で、そこにある物が徐々に形を取り始める。
どこまでも続く黒灰色の回廊。
背後の闇に、時折赤い炎が閃く。
行く手を妨げる煙は熱く、空気を求めて呼吸するたび、じわりと喉を焼いていく。
かすむ視界は、足を踏み出すごと、上下に左右に大きくブレる。
そうしてどれくらい経ったのか。やがて前方に、一筋の淡い光が差し込んだ。
灼くように眩しい呪印の光ではない。あれは間違いなく外からの光。出口の証だ。
『驚きましたよ。まさか、貴方の方が生き残るとは』
背後からの声に、一瞬、視界が静止する。
『それで、どうするおつもりか。その状態では、貴方はそう永くない。じきに薬酒の効果も尽きる。あそこまで辿り着けるかすら怪しいものだ』
まるで日常の会話と変わらない、平坦で抑揚を欠いた声。
追い縋る炎は、じきにここまで到達する。それを十分承知の上で。
冷静さを通り越した声は、更に続ける。
『そうまでして外に出たかったのですか。何とまあ、呆れるほど些細な望みだ。この離宮を破壊し尽くし、多くの番人の命を奪い、そればかりか大事な友とやらまで切り捨てて。おびただしい犠牲を払いながら、たったそれだけが望みは。彼らは無駄死にもいいところだ』
易い、見え見えの挑発だ。
だが次の瞬間、それまでの遅々とした足取りが嘘のような激しい勢いで、景色が流れる。
振り向いた視界の中心に飛び込んで来たのは、黒いフード付きのローブを纏った、一人の番人。
『どうしてお前にそんなことが言える! お前らが何をやって来たか、知らないとでも思ってるのか! お前らが、あんなっ・・・・・・!』
フラッシュバックする光景。
あれは、幾重もの結界に覆い隠されていた離宮の地下空間。
薄紅色の薬液の中に、何十もの人間の形をしたものがひしめいている。彼らが何者であるかは、その体内で歪に揺れる炎の色が語っている。
そんな幾多の薬槽の果てには、全てを奪い取られ打ち捨てられた、身体。身体。身体・・・・・・。
それは、真理の番人を自称する者どもがこれまで続けてきた所業の、もの言わぬ証人たちだ。
カリムもアシェルも、きっと、あの場所から来た。
耳障りに掠れる声は、喉を焼く煙のせいだけではなかったはずだ。
が、怒りに任せた声は、続く言葉を発しなかった。
目の前の男は微動だにしない。
フードの奥に深く隠れた、男の表情を伺い知ることは出来ない。
ただ、男の全身を濃密な魔法が一分の隙無く覆っているのが視て取れる。たとえ全身が炎に包まれようとも、その男はきっと、平然と立っている。それだけの魔法を身の内に蓄えている。
数多の番人の中で、一人、その男だけが。
『我らは塔のために必要なことを行ったまでのこと。それは即ち、世界のために必要だということ。そこに疑う余地などありはしない。貴方にも、私にも』
『・・・・・・』
『私は別に、貴方がどうなろうと構わない。このまま野垂れ死ぬならそれも結構。ですがもし、貴方に多少なりとも犠牲を悼む気持ちがあるのなら、違う道を示して差し上げてもいい』
『お前に期待することなど無い』
『ならば私など無視してしまえばよろしいでしょう』
全くその通りだ。そんな奴、気にする価値もない。
だが、その男を真ん中に据えたまま、視界は微動だにしない。
『解っておりますとも。貴方は、たかが感情如きに全ての判断を委ねるほど愚かではない。一時の感情がどれほど頼りないものであるか、よくご存じだ。私の話を量りもせずに一蹴などなさらない』
『・・・・・・言ってみろ』
『何も難しいことではない。経緯がどうあれ、貴方は集められた数多の素材の中から、ただ一人生き延び這い上がり、羽根の力を手に入れた。ならば堂々と上級天使の位を得ればよい。貴方には、その資格がある』
『馬鹿げたことだ。こんな破壊の限りを尽くした出来損ないを誰が認める? 辛うじて生かされたところで、道具として利用されるのが精々だ』
『とんでもない。これだけのことがお出来になるからこそ、貴方には価値がある。無論、私が口添えすればの話ですが』
『・・・・・・』
『考えても御覧なさい。ひとたび上級天使に列せられれば、その後何をしようと貴方の自由。最低限の責務さえ果たしていただければ、誰も口出し出来ますまい』
『俺がそれを望むとでも?』
『困りましたね。貴方がそんなご様子では、とても手助け出来そうにない』
『親切ぶりやがって。ハッキリ言ったらどうだ。困っているのはむしろお前の方だろう。この事態で、お前が失態を問われないはずがない。処分を免れるには、それなりの成果を示す必要がある。だから俺が必要なんだ』
はじめて、男のフードが僅かに揺れる。僅かな明かりを受けて、男の耳飾りが金色の光を弾く。
『これは少々侮り過ぎましたか』
『俺は、お前を信用しない。塔に忠誠を誓うつもりもない』
『では、こういう話は如何か。私は何の後ろ盾も無い一介の番人に過ぎない。数名の責任者以外、ここにいたのは元々そのような者達だ。今回のような事態が生じた場合には、全てを無かったことに出来るように。捨て駒なのは、貴方に限ったことではない。今更私が出頭したところで、許される可能性は皆無だ。それでも私は、こんな所で倒れるつもりはない。貴方はどうなんです。ここで無駄死にするのを良しとしますか』
『・・・・・・』
『私を信用する必要など無い。ただ、私達の利害は一致する。それで十分でしょう。目的の為に互いを利用すればいい。貴方には何を犠牲にしてでもやりたいことがあるのでしょう。ならば、途中で投げ出すことは、犠牲にしたものを蔑にするに等しい。塔だろうが世界だろうが、あらゆる全てを利用し尽くしてでも。・・・・・・ほんの僅かでも、アシェル様に報いるつもりがあるのなら』
『あいつを引き合いに出すのはやめろ。お前にあいつの何が解る。・・・・・・お前が言っていることは、俺に、お前の同類になれということだろう!』
どれほど言葉を取り繕おうと、カリムの命を肯定することは、塔の非道を恩恵として受け入れるということ。上級天使になるということは、塔の意向に従うということ。
それは、離宮ごと全てを破壊することを選んだアシェルを、裏切り続けることだ。
『おや、違うと仰いますか』
目を閉ざしたのは一瞬。
『・・・・・・いいだろう。お前の手駒になってやる。だが、それも俺が塔を去る時までだ。俺を利用したいというのなら、俺の気に沿うよう精々便宜を図ることだ』
あの時。
どうして黒い炎は現れなかったのか。
黒い炎を受け入れることなく、カリムは天使となることを自ら選び、受け入れた。
そして、カリムと契約を交わしたあの番人の男は。
自分の望みのためならば、どれほど大切なものだろうが犠牲に出来る、カリムの同類は。、
全てが離宮と共に燃え落ちた中、研究の委細を知る唯一の存在としてのし上がり、現在では一派の長にまで上り詰めている。
天使とは、魔物を狩るものだ。
では魔物とは何か。何をもって魔物とするのか。
それは、塔の上層部の意向によってのみ決まる。
政治的判断や、ほんの些細な思惑や、取るに足らないエゴによって、その判断がどれほど歪められてきたことか。
浅薄な目論見の陰に、敢えて見過ごされる魔物がある。
ために、どれだけの命が犠牲となっただろう。犠牲になる必要のなかった命が。避けられたはずの悲しみが。
あるいは、故意に魔物とされたものがある。
そこに理由が無いとは言わない。場合によっては、それも必要なことだったから。だが、何の咎も無く魔物の汚名を着せられ消されていった者も、確かにいたのだ。世界のために必要だから、と。
どれだけのものが犠牲になったのか。どれだけのものに自分自身が関わっていたのか。それすらも、もうとっくに判らなくなってしまった。
塔のシステムは、根本的に悲劇を食い止めるものではない。
それどころか、悲劇を必要とするシステムであるとさえ言える。
塔も、天使も、魔物も、黒翼の天使も、そして人間も。システムを構成する歯車の一つに過ぎない。
それでも構わなかったのだ。
幻の中の彼女を見つけ出すこと以外、俺にはどうでも良かったから。
だからせめて。
憎まれることは受け入れよう。恨みくらいは受け止めよう。
魔物であれ、魔物と呼ばれた者であれ、カリムが手にかけながら、覚えていられなかった者たちには、憎むものが必要だ。憎むものの名が必要だ。
それが、力の器に与えられた、便宜上の名称に過ぎなかったとしても。
解ってきたことがある。
死を受け入れることと、死を望むことは全く違う。
冷たく優しい冥闇に眠ることが、俺以外の者にとっては、忌み怖れるべきものでしかないのなら。
この命は間違いだ。
永続を望むゆえの歪んだ世界にとって、死を望む命などは更なる歪み。災いであり、間違いだ。間違いは、いつか正されねばならない。
『・・・・・・ボクが間違っていたよ。闇がこんなに優しかったなんて知らなかった。光の中に繋がれてたみんなは、ボクが眠らせてあげたよ。命を弄ぶ悪魔どもは、ボクが地獄に送ってやったよ。これでもう誰も、ボクらみたいに眠りを邪魔されたりしない。さあ、あとはボクたちだけだ。一緒に行こう、静かで優しい闇の底へ。ボクが、連れて行ってあげる・・・・・・』
『・・・・・・ねえ、どうしてボクを裏切ったの? ボクだけを殺したの? それで、キミは何をしたかったの? 何が出来たの? ねえ、教えてよ。キミがボクより大事だったものって、一体何だったのかなあ?』
恨むのは当然だ。憎むのは当然だ。
アシェルが魔物として生きるにはカリムの命が必要。それが、アシェルが魔物の力を手にする条件。
だから、なのか?
だからアシェルは、再び俺の前に現れなければならなかったのか?
間違いは、正されなければならない。
彼女の魂を持つアシェルを以てして、世界は間違いを正そうとしているのか?
(その感覚には、覚えがあります。僕にも・・・・・・わたしにも、滅びを望んだ時があった・・・・・・)
リィィィィィン・・・・・・
空間を震わせる響きの余韻の中で。
音が、声が、声が、人が、一瞬にして交錯する。
穏やかに波が打ち寄せる海辺。
鮮やかに彩られた、秀麗な建物の連なる古代風の都。
白い石壁の荘厳な神殿。
至る所に飾られる、極彩色の塑像。
神話そのもののような、華やかな衣装を纏った人々。
儀式に連なる、大勢の市民たち。
一際鮮やかな衣装を纏った、王族と思われる偉丈夫。
見渡す限りの丘を埋め尽くす、鈍色の甲冑を纏った軍勢・・・・・・。
(ねえ、美しいでしょう? そして、醜いでしょう?)
声ならぬ声は、すぐ傍から聞こえた。
(お前・・・・・・思い出したのか?)
(わたしはかつて、この地に生まれた羽根使いの一人。そして、あなたが炎の結晶と呼ぶ力を得て、この地の守護となった者。今となっては、その僅かな片鱗。燃え尽きる寸前の儚い残像・・・・・・)
それは、僅かな気配だけの存在だった。他者の姿を借りねばならなかった先刻よりも、ずっと脆く儚い。
だが、どんなに色を薄めても、もう二度と無色だとは思わないだろう。他の何者とも、見間違うことはないだろう。
(人生、何があるかわからないものですね。長生きはしてみるものです。本当にね、わたしの最期に立ち会ってくれる者がいるなんて、想像もしませんでした)
気配だけが、穏やかに微笑む。
(何を・・・馬鹿なことを・・・・・・)
(そうですね。でも、それでいいんだと思います。同胞から遠く離れて、一人生き延びることは、決して私の望みではなかった。恨みも悲しみも絶望も、きっとわたしの内にあった。でも、そんなものに拘る意味はとっくに無くなっていた。そしてようやく、同胞たちの元へ行くことが出来る)
穏やかにしか振る舞えないのではない。穏やかであることを受け入れたものとして。
(・・・・・・それでいいのかよ?)
(心残りと言えば、あの時、もっとちゃんと護って上げられれば良かったのですが・・・・・・それを言ったところで仕方ありません。わたしの後悔は、貴方の感覚で言えば、遠い遠い、神話のような過去の話ですから。・・・・・・大きな戦があったんですよ。攻め込んで来た者たちは、わたしたちに降伏すら許さなかった。そしてわたしたちは、国を護るためという理由で、徹底的に利用されることになった。けれど、思うんですよ。わたしたちをこのようにした者の中に、どんな形であれわたしたちに生きていて欲しいという願いが存在しなかったと、どうして断言出来るでしょう)
(・・・・・・)
(人間はね、違う気持ちを同時に持つことが出来るのではないですか? 一つの想いだけが全てなんて、そんな単純な存在ではないと思いませんか? それこそ、様々な神を矛盾なく等しく崇めることが出来るように)
(・・・・・・)
(それにね、人間は自分の全てを知っているわけじゃない。アシェルさんが何を思いどう行動したとしても、結果的に、貴方は今こうしてここにいる。それこそがアシェルさんの、本当の望みだったのだとは思いませんか?)
(そんなワケがあるか! 知ったかぶるな。お前に俺たちの何が解る!)
(解りはしません。でもね、わたしは羨ましいと思ってしまうんです)
(!?)
(言葉では語らなくとも、意識すらしていなかったとしても。自らの存在の全てを賭して、大切な人を生かし護ったアシェルさんを。わたしもそんな風に生きられたなら、どんなにか・・・・・・)
ずっと心に引っかかっていた。
と同時に怖れていた。
アシェルは俺の望みを叶えようとした。死を望んでやまない、俺の望みを。
だがそれは、アシェルにとって最もやりたくないことだった。冷たい冥闇の優しさを知り、闇の色に染まってなお、それを悲しいと思ってしまった。
だから、アシェルは魔物の力を望んだのか。
恨みと憎しみを理由とするために。
どうしてもカリムを殺さねばならないところに、自分自身を追い込むために。
だとしたら、アシェルの望みは。本当の望みは・・・・・・。
(今更・・・・・・そんなことが許されるものか!)
(どうして? 誰が許さないんです?)
(それは・・・・・・)
(もう、いいんじゃないですか? ここで自分を許してあげても。いえ、許しを求めるべきです。あなたがアシェルさんを大切に想うのなら、アシェルさんのためにも、そう努力すべきです。それが、断罪を求めるより、ずっと苦しいことだったとしても)
(・・・・・・!)
ふわりと、陰が溶ける。
(ああ、また言い忘れるところでした。ありがとう、カリム。あなたに会えて、本当に良かった。これは、わたしに出来る精一杯のお礼です。これがあなたの助けになるかどうかは、あなた次第ですが・・・・・・そうなることを願っています・・・・・・)
穏やかな気配すらも、空に溶けて消えていく。
(・・・・・・ありがとう、わたしのはね・・・・・・いままでずっと、いっしょにいてくれて・・・・・・)
ィィィィ・・・・・ン!
通り過ぎる景色の果て。
白い遺跡に一体だけ残されていた少女像が砕け散り、その核となっていた炎の結晶が、輝く火の粉となって飛び散った。その一つ一つから眩い光球が生まれ、再び凝集し朝日の如く輝いて。
光の中心に生じた高圧の力の源は、ビリビリとした波動を撒き散らしながら、一気に空へと駆け上がった。
封印を解かれ、数百年振りに自由を得た羽根が。
新たな主を得た歓喜に打ち震えながら。
「助けてあげて、カリム。イリィを、あの人を・・・・・・助けて、それからちゃんと戻って来ること。・・・・・・キミを殺すのは、他の誰かじゃない、このボクだけなんだから・・・・・・」
目の前に荒れ狂うのは、今はあの娘のものとなった羽根。
積極的に攻撃して来なくとも、最強の退魔具たる羽根の圧倒的な力は空間を揺るがす嵐となって、近付く者を打ち据える。
主の平安を乱す者は誰であろうと許さない、敵と見做して排除するぞ、と。
殺気立つ羽根の波動を全身に受けながら、カリムは一歩、足を踏み出す。
たったそれだけで、叩きつけられる重圧は数倍にも跳ね上がる。
それでも、また一歩。
羽根の向こうで心を閉ざしてしまった少女を、真っ直ぐに見据えながら、カリムはしっかりと歩を進める。
口元には、微かな笑みさえ浮かべながら。
もし俺がまた何かに対峙する時が来るとすれば、それは天軍か魔軍を相手に玉砕戦を挑む時だけだと思っていた。
人生何があるか分からない、か。好き勝手ばかり言うヤツだったが、それだけは認めていいかもな。
他人などどうでもいいと言い続けてきたこの俺が、よりにもよって人助けとはね。それも、今一番傍にいなきゃならない奴を置いてまで。
判っている。それがどんなに馬鹿なことか。
守護者は最後まで、この地を頼むとは言わなかった。それは、守護者自身がやらねばならないことであって、他人に望むことではなかったから。
それにアシェルだって。あの母娘を助けたいのは自分であって、俺に望むことではないのだと。
それはそうだろう。
羽根を手放した今の俺に、大した力は無い。
徒手空拳で暴走する羽根に挑むなど、無謀でしかない。
なのに二人を助けるだと? いっそ奇跡でも起きない限り、そんなことは不可能だ。きっと誰だってそう思う。明らかに能力のない者に、望む馬鹿などいはしない。
冷静に考えろ。
偶然出会っただけのものに、一体どれだけの価値がある?
比べるまでもない。この命はアシェルのためにこそ使うべきだ。
それこそが、正しい判断というものだ。
だが、いいのか、それで?
今まで塔に従い数多の命を切り捨てて来たのは何のためだ?
塔のためか? 世界のためか? 違うだろう?
ただ、彼女に会いたいと思ったからだ。彼女が存在するはずの世界を壊すわけにはいかなかったから。そのためには、自分の命を惜しまねばならなかったからだ。
もう、その必要は無くなった。
なのにまだ傍観を続けるか?
力が無いから。羽根が無いから。関係無いから。この命はアシェルの為のものだから。そんな言い訳で、僅かな時間を惜しむのか?
そんな命に、求められる資格があるとでも? そんなものを、俺はアシェルに差し出すつもりか?
その程度のものでしかないなら、惨めに滅びる方が似合いではないか。
なあ、アシェル。
俺の無謀を承知の上で、それでも、お前は望んでくれたな。
いつでも、お前だけが、力の器ではない欠陥だらけの俺をそのまま認めてくれた。
もしも許されるのなら、俺は、最期の一瞬まで、お前に応えられる俺でありたい。
そのために奇跡が必要だというのなら、今、この瞬間に、その奇跡を起こしてやる。
そしてきっと、お前の元に戻って見せる。出来ないはずなどあるものか。
だって、そうだろう。
一番の奇跡はもう、お前がくれた。
失ってしまった者と再び巡り会えることは、どれほど望んだとしても、決して叶うはずのない奇跡。
お前こそが、この世界で最高の奇跡。
目の前に、羽根の生み出す風壁の先に、心を手放した少女の姿が浮かんでいる。
もう少し。あと、もう少しで手が届く・・・・・・。
その瞬間、無数の羽根が、カリムの身体を貫いた。
第28話 嵐の中
一斉に牙を剥く羽根の刃、その全てを躱し切ることは不可能だった。
切り裂かれた四肢から、ぱっと赤い飛沫が飛び散る。
肩口を貫いた鋭い痛みに、カリムはギクリとして目を見開く。
傷を押さえた手の平に、べっとりとした感触。ぬるりとしてものが腕を伝って滴り落ちる。
だが、カリムの視線は真っ直ぐ前に向けられたまま、微動だにしない。
そこには先刻と寸分変わらない、心をどこかに置き忘れたまま立ち尽くしている、イリィの姿がある。
(大丈夫・・・・・・)
カリムは詰めていた息を吐き出す。その口元が、ハッキリと笑みを刻む。
(大丈夫だ。あの娘は無事でいる。傷ついたりなどしていない)
ここにはもう、誰彼構わず襲い掛かるような凶悪な羽根は存在しない。
羽根は普通、羽根使いが敢えて命じない限り、人間を標的にすることはない。
だが、完全に攻撃型に特化したカリムの羽根に、その常識は当てはまらない。
常に大振りな曲刀の形状に具現した状態にある羽根は、その外見に違わず、カリムが少しでも気を抜こうものなら簡単に手綱を振り切ってしまいかねない獰猛さを秘めている。
普段は抑えていられるが、ひとたびカリムが攻撃を受けようものなら、その猛り方は凄まじい。獲物を求める猛禽のように、喜々として躊躇なく、敵を定めて襲い掛かる。
相手が魔物だろうが、人間だろうが、同じ羽根使いだろうが、そんなことには一切構わず。
カリムのものでありながら、カリムの意志などまるで顧みもしない。
道具と呼ぶには、あまりに凶悪な力。
(だが、あんなものはとっくに捨てた。もう何も心配ない。なのに・・・・・・)
カリムの表情から安堵の笑みが消える。そして、感情の伺えない硬質なものへと。
(・・・・・・気分悪ぃ。未だに俺は、それを一番に案じるのか? それじゃまるで、羽根に何かを期待してるみたいだろ! 冗談じゃない、全く、冗談じゃないぞ!)
『・・・・・・ありがとう、わたしのはね・・・・・・いままでずっと、いっしょにいてくれて・・・・・・』
カリムの脳裏に、守護者の声が甦る。
「全く、冗談じゃない。その羽根こそが、お前を・・・・・・!」
吐き捨て、カリムは拳を握り込む。
ここで激昂するわけにはいかない。
暴走する羽根の支配する空間で、敵意を顕わにすることは自滅行為だ。
だが。
「どうした・・・・・・何故二撃目を放って来ない?」
主の支配を離れ、主を取られまいと攻撃に転じた羽根に対し、カリムは僅かにも退いてはいない。気が挫けたわけでもない。
それなのに、威嚇から攻撃に出ておきながら、畳み掛けもせず遠巻きにするなど。
まるで、カリムを傷つけてしまったことに、戸惑ってでもいるかのように。
「だったら、大人しく主を放せ。そうしたところで、別にお前から引き離そうってわけじゃない」
と、言って通じるものでもないだろう。何か、別の角度から仕掛けてくるつもりか。
警戒しつつも、カリムは再びイリィの方へ、圧し潰されそうなほどの呪圧の源へ向かって、その手を伸ばす。
直後、あらぬ方向からの突風が、カリムとイリィとの間を駆け抜けた。
「!?」
咄嗟に身構えたカリムだが、それ以上何かが起こる様子はない。少なくとも直接攻撃はなさそうだ。
目の前のイリィの姿も、変わらない。
いや。
目に見えているものは同じだが、先刻までとは決定的に何かが違う。奇妙な、違和感。
「・・・・・・やってくれる」
イリィの姿に、実体としての存在感が伴っていない。
イリィの気配自体が消えたわけではなく、羽根の支配するこの空間の、遠く、近く、強く、弱く、灯っては消える蛍火のように、頼りなく曖昧に。
しかも、アシェルがイリィに持たせた目印の気配までもが、見事に消え去っている。
「隠れんぼのつもりかよ。ったく面倒なことを」
ウンザリと、カリムはつぶやく。
羽根がやっていること自体は単純だが、直接攻撃を受けるよりも、ある意味ずっと厄介だ。
「諦めて去れ、というわけか。まさかそれで通るとでも?」
カリムの蒼い瞳が、挑戦的に細められる。
腕の先から伝い落ちた赤い滴が、地に届く前に風に煽られて、何処かへと舞い散った。
息を詰めてカリムとイリィの様子を見守っていたアシェルは、ふと、自分の周りを探るように見回した。
「風の吹き方が変わった?」
強風の合間にほんの僅か、風が途切れる瞬間がある。
「羽根が起こしてる風だもんね。カリムに気を取られて、他まで気が回らなくなったかな? ・・・・・・今なら! イリィのお母さんの所まで行けるかも。あんな羽根の近くにいたんじゃ、いつまた危なくなるか判らないもんね!」
一つ大きく頷くと、アシェルは風の止むタイミングを見計らいながら、ぐったりと倒れ伏している女性に向かって、そろりそろりと慎重に移動し始めた。
アシェルの思った通り。カリムがイリィに近付くにつれて、風のうねりは更に不規則に、そして間断の差も大きくなっていく。
「でも、羽根が動揺なんかするのかな? 暴走ってのは、カンシャク起こした子供みたいなモンでしょ? 気が治まるまでとにかく暴てやる、みたいなさ? それともイリィちゃんの意識が戻り始めてるとか? だったらいいんだけど・・・・・・」
祈るような目で見守る中、カリムはゆっくりと、だが確実にイリィとの距離を詰めていく。カリムの髪が、荒れ狂う風を受けて激しく波打っている。
普通の人間であれば立ってもいられないだろう空間で、真っ向勝負を挑みつつも、羽根から受ける呪圧を可能な限り受け流している。それは羽根の特性を熟知した者にしか出来ない芸当だ。
「がんばれ! あとちょっと!」
思わず呟いた、次の瞬間。
アシェルとカリム達の間を分断するように、逆方向からの突風が駆け抜けた。
たまらず両手で顔を庇い、固く目を閉ざしてやり過ごしたアシェルが、次に頭を上げた時。
「カリム! イリィ!?」
二人の姿が無い。見えない。
嵐の中心に濃い霧の柱のようなものが出現し、二人の姿はその奥に飲み込まれてしまっている。
「羽根の状態が変化した!? やっぱり、ただの暴走じゃないってこと? カリム!」
最強の退魔法具の直接攻撃にあえば、羽根を持たないカリムになすすべはない。羽根は、炎の結晶を破壊出来る。
「待っててカリム、今・・・・・・」
咄嗟に両手を伸ばして空間に干渉しようとしたアシェルは、すんでのところでそれを思い留まった。
「ううん、カリムはそう簡単にどうにかされたりしない。羽根だって全力で攻撃するつもりなら、こんなまどろこしいことはしないはず。それに、イリィはカリムのことが・・・・・・だから、イリィの羽根が簡単にカリムを殺そうとなんて、するはずがない・・・・・・」
アシェルは両手を胸の前で強く強く握り込んだ。
「カリムは任せろって言った。なのにボクが、今、闇雲に手を出したりしたら・・・・・・カリムを邪魔しちゃうことになる」
イリィにはもう時間が無い。一刻も早く羽根を抑えなければ、その命に深刻なダメージを残してしまう。魔物の力を持つアシェルが不用意なことをすれば、それだけイリィの羽根を刺激してしまう。
「カリムはきっと、全力でイリィを助けようとしてる。諦めて引き下がろうなんて、考えようともしないんだ。だから、ボクが足を引っ張るわけにはいかない・・・・・・いかないけど!」
アシェルはキッと顔を上げた。
「そう長くは待たないよ! 言ったよね? ボクはもう絶対に、キミをただ見送るなんてしないんだから! 邪魔になろうが知るもんか! ボクがカリムとイリィを探してやるんだ!」
決意も新たに、アシェルは前を見据える。
「まず、イリィのお母さんを助ける、それからだ!」
逆巻く風は、まだ治まる気配を見せない。
(っざけんあよ、あン野郎ぉぉぉーっ!)
そんな内心の怒声をおくびにも出さず、フェグダは精一杯の愛想笑いを顔に貼り付かせて立っていた。
ざわめく村人達を前にして。
「あのぉ、俺はアヤシイ者じゃありませんから。本当に、決して、」
だが、数歩分離れてフェグダを取り囲んでいる村人達の目は、あからさまな不信感にあふれている。
それも無理はない。
何の前触れも無しに村を襲った激しい嵐に、広場で祭りの準備の最中だった村人らは、村で一番大きな建物である聖堂兼寄合所に緊急避難してきたところだった。
窓という窓を閉めて戸締りしてやれやれと一息ついたそこに、見も知らない他所者が混じっていたとなれば、警戒して当たり前。
この状況を考えれば、村に災厄を呼び込んだ張本人として吊し上げられたって文句は言えない。むしろ暴風の中に無情に放り出される程度で済めば御の字。そんな一触即発の、緊迫感に満ち満ちた場面である。
(それもこれもあれもどれも! 全部あの野郎のせいだってーのに、ヒトのこと放っぽり出して一体どこ行きやがった! てか、俺に何しやがったんだよ?)
そう。ほんの一瞬前まで、フェグダは村を見下ろす丘の上にいた。
何だかんだあったものの、厄介な瘴気もサッパリ晴れて、呑気なほどに穏やかな昼下がりの日の下。
ところがだ。
護符の回収も終わってやれやれと思った時、妙な緊迫感を伴う風が吹き抜けた。
その直後にあの野郎がいきなりフラッと前のめりに倒れかけて、思わず手を差し伸べちまいそうになって、待てよそんな義理ねーだろと思い直したところに、引っ込め損ねた腕をあの野郎に掴まれて、思いっきり強く引っ張られて、逆にこっちが転びそうになってたたらを踏んで、何とか踏み止まって、盛大に文句言ってやろうと目を上げたら、そこは何と村のド真ん中の広場で、あの野郎はきれいサッパリ掻き消えていて、しかもいきなりドバーッと強風が襲って来て、考える間もなく駆け出した村人達の後について飛び込んだのが、ここ。
閉まりかけた扉越しに、広場に組んであった櫓がバラバラになって吹き飛ばされるのが見えたから、本当にギリギリセーフだ。
胸を撫で下ろしたところで、近くにいたチビが『誰だコイツ!』とフェグダを指さして大声を上げた。
そして、現在に至る。
村人達の視線の集中砲火を浴びながら。
(やめてくれねーかな、もう! 状況聞きてーのはこっちだっての! いや、待てよ? この妙に羽根が絡んでるっぽい怪しさ満点の嵐は、もしかして村に着いた時に一瞬感じた、あの羽根のもんじゃねーのか? 先刻消し飛ばした瘴気にしたって、本体倒したワケじゃねーし。ってことは、やっぱりあの野郎が絡んでやがるんじゃねーか! つまり、俺を足止めするためにワザとこんなトコに放り出しやがったんだな! 今度会ったら覚えてろよ!)
「おいテメー! どこの何者で何しに来やがった!? ヘラヘラしてねーでとっとと喋りやがれ!」
微妙な膠着状態を破ったのは、村人の輪から飛び出して来た少年の、威勢のいい啖呵だった。
「こ、これ止めなさいコリオ!」
無鉄砲な少年を慌てて制したのは、目が細くて恰幅のいい中年オヤジだ。
「何だよ村長! 居るんならノンビリ見てないでちゃんと仕事しろってんだ!」
少年を睨みつけてから、その男はオホンと一つ咳払い。
それを合図に、コリオと呼ばれた少年は、いかにも農作業で鍛えましたといった風体の男らによって、ぽいっと後ろにつまみ出される。
「何しやがんだクソオヤジ!」という少年の抗議は、あっさりと無視される。
少年に代わって村人の輪の前に出た肉体派の男らは、村長の号令一下、不審者をつまみ出す気満々だ。
応援を得た中年オヤジは、満足そうな笑みとともに、フェグダの方に向き直る。居丈高に。
「失礼した。私は村長のオーリーという者だが、」
「おお、あなたが村長殿か! これは丁度良い!」
演説をぶとうとする村長を遠慮なく遮って、フェグダは芝居がかった声を上げた。
(こーなりゃヤケクソだ!)
腹を括ったフェグダは、大仰な仕草で一同を見回す。
「いきなりの来訪により、皆を騒がせたことを詫びる。私はフェグダ・ノル。白亜の塔より遣わされし者だ!」
権威とは、利用したい時に利用するために存在する。
ついでに、証拠にと掲げてみせた身分証のメダルは、正真正銘本物だ。小さな村の村長であれば、身分証の意味くらいは聞いたことがあるはずだ。実物を見るのは初めてかも知れないが。
「こ、これは! では貴方は白亜の塔から降臨なされた天使様であらせますか!?」
思わぬ急展開に、シンと呆けた空気の中で、それでも一番に立ち直ったのは、細い目をピクピクさせた恰幅のいい男だった。
村長の名は伊達ではないらしい。権威に敏感だという意味で。
「天使様だって!?」
村人らのヒソヒソとしたざわめきは、やがておおーというどよめきに変わる。
「う、うむ。偶然この地に立ち寄ったところ、この嵐に遭遇した。これは自然に発生したものではない、何らかの呪術によって起こされたものだ。誰か、この原因に心当たりのある者はおらぬか?」
「おお! 何と!」
「では貴方様は、この地の災いを除きにおいで下さったのですね!」
「ありがとうございます天使様!」
「え? いや、誰もそこまで言ってねーし」
一足飛びに進んだ話に、訂正を試みようとするフェグダだが、どうやらもう手遅れのようだ。
「聞いたかみんな! 白亜の塔の天使様が、我々を救いに来て下されたぞーっ!」
たちまちわああっという歓声が上がり、遠巻きの警戒モードから一転、フェグダは押し寄せる村人たちに完全に取り囲まれた。
彼らの目はキラキラと眩しいほどの期待に輝いている。
「あー、いや、もー、とりあえず何が起こってるのか、説明出来るヤツ誰かいないか?」
こうなればヤケクソついでだ。
フェグダは村人達を落ち着かせるように両手を上げると、改めて全員をぐるりと見回す。
「はい、天使様! 実は・・・・・・」
と、誰かが口を開いた、その時だ。
「あー!」
村人たちの後方で大声を上げたのは、先刻一番にフェグダに詰め寄ってきた、コリオという名の少年だ。
「どこだジーロ返事しろ! おい誰か! ジーロ見てないか!?」
一同ざわりと辺りを見回し、
「いないぞ!」
「まさか、逃げ遅れたのかい?」
「この嵐の中で・・・・・・」
ざわめきの中、閉ざした扉や窓のみならず、建物全体がぎしぎし揺れる。いかにも不吉といった様子で。
示し合わせたように、人々の目が一斉にフェグダに注がれる。
「・・・・・・だから、何がどうしたって?」
諦めたように両手を上て、フェグダは少年の方を見やった。
「で、そのジーロって子供が、この嵐の中に出てったって?」
「きっとイリィんとこに行ったんだ! あいつ、イリィのことになると見境ないから、いつもみたいに軽い気持ちで・・・・・・おいお前ら放せよっ! 早く探しに行ってやらなきゃならねんだから!」
「何、出て行こうとしてるんだよ!」
「無茶だよコリオ! 嵐相手にスゴんだって通じねーよ!」
威勢の良いコリオだが、仲間と思しき少年二人と、加勢に入った筋肉オヤジに力いっぱい押さえつけられては、さすがに逃れようがない。
「いいから放せよクソオヤジ!」
「いやダメだ! ジーロは俺が探しに行く!」
「だったら俺も行く!」
「そんなワケにいくか! お前にもしものことがあったら母ちゃんに言い訳が立たねえ!」
「何ハズカシイこと言ってやがんだコラ!」
(ったく、何なんだ、この三文芝居は。美しき家族愛ってか?)
イラつく気分を顔に出さないよう努力しつつ、フェグダは思考を切り替える。
そうだ、そんなことよりも。
「おいお前、イリィって言ったか?」
「あ? ああ・・・・・・」
それはつい先刻、遺跡まで(結果的に)案内してくれた少女の名だったはず。
しかも、少年がその名を出した途端、村人たちの雰囲気がぎこちないものに変わった気がする。
「そのイリィって娘に何かあるのか?」
それに対して、村人たちは一様にシンと黙り込み、村長へと視線を向ける。
「・・・・・・それは、あの、村はずれの小屋に住まう、憐れな境遇の娘でして、その・・・・・・」
仕方なさそうに口を開いた村長も、すぐに言葉を濁してしまう。
フェグダが村人達を見回せば、今度は誰もがきまり悪そうに目を逸らす。
彼らの態度に見え隠れするのは、怒りと、恐れと、何よりも強い罪悪感・・・・・・。
それは、フェグダの知らぬものではなかった。
「つまり、この嵐の原因はその子かも知れない、と言いたいわけだな」
「・・・・・・」
フェグダの問いに対し、言葉を発する者は一人もいない。が、それ自体が何より明白な答えだ。
(通りで。村の案内を拒否るワケだ)
あの時の少女の何とも言えない困惑顔が、フェグダの脳裏に蘇る。
村という集団の中で、一人。
それは誰もいないところで一人でいるよりも、はるかに孤独だ。そう言ったところで、経験したことのない者には、決して解らないだろう。
(それより! これにあの野郎が関わってるとなると、イリィちゃんが羽根使いってことでガチだよな。なのにどうして塔の天使だって判ってる俺が邪魔にされるんだよ? あの野郎、ホントに塔を裏切ったってのか? じゃあ、一体何やろーとしてやがるんだ? それってもしかして・・・・・・! おいおいおい! こんなトコでノンビリ静観してる場合じゃねーぞ!?)
ぐるぐる思考を巡らせたフェグダは、一つの結論に達してキッと顔を上げる。
ちょうどいい口実もある。
「わかった! そのジーロって子供は、俺が探して来てやるよ!」
その途端、シンとしたままフェグダを見ていた村人達は、待ってましたとばかりにおおーっとどよめいた。
虫がいいと言うか、何と言うか。
(・・・・・・ま、いいけど、こー、何だかなー)
村人らの為に行くわけではないとはいえ、軽く脱力気分に陥ってしまいそうなフェグダである。
「待ってくれ! 俺も行く!」
村人のどよめきに負けない大声で主張したのは、少年らを蹴倒し、オヤジに一発食らわして羽交い絞めを振り切ったコリオだった。
「ジーロもだけど、イリィのことも放って置けない! 他の奴らはイリィのことなんか気にも止めやしねーんだ。だから俺が行かないと! それにあんた、道案内がいねーとイリィの家がどこだかも判らねーだろ!」
(意外とモノ考えてるんだな、コイツ・・・・・・)
騒がしいだけかと思いきや。真剣そのもののコリオを、フェグダはちょっと見直した。
が、それとこれとは別の話。
「では、こっちに来い。お前にはやってもらいたいことがある」
「おう!」
勇んでフェグダの前へとやって来たコリオは、大暴れしたせいであちこちボロボロになっていた。
「これを部屋の四隅に置いて来い」
と、フェエグダが手渡したのは、先刻の瘴気騒ぎで破損を免れた分の護符だ。
「・・・・・・あ?」
「この建物全体に結界を張る。俺が外に出ても、建物が壊れないようにする為だ」
「よし解った!・・・・・・これでいいか?」
コリオが教会堂の四隅を回っている間に、フェグダは手近な村人に燭台を持って来させた。
「さて、お前に重大な任務を与える。結界が崩れないよう、この蝋燭の火を見張れ」
「な!? 話が違うぞ! 連れてってくれるんじゃねーのかよ!」
当たり前だ。
酔狂にも羽根絡みだと予想出来る嵐の中に突っ込もうと言うのだ。自分一人でも十分危ないというのに、他人を守りながらなどキッパリごめんである。
「あー、言っておくが、俺が出てってからドアだろうが窓だろうが、ちょっとでも開ければ即、結界は崩れる。それで建物が壊れてみろ、こにいる全員、どうなっても知らないからそのつもりでな!」
フェグダはバシッと宣言して、不満そうなコリオを黙らせる。
村人全員の安全がかかっているとなれば、いくらコリオが無鉄砲でも、そうそう下手なマネは出来ないだろうし、馬鹿をしでかそうにも村人達が全力で阻止するだろう。
「ありがとうございます天使様。ジーロのことをどうかよろしくお願いいたします! そしてきっと、この村をお救い下さい!」
ハッキリ言って、こんな村がどうなろうと、知ったことではないのだが。
「お願いします、天使様!」
「・・・・・・もちろん! 俺に任せておくが良い!」
ムサい連中のかわりにすすすっと進み出て来たカワイイ女の子たちに期待のうるうる目で見つめられるのは、まんざらでもなかった。
「チクショ。頭がガンッガンする・・・・・・」
いつの間にか風は凪ぎ、辺りには濃い霧が立ち込めていた。さら雪を細かくしたような、濃密な白い霧。その微細な一片一片が羽根の具現であり、敵意も顕わなその中に身を置くことは、肉体を苛まれる以上に精神をギリギリと圧迫される。
嫌なものを全て振り払いたい気分で悪態をついたカリムだが、もちろんそんなことが出来るはずもない。
(どこだ、どこにいる?)
地面を踏んでいる感覚はあるのだから、異空間に放り込まれるまでには至っていないはず。
だが、他者の羽根の支配が優勢なこの状況で感覚を解放することは、神経を炙られるような苦痛を強いられる。
それにも増して、感覚の先に触れるイリィの気配は、捉えたと思った瞬間には忽然と消失し、全く別の所に再び出現する。それが囮であることは判っていても、集中をかき乱す効果は十分だった。
らちの開かぬ状況に、じりじりとした焦燥感だけが募る。
(これだけ探して目印すら見えないってのは・・・・・・)
あの髪留めの赤い石はカリムにとっては目印だが、それ自体に何らかの呪力が込められているわけでもなければ、他者にとって呪的な利用価値があるわけでもない。
そんなものに、羽根が警戒を払ったとも思えない。
(あの娘を別次元に切り離して封じでもしたか? まさか、主を得たばかりでマトモな発現も覚束ない羽根に、そんな器用なマネが出来るものか? だが、このままではこっちが消耗するだけだ。何か他に、道を探る目当てになるものは・・・・・・)
と言っても、昨日会ったばかりで良く知りもしない少女のこと。早々いい手が浮かぶわけもない。
(まだ、試していない方法・・・・・・)
一つ、ある。
今となっては、それも多分に不可能に近いことだが。
試してみることだけは、可能な方法が。
羽根があれば・・・・・・こんな空間など一撃で粉砕出来る。その上で、イリィを見つけて、正気付かせて。それでも暴走が治まらないなら、強引にでも干渉してねじ伏せる。
たったそれだけの、簡単なことだ。
イリィの身に多少のダメージはあるだろうが、命を丸々削られるのに比べればずっとマシ。
羽根を、呼び戻しさえすれば。
『・・・・・・ありがとう、わたしのはね・・・・・・いままでずっと、いっしょにいてくれて・・・・・・』
繰り返し脳裏に甦る、守護者の最期の心の声。
不意に、ズキリと胸中に走った痛みに、カリムは溜まらず膝を折った。
鼓動が早鐘を打ち、耐え難い息苦しさが襲い掛かる。
(・・・・・・これは怒り、憤りの感情なのか? 何故そんなものを、この期に及んで・・・・・・)
羽根とは何か?
何のために、存在するのか?
第29話 羽根
「ジーロっつったか。まさか、こんな所まで来てたなんてなあ」
半ば感心、半ば呆れた気分でフェグダは、木にしがみついた格好で気を失っている少年を見やる。
ここはもうほとんど村はずれ。
フェグダが当たりを付けた羽根の暴走地点の、目と鼻の先だ。
「よっぽど、イリィちゃんが心配だったんだな」
だが、ここから広場に面した小屋までジーロを連れ帰るには、少々手間だ。
ざっと見たところ、かすり傷以上の怪我は無さそうだし。
「俺もあんまモタモタしてるワケにはいかねーから・・・・・・悪いな、また後で」
フェグダはジーロの周りに簡易結界を張ると、すぐにその場を離れた。
これでも一応天使なのだから、暴走する羽根をそのままにしておくわけにもいかない。それ以上に気になるのは、おそらくあの場に居るだろう、災厄の天使に似た少年のこと。
「あれが本当に災厄の天使なら、こんな暴走くらいソッコー抑えられるはず・・・・・・それとも別の何かを企んでやがるのか・・・・・」
どちらにせよ、是非ともこの目で確かめておきたい。
油断すれば吹き飛ばされかねない強風の合間を縫って、最後の起伏を越えた直後、半壊状態の小屋と、さらに岬に続く小道の果てに暴風の中心である竜巻状の風柱が目に飛び込んで来た。
その時だ。
「遅い!」
「あ!?」
その妙に高音の声が怒鳴りつけた相手が、誰でもない自分であると知って、フェグダは少なからず驚愕する。
竜巻からほど近い地面に倒れ伏している老婆。そして、その脇で手招きするように身を乗り出している小さな、人間ではありえないくらい小さな赤毛の妖精っぽい生き物。
「な、誰だお前は!?」
「そんなこと、今はどーでもいいの! こっち来て手伝って! 早く!」
いや、どーでも良くはないだろう、と口の中でブツブツ言いながら、フェグダは前進を再開する。
とりあえず緊急事態であることだけは確かだったし。
(にしても、どーしてこー誰も彼も、人をパシリ扱いするかなあ・・・・・・)
妖精モドキは、遮蔽物が全く無くなったこともあって、苦労しながら近付いたフェグダに向かって。
「彼女を安全なトコまで運んで! 超特急!」
「ああ、まあ、それはいいんだが、アレをどうにかするのが先だろ?」
フェグダが指し示したのは、もちろん妙な竜巻の方。
渦巻く風の中心がどうなっているかは見えないが、羽根を暴走させた羽根使いがいるのなら、まず間違いなくそこだろう。
フェグダが羽根を最大限に発現させれば、相手の力の影響を受けることなく、竜巻の中に入ることは可能だ。ただし、先刻力を使い過ぎたばかりなので、正直少々キツいのだが。
「キミは来なくていいの! 手助けにはボクが行くんだから!」
「手助け? イリィちゃんの・・・・・・それともあの野郎のことか? ・・・・・・お前もしかして、あの時遺跡にいた奴か!? それより、これは・・・・・・魔気?」
赤毛の妖精モドキは、不機嫌そうな緑の瞳でフェグダを見る。
「だったら何?」
「お前、魔物の類か!? 羽根を暴走させたってことは、それなりの事態が起こったってことだよな。お前ら、イリィちゃんに何をした!」
「ったく、そん場合じゃないってのに!」
両者の間に火花の飛びそうな緊張が走った。
(邪魔だな・・・・・・)
目の前に立ち塞がり、感覚を掻き乱す羽根が。思い出したように時折襲ってくる攻撃が。
苛立ち、憤り、焦り・・・・・。そんな感情に支配されることこそが羽根の狙いなのだから、それに乗るわけにはいかない。解ってはいるのだが。
『邪魔ってキミさぁ、そんな呑気なことを言ってる場合? 自分が危ないことやってるって自覚あるの? もうちょっと真剣に怖がったらどうなのさ!』
もし、この場にアシェルがいたならば、こんなことを言っただろうか。
遠慮なく叱りつけてくる顔を思い浮かべて、カリムは少し肩の力を抜く。
そんな台詞を度々聞かされるくらい、離宮にいた当時のカリムには、怖いということが実感出来ていなかったのかも知れない。
だが、恐怖することを知った今でも、他者の羽根を怖いとは思わない。
対抗する手段を失くしていてさえ、不思議とそのような感情は湧いて来ない。
羽根だけに限らず、今ここに高位の魔物や、魔剣や神剣の類のような、一撃で炎の結晶を破壊するような脅威が出現したとしても、それに恐怖はしないだろう。
死に安らぎを感じる心がある限り、死をもたらすものに恐怖を覚えることはない。きっと、そういうことなのだろう。
脅威を前に思うのは、むしろ、ありったけの力を叩きつけて自分と相対することが愚かな行為だと知らしめたい、そんな単純な破壊衝動だ。
その衝動は、あながち間違いという訳でもない。実際、ここに自分の羽根があれば、こんな暴走などすぐにでも止められるのは事実なのだから。
一時しのぎという意味では、だが。
結局のところ、羽根に選ばれた人間は、自分の心にケリをつけない限り、常に暴走の危険を抱えることになる。
そして、羽根使いになることを拒否し続ければ・・・・・・待っているのは、羽根と共に消滅する運命。
羽根とは、そういうものだ。
勝手に憑りつく人間を選び、強引に力を押し付け、運命を受け入れることを強要し、それ以外の生き方を決して許さず、心までも屈服させる。
すぐ傍にありながら、この世界とは異質な強大過ぎる力を内包した、人間の智など遠く及ばない、得体の知れない、何か。
羽根に選ばれた者が何を思おうと。あるいは塔の連中が何を考え、どれほど研究し、どんな技術を編み出そうと。そんな人間の努力など全く意に介することなく、羽根はただ、そういう存在として在り続けるだけ。
羽根使いが限界を迎える、その時まで。
そんなものを受け入れない限り、イリィはこの先、生きてはいられない。
特別など望まないと言い切った、あの娘は。
羽根とは何か?
何のために、存在するのか?
そんなことは知らない。
知る必要もない。
むしろ、羽根など要らないと、この世界から消え去ってしまえばいいと思う。
魔物など知ったことか。塔も、世界も、どうだっていい。
そう考えて、何が悪い?
いっそ羽根だけを消滅させてしまえるなら、それがどんな方法だろうと躊躇いはしないものを。
(だが、それは俺が気にしてやることじゃない。どうせ、俺が手を貸せるのはこの一回きり。どんな決断であろうと、後は本人が決めることだ。あの娘だって、いずれは全てを受け入れるに決まっている。・・・・・・あの、守護者のように)
『・・・・・・ありがとう、わたしのはね・・・・・・いままでずっと、いっしょにいてくれて・・・・・・』
じわりと湧き上がる怒りの感情。押し殺しても無視しようとしても、何度も、何度でも。
「本当に、それがお前の本心だったのかよ!?」
ついにカリムは、激しく叩きつけた。もう存在しない相手に、その言葉を。
今まで、数多の羽根使いを見送って来た。
徹底的に羽根を拒絶した者もいれば、羽根に全てを捧げるほど愛していた者がいた。共にあるのが自然なことなのだと、飄々としていた者もいた。
どんな風に羽根と出会い、受け入れ、あるいは拒絶し、そのことについて割り切っていたのか、納得し切れず悩みつづけていたのか。
其々が其々に、思い惑いながら、羽根使いとしての人生を生き切った者たちがいた。
その名も、姿形も、とっくに定かではなくなった。ほんの一瞬すれ違う以上の、何かを共有したわけでもなかった。そんな彼らの何かを語る資格が、自分にあるとも思わない。
だが、一つだけ。
どれほど拒絶しようとも、憎もうとも、目を逸らそうとも、実際に羽根を無視してしまえた者など、きっと一人としていなかった。
どんなに愛しながらも、どれほど憎みながらも。どれほど短いものだったとしても、他者からはどれほど馬鹿げたものに見えたとしても。彼らは羽根と共に生き、羽根と共に滅びて行った。
自ら選んだものであろうと、戦いの中で散ったのであろうと、羽根使いとしての力が尽きてその時を迎えたのであろうと、最期の時を、自らの羽根と共に。
シャリィィィィ・・・・・ン・・・・・・
まだ、聞こえる。
全てを震わせ、どこまでも広がっていく響き。遠い残響。
『ありがとう・・・・・・そしてすまない・・・・・・それでも君以外、頼める者がいなかったんだ・・・・・・』
黒く染まりかけていた結晶が砕け散る音と共に、すぐ耳元で聞こえた声。蒼空の天使と呼ばれた者の、最期の言葉。
『ジェレミオと言うんだ。それが、僕の本当の名だ・・・・・・けれど、覚えておく必要はない。他の全てと共に、忘れてしまっていい・・・・・・。君は、反逆者と戦って、やむなく結晶を破壊した。ただ、それだけのことだ・・・・・・』
『どうして・・・・・・!』
『さあ・・・・・・それは僕にもわからない・・・・・・ただ、これしか思いつかなかった・・・・・・だから、僕は今、満足しているんだよ。そう、きっと、これでいい・・・・・・』
残響の中、淡く溶けていく蒼空の羽根。
これは、記憶。
蒼空の魔法によって封じられていた、事実の記録。
それは手を下した者に対する、彼なりの思いやりだったのか。あるいは、最期の記憶の共有を望まなかった故なのか。術をかけるまでもなく、その時の想いを留めておくなどカリムには出来はしない。彼と同じく、結晶に封じられた命を持つカリムには・・・・・・。
脳裏に真っ白な閃光が走る。
圧倒的な力で全てを飲み込み灼き尽くす真っ白な闇の中に、溶け落ちていく無数の人影。
空しく伸ばされる、大きな傷を刻んだ手・・・・・・。
繰り返し繰り返し甦る、戦慄の一瞬。届くことのない夢幻。
あの光景が羽根の暴走によるものだとしたら、それを引き起こしたのは何なのか。誰で、あったのか。
あれがカリムとなる以前の自分の、最期の瞬間だったのなら、あの時起こったことは・・・・・・。
それでも、なお、魅かれずにはいられない。
暴力的なまでに魅了する、強く鮮やかな、自分だけの輝き。
この世界の何よりも醜く、美しいもの。
いるはずがないのだ。
羽根を無視してしまえる人間など。
炎の結晶と同化した命を与えられ、人間とは違ったものに変えられてさえ。人間として生を受けた存在である以上、羽根という人智を超えた至高の輝きから目を逸らすなど、不可能なことなのだ。
だからこそ、嫌った。心底憎んだ。
羽根などこの世界に存在しなければいいと、本気で思った。
始めから存在しなければ、どうしても羽根を無視することの出来ない自分に、気付かされることもなかったのだから。
『・・・・・・ありがとう、わたしのはね・・・・・・いままでずっと、いっしょにいてくれて・・・・・・』
(お前は、それで良かったのか?)
何度も甦る響。
応える相手を失ってなお、どうしても問わずにはいられない問いかけ。
守護者と、仮に称していたあの存在は、もうとっくに人間ではなかった。
気の遠くなるほどの年月を、自らの羽根とともに結晶の内に封じられ、この世に繋ぎとめられた存在。
人間であった時の思い出も、感情も、考えるということさえも、遥か彼方へと置き去りにして。
何もかもを、あるがままに受け入れて。
存在をまるごと、人間ではないものに昇華させて。
だが、それでも、問わずにはいられない。
本当に許せるのか、と。
本当に平気なのか、と。
自らの羽根によって砕かれることが、ではない。
もしも、自らの羽根によって滅びることが可能だったなら、ジェレミオは進んでその手段を選んだはずだ。
自分と羽根との間に他者を入れずに済むのなら、カリムに願う必要など、どこにも無かった。
俺であれば、きっと、そうする。
だから、問いたいのはたった一つ。
自分だけのものであるはずの羽根が、他者の元へと渡る光景を目の当たりにして。どうして納得出来たのか。どうして平静でいられたのか。どうして許すことが出来たのか。
あの言葉は、本心からのものなのか。
人間ではない存在になれば、それすらもどうでも良くなってしまうのか。
それは、自分という存在が、無に成り果てるに等しい。
解っている。
羽根との関わりは、羽根使いだけのもの。守護者が羽根をどうしようと、それは守護者だけの問題だ。そこに他者が介入する余地は無い。
だから、これはただの願望だ。相手の中に、勝手に自分の好ましいものだけを見る、そういう類の願望に過ぎないものだ。
では、どこにやればいい?
この、やりきれぬと感じる心は?
消えるのを待つだけなのか?
いつものように、二度と戻らぬ彼方へ消え去るのを、ただ待つだけなのか?
(もしも・・・・・・そうではないとしたら?)
カリムの心の内で、何かが、瞬いた。
それはあまりにも楽観的な希望。
笑ってしまうほど、ご都合主義な期待。
今まで、全く顧みることなく切り捨ててしまってきた、可能性。
(純化に純化を重ねた透明な炎・・・・・・俺の結晶に何の不自然無く共鳴するほどに・・・・・・)
その共振故に伝わった意志。呼び起された心。それは、本来の守護者ではなく、模擬人格のようなものだったのかも知れない。
だが、守護者に影響を与えたのは、それだけだったのか?
明確な共鳴ではなくとも、小さな揺らぎのように、緩やかに穏やかに、影響を与え合う存在があったのだとしたら?
例えば羽根を介することで、イリィと守護者は、互いに影響しあっていたのではないか?
だからこそ、そこに矛盾が無かったとは言えないか?
羽根が渡った先が、自らの分身のような存在だったから。両者の魂に明確な区別が存在しなかったから、守護者は全てを受け入れ消え去ったのだと、そんな風には考えられないか?
(だとしたら・・・・・・俺は既に、お前の心に出会っていたことになる。それが、イリィ、お前を探す手掛かりだ・・・・・・)
「ここにいたのか」
何も無い空間で、少女はじっと、自分の手を見つめていた。膝を抱えて、うずくまって。俯いた顔の前に、小さく開いた両手の平を、穴が開くほど食入るように。
「何を見ている? それとも、何が見たいんだ?」
「・・・・・・どうしてなんでしょう」
消え入りそうな小さな声。だが確かな応え。それは、他者を完全に拒絶してはいない証。
「どうして・・・・・・こんなに痛いのに、どこにも怪我が無いなんて・・・・・・本当に、傷一つ、見えないなんて・・・・・・」
「傷があれば安心するのか?」
「安心・・・・・・そうかも知れません。痛いのは、私の気のせいでは無いって思えるなら。・・・・・・ああ、でも、そうしたら、お母さんを悲しませてしまう・・・・・・お母さんは、私が怪我をすると、私よりもっと痛そうな顔をするから。可哀想に、私が代わってあげられたらいいのに、って。・・・・・・私は、お母さんを責めていたんでしょうか。私があんなことを考えていたから。それでお母さんを追い詰めてしまったんでしょうか・・・・・・」
繰り返される自問。答えの見えない問いかけ。
「この世界のどこかに、私の本当のお母さんがいて、でも、私はその人を知らなくて、私を愛してくれたのかなんて、そんなことも判らないのに。・・・・・・本当のお母さんのことは知らなくても、今のお母さんのことは何でも知ってるって思ってた。お母さんだけは、私がどんな子でも好きでいてくれるって。でも、私はお母さんの何を知っていたのか・・・・・・本当は、私が思うのとは全然違う人だったのかも知れないのに、でも、そんなの信じられない。どんな事情があったとしても、お母さんが私のことを大切に想ってくれたのは嘘じゃないって・・・・・・。でも、わからないんです。何が本当で、何が嘘なのか、私には、もう・・・・・・」
「お前は、母親が許せないのか?」
「そんなこと! 私にはお母さんしかいないのに」
「あの元気過ぎる兄弟は?」
「ジーロもコリオも、本当の私のことなんて何も知らない。私がこんな、怖い力で人を傷つけるような魔女だってことを。村のみんなが怖がるのは当たり前です。私だって、私が怖い・・・・・・」
「悪いのは、自分一人なのか?」
「だって、そうなんでしょう・・・・・・?」
「少なくとも、そう思っていれば周りを責めずに済むものな。人を憎まずにすむ。愛されることを求めずに済む。けれどそれは、寂しいことだ。そう、気付いてしまったんだろう?」
「望んではいけないんです。そんなことは」
「何故? お前は母親や村の連中が好きではないのか?」
「好きです! 大切です! 誰も傷つけたくなんかないです! だから、」
それが正解。私が消えれば、それで全てが上手くいく。
「お前は偉いな。大切なものが何なのか、ちゃんと解っている。だから、お前の望みは間違っていない。痛いと思えば、傷があろうが無かろうが痛がって構わないし、愛されたいと望んでいいんだ」
イリィが飲み込んだ言葉を故意に無視して、カリムは断じる。
「・・・・・・そんなこと! だって、私には、こんな怖い力があるのに!」
「そうだな。それは誰にも、どうにも出来ない。でもな、それだけが全てなのか? お前は、連中を少しも怖いと思わないのか?」
「それは・・・・・・」
「怖いのは何故だと思う?」
「・・・・・・わかりません」
「そういうことだ」
「・・・・・・?」
「お前には、連中が何を考えているのかわからない。だから、怖い」
「・・・・・・!」
「いいんじゃないか。怖いなら、怖いとそう言えば。そうすれば案外、相手も似たようなことを考えているのかも知れないぞ」
「・・・・・・でも、もしかしたら、それで完全に終わってしまうかも」
「それで何か困るのか? もう理解っているだろう。世界の全てが味方ではなくとも、全てが敵になったりしない」
「でも・・・・・・」
「それに、お前の力だって同じだよ」
「・・・・・・!?」
「怖いってことが、だ」
「・・・・・・力が、怖がる?」
「お前が力のことを得体が知れないと思うように、力の方も、お前が何を望むのか判らない。同じことだ」
「力も、同じ・・・・・・」
「ほら、何か聞こえてこないか?」
「・・・・・・これは・・・・・・泣き声?」
「それは、お前にだけ訴えかける声だ」
「私・・・・・・あそこへ行ってあげなくちゃ! でも、どうしたら・・・・・・」
「あるだろう。お前の得意なことが」
「・・・・・・歌?」
「歌には伝える力がある。だから教えてやればいい。怖いと思う心、優しくする心。お前が望もののこと。お前が在るってことを」
「私に、出来るでしょうか?」
「お前以外の誰に出来る? さあ」
「・・・・・・」
目の前に差し出された白い手と、その先の蒼い瞳を、イリィは縋るように見つめる。
「及ばずながら、勇気の足しだよ」
蒼い瞳に、優しい笑みが宿る。
「だって、私は貴方のことも傷つけて・・・・・・」
「そう、見えるか?」
「・・・・・・?」
「その程度で傷つくほど、この俺が弱いとでも?」
「い、いいえ! そんなことはありません!」
「それでいい。では行こうか。お前の行きたい所へ。好きな人の元へ。お前の望みのままに・・・・・・」
「はい!」
カリムの手に、イリィの細い手が重なる。
その瞬間に、閉ざされていた世界がぱあっと開いた。
「歌が・・・・・・」
睨み合っていたフェグダから目を逸らして、赤毛の妖精モドキは空を仰ぐ。
「おい、まだ話は、」
「うるさいな、ちょっと黙ってて!」
ピシャリと叱られて、フェグダは思わず頬を膨らませる。
そこまでどうでも良さげに扱われる覚えはない、と思いながら。
「子守唄・・・・・・間違いない! 戻って来たんだ!」
パッと表情を明るくしたそいつは、風の柱に向き直る。
「それって、イリィちゃんがか!?」
「決まってるでしょ!」
二人が見守る中、あれほど吹き荒れていた風が急激に弱まり、立ち上る竜巻のようだった風の柱が崩れ始める。
閉ざされていた柱の中空に、ぼんやりとした影が現れる。影は徐々に形を成し、重なり合って浮かぶ二人の姿へと変わっていく。
一つは、緩く瞳を閉ざして子守唄を歌う少女。
そして少女の後ろには、励ますように細い肩に手をかける、長い髪の少年。緩く俯いた彼の表情は、煽られる髪に隠れて窺えない。
「もう、二人とも心配かけて!」
感極まったような赤毛が駆けつけようとした、その時。
少年の手が、僅かに少女の肩を押した。
「危なっ!」
「・・・・・・!」
何の抵抗もなく、フワリと高所から落下する少女を、慌てて落下地点に駆け寄りったフェグダが、間一髪受け止める。
「お前、なんてことしやがる・・・・・・」
怒鳴りつけようとした声が、途中で途切れる。
少年の様子が何かおかしい。
飛び出そうとした恰好のまま、勝ち気な妖精モドキが、竦んだように動けなくなっている。
パタリと。雨のようなものが、少年を見上げるフェグダの頬や腕を打つ。
その、鮮やかに赤い滴は。
「おい、お前・・・・・・!」
フェグダの声が合図であったかのように、少年の身体がぐらりと傾いで、そのまま背後に倒れ込むように、落ちる。
そこは岬に続く崖の際。
フェグダの脳裏に、村に来る時に通った崖沿いの道が甦る。海は、切り立った崖の遥かに下だ。
イリィを抱きとめた格好のまま、伸ばした腕が空を切る。
フェグダの指先に掠ることなく、少年の身体が視界から消える。
その時だ。
「カリム!」
赤い髪の残像がフェグダの横を駆け抜ける。落ちた少年を追って、何の躊躇いもなく崖下へと。
「何て奴だよ・・・・・・」
フェグダはぐったりと気を失っているイリィをその場に横たえ、膝が笑うような崖の下を覗き込む。
「カリム・・・・・・それが、あの野郎の名なのか・・・・・・」
白い波が砕ける崖下に、人影らしきものはどこにも無かった。
第30話 双つの月が出会う刻
波音が聞こえる。
低く、静かに、繰り返し、繰り返し。穏やかな鼓動のように、不断の時を刻み続ける。
過去から未来へ。世界の初めから終わりまで。命の誕生から終焉まで。
燃えるような空の下、彼方へと広がる海も、果てしなく続く渚も、遥かに遠い山々も、世界の全てが赤く染め上げられている。
天空に浮かぶのは、弓のような三日月。
穏やかに凪いだ海の水面にも、鏡に映したような白い月。
ここは、どこでもない世界。
不断の ぬるま湯のような安堵感に満ちた、全き安寧の世界。
そしてここには、痛みも苦しみも存在しない。
熱さも冷たさも、指先に触れるものがあるか無いかも、息が苦しいかどうかさえ。
身体感覚の全てが意味をなさない。
優しい暗闇さえも、この世界は拒絶する。
あるのはただ、静寂のみ。
こんな所にいてはいけない。
行かなければ。
戻らなければ。
アシェルの元へ、今度こそ。
必ず戻ると、そう言った。
どうしても、伝えなければならないことがある。
絶対に。
だから、立ち上がらなければ。
強いフリなど出来なくていい。
どんなに無様でもいいから、
「行かなくちゃ!」
矢も楯もたまらず、アシェルは飛び出していた。
「今度こそ、絶対に!」
カリムに追いつくこと、ただそれだけを思って。
見送るしか出来なかった、かつての自分。
それを後悔したのは、喪ってからだった。
取り返しがつかなくなって、はじめて彼の気持ちを理解した。
だけど今なら出来る。どこまでだって追いかけて行ける。
今だからこそハッキリ言える。
アシェルの力は、そのためにあるのだと。
あの白い離宮で。アシェルとカリムは、相前後して目覚めた。
過去、人間の手によって炎の結晶と同化させられた例は数多あるが、目覚めるまでに至ったものは僅かしかなかった。その目覚めた僅かでさえ、羽根を手にするに至った例は皆無だった。
数多の羽根使いと、それ以上に多くの犠牲を積み重ねながら繰り返されたその施術は、まだまだ不完全で実験的な試みの域を出ないものだった。
そして、ついに待望の羽根使いが誕生する。同時期に、二人もの。その事実は異例と受け止められたか、あるいは研究が進んだ成果だと考えられたか。
しかし、それで彼らは満足しなかった。
彼らが造り出したかったのは、羽根の力を最大限に操ることの出来る、上級天使を名乗るに足る存在だったから。
ところがアシェルは、羽根を手にしたものの、期待されるほどの力を引き出せないでいた。
カリムは、引き出せる力こそ強かったものの、制御にかなりの難があった。
番人どもの焦心はどれほどだったろう。
彼らが実験に着手し始めてから、既に相当の年月が経過している。彼らは何としてでも成果を上げる必要があった。
塔の中で、真理の番人の地位を確かなものとするために。
(だから、番人達にはどちらでも良かったんだ。ボクかカリムか、どちらか一人だけでも。実験が有用であると証明出来さえすれば)
そのために上位の番人が試みたのは、研究に直接従事する番人をアシェルの班とカリムの班に二分し、両班を競わせることだった。
アシェルとカリムの実績が、そのまま班の評価に繋がる。
結果として、下級の番人らは次第に反目し合い、事あるごとに対立するようになって行った。
アシェルがカリムに会いに行くことを彼らが良く思わなかったのは、そういう意味では必然だったのだろう。
(だけど、もしも・・・・・・)
彼らが方針を変え、アシェルとカリムを共に伸ばそうとしていたら、何かが変わっていただろうか。
互いの正体を知らぬままに。
そうすれば、少なくともあの悲劇は起こらなかったのだろうか。上級天使として、二人で共に歩む道が。アシェルが語った楽しい未来そのままに。
それとも。
カリムはやはり、過去の幻を捨てられなかっただろうか。手の届かぬものを追い続けるしかなかっただろうか。
ボク以外の何かを追い続けるカリムを、ボクは許すことが出来たかな。カリムが追っているのが、昔のボクだと気付かないまま。
この手で離宮を燃やし尽くしたあの日、傍にいた誰かが、ボクに小さな世界の真実を教えた。親切なんかじゃない、それを知ったボクが正気でいられなくなると承知で。
だけど、誰かがそう仕向けなかったとしても、いつかボクは、やっぱり同じ選択をした気がするんだ。
ボクの結晶が黒い炎に染まらず、彼のことを忘れたままだったとしても、キミがボク以外の誰かのために在ることに、いつか耐えられなくなると思うから。
だって、そうでしょう?
離宮で決別したあの日から何年もの時を経て、再会したボクたちは、結局殺し合うしかなかったんだから。
そうすることでしか、救いを見出せなかったんだから。
最後の一撃が互いを貫いた瞬間、飛び散った炎の欠片が共鳴して、ボクたちははじめてお互いの正体を知ったんだから。
おかしいよね。
昔からボクたちは、大切なことに気がつかないまま、すれ違ってばかりいるんだから。
キミは、キミの中の彼女が笑っている理由を知っている?
それはね、そうしていないと、キミとはもう二度と会えなくなるって、彼女は知ってたからだよ。
キミが、彼女には安全な場所に居て欲しいと考えていたことくらいは分かっていたよ。だから、彼女は望むことが出来なかった。キミの想いを無視して、追いかけて行くことは出来なかった。
でも、せめて、戻って来て欲しかったから。
それだけは、どうしても譲れなかったから。
だけどそのことが、こんなにもキミを縛り付けてしまっていたなんてね。
そんな彼女に、ボク自身が嫉妬してしまっているなんてね。
バカだなあ・・・・・・。
いつまで経っても、同じこと繰り返して、ホント、バカ。
それでもやっぱり、他の道なんて選べない。
何度別れても、何度出会っても、やっぱりまた繰り返す。
ボクの全ては、いつでもキミが持っている。
だったら、これこそが、ボク達の運命なんだよね・・・・・・。
いいよ。
キミがボクを助けたいと思うのなら、そうさせてあげる。
演じてあげる。キミが一番見たいアシェルの姿を。
ほんの一瞬だけ、だけどね。
キミからもらった力を、ボクはボクを助けるために・・・・・・この世界から消え去るために使うよ。
キミがいない世界で、ボクの願いが叶うことなんて無いんだから。
今度こそ全てを終わらせる。
そのために、ボクは今また、キミの前に立つよ。
赤い波の上に、滴を落としたように微かな波紋が立った。
一瞬たりとも形を留めぬ波間に、けれどその波紋はかき消されることなく、水面に小さなしわぶきを広げていく。
一つ、二つ、三つ・・・・・・
それは、近付く者の気配に他ならない。
姿は無く、音さえ無く。
だが、決して気のせいではない。
そして、こんな閉ざされた空間に入って来られる者がいるとすれば、それはただ一人だけ。
いつもそうだ。
あの呪符だらけの迷宮でさえ、いつも間違えることなくカリムを見つけてくれた者。
カリムにとって、たった一つの確かなもの。
(アシェル)
声すら存在しない世界で、カリムはその名を呼ぶ。
届くかどうかは判らない。届いて欲しいと、願うしかない。
その、永遠にも似た時間。
「そうだよ、カリム」
応じたのは、ひどく静かな声。
安堵と同時に、ひどく後ろめたい気持ちがこみ上げる。
アシェルは今、どんな顔をしているだろう。
懲りない奴だと呆れているか。無茶ばかりしてと怒っているか。
それとも、悲しみを飲み込んだ笑顔を向けているのか。
カリムが何かをしようとすればするほど、アシェルを悲しませることになる。
悲しまないでほしいと願えば願うほど、逆に悲しませてしまうことになる。
きっと、これからも。カリムと一緒にいればいるだけ、それは続くことになる。
それでも、どうしても伝えなければならないことがある。
どんなに悲しませることになるとしても、それを伝えることが、カリムに出来る精一杯だと思うから。
それで、永久にアシェルを失ってしまうとしても。
伝える方法が残されている内に。
(アシェル、頼みがある。一度だけ、彼女に話かけることを許して欲しい。彼女に、傷のある奴からの伝言を・・・・・・)
「・・・・・・彼は、何て?」
(「さようなら。直接別れを言えなくてすまない」と)
「・・・・・・!」
(お前に彼女の記憶があることを承知で、これを言う)
(俺が今まで生きて来られたのは、彼女のおかげだ。一目だけでいいから、彼女に会いたいと思っていた。だが、本当のことを言えば、もう探すまいと何度思ったか分からない。俺が彼女に辿り着ける可能性など、万に一つだってあるはずがないのだから、と。なのに、出来なかった。どうしても、探さずにはいられなかった。・・・・・・その想いだけが、俺を俺たらしめた。彼女を見つけたいという支えが無ければ、俺は何も出来ないまま、とっくに終わっていたはずだ。・・・・・・だが、もしも彼女に辿り着けたとして、それからどうするのかを考えたことは無かったように思う。その先なんて、俺には必要無かったから)
(当たり前だよな。彼女は昔の俺にとって、きっと大切な人だった。だが今の俺は、彼女の何かを知っているわけじゃない。どんな人だったのか、どう大切だったのか、どういう間柄だったのか、本当に、何一つ・・・・・・)
(・・・・・・俺は、どうして彼女に会いたいと願ったんだろう。本当は、ただ証明したかっただけだったんだろうか。かつての俺が、何も遺さず誰も幸せに出来ずに終わったのではないことを。それを証明出来さえすれば、何も悔い無く終われるのだと・・・・・・。馬鹿なことだ。どんなに足掻いたところで、昔の俺に戻ることなんて出来やしない。もし昔の記憶があったとしても・・・・・・いや、記憶があればなおさら、戻れないと思い知ったはずだ。俺が彼女を探すことは、彼女の為にはならない。誰の為にもならない。過去への想いなど、亡霊の妄執に過ぎない。それに囚われることで、俺は今まで、どれほど間違いを重ねて来たことか)
(俺は、世界なんか嫌いだった。塔も、番人どもも、天使も、薬酒も、羽根も。・・・・・・だが、一番嫌いだったのは”カリム”の存在そのものだった。この手に力があったとしても、所詮は全て借り物だ。力も容姿もこの器の本当の持ち主のものであって、それは絶対に自分とは違う存在だ。・・・・・・だが俺は、その事実に甘えていた。違うという確信だけで、何が違うのか知ろうともせず、違うと主張することだけが自分なんだと、そんな風に思い込んで・・・・・・。少し考えれば解ることだ。かつての俺がどれほどの奴だったのか。それこそ山ほどの後悔を残して死んだから、新たに目覚めてなお執着心を捨て切れなかったんだろうに、同じことを、何度も何度も・・・・・・。ったく、そんな奴に、価値などあるものか)
「・・・・・・だから、キミは滅びるのが正しいって? 滅びるべきだって言うの?」
たまらず、アシェルは声を荒げる。
「キミにとって、彼女には何の価値も無かった。それこそが真実だった。じゃあ、そんなキミに心を止めるボクは、キミ以上の大馬鹿だね? ・・・・・・そう言っておけば、ボクは心置きなくキミを壊せるとでも? そうまでしてキミはボクに・・・・・・」
”アシェル”を演じることなど忘れて、被っていた仮面をかなぐり捨てて。堰が切れたように、心に溢れた激情が、言葉となって迸る。
止められない。自分でも、どうしようもない。
(違うよ、アシェル。彼女に価値が無かったんじゃない。彼女の価値に甘え、彼女以外の価値を受け入れなかったことこそが、俺の間違いであり、弱さだったってことだ)
「・・・・・・!?」
(なあ、シェル。お前だけは、いつも俺を見つけてくれるよな。そして幻のままではなく、姿を変えこの世界の一部となって俺に出会ってくれた。確かなものの何も無いこの世界で、カリムにはお前だけが真実だった。転移の間でお前に再会した時・・・・・・本当はすぐにでも、お前の元へ駆けつけたかった。黒翼の天使だとか、魔物の力だとか、そんなものはどうでも良かった。憎しみからだったとしても、お前は俺を選んで会いに来てくれた、それだけで十分だった。だが、それでも殺し合うことしか選べなかったのは、俺自身が、カリムを認められなかったからだ。俺がカリムを嫌い続けていたから・・・・・・カリムにとって大切なものを認めることが出来なかったんだ。今になってみて思う。彼女は、俺に時間をくれたのかも知れない。大事なことに、気付くための時間を。だって、あれはお前だ。お前は、彼女とアシェルに分かれて、俺に会いに来てくれたんだな)
「・・・・・・」
(俺は、お前から、たくさんのものを貰った。最高の奇跡を。この上ない幸せを。だから、少しでも報いられるのなら、何でもやりたかった。お前のくれたものには到底及ばないが、俺に出来ることなら何だって。・・・・・・そのためには、自分の心に決着をつけなきゃならなかった。自分が何者か決められなければ、お前のためなんて言っても、ただの虚言にしかならないから。それがお前が望むものではなかったとしても、答えを出さないままでいることは、あまりに卑怯だ。・・・・・・ごめん、アシェル。こんなものしか渡すことが出来なくて・・・・・・)
「だからキミは、薬酒を飲まなかったっの。こんなになるまで・・・・・・」
(昨日言ったことは撤回しないよ。この命は、やはりお前のものだ。お前の好きに使っていい。お前のためになればいいが・・・・・・このまま打ち捨て去られたとしても、仕方ないと思う。それだけのことを、俺はしてしまったから)
「キミは、ずるい。またそうやって、ボクに決めさせようって言うの。そうやって、いつも、いつも・・・・・・。ねえ、ひとつだけ聞かせてよ。キミは、後悔したの? 今も、後悔してるの・・・・・・?」
(・・・・・・後悔はしなかった。何度繰り返しても、あの時の俺は、あれ以外の道を選ぶことは出来なかったから、後悔するわけにはいかなかった・・・・・・。だが、それは間違いだったのかも知れない。あの時、もっと、お前のことを信じていたら・・・・・・)
「・・・・・・」
(後悔したところで過去は変えられないが、今なら言えたかも知れないな。一緒に行こう、と。塔にも魔物にも追われることになっても。ほんの僅かしか猶予が無いとしても・・・・・・いや、一時間でも、一分でも構わない。それが短いなんて思わない。二人で、行けるところまで行くのなら)
「・・・・・・それに意味はあるの?」
(何の意味も無いかも知れない。だが、もしかしたら”湖の国”が見つかるかも知れない。俺は世界を嫌うばかりで、この世界がどんなものか、何も知ってはいないから。それは多分、一歩でも、自分の意志で歩かなければわからないことなんだろう)
「・・・・・・!」
(もし、この先にほんの少しでも意味があるとすれば・・・・・・それはお前が持っていてくれるよな。ここで終わっても、終わらなくても、俺には持ち続けることは出来ないから)
「・・・・・・この、馬鹿!」
アシェルの口を突いて出たのは、嗚咽で掠れた声だった。
けれど、それくらいはいいだろう。今のカリムに、涙で一杯のアシェルの顔を見られる心配は無いのだから。
「・・・・・・キミの望み通り、キミはボクが貰う。ボクがキミをどうしようと、ボクの勝手。それで、いいんだね?」
(ああ。お前の望みのままに)
キミが間違えたと言うのなら、ボクも間違えたていたんだね。
ボクたちにとって、死は安らぎで、救いそのもの。
でも、キミは安らぎも救いも求めない。
ボクは、キミを許せないと思っていたけれど、同時に終わらせてもあげたかった。
どちらも、本当だったんだ。
でも、心のどこかでは知っていたのかもしれない。
キミは、どんなに絶望していたって、結局、諦めてしまうことは出来ないんだ。開いた箱から飛び出しそこなった、弱いくせに人を魅了してやまない"希望"という名の悪魔の虜。とことん諦めと要領の悪い、一途で不器用でやること目茶目茶なバカ。
だけど、考えたことはある? とことんバカに生きられる奴は本当に少なくて、みんな賢い生き方を選んでしまう。賢い、妥協した生き方をね。
だからこそ、キミは人を魅了する。きっと誰も、キミから目が離せやしないし、その瞳に映ることを望まずにはいられない。
でも、それは教えてあげない。
だって、キミはボクのものなんだから。
ボクが見つけた、世界の全てなんだから。
赤く輝く空の下に、赤く染まる渚で。
空の三日月と海の三日月が魅かれ寄り添うように。
横たわる影の上に、翼を持つ小さな影が舞い降りた。
第31話 解放
「とりあえず、こんなところか?」
気を失ったイリィと、その母親だと思われる痩せ細った女性を小屋に運び入れたフェグダは、二人をベッドに並べて寝かせたところでやれやれと息をつく。
元々粗末な造りの小屋は、壁が壊れたことで強風が入り込み、散らかり放題の荒れ放題。小さなベッド一つを人が寝られるよう整えるだけでも大変な有様だった。
これがイリィのためでなければ、努力など最初から諦めて、外に放置していたかも知れない。
「ま、こっから先は、誰か呼んで来て世話して貰うのが正解だよな。あのジーロってチビも放って置けないし、それに・・・・・・」
フェグダは、頬を拭った袖口に目を落とす。くっきりと染み込んだ、濃い赤色。
やはり、幻ではない。崖下に消えた少年と、赤毛のちびっこい妖精モドキ。
「あの高さから落ちたんじゃあ、とてもじゃねーが無事じゃ済まないよな。どうする? 村の連中に捜索を手伝ってもらうか? ・・・・・・けど、何のためにだ? ・・・・・・あれが災厄だろうが別人だろうが、こんなところでくたばるようなら用は無い。だろう? そうさ、俺が何かをしてやる義理なんてねーんだ・・・・・・」
自分自身に言い聞かせるように呟いてから、フェグダはかぶりを振って立ち上がり、足元に細心の注意を払いつつ、その小屋を後にした。
嵐さえ過ぎ去ってしまえば、小屋からジーロを置いてきた場所までは、大したことのない距離である。が、
「ええと、確かこの木の辺りだったはず・・・・・・」
吹き飛ばされてきた落下物のせいで多少趣が異なってはいるが、まさか完全に間違えてしまうはずもない。
「それとも目が覚めたんで自力でどっか行ったのか? いや、イリィちゃんを気にして飛び出したんだから、まず小屋の方に来るよなあ。やっぱもう少し先だったのか?」
ジーロを探しながら元来た道を逆に辿ったフェグダは、振り出し地点である広場の辺りに賑やかな人だかりが出来ていることに気が付いた。
「それがさあ、ホントにスゴかったんだぞ! 風がピタッと止んだと思ったら空からキレーな光がぱーっとさしてきて、その真ん中にイリィが立ってたんだよ! こう、天使様みたいなカンジでさ! そんで、昨日の兄ちゃんがオレに向かって言ったんだ、『魔は払われた、もう何も心配することはない』ってさ!」
村人の輪の中心で、興奮に頬を上気させながら身振り手振り付きのオーバーアクションで熱弁を振るっているのは、誰あろうジーロである。
「それからさ・・・・・・あ、あの人!」
村人の後方で立ち止まったフェグダを目ざとく見つけたジーロは、ビシイッと真っ直ぐに指を差す。
「え、お、俺!?」
「そう! 後のことはそっちの旅人兄ちゃんに任せろって言ってさ、妖精さんと一緒に光の中に消えちゃったんだ!」
「はあ? 何で俺が? てか誰の指名だって?」
「いやー、そうでしたか! やはりあの方々は魔物から村を救いにお出で下さった天使様! そして貴方はその下僕の天使様だったのですね!」
「おい! 何で俺が下僕扱い! てか、一体どっからそんな話に・・・・・・!」
「おおー!」
「ありがたや、ありがたやー!」
「きゃー!」
「わー!」
完全に興奮状態の村人たちには、何を言っても無駄な気がする。
「ったく、何だって俺はこんな役ばっかなんだよぉ・・・・・・」
正直、人目もはばからず頭を抱えて唸りたい心境である。
「さあさ、どうぞこちらへ! こんな有様で大したことは出来ませんが、多少なりとも宴席を用意致します! どうぞごゆるりと寛がれて、魔物退治の様子などをお聞かせ願えませんでしょうか!」
その瞬間、フェグダの耳がぴくっと動く。
「そ、そんなに言うんなら、無下に断るのも申し訳ないな。忙しい身ではあるのだが、ほんの少しだけならば」
わあっという歓声と共に、村人たちが押し寄せた。
彼らの突撃を宥めようと両手を高く上げたフェグダは、ふと違和感を覚る。
その僅かの隙に、フェグダは完全に取り囲まれ、容赦なくわやくちゃにされる。
(・・・・・・ま、いっか。どーせ面倒事からは逃れられやしねーんだから、ちょっとくらいお祭り騒ぎに付き合ってやったて悪かないよな。それに、幻術だか魔法だか知らねーが、こんなことが仕組めるのはあの野郎の外にいるわきゃねーし)
フェグダの袖口に染み込んでいた、鮮血の赤が消えていた。最初から何も無かったかのように。
(冗談にしたって人が悪すぎるぞ。ったく、心配して損したぜ・・・・・・じゃなくて、誰が心配なんかするかってーの!)
幸いと言うべきか、フェグダの内心の葛藤に気付いた者は誰一人としていなかった。
「流石だな」
広場の様子を遠くに感じながら、カリムは素直な感想を口にする。
「でしょ! ダテに黒翼の天使なわけじゃないんだよ」
眠っていたジーロにそれらしい夢を見せて、村人たちを煽るよう仕向けたのはアシェルだ。
人間の精神に直接働きかける類の術は黒翼の天使の得意技の一つなのだが、それに散々苦労させられた経験を持つカリムとしては、少々複雑なところでもある。
「それじゃ、仕上げと行きますか」
アシェルは乱雑に散らかってしまった小屋の中で、唯一整えられたベッドに目を向ける。そこには寄り添って眠り続ける、母娘の姿があった。
「・・・・・・やはり、魔物には視えないな」
イリィの母親が契約者であることは判っている。だが、カリムの眼には彼女はただの人間でしかない。
「そりゃあそうだよ。契約者は人間だもの。魔物の力を借りることは出来ても、力を行使しない限り見分けはつかないよ。黒翼の天使にとって魔物は単なる手駒じゃない、負の感情に染まった人間の命を集めて精製するための重要なアイテムだ。ボクらにとっての薬酒を得るための。だから魔物を製造するための契約には、途中であっさり見破られるようなチャチな術は使わない。持てる技術を総動員して用意周到なくらい手間暇かけて一体一体に見合った方法を取るわけだから、それはもう芸術って言ってもいいと思うな」
「・・・・・・お前、魔物を造ったことなんてあったのか?」
「あるわけないじゃない。それが?」
「いや別に」
それにしては熱っぽく魔物を語ってたよな、とは口には出さない。
「負の感情に染まった命が黒翼にとっての薬酒・・・・・・その最たるものが死の恐怖か」
「だから魔物は本能的に人間を殺戮する。そして殺人は、契約者が魔物に変わる条件の一つでもあるんだ。つまりね、彼女のように契約してから二年もの間、その条件を満たさずにいられたなんて、本当に稀なことなんだ。守護者がこの地に及ぼす力も一役買っていたんだろうけど、何より彼女自身がそういう人間だからだと思うよ。・・・・・・彼女と契約した奴は、じっくり待つつもりなんだ。なかなか魔物にならないような人間を契約者に選ぶことは、強力な魔物を造り出す秘訣でもあり、契約主の自尊心を満たす愉悦でもあるからね」
その口調とは裏腹に、アシェルは翳りを帯びた瞳でじっと二人を見下ろしている。
「彼女がどんな人間だとしても、契約が結ばれてしまっている以上、いずれ魔物に変じる運命は変わらないのだろう?」
「そうだね。契約を破棄するには、予め設定した破棄条件を満たすか、契約主の合意を取り付けるしかないけど、そもそも破棄条項なんて設定してるはずないし、契約主が破棄に合意するなんて有り得ないからね」
「彼女を魔物にしない方法は、一つしかない、か」
振り向いたアシェルは、静かに佇むカリムを見た。
イリィに母親と話をさせたいと、アシェルは望み、カリムはそれが叶うよう全力で応えた。
二人が目覚めれば、その願いは叶うだろう。アシェルの考えが正しかろうと、そうでなかろうと、イリィは答えを得られるだろう。
けれどもしも、母親と話すことで彼女の事実を知ってしまったら、イリィは辛い決断を迫られることになるだろう。
イリィに非情な選択をさせるよりは、敢えて自分の手を汚すことを、カリムは厭わないだろう。
自分がイリィに憎まれることになろうと、躊躇いはしないだろう。
憎しみに縋ることが、往々にして支えとなることを、カリムは否定したりはしないから。
(ボクが願いを口にした時から、キミはその可能性に気付いてたよね)
蒼い瞳は、全てを深く深く沈めて、ただ静かにそこに在る。
「ねえ、カリム。黒翼であるボクには、契約者に刻まれている契約印が視えるんだ。契約印は他の黒翼や魔物に対して、これは自分の所有物だから手を出すなって警告だから。それを侵すことがどういうことか。だから魔物は絶対に、契約者に手を出さない。けど、わざわざ警告するってことは、そうする意味があるってことなんだよね」
「・・・・・・」
怪訝そうなカリムをどこか楽しげに振り返ってから、アシェルは眠っている二人の傍に降り立った。
「ねえ、カリム。そこで見ていて。絶対に手出ししないって、約束して」
「・・・・・・」
カリムは返答しない。理由は簡単。もしもアシェルに危害が及ぶ可能性があるなら、それを黙って眺めているつもりなど無いからだ。
「キミの気持ちは解るよ。でも今は、黙って見ていてくれることこそが、一番ボクのためになるんだよ。だから、ボクを信じて」
「信じて、いればいいのか?」
カリムは瞳を一度伏せてから、しっかりとアシェルの緑色の瞳を見返す。
「分かった。ここで見ている」
「うん! 待ってて!」
とびっきりの笑顔で頷いてから、アシェルは死んだように動かないイリィの母親と正対した。
アシェルの瞳に、黒い炎が浮かび上がる。
その背の金属を溶かしたような羽根が、大きな黒い翼へと形を変える。
「ボクの声が聞こえるね?」
その瞬間、イリィの母親がカッと目を見開く。その眼窩の奥に瞳の色は無く、ただ闇だけが存在する。
「答えなさい。お前の名は?」
威圧的に、アシェルは命じる。
「ウ・・・・・ア・・・・・」
開かれた口から、苦悶に満ちたしわがれ声が漏れ出す。
「答えなさい!」
「・・・・・・イ・・・サラ・・・・・・」
「そう、イサラ」
「グ・・・・・・ウゥ・・・・・・」
「お前は黒翼の天使と契約を交わした。その際に何を願ったのか、言いなさい」
「ウ・・・・・・ウウ・・・・・・オ・・・許シ・・・・・・」
「ダメだよ。イサラ、これは命令だよ。答えさない!」
「ウ・・・・・・ガアッ・・・・・・!」
イサラの身体がビクッと跳ね上がるや、野獣の唸り声と共に、正面のアシェルに肉迫する。
カリムは、動かなかった。
アシェルはカリムを見なかった。ただ、イサラの目だけを見つめ続けた。
操り糸に手繰られる如く飛び上がったイサラの身体は、アシェルの眼前で見えない壁にぶち当たったかのようにバンッと急停止する。なおも手足を震わせてもがき続ける彼女に、アシェルは命令を重ねる。
「答えなさい、イサラ。それがお前の・・・・・・お前の大切なイリィのためだよ」
「ウぅ・・・・・・イ・・・リ・・・・・・」
「イリィのためだよ。解るね?」
「ウ・・・・・・ああっ・・・・・・!」
イサラの空虚だった眼窩から透明な液体が、涙があふれ出す。
「・・・・・・ノ、望ミ・・・・・・イリィを、守ルこと・・・・・・約束したカラ・・・女神さまト・・・・・・ぐ・・・・・・うがあっっっ!」
見開かれた眼窩から、叫びを上げる口から、そして彼女の全身から黒い炎が吹き上がり、大きな火柱となって渦を巻く。
黒い火柱の中に、イサラと、アシェルの身体が呑み込まれる。
「・・・・・・!」
カリムは、動かなかった。
両手の拳を力一杯握り締めながら、一歩たりとも動かなかった。
その光景から目を逸らすことなく。
それは、どこかの街だった場所。
劫火の後の、真っ黒に焼け焦げた残骸。
所々に、煤けた身なりを構いもせずに力なく項垂れる人影。
そんな中に現れたのは、一人の女性。
粗末な身なりではあったが、黒く澱んだ世界の中で、その女性だけが色を持っていた。
その腕の中に眠るのは、輝くような一人の赤子。
女性は傷を負っていた。
それでも消えることのない紫色に輝く瞳を、小さな小さな命に向けて。
・・・・・・彼女は一人、去って行った。
女性の言葉はよく解らなかったけれど、小さな命をお願い、と。どこに行ってもいつか必ず迎えに来ると言い置いて。
託された小さな命をしっかりと抱き締めながら、物陰に隠れて息を潜める。その横を、黒装束の一団が駆け抜けて行った。
あれが何者かは判らない。ただ、黒ずくめの先頭に立っていた女の燃えるような目は、一度たりとも忘れたことが無い。
(その女性に託された小さな命がイリィ・・・・・・。貴方は、そんなになってまで守りたかったの? ほんの一瞬出会っただけの、その女性のために・・・・・・)
(イリィは、女神さまに託された希望・・・・・・大切な光・・・・・・だから、願った。イリィを託せる者が現れるまで、守る力が欲しい、と・・・・・・。私の大切な女神さま・・・・・・私の全て、私の希望・・・・・・)
(そう、愚問だったね。誰かを好きになるのに、理由なんて要らないね。好きになったその瞬間こそ全てなんだから)
黒い炎は勢いを減じ、風の渦となって収束していく。
その渦の中心に、大きく腕を広げた格好のアシェルが立っている。黒い渦は次第にアシェルの胸から身体の内へと、飲み込まれて消滅した。
中空に浮かんでいたイサラの身体が、そのままドサリとベッドの上へ落ちる。
眠り続けるイリィの横に、何事も無かったかのように。
黒い炎を吸収し尽くしたアシェルは、閉ざしていた瞳をゆっくりと開ける。
「・・・・・・もう大丈夫だよ。これであなたはイリィの行方を見届けることが出来る。・・・・・・だけど、誰かに頼る必要はないんじゃないかな。イリィは、ちゃんと自分で歩ける子だよ。カリムもそう思うよね!」
そしてアシェルは、カリムのへと向き直った。
緑色の、悪戯っぽい瞳で。
「どう? 見た見た見た?」
飛びついて来たアシェルを受け止めて、カリムはそっと小屋を後にする。
「・・・・・・何をしたんだ、アシェル?」
「うん。強制的な契約破棄! 黒翼だけに可能な裏ワザだよ! ってか、契約の力の横取りなんだけどね。これで彼女は、もう魔物にはならないよ」
「横取り?」
物騒な言葉に、カリムはひそめていた眉を更に引き絞る。
「つまりお前は、黒翼の天使が契約に使った力をわざと分捕ったってことか?」
「そういうこと! おかげで今とってもお腹一杯!」
「それは要するに・・・・・・」
「彼女の契約主な黒翼の天使に真っ正面から喧嘩売ったってことだね!」
「やっぱりか」
「さーて、どんな仕返しされるんだろー。手間暇かけた所有物を横取りされて笑ってるよな黒翼なんて居ないだろーしねー」
「所有物ね・・・・・・」
すいと、カリムの瞳が冷やかに細められる。
「先刻から聞きたいと思ってたんだがな」
「うん?」
「お前はどうやって魔物の力を手に入れたんだ? 条件云々を聞いた限りじゃ、自分で自分と契約することは出来ないよな?」
魔力を分捕ったことに対して「どうしてそんな危ないことを」と怒られる展開は覚悟していたのだが、何だか怒られる方向性が予想と違う。
「それはその・・・・・・他の黒翼と契約、とか・・・・・・?」
「で、お前は今の所まだ魔物に成りきってない、と」
「まあ、他者の命を奪うって第一条件はクリアしちゃってるけど、契約した望みはまだ叶ってないから」
「お前の望みは俺をその手で殺すことだったよな」
「・・・・・・うん」
「それが叶ったら、お前は魔物として契約主の所有物になるって、そういうことか?」
「・・・・・・そうなる、かな?」
「冗談じゃない!」
「・・・・・・もしかして、ムカついてる?」
「当然だ。何で俺の一番が他の奴の物にされなきゃならない? そんなことを、この俺が認めるとでも?」
全身から立ち上る怒りのオーラに、カリムの長い髪がゆらりと不穏に揺れる。
「そう言われても、ボクの場合はホラ、契約の解除も裏ワザも無理だろーし、」
「だったら、お前が完全な魔物になるのは断固阻止してやる。俺はお前のものだが、絶対に殺されてはやらない。それに、魔物にならなくたって黒い滴さえあれば問題無いんだろ。なら契約の横取りだろうが、魔物を狩って分捕りだろうが、遠慮なくやればいい」
「だから、それ、他の黒翼に喧嘩売りまくるってことなんだってば・・・・・・」
「何を今更。先刻はお前自身が喧嘩売ったってのに、俺にはイチャモンつける気か?」
「それはホラ、一回くらいならゴメーン間違えちゃったーで済ませてもらえないかなーって」
「済むと思うか? 本当に?」
「・・・・・・無理、かな?」
「無理だな。そのために俺がいるんだろ?」
「だって・・・・・・いいの? そんな大口叩いちゃって。薬酒は先刻ので使い果たしちゃったし、根性だけで何とかなる相手じゃないんだよ?」
「それはもちろん・・・・・・」
「何か勝算があるっての?」
「いや、それほどのものじゃ・・・・・・」
言葉を濁したカリムに、ここぞとばかり、アシェルは畳みかけを敢行する。
「ねえ、もういい加減手の内明かしちゃいなよ? キミはさ、勝算が1パーセント以下だろーと全賭けしちゃえるヒトだけど、逆に言うと、勝算が完全にゼロなコトを言ったりしないよ。あるんでしょ、何か奥の手が?」
「・・・・・・」
「それとも、ボクが大事だとか大見得切ったの、後悔してたりしてー?」
「するか馬鹿!」
「えーじゃあ聞くけどさー」
「何だよ?」
「ボクが彼女の魂を持ってるって知らなかったら、あんな風にプロポーズ出来た? 男の子の姿なアシェルに対して、さ?」
「・・・・・・!」
思わず固まったカリムに素早く近付いたアシェルは、軽くキスして、ぴょんと飛び退く。
「お、お前な・・・・・・」
からかわれたと気付いたカリムが、がっくりと脱力する。
「どうかしたー?」
五歩分ほど先まで飛んだアシェルが、心持ち照れ笑いで振り返る。
「・・・・・・俺は、お前にちゃんと伝えられただろうか?」
「え? 何か言った?」
「いや、何でもない」
カリムはアシェルに追いつこうと、大きく一歩を踏み出した。
『それで、二日もどんちゃん騒ぎしてたってわけ? 連絡するヒマも無しに? ったく、いいご身分だこと!』
「しようとしたよ連絡は! けどそっちが通信に出なかったんじゃないか。俺だけのせいにすんなよな!」
『あんた一人のために四六時中通信珠の前に座ってろっての? 冗談でしょ。休憩時間に休憩出来なくて、どこでガールズトークしろってのよ?』
それはクミルの生き甲斐であり、フェグダにとっても貴重な情報源である。
「・・・・・・そう言うなよ。これでもちゃんと仕事はしてたんだぜ、最低限は」
『ええっ! それって災厄の天使様か星焔の天使様に会えたってこと!?』
クミルの声が期待に弾む。
「あ、ああ・・・・・・」
村中総出て盛り上がった後の夜更け、こっそり遺跡に行ってみたのだが、そこにはもう誰もいなかった。だが、遺跡の奥まったホールで、フェグダは少年が残したと思しき装身具を発見した。”三対翼と矛と交差する二つの三日月”の紋章があしらわれたそれを。
「・・・・・・まさか、そんなカンタンに見つけられるかよ!」
『なーんだ。ま、期待はしてなかったけどさ・・・・・・』
とは言いつつも、クミルの声には落胆の色がありありと浮かんでいた。
『それで、あんたは一体何してたのよ?』
「だから、言ったろ? この村に羽根使いがいたんだよ。それを狙った(のかも知れない)魔物と一戦交えたり、羽根の暴走を食い止めた(ヤツを見届けた)り、その後の事後処理(連日の宴会)や事情説明(旅の面白話)を求められたりや、何やかやだよ!」
『ふーん。あんまりネタになりそうじゃないなー』
「俺の話もトークのネタかよ。それはともかく、スカウト係の手配はどうなってる? いつごろ来れそうなんだ?」
『あ、それね。今こっち手一杯だから、その子を転移門のある街まで連れて来てくれない?』
「何で俺が!」
『だって、大した用なんて無いんでしょ。ついでよついで!』
「あー、まー、そりゃそーなんだが・・・・・・」
『歯切れが悪いなあ! 言いたいことがあるんならさっさと言えば?』
「いや、ちょっと・・・・・・ああもう、分かったよ! 転移門のある街まで連れて行けばいいんだな! それだけだな!」
『まさかとは思うけど、それで貸にしたつもり?』
「はいはい、クミル様にお借りした今までの御恩の数々は決して忘れちゃいませんって!」
『だったらいいのよ。・・・・・・それとね』
通信珠の向こうで、クミルは声をひそめる。
「ん?」
『例の物、もしかしたら手に入るかもなんだけど・・・・・・』
「何だって!? お前ずっと、無理だ無理だってつっぱねてたじゃねーかよ!?」
『シイッ! ・・・・・・・あたしだって調べてはいたのよ、一応は! で、ようやく倉庫係(主塔在庫管理室)の子のツテで、何とかなりそうなカンジなのよ。まあ、今すぐってわけにはいかないけど。その様子じゃ、今更要らないなんて断ったりしないよね?』
「ああ、モチロンだ!」
『・・・・・・』
「クミル?」
『あ、ううん、何でもない。で、いいこと? この貸しは大きいからね、覚悟してなさいよ」』
「もちろん、今度聖都に行ったら必ず、今までの分とまとめてどーんと払うから期待していいぜ!」
『まとめてじゃなくても、プレゼントは随時受け付けていてよ。それじゃ、街に着いたらいつもみたいに連絡ちょうだい』
「ああ! 頼りにしてるぜ!」
『当然でしょ!』
発光の治まった通信珠を見据えたまま、フェグダは暫く動かなかった。
(まさか、ここで手に入るなんて・・・・・・白亜の塔の秘中の秘、奇跡をもたらす禁断の秘薬、炎の滴! その正体さえ解れば・・・・・・。あんな男を頼らなくたって、俺が必ず解放して見せる! だからもう少し待っててくれよ、母さん・・・・・・)
務めて明るい調子で通信珠を切ったクミルは、余韻の発光が完全に消えてしまってから、ふーっと深い息を吐いた。
「ご苦労だったね」
クミルの背後で、その人物は労いの声をかける。
「いいえ。この役は、私以外には出来ませんから」
背後を振り向くことなく、クミルは応える。
「ですが、どうしてなんですか。ずっとフェグダのことを遠ざけていたのに、今になって急に・・・・・・」
「・・・・・・」
「一つだけ、お答え願えませんか。これは、フェグダのためになることなんですよね?」
「もちろん、そうだよ」
その声はどこまでも優しげだった。いつも通りに。
「すみません、出過ぎたことでした」
「構わないよ、クミル」
その人物はゆっくり近付くと、通信珠の前に座ったままのクミルの肩に、そっと手を置いた。
第32話 夜明けの歌

「おはようございます、フェグダさん!」
「おわあ! っとっとっと・・・・・・!」
完全に周りがお留守だったフェグダは、声をかけられたはずみに、手の平に乗せたままだった通信珠をお手玉してしまう。
「あ、危なかった・・・・・・」
あわや地面に激突という寸前でどうにかキャッチに成功したフェグダは、ホッとすると同時にがっくりとその場に脱力する。
「ご、ごめんなさい。そんなにビックリさせちゃうなんて思わなくて・・・・・・」
「い、いや、ちょっと考え事してたもんで・・・・・・・てーかイリィちゃん、その格好・・・・・・・?」
「ええと、やっぱり変ですか?」
「や、そーゆうことじゃなくってさ、それ、ひょっとして旅支度?」
「ええ、そのつもりですけど」
「何でまた急に・・・・・・」
「そう言うフェグダさんだって、こんな朝早くに荷物まで持って。みんなに捕まらない内に、コッソリ出発するつもりじゃないですか?」
「まあ、実はそのつもりだったんだけどさ・・・・・・色々事情を押し付けてくるヤツがいて、予定変更せざるを得ねぇっつーか・・・・・・」
「・・・・・・ちょっと意外です」
「あ?」
「あなたは人当たりは良いけれど、実はもっと自分の事情を優先させる人じゃないかって思ってましたから」
大人しげな娘だとばかり思っていたイリィが、そんな風に他人を評すとは、それこそ意外だ。
「・・・・・・イリィちゃんこそ。確かに俺は「羽根使いは塔に行かなきゃなんない」っつったけどさ、何もそこまで急ぐ必要は無いんだぜ? おふくろさんはもう気が付いたんだっけか? にしたって、まだあんま話せてないんじゃね?」
あの大嵐の日から、イリィは母親と一緒に村長の家の離れに間借りしていた。
あちこち壊れてしまった小屋は、村のみんなが、もっといい家に建て直すと約束してくれた。
それだけでなく、親身に世話を焼いてくれたり、妙に同情されてしまったり、頼むまでもなく先回りしてお母さんの介抱をしてくれたり、踊りの輪の真ん中に連れて行かれて歌をせがまれたり・・・・・・。
それもこれも、イリィは”村に舞い降りた天使”で母のイサラは”魔物の災厄を身を持って押しとどめた功労者”。何がとう転んだのか、いきなりそういうことにされていて、今まで疎んじていた負い目もあってだろう、村人たちは完全に貴人を遇する姿勢でイリィに接してくるのだった。
手の平を返したような村人たちの態度に困惑するしかなかったイリィが事情を知ったのは春祭り当日、同じく主役に据えられたフェグダから話を聞くことが出来てである。
その夜だ、お母さんが目を覚ましたのは。
『ごめんね、イリィ。お前のことを、ちゃんと守ってあげられなくて』
お母さんはイリィの手を握るや、開口一番にか細い声でそう言った。
『そんな、お母さん。私こそ・・・・・・』
だが、お母さんは緩く首を振って、言い募ろうとするイリィを遮った。
『お前には言っておかないといけないね。・・・・・・本当は、お前がもっと大きくなって、お前を大事に守ってくれる人が現れた時に言うつもりだったけど・・・・・・』
そうして、お母さんは語り始めた。
縁あって村を遠く離れた街に嫁いだこと。
ある夜、その街が大火に見舞われて、夫と、まだ小さかった坊やを亡くしてしまったこと。
何日も焼け跡を彷徨い、自分一人が生き残ってしまった罪悪感に責め苛まれる彼女の前に、突然、女神さまのように神々しい女性が現れたこと。
傷ついていた女神さまは、腕の中の小さな赤ちゃんを託して、どこかに去ってしまったこと。
そのすぐ後で、悪魔のような黒服の一団が、女神さまを追って行ったこと。
小さな赤ちゃんを守る為に、身内は誰もいないと知りつつも、生まれ故郷の村へ帰って来たこと。
それからもう二度と、女神さまにも悪魔の群れにも出会ってはいないこと。
『そんな・・・・・・通りすがりの人のために、お母さんは私を育ててくれたの? どうして・・・・・・』
『違うんだよ、イリィ。あの方は、私に希望を与えて下さった。あのお方の言葉はよく解らなかったけれど、お前を頼むと何度もおっしゃっていたことだけはよく解った。だから私は、命に代えても守ると誓ったんだ。何も迷うことは無かったよ。あの時、本当に心から、私はそう願ったんだから・・・・・・』
その光景を思い浮かべているのだろう。お母さんは目を閉じて、うっとりと優しい表情を浮かべた。
『あの方を追って行ったあの悪魔どもと、その先頭に立っていたあの女。あいつらのことは、片時も忘れたことが無い。あいつらからお前を守れるのなら、どんなことをしたっていい・・・・・・でも、もう、そういうわけにはいかなくなってしまったようだね』
『そんなことない! 今度は私がお母さんを守るよ、今までの分も、ずっと!』
ところがお母さんは、きっぱりと首を振った。
『それはいけないよ。お前は私なんかのために、縛られたりしちゃいけない』
『縛られるだなんて、思ってない!』
『ああ、分かっているよ。お前は優しい子だから。でもね、聞いておくれ、私のイリィ。私の大切な天使さま。お前はもう、私がいなくても大丈夫、どこまでだって飛んで行けるよ』
『行かない! 出て行ったりしない! 私はお母さんと一緒に居るんだから! この村で、ずっとずっと・・・・・・』
『だめだよ、イリィ。お前はこんな村で終わっちゃいけない。もっともっと広い世界で、幸せにならなきゃね。広い世界で、お前の大好きな歌を歌って、みんなを幸せにしてあげなくちゃ。そしてもしも、あの方に会うことが出来たら・・・・・・お前と暮らせて幸せだったって、伝えてくれるかい? ああ、私のことは心配要らない。何しろ天使さまの育ての親だ。村の者だって無下になんかするものかね』
そう言って、お母さんは笑った。
娘に心配させまいとする、強かで優しい笑顔だった。
『大好きよ、お母さん! 私も、お母さんみたいに強くなりたい・・・・・・』
『何を言っているの。こんな優しいお前だもの。私なんかよりもっと強くなれるよ。私はね、お前の幸せを願ってここで暮らすよ。だからもう泣かないで。今だけは私のために歌ってくれるかい? そう言えば、ずいぶん長い間、お前の歌を聞いていなかった気がするよ・・・・・・』
イリィは頷いた。涙でうまく声が出なかったから、代わりに何度も頷いた。
涙が治まって、泣き声でない声が出せるようになるまで。明るく元気な声だけを、ずっとずっと、お母さんに覚えていてもらえるように。
「・・・・・・不思議ですね。物心つく前からずっと一緒に暮らしていたのに、昨夜のたった一時の方が、今まで一緒にいた時間よりずっとずっとたくさん話が出来た気がします」
「そりゃあ良かった。けど、塔に入っちまったら、そう簡単には帰って来れなくなるんだぜ? 今の内に精々孝行しといた方がいいんじゃねーの?」
「そうしたいけど・・・・・・それはお母さんが許してくれないと思います。私に出来るのは、お母さんとの約束を精一杯守って、どこに行ってもがんばることですから!」
気合十分の握り拳で、イリイは明るくなり始めた空を仰ぐ。
「ま、まあ、それは分かったけど。ほら、村の連中とのわだかまりも解けたことだし、トモダチとだってもっと話すことがあるんじゃないのか? 祭りの間はそんな暇無かっただろうしさ。送別会とか、見送りとかも、色々と」
何で俺がそんな心配しなきゃならないんだと思いつつ、フェグダは更に言葉を重ねる。
別にイリィが村を出るのを反対しているわけではないし、むしろ自分からその気になってくれるのは説得する手間も省けて好都合なのだが、苦労した末にようやく村の一員として受け入れられながら、それをどうしてあっさり手放してしまえるのか。正直フェグダは、理解に苦しむ。
「・・・・・・私が天使だって知って、みんなは私のことを大事に、本当に大事にしてくれるようになりました。でも、私が望んだのは、村のみんなともう一度仲良くなることだったんです。村の一員として」
少し寂しそうに、イリィは微笑む。
「だけどその望みはもう、かなわなくなってしまいました。私が、特別な存在になってしまったから」
祭りの間中、ジーロやコリオを含め同年代以下の子供らは、無礼があってはいけないからとイリィから遠ざけられてしまっていた。
もっともジーロに限っては、隙を見て窓からこっそり会いに来ては大人たちに見つかって追い払われたりしていたが、さすがにコリオの方はそこまで大胆にはなれなかったようだ。なられても困るが。
「村のみんなには申し訳ないけれど、同じ旅立つのなら、私はお母さんの娘の、ただのイリィとして旅立ちたいんです。それが私の、最初で最後のわがままです。ダメですか?」
「い、いや、ダメじゃねーけど。そりゃ、全然!」
たとえそれが超の付く無理難題だったとしても、綺麗な紫色の瞳でじーっと見つめられた日には、ダメと言える男などいるはずがない。少なくともフェグダの知る限りは。
「・・・・・・ったく、意外はこっちだぜ。まさかイリィちゃんがそんな確りしてる子だとはね。最初はもっとこー、流されタイプなよーに見えたってーかさ」
「いえ。きっとその通りでしたよ。でも・・・・・・お母さんだけでなく、私のことを信じてくれた人がいましたから」
真昼の青空のように晴れ晴れとした顔で、イリィは笑った。
「それってもしかして・・・・・・」
あのインケン野郎と赤毛のチビ、という言葉をフェグダは飲み込む。
「私、お礼さえまだ言ってないんですよ。なのに知らない間にいなくなってるなんて、ヒドいと思いませんか?」
「・・・・・・まさか、あいつらを追っかけるつもりか?」
「はい!」
無邪気なほどあっけらかんと応えられて、フェグダは思わずたじろいでしまう。
「そんな簡単に・・・・・・あいつらが村を出てったのって、例の事件の直後だぜ? 今から追っかけて間に合うなんて保証は、」
「だからノンビリしてる場合じゃないんです。早く出発しなきゃ!」
「や、そーゆーことじゃなくてだな。てか、俺もか?」
「だって、フェグダさんもそのつもりだったんでしょう? それが二人一緒なら、幸運だって二倍になるかもって思いませんか?」
「・・・・・・」
「ダメですよ。いつまでも迷ってたら、幸運の女神さまに愛想尽かされちゃいますよ」
「それ、妙に説得力あるなー。正論かどうかはともかくとして・・・・・・」
「本当はね、絶対に追いつけるなんて思ってるわけじゃないです。ただ、白亜の塔に行って天使になるなんて言われても、全然ピンと来ないんですよね。それよりも、お世話になった人にお礼を言うための方が、私が一歩を踏み出す理由としてはいいかなって、それだけのことなんです」
(すげーな、この子は・・・・・・)
ずっと以前に聞いた昔語りに、小さな子供が一晩で成長する話があったような気がする。その時は下らない夢物語だと嗤って、すっかり忘れてしまっていたが、それはもしかしたらこういうことなのかも知れない。
「そうだな、ここでノンビリしてたところで仕方ねーし、このまま出発しちまうか!」
「はい! それじゃ南と北と、どちらに行きます?」
「あ?」
「フェグダさんはあっちから来られましたけど、向こうに行っても街道に出ますから・・・・・・」
「まあ、街道まで出られさえすりゃ、乗合馬車も通るだろうし、どっちでも大差ないっつーか・・・・・・気分の問題? イリィちゃんはどっち行きたい?」
今のイリィには最高に強運の女神さまがついているんじゃないかと、かなり本気でフェグダは思う。
「それじゃあ、こっちの方!」
「即決? 何か理由でもあんの?」
「はい。景色が綺麗な所を通るんです。今日はお天気が良さそうだから、きっと気持ちいいですよ」
「ああ、なるほどね。俺も崖っぷち歩くのは正直ウンザリだしな」
「すみません、こっちに行っても崖道にはなっちゃいますけど」
「そ、そっか・・・・・はっはっはー」
フェグダは思わず浮かべてしまったに違いない落胆の色を、笑い飛ばして誤魔化した。
山側の背後から上る朝日は、顔を出すのが遅い。
空が明るく染まって、雪を頂いた山が紅色に縁どられる頃、はじめて最初の一条が地に届く。
朝の新しい光に照らされた草原に、カリムが立っている。
半眼を閉ざし、片手を胸の前に軽く翳して。
一つに束ねられた長い髪が、吹き上がる風に煽られるかのように揺らめいている。
やがて、翳した手を中心にして、カリムの周りに青白い光の粒子が舞い始める。
不規則な乱舞は、やがて二重三重の渦を巻く螺旋の流れへと変化し、粒子はさらに数と密度を増して輝き、ある形状へと収束していく。
カリムの背丈ほどもある、大振りの曲刀。羽根の力が具現した形へと。
輝きを放つ曲刀は、その柄を握られるのを待ち構えるように、カリムの目前に静止する。
刀身の中央辺りに、微かに、本当に微かに燃える紅い炎。
青白の輝きに包み込まれるようにして、ひび割れた炎の結晶から分け放たれた、小さな小さな欠片の色が。
カリムが羽根を取り戻すと言い出した時、アシェルは別段驚いたりしなかった。
塔の天使狩りに、魔物に、黒翼。それだけの相手と渡り合う以上、戦う力は必要だ。アシェルと一緒に生きると決めた時、カリムは既に羽根と向き合う決心をも固めていたはずだ。
俺から離れていろ、ではなく、そこで見ていて欲しいとカリムは言った。迷いない笑顔を向けて。
それは、必ず羽根を制御し従えるという、決意の言葉だ。
羽根の力と魔物の力は相反するものであり、少しでも制御を誤れば双方が共鳴し暴走するかも知れない。だが、危険は充分に承知の上。二人で一緒にいるためには、決して避けては通れない道だ。
やるなら早い方がいい。薬酒の効果が充分である内に。
今や完全に具現した曲刀を前に、だがカリムはその柄を握ることなく、正対したままでいる。カリムを取り巻くオーラが、燃え盛る炎のように煌々と輝く。
両者の間で交わされているのは、対話なのか、主導権を巡る攻防なのか。羽根と羽根使いとの間に流れるものを、他者が伺い知ることは決して出来ない。
そうしてどれくらい経ったのか。曲刀の形状が、一瞬にして解ける。
再び光の粒子と化したそれは、さらに収縮へと向かい、痛いほどに高圧の輝きを放ってから、ふわりとカリムの手の上へと舞い降りた。
辺りを青白く圧していた光は、柔らかい蛍火となって、溶けるように見えなくなった。
(やった! 成功したんだね!)
そう思った瞬間。
アシェルの背後から、ざざざーっと一陣の風が吹き抜けた。
(何これ、力の反動?)
不自然な大気の流れに咄嗟に顔を伏せたアシェルだが、それ以上の変化が起こる様子は無い。
「何だったの、今のは? ・・・・・・カリム!?」
険しい顔をしたカリムが立っていた。
若緑の草原を席巻してしまった、黄色い花畑の真ん中に。
「え? ちょっと何で花畑? あ、あっち蝶が飛んでるし! これ、ひょっとしてカリムが・・・・・・!?」
「・・・・・・っの馬鹿が!」
仏頂面で吐き捨てるや、カリムは勢いよく花畑の中に倒れ込んだ。
「カリム、おーい?」
アシェルはひと飛びすると、仰向けになったカリムの、頭の方から覗き込む。
「羽根は戻って来たんでしょ? なのに何ぶーたれてんの?」
アシェルの目の前を、数匹の蝶が戯れながら横切っていく。
その中に妙な物が見えた気がして、アシェルは目で蝶の群れを追う。
ほんのりと青みがかった白い卵に、のっぺりとした羽根が生えた、妙ちくりんな物体。卵の中心には、微かな紅炎が揺らいでいる。
蝶を追ってふわふわ漂っていたそれは、向けられる視線に気付いてか、アシェルの傍に寄って来ると、窺うように周りを回る。
一瞬身を固くしたアシェルだが、そいつは動くものを興味のままに眺めているだけのようだ。
何とはなしに腕を伸ばしてみれば、それは蝶が羽根を休めるように手の甲へと止った。ぽってりした見てくれに反して、蝶ほどの重さすら感じられない。
「・・・・・・あの馬鹿が持ってやがったんだ」
不意にポツリと言われて、そいつをつつこうとしていたアシェルは、寝転ぶカリムに目を戻す。
「それは・・・・・・塔に封印されてるはずのカリムの羽根を、実は何と! ”あの馬鹿”くんが持ってたって、そういうこと? ちょっと待ってよ、羽根を御せるのはその羽根に選ばれた一人だけなんだよ? どうやったらそんなことが・・・・・・」
出来るのかと言いかけて、アシェルは言葉を飲み込んだ。
転移の間でカリムと死闘を演じていた間中、必死になって割り込み続けた少年のおぼろげな姿が脳裏に浮かぶ。
(もっとちゃんと、顔を見ておけば良かったな)
彼が只者でないのは確かだ。普通の羽根使いには不可能な行為すら、彼ならやってのけるかも知れない。
それに。理屈はどうあれ、カリムが羽根を呼び戻すのに白亜宮の封印術を突破せずに済んだことは、大いに助けになったはずだ。
「しかも、”迎えが遅い”だの、”寂がって泣いてましたよ”だの、言うに事欠いて好き放題!」
「”あの馬鹿”君なら、いかにも言いそう」
「ほんの一瞬だったが・・・・・・あいつが居た場所、あれはどう見たって聖都じゃなかった。あの馬鹿、どこで何してやがるんだ。また変に首突っ込んでマズいことになってやしないだろうな・・・・・・」
「あーなるほどー、だからそんなに不機嫌なんだー。大っきな借りが出来ちゃったもんねー」
「構うか。今まで俺が面倒見てやってたんだからこれでチャラ、いや、まだ貸しのが多いくらいだ!」
カリムは頭の下で腕を組んで、穏やかに明るい空を睨むように仰ぐ。
「でも、気になってるんだよね」
「・・・・・・」
「それから? 他にも言うことがあるんじゃない?」
アシェルはわざとゆっくり、カリムを中心に丸い花畑と化した草原を見回した。
「・・・・・・」
カリムが空へ向けて伸ばした手の先に、アシェルの手を離れた羽根付き卵がふわりと飛んで移動する。
「・・・・・・この世界に在るものは、存在するためのエネルギーを内包している。大地には命を育む力が、種には芽吹く力が、卵には孵化する力が」
「蕾には咲くための、幼虫には蝶になるための?」
「生き物は食べることで、その力を取り込んでいる。力を奪ったり与えたりして、エネルギーを循環させる輪の中に在る、それがこの世界に生きるってことだ」
「ええと、これ何の前振り? ややこしいハナシになるの?」
アシェルは思わず、小声で呟く。
「だが、炎の結晶と同化した命は、この世界の流れから逸脱している。だからこそ、力を補うのに薬酒なんてものが必要になる」
「うん。それがボク達の常識だ」
上級天使だろうが、黒翼の天使だろうが、循環する流れの中に無いという意味では同じ。
アシェルやカリムには、人間のような食事は、嗜好品程度の意味合いでしかない。
「だがもしも、薬酒に頼らずエネルギーを変換して取り込む方法があるとしたら?」
「・・・・・・そりゃあ便利だと思うけど。それが出来ないから、ボク達は苦労してるんじゃないの? って、余計なツッコミは置いといて。あるんだね、そーゆう都合のいい方法が」
「羽根を自在に操るほどのパワーは覚束ないが、普通に動くのに支障ない程度には、だが」
「それ、もしかして、あの遺跡の守護者と関係が?」
不自然なほどに、そこだけ砂に埋もれた神殿。
あれが、結晶に封じられていた守護者によって、長年に渡って生き物や地脈の力が吸い上げられた結果なのだとしたら。
「守護者が最期に俺に伝えたのは、いくつかの術に関するノウハウだ。実際試してみるまでは半信半疑だったんだが・・・・・・」
「それってすごいことじゃない!」
声を弾ませたアシェルに、しかしカリムはニコリともせずかぶりを振る。
「変だろ?」
「えーと、変ってどの辺りが?」
「だから、ちょっとコツを聞いただけの俺が、ぶっつけで試して手応えがあるなんて、どう考えても変じゃないか」
「それは、ええと、いつまで経っても羽根のパワー制御に難ありな壊し屋のカリムでも、頑張ればモノに出来そうだと思うくらい簡単な技だってことかな?」
変な所で冷静に自己評価してるよなあと、アシェルは内心で呟く。
「つまり、これは基本技の部類で、守護者が羽根使いだった頃は出来て当たり前だったんだと思う。なのにどうして、今じゃキレイさっぱり失われてしまってるんだ? 似たような方法を試してみようとすら、誰も考えなかったのか? 俺なんかよりずっと年季が入ってて、マスターしてる術の数もハンパないような連中にしても?」
「もしかして、故意に消された術だとか?」
「さあ、どうだろうな。薬酒の効果が桁違いに凄いのも事実だし、だから単に廃れただけかも知れないが・・・・・」
「ったくさー、新技ゲットだヤッターって素直に喜べばいいものを、どーしてそー面倒くさいコト考えちゃうかなー」
やれやれと、アシェルは盛大にため息をつく。
「で、それ、今のボクたちにどう関係するの?」
「いや、あんまり」
「あっそ」
何を聞いても驚くもんかと身構えていたアシェルは、拍子抜けして斜めに傾ぐ。
「ただ、俺は今まで、色んなことから目を背け続けてたんだな、と思っただけだ。目の前にあるものすら見ようともせず、何も考えずに切り捨てて・・・・・・・もっと早く周りを見回していたら、もっと色んなことに気付けたかも知れないのにな」
「気付くって、何に?」
「俺たちが、誰のために何を望まれて造り出され、今もこうして存在させられてるのかってことに」
「・・・・・・!」
思わずアシェルは息を飲む。
「それって、上級天使が必要だって以外に、何か理由があるってこと?」
「だと思っている」
「キミがじゃなくて、上級天使はみんな?」
「もちろん、お前も含めて」
「ボクの・・・・・・黒い炎に染まった結晶・・・・・・」
「なあ、お前が転移の間にいた俺を強襲した時。あの結界の厳重な塔の中心部に、どこからどうやって侵入出来た?」
「それは・・・・・・」
「確かに、黒翼の術があれば不可能じゃないだろうな。塔の連中が思っているほど、それは難しくないかも知れない。それでも。お前はそもそもどこにいた? あの燃える離宮から結晶の欠片を集めて保管し、再生を試みたのは、一体誰だ?」
「・・・・・・」
「あいつじゃないのか。俺付きの番人の一人だった、あの男。あの日離宮にいた番人の中で、たった一人の生き残り」
「・・・・・・そこまでは判らないよ。さすがに眠っている間の記憶は無いから。でも、そうだよ。ボクは塔に侵入したわけじゃない。元から、あの結界内にいた」
「そうか・・・・・・」
「それで、キミはどうしたい? 犯人を捜して仕返しする? 今更そんなことに拘って何になるの?」
「・・・・・・とりあえず」
「うん?」
「技のコントロールを何とかしないと。今のままじゃ、奇術のネタにしかならない」
「ああ、うん。そーね。あと、このディティールはもうちょっと何とかしようよ」
アシェルは自分の周りをふよふよと飛んでいる物体に目を向けた。
「そのままじゃダメか?」
「ダメだね。羽根を仕舞うのが苦手な珍しーい羽根使いさん」
羽根使いは、普段は羽根を自分の身の内に収めていて、術にしろ武器化するにしろ、使う時にだけ発現させる。その方が安定するし消耗も抑えられる、と言うより断然楽なのだ、普通は。
「苦手っつーか、俺にはそれくらいのスタンスが合ってんだよ、多分」
「だったら手抜きしないで、もう少し可愛くするくらいの程度の努力はすべきであるぞよ」
アシェルの重々しい託宣を受け、カリムは神妙な面持ちで頷いた。
第33話 それぞれの一歩

振り向けばそこにはいつも、冷たい暗闇が佇んでいる。優しい腕を広げながら、そっと静かに、寄り添うように。
迷うことなくその手を取ることが出来たなら、どんなにか・・・・・・。
「うっわあぁぁ!」
「・・・・・・キレイ!」
黄色い花で埋め尽くされた一面の花畑に、フェグダとイリィは同時に歓声を上げる。
「こりゃ絶景だなー。なんつーかこー、疲れも吹っ飛ぶ光景だよなあ」
「ええ。・・・・・・だけど、ここの花が咲く時期はもっと先だった気がするんですけど・・・・・・?」
イリィが首を傾げた、ちょうどその時。黄色い花が一斉にもこもこっと揺れて、花の間からどばっと白っぽい点々が飛び出した。
蝶だ。
しかも、ものすごい数の。
それが申し合わせたように一斉に飛び立つ様は、壮観というか、一種異様な光景ではある。
蝶の大群は、そのひらひらした飛び方からは想像もつかないような速さで舞い上がると、たちまち散り散りになってどこかへ飛び去って行った。
「これって、嵐の前触れか何か?」
「でも、こんなにいいお天気・・・・・・え?」
不意に、ぱらぱらぱらっと大粒の雨が二人を襲う。
「嘘だろ、おいっ!」
「きゃあ! どうして急に・・・・・・あら?」
マントを被る間も無く、雨は降り始めたのと同じくらい唐突に、ぴたっと呆気なく止んだ。
「何がどーなってんだ?」
「さあ?」
呆然とする二人の耳に、聞き覚えのある笑い声が飛び込んで来た。
「あーあ、また失敗!」
「・・・・・・だから、こういう細かいコントロールは苦手だって言ってるだろ」
「あははははっ! もっと練習すれば? 体術くらい熱心にさ」
「簡単に言ってくれる」
花畑の中で、冠や首飾りや腕輪など大小様々な黄色い花輪を量産している真っ最中なのは、赤い髪の小さな妖精さん。
そのすぐ傍で、頭の下に腕を組んで寝転んでいるのは、長い髪の少年。
「アシェル! カリムさん!」
「お、お前ら、何でこんなとこにいんだよっ!? てか、このふざけた騒ぎはお前らの仕業かっ!?」
「騒々しい奴だな」
いかにもかったるそうな態度で、カリムが半身を起こす。
「わあイリィちゃん二日ぶり! 元気だった?」
ピョンと飛び上がったアシェルが、再会の感激もあらわにイリィの首に抱きついてぶら下がる。
「あ、はい、元気です。アシェルも元気そう」
「ふふふ、モッチロン!」
「おーい」
「で、その格好どしたの? どっか行くの?」
「実はちょっと色々あって、村を出て来たところなんです」
「思い切ったねー。でも良かったじゃない。じゃあ、目指すは歌姫デビュー?」
「・・・・・・そ、それより私、二人にお礼を言いたくて」
「お礼? ボクたちお礼なんか言われるようなこと、何かしたっけ?」
「さあ?」
「おーまーえーらー?」
「でも、私はすっごくお世話になったと思ってるし、どうしてもお礼を言いたいんだから、お願いです、言わせて下さい!」
「そういうお願いって初めてされちゃったよ。何だか照れるなー」
「もしもーし?」
「何かここ、うるさいね。あっち行こっか、イリィちゃん!」
「あ、はい!」
「じゃあ、俺はそこで寝てるから」
「えー、カリムも参加しよーよー」
「って、お前ら無視すんなよな!」
会話から取り残されたフェグダが、一人空しく海へと吠える。
「ふーん、それで黙って出てきちゃったのかー」
例によって少し離れた所に引っ張って行かれたイリィは、興味津々のアシェルによって、村を出て来た顛末について根掘り葉掘りの質問攻めにされていた。
「ええ。お母さんは許してくれましたし、他のみんな宛てには置き手紙して来ましたけど」
「そっかー。ジーロ君なんか、置いてきぼりにされたって怒るかもなー。でも、面と向かってサヨナラ言ったら、ついて行くって駄々こねられそうだしなー」
「ホント、そうかも」
想像するまでもなく、その光景が目に浮かぶ。
「だけどいいの? あんなのと一緒でさ」
アシェルは思いっきり胡散臭そうな目で、カリムに向かって何やら食って掛かっているフェグダを見やる。
(彼が、例の・・・・・・)
『・・・・・・あの番人のことは、何か覚えているか?』
三度目の失敗の後で、カリムはぽつりと、そんなことを聞いてきた。
珍しい気がする。カリムが話を蒸し返すことは。
『あー、キミ付きの番人だった? ボクに対してはいっつもムスッとしてて、無駄にエラそうで、ホントいけ好かないヤツだったなー。そのクセ上には不満のフの字も見せないスナオないい子ちゃんでさ、ハッキシ言ってそーとー腹黒いってーか、何考えてるかさっぱり判んないヤツだったなー』
いい大人を捕まえていい子も何も無いのだが、印象としては、まあ間違ってはいないと思う。
『とにかく、あんなのとはお近づきにならない方が身のためだとボクは思うねっ! カリムもいつまでも気にしてないで、さっさと忘れちゃった方がいいよ絶対!』
『残念ながら、それは手遅れだな。・・・・・・離宮が燃え落ちたあの日、俺は奴と契約した。互いの立場を利用して塔での地位を確立するために。だから利用価値が無くなれば、一方的に解除してもいい条件で。俺はどんな形にせよ、いつか塔を出て行くつもりだったし、そうなれば奴にとって俺には価値がなくなるどころか、逆に足を引っ張ることになる』
『ってことは、今の状況からして、キミとの契約はとっくに解除されてなければならない。けど?』
『結界が消えてはっきりした。契約は、まだ効力を持っている』
『・・・・・・』
『奴の魔術師としての力量があれば、契約を手掛かりに俺の居場所の見当はついたはずだ。ましてや今は守護者の結界も消えて、お前があの母親を解放した時点で黒翼の結界も消滅している。それからだって丸一日以上経つってのに、この平穏さは何なんだ? 俺たちを始末しに天使狩りが送られたなら、もうとっくに遭遇していていいはずなのに・・・・・・』
事実上、天使狩りの所属する第五軍管理部隊は、番人の傘下に置かれている。番人の長が天使狩りの派遣に無関係なはずがない。どころか、さっさとカタを付けて手柄にすれば、それだけ上層部の覚えも目出度くより発言権も増すだろうに。
『・・・・・・ったく腹立たしい! この期に及んで、まだ何か企んでやがるのか? しかも、どうして俺が奴の思惑なんて下らないことを気にしなけりゃならない!?』
カリムは険しい目を、この場にいないはずの相手に向ける。
『要するに、彼には契約を解くつもりがない。ひょっとしたらカリムを脱走天使扱いすらしてない可能性が高い? ・・・・・・実際、ボクらは転移門に落っことされて聖都を離れたわけで、自分の意志で出て行ったんじゃないし、理屈としては通ってるよね。すっごく苦しい言い訳だけど』
『ったく、わけが解らん!』
『単にカリムのことを眺めてたいって理由だったとしても、別に驚かないけどね』などという不用意な発言は差し控えることにする。
『番人の長って、派閥だらけの塔の中で、そんなに影響力あったっけ?』
アシェルの知る塔の組織図は、過去のうろ覚え程度のものでしかないが。
『ここ数年で、かなり上まで食い込んでいる。やり手だよ、奴は。それに・・・・・・』
カリムは思案気に目を細める。
『偶然みたいな顔をして現れた、あの天使・・・・・・』
『ああ、そんなのもいたっけ。すっかり忘れてた。ええと・・・・・・フェグダってったっけ、結局何しに来たんだろ? ボクらを追ってだったら、タイミングが良過ぎと言うか、現れるのが早過ぎと言うか。ホントに偶然じゃないのかなー?』
『この近くをうろついていたのは、偶然だったかも知れない。だが、何かが腑に落ちない・・・・・・』
『そう言えばさ、彼、金色の耳飾りしてたよね、三角の。それ、番人のあいつもじゃなかった?』
『・・・・・・そうか、通りで見覚えがあるはずだ! 離宮に居た頃はそんなのを・・・・・・いや、その後も暫くは付けてた、か?』
『いつから、どうして、付けなくなったか、なんて聞いてもムダだね』
『ああ』
至極当然のようにカリムは頷く。気にしない人とはそういうものだ。
『それじゃあさ、あのフェグダってのは番人の一族? それとも彼の個人的な身内!? でも、あの陰険男に同族意識や身内意識って、ちょっと想像つかない・・・・・・』
『そうか? 隠している顔がどんなのだって、今更驚かないと思うが』
『冗談! 実はお茶目なマイホームパパだったとか、絶対に考えたくないね!』
自分で言っておきながら、うっかり想像してしまったアシェルは、本気で青くなって身震いする。
『けど冗談抜きでさ。素性がどうあれ、あんなのがそこらをウロウロしてたんじゃ、ボクたちのことは塔に筒抜けになっちゃうよね? さっさとどうにかした方が良くない?』
『・・・・・・それなんだが。考えようによっては、奴が俺たちの動向を把握したいなら、敢えて乗ってやるのも悪くないと思う。奴がどういうつもりか知らないが、』
カリムは一瞬、心底嫌そうに顔を顰める。
『それで天使狩りに煩わされる心配は格段に減ると思う』
『そうかな? いくら何でも見通しが甘過ぎない? 下手したら派手に足元すくわれちゃうよ?』
『その時はその時だ』
『・・・・・・言うと思った』
実際、試してみないことには何も判らない。
『アシェル』
打って変わった真剣な声に、アシェルははっとしてカリムを振り向く。
『俺はもう一度、塔に行くべきなのかも知れない。行って、色々とカタを付けなきゃならないのかも知れない・・・・・・。アシェル、頼みがある。もう少しだけ、俺に付き合ってくれないか?』
カリムの目が、真っ直ぐにアシェルを見ている。
『それなら聞くけど、キミはボクの望みを覚える?』
『ああ、覚えている。俺はお前と、ずっと一緒にいる。塔だろうが、黒翼の居城だろうが、魔物の包囲網の真っ只中だろうが、どんな危険な所だろうが、もう二度と、絶対に置いて行ったりしない』
深く蒼い瞳の中に、アシェルの緑色の瞳が映る。
『なら、改まって聞く必要なんか無いよ!』
アシェルはくるりと背を向ける。上気した頬に、気付かれたくなくて。
(い、今更ハズカシイとか、何やってるかなボク。どうせカリムのことだから、深いイミなんてあるハズないんだからっ・・・・・・)
どこどこ跳ねまくっている鼓動を必死に宥めながら、アシェルは首を少しだけ傾けてカリムを窺う。
『・・・・・・そ、それにしても、肝心のフェグダ君はちゃんと追いついて来れるのかな?』
『さてね。あれにもあれなりに思うところがありそうだが・・・・・・自分がスパイにされてるとしても、その自覚があるかは怪しいものだな』
「ち、違いますっ! フェグダさんと一緒だなんて、誤解ですよ!」
思いがけないイリィのうろたえっぷりに、アシェルは思わずたじろいでしまう。
「その、フェグダさんとは次の街まで行くだけで、その後のことは全然!」
特に意識したつもりはなかったのだが、どストライクな質問をしてしまったらしい。
それならそれでと、アシェルは人の悪いにまにま笑いを浮かべる。
「だよねー。だってイリィちゃんのお目当ては・・・・・・」
「違います違います違いますっ!」
アシェルの言わんとすることを瞬時に察したイリィが、全力で否定する。
「えー? ボクまだ何も言ってないけどー? 一体何が違うのかなー?」
「やめて下さいよぉ・・・・・・」
「だ、け、ど! 他にどんな理由があったら、村飛び出して追っかけようなんて思って実行しちゃうような思い切り方が出来るのさ? 後先なんてこれっぽっちも考えずに。それが、好きだってことじゃないの? ほらほら、スナオに認めちゃいなよー、そしたら気が楽になるよぉー」
「えっと、えっと、えっと・・・・・・」
「んー? どうしたのかなー?」
進退窮まるイリィに、追い打ちをかけるアシェルだったが。
「・・・・・・私! アシェルのことも大好きよ? これからもずっと仲良く出来たらいいなって思うんだけど、それじゃダメ?」
「・・・・・・」
開き直ったらしいイリィに正面きって真顔で言われて、アシェルは一気に脱力する。
清純派の破壊力、恐るべし。
「あーもー! 分かった、降参! 十歩、いや百歩、でも足りないか。ええい! 百万歩譲って! カリムのこと見てるだけなら許す!」
「え? ええと、ありがとう。それって、みんなで仲良くしようって意味よね!」
「ま、まあねっ!」
(イリィちゃんってばカワイイ! けど、完全に恋する乙女モード、しかも無自覚って・・・・・・もしかしたらすっごい強敵かも・・・・・・?)
内心、かなりフクザツなアシェルである。
一方、フェグダは。
「お前! あの時はよくもやってくれたよな!」
「ああ? 何のことだ」
「ンのやろー! 忘れたとは言わせねーぞ! 俺がちょっと大人しくしてりゃ、チョーシ乗っていいように利用しやがって! 何様のつもりだ、ええっ!?」
「済んだことを、細かいヤツだ」
フェグダの啖呵は、完全に不発に終わる。
が、ここであっさり引き下がるわけにはいかない。同道するつもりはないにしても目を離すつもりがない以上、このまま付け上がらせては後々苦労するのは目に見えている。それに相手が何者だろうと、少しは他人に敬意を持って接することを覚えて然るべきだ。
フェグダは脳みそフル回転で、糸口を探す。
「お、お前こそ! 女みてーにズルズル髪伸ばしやがって、鬱陶しい!」
「・・・・・・何だと?」
蒼い瞳がすっと細められ、思わず及び腰になりかけたフェグダは、ありったけの根性を総動員して耐える。
「おう! 見たまんま、本当のこと言っただけだろ! 何か文句あんのかよ!」
下らないイチャモンもいいところなのだが、こうなっては撤回もままならない。が、
「そういうものか?」
「は!?」
売り言葉に買い言葉と思いきや、カリムはフェグダから目を離して、思案するような素振りを見せる。
「今まで言われたことは無かったが・・・・・・そうだな。考えてみれば、確かに邪魔だ」
「え、あ?」
面食らうフェグダの横を、す、とカリムが通り過ぎる。
「借りるぞ」
その手には、フェグダの短刀が抜き身で握られていた。
「あー、お前また勝手に! てかちょっと待て!」
思い立ったら即実行。カリムは片手で束ねた髪を掴み、無造作に短刀を押し当てる。
寸前で。
「キャーっ!」
「ダメーっ!」
短刀を構えたカリムの腕に、超スピードで飛び込んで来たアシェルがしがみつく。
アシェルの背後には、今まさに殺人事件を目撃する瞬間のような顔をしたイリィが。
「ああ、別に何でもない。髪を切ろうと思っただけだ」
「それがダメだってのーっ!」
「あ?」
「あ、じゃないでしょ! こんなにキレイなのに、切るなんてもったいない! てか絶対ダメ! そんなのボクが許さない!」
実力行使とばかり、アシェルは短刀をもぎ取りにかかる。
「まあ、お前がそう言うんなら」
されるに任せて、カリムは短刀を手放した。
「はーっ」
「良かったー」
奪い取った短刀を即座に投げ捨てたアシェルと、微動だにせず成り行きを見守っていたイリィが、揃って大きな息をつく。
「何を大げさな、てか、俺の短刀に何しやがる・・・・・・」
「うるさい! そもそもカリムに余計な事言ったのは誰!?」
アシェルはぎっと凶悪な目つきでフェグダを睨む。
「え、俺が悪者!?」
「そうだよ! 覚悟はいいね!」
「いいわけないだろっ! あいつが自分でやったんだぞ! 俺に何の責任があるってんだよ!?」
「問答無用!」
「ねえアシェル、もうその辺りで許してあげて」
今にも噛みつきそうな勢いのアシェルを、見かねたイリィがやんわりと制止する。
「おお、イリィちゃん! キミは天使だ!」
「えー? 何で止めるのさー?」
勢いを削がれたアシェルは、あからさまにホッとしているフェグダを睨み付けたまま、不満げな声を上げる。
「だってほら、最悪の凶行は防げたんだし、フェグダさんだってもう十分懲りたでしょうし・・・・・・懲りましたよね?」
おっとり声にも関わらず、内容は意外に辛辣だったりする。
「イ、イリィちゃんまでそんな・・・・・・」
「ごめんなさいフェグダさん、こればっかりは譲れませんから」
「勘弁しろよ・・・・・・」
多勢に無勢。諦めるしかないフェグダは、のん気に明るい空を恨めしそうに仰いだ。
「んーじゃあ許してあげるとしてー・・・・・・ボク、そろそろお腹空いちゃったなっ! 街まで行ったら、何かおいしいものが食べたいなー」
「それなら酒もな」
「いいねそれ! あとねー、泊まるなら浴場付きの豪華な宿がいいなー。この国には有名な温泉地がいっぱいあるんだよねっ?」
「そうですね、一番近くて有名なのは・・・・・・」
「待て、ちょっと待て! それ全部俺にたかる気かよ!?」
「え? まだ反省が足りない?」
「だから何でそうなるんだよぉ」
三者三様の視線の集中砲火を受けて深い深いため息をついたフェグダの頭上に、青白い蝶がひらりと舞って止まる。
(蝶に慰められてりゃ世話ないぜ・・・・・・。まあ、何だ、これで怪しまれずに同行する言い訳が立つんだったら、渡りに舟って言えなくもない、か?)
釈然としない気持ちは大いに残るが。
先に立って歩き出した三人の背中を追って、フェグダは足を踏み出した。彼の受難は、まだ始まったばかりである。
闇は今も、すぐ傍に寄り添っていて、変わらずに優しい手を差し伸べている。
甘美な誘惑を振り切るのは苦しい。無視することなど到底出来ない。
この瞬間にも、その手を取ってあちら側へ行ってしまいたい衝動が、身の内を焦がしている。
なのに何故、何を求めて、騒動に抗い、灼けつく光の中に立ち続けるのか。
それでも、もう少しだけ、闇から目を背けていよう。
案ずる必要なんて無い。
それはほんの束の間のこと。
闇はきっと、変わらず隣にいてくれる。優しい腕を広げたままで。
だから今は。
永遠にも等しい束の間の一瞬を、儚く確かな命に寄り添って、共に光の中を歩こう。
赤い渚に浮かぶ月
生まれて初めてあとがきとゆーものに挑戦です。
って、そりゃそーでしょ。話を最後まで書き上げないと、あとがきは付けられないんだからw。
初完結小説、やほーっ!
いやいやそんなことより、ここまでおつきあい下さった読者様、本当にありがとうございました!
こんなブルー入りまくりな、途中で飽きられても仕方ないよねーでも自分が書きたいから書くんだもんね的、完全に読み手より書き手優先な作品を(マジな話、ホントにカウンター止まりっぱなしになるんじゃないかと思ってた)よくぞ見捨てずおいで下さいました。感謝感激です。
だ・け・ど!
この終わり方って、完結とは言えないんですよねー。
謎なんか全然解き明かされてないし(最終回でさらに盛ってるし)何よりカリムもアシェルイリィもフェグダも、みんなしてようやくスタート地点に立ったトコ!
てかスタートに立つまでが長かった長かった!
けど、自分はそれが書きたかったワケでw。
色んな事情を抱えたキャラが、それでもスタートラインに立とうとするところが。
各話毎に言い訳しまくってるブログの方でも書きましたが、カリムやアシェルが自分の頭の中にやってきたのは、震災の年の夏頃です。あの日を境に、直接は震災の被害を受けなかった人でも、それ以前とは何かが決定的に変わってしまった、変わってしまうことを知ってしまった、そんな年です。
カリムたちの状況も事情も悩みも、自分とは全く関係無い。ファンタジーなんだから、それが当然。
でも、だからこそ、とこっとん悩んで、乗り越えるところを書きたかったんだと思うですよ。今にしてみればね。
最後に。自分の中ではこの子たちの物語は、過去にも未来にも広がってるし、ちょい役としてしか登場しなかったあのヒトやこのヒトや出番が全く無かったヒトビトが大手を振って闊歩してたりします。
その中で一番書きたかった部分が書けたことにはひとまず満足してますが、そうなると欲が出てくるものでして、いつか何らかの形でまとめられるといいなあ。
で、もし次書くんだったら、「とにかく完結させる」って目標から一歩進んで、自己満足止まりじゃない作品を目指したいなあ。
ではまた、いつかお目にかかれますように。
UMA・m


