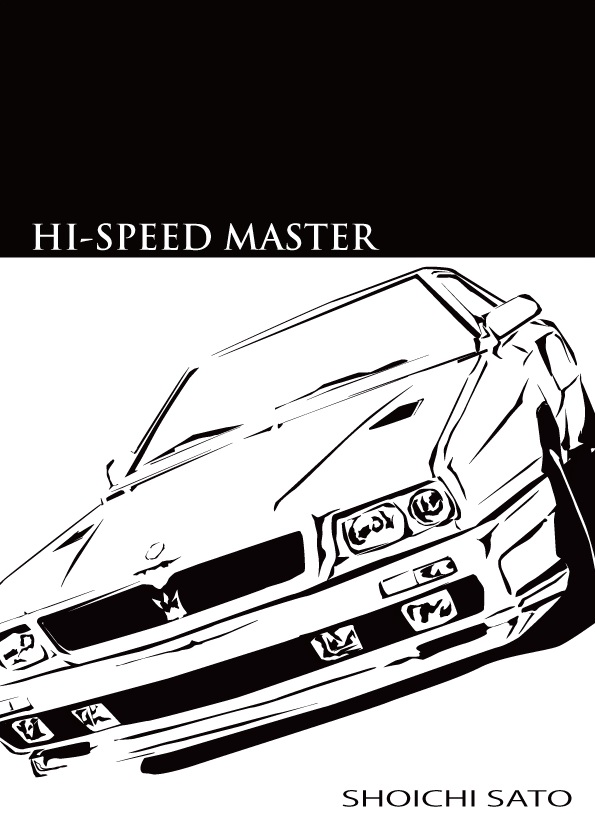
HI-SPEED MASTER
真夜中の大黒パーキングに現れたマセラティ・シャマルと湾岸線を激送あうる謎のフェラーリ288GTOを中心に二つのストーリーが同時に展開していく…。
NIGHT SPEED
真夜中の大黒パーキング。
男がクルマに乗り込み、エンジンを掛ける。
“キュキュキュ…ヴァンー!”
心地よいエキゾースト・ノートと共に、マセラティ・シャマルが目を覚ました。
男はメーター類を確認する。エンジンは既に暖まっていた。
ブースト計も安定している。
左足と右手を連動させ、ゆっくりとギアを入れる。
その時だった。
突然、助手席のドアを開け、女性がクルマの中に飛び込んできた。
「お願い、匿って!」
「なんだぁ?」
男は思わずエンストしそうになった。
「早く出して…お願い!」
「ハァ?」
窓から体が出ないよう、屈むように身を潜める女性は、バックミラーを気にしている。男もつられてバックミラー目をやると、一台のポルシェが迫って来ているのが見えた。
ポルシェはシャマルの前を塞ぐように急停止すると、中から血相を変えた20台後半位の男が走り寄ってきた。
色黒で髪の毛が肩まで伸びた、ホスト風のイケメンだ。
(あ~なんか面倒っぽい…)男はうんざり顔で空を見つめる。男と女のイザコザなんて、関わって得する事は一つもない。
男は助手席を見た。女性は怯えたような表情でこっちを見つめている。
「勘弁してくれよ…」思わずそう呟くとギアをバックに入れ、アクセルを踏みこんだ。
シャマルは勢いよくバックしながら方向転換すると、そのままパーキング内を逆走気味に出口へ向かう。
「―っざけんなよっ!」イケメン男はすぐさまクルマに乗り込み、ポルシェはシャマルを追ってエンジンの咆哮をあげた。
東京湾岸線。
二台のクルマが絡み合いながら疾走している。
ディープパープルのR34型スカイラインとソニックブルーのFD3S型RX-7。
どちらも湾岸では一目置かれる実力派の走り屋だ。
そんな二台の前方に、一昔前のシルエットを持つクルマが走っている。
フェラーリ288GTO。1980年代中盤に製造された、スーパースポーツカーだ。
今R34やFD3Sのステアリングを握っている男たちと、年令的には変わらない。人間なら体力、気力共に最盛期に近いが、クルマとなると話は違う。ファミリーカーならとっくの昔に現役を退いている年代の代物だ。
そんな年代物のクルマが、現代のフルチューンマシンをコーナーごとに引き離している様を目の当たりにした人間は、まず自分の目を疑うに違いない。
事実、遠ざかるフェラーリのテールに、追いかける二人の男は自分達の身に起きている現状が理解出来ずにいた。
「なんなんだよ、あのクルマ!」
R34のステアリングを握る松木が怒鳴る。FD とバトル中、行きなり後ろに張り付かれたと思ったら、あっという間に追い抜かれた。
最高速バトル中、ここまであっさり追い抜かれたなんて、過去記憶に無い。
一方、R34を操る新野は無言でフェラーリのテールを見つめていた。
その目からはいつになく闘争心の炎が燃え盛っている。
しかし、そんな二人の思いも空しく、フェラーリのテールは見る見る小さくなり、遂には二人の視界から消えていった。
走り出したはいいものの、何処へ向かったらいいのやら…。
男は戸惑いながら比較的ゆっくりしたペースで高速のスロープを上がっていく。
助手席の女性は何度もバックミラーを見ては気が気じゃないといった感じだ。
「…もっとスピード出ないんですか?」
鬼気迫る表情のさっきより、少しだけ落ち着いた声のトーンで男をせかす。
「安全第一がモットー。お巡りさんに捕まりたくないんでね」
そう言ってる後ろから、物凄いスピードでヘッドライトの明かりが迫って来た。
「追い付かれちゃう…!」
女性の表情が再び強張る。
「あのなぁ…最新型のポルシェ相手に、20年前のクルマでどうしろってんだ?」
1990年代に造られたシャマルは、当時のマセラティのフラッグシップモデルだった。
ピーキーで扱いずらいクルマながらも、腕に覚えのあるドライバーがステアリングを握れば、戦闘マシンとしての本性を発揮する。
とはいっても、現代のクルマと比べれば時代遅れ感は否めない。
「お願いします! 後でお礼でも何でもしますから」
流石の彼も、真剣に懇願する彼女の態度に他人事という訳にはいかなくなってきた。
何があったかは知らないが、どうみても悪そうな女性には見えない。
(…いやいや、女が一番危ない…)
心の声が葛藤している間に、ポルシェはシャマルのすぐ後ろに着き、パッシングとホーンを鳴らしまくっている。
ろくでもないこの状況で唯一救いなのは、助手席に飛び込んできた女性が可愛いという位か。
「…ま、いいか」
「―え?」
「いや、何でも。…とりあえずシートベルトしてくれる?」
シャマルとポルシェターボは、大黒ジャンクションから横羽線へと入った。
「ジェットコースターは好き?」
「え?」
おもむろに聞いてくる男の言葉に答える間もなく、彼女の体は急激にシートへ押し付けられた。
「―!」
急な加速、目の前にはクルマのテールランプが迫る、ぶつかる!…と思ったら今度は横G と共にクルマが右車線へ、また急加速…!
「…!」
目の前で展開される異次元の光景に、彼女は言葉も出せないまま正面を見つめていた。いや、正確には体が硬直して動けないといった方がいいかも知れない。
まるで生き物のようにしなやかに走るシャマル。路肩の殆ど無い横羽線のブラインドコーナーを疾風のごとく走り抜けていく。
余りに非日常の世界に、助手席の彼女は、もはや自分が何故このクルマに乗ったのかさえ、忘れかけていた。あれほど気にしていたバックミラーも、今では目を配る事もない。それより今はただ、目の前の景色に、ただただ釘付けになっていた。
一方、コーナー3つでシャマルが視界から消えたポルシェターボのドライバーは、泣きそうな顔で精一杯のドライビングをしていた。
「―っざけんなよ~っ」
彼の名は木下拓実。自称湾岸最速のポルシェマスター。あくまで自称なので、誰もその呼び名は知らないが。
俗に言うクルマの性能と自分の腕を取り違えている勘違い野郎である。
今宵、彼が再びシャマルの姿を再び目にすることは無かった。
首都高湾岸線、市川パーキングエリア。
何台かのクルマに混じって、フェラーリとのバトルに敗れた二台の姿があった。
「あぁ、しってるよ。黒いフェラーリだろ?」
そう切り出したのは新野と松木の走り屋仲間、桜場だった。因みに彼の愛車はNSXタイプR。二人に負けじ劣らずの実力を持つ湾岸ランナーだ。
「俺はまだ見たこと無いけど、ここ何日か頻繁に現れてるらしい。噂じゃ、司馬さんのR32もちぎられたって話だぜ」
「司馬さんが?」
新野が思わず声を上げた。
「司馬さんがちぎられたんじゃ、俺らがどうにか出来る野郎じゃないって事か」
松木が負け惜しみのように呟く。
「野郎じゃなくて女らしいけどな」
「!…マジ?」
さすがの松木も動揺を隠せない。
「まぁな。早くも『湾岸の魔女』だっつって噂してる奴らもいるよ。まぁ、二人が同時にちぎられたんじゃ、噂は本物だろうけどな…ってか、実際そんなに速かったの?」
桜場の問いかけに二人は言葉に詰まった。相手が女だと知り、流石にショックを隠しきれない様子だった。
シャマルは横羽線から湾岸に入り、尚も加速を続ける。
300キロ近いスピードで駆け抜ける東京湾トンネルの景色は、まるで異次元に向かうトンネルのようだ。
トンネルを抜けると今度は暗闇の中、物凄いスピードで灯りが前から後ろに流れていく―。
彼女は思った。今日の光景を生涯忘れることはないだろう、と。
新野達三人が別れて約1時間後。
首都高湾岸線葛西ジャンクション下り合流車線に新野のFDがアイドリング状態のまま待機していた。
車内の新野は、ハンドルにもたれ掛かり、バックミラーに視線と意識を集中させている。
「………」
その目は暗闇で獲物を待つハンターのようだ。
獲物は勿論…湾岸の魔女。
新野と松木は正反対の性格をしている。松木は普段から感情を表に出して生きているが、新野はちがう。常に何処か冷めていて、感情を表に出さない。
しかし、負けん気の強さで言えば、新野の方が上かもしれない。
感情を表に出さない分、内に秘めた闘志は人一倍だ。
遠くで特徴のあるエキゾースト・ノートが微かに聴こえた。
新野は反射的にギアを入れる。
FDは何かに弾かれたように加速し、支線から湾岸線へと合流した。
ムラなく加速するロータリーエンジンは、甲高いエキゾースト・ノートを響かせながら真夜中の首都高湾岸線を爆走する。
そんなFDの後ろから、急接近してくるヘッドライトがあった。スピードメーターは250キロを表示し、尚も加速を続けているFDに対し、あからさまなスピード差で迫ってくるクルマなど、この湾岸でそうはいない。
新野は三車線ある湾岸の一番左に車線変更し、ラインを開ける。その直後、右側から黒いフェラーリが姿を現した。
その瞬間、新野にはスローモーションのように時間がゆっくりと流れ、彼の目にはフェラーリのドライバーの姿がハッキリと映し出された。
時間にしたら一秒にも満たないその瞬間、新野の全身に熱いものが込み上げてくる。
“ヴォォォオー…ッ!”
フェラーリのすぐ後ろから新野のFD を追い抜くクルマのマフラー音で新野は一瞬の幻想から我に還った。
「…ハッ、あ、司馬さん?」
フェラーリを追いかけていたのは湾岸最速の白いR32型スカイラインGT-R だった。
新野は更にスピードを上げる。13Bロータリーツインターボが更に唸り声を上げた…が、ランデブー時のスピード差が有りすぎた為、追従出来ない。二台は果てしなく伸びる湾岸線の、その先にある暗闇へと消えていった。
シャマルは湾岸線の辰巳ジャンクションにある小さなパーキングに入った。
自分から先にクルマを降りると、彼女にも降りるよう助手席のドアを開けて促す。
(わぁ…)
クルマを降りた彼女は、目の前に広がる湾岸の夜景に思わず目を輝かせた。暫く夜景を眺めていると、後から声をかけられる。
「…ほら、これ」
振り返ると、そこにはジュースを差し出す男の姿があった。
彼女はちょっと遠慮がちにジュースを受け取り、軽く頭をさげる。
「あ、すみません…なんか、色々と」
やっと自分を取り戻したのか、彼女は自分のした事を恥じているように俯きかげんのまま、小声で謝っている。
男はため息混じりに苦笑いを浮かべた。
「よく平気だな。…ま、何があったかなんて聞く気はないから。とりあえず東京と横浜、どっちで降りる?」
女の下らない愚痴に付き合うのはゴメンだ、そんな言葉に聞こえる。彼女はさっきまでの態度とはうってかわり、小さくなって「すみません、すみません」と平謝りを繰り返していた。
流石に男も気の毒になったのか、「もういいから…」と、声をかけた。
遠くで走り屋のクルマ達が爆走している音が聞こえる。
「おーおー、今夜も魔女狩りにはりきってるねぇ…」
「え?」
「いや、何でも」
市川パーキング。
完全に二台を見失った新野は、縁石に座り缶コーヒーを口にしていた。
一つ、大きなため息をつく。
見上げた空には、見慣れた大黒ジャンクションのループが幾重にも重なり、新野の複雑な心境を映し出しているかのようだった。
頭から彼女の事が離れないー。そう、彼女は『湾岸の魔女』その人だ。
ただ一瞬、横顔を見ただけなのに、気になって仕方がない。
(…え?これって……一目惚れ?)
自分でも信じられなかった。
過去、彼女が居なかった訳ではない。むしろクルマと出会うまでは彼女を欠かした事は無かった。でも彼女が居ても心にいつも穴が開いてるような、そんな感覚が新野にはあった。
それを充たしてくれたのがクルマーそして湾岸だった。
それまで何かに夢中になったこと等無かった彼にとって、湾岸ランナーとしての自分は心底夢中になれる、生きている瞬間を味わえる唯一の場所だった。
そんな湾岸で出会った最高速の彼女。
(いったいどんな女性なのだろう…)
知らず知らず妄想が膨らんでいく。
“ヴォォー…”
新野を妄想から引き戻すように、低いRB サウンドが響き、白いR 32がパーキングに入ってきた。
(…あ!)
新野は思わず立ち上がる。白いR32はゆっくりパーキング内を巡回し、新野のFDの近くに停まった。
「司馬さん!」
R32から降りた男に、新野が声をかけながら歩み寄る。
「…おぅ」
その表情はいまいち浮かない様子だ。
「―さっきの…『湾岸の魔女』っすか?」
「あぁ、多分な。なんだ、お前も魔女に惚れたくちか?」
(…お前…“も”?)新野は司馬の言葉に引っ掛かったが、あえて触れない。
「んで、どうだったんすか?」
「どうもこうも…完敗だ。あれは早いぜ」
司馬は肩をすくめた。新野は言葉に詰まる。
「あ…いや、…マジっすか…」
こうもあっさり敗けを認める司馬の姿を、新野は見たことがなかった。
司馬は缶コーヒーを買い、一気に喉に流し込む。
「―ふぅ。…追うのか? あいつを」
「あ、いや…どーっすかねぇ。今まで司馬さんが勝てないなんて聞いたこと無かったし」
「…止めとけ」
「…は?」
「あれは走り屋とか湾岸ランナーとかのレベルじゃない。あのスピードに飲み込まれたら死ぬぞ」
司馬があまりに真面目な顔で言うので、新野も冗談ひとつ言えない心境になってしまった。
「今日走ってみて分かった。あの走りについていったら死ぬ。スピード云々よりも感覚の問題だ。ありゃあ本当に魔女かもしれないな」
「はぁ…」
納得しない様子の新野に、司馬は少しイタズラっぽい顔で尋ねた。
「…惚れたんだろ?」
司馬の言葉に新野は一瞬動きが止まる。
「ー別に隠すことじゃないだろ。それにあれと出会って惚れたってやつは、もう何人も居るしな」
「え? そうなんすか!」
司馬は新野の肩に腕を回し、ヘッドロック状態ひした。
「…俺もそのひとりだ」
「イテテ…」
「ハハハ…!」
今度は笑いながら新野の背中を叩く。
「ま、あれだ…別にライバルとかそういうんじゃねぇよ。つまり、あの『湾岸の魔女』はその位危ねぇって事だな」
「…よく分かんないっすけど?」
新野はとばっちりを受けた気分だった。
とりあえず横浜で降りるという彼女を乗せ、シャマルは再び湾岸線を横浜へと向かった。
誰に追われてる分けでもないので、今度はクルージング・ナイト・ドライブととなったシャマルの車内は、妙な空気に包まれている。
どちらが話し掛ける訳でもなく、ただ静寂の時間が流れ…たまらず男はカーステに手を伸ばした。
深夜のFMはゆったりとしたジャズが流れ、 通り過ぎる羽田空港の夜景と音楽が重なり、計らずもロマンチックなムードが漂う。
この先トンネルを抜けると夜景の絶景ポイントが続くだけに、これがデートなら最高のロケーションだ。
「…あの、本当にさっきはありがとうございました」
今宵はじめて聞く彼女からの感謝の言葉が、男には妙に照れ臭く感じた。
「だから、いいって別に―」
また暫く沈黙が流れる。
「……あの、さっきは凄かったですね」
「―ん?」
「クルマの運転、ジェットコースターより、よっぽど迫力ありました」
「あぁ、まぁ命の保証はないからねぇ…怖かった?」
「―いえ、意外と楽しかったです!」
そう言って微笑む彼女の表情は、嘘偽りの無いモノに見えた。
「まぁ、だからといって知らない男のクルマにホイホイ乗り込むのはどうかと思うけどね。俺が言うのも何だけど…」
チクリとトゲを刺す男の言葉に、彼女は苦笑いを浮かべた。
「大丈夫です。私、人を見る目は確かなんで」
「よく言うよ。さっきまで逃げ回ったクセに」
「あれは…仕方なかったんです! まさかこんな所に連れてこられるなんて思わなかったし…」
次第に声が小さくなるも、男には最後まで聞こえていた。…が、あえてそれ以上はきかなかった。
シャマルは扇島の長いトンネルを抜た。先には工業地帯のオレンジ灯が妖しく幻想的に瞬いている。その先はつばさ橋、ベイブリッジへと続くデートスポットだ。
お互い名も知らぬ男と女が真夜中にドライブするには、余りにもムードがありすぎるかも知れない。
その時だった。
後方からバックミラー越しに、物凄い勢いで迫って来るヘッドライトが見えた。
続けて聞こえてくる独特の甲高いエキゾーストノートに、男は思わず舌打ちする。
「ちっ…」
「?」
助手席の彼女は不思議そうな表情で彼を見たが、次の瞬間―。
“ッグァン!”
突然真横に出現した黒いスポーツカーに面食らった彼女は、そのまま固まってしまった。
暗くて車内は良く見えないが、女性らしき口元が微笑んでいるように見えた…のは気のせいだろうか。
シャマルに横付けしたスポーツカーは、5秒程弊走したあと、何かに弾かれるように一気に加速し、つばさ橋を走り抜けていった。
何が起こったのか全く分からない彼女は、暫くの間そのまま固まっていた。
絶好のデートスポットを他愛のない会話で通り過ぎ、シャマルは横浜で高速を降りた。
男は横浜駅東口でクルマを停める。既に電車は終電を終えているが、客待ちのタクシーが列をなしているので、帰りの足に困ることはないだろう。
「本当に有り難うございました」
「あぁ、気を付けてな」
一瞬の沈黙のあと、彼女はクルマのドアを開ける。
なにかを…期待したのかもしれない。
真夜中のドライブは、お互い相手の名も知らぬまま終わりを迎えた。
走り去るクルマを見送った彼女は、一つ大きなため息をついて夜空を見上げた。
“ヴアアアアンン…”
再び高速へ帰っていくクルマのエキゾーストノートが、ビルに反響して夜空に鳴り響いた。
HI-SPEED MASTER

