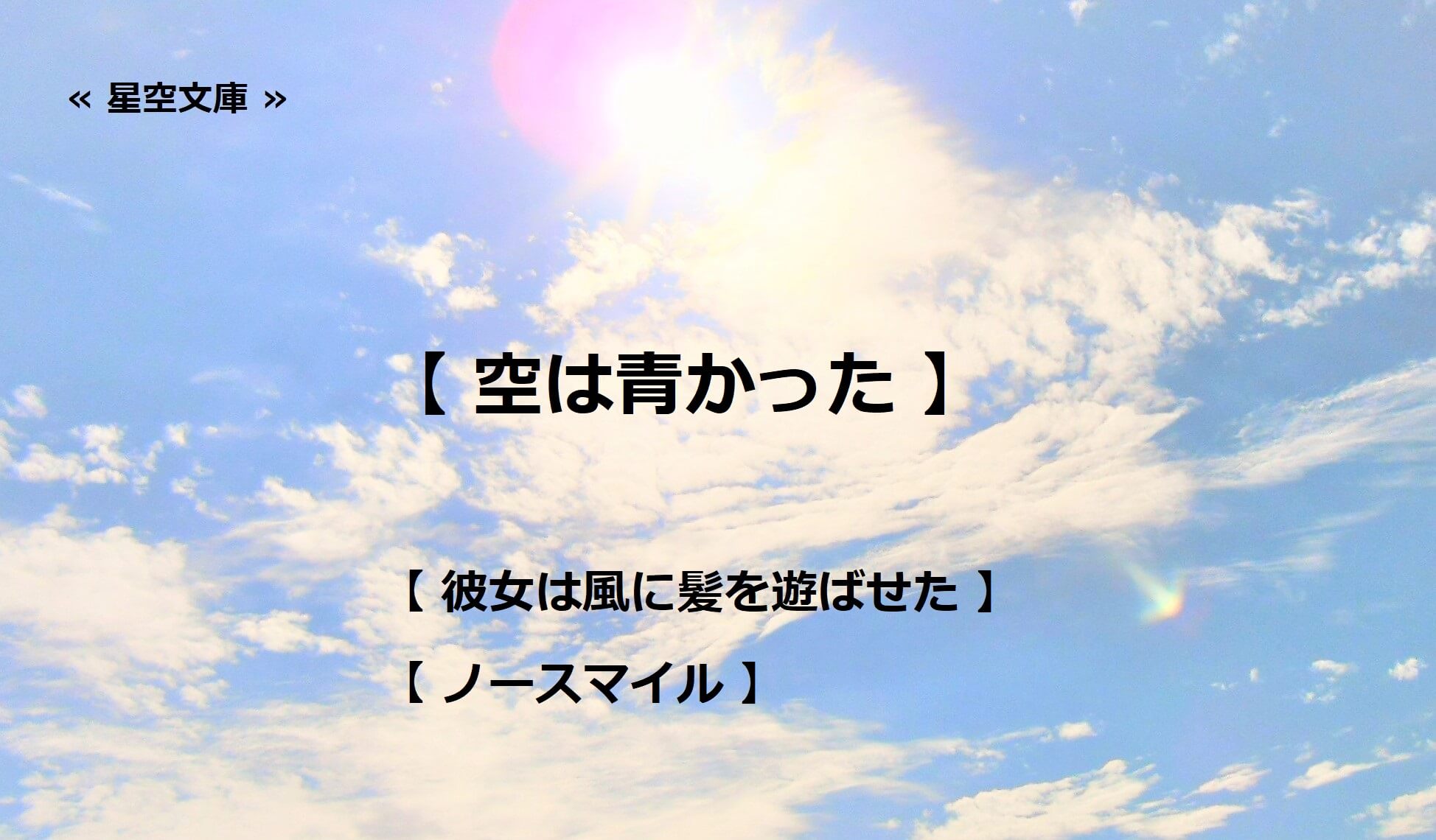
空は青かった
3部作です。
『空は青かった』
三時間目のチャイムが鳴り出した頃、僕は誰もいない学校の屋上のベンチに寝転んだ。
眩しすぎるぐらい晴天な空を微かに睨み、腕を伸ばして目を覆った。
少しして「よっ」と言う声が聞こえ、顔を横に向けると短めのチェック柄のスカートからスラリと伸びた細い脚が目に飛び込んで来た。
ドキッとして起き上がると黒髪で長めのポニーテールの少女が赤いフレームのメガネ越しにこちらを見ていた。
同じクラスのカヤノだ。
彼女は微かに笑むと、パック飲料を一口飲み言った。
「カズ、こんなトコで何してんの?」
「見りゃ分かるだろ。寝てんだよ」
僕はもう一度寝転んだ。
「そっ」
彼女は隣のベンチに座った。
「そっちこそ何してんだよ」
「サボり。体育つまんないんだもん」
「そっ」
少しの沈黙。
ズズズズズッーーとパック飲料を飲み尽くした音が聞こえ「ねぇ、カズ、起きてる?」と彼女は口を開いた。
「何?」
「もしさ、もしだよ」
「あぁ」
「私が居なくなったら、悲しんでくれる人って、この学校にどのくらい居るんだろう」
一瞬頭が真っ白になって、彼女が何を言っているのか、どう答えるべきか、分からなかった。
固まってる僕を見て彼女は取り繕うように「冗談だよ、冗談…」と笑った。
「そう…。どのくらい悲しんでくれる人がいるか分からないけど、でも、俺は悲しいよ」
と頭で考えてる事より先に口が開いていた。
「そっ…」
「あぁ…」
数分の沈黙。
微かに鼻をすする声が聞こえ、小さな声で「ありがとう…」って聞こえた気がした。
やっぱり悔しいほど空は青かった…。
- end -
『彼女は風に髪を遊ばせた』
「チエ…。起きてんのか? チエ…」
ドア越しに父の声が聞こえた。
「うん。起きてるよ」
私はいつものように当たり障りのない返事をした。
今日も一日が勝手に始まってしまった。
見た夢もいつもと同じ。
学校の屋上から飛び降りた瞬間、いつものように父に起こされた。
制服に着替え軽く化粧し、最後に鏡を一瞥してリビングに向かった。
「おはよー」とエプロンを付けた父の後ろ姿に言った。
「おはよう。今日はハムエッグだ」
「ふ~ん。おいしそう」
愛想良く返し顔を洗い椅子に座った。
これが私の父だ。
母は私が五歳の時事故で亡くなりそれからずっと二人で暮らしてきた。
父は再婚する気がないらしく、母が亡くなってから家事、洗濯、掃除を二人で分担して生活していた。
「あっまずい。遅刻する~」
私は掛け時計を見て言った。
「ハムエッグは?」
「トーストだけでいいやっ」
バターの塗られたトーストを咥え玄関で革靴を履きドアを開けた。
「行って来ま~す」
「車に気を付けろよ」と奥から聞こえた。
「は~い」
急いで玄関を出て、少し走り、曲がり角からはゆっくり歩いた。
「遅刻する~」とは言ってもまだ10分ぐらいバスの時間まで余裕があった。
私は父が苦手だ。
得に意味はない。
ただ苦手なだけなのだ。
反抗期かな?
先月一七歳になったと言うのに父の「車に気を付けろよ」という口癖は小さい頃から変わらない。
母が交通事故で亡くなったからしつこく言うのも分かるけど…。
学校に着くと自分の教室に入る前に隣の教室を覗き込んだ。
あれ? カヤノ来てないんだ…。
そう思っているとチャイムが鳴り慌ただしく教室に駆け込む団体に混ざり自分の教室に入った。
それからすぐ担任が入って来た。
「知ってる者も居ると思うが昨日の夜、本校の女子生徒が学校近くでトラックに撥ねられ今朝亡くなった」
ざわつく教室内。
誰?
「時間変更がある一時間目は…」
私は担任の声より前に座る男子達の小声が聞こえて来た。
「あれって隣のクラスの瀬戸カヤノって娘だろ」
え? カヤノが死んだ?
私は自分の耳を疑った。
「らしいな」
「瀬戸ってあのおとなしい娘だろ」
「あぁ」
「そういえばさっき職員室で、まだ事故か自殺か分からないけど、たぶん自殺だろうって言ってた」
カヤノが自殺?
「何で自殺なんか…」
「知らねぇよ。でも自殺なら逃げたんだよ現実から」
「お前その性格直さねぇと友達無くすぞ…」
カヤノが自殺した? 何で?
…屋上行かなきゃ…。
立ち上がるとキーっと耳障りな音が響き、皆がこっちを振り向いた。
「どうしたんだ?」と言う担任を一瞥し何も言わずドアを開けた。
「どこ行くんだ!」
「どっか…」と呟きドアを強く閉め廊下に出た。
ざわつく教室。
私は女子の友達が出来にくい性格らしい。
男子みたいにサバサバしている方が好きなんだと思う。
でも、そんな私にも最近女の友達が出来た。
長い髪を二つに縛り、メガネをかけて本ばかりを読んでいたカヤノだ。
私は『立ち入り禁止』と書かれた看板をどけ階段を登り重い鉄のドアを開けた。
最初に会ったのも屋上だったけど、最期に会ったのも屋上になった…。
「バカ…」
カヤノが死んだから悲しんでいるんじゃない。
カヤノが私に何も言ってくれなかった事が悔しいだけ…。
お母さんもそうだった。
「来年は五年生だね」って言ってたくせにいつの間にか私の前から居なくなっていた。
でもカヤノは違う。
もしカヤノが自殺したんだったら…。
教室で前の席の男子が「逃げたんだよ現実から」と言った時、悔しかったけど私もそう思った。
「死んだらおしまいなんだよ…」
呟き、結んでいたゴムを外し風に髪を遊ばせた。
- end -
『ノースマイル』
授業が終わり僕は何処にも寄らず家に帰えり「ただいま」と店先の鉢を片付け出したバイトの甲斐さんに言うと「カズ君、おかえり」と彼女は口の端を持ち上げた。
「もう片付けんの?」
「うん、真紀さんが雨降りそうだからって」
「そう、母さんが…。後で手伝うよ」
「うん…」
店のドアを開けるとカランコロンとベルが鳴った。
中に入ると母に「おかえり。今日は?」と聞かれ「ただいま。手伝うよ」と返し店の奥の階段を上がった。
去年から母は自宅の一階で花屋を始めた。
店の手伝いをするとそれなりに給料がもらえた。
僕はジーンズに着替え店の前掛けを付け甲斐さんの手伝いを始めた。
母と甲斐さんは「ちょっと商品チェックしてくるね」と奥の倉庫に行ってしまい、店番をしてるとカランコロンとドアが開き入って来たのは同級生のチエだった。
「よっ。まだ帰ってないの?」とチエの制服姿を見ながら言った。
「うん…」
「いつもの?」
「うん…」
「少々お待ち下さい」
壁側にあるガラスケースを開け中からカーネーションを一本取り出し「これでいい?」「うん」「じゃ包むから待ってて」「うん」とチエは僕が包むのをカウンターの前で待っていた。
「今日だっけ?」
「うん…」
「これから?」
「うん…」
「雨降るらしいよ」
「そうなんだ。でも行かなきゃ」
「そう。はい」
「ありがとう」
精算し終えたチエはカランコロンと音を残し出て行った。
それから数分が過ぎ母と甲斐さんが戻って来た頃雨が降り始めた。
「やっぱり降って来たわね」
「そうですね」と外を見ながら話し合う二人に「ちょっと出かけて来る」と僕はエプロンを外しカウンター横にある自分の傘を持ち外に出た。
まばらに降り始めた雨が勢い良く降り出すのにさほど時間はかからなかった。歩いて行くと交通量の多い交差点付近の歩道にしゃがむ人影を見つけ僕は近づき頭上に傘をさした。
振り返ったチエを見ながら僕は言った。
「バーカ…」
「来るなら花ぐらい持って来てよ。それに私の分の傘は?」と空元気なチエ。
「うるさいな…。家まで送るよ」
「うん…」
僕らは無言のまま歩き始めた。直ぐ横をトラックや乗用車が引っ切りなしに通り喋りながらなど歩ける状態ではなかった。
僕はチエの耳元で「住宅街の方行かない?」と言うと頷き交差点を曲がり五分ほど歩くとさほど車の音が気にならなくなった。
「そういえば何でカーネーションなの? 母の日じゃないんだから…」
「うん。私もそう思うけどカヤノが好きだったし…」
「そっか…。今何考えてる」
「そっちこそ」
「お前が笑わなくなった理由…」
「理由なんてないよ」
「そお?」
「だからやめてって! 何か聞き出そうとするような言い方」
「そんな言い方してないだろ」
「した!」
「そっ」
半年前、同級生のカヤノがトラックに撥ねられ死んだ。
事故か自殺かいまだに定かではないらしい。
カヤノが死んでからチエは月に一度同じ日にカーネーションを一本買いに来るようになり。
…その頃からチエは笑わなくなった。
何かに脅え、何かに苛立ち、少しずつ変わって行った。
僕は隣を歩くチエを見ながら「バカじゃねぇの…」と呟いていた。
「え?」
「お前が笑わなくなったからってカヤノは帰って来ねぇだろ」
「それぐらい分かってるよ」
「じゃ何で…」
「分かんないよ」
「カヤノは死んだんだ。ちゃんと泣いて自分の気持ちに整理つけて行かないと辛くなるのはお前だろっ」
「分かってるよ…。分かってるからもう言わないでよ…」
チエは立ち止まり、じっと僕を見つめながら、泣き始めた。
「誰が何と言おうとカヤノは自殺なんてしないよ」
僕はチエが泣き止むまでそばに居ようと思う。
あの日、屋上であったカヤノは確かにいつもと違って居たけど、自殺なんてしない…。
- end -
空は青かった


