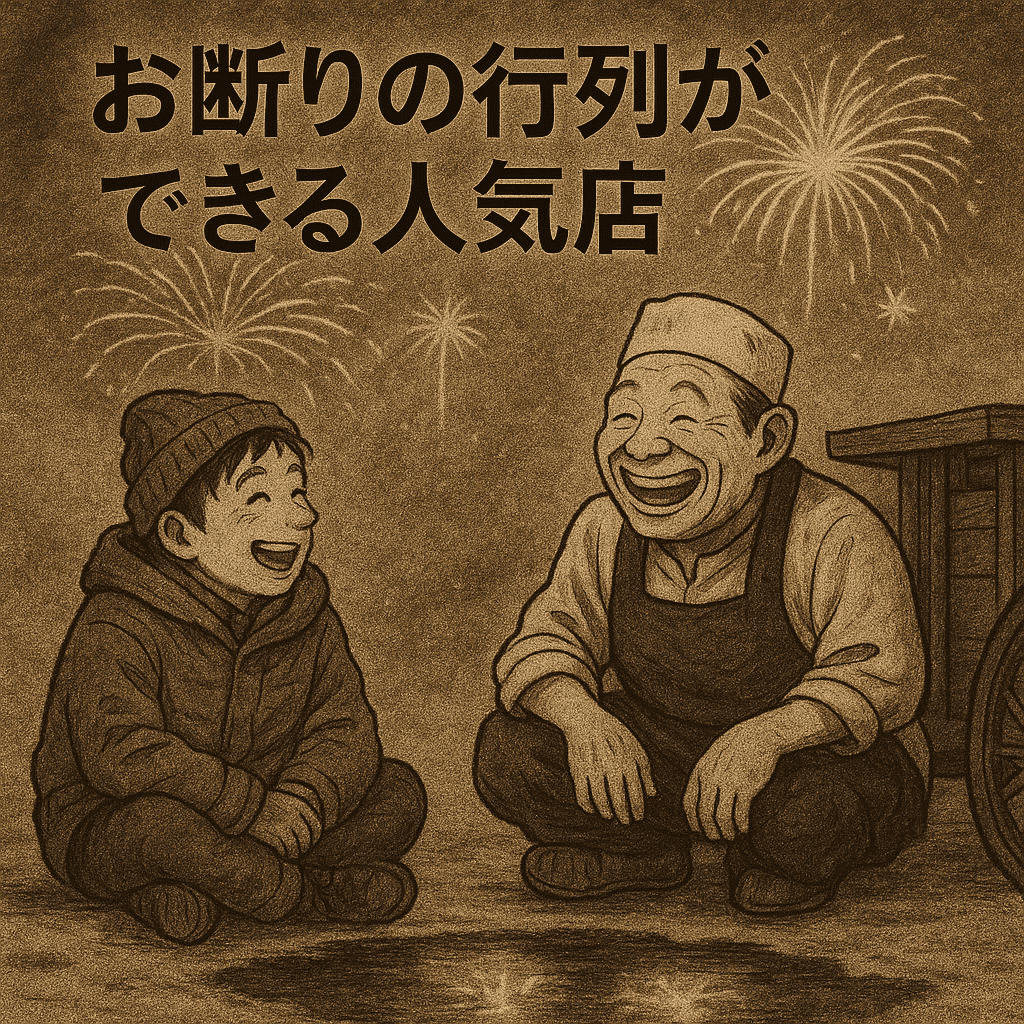
◽️プチストーリー【お断りの行列ができる人気店】(作品No_16)
【作者便り:気持ちが通じたときのお互いの笑顔ってかけがえのない瞬間ですよね】
発する声に霜がついてしまうような寒さ。
俺は一歩一歩踏みしめながらリアカーを引いている。
吐息が白く着色される。
ただ俺は幸いにもそんなには寒くない。
まあ、生計を立てるための懐事情は年中寒いけどな。
・・・いけない、そんなことぼやくようになったら俺も目も当てられないな。家族が俺を見つめている顔が、頭に浮かんだ。
寒くないのは、後ろで湯気が立っていて温かいからだ。
そして、鼻の奥に窓を開けた瞬間に吹き込む風のように醤油の香ばしい匂いが運ばれてくる。・・・たまらん、最高だ。
肺を大きくして思いっきり吸う。やはり最高だ。俺が創った自慢の風だ。
俺はラーメン屋。リアカー屋台で商いをしている。
俺の性分から、お店で客を待っているのがどうにもじれったくて、客のところまで俺から出向いて、少しでも早く一口目を、俺のラーメンを食べて欲しい。そんな想いからリアカー屋台を始めた。
なのだが、さっき自然とぼやいてしまったように、今日は客とほとんど出会っていない。それは・・・
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうううう
ばっばーーーーーーん
俺は足を止めて、音が打ち上がった方向の空を見上げた。
落ち着いた空を一瞬で華やかに演出し、見る人をただただ魅了する。
今日は、俺の住む街の毎年恒例の冬の花火大会。
花より団子といったもんだが、今日はあいにく、ラーメンより冬花火。
冬はラーメン屋台の稼ぎ時なのだが、毎年、この日だけはどうにも敵わない。頭でわかっていてもなんだか悔しい。まったくの八つ当たりだが、ラーメン屋を始めてから少し花火が嫌いになってしまった。
俺はサラリーマンを辞めて、一念発起、家族の応援と心配そうな視線を浴びながら始めた。だから、仕方ないとか、ここまででいいなんて納得がいかない、しちゃいけねぇ。
冬花火の魅力を越えて、みんなが一斉に視線を向けてくれる、
そんな俺のラーメンでありたい。俺のラーメンで笑顔にするんだ。
この街の人たちを、そして俺の家族も。それが最高だ。
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうううう
ばっ、ぱっばーーーーーーん
花火が俺を牽制しているように感じてしまう。俺もいつまでも策を講じてないわけではない。今日は長年かけてこの街の様々な道を巡り、試行錯誤で辿り着いた普段営業しているベストルートではなく、いつもはいかない道を、冬花火に人が集まっているので、人通りは比較的にない道を探しつつ、リアカー屋台を引く。
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうう
ひゅぅぅぅうぅぅうううううううう
ばっ、ばっぱっばーーーーーーん
大玉の冬花火の光が地上を一瞬照らした。
うん?この道の先に、、、、人がいる?
冬花火によって、点滅するように光が注がれる。
いた。成年があぐらを崩して道の地面にひとりで座っていた。
冬花火を観る定番スポットではないから周りには誰も居ない。
「おーい、そこの兄ちゃん! 寒いだろうからラーメンを一杯いらんかね?」
「・・・・」兄ちゃんは振り向かないし、口も開かない。
「おーーい!!兄ちゃん!うん?寒くて凍ってしまったのか?それなら、なおさらよ、うちのラーメンよ!俺の自信作で最高だぞ!一杯いらんかね?な?」
「・・・・・」
「ほんとに凍ってないだろうな。それなら救急車呼ぶぞ。それで救急車の中で・・・俺のラーメンを食らうと。兄ちゃん、これはそうそうできない体験だぞ。な。一杯どうだ?」
兄ちゃんはふいにこちらに振り返った。俺の白い帽子の頭の先から黒いジャンパー、中には白衣、足の長靴まで、値踏みをするように目でスキャンした。そして、言い放った。
「お断りします」
「いあ?!お?なんと?」変な音が漏れてしまった。
最高の俺のラーメンに、さらに最高の隠し味である冬の寒さというトッピングがあるにもかかわらずだ。兄ちゃんから発する言葉はあまりに俺の想定外だったので、構えていた心のキャッチャーミットから大きく外れた。
「お断りします」もう兄ちゃんは俺を見ていない。まだ俺は何もまともな言葉を言っていないのに言葉を投げてきた、ノールック投法だ。
「あー。あー。なるほど。なるほど。わかった。負けたよ、兄ちゃん。おっけい。今日は特別な日だもんな。ネギ多め。これで手を打とう」
「お断りします」
「なぬ。おいおいおい、おい!うちのネギは最高だぞ。それをたっぷりとと言っているのに・・・わかった。もう。チャーシュー、1枚追加!」
「お断りします」
「2枚追加!」「お断りします」
「3枚!」「お断りします」
「6枚!!」「お断りします」
「10枚っ!!」「お断りします」
「30枚!ってこれだとラーメンじゃなくてチャーシューが主役になって、麺チャーシューになっちまうぞ?いいのか?」
「お断りします」
「いいすぎだー!!これだけお断りしますを言われるとな、【お断りしますが行列している】みたいじゃねえか!勘弁してくれよ。行列はね、客にしてもらいたいのよ。縁起でもねぇ」
俺は顎を左手で乱暴に2回かいた。まいったな。
ところで、兄ちゃんは何で道で足をくずしあぐらかいて座っているんだろう?立っている俺は、兄ちゃんの頭から地面へと見下ろすと、兄ちゃんは道のへこんだ部分にある水たまりの方を観ていた。なんだ?変わった人だな。だから、俺の最高なラーメンに抵抗するんだな。
「兄ちゃん、そういえば、なんでこんなところでひとりで座っているんだ?変なものでも食べたのか?教えてくれよ」
数秒の間。場に出た言葉は。
「お断りします」
「おおおい!おいっ!俺のラーメンは注文しないわ、なんでここにいるかも教えてくれないわ。というか、兄ちゃん、思えば、お断りしますという言葉しか言ってないじゃねぇか」俺は思わず、言葉を発するタイミングに合わせて両手を上下にきびきびと動かしながら、おまけに兄ちゃんのはっきりとした意志たっぷりの口調を真似していた。
そんなふうにひとりでヒートアップしてしまった俺の無意識の行動を自覚したとたん、いったん静かになり、改めて口をゆっくりと開けた。
「脱サラして始めたんだよ。俺のラーメンに自信を持っている。誇りも持っている。食べればわかる。いや匂いでもわかる。家族を養うために稼がないといけないんだ。な?わかるだろ?
あ、わかった。引くに引けなくなって、お断りしますって言い続けてるんだな。兄ちゃん俺はそういうこと気にしないから。今が、初めて話しかけた気持ちでいこう。さあ兄ちゃん、俺のラーメン食っていくか!どうだ!」
「お断りします」兄ちゃんは俺が言い終わる前に言葉をかぶせてきた。
ハァハァハァ。あの手、この手のありったけの言葉をマシンガンに入れてぶっ放したので俺はいいかげん息が切れた。
俺の頭の中に試合を終えるゴングが聞こえたような気がした。
はぁ・・・。俺は立ったまま曲げた足に手をそえて、頭が自然と下がった。
「・・・冬花火を観ているんです」
聴いたことのない新鮮な言葉が、澄んだ空気に流れた。
「うん?お断りします?何を?」
「今は言ってないです。冬花火をここで座って観ていると言ったんです」
兄ちゃんがしゃべった。しゃべれた。もうなんだかそれだけですごく嬉しく感じる俺は、もうどうにかなっているのか。
「兄ちゃん、まずは見ての通り、俺と兄ちゃんしかいないよな。つまりそりゃ、ここが冬花火の指定された観覧場所じゃないから。それに、兄ちゃん、花火は上に打ち上げられているんだから、上を観ないと。さっきから兄ちゃん、ずっと下を観ているじゃねぇか」
「この水たまりにできた氷に映る冬花火を観ているんです」
「なんで?また?」
「この水たまりに映る冬花火は、この水たまりにまるで納められた生花のようで、この花火に目線を送っているのは僕だけだから、なんか気に入っているんです」
明らかに言いたくなかったこと、言葉を選んで伝えてますよと俺に態度で示していた。
「へぇ、初めて聞いた。どれどれ、そんなにいいものなのかい」
俺は兄ちゃんにさらに近づいて、水たまりに張った氷を覗いて、冬花火が打ち上がるのを待った。
きたきた。ひゅうーーーー。ばっばっーーん。
「兄ちゃん、氷が綺麗な鏡のようになっていないから、ぼやけちゃってるじゃないか。これなら、普通にみんなと同じで上を見上げて、街名物の冬花火を楽しんだほうがいいんじゃないか」
「お断りします」
あ、兄ちゃんまた戻った。しかも、もう話しかけないでという圧がすごい。
俺は無言で兄ちゃんをみた。兄ちゃんは、水たまりの氷に映る冬花火をじっと観ていた。
悔しいけど、やっぱり、冬花火には敵わない。俺の負けか。
俺はラーメン屋台の轅(ながえ=取って)に手をかけて、前進させた。
――――
ラーメン屋台が動き出した音が僕の背中から聞こえた。音は物凄いスピードで、どんどん遠ざかっていく。やっと、またひとりになれた。
花火の音に負けないくらい、大きな声の店主だったな。まいった。
さてさて、1年に1回の僕が見つけた楽しみを再開しますかね。
ここを見つけたのはほんと偶然だった。高校三年に通っていた塾の帰り。受験というリュックを背負った僕は、リュックに無造作に詰め込んだ答案用紙がこすれて火種がくすぶっているようだった。なんだかすぐに帰りたくない気分だった。自然といつもより遠回りで違う道を、そして頭は下を向きながら歩いていた。
タッ・・タッ・・タッ。僕の足音が耳に響く。
すると、突然、僕の視界一面に花火が上がった。
いや、下を向いているから上がるはずがない。
水たまりに氷が張っていて、そこに花火がぼんやりと映っていたのだ。僕は気付いたら立ちどまっていて、涙が目にたまり、余計に氷に映る花火がぼやけて見えた。
僕には、花屋で誰かのために束ねてもらった花束にみえた。氷に入ったこの花束は、いま、僕しか観ていない。
・・・僕に花束をくれるんですか。誰に言うとなく自然と問いかけていた。とうとう涙が頬をつたう。
ありがとうございます。僕は地面にゆっくりと座って、花火を観つめた。その日から、何か吹っ切れたのか僕は志望大学に合格できた。
あの日に僕の中に意志が宿った気がする。大げさだろうか。ともかく、僕には特別な場所なんだ。それ以来、毎年、僕はここに来ている。
来ている・・・。うん、なんか、急に息苦しい。なんだ?
「なるほどねぇ。これもまた乙な物ですなぁ。
なぁ兄ちゃん」
聞き覚えの余韻が耳にまださんざん残っている花火の音でなく、声が。
おそるおそる、顔は動かさず、目を横にすると、
頭には白い帽子、黒いジャンパー、中には白衣、足の長靴。
あの店主だ。僕の横にあぐらをかいて水たまりを覗き込んでいる。
「あの!」普段大声出さない僕がありったけの音量で。
「まぁ、まぁ、さっきは色々と悪かった。水たまりをみる兄ちゃんの姿がなんだか頭から離れなくて。屋台をいったん戻して、急いで戻ってきちまった」
よく見ると店主は汗で顔を拭いたかのようになっていた。
「兄ちゃんの気持ちわからないのに、勝手なこといってすまなかった。今日だけは一緒に同席させてくれないか」
僕の答えは決まっている。とっさに言おうと口を開けて
「おことひゃりします」
店主もとっさに僕の口に手をあてて言葉を戻させた。
「頼むぜ。もう、その言葉はこりごりだ。
袖ふれあうのも他生の縁ってさ。な、今日だけ」
もう僕は観念した。もしかしたら、今の店主にこの花束が必要なのかもしれないとふと頭によぎったからだ。僕がここでもらったように。
僕たちは、そのあと、いっさい無言で、氷をのぞき込み、映る冬花火を観ていた。
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうう
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうううううう
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうううううう
ひゅぅぅぅぅぅうぅぅうう
ばっばっ ばっばっ
ばっばっ
ばっばっばっばっーん・・・・・
最後を飾る、豪華絢爛の複数の特大の花火が映り、今年の冬花火は終わった。
とたんに冬の空気は静けさのカーテンが終演をつげるように降りてきたようだった。
そんな静けさの中・・・・ぐぅううう。
・・・・僕のお腹で終わったはずの花火が上がったように鳴った。
「ははは。はははははは」
自然とふたりで笑っていた。
僕はおもいっきり笑ってすっきりとした頭に浮かんだ言葉をそのまま伝えた。
「店主、いまさら、ですけど、店主のラーメン注文させてください」
店主は僕をしっかりと目を合わせて。
『それはお断りします』
店主は即答した。
「え?!あんなにラーメン注文して欲しかったんじゃないんですか。お断りするんですか!」
「まぁまぁ最後まで聞いてくださいな。今宵こんな花火の楽しみ方を教えてもらったお礼に、今日は奢らせてもらいますよ。と、いうことです。さ、いきましょか。俺の自慢の屋台までご案内します。兄ちゃんが今日最後の客だ」
僕たちは立ち上がり、道の先へと歩いていった。
にしても、やはり店主は常連の顔を忘れている。がっかりだ。
僕はこのラーメンの味をよく知っている。日によっては行列ができることもあって、道に人が増えると困るから、【行列をお断りするくらいに正真正銘の人気店】であることもよく知っている。それでも並んで食べたことだってある。
そう知ってる。冬花火に負けない、最高のラーメンだと。
(了)
◽️プチストーリー【お断りの行列ができる人気店】(作品No_16)

