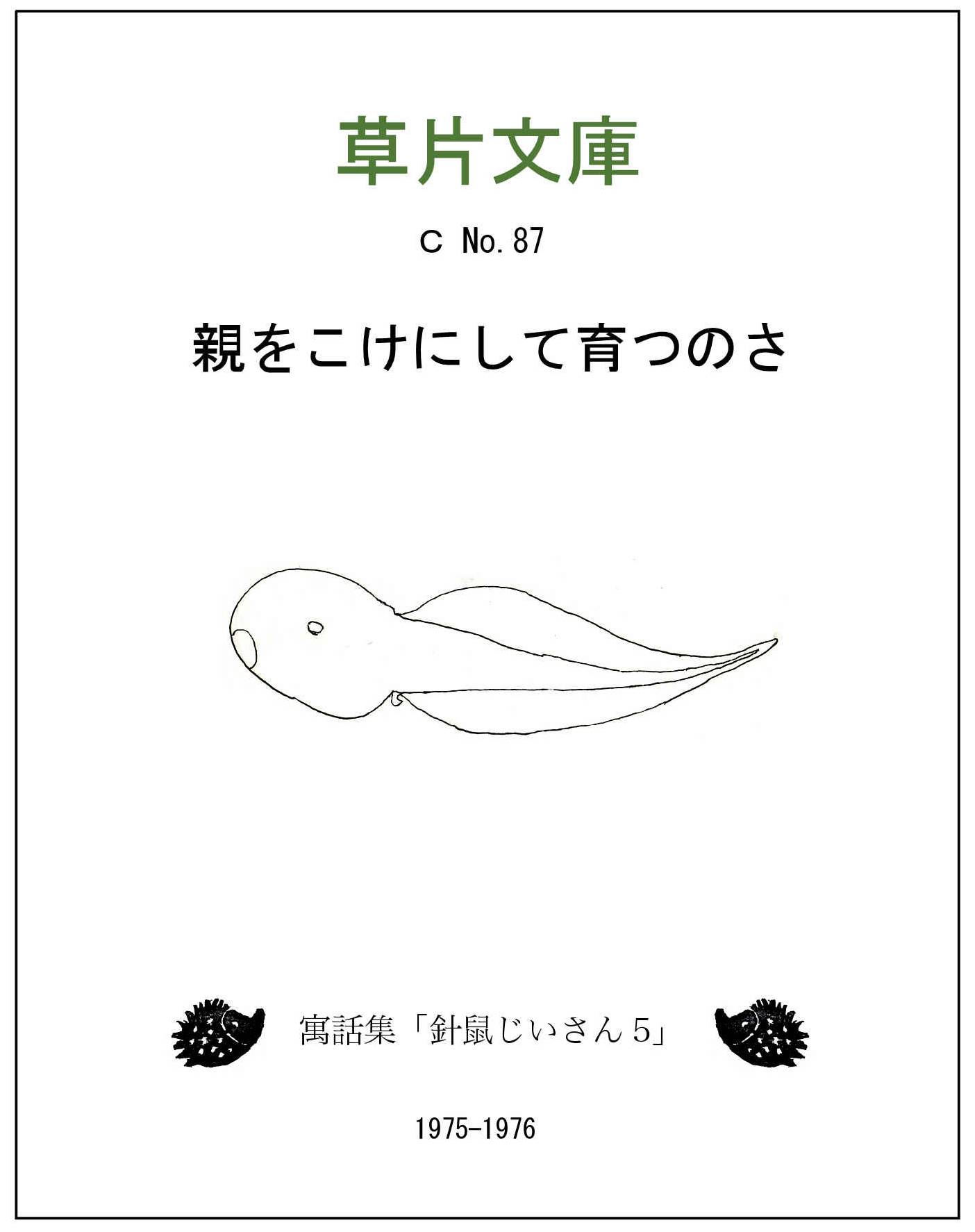
親をこけにして育つのさー寓話集「針鼠じいさん5」
春になった。
池の水もぬるまったくなって、水の中の虫たちも、すちょこすちょこ動きはじめた。
いつのまにか、ぶよぶよの寒天からぬけだし、いっぱしに泳げるようになったオタマジャクシが、藻のまわりに集まって、口をもぐもぐさせていた。
「この水草はうまくない」
やせたオタマジャクシが、からみあった藻の一つをつつきながらつぶやいた。
太ったオタマジャクシは、口いっぱいに藻をほおばって言った。
「そんなことありゃせんよ、うまいぜこれは」
大きな音をたててむしゃむしゃ食べた。
その音を聞きつけて、大きなゲンゴロウがやってきた。
「よく太ったね、おまえさん」
そう言うと、太ったオタマジャクシをかかえていってしまった。
オタマジャクシの一匹が、不思議そうな顔で、仲間に聞いた。
「あいつはどこに連れていかれちまったんだ」
やせたオタマジャクシは知っていたんだ。
「食われちまうんだ」
「そうか、食われちまうんか」
みんなはなんとなくうなずいた。
その時、大きなカエルが水の中に飛びこんできた。
オタマジャクシたちは、いっせいに水底にかくれると、ひとかたまりになって、食事中に飛びこんできた無作法なやつを見た。
「なんだあいつは」
オタマジャクシたちは、カエルが何ものか知らなかった。
カエルは、後ろ足を上手にけり上げ、池のまん中にある島に向かってすいすいと泳いでいってしまった。
安心したオタマジャクシたちは、また藻を食べはじめた。
「みにくい格好をしたやつだね、腹はふくらんでいるし、口がこんなに裂けていたじゃないか」
オタマジャクシは、自分の口をきゅうーと横にのばして、そいつのまねをした。
「だが、ゲンゴロウみたいにおれたちを食いにきたんじゃなさそうだ」
「あんなのに食われたかないね」
「手にゃ水かきがあって、足はひんまがってなんと不恰好なやつだ」
「乱暴に泳ぎやがって、水がにごっちまうよ」
言いたいほうだいのことを言うと、オタマジャクシたちは、また黙々と藻を食べだした。
しかしすぐにだべりはじめた。
「あいつにゃ尾っぽがなかったよ」
「あいつの目玉にゃ膜があって、開いたり、閉じたりしていたぞ」
オタマジャクシは、立派な尾っぽが自慢で、目にじゃまなまぶたなど無いんだ。
おいしいものを食べながら、他人の陰口をたたくのは、楽しいかぎりさ。
「あいつのからだはいぼだらけだ」
「俺たちはこんなにすべすべ」
「ところでよう、あいつはどこに行ったんだ」
「島のほうに行ったぞ」
「島にゃなにがあるんだい」
「あいつは島に何しにいったんだ」
「いいところなのもしれないぞ」
「おれたちもいってみるか」
「ずいぶん遠いけどいなあ」
そういいながらも、ものずきなオタマジャクシたちは尾を振って、泳ぎはじめた。
だけどやっぱり、島に行くには時間がかかった。
まだ子供だからしかたないさ。
ぞろぞろとむれをなして、泳いでいくうちに、雨がしとしとと降りはじめた。梅雨になっちまったのさ。
「島に行ったあいつはどこか、おれたちににていたな」
そう言った一匹が、腹を上に向けて泳ぎだした。
しばらくすると、他のオタマジャクシも逆さになってしまった。
島に行きつくころには、オタマジャクシたちに足がはえていた。
尾っぽもなんだか縮んだようだ。
一匹のオタマジャクシが、
「なんだこれ」と、自分の足をひょっとのばした。
からだがぐいっと前にすすんだ。
尾っぽをふろうとしたが、ちっちゃすぎて前にすすまなかった。
それだけじゃなかった。
オタマジャクシたちは、藻を食べたくなかった。
「うまいものを食いたい」
オタマジャクシの一匹が、なまずみたいな口をあけた。
そこに、カエルが島の上からぼちゃんと飛びこんできた。
オタマジャクシたちは、大あわてで石にかじりついた。
もう手も生えていた。
オタマジャクシたちは手を動かしてみた。
石の上にからだをもち上げることができた。
カエル子になったのだ。
ぞろぞろぞろとカエル子たちが、水の中から顔をだした。
「いい天気だな」
カエルの子は小さな手足を動かして、ぴょこぴょこと島にはいあがった。
尾っぽもなくなっている。
息を吸った。
「空気がうまいなあ」
目をぱちぱちさせて空をあおいだ。まぶたがついていた。
またぽちゃんと音がした。
カエルの子は、カエルが泳いでいくのを、島の上から見た。
そしたらね、
水面に小さなカエルの顔がいっぱい映っていた。
一匹が口をあけた。
裂けた広がった口が水に映っていた。
「いい顔になったなあ」
オタマジャクシだったカエルの子たちは、そう思ったということだ。
そして、虫が食べたくなったんだ。
親をこけにして育つのさー寓話集「針鼠じいさん5」
寓話集「針鼠爺さん、2015、209p 一粒書房)所収
絵:著者


