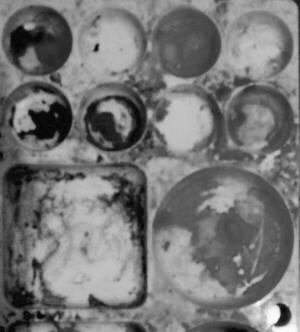tax
「電車で来たの? 駅まで送るよ」
その言葉に甘えて、僕は車の助手席にいた。
「ねえ、なにかいっしょに食べて帰ろうよ」
「すみません、仕事も残っているので……」
車のなかはお香の匂いが立ち込めていた。
それに、クラブミュージック……に分類されるのだろうか。そういう、僕の詳しくない分野の音を流しっぱなしにしているし、妻と違うところばかりが目についた。
「仕事、たいへんなの?」
「まあ、それなりに」
帰ったら、図面を完成させねばならなかった。
クリエイティブな仕事、と言えば聞こえは良いが、実際のところは明確に数字でバッサリと線が引かれている。予算や、面積……決められた枠のなかでどれだけ独立した立体を作ることができるかという世界だ。
「あの子だいじょうぶ? よく身体壊しているみたいだけど」
彼女は運転をしながら僕に話しかける。
「ええ、まあ……ふだんは元気ですよ、最近寒かったので」
そう返答しながら携帯端末にメッセージを打ち込む。
寝てる? というシンプルな質問を飛ばした。
ふだんはたいていすぐに返信があるのだが、今日は一向に反応がなかった。
妻は病に伏せていた。
本来であれば、今日、妻もこの場所にいるはずだったが、やむなく僕だけが参上したのである。
「むかしから、あの子は、喉が弱いみたいで……ひさしぶりに話したいことがあったのにな」
妹のことを話す彼女を、僕は羨ましく思った。
そう思うのは僕には兄弟というものがいないからかもしれなかった。
血の繋がりがあるという理由だけで他人を大切に思えるという単純で常識的なことが僕にはとても難しい気すらしていた。
「どうしてそんなに仲がいいの、羨ましい」
なぜか、僕が思っていたことを逆に返された。
「え? 僕たちですか」
「そう」
唐突に突き付けられる言葉にはしっかりとした方向性が定まっているように思えた。あとはそちらに向かって進んでいくのみだった。
「まあ……、僕もなんでも話しますし……もちろん腹立つときもありますけど……」
「そうなんだ、私たちなんて、結婚したら、とつぜん話合わなくなった感じ」
運転する彼女の薬指に指輪が光っていた。
「まあ……努力は必要ですよ……」
言いながら僕は、彼女の横顔に、妻を発見したような気がした。
とうぜんではあるが、姿形に面影があった。
知らなかった風景が、とつぜんいちばん身近なものに変貌していくようだった。
この車のなかでは今日この日、本来あるべきはずだった妻を補給するためにすべてが動いているように思えた。
「いいなあ、私も努力してくれるひと見つければよかった」
彼女の言葉に裏というものはなかった。
どこまで進んでも表ばかりで、そしてだからこそ僕は惑った。
純粋で鈍感なところは、妻によく似ていると思った。
信号には引っかからずに車はスムーズに僕を運んでいた。
心地よさと気分の悪さを同時に感じていた。
免許を取ってからは治ったはずの乗り物酔いというものが思い出されるようだった。
この車という枠のなかだけが外界から独立してしまっているような気がしたし、目の前のとつぜん現れた近しい存在に、際限なく甘えてしまえる気がした。
彼女がこんな話を始めたことが悪いような気もしたし、彼女が妻に似ていることが悪いような気もした。
僕に異性の姉妹がいなかったのが原因のようにも思えたし、妻が風邪で来れなかったことが悪かったような気もした。
あるいはじぶんには致命的に、性格に欠陥があるようにも思えた。
僕は駅に到着するまでに何度も携帯端末を確認した。
しかし通知音は鳴らなかったし実際にメッセージはなかった。
「着いたよ」
ドアが開いて外の空気が流れ込んでくる。
やはり、運転席にいた女性は妻ではなかった。
「ありがとうございます」
「じゃ、また」
閉めるときに触れた車のドアは冷たかった。
tax