
百合の君(67)
八津代の上噛島城は、第二子誕生に沸いていた。弟君誕生の知らせを受けて、珊瑚はしぶしぶ母の寝所を訪ねた。
まず彼が驚いたのは、父がいたことだった。そこは父の城ではあるが、全国を駆け回っているその人と会うことは、年に数えるほどしかない。
そして父の印象は、珊瑚の記憶とかけ離れていた。父は大事そうに、その赤ん坊を抱いていた。まるで地球を抱き上げるみたいだった。母は臥せっていて、病人のように白い顔をしていた。まるで魑魅魍魎が両親に化けているようで、珊瑚は逃げ出したい気持ちになった。
しかし、内心の焦燥とは裏腹に、珊瑚は身動きできなかった。気持ちとしては逃げ出したいが、義務としては両親に向かって進むべきだと分かっていた。そして、それを分かっていると知られると、かわいげがないと思われ、母の愛を失うのではないかと恐れた。
ためらっている珊瑚を、その母の視線が射た。それは氷の矢のように冷たく、珊瑚は嫌な予感が的中したような気がした。
「珊瑚も抱いてみなさい」
声も、知らない大人のようだった。いや、知らない大人でなく、彼をのけ者にする城の大人が、母の皮を被っているようだった。やっぱりだと珊瑚は思った。ずっと渦巻いていた嫌な空気が、形をとった。それは初めて母が珊瑚の意思を無視した瞬間だった。珊瑚は泣きだしたい気持ちになったが、そこはめでたい場であり、泣き出すのは最もふさわしくないと、子供心に悟っていた。
珊瑚は、自らの心を踏み越えて、赤子に向かって歩み寄った。母は雪原のような白い肌に、クレバスのような笑みを浮かべた。
「白浜、兄上ですよ」
白浜と呼ばれた赤ん坊は、猿みたいな顔で不潔だった。珊瑚はそれを抱きたいとは全く思わなかった。父の隣に座ると、おくるみの端を見つめた。それは嘘くさいほど真っ白だった。父は珊瑚に一瞥もくれず、その腕の中の赤ん坊をあやしている。
珊瑚は、そこまで父に近づいたのは初めてだった。そのうえ、彼自身が望んだことではないとはいえ、その腕に触れて赤子を奪うなど許される事ではなさそうに思えた。
「珊瑚、緊張しているのですか?」
珊瑚は母に照れ笑いをつくって応えた。この期に及んでも、彼はまだ赤ん坊を抱くことを免れるのではないかと期待していた。
「大丈夫ですよ、弟なのですから」
しかし母は、それが出産に欠くべからざる過程であると信じ込んでいるのか、絶対にその新生児を珊瑚に抱かせるつもりのようだった。珊瑚の視線は、母からはね返って自分の体の内側を見た。しかし、その小さな身中には、母の強固な意志を曲げられそうな物は見当たらなかった。
珊瑚は頭皮の奥、毛根の辺りがわじわじするのを感じた。父はちらと実子から、養子に視線を移した。珊瑚の見たその瞳の色は浅かった。押し出されるように珊瑚は目を伏せた。
その視界に、赤ん坊が侵入してきた。父に差し出されて、弟は威圧するように迫ってくる。
観念して、珊瑚は赤子を受け取った。その温かさが小便を漏らしたみたいで不快だった。真っ黒い瞳が彼に向いた。その瞳は、すべてを見透かしているようだった。見透かしている上で、問うていた。問うているのは、その赤子との関係であり、父との関係であり、母との関係であり、過去の道程であり、未来の運命であった。それは問うているのではなく、奪おうとしているのだと珊瑚は思った。そして、さらにいらついた。
いま手を離したら、どうなるだろう?
それは珊瑚が初めて抱いた殺意だった。珊瑚の頭の中で、赤ん坊の猿みたいな顔がしわくちゃに崩れて泣き叫んだ。
「かわいらしいものですね、これが兄になる感覚というのでしょうか」
しかし笑って見せた。母は花咲くように笑い返してくれた。それは本当にうれしそうだった。今まで見せてくれたことのない笑顔のように、珊瑚には思えた。現に、まだ九年の珊瑚の人生の中で、母と離れていた五年間は長すぎた。
それからはもう茫然自失だった。逃げるように部屋に戻ると、珊瑚は母からもらった人形を持ち上げた。首をひねろうとして、その瞳に気付いた。それは、白浜のものとは違っていた。人形の目は、何も映してはいなかった。何も問わず、何も奪おうとしなかった。その目に、珊瑚は不思議と見惚れていた。
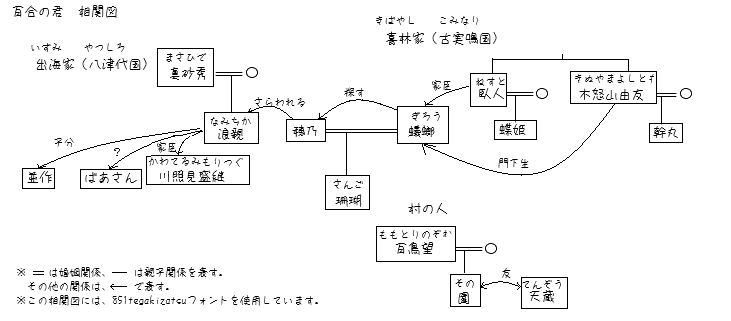
百合の君(67)


