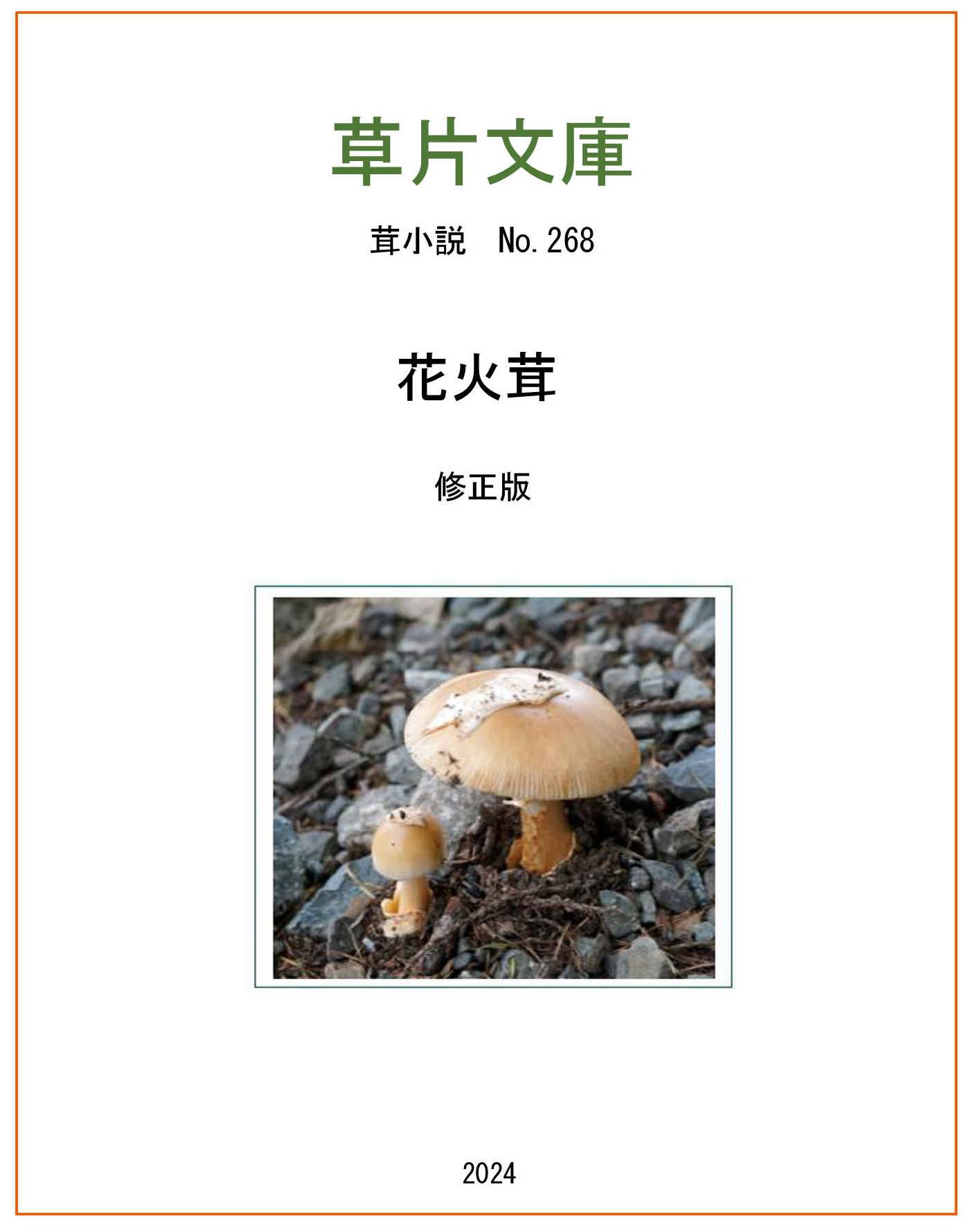
花火茸
茸と花火のファンタジー、指小説
夏の終わり、丘の林の中に茶色い茸が顔を出した。
これからは茸の季節だ。
とっとと大きくなって、羊歯の一番下の葉裏に頭の先がふれた。
茶色の茸が、辺りを見回すと、赤い茸や黄色い茸、真っ白の茸、おや、青っぽいのや、緑色のものまである。
きれいだな、自分の茶色は土の色、土の中で土の色をもらっちまったんだな、赤い色の茸に蠅が来た。ほかの色の茸の傘の上でも蠅が手足をこすっている。僕のところにもこないかな。
三日ほどすると、赤や黄や白、それに青や緑の茸たちが萎れてしまった。
茶色の茸は元気にたっている。まだ茸蝿がやってこない。
みんないなくなっちまった。寂しいね。
茸蠅がとんできた。
「茶色の茸の兄さん元気だね」
茶色の茸はうなずいて、うん、卵をうんでいいよ、といった。
茸蠅は、「そりゃありがとう、だけど俺は雄なんだ、申し訳ない」とあやまった。
「周りの色とりどりの茸がみんな萎れて土になっちまった」
「そうだなあ、俺はあっちに生えていた黄色い茸から生まれたばかりなんだ」
茸は、卵からかえった茸バエの幼虫に食べられて、死んでいく運命だ。
「それがな、ふしぎなことに、雌が生まれなかったんだ、だから、雄ばかりだ、それで、俺もこれから、隣の林に雌をさがしにいくんだよ」
雄の茸バエは飛び立っていった。そういえば、蠅がいない。いつもはうるさいくらいだ。
その夜、暗くなったら、どーんと音がして、茶色の茸がゆれた。
なんだ、と見上げると、空の上に、いろいろな色の花がさいた。
また、どーんと音がした。
見ていると、夜空に赤青黄色の光の花が咲いて萎れた。
一つ一つが、茸に見えた。
茸の仲間が空にあがって、燃えていく。だけどきれいだな、僕も夜空にのぼって、光りたい。
周りの茸がとろけていくのをみて、そうなりたくないと思っていた茶色の茸は、空に上がって消えるのはいい名と思った。
「ありゃ、花火って言うんだ、人間がつくって、夜空に打ち上げるんだ」
頭の上から声がした。羊歯のじいさんが教えてくれたんだ。
「僕も花火になりたい」
「どうしてだい」
「夜空の上から、林を見下ろして、ぱっと消えていくのきれいじゃない」
「花火は人間のものだからな」
羊歯のじいさんはむずかしいよといった。それに、茶色はないんだよといった。
「どうして、茶色はないの」
「目立たないからかな」
やっぱりそうかと、茶色の茸はちょっとしょげた。でも、花火になって、空にあがりたい。
そう思っていると、もぞっと身体が動いた。
「いっておいで」
土の中から声がした。
誰だろうとおもっていると、菌糸だよといっている。菌糸ってなんだろう。
「菌糸は茸そのものだ、あんたも菌糸でできているんだよ、でも、今俺たちから切り離したから自由だ」
菌糸に言われ、茶色の茸は動こうと思った。そうしたら、つつつ、と羊歯の下からでることができた。
これなら、山からでて、丘から降りて、人間の世界にいくことができる。
「行っといで、だが気をつけるんだよ、人間は茸を食っちまうんだ」
羊歯のじいさんが注意した。
茶色の茸は礼を言って、丘を覆っている林の中を降りていった。
どーんと、また花火が揚がった。
立ち止まって見上げた。なんときれいなんだろう。花火になろう。
急いで、丘の麓にでると、夜の町をみわたした。家々に明かりがともり、それもきれいだった。
光りたい。茶色の茸は思った。
家々の間をすすんでいくと、
一軒の家の庭で、小さな花火が見えた。
茸は垣根の間からのぞいた。
女の子が手に持ったひもの先から、花火が散っている。
かわいい花火だ。
垣根の木の葉の上のでんでん虫が、
「線香花火って言うんだ」と教えてくれた。
「空にあがる花火になりたい」
はて、茸は花火になれるかな、蝸牛はちょっとわからなかったが、茶色の茸の夢は壊すべきではない。そう思って、
「町のはずれに、花火を作っている工場があるよ」と教えた。
茶色の茸礼を言うと、町の真ん中を流れ川の上流にむかった。
ここらあたりかと、見上げると、そこに花火工場があった。
花火工場では打ち上げ花火をつくっていた。
花火の殻にいれる火薬が小さく玉になって机の上につんであった。これから人間が手作業で、殻に詰めていくのだろう。
ちょうど茸の大きさじゃないか。
茸は火薬の玉のように、柄を縮めて傘と合わさり球になった。
花火職人が、火薬を一寸玉の中に並べていく。一番真ん中に茸が入った。
こうやって、花火の玉の中に入った茸は、打ち上げられるのをまった。
夏の終わりになった。また花火大会だ。
茸のはいった花火の玉は、町を流れる川の川原に運ばれた。
花火師が筒に火薬を込め花火玉をいれた。
火がつけられると、ポット音がして、しゅるしゅると夜空にあがった。
どーん、おなかに響く音が森中にひびくと、大きく花火が開いた。
その真ん中で茸は自分の森を見下ろした。
濃い緑におおわれている。花火の光で木の葉が輝いている。
森もきれいだな。
茸は思いっきり傘を広げた。
白い胞子が飛んだ。
茸は白い粉の尾をひいて、ひらひらと落ちていった。
花火を見ていた子供たちが、落下傘だと思って追いかけた。
落下傘茸は森の真ん中あたりにおちっていった。
花火茸は森の中に小さな泉を見た。
その回りには、色とりどりの茸がはえている。
泉がどんどんせまってくる。
ポチャンと水しぶきがあがった。
茶色の茸は泉の中にはいると爆発をした。
人生は爆発だ。
その通りだ。
茸の爆発は、泉の周りの茸たちも爆発させ、
いろとりどりの茸の破片が水の中に広がった。
泉の底にいたナマズの子どもがおどろいて顔を出した。
ひげの上に茶い茸の破片が落ちてきた。
それにいい匂いだ。焼いた茸の香りだった。
ナマズの子供たちは、いろいろな色になって砕けた茸を食べた。
とてもおいしかった。
色々な色の茸の破片を食べた。
中でも、茶色の茸の破片が一番美味しかった。
もっと食べたいな。
ナマズの子供たちは、夜空に花火が揚がると水面に髭をだした。
大きな花火の輪はとてもきれいだった。
だけど茸はおちてこなかった。
花火大会がおわってしまった。
茶色の茸は森の中で一番おいしい茸だった。
ナマズの子どもは何度も何度も、泉の水面に顔を出して夜空を見上げた。
ふと、泉の脇を見た。
茶色い茸の子どもが顔を出していた。
一番美味しい茸だ。
大きくなったら、花火茸におなりと、いってやろう。
花火茸


