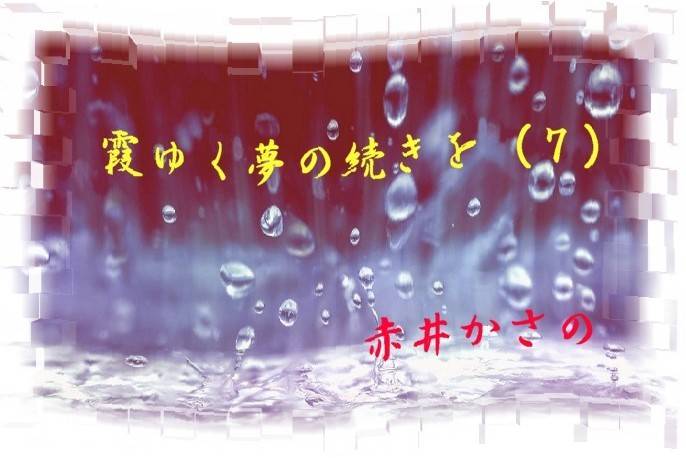
霞ゆく夢の続きを(7)
(45)
今にも雨が降り出しかねないモルタルの曇り空。空が灰色に塗装されている。空に透明感がない。たれこめる雨雲。光が虚空に吸い込まれていく。暗鬱な色の叙述。塗り絵のようだ。暗い色調が風景を覆う。テレビ画面の灰色の点描。雨雲を押し広げ、太陽をのぞかせてみたくなる。あの黒雲母の空の欠片を剥がせば、そこから光が射しこんでくれるかもしれない。
天幕が水を含んでじっとり重い。厚き雲がのしかかる。この黒々とした雨雲が今にも鉄板に変じて頭の上に落ちてきそうだ。この広い空全体が重みで落ちてきたらどうなるのだろう。もし落ちてきたとしたら、空ってもんは持ち上げることができるものなのだろうか。おっとその前に、僕はチビだから空に梯子を架けなきゃな。
ここはバスの中である。外界と区切られた空間、そこは街と異なる時間が流れている。バスがビル街をぬって走る。車窓が流れゆく風景を切り取る。
さすが福岡の中心街だ。平日なのに人通りが多い。この人たち一人一人にも、それぞれ微かに異なる時間が刻まれているのだろうか。時計の針が刻まれる音に合わせて、鋏がチョキチョキとそれぞれの人生を切り取っていく様子が見えるかのようだ。
レジ袋が風をふくみ、歩行者たちの足許を縫うように転がっていく。窓枠に遮られレジ袋が目で追えなくなったところで、赤井君は神妙な面持ちで空を見上げはじめた。彼の心にもいささか暗雲が宿りはじめたらしい。
通退勤者は回遊する魚のように、定まった時間帯に群れをなして移動する。ラッシュアワーを外れた車内はことのほか空いていた。赤井君は最後列シートにゆったり座っている。
アイツの件で魂消てしまった赤井君は、とうとうそれを彼女への電話を先延ばしする口実にしてしまった。散らばった感情はいまだに組み立て直せない。ドリフのコントよろしく頭に金盥を落とされた気持ちだ。彼はアドリブに弱い。いったん予定が狂うと、焦燥感をかかえながらも最後の最後まで狂わせたままでいるタイプである。
───県庁から電話するのはダメだ、アイツが現れるとは思いもよらなかった。いつ何処に現れるか分からない、まったく。もしかしてアイツは何人もいるんじゃなかろうな。よしてくれよ、分身の術か。そんなにアイツがいっぱいいるのなら首実検しようがないではないか───
こんな下らないことを色々と考えているうちに、電話するのは場所を変えて気持ちの整理がついてからにしようということに落ち着いてしまったのである。煮えきらないこと、この上ない。この期に及んでも決断のヤジロベエが左右に揺れている。
冷静に考えれば、アイツが花菱社長の息子だろうが赤の他人だろうが、そんなことは大したことではない。しかし小心者の赤井君は、太陽の黒点のちょっとした変化で地上に磁気嵐を起こしてしまう。おかけで計器はくるいっぱなし、誤作動で異常な数値を指す。
〈君はどういうシステム障害を起こしているんだ。脳内がオーロラの鮮やかな色彩に照らされて、はからずもフィーバーしちゃってるのかな。なんでこんな取るに足らないことで地が割れたように動揺をする。針小棒大に自分の運命にもからませて考えてしまうから、無駄に羽を生やして雲間に迷うことになるんだよ〉
気まぐれに乗ったバス。辺りはいよいよ暗くモノクロに沈んでいく。薄紙にすかした情景はどことなく遠のいて見える。ガラス越しに見ているからだろうか。この灰色の情景をクレヨンで塗ったら、童話にでもなるのかな?
きめ細かな雨がすでに降っているのかもしれない。街全体が蝋人形の眼の、奥深いガラス色に包まれている。湿潤な大気と空が今にも僕の肩に灰色コートをかぶせそうな気配がする。
赤井君は今、“どこから彼女に電話しようか”と、ノロノロ運転の車窓から落ち着けそうな場所を物色している最中である。羅針盤を持たぬ地図なき航海。目的地は朧月のように霞んでいる。さて、どこかに小粋な喫茶店でもないものか。
───風にのり何処にいくのかシャボン玉
そう、彼はシャボン玉だ。当てどもなく宙にぷかぷか浮かんでいるだけ。何をぐずぐずしているのだろうか。菜の花畑をお散歩か。全くのんびりしたもんだ。あの時からずっと下りエスカレーターを逆向きに上ろうとしている。事態が一向に進展しない。彼が女にまったく相手にされないのは、見てくれや甲斐性無しのせいだけでもなさそうだ。

雨の雫が窓ガラスに数粒たれた。これはまずい、ついに小雨が降りだしたか。雨の一粒が心にも落ちて、肺の奥に小さな染みをつける。ここでいくら言葉を発しようとも、発したそばから煙や蒸気と化して、黙に帰してしまいそうに思えてくる。
細き雨が喧噪の街に音なく光る。微かな雨音が都会の混沌にそっと加わろうとしている。黒い雲の下の不安、鼓膜に滲み入る雨滴。雨がアスファルトを冷やす。雨が肌ざわりをもって感じられる
通り雨であってくれればいいが。いつの間にやら街路樹の葉に小さな雨粒がきらめきだす。葉に躍る水晶玉。花びらの一枚一枚が色濃く雨を含み、ほんのりと華飾をよそおう。
過ぎゆく風景を窓から眺めるうち、頭の中で雨が音階を奏でだした。雨粒が五線紙に音符を置いていく。雨音が囁く。雨音が歌声を響かせる。
雨粒が透明な糸を引き、窓ガラスに水の簾を流している。色合いと彩度が落ちた都会の塗り絵。街並みや行きかう人たちが全て蝋細工に変じた。窓の外、風景がモノクロに沈んでいる。透き通った蜃気楼の街並。流れる水墨絵巻。色のない夢の中にいるかのようだ。空も暗い膜が覆っている。そこで一首。
───灰色の遠き果てより落つる雨 未来を知らぬ寝顔にかかる
風景が重々しく暗い。巨人の灰色の手の平が空を割って、すべてを押し潰そうと今にもかぶさってきそう‥‥‥そんなふうにこの雨空を擬人化したくなる。もしここにうつらうつら微睡む子供がいたなら、悪夢に迷い込んでしてしまっても不思議でない。
見下ろす巨人と見上げる小人───「よお、大巨人さんよ、こんな雨の日に現れて、電線で綾取りしようものなら感電しちゃうぞ」
小人がそう呟けども、もちろん返事はない。天と地は結び合えない。いくら呼びかけようが、空模様にユーモアは通じないのだ。
短歌も陳腐ならユーモアも空振りだ。小説はもとより何から何までぜんぶ素人。箱村の言うとおり自惚れているだけで僕には才能は欠片もないのかな。書く小説書く小説、読む人が読んだら、ただ文字の死体が並んでいるだけなのかもしれない。
それにしてもアイツはまるで不知火だ。沖に浮かぶ漁火が冷気によって屈折し、さまざまな形に変化するように、正体の捉えどころがない。
ひょんな時にふらりとやって来ては、すぐいなくなる。いなくなったと思ったら、また顔を出す。すぐ現れすぐ消えるところも不知火とそっくりだ。そうやって関係がつかず離れず未だに続いている。
大学時代はどちらかと言えば大人しいタイプだったので、お堅い縦組織に就職したのはよかったと思っていたところ、どうやら今は縦組織にありながら横車を押しているらしい。おまけにえらくお喋りに変貌していた。皮肉っぽく言わせてもらえば、あの講釈好きには辟易する。このように、アイツとばったり遇うごとに今まで知らなかった意外な発見がある。
この度もそうだ。不意打ちをくらわされた。アイツが花菱の息子だとすれば驚きである。不意打ちといってもアイツが隠していたわけではない。こっちが今まで気づかずにいただけのことだ。パーソナリティーには色々な側面があるので、どれが本物なのか分からない。たまたまその色を見ていなかった。それが気づかなかった理由だろう。
アイツは多様な人格を具材にして煮込んだ寄せ鍋なのか。それとも仏師が幾つもの魂を入れた寄木造りの仏像か。このことは箱村にも通じる。そして、もしかしたら僕にも?
それより何より普通、名前ぐらい尋ねるだろう。今まで名前を知らずによく付き合ってこれたもんだ。お互いそれで気にならなかったと言うことだ。妙な話である。
たしか歳時記には不知火は秋の季語とある。なるほど俳句などは季節感が大切なんだろうが、異常気象の影響でこう暑さ寒さがくるくる入れ替わると、季語を無理してはめ込む意味が分からなくなる。最近では秋と言っても名ばかりで、地球温暖化の影響で猛暑が続く。季節柄アイツも涼風をつれて現れてくれればいいものだが、遇うたび何となく暑苦しい。暑気払いしたくなるほどだ。トコロテンのようにツルンと出てくる奴だと聞けば涼しげだが、とても軒風鈴を鳴らす爽やかな風とはいかない。
今回だって、詰まるところアイツの結論は「小説なんてジジイになってから書け」だ。まったく箱村と同意見。御両人、人生に二毛作させようとする魂胆らしい。これが大人の見方というものか。一回こっきりの人生に、違う生き方が二度できると本気で思っているのだろうか。忠告が優しさだということは重々承知しているが、正直暑苦しくて有難迷惑である。
暑苦しいと言えば、花菱の忠告も回りくどくて暑苦しい。やはり花菱の子供なのだろうか。アイツが花菱の子供だとすると、花菱は50代後半から60代前半に息子を授かったことになる。うん、あのヤリちん社長ならあり得るな。死んで棺桶に寝かされてもアソコだけは立っているようなエロ爺いだ。
離婚した奥さん、つまりアイツのお母さんは、かなり年下女房だったんだろう。金にまかして若い女を釣り上げたな。絶倫助平じいさんの花菱のことだ、50代はまだ性欲真っ盛りだろう。これもあり得る。
雨が大降りになってきた。荒れ模様だ。大雨の中、ぬかるみに足を取られた気持ちだ。悪くすると、ぬかるみがそのまま泥沼になってこの身を呑みこんでしまいそうな勢いである。
雨の層が幾重にもかさなり厚みを感じさせている。雨音の連鎖。音が跳ねる。流れる音が繋がる。降り注ぐ雨が地面を打ち、水煙を立ちのぼらせる。噴煙が空を焦がしたかのように、辺りが瞬く間に暗くなった。
ブラックボックスを無理にこじ開けようとしても無駄である。変数が多すぎればグラフは描けない。深読みだろうが浅読みだろうが、いずれにせよ想像するだけでは埒が明かない。事実を確認することなしに思考を積み上げても堂々巡りになるだけのことだ。ちょうど今のこの窓ガラスと同じで、拭いても拭いても曇ってしまって視界不良、結論が出ない。そんなこと、分かりきっている。
夜霧の銀河鉄道、絵本の中に夜汽車が走る、行き先はどこ? 闇夜の線路はどこまで延びるのか。レールの先は暗くて見えない。
血の巡りが悪いうえに科学的思考力のないド文系の彼にとっては、喩えるとすればそんな具合である。空想が空想を呼び、そのうち寄り道しては、ふと異国情緒たっぷりのメルヘンの世界へ誘われかねないありさまだ。子供の頃からそうだ、不器用で出来が悪かった。四角い色紙をどこまで折っても鶴になってくれないのだ。必ずどこかで折り方を間違えた。
「居着く」という武術の概念がある。大まかに言ってしまえば、局所的に意識が集中し過ぎると、それ以外の情報がみえなくなり、臨機応変な対処力を自分から奪ってしまうという意味だ。果し合いにたとえれば、相手の刀ばかりに気を取られ、相手の全体の動きにまで目がいかない。結果、体がかたまって攻撃にスムーズに即応できなくなってしまうのだ。
赤井君の思考はいつも居着いている。思考停止ならまだしも、一つの事柄に集中するあまり堂々巡り、そのうち不快なネガティブ感情のスパイラルに入っているから始末が悪い。もっと視野を広げ、いろいろな角度から分析し、一点に心がとらわれないようにすべきなのだ。
とはいえ、彼に「居着くな」と言ったところで蛙の面に小便、ダメの皮だ。硬直思考の赤井君。体の硬い奴は頭も硬い。数時間前には浮かぶのは箱村の奥さんのことばかりだったのが、今はアイツのことで頭が一杯。
雨粒が窓ガラスに水の星座を描いている。ガラスに映った赤井君の顔が雨水でゲル状に流れ落ちる。街路樹が風に舞い、雨に濡れた葉が光っている。大波が粗い砂を鳴らす音。雨音が神経を逆なでする。雨が打ち寄せる波になる。護岸に砕ける波が形なき時間を散らす。
水風船を割るがごとく一気に大粒の雨が落ちてくる。車窓がさらに濃い着色ガラスに変じた。薄紙に透かした枯色の街。雨の一粒一粒、その中に小さく変形した街々が映り込む。レントゲン撮影された街。人や風景の輪郭が濡れ色にぼやけて心霊写真になる。
風景は人の心を映す鏡だ。普段なら何のこともない雨模様も、心のありようで今のように暗く打ち沈んで見えることもあり得よう。
───街がまるごと消え去ったとしても雨は降り続けるのだろうか。はたして雨だけで無を表現できるものなのか。ムリだな、雨の筆は無を描けない。
想定していたのは、雨上がりの色鮮やかで澄みきった都会の風景である。土砂降りではない。原色の光の詰め合わせ、都会のフルーツバスケット。迫りくるパレードの華やかな色彩と演奏。期待していたのは、喩えていえばそういった明るくて爽やかな花籠のイメージだ。ああ、雨上がりの情景が見たい。乾いた土の匂いが恋しい。
晴れ渡った青空の下、どこか小粋な喫茶店でも目に留まれば、バスを降りてそこから彼女に電話しようと思っていた。タクシーではないので多少歩かなければならないだろうと、そこまで織り込み済みだったのだが。
ところが現実はこの有り様だ。広げた地図が雨雲の影にどんどん欠けていく。「彼方に雷鳴が聞こえようが、さすがにここまで近づいてはこまい」と高をくくった報いである。ガラスごしに透かし見る景色は、雨煙の壁にぼやけている。まさか雨のおかけで外の景色がよく見えなくなってしまうとは。そのうえ濡れ鼠になるのも真っ平である。
ああ予定が遠くに外れていく。こうなりゃ狂いに狂って一周まわってワン! で元の位置───とはいかないだろうか。いかねぇだろうな。イェ~(「松鶴家千とせ」のつもり。若い人には分かんねぇだろうな、イェ~)
車窓に雨粒がはじける。風の方向や強さによって、ある粒はガラスに貼りつき水滴の鎖を連ねつつ下方に垂れる。またある粒は透明な火の粉となって飛び散る。溶けかかった氷塊の表面を通して見る模糊とした風景。都会が水底に沈んでいる。僕はアクアリウムのなかを泳ぐ。
雨水の透明な膜がビルの外形をかたどって流れ落ちるのが見える。それら林立するビルの間にいりくんだ路地という路地。いったいどこに行ったらいいのだ。選ぶべき場所はどこだ。宛名はこの雨滴に滲んで判読できないままだ。手紙をどこに届けたらいいのだろう。表札の文字も雨で消えかけている。
苦情の電話を入れてもずっと待たされる。ようやく出たのが機械音声のオペレーター、あちこち回されるが結局目的の窓口に到達できない。思いは夢にこだまするだけ。そんなやるせない気分だ。
戸口の郵便受けにボンッと手紙の落ちる音。だがやっと届いた手紙の文字は透明で、読むそばから流れ落ちる。
ああ、心が冷えゆく。あたかも血管が凍り、窓ガラスに霜の結晶をひろげていくかのようだ。その透明にひび割れた触手。氷の細い指がさらに冷たく僕の神経をなぞる。
車内の淡い明かりに浮かんだ僕の顔が氷塊にはりつく。外は仄暗い。輪郭がぼけていて、歪んだ鏡に映っているかのようだ。顔の上を水滴が走る。眼のあたりを走る水滴は涙に見えないこともない。この都会の傘の下には今も悲しみに打ちひしがれている人が一杯いるはずだ。この雨の雫が涙の雫でないと誰が言い切れよう。
目交に浮かぶ亡母の面影。思い返すたび感謝があふれる。あそこに赤い傘をさして歩いている人は、もしかしたら母ではないのか。そう、あの通りを横切った人。あの頃は母がいて、僕がいて、笑いがあり‥‥‥そして今は背景だけの絵が残る。
錯覚か。また母のことを思い出してセンチなってしまったとでも言うのか。ちょっと女々しいんじゃない? しつこ過ぎる。あらかた条件反射になっている。いつ親離れするのだ。死んでからもうかなり経つのに実に情けない。
〈大丈夫だ、赤井君。君は桃から産まれたわけじゃない。お母さんはいないけど、そこにいるんだ〉
雨は泣いている人も笑っている人も等しく濡らす。不意に悲しみが訪れた時はひっそり隠れて泣くがいい。辛い記憶も涙とともに流れ落ちる。そして心に滲みこんだ涙が、悲しい思い出を少しずつ懐かしいもの変えてくれる。
窓ガラスの向こう側に眼の焦点を合せれば顔は消え、都会の風貌が後方に次つぎ飛んでいくのが見える。光景がどんどん横滑りしていく。色落ちした青や緑や赤や黄や‥‥‥様々な都会の多色刷りがガラス面にゼリー状の輪っかを幾つも広げては窓の区画の外側に逃げていく。
雨が無数の針のギラつく光に見える。透明な箱のなかで爆ぜる花火。僕の顔と水滴と都会の光や看板が、透明な箱の内部で二重にも三重にもかさなり合って、闇中に不安定な底無しの広がりを感じさせる。
さっきから赤井君は心のキャンバスに若かりし花菱社長を描いている。痩せさせて、身長を20センチぐらい高くして、それから顔の皺をのばして‥‥‥そうやってどんどん逆算していくと‥‥‥うん、アイツに似ている、このマルポチャ顔。いや似てないところもあるかな。
いっそ隙をみて二人の毛髪をどこかで拾い、DNA鑑定してみるか。検査に金はいくらぐらいいるのだろうか。アチャ~だめだ、だめだ! 花菱社長はハゲあがっていて、もうあんまり毛がない。
読みの多くのは外れるものである。とはいえDNA鑑定して万一的中してしまったらどうするのだ。二人の間を取り持つべきか、それとも放っておくべきか。花菱社長には拾ってもらった恩がある。だが取り持てば、悪くすると恩を仇で返すことになりゃしないか。
雨の叩く音が激しい。のしかかる雨音。雨音の濃淡はいよいよ浮き立つ。横殴りになる風雨。街路樹が揺れる。雨音と風のまにまに漂う喧騒が混じりあって、不気味な交響曲を奏でている。バスが箱舟に変じて荒波を航海している。
───しかし二人が親子なんて、そんな偶然がそんじょそこらに転がっているものだろうか。なんだか全部、丸ごと夢なのではないかと思えてくる。そもそもこの世とあの世だってどっちが夢か分かんないもんな。もともと夢のない眠りだってあることだし‥‥‥。
考えれば考えるほど、夢の境目は遠くへ霞ゆく。赤井君は自分の脳ミソの森に迷い込み、行き場を失ってしまった。いくつもの訳の分からぬ数式が頭の中で絡まっていくかのようだ。そんな数式、学校を出たら実生活では何の役にも立たないのに。
───まあ、待ってみよう。いずれ時間が答えを出す。手掛かりなしに問題を解こうとしても無駄だ。人間、知らないほうが幸せな場合もある。ここはいったん模様眺めといきますか。隠れたものを炙り出すには時間がいるものだ。
車窓の外、雨足は激しくなるばかり。やむ兆しはなさそうだ。バスが瀑布をくぐり抜けていく。雲の中に住む高木ブーこと雷様が怒りだし、雷鼓を背負ってゴロゴロと近づいてこないことを祈ろう。
───もしかしたら花菱は僕が自分の息子の友達だということを最初から知っていて、その縁でこっちにターゲットを絞りモーションをかけてきたのかもしれない。いやいや花菱は子供ができなかったと言っていた。彼が嘘をつくメリットはない。なにより嘘をつく人間には思えない。
さてさて、そんなことをつらつら考えているうちに、様々な憶測がそぞろに去来して、雷様ついでにアイツの顔まで若き日の高木ブーに思えてきた。なんてこった。アイツの出自のことを気に掛けるほどに、思考が朝顔の蔓となって絡まる。頭の中の缶蹴り───中身のない雑念と妄想だけがカラカラと転がっていくばかりだ。
───いずれ時間が答えを出す‥‥‥それって本当なのか? ヘボ将棋はいつまで経っても詰まないだろう。
何がどこへ向かうのか、誰がどこへ向かうのか、漂いゆく心は追いきれない。思考の道筋には迷路に至る白い足跡が残されるのみ。銀の針金のような雨が知覚の糸車に巻取られ、観念の舌を冷たく濡らしている。赤井君は昏迷の底に沈んでいくばかりだ。
(46)
バスを降りた。靴底が濡れた地面に触れる。無数の雨滴が水の絨毯に落ちて、大小様々の輪を描く。水溜りに映った都会のビル群が、落ち続ける雨の滴に放射状に分解していく。予想外に寒い。季節外れの花冷えか、よしてくれよ。
雨音と街のありとあらゆる騒音の、それぞれ違う周波数がまざりあい、街が独特の和音を奏でている。この身がその和音に包まれる。もしもっと音感があったなら、織りなす旋律を辿れるであろうに。
ここは初めて来た場所で土地勘がまるでない。深い森のなかで方向感覚を失ってしまったかのようだ。天気図を思い浮かべる。福岡に前線なんか通りそうだったかな。高気圧ど真ん中だった気がするが。
やれ困った。よりによってこんな時にこんな場所でなぜバスを降りたのだろうか。苛立ちと不安の雨が矢となって心の暗奥にその先端を突きさす。
雨の中、小走りに急いだ。何処へ? 分からない。何処かへ行こうにも既に大雨が遠景を消し去り、行き先を特定しそれを目視することさえできそうもない。どうせ濡れるなら走ろうが歩こうが同じことだが、靴底が「走れ走れ」とせかすのだ。
走ったところで何になる。メロスなら走る意味を知っているだろうが、あいにく彼はメロスではない。もしかしたら彼の目指す場所は、彼の見る夢の中にしかなく、決して行きつく場所でないかもしれない。
風の浮力にのって、しゃにむに走る。のんびり屋の彼にして稀にみる疾走感だ。雨が足許に分厚い水のカーペットを敷いてる。雨滴が地面に当たり飛び散る。ラムネのように泡立つ雨粒。雨の音符が爆ぜる。ドタバタ劇を演じる透明なオタマジャクシたち。
もう雨しか見えない。進むほどに遠ざかっていく雨の舗道。もはや街から暖色系の色は消え去った。雨の膜に白っぽくなった視界、その中央におぼろげに黒点ができ、体が両腕両足からその点のなかに吸い込まれていく───そんな不思議な感覚だ。
どうしたんだ、心だけが理由なく逸る。吹き荒るる雨。水しぶきがかかる。雨が河の流れとなりアスファルトの路面を這う。濃紺のスーツが雨に打たれ、雨を含み、アジサイのようにその色を増す。
水を吸った靴が重い。濡れていくのは足先から。ズボンが雨水を浴びて脚にまとわりつく。彼は雨の河に漂う笹舟だ。水面に浮かぶ桜の花びらだ。流れ流れて何処へ行く。

いよいよ雨は大粒になる。路面には自分の姿が映るほど水があふれ、その映った影をさらに落雨が叩く。彼は風と波にあらがうサーファーになる。頭と肩に雨のシャワーを浴びる。空から銀鱗を振りかけられているかのようだ。
───こんなんじゃ、フルフェイスのヘルメットがいるな。このまま雨に沈んでしまうのではなかろうねぇ。それじゃ、サーファーじゃなくて水鉢の底であえぐ金魚じゃないか。
強く降りしきる雨が街の色や、形や、灯りや、空気を縦に裁断している。アスファルトを叩く雨音が耳の底にはりつく。いま現在も、雨の大都会には怪しく蠢く人々が大勢いる。その無数の泥の顔を一気に流し去ってしまうほどの、この雨の勢い。
雨が犬の唾液のようにショーウインドウを流れ落ちている。風がうねる。雨に打たれて溶けていく白鳥。雨が納豆の糸のように絡みつく。先の尖った雨。雨粒の冷たさを肌に感じる。雨が肌を刺す。刃物を研ぐ雨足。
風も尖ってこの身に当たる。風を呑む赤井君。耳にふれる風音は、口笛のかすれた響きにも似て。雨粒も顔に当たる。光の散乱、ガラスの回転扉に巻き込まれ、このまま海底に連れていかれそうだ。
───雨は香るんだ。今まで気にしたことはなかったが、都会の雨ってこんな匂いがするんだな。知らなかった。何と言ったらいいんだろう、色々な匂いが想像と記憶のうちに混ざり合う。現実の匂いであって現実の匂いではない。
手の平に薄っすら残る灯油や薬品、あるいは乾かした女の髪の匂い───それから───廃線の鉄路、日射しに焼けた鉄錆レールの匂い。新しい本を開いたときの匂い。それら雑多な匂いが想像と過去の記憶のうちに混ざり合う。
それから、それから───この短いが濃密な時の流れに、これまでのあらゆる出来事の断片が匂いをともない去来する。数多の思い出の匂い、底が尽きない。湿ったようで、それでいて乾いた香り。なんとも表現しづらい匂いと色と記憶の配列。水底に沈んでいく虹のようだ。
滝の雨をくぐる彼には傘がない。あのダークな空にコンパスで円を描いて傘にしたい。切り取られた円の向こう側は青空なのか? そこから陽射しがここまで差し込んできてくれればいいのに。巨大な傘の陰にはいりたい。雨に濡れたワイシャツの胸のあたりに手を当てて、冷たくなった肺にそっと触れてみたい。
彼は彼の内部を見ている気がした。それは宙に浮かぶ巨大な黒気球となって、彼自身を圧し潰そうとする気がした。彼の内部が彼を圧し潰すなんて意味をなさないけれども、何とかこの感覚を分かってもらえないだろうか。彼が彼の内部で膨張し、ついには彼自身を飲み込んでしまう。そして巨大な傘の陰にいる彼の内側からは溢れんばかりの雨滴が弾けて飛び散るのだ。
透明なビニール袋を頭から被らされたように、雨に視界が歪んで見える。暗い雨が排気ガスに染まり、汚れた靴底が地面を跳ねる。雨が足跡を一瞬もとどめず洗い流す。革靴の隙間から雨が滲み入る。
傘のない赤井君は今、雨水の衣装を纏い、立ち泳ぎするかのように人波をわけて進んでいる。いや、立ち泳ぎというよりも、どちらかと言えば犬かきか。いずれにしてもスイスイと平泳ぎとはいかないようだ。
分け入っても分け入ってもシャングリラには辿りつかない。失われた地平線だ。過ぎ去る街並みが透けていく。雨と風の糸が心に冷たく刺繍を縫いつける。
───♪だけども~~問題は~~今日の雨、傘がない~~。行かなくちゃ、君に電話しに行かなくちゃ、雨の中をォゥォ〜‥‥‥(・_・; カシ、チガワネェ?
ねっとりと生温かい湿気がからみつく。この身が都市空間の暗い体液のなかに沈みこんでいく。色のない雨煙のなかに模糊と浮かび上がった道標に導かれるかのように、目的地を定めぬまま彼は闇雲に走る。いつ果てるかもしれぬ水の回廊。心拍音が、雨が鳴らすトタン屋根のドラムに重なる。
汗と雨が混じりあい、もう寒いのか暑いのかよく分からない。息もかなり荒くなってきた。心臓が早鐘を響かせ、鼓膜を震わす。苦しくて大鯨の内臓脂肪の中に丸ごと顔を突っ込んでいるかのようだ。周囲の空気は粘っこく、生暖かく、そして暗い。
急に強い風が渦を巻いて吹きはじめた。風の形相が怖い。局地的な旋風だろうか。丸めたゴミ屑が人の顔をして地べたを転がっていく。ヘリコプターが真上から下りてきたように風が逆巻き踊る。水晶体が歪み、風景が揺らぐ。
風はどこから吹いてくるのか、誰かその大きな扇風機をとめてくれ。平衡感覚を崩し、風圧に耳をふさぎたくなった。耳の奥で爆竹が鳴り、頭の中に轟音がとどろき渡る。風鈴のなかで耳をふさぐ小人。これはヘリコプターや扇風機どころではないな。空から下りてきたのは風神雷神なのかもしれない。
一瞬、感冒や高低差の耳詰まりのことを思い出す。ビル街の狭間にて、たまさかエアポケットに入ってしまったとでもいうのか。灰色の空に吸い込まれていきそうだ。いまにも雪崩が荒々しい顔をつくって頭上から落ちてきそうな、憂鬱で暗いその空の色。
───頼りにしていた道標の赤矢印はどこに消えた? 雨に滲んで流れ落ちてしまったのか? サインボードをつたう赤いインクが雨の色に溶ける。彼は遊園地の迷子になってしまった。これから道標のない登山道を上っていくのか。それにしても、はじめから無いと分かっているものを頼りにこれまで走っていたなんて、本当にどうかしている。降ってくるのが死の灰でなく、雨でよかった。
(47)
人波の途切れに乗じて、藁にもすがる思いで目の前の店に飛び込んだ。ウクライナやガザ・レバノンの空爆のように、そのうち雷が落ちてきたらたまらない。ところで偶然とはいえ何でこの店に入った? 店の扉がパクパクと口を開いて彼を呼び込んだわけでもあるまいに。
ちょっと見、何の店だか分からない。ビルの谷間のこぢんまりとした店だ。喫茶店なのか食堂なのか雑貨衣料品店なのか、それとも意外なところでゲームセンター? まあ、なぞなぞの答えを見てみるのも悪くない。
入ってみると店内はことのほか広く、どことなく馴染みのある光景に見えた。この光景はどこかで見たことがある。しかしここは初めて来た場所。であれば夢の中で見たのか。なら、その夢は予知夢ということになるな。
それはともかく、服が雨でびしょびしょだ。濡れた足裏の不快感が気になる。この気持ち悪さといったら、化け物屋敷に入って幾つものコンニャクの手で撫でまわされている心地とでも形容したくなるほどだ。この不愉快さ、どうにかならんものだろうか。
一方この場所はと言えば、都会という名の戦場の、ごくごく狭い緩衝地帯と呼ぶにふさわしい。扉を開くと懐かしいオルゴールのメロディーが漏れ聞こえてきたといった風情だ。無論ここにいる全員が初対面、誰ともつながっていないはず。にもかかわらず気づまりな雰囲気がないのはどうしてだろう。
この時代がかったレトロなムード、ああ安らげる。レトロったって東京や大阪の地下鉄のことじゃないよ(w)。まさか過去に連れ戻されたのではあるまいねぇ。なんというか、古いアルバムをめくっているといった趣だ。そこはかとない味わいがある。めくる度、空気を震わす僅かな風に、幼い昔の楽しかった思い出も揺れる。
レトロ調のこの光景も、半世紀前ならそれなりにハイカラに見えたことだろう。今風とか流行とか、そういう概念に背を向けている場所。大都会の中、ここだけ切り取られてずっと昔にとり残されている。だがそれでいて客や従業員は、それぞれに装丁のきらびやかな本の中の登場人物の面影がある───そういった感じの店だ。
入りくんだ街路と喧騒の網の目をくぐり抜け、ようやく陽だまりに辿りついた安堵感。僕は水槽にやっと落してもらえた金魚なのか。それとも長旅の末、浜辺に流れついた椰子の実か。ああ、生き返る。都会の片隅にこんなパラダイスがあろうとは。
ここは現代社会の刃に傷ついた心の乱れを、そっとカサブタのように覆う場所に思えた。いつの間にやら赤井君は、濡れ鼠の不快さを忘れている。
最初に目に飛び込んだのは機敏に行きかう女の娘たちの姿だ。機械人形の正確な動き。そこにはAI動画さながら、アニメ的な時間が流れていた。みんな若くて可愛い踊り子だ。動きにあわせてスカートが花びらのように揺れる。柔肌に吸収される熱のオブラート。照明の光にとろけながら、艶光る綺麗な絵柄が舞う。今にも地下アイドルが歌って踊ってと、一糸乱れずのライブパフォーマンスを始めそうな雰囲気である。
君、どうして歌うの?
どうして踊るの?
さみしさを埋めるため?
この永久に自分から去ってくれない、さみしさを。
もしかして今自分は夢の中をさまよっているのではないかと、さっきから少し気になっていたのだが、このワクワクする臨場感からして、どうもそうではなさそうだ。落ち着いて彼女に電話するためにこの店に入った。それは確かだ。どうしてそんな時に夢路など辿れようか。
だとしたら、これは物語か? 僕はきらびやかに装丁された本の中にいるのか? まさか。これがぜんぶ物語で、架空の出来事の中にいるだなんて。あり得ない。なにを血迷ってる、馬鹿々々しい。
───素敵だ。君のスカートは広がり揺れる扇かい? それとも風に開くパラシュートなのかな。
おいおい、違うぞ。見てみろ、そんなキラキラ衣装じゃないぞ。みんな作業着じゃないか。それにしても今どき紺の制服かよ。もしやここはメイド喫茶なのか? まさか福岡までメイド喫茶が進出してきてるんじゃなかろうな。突然「お客さん、萌え」ってのは嫌だよ。何を話したらいいか分かんないじゃないか。だって萌え語も知らないし。
なにせ赤井君はSM店に誤って入ってしまった前科がある(霞ゆく夢の続きを〈1〉─9)。またやっちまったか、と一瞬ギクリとする彼であった。とはいえ、間を置かず「これがメイドでなくて冥土喫茶なら、幽霊どもがライブパフォーマンスで萌えまくるんだろうか」と下らないギャグが思い浮かぶや、一転して吹き出しそうになる赤井君である。君は蛭子能収か!
───冥土に土産を持って行くなら、我が手製の小説本にするかな。何冊もって行こうか。あの不揃いさがむしろ手作り感があっていい。いま考えれば箱村の言ったとおりだ。
幸い窓辺に席が空いていた。そそくさと陣取り大きく深呼吸すれば、警戒心のコルセットが一気に外れる。暑からず寒からず快適で、濡れ鼠も知らぬ間に乾きはじめている。ああ、この気だるさ。いいムードだ。ゆったりとした時間の流れ。気持ちがほぐれていく。ここはエデンの園かオアシスか。いい店に入れたもんだ。犬も歩けば棒に当たる。さすが華やぐ大都会だけあって、まだ棒の切れ端ぐらいは転がってるんだな。
雪の中、やっとこさ見つけた露天風呂に肩までつかった気分だ。うららかな日差しに照らされているようなこの至福感。贅沢なひと時。湯加減もちょうどいい。このままトロトロと眠ってしまいそうだ。手編みのマフラーに包み込まれているというか、そんな感じ‥‥‥そのマフラーも駅で配った僕の小説本よろしく、彼女のお手製だったら最高なのになぁ。彼女のマフラーに首をうずめれば、寒気なんて一気に吹っ飛ぶ。
そんなこんなで赤井君の妄想は、恋文を綴るがごとき執拗さをもってとどまることを知らない。あの時ときめいた胸の鼓動がいまだに残っている。時間が詩を奏で続ける。
「あんなサプライズ的な誘い方をするからには、きっと僕にホの字に違いない」と勝手に決め込む彼なのであった。どうやら人には、好きな相手には好かれていると思い、嫌いな相手には嫌われていると思う傾向があるらしい。
彼は過去へと記憶を巻き戻す。今なおあのときの彼女が忘れられず、平らげた皿をまだ執拗にしゃぶっている。展望レストランでの短いひと時、彼女の仕草、言葉の記憶の一つ一つを丁寧に拾い上げていく。その場面の一つ一つを思い出す度、女のスカートの糸を少しずつ魔術師の糸車が絡み取っていくのを見るような、やけに少年っぽい胸のときめきを感じている。柑橘系の甘酸っぱい青春のときめきだ。
───男という生き物はどうしてスカートからのぞく脚にこうも魅了されるのだろう。たぶんそれがこの世に生まれ出て初めて見るものだからかな?
赤井君、足湯だからといって、少し湯加減が熱すぎやしないか。冥土に足を突っ込んで冷まさなきゃね。でも冥土に行った幽霊に足はないか。
早くも色ボケ妄想でのぼせ上がっている彼。頭のなかはカメラ小僧のスナップショットで溢れんばかりである。ほらほら、のぼせすぎて熱中症になるなよ。彼女のあの時の一挙手一投足は記憶の画布にしっかり塗り込まれている。水に浸した絵筆の濁りまで指でたどれそうだ。
とりわけこの言葉が胸を焦がす。今まで何度も何度も心のなかで反芻した褒め言葉。繰り返すたび小躍りしたくなる。単純な男だ。そのセリフのあるページに栞をはさみ込み、幾度となく読み返す。過去の日記帳をいくら読み返そうとも、同じ出来事は二度と起こらないのにもかかわらず。
「赤井さんの作品には一途さがあるもの。それから詩情もある。孤独な人たちには詩が必要だわ。人を揺さぶり、そして癒す」(霞ゆく夢の続きを〈5〉─38)
確かにその通りだ。詩情はこの怒涛の現代社会の中にあって、我が心を守る。たとえ束の間であろうとも、辛い現実から離れて小さくとも美しい世界に自分を逃がすことができるからだ。
それにつけても、赤井君はどうして箱村の奥さんにこうも首ったけになってしまったのであろうか。自分のほうから相手に働きかけることが苦手なタイプの男は、そもそも女との関わり自体が少ない。今の若者はそうでもないという話も聞かないこともないが、女から男に働きかけるケースは古今東西ごく稀だからである。
それゆえ、彼のような陰で劣等感に苦しむ消極的な男が、女から言い寄られる体験をしたとするならば、それは圧倒的に価値のある体験なのである。通常、そんなことは生涯起こらない。もし起こったとするならば、一生に一度あるか二度あるかの体験といっても過言ではないだろう。このため言い寄られたという事実だけで心が腑抜けになってしまい、たとえば「なにか裏がなければ普通そんなことは起こり得ないはずだ」といった冷静な判断ができない。
万一彼女が性悪女であろうものなら、そういった甘々の弱点を見ぬいて獲物にすること請け合いである。悪女は心に十二単を着こみ、時折り襟元をはだけたり裾を崩したりと挑発するのではあるが、素振りは見せども一筋縄では脱がせない。結果として身ぐるみ剥がされるのは決まって男のほうだ。もっとも素寒貧の赤井君に限っては、剥がそうにも剥がすものが何もないんだけれども。さいわい彼は紀州のドン・ファンではない。
ホビホビ男が妖しい美人に言い寄られる。まるで「美女と野獣」ならぬ「美女と小人」の世界だ。小人の夢が叶ったと大喜びしていたら、実際にホンマモンの夢の中にいた───なぁ〜んていう笑えない落ちだけは勘弁してくれよな‥‥‥と、とりとめもなく抜け作めいたことばかり考えては一人悦に入る赤井君である。本質がまるで見えていない。馬鹿というか平和というか。
それはともあれ、窓際のソファーに陣取りゆったりとした気分に浸る彼。首振り扇風機さながら、しっかりと辺りを見回す余裕もでてきたようだ。
改めて見てみるとメイド喫茶でも地下アイドルのライブハウスでもなさそうである。客層を見渡しても若い娘めあてで集っているミーハー連中とは思えない。彼女らが機械人形でもアンドロイドでもないのは言わずもがなだ。だいいち女の娘たちのスカートが短くない。いかにも機能的な紺に統一された仕事着といったところだ。昭和感たっぷりのウエイトレスだ。あの頃の古雑誌を開くような懐かしさがある。
僕は時代の流れの狭間で迷子にでもなっているかな? このレトロな雰囲気、にもかかわらず手作り弁当箱を開けるようなワクワク感もある。ああ、なかなかいい。落ち着ける。
タイパ、コスパ重視の令和の世知辛い世の中で、複数人の女性ウエイトレスを雇っても経営上やっていけるとは。さすが福岡県の中心街の一つ、天神は大したものだ。
アンドロイドではないにせよ、ウエイトレスの動きは正確かつ効率的でゼンマイ仕掛けの玩具を想わせる。これがタイパ、コスパ重視の令和の動きというものか。だがそれでいて動作一つ一つはしなやかだ。澄んだ川底の鮎さながら、滑らかな動線を辿る。
だが見方によっては昭和の動きにも通じるところがないこともない。それが証拠に、昭和にも「タイパ・コスパ」に相応するであろう「費用対効果」という言葉はあった。にもかかわらず若者は皆、もっとのんびりしていたように思える。近頃の若い子たちは昔と違って、何でもそつなくこなすのか。それとも今は人手不足だというのに、この店にかぎっては特別しっかりとした新人研修をほどこしているというのか。
そう言えば、スマホの小さな画面に打ちこむ指の動きの素早さ、複雑さは令和特有だ。昭和以前にはああいう細かで滑らかな指の動きはない。あえて言うなら生産性と効率性のみ求める指の動き。スマホは時代を映す鏡だ。
そうなんだ、今は令和だ、昭和ではない。旅先のちょっとした景色もスマホに入れて持ち帰れる時代なんだ。令和は車内の若者のほとんどがスマホとにらめっこしている時代だ。石川啄木が令和の若者だったら、きっと手の平でなくスマホ画面を見ていることだろう。でも令和より昭和の方が好きだ。人を生産性や効率で序列化する社会は何とも味気ないではないか。そんな感じがするのは満員の車内の中でただ僕一人、いつも別の世界にとり残されているからかもしれない。月日の流れは僕を置いていく‥‥‥。
おいおい、昭和? 若い子? 自分も令和の若い子の一人ではないか。なにを恍けたことを考えている。お前はジジイじゃないだろう。不思議だ、急に時代感覚が大きく狂ってしまう。時々こういうことがあるのは何故だ。
女の娘たちの無駄のない動きは、海面すれすれを飛び回る鴎とでも形容したいところだ。なぜそういう連想をするかというと、彼女らの仕事着は海の色、白いエプロンの結び目は鴎に見えるからである。飛び回るのが閑古鳥でなくってよかったね。鴎のおかげで客はいっぱい入っている。
こうやって店内を眺めまわすと、いろんな人たちがいる。都会の片隅で雨宿りする人々。この光景がやけに平面的で、どことなく現実感がないのはどうしてだろう。テーブルの上に所狭しといろんな物が雑然と置かれている。そしてその中の一つに小さな人形になった僕もいた。そんな感じだ。自分の人生の主人公は自分以外にないのであるが、ここにいると何故かそうではない気がしてくる。妙な話だが、今ここにいる実感がわかない。
もう仕事は終わったのだろうか、労務者風のたくましい男らがビールをがぶ飲みして怒鳴りあったり笑いあったりしている。ある者は北朝鮮の報道官よろしく語気荒くオーバーな話しぶりで。またある者は呂律が回らず、アルコールに染まった赤ら顔をシーツのように皺くちゃにしながら。
口さがない連中である。うるせぇなぁ。アイロン掛けしてその皺をのばしてやろうか。“歓楽の泥水に浮かぶ紙屑ども”───そんなふうにシュールに喩えても何らおかしくないほどの馬鹿ヅラだ。こっちも他人の顔のことは言えた義理ではないのだけれども。もっとも合理的に考えれば顔なんてありさえすればいい。他人と自分を判別できさえすればいいんだ。
あの太った男は痒いのだろう、さっきから後ろ手で尻をボリボリ掻いている。全盛期のシュワちゃんのように筋骨たくましい男も、これまた痒いのか、何故かはだけた腕を始終もう一方の手でこすってばかりいる。まさかとは思うが、黒く浮き上がった垢が風にのってこちらに飛んでくるんじゃあるまいな。アルコールで火照った彼らのシャツの内側に、玉の汗が流れ落ちる絵が浮かぶ。
男たちの話題はおおかた競馬か野球か女か、そういったところだろう。何を話しているんだろう。耳をそばだててみる。注意力を集中するが、聞き取れない部分のほうが多い。
「袋を頭からスッポリかぶされたみたいに、殴られたら視界がボワ~ンと暗くなっちまってな」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「なに関係ねぇこと、話してんだ。俺が話しているのは、ガラスの破片を一杯飲み込んで、腹の中を血だらけにして死んだ、あの気違いのことだぞ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「ばってん、わしは死人の肺のなかの空気を吸って長生きするんじゃが」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「アホか、お前。歳とって老いるのは体でなくて心なんだよ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「あいつはジャムパンだ。血がジャムみたいにドロドロなんだ」
「「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「あの糞デブ野郎のことか。ちゃうちゃう、アイツはちゃう。あのデカ腹を見てみろよ。やっこさん、便のいっぱい詰まった皮袋だ」
───彼ラハ、何ヲ、話シテイルンダ。全ク意味ガ取レナイ。
「あの女、真っ黒けに目の周り塗ってな。糊みてえにカチンカチンにしてやがんの」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「俺は昨日、乳首を紫色に塗っている女と寝たよ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「なんでぇ、俺なんざ昔、体じゅうに緑色の産毛がはえている女と寝たことがあるぜ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
───変ダ。彼ラノ、声ガ、遅レテ、耳ニ、届ク。
「俺なあ、ハメハメしてるときな、何かこう女のポンポンがよお、ゴム風船みたいにどんどん膨らんでいってさあ、そのうち破裂しちまうんじゃないかって気がしてくるんだ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「んで、抱いてると、なんかこう、火薬の一杯つまった皮袋を抱いてるような怖さがあるんだわさ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「************************************!」
「ほんで囁いてやったわけよ。おまえの唇を火であぶるような熱い接吻をしてやろうってな」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「地球のはらわたの中にイチモツを差し込んでいるような感じがすんのよな」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「体ん中のいっさいがっさい、内臓も、筋肉も、骨もバターみたいにトロトロに溶かしてやるぜ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「************************************!」
「ヘッ、そげなことホントにほざいたのかいな、その間抜け面で。この嘘つき野郎が」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「************************************?」
「おい、やりっぱなしだぜい。突撃だ。もうすぐ子宮に俺たちの快速の地下鉄が突っ込んでいくぜ」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「トンネル掃除か!」
「〇▼※△☆▲※◎★●!」
「トンネル大爆破だ!」
「〇▼※△☆▲※◎★●************************************!?」
「そんなこと言ったってオメェ、死体に重りをつけて沈めても‥‥‥沈んで沈んで、もっと沈んで‥‥‥地獄をくぐり抜けて‥‥‥しまいには地球の裏側にポッカリと浮かぶことになるんだぜ」
男たちは笑っている。なにが可笑しいんだろうか。なんで言葉が切れ切れに遅れて届くんだ。ヒップホップ音楽のラップでも刻んでいるのか。それとも腹話術師のいっこく堂か。どうやらセックスを話題にしているようだが、なんせ常人がこんな所で話す内容とは思えず、下品きわまりない。おまけにブツブツに途切れて聞こえてくる始末で、何を言っているのやら。中には危ない内容も含まれているらしい。
どうせホラや作り話の類だろうが、女を人形かボロ布をあつかうように話しているのが若干気になる。もっとも女だって男をお買い得商品を選ぶように見る場合も少なくないだろうが。もちろんそれがいけないと言っているわけではない。秘め事を大声で笑いながらネタにする神経が理解しづらく、居心地がわるいだけのことだ。どうも奴らからは離れた方がよさそうだ。
その隣のテーブルは、母子ともども連れ立って繁華街に遊びに出てきたといったといった雰囲気だ。子供は二人いる。母親が幼児の汚れた口を拭いてやる一方で、もう一人の子供は足をぶらつかせ、潰れたカリフラワーのように泣きじゃくっている。紅いほっぺは桃の果実だ。かわいいキューピー人形なら笑えばいいものを。
こりゃお母さんは大変だ。見かけから言えば、泣きじゃくる様子はカリフラワーというよりは変色したレタスかも。もうサクサクしていない萎びたレタス。畑の土にポンと捨ててある、半分野菜で半分土と化したレタス。肺が土に埋もれて崩れゆく、そんな感じの脆いレタス。
はてさて、カリフラワーとレタスが微妙なバランスで綱引きしている。滑稽な話だ。カリフラワーとレタス‥‥‥あらためて思案してみれば別にどこがどう違う訳ではない。カリフラワーはカリフラワーで、レタスはレタスだろう。これがキャベツだったらどうなるか。アホらし。いずれにしても芯は甘い。幸せいっぱいの親子ではないか。外野から観戦する者は、ことほどさように無責任である。
「ちょっと静かにしなさい!」
母親がまだ言葉も十分わからないであろう年端もいかない子供に、ヒステリックに喚きたてた。叱られた子供は一層はげしく泣き出してしまう。とうとう子供の顔はカリフラワーから丸めたレジ袋になってしまった。
「天神というところは、どうしてこうエキサイトさせるんかの。ワシゃ、天神や中洲の地図を広げると糞がちびり出ちまいそうになるんよ」
「こん、どスケベがぁ。なんば言っちょうぉ」
「〇▼※△☆▲※◎★●*****!」
また下品な野郎どもの笑い声が耳に絡んできた。聴くまいとつとめても、奴らの軽くて中身のない言葉が、綿毛のように空気に乗って耳に届く。やはり声には微妙なズレを感じる。この奇妙な違和感。これは現実なんだろうか。実は彼らは地球の反対側どこか野蛮な国にいて、それが高速ネットワークに繋がっている。そしてそこに若干のタイムラグが生じてここまで届く。そんな具合に彼らの声はやけに不自然な余韻を残す。
「ああ、腹が痛え。俺、胃袋ん中の海で溺れそうなんよ。腹を裂いて、胃袋ひき出して焼いちまいたいぐらい痛えよ」
「ぽんぽこが痛いならもう飲むな。なに食ったんやボケ茄子! お前みたいな奴はな〇▼※△☆▲※◎★●***********************!」
───何ヲフザケ合ッテイルンダ。腹ガ痛イダッテ? ウルサイ、消エテクレ!
さて気を取り直し、その隣はと‥‥‥‥若い女だ。厚い化粧、赤茶に染めた髪、マスカラをたっぷり含み反り返った睫毛。耳たぶに刺さったイヤリングが揺れる。かなり大きなメタルの耳飾りだ。派手な露出系の服装をしている。むき出しの肩がつるつると丸みを帯びて眩しい。磁力を感じる。磁力で僕をひきつける女。
はて? この女はどこかで見覚えがあるぞ。どこだったかな‥‥‥あ、思い出した! 今日の朝、夢に出てきた女だ。寸分たがわず、そっくりそのままこの女。場所は‥‥‥小倉駅。
何、小倉駅? 小倉駅で会ったのは箱村の奥さんではないか。顔がまるで違うだろう。不思議な感覚だ。こんな妙な現象も脳内では起こるんだな。過去の出来事と今見ている現実が、今朝見た夢の中で溶け合ったのか。そうか、女に磁力を感じたのはそのせいなんだ。
女は広隆寺の弥勒菩薩像の指に煙草を挟ませたような姿で、かすかな笑みをたたえながら紫煙をくゆらせていた。どことなく雌猫の雰囲気を漂わせている。僕が見つめているのを知ってか知らずか、女は開けた素足を組みかえた。交差させる動作によって女の色気は生ずる。バブル期にボディコンというミニのワンピースが流行った。ボディ・コンシャスの略だが、文字通り女が自分の体を意識しているのが見て取れる。
内面から湧き上がってくるこの色気。おそらく水商売関係だろう。こんな大衆化した場所にあっても、その色香が目に流れ込んでくる。色気が女の武器であることを熟知しているのだろう。猫は人と違って、限られた色しか見分けられないそうだ。なるほど夜の世界はもともと暗いので、色を見分けるまでもないということか。さすが雌猫だな。
夜を彩るネオンに合わせて化粧するいつもの癖で、こんな場所に来るに際してさえ、薄化粧のつもりでも塗っているうちに厚化粧になってしまうのだ。のせ過ぎたせいで顔が骨のように白い。まだ若そうで素顔も十分美しいはずなのに、もったいない話である。
煙草の火を消した後も、女のポーズはあまり変わらず、半跏思惟像のままだ。親指と人差し指で輪っかをつくり、地獄の沙汰も金次第でっか? さすが風俗関係だな。この不景気だ、生き残り競争もなまやさしくなかろう。
何を飲んでいるのだろう。あの緑色はソーダ水か。お、飲み始めた。ソーダ水らしき緑の沼をストローで吸い上げている。子供みたいな仕草だ。かき回す際、テーブルに零れた無数のソーダ水の玉。その玉の中を店を行きかう人たちの影が揺れて通る気配を感じる。
吸い込む度に喉のあたりの筋肉の波打つ動きが見える。僕はその波打つ動きに、ホラー映画よろしく、一口のみこむごとに沼の蛙を食道へ流し込む怪物を想像した。
飲み終えた女は、静かにストローに付着するルージュの朱を拭きとった。思ったより神経質で繊細な性格らしい。その指先の動きから日常の全てを描き出せるような気がする。マニュキュアもルージュと同系統の色だ。消した吸殻にも口紅の跡がついている。むき出しの素足、ペディキュアも同じ色。イヤリングもそうだ。
さしもの女も、大衆化されたこの場違いな場所、この雰囲気を全てその色で染め上げることまではできまい。
ティッシュペーパーにくい込んだ赤い爪、雪中に息絶えた戦士の傷口、白肌に垂らされる血の雫、雲の腹に牙が‥‥‥牙、牙、牙───
ふいに女がこちらに目をやり、想像の糸がプツリと切れる。
体の内部まで射ぬかんばかりの視線。マフラーのように視線が首筋にも絡みついてくる。血走った眼玉が非難するかのように僕をとらえ、心臓に氷の刃を突き立てた。青みがかったアイシャドウが光に深くえぐり取られて、死体を埋めるための溝に見える。今朝みた夢、駅の喧騒から発されたあの視線が時間を隔てて僕を射抜く。
咄嗟に視線をそらす。コウモリのように一瞬の不安が目前に影を落とす。心がドライアイスに触れた。恐怖で血がたぎるのを覚える。夜、眠っている間に女の赤マニキュアの尖った爪が、首を掴み、じわじわと食い込んでくる───喩えればそんな恐怖だ。
磁力が重力に変じて両肩にのしかかる。心が安定しない。驚きと怖れが胸のなかを駆けめぐる、尻尾を切られた蜥蜴のように。陸に打ち上げられ、もがきバタつく魚のように。誰かブラインドを閉じてくれ! 女の眼の光が怖い。
ここは入り口もなければ、出口もない場所
水中にいるかのように音も聞こえない
心の春はどこに吊り下げられたのか?
背中が凍っていく
両の耳は大きな貝殻にふさがれた
───熊に襲われない秘訣は、熊の目を見ないことだとか。どうした、なに臆病風に吹かれている。こんなときに限って、目は口ほどに物を言うから困る。噛まれたくなければ逃げるな。逃げれば犬は追ってくる。ついさっき露天風呂に肩までつかった気分だったじゃないか。ひどい寒暖差だ。湯冷めしちまうぞ。
今しがた長調の調べを奏でていたのに、いつの間にやら短調の暗い音律に変わっている。感情が暖色と寒色に次々と塗り変えられていく。お前は土壌によって花の色が変化する紫陽花なのか。
「心ころころ」という氷川きよしの歌があるが、こうクルクル心の状態が変わってもらったら困る。ただ女と目が合っただけじゃないか。お前はこんな些細な衝撃にもヘコんでしまう柔なボールなのか。それでも男か、付いてるものが泣くぜ。感情に防弾チョッキを着せろ。動揺するな。ハートを石に変えろ。
───いや待て。これは小学校のとき受けたイジメが影響してるのか?
小学校の頃、イジメられたことについては以前述べた(霞ゆく夢の続きを〈6〉─43)。幼少期にひどく責められたり害されたりした経験があると、大人になっても自分が常に他人から責められたり害されたりする危険にさらされているような気持ちになってしまうものだ。人は子供の頃に形成された人格モデルをなぞって生きていく傾向にあるからである。幼少期につけられた深轍は生涯消えないのだ。
だから女のちょっとした視線も、咄嗟にそれをイジメを加えた人や行動の類型の一つとして位置づけてしまう。残酷な人に囲まれて子供のころ学校で過ごしたのなら、たとえ温かい人の視線を見ても、冷たい視線を投げかけられているのと同様の反応してしまう。それは僕自身の責任というよりは、残酷な人間が集まる場所に放り込まれたことに責任があるのではないか。
そう思っておっかなびっくり女を見てみると、退屈なのか眠たいのか大アクビをしていた。な〜んだ、どこにでもいる雌猫じゃないか。
───ヨッ、猫あくび!
アクビする姿が猫そっくり。むしろおっとりした性格に見える。今にも「の」の字にまるくなってウトウト寝てしまいそうだ。
赤井君は安堵した。彼の脱力した背中がそれを物語る。磁力が重力に変わり、そして今は浮力になっている。心が軽い。落ち込んでいたものが浮かび上がる。
一説によると、猫という呼び名の起こりは寝子だとか。なるほどアイツらしょっちゅう寝てるな (-_-)zzz。 どう見てもこの女、膝にのせて頭を撫でてやりたくなりそうな猫ちゃんでしかない。どうしてこんな女に圧を感じて怖がった。
つまりはアレだ。道ですれ違った人がたまたま不機嫌そうに自分の顔を見た。それがなぜか後々まで妙に気にかかる。よくある、あの心理の類だろう。要はどうでもいいことを過剰に意識してしまったということなのだ。
なんという馬鹿げた幻覚を見ていたのだろう。あのまま幻覚を放っておいたら、そのうち女の耳の穴からにゅるっと緑色の蛇の舌でものぞいたんじゃなかろうか。放っておけば何が起こったか知れたものではない。
そんなことをつらつら考えていると、猫ちゃんが再びこちらを向いた。頬杖をついたままだ。
───ただのアイコンタクトじゃないか。そうさなぁ、こっちが見ているから、あっちも見るんだ。当り前じゃないか。不躾に見つめられたら、誰だって見返す。ニワトリが先か卵が先か。最初に見つめたのはこっちの方だ。
目をパチクリさせている。もしかしたら僕が濡れ鼠だからか。君のお目めはアレだな、アレ。外がドシャ降りだからあえて言うわけではないが、雨蛙だ。蛙さんの瞼のなかに見え隠れする大きなお目め。
“なにこの人、こっちを見つめてるのかしら”───君がそう考えているんなら、“にらめっこ、まあそんなところだよ”───と、僕は答える。
笑った。瞳が細る三日月に変わる。SNSの顔文字のような笑みだ。開いた瞳も仔猫のように愛らしいまん丸お月さまである。優しそうな眼差し、癒し系の猫女だ。この柔らかな眼光の何にビクついていたのだろう。こうやって見るとむしろいい女の部類に入る。
目と目が合ったらミ~ラクル(^^♪‥‥‥目が合うといっても直接くっついたわけじゃない。ありゃ宙で合うんだ。けど、口と口ならくっつけられるな。宙は宙でもチュ〜とくらぁ。でも鼠じゃないよ(w)───と、調子に乗ってスケベな戯言を口にしそうになる赤井君だ。君は女だったら誰でもいいのか!
一転、完璧に着飾った美人のスカートに小さな染みを見つけたような、何ともほっこりとした気分になる。相手が猫だけに、猫なで声でつい「お美しいですね」とおべんちゃらの一つでも言ってやりたくなるほどだ。どうなってるんだろう。さきほどの不安や恐怖が波にさらわれる砂山同様、たちどころに消え去ってしまった。
ブランコを漕いでいるのと同じで、気持ちが明から暗へ、陰から陽へと前後左右にブラブラ揺れる。我が心は一つしかないのに、揺らしているのは誰の手だ。いくら揺らしたところで動揺しないぞ。ハートを宙に放て。
ふと思った。猫も人同様に恋をするのだろうか。発情期はあるだろうから、猫にも恋煩いがあるのかもしれない。それともニャ~としか言えない語彙力では恋などという高度な脳の働きは無理なのかな?
あるいは自殺する猫というのはいるのだろうか。ニャンともキャンともそんな話は聞いたことがない。人も動物も自らの意志で生まれることはできない。ならば死ぬことはどうであろうか。猫の頭のなかは推測しようがないので真実のほどは分からないが、おそらく自らの意志で自殺できるのは人間だけだろう。
どうしてそう思うかと言えば、端で見ていると、どうやら猫には時間が経過していくという感覚がなさそうだからである。猫に時間という観念がないとすれば、自分がいつか死ぬという観念もない。猫は死を考えない。ゆえに自殺もしないのだ。
常に現在にのみ生きている。彼らはその身に訪れるいかなる生命の危機も、訪れた瞬間に思考を通さず反射で避ける。ただそれだけ。人間のようにアレコレ悩まない。すべて一瞬で決着がつく。猫は人間より幸せだな。猫の魂は人間より軽い。フワフワと浮かんでいる。お気楽なもんだ。
それにしても何だ、こんな女にビクつくなんて。どこにでもいるコロコロ車輪の猫車女じゃないか。どうせアンタも猫と同じで、お気楽ネエチャンなんだろう。別に僕に悪感情をもったわけじゃないさ。ほんとにたまたま目が合っただけのことだった。なんとなく見るともなしに見つめたに過ぎない。自分を咎めたてる視線と勘違いするなんて、ちょっと自意識過剰がすぎるな。これはあの罪悪感からきているのか?
(48)
罪悪感と言うのはこういうことである。赤井君は風俗に行くのが日課になっていた。独りぼっちの夜は長い。孤独に強いと自負していた赤井君であったが、なんとなく人の温もりが欲しくなる。どうあがいても理性は本能に勝てない。
───どうせ人恋しくて温まるなら女の体だ。心のカーテンを開けはなして、たまには夜の街にくりだしても罰は当たるまい。なあに、今や都知事選の政見放送や掲示板にさえ、お色気ムードが漂うご時世ではないか。
そんな軽はずみな気持ちが二度になり三度になり、やがて金を貰っては風俗に注ぎこみ、翌日また金を貰っては風俗に注ぎこみと、宵越しの金は持たない江戸っ子を地で行く振る舞いとなる。いったん手を汚したら、とことん汚すしかない。人の性とはそういうものだ。
向こうも商売なのだから特段気にしなくてもよいのだが、とはいえ根が小心者の赤井君は、毎夜でかけては女性を汚しまくっているという不合理な罪悪感が積み上がっていくのを禁じ得ないのである。
さっきの猫の話ではないが、もしこの世界に時間というものがなかったとすれば、歓楽街の路地裏で何人の自分とすれ違うことになるのか知れたものではない。
時間の縛りをとっぱらってしまえば、すれ違うのは自分ばかりとは限らない。ここは来る者と去る者が入り乱れ、夢と現実が交錯し、生ける者と死せる者が明滅混淆する場所。何人の死者とすれ違ったかも分からない。この世とあの世は裏表で重なっている。夜の歓楽街には生者だけでなく生霊や死霊も愛欲の匂い嗅ぎつけ集まってくる。さまよう彼らといつ隣り合わせになっているかしれたものではないのだ。
赤井君が抱いた女のなかにも一人や二人ぐらいはあの世の魂の化身がいたかもしれない。いわゆるピンクゾーンとは、生と死の地平すれすれで、酩酊のうちに交わる場所でもあるのだ。
若さのせいなのかそれとも夢茶のお陰なのか、夜に惜しげもなく発射しても朝起きれば精子はちゃんと生産されている。あまり食べていなかった以前とは打って変わって性欲モリモリの毎日である。
もはや風俗は彼にとって癒しの場となっていた。もっともそれは箱村の奥さんと会食する前までの話だが。何でか知らないが、彼女に魅されてから風俗への欲求はプシュ~としぼんでしまった。
赤井君は、女の投じた視線に波立った気持ちを落ち着けるためなのだろう、一か月ほど前に買った商売女のことを思い浮かべている。朝の光を知らない吸血鬼の日々を送る女だった。買った多くの女の中で、なぜが彼女のことだけ鮮明に記憶に残っている。
あの夜───女の笑いを含んだ唇が三日月の端に引っかかっていたあの夜。今にも月が溶け、雫のしたたりそうなあの夜。星々があたかもクリスマスツリーの飾りのように夜空に吊り下がっていた。夜の海に浮かぶ灯火。光の糸が夜を縫う。
ネオンのキャンドルライトが点り、煌々と歓楽街を照らす。売春婦の頬も青白く染める。夜空を彩る電飾のページェント。涙と笑い、憎しみと嫉妬がそろそろ夜の底に渦巻く時刻だ。
けたたましい騒音をたてながらオートバイを乗り回す男たちがいる。バーやキャバレーで酒の空瓶を転がす飲んだくれがいる。闇夜に浮かび上がる怪しい突起口からは今日もまた、吐瀉物や流動物や精液が吐き出される。足許には黒柘榴の怪しげな穴があいている。
寝っころがり駅のホームの椅子を占有している者もいる。彼らは終電が出てしまった後も、ああやって眠り続けているのではないのだろうか。仕事もうまくいかず、家族との心も通わず、帰るべき家を失ってしまった男たち。彼らは様々な重荷を積んだ、夜の海を渡る箱舟。最近では感情のメトロノームの振り幅に嘆く日々が続く。
今日も夜空に絶望の溜息を吐く。凍える冬になれば、溜息は雪となり彼らの肩を白い幕でおおう。一体ここはどこだ。ここは夜の翼の下に眠る墓場なのか。あるとき彼らは、心労から自分の心が壊死しそうになっていることに気づき愕然とする。もしかして劇は幕があがる前から終わっていたのはないのかと。
心に鉄仮面をかぶった男たちが毎夜、都会のはらわたに吸い込まれていく。そんな男たちに群がるのが夜の蝶。極彩色の万華鏡のなかに彷徨い、眩惑される男と女。着色された夜の花粉が舞い踊る街。毒グモが罠と策略の蜘蛛の巣をはりめぐらす街。今日も色と、欲と、騙し合い───ありとあらゆる亡霊が跋扈する。
歓楽街は真空エリアだ。なにもかも忘れて真空になれる。空っぽの自分でいられる。真空の小箱からあふれる色とりどりの宝石のイルミネーション───海底に沈みゆくダイヤモンドのように、そぞろ歩く男たちの蒼白い顔を七色に照らしだす。
その男たちの中に彼もいた。何故だか知らないが、彼もまた、ときに巨人の黒い塑像が自分に向かって倒れてくるような切迫感に襲われる。金さえあれば飛ぶ鳥も落ちる。金さえあれば‥‥‥。そしてたまたま、ある女が彼の落とした月の銀貨を拾い上げるのであった。
「あなた何処から来たの?」
開口一番、女はそう訊いてきた。
「僕は僕の中から来たのさ」
「え? どこに住んでるかってことよ? 変な人。言いたくないならいいわ」
そのとき赤井君は性に飢えていた。黒焦げ死体の内臓に少しだけ残っている水分を必死で舐めまわす火炎地獄の餓鬼のように。この渇望感と衝動はおそらく女にはないものだろう。男は性欲で泥沼に入っていくが、そういう女はあまりいない。女が泥沼に入っていくのも欲望ではあるが、違った種類の欲望によってである。
人生を大過なくすごすには、まず女と関わらないことだ。理性ではそう思う。だが理性ではそう思っても、感性と肉体がそれを許さないというのが今の彼の現実だ。夜ごと自らの遺伝子に尻を叩かれている。
彼が性に飢えていたのは、仕事でしこたま夢茶を飲んだせいもあろう。よほど相性がいいのか、飲む度その夜ビンビンになる。おまけに半酩酊状態のせいで、普段いうことの変わっている彼がますます変なことを言い出す始末だ。
かつてカマトトだった彼も、数を重ねるにつれてカマトトでなくなった。人づきあいで疲れないコツは演じないことである。たとい夢茶でグデングデンになっていようとも、その時の自分をありのままに出すことにした。経験上その方がかえって嫌われにくいことも分かった。無論、ありのままの自分を出して嫌われようが悪く言われようが知ったことではない。どうせ一夜限りの関係だ。おそらく次はない。嫌われようが罵られようが、自分を空にさえできれば、それは相手の問題であって自分とは無関係なのである。
貪婪な夜の唇が宵闇といっしょに下りてきて、理性をくわえて去っていった。彼はそのとき女といた。女と───
リバティ。それがラブホの名称である。さまよい歩けば月もついてきそうな長い夜を目前にして、二人はそこに入っていった。窓からは遠く小倉沖に広がる海が一望できた。かろうじて茜空が残る時刻だ。

赤井君の当時の記憶がクラゲのように透き通り、骨の抜かれた肉体のように滑らかにあの夕刻の歓楽街上空を飛ぶ。日没間際、トワイライトの歓楽街は多色の血管が浮き出た人造人間の脳をイメージさせる。蓋をパカッと開くとキラキラ光る無数の電飾が徐々に姿を現す。やがて脳を包み込む頭巾のように、ゆっくり夜が空から下りてきた。
「あたしは無造作に捨てられた花束。あとは焼かれるだけ。まだまだ咲いていたいのに。ねえ、あたしってまだ綺麗?」
彼に向かってそう言う女。芝居がかっているとはいえ、男心をぐっと引き寄せるその切ない言葉の響き。美しい模様の蝶の羽のように女のスカートが揺れ動いた。彼は女の脚を見ながら、ふとマネキンの足首に赤い紐を巻きつけていく情景を浮かべる。
「どうせ人なんてほとんどが、大輪を咲かせようとして徒花に終わる。僕だってきっとそうだ。綺麗だよ、とりあえず今を楽しもうや」
慰めにならなかったのだろう。女はぎこちなく笑った。女の眼をじっと見つめれば見つめるほど、スカートの裾に火がついてじわじわと這い上がってくるように、少しずつ興奮の高まりを覚えた。
「今日出る月はまんまるだって。十五夜よ、気づいてた?」
「うん、新聞のコラムで」
「最後に新聞よんだのいつだったかしら。学校に通ってたころ? 今は全然読まない」
「僕も会社にあるから読むだけで。読まないと時間が潰せないんだ」
「月から地球を見たらどんなふうかしら」
「そりゃ、同じまんまるだよ。テレビとか雑誌とかで見たことないの?」
「ある。ただ訊いてみたかっただけ」
「月から見たら、地球は言ってみれば林檎みたいなもんだな。それぐらいの大きさに見えるんじゃないの? いや、もっと大きいかも」
「地球に巨人がいたのなら、それは林檎の上部の窪みに突き出た芯よね」
「巨人が突き出た芯のように直立していると‥‥‥それから、それから。それからどうした」
「巨人は両手で林檎を真っ二つに割るの」
「それってどうやって割るんだい。巨人は地球の上に立ってるんだろう」
「そんなこと、どうでもいいの。それよりあれって何とか言ったわよね」
「何とかって?」
「その半分半分の名前」
「ああ、北半球と南半球だよね」
「そうそう、それそれ」
「あ、間違えた。東半球と西半球か。ふつう林檎は縦に割るからな」
「どっちでもいいわ。そんなこと。あんた、男のくせに細かくて、ねちっこい人かも。じつは女なの? 名前なんて言うの?」
「赤井かさの」
「わぁ、化粧してないだけで、やっぱ女」
「なら、男だということを証明してやろうか」
女は腕の中の甘美な感覚に身をゆだね、微笑みを絶やさなかった。ゴムのように女の脚が柔らかくしなった。電話機コードのよじれのような女の動き。背中から足許に擦り落ちる薄絹の流れ。
彼は女を犯した、月を夜空から剥がすように。彼は女を犯した、斧で樹皮を巨木からはぎ取るように。ただでさえ都会の夜空は星が少ない。その少ない星を奪いあう二人。二人は絡み合う蛇だ。三日月の刃が漆黒の夜を切り裂いていく。
いかにも裏返せそうなペーパームーンの薄明かりの下、安ラブホテルで彼と女は時の沼にゆっくり沈んでいく白い肉塊と化していた。竪琴の弦が切れ、か細い糸が風に靡き、女の乳房に触知的な愛の囁きを奏でる。
女体に注がれる樹液が、真空の宇宙に炎の雫を散らす。夢の彷徨のうちに死せる魂。その魂の溺死体を宇宙に泳がせる。女は艶めかしい唇を氷の大地に這わせながら、溺死体たる男を抱擁し、敵対する野蛮な悪魔の内臓を舌のうえで転がす。
「あたし今日の朝、怖い夢を見たのね。自宅のドアを開けるとぉ、テーブルの上にトランクが置いてあったのね。トランクを恐る恐るひらくとブリキ屑が一杯詰め込んであったの。その中をまさぐってみたら何かがあった。人の手首よ。切り落とされた手首が中にあったの。そんな怖~い夢」
面白い話をする女だ。たぶん本人はそのことに気づいていないのだろう。ふつうに話していると思っている。芸術は思わぬところに転がっているものだ。いくら怪奇な色調を帯び、毒々しく、歪むだけ歪んでいても、芸術は芸術である。ICレコーダーに録って花菱に聞かせたら喜ぶことだろう。そういえば昔、こんな語り口の女と付き合っていたような気がする。誰だっただろう、なぜか思い出せない。
「それからこんな夢も見たことあるわ。地底に続く長い洞穴をずーっと歩いていくと、明かりが向こうに見えたの。ほどなく分かった。そこは部屋だったの。さっきと同じ、あたしの自宅の部屋よ。部屋の真ん中には棺桶があって知らないお爺さんが眠ってるの、棺桶の中でよ。そして棺の横には、葬儀屋さんかしら、黒い外套をまとって仮面をつけている人がいる。男かしら女かしら。手に包丁を持って突っ立ってるの」
繁華街。そこは無数の性器とそれをなぞる無数の触手が、迷路となって絡み合う場所。無限の苦海を無数の男が泳ぎ、また別の苦界には無数の女が沈んでいる。彼らは卑猥な妄想によって緑色の嘔吐をし、人差し指を天空にかざして自らの脳ミソを愛撫する。
「小倉の街ってのは、何千何万もの頭蓋骨が手足を生やしてうろつき回っている街だよ。とくに歓楽街はそう。みんな大脳生理学がキノコのように体じゅうから生え出ている。そんなのが生きてるのだか死んでるのだか分からぬままに、あっちこっちをゾンビ徘徊してるわけだ」
「え? 突拍子のないことをいいだすのね。何言ってるんだかサッパリ。頭から手足がにょきにょき出てきた変なのが辺りをうろついているわけなの? 違うわよ、そんなの。夜の歓楽街はね、頭の暗闇にすくう欲望が、入り組んだ鏡の迷路にまよう場所。それが歓楽街。そんな気味悪いもんじゃないの」
「つまりだね、歓楽街をさまよう人間どもはみんな、こういうことなんだよ。ノートに引いた二本の赤線にそって使い古しの丸まった消しゴムがコロコロと転がる。それが頭ってこと。当人が知らないだけで、もう最初から運命のレールは死ぬまで引かれてるってわけ。もちろん頭には個性もあれば顔もある。線上の顔だな。グラスの底に顔があっていいなら、レールの上に顔があってもいいはずだ」
「何いってるの? ほんと、あなたって狂ってる。ぜんぜん話に脈絡なくて会話になってない。正真正銘の狂人ね。あなたと話してると目に見えない壁が累々と周囲に築かれていくみたいな感じ。もっとも演技かもしれないけど。だったら口だけ狂人男だわね。気違いというより弱虫」
「狂っているのは僕でなくてこの街さ。廃人どもの反吐で下水があふれだす街。何百、何千もの飢えた子供たちが、氾濫した反吐の汚水に溺れかけている」
「それってどこの国の話? そんな酷い国は世界のどこかにありそうだけど、そこってどこよ」
「夜の都会の大時計はいつも間違った時刻を告げる。あの鐘の音を氷の森に投げ込んでしまいたい。いっそ時間というものを殺してしまいたい。夜の世界のすべての時計は、気違い犬のように笑い転げている。僕を軽蔑してるのさ。君にはあの笑い声が聞こえないのかい? やめろ! 笑うのはやめるんだ!」
「はあ? あたし、笑ってないわよ」
「僕の頭の中にある街。ああ、言葉が出てくる‥‥‥骨が足許から腐食していく気分だ。数知れない禿鷹が地上に舞い降りてくる。死人の肉をついばむためだ。街全体がカサブタに覆われたようだ。都会の憎悪の沼からは舌が生え出て、白痴化した豚人間どもの尻を舐め尽くす。この街は自分の産んだ子を食ってしまうネズミみたいな奴らに牛耳られているんだ。死体、死体、死体の山。奴らの鼻も死臭に痙攣して今にも爛れ落ちそうだ」
「う~ん、もういい、聞きたくないそんな気色悪い言葉。言葉が出てくるのはあなたの勝手だけど、出てきても黙ってて」
「君は夢を追いかける夢を見ながら、世界の果てまで希望を求めて旅する必要はない。何故かって言えば、夢自体が閉ざされたものだから。セキセイインコの夢は本来、鳥籠のなかにあるんだよ」
「意味不明。だからぁ黙ってて、と言ってるでしょう。あんた、狂ってるわね。セックスはまともだったけど、今は違う。ラリってない? 変よ、というか強烈すぎ。悪魔的だわ。狂人と話してるみたい。何をきっかけに発狂しちゃったのかなぁ、赤井かさのク~ン」
「ふっ、発狂とはオーバーな」
「あなたって白い石板に刻まれた象形文字よね。不可解で冷淡で‥‥」
「君はホントの僕を知らないだろう」
ホントの僕? いったいそんなものあるんだろうか。前面には入り組んだ鏡の森があり、そこに無数の僕が映し出されている。
「あたし寝るわ。疲れたから今日はここに泊まる。あなたも口を噤んでさっさと寝れば」
「でもお金が‥‥‥」
「あら、現実をつきつけられてハイド氏がジキル博士に戻ったの? やっぱり偽物。男のくせにケチ臭いこと言わないで。わき目もふらず馬車馬になって働けばいいじゃない」
かように男と女は事を終えてしまうと力関係が逆転するものである。彼は行きがかり上、断ることができなかった。
周囲を黒く塗った女の眼。充血している。ネオンサインのけばけばしさにも負けないほどに、どぎつく派手に化粧したその眼。彼らはその瞳の奥に吸い込まれていくかのように眠りに落ちた。二人の手には氷の星が握られている。
そして朝。都会は薄霞の中、いまだ静寂に包まれていた。朝まだきに路ゆく人とてない。静かだった。海面に落ちるひとひらの雪の花──その花びらが溶ける一瞬の微かな音だに聞こえそうなほどに。
外灯はまだ点いている。水瓶から溢れ出すかのごとき無色無臭の明かりが辺り全体を淡く染めている。微かな明かりの海に巨大な都市はまだ眠っている。巨大な都市の浮き沈みする白い腹。女のたてる寝息がその動きに重なる。
やがて朝焼けが空に琥珀のシロップを流す。明けゆく空。立ちのぼる微細な水蒸気の粒に太陽がその色を溶かし込む。大地が染まる。陽光が茜雲をつきぬけ部屋に差し込む。光の屈折か何かだろうか、それが靄の海にマッチの炎が不思議な弧を描いているかのように見える。
雲間からのびる一条の日射しは、銀のスプーンとなって昨夜の疲労と罪の意識をすくい取ってくれるのだろうか。曙色の波。窓ガラスが東雲の赤ペンキを帯び、血を吐くピエロの顔に変じる。
女の付け睫毛が風にぎこちなく揺れている。蠅取り紙にはりついた蠅の足のひくつきのようだ。ねむっている女の黒い目ヤニ。耳のピアスが昨日の夜の微かな明かりを宿して震えている。
女は化粧を落とさず眠ってしまったらしい。濃すぎる口紅で唇が処女の生き血を吸った吸血鬼のようだ。歓楽街の過酷さと非情さに傷ついた女は、未明の薄闇にミイラとなって浮かぶ。汚れた肉体を忘れていられるのは夢のなかにいる時だけ。
目の奥に沁み入る化粧水の匂い。魂の底に澱む生ぬるい精液。果物ナイフに映るマニュキュアの色‥‥‥。
そうだ、思い出せ。夜中に悪夢にうなされながら流したであろう黒い涙に、ほんの少しだけ優越感を抱いたのを。いや優越感というよりは、同じ底辺に住む者どうし、互いに理解し同情し合う気持ちを感じ得たことを。
(49)
さて、回想はおしまい。ここは大雨のなかの雨宿り、再びあの店のあの席だ。
視界が下部へ流れ落ち、室内照明の光波がフロアーを這っているのを見る。その光波を視線が巻き取っていく。照明を追いながら上方にスライドするカメラアイズ。レンズはテーブル下の男の革靴をとらえたところで、いったん静止した。
そこから水平に移動撮影開始。眼底に埋め込まれたレンズが、映写機の回転音とともに脳膜にいくつもの脚の線を映し出す。一瞬その脚の一つに注意をひかれた。咄嗟にパンするのをやめ、そのままクローズアップ。
何の変哲もない女の脚だ。さっきの女だろうか。それさえ分からない。馬鹿な、さっきの女なら一周回ってしまったことになっちゃうじゃないか。しかし何故この脚がことさら目に留まったのか?───うん、そうだな。きっとあの履物のせいだ。
ほぼ10センチ見当の、むしろ陳腐な幅広ヒール。そこからニョロニョロと脹らはぎの中ほどぐらいまで、紐が脚を締めつけながら這い上がっている。あたかも白壁に絡まる蔓か、それとも獲物をしめ殺す蛇であるかのように。
どうもそれが神経に紙ヤスリをかけてくるらしい。頭を締めつける発条の切り口。神経の震えが張りつめた弦に共振する。踝を挟み、アキレス腱を圧迫しながら足首に紐が巻きついているあたりは特にそうだ。そこに浮き出た青筋とともに、あの紐を切ってしまいたいという強迫観念をいだかせるのだ。
おかしい。僕は額が斜めに掛けてあっても全く気にならない性格なのだが。夢茶を飲んでいないのに、何だかおかしい。なぜか現実感が希薄で夢の中にいるかのようだ。僕はますます幻覚体質になりつつあるのかもしれない。
いやいや、この現代社会自体が暗示だらけで夢と紙一重ではないか。確かに僕の場合は、やたら心が夢の中に戻りたがる嫌いはあるんだけれども。そもそも人の心ってもんはそう簡単に調律できるピアノではないだろう。ずれた音階を響かせることなんてザラにある。こんなの大した事じゃないんだ。
女の脚は白くて中が透けて見えそうだ。なぜか皮を剥いだ蛙の虹色の繊維が浮かんできた。その繊維を舐めている僕がいる。舐めるたびに電気的ショックが全身を駆け巡る。舐めることを止めればいいのに止めることができない。もちろんマゾヒストのごとく苦痛を快楽に変換できるわけではない。ただ波のように周期的な苦痛にただ身をまかせている。僕はそれを当然のことと思い、慣らされ、ある意味この場所に安住している。人生は苦だと釈迦は看破した。この絵は人生の縮図だ。生まれ出た人々は全員、この絵のなかに描き込まれる。
なんだ、これは。幻覚か? 現実と非現実の境界が判然としない。自分が誰か知らない人の現実をこの場で見ている感覚がある。何度も言うが、夢茶は飲んではいない。そうなら夢茶の副反応かなんかだろうか。いやいや、何でもかんでも夢茶のせいにしてしまうのでは芸がない。夢茶が至って害がないのは経験済みだ。言ってみれば栄養ドリンク剤みたいなもんで、今や晩酌と同じ。やめたらかえって体調が悪くなってしまうんじゃなかろうか。だとすれば、これはいったい何? 毒を以て毒を制すと言う。迎え酒よろしく、ここで夢茶をガブ飲みすれば、意外と正常にもどったりして(w)
ふつう人は意識しなくとも、あらゆる思考や感情が自動的に生成されるものだ。それは意図的になかなか制御し難い。何でか知らないが可笑しい。何でか知らないが腹が立つ。考えて得することのない悲観的なことを、何でか知らないがつい考えてしまう。そういうのは解る。日々だれもが経験することだ。
だが想念でなく映像が自然発生的にポコポコと湧き上がってくるのはどういうことだろうか。あまつさえそれを全く制御できない。眠りのなかで夢の展開を制御できないのと同じだ。これは自分の心が実は自分のものではないことの証左か? これまた何度も言うが、まさか僕はいま夢を見ているんじゃないだろうな。
ボタンを押したら幻覚の映像フィルムが回る。ドアをノックしたら中から幻覚がひょっこり顔を出す───そんなふうに自分でコントロールするわけにはいかないものだろうか。いかないだろうなぁ。無意識の底からランダムに浮き上がってくる悪夢の泡、さすがにこれは如何ともしがたい。
───縛られたくない、自由になりたい‥‥‥何から? この悪夢からだろう。でもその正体が分からないではどうしようもないではないか。
なんとなく手首を締めつけている時計バンドの圧迫感が気になりだした。手首にはしる赤い亀裂のイメージが心を締めつけだす。神経の殻に刺さった棘。動悸がする。なんだか息苦しい。唾を呑みこむ。唾を呑みこんでも同じだ。これから箱村の奥さんに電話しなければならないというのに、心のスマホが充電切れを起こしそうで、甚だ心もとない。
時計を外してテーブルに置くことにした。やはり窒息感がある。ぼんやりとした不安はなくならない。なんの理由もなく不安感に襲われるのは何故だろう。今ここにある不安ではない。不安を予期している。だがその不安の正体は分からない。お前は何者だ。正体を明かせ!
早鐘を打ちはじめた心臓をなだめるべく、深呼吸して瞼を閉じる。
目を閉じてもなお、目の裏側には女の脚の白い外形が残っている。薬品に沈む脱脂綿そのままに澱んで見える。幻影をふり払おうとしても、すればするほど逆に色濃く像を意識に刻み込んでくる。恐れるなと思うほど、かえって怖くなる心理と同じだ。自分の心は自分のものではない。だから意のままにならない───と、今はやり過ごすしかなさそうだ。
それでも無駄と知りながら、綿菓子だとかゴム人形だとか、努めてほほえましいイメージとダブらせようと試みるが、うまくいかない。そうこうするうちに女の脚には、紐をほどき履物を脱いだ時にできるであろう、赤い条痕が浮かび上がってきた。赤井君はその赤い痕に血を想起せざるをえなかった。
すると、意識の隅っこに殻をむいた茹で卵らしきものが現れた。テレビ画面の端にはめ込まれたワイプ画像のようだ。ワイプは次第に大きくなっていく。今、茹で卵の滑らかで柔らかい肌に、ピンと張った糸が切り込みを入れたところだ。切り込みは深くなっていく、少しずつ、少しずつ‥‥‥。
心臓の振り子の周期が再度短くなり、肉の壁面を早鐘よろしく速射的に打ち鳴らす。
おっ、中から何やら薄赤い繭のようなものが覗いた。雛鳥だった。まだ毛も十分はえていない、産まれたばかりの雛鳥。その意外な展開には仰天せざるを得ない。
───危ない! 糸を切らなきゃ、鋏はどこだ!
捜している暇はない。咄嗟に指を入れて糸の動きを止めた。すると指に糸が接触した途端、血が噴き出てきたではないか。痛みに思わず指を引っ込めてしまった。だが実際に痛かったわけではない。ここは幻視の世界、反射的に痛いと錯覚しただけだ。次の瞬間、雛鳥の体に糸が触れる。
ストップモーション! 時間と空間を切り落とすんだ! そのとき動画が一枚のフォトになる。視界に動きあるものが何一つなくなった。すんでの所だった。全てが静止し、時も凍った。
───ふう、よかった。
安堵に目を開けば、視界に光が流れ込み、店内の音も蘇る。今のは何だったのか。振り下ろされた熊の爪を紙一重でかわした気持ちだ。胸が悪い。観念の外側の嘔吐。頭の中に大きな石がいっぱい詰まっているかのような頭痛がする。
不思議だ。実際に起こっていない世界のほうがよりリアリティーがある。何故だ。今このテーブルの前に座っている自分が、むしろ夢のようで現実感がない。
何の気なしにガラス越しに景色を眺めようとしたその時である。窓ガラスに反射して内側に男の顔がぼやけて映るのが見えた。岩陰から急に首を出した恐竜のような唐突さだ。
「ああ、腹が痛え。俺、胃袋ん中の海で溺れそうなんだ。腹を裂いて、胃袋ひき出して焼いちまいたいぐらい痛えよ」
声に横を向くと、なんとあの男が立っているではないか。そう、別のテーブルでビールをがぶ飲みして怒鳴りあったり笑いあったりしていた労務者風のたくましい男らの一人だ。あの腹が痛いと言っていたガタイのおおきな男。肩を落として、横に突っ立っている。やおら僕にむかって話しかけてきた。
「ああ、腹が痛え。俺、何匹もの毛虫を食ってさ。ほら、歯に毛虫の緑色の体液や茶色い毛が付いてるやろ。巨人の口の中にな、俺の首っ玉を突っ込んでるよな感じなんよ。怖いよ。ほんまに怖い。聞こえないか? そら、あの音だ。そうなんだ、噛みちぎってるんだよ。音だ、分かんないのか。巨人が俺の首をさ。その音だ。俺、首、なくなちゃってさ。痛がってあばれてるだろう、手をバタバタさせて。首の切り口からドロドロしたもんがはみ出してきてるよ。内臓かもしれない。おい、吸ってるよ、巨人の馬鹿でかい唇が俺の内臓を。殺してほしいぜ。早く俺をぜんぶ食っちまってくれよ。血をぜんぶ飲み干してくれよ。俺を消してくれよ。早く、早く頼む」
慄然とした。悪寒が背筋を走り、鳥肌が立つ。男の言葉がネチネチと蛇のように体に巻きつき自由を奪う。
「失礼ですが、どちら様ですか? 何処からいらっしゃったんですか。あちらでビール飲んでいらした方でしょ?」
「‥‥‥‥」
黙して語らずだ。面と向かって見ると変な顔立ちだ。なんというか、雑巾がクシャミをしたみたいな顔である。なんだ、コイツは。このゴロツキ野郎がぁ。居心地の悪い時が流れる。しばらくして再び男が語りはじめた。
「華美だが、それでいて実に空虚な人間という廃墟の城。あるのはただ見下ろす度に崩れ落ちていく、過去という名の螺旋階段。そしてただ死体安置所に至るだけの、未来という名の闇の通路。そう、この狭い部屋のどこかに二つの世界を結ぶ通路がある。現実と幻、真実と虚構。私はその通路をとおってここにやって来た」
何を言っている。いったい何処から来たっていうんだ。支離滅裂で言ってることがサッパリ分からん。デタラメ並べて意図的に話の腰を折ったのか。
アンタ、あそこのテーブルで腹が痛いと喚いていた男じゃないか。酔って、ぷら~りとこっちに来たんだろう。はた迷惑な奴だ。それにしても何だ、さっきとまるっきり口調も声質も違う。どうなってるんだ。しかもこのセリフ、前どこかで聞いたことあるな。どこだったろうか。
「おっさん、もしかして、からかってるの? アンタは誰だ、誰なんだ!」
「私だ」
「その私が誰かと聞いているんだ」
「私というのは僕だよ」
「えっ?」
「君は既に私になりつつあり、私は君になりつつある。すなわち僕だ」
「なに訳の分からないことを言っている、お前は誰なんだ!」
「誰でもあり誰でもない、すべてだ。あまねく無尽に存在する」
「どういう意味なんだ」
「同じ波長をもつ者どうしのほうが互いに交信しやすい。つながるためには相手の心に自分の魂を入れてしまうこと。すでに私は君の中に入っている。すでに、だ」
思い出した! コイツに一度会ったことがある。そう、夢の中でだ。いつかコンビニにオニギリを箱村が買いにいっている間に見た夢。その中に出てきた男(霞ゆく夢の続きを〈3〉─21)。アイツだ。
もう忘れかけていた。この男はあくまでも霞ゆく夢の続きを見させようとしている。私を忘れないでくれと‥‥‥何度も、何度も。
その時である。フロアーが滑らかなガラス状に透きとおり、とつぜん白い泡を吹き上げながら足許から僕の体をその貪欲な胃袋に吸い込んでいった。
というか、より正確には「吸い込んでいったような気持ちになった」と言うべきであろうか。それというのも今僕はマイクロスリープに落ちていて、ごく短い夢を見ている最中かも知れないからだ。夢の中にありながらこれは夢だと気づいている、いわば明晰夢を。もしこれが夢だとすれば、胃袋に吸い込まれるというこの夢のシチュエーションも、きっと腹が痛いと喚いてたあの男の印象のせいだろう。
いや待て。あの男だって果たして現実かどうか分からない。現実にしては態度や言っていることがあまりにも不自然だ。もしやあの男も本当は存在せず、夢や幻の類だとしたら‥‥‥そんなぁ、夢の中で夢を見る、際限がないじゃないか。そんなことを言い出したら、夢という概念を重層的にとらえ直さなければならなくなる。えい、ままよ、夢なら覚めてくれ。あとは野となれ山となれ、だ。
そのように妙に冷静に状況を分析しながら、同時にそれでいて夢と半覚醒の間を揺れ動く、曖昧な振り子の自分がいる。
そのまま仰向けに落下しながら上方を見れば、空が暗い。闇の外套を重々しくはおっている。目を凝らすと、おぼろげに宙に黒衣の年老いた魔女が浮かんでいるのに気づいた。老婆が魔女だと思ったのは箒に乗って浮かんでいたからだ。
魔女はゆっくり下降し、僕のすぐ上にやってきた。碇につながれて沈められたかのように体が動かない。張りすぎて今にも切れそうな弦を見るときの息苦しさ。魔女は箒の上に立つと、見下ろしながらその口を耳まで赤く裂いて笑い、そして股を見せた。
しばらくして股から嫌な臭いのする粘液が、ねじれた紐状に尾を引いて落ちてくる。舌に貼られた折り紙のように、その悪臭が肌全体にはりついてくる。体が石になって動けない。粘液は僕の顔にあたり、視界に赤い飛沫をとばした。
何だ、これは。そう思い顔をぬぐう。広げると手の平が赤く染まっていた。血だった。細めた目の間に沸騰した赤い海面が見える。それは下腹から噴き出す魔女の血だった。
「ほ~ら、舌の先で魔術師がステッキを持って踊っているじゃろう。これは箒でなくてステッキなんじゃよ」
老魔女はこちらを見つめつつ、訳の分からない言葉を吐いた。
舌の先でどうしたって? 舌、舌、舌、舌───なにも言えない。それこそ車輪に舌の先がからみとられていく気分だ。足許の床が抜けたような無抵抗感。このまま、されるがままでいるしかないのか。
そこで急に睡魔が襲った。感覚がゴムの樹液のなかに溺れていく。その粘度のある白い舌に舐めまわされて、次第に理性が外形を失っていく。頭蓋骨に開けられた穴から思念が液体となって流れ出す。底を見れば闇が渦状にとぐろを巻いている。曖昧模糊とした状態のまま、いつしか眼界にカーテンが下りて、意識に閂が掛けられた。
どれだけ経ったのだろう。数時間のようでもあり、ほんの数分のようでもある。恐る恐る目を開けば辺りは前と変わらない。ただしあの不気味な男がいないことを除いては。辺りが少しも変わらないということは、あれは数分どころか数秒の出来事であったのかもしれない。虚構世界と現実とではたぶん時間の流れるスピードが違うのであろう。
誰かにAIのつくったフェイク動画でも見せられていたのか。まさか、そんなことはあるまい、ただの夢だ。いやそれは断言できないかも。夢にしてはリアルすぎるのだ。リアルすぎて、いったい何処までが現実で何処からが夢かも判然としない。
もとより夢から何かの確証を引き出すこと自体、無理スジである。夢は写真に撮ることも録画することもできない。あまつさえ触ることもできなければ、面積や重さもない。こんなあやふやなものから何を証明しようと言うのだろうか。
あれが夢でないとすれば、たったいま実際に僕はもう一つの現実を見たということになる。まさに拡張現実だ。現実の上に別の予期せぬ現実が投影される。まるでコンピューター生成画像を重ね合わせたかのように。
AIが人間の知性を越える特異点、いわゆるシンギュラリティは来ないという説は確かにある。だがその一方でシンギュラリティの到来は時間の問題だとする説もある。どちらが正しいかは、最終的に時を待つしかない。
だとすればAI説も荒唐無稽と一笑に付すことはできないのではないのか。これが何らかの方法で、知らないうちに僕の脳のどこかに組み込まれたAIプログラムの仕業としたら‥‥‥まさかな。何を血迷っているんだ。そんなSFがあってたまるか。いつ、どこで、誰がそんなプログラムを僕の脳ミソの中に仕込んだと言うんだ。
現実を見る自分と悪夢を見る自分。自分の内側に二つの人格がある。悪夢は断崖に落ちてくれたのか。体から黒い影が悪夢と共にはがれて落下し、地に叩きつけられ砕ける。あとには白い自分だけが残ってくれればいいのだが。
幻覚は深層心理から浮かび上がってくるのだろうか。ではその深いところにある心理とは何か。自分の心理なのに分からない。そんな馬鹿なことがあるだろうか。覚醒した普段通りの意識のままでずっといたいのに。自分自身のことながら分からない。なんてこった。迷惑このうえないではないか。
これはまともな精神状態ではない。どこに本物の自分がいるのだろう。理性の秩序が崩れていく。このカオスと対峙して、あるべき姿に戻る方途はあるのだろうか。脳か心か、必ずどこかに病巣があるはずだ。何とかその病巣を見つけ出し、切除できないものか。
鏡に映った自分の像に「お前は誰だ」と問い続けるといずれ発狂する、というよく知られた都市伝説がある。少しずつ自我が崩壊していき頭がおかしくなると言うのだ。精神医学上それが正しいかどうかは、試したわけでもなく、また専門性を持ち合わせない僕には確かめようがない。
だが昔、鏡の自分に話しかける認知症患者にお目にかかったことがある。その時、この人はボケが進んでテレビ画面に話しかけるご老人とは根本的に違うな、という感想をもった。鏡の自分に話しかける人は、おそらくゲシュタルト崩壊が起こって自分の顔が他人の顔に見えるのだろう。
正常人であっても手鏡をよく覗く人は、自分の顔が各パーツごとに分割して認識され、ごくまれに「あれ? これ私の顔なの?」と錯覚することがあると言うではないか。つまり自分が二人いるのである。自分が二人いれば人格が二つあったっておかしくないだろう。
関係ない話だが、今は容易に顔を画像補整できる時代だ。SNSなんかでは自画像の修整だらけだと聞く。そういう世の中なんだ。みんな複数の顔を持っていて普通なのだ。仮想現実がはびこる現代、そんなことはけだし当然だろう。今の自分がことさら異常だというわけではない。ただ気が狂うのではないかという暗示にとらわれているだけのことだ。
聞くところによれば、百人に一人が統合失調症を患い、幻覚や幻聴に悩まされているということだ。しかもそれは若年層に多い。そう考えれば僕が幻視に苦しむのも決して異例ではなく、よくある身近な症状ということになる。誰だって一生に一度ぐらいは病気を発症するだろう。なんてことはない。ちなみに、日本では同様に百人に一人が一億以上の資産を持っているとか。おなじ百人に一人なら億万長者のほうがいいが、さすがにそれは虫が良すぎる。無い物ねだりは言うまい、エヘヘへ。
こんな具合に赤井君は付け焼刃で屁理屈をこねまわし、なんとか自分を納得させた。理性と感情は別だが、汚い部屋も強引に整理すれば少しは気持ちも収まるものだ。とはいえ付け焼刃は付け焼刃、鈍はいつ刃先が欠けるか知れたものではない。用心するにしくはないと思う赤井君である。
───もう目を閉じるのはよそう。閉じればカットバックで異様な映像が間に挿入されてしまう。せっかく手編みのマフラー気分にホッコリと浸っていたというのに、ほつれた毛糸を引っ張ってほどけさせるような馬鹿な真似はすまい。
そう思いながら、すでに彼の脳裏には闇のなかにマネキンの手足が転がっている光景が浮かび上がりつつある。きっとゲシュタルト崩壊という言葉のイメージによって自動生成されたものだろう。やはりAIに脳が占有されているのだろうか。
腋に冷や汗が一条たれた。額にも玉の汗。知らぬ間に汗だくだ。汗が生き物となって肌を這い、時に跳躍する。冷気が氷の剣となって背筋に触れる。呼吸も荒い。薄い酸素にあえぐ金魚のようだ。千々に乱れるこの心の持っていき場所が分からない。クラクラと揺り籠にゆられている気がする。ゆらしているのは誰の手か。
ここは都会の刃に傷ついた心をそっとカサブタのように覆う場所だったはずではなかったか。今は心の傷口をつつむ繃帯がじわじわと胸を締め付けている。店に入ったときは暖かく眩い光に包まれている気がした。ところが今はどうだ、何か黒々とした悪鬼、悪霊の類に呑みこまれようとしているのではないのか。
再三再四言うが、それにしても夢茶を飲んでいないのになぁ。こりゃ、ちと変だ。冗談じゃなく、祈祷師にでも邪気をはらってもらわなきゃ。あるカットから別のカットに急に飛び、また元のカットに急に戻る。映画でも見ているかのようだ。認知が断片化し、連続性がない。
こんな具合に自分で自分をコントロールできなくなったときは、外から自分を客観的に見るんだったな。カナちゃんがいつか言っていたようにだ(霞ゆく夢の続きを〈1〉─9)。つまりカウンセラーになって僕の心の相談に乗ってあげたらいいんだ。さて僕にどのようなセラピーをすれば癒しをもっとも効果的に与えることができるのだろうか。
う~ん、難しい。何て言ってやればいいのかな。メタ認知と言葉でいうのは簡単だが、やってみるとなかなかうまくいかない。
〈君はいったいどうなってるんだ。どこまでが現実でどこまでが非現実なのかい? 現実と虚構が目まぐるしく入れ替わるんだね。いや虚構というよりは、これもある意味もう一つの現実だよ。すなわち二つの現実がいとも容易に交錯していくんだ。どうもさっきから意識が混濁しているみたいだね。小学校でイジメを受けていた時のように、このまま地滑り的に精神が崩壊していかなければいいけどね‥‥〉
そうか、やはりイジメか───
過ぎし日の胸にあいたトラウマの穴が疼きだす。ずっと昔のこととはいえ、忘れたいことを忘れるのは至難の業だ。いったん記憶のアルバムに貼られてしまった出来事は、そう易々とはがれない。むしろ遠くに離れた場所に逃れてみてこそ知る傷の深さである。
僕がイジメられていたとき、冷酷な現実から離れて想像上の友達を何人もつくりあげたことは以前に述べた(霞ゆく夢の続きを〈6〉─43)。想像の世界で彼らと遊んでいる限り優しさに接していられたからである。何をおいてもこの辛い現実から逃げたいという欲求が根強くあったため、想像上の閉鎖空間にこの身を置かざるを得なかったのだ。
解離性同一症というよく知られた精神障害がある。幼少期に適応能力を遥かに超えた激しい苦痛を体験することによって、一人の人間の中に全く別の人格が複数存在するようになる神経症のことだ。
僕にもあの時以来そういう精神的傾向が根を張り続け、現在まで至っているのではないのか。事実あのころ僕の頭の中には、想像上の友達という複数の人格が確実に存在していた。それは通常は裏に隠れているものの、あるとき何かのきっかけで急に表にあらわれる───そして最近再び、その種の心的傾向がかなりの頻度をもって蘇りつつあるとしたら。
そう考えれば、次々と上書きされていくかに思えるこの世界も、あらかた説明がつかないこともない。箱村などは幻覚体質と簡単に片づけてしまうが、幻覚と思えし映像も実は幻覚でなく、もう一つの現実だと見なすことはできないものか。人格がいくつもあれば、現実もその数だけあっておかしくないではないか。
自分の内に自分に似た他人たちが住んでいる。もしかすると彼らは自分が忘れ去った過去の自分なのかもしれない。あるいは逆に、彼らが僕という存在を忘れ去ったのかもしれない。いずれにせよ僕の中に何人もの違った僕が潜んでいる。実は頭の中に幾つもの部屋があって、そのうちの何部屋かは入れない。彼らは僕にかわって自由に部屋を出入りする。鍵は彼らだけが持っていて僕は持っていないのだ。
心の中に自分が支配できない場所があったからといって少しも変ではないだろう。人間たるもの、むしろそっちの方が自然なのではないのか。自分の中に自分に似た他人が住んでいる。考えてみれば僕だって電器店の糞オヤジの倉庫に勝手に住み込んでいるじゃないか。そう、薄暗いお化け屋敷のようなあの倉庫だ。あれと同じことだ。あの糞オヤジにしてみれば、豆柴のくせして家主のような顔して怪しからんとなるのだろう。でも考えてみればチビ犬はキャンキャン吠えたところでチビ犬だ。ちっとも怖くない。問題にするほどのことじゃないのだ。恐るるに足らずである。
さてさて、こんなふうに支離滅裂でもいいから事態を解きほぐしていけば、複数の現実がいとも容易に交錯していくのも何ら不思議はないと納得できる時がいずれやって来るんじゃないのだろうか。その時を待とう。
依然あの女の脚は眼前にある。脚に巻きついた紐と履物を脱いだ後の赤い痕───それらが微妙に視覚と感覚、そして現実と空想のなかで混ざり合う。思うに、この光景は天までのびた樹に絡みつく赤い蛇を連想させないか? 蛇がその口を開き、研ぎすまされた牙をむきだしにして‥‥‥おい、何だかまた幻覚がもう一つの現実をつくり始めた。もういい加減にしてくれ!
心が何か別の生き物であるかのように勝手気ままに幻視の糸を紡ぎ出す。この感情や光景は本当に自分自身のものだろうか。別人格の仕業か? 僕の頭はどうなっているんだ。赤井君はさも魂がぬけ落ちたかのように、放心状態のまま窓の外を眺める。身も心も空中に浮かぶビラとなって街の情景に舞っている。
───こりゃアイデンティティー・クライシスだな。
そう冗談めかして呟く彼である。彼なりに幼稚な理屈は積み上げたつもりではあったが、隔靴掻痒───靴の上から痒いところを掻く按配で、まだ心底腑に落ちてはいないようだ。とはいえ馬鹿げた冗談も浮かぶぐらいだから、まだ心の余裕は残っているらしい。
───それにしてもウエイトレスはいつ注文をききに来てくれるのか。ここで指笛でも鳴らせば気づいてやってくるのかなぁ。
少々苛立ちを感じてテーブルの上の時計を見れば、入店してからさほど時間が経っていない。意識がかくも緩やかに時間を運ぶとは。これならまだ来なくても不思議はない。かなり時間が経過しているかに思えるのだが何故だろう。時の進まない空間にでも迷い込んでしまったのだろうか。僕の持っている砂時計だけが特別で、ゆっくりと時間の砂粒を落とすのか。
もつれ合う蝶のようにウエイトレスが飛び回るのを眺めながら訝しく感じていると、
「ご注文はお決まりですか?」
一瞬ギクリとする。パーティーのピエロが心の呼び鈴を鳴らしたかのようだ。発したその声の語尾がこころもち震えている。どことなく様子がおっかなびっくりに見える。いつの間にやらウエイトレスの一人がテーブル横に立っていた。
決して美人とは言えない、おかめ顔の少女。目は糸のように細く、鼻はつぶれたピンポン玉だ。いつそこに来た。君はそっと背後に忍び寄る見えない影か。それとも隙間風か。どうやって木立の間を縫ってここまで吹いてきた。あたかもマジシャンが白鳩を取り出す素早さと唐突感でそこにいる彼女。風となった君はどうやって時間と時間の隙間をくぐり抜けてきたのか。
表情が強張っている。リモコン操作で泣き笑いさせられるロボットのようなストーンフェイスだ。勤めだして間がないのかもしれない。硬くなる心情は察するよ。人形遣いの糸に操られるまま、意思を持たないマリオネットがここまで連れてこられた‥‥‥そんな佇まいである。
試しに顔をじっと見つめてみた。すると気圧されたのかどうか、蚊を追う視線のように目が泳いでいる。
絵に描いた作り笑いでもいいから浮かべてみたら? そうだ、ここでチアダンスでも踊ってみるか。盛り上がること請け合い! けどいくら何でもそりゃ無理だよね。
そうそう、「ご注文はお決まりですか」‥‥だったと。あっ、それどころじゃなかったんだ。まだメニューも見ていなかったっけ。
「コ、コーヒーお願いします。あ、あのォ、砂糖、たっぷり入れて下さい」☕
やれやれ、硬くなっていたのはこっちもでした。
「えぇ? お砂糖ならテーブルの上にあるでしょう」
“なんだ、弱っちい男ね”と見くびったかどうかは知らないが、彼女はそっけなく砂糖ならぬ塩対応だ。二人の間にガラス細工の空隙が生ずる。心の隙間は埋めないといけないよね。
「あ、ごめんなさい。ここにミルクもちゃんとありますね、あららぁミルキーウェイ気分じゃんか」
ウエイトレスがクスッと笑う。その笑い声は先ほどから一転、色もあれば香りもある。ウン、なかなか魅力的な笑顔だ。含み笑いだけど、いい線いってるよ。みんなして嘘でもいいから笑おうよ。口角を上げれば運気も上がる、ってね。笑う門には福来たると言うじゃないの。
世の中には笑いたくても笑えない、切羽詰まった人がいる。かたや彼女みたいに接客で笑顔を強いられる人もいる。さあみんな、心の底から笑おうじゃないの。はい、指圧の心は母ごころ押せば命の泉湧くア~ッハッハッハッハァ───浪越徳治郎だぁ(チョ〜古!) 笑えばメンタル的にもフィジカル的にも健康になるよ。
「あの、ウエイトレスさん、笑わないで笑ってみたら?」
「はい?」
「心で笑っていなくても、試しに笑ってみたらって意味。こんがらがっちゃった? でもこれ、余計なお世話だよね。指圧の心は母ごころ~~~なんちゃって」
いつになくハイテンションの赤井君だ。心のスマホがどんどん充電されていく。さっきまで落ち込んでいたのに、その高揚感は何処からきたのだろうか。急速充電だ。今しがた恐怖に慄いていた自分が嘘のようだ。君は躁鬱病の北杜夫か! (ん? これも昭和世代にしか通じないネタでした)
だが、赤井君の印象とは裏腹、彼女は胸中、半ば小馬鹿にしている。
───この人、頭がおかしいんじゃないの? なに意味のないことを言ってるのかしら、変わった客もいるもんね。びしょびしょに濡れてるし。傘がないなら、そこいらのコンビニで買えばいいのに。
「コーヒー、なみなみと注いでね。そしたら僕が銀河の中心にミルクを吸い込ませるから。君の魅力はブラックホールなみだ。君の魅力に吸い込まれたらもう脱出できない。ブラックホールの重力は空間や時間を歪めるほど強い。強烈な重力で背骨が曲がっちまって、アレ、ますますチビになっちゃいそうだ。やばい、やばい」
馬鹿にされているのも露知らず、ウエイトレスから笑いを取ったとばかりに赤井君は浮かれてしまった。あっけらかんと与太を飛ばし続ける。女心に暗い彼がここまでズカズカ踏み込めるとは、一体どういう心境の変化か。ついさっきまでとは打って変わったこの態度、なにかに操られているとしか思えない。
かたやポカンとした顔の彼女。ややあって今度は声をあげて再び笑う。こらえていたタガが外れたのかも。ほどけかけた蝶々結びの笑いだ。そのやわらかな響き、どんな色彩にも合わせられる優しい色調の性格のようだ。もう硬さはあらかた取れたらしい。
「お客さん、いつもそんなに変なんですか?」
興味がわいたのだろうか。そんなふうに尋ねるところをみると、この人がどんな味か試食してみる気になったのか。好奇心いっぱい、若いねぇ。
「変も変、めいっぱい変。いっそのことコーヒーカップのなかで二人の運命をかき混ぜようか。ね、銀河って地球から見るとひとかたまりのミルクの河だけど、実際は無数の星の集まりだったんだよね。僕も星なら君も星、一つの天の川で互いに溶け合ってるんだよね。ロマンチックだなあ」
臆することなく突き進む、恥知らずの赤井君。頭の中はコーヒーの豆挽く音や香りで一杯だ。いささか横着がすぎる。躁鬱病、躁のサイクル真っ只中。締まりなく調子ぶっこいている。おかしいな、もともとこんな陽気な性格ではなかったはずだが。まさかこれを契機にこの娘と付き合おうなどと、下心ありありなのではあるまいな。
───まだ訳のわからないことグダグダ並べてるわ。馬鹿まる出し。二人の運命を混ぜようなんて気色悪い。引いちゃう。どこがロマンチックなのよ。どこかで飲んで、かなり出来上がってるのかしら。そんな気障なこと言って恥ずかしくないのかなぁ。軽薄で浅はかで、ちょっとこの人、逆に受けちゃったりしちゃうんですけど。間の抜けたお笑い芸人みたい。
彼女はますます赤井君がとんでもなくおバカな、うらなり青瓢箪に見えてくる。穴を開けたゴムチューブよろしく、緊張していたウエイトレスの顔はもうすっかり脱力状態である。今にも大声たてて笑い出しそうだ。なんでも面白い年頃なのだろう。
「おかわり自由ですよ、何杯でもどうぞ。呼んでください」
軽くあしらわれてしまった。
「僕、違いの分かる男じゃないんで、味より量なんだよね。よろしくね。ダバダ~ダバダ~~」
あしらわれても依然しつこい軽佻浮薄の赤井君である。馬鹿にされていることに気づいていない。
───これ、分かっただろうか。懐かしきネスカフェ・ゴールドブレンドのCMだもんな。若い女の娘に受けるわけないよな。しかし砂糖やミルクが目に入らないばかりかメニューも見てなかったとは迂闊だった。まあ、少しでも笑いがとれたならいいか。
そうこうするうちウエイトレスは事も無げに向こうに行ってしまう。いつまでもおバカの相手をしている暇はない。所詮たくさんの客の中の一人、当然赤井君のことなどさほど意に介していないのだ。
───ホントにおかしな人だわ。スルメや干物みたいに痩せてて顔色悪いし、危ない人だったら怖いわね。気をつけよぉ。
背中から尻へのラインが、形の整った茄子に見える。彼女はストッキングでなく素足で、踵のないズック靴をはいていた。
柔らかな物腰。森のような蒼い深海を泳ぎ回る白魚。後ろ姿に海風が匂う。浜辺の質感を僕の五感がとらえる。波や、砂粒や、光や、色。波の言葉と歌、それを風がひろえば詩と物語ができる。人影のない銀色の砂浜で広大な海をずっと見渡し続けていると、誰しも画家になり、詩人になり、そして小説家になるのだ。
腰に巻きついたエプロンの結び目は青空に広げた鴎の翼。君の鳴き声が風に乗る。鴎は海面ぎりぎりを華麗に旋回した後、水平線にむかって飛び去る。夕焼けに染まりながら、海に溶け込む水平線の彼方へ。やがて遠ざかる君の姿は、水に浮かぶ下着そのままに白くて、小さくて、淡くなった。渚のほとりに佇み、僕は視線を海の果てへと送る。望遠レンズを通したかのように君の姿をどこまでも追う。
燃える夕べのひと時、思い出の水際が陽光に反射してキラキラ光る。波頭がほんのりと赤い。影もほんのり赤く傾く。影、それはオレンジ色の雲の下に長く伸びる虚像。羽ばたき去る君には、岸辺にどんどん小さくなっていく僕の姿が見えるだろうか。波をすくってみた。指先から雫がしたたり落ちる。白痴のたらす涎のようにしたたる。草にお辞儀をさせつつ地面に落ちる霜。木綿糸に沿ってつたう涙。
水平線に触れた太陽が、たったいま大きな飴玉となって、海の舌の上でオレンジ色に溶け出しはじめた。太陽といえども永遠ではない。太陽も眠りにつき、漆黒に溶け、いずれ死にゆく。そして太陽が死に、夕陽が消えゆくときはまた、君の姿も僕の背中も闇に消えゆくときでもあるのだ。
君はまだ若い。ポケットいっぱい、夢いっぱいだ。見るもの聞くもの皆楽しい。幸せの翼の生えた彼女は、どんな国境線をも難なく越えて飛翔する。どこまでも遠く、はるか遠く、この世の果てに向かう。
───コーヒーはおかわりOKか。太っ腹だ。なんだ、ちゃんとメニューにも書いてあるじゃないか。コーヒーだけ続けて何杯も飲めないもんな。見え透いてるけど、他になにか甘いもの、たとえばケーキなどを注文させようとする魂胆かな? ちょっと深読みが過ぎるか。
彼女がコーヒーを持ってくる僅かばかりの時間の谷間。その谷間に赤井君は一本の白いロープを張る。女の、締めつけられた脚の幻影が下界の闇に墜落していく。彼は幻影とともに危うく下降しかける自分の心を、おどけて綱渡りする道化師のように、微妙な平衡のうえに保とうとするのだった。
さっきから赤井君は意味なくテーブル上の腕時計に注意がいく。ケータイを携帯するのに不慣れな彼は、スマホで時刻を確認できることにすら気づかない。直線的発想しか浮かばないアナログ人間まるだしだ。
───誰一人として終点の見えないこの人生。悪くすると二、三分後に死ぬかも知れぬこの人生。死んだらお終い。そうだ、人生は腕時計じゃないんだ。止まっても電池を入れ替えればまた動き出すわけではないんだ。人生は有限。しかも過ぎた時間は巻き戻せない。だったらもう彼女に電話しなくっちゃね。ホント、ぐずぐずしてる暇はない。そもそもここに何しに入ったか忘れたのか。早くも認知症かよ。「置いたはずだがここにない。忘れたときは元の場所へ」ってか! おいおい、僕はボケ老人か。アホらし、元の場所に戻って、早く電話しなきゃ。
赤井君は差し迫った気持ちで、内ポケットの彼女のスマホを手で確かめる。
───しかし電話するといっても、もし彼女が不倫をしようとしていたらどうなるんだろう。ホテルにでも誘われて事を起こしてしまったら。不義密通は江戸時代なら死罪だぞ。
ま、いいか。いまは江戸時代じゃないし。どうせ向こうにとっちゃ摘み食いなんだ。黙ってれば分かんないか。いやいや、ちゃんと誘いを断って箱村さんにそれとなく伝えないと。それが大人の流儀というものだ。
あれやこれや想像しては気をもむ赤井君。ホバリングしたままだ。君の脳ミソは大腸なのか。いつまで善玉菌と悪玉菌がせめぎ合っているんだ。あれこれ考えてはボソボソ独り言をいうぐらいなら、さっさと彼女に電話してスマホにボソボソと語りかけたらよさそうなものを。さっきから身動き取れないのはどうしてだ。君は電信柱にからまった凧か。困ったもんである。
そのとき彼女のスマホに着信音が。心の小箱の中で鈴が鳴なった。褐色に枯れかけた気分から彼は一気に跳ね起きる。優柔不断に先延ばしばかりしているからだ。
───しまった、ついに痺れを切らして向こうから掛けてきたか。
「もしもし」
「あ、箱村さん。この前はお世話になりました。◎×◇◇商事の花江です。早速ですが例の契約の件なんですけども、会社に直接かけるのもナンだと思ったもんですから携帯のほうに───」
「ちょ、ちょっとお間違えになっているようです。わたくし箱村ではございません」
「あれ? 男の声だ。すみません、こりゃ失礼しました。変だなぁ」
男は電話を切った。
───花江? なんだお前は。これまで一度も読んだことのない文脈で電話してくんなよ、オッサン。びっくりするじゃないか。またすぐ掛かってくるに違いない。着信音が妄想の酔い覚ましになってくれたのはいいが、それにしても早く彼女に掛けないと。
赤井君はスマホにふりまわされている。はらはらドキドキ、本来スマホを操るべき主人がスマホの奴隷になっている。箱村の言ったとおりだ。スマホを使うどころかスマホに使われている。
〈現代人は電波の糸にぐるぐる巻きにされている。君は現代には向いてない。糸車の嘆きが聞こえてくる。昔は家の暖房器具は炬燵ぐらいしかなかった。だけど心は今と昔、どっちが温かいのかな? 君はあの世代に生まれるべきだったね〉
そうこうしている間にも文字盤の針が時を刻んでいく。揺れる心の天秤にどうにか理性の分銅をのせ、バランスをとろうとする赤井君である。
電話してみると「おかけになった電話番号は現在使われておりません」とアナウンスが聞こえてきたら笑うだろうな。
緊張をほぐすために冗談を呟いたが、いよいよ切羽詰まった彼にはあまり効果はないようだ。
この期に及んでも苛まれる赤井君。頭のなかでは神と悪魔が言い争っている。
「これは不倫じゃないか、そんなことしていいのか」‥‥‥「いやいや単なる彼女のつまみ食いだ、たいしたことじゃない」‥‥‥と、いつまで経っても堂々巡りが終わらない。さっさと踏ん切りつけろ、とドヤしたくなる。
とうとう赤井君は石川啄木ばりにじっと手を見だした。いくら何でもそれはないだろう。土壇場で何の騒ぎであろうか。手の平に自分の影が吸い込まれていくのを哲学的に見届けたいのか。それとももっと安易に、恋愛線でも見てるのだろうか。手の中に人生があるのかい? 手の平の線で運命が決まるなら誰も苦労はしないだろうに。
彼はやることなすこと、いつも空回りだ。小説にしても女にしても、鳴りそうでなかなか鳴らせない指笛である。小説はついに鳴らなかった。これからもずっと鳴るまい。女だってそうだろう。大方の察する通り、こんな煮え切らない性格ではうまくいくはずがないのである。
再びスマホを手にする赤井君。───かの乙姫は、いかでかこの玉手箱を土産に渡しけむ。直接言えばいいものを。こんなもの、自分の正体を知らされるようで、フタを開けるのが怖いじゃないか。フタを開けたらアッという間に古稀のお爺さんってか? ま、それもありか、物語なら。
〈赤井君、それは物語ならずとも大いにありだ〉
砂時計の落ちゆく砂。自分に残された時間が見える。切迫感に耐えかね、ついに赤井君は腹をくくった。腰の重い彼もようよう踏ん切りをつけたようだ。スマホを持つ手が震えている。
君の灰に雨の雫の炎を落とせ
跳躍するのをやめた波止場の霧のように
頭の中に無意識的に言葉が流れる。まったく意味をなしていない言葉の羅列。詩のフレーズなのか、ランダムに単語の記憶が蘇っただけなのかよく分からない。これもプレッシャーの仕業だろうか。
スマホに手の平の体温がつたわる。この熱量は果たして彼女のところまで届くものやら。しばし脈拍が整うのを待ってから彼はやっと電話した。いまだ慣れないタッチパネルの感触。どういうわけか液晶画面に重なって黒電話のダイヤルを回している指先の動きが見える。妙な感じだ。ダイヤルを回すなんて、それっていつの時代の記憶のスクリーンか。
先方が出るまでの短いはずの時間が、変に長く感じられる。壊れかけ中古パソコンの立ち上がりを待つかのようだ。緊張のせいだろうか。氷柱の滴りと滴りの合間に流れる、凝縮された時間がここにある。なんとなく今、あの世に電話している気がしてきた。あの世に電話をかけたんじゃ、もしかして脈はないかもね(w)。
「はい、〇▼×◇保険株式会社営業部、蛍石です」
「わたくし赤井というものですが、箱村さんにお取次ぎいただきたいのですが」
「部長の箱村ですね、少々お待ち下さい」
「いえ違います、女性の方です」
「うちには箱村は一人しかおりません。それに女性ですし」
「若い方ですよ」
「若くはありませんが‥‥‥‥どうしましょうか‥‥‥一応お回しします」
しばらくして、
「わたしよ」
受話器の向こう側に彼女の顔が見えた。
「この電話、営業部直通だったんですよね。大胆なことするなあ。スマホ持ってないんですか? あ、スマホは僕が持ってるんだった」
「いいわよ、個室だから」
「えっ、個室!? 部長さんって本当だったんだ」
「そうよ、歳相応に」
「歳?」
「いえいえ、そうじゃないの、そうじゃないの。頑張ったからかな、旦那がアレだから。電話してくれないから、メール送ったんだけど」
「メール? アッ‥‥‥それは‥‥‥そのお~」
「いいの、いいの。メールといってもよく分かんないんでしょ? 旦那から聞いた。それより今度二人っきりで逢わない?」
「逢うって、何か困ったことでも‥‥‥」
「逢いたいの」
「逢いたいって、何処で逢うんですか」
「勝山公園で今週の土曜日の18時に。アナタ、勝山公園って知ってるわよね」
「知ってますよ。宿無しの時あそこのベンチで寝てましたから(『女と』)」
「来ないとそのままずっと待ってるわよ。スマホ返してもらわないと仕事で困るの。いい? じゃ、約束あるから切るわね」
「あ、花江という方から今さっき‥‥‥‥」
「花江さんね、心配しないで。こっちからすぐ掛けるから」
「それで‥‥‥ご主人、このことを知ってるんですか」
野暮なことを訊いてしまった。忙しいのだろう、彼女はもう電話を切っている。置き去りにされた赤井君。終電は行ってしまった。駅のホームにぽつねんと佇む面持ちだ。
テーブルには飲みかけのコーヒーカップが置かれている。いつの間に運ばれ、いつそれを飲んだのだろう。記憶がぬけ落ちている。コーヒーカップの底には淡い憂鬱が浮かんでいた。

(50)
仕事場のドアを開けると、花菱が寝転がっていた。アイスクリームのようにソファの上に溶けている。ドアを開けるたび社長は判で押すがごとくこの態勢、完全にトド爺さんになっていた。太っとい腹巻きをしたような脂肪が上下に浮き沈みしている。いや、腹巻きというよりはお相撲さんの褌まわしだな。アンタは恵方巻か!
トランポリンのようによく弾みそうな太鼓腹、いったい中に何が入っているんだろうか。おそらく怠惰と倦怠と退屈がいっぱい詰まっているんだろうね。
小指の先に童話の国の三角形の城がある。城の門を玩具の兵士が出たり入ったり───その小刻みな周期は、呼吸と共にヒクヒク動く花菱の小鼻。城ではまさに小人の王様の午後のお昼寝が始まろうとしていた‥‥‥。
おいおい、まだ朝じゃないか。なんで寝るんだ。それにこの人、王様でも小人でもないし。確かに僕に似たホビホビではあるが、小人扱いするほどじゃない。でぶ、ちび、はげ──三拍子そろった、ただのお爺ちゃんである。物語とはいえ、そもそも王様にしてしまう設定が間違っている。
さて、もう一度いうけど何で朝っぱらから寝るの? 背広を着ているところからすると多分一度は起きたはずなんだが。
花菱は相も変わらず寝てばっかりいる。出社すれば寝てる、退社すればまた寝てる(-_-)zzz。寝る子は育つ、ならぬ寝る子は太るだ。花菱を見ていると、人は余分に眠るほど健康で長生きするのではないかと思えてくる。とりあえず、眠る時間もないあくせくした人生より、眠りたいだけ眠れるこんな呑気な人生のほうが幸せであることだけは間違いないが。
「ふわぁぁぁ〜」
寝ボケまなこが開いた。お目覚めらしい。ずんぐりとした体がむくりと起き上がり、ソファーにふんぞり返る。寝ぼけているのかもしれないが、なんとなく偉そうだ。パラドックスだな。偉そうにするほど偉く見えない。偉そうにするほど馬鹿に見える。
僕を見るなり顔をほころばせ、笑みをこぼした。これも例のごとくだ。
「おお、来たんか、来たんか」
社員だから来るに決まってるじゃないか。こんな気楽な仕事なのに、誰が出社拒否する。
「赤井君、まあこっちで話でもしようや」
朝一番からこれだ。箱村がいないとき彼はいつもこんな調子。これからひとしきり、句読点なしの独演会に付き合わされることになる。箱村がいなければいないで状況は同じことだ。やれまあ、今日も長丁場だ。一難去ってまた一難、まさに「前門の虎、後門の狼」。いや後門の豚か。
僕を自分の孫かなんかと勘違いしているのではないのだろうか。優しく接してくれるのは有り難いのだが、やたら馴れ馴れしく纏わりついてくるのには閉口する。
いつもどおり煙が蛇のトグロをまいて宙を漂っていて、灰皿には吸殻があふれんばかりに‥‥‥と、思いきや、なんと灰皿がない! 赤井君は蛍光灯のように目をしばたたく。
灰皿がない! どういう風の吹き回しだ。こんな妙な風の吹き回しなら、煙が舞い舞いコンコンしていないのも無理はない。
「どうしちゃったんですか? 今日、煙草は?」
「うん、やめた。ワシの芸術性と文才を引き継げる才能が現れたもんでな。もうちょっと長生きしても悪くないと思ったんだ」
「え? 誰ですか、それ。箱村さん?」
「何でここに独活の大木、あのお祭り野郎が出てくるんだ。君だよ、君。赤井君だよ。この前、箱村といっしょに録音したデータファイルを聞いた。そうそう、そうだよ。ワシがズル休みしたときのだ」
悪びれずあっさりズル休みを認めている。自らバラすとは大胆不敵だ。だけど経営者だから別にいいのか。小学生や平社員じゃないもんな。
「君のおかげでヤル気が出てきたわい。歳はくったが、ワシャまだまだやれる。バイデン大統領じゃないんだ、タオルを投げ入れるなよ。子供が家に帰ったあとも公園のブランコはしばらく揺れているんだ───お、これ、ポエジーじゃないか。今日も冴え冴えじゃわい」
花菱がはしゃぎ出した。いつもの調子だ。
「だいたい最近の若いのが書く代物は稚拙で凡庸で‥‥もう読むに堪えんだろう。あんなのは、まだ商品になっていない未完成品だ。いっぱい赤ペンをいれてやりたくなる」
突然話がとび、花菱のいつもの若手作家腐しが始まったかと辟易しそうになると、
「若者には失望してたんだが、君が現れた。あれはなかなかのもんだぞよ。近頃の若いのは安っぽくて百均ばっかしだと思っておったら、手に取れば君だけは三百円商品だった。変わり種、見っけだ。意外性じゃよ」
百円と三百円なら大して変わらないじゃないか。でも話はつながっていたようだ。
「え? あんなのがですか?」
「そうだ。もっとワシの審美眼、文学観を信頼したまえ」
「はあ」
審美眼、文学観? 御大層に。ただの好き嫌いでっしゃろ。
「若いのにもごくごく稀に逸材がいるもんだ。しかもまだまだ伸び代がある」
「伸び代があるということは、まだ伸びてないってことですよね」
「何がだ」
「身長が」
花菱はキョトンとしている。爆死だ。
褒められて嬉しくない者はいないが、ちょっと花菱の買いかぶりは度を越している。たまたま彼の文学の趣味に合っただけのことだろう。どう考えても言われるほどの才能はないので、最近では恐縮ぎみの赤井君である。
「君の書く小説の文体も奇妙奇天烈でなかなかいい。純文学なら純文学、時代小説なら時代小説、ライトノベルならライトノベルと、いろいろジャンルは違えども皆それぞれ似たような文章スタイルだ。内容は別として、ぜんぶ整った同じ感じの文章じゃ面白くないだろう。みんな型から入る優等生たちじゃな。あれじゃ、コクのない脱脂粉乳だ。君みたいにイカれた奴が出てこなくちゃ」
「作風があんな風だと読むのしんどいんじゃないすか。とにかく必死こいて憑かれたように書き殴るだけ。悪戦苦闘の末にやっと針に糸を通した───そんな感じの仕上がりでしょう。人が一日ですむものを十日かけて書いてるんですから」
「アホ言え、それでいいんじゃよ。なんも分かっちゃおらんな。オーケストラで一人、他人と全然違う珍妙な音をとつぜん鳴らすからいいんだ。ドリフのコント、ずっこけ一本だ。不協和音、大いに結構。国語の答案を書いてるんじゃないんだぞ。読み手に“なんじゃ、これは”と言わせろ。それがアートだ。“なんじゃ、こりゃ”ったって『太陽にほえろ!』の松田優作じゃないぞ。太郎だ、岡本太郎を見習え。芸術は爆発だ! 狂いに狂った言葉で埋め尽くせ!」
花菱に言わせれば、何やらわけの解らぬ狂った作品がアートらしい。それより今、アンタに必要なのはアートネイチャーでっしゃろ。
彼が作品を褒めるのは、あるいは僕を若き日の自分と重ね合わせているからかもしれない。だから愛着がわく。ああワシにもコイツみたいに未熟な時期があったんだなぁ、という感覚だ。花菱という箱のフタを開けると、あらまあ僕という箱が入っている。なるほど容れ物として考えれば、彼は太っているのでそっくりそのまま僕が入るというわけだ。大は小を兼ねるだ。あれ、この諺の使い方まちがってるかな? 箱の中にまた箱が‥‥‥なんともかんとも、人間マトリョーシカなんか~い。😥
「いつも褒めていただけるのは感謝感激炭火珈琲なんですけど、いつも社長が若者の作品を腐すのは気になります。僕のだけ褒めてもらって」
「どういう意味かね。上から目線の口ぶりが気に食わんとでもいうのか」
「いえいえ、そんなつもりは毛頭あるません。ただ叩くなら最初から最後まで読んでみてからにしてもよろしいかと」
「だから、わざわざ“稚拙過ぎて読むに堪えん”と前置きしてるだろう。聴いてなかったのか」
さすがに“稚拙過ぎ”はあんまりだ。若者を十把ひとからげに束ねて考えている。若者という言葉は普通名詞であって、固有名詞じゃないだろう。若者といっても色々だ。何かと言えば「若者」にあえてアクセントを打ち、「作品が幼稚だ、幼稚だ」と痛烈に批判する。何度きいても、いつも同じ腐し文句の繰り返し。馬鹿の一つ覚え。アンタは選挙カーか。
前言撤回。やっぱし彼は王様───いわゆる裸の王様ってやつだ。世間の見方とまったくズレていて、そのことに気づいていない。バカ殿さまは歳くうほどに恥がなくなり、より大胆に衣服を脱ぎ捨てる。腰元たちは大迷惑。僕だってアンタのストリップショーは見たくない。ウエッ、だ。
花菱が若者の作品を金玉‥‥‥じゃなかった、槍玉に挙げるのは毎度のことだ。だから愚痴や非難は一括りにして忘却のゴミ箱に捨てることにしている。ガラクタでも少しは中身を吟味して分別収集したほうがいいのかもしれないが、どうせ廃棄するものなら無駄な労は惜しみたい。
とはいえ赤井君は痩せても枯れても(見るからに?)若者の一人だ。ずっと花菱の若者腐しに対して、不満が心の底にわだかまっている。家臣として忠言すべきだろうが、「忠言耳に逆らう」との慣用句もある。躊躇されるところだ。クビにされたらたまらないもんな。
試しに作品の内容についてちょこちょこと突っついてみれば、ついぞ最後まで読んだ形跡が見えてこない。読まずに批判しているのは確かなようだ。
かつて標榜した前衛文学も、いかんせん時の流れに後衛に堕してしまった。ノスタルジーに浸るのもいいが、若かりし頃はアバンギャルド気取りだったであろう花菱も、最近ではむしろ古典に近づきつつあるのではないのか。彼は化石化している。脳ミソが経年劣化で錆ついているのだ。もはや昭和の文芸隆盛期の残滓でしかない。彼の手にかかれば、たとえいま第一線で活躍する売れっ子作家の作品であろうとも、ただ若いというだけで小学生の作文に毛が生えた程度の代物と見なされ、お子ちゃまランチ扱いされてしまうことであろう。
若者の優れた作品は一杯ある。これは小説だけに限らない。人類は進化するのだ。このご時世だけに、いくらアドバルーンをあげようが、文学はいずれ落日を見る定めにあるのかもしれない。だが例えば、たまたまユーチューブなどのネット世界を覗いただけでも、「これは」と唸らせる若者コンテンツがうじゃうじゃ出てくる。穿った見方をすれば、僕のようにたまに脳に異常が生ずる変な若者であったとしても、若くさえあれば、それも進化の次の段階と言えないこともない。決して絶滅危惧種の烙印を押すにあたらないのだ。
彼は遅れている。今やLINEのやりとりに句点を打つだけでマルハラ呼ばわりされる時代だ。今どき若者叩きなど時代錯誤も甚だしい。月日が知らぬ間に経ち、かつて栄えた町がさびれ、気づけば周りに人家のない一軒屋に住んでいる。それが花菱である。
花菱が大昔、どういう形で出版業界に関わっていたかは知らない。なるほど分母の大きかった昭和や平成前半なら、若者の作品を厳しく論評して世代間の対立を煽ることに、ある程度の商業的メリットが期待できたであろう。だが今はむしろ逆効果だ。大衆は素直に書評を受け入れ、専門家が腐すような本なら敢えて読むまい、となる。令和はタイパ、コスパの時代。誰しも時間と労力の無駄は避ける。令和はあることないことベタ褒めして販売部数を伸ばす時代だ。上っていくときと下っていくときの違いである。
「それって変じゃないですか」
思わずもらしてしまった。
「どこが変なんだ! 偉そうに。ちょっと前に産湯を使った小便小僧のくせして!」と花菱。
目がすわっている。語気の強さから花菱が臍を曲げてしまったことが分かった。よほど癇に障ったらしい。やかん頭から湯気がのぼりそうだ。眉をひそめ、ブスッとした表情、しばし。
しまった、余計なことを言うんじゃなかった。怒らしてしまったようだ。
赤井君は戸惑って言葉をさがす。
「いえ、よく考えてみればやっぱり変じゃないです。どうも認識が薄っぺらすぎたようで」
と、矢も楯もたまらずフォローしたものの、時すでに遅し。いくら本音をオブラートで包もうが、ウインドウズは閉じたままだ。赤井君の揉み手から焦りの砂が零れ落ちる。
この人は気に入らない発言があると、子供みたいにすぐ膨れてしまう。トラフグだ。しばらく経つと自分が膨れていたことも忘れてしまうので、ここはいったん譲歩して待つことにしよう。
赤井君は首をひねる。花菱はどうしてこんなに頑ななのか。この令和には昭和のあの反骨的な若者はいないのだ。誰一人、学園紛争を起こそうとする若者はいない。今の若者はかつてと違ってずっとシニカルでずっとデリケート。子供の釘打ちと同じで叩けば叩くほど曲がってしまう。この令和の時代に世代間でぶつかり合っても化学変化は期待できない。そのことを分かっているんだろうか。
令和と昭和では、若者の意識が変わっただけでなく、社会そのものが変わっている。花菱の若かりし頃に、スマホ画面を指で叩けば何でも手に入る時代が到来すると誰が予想しえただろう。花菱はITなき古き良き時代に今なお生きている。主観と客観がズレまくりだ。ありもしないサッカーボールを蹴ろうとして自ら転んでいる。
彼が若者作品を無茶苦茶いうのは、要するにルサンチマンを解消したいだけなのだろう。若さへの嫉妬か? 表舞台に出た人達への嫉妬か? そこいらが彼の痛点なのではないだろうか。過去───おそらく彼が出版とやらに関わっていたであろう日々の傷跡がうずくのだ。
もしや彼は僕や箱村と同じで、若き頃プロの作家になりたかったのではあるまいか。あんな歳になってしまえば夢はほぼ潰えたに等しい。ただでさえ年寄りを締め出すシステムがこっそりと構築されていく令和の世の中だ。そう思うと何だかこの老人が哀れで気の毒にすら見えてくる。
けれども、過去の古傷が痛むとははいえ、そんなに意固地になっていると、他人から学べなくなるので最終的に損することになるんじゃないのか。感情に押し流されず、もっと功利的になったらいいのに。過去にこだわるには、人生はあまりにも儚い。
刻々と近づく死を前にすれば、気をつけていないと人はこんなふうになってしまうんだな───と、ちゃっかり他山の石にしてしまう赤井君である。
ややあって、ようよう花菱が不満げに口を開く。
「そうだろう、変じゃなかろう。若いうちなら力まかせに手当たり次第読みまくりゃいいが、歳くってくるにつれて読書についやせる時間は限られてくるんだ。読み出してもすぐに眠くなっちまうんだよ。いいか、年寄りは本があれば羊はいらんのじゃわい」
あん、どういうこと? ‥‥‥あ、そうかそうか、そういうことか。しょーもな。
「行動がのろくて寝てばっかりいるワシら年寄り連中はどうしたらいいちゅうんじゃい。ノロノロ亀さんに月に何百冊も読めって言うのか。読むものを選ばにゃいかんじゃろうが」🐢
なるほど理屈は一応とおっている。けど、いくらスローモーだからといって、読まずして決めつけるといった食わず嫌いは、やはりいただけない。読み終えていないのならコメントするな。それってフェアじゃないだろう。普段はズボンやパンツを裏返しに穿いても気づかないほどルーズなくせに、こと文学に関してだけは細かくて気難し屋だから困る。
ん? 待って。フェアじゃない? もとより小説自体がそんなにフェアなもんじゃない、巡り合せと運じゃないか。花菱の発言がそれを踏まえてのことだとすれば、ごもっとも。これは小説に限らず、世の中の半分がそうだ。
老年になって判断の狂いやミスが多くなり才能が枯渇していくのは、劣化というよりは変化ととらえるべきだ。程度の差こそあれ全員そうなるからである。いずれそうなるのなら、劣化というより変化ととらえる方がメンタル的によいではないか。肉体が衰えるのと同様に脳ミソも衰える。当然の成り行きだ。しかし狂人にあなたは狂人だと言っても信じないように、自分ではそう思わないことの方が多い。花菱もその一人なのだろう。歳をとったら才能が枯れてヘマばかりするのが、むしろ自然であると思うべきなのだ。そのほうが世代間の無駄な軋轢も減り、物事に柔軟に対応できることだろう。
まだまだ先の話だが、赤井君は将来そういう爺さんになることを欲した。ヨボヨボでノロノロ、そしてボケッ~として失敗ばかり、そういうのを一流の後期高齢者というんだ。花菱社長、世間様に対して頑固に意地をはってるようじゃ、まだ二流以下ですぞ。人生はまっすぐ続く、遠く地平線に呑み込まれる一本道だ。一方通行で決して過去へ後戻りはできない。ならば晩年には、せめて来し方の直線美を振り返って味わうぐらいの余裕はほしいものだ。
そんなことをよくよく惟みるに、若者の作品をあまり読んでいないことは、花菱当人にとってもよいことなのだと考えを改めたくなった。読めば嫌でも現実を思い知らされることになるからである。
昭和は遠くなりにけり。令和もいずれそうなる。いま若者である僕も、いずれ未来の花菱になる。この世は諸行無常。変わらないものはないということだけが、変わらない真実だ。
「そこで花菱社長、今日はちょっと折り入って特別なお話が」
そうだ赤井君、ぼやぼやしている場合ではないだろう。一番にアイツのことを確かめねばならないじゃないか。アイツが花菱の子供かどうか。小説論や世代論など今はお呼びでない。
「ふ~む。そうか、住まいのことか。住む場所を世話してほしいんだな。あの狭っくるしい倉庫じゃあんまりだな。ふむふむ、そうだと思った。君の思ってることは手に取るように分かるんだわ。よし、このフロアーの部屋の幾つかはワシの名義になってるから、その一つを君に貸してやろう。もちろんロハでだ。どうだ、悪い話じゃあるまい」
なんで住む場所の話になるんだ。とはいえ、どうやらいつもの心優しい、世話好きの花菱に戻ってくれたようではある。潮目が変わり、ウインドウズは開いてくれるかな?
「いえ、どうせ丸まって眠るだけですから、あの倉庫で十分です。狭い場所にいつも体を曲げて寝てるから、まるで蠍座になった気分ですよ。寝る場所があるだけ有り難い話です。そっと起きそっと出かけてそっと寝る───よくあるお笑い川柳の世界ですかねぇ」
「こらこら、無断で他人の川柳を使い回すな。笑いをとりたかったらオリジナルで勝負せんかい。しかしなんだな、君は見かけによらず霊格が高いな」
「え、それはどうしてなんでしょうか」
「霊格が高い人ほど自分は神様、仏様によく処遇されてると感じるからじゃ。外からは何て可哀想な環境にいる奴だと思われていたとしてもだ。つまり自分は幸運だと勘違いで感謝するわけだ。霊格の高い人はある意味、めでたいんじゃな。他方、神様仏様の処遇は不公平だと感じている者も一杯いる。たいして不運でもないのに、自分だけ不運なのは不当だと怒り狂うんじゃよ。人の運不運なんかにそれほど大きな差はないのにな。おそらくだが、それでも幸運な人と不運な人に分れるとすればだな、感謝するか恨むかの差じゃわい。神様仏様の身になってみれば、自分に感謝してくれる人を好くか、それとも恨んで怒り狂う人を好くか。自明の理じゃわい、そう思わんか」
これはストンと落ちる。誰かの受け売りかもしれないが、今日はじめて彼の口からまともな話を聞いた。
「そうかぁ、納得です。僕も数年前まで怒り狂う側の人間でしたから」
「それっていつのことだね」
「学業そっちのけで、学生アパートにこもりっきりで小説を書いては、出せども出せどもぜんぶ一次で落ち続けていた頃です(『女と』)」
「ほう、それが今は感謝の日々とは。どげんかしたとか?」
「ある女の人と一時くらしてから、若干かわったみたいです」
「まあ、君もおぼこい顔して色々あったんだな。敢えて根掘り葉掘り聞かんが。じゃが今だって、あんな狭くて暗いとこでよく生きていけるわい。あげな生活で本当にいいのか? 感心する」
「いいんです、今のままで。学生アパートを追い出されたときは完全に野良犬でしたけど、今はかろうじて犬小屋に住まわせてもらってます。余計な一言ですが、今の生活はお御籤で言ったら小吉ですかね。これからも小吉を持続して、少ない喜びでも用心してこぼさないように生きていきますよ。ここ、地震大国・日本でしょ? 祖国は取っ替えられない。人生の活断層上に寝そべるのも悪くないと」
「ん? 最後のはギャグなのか。それともエスプリを効かしたつもりなのか。活断層? しょーもな。格好つけてあまり練りすぎると、かえって面白くなくなるぞ。そこまでして“いいね!”がほしいのかぁ。そんなに“いいね!”がほしけりゃ、自分で自分の作品にカチッとやりゃいいじゃないか。たぶんバレて笑われるだろうけどな。だいたい“いいね!”を押す奴って誰なんだ。文芸・出版関係の人なのかね。あるいは読むことを生業にしている人なんかい。それともただの機械人間かぁ。何割の人が君のアクの強い作品を最後まで読んでくれると言うんだ。誰もユーチューブみたいに気前よく押してくれるもんか。ワシのような目利きに巡り会うのは針の穴を通るより難しいんだ。他人の目なんか気にせず、たんたんと書きたいものを書きたいように書きゃいいだけだろう。いったい君は何に操られようとしておるんじゃ。幼いころ不遇だったからといって、承認欲求のお化けになんかなるな。もっとアホになれ。このアホ!」
あら、アホになれとアホに言っている。二重否定で僕は利口なのか? 持ち上げられたと思ったら今度は落とされた。アンタはスキャンダル芸能レポーターなのか。なんでここで“いいね!”などというピント外れの話が出てくるんだ。一言も“いいね!”がほしいなんていってないのに。だいたいアンタから“いいね!”をもらってもねぇ。美女からもらうんなら別だけど。
花菱は何に怒っているのか、説教調で話しはじめている。この気分屋には参った。おのれ、プンスカじじい。どこで地雷を踏んじまったんだろう。
「よしんば何かの偶然で世の耳目をちょっと引くことになったとしても、そんなのは一時期だ。長くは続かないんだ。黒板の落書きと同じで昼休みが終われば、すぐ消される。それとも何か、君は公衆便所の落書きみたいにしぶとく生き恥を晒し続けますかな。恥を知れ、恥を!」
恥を晒して恥を知れとは? 自ら晒すぐらいだから知らないはずないだろう。たかが活断層のジョークがダダ滑りだっただけじゃんか。好きな女の娘を笑わせるためならいくらでもハッスルするが、相手がアンタじゃ話にならない。悪ふざけなのか真剣なのか、何でこんなことに辛子をきかす。呆れて物が言えない。そんなにスパイシーになってどうするってんだ。インドカレーか。
火災は鎮まったものの、花菱には怒りの燃えカスがまだ残っているらしい。臍はまだ曲がったままだった。ハゲているので旋毛を曲げたかどうかは定かではないが(w)。
「なんで君は商売人の作った見え透いた仕掛けにひっかかって、いつも操られるんだ。ただ椅子取りゲームに負けただけじゃないか。君の実力とは無関係だ。椅子取りゲームは図太くズルして人を押しのけないと座れないんだよ。じゃが、君はそんな気ぜわしい人生でいいのか。椅子取りゲームなんてやめとけ。そのうち椅子取りゲームにとりつかれ、馬鹿チョン人生を送らされる羽目になるぞ。イチ抜けた~ぁ、だ。賢けりゃ、一回経験しただけでそんなことぐらい気づいて、努めて距離を置こうとする。君には哲学というものがないのか。少しでも思索する力があれば、人間全員がエゴの塊だというのは自明じゃ。それをしっかり感じとりゃ、がむしゃらに椅子取りゲームにしがみつくような恥さらしには耐えられなくなるはずなんじゃがな。君はどこまで薄ら馬鹿なんだ。なんで性懲りもなく何度も出すのかね。君は君だけのヒーローでありさえすればいいんだろう」
「でも立候補しないことには落選すらしないでしょう」
「君は小泉構文のセクシー進次郎なのか。どこがセクシーだ、短足のくせして。総裁選に立候補しても誰の目にもとまらんよ。お騒がせの泡沫候補にもなれん。推薦人はワシと箱村の二人しかおらんじゃないか」
「え? ど、どういう意味ですか?」
「歌唱力だけでは歌手デビューはできん。演技力だけでは役者デビューはできん。華がいるんだよ、華が。短足の鼻たれ小僧に華があるのか? 君なんかアレじゃよ、何かの賞でも取ろうものなら、あまりの額縁の立派さに圧倒されて、次の絵が描けなくなる口じゃろう」
「は?」
「世の中には二種類の人間がおるんじゃ。騙す者と騙されるもの、盗む者と盗まれる者、奪う者と奪われる者だ。どうも君は自分が後者の人間だということを理解しておらんようだな」
「おぼろげながら理解しているつもりですが。むしろそれでいいとすら思っています」
「今の君には椅子取りゲームよりもっと大事なことがあるだろう。死ぬと分かっているのに、どうしてこの人生の砂漠で苦しみ続けなければならないのか。さらに言えば必ず死ぬという、その死の向こう側には一体何があるのか。君の小説の中心テーマに答えを出すという大問題が残っておるじゃないか。解決できたのか。君が生きてる間に解決できそうなのか。誰かサンの話を聞いて分かったつもりになった、では済まんぞ。我が身をもって真実を体得せんことには、この大問題を解決したことにはならん。“賞が欲しい、賞が欲しい”と言っとるようじゃ、まだ糸口も見つかっとらんじゃろう。“賞をくれ”といくらほざこうが、君なんか誰にもすくい上げられず海までドンブラコと流れていく桃だ。海で死ぬまでぷかぷか浮かんどけ。鬼退治なんてできっこないんだ。仏様の前でこれ以上、醜態をさらすな。夢は目覚めれば忘れる。そして眠ればまた新しい夢を見る。そして眠って忘れて、眠って忘れて‥‥‥月の満ち欠けと同じで、死ぬまで繰り返す。いま君の見ているのはそんな、霞ゆく夢なんじゃよ。何も解決しちゃおらん」
今度は何を言い出した。う~ん、頭ん中がとっ散らかる。次から次へと話題が変わるので追いつけない。なんとなく僕の小説内容と出版社への応募のことを言っているのは分かるが、抽象的すぎてサッパリだ。
まだ潤滑油が足りず、開けようとしたらウインドウズがギイギイ鳴りだしてしまった。そのうち降ってもいないのに雨戸を閉められるのではないでしょ~~か。
いや待って。これって最初からこれまでずっと、つまり僕がこの部屋のドアを開けた時から今までずっと“小説”で話はつながってるわけ? であれば、それに気づかない僕がやっぱアホってこと?
何はともあれ、こう自信たっぷりにスカタンを言われると、思わず説得されそうになる。何をどう説得されたのかチンプンカンプンではあるが。
言いよどんで殊勝な顔を取り繕っていると、反省していると取り違えたのか、一拍おいて花菱が口をひらく。珍しく抑揚をおさえた物静かな語り口だ。
「おっと、なにも君を責めてるわけじゃないぞ。気に病むな。ちょっと指摘が辛辣過ぎましたかな。ワシも反省じゃ。さて、小説の話はこれぐらいにするか、君も退屈したじゃろうて」
うん、この言い回し。こういうちょっとしたところに彼の人柄がにじみ出る。酸いも甘いも噛み分けて、だてに歳はとっていない。情に通じている。うんうん、悪くない。好きだな、さり気ない優しさというか、目配りがある。ときおり花菱は思いやりをそっと花瓶に活けることがある。これ見よがしに花束にして押しつけたりしない。
「それにしてもな〜んだ、塒じゃなかったのか。塒だと思ったんだけどなぁ。しかし読みが外れるとは焼きが回ったかな、ワシとしたことが。だったら何だ。そうか、箱村がワシらの仲に楔を打ち込もうと画策してるんだな。見え透いた謀をするなんて、けしからん奴だ」
褒めた途端にこれだ。ひどい早とちりである。どうしてそんな突飛な話になるんだろう。それに先走りすぎるし。年寄りだから先が短いからかな。
「いえ、そういうんじゃなくて‥‥‥」
「そういんじゃなかったら、こういうんだろう。君は人がいいから、先輩の悪だくみを暴露するのが辛い。辛くて何も言えずにもじもじしている。心配はいらん。ぜんぶお見通しだ。ワシは人感センサー付き照明具だ。言わなくてもピンとくる。君が真っ暗な通路を通るときは、そっと脇から優しく照らしてあげよう。ああポエジーだ。今日もワシは切れ切れだな。それにしても箱村の奴ときたら油断も隙もありゃしない」
いつ箱村の造反劇から離れるんだ。ひどい濡れ衣である。独りよがりの暴走運転を続ける花菱。いったいこの人は何を考えているんだろう。免許返納してほしい。
「いえいえ、そういうことじゃなくて」
「そういうことでないなら、どういうことかね」
「実は花菱社長のお子さんのことで」
「君はアンポンタンか。いつか子供はできなかったって話しただろ。あれ? まだこれ、言ってなかったかな。忘れちゃったぞ。尋ねられたら話すだろうが、君から尋ねられたかな。それも忘れちまった。頭脳明晰なワシとしたことが。まあいい、子供の話はいい。アホ箱村の話をしようや。アイツの悪口で楽しもうや。子供の話をしたけりゃ後にしろ。嫌な話は後回しだ。だいたいアイツときたら‥‥‥」
赤井君はげんなりする。半ば予想はしていたものの、てんでお話にならない。問答無用だ。遠山の金さんよろしく、なかなか「これにて一件落着」とはいかないもんだ。本題を切り出す前に、ひとまず彼のペースに合わせることにしよう。
それにしても、これだけよくしてもらっているにも拘わらず、どうして花菱に苛立ちや疎ましさを感じてしまうのだろうか。なぜだか知らないが、事あるごとに感情の複雑な幾何学模様が僕を苛立たせる。思うに、これがまさしくいつか箱村が話していた「遺伝子に操られる」と言うことなのではないのだろうか。
確かそんな内容の話をグチャグチャ喋りまくっていたのは、彼の奥さんと三人で食事会をする道すがら、車の中でのことだ(霞ゆく夢の続きを〈4〉─33)。うろ覚えだが、「遺伝子に操られる」などという奇異な表現をしていたので記憶に残っている。
私たちは相手が赤ちゃんなら無条件に愛着を抱く。反面、「楢山節考」とまでは言わないが、老害という言葉が示すとおり自己主張の強い高齢者に対しては冷淡でやたら毛嫌いするところがある。もしかしたらこれも「遺伝子に操られる」ことの一つなのかもしれない。
赤ちゃんには未来があり、人類という種族保存に今後大いに貢献する。かたや年寄りにはその可能性がほぼない。人類繁栄にとっては邪魔者、ただの消えゆく個体にすぎない。若さに優しく老いに厳しい傾向は、あるいは先天的に遺伝子に組み込まれているものなのではないのか───そんな気がしてくる。用済みは早く消滅してくれたほうが人類全体の利益をはかれるからである。
乱暴な言い方だが、人類にとって重要なことは種の保存であって、個々人の幸不幸などどうでもいいのである。だから遺伝子レベルでは、個の幸福を犠牲にしても種の保存に貢献させようと仕向けるのだ。
いま自分が躍起になって求めているものは真に自分を幸せにするものだろうか。たんに遺伝子に操られて種の保存に奉仕させられているだけではないのか。そんなふうに真剣に問い詰めてみることはつくづく大事だと思う。理性を麻痺させ女にのぼせることなど遺伝子のよる個人操作の典型だ。男だけではない。女が金持ちで生活力のある強い男を打算で手に入れようとするのも、子孫を安全に未来に残すという点からは、これまた種族に個人が操られている例の一つと言えないこともない。
耳の痛い話である。いま僕も後々面倒になることを知りながら、箱村の奥さんにのぼせあがっているではないか。まあいいか、理屈と実際は違う。人は自分の感情や行動を論理立てて説明できないものだ。種族保存と自己保存がせめぎ合う矛盾した存在───それが人間というもんなんだろうな。
「なあ、赤井君、何か箱村の悪口はないのか。いつも金魚のフンで付いて回っているからあるだろう。ぶちまけてスカッとしようや」
花菱は僕が乗ってこないことに不満げだ。
「悪口ってことじゃないんすけど、箱村さんは“人は死んでも生きている”って言うんですよね。人は永遠に死なないって(霞ゆく夢の続きを〈4〉─28)。僕、分かんないんですよねえ。死んだら霊魂になって生き続けるってことを言いたいのかな。死後の世界ってあるのかなあ。死んでも生きてるなんて、死後そんなふうに脳をまるごとどこかにコピペできるもんなんでしょうか」
「ウンそれそれ。それをさっき指摘したんだ、君はボーッとしとったが。人生の大命題じゃよ。これを探求せずして何を探求するのか。“いいね!”押してもらう方法を探求するのか。アホちゃうか」
まだそこにこだわっている。しつこいな。こっちが「アホちゃうか」と言いたくなる。
「『死後の世界がない』という証明は悪魔の証明だ、ってよく言うだろう。無いことを証明するのはほぼ不可能だから、悪魔の証明ってな小洒落た言い方してるんじゃろうな。今は亡き安倍総理が予算委員会で野党から『悪いことした事実がないなら、総理自ら潔白を証明しろ』と詰め寄られたとき、『そんな悪魔の証明なんてできる訳ないじゃないか』と切り返していただろう。死んじゃったから褒めるわけじゃないが、鮮やかな返しだ。ま、赤井君はノンポリだから予算委員会なんて聴いてないか。ネットで審議中継やってるから今度見てみな。これはありきたりな話で面白くないかもしれんが、無いことを証明するのは悪魔の証明で、出来っこないんだな。この世に白いゴキブリはいないことを証明しろ、って言われたら世界中の何百億匹いるともしれないゴキブリ全部にあたって全部黒だってことを確認しなきゃなんない。宇宙人がいることを証明するなら宇宙人を連れてこりゃいいだけだが、逆に宇宙人がいないことの証明はほぼ不可能だ。無限の広さの宇宙を隅から隅まで総ざらいして、いないことを確かめなけりゃいかんだろう。そんなことできっこないじゃないか。だから学者然として『死後の世界なんてありません』って言ってる奴らはみんなイカサマ野郎だ。自分の情緒的な思い込みを、さも科学的であるがごとく装ってるに過ぎんよ。あいつらだって、証明できっこねえんだから。どうだ赤井君。滝壺の奥に悪魔の顔が浮かんだ気分じゃろう。暗くて顔が見えなきゃ、もっと照明を当てろ。悪魔の証明だけにな」
(-_-;)‥‥フウ、クダラナイ
「なるほど。だとすれば『神様なんていない』と言う人も、証明できないからペテン師か。ニーチェもペテン師か。ああ違う。『神は死んだ』んだから、生きていたときもあるのか。あれ? 神様って生きたり死んだりするもんなの?」
「なにアホなこと言うてまんねん。これとそれとは全然関係のない話だぞ。それにしても、あのノッポ、赤井君にも、あのいつ途切れるとも知れないクソ長話をしたのか。耳タコだ。アイツは絶対すべらない鉄板ネタだと信じ込んでんだ。何度も何度も、まったく‥‥‥‥‥ほとんど暗記しちまったよ。興奮して熱弁を振るうのはいいが、馬の小便をずっとひっ掛けられっぱなしの身にもなってみろ。困ったもんだ。アイツはかのモンテスキューの名言『人間は考えることが少なければ少ないほど余計にしゃべる』の典型だな。ワシは学があるから英語でも言えるぞ。The less men think‥‥‥‥」
「あ、英語はいいです、いいです‥‥‥」
「遠慮するな、君は外国語学部だから関心あるだろう。The less men think, the more they talk.だ。どうだ、驚いたか。発音もネイティブばりでバッチリだわい。ワシャ知識の宝庫じゃろが」
「あの、モンテスキューってフランスの人じゃありませんでしたっけ?」
「それがどうした、そんなの知らないぞ‥‥‥‥おい、そうだって。ホントだってば。ワシャ若い頃、確かに英語版のを読んだんだ。嘘じゃない、嘘じゃない。赤井君、そういうとこだぞ。君の人として至らないところは。細かいところをほじくるな。お掃除ロボット・ルンバみたいに部屋の角っこはやり過ごせ」
「はあ」
大風呂敷もいい加減たたんでもらいたいものだ。何だかいっぱい穴があいていそうだぞ。
「しかしなんだな、赤井君もアイツの馬鹿の一つ覚えの被害者だな。なんでこんな当たり前のことを、ああ長々と要領を得ず喋りまくるのかね。長々話すわりにまるで説得力がない。ピンボケだな。寡黙でいりゃ結構いい男なのに、あんなにグダグダ話すもんだからボロがどんどん出てきて、あれじゃ奥さんにも嫌われるわけじゃよ。何十作応募しようが通らなかったのも無理はない。たとえばこういった説明ができないもんかね」
「できれば短めにお願いします」
「箱村と違ってピリッと簡潔明瞭だ。目の前にドアがある。君は開くのが怖い。だが思い切って開いてみると、向こう側はギラギラと明るい。そして『おかえり』という懐かしい声が聞こえてくる。そういうことだ、以上」
「え?」
「“え?”って何だ」
「おっしゃっている意味がつかめません」
「なんだ君は。ほんまもんのアホちゃうか。一を聞いて十を知るということがないのか。なら仕方ない。少し長めに解説してやるか。君は『アバター』という映画を見たことがあるかね。けっこう有名な映画だそうじゃぞ」
「え? 社長、ああいうのも見てるんですか。若いなあ。てっきり黒澤明の『七人の侍』とか山田洋次の『男はつらいよ』シリーズとか、そういうのを見てるものとばかり‥‥‥」
「あんな名作然とふんぞり返ってる映画なんて誰が見てやるか。たぶん面白いんだろうが、ワシの気概が許さん」
「フ~ンそうですか、笑えて、泣けて、ワクワクして、結構面白い作品なのに」
「それよりアバターだ。映画の中身を簡単にまとめちゃうと、人の心がアバターのなかに入り、そのアバターが惑星上で活躍するというストーリーだ。アバターってのは英語で化身という意味だよ。いや元を辿ればサンスクリット語かな?」
「アバターの“バ”って下唇を噛まなきゃ通じないのかなぁ。アホらし、どっちでもいいじゃないっすか、そんなこと。外人と会話を楽しむわけじゃなし。もう日本語にもなってるでしょう」
「いやいや、気になるな、どっちだろうか。こんな時のために大学に図書館があるんだ、赤井君、たまには学生らしく今度調べとけ。これは職務命令だ」
「アタタぁ‥‥‥そういえば昔、ある女の人からも何語か詰め寄られたことがあるような気がします(『女と』)。これって夢の中の出来事かもしんないけど」
「ほほう、それは興味深い。夢の中に忘れ物をしたことを君は思い出したんだな。それで謎は解けた。だから気になったんだ。すなわち君のその夢とも現とも知れぬ出来事は、ワシのこの発言を引き出すための導入部、いわば神が仕組んだ伏線だったんだ。赤井君、その女に詰め寄られたのはいつのことだ」
「それが分かんないんですよね、昨日のことにも思えるし、ず〜っと前のことにも思えるし」
「なるほど、そこ、重要なポイントだ。ともあれそれほど長いあいだ期待をもたせたとあっては、さっそく伏線を回収してあげないわけにはいかないな。つまりだ、つまりワシらがこの世で生きているということはだな、実を言えばアバターが真の自分に成り代わって生きているということなんだ。みんなそれに気づいてないけどな。真の自分、それは魂と呼んでもいいだろう。魂が肉体というアバターのなかに入り、化身として今の世に、こうやって生きているんだ。本当の君も本当のワシも実のところ、今この場所でなく他の場所にいるんじゃぞ。だから肉体が死んでも魂は死なず、肉体から脱け出し、一瞬にして魂の故郷にもどるというわけだ。もどるのは魂だけ。だから金も地位も名誉も向こうの世界へ持っていけないのはあたりきしゃりきじゃよ。持っていけるのは生前なにをして何を心に刻んだかということだけだ。つまりワシらは錯覚してるんだな、この肉体がアバターでなく自分のものだと思って生活してるから、向こうの世界が真実の世界なのに、こっちの世界が真実の世界だと思い込むことになっちまうんだ」
伏線回収などとナンヤカンヤ言っているが、どう考えても花菱の話とその女とは無関係だ。こういうふうに社長には強引にこじつけて納得してしまう妙な癖がある。
「それってもしかして、都合のいい映画があったから、それにかこつけて自説を後付けしただけなんじゃないっすか? なんか狡い感じもしちゃうんですけど」
「何を言うか! 低能な君にも分かるようにレベルを下げて説明してやってるんじゃないか! そんな生意気いうと、お仕置きであそこをモミモミ、性加害しちゃうぞ」
「うぇぇぇ~~~」
花菱はうろたえる赤井君に大笑いである。
「ああ笑た、笑た。いやいや、ジョークだよ。何度からかっても面白いな。本気にする奴があるか。君はいつも反応がワンパターンだ。君だから許されるんじゃな。シャレの通じん奴ならセクハラじゃろて」
冗談と分かっていながら慌てふためく自分に恥じ入り、赤井君はきまり悪く愛想笑いを浮かべる。それ見て花菱もニッコリ、顔が円いせいもあって母親の笑顔をまねて笑う赤ちゃんみたいだ。機嫌は完全になおったようである。
「さっきは君みたいな何も知らんオボコに腹を立てるとは。ワシとしたことがなあ。恥ずかしいぞ。成らぬ堪忍するが堪忍だ」と花菱。
「実は『アバター』、見たことないんっすよ。なのでピンときませんでした」
「なんだ、なんでそれをもっと早く言わん」
「いえ、気持ちよさそうに話しておられるので途中で遮るのも、と思ったもんですから。できればもっとどこにでもあるような、ありきたりの説明してくれませんかねぇ。僕でも分かるように」
「しょうがないな。小学生でも分かるように話のグレードをもっと下げるか。要するに、みんな死んだら魂の水源みたいなところに入るんだ。水源の水は溶けあっている。だからワシも赤井君も死んだら違ってるようで同じで、同じようで違ってて、違ってるようで同じで、同じようで違って───おい、何回言わせるんだ!」
「ひどいなぁ、社長が勝手に言ってるんでしょう。で、結論は違ってるんですか? 同じなんですか?」
「赤井君、そんなことにこだわるなんて、小さな男だな。いや身長のことじゃないよ。ワシャ、人を外見で貶める人間じゃない」
あんたもチビじゃないか。自分のことは棚に上げている。箱村と同じだ。
「でも、どっちかぐらいは分からないと」
「まあ待て。つまりだ、つまり大樹といっしょなんだよ。葉っぱや花は毎年枯れ落ちるが、翌年になったらまた生え出てくるだろう。葉っぱや花はあの世に行って、またこの世に帰ってきたんだ。その間も大樹の太い幹は大地にしっかり根をはって、そのまんま東だろう、なあんちゃって」
「ん?」
「すなわち人の生死もこれとおんなじ原理なんだ」
「はぁ?」
「まだ分かんないのか。よし、そこまでアンポンタンなら特別に一言で片づけてやるよ。死っていうのはな、一言でいえば‥‥‥」
「一言でいえば?」
「ドラえもんの、どこでもドアを開けることだよ」
「???」
鉄砲の先から旗が出た。何を言い出すんだ。膝カックンされた気分である。
「どうだ、今日はドアづくしで行くぞ。死後の世界へのドアを開けてみた途端、だだ思っただけで瞬時にして何処へでもいける‥‥‥‥そういう自分に会える。ノブに意思読み取りセンサーが入ってるから、ドアを開けるだけでどういう状態の世界へも行けて、どういう状態の自分にもなれる。自由自在、思いのまま。もう肉体っていう邪魔なものがないから、そうなるのも当然だ。いいか、それが死ぬっていうことだよ。もっとも何処へでも行けるからといっても何処へも行かないし、何にでもなれるといっても多くは今のままでい続けるけどな。なぜならもう既に悟ってしまった魂は、どこへ行こうと何になろうと同じだということが分かっているからだ。どの場所に立とうと『ここは自分にふさわしい場所ではない』と思えてくるのが魂の性だよ。あの世ではみんな、そのことを分かっておる。まぁそれはともかく、人は永遠に死なないっていうのは正解じゃな。つまりだ‥‥‥つまり『あの世でも死ねばこの世になる』ってことだ。どうだ、シャレたフレーズだろう。ワシはどうしてこんなにセンスがいいんだろう」
「結論は箱村さんと同じなんですね」
「同じだが違うんだ。説明力の差だよ。あいつにはこんなシャープな切り口でものごとの本質を説くこたぁできない。知性の差だよ。あのバカ、正解を言ってるのに、説明が下手だから赤井君が分かんないんだ。それに引き換え、どうだ、ワシの解説は分かりやすい上に含蓄にも富んでるだろう。冴えわたっている。池上彰レベルだな。やっぱワシゃあ、名刀だ。今日もスパッと切れ切れだ。君らみたいな錆びた鈍刀とは違う」
「別の言い方するとこういうことですよね。人間とっては肉体がパソコンのハード本体。で、魂がソフト。肉体というハードが耐用年数が過ぎて死んでしまっても、魂というソフトは残り、新たな肉体に再インストールされる。前世の学びもUSBメモリーやSDカードみたいな記録媒体に保存され、新たな肉体にうつしかえられる。そうやって何回生まれ変わろうと、魂の学びはどんどん更新され続ける。だから人は永遠に死なない」
「箱村よりスッキリまとまっているけど、誰がソフトをインストールしたり、記録媒体を抜いたり差したりするんだね」
「そりゃ神様とかぁ‥‥」
「君の理屈は最後には何でもかんでも神だのみなんだな」
「そんなぁ、たかだか喩え話なのに、そんな意地悪に突っ込まれても‥‥‥」
「デヘヘヘ、君はまだまだだ。もっとワシから学ばんとな」
「んで、どうして花菱社長はそれが分かったんですか?」
「分かったって?」
「死後の世界が、ドラえもんのどこでもドアみたいだってことが」
「あぁ、当然そう来るよな。赤井君は目がない魚のこと、知ってるか」
「いえ、全然。聞いたこともありません」
「いわゆる盲目魚とか洞窟魚とか言われてるやつだ。ブラインド何とかっていう名前の魚だ。忘れちまった。歳はとりたくないな。そいつは目ん玉が無いんだ。洞窟には餌がほとんどないから、エネルギーを節約するために視覚を犠牲にして進化したそうだ。アメリカの科学雑誌には、魚にとって視覚に使うエネルギーは総消費エネルギーの15パーセントって書いてある。ホントかよ、ってな数字だな。深海魚だってそうだろう。光の届かない深海にいたら、もともと物なんて見る機会なんてない。だから少しぐらいの視力はあるだろうが、目が見えないのとおんなじだ。使わないからどんどん退化していく。こういう話は面白いだろう」
「僕、あんまりその手の知識欲がなくて‥‥‥‥」
「これが面白くないなんて、変わってるな。君は知識のための知識と言うか、知識を楽しむための知識と言うか、そういう概念がスッポリと抜け落ちちゃってんだな。IQが低い証拠だ。生活にいかせる実用的な情報やスキルにしか興味がないというもの一つの生き方だが、そういうのは人生を十分楽しめていない、もったいない生き方なんじゃないのかね」
「僕、頭のハードディスクの容量が少ないんで、実生活で本当に役立つ知識しかそそられないんです。すぐには役に立たない蘊蓄を保存し過ぎちゃうと、いざという時におんぼろパソコンみたいにゴトンゴトンというばかりで大事なデータが読み込めなくなっちゃうんです。僕の持ってる中古パソコンもそうです。キーを押しても、そのままブ~ブ~と独り言をいうだけで、なかなか動いてくれないんですよね。アイツは何をそんなにもったいつけて思案してるんでしょうかね」
「そな、アホな。重いのは、エッチサイトの動画の見過ぎでパソコンにウイルスが侵入してんだよ。せっかく作ったデータも取られちまってるんだ。それかぁ‥‥‥それか君があんまり食わないから、持ち歩いてるノート型パソコンがバッテリー不足で使いものにならないんだよ。日ごろからもっと食わなきゃいかん」
花菱は頭をのけぞらせて笑っている。そこじゃないんだけどな。
「あの、言いたいのは僕のおんぼろパソコンの方じゃなくて、僕に知識欲がないという話だったでしょう?」
「おっとっと、そんなこた、分かっちょるよ。君はメタファーの理解力がないな。博識な大学教授を論破する大阪のオバチャンにでもなりたいのか」
「????」
「どうした、プラグマティズムだろう」
「あの、意味、わかんないんですけど」
「おお、ゴメン、ゴメン。やっぱりこのジョークは君には高度すぎたか。んで、赤井君がワシに訊いてたのは何だったかな。横道にそれたんで忘れちゃったぞ」
「え~と、どうして死後の世界の様子が分かったのか」
「ああ、それそれ。でな、盲目魚でも深海魚でもどっちでもいいんだが、もしその中の一匹に突然変異が起こり、目が見えるようになったら、どうだ? 魚にも無数の遺伝子が備わっている。だけどずっと使わない遺伝子はそのうちオフになっていくだろう。ほとんどの盲目魚も深海魚も物を見る遺伝子は退化してオフになったままだ。ところがある一匹だけは遺伝子がオンになり、光や像を識別できるようになったらどうだ? 人間はふつう、死後の世界なんて見えない。だから人によって、死後は有ると言ってみたり無いと言ってみたりするわけだ。とはいえ、だ。とはいえ何かの拍子に、誰かの死後の世界が見えるスイッチがオンになったとしたらどうだ。彼は死後をありありと見る。もともと太古には人類にも死後の世界が見えていたはずだ。それが前頭葉が肥大したせいで、いつのまにかオフになっちまったんだな。盲目魚に見えなくとも、物体はちゃんと存在してるだろう。それと同じで、死後の世界も普通の人に見えないだけで、ちゃんと存在しているんだ。どうだ、ワシの言うことは奥が深いだろう」
「存在してんのかなぁ。ぼんやり存在してるような気はするんですけど、いま現に見えないんじゃ存在しているともしていないとも‥‥‥」
「目に見えるものは事実ではありえても、必ずしも真実とは限らないんだぞ。空気は見えないけどあるじゃないか」
「見えないけどこうやって深呼吸できるから、ですよね」
「赤井君は高校で光の三原色って習っただろう」
「ええ」
「人の目の神経細胞は赤と緑と青しか識別できない。これ、いくら劣等生の君でも知ってんな。あとの色はどうやって感知してるか。絵の具やカラープリンターみたいに、三色の重なり具合っていうか、混ぜ具合っていうか、いい感じで調節して認識してるんだ。これを人間が見ることのできる光の限界ということで、可視光線なんて呼んでるな。どうだ、この言葉、授業で習ったろう。思い出してきたか? だけど例えば鳥や虫なんかは人の見える光の限界を超えて様々な他の色が見える。可視光線の外側も見えるんだな。昆虫なんて複眼をもってるから、紫外線ですら色として知覚できる。人に見えないからって、見えない光も色もちゃんと存在してるんだよ。だから死後の世界も見えないだけで存在してるんだ!」
誇らしげな花菱は、真理を天秤にのせて重さをはかる物理学者や裁判官といった風情だ。あんたでも学者になれるなら、アカデミックも地に落ちちゃうよね。
「そんなに言い切っちゃっていいんですか?」
「いいんだよ」
「ほんとに?」
「いいんだ。なぜか。なんとスイッチがオンになった盲目魚が、たまたまワシだったからだよ。最初に突然変異した一匹とは、実はワシのことだったんだ。一番確かなのは目で見たこと、次に確かなのは聞いたこと、一番アテにならないのは思ったこと。ワシはこの目で実際に見てるからな」
「なんかどこかで聞いたようなセリフ。どこだったかな?(霞ゆく夢の続きを〈3〉─20、赤井君自身がこのセリフを言っている)」
「何?」
「いえ、独り言です。聞き流して下さい」
「ワシはついに砂漠にオアシスを見つけたんだ。妙な草とかを吸ったり飲んだり、いろいろ試行錯誤していくうちにな。人の中には意識できる自分と意識できない自分がいるだろう。ワシは意識できない自分に集中的に働きかけることにしたんだ。そうしてるうちに神や仏と言われるものが、意識できない自分のなかにもいることを知った。そこからあの世を見るまでの道のりはたいしたことはなかったな。そしてついに成功した。夢遮断法というメソッドだ。ワシ独自のメソッドだよ。なにを隠そう、夢遮断法という名付け親もワシだ。箱村が自分のオリジナルだって言っても信用すんな。夢茶だって婆さんのオリジナルじゃねえか。アイツはそういうコソ泥みたいなところがある。アイツはただの被験者第一号だよ。だからアイツもあの世は見ている。けど発明したのはアイツじゃない、ワシだ。ところで『人生は砂漠だ』というのは赤井君の専売特許だったな。『砂笛の孤独』は傑作だよ。とは言うものの評価できるのは日本広しといえどもワシぐらいのもんじゃろうがな。どいつもこいつもあの秀逸さは理解できん。だが画竜点睛を欠くだ。肝心要の点がぬけている。人生は苦しみの砂漠、必ず死んでしまうのに、なぜ生きるのか‥‥‥その問題提起はいい。だけどその答えがないじゃないか。主人公は茫然自失のまま小説が終わっちまう。何だ、そりゃ。カタストロフィもいいが、答えを出しなさい。答えが出せないのは、死んだその先を見てないからだよ。見てないから人生は地獄、苦しみばかりと思う。だけどその先を見ることができた者にとっちゃあ、『なあんだ、人生なんて双六ゲームをしてるようなもんじゃないか』ってなる。一瞬でハッピーになる、この世に籍を置いたままでな。分かるんだ。本当の現実は向こうの世界で、いま生きてるこの世界は実は夢を見ているだけだってことが」
「ちょっと待ってください。また混乱してきました。その夢を見てるというのは‥‥‥‥」
「相も変わらずだな。やっぱ君には冴え冴えのワシが噛んで含めたように説明してやんなきゃダメか。毎度のことだからもう慣れたよ。いいかね、赤井君はただいま生きているこの場所こそが、我が人生を歩む途上だと信じて疑わない。『人生という綱渡り。独りぼっちの綱渡り。僅かでも道を誤れば転落する。命綱もなければ下にネットもはられていない』(霞ゆく夢の続きを〈プロローグ〉)‥‥‥そう信じて今を生きている。だけど一丁目一番地から違うんだよなぁ。冒頭から違うんだ。卓袱台返ししなきゃぁ。真実はこうだ。いま生きている人生は小説のなかに没入している状態にすぎない。ところが御当人は生まれ出た瞬間から、自分の人生が一篇の小説に過ぎないことを忘れちまってる。悪い登場人物が現れれば怒り、可哀想な登場人物が現れれば同情する。美しくて優しい女が登場すれば恋をし、愛する人と死別すれば涙さえ流す。完全に物語のなかに同化している。物語の主人公を必死になって演じている。自分が物語の中にいるだけだというのは、自分が実際にあの世に行くとき、すなわち本を閉じる瞬間まで分からない。あの世に行ってみて初めて、無常の人生で悪戦苦闘していた自分は本当の自分ではなく、今ここにやっと真の自分が現れてくれたのが分かる。なぁんだ、あの悪役もヒーローも恋に落ちた相手もみんな、ただの登場人物だったんじゃないか。なんであんなに悩み苦しんだんだ。ただ小説を一篇、夢中で読んでただけだったじゃないかってな」
「はて? 分かったような分からないような。僕って小説の登場人物の一人にすぎないんですか?」
「そうだよぉ」
「主人公なんですか?」
「ダメだよ、君なんてぜいぜい死体役だ」
そう言うが早いか、花菱はゲラゲラ笑い出した。花菱はいつも心の底から笑う。彼には作り笑いというものがない。よくこんな下らない冗談で笑えるものだ。
「死体だったら死んでるから同じじゃないですか」
「そりゃそうだ」
花菱はさらに大声で笑う。
「でもそれってかの有名なシェイクスピアの『お気に召すまま』に似てますね。この世は舞台。人はみな、男も女もその時々に合わせて色々な役を演ずる役者にすぎない‥‥‥」
「どこが似てる、ワシのオリジナルだ。シェイクスピアが劇の役者で、ワシのは小説の登場人物だろう、ぜんぜん違うやんけ。シェイクスピアのあのセリフなんて誰でも彼でも引用するからもう手垢まみれだ。それに比べてワシの斬新さといったら、もう神の領域だな。そんでも君はアレに似てるって言い張るのかな? よし、そこまで言うならシェイクスピアがワシを真似たんだ!」
「それはちょっと横車の押し過ぎじゃあないかと。ところでこのシェイクスピアの有名な喜劇のセリフ、得意の英語で言えます?」
「ほう、そう来たか。君も処世術が飲みこめてきたな。可愛げがでてきたようだ。もちろん言えるぞ。All the world’s a stage. And all the men and women merely players‥‥‥‥あれ? 次なんだったかな、赤井君が要らん脇道にそれるもんだから、忘れちゃったじゃないか。こういう有名どころは若い頃、格好つけるために必死で暗記したんだがなぁ‥‥‥‥なんだ、ニタニタして。おちょくってるのか!」
「いえ、めっそうもない」
「ふむ、まだ十分理解できてないようだな。完全に思考停止してるぞ。シェイクスピアなんざ生き仏でも何でもないんだ。アイツじゃ駄目だ。本家本元に御登場願わんとな。やっぱり阿弥陀如来や釈迦が出てこなきゃあ。釈迦が維摩経の中で、この世は醜くて汚いと嘆く弟子の舎利弗にうまいこと言ってるぞ。 『醜くて汚く見えるのは、それを映す心が曇っているからだ。お前が見ているのは実際の姿ではない。お前自身が生み出したものだ』とね。そうなんだよ、話の肝は何かって言うと、いま君が無我夢中になって読んでいる小説のストーリーというのが実は生前君自身が書いたものだってことだ。今のこの世はホントは存在してないんだ。君自身が想い描いたものに過ぎないんだよ。本当の世界は向こうで、いま生きているこの世界は夢なんじゃ。その重大なポイントが抜け落ちちゃってるんだよなあ。無我夢中ってのはこういうことだ。ワシら無我夢中でこの世を生きているが、それは文字通り夢の中にいるだけで、我で無い状態なんだよ。ほんとの自分はそこにはいない、別のところにいるんだ。夢遮断法を試してみろ」
「夢遮断法?」
「誰も憶えちゃいないだろうが、一作目の『女と』の最初のほうにちょこっと出てきたろう。粘着質の作者はしょっぱなから全体の図面を描いているんだよ。アホかいな、計画が設計図どおりにいくもんか。プラモデルをつくってるんじゃないんだ。そのうち登場人物が好き勝手に動きだす。作者はとり残されるだけじゃ。構想なんてあってなきがごとし。ちっとも分かっちゃおらん。それだからトーシローは困る」
「作者って何のことなんです?」
「それはうっちゃっとけ。いちいち説明するのは面倒くさい。それより夢遮断法だ。論より証拠、言ってることが具体化するぞ。夢を見ている最中も、『ああこれは眠る前に自分が思い描いた筋書き通りなんだな』と意識している真の評価者がいる。彼こそが真実の自分、真実の我だ。明晰夢とも違うぞ。明晰夢を見たなんて天狗になってるようじゃ駄目だ。『これは夢だと認識できるぞ』と威張ってる御当人様だって、ひっきょう夢の中の登場人物の一人に過ぎないことに気づいていないんだよ。どうだ、ワシがあまりにも高邁な理論を開陳するんで、その年代物のブレインハードディスクがいよいよパンクしそうか」
「ほんとパンクしそうです。何が何だか‥‥‥」
「夢の中で“これは夢だ”と気づけば、どんなに恐ろしく辛い夢でもそこに苦しみはなくなる。怖くもなければ、辛くもない。同様にいま生きているこの現実が実は夢なんだと心底納得できれば、この世の苦しみは一掃される。それが悟るということで、生き仏になるということだよ」
「ああ、その理屈は何となくわかります」
「ホントかあ?」
「ホントですって」
「どうもあやしい。どうやら君にはワンランク下の説明が必要だな。あの有名な般若心経に“空”という言葉が複数回でてくるだろう。これは誰でも知ってる話じゃな。じゃ“空”の定義って何だ」
「まぁ、一般的には“常ならぬ移ろいゆくもの”とか、そんな感じ」
「君はどうなんだ、君自身が定義をさだめなきゃ議論ができないだろう」
「考えたこと無いです、そんなこと」
「赤井君は自分のことを“常ならぬ移ろいゆく存在”だと信じて疑わないのか。次々と変わっていく、あやふやなものが真の自分だと思っているのか。そんな常に移ろいゆく実体のないものが、本当の赤井君のはずないじゃないか。さっきの映画『アバター』の話でレクチャーしてやったろう。今ここにいて、自分が自分だと信じ込んでいる自分は本当の自分ではない。言い切るぞ」
「???」
「何を戸惑ってる。ここにいる赤井君は真の赤井君でないということだよ。君がいま人生だと思ってるものは、言ってみりゃ運命相手に将棋を一局さしているようなもんだ。途中で“人生詰んだ、あの世行き”となっても“面白い勝負だった。もう一局やろうぜ”って何度でもやりゃあいい。運命は手ごわいからなかなか勝たせてもらえないけど、君は選ばれし人間だからそのうち勝てるよ、すなわち『ついに生き仏になれた、ハッピーじゃん』でメデタシ、メデタシで終わるわけじゃ。たいしたこっちゃない。もっとも夢遮断法で向こうに行って戻ってきたワシだから、赤井君に自信を持ってこういうレクチャーをしてやれるんじゃがな。たいていの人間は行ったままで終わり、帰らぬ人だ。よって生きながらにして解脱することができない。すなわち生き仏にはなれないってことだよ。運命が手ごわいというのはそういうことだ。この世に即心是仏、即身即仏がこれだけ少ないのも無理はないな。どいつもこいつも生き仏になりそこねるのは何故か。単純な理由だよ。死後の世界に通じる術を心得ていないからだ。ワシャもう即心是仏、即身即仏になっちゃってるから、死ぬことだってちっとも怖くない。むしろ楽しみなぐらいだな。この世で死んでも、せいぜい将棋で詰まされる程度の話だからな。生きててOK。死んだらなおOK。どっちであろうがバッチ、グー。いいかね、そういうのを悟るっていうんだ。一度夢遮断法を試して本当の赤井君に会ってみることだな。向こうの世界から全てを見下ろしている偉大なる観照者としての自分をだ。実際に会ってみなけりゃ、そいつがホントにいるかどうかなんて分からないのが道理じゃからね」
「死が怖くないんですか?」
「そうだよ、将棋で負けるだけのことだからな」
「ほんまかいな‥‥‥‥あ、すいません、ちょっと口のきき方が‥‥‥でも今がホントに夢なのかなぁ、こうやって頬をつねると痛いし」
「痛いと思うから痛いんだ。赤井君の心が痛みを捏造してるんだ」
「え? それって詭弁にもならないんじゃ‥‥‥」
「狐おばちゃんは君がつねったとき痛がったか? カナちゃんはどうだ? 二人とも気持ちよさそうに寝てたんじゃないのか?」(霞ゆく夢の続きを〈1〉〈2〉)
「えええええッ!!! 何でそれ知ってんですかぁ。」
花菱が豪放磊落に高笑いする。
「だからさっきからワシは生き仏だと言ってるだろう。そんなの見通すのは訳ない。気をつけろよ、生き仏は色んな人間の姿を借りて、気づかれぬようにこの世にやって来てんだ。彼らは一見うすら馬鹿に見える。ところがどっこい生き仏なんだよな。ワシみたいに見るからに生き仏ってのは珍しい」
「たまげたな、こりゃ。とてもこの世の話とは思えない。だから人生はあの世で自分が書いた小説ってなるのかな???」
「君のようなフザけた凡夫には対機説法がいるわい。今が夢の中だという真理は、ここに置いとこう。君には受け入れるのがまだ無理だ。説明を通俗的なランクまで下げてやる。夢であろうとなかろうと、死ぬと言うことは人類にとって必要不可欠なことだろう。老いた者は消えていかなきゃならない。咲き終わって萎れた花はそのままにしといちゃダメだ。摘み取らなきゃ。しおれた花が若い花の養分を取っちゃうことになるからな。だからこれまで有難うございましたと言って幸福のうちに死んでくべきなんだ。だいたいじゃな、人が死ぬとき死神がやって来るというだろう。死神だってその名に“神”と付く限り神様の一人に違いないんだ。神様が人に苦しみをもたらすようなことするか? 死がそんなに恐ろしいものであるはずがない。死は神様がくれたプレゼントだ。恐るるに足らんよ」
「ようやく少しは詭弁らしくなってきましたね」
「人はあの世にいる状態が通常で、この世に生きている今の状態のほうが稀有なんだよ。本来の常なる状態をなんで恐れなきゃならない。良寛さんの有名な辞世の句があるだろう。『散る桜 残る桜も 散る桜』ってな。老いも若きも男も女も全員いつかは死んじまうんだ。あの世はワシらの故郷だよ。なんでもっとあの世と仲良くなれないのかな。赤ちゃんは泣いて生まれてくる。お釈迦様が言うようにこの世は苦だからだ。だからあの世に行く時は、今度は笑えよ。死の向こうには、ようやく苦から解き放たれた喜びと安らぎがある。あの世に行った直後にすぐそれに気づくよ。一念でそれを悟る。こう考えてみろ。ここでワシが百万円やるから海外旅行に行って来いって言ったら、赤井君は行くかな?」
「そりゃ行きますよ、お金だしてくれるんなら」
「どうして海外旅行に行きたいと思うんだ」
「だって今まで一度も行ったことのない未知の領域にふれるのは楽しいじゃないですか。好奇心を満足させることができて。未知の出会いが世界観も変えてくれそうでしょう」
「死後の世界だって未知じゃないか。どうして恐れる」
「そう言われてみればそうだ。どうしてだろう」
「そこなんだよ、ポイントは。海外旅行には赤井君の他にも何千、何万の人が行っている。海外旅行に行った人は帰ってくるな。だから怖くない。ところが死後の世界は全員必ず行くことになるくせに、そこから帰ってきた人が極めて少ない。だから怖いんだ。怖がらずにすむ方法は二つぐらいしかない。一つは認知症で完全にボケちまうこと。もう一つは実際に自分自身が死後の世界に行ってみて、あの世がこの世よりずっと素晴らしい世界であることをその目で見てくることだ。いきつくところ夢遮断法しかないんだよな。実際のことを言えば、生まれる前にいた所と死んだ後に行く所は、たいてい似たような場所なんだ、よほどの大罪を犯すかよほどの善行を積まないかぎりはな。大概もといた場所に帰るだけのことだ。どうってことない。それでもやたら怖いのは実相をその目で確かめていないからだ。白内障手術と一緒だよ。視界が霞んだまま、箱村みたいに手術がおっかないと初老になってもビクビク怯えていてどうする。図体デカいくせに霧のなかにクラーケンを見たとかトンチンカン言って、眼科に行かない口実にしちまってる。怪物が霧に霞んで見えるのは。お前が眼医者にかかろうとしないからだ。白内障が進行してるんだよ。ほったらかしていると成熟白内障になって光だけしか感じられなくなるぞ。お医者さんだって手術の難易度が上がって迷惑じゃ。案ずるより産むがやすし、行動あるのみだ。どうだ、ワシの説明は説得力アリアリだろう。池上彰も真っ青だな」
「はあ」
「君はハアばっかりだな。死は怖いものでも何でもないんだ。赤井君は死というものを誰がつくったと思ってるんだ」
「そりゃ、神様が人をつくる時にいっしょに人の死もつくったんでしょう、知らんけど」
「また神様が出てきたか。君は分からないことはぜんぶ神様まかせだな」
「神様におっかぶせれば思考停止できて楽でしょう」
「まあ神でも、大自然でも、宇宙でも、仏でも、遺伝子でも何でもいいが、ドイツもこいつもフランスも死を災いとしてとらえる。怪しからん話だ。死ほど自然で不可避で普遍的なものを、君が大好きな神様が災いとして人に課したと言うのかね。そんなに神様というのは意地悪でサディスティックなのかね」
「そうか、そう言われてみれば」
妙な説得力がある。でもそれより「ドイツもこいつもフランスも」というのはギャグのつもりだろうか。そっちのほうが気になる。
「そうだろう。どうだ、ワシの言うことは厚みがあってシャツの胸ポケットには入らんだろう。中身があって重いから百科事典のように手に持って歩かんとな」
あれま~、時代錯誤。
「なにもそんなの、持って歩かなくたってスマホでググれば一発じゃないすかぁ」
「なに? ググ何?」
もとい、超スーパー時代錯誤。
「いえ、いえ、いえ、いえ‥‥‥」
「ところで赤井君はプラトンの『パイドン』を読んだことあるかな」
「ええ、有名な本だから、一応。でも中身は全部わすれちゃったです」
「なんだ、赤井君には犬に論語、牛に経文だったってわけか」
「どうもそうだったらしいです、なにも残ってないから」
「君みたいなノータリンに教養をひけらかすのは嫌味だが、あの本の中でソクラテスが“正しく哲学している人たちは死ぬことを練習している”と言ってるんだ。ワシはそこいらのえせインテリ達と違って正しく哲学してるんだよ。なんせ夢遮断法で何回も生きたり死んだりしてるからな。他の奴らにはそんなこと、できないだろう。あらゆる哲学も宗教もその目的は死を克服することなんだよ。ワシは見事にそれをやってのけたんだな。どうだスゲエだろう」
「あの~~ォ、死と生を行き来できるエキスパートに一つだけ質問があるんですが、いいですか?」
「遠慮するな、なんでも尋ねてみろ。なんでも答えてやる。いつも言ってるじゃないか」
「生きている世界と死んだ後の世界はどう違うんですか? 抽象的でなく具体的な例を一つあげてほしいんですが」
「そうか、そんなのは一杯あるけどな。まあ分かりやすいのを一つあげればだな、この世で大きなものはあの世では小さくなり、この世で小さなものはあの世では大きくなる。この世で地位や金や名声を得て大きく扱われている人は、あの世ではたいてい小物として小さく扱われる。特に策略をはりめぐらし、力関係を読み、威嚇でそれを手に入れたような奴はな。あの世は物質の世界でなく、心の世界だからだ。これと逆に‥‥‥‥逆はいいか、だいたい言わなくても分かるよな」
「ぼ、僕も夢遮断法、させてもらっていいですか? それ聞いて俄然ヤル気がでてきました。夢茶と同じで副作用なさそうだから」
「おう、ウエルカムだ。そうこなくっちゃ。その言葉を待ってたよ。まだ時期尚早なんで、折をみてボチボチ試してみるか。じゃが、肝心のこの小説の作者が、最近書くことに嫌気が差しているそうな。万事休す、あいつが作品を尻切れトンボにしちゃう前に一度ぐらいは君に経験させなきゃな。いつムクれられて手遅れになるやもしれん」
「その人に“投げ出すのはもう少し待って”と言っといてください」
「今度あうことがあったらな。でも無責任で君と同じく頑固だから、どうなるか知らんぞ」
頑固くらべをしても始まらないが、頑固者は花菱社長、アンタの方だろう。
「白いゴキブリがいることの証明は、いないことの証明と違って簡単じゃ。実際に白いゴキブリを一匹つかまえてきて、相手の目の前に『ほらよ』って見せてやりさえすりゃいいんだ。死後の世界だって、夢遮断法で行って戻ってこりゃそれだけで十分事足りる。もっとも死後の世界の方は物質的なものじゃないから、ゴキブリみてぇに『ほらよ』とはいかないがな。まぁいいよ、どうせ信じない奴は、証明できるできないを問わず端から信じないんだから。赤井君も実際に行ってみることだな。向こうの世界のことは克明に憶えとけよ。後からパソコン入力して売り物にしなきゃな」
「売り物にする?」
「なんだ?」
「いえいえ何でもありません。でも、もしかして僕の見るあの世は地獄なんじゃないでしょうね」
「だいじょぶだ、大丈夫。少なくとも善人なら誰だって、あの世はこの世より素晴らしい世界のはずだ。超極悪人がどうなっちゃうかは知らんが。箱村みてえなコソ泥野郎でも、あっちは素晴らしい世界だと言ってたぐらいだからな。生きててもそこそこハッピー、死んだらもっともっとハッピー。それが赤井君の真の姿だ。バッチ、グーだろう」
「僕、極悪人じゃないけど小悪人かも」
「平々凡々の君がか? 笑わせるなよ。たまに子供がオイタする程度だろう。もし赤井君があの世に行って地獄なら、もう心の中は既に地獄になってるはずだよ。情緒が極端に不安定で、あっちこっちで怒鳴りまくったり暴力ふるったり、今にも都心で連続無差別殺人をやらかしそうな人間になってるはずだ。この世とあの世は地続きだからな。君はそんな人間か? そうじゃないだろう。いかにも頭の悪そうな、ただのボケッとしたニイチャンだろ」
「でも本当に大罪を犯しているのは、たいてい最も疑わしく見えない人でしょう」
「なに子供が背伸びしてるんだ。アップップウのくせして。君に大罪を起こすような極悪エネルギーがあるもんか。だいたい人間なんて全部が全部、人に知られたくない醜いものを心の内に宿しているもんだ。外側からそういう風に見える人と、そういう風に見えない人がいるだけのこった。一つ教えてやるよ。地獄があると思っている奴はたいてい地獄には行かない。“地獄なんかあるもんか、死んだら無になるだけだ”と思ってる奴が、例外中の例外で逆に地獄に行く場合があるんだよ。どうせ死んだら無になるんだからと、見ず知らずの人たちを大勢道連れにして自殺するような輩だよ。地獄があると信じる者には無くて、そんなもん有るかと思う者には有る。皮肉なもんだな。『教祖様を信じなけりゃ地獄に落ちるぞ』と脅すカルト教団があるだろう。悪徳宗教の常套句だ。ところが実際は当の教祖様自身が地獄の存在を信じていないんだからな。ところが皮肉なことに、そんな教祖様こそ死んだら真っ逆さまに地獄に落ちちまうんだ。懲罰的な意味じゃない。そういう極悪人に地獄の存在を学ばせるため、神様仏様がスペシャル粋な計らいをしてやってるんだよな。地獄に行くのは天国に行くよりずっと狭き門なんだぞ。赤井君が地獄なんかに行くもんか。そんなことより赤井君が夢遮断法で解脱して即心是仏になったら、『砂笛の孤独』の続編でも書くか。題して『青年は砂漠を越えて』だ。青年というのは赤井君のことだよ。うん、ベストタイトルだ。今日もワシャ才気煥発、切れ切れだな」
「それって、なにかの映画の題名にあったような‥‥‥」
「五木寛之の『青年は荒野をめざす』だろう。どこが似てる。語呂合わせにもなってない。赤井君はいつも犬に論語、牛に経文だな。心配ならワシの秘密兵器のブロックチェーンで確認してみるか? なんせデジタル空間に国境はない。世界中をカバーするぞ。金が絡んでくるから、同じものが無いか、みんな、必死でアラ探しするんじゃ」
う~ん、なんとなく仕事の全貌が見えかけてきたぞ。ま、それはともかくとして、
「ちょっと訊きたいことがあるんですが」
「何だ」
「花菱社長は行って戻ってきたから、ソクシンなんちゃら仏になってるんですね」
「ああ、やっと理解できたか」
「ソクシンなんちゃら仏と普通の人との違いって何ですか?」
「なんだ、まだ理解できてなかったのか。ズッコケたわい。手の焼けるやつだ。また池上彰ばりに解説してやらんとな。人生は思うがままにならないだろう」
「ええ」
「だったら寝てる時に見る夢は思うがままになるか」
「ならないですねえ、ふつう夢も」
「人生は一夜の夢だ、というのはそういうことだ。ここまではいいか」
「はい」
「だか、夢を見ながら『これは夢だ』と気づく人がいる」
「ああ、明晰夢ってやつですね」
「そして中には、これは夢だと気づき、そのストーリーを思うがままに作りかえることができる人がいる。それを目覚めた人、つまり心身がそのまま仏となるという意味で即心是仏、即身即仏というんだ」
「明晰夢を見る人って色のついた夢を見る人と同じで、ただ超疲れてるとかストレスまみれとか、そういう人なんじゃないですかねえ」
「馬鹿いってんじゃないよ。夢のストーリーを思うがままに作り変えることができる人というのは、同時に自分の人生も思うがままに作り変えることができる人のことなんだ。これが生き仏でなくて何なんだ!」
「そうなんですか、どうも今ひとつピンと‥‥‥‥」
「今ひとつって何だ!」
「いえ、何でもありません。さっきの色のついた夢を見る人の話で思ったんですけど、ソクシンなんちゃら仏なら人の魂の色って、見えますよねえ」
「もちろん見えるぞ。ワシャ生き仏だからな」
「僕の魂って何色でしょうか」
「赤井君は魂に色はついてないよ、無色透明だ。たいてい人には何らかの色がついてんだがな。君、いま本当に生きてるのか。ここにいる赤井君は本当に君なのか。蜃気楼じゃないのか?」
「え! 色なしですか」
「そうだよ」
「社長の色は何色なんです?」
「残念だけど自分の色だけは分からんのじゃよ。自分で自分を見るわけにはいかないだろう。占い師だってな、自分を占うことはしないだろう。だって占えないからな」
「鏡に映したら?」
「駄目だよ、鏡は人工物だろう」
「僕のとこにやって来た作家やその他の人たちの魂の色も、花菱社長にぜひ見てもらいたかったなあ。そうすれば彼らの意図が僕にとってプラスかマイナスか予想がついたのに」(『女と』)
「惜しいことしたな。ワシにかかりゃあ、そいつらがどういう心の持ち主かバレバレだろうによ。ワシは色の意味もちゃんと分かってるからな。まあ、それが分かったって何の得にもならんが」
「箱村さんにも色があるんですよね」
「あるよ。でも本人以外に教えちゃいけねえんだ。教えたいのは山々だがな」
「どうしても知りたいんですが、そこを何とか教えてもらえませんかねえ」
「だめだな、信義にもとる」
「じゃ、箱村さんの奥さんの色は?」
「今だめだって言ったばかりだろう、本人以外に教えちゃいけないって。やっぱり赤井君はノータリンだな」
「そこを何とか‥‥‥」
「どうしてだろうかなあ、箱村の奥さんの色だけは分かんないんじゃよ」
「社長、箱村さんに嫉妬してません? あんな美しい奥さんと暮らしてるから。だから心眼が曇って見えないんだ」
「何をいうか! 赤井君も箱村の悪影響を受けて生意気になってきてるな。チビでモテないだろうから許してやるがのお。たぶん箱村と似たような色だろうよ。よく似た色どうしが惹かれあうからな。君と箱村が馬が合うのもそのせいじゃろうな」
「なるほど、それで分かりました。箱村さんも限りなく透明に近いんですね。なんかの小説のタイトルじゃないですけど」
「なんで分かっちゃうの?」
「そりゃ、いま社長が言外に認めたようなもんじゃないですか。ノータリンなのはもしかして僕じゃなくて花菱社長のほう‥‥‥」
「なんだ?」
「いえ、独り言です。そうかあ、箱村さんも箱村さんの奥さんも僕も似た色なのかあ。だから奥さん、僕なんかとあんなふうに‥‥‥‥」
「バレちゃったら仕方ないか。箱村も赤井君とよく似た色だよ。奥さんの色は見えないから分からん。君と箱村は心がとてもよく似ている。双子みたいだ。君らは互いに正反対だと思ってるようだがな。とても薄い色だ。実をいうと‥‥‥‥アイツ、もう長くなさそうなんだ。思い違いであってくれればいいが。最近ますます魂の色が透明になってきている。今がアイツの最終章かもしれんな。これは本人には絶対に言うなよ。努めて今まで同様の態度で接するようにはしてんだがな、なんか気づきはじめてるようでな。ま、いいか。アイツも死後の世界の素晴らしさを見てきたわけだし」
「えぇっ!!」 (◎_◎;) ウッソー!
脳天逆落としを食らった。自分がどんどん透明になって、そのうちスッと消えてしまうような衝撃である。
「君が箱村と最初に駅であったとき、どうして箱村が君を君だと分かったと思う、君の顔も体格も知らないのに」(霞ゆく夢の続きを〈1〉─5)
「ちょっと待ってください。気が動転して、ついていけない」
「赤井君の魂の色を見たんだよ。君らみたいな色の魂の持ち主は滅多にいない。だからすぐ見分けがついたんだ。ワシが採用するのは、そういう魂の色をもった奴だけだ。これなんか、どこぞの新人文学賞をとるより、はるかに難関だぞ。君がこの部屋に初めて来たとき、ワシは一目見て君が人がいい人間だと見ぬいたろう。瞬時で見ぬけるんだわ。なんで見抜けたか。魂の色を見たんだよ。確かこう言ったはずだ。“君は神様や仏様に好かれるタイプだ。きっと平凡で浮き沈みの少ない人生を送れるぞ。目立たない低空飛行の人生だ。決して『山高ければ谷深し』のストレスまみれの人生じゃない”ってな。憶えてないか? 若いから憶えているだろう。箱村は魂の色なんか見えないと言ってたか。見えるよ。アイツもあっちの世界に行って戻ってきたんだから」(霞ゆく夢の続きを〈1〉─7)
「ちょっと待ってください。箱村さんの先が短いとすれば、まったく色のない僕はどうなっちゃうんだろう」
「知らないよ」
「知らないって、そんなあ」
「知らない。それは君自身が決めることだ。他人が自分の人生に責任を取ってくれると思うのかね。というか、そもそも取れないだろう」

最後までお読み下さり有難うございました。
赤井かさの(ペンネーム、挿絵も。広告は違います)
霞ゆく夢の続きを(7)

