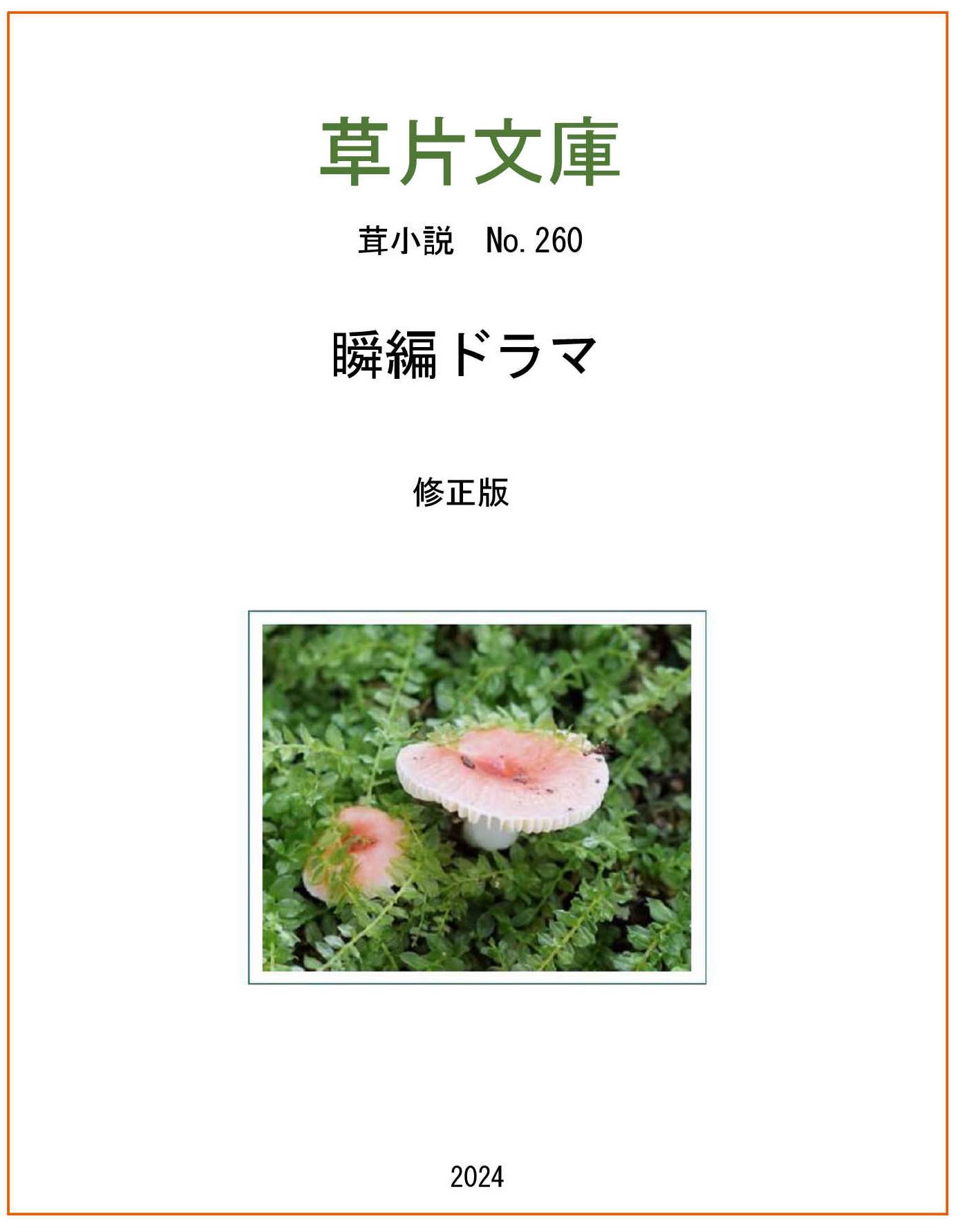
瞬篇ドラマ
茸指小説です。
いかん、全く話が浮かばない。舜編ドラマを考えなければならない。短編ドラマではない。新しく提唱した舜編ドラマである。小説で言えばショートショートで、十分間の味の濃い話を作らなければならない。
いままで三十分の短編ドラマをつくっていた。おもしろそうな短編小説をドラマ化するということで、脚本は専門家にたのんでいた。
俺は小さな映像会社に所属するテレビドラマ監督である。ストーリーを読んで、どの役にはどの俳優がいいとか、場面をこのように作ろうとか、総合的な観点から、それぞれの担当に指示をして、まとまった映像を作る。仕上げは撮りあがった映像をつぎはぎして、二十五分ほどの短編にする。
そういった物を作っている、テレビの下請け映像会社の監督仲間で集まってよく飲む。会社としては競争相手でも、監督個人となると、映像作家として仲のよい友人たちである。会社の最低限の守秘義務はあるが、映像を作ることに関しては、みなそれぞれ個性があり、話をすることは楽しいし、考え付かないような視点を学ぶ有意義なことでもある。
飲みながら話をしている中で、金をかけずに舜編ドラマを作って、見せ合おうと俺が言った。みんなも面白いかもしれないとうなずいた。
ストーリーの作成から、台本づくり、撮影場所などの設定、もろもろを全部自分でやるというものにしよう。
一緒に飲む監督仲間は5人だがみな中堅どころ、それぞれの会社の製作スタジオは、あいていれば自由に使える身分である。企画書を出して、通れば好きなものも作らせてもらえる。登場人物を演じる俳優は、小さな劇団の新人や、俳優養成所のまだ売り出していない若手を起用すれば、ポケットマネーで一生懸命演じてくれる。
中の一人が、それを若手監督のコンペティションにしようといいだした。そうすると、自分たち五人だけではなく、世間の眼を引いて、できたものをどこかで放映してもらえるかもしれない。参加費をとって、広く呼びかけるか、ということになり、それぞれ、会社に企画書を出した。会社は喜んで協力してくれることになり、賞金や作品を選ぶ有名な監督などの費用もだしてもらえることになった。
瞬篇テレビドラマコンペティション、「瞬き」とよぶことになり、俺がまとめ役ということになった。
締め切りは半年後。応募要領をテレビに流してもらった。
自分たちも参考作品として一作、作ることになった。そのストーリーを今考えているのである。
うわさを聞きつけたあるテレビ局から来年放映したいと問い合わせが来た。もちろん喜んで受けた。ウイークデーの夜中の十二時から十分間、毎日流すということだ。大変喜ばしいことで、応募作品が増えるだろう。監督希望の若者は、深夜族の心をくすぐるような話もつくるだろう。
瞬編は短い時間に起承転結をうまく織り込み、特に結があっと驚くようなものになっていないと受けな。
そう言った作品を作る人たちに対しての参考作品になるわけだから、いい加減なものは作れない。まず基本となるストーリーが面白くなければならずそこが肝心だ。気が重いなあ。
仕事場ではそれに集中することはできない。おのずから、家にいるときに話を考えることになった。
部屋に閉じこもり、机に向かっているのだが、いざとなったら難しいものだ。すぐに書けると高をくくっていたのだが、そうはいかない。でてこないじゃないか。若い頃SFに没頭し、ショートショートの大御所、星新一のものを横目で読んだものだが、いざ書くとなると大変なものだ。その頃好きだったのはレイブラッドベリーだ。叙情的な短編、少年少女小説、場合によればかなり社会批判も盛り込んだすばらしい作品がある。変わった幻想的な探偵小説もある。レイブラッドベリーは一週間に一作書くような生活をしていたという。すごいなあと思い、学生時代まねをして、毎週何かを書いて、小説募集に応募したものだが、一度も最初の審査をクリヤーしたことがない。
作家の頭は持っていないと自覚し映像の世界に入ったわけである。会社が頼まれた映像作品の監督という仕事は自分としては向いている。
深夜机に向かって、書いては消し、書いては消しを繰り返し、なかなか気に入ったものができない。
高校生の頃から使っている、木でできた勉強机の上をみつめている時間が多くなる。
父親が気に入って、町の古道具屋から買い受けた。きくい虫が食い散らかした穴があいている。そのころ、高校の友人たちは、新しい机をかってもらっていた。友人の家に行くと、はやりのスティールの勉強机だったり、親が使っていたというイギリス風の黒光りするような机だったり、畳の部屋を使っていた友人は、座り机の立派なものをもっていた。もっとも、そいつの家は寺だったので、座り机はごろごろ転がっていたのだろう。
僕は勉強が好きなわけでもなく、すでに大学をでて結婚した姉のちょっと女の子っぽい机をつかっていたのだが、古いもの好きの父親が、古道具屋でみつけたといって、買ってきたものがそれにかわっているわけである。
父親はいいだろうと言うのだが、姉貴の机と大差はないと思ったにすぎなかった。
それでも、大学受験はその机の上で参考書を広げ、なんとか私大の文学部に合格した。
大学の四年間はいったいなんだかわからなかった。文芸書を読むこともなく、気ままに、古本屋で見つけたあまり読み手がなかったような文庫本を読んだりしていたが、ある時、文芸倶楽部の女の子がすすめてくれたSFを読んでのめりこんだ。それでJGバラードやレイブラッドベリーなどのサイエンスからちょっと距離を感じるSFを読みあさったわけである。
その結果、映像作成会社のドラマ作成部署に就職してしまったということだ。
だが、助手をやりながら、要領を覚え、監督になった。
この古いきくい虫の穴のあいた勉強机、受験戦争でも一緒に戦い、今おまんまの種を作る大事な相棒になっている。
いいアイデアがでないので、そんな思いで、きくい虫の掘ったほんの一ミリほどの穴に目をやっていた。
おや、
いくつもあいている小さな穴の一つから赤い光がでた。ように見えた。
目を凝らしていると、赤い光ではなく、赤いゴミのようだ。校正に赤鉛筆を使うので、その滓でもはいったか。
そう思って目をそらしたとき、赤いものがもそもそと穴からはいだしてきて、いきなり、目の前でぷーっと膨らみはじめた。みるみる紅茶ポットほどの大きさになった。
茸じゃないか。
赤い傘に白いぽちぽちがついていて、柄は真っ白、よく子供の本に出てくるような茸だ。毒茸にもみえるし、子供たちが遊ぶかわいらしい茸にも見える。
机から茸が生えた。そんな話を読んだことがある。
茸っていうやつはおいしい食材でもあり、毒の大元でもあり、子供の枕元で揺れているぬいぐるみのようでもあったり、いろいろな要素を含んでいる。
ドラマの脚本もそうであると、とてもおもしろいのであろう。
そんな思いで、目の前の茸を見ていると、
「やだ、そんな目でみちゃ」
と、若い女の声で、赤い傘を揺らした。
「俺がどんな目で見ていた」
だいたい、自分が人を見るとき、その人は俺の目をどのように見ているのだろう。
「欲求不満」
何だ、欲求不満とは、そうか、欲求不満と言っても、セックスのことだけではないな、いいドラマを書こうと思っているのに、アイデアが出てこない、それも欲求不満だ、そんな目をしていたのだろう。
そう思って、この茸、なかなかよく俺を見ていると思ったら、
「ばっかみたい」
といいおった。
「なにが」
ちょっとむっとした。
「一番ふつうに考えたときの欲求不満よ、そいつが、アイデアを塞いでいるのよ」
確かに、妻に内緒の彼女とはずいぶん会っていない。と言って、自分はそんなにがっついている人間ではない。
「人間も動物よ」
「他の動物とは違うんだ人間は」
「そう思っているから、文学ではだめね、人間はただの動物よ、あんたは繁殖期だから雌を追いかける雄と同じなのよ」
「俺は繁殖期ではない」
「あーら、ばーか、人間は一年中繁殖期で、発情してるのよ、そういう動物なの」
まてよ、大学の一般教養の生物学の教師がそんなことを言っていたような気がする。
茸はふらふら揺れながら、白い柄を少し膨らませた。女の足に見えてきた。赤い傘に隠れているところ、スカートに隠れているところ、だんだん、茸の言うとおりに発情してきた。自分の茸が固くなってきた。
最近、警察官、裁判官、教師、そういった堅物であるところの男たちが、スカートの下を盗撮したりしてつかまっている。なんとも、はずかしいのだが、それは人間が動物で、本能を御しきれなかったからなのか。
「そうよ」と
赤い茸が机の上で、ごろんと横になった。
横たわるマハ。いやあれはあまりセクシーではない。この茸の方がずーっとセクシーだ。
思わず指が伸び、茸の白い柄に触りそうになった。
茸の柄が二つに割れた。
女の足そのものになった。
もう、がまんができない。
「あなた、机の上に乗ってなにしているの」
妻が部屋にはいってきて、またかという目で俺を見た。
瞬篇ドラマ


