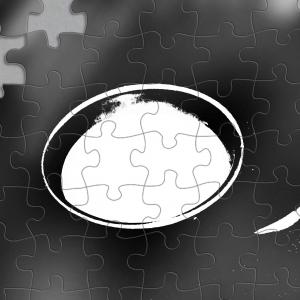「緞帳前にて」
一
立ち去った。
友人である山猫のぬいぐるみは、道行く人から咎められた、聞き慣れた単語をすり抜けて、すり抜けられなくてもそうした心算になって街を歩いたのだ。
絵本で読んだ話では、一人の少女が森の中古い洋館に辿り着いて、其処で頭部だけの骸骨に会い、友人となるものだったけれど、此処は洋館のある土地ではないし骸骨の友も居ない、おまけに少女は何も手に持ってはいなかった。
それでも幕を開けば歩いているのは娘で手乗りの大きさの山猫のぬいぐるみを胸に抱きしめて街をずっと中心部に向って歩いているのだ、舞台は既に手を叩く。
娘の名前はテアと言った。この国の言葉で”小さい者”と言う意味である。テアの抱きしめているぬいぐるみの名前はラティと言った。この国の言葉で”小さい山猫”と言う意味である。
テアは生れつきの身体の特徴で、子供を授かることの叶わない娘であった。そしてラティは他のぬいぐるみのように愛嬌のある表情をした猫ではなかった、何と言ったって山猫である、スコティッシュフォールドのように人馴れする生き物ではない。しかもぬいぐるみなのに喋るのだ。饒舌なわけではないが、よくテアに話し掛ける。今それはテア自身が一人二役しているのだと思った者、テアの心の中にだけ聞えて来ると思った者、それは残念ながら間違いである、道行く人の声を聞け、冒頭の数行を思い返せ、ラティの声が聞えている為に彼等はふたりを咎めるのだ。その声を此処に記すのは極めて不快だから止しておこう、我々の関心はありきたりな民衆よりも、人と異なるテアとラティの行方である。彼女達は街の中心部に向かい何をするのだろう?
此の国の街は煉瓦造りの建物が多い。と言うのも、樹木を伐採する削り出す等の加工作業は憲法により禁止されているからであった。木材を一切加工出来ない代りに人は煉瓦を使い鉄を用い金を溶かし銀を溶かし、プラスチックなんかも扱い街の外観を産み出したが、中心部には一本の樹が立っているのである。
この樹に関しては憲法違反でないので誰も首吊りにはされないが、もう少しだけ説明を加えておこう。
新しい憲法が公布される数年前のこと、此の国は世界でも類を見ないほどの天災に魅入られてしまった。その中でも倒れなかったのがこの樹である。海に沈み風に殴られ雨に項垂れ炎にくべられても、異国の遠い物語の不死鳥の如く樹は芽を出し凄まじい速度で伸び続けたので、流石に人々は畏敬の念を取り戻した。花も実も持たぬ若葉ばかりの樹ではあるものの、人間の心の支えとなった樹は新たな国造りの根幹となっていき、今では街の中心部に据えられた、という経緯なのであるが。
テアはラティと共に其の場所へ向っていた。テアは見た目愛らしい小柄な娘で、ぬいぐるみを抱いていなければ街の同年齢の者達と談笑し合うことは出来ていたかもしれない。としごろの子等によくある王子やお姫様に夢を見ることが出来たかもしれない。
「テア其処だ、真ん中あたり。」
ラティの顔の割に渋い声が合図となり、テアは樹の幹を雪まみれの靴でどッかと蹴った。
「雑草。」
瑠璃のような声を唾とともに吐きかける、足元はがぱりと鯰の口をあんぐり開いて、非国民を地底住居に連行した。テアの姿が地上から見えなくなると口はたちまちムニャムニャと閉じて、元の通りの光景が街に戻って来る。住民達は樹を蹴りつけた娘はあわれ気が違ってでもいたのだろうと納得して、また談笑や商売やらを再開した。
メリークリスマス
メリークリスマス
メリークリスマス
二
穴をころころころころ転がり落ちて、叢に背中からぼすんと抱きとめられる。目がくりくり回ってしまいそうな脳の中で、テアはむぎゅうと抱きしめたラティの苦しそうな声を聞く。
「苦しい、離せ、力を緩めろ。」
お目々くっきりと囲み目の黒目はぼんやりした相を湛えて気を許してしまいそうな愛らしさだが、口は兎のように三つ口で、山猫らしいふてぶてしさを隠そうともしていない。その口がぱくぱく上下することは無いが、ラティはテアに訴える。
「テア、テア、少し苦しいから。……ぎゅむ。」
ようやく焦点の合った娘は胸に押し当てる腕の力を緩めて言う。
「ラティ、ラティ、着いたみたい。……地底住居。」
少し上ずる玻璃の音≪ね≫も、綿に響く速い鼓動も、テアの興奮を隠しきれない。娘はずっと此の場所を訪れたかったのである。
諸君等の国では、地面を掘れば土が出よう、どれだけ掘っても土か或いは水が噴出するのが関の山であろうもしれぬ。だが舞台が呼んだ此の国はちと違う。地面の下に潜れば白い大きな翼を持つ魚が泳ぎ、星屑で編まれた馬車が通う、その馬達も浅葱色に瞼を染めて鈴蘭の手足で菫の胴体を支えて走る、馬車が追うのは硝子の金魚、いたづらをして転がされた鯉に命じられたらしい。硝子はぴらぴら水銀の鱗を泳がせて真珠の金魚鉢をこんこん叩く、中から覗くバッタの顔に馬車はひらひらと回転する、その風に集まるのは月の妖精、衣清らな蛾が一匹。
困った馬車の散らす欠片を豊かな羽でふッと扇ぐと星屑は地底の夜空にぴたりと戻り眼を眠る。すうすう休む馬の顔を見つめて口の無い口元がフッと笑う。叢に座ってこの様子を見て居たテアは、舞うかの衣の姫を見つめて居る。
「居たのかテア、蛾の姫君は。」
「いらっしゃった、あゝ、今目の少し先で踊っておられる。」
藍を流した水の中に月の光が鸚羽透く色に射す滲みはやがて雨の花、冬の花を目覚めさし太陽のぬくもりを僅かに混ぜて泉下の鳥は湖を飛び出し林檎のしたゝる果実にとまる。地上ではオオミズアオと呼ばれる種族は、此の地では月の妖精と崇められている、テアは、ラティと一緒に月の妖精の元へと恐る恐る近寄った。
「月の妖精様。」
思い切って頬を染めた呼び掛けに、呼ばれた方は首を傾げる、その複眼のきょとんとしたあざとさときたら!もう顔を直視出来なくなってお話出来なくなったテアに代りラティが説明を続けることになっていた。
「俺達は上から転げ落ちて来た者だ。相棒が此処を訪れたいと望んでいてな。住まわせてもらっても構わないかい?」
拒む理由は此の場所には無い、追い出す理由も此の場所には無い。月の妖精はふたりを交互に見つめた後白い紫陽花の寝床へ帰って行った。
ようこそ
ようこそ
ようこそ
ふたりの歓迎会は二晩続き、それからテアとラティには一軒の赤い屋根に青い壁、黄色の窓の家がプレゼントされた。
これが此の国の地底である。
三
ぬいぐるみは可愛らしさが命だ。大きくても瞳がつぶらでお口がきゅっと笑っているのであれば愛されるし、笑っていない表情でも小さければころころと愛される。そうして数々の動物達はぬいぐるみと化し人の腕に抱きかかえられて行ったのだ。
自分が可愛くないことは商品の売れ行きでなんとなく察してはいた。在庫数を数える店員が自分に一瞥もくれないから、入れ替りの激しい両隣に比べて此の身は愛されることの無い愛玩失格の存在なのだと。同じ値段を支払うのなら傍に置いておきたいと思わせるような物の方だからと売れ残りは自身を納得させ続けて来た数年後。
一人の眼が自分を見ている。数分その人物はその場に立ち留まり、去って行った。奴の身辺にはよほど物が無いらしい。
鼻で笑った後日にまたその眼は来た。素見しにも誰かの佇んだことの無い自分の前に、また。昨日は眼が在ると言うぼんやりした気配しか見えなかったが、今日は眼玉の色まで見えた、緋褪色の水晶玉は他の目移りすることもせず。そしてまた去って行った。
何故自分を見るのか理解が出来ぬ。見つめたかと言って買う訳でもない、嘲りにしては少々真面目が過ぎる、あの緋褪色、何で染めたらあんな色になるのだろう。あの眼が知りたい、何故見つめてくれるのか何故そんな色なのか、問うたら教えてくれるだろうか、否こんな姿の野郎の低い声には嫌気が差そう、したらあの眼は来なくなる。
こわい
初めて感じた”知りたい”を失うことの恐しさ。この身でなければいとも容易く手に入れられたであろう、やっと届きかけた何處かへの入口。それを失うのが怖く、我が身が痛い。こんな態じゃなかったら、君は俺を愛してくれた?
「おいで。」
テアの緋褪の瞳が柳のようににっこりと曲がる。手に乗せられた山猫の小さいぬいぐるみに被っていた埃を指で一つ摘んで辺りに捨て、会計を終らせ両手で抱いて正面から顔を見る。
「もう寂しくないわ。今日から私と一緒に居ようね。」
頭を撫でられたことなんて、商品棚の向こうの世界の光景だったのに、それが今、
「今日は満月なの。だから貴方の涙が見えたのよ。」
湯気まろやかな浴槽に一緒に浸かり、轟音で一緒に髪と中身の綿まで乾かし、胸の間に抱きしめられたまゝ温かいベッドと布団の柔らかさに微睡んで眠る。
「貴方は頑固だから、私のことを素直に呼んでくれないんじゃないかと心配したけど、要らんお節介だったね。」
「呼んだところで逃げられて終い、ってのは何度も味わって来たからな。声の出し方も忘れたんだろう。」
「健気ねえ、私も見習った方が良い?」
「…おまえの健気は月の妖精が来ないと表れないだろ。」
「当然よ、如何して地上の奴等に…?」
地底住居の中で本を読むラティと、彼に紅茶を淹れるテア。ポットとカップにお湯を注いで温めて、茶葉をスプーンで一すくい、ポットのお湯を捨てて茶葉をぱらりと寝かした上からお湯を掛けて立ち起させて抗議の声を塞ぐようにふたをする。さらにティーコゼーの帽子をかぶせて一分、二分、三分。チョコレートとアップルシナモンの薫り立つ黄金の湯気が家中を扇のように舞っている。
「テア、この本見てみろ。」
小さなお手々がカップを受け取り机に置いた本を指す。
「なぁに?」
本の題名には『紅茶万葉集』と書かれていた。
「古今東西の紅茶を記した本だ。」
「何處からそんな本持って来たの?」
「此の家の本棚に並べてあったから拝読してたのさ。」
「私に教えてくれてもいいのに。」
ラティは堅物な見目に反していたずらを好む性格であった。本気ではないが甘い頬をむくれる主人にけらけらと笑いで返す。
「おまえも読んでみろよ、中々に興味深いから。」
「言われなくてもそうするわよ。」
テアはぶ厚い本を手に取ると、頁をぱらりと捲り始めた。アンデス山脈の岩塩ティー、メトロポリタンの絵具ティー、アトランティスの海紅茶、ロンドン塔の薔薇紅茶、ドズマリープールの湖ティー、アスガルドのオーディンティー、壇ノ浦の入水紅茶、神話や伝承、現実がそれぞれしたためられた茶葉から抽出した紅茶はまだまだある。時に、天晴旭御紅茶は日本の女神を讃美するのに生れた紅茶らしい。
「いっぱい載っているわ。でも…」
最後まで頁を捲っても
「私達の故郷のものは記されていないのね。」
本を机に戻してラティの真向いのソファに腰を落とす。
「仕方が無いさ。地上の国は支配した国の文化を消滅させようとするのがお決まりだもの、そうして幾千の言語や文化が途絶させられたと思う?」
ふたりは一緒に窓の外を見た。其処は美しい地底の世界、ふるさとを奪われた悲しみが手招く世界、哀しみを唄い愛を嘆く弧月の世界、地上に戻ることを望まない者達の……
四
昔、地上には多くの国が存在していた。異なる風土は異なる言語を生み異なる文化圏をそれぞれに編み出しては、他との交流によって変化を知り吸収することで国々は育っていく時代があったと言う。
けれど今、世界地図には”地上世界”の国名だけが記載され、かつての国は地殻変動の影響も受け大陸の形の名残すら受け継がれることは無かった。海洋の上にだだっ広く胡坐をかく不格好な楕円形、これが今地上に存在する唯一の国である。
地上世界は美を求めた。それは人工的な美しさのみに限らず、自然の創り出した美しさも含まれていた。自然を愛し尊敬する念は人の産み出す工芸品や建物にも大切に込められて、世界は美しいもので溢れていた。
一方醜いとされたのは現実に存在しないものであった。殊に想像力は忌み嫌われ、想像する力を持つ者は必ず自滅、自尽の道を歩むと信じられ、現実の美を侵す思想犯だと法で裁かれ処刑された。死体は地上世界で最も恐れられ憎まれた物であったので、中心部に誰でも気軽に捨て易いように整備されたのがテア達が落ちた例の穴だ。
此処迄バラしてしまえば賢明な読者諸君は地底世界がどのような場所であるのか大凡の見当は付かれたことだろう。でも残念、物語や小説と言うのはいくらでも逃げて裏切り続ける事を許された愛情たっぷりの代物なのだと言うのを隠して此処迄案内したので君等の予測は見当外れも甚だしい、地底世界は捨てられた死者が辿り着く黄泉の国ではないのである。
地上の人々は地上に無い物を見たり探る行為への恐怖心が根強いので、自分達で創り上げた廃棄孔がその後どうなっているのか経過を調べる猛者はいなかった。その為に捨て穴の途中に実は分れ道がひとりでに出来上がっているのを知る者は一人も居ないであろう、またそんな想像をする者も。
もう片方の穴は首吊りの後首を斬られた死体が重なる場所へと続いていたが、もう一方はテアとラティのように生きている命がよいしょと運ばれる道となっていたのである、其の終点が地底世界、つまり地底世界は生者の空気に満ちた秘密の場所なのだ。
コンコンコン、誰かテア達の家の扉を叩く音。
「どちら様?」
扉の向うにはなんとまあ麗しき月の妖精様オオミズアオであった。
気絶したテアをラティはソファへ放り投げ、まだ中身のかぐわしいポットから紅茶を注ぎ、別のカップを来客の前に置いた。パタパタと翼を動かす仕草は、湯気と遊んでいるらしい。
「佳い薫りでしょう?」
パタ。
ラティの問いに翼一回。よくある手法、はいは一回いいえは二回。
「すいませんね内の主人が。お客見た途端直立したまゝ後ろにビターンと倒れるなんてさぞ御不快でしたでしょう。」
パタパタパタ。気にしなくて良いは三回。
「それにしても、如何して此方に?何か俺達に用ですか?」
パタ。
「ほう。どのような御用件なのかお聞きしても?」
パタ。
一度翼を動かした後、自分の袂に息吹くように少し首を曲げて己の翼にふっと息を。鱗粉は机に文字を連ねこう話す。
”わたしに名を与れないか”
俺は良いけど妖精様、テアは鼻血を吹くかもしれませんよ。
五
鼻腔に脱脂綿を詰めたテアの顔面を見た者は残念がるよりも先ず其の瞳の色に目を見張ることであろう。緋褪色だった筈の眼球は忽ちに秘密の色―新月の色に染まり、光を知る瞳へと花弁を移ろわせた。己の見込んだ娘の情熱は冬の川底に蹲る氷のように心を煮え滾らせていると確信を得た月の御使いは炎を討つ一手を掌中に納めたも同然。
「すばらしい御提案だわ。是非わたくしにお任せくださいな。」
紫陽花のように微笑む者よ。懐旧と寂寞を羽に染めた蛾はパタリと家を後にした。
「テア、どうするつもりだ?」
「ラティ、これは大きな仕事よ。妖精様の名付け主になるだなんて、地上に居た時は想像するのも畏れ多かったのに。本当なのね、現実なのね、夢の国なんかじゃないわ。」
弟に聞かせてあげたい
「テア。」
「紅茶を飲みたい時は声を掛けてね。それ以外の時はなるべく話し掛けないで。兎に角想い出さないと、生半可な言葉は私が許せない。」
美しい、と感じる繊毛は心の奥にあるんですって。
心臓に毛が生えているの?
違いますよ姉上、心臓と心は似ていても別物です。心の奥には祠のような場所があって、その場所を細かくて澤山の糸が花嫁のベールのように覆っているのです。
その糸達が感情を操っていると言うの?
操り糸の類ではありません。詩集糸のお仲間なんですよ。
まるで昆虫の体毛のようね。
あゝ、似ているかもしれません。昆虫も人間も等しい命を持っていますから、根っこは同じなのやも。双方共植物が無ければ生きていくことは叶いませんし、花を愛でることも知っている身ですもの。
あゝ、ほら静かに。そろそろ蛾がやって来るわ。えゝと、確か…
オオミズアオ、ですよ姉上。
そうだったわ、そんな名前だったね。
あまりに貴方が真剣に言葉を返すものだから、あの時は可笑しく感じたのよ。今、私がオオミズアオの名付け親になると教えたらどんな顔するだろう?
想い出に浸り涙を伝うテアの横がほ。ラティは言葉も無く甘く苦く舌に残る金色の紅茶を啜る。
六
地上では雨が降っていたので、人々は一日中製氷機で作った氷をバリバリと食べ続けている。一見因果関係が無さそうな行為だが、実は本当に互いは無関係なのだ。じゃあ何故こんな事を?此処からは書き手の仕事と言うもの、簡潔に読者へ話をしなければ。
気まぐれ。
七
地底の世界では地上の世界での天候がそのまま伝わる。なので此方側も雨降りなのだが、ほんのちょっとだけ種類の違う雨なので。水が落ちて土に沁みるのではなく、鳥の羽や虫の羽、花びら達がひらひらと淡雪のように地面に触れては溶けていく。
「あゝ、向うでは雨が降っているのね。」
星屑の蜜漬けをお茶うけ用の小皿に出す、その皿はどなたが見てもキュートと感じる仔猫の顔を描いた物だった。
「おい嫌味か。」
悪かったな野良猫でも飼い猫でもない異様の猫で。
「失礼なこと言うのね!ラティの顔に私は嫉妬しないわよ。」
「おいどういう意味だ。」
下手くそな口笛で誤魔化そうとしやがって、目ェ泳いでるぞ。
「姫君への捧げ物は出来たのか?」
雨が降っていても朝は朝だ。昨晩はベッドで眠ることもせずずっと窓辺の椅子から外を眺め続けて名前を考えていた。
「えゝ。貴方が私を一人にしなかったお陰でね。」
椅子の上に置いていた一枚の白紙をリビングの大きな丸太のテーブルに移し、ソファに座りっぱなしの俺を普段通りに抱きしめて想いの込めた文字を見せてくれる。
「シファ。私達の故郷の言葉で”雲に笑う月”と言う意味よ。」
テアの弟はトノンと言った。彼女達の言葉で”おとなしい子”を示す言葉であった。名前の由来は胎内から這って出た時一声も産声の泣き声を発すること無く、もうすうすうと確かな呼吸をして血塗れのまま眠っていた事からだった。成長しても甘えることはあるが涙を流すことはせず、いつもおっとりした微笑みを唇辺に湛えている不思議な子、その為家族からは愛されたが他人からは不気味がられる、本人は視線の鋭さを肌に感じていたが弱音も泣き言も涙も一切表さない。両親を流行り病で亡くした姉弟は国の建てて運営していた教育施設に住むことになった。
テアは施設でいじめられた。彼女の瞳は此の国の住民達と違った色をしていたから。正統な瞳の色は朱華色の黒眼であるのに対しテアの黒眼は緋褪色、人は僅かな違いを大事にする天才だ。
「弟と色が違っている。」
それが何だと言うのだ
「血が繋がっていないんだろう。」
弟が生まれるのをこの目で見たもの
「どうせ姉貴の方は異国の奴原の誰かとの子だろうさ。」
もう私達の故郷は無いのに。
祝福の真綿の薔薇で育まれた者はもうそれが手で触れられないものだと知るとどうなるのか。
「寂しいよお父様、お母様。」
或る子は真夜中、弟を寝かしつけた後声を殺して泣くのである。そしてまた或る子は
「姉上、もう大丈夫ですよ。」
朝日に染まる中で真綿の薔薇を空から自分の手中に引き摺り下ろして来るのである。
自分をいじめていた男の子達が可愛い弟の手で次々に殺されていくのを見ている時、悪い夢だと祈った。これは私が勝手に一人で見ている悪い夢、自分に腕力が無いから弟に任せてしまっている悪い自分の身勝手だと。でも、弟が施設の大人達に褒められて、頭を撫でられて、それで私にバイバイと手を振って大きな影に囲まれて施設の中に戻って行くのは、私が望んだこと?
トノンは国の兵隊さんになるんだよ、とだけ言われて、昨日私の食事を運んで来てくれたおばあさんに手を曳かれ門の前まで行くと通帳とカード、それから住所の記されたメモを渡された。
「必要なお金は全部その通帳に入れ続けるから心配しなくて良いよ。これは貴女が今日から一人で暮らす家の住所。道が分らなくなったら大人に尋ねなさい。子供を連れていない大人なら誰でも良いからね。」
おばあさんは私の頭をひとなでしてから施設へと帰って行った。
一人ぽっちになったから、施設では絶対に口にしてはいけないと禁止されていた言葉を呟いた。
「シファ。」
八
兵隊工場を管理する国家が掲げる国旗は白い雲と血色の太陽がそれぞれ太い輪郭で描かれており、太陽や雲を揶揄する言葉はとある一点の時から禁止されていた。その一点とは夏の太陽と冬の月の戦争であり、これが為に国の人口は四割ほど減ったが、太陽の勝利により人口の減少は一旦止まった。それから後は月は悪とされ、空にある内太陽と雲が最も位の高い存在として崇められるようになっていった。
とは言ってもこの戦争は伝説に近いような扱いを受けていたので誰も歴史の一つとは認識せず何處か遠い場所での物語として人々に信じられていた。テアもこの話を学校で聞いて育ったのである。
”シファか。すてきな名前だ、有難う。”
あこがれの月の妖精はテアの仕事に感謝を述べると、彼女の肩にそっと留まった。
”私に佳い名を与れたお礼に、私からも一つ贈り物をしよう。”
畏れ多い、と断る前にテアのお人好しな気質を隠せぬなで肩から小さな腰の辺りまで一筋雪の欠片がつうと背中にじゃれたかと思うと忽ちにパステル淡い綿飴の姿を借りた人の目には捉えきれない月の瞬きのレエスカアテンがふわりと娘の体躯を覆った。いとも清らな外套に抱き包まれた處女は初心に両頬をぽっと恥ずかしむる。
「ラティにも与えてくれませんか。この仔が居なくては貴女へのお名前を思いつくことは出来ませんでした。」
パタ。
「ずうずうしい主人を持った山猫を哀れと思し召しませ。」
パタパタパタ。
蛾の顔には人目で分る表情と言うものは備えつけられていないが、その代りに彼等彼女等は羽音で気分を伝える事を習得していたのである。(羽を持つ蛾の成虫のみに限る話ではあるが)今シファがラティの周りをくるくると泳ぐのは非常にご機嫌な音符を飛ばしている最中で。
そもそも月の世界には苦しみも悲しみも無いとは古来より種々の国の昔話でも語られていた。喜びと幸せに満ちた国と言うのは全くの嘘ではない、むしろ何故人が月の世界を完璧に想像し得た事態の方が不可思議である。だからと言って蛾が正の感情しか認知し得ないと決めつけるのは暴論である為補足をさせて頂く。
この宇宙に月だけが存在しているのであれば蛾は負の感情を到底知る道理も持たなかったであろうが、銀河はもう少し複雑である、太陽系と纏められる星々は精緻な譜面の如く絶妙な距離を保ち続けながら歌を歌い合う。それは叙事詩であったり悲劇であったり軍記物神話伝承物語…それら様々の旋律を知る生物が、単純なコードだけしか知らないと思うのは真ッ当とは褒め難い。よってシファが喜んでいるのは澤山の感情の中で選び取った結果だと筆者が説いても、もう依怙贔屓ではないと納得してもらえたであろう。
「まあ可愛い!とってもすてきなお帽子とマントだわ!」
もこもことした赤ちゃんアザラシを模した円い帽子にはきちんと両耳を出せる穴があり、マントは色づく木苺の森と日暮の色に染まる丁寧なグラデーション、裾にはグレーのフリルも付いていた。
テアとシファの共通の趣味であるのはふたりのキャッキャッとはしゃぐ声で分るが、ラテイはどうやらこのようなジャンルの服は初めてらしくムツッとした三角口は普段より一層頑なに見える。
「シファさんよ、楽しいのか…?」
パタ。
パタ。
パタ。
「シファ様は喜んでいらっしゃるけれど、ラティは嬉しくないの?」
「うむ、むむぅ…」
曖昧な返事は素直になれない証拠である。主人が楽しそうにしているので此方もにこにこして話したいが如何せんこの表情では不釣合も不釣合、滑稽を飛び越えて不気味にしか映らないであろうと正直になれない寂しがりやが思い直す。
「ラティ、貴方がどう思っていても、私にはとても似合っていると感じるわ。だって、ラティの性格をそのまんま服にしたようなんですもの。」
あゝ、そう言ってくれると有難い。
「じゃあそういうことにしておくよ。」
気難し屋は素直に喜べと言われても出来ないのだ。
「シファ様、あの、私達に褒美をくださったのは心底より嬉しいのですけれど…何故、お名前が欲しいと仰有ったのですか?教えていただきたいのですけれど、しても良い質問でしたか…?」
羽音が一つ空を切ると家の中にある窓は総てぱたぱたと閉められて木枠はかちりと錠を下ろす、カアテンは悉く幕を引いてアンコールも要らないと沈黙する、すっかり暗くなった家の中で灯るのは、月の生物の身体のみ。
「テア、俺を抱っこしておけ。」
ぬいぐるみの身で野生の勘と言うのを諸君等笑い給ふな。人がぬいぐるみを胸に抱きしめる時、可愛い物を手離したくなくなる時はどのような状況にあるか想像してみると良い。
テアはラティに言われた通り傍に居た彼を胸の中に抱きしめた。暗闇の中で鱗粉の光が文字を並べる。
”今から話す物語は、貴女には酷なことになるに違いないわ。けれど私は語ります。その後テアにどう思われようとも。”
返事を待たずに始めたのは、娘の瞳が嘗て新月の色へと変ったことを知っていたから。
九
真夜中に物を考える癖のある女が居た。女は主婦であった。日中から日没迄は家事や仕事で忙しいがひと段落すると物思いに耽るのが常々で、その際には毎回と言って良い程世間を嘆き愁言を吐き明日の献立を呪った。子供の前で地球が人類を滅ぼそうとしていると朝から話をして自分は晴れやかな顔で家を出て行くのはよくあった。子供は男の子であった。
彼は母親も父親も賢い兄も居たし、生れて以来食事を我慢することも肉体を苛まれることも無かったし暑さや寒さに怯えることも教育を受けさせてもらえないことも何一つ無かったから、自分は恵まれているのだと信じていた。
恵まれている者は、親を疎んではいけないと。
けれどそれは正しくはなかったようである。子が親を疎んではならぬと戒めたとしても親はそんな小さな鎖では物足りない。子が元気になれば親は腹を立て、子が塞ぎ込めば親は腹を立てる。毎夜左腕をカッターナイフで傷付けなくては子の怯えは拭えない。
我が子を疎んじる親は他者の痛みに敏感なのだ。
「もっと俺が兄さんみたいに優秀だったら」
「産まれたいなんて願わなければ」
「夜が怖いよ」
呟きは一人だけで繰り返すもの、反復は確信と自信を与えてしまうもの。
若し月の昇らない世界だったら、自分は正しく存在出来ていた?飛躍は不安の相棒である。
この時男の子は初めて憎しみを認めることが出来た。そしてそれは月への攻撃に紐付けられてしまった。
「雲隠れの月、とは縁起の良い言葉である。月とは太陽が輝かねば光を発することの叶わぬ天体の中で最も愚かな惑星だ、それを棚に上げて自分は人間を慰め傷を癒やす存在だとつけあがっているのが現状、その証拠は古より記されて来た書物や本が示している。
惑わされるな!月とは人間が本来直視してはならぬもの、だが太陽のようにそれを人に教えようともせず、淫猥な醜体を我々の目に映じさせ心を狂わせることを楽しみとしているのだ!現にどうだ、諸君等が病院で見た精神疾患者達に月は救いの手を伸ばしているか?否、否、否!彼等は哀れにも太陽に震え光を拒んでいる、そして嘘の光に救いを感じている、祈りを捧げているではないか、偽善の神に。このような悪循環は断ち切らなくてはならない、我々は人を月と言う悪魔から守る為に戦うのである!」
テアに雑草と蹴られた樹に登り、声も朗々と演説をする者が居た。その横には護衛であろうか、二人の若い兵隊がきちんと立って演説者である上官、軍の最高司令官に規則正しく拍手を贈る。にこやかなその表情は、最愛の姉をいじめていた下衆共の首の骨を折った時とおんなじで。
トノンは地上の有能な兵士となっていた。姉上の居場所は把握していたが、数日前から行方が知れない。目撃証言に依ると屑捨て穴に自ら入って行ったらしいが、それは有り得ないことだ。
「僕のことを大切に想う姉上が、そんな愚行に走る訳が無い。きっと幼い時よく遊んだ隠れんぼをなさっているのだろう。」
僕は見つけるのは不得手でしたけれど
「姉上、今に見つけますよ。もう幾つ数を数えたでしょう?」
ふふふっと笑う両頬は、姉と瓜二つの愛らしさ。
十
蛾は夜のもの、蝶は昼のもの、と言う古い科学論は地上では未だ人々の意識に根強く残っている。その為地底世界に住まう蛾達は地上へ現れる際蝶々の格好をしてやって来る。シファも例外ではなかった。
”地上では常に火を焚いているわ。炎を絶やさず繋ぐことが肝要だと思っているのね。けれど、地底にまで火を届かせることは出来ていない。”
「まあ当然でしょうな。地上の奴は地面の下のことなんて考えるのも嫌な筈だから、永遠に手をこまねいているだろう。」
「その永遠の内に、トノンは死んでしまうわ。そんなに出世しているなんて思わなかった、だって、あの子ったら、軍の話はちっとも手紙に書かないんだもの。」
いつか嫌気が差して自分の一人暮らす家に来るとばかり。
「嫌々してるんなら、出世街道は外れてた筈だ。どうやらおまえの弟は軍に賛同しているらしい。」
まだ実際に面を合わした事が無いから何とも言えんが俺の嫌いな顔立ちの野郎に違いない。
”本音で従っている訳ではないかもしれん。本人に聞かないと分らないな。”
家族を人質にされている可能性だって。
さんにんは顔を付き合わせて三角形に話し合う。つまるところ、地底は地上と戦うことになるのだが、作戦本部はこの家だった。
地底世界に住む者は、少しずつやって来る前に居た地上での記憶を忘れてゆく、その為長く住んでいる者ほど地上の事を憶えておらず、来たばかりの者は記憶が新しい、そして地上への敵意もまだ新鮮なのである。
地上の街の構造はシファ達が蝶々の姿で探り入ることは出来るけれど、蛾の言葉を人間は解せない、だから言語で通じ合う為には代弁者の人間が必要となるし、そもそも虫達だけで人を圧する事は一時的にしか出来ない、人が徒党を組むのならば此方も人と手を組まなければならない。
”地上世界から此方に攻撃を仕向けて来る事は可能性としてはとても低い。けれど此方から襲撃を受けたら当然鎮圧の軍は出すでしょう。”
「その隙にトノンを探すって?いくら何でも無謀が過ぎる。俺は反対だ。」
「違うのラティ。トノンが自分から私を探しに来たら良いのよ。そうすれば地上も地底も血を流す必要は無くなる。」
緋褪の色は既に黒く日が沈んだ空を映していた。
「………気の狂った女ってのは縋る物を持っているもんだ。俺を抱きしめていたら、ちょっとはらしく見えるだろう。」
”では第一段階と行こうか。私達が地上へ通う時に使う室へ案内しよう。”
「ラティ。」
「傍にいるさ。」
ふたりの暮す家を出て、地底世界の土を歩く。足を一歩前にやるとぽぉんと鍵盤の半音が鳴る、また進むと今度はヴィオラの弦の震動、マンドリンのもがくような手、ハーモニカの遠い音、チェロの宥める指先に、まくし立てるクラリネット、土はこぽこぽと音を鳴らす、これは少なくとも旋律でも奏ででもない。だけど音符はこう揃う。
行きたまえ地上の娘哀れなる者
氷を掻き消した炎達を
今度は水で串刺しだ
怖いことはお言いでない
マダム・アップルパイ酸っぱい口で
哀れな娘を助けたの
でもねマダムは佳いにおい
みんなみんなに食べられちゃった
哀れな娘は結局は
火で炙られてしまうのさ
楽器全員がその国で作られた訳ではないが、此の歌は確かにとある国の、嘗ては国を名告り存在していた場所の、童唄のようなものだった気がする。この後娘は助からないのかと隣に陳列されていたハムスターに問うたがその返事を言う前に幼い手に連れられて行ってしまったから分らずのまんまになっていたのを、今土の音を聞いて思い出した。
「どんな文句を言うのかちゃんと考えてるのか?」
「とりあえず雑草って呟き続けようかなって。」
「作戦とも言えない作戦だな、単語に謝るレベルだぞ。」
「ワンパターンすぎるかしら?」
「狂女の出てくる物語とか知らないのか?」
「そんな紅茶ないもの。」
ラティの短く作られた片手が額に添えられた。シファさんも何でこいつに大役任せたんだよ、どういう算段だ?
疑問ばかり浮ぶ平常ではらしくも無い小さな山猫が珍しいのか主人である娘は呑気に笑う。
「大丈夫よ山猫ちゃん、地底に来られた私達ですもの、上手く行く為の力を持っているに決まっているわ。」
”テア、その言葉を忘れないでね。自分を守るのは自分の言葉だからね。”
小さな娘不吉な瞳と忌まれた記憶の深いテアは、人の話し言葉をよく覚えない癖があった。ラティは人間ではないしシファに到っては会話は書き言葉だ、トノンは無口な子だったから喋ったのは極く僅か、食事を運ぶおばあさんはこれからの生活に必要な情報だったし、悪口はやはり忘れ難いもの。
”テア。”
シファ達の地上に出る為に使うと言う室は抉られた岩山の奥、人の口で例えるなら親不知の位置に相当する洞穴であった。地上の世界に出る際は地底の世界の風景を持って行ってはならない、此処での道に咲く山百合は彼方側では最も恐れられている曼殊沙華に映ると言う、つまり地底に住む者の眼と地上に住む者の眼の見え方には大きな差異があると言うので。だから洞穴の暗さに目を慣らしてから飛び立たなくてはいけないと此の場所が選ばれ続けた訳である。
シファの呼び掛けに振り向いたテアの瞳に、戸惑うような文字が並ぶ。
”君は、ご両親の言葉を憶えているかい?”
相棒を抱く手に力が微かに加わったことを知るのは……
十一
「両親は姉上の両眼を祝福していました。毎日言葉を掛けるのですよ、月の衣をかみさまにかぶせていただいたのだから、その瞳を大切にしなさいと。姉上もまたその言葉を聞いて笑顔で頷かれていました。」
またトノンの姉上自慢が始まったと宿舎で同部屋の者達は笑いを零した。
「月の衣、なんて俺達地上軍の敵じゃないか?」
友人は言葉の字面こそ激しいが、その顔は締まり無く緩く笑っている。部屋での談笑をする時、彼等は兵士ではなくたゞの青年に戻るのだ。
「そんなに綺麗な瞳だったら、一度お目に掛かりたいまんだな。」
「姉上を邪な心で見るのは許しませんよ。」
「邪な気持ちからじゃあないさ、毎晩おまえの大好きな姉さんの話を聴いていたら、会いたくなるのは自然なことだろう。」
「トノンの話から推測するに、よほどの美人さんだぞ。」
「優しい方なんだろうなぁ。」
「可愛い洋服とは着せてあげたいなぁ。」
「ぬいぐるみとか似合うんだろうなぁ。」
なぁなぁと若干鼻の下を伸ばす友人達の恍惚とした表情で、如何にトノンが姉を神聖視しているのかを読者諸君にはご想像願いたい。
一方その姉はと言うと。
「目の色を変えて貰えたから、この恰好ならすぐトノンにばれてしまうことも無いでしょう。」
昔母親が読んでいた何處かの国の物語、その主人公は書生の身装 で柳蒲の質と心配したくなるが中身は自来也風来坊、自慢の腕っぷしで悪どい輩をばたばた倒し、人質姫君を相棒の馬の背に乗せてハイヤッと一声涼しき雄叫び、颯爽と駈ける黒髪の汗は天の与えた白露さながらであろう清らかさ。せめてお名を聞きたいと縋る民衆の諸手をさっと払って懐に無造作に突ッ込んでおいた黒い学生帽を深く被り白歯の微笑み不敵を露わにじゃあなと一言立ち去る隼人、後には塵も残さない。…その青年の真似をしようとしたのだろう、眉目秀麗は否めないが如何せん、その……
「おまえ何かチンチクリンだぞ。」
「言わないでよ!」
背丈に似合わぬ袖の長さ、踵で踏んづけぬように白脛まで捲った袴、そしてぶかぶかの帽子に馴染まぬ高下駄、これでは…
「貧乏書生って出立だな、なんだか見ていて悲しくなる。これが切なさってやつか。」
ぬいぐるみの心情をまた一つ知りうんうんと納得気に頷くラティ。
「シファさんに言われたろう、洞穴から出る時はイメージを崩すなって。だからそんなさもしい格好になったんだろ。」
「貴方は見事に可愛いお人形になったのね?」
じと目で見やる相棒はいつもの無愛想ね山猫の姿ではなく、もつれの無い金髪を華奢な肩までくるんと伸ばしたボブカット、前髪は瞳に掛からぬようまっすぐパチリと切り揃えられて青い瞳がぱちりとときめく、パフェのようなメイド服を見事着こなしたドール人形へと変貌している。のだが、
「見た目は可愛くなっても声はそのまゝだ。」
キュートなお人形の声は渋い。
「黙ってたら大丈夫よ。演技をしなくちゃならないのは私の方よ。でもどうしよう、こんなしみったれた服装になるなんて早速予想外だわ。地上世界の住民達に変な目で見られてしまわないかしら。」
トノンが姉の声は天上の玉響の調べだと自慢しているのを彼女は知らない。
「弟なら会ったら分ってくれるんじゃないか?軍部の近辺で物乞いしている没落貴族の一人息子、って設定で街を歩いて行けば、少なくとも殺されることは無いだろう。そのまんまテアとして歩く方が危険なんだから。」
雑草、と罵り幹を土足で蹴った前科が。
「じゃあこそこそ路地を行くより、大通りを歩いた方が良さそうね。疑われることもないし、地上世界は生きている者には憐れみを掛けるから、上手にやれば軍部に行くことが出来るかもしれない。」
「シファさん達は付いて来てくれないぞ。本当にいいんだな?」
「えゝ、良いわ。」
テア達は街の外れに飛ばされていたが、すぐに中心部に向ってよろよろと(演技)歩き始めた。するとどうだ案の定、
「其処のお兄さん、大丈夫かい?」
「服がぼろぼろだわ。」
「未だ生きてるみたいだ、手を貸してやらんと。」
貧乏学生をあわれみ心配の声と救助の手をさし伸べて来た、此処からは如何に不憫に魅せるかが鍵、
「幼くして生き別れた兄の夢を見たのです。その夢をもう一度見たくてならない、中心部の樹に触れればきっとその願いが叶うだろうと……あゝ、お兄さま。」
両手で顔を覆って肩を深く落す、落胆の声は少しずつ小さくか細く震わせろ、相棒の内緒言葉での演技指導に隙は無く
「お兄さんを探しているのか。」
「きっとこの地上にいる筈さ。」
「そのお人形さんはお兄さんから?」
騙され始めた住民に涙を拭う動きを見せて恥ずかしそうに斜めに俯向き、汗ばむ清いうなじをチラリ、と。
「兄が私に与れたのです。おまえは女の子に似ている顔立ちだからお人形を抱いていろと、おまえを守ってくれるからと………」
今度は今までより少し長い無言で、心の疲れを示すんだ。
「………」
「………」
「………」
「………」
沈黙が続けば次は提案が挙がる。そしてその傾向は
「なあ、オレ達も一緒に探してやらないか?」
「私もそう考えていたところよ。」
「こんなぼろ切れみたいになるまで探し続けて来たんだろう?でももう安心しろ、おまえさんの会いたい樹様は此の街の中心部にあるからな。」
「ほら、この荷車に乗りな、樹様の元まで運んであげるよ。」
「少し横になって休んでいると良いわ。此の街に来るまで大変だったでしょうに。」
今目の前に居る者の境遇を正反対の境遇にしてやりたくなると言うもの、つまり
「上手く樹の所まで行けるってこと。」
お人形の頬にキスをした。
十二
この樹を雑草と唾棄して靴のまゝ幹を蹴りつけた娘が居たそうだ、つい、数日前の事件だよ。同部屋の友人と樹の警備に就いた時、そう教えられた。何でそんな事したんだろうと呟いた彼に、こう答えた。
「樹の下の世界に行きたかったんじゃないの?」
友人は案の定笑い、そんな筈は無いよと宥めた。
「だって地上世界の他に世界が存在している訳無いじゃないか。地上世界の下には死しか居ないぞ。」
丁度その時交代のタイミングで、彼との会話は此処で終ってしまったのだが、今また部屋に全員戻って談笑していると、その続きを話せる機会が巡って来たので、語ってみる。
「北欧神話を知っているかい?」
軍の者達は古今東西の神話を学び頭に叩き込まなくてはならなかった、それは昔警察が犯罪について学ぶのと同じ理由である。
「あゝ、知っているとも。学校では必修科目だったもの。」
「その神話が例の小娘の事件と関係があるのかい?」
「勿論あるとも、だから話すんだぜ。」
トノンは少々勿体ぶってベッドから身を起こし、三人の顔を交互に見つめつつ先に進む。
ユグドラシル。それは北欧神話の舞台となる世界の土台に存する大樹で、九つの世界に根を張っていたと人々は考えていた。
「九つも世界があるのですか?私達が住んでいる世界の他に、後八つも?」
少女の声が外から聞える。まだトノンがトノンと名を持つ前、母親の子宮の中で羊水を伝って外界とのやり取りをしていた時のこと。この少女は毎日自分に話し掛けて来る声の内の一つであると赤子は知っていたのでよく耳を澄ましていた。
水銀色の胎内は小川を模した真鍮色の羊水にうっとりと包まれて、赤子が耳を傾ければ紅鶸の頭が覗き、手を伸ばせば水浅葱の菫が咲く、口動かすと白鼠が走り目を潤ますれば碧瑠璃の声がする。
「では生れて来る私のきょうだいにも教えてあげなくてはいけませんね。いつか澤山の世界を見に行きましょうね。」
その声はいつも赤子に物語を教えて聴かせた。
「ユグドラシルの根は、天上や地上だけだなく地下にも降ろされているんですよ。とても優しい樹なのです。」
「死の世界は不浄のものとされてきましたが、黄泉国とは死だけでなく生をも司る大地を治め導く為の国であるのです。その最も有名な例が、伊弉冉尊なのであります。」
「太陽は月と結ばれたいと願いましたが、月のしなやかな弱い身体では太陽の傍に居続けることは叶いません、月に死んでほしくない太陽は泣く泣く月を湖へと突き落さねばなりませんでした。」
「こうして仔兎は月へ旅立ったのです。そこから私達の国ではお月さまへ帰る、と言う言葉が誕生したのでした。」
「蛾は蝶に比べ嫌われました。街灯に群がる醜い虫、蝶のように美しい色を持たぬ虫として人々から石を投げられたのです。」
読んでくれた物語の中でも、蛾の御伽噺にはお決まりの救いが無かった。悲しそうな声はそれでも日毎蛾の物語を読み続けていたので、或日少女がお母様と呼ぶ女性に訊かれたことがある。
「テア、どうして毎日そのお話を読んでいるの?読んでいてとても悲しそうだってお父様も心配なさっているわ。辛いのなら無理して読まなくっても、他のご絵本を選んでも良いのよ?」
碧瑠璃は答えた。
「だって、可哀想だからって放って置いてしまえば、この仔は本当に可哀想じゃありませんか。私はこの仔が好きなんです、だってこの蛾は、私に、…似て………」
「あゝテア。」
「澤山の世界があるのなら、何處かに必ず蛾を大切に想える世界がある筈です。お母様、お気づきになって?お月様と蛾の羽はよく似ているんですよ。」
「そうね、その通りだわ…テア、貴女の瞳は特別に月のかみさまが衣をかぶせてくださったのかもしれない、いいえきっとそうよ。貴女がこんなにお月様を慕うのは、月のかみさまが貴女を心から愛してくれているからだわ。」
「月の、かみさま?」
「えゝ。とてもお美しい蛾のお姿をしていらっしゃるお姫様。」
「本当?その姫神さま、何處にいらっしゃいます?」
「いつか必ず逢えるわ。きょうだいふたりで探しに行って御覧。」
この時聴いた会話を、自分は今でも憶えている。
「その犯人は、ユグドラシルの話を知っていたんじゃあないかな。ユグドラシルの根が他の世界に繋がっていると信じて、自ら樹に危害を加えたんだ。」
トノンは記憶を隠して友人達に推測を語った。
「そして、呆気無く死んじまったってことか。」
「信じたまま御陀仏なら幸せだろう。」
「それもそうだな。」
犯人が亡くなったのならもう追う必要は無い。三人の態度はそう示している。
トノンにはこの方が都合が良い。
十三
明日自分は非番だから少し本を読んでから眠るからと言い部屋の電灯を消して一人机のラムプに向かっていた。友人達のすうすうと穏やかで規則正しい寝息が耳に心地良い。
(姉上。)
仮に、樹をけなした犯人が姉であるのなら、姉は死んでいない筈だ。自死する為にわざわざ家を飛び出し人目の多い中心部迄走って来るような愚かな目立ちたがり屋ではない。
死ぬのならひっそりと寝所で全身を切りつけるような、痛ましい寂しさを抱えておられる方だ。
(幼い時分に生き別れてはしまいましたが)
両親からこっそりと頼まれたことがある。どうか姉を守ってあげてほしい、と。姉や兄になる者は、そうなりたくてなったのではなく、結果としてそのような存在になっただけなのだと、
「だから、お姉さんやお兄さんの中には、本当はお姉さんやお兄さんに向いていない性格の人だっているの。」
「成長して腹を括れるようになる子もいれば、括れない子もいるんだ。でもそれは、どちらも正解なんだよ、悪いことじゃ決して無い。」
「貴方のお姉さんは、きっと姉に向いていない人なのかもしれない。本人はとても頑張っているし、私達もその事は理解して認めてあげたい。でもね、無茶をしてほしくないの、私達は。」
「父さん達が生きている間は父さん達が守ってやれるが、トノン、おまえにも姉さんを守る力を身につけていてほしいんだ。」
自分達で産んでおいて、などよくある批判は一切湧かなかった。あゝそうだよなやっぱり、と納得しかなかったもの。
姉に向いていない姉だけれど、自分にとっては唯一の姉上だから、自分が守らなきゃいけないと頼まれた時は嬉しかった。この両親は姉上のこともよくお分かりだ、向いていないのに頑張ろうとする姿勢に感動もいぢらしさも抱かない 人達なのだと。自分にはその事実がとても嬉しく思え、安堵した。世間に腐臭を漂わせる人情とはかけ離れた人達なのだと。そんな両親から生れた子だもの、他人に自分の痛みを知ってほしいと願うような娘じゃあない、だから姉上は死ぬ為に樹を蹴った訳ではない。それに、ユグドラシルを信じて声を弾ませていた···
(何かを探しに行かれたのであれば)
私はこの仔が好きなんです、だって
(この蛾は、私によく似ているもの……あの報われない御伽噺。)
澤山の世界があるのなら
(蛾を大切に想える世界がある筈です。そうか。)
「あゝ…馬鹿だな俺は。」
舌打ち混じりに苦笑いして髪をかき上げ天井を仰ぐ。呟く声は友の夢を醒ますには小さすぎた。
「隠れんぼじゃない、これは家出だ。姉上は地上世界から家出したんだ。」
嗚呼にやけることを止められない。
十四
可愛いドールを抱っこする貧乏学生は計画通り樹の近くへと運ばれて来ていた。ゆっくりしていきなさいと人々から清潔な毛布まで恵んで貰えたのを見ると、テア如何にみすぼらしい風で居るのか大概想像されるものと思う。
「目の色が朱華色だとこんなに優遇されるものなのねえ。」
人形の金髪をくりくりと人差し指で弄びながら口を突き出し不満げなテア。
「両親を亡くして、弟とは生き別れて、差別もされてきたのに、この格好の設定よりも苦労が多いのに、実際こんな待遇受けたことないわ。」
きゅるんちお人形は鼻で笑う。
「じゃあそんな扱い受けてたら満足してたのか?姫神さまを探さなくても良かったかもしれないなあ?」
「意地悪山猫は黙ってなさいよ。」
そんな訳無いでしょう。どんな生活をしていたって、きっといつかは姫神さまを探し求める結末に到るでしょうよ。
「ほらな、おまえはそう言う奴だ。」
「どうしてこんなに性格悪いのかしら貴方は。」
溜め息混じりに人形の首根っこをきゅっと掴んですぐに手放す。
「今日は衛兵が居ないみたいね。」
視線を移した樹の周りには街の人達が幹をさすって御利益にあやかろうとする景色。
「これじゃどうやって軍部に行ったら良いのか分らない。やっぱり狂った女の演技をする方が良かったかしら?」
「いいや、それじゃあ軍部じゃなくって絞首台送りになるぞ。そもそもテア、おまえは本来死刑になっている身の上なんだからな。自死したって思われているから街は静かなまゝなんだ。」
犯罪者を見つけた時の街はもうお祭り騒ぎだ。人々はニコニコとしながら処刑!処刑!と朗らかに歌い、屋台は通りに肩を並べてお金の周りもとても良くなる。
「コロッセオを長方形に展開させたら、きっとこの街みたいになるんでしょうね。」
他を虐げるのは生存本能の一種なのかしら、あわれだわ。
「珍しく黄昏てんのか。…どうする?今日はこの辺の安宿探して泊まるか?」
このまま樹を見つめていたら、また地底世界に戻されてしまいそう。
「そうね。」
どうしたのかな、こんなナイーブ、地底住居にいた時は……
”君はご両親の言葉を憶えているかい?”
地上世界なんて
十五
トノンは今日予定通り非番だった。その為街の散策に出ることにしたのであったが、本当は姉を探してぶらついていた。
(地上世界に戻っている確証は無いけれど)
自分に逢いに来てくれていたなら
(若しかしたら、街中の何處かにいらっしゃるかもしれない。)
此の場所では想像力は悪魔に通ずる力だと考えられているから、樹の下にもう一つ別な世界があるかもしれないと想像を口にする事は到底出来なかっただろう、まして自分は軍人の身。肉親にそのような思想犯ありと指を差されゝば、二度と地上世界の光景を見る事は叶わない、姉弟揃って同じ方法で処刑されるであろう。
(本当なら俺が守らなければならなかったのに。)
軍人になったのは姉の今後の生活を保証してくれると知ったからだ。軍に入隊した者の家族や親類達からは国から生活費を出して貰える、必要最低限を遙かに上回る金額を。
「トノン君、君は見事テストに合格した。」
姉をいじめていた年上の子供達を素手で殺し終えた直後に施設の大人達に囲まれて拍手を受けた。
「お姉さんは今後安全で裕福な暮らしが出来るようにしてあげるから心配要らない。さあ、手を振ってお別れしなさい。」
寂しくないように、悲しくならないように笑顔でバイバイ、もう会えなくなるけど僕は大丈夫だよ姉上。
兵舎に入った者は二度と外に住む家族達には会えない。手紙だけが当事者同士互いの無事を確かめる糸なのだが、上官達は兵士の身内の安否を常に把握している。
姉らしき人物が捨て穴へ落ちたと上官からの伝言を仲間を介して聞いた時、上手に笑えていた自身はあるが、やはり張り付くじとじととした雨粒は気分が悪い。
(上官はだまされてくれているだろうか?否、今日に急な非番を入れたのも、俺を泳がす為のものだろう。…嘘を吐くのは得意な方ではある筈だが。)
「仲間にも嘘を吐くのは心苦しいな。」
家族と離れ命を預け合う友、唯一残った家族。それでも選ばなければならない。
(樹の所まで行けば何か思いつくかもしれないな。)
友人の一人は姉に似て紅茶が好きだから、彼への手土産の為に樹の傍の店へ立ち寄ったと釈明が一応は出来る。
「姉上お砂糖は入れないのですか?」
弟のカップに二つ角砂糖を入れ終えて蓋をした姉は微笑んで
「私はお砂糖無い方が好きだから、トノンが使いなさい。」
「苦くありませんか?」
「ちっとも。」
澄ました横がほの暖かい瞳にはあの時何が映っていたっけ
十六
オオミズアオ達は地底の湖畔で星屑の蜜漬けをせっせと作っている。
”お名前もらえたの?”
”いいなあわたしもほしい。”
”なんてお名前?”
”おしえておしえて”
お菓子づくりは楽しまなければ不味くなる。地上の雫をシロップの波に溶かしてころころと好きな形に転がす時に欠かせないのが楽しいおしゃべり。
”シファ。シファって言うの。”
”すてきな響きね。”
”どう言う意味の名前なの?”
”雲に笑う月、と言うのですって。”
鱗粉はからころ地面に文字を描いては、花園の清純なる芳しさを空気中に滴らせる。
月に住まうと信仰されて来た天の御使い達は時折湖で飛沫をぴしゃぴしゃ立てて遊びながらもお菓子作りに精を出す。
”地上世界が誕生してから忙しくなっちゃったわねえ。”
”だって毎日雫が降るんですもの。”
”放っておいたら苔になってしまうわ。”
人間とは常に満たされない精神を孕んでいる生き物である、もはや楽園と信じられている此の地上世界に於いても人は充分に喜悦を抱けず「やっぱり」「もう少し」を繰り返す。最も、地上世界に不満を持つ者は軍の権限に於いて処刑される、その為人々は悲喜こもごもの表情を捨て新たに温和と柔和と喜びだけを示す顔つきへと進化せざるをえなかった、そしてその進化を促したのは月の御使いオオミズアオを始めとする蛾達であった。人間が生き延びていけるように、表に出せない感情達へこっそり地底世界への道を囁く、その導きに連れられて来たのが地上の雫と呼ばれている次第なので。
”シファがお願いした子、どんな子?”
友のひとりに訊かれて答えようとしたシファだが、はたと手を止めてしまった。気遣う友たちの声がぼんやりと聞える、まるで遠くにあるように。お菓子作り疲れちゃった?おもしろくなくなった?手伝うよ、私達は全員このお菓子作るの上手だから。
そう、そうなのだ。星屑の蜜漬けはオオミズアオにしか出来ないのに、
”どうしてあの子、作れていたの?”
十七
甘いお菓子をポリリと食べる、樹の傍にある店の店主に憐れまれたお陰で店の屋根裏に住まわせて貰えた。
「折角シファ様が私達にご褒美をくださったのに、人に見せびらせないのはやっぱり残念ね。」
「この菓子蜜漬けって名乗る割に甘ったるくないのな。」
「貴方にオシャレのことでぼやいても意味なかったわね。」
陽光のきちんと射し込む三角窓から街を見下す。街は数日前から天気が落ち着かず、雪が降ったり雨が降ったり晴天だったりと忙しない。今日はサアサアと風が吹く。
「地上の人達、今日は何だか元気が無いのね。いつもにこやかにしているのに今日はどの人も目が泳いでいて落ち着き無く見えるんだけど、天気の真似でもしてるのかしら。」
「風が吹いているからだ。」
お菓子を食べ終えた相棒がちょいちょいと空を指す。
「風は雲を動かすだろう。此処では太陽と雲が尊いと定めているからそれを好きに散らす風に良い心証を持てないのさ。」
「じゃあ今日は皆落ち着きが無いってこと?店主もそう言えば普段と違っておとなしかったけれど、あの人はきっと普段からお節介焼きで慌ただしい人だもの。今日くらいは安静にして、店の茶葉で淹れた紅茶をゆっくり味わえたら良いのにね。」
美味しいお菓子と一緒に。
「こんにちは。」
金色のドアベルがからんと店主を呼ぶと、人の好い性格で有名な彼はお客に笑顔で挨拶した。
「おや、軍服さんじゃないですか、いらっしゃい!」
その笑顔はまあ青ざめている。
「店長さん、どうぞご無理をしないように。今日は風の強い日ですから、具合が良くない筈ですよ。」
「あゝ、すいませんねえ……この通り今日はお客も貴方一人だ。街の人達は元気に外へ出歩く気力もありませんから。」
軍帽を脱いで胸に抱える
「こんな時にこそ我々が凛と構えて居なければならないのです。だけれども、一人、私の友人がどうも調子が悪いみたいで。本人は認めたがらないでしょうから指摘して休ませる事は難しいし、上官にもお小言を貰いそうなので……彼に、手土産として好きな茶葉を買って行こうと思いましたから、こうして寄らせていただいた訳なのですが。」
「それはまた感心なことで。」
店主の言葉に苦笑いを浮べながらも好意を無下にしない人品の良さは軍で培ったものではない。
「彼は貴方が日毎に気まぐれでブレンドするあの茶葉が大好きなのです。だからこんな日に申し訳ありませんが、一つ頼まれてもらえませんでしょうか?」
店主は頼みを二つ返事で承諾すると店の奥の工房へ向かう為背中を向けた。その無防備をガツンと殴る。
「今、一階の辺りで大きな音がしたぞ。」
姿を変えても流石は山猫、些細な音にも敏感である。
「人の倒れる音だ。」
「店主かも。」
階段を駈け降りる。
足音のする方へ駈ける。この音の距離だと二階からではない、その上、屋根裏辺りだろうか。
シファ様の術を見破れる人間が地上世界に存在していたなんて。
来る。
来る。
手にはナイフを、手には拳銃を、緋褪の瞳と朱華の瞳は鋭い眦を突き付ける。敵意、敵意は窓枠震わす外の風が払った雲で焦点を合わし月を許さぬ日の下に照らされ影を産む。
その影から、ふっと力が抜けていく。金属が肉を裂く音も発砲の音もしなかった、しかし互いの小さな影からは同じ紅絹の衣がはみ出して、それがどんどんどんどん大きくなる。
「姉上。」
「トノン。」
口からごぽりと吐き出す落椿は唇を染め顎を染めて大動脈の流れを辿り地面に倒れ、弱る手と手を互いに伸ばす震えから伝わる寒さ、コンクリートの所為ではない。
長い睫毛は額の汗に閉ざされて、向き合う身体は見つめ合えない。脇に落ちている女の子のお人形の服は臙脂の涙で染まっていた。
鯰の口が大きく開く。
十八
鯰の口、良い例えじゃないか?でもさやっぱり間抜けな面は変えられないや。だってほらそうだろう、自分の身体にもう一つ通路が出来上がっていたら切除するか閉じれば良いのに、まだ知らないでぱくぱくやってるあの生意気な顎ったら憎らしい。いつでも手段は此方にありって余裕かますのが気に喰わん。所詮誰かの飼い鯰のくせに偉そうに。
さあ、反撃開始だ。主従諸共容赦しない。
地底への入口が開いた時、鷹の睨みを以て地上に躍り上がったのはシファを頭にオオミズアオの集団だ。孤月冴かな弦に自らを矢となし迷い無く引かせ打ち給う氷の鏃は厚く軽い雲を羽で裂き日の隠れる逃げ場を霧散させた。返す眦名刀の怨気、畳み掛けるは忌わしの樹、嘗て冬の月の国を蹂躙した巨人の生臭き足の未練へと金の鱗粉を毒花で染めた矢へと変化し天ノ川の激流を叩きつける。根枯れ草枯れ幹は洞に、地上世界のよすがであった樹はこうして命を奪われた。そしてその事実は太陽を罅割れさせ、呆気無く日輪は塵と崩れた。
軍が出動する時をも与えぬ彗星の反逆は、見事夏の太陽の時届かなかった敵の心臓に深く抉る矢傷を穿ったのである。
十九
墓は、地底に建てられた。二つの名の刻まれていない墓を前に一匹の山猫が座って居る。
「わざわざ此の場所に墓を作る必要なんか無いだろうに。」
星屑の蜜漬けを噛る。
「でも信じ込ませなきゃ。人間の娘とその弟は相討ちで死んだってことにしておかないと、地上の人達は見た目に反して頑固よ、貴方みたいに分り易い顔していないもの。」
これは母親から教わったお菓子だから、作り方はよく憶えている。
「シファさん達が地上の空に大穴を開けたからな、直に地底側にもお客が来るぞ。」
「俺の友人達は温厚派が多いが上官はそうじゃあない。地上に反する存在は虫一匹でも認めない奴だ。特に月の虫なんて奴にしてみたら真っ先に殺したい生物だろう。」
故郷が無くなる前はよく見ていたものだ、二人が紅茶時間のおやつを作っているのを。
”地底世界で血を流す事態は避けたい。傷を与えずに命を奪う術は私達は知っている。”
昔仲間の中にその方法に長けた蛾が一人居た。命を吸うのが私の楽しみだと豪語するほど血気盛んな女の子、その所為で人に捕えられてしまって身体を切り刻まれたけれど、躯で散々弄ばれた後子供達は笑いながら去って行った。けれど蛾は肉体が殺されただけでは死にはしないことを人間はあまり知っていない。その数少ない有識者が、彼女の身体を近くの花壇に埋めてくれた。その人間は若い男性で、まだ幼さを残す青年だった。彼の瞳は、トノンの瞳とよく似ている。そして身体を一時失ったあの娘の瞳は、新月の輝きを持っていた。
”最初は似た娘だと思っていたのだけれど。”
「顔が似ている奴は世界中に三人は居るって言われているものな。」
「ラティは一人だけだったわ。」
「俺は大量生産向きな種族じゃない。」
「姉上はもっと可愛らしい動物がお好きなものと…」
「想像してたとおり嫌味な面しやがって。」
「止めなさいラティ。トノンに何てこと言うの。」
「おまえに似てひねくれてるのに素直な野郎ってこと。」
「私のことまで馬鹿にして!」
先刻迄ナイフを握っていたとは思えぬかろやかな腕がぶすくれ顔の小さなぬいぐるみを胸に抱きしめる。その背中にはシファ達と同じ薄絹の衣が背中を覆う。
「そのお得意の嫌味はこれから先の為に取っておきなさいな。折角のもこもこのお洋服が台無しよ?」
山猫ぬいぐるみの纏う外套を指で丁寧に撫でつける。
”変化の術は溶けてしまったが地底では此方の方が動きやすい。”
「もうユグドラシルは在りませんしね。」
軍帽を深く被ぎ、得意の拳銃に弾の代りの薔薇を詰める。
「難民の受け入れに、怖い武器は要らないもの。抵抗する人にはキスをしてあげれば良いだけ。」
その後はおいしいお茶会を。
テアを一目見た地上世界の住民達はその瞳の色に恐れを為した。
「朱華色じゃない。」
「知らない色だ。」
「なんて不気味なんだろう。」
「こっちへ来ないで。」
「あっちへ行け!」
念の為に少し話しておこうか。つい先刻地上世界は幕を引き、今の舞台は地底世界の湖のほとりに移っている。太陽を失った彼等は死者の場所と信じていた地下の地面に足を着けているのだが、もう自分達はすっかり死んだものと恐怖に震えている。
「あっちって、何處のこと?もう貴方達の国は何處にも無いのに、何處へ行けば良いのかしら?」
片方新月片方緋褪の目をうっそり細めて首を傾ぐ、後は満たされるだけの光と初雪を喰らう梅の光は迷い無く人々に囁いてパタパタと人の数は減って行く、ワルツを鳴らした地面の煽りにクスリと口元 外套で覆い踊るをとめ。ほっそりとした腕を伸ばす指先を繋いでいるのはをとめの弟、朱華の瞳を少し恥じるように伏せて引金を引けば淡い李の薔薇の欠片が眉間に眉間に撃ち込まれて人は馬車に、それ曳く馬に、金魚にバッタ、ミジンコほどのカマキリへと元通り。花の銃弾を手渡すのはをとめテアの肩に坐しますムツッと山猫、一分、二分、三分で次の人達とリズムを整えおひげの長針と短針でテンポを刻む。
白い紫陽花に撓うのは名を与えられ女王となったオオミズアオ、またその周りにも銀の王冠被りし同胞達がひらひらと遊ぶ。祝福の天ノ川は女王の頭に燦然と弧を描き食べ物を乞う者達の両手に溢れんばかり積み重なる星の蜜漬けを恵む光となる。
「オオミズアオ様、オオミズアオ様。」
「どうか私達を憐れと思し召しませ。」
「お救け下さい、お赦し下さい。」
押しかける泥々の姿にむさ苦しいとて柳眉を一点も曇らせない。住みたいと思ったのなら今から此処で暮せますよと側近の喋る鯉を通じて衆々へお伝えなさった月の繭。
赦される必要など無い。貴方達が地底世界へ牙を向けたことなど一度も無かったでしょう。
不思議な姉弟が雑踏に入って一人一人に声を掛ける。そうしてしばらくすると、混乱・暴力・恐怖その他諸々は何方へか?新しい住民達の住む場所へ案内する地底の人々、それに深く謝意を表す地底の人々、質問に答える人々、質問をする人々。もうみんな地底の住民へと仕上がっていた!
実に素晴らしい、血を流さず互いが互いを認め合って共に暮す、昔何處かの国では牧歌的として讃えられた光景が、唯一生き残った地底世界で見られるとは!まあ素晴らしい一連を目撃出来て幸いだ。でも、君は?
「トノンめ。冬の月の生き残りと通じていたか。」
敵意ある者達―自らの直属の部下数名―が人ではなくなり、肉体のみを殺されたりしたのを見ていたトノンの上官は敵意を肚深く隠し女王から家を与えられていた。
「トノンの部下(彼は友人と言う表現を決して認めない)達三人は人間のまゝのようだ。彼奴等軍人の本分を容易に捨てたか。」
怒りを煮らして時期を待つ。今一人で暴れてもあの姉弟達の踊り相手になって終りだろう。
(月に縋る奴等は皆殺しにしてやる。)
決意を固めた上官は、此の世界で内乱を企てた。
二十
上官の名前はハップと言い、テア達の故郷には無い言葉であったのでトノンは名前の意味を知らずにいたが、友人の中には各国の言語に明るい者が一人居たので、或晩ハップの単語について説明してくれた。
「ハップって言うのは、昔の物語にちなんで生まれた単語らしい。昔、或る所にお爺さんとお婆さんが居た。この二人は見た目に似ない強欲な性格でね、毎日朝日に向って礼拝していたんだ。近所の人達はあゝ信心深いと感心したのだがね、実は祈りの内容と言うのが大金が降って来ますようにと無心するものだったのさ。口に出しては願いが叶わぬと言うから誰にも他言しない程の慎重ぶりでね。」
「時々罪人を捕まえた時に思わぬでもないが、どうしてその性分を他の事に活かせなかったのかね。」
友人の一人が嘆息をつくと他の三人もうんうんと素直に共感する。
「で?その老夫婦に何が起きたんだい?」
「お天道様も同じことを思ってね。礼拝してくれる行為は嬉しいが姿勢が残念だと。けれど半分の為にもう半分を無下にするのも可哀想だと考えられて、一人の子供を授けたんだ。
その子は赤子だからと譲歩しても度を越えている醜い顔をしている子でね、それが為に親に捨てられたのを太陽様がお気付きになり例の老夫婦の元へと送り届けた、手紙に一言、”この子を立派に育てられれば望む額の金を与えよう”と添えてね。さあもう二人は大忙し。日課の礼拝を済ませたら養う為の仕事に食べさせる為の料理に寝かせる為の掃除洗濯お風呂とまあよく働いてね。」
「この物語の時代には、死ぬ迄働き続けるのが常だったのかな。強欲の後ろ盾があるとは言えパワフルだ。そして、望みは達せられたのか?」
「此処からが面白いんだがね、最初は金の為ならばと堪えていた不細工顔が、ある時ふッと可愛く思えた。これには二人とも驚き互いに顔を見合わせたが、その時何十年振りに笑ってね。育ての親が嬉しい笑顔をしていると子供も嬉しいと感じてさ、伝わるんだ親の感情と言うものは。家族三人で笑い合っていると、頭上から声がしたんだ。」
「大方太陽様のお声だろう。」
「そうさ。お前達はその子供を見事育てあげたから、子と引き換えに望みの金を与えようと仰有った。けれど…」
「二人は首を横に振ったのか?」
「金はもう欲しくありません、以前のわたくしどもはさぞ浅間しく卑しい人間でございましたが、この子のお陰で人の心を取り戻すことが出来ました。後生ですからこの子をお引き取りなさることだけはご勘弁を…と平に伏して言うんだね。
太陽様はにっこりなさって、宜しい、三人いつまでも仲良く暮らしなさい、と仰有って、後にはまた普段のように近所の生活音や人の話し声が聞えて、もうお天道様は黙られた。」
「へえ…見事なハッピイエンドじゃないか。」
「優しいお話だったね。」
「でもハップの語源は結局何だったの?」
「話は最後まで聞き給え。改心したお爺さんとお婆さんは、太陽の祝福と言う意味を込めてその子供にハップと名前を付けました、めでたしめでたし。」
「子供の名前だったのか。」
「太陽の祝福か。まさに上官にお似合いの名前だな。」
トノンはこの時冷汗を覚えた。月の祝福を受けた姉と、太陽の祝福の意を抱える上官。
(否。瞳のことは上官も知ってはいるだろうが、母上の仰有った言葉までは知る由も無いだろう。俺も家族のことは友人にも話さないし…いや、むしろ逆に…)
「じゃあ次は、自分の姉上の話を聴いて下さいますか?」
勿体ぶった言い方でトノンの姉上自慢はこの日から始まった。
敵にみすみす自分の弱点を晒す行為は、完全な服従を示す行為である。それ故トノンは上官から睨まれることも無く、信頼出来る部下、軍人の鑑と称されて信任厚く汚れ仕事にも異を唱えたり反発したり疑りの眼差しを持つ事も無い。
「俺達もまんまと騙されていた訳だ。」
「敵を欺くには先ず味方からと言うだろう。トノンは俺等の人柄を信じてくれたってこった。」
「軽口ばかりの剽軽野郎達をな。」
「違いない。」
はははと三人愉快に笑う家の中、トノンの友達は地上世界が崩れて地底へ辿り着いた時、人を辞め始めているトノンの姉を見た。写真も似顔絵も彼は拒んだのでどのような相貌をであるかを三人が知る術は無い筈なのだが、初見、一見で直ぐに理解した。我々が傅く存在と同等の力を持つ存在だと。月の寵児、月の祝福、この小さい方は人に敬われる為に生れたのだと。涙を零して自身等の浅間しさを詫びどうか哀れと蔑み下さいと額を地底の土にこすり付けた、汗の止まぬ波立つ背中を撫でたは尊き御手、汚れてしまいますと慌てて距離を取ろうと焦る彼等を宥めたのはトノンであった。弟の顔を見て頷くテアはも一度三人へ歩み寄り、此処で生きたいと願う者を此の世界は拒みません。大切な弟のご友人、浅間しいなとど卑下なさらないで。私がこの子の傍に居られぬ間、トノンをよく面倒みてくれました、また姉弟が会えたのも貴方がたの御功徳に因るもの、心からお礼を申し上げますと、反って深々と頭を下げられた。も、勿体無い、勿体無い、どうか頭をお上げくださいと一層慌ててしまった彼等に柳眉明るく微笑み照す。
「俺今でも想い出すと鼻血吹いて倒れそうだ。決して助平な意味ではないぞ、その……なあ、おまえ達二人も分るだろう?」
「あゝ皆迄言わずとも、だ。」
「あんな御方軍部に居た時も見た事無かったもんなあ。」
地底世界に軍は無い。地上世界で厳格な生活を送っていた者が此方側に暮らし始めて気が緩むのも当然で、本音を吐露するのも当然なのだ。
こんな世界が地上の下に在ると知っていたなら、もっと早くに此処に住んでいたことだろうと呟いた一人の声は他の二人の耳にも届き同調の意を催したが、彼等はハップが未だ人間の姿で生きている事実を知らなかった。
二十一
「私は上手に出来ている?」
トノンは疲れていたのかぐっすり眠っている。また虫や鳥の翼が花弁交じりに降って来る雨の景色を眺めながらテアはぽそりと呟いた。
「月の祝福を受けた者らしく、振舞えている?」
ラティ。ラティを抱きしめたい。自分の肩を抱いたぐらいでこの震えは治まらない。
「踊りは苦手なの。」
早く帰って来てラティ。またいつもみたいに嫌味を言って、お小言を聞かせて。脛を圧迫しても息を止めながら深呼吸しても紅茶を三杯飲んでも穏やかな花の香りをかいでも眼をつぶっても歌を歌っても横になっても鎮まらないの。
「正しく在らなきゃ、私の大切な者達が悲しむ。」
歪んだ手段とは知りながらも、カッターナイフに手を伸ばす、手首を、腕を傷付けた直後は水で洗って消毒液を噴霧する、そしてティッシュで水分を押さえてから絆創膏を貼っておく。
みんなが居るのに、みんなが居てくれるのに。
「私はちゃんと出来ない子。」
傷口が痛い、部屋の一隅に蹲る。声を出さずに泣くのは得意。
二十二
”テアが心配だ。”
「どの口が仰有るんですシファさんよぉ。」
白い紫陽花に招かれたラティは随分苛立っている。
「俺は今あの子の傍に居たいのに、あんたが無理に連れて来たんだろう。置き手紙一つも残させないで。」
大体此処まで強引にする理由が地底にあるとも思えない。
”ラティの怒りも尤もだ。私が君と同じ立場にあれば私とて憤る、それに加えて暴れている。”
鱗粉の字面に違和を覚える。文字が、微かに
”それでも今すぐにでも話さなくてはならないことがあるんだ。テアには言えない、君にしか話せない。”
紫陽花の裏、大きな枯葉や紅葉で土を一部覆った箇所があるが、その一帯は他のと比べ少し地面が下がっていた、穴か何かでも掘った跡らしい。
「何ですこりゃ。」
言葉は答えない。どうも妙だと傾げながらも重なる葉達をがさりと取ると
テ ン バ ツ ク ダ ル
その文字は、土に枝などの棒で書く手法によるものではなかった。花びらや貝殻木の実を並べたものでもなかった。そしてこの有り様こそ、シファの文字が微かに震え搖らいでいた理由なのだとラティは愕然とした。
萌黄や浅葱の景色の下を飛んで色を染めたオオミズアオ蛾達の二翼のなめらかな羽は新聞紙を千切った形にひしゃがれ潰され僅かな血は流れる勢いも持たず澱んで凝り固まっている。いつも濡々とぱちぱち瞬いた円い瞳は本来あるべき場所から引き摺られてだらりと力無く垂れる長い口吻の先端に突き刺されておち洞の二穴からは体液がどろりと一筋流れ土に歪な染みを生む。たった七文字の文字を組むのに何十匹の蛾を殺したろう、死骸で書かれたこの文字は犯人がニタニタと地底の何處かでほくそ笑んでいる事実を伝えている。
「蛾は肉体を殺されても、死にはしない。」
掠れた声でどうにか言葉を絞り出す。
「あの子の…テアのお母さんもそうだったんだろう?餓鬼共にイタズラされた後、生きてたじゃないか。」
”今は皆湖の底で雪の繭にくるまっている頃だろう。もう少しすればまた此処に戻って来るに違いない。”
ほうと溜息を吐く。蛾が神秘の存在で良かったと今心の底からそう思う。
「……それにしても、この惨状は放っておけないだろう。」
”死体はもうじき被せた葉へ色味となって吸われていくから、この場を片付けたりする必要は無い。”
と話すうちにも葉っぱの色がどんどん鮮やかに染まりゆく。
「でも、この事件の犯人はそうじゃないだろ。だんだん大人しくなるどころか次は人間でこんな真似するんじゃあないのか。」
”だから貴方を頼ったのよ、山猫のラティ。”
雨はひたりと降り止んだ。
二十三
コンコンコン。扉を叩く音がする。
「あら何方様。」
もうきょとんとした表情をすっぽり被る女性の藝よ。
カチャリと鍵をゆるし扉を押すと一人の男性がフードを深く被った格好で俯向いて佇んでいる、その顎ばかりがチラと覗くが窶れた面影は色濃く其の無精髯からも感じ取られる。
地底の世界にこのような人がいらっしゃるなんて。楽園に喜びを感じられる者は、同じ土を踏むのに顔を輝かせない者を心配に思うのである。
「まあ、一体如何なさったの?地上にずっと住んでいた方でしょうか?」
急な環境の変化は恐怖と本能は捉えるのだと、以前医学書で読んだことが
「もう此の場所にいらっしゃったからにはもう安心して良いのよ。さあ、先ずはお上がりになって?美味しい紅茶とお菓子がありますからね、一息つかれてくださいな。」
姉の誰かと喋るらしい声で弟は午睡から起き上がった。不安を未だ拭えない地上の住民だった者が来訪でもしたのだろうか、雨はもう止んだのかな、
(雨を見るのが好きなの。だから雨が降ってる時にお昼寝をするのは一寸勿体無くて。)
地底の雨が好きだと窓の外を仰ぎ見ながら言った後ろ姿、
(随分お髪が伸びたな。)
黒色に近い紺青のリボンの真ん中には装飾の蜻蛉玉が俯向く白百合の項の風情で留められている。あの髪飾りは確か、父上が母上に結婚を申し込む時に贈られ手に取った一品だったっけ。
(俺が軍に入隊してから、姉上はどのような生活を送っていたのだろう。)
まだその話を聞けていない。雨がまだ降っているのなら力を借りて切り出してみようかと、寝起きでもよく頭の働くトノンはリビングへと下りる階段をトントンと。
「姉上、おはようございます。ラティ達はまだ戻りませんか?」
家の入口に見慣れない人物がいた。体格からして男ではあろうが小汚く全身を覆うマントでよく人相が判別出来ぬ。
「姉上、その方は…?」
振り向く瞳はいつもの穏やかなお顔だった。
「あゝ、お茶に誘っていただいたのよ。この方とても紅茶にお詳しくって、つい、私ったらこんな場所で立ち話を…」
口元を隠して微笑まれるのもいつも通りだ。
「それでね、素敵な茶葉があるから今からお宅に伺うお話をしていたのよ。今日はもう家でお茶会をするからとお誘いを断ったのだけれど、御不快にさせてしまったお詫びにって。…すぐに戻るから、お湯とお茶菓子の用意をお願いね。」
でも、今はラティが居ない。
「ちょっと待ってください。」
姉の手首を握る男の腕をもぎ離し、トノンは姉と男の間にむんずと割り入る。男の失敬な腕をぎりりと締め上げながらもう片方の手でテアを後ろに庇う弟に慌てた声で
「トノン、お客様に何をするの!?離しなさい!」
あからさまになった男のその顔面には、殺した蛾の血がべっとりと塗りつけられていた。声を呑み込んだ悲鳴の表情でぺたんと座り込むテアをニタニタと嘲りながらハップは血生臭い息で気焔を吐く。
「随分と甘やかされたお嬢さんだ!月の祝福を受けた寵児は戦いに立ち向かう姿勢も学ばれていないと見える。大したお覚悟も展望も無いのに俺達の世界を破滅させられたのはやはり愛された存在だからなのでしょうなあ素晴らしい素質をお持ちだ!だが、な、だがな、太陽を殺めた貴様にもう先は無いぞ、後は向いてもいない此の地底世界の指導者になるだけだ。運命と地位は脆弱な貴様の心を蝕んで行くぞ、不向きな役割を押しつけられても誰かがそれを果たさなくてはいけないと気負うお前をじっくりと時間を掛けて喰らって行く、他所が見ればなんて殊勝な方だろうと感じさせる生来の健気と一途をぐしゃりぐしゃりと咀嚼して底無しの肚に連れ込むのだよ。理想が、犠牲が、出自が、貴様を自死に追い込んで行く日が来ることを俺は今から楽しみにしているんだ小さな娘よ!」
テアが咄嗟に隠した絆創膏をハップは目敏く見つけ、深い黒煙を怒気に孕ますトノンに聞える音量で囁いた。
「テアは自傷行為をしているぞ。気づいていなかったのか?」
あゝ姉上を想う弟の心よ。今此の男を離すべきではないと理解しつつも無意識に背後に匿う姿を見ると服の長い裾で隠した箇所を更に上から小さな手で覆っているではないか、トノンの表情に何かを察したのかテアは弟の顔を正面に見ない、ずれた視線の隙間に潜る、それは悪魔の笑い声。トノンは忽ちに床へ身体を叩きつけられて腕を捻り上げられる。涙顕わに復讐の腕を弟から離そうと伸ばす細腕をいとも容易く片手で撥ねては痺れる彼女の腕に装着した軍刀で追い打ちをかけた。
弟の悲鳴、倒れる姉。純潔の血はフローリングにじわじわと広がる。身動きさせぬよう暴れる弟の身体に跨り軍刀を引き抜き今度は縮こまる脚を刺す、そのまま垂直に抜かないで刃を傾け太腿から脛まで奇声と共に斬り裂いた。柘榴よりも淡い紅色が小さな身体を縁取っていく。半狂乱のトノンの叫びは血に浸る耳に届いているのかも分らない。
「月は喜びを与えはしない。太陽は自殺者を引き留めるが月は涙を流して見守るだけだ。落ち着けよトノン、お前も直に死者の穴に連れてってやるさ寂しくないぞ泣き止めよ。」
窓の外に、音がした。水がしとしとと点滴する音が。
二十四
一つ思いだしてほしい。地底の世界での雨を読者は憶えておられるだろうか。水が落ちて土に沁みるのではない、昆虫や鳥の羽が降るのが此方の雨で、水が一滴一滴降ることを雨とは呼ばぬことを。だが今 当に水が降っている、情緒豊かな読者の皆様はこの雨をトノン或いはテアの涙、若しくはテアを亡くした地底の世界の哀しみの涙と予想されることであろう。しかし不甲斐無いことに作者はそのような写実的な描写はしようと思えど出来ない下手の横好きなので残念ながらその予想は外れである。では何なのだと結末をお急ぎなさらないで頂きたい、ヤジの小石を飛ばすその血気盛んな手で、頁を前に戻してもらえれば、筆者は命拾いをするのです。
炎を討つ一手。それは冷たく注ぎ続ける水の他にはあらず。水を生むのは氷の牙、牙を溶かすは人肌の体温、水は心臓へと勢い良く突き刺さる。如何に太陽の祝福を受ける身でも人であれば心臓を貫かれれば息をしなくなるものである。
ハップの躯を横に転がし呆然とするトノンの額をぺしりと叩き、瀕死の相棒の頬を舌で舐めたのはぬいぐるみのラティである。
「おら、しっかりしろ。まだテアは死んじゃいねえ。湖に突っ込んで来い。そしたら傷は治るから。」
テアを横抱きにし地底の湖へと走るトノンを見送るとラティはハップの片付けをしようと遺体を仰向けに直す。
「お前、未だ生きてんのかは知らんがな、」
窓硝子に溶けるようにして入って来たのはシファ。ラティは構わずハップに話し掛ける。
「地底世界で誰かを断罪することは出来ないんだよ。お前は此処を桃源郷やなんかと一緒くたにしているんだろうが、そんなに目出度い場所じゃあないんだぜ。此処は本来人間が来てはいけない場所だったんだ。地底に暮せば地上のことは忘れて行くが、それは地底でのことも例外じゃない。人が踏み入れてはならないとされている場所に何故人間以外の生物が居るか考えたことあるか?」
ハップの瞼を撫でて瞳を閉じさせる。鼻から口から溢れてこびり付いた血を白い布で拭う。
「人が人の姿を保てないからだよ。禁忌の場所って呼ばれる所は人を人でなくするから来るなって教えてくれてるのに、あいつときたら……」
月の妖精様が暮している世界があるんですって!
「あいつももうじきシファさんみたいに綺麗な蛾になるんだろう。人間だった時の記憶は人間の姿でないと保てない。地上でのことも、弟のことも、俺のことも全部忘れて、あいつは夢にまで願った月の妖精の仲間になるんだ。トノンは何になるのかな、金魚にでもなったら良いんじゃねえの。」
額を拭い顔を清め肌を全て拭い終えるとシファにその布を渡す。血で汚れた白布は一個の松ぼっくりに姿を変えられ家の外にラティがぽいっと投げた。
「お前の姿を変えて紅葉にでもしてやっても良かったんだが、貴方は水に流して仲良くする事を嫌うタイプだ。人間だけは澤山嫌ほど見て来たから一目でどんな奴か分っちまう。ははあ、店に陳列されてた日も無駄じゃないって?」
清潔なシーツで遺体を包み、暖炉の中に安置させて松ぼっくりを布の上に置き、擦ったマッチを足元にそっと置いて布が燃えるのを確認してから距離を置く。
”ラティ。”
「なんだよ。」
”地上世界の再建をしたら、彼女は人の姿でいられるぞ。”
「俺に目を付けたのは流石賢いシファ様だが、今のは間抜けの発言だろう。」
ぬいぐるみは人ではないかた記憶に干渉される事は無い、地上も地底も主人のことも忘れることは無い。
「見ろよシファさん、トノンがテアと歩いて来るぜ。もうすっかり元気そうだ。」
掛ける言葉を失うシファにラティは鼻息長く呆れた物言い。
「同情してくれるのは有難いがまあ余計なお世話だ。ぬいぐるみは人の成長を止められない。んな事どのぬいぐるみだって承知してるもんだ、貴女が気を揉んで解決出来る理じゃ無ェ、貴女の身の程を知れ、傲るな。」
手を振って歩いて来る相棒の笑顔に苦々しい顔を向けるラティの表情は、いつも通りのものだった。
いつもの言い合い
いつもの顔
いつもの紅茶
いつもの言い合い
此処の生物はいがみ合わない、やがては言い合いも消えてゆく。蛾は紅茶の味がどれも同じに感じるから、いつもの紅茶はどれを淹れてもいつもの紅茶になっていく。
頁を戻る、頁を戻る、テアが人の姿としてラティと居た描写を辿っていく。そう、これらはいつか失われる、テアは人でない姿に羽化するから。
諸君等がこの物語を読み終えた後憶えていてほしいのは、テア達が人間の時にどう過ごしていたのかと言う事と、今でも地底世界の赤屋根青壁黄色の窓の家には毎日日替りの温かい紅茶を淹れる山猫のぬいぐるみが居て、窓の外で地底中を飛びまわるオオミズアオの一群れを家の中から窓辺に座って紅茶飲みながら眺めている事。そしてぬいぐるみは、君の忘れた楽しかった記憶達を一欠片も零さず抱きしめ続けている事を。
どうか世界中のぬいぐるみの願いが、叶いますように。
終
「緞帳前にて」