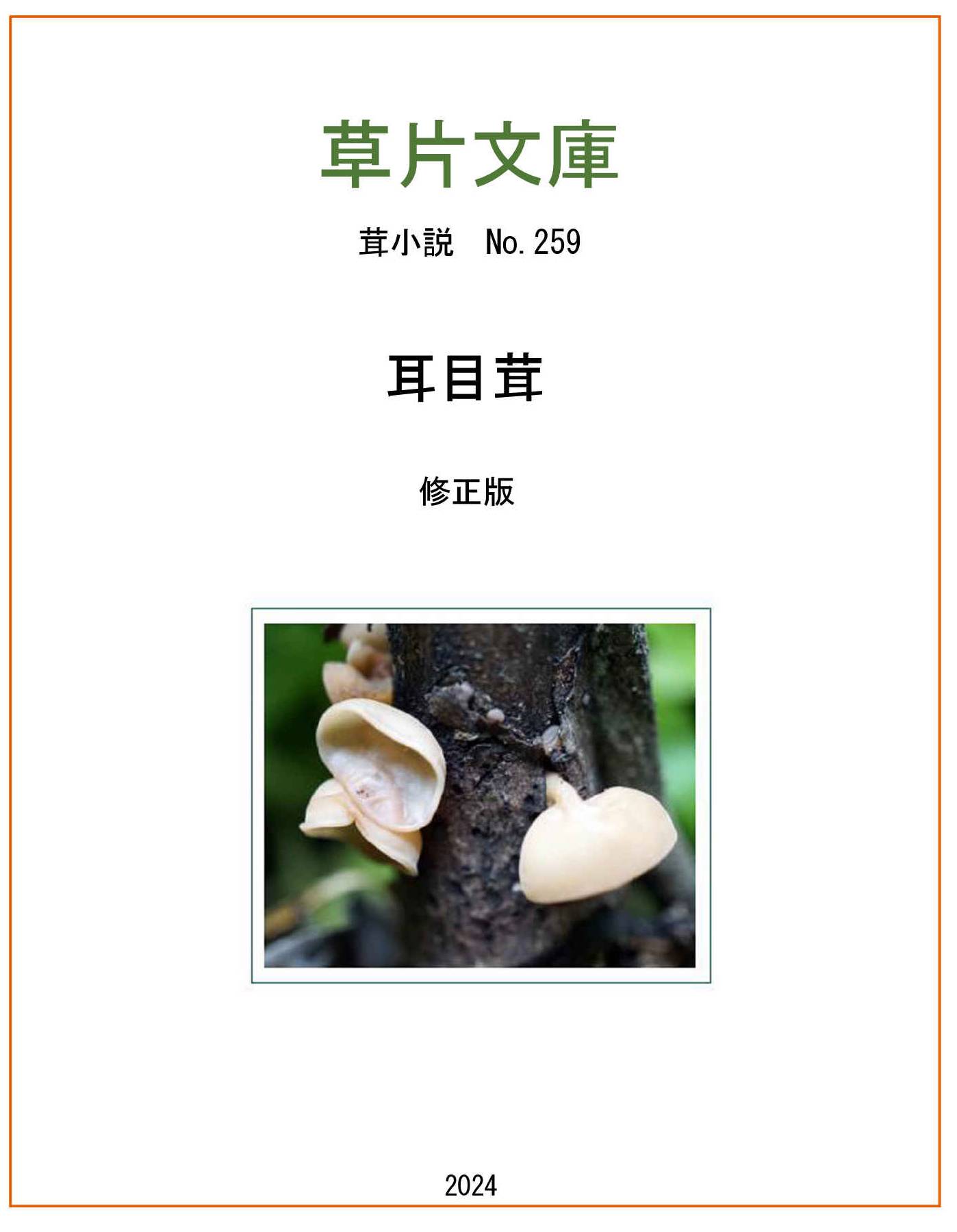
耳目茸
茸昔話。
耳目茸
「おまえさん、やられたね」
家に帰ってきたゴン助は、土間で朝飯の支度をしていた女房のオマメに言われた。
それでやっと気がついたのだが、左目がからっぽになっている。
「ああ、いまさかりの鳶茸採りに行ったんだ、たくさんとれたよ」
かごをおろした。
「どうなの、片目になって大丈夫」
「ああ、おまえも耳がなくなったとき、気がつかなかっただろう、同じだ」
女房のオマメは左耳がない。耳たぶがないだけではなく、耳の穴がふさがっていた。だが、聞くことには不自由をしない。残った耳で十分のようだ。
村の者の大半は、目か耳の片方がない。乾山(いぬいやま)に茸とりに行ってこうなって帰ってくる。といって、茸採りいかなかくても、寝ている間にそうなる人もいる。いずれにしても、秋の茸の盛んな時期におこることである。
片目や片耳がなくなるようになったのはここ三年ほどのことだ。山に行ってなくなるのは乾山だけである。
村の年寄りたちは、おそるおそる犯人探しをしたのだがわからなかった。探りに乾山に行ったみんな片耳になった。だがそのときは犯人探しのついでに、よく育ったマイタケをごっそりととって帰ってきた。
誰か乾山を怒らせることをしたんだろう。
老人たちは言った。
そういう怖い山でも、元気な若者は乾山に茸とりにいきたがった。秋になれば他の山ではみられない立派な茸がはえる。
まだ、乾山に行くと片目片耳になると言われていなかった頃、乾山にいって片耳をなくした男がまた乾山に茸とりにいった。ともかくあんなにうまい舞茸はそこでしか採れないと思ったからだ。ところが、帰ってきたら片目がなくなっていた。それでもまた、乾山に行った。残っていた片耳がなくなってしまった。両耳がなくなると、周りの音はほとんど聞こえなくなった。男は片目だけで生活をしなければならなくなった。家族が残った目がなくなると大変だから、もう行くなと言った。男もうなずいて、それから一度も乾山にいかなかったということだ。
その話が村中に伝わり、村人は、一度は乾山に行ってうまい茸を食いたいと思ったが、二度行くことはなかった。
ゴン助とオマメは、村境の峠に飯屋を開いていた。二人とも、いくつか山を越した町の者で、飯屋をやっていた。しかし、まわりにたくさんの飯屋があったことから、立て込んでいる町から離れ、旅人相手の飯屋を開きたいと思っていた。どこかいいところがないかと気にしていたところ、この村の山菜や茸がうまいことを知り、この村のはずれにあるに峠に目をつけたわけである。村の下見をし、ここがいいと二人の意見は一致して、村長に挨拶に行った。
だが、そのとき、村長は乾山のことを言いそびれた。
峠に飯屋をひらいてから、しばらくして、オマメが茸採りにいき、知らぬ間に乾山にはいった。たくさんいい茸をとって帰ってきたのだが片耳がなくなっていた。
ゴン助はオマメをつれて村の医者のところに行った。医者はオマメの耳をみて、またかという顔をして、「だいじょうぶじゃ、だがもとにもどらん」と言った。オマメはそれを聞いて驚いたのだが、その医者も片耳がないことに気がついた。
「どうして、かかあの耳がなくなっちまったのかね」
ゴン助が医者に聞くと、村長が乾山のことを言わなかったかとたずねた。
二人は首を横に振った。
医者は乾山に行くと、耳か目の片方がとられると説明した。
医者はこうもいった。
「だがな、いずれは、耳か目がなくなるのだから、乾山にいってうまい茸をとってきて食った方がいいかもしれんな」
そういわれたのだが、そのころのオマメとゴン助には意味がわからないことだった。医者はその理由をこう言った。
「茸採り行けない寝たままの病人でも、秋になるといつのまにか片目か片耳がなくなっちまうことがあるんだよ、どうしてそうなるかわかっとらんがな」
それを聞いたゴン助はいつか乾山に行こうと思った。行っても行かなくても片耳、片目がなくなるなら行ってうまい茸をたくさん採ってこようじゃないか。
そういうことを知って、今年は山で鳶茸がたくさん生えていることもあり、乾山に行ったわけである。
片耳がなくなるのは覚悟の上であった。
「おめえは片目、おれは片耳、ちょうどいい夫婦じゃねえか」
「そうだね、これからは欲張らずに、外の山で採れた茸でがまんしようよ」
「それがええな、だがよ、乾山じゃないとこの茸もみなうめえしな、いい茸飯ができるから大丈夫だ」
二人の営む峠の飯屋は、茸飯がうまいと評判になっている。
「でも、乾山の片目片耳を奪う妖怪はどんなやつか見てみてえ」
しばらくすると、ゴン助とオマメに子供ができた。
「めんこい女の子でよかったな」
娘をオコメと名付けてとても大切に育てた。
そのころになると、二人は村人たちともなじみになり、仲良く一緒に山にでかけた。
特に同じくらいの子供を持った夫婦とは、一緒に山菜採りや、茸採りに行き、彼らのとった余分の茸を買い取ったりして喜ばれていた。茸たっぷりの茸飯をつくるためだ。
茸採りの仲間の一人が
「そろそろ気をつけてなければなんねえな」
と言った。
「なにをだね」
「娘が十になるべ」
「うん、明日が誕生日だ」
その男が、十をすぎると、乾山にいかなくても、片耳片目がなくなることを教えてくれた。
「どういうことだ」
「十より若いときに、片耳や片目をとられたのはおらんだよ」
「いったい誰がとっちまうんだ」
「わかんねえだ、朝になると、片耳片目がなくなっている、気をつけててもだめだ」
「妖怪だな、おらが大事な娘をそんなにされてたまるもんか、これから毎晩みはって、妖怪をたいじしてやる」
「だがな、十になったからって、すぐとられちまうわけじゃねえんだから、毎晩見張ってもいつになるかわかんね、十五になったときかもしんねいし、二十歳かもしんねえ」
「十で片耳とられたんは、男かい、女かい」
「ほら、三蔵さんのところの、秀ぼうだ」
「あの、勉強ができるやつだべ」
「鳶が鷹うんだっていわれてるよ」
「片耳とられと、頭よくなるんかね」
「わかんねえけど、十三で片目をとられた捨吉の娘は足がはええな、運動選手だ、捨吉は不器用だけどな」
「子供の頃にかたっぽとられると、なんかよくなるんか」
「そうかもしんねえ」
「それじゃ、ほっといてもいいのかね」
そんな話をした次の日のこと、小学校から帰ってきたオコメにゴン助は、いつか片目がなくなるかもしれんが、怖くはないからと、言い聞かせた。
「チャン、知ってるよ、この村の人は耳や目が片一方ないもん、どっちがなくなるか、みんなで話てんだ、おらは、母ちゃんみたいに耳の方がいいな」
「どうしてだ」
「あたいの目はちいちゃいから、片っぽうになったら、見えにくくなると違うかな」
「そんなことはないべ、だけど、とられない方がいいだろう」
「そんなことないよ、この村の人と同じになるだけだから」
ゴン助はなるほどと思った。怖がることはないわけだ、だが、なにが片っぽうをとるのか。何とか確かめようと思った。
乾山に行くと必ず片一方をとられる、だけど、行かなくてもなくなるのは、乾山にすんでいて、あまり歩くのが得意じゃないやつにちがいない。鳥のように飛ベるやつなら、乾山で待ってはいないだろう。
歩くのがゆっくりな妖怪なら、村に出てきて、目や耳をとって、持って帰るのに時間がかかるに違いない。村でと片目片耳がとられちまうのは夜のうちだ。夜になったら乾山から村にはいる道で見張っているのはどうだろう。だが、いつ来るかわからんのに大変だ。
もう一つわからんことがある。村人からとった耳や目をどうするんだ。食うのか。
ゴン助はオコメにそんなことを話した。
「なあ、とうちゃん、おら、明日学校休みだから乾山に行ってくる、どんな奴が目や耳をとるのか見てくる、どうせとられるんじゃ」
オコメは賢くて強い
「オマメがなんというかな」
「母ちゃんにはもう言った、父ちゃんに相談しろってよ」
「そんじゃな、乾山の入り口まで一緒にいくからな、そこでまってる、怖かったらすぐ逃げてこい」
「うん」
明くる日、朝になると、オコメが魚をすくうタモ網を持って、家の前でゴン助をまっていた。
「そんな網どうするんじゃ」
「耳をとる奴をとっつかまえる」
「うーん」
ゴン助はそんなんじゃ捕まえることはできないだろうと思ったが、頼りにするものを持っていた方がいいかもしれんと思って、
「そりゃええ、でも気をつけるんだぞ」
と、一緒に乾山に向かった。
乾山の森の中に朝の光が射し込んでいる。
シダや草草の下には、いろいろな茸が生えているのが見える。うまそうなのもある。
「オコメ、せっかく入るんじゃ、片耳か片目がなくなるかもしれんが、どうせなら、うまそうな茸を探せ、こ母ちゃんが茸飯作ってくれべえ」
「んだ、うめえ茸採るでよう」
そう言って乾山の中に入いると、オコメは「オコメがきたぞー」と大声を上げた。
元気な娘だ。ゴン助はオコメの後姿を見送った。
しばらくたった。
ちょっと心配だったゴン助が森の中をのぞくと、シダや草が動いて、こそこそと音を立てている。
何だ、と見ていると。
小さな今まで見たこともない茶色の茸がゆっくりゆっくり出口の方に動いてくる。
その後ろからオコメが魚の網に大きなものをいれてかついでくる。
「おーい、だいじょうぶか」
ゴン助が呼ぶと、
「だいじょうーぶだよー、ほーれ、大きなマイタケもらった」
誰にもらったんかい、と思いながらも、まず、耳と目とどちらをとられてしまったのか気になった。
オコメが元気にゴン助の前にあらわれた。
ゴン助はぎょっとなった。
まず、オコメの顔を見た。目玉だらけだ。一つになったのではなく、顔中に小さな目玉がくっついている。あれ、顔の周りは耳だらけだ、耳で顔が囲まれている。
「ほれ、マイタケ立派じゃろ」
魚の網から大きなマイタケを抱えて、ゴン助の前に差し出した。そのオコメの左手には目玉がずらーと並んでくっついている。右手には耳がやはりずらーっとぶるさがっている。
「オコメ、体中が目と耳じゃねえか、どうしたんだ」
オコメの足下で、たくさんの茶色の小さな茸がゆらゆらゆれている。
「返してもらったんじゃ、森の中で、目と耳かえせー、どろぼー、っていったらな、大きな、オラくらいの茶色の茸がでてきてな、どうしたっていうから、村の人の片耳や片目が、乾山で盗まれた、と話したんだ、したらな、その大きな茶色の茸が、そんなことしたの誰だー、森の中でどなったんだ、
でてきたでてきたよ、土の中からもぞもぞと、小さな茶色の茸がでてきたよ、そいつら、みんな目があったり、耳があったりしてかわいかったな。
大きな茶色の茸が、あたしの産んだ子供が盗んだようです、人間の目や耳をつけてみたかったようで、すみみませんでした、ほらあやまりなさい、といったんだ、子供の茸がごめんなさいっていって、お辞儀をすると、オラの体中に目や耳がとんできてくっついた」
オコメは笑って、胸をはだけた。少し膨らんだ左の乳の周りには耳がくっついていて、右には目がくっついていた。
「これ村の人にかえすんだ」
オコメの周りで、ゆらゆら揺れていた茶色の茸の子供が、「ごめんなさい」と傘をさげておじぎをした。
ゴン助は、「そうか、茸の子供がとったんか、なあ、森には虫たちがたんといるだろう、そいつ等は、たくさんの目を持っているから、そいつらから一つもらいな」
と子供の茸に言った。
茸の子供たちは「うん」とお辞儀をして、森の中に帰っていった。
「そんで、とうちゃん茸が森の奥にいって、このマイタケもってきて、おわびだって」
「おお、そうかい、そりゃあうまそうだ」
こうして、目と耳だらけのオコメをつれて家にかえった。
オコメをみたオマメはびっくりした。ゴン助が話をすると、
「そうかい、ほら、オコメの鼻の上の目は、隣のヨシの目じゃな、かえしてやるとよろこぶぞ」と言った。隣の家のかみさんの目であることがすぐわかったのだ。
こうして、峠の飯屋の娘のオコメが取り返した目や耳は村人たちに返された。父ちゃんの目は父ちゃんにかえした。母ちゃんの耳は母ちゃんに返した。元に戻った村人たちは、ますます元気にしごとをした。
村人たちは喜んで、だれもが峠の飯屋に茸飯を食べにくるようになった。
だが、この三年の間に亡くなった人の目は返すことができなかった。オコメの顔にあった目と耳はからだにはまだ耳が八個、目玉が十二個もくっついていたままだった
オコメが大きくなってもそのままだったが、オコメは、よく聞こえるしよく周りが見えるからええよ、と元気に飯屋の手伝いをしていた。
あるとき、目の不自由な座頭が六人、峠の飯屋に寄った。
オコメが、「茸飯を運で目はいらんか」と聞いた。
すると、座頭たちは、「そりゃあ、ほしいさ、だれぞくれるやつがおるんかい」言った。
「それじゃ、やるべ」とオコメは着ているものをするすると脱いだ。
はだかないなると、オコメのお乳のした、へその右左、腕の付け根、太もも、それに両方の尻に目がついていた。耳は左右のわきの下から三つづつ付いていた。
座頭たちは、目の匂いがする、と手を合わせ、オコメを拝んだ。
すると、オコメのからだの目がひょいと飛び出ると、座頭たちのまぶたの中にもぐりこんだ。
座頭たちはぱちりと眼を開けると、前に真っ白なきれいな女体があった。
「あ、ありがたや、目が見えるようになった、観音様が目の前に立たれた」
座頭たちは床にひれ伏して観音様を拝んだ。
オコメは「さめないうちに、たべなよ」といって、着物を着ると、奥に入っていった。
それから百年ほどたつ。村の峠の飯屋のあったところに、オコメ観音を奉る社が建っており、盲人たちの聖地になっているのである。
オコメについた耳は一生涯そのままで、オコメは年をとっても耳がよく聞こえたという話である。木彫りの観音さまには、耳は二つしかなかったが、着ている衣には六つの木耳がぶらさがっていた。
耳目茸


