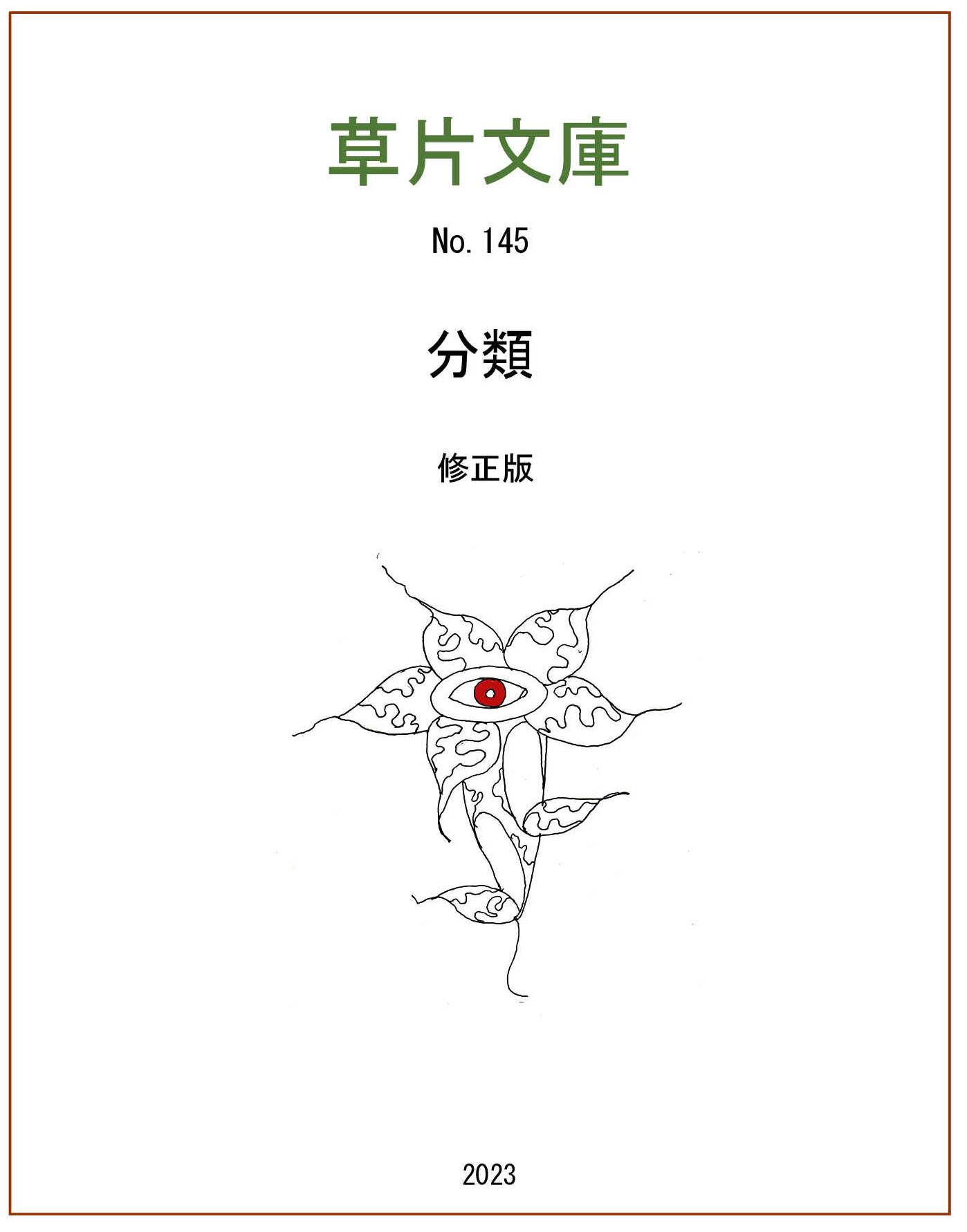
分類
空想科学小説です。
都内の大学に勤めている男には人にはいえない趣味がある。もし外部に知られたら大学は首になるのは必定、下手をすると後ろに手が回る。
彼は一つの学部の教務課の学生担当事務員で、三千人ほどの学生の情報管理を担当している責任者だ。大学の職員に採用されたのは5年前、かなり事務経験豊かな者といってよいだろう。
毎年700人ほどの新入生が入り、必要とする学生の情報を短期間にまとめなければならない。その後も絶えず変わる学生の情報を受け入れ、正確な情報がいつも整っている必要がある。学生の寄宿先は変わることが多く、住所変更は毎日のように誰かが言ってくるし、体調による休学や、勉学の留学のための休学処理、さまざまある。外国からの受け入れもかなり複雑である。正式に入学した者、短期留学の者、研究生としての受け入れ等々だ。
簡単に言えば学籍簿の管理だが、それだけではない、問題を起こした学生の処分の問題、周りからの学生に対する苦情処理の窓口にもなる。大変だ。
彼は事務処理が的確で早いことから、周りから頼られる存在である。
規則正しく朝8時には出勤して5時には引けるが、急な時間外労働もいとわず引き受ける。
男のアパートの一室には自分の集めたファイルが棚にずらっと並んでいる。
元来収集癖があったが、ほしいものが何でも買える身分ならいいが、大学時代は給付奨学金と貸与の給付金を借りまくり、今その返済に追われている。幸い大学職員という安定した職業に就いたことから、月々の返済は滞ることはなく、少しは貯蓄に回すことができた。そういうことで、お金を払って好きなもののコレクションを自由に楽しむほどの身分ではなかった。
若い頃は道に落ちているきれいな模様の石を拾って集めたり、飲んだコーヒー缶をとっておいたりしたが、場所をとることもあり捨ててしまった。しかし収集癖がある人間は何かを集めていないとストレス状態になり、なにをしでかすかわからない。そんな自分をよく知っている男は、ほとんどお金がかからず、誰もやっていないコレクションを始めたわけである。
それは大学の職員になってからである。
彼は何千といる学生の顔写真を見ていて、自分の頭の中で自然と顔の分類をしていた。この娘は女優の誰々のタイプ、この娘はだれだれに似ている、と日本の女優の顔を基準として分け、自分のUSBにしまっていた。古い女優から、今の女優、美人女優から個性派女優、世の中結構似ている顔があるもので、そうやって分類すると女優の誰かのファイルにおおよそはいってしまうことに気づいた。小さな劇団の女優のことまでも調べ上げ、基準となる女優の写真も手に入れた。
彼は家に帰ると、USBにいれてきた女子大生の顔写真を、自分のPCに作ったフォルダーに分類した。たとえばファイル1、吉永小百合、と言った具合で、それぞれのファイルに何人もの顔が集まっていった。
ただ顔を集めたただけであって、その娘に声をかけたり、会ってどうこうしようという気持ちを持っていたわけではない。顔を分類してファイルにたまっていくこと自体が楽しかったのに過ぎない。
まあ、変わった収集といっていいだろう。
集め始めて二年ほどたってから、彼は面白いソフトを考え付いた。それは、化粧を落とすソフトである。昨今、顔の写真にメイクをするソフトはいくらでもある。彼はその逆を考えた。女優の顔写真の化粧を落とすことに成功した。
そこでそのソフトを使って、女優さんの顔の化粧をおとし、それをもとに分類をしなおした。より正確になったと自分で思った。
やがて、女子学生の顔写真だけではものたりなくなった。家でコンピュータを開いき、一般の女性の顔を拾った。公にしている大学病院のスタッフだとか、農業の生産者の顔が載っているものだとか、そう言った掲載されているものを拾いだして顔写真を集めた。婚活サイト、友達探し、中には犯罪者の女性などもある。といってもバックグラウンドは関係なく、顔の造作だけが彼にとっては問題なのである。
そうやっているうちに、俳優に似ているという分類方法に飽きてきた。もっと違う分類で集めたらどうなるか、そう思い立ち、基準としてきた、メイクをおとした女優の顔写真をならべてみた。
女優の顔をながめていてふと気がついた。この女優は猫のようだ、とか、犬のようだ、ウサギのようだ、ネスミのようだ。そのように動物の顔が見えてきた。これか、分類の基準は女優じゃなくてもいい、動物の顔にしようと考えた。
これはやりがいがあるかもしれない。
ネットから、動物の顔写真を選び出した。それは獣だけではない、魚、蛙、イモリの顔、蛇やトカゲの顔、亀の顔、魚類、両生類、は虫類、鳥類の顔はその中でも特徴のある顔がいくつもある。虫の世界もおもしろい。昆虫の顔がいろいろある。
そんなことで、一年かけて、新たな顔の基準を人間以外の生き物から抽出したわけである。
今まで集めた女性の顔をもう一度見直して動物に当てはめていった。楽しい作業だった。それに、女性だけではなく、男子生徒の写真も集めた。もちろん、一般の男性もである。
大学の仕事から帰ると、夜中の2時頃までその作業にかかりっきりになった。新たにネットにあがっている顔もどんどんコレクションに加えていった。
僕の顔はそうだ、羊だ、と思って、自分の顔は羊の特に綿羊のファイルに入れてみた。
こうやって今までのものも新たな基準でファイルすることができた。
彼の印象として、深海の生物の顔は人間離れしているものが多いと思った。
そこで、深海魚に似ている顔に着目して見たが、以外と人間にも似ている顔があるものだと驚いた。
深海にはいろいろな生き物がいる。エビやカニの顔は数千メートル下の海底で生活している。だが一部をのぞくと海岸で見られるエビやカニと大きな違いはない。一方で魚の顔はずいぶん違うものがある。よく知られている竜宮の遣いという大きく長い魚の顔を見ると、下顎が前につきだしているようで、SF映画にでてくる地球外生物のすなわちエイリアンの基礎的な顔をしている。もっとエイリアンぽいものもいる。ダイオウホシエソ、ミツクリザメ、キバアンコウ、ミズウオ、ミツマタヤリウオ、ホウライエソ、ギンザメ、リボンイワシ、フクロウナギ、ラブカ、テンガイハタ、イチハタビロウドザメ、まだまだある。もちろん魚らしい顔をした魚だっていないわけではない、ともかく深海魚顔というファイルを作った。
このように彼は自分の収集癖を満たすため、新たな基準をつくって、女性と男性の顔を集めたのである。
彼収集したものを他人には全く見せたことがない。倫理に反する面があることを彼は重々知っていた。とりあえず、誰にも迷惑をかけない趣味である。
職場では、どうして学生の名前をよく知っているの、と聞かれることがある。教員から学生について尋ねられたとき、学籍簿からその学生をすぐに見つけだすことができた。彼は視覚にもとずいた情報についての記憶力が高かったことは事実である。
大学には学生担当という役割の先生がいて、学生に問題が起きると連絡がその先生にいく。そういったとき、彼が補佐をして、その先生を助けることになる。学生担当は学部長が変わると、別の人に代わる。
その問題がおきたとき、学生担当教務主任は物理学の学者で、ロケット工学の領域ではよく知られた人であった。彼の顔は殿様バッタのファイルにはいっている。
一年の女子学生の親から音信不通になったと大学に相談があった。警察にいう前に、大学での様子を聞きたいということだった。連絡がつかなくなって四日だと言うことなのだが、入学して一月しかたっておらず、初めての一人暮らしをさせていたことから、両親はかなり心配をしていた。学生担当の先生に連絡がいったが、その先生にとっても全く知らない学生であることから、学生課に調査をするように指示があった。そのとき、彼は名前から顔を思い出し、キャンパスの中で、あるサークルの学生たちと話しているところを見ていたことから、それが糸口になって、彼女のいる場所がわかった。
文学サークルの一つで、缶詰ごっこという歓迎イヴェントに、その女子学生は参加していたのだ。女性の先輩の部屋に缶詰になって、一週間、小説を書くというものだった。小説家が締め切りを前にして、出版社が用意したホテルに缶詰になり、原稿を書くということを経験してみようと言うことらしい。授業にはでるように言われたが、他の人とは話をしてはいけないというルールだった。その学生はルールを守って家にも連絡をしなかったようだ。
それがわかって、親が大学に感謝して、大学にかなりの寄付までしたことから、学生課の彼は上からほめられた。そういったことが何度かあったからであろう、彼は若いのにも関わらず課長補佐にまでなった。もちろんそうなっても、学生窓口での学生への対応も続けていた。それは学生の顔をの収集のためでもあった。
新たな顔の分類をはじめかなりたった頃、これはエイリアン、すなわち深海生物に分類すべきだという顔の女子学生が入学してきた。書類をとりに学生課の窓口にきたとき、かなりの美人に分類されるべき顔なのだが、横顔をから彼はなぜか深海の生き物を思い浮かべた。彼の感覚であり、理由を聞かれてもわからないと答えるだろう。深海にいる生き物、特に魚は言い方をかえると、人間離れしていてエイリアン的な顔である。そういう顔は意外と少ない。彼女の顔は怖い顔ではなく、大王イカの雰囲気の顔だった。大学では彼が初めてあった深海生物のケースである。
「給付奨学金の案内がほしいのですが」
彼女の声は、透き通るようで、清らかで、昔だったら、天女の歌声のようだと表現されるだろう。ふつうの学生だとスマホを眺めるのと同じ顔で窓口の担当者を見る。ボタンを押せば出てくるといった人間不在の目だ。彼女は違った。腰掛けている足の先がうきうきして、踊り出しそうな軽やかな声だった。
「パンフは、壁の前の机の上につんでありますから、そこから持って行ってください。読んでわからないことがあったらいつでも聞きにきてください。これは大学にきている、給付奨学金の一覧です、参考にしてください」
彼はそう言って一覧表を渡した、もっと詳しく聞いて、返答したかったのだが、後ろに数人待っていたので説明はそこまでにした。
彼女は「ありがとうございます」といって、横顔を見せ、パンフの積んである机の方に向かった。そのとき彼はエイリアンだと思ったのである。
それから、ときどき、キャンパスの中で、彼女が歩いているのを見かけた。彼はすでに、彼女の名前も住んでいるところも頭の中に入っていた。
赤川クリスティーナ、18歳、月島のマンションに住んでいる。そのマンションはとても一般人が住めるようなものではない。父親は日本人の名前だったが、母親の名前は英語圏の名前だ。
だが、なぜこのような家庭環境の学生が給付奨学金のパンフレットを取りに来たのだろうか。彼はその年に受け付けた給付奨学金の希望者を調べたがその学生はいなかった。結局本人は書類をだしていない。友達の代わりにパンフを取りに来たのかもしれない。彼はそう思ってそのことは忘れてしまった。
次に彼女の名前を目にしたのは、次の年度になり、成績優秀者のリストを見たときである。ほとんどトップである。そのように成績がいい学生は、大学独自の給付奨学生に推薦されるはずである。確かに推薦されてはいたが、書類は提出されず、給付生にはなっていなかった。よほどお金にはこまらないのだろうと、その件も忘れた。
彼の顔の収集の深海生物というファイルにはいろいろな領域から十八名ほど選ばれていた。若い会社員もいれば、中年の女社長もいる。どの顔も真正面から見ると魅力十分の美人に属するものだ。ところが、横顔になると、おやっと思うほど深海魚の雰囲気がただよっている。自分の勤めている大学の学生に関しては詳しく知っているが、ほかの女性たちはわからなかった。
男性で、深海魚の顔を持った人間も数人いた。ほかの大学だが、学生もいるし会社員もいるし社長もいる。
そこで彼は気づいたのだが、社長の女性も男性も、航空機の部品メーカーだということである。会社員もやはり、ヘリコプター、飛行機の部品メーカーに勤めている。
同じ傾向の顔の人は、同じ様な職業に携わっているのかと思って、よく考えたら、そうならば一つの会社に同じ系列の顔の人が集まるはずだが、調べて見ても決してそうではないことからその考えは破棄した。
深海魚系の顔の人が同じ業種の会社にいることは偶然だったのだろうと納得をして、その話は彼の頭の中から消えていた。
面白いことに気づいた。アイドルグループの顔を分類したら、同じ傾向を持つ者が集まっているのではなく、全く違う分類にはいる人たちが集まっている。女性アイドルグループは、マンガの影響か、この時勢の好みか、だれもが長いつけまつげをして、目の周りを黒くして大きく見せて、みなそっくりだ。ところが化粧を落とすと、猫の顔、犬の顔、ネズミの顔、猿の顔、キリンの顔、とそれぞれだ。だから逆に、グループとしておもしろいのかもしれない。男の子のグループもそうだし、漫才コンビにしても、顔を分類すると違ったファイルにはいるものだった。例外的に双子のコンビなどは同じ顔ということで、人々の興味が集まるようだ。全くの他人なのに、何とか姉妹と言って同じ格好、同じような眼鏡をかけて似せることで興味を引くこともある。
そのように様々な角度から、人の顔を見ることができるようになった彼は、すれ違う人の顔も即座に分類してしまった。楽しみでもある。
大学が夏休みに入ったある朝、事務室に向かうと、学生担当の教務主任をしている先生に呼び止められた。
彼がおはようございますと答えると、教務主任室にきてほしいという。朝の8時ちょっと前である。一時間目に授業ある先生は早いこともあるが、先生方が来るのはだいたい十時ぐらいである。こんなに早く教務主任の先生がきているということは、学生が何かしでかした可能性がある。面倒だ。
「先生、なにかあったのですか」
彼はタイムカードを押して、カバンを自分の机におくと、教務主任室にでむいた。
「いや、問題はなにもおきていないのだけど、実は国のある機関の人から、学生のことで知りたいことがあるので会いたいと言ってきた。もう一月も前のことだから、前期の試験期間中だった。学生担当の私が応対したのだが、私には理解できないことでね、向こうもあまりはっきり言わないし、こちらも困っていると、
「学生の顔を一番知っている人はいますか」と尋ねられてね、学生の顔をよく覚えている君のことを話したんだ、そのときはね、また連絡します、それまではこの話は他言しないようにお願いします、帰ったんだ、ところが突然夜に学長から電話があってね、君と一緒に今日その国の機関に行ってほしいと言われた。急なことだと思ったよ、学部長ではなく、直接学長に連絡がいったということはよほどのことだと思う。学部長もすでにそのことは知っているそうだ。それで今部屋に来てもらったわけです」
「僕がそこにいくのですか」
「うん、しばらくそこで向こうで働いてください、引き受けてもらいたい、学部長からも大学の任務と言うことで、事務長には連絡してあるそうだ」
「なにするんでしょう」
「僕にはわからないな、国の機密事項のようで、それしか知らないんだ」
話は半分以上進んでいて、断れる雰囲気ではない。学生担当教務主任の先生は温厚な人で知られ、話し方は柔らかいが、今回はその通りにしてくれと言う雰囲気だった。気味が悪い話ではある。
「たのむね」
念を押され、彼はうなずいてた。
「どうしたらいいのでしょう」と聞くと、「連絡がくるから、事務所で待機していてほしい、他言は無用だよ、事務所のみんなには早引きをすると言ってください」
そう言われた。
夏休み期間なので、事務所に出勤しているのは半分ほどだ。みなに、早引きするのでよろしくと頭を下げた。
課長も休みなので、課長補佐の彼が学生課のトップである。
8時半時になると、事務室があき、夏休みだが、成績証明書や在学証明書をもらいにくる学生や卒業生がちらほらくる、今はコンビニなどで、そういった証明書は取得できるが、まだ直接来る人もかなりいる。夏休み中の対応は午前中だけになっている。
十時ちょっと前に、教務主任の先生から電話があって、帰り支度をして門をでてほしいということだった。彼はまわりに挨拶をして事務室をでた。
事務室の裏口から校庭でて門に向かうと、教務主任の姿があった。
「門の脇に白い車がきています、それじゃよろしく頼みます」
「え、先生も一緒じゃないのですか」
「申し訳ない、用事ができて、こちらのことはすべて大丈夫ですので、向こうに協力をしてあげてください」
と頭を下げた。
先生に頭を下げられても、なにがなんだかわからない彼は、どうなるのだろうと心配ながら門をでた。
白いよくある乗用車が道の脇にとめてあり、中肉中背の男性が降りてきて、彼の名前を言った。
おや、竜宮のつかいだ。そんな顔をしている男だ。
「お願いします、これからまず捜査室の方にきていただきます」
何だろう、捜査室とは。
彼が車の後ろのドアをあけた。
彼はおじぎをして後部座席に乗った。
その男は運転席に戻ると、
「作業室にいったら、すべてをお話ししますので、ご心配でしょうけど、大丈夫ですのでよろしくご協力ください」
そう言って、車をだした。
彼が使っている駅とは反対の方に走っていく。
知っている町並みを見ていると、いきなり窓が真っ黒になった。
「着くまで外が見えないと思います、前にあるモニターでテレビでも見ていてください。脇にリモコンがあります、クーラーボックスには飲み物がははっています、ご自由にお飲みください」
向かっているところは秘密なようだ。
腰掛けている前にモニターがありリモコンがある。そういわれても、テレビなど見るような気持ちにもならない。
クーラーボックスをあけてみた。清涼飲料からコーヒーまではいっていた。
「どこにいくのでしょうか」
やはり気になる。
運転手は「あと三時間ほどでつきます、ご心配はわかります、簡単なことはお話しできます。われわれは、国の諜報部です、といっても、戦時中や自衛隊組織の諜報部とは違います。宇宙諜報部です」
日本の自衛隊も宇宙自衛隊と名前を変えるようなことを言っている。それと関係あるのだろうか」
「宇宙自衛隊とは違います。あれは、人工衛星によるサイバー攻撃などを防ぐ役割を果たすところです、地球内のことですが、我々は地球外からの情報を得て、対処を考えるところです」
なにを言っているんだ、それじゃ地球防衛隊ということじゃないか。
運転手は「確かに、地球防衛隊のようなものですが、軍事力を使って防衛するというのではなく、情報を入手して、対応を考えると言うものです、もし軍事力を持って地球にくるような宇宙人がいたとしたら、我々かなうわけはないでしょう、ともかく、宇宙からの情報を得ることが第一です」
運転手は彼の心を読んでいるように説明を繰り返した。
言っていることはよくわかる。わからないのは、なぜ彼が呼ばれたということである。
彼の脳裏にちらっと、自分の趣味のことが浮かんだ。学生の顔を集めていることである。だが、誰も知らないはずである。大学の資料を無断で集めてしまったことは大変なことになる。首を切られてしまう。
フロントグラスからいきなり外の景色が目に飛び込んできた。景色といっても、コンクリートの湾曲した壁である。トンネルだ。車はおそらく時速百キロはでているだろう、その早さでトンネルの中を走り始めた、高速道路にこんな長いトンネルがあっただろうか、と思っていたら、左に回り出した。しかも下っているようだ。少し速度を落としてはいるが、それでも7、80キロはでている。
トンネルの中を左回りに30分も走っただろうか。車の走りがゆっくりになり、窓が透明になった。広い場所にでた。建築物の中を30分も下ってきたということは、相当の深さの地下である。
運転手が声をかけてきた。
「驚いたでしょうね、今、深い深い地下にいます。もうすぐつきます」
車は地下駐車場といったところに止められた。
運転手が降りてきてドアを開けてくれた。
「こちらにどうぞ、もうおわかりでしょう、おそらく総理大臣も知らないところです、総理大臣は何年かで変わりますから、知られると困るのです」
「国の組織ではないのですか」
ちょっと怖くなってきた。
「日本の国の組織ですが、どの省庁にも属していないもので、独自に運営されています、外国に本部があって、そこにつながっています」
「国連ですか」
「ちょっと近いのですが違います、国連ができて、数年後にある人たちが独立させたのです、今は国連とは関係ありません」
「だけど、運営するにはお金がかかりますが」
「今では、ノーベルに相当する発明をした人の家系が、そこで得たお金をすべてこの組織の運営にまわしてくれています」
こんなことまで話してくれてしまっていいのだろうか。自分はどうなるのだろうか。彼はますます怖くなってきた。
どうぞこちらに、運転手はエレベーターに彼を連れていった。
エレベーターをおり、連れて行かれた部屋には、二人の男と、一人の女性が、彼を待っていた。
「よくきてくださいました、そちらにおかけください」
彼はテーブルについた。運転手も席に着いた。
「これから手伝っていただきたいことがあります」
女性の言い方は丁寧であるが、従いなさいという圧力が伝わってくる。
ここまできたのだからしかたがない。
彼はうなずいた。
運転手が言った。
「宇宙諜報部の人たちです、私が責任者Aです、彼女は秘書のB、補佐役のCとDです、あなたのことはすべて調べさせていただきました」
Bはコウモリタコ、Cは幽霊鮫、Dはオウライエソのイメージだ。それにしても、自分を調べたというが、どこまで知っているのだろう。
「学生や一般の人の顔を分類するのが趣味ですね」
Aが言った。どうして知ってる、彼はぞくっとした。だがうなずくしかなかった。
「あなたはとても記憶力がいい、なみはずれています、ただうまく使われていない」
Cの男性が話し始めた。そんなはずはない、小学校から大学までの成績を見てもらえばわかる。いつも中くらいである。
「成績は関係ないのです」
ここの人たちは彼の考えていることを読むことができるようだ。
「そうなのです、顔から考えていることがある程度わかるのです」
Cはそういった。
「我々も選ばれて、トレーニングをうけました、しかし、あなたの顔にたいする記憶と分類能力は天性のものです」
彼はおずおずと聞いた。
「どうして、僕が顔の写真を集めていることを知ったのですか」
「私がお話しましょう」
Bといわれた女性が説明をしてくれた。
「我々は、宇宙人を捜しています」
なんてことを言うんだ、そんなこと信じられるわけがないだろう。三流SF映画じゃないか。
「SF映画じゃありません、現実です、宇宙人が人間の顔をして紛れ込んでいます、それを探してます、だから、あなたの顔の認識力と分類力が必要なのです」
なんてことだ。
「私どもは、いろいろな顔と接する職業に就いている人から、そういった能力のある人を捜していました、あなたの記憶力で、いなくなった学生を探し出して表彰されたことなどをききました、我々はネットをつかい、普通では入れこめない部分まで侵入できます、だから情報をいくらでもとれます、あなたが、大学の学生ファイルの利用回数が、公務で必要な回数より高かったので、どうしたのかと調べました、それがUSBに落とされていることがわかり、同じ情報があなたの自宅のコンピューターにあることがわかりました。さらにあなたのコンピューターの中から、膨大な顔を分類したファイルをみつけました、最初は俳優などの名前のファイルでしたが、今は生き物の名前のファイルになっています、これはなにをするためというより、コレクターだと言うことに気がつきました」
自宅にある外付けのハードディスクにファイルはしまってある。コンピューターに接続しなければ、情報はひきだせない。ネットにつなぎ作業をしているときにアクセスしたのだろうと彼は思った。
「あなたは顔の分別能力、分類能力はとても優れてます。さらに調べたら記憶力も抜群と言うことがわかりました」
すべて知られてしまっている。観念するしかないだろう。
「僕は、なにをしなければならないのですか」
運転手だったAが、「おわかりになったようだ、やはり、飲み込みが早いし、決断力もある、それでは、作業室まで案内します」
こうやって、彼は宇宙諜報部の一員として、夏の間働くことになった。終わった後は、また大学職員にもどれるということだった。
作業室では、数人の若い男女がコンピュータ画面を見ながら、仕事をしていた。みんな深いところにいる魚の顔をしている。
彼が入っていくと、腰掛けていた椅子を転がして集まってきた。
Aが彼をみなにZ(ズィー)と紹介した。そこにいた人たちは分析官と呼ばれていた。Zとは臨時の分析官ということらしい。
女性の分析官が、「Z分析官のことはきいています、5年前、ある星から数十人地球に偵察にきています、それらを見つけて追い払う必要があります、まず見つけなければなりませんので協力してください、人間の格好に化けています」
彼はうなずいて「化けることのできる宇宙人ですか」ときいた。
「あれこそSFです、そんなに簡単にからだをかえることはできないでしょう、やはりうまくメイクする技術ということでしょう」
「それで、僕はなにをしたらいいでしょうか」
「Zさんが、顔を分類した中で、分類からはずれた人がまず候補になると考えています」
彼は侵入者は深海魚に分類した人だろうと思ったのだが、はずれたので腑に落ちない顔をしていたようだ。
「特徴のない顔を持っていると考えたわけです、目立たない日本人としてまぎれこんでいるでしょう」
なるほど、さすがプロの判断である。
彼はカバンから自分のノートパソコンを取り出した。
「Zさん、自宅から外付けのハードディスクをもってきています、参考に必要となるかと思いましたので」
すでに盗まれていた。だが、さすが諜報部である。外付けハードディスクに重要な部分がしまわれている。
Aがハードディスクを彼のコンピュータにつけた。彼は大画面に画像を飛ばした。
「これが、どれにも属さなかった今の学生たちです」
ここ五年間というと、少ないと言っても百人近くいる。写しおえると、分析官たちは「なるほど」といって、
「それでは、我々が画面に映す顔が、Z分析官はなにに分類するか教えてください」と写し始めた。
「この人たちはどういう人ですか」
「言動などから、怪しいとにらんだ人たちです、日本に数百名います、日本に来た宇宙人は十数名だと思いますので、絞りたいのです」
「このデータをZ分析官のコンピューターに送ります、これから用意した部屋にご案内しますので、そこで分類してください、どうぞ」
Aがそう言って立ち上がった。
彼もあとをついた。とても広い部屋であった。居心地のいいように、音の施設、映像の施設が備え付けられ、、もちろん居住のための上等な家具などもあった。冷蔵庫にはなんでもはいっていた。
「明日の十時にミーティングを行います、そのとき分類が終わった人間の確認を行います、急いでする必要はありません」
そう言ったAに、彼は「この宇宙からきた人たちの目的はなんでしょうか」と聞いた。
「宇宙人種によって違うので一概にいえませんが、今回は、まずつき合えるかどうかの捜査にきたのだと思います」
「それだけなら、ほっといても大丈夫じゃないですか」
「おっしゃるとおりなのですが、こちらとしても宇宙人種の性格や、最終目的などを聞き出す必要があります、将来、地球人がうまく利用されてしまうかもしれません」
「奴隷になるとか」
「地球では他の国の人間を奴隷あつかいしたことがありますが、とても野蛮行為です、今はそのようなことはしないでしょう、宇宙を高速でとべるようになったような宇宙人種は、その課程を乗り越えています、あからさまな奴隷などにすることはありません、必要なら人工頭脳のロボット奴隷をすでに作っているでしょう、その方がずっと便利です」
言われるとその通りである。
「だけど、SFのように、乱暴な宇宙人もいるのではないでしょうか」
「確かに、例外はあるでしょう、そういったのがいたとしたら、相手の姿になって、様子を探るような面倒なことはしないと、我々は考えています、もしそういう連中が地球にきたら、我々はあきらめなければならないでしょう、我々が過去から導いた結論は、そういった戦闘しか考えられない宇宙人種は絶えていると思います、宇宙航行技術をもつほどの星人はもっと頭がいい、逆に怖いこともあると言えます」
そういったものなのだろう。いま地球上の国は防衛という名目でほとんど軍隊をもっている。無駄なエネルギーの消費なことは確かだ、それが科学の向上や、芸術系の向上に向けられたら、人間の頭の進化はもっと早いだろう。
Aは彼に部屋の使い方を教えると、人を呼ぶときはこれを押してください、とデスクの上の赤いボタンを示した。食事は運ばれてきますから、とも付け加え、部屋から出ていった。
部屋の鍵はと、聞くのを忘れたことに気がついた。やはり、とらわれのみと思ったとき、ドアのブザーがなった。
「係りのものです、入ってよければ、机の上の青い光に手をかざしてくださいをください」と声が聞こえた。
彼が机の上を見ると、たくさんのマークがあり、説明がかいてあった。彼が入口とある青い光に手をかざすと、ドアを開けて女性がはいってきた。
「これから、お世話をさせていただきます、アミコです、よろしくお願いします、今日の夕飯はトンカツ定食になります、お飲物はどうされますか」
きれいな女性だ。声もすずやか、顔はなにに分類されるだろうか。ふっとおもったのは、魚じゃない、アンドンクラゲだ。それにしても、彼の好物も調べ上げてあるらしい。彼はマンションの近くのトンカツ屋に週一度は食べにいく。
「あ、ありがとうございます、あの、お茶で」
「お酒はいりませんの」
「はい」
「7時にお持ちします」
彼は鍵のことを思い出して、自分が外にでたときの、鍵がほしいというと、
「本人認証になりますので、ドアの前にたちますと、あきます、それでは7時に」
そう教えてくれて、部屋から出ていった。
夢じゃないかと思えるほど現実離れしている。
それでも彼は、コンピューターを立ち上げ、デスクの上のディスプレーと書いてあるコネクター部分につないだ。
ディスプレーは机の上に三つ、壁に大きなものが一つあった。デスクのディスプレーの表示のあるところに1から4までのスイッチがあり、彼は1を押してみた。自分のコンピュータの画面が机の上のモニターに映し出された。4をおすと、壁の大きな画面になった。
作業は1のディスプレーで十分だ。画面上の分析室から送られてきた顔写真の分類を始めた。彼の頭の中で、獣や魚、両生類、は虫類、鳥類、無脊椎動物のイメージがわきあがる。
画面に映し出される人の顔に、生き物の名前をあてはめていった。122番目の一人の男の顔がでたとき、彼は長く考えていた。
「いない、この顔に当てはまる生き物がいない」
そうつぶやいて、該当なしのファイルの中にその男の顔をしまった。
そのとき、ドアのチャイムがなった。
「アミコです、お食事です」
先ほどの女性の声が聞こえた。彼は青い光の部分に指をかざした。
アミコがワゴンを押して入ってきた。
エプロン姿である。キッチンに行くと、ワゴンの上のものをとりだし、料理を始めた。
できたものを持ってくるのではない、その場で作っている。
「ここでつくるのですか」
彼女は振り返って微笑んだ。
「そうです、ここでお仕事をしている方は、こういう形で、サポート役の人がついています」
「何人ほど働いているのですか」
「この施設では三十人です」
意外と少なかった。
「それだけでは、宇宙人の捜索はむずかしいでしょう」
「精鋭部隊ですから、十分です」
たしかにそうだった。
「朝食は7時です、パンとご飯どちらにしますか」
彼はパンと答えると、彼女は「夕食のかたづけは、朝しますので、そのままにしておいてください」ともどっていった。
彼は用意されたトンカツを食べた。いつも食べにいく店の味をポリッシュしたいい味だ。
食後、また仕事に戻ろうとデスクに向かうと、壁の大きなディスプレーが点灯し、今日の仕事の終了時間は十時です、朝は五時から可能です、という字幕が流れた。
彼はすぐに続きをはじめた。どの分類にも入らない顔はすくなかった。
彼の判断はとても速く、どんどん判定していく。分類不能以外の顔には、動物の名前をうち入れる時間が必要なので、1分2人として、一時間で120人、10時までに250人弱の判定ができた。数百人なので、明日の午前中早いうちにすべて終わってしまうだろう。
彼は夜の十時なると、風呂に入って、寝る支度をした。ベッドにはいるのは十二時より前と言うことは少ないので、いつもより格段に早い時間である。
朝は五時に目を覚ました。仕事に行っているときと代わりがない。七時にドアの呼び鈴がなり、アミコがおはようございますとはいってきた。顔色がいい、元気のいい顔だ。すぐにキッチンでトーストの用意をはじめた。
テレビを見ていると、用意ができたと、食事をテーブルの上にならべた。目玉焼き、ハム、野菜、紅茶、ヨーグルト、ジュウス、うまそうだ。
「何かほかにいるものがありましたら作ります」
「いや、十分です、昨日より血色がいいですね」
「そうですか、もうすぐ一月の休暇なのです、そのせいかしら」
「ここでは一月の休暇がもらえるのですか」
「はい、外にでられます」
「それ以外は、毎日働いているわけですか」
「いえ、ここの職員はどういう立場の人も、週休は1日、しかし、外にはでられません、しかし、年に一月まるまる休みがもらえます、そのときには外にでてどこに行ってもいいのです」
「この組織は極秘のもののようですね」
「はい、ここで働くものは、秘密を守らなければなりません、外でここのことを言うのは禁止です」
「もし漏らしたらどうなるのです」
「首になります、忘却薬を投与され、外に戻ります」
「僕のような臨時の人間もその薬を投与されるのですか」
「はい、そうなるか、ここの職員になるかです」
「アミコさんはご両親にはどこで働いているといってあるのですか」
「情報会社といってあります、だから会社のことは言えないといってあります」
「一月の休暇のときにあうのですか」
「はい、前回は両親と、北欧に旅行してきました、今回は友達と旅行します」
「それはいいですね」
「十年働くと一年のサバティカルがもらえます、それからは五年に一度もらえます」
「分析官も同じですか」
「はい、ここで働く者の条件に違いはありません」
待遇はとてもいいことがわかった。そのあと、すべての顔をチェックして分類をすませた。どうしても分類できなかったのは、十人ほどになった。そのデーターは分析室のホストコンピューターにすでにいっているはずである。
早く終わってしまった彼は壁掛テレビをつけた。外は晴天のようだ。特に目立ったニュースはない。
デスクのモニターが光った。
今日の会議は作業室で十時からですと映し出された。
あと三十分だ。どのように行ったらいいかおぼえていない。そんなに遠い場所ではないはずだ。
五分前にドアのチャイムが鳴った。
「アミコです、分析室まで案内します」と声がきこえた。
彼はデスクからはずしたコンピューターを抱えると、外にでた。アミコがスーツ姿でたっていた。
「こちらです」
彼女のあとをついていくと分析室はすぐそばだった。
中にはいると、作業室ではAと八人の分析官が大きなモニターに映し出されている彼が分類した顔写真を食い入るように見ている。
「おはようございます、短時間でよくこれだけ分類しましたね、とても参考になります、われわれも、Z分析官の見方をとりいれるように、学んでいるところです、これから、分類なしの十人の顔を調べますので、Zの意見も聞きたいと思います」
Aが彼に一番後ろの席を指さした。アミコも座っている。大きなスクリーンには十人の顔写真が並んだ。どれも整った顔をしている。
Aが「左から順番に細かく見ていくので、人間と違うような部分があったら指摘するように、Z分析官も参加してください、一部動画もあります」
最初の顔は男性のものだった。
一人の分析官が、「眉毛の毛の生え方が不自然にそろいすぎです、拡大願います」といった。その声に反応して、眉毛がズームされた。
彼は後ろをふりかえった。上のほうにガラス窓があるが、その部屋で分析室全体をコントロールしているようだ。
もう一人の分析官は自分のデスクのボタンをおした。「かなり規則的にですが、長さに多少の違いがあります、人工的なものではないですね」といった。先の分析官も、
「そうですね、それ以外に問題は、なさそうです」と答えた。
その男の横顔や後ろなど、角度を変えて画像が映し出され、食事をしている動画がでた。おかしなところはない。八人の分析官がそれぞれのデスクのぼたんを押した。隣のアミコが問題なければNEXTのボタンを押してください、そう教えてくれた。彼がそのボタンをおすと、次の顔写真が現れた。
髪の長い女性であった。髪の毛の中まで見えるほど拡大した写真が画面に現れるが、おかしなところもない。動画が流れた、女性の歩くところである。全く違和感はない。この女性も問題なしとされた。こうやって、5人目の若い男性の顔がでた。長い髪の毛を目の上に被さるほどのばしている。額が広いが日本人の平均的な顔である。隅々まで拡大された顔に特にかわったところがなかった。
映像は電車から降りてくるところだった。ふと、彼は男の目の動きをみた。電車から降りてくるときに、彼は気になるところがあった。ボタンを押すのに躊躇していると、アミコが、おかしいと思ったら、?のボタンをおしてくださいと、いうので、そのボタンを押した。それでも次の人に変わった。「一通り終わると、?を押した人の写真の人をもう一度チェックするのです」アミコがおしえてくれた。
こうやって、8人のチェックがおわると、Aが、5番目の男性をもう一度行うといって、その顔写真を出した。彼は「映像をお願いします」と言った。
スローモーションで、男性が電車からおりてきた。降りる前、目はホームの中程をみている。降りるときは足元を見て、次に行く方向、右に目を向けている。降りてからは左右のほかの人に目をやりながら進んでいく。
「Zさん、どうでしょう」
Aが彼に声をかけた。
「あのう、もう一度ゆっくり再生してもらえますか」
降りるシーンが再度始まった。
「おでこの真ん中あたり、髪の毛に隠れがちですが、よくみてください、おでこにはほとんどしわはみられません、しかし、降りる瞬間、おでこの鼻の上にある細い縦じわがかすかに動いていませんか」
彼が言うと、みんなも男の額に集中した。
「縦じわのある皮膚が下に動いたように見えますね」
Aが言った。
「確かに」
ほかの人もうなずいている。
男のホームの上に降りると、またおでこの縦じわの皮膚が右の方にむかってかすかに動いた。
「だけど、このような顔の皮膚の動きはいつもみられるのではないですか」
一人の女性の分析官がいった。
Zは「二つの目の動きと会わせて見てください」
おでこの真ん中あたりが、二つの目と同調して動いているように見える。
彼がそいういうと、
Aが「そうですね、それで、Zさんはどう思ったわけでしょうか」と質問した。
「おでこの皮膚が、目の動きと同期するものでしょうか、確かにおでこの皮膚にしわがよるのは一般の人でも見られます、しかしこの人は、右に目がむくと、皮膚がかすかだが右の方に動いています、違和感があります」
「うーん、たしかにそうだな」
別の分析官もいった。
「わかりました、マークします」
Aがそういうと、分析室に明かりがついた。
「Z分析官、ありがとうございました、部屋にお戻りになって、お休みください」
アミコが「もどりましょう」と彼を部屋までつれていってくれた。
「アミコさんも、分析の手伝いもするのですね」
「われわれは、生活のサポート役ですが、分析官たちの分析の方法も、機会があれば学びます、休暇で、外にでたときに、おかしな人をみつけたら、こちらに報告することになっています」
「遊びに行っても仕事を考えるのはつまらないのではないですか」
「いえ、宇宙から人を見つけようとしなくていいのです、何かおかしいなと感じた人がいたら、ということだけで、義務ではありません」
確かに、生活の中でのほうがおかしな動きをする人を見つけやすいだろう。
「それでは、お昼は十二時におもちします、なににしましょうか」
仕事をしているときは、大学の生協食堂で、定食をたべたり、そとにでて、ラーメン屋にいったりする。
「ラーメンおねがいできますか」
アミコは笑顔になってでていった。
アミコの作ってくれたラーメンは、とてもうまいものだった。毎日でも食べたい。
その日は用事がなくなってしまい、テレビをみていると、アミコがきた。
「運動施設に行ってみますか」
誘ってくれたので案内をしてもらった。彼は運動をする趣味はないが、街の中はよく歩く。
「ここでの生活は運動不足になります」
ジムにある運動器機の使い方をアミコが教えてくれた。
自転車にまたがってこいでみると、前の大きなモニターに景色が映し出され、森の道を自分が走っているような気分になる。これはいい。
しばらくこいでいるとAがやってきた。
「Zさん、あのマークした男を追跡官がおいかけています。どうですか、運動中で申し訳ありませんが、分析室の方においでいただけますか」
そう言った。
彼はうなずいて分析室に行った。
モニターには外務省から出てくる男が映し出されていた。帰宅時間のようだ。
彼が席に着くと、Aが「顔だけではなく動きを見てください、どうですか」
そういわれても、普通の人間にしか見えない。
Aは「われわれには、手の動きと足の動きが変にずれて同期しているように見えます、Zさんにおでこの皮膚の動きがおかしいと指摘されなければ、彼をみつけることはできなかったでしょう」
確かにおかしいところがある。だがAの口調はもうその男をエイリアンだと決めつけている。
「外務省の主席事務官で有能な人です、国の中枢にはいりこんでいます、エイリアンの可能性がとても高い、エイリアンは地方では目立ちやすいし、国や地球の運営のことを知ることもできないので、だいたい都市部の人間に化けます、しかも公官庁で働いています、昨日見ていただいたほかの顔写真の人間も省庁で働いていす、外務省はまさにうってつけのところです」
なるほどそういうものなのだ。
「もしエイリアンだとして、地球になにしにきているのです、征服したければ簡単にできるでしょう」
「いえ、前にも話したように、宇宙人は戦争みたいなことはしませんよ、あれは下等なものです、人間だって人が死ぬ戦はしないようになってきているでしょう、バカな国はまだやってますが、基本的に情報戦になるものです、エイリアンは地球の情報をあやつって、地球を征服するのです、地球はインターネットをつくりだした、宇宙の仲間入りの一歩ですが、情報網が発達したての星にはエイリアンがはいりやすいのです、情報網から入り込んで地球人に信用させて、それから乗り込んできます」
なんだか正しいようなきもする。
「それで、あの男がエイリアンだったら、どうするのです」
「追放します、というより、正体がばれたら、自分から戻っていきますよ」
そんなものなのか。
画面では男が電車から降りて、駅から外にでたところだった。場所は横浜だ。新しいマンションが林立している。男は一つのマンションにはいり、エレベーターに乗った。そこで映像はきれたが、すぐに再開した。自分の部屋のある階でエレベーターを降りるところからはじまった。自分の部屋の鍵をあけたところで、二人の男があらわれて、男を部屋に押し込んだ。見たことのある男たちだ。そうだ、CとDだ。補佐官と紹介された人たちだ。
結構乱暴な扱いだ。男は椅子に座らされ、CとDはなんとピストルのようなものを取り出した。
音も入っていて声が聞こえてくるが、日本語ではない、キーキーとしか聞こえない。
椅子に座っている男が手を挙げた。
彼は顔を見ておどろいた。おでこの皮膚が異様に激しく動いている。
あっと、彼は声をだしてしまった。
男のおでこの皮膚が破れ、大きな目玉があらわれた。きょろきょろ動いている。顔の皮膚が破れ、薄青っぽくなった。唇も赤くなく、青緑といったところだ。目と鼻はそのままだ。耳はなくなっている。あなだけのようだ。
三つ目の顔だ。SF映画のクライマックスみたいだ。
Aが言った。
「観念したようですね、Zさんのおかげです、この組織ができたのが百年ほど前、明治時代です、今まで一人もエイリアンを見破れなかった、この一人をつかまえたので、後は何人日本、いや地球に入り込んでいるのか、白状させ、自分の星に帰るように促します。
世界中に宇宙諜報部はあります、まだ本物のエイリアンを捕まえた国はありません、ニューヨークが最初になるかと思っていたのですが、日本が初めてです、それもZさんのように、顔の微細な形や動きをみて、分類できる繊細な能力を持つ人間がいないからです、感謝します」
「それでは、僕はこれで家に帰れますか」
「もちろんです、だけど、こんなに早く解決すると思っていなかったので、休暇が余っているでしょう、どこかにいったらいかがです、世界で初めてエイリアンを捕まえたのですから、宇宙諜報機関から報奨金がでます」
SFの夢でも見ているのではないだろうか。
「アミコが一月の休みをとって、最初に二週間ほど南米に遊びにいくといっていましたが、どうです、一緒にいっては、顔の分類を少し忘れてリラックスしてこられたらいいですよ」
どうしてAがそんなことを言うのだろう。
「友人と休暇にいくと言っていたと思います、アミコさんには迷惑なことだと思いますが」
「いえいえ、もしかまわなければ報奨金の中から三人分旅費を支出してくだされば、彼女も喜びます」
大学の教務主任が夏休み中は休んでもいいと言っていたし、まだ、海外はいったことがない、いいチャンスではある。だが。
「アミコさんの友達がどんな方かわからないし」
「なかのいい女性の友達です、いい人ですよ」
彼がまよっていると、Aは、
「行くのが一緒でも、向こうではそれぞれが好きなことをすればいいので、気になさらなくて言いと思いますよ」
確かにそうだ、そう思った彼は
「行ってみたいです」と答えていた。
「アミコに伝えます、明日、出発する家まで送ります、Zさんの旅行の準備はこちらでととのえます」
何から何までやってくれる。彼はまだ信じられない思いで部屋に戻った。あの三つ目の宇宙人は本物だろうか、映像だけ見せられたので、作られたものだったのかもしれないではないか、もやもやしている。
次の日の朝、戸をたたく音とがした。アミコですお話があります、と声がした。戸を開けるボタンを押すとアミコがはいってきた。
「Zさん、一緒にアマゾンにいってくださるそうですね」
え、アマゾンにいくのか。
「かまわないんですか」
「よろこんで、友人も一緒ですが、いいですか」
彼はうなずいた。
「それでは、このまま一緒にでませんか、朝食は外で」
いきなり提案されたが、Aはどういうのだろう。
「Aにおくってもらいます」
それならだいじょうぶなのだろ。
彼はカバンをもって、部屋を出た。
Aが車のところで待っていた。
「これから、アミコの泊まる家にむかいます、そこから、あした南米の旅行に行くことになります」と言った。
ずいぶん手回しがいいことである。それにしても早い。なんだか仕組まれているような気がしなくもない。
それでも彼はアミコと車にのった。彼が連れてこられたときの車だ。Aは運転手にもどった。
「Zさん、ホテルに向かう前に、ちょっとよるところがあります」
車は長いトンネルにむかった。二時間も走っただろうか。その間、Aとアミコはなにかと彼に話しかけ、退屈はしなかった。彼らは物知りで、宇宙人を捜す時のこつなどのようなことを話してくれた。それでも見つけるのは難しく、Zのような特殊能力を持った人の助けが必要だと言った。
AはZに分析官にならないか、といった。宇宙諜報部の建物に缶詰になるが、アミコがはなしてくれたように、一年のうち一月の休みがもらえるし、五年たてば、一年のサバティカルもあるということだ。
「顔の分類をして楽しめますよ」
Aは彼の弱いところをついてきた。
「おもしろそうですけど」
「返事はいまでなくていいですよ」
Aは言った。
車が止まったのはトンネルの中の駐車場だった。
「ここは、宇宙諜報部の分室です」
アミコが外にでるように彼に促した。
トンネルの壁にドアがあった。Aがドアを開けた。
「はいってください」
彼とアミコが入ると、一つの部屋に案内された。
中にはいると、CとD、それにBがいて、捕らえられた三つ目の宇宙人がいた。
「ごくろうさま」
AがCとDに声をかけた。
「地球に三千人いるそうです」
「そんなにたくさんきてたのか」
Bの秘書が言ったことにAは驚いている。
「いくつかのSNSの会社の社長もそうだそうです」
Cが言った。
「あのマスクもか」
Aがいうと、Dが「そのようです」と答えた。
「全部星に返すことはできるのか」
「宇宙諜報部に見つかったら、しょうがないから帰ると言っています」
Aは「残念だったな、もう宇宙侵略はあきらめろ」と宇宙人にむかっていった。
宇宙人は三つの目を動かして、
「この地球人か、俺を見破ったのは」と彼を指さした。細長い指が七本、手の平から延びている。
「そうだ、超優秀な分析官だ」
「そうだな、俺たちの変装をみやぶったのだから、地球の侵略はどのみち無理だったかもしれんな、百年見つからなかったから大丈夫かと思っていた。こんな新しい人種がでてきたわけか」
「地球人はかなり敏感な種族だぞ」
Aが宇宙人にいった。
「Zさん、この星人に何か聞いてみたいことはあるかな」
彼はおずおずと、「どこからきたのです」と聞いた。
宇宙人は、地球から千光年ほどはなれた星からきたんだよ」と笑った。
彼は宇宙人も笑うのだと思った。
「笑うのは高度に発達した生き物しかできないさ、地球人は笑うので、俺も楽しく過ごしたよ、なかなかこんなにいい環境の星はないんだぜ、だいじにしなよ」とまた、笑った。
彼はもう一つ質問した。
「どうやって地球に来たのです、光のはやさで飛べるものでも千年かかる」
「それは死んでも教えられない、光より早く飛べないという物理の原理を超えたのはわれわれだけだ」
「Zさん、それはあとでおしえてあげます、おまえたちだけではない、われわれはすでにその超物理現象を知っている」
それを聞いて宇宙人はびっくりしてた。
宇宙人が言った。
「そんなことはないはずだ」
AはBに「図面をみせてやれ」といった。
Bがモニターに複雑な宇宙船の設計図をだした。彼にはちんぷんかんぷんの世界だ。だが、それを見た宇宙人の顔色が青くなった。
「どうだ、われわれ宇宙諜報部にはわかっていることだ」
「わかった、もし黙って帰してくれたら、地球にはもう危害を加えない」
AはBとCに「いい返事だ、この宇宙人に誓約書をかかせておけ、もしその約束を破ったら大変なことになることを説明しておいてくれ」と言った。
BとCはうなずいた。
「それじゃわれわれはいくよ」
Aは彼とアミコに手を上げていく合図をした。
本当に宇宙人は地球に侵入していたのだ。だが、ここで疑問がでてきた。Aたちは本当に地球人なのだろうか、光より早く飛ぶことなどできないはずじゃないか、Aたちは宇宙人がうまく化けた地球人の可能性もある。しかし、まてよ、そうだとしても、俺をだまして何の特があるんだ、彼の気持ちは揺れ動いて、すっきりしていなかった。
そこからでてしばらくすると、窓ガラスが透明になった。もう銀座の高速道路の上だった。
月島のマンションに着いたのはそれからまもなくである。 彼とアミコは一つの大きなマンションの玄関で下ろされた。
Aは「それじゃ、気をつけてたのしんできてください」と声をかけて、もどっていった。
アミコも彼と同様大して荷物を持っていない。
「一緒にいく友達の家なのよ、今日はそこに一泊して、明日の朝、出発なのよ」
アミコはエレベーターのボタンを押した。
「旅行の荷物はお友達のところにあるのですか」
彼が聞くと、うなずいて、「Zさんの荷物も届いているわ」、と言った。昨日の今日のことなのに、早い、ふつうそんなことはできるはずはない。
5階でおり、515号室の呼び鈴を押すと、ハーイと言う声が聞こえた。
「アミコきたのー」戸が開いた。
え、あれ、彼は目を丸くして出てきた友達の前につったった。
「友達の、赤川クリスティーナ、大学三年生」
あの、うちの女子大生じゃないか。行灯くらげだ。おっとりとしているが、やっぱり深海の顔だ。大王イカのアミコと知り合いだとは思いもしなかった。
「子供の頃、近くの家だったの」
アミコがそう言うと、「こんにちは、よろしくおねがいします」と、クリスティーナは大きい目を彼に向けた。学生課の窓口にきた女子大生にまちがいない。
彼はどもりながら自分を紹介した。
クリスティーナが中にはいるようにうながした。二人ともとびきりの美人だ。彼はわくわくするより、縮こまってしまった。
彼はまたクリスティーナを見た。
クリスティーナはなにという顔をした。
「あの、大学の事務所で学生の窓口にいます」
「あ、もしかしたら、奨学金のこと聞きにいったときの」
彼女も思いだしてくれたようだ。
「Zさんは、人の顔をわすれないのよ、でもクリスティーナ、Zさんのこと人には言わないのよ」
アミコがクリスティーナに言っている。
「だいじょうぶよ、でも、アムコの知り合いっていうのが、私の大学の人だとはおどろいたわ」
「そのことは忘れて、三人で楽しく旅をしましょう」
「もちろんよー」そういって、クリスティーナはお茶の用意をはじめた。
部屋の中はとても広く、客室が三つもあった。一つの部屋にはいると、彼のための旅行用のものがおいてあった。コンピューター用のかなり大きな電源がおいてある。こんな重いものはアマゾンに持っていけない。衣類などがかなりあった。
居間に行くと、「今日は早夕飯にします、明日は暗いうちにでますから、料理は二人で作ります。Zさんなにが好きなのかしら」
自分はなにが食べたいのか、はっきりわからず、もごもごしていると、
「ヒレステーキなんかどうかしら、簡単だし、サラダやおつまみもつくりろう」
クリスティーナがそういったので、彼は「すごい」とやっと声に出した。
「それじゃ、お風呂にはいってゆっくりしてください、温泉のお風呂なの、飲み物なんかは客室の冷蔵庫にあります、自由にどうぞ、お風呂のあと居間か部屋でお好きなようにしていてください。その間に食事をつくります」
ぼーっとしていた彼はいわれるがままに、浴室に案内され、そのまま風呂にはいってしまった。風呂の窓から、富士山が見える豪華な部屋である。
どのくらい浸かっていたかもわからず、脱衣室に行くと、新しい下着とパジャマが用意してあった。
浴室から出ると、アミコが「居間でテレビを見てくださってもいいですよ」と、さそってくれたが、ともかく自分の部屋にいって、ベッドに横になった。すぐに瞼が閉じてしまった。
目が開いたのは、戸をたたく音が聞こえたからである。
「ごはんできてます」
アミコだ。
居間には大きなステーキができあがってじゅうじゅういっている。こんなすごいもの食ったことがない。
その夕方の食事は彼の味覚を強烈に刺激し、しかも、いつも飲まないワインやビールをつがれ、いつの間にか、ベッドに入っているという始末だった。
朝はやく戸をたたく音で彼は目が覚めた。まだ外は暗い。
「早く起こしてすみません、4時には迎えがきます」
あわてて起き上がり部屋からでた。
「朝食はなかでしますから、すぐでかけます」
いそいで顔を洗って、服を着替えた。だが、部屋にたくさんの荷物がある。これだけもっていけるのだろうか。
入口のブザーが鳴っている。
自分のリュックを肩に掛けたアミコがきて、「迎えがきました、手荷物だけもって出かけましょう」と言ったのだが、彼ははたと気がついた。いままで一度も海外に行ったことがない。
「あの、パスポートが」といいかけると、アミコが「用意してありますから大丈夫です」といった。宇宙諜報部の人たちは考えていることをよむ。それにしても、パスポート用の写真など撮ったことがないのだが。
彼はパソコンの入ったいつものカバンをもった。クリスティーナもリュックを抱えて自分の部屋から出てきた。
入口から四人の男性がはいってきた、どいつも深海の生物に似た顔をしている。「荷物を運びます、先に行ってください」、先頭の男がクリスティーナに声をかけた。
彼は「コンピューターの電源は要りません」
と伝えた。男性たちはうなずいて、彼の部屋にはいっていった。
彼は二人の女性と部屋から出た。
アミコがエレベーターのボタンを押した。上のボタンを押している。
エレベーターは上にむかう。どこに行くんだと思っていると、すぐに戸が開いた。
屋上だ。周りはまだ暗い。ヘリコプターがとまっている。
性たちはヘリコプターに歩いていく。操縦士らしい男が、ヘリコプターのドアをあけて、どうぞといった。そのあと、男は彼を見て「おはようございます、Z分析官」と、彼のことを知っていた。
彼もおはようございます、と挨拶をして、ヘリコプターに乗った。四人の男たちが荷物をヘリコプターに積み込んだ。
「それでは成田に参ります」
操縦士がボタンを押した。
ヘリコプターに乗るのも初めてである。すごくお金のかかる旅行じゃないか。また不安になってきた。
「空いてれば、宇宙諜報部の乗り物が使えるの」
アミコがそう言って、ポシェットから、パスポートを出して、彼に渡した。「Z分析官のです」。彼が開くと、彼の写真がきちんと張ってあり、十年先の有効期間がかかれていた。いつこんな写真とったんだ。なんでもできる組織でやっぱり怖い。
東京の空に舞い上がったヘリコプターはあっという間に成田についた。
明るくなってきた、成田のヘリポートに着くと、「つきました、乗る飛行機はむこうです」と操縦士が指を指した。その先には、緑色の線の入った小型のジェット機があった。
プライヴェートジェトだ。これも宇宙諜報部のものなのか。
「あれでいくんです、快適ですよ」
アミコはクリスティーナと並んでジェット機にむかった。
タラップの下には帽子をかぶった人と、操縦士らしき二人がまっていた。
「おまちしていました」操縦士は、彼に向かっておじぎをした。「パスポートをおねがいします」と帽子をかぶった人が手をだした。税関の人のようだ。彼はもらったばかりの赤いパスポートをわたすと、その人は開いたところに手に持っていた判を押した。クリスティーナとアミコのパスポートにも押した。
「おきをつけて」そう言って、税関の人は建物の方にもどっていった。
「さあ、どうぞ」操縦士たちの声で、三人はタラップを上り、ジェットの中にはいると、入口の広いラウンジのソファーにこしかけた。
「一時間後に離陸です、好きな席にどうぞ」副操縦士らしい人が後方にある二列のイスをさした。十人用のジェット機のようだ。
「飲み物などは、ここの冷蔵庫に入っています、ご自由にどうぞ、食事は私がはこんできます」
操縦士たちはコックピットのなかにはいった。
彼は最後列のイスに腰掛けてベルトをつけた。女性二人は、一番前の席に隣り合って腰掛けている。
ジェットは時間通りに飛び立った。
窓から見ていると、地上がぐんぐん小さくなっていく。雲の上を飛ぶのは初めての経験だ。富士がきれいだ。驚くことばかりだ。
ベルトをはずしてもいいサインがでた。彼女たちが手招きをしたので、ラウンジにいってソファーにすわった。
「行くところはアマゾンしか聞いていませんがどこの国ですか」
「アマゾンは主にブラジルを流れているのだけど、支流がたくさんあって、そこも含んでアマゾンだから、たくさんの国にまたがってるわ、ペルー、コロンビア、ベネズエラ、エクアドルなどです、今回行くところはフランス領のギアナですよ、アマゾンの森の中です」
「ギアナ高地は名前を知っていますけど」
「まあ、そのあたりですね」
なんだかいい加減だ。大丈夫なのだろうか。
「言葉が通じない」
彼が心配すると、「公用語は英語よ、だけどとまるところはクレオール語のところ」
なんだそれは、英語はなんとかなるかもしれないが、クレオールとは、そう言えば料理にそういう名があったような気がするが。
「クレオール語って、植民地で発達したのよ、ピジン語のなの」
怪訝な顔をしていると、
「ピジン語って、二つの言語が融合して話されるようになったことばのこと」
それでもわからない。
「ギアナはフランス領ギアナだから、クレオール語はフランス語と似ているところがあるの、ありがとうはメルシーにちかいわ、メシっていうのよ」
やっぱりわかない。
「ギアナまでどのくらいかかりますか」
「このジェット早いから20時間、ふつうの旅行だと、30時間はかかるのよ」
アミコはよく知っている。前にも乗ったことがあるようだ。
「お二人はそこでなにをするのです」
「ワニと一緒に泳いだり、森の中を散歩したり」
鰐は冗談だろう。
「ホテルというわけではないのでしょう」
「大丈夫です、地元にたのんであるから、特性テントができているはずです、食事の用意も、森の案内もなんでもしてくれるわ」
それなら、確かにすごいレジャーだ。
飛行機の中は快適だった。初めて雲の上を飛んだ気分もよかったが、食事もよく、彼にとって、20時間の旅は猿の顔への思いがかきたてられるものとなった。
それはこういうことである。クリスティーナが、アマゾンの生き物の映画をみましょうと提案した。食事のメニューとともに、映画や音楽のメニューも用意されていて、それを見て言ったのだ。
「そうね、おもしろそう」
ラウンジの前に大きなスクリーンがあって、映画の番号を押した。アマゾンの生き物の映画だ。川の中には鰐の仲間も迫力があったが、なにしろたくさんの魚類がいて、おもしろい生態のものもたくさんいた。さらにすごかったのが昆虫類である。かたちや模様も奇抜だが、不思議な生活をしている連中がいっぱいいた。鳥に至っては、体に飾りをつけて、変な求愛行動をしているものがおもしろい。ほ乳類は猿の類が多く、木の上で生活をしている。まだ見つかっていない猿の種類もあるようだ。
彼はその猿の表情に興味を引かれたわけである。同じ種類でも顔立ちが違うが、猿にも人間と同じように、個体によって顔の造作がさまざまで、彼は虫にあてはめてみていた。猿の顔は虫で分類しようと思って、出てくる猿ごとに、虫の名前をつけていた。あいつはキリギリスだ、あいつは蝉だ、などだが、決して形が似ていたのではなく、動作など複合的なものが、彼の脳裏に昆虫を思い起こさせたことから、猿顔に虫をあてはまたわけである。かめ虫の雰囲気の奴、蟻、バッタ、蝶、カブトムシなどである。
「行くところに猿はいるでしょうね」
そう聞くと、アミコはうなずいて、「たくさんいますよ、新しい種類も見つかりますよ」といってくれた。
「お猿さんの顔も分類できますか」
クリスティーナが興味を持ったようだ。
「ええ、おもしろそうです、今の映画の中の猿を分類してみました」
「種類によって違うでしょうね、同じ種類の中でもさらに、分類できるのかしら」
「やってみました」
「おもしろそう、これから行く森の中にいる猿をやってみるわけですね」
彼は俄然これから行くギニアの森に興味がわいた。
それからいくつも生き者たちの映画を見て、彼はどんどん猿にのめりこんでいった。
ギアナの空港におりると、プライヴェートジェットだからだろうか、わざわざ、制服姿のフランス人らしき男性が三人をむかえにきた。
フランス語でクリスティーナに話しかけている。顔はアランドロンと言いたいところだが、金目鯛に似ていなくもない。金目鯛も深海にすむ魚だ。
「アランが、おもしろい森の脇に小屋を用意してくれているって」
アミコが説明してくれた。やっぱりアランという名前なんだ。
「どなたの小屋なんですか」
「あの人の、クリスティーナの遠縁みたい、クールーにあるフランスの国立宇宙センターのロケット打ち上げ基地につとめているのよ」
すごい人と知り合いのようだ。
クリスティーナがアランを彼のところにつれてきた。
「アランよ、こちらはZさん」
とうとうZになってしまった。
「こんにちわ」とあいさつすると、にこにこと「よくいらっしゃいませ」と日本語で握手をもとめてきた。感じのいい男だ。
彼と一緒に空港の建物にいき入国手続きを済ますと、
「今日は空港内のホテルに泊まるの」と、クリスティーナはアランとともにホテルにはいった。アミコと彼もついていった。宿泊の手続きはすでにとられていた。
アランは部屋まで案内してくれると、日本語で、またお会いしましょうと、帰って行った。
「その森は遠いのですか」
彼はクリスティーナに聞いた。
「二時間くらい」
「そんなに遠くないのですね」
「高速のヘリコプターだから、時速350キロよ」
ひゃ、またヘリコプターだ、新幹線のはやさか、森まで700キロ、東京から大阪くらいだろうか。
明くる朝、大型のヘリコプターに乗せられ、空に舞い上がった。地上には家がちらほらあったがすぐに森しかみえなくなった。川が筋のように見える。
大きな鳥が何羽も森の上を舞っている。
副操縦士が、動物の死体でもあるんだろうと教えてくれた。ワシの仲間だそうだ。
二人の女性はスマホを見ながらなにやら話している。
座席の前にあるモニターがいきなり点灯した。
現れたのは宇宙諜報部のAの顔だ。
「みなさん、旅は楽しんでいますか、Zさんのおかげで化けの皮をはぐことのできたエイリアンは、東京や大阪、それに名古屋などに集中していました、すべて自星に帰るように説得しました。聞き分けのいい種族で、銀河系の反対側にあるかなり遠い星の連中のようです、科学はとても発達しているようで、地球を属星にしようとしていたようですが、あきらめると言うことでね、もうすぐ海王星の裏に着陸している母船にもどるそうです。母船から迎えの船が明日到着すると我々の任務もとりあえず一段落です、どうですZさん、我々の元で働きませんか、趣味と実益が一致しますよ」
Zはまだその気にはなっていない。あの建物に何ヶ月も缶詰になる気がしてない。
「アマゾンの森は楽しいですから、十分鋭気を養ってください」
彼はそう言って連絡をきった。
「地球を属星にするって、どういうことでしょう」
アミコたちに聞いてみた。
「宇宙には生命の生まれた星は数え切れないほどあるのですけど、知性がともなう生命体にはなかなか育たないのだと思います、地球人の脳がもっと進化したときに、その脳を利用したいと思ったのでしょう、地球をコンピューターのようにしたかったのです」
「あの星人より頭がよくなるのでしょうか、もしそうなら、地球人にとってよいことじゃないですか」
「いいえ、脳ばかり発達すると、生命の維持に機械を頼ることになり、地球の人間は地球というコンピューターの一つのICチップに過ぎなくなるのではないですか、からだの刺激がなくなり、そういった楽しみがなくなります」
「それはこまりますね、それを防いだわけですね、でもそうなるのに、長い時間かかるでしょう」
「そうですね、五千とか一万年とかの単位ですけど、せっかく宇宙で最高の生き物になろうとしてたのが、生きているただのコンピューターにされては悲しいでしょう」
彼女が言っていることに間違いないが、そんな先のことを予測して、地球を守っている組織があるとは信じがたいことである。
ヘリコプターは小さな湖の脇に着陸した。周りは森である。大きな丸木小屋が建てられていて、何人もの人が働いている。
我々がヘリコプターからでると、男性と女性が近寄ってきて、フエルカムと挨拶をした。どちらかというと、深海にすんでいるカニの雰囲気の顔をしている。
アミコがいうには、管理をしている夫婦だそうだ。彼も日本語で挨拶をした。
丸木小屋の前には小さな川がゆったりと流れていて、周りは木だった。森の一部と言っていいのだろう。
荷物を下ろしたヘリコプターが帰って行く。
何人もの人が三人の荷物を丸木小屋に運び込んでいる。
彼も管理人夫婦について丸木小屋の中に入った。広い部屋で、大きな木のテーブルがでんとおいてある。そこが食事の場所でもあり、くつろぐところでもあるのだろう。
奥さんがアミコとクリスティーナになにか説明をしている。
アミコが彼に言った。
「二階に我々の部屋があるそうよ、Zさんは一番奥の部屋、トイレ、シャワーや洗面所は一階のおくよ、食事はここです、水は私たちの部屋に用意されているって」
「ありがとう、テントのようなところで生活をするのかと思っていました、僕のマンションよりずっときれいな部屋ですね」
「宇宙センターのアランが用意させたようよ、クリスティーナがだいぶ前に話していたらしいの」
開いている窓から何かが覗いた。窓と言ってもガラス戸があるわけではなく、木の扉が外側に開いているだけのものだ。彼がそちらに顔を向けると、猿がのぞいている。
彼は猿と目があった。つぶらな目で、何となくテントウムシのようだ。あそこに猿がいると、指差したときには、猿はいなくなっていた。
ロッジの奥さんがクリスティーナになにかを言った。クリスティーナが彼に、
「猿はたくさんいて、人をおそれないので、近寄ってくるそうよ、森にはいると人をながめにくるんだって」
そう説明した。
それはとても面白い。
「写真を撮っても逃げないかな」
彼が言ったことを、クリスティーナが奥さんに伝えたら、奥さんは、彼に向かって、指でOKの合図をした。
「大丈夫みたいね」
彼は猿の顔を分類してやろうと大いに楽しみがましてきた。
「この森は光がよくはいるし、明るいので歩くのは問題ないそうよ、猿は何種類いるかわからないくらいらしい、そうそう、毒のある虫がいるようだけど、たとえかまれても、大した痛みではないし、長く痛みが続くことはないって、蛇は気をつけてほしいけど、だいたい向こうが逃げるので、問題ないそうよ、ゲートルを巻いて皮の長靴を履いていけばかまれても大丈夫だって」
彼は猿の種類については全く知識がなかった、だが、それはどうでもよかったのだ。顔を分類して、PC内で整理をしてしまうこと、それが楽しかった。
「あした、ここのご主人が森の中を案内してくださるそうです、私たちも行きます、なれたら一人で行ってくださいということでした」
ご主人はトムさん、奥さんはメリーさんというそうだ。本当の名前かどうかわからないが、彼にとって覚えやすい。
次の日、トムさんは彼の部屋にやってきて、無言のジェスチャーで服装について指導してくれた。おかげで、彼は映画によく出てくるジャングルの探検隊の格好に仕立て上げられた。インディージョーンズのように格好いいわけではない。
一階に降りると、彼女たちも探検隊の格好をして待っていた。
「準備できてますよ、いきましょう」
クリスティーナがトムにも向こうの言葉でそう言って外にでた。メリーも送りに出てきた。
背の高い提灯アンコウのイメージの顔の青年がやってきた。トムが何か言うと、うなずいている。
クリスティーナが、「彼は、ヌヌ、森にはいるときのボデーガードだって、英語の単語を少し知ってるそうよ」というと、ヌヌは彼のところにきてお辞儀をした。
彼もあわてて、お辞儀をして、握手の手を出すと、ヌヌはうれしそうに手を伸ばして強く握ってきた。
「目上の人から握手を求められるのは、光栄で嬉しいことです」
クリスティーナがそう説明した。
五人は森の中に入いった。彼の耳には、ホーオ、ホーオ、と動物の声が聞こえた。
「ウククと言う猿だって」
クリスティーナがトムから聞いて教えてくれた。
森の中は変わったシダが茂っており、その下に茸が生えている。
「暑くないわね、これならいつもの格好でもいいわね」
アミコが言うと、クリスティーナが「虫がはいっていいならね、開いている胸元から、飛び込むわよ」
と笑った。
「それはいやだな」
トムとムムが木の上を指さした。木の枝にチョコンと止まって、猫ほどの大きさの白い顔の猿が見下ろしている。鳴いていた猿のようだ。
彼が見上げると、猿がどんどん増えてきて、人間を見下ろしている。彼はカメラをかまえた。逃げようとしないので、何枚もとることができた。ウククとよばれているようだが、自分なりにイナゴとつけた。イナゴの顔の雰囲気だ。色のきれいな鳥が猿たちから少し離れた木にとまっている。見たことのないものばかりで、ファインダーから目を離す暇がない。
「Zさん、写真機ばっかりのぞいている、森の中をゆっくりみればいいのに」
アミコに言われてしまった。だが、彼にとって、撮った猿の集団写真を、ソフトで一匹づつ切り離し、証明書の写真のようにして、ファイリングすることが楽しいのである。
しばらく歩くと、「私たちもどるね、川に入って楽しみたいのよ、後はムムといっしょにいってくださいね」
アミコとクリスティーナはトムと一緒にもどることになった。
彼はうなずくと、ムムに行こうと英語で言って、森の奥に入っていった。
またカメラを木の上に構えた。
赤っぽい色の少し大きな猿が一匹枝に腰掛けている。顔も赤っぽく鼻が大きい。彼も知っている天狗猿に似ているが本当の名前はなんというのか。コクゾウムシにも似ている。もう一匹別の枝にいる。夫婦だろうか。
ムムが肩をたたいた。指さす方をみると、茂っている丈の高い草が揺れ動いている。黒いものがゆっくり立ち上がった。猛獣か、彼はあわてたが、ムムが大丈夫という仕草をした。
彼はムムに英語であの猿知ってるか、ときいてみたが、ムムは首を横に振って、にゅう、といった。はじめて、といいたかったのだろう。
黒い猿は立ち上がって彼らをみた。少し離れているから、おそわれそうになったら逃げれば大丈夫だろう。
だが、その心配はいらなかった、ずいぶん大きな猿の仲間だ。ゴリラかと思ったが、あいつ等はアフリカだ。新種かと思いながら、レンズを望遠に変え、写真を撮った。ゴリラとは顔が異なる。虫で言うとスズメバチに似ていなくもない。目がかなり大きい。そいつはZらを認めると、あわてて奥に走っていってしまった。
時計を見ると、すでに二時間ほど歩いている。昼食の時間は聞いていないが、そろそろもどったほうがいいだろう。彼はジェスチャーで、戻ることをムムに伝えた。ムムはOKのサインをして回れ右をした。話ができないのはもどかしい、メシ、メルシーと言ってみたら、サンクスと言われてしまった。英語が通じそうだ。
ロッジに戻ると、二人はまだ帰っていなかった。ムムが川を指さしたので、そのまま外にでて川の畔に行ってみた。アムコとクリスティーナが川辺で甲羅干しをしている。離れたところにはボディーガードだろう、筋肉質の男がすぐ水に入れる格好で立っている。
二人ともワンピースの水着をつけている。こういうところでは、ビキニじゃないのか。虫に刺されるのを警戒しているのだろうか。
「もどりました」
声をかけると「お帰りなさい」とサングラスをかけたアンドンクラゲと大王イカが立ち上がった。二人とも背も高いし均整がとれている。
「水がとってもきもちいいの、Zさん浴びない」と言われたが首を横に振った。
「僕はシャワーをあびる、お猿さんの写真たくさんとったから整理しなくちゃ」というと、二人は「もういちどいこ」と後ろを向いた。
おや、っと思った。アムコはだいだい色の水着、クリスティーナは水色の水着で、後ろが大きく腰の近くまであいている。気になったのは背骨のところが丸みをおびて膨らんでいることだ。二人ともである。ふつう肉付きのよい人でも、背中の真中は突起が見えるものである。尻のところから肩胛骨の下のレベルあたりまで蒲鉾型に盛り上がっている。奇妙な感じだが、と思いながら彼はロッジに引き返した。
トムが厨房からあらわれて、ランチといって、食べるまねをした。お昼のようだ。彼は、シャワーをあびて、カメラから写真をPCに移し、カメラは小型の充電器に接続した。
一階のラウンジに降りると、二人が帰っていた。
「水の中とても気持ちがよかった。水の中の魚がよってくるの、鰐がいたけど、セコムさんが見ていたから大丈夫だったわ」
と楽しそうだ。あのおとこは日本の警備会社と名前が同じだ。
テーブルには、シチュウのなべと、果物と、パン、バターチーズ、ボトルの飲み物などがならんでいる。
「好きなように食べてほしいということよ」
二人は、シチュウをカップにすくって、パンを浸して食べはじめた。彼も同じようにする。彼女たちは水着のままだ。
「今日これから、水上スクーターで下流の方に連れて行ってもらうの、一緒にいきますか」
「水上スクーターでどこにいくのです」
「水の上の散歩、一時間行くと、小さな町もあるそうよ」
「頼めばいつでものれるのですか」
「トムに言えば大丈夫よ、上流の方の森にもいろいろ猿がいるって、連れて行ってくれると思うわ」
「今日はもっと、この森を歩きます」
彼は断って、おいしい食事を楽しんだ。
そのあと、部屋で写真の整理をした。ずいぶんたくさんの猿の写真を撮ったものだ。写真をPCにしまうと、フォルダーに日付を入れる。それを原簿として、加工用にフォルダーをコピーする。フォルダーの中の写真一枚一枚は、画像の経歴を調べれば撮った日時が分単位で記憶されている。
コピーしたフォルダーの中の写真は個体ごとに、日付のはいった全身像と顔だけの写真をつくり、顔の印象から、似ていると思われる虫のフォルダーにしまっていく。その日は、イナゴ、コクゾウムシ、スズメバチ、カメムシ、セセリ、カミキリムシ、など6種類もの猿に出くわした。
それをまた、個体ごとに違いをみつけ、一言加えておく、イナゴ鼻まがり、とかイナゴ目離れなどと書いていく。そうやって、その日の午前中は五十五匹の猿の顔を収集した。
実におもしろい。特に、最後に出会ったゴリラのような大きさの猿は、逃げてしまったが、知性がかなりありそうだ。もう一度会えるだろうか。
その猿の顔写真を拡大した。スズメバチに見えたのは、少し猿にしては離れた大きな二つの目のためだろう。彼の最初の印象で、ほかの人が見てもスズメバチには見えないにかもしれない。
明日は、森の奥に直行しよう。
その日、ムムと入っていった森の奥、歩いて三時間のところには泉があった。きれいな水がわきだしている。あまり深くないが、金魚と間違うほどの赤くきれいな魚が、ひらひらと泳いでいる。ムムに指さして英語で何の魚かと聞くと、首を横に振った。あまりきれいなのでみとれていると、急に日が陰った。彼もムムもちょっと驚いて、後ろを振り返った。
あのゴリラの姿をした黒い猿が、何十匹も二人の後ろで立って、泉の中の赤い魚を見ている。まねをしているのだろうか。
ぎょっとしたかれは、どうしたらいいのかとまどった。猿たちはただ魚を見ているだけで危害をくわえそうにはみえないが、変に動いたらなにをされるかわからない。
するとすぐ後ろにいた猿が、「ぶぶぶ」と小さな口をならした。大きな離れた目と、ちょっととがった小さな口、それでスズメバチに見えたのだろう。大きな体の割には小振りの顔立ちだ。
こういうときには同じ言葉を発するといいのではなか、とっさにそう思った彼は、赤い魚を指さして、「ぶぶぶ」と言った。すると、猿たちの顔が一斉に笑ったような顔になった。いや、きっと笑っているに違いない。笑うのは表情筋のひっつれで、一種のリラックス状態、脳の中の気持ちが自然とあらわれるものだ。ほかの動物でもすこしは感じ取れることもあるが、顕著に笑うという表情をする動物はいない。こいつら笑猿だ。
かなり高度な脳を持っている猿だ。
彼は自分のカメラを猿たちに見せた。そして、それをムムに向けシャッターを押した。ディスプレーにだしたムムの顔を猿たちに見せると、すべての猿がのぞきにきた。
そこで、すぐ後ろにいた猿にカメラを向けた。いやがる様子がない。そこで、シャッターを押して、その猿にディスプレーの顔をみせると、やっぱり笑った。
それを見ていた、周りの猿が、指で自分をさして、カメラをさした。写してくれと言うことだろう。
彼はその猿を写して画像をみせた。ほかの猿が彼の前に一列に並んだ。みんな写してほしいらしい。
彼はみんなの顔を写した。そのあと、順に本人のいや本猿の顔を画面にだした。
猿たちは、やいやい言って喜んだ。
一匹が何かを持ってきた。
大きな木の実だ。ムムが驚いて「クスス」と言った。彼が木の実かと聞くと、グッド、ベリーグッド、と口に入れるまねをした。
何匹かの猿たちが、その実をもってきた。
彼は日本語でありがとうと言った。
猿たちは笑って、おじぎまでして森の中に消えていった。
彼はムムに実を持って帰ると言って、いくつかの実をひろって抱えた。ムムも持ってロッジに戻ったのである。
ロッジにもらった実をかかえてはいると、奥さんのベティーが「わーっ」と言う声を上げ、手を広げた。彼女は英語が得意ではないので、手まねであげますと、彼が実をわたすと、彼女はメシ、メシと言った。ありがとうありがとうだ。
夕方、アムコとクリスティーナが帰ってくると、その実は滅多にとれないおいしい実で、食べると元気がでると言うものだということをベティーからきいてくれた。カコの実というらしい。夕食時に皿に盛られて出てきた。
たべてみると、感触はメロン、とても甘くて、食べた後、ふわふわと空を飛んでいる気分になってきた、気持ちがいい。それも数分で収まり、幸福感に満たされた。きっと幻覚成分が入っているのだろう。
現地では貴重な実のようで、売りにいいっていいかとトムに聞かれたので、もちろん、と言うと、次の日、彼は水上挺で町に持っていき、たくさんの西洋の食べ物と交換してきた。
彼は笑猿たちの顔の整理をして、個々に名前までつけた。その日、PCをもって、三時間かけて泉にやってきた。
笑猿のこどもが二匹遊んでいて、二人を見るとあわてて森の奥に走っていった。それからすぐに、大きな笑猿が三匹、泉のほとりにあらわれた。彼は三匹の顔の区別ができた。
彼は笑顔を作って、PCを開いて泉の岸の岩の上に置いた。その三匹の顔写真を画面にだすと三匹はのぞき込んで手をたたいて喜んだ。
そんな様子を、彼は写真と、動画におさめた。猿の研究者が見たら仰天するだろう。こんなに知能の発達した未知の猿がいるとは考えていないはずである。
彼はこうやって、毎日森の奥までやってきて、笑猿と交流をした。ロッジに戻ると、それぞれの顔写真に、顔や体の特徴ばかりではなく、動作や仕草のそれぞれの違いまでも書き添えて、誰と誰が仲良くしているか、夫婦ではないか、などまで考え、笑猿の社会構成を図示までしたのである。
アミコとクリスティーナは川に遊びに行ったり、森にはいることもあったが、たいがい水上挺にのって、村や町に行って遊んでいた。
あっという間に日本に帰る日が近くなった。
次の日はギアナの空港に移るという朝、食事をしながら、アミコが言った。
「Zさん、あの珍しい猿のことずいぶん詳しく調べたのですね」
「とても知能の高い猿です、顔の表情も豊かだし、温厚でいいお猿さんです」
「人間もああいう時期を通り越して、進化してきたのでしょうね」
「きっとそうですね、新種ですよ、今までこんなに大きな猿がみつからないでいたとは不思議です」
「そうですね、とてもいい人間に進化しますよ、このような猿が、もし悪い星の連中にみつかったら、その星の都合のよいように遺伝し改変され、たとえば、奴隷のような存在にされてしまうかもしれません、Zさんが退治した星人は、地球人に化けて、人間をうまく捜査していこうとしていました、もし、他の星人がああいう猿たちを奴隷にしようとすると、なにをすると思いますか」
アムコはいつもとは違う、ちょっと憤った感じだ。
彼もそれを聞いて、まじめに答えた。
「猿の仲間のような姿になって、猿の王様になり、誘導して、家畜化するでしょう」
「その通りよ、それを防ぐには、化けた猿を暴く方法を考えないといけないの」
アムコが言うと、クリスティーナが続けた、
「それができるのは、Zさんしかいないわね、ほかの猿とどこかおかしいと気づいて、化けの皮をはがすのよ」
「Zさん、以前Aが言っていたように、宇宙諜報部にはいらないこと、趣味が人を助けることになるのよ」
「地球にまだ異星人はいるのですか」
「今のところいないけど、おそらく、そう言ったインベーダーは、宇宙のいろいろなところで悪さをしていると思うわ」
「僕のやっていることは、とても原始的なことですけど」
「そう原始的なことって、もっとも自然で、生きている脳がおこなうことで、コンピューターにはまねのできないことなの、ただ、そう言った能力を生まれつき持っている脳を持つ人は少ないわ、Zさんは日本どころか世界にもまれなのよ」
ただの収集癖にすぎないんだよ、と彼の頭の中では不思議な思いになっていた。誰にも知られずにそーっと楽しんで、一生を終わると考えていた。それが、宇宙諜報部に加わるなどできるはずがない。だけど、確かに収集して、ファイリングして、顔を眺めていられるのだとすると、満足感は大きい。しかも、もしそれが、今回のように役に立つのなら。
「もうちょっと考えますね」
朝食が終わると、「最後だから、その川で一緒に泳ぎましょうよ、そのときお返事くださるわよね」とクリスティーナが言った。
彼は迷ったが、そう言われれば、ロッジの前の川にはいっていない。せっかくきたのだからそうするかと思いうなずいた。
「私たち先にいっているわよ」
二人はラウンジからそのまま外にでていった。
彼は部屋に戻ると、用意されてあった水泳パンツをはいた。川につかるなどは高校以来のことである。
川の縁で彼女たちはまっていた。洋服を着たままである。なんで水着になっていないのだろう。
「川にはいらないの」
「入りたいけど、Zさんのお返事を聞いてからと思ったのよ」
彼は返事をする約束を思いだした。大学の学生課にいて、いつか自宅に学生の情報があることが知られたら、首どころか、刑事責任にとわれかねない。
「宇宙諜報部に入ります」
と返事をしたら、アミコとクリスティーナは大喜びで、「うっれしー」と声をあげると、彼の方を向いたまま、洋服を脱ぎ始めた。
水着をすでに着ているのだろうと思ったら、違った。すべて取り去って、彼の方を見ている。
見事な肢体だ、胸は立派だし、腰はくびれて、大腿ははぴっちぴち、股間は金色の毛が輝いている。
女性の裸をまともにみたのは初めてだ。
彼はびっくりして声もでない。
「もう、仲間よおーー」
アムコが叫ぶと、クリスティーナも「こっちにきてー」と彼を誘った。
彼女たちは驚いている彼の目の前で後ろを向いた。さらに肌色のズボンのようなものを脱ぎながら、川に向かった。
きれいなお尻の間を見た彼は卒倒しそうになった。二人が肌色のものを脱ぐと、お尻から、太い大きな尾っぽがとびだした。
二人の女性、いや宇宙諜報部の隊員と友達は、狸のようなふっくらとした尾っぽを揺らして、川にはいっていった。
水の中で、またこちらを向くと、はやく、いらっしゃいよ、と叫んだ。大きな胸と尾がゆれている。
彼がおずおずと、川にはいると、二人の女性は尾っぽを彼に差し出した。どうしたらいいのか迷った彼は、左の手でアミコの尾と、右の手でクリスティーナの尾をつかんだ。
「きっもちいいわー、さすってちょうだい」
彼は手で尾っぽをさすった。
「わー、気が遠くなりそう」
女性たちは川を泳ぎ始めた。
彼は水の中にはいると、首だけ出して、裸の尾っぽの生えた女性をいつまでも見ていた。
彼は宇宙諜報部の一員となった。Aがこれから出かけるところを説明していた。その星は、地球でいったら、五百万年ほど前の状態だそうである。ネアンデルタール人、北京原人が三十から八十万年前、猿人が七百万年前といわれいることからすると、これから、地球で人が生まれる初期の状態だと考えられるそうだ。
その星では、とある発達した星人が侵略しようとしていて、猿人に形を変え、その星の現住猿をだまして、遺伝子を改変しようとしているという。そこにいって、混じり込んだインベーダーをさがしだし、追い出す作業をするそうである。
そのようなまだ未開発の星に、建物を造ったりする事は宇宙条約で禁止されており、その惑星の衛星、すなわち月に基地をつくって、そこから、監視をすると言うことである。それには彼の顔に対する感覚が役立つそうで、現住猿とは異質の顔を探し出して捕まえる必要があるそうである。
宇宙諜報部は、ギアナの森にまだ知られていない猿人が密かに暮らしていることを知っていて、彼をつれていったということだ。そこで彼は猿の顔の分類の方法を覚えた。トレーニングをうけたわけだ。
アミコとクリスティーナは銀河の中程の同じ星の生まれで、宇宙諜報部に加わっているそうだ。その星の住人には尾があり、もっとも敏感なところで、電磁波まで感じ取ることができるという。
アミコは彼と一緒のチームに入って、猿人の星に向かう。クリスティーナは地球に残って、地球の防衛をもう少し続けるそうである。クリスティーナがそうっと教えてくれた。
「あなたが深海魚ってまとめたファイルに入っている顔写真の人は、ほとんどが、宇宙諜報部の分析官だったの、私が気がついて、Aにあなたを宇宙諜報部に誘うように言ったのよ、ごめんなさいね、ご両親は心配ないわ、アバターをつくって、今まで通り大学ではあなたが学生課で働いているから、いつか宇宙諜報部から退職したら、もとにもどれるの」
それを聞いて、驚くと同時に、両親との連絡を心配していたので、ちょっと安心した。アバターも顔のコレクションをするのだろうか。
「アバターはふつうの地球人の生活をするわ」
クリスティーナが言った。
地球の僕は結婚をして、子供を作っておいてくれるわけだ。
この宇宙諜報部に地球人が選ばれたのは、彼が初めてだそうである。チームは二十名で、出身の星はいろいろだそうだ。Aが総指揮をとる。
ギアナのフランス宇宙ロケット打ち上げ基地には、宇宙諜報部の宇宙船の格納庫がある。
彼は再びその地に訪れ、フランス人のアランの手引きにより宇宙船に乗り込んだ。アランは本当はどこの星のうまれなのだろう。
こうして、彼は銀河の反対側に向かって宇宙の中を航行中である。一年かけて、その星に行く。
猿の惑星に向かっているのである。
分類


