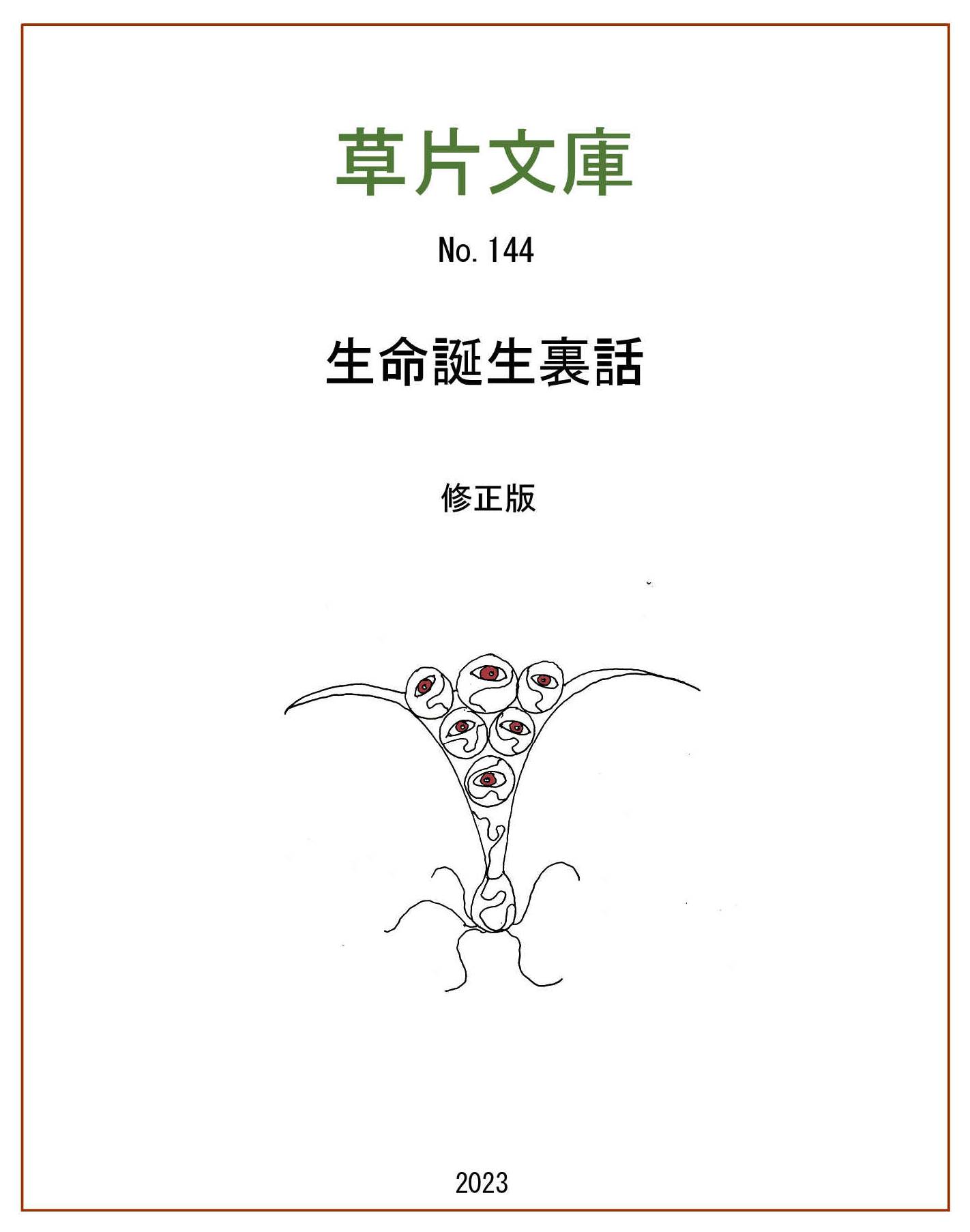
生命誕生裏話
ヘンなSF話し。
朝目を覚ましたら、頭の上を金魚がふわふわまっている。僕の金魚だ。水槽の中でもう十年も生きている。頭に粒々ができて、貫禄十分のやつだ。だけど水の中でゆったり泳いでいるところは、かわいらしくて、乙姫様のようなのだが、ふっくらとしているので、太姫と名前をつけてやった。
一月前に大きな水槽を買って、取り替えてやったばかりだ。なんで空中を飛んでいるんだ。
「おい、フトヒメ、なにやってるんだ」
声を出して聞いてみた。
「にゃー」とないた。
なんだ、猫のような声を出して、と、そろそろ夢もさめていいはずなんだが、さめない。
ベッドの上に上半身をおこした。
フトヒメが目の前に浮かんできた。幻影が消えない、頭がどうかなったんだろうか。
寝室の戸が少し開いている。フトヒメの奴、ここからはいってきたのか。イヤイヤ、金魚が空を飛ぶわけはない。
ベッドからでて、一階の洗面所にいった。
金魚がついてくる。
歯を磨く前に、居間の水槽をみにいった。自分が入れるほどの大きな水槽で、大型の熱帯魚を飼うためのものだ。そこにフトヒメ一匹がのんびりと暮らしているのだ。
え、なんだ、
水槽の水の中で、空気ポンプからわき出る空気の泡を気持ちよさそうにして、浴びているのは、僕の猫だ。
子供の頃、捨てられていたのを拾ってきて、飼い始めた茶虎の猫だ。ちょっと目尻が下がって見えたので、フニャと名前をつけてやった。
なんでおまえが水槽の中にいるんだ。
フニャは僕の方をみると、ふにゃっと笑って、空気の泡を吐き出した。
金魚のフトヒメが尾鰭をふりなが、空気の中をおよいできた。
うーん、こりゃ、自分の頭がもうおしまいか。最後の歯磨きでもしよう。
そう思ってしまった僕は洗面所に戻ると、顔を洗い、歯を磨いた。鏡に映った自分の顔はいつもと変わったところがない。
腹が減っている。朝のトーストと紅茶だ。キッチンで用意をして、とりあえず紅茶を飲んだ。トーストが焼けたので、バターを塗って、ハムを乗せ、辛子をつけて、食べた。よくこうやって食べる。
キッチンの小型テレビをつけた。
ニュースで、世界の大異変とある。
深海の底で象が群をなして歩いている。深海底の映像である。カメラが上を向くと、カバが猛スピードで泳いでいった。
画面が変わると、湖の底を犬が散歩している。なんだ、鳥が水中を泳いでいる。
今度は山の林の中だ。海星やウニがこけの生えた石の上にのっている。高足蟹が歩いてきた。
どうなっているのだ。
10月31日のハロウィーンを最後に、生き物の住みかが変わりました。
とアナウンサーがいっている。
だいたいハロウィーンとは、キリスト教の人たちがやることで、昔の万世節の前夜の祭りじゃないか。本来、この時期はこの世とあの世の門が開いて、死んだ人などがこの世におとずれる。日本で言えばお盆だな。
ケルト人たちは一年のうちのライトハーフ、ダークハーフになる日だと考えていたのだから、その日を境に死霊たちが迷い込むわけだ。
だからこうなったのか。
魚は陸に獣は水に、鳥は水中、エビは木登り、かわらないのは人だけよ、などと変な口調でしゃべっている。中継するアナウンサーも変わった。
これが本当なら、僕はおかしくない。
金魚のフトヒメが猫のフニャのかりかりを食べている。
居間に行ってみると、フニャが水槽の中で、フトヒメのために入れておいた、浮いている金魚の餌の粒を吸い込んでいる。猫には足りないだろうと思うのだが、ほんの一ミリの粒を一つ一つ吸い込んでかんでいる。
居間のガラス戸を開けて、庭をみた。なまこが椿の上に登っている。スベスベマンジュウガニが大手鞠の根本でうずくまっている。
外にでてみた。水蓮鉢の中で、かめ虫がおよいでいる。
なんてこった。
蟻の奴はどこへ行った。だいたい昆虫が水の中に行ってしまったとすると、海も川も湖も昆虫だらけだろう、なにしろ、地球上の昆虫の数は天文学的な数字になる。だが、地球表面の海の割合は7割りにもおよぶ、湖や川などをいれたらもっとになる。昆虫たちにとっても広々としたところで暮らせて幸せだろう。
だが、飼われていた獣たちはたいへんだな。家の中でのうのうと暮らしていた猫や犬は水の中だ。そういえば隣の犬はどこに行ったのだろう。大きな水槽など持っている家は少ない。風呂桶に水を張ったら人間が入れなくなる。きっと、一番近いところにある水のあるところに、トランスポーとされているに違いない。それでないと、道のそこいらじゅう、犬や猫市外だらけのはずだ。テレビではそういっていないのだから、何らかの形で海や湖にいったに違いない。海の遠い我が家の庭にカニがいるんだから。
庭にでたが蚊がくいついてこない。今年は10月にもなって、夏日がつづいていたので、蚊が飛んできて、うるさくてしょうがなかった。だがいないとなるとなんとも物足りない感じもする。
睡蓮鉢をのぞいてみた。いるいる。睡蓮の葉っぱの裏側に蚊がわんさかとくっついている。こいつら水の中でなにの血をすうんだ。すいれん鉢には虫しかはいっていない。昆虫の血液は緑色だ。魚は陸にあがったはずだから、水の中にすむようになった蚊は赤い血を吸えなくなったのだ。蚊をつぶすと緑色の血がついてくることになるだろうが、吸われることがなくなったわけだから、つぶす必要もなくないわけだ。あ、間違えた。蛇は赤い血ではなかっただろうか。蛇は水のなかでくらしているから、蚊は赤い血が据えるのだ。 まあ、どっちの血の方がうまいかしらないが。
あ、鯉が飛んで庭にはいってきた。群をなしている。この近くで、池があるのは、角の今井さんの家だ。空を飛べるようになった魚はどこに住むのだろう。なんだ、柿の木の枝にとまった。こいのぼりの木になっちまった。
木の枝にたくさんの魚がとまっているのは、またみごとなものだ。
釣りをする人は、釣り竿をかえなければならないな。補虫網で魚とりか。
家の中に入らないようにガラス戸をしめて、しっつしっつと追い払った。鯉の軍団は空高く飛び上がって、山の方に行ってしまった。カラスのようだ。カラスの奴はどこにいった。湖か海か。深海にでも行ったら真っ黒で忍者のようじゃないか。
あ、柿の木にクラゲが止まっている。あれは水クラゲだ。あのくらいの大きさだからいいが、越前クラゲなんぞが止まったら、細い枝だと折れちまう。
と思っていたら、太陽が遮られて暗くなった。何だと見上げると、越前クラゲが一匹太陽の前に浮かんでいる。だから日が遮られたのか、今越前くらげのことをおもっていたとこだ。でっかいクラゲだ。そういえば、クラゲは毒針で小魚を弱らせ触手を絡ませ、食っちまうじゃないか。
気をつけなきゃ、あ、とっつかまった。鮎が越前クラゲの前を飛んでいったんだ。鮎の奴クラゲを見たことがなかったんだな。危険なんだぜ。
まてよ、なんで水の中の生き物と陸の生き物がいれかわったんだ。進化の過程で周りに水や空気があったから、それようのからだになって、海に住むやつ、陸に住むやつがうまれたんじゃないか。いきなり変わったら、魚の鰓呼吸では空気の中の酸素をとりいれることができない。逆もそうだ。空気を吸うため肺の中に水が入ったら、トカゲだって、鳥だって、獣だって死んでしまう。
水クラゲが柿木から僕の前に降りてきた。目の前に浮かんで傘の四つの輪を赤く光らせて、「星が人の言う神様なんだ」といった。
どういうことなんだろう。
「星は神で星の上のものを自由にできる。俺たちの体に酸素細胞ができているんだ、空気からその細胞が酸素をとりいれる、こうなる前は水の中から酸素を取り入れていた細胞がそれにかわったんだ、この星、地球がやったことだ」
「なんで、地球は陸と水の生き物を入れ替えたんだ」
「あきたんだろう」
「でも僕たち人間はそのままだ」
「地球は地球の考えがあるのだろう」
「太陽や月や火星や、諸々の星も考えをかえたのか」
「それは自由だ、火星にはいま酸素がたくさんあって、前の地球のように生き物がたくさんいる、もしかすると、人間を火星にやっちまうおうというのかもしれんな」
「だけど、火星は火星、地球は地球じゃないのかい」
「そうだよ、それぞれ自分たちの考えがある、だけど、お互い会話をするし、融通をきかせてるんだ、地球の海の生き物の半分は火星に移住した。
「火星でおまえさんたちや、魚が空をお飛び、カニや海星やウニが歩いているのか」
「そうだよ、酸素がなくても生きていけるようになってね」
シラノドベルジュラックの月と太陽と星の滑稽譚をおもいだした。まだ読んだことがないが、タイトルがおもしろくてあたまに残っていたようだ。
「ところで、人の言葉を話せるのは、くらげだけなのですか」
そうきいてみると、
「いまのところはね、やがて、どんな動物でも人の言葉をはなすようになるよ」
「海の中の生き物もそうなるの」
「そうだよ」
海の中で鳥や獣が人間の言葉で話しているのを想像して、うるさいだろうな、といやになった。
「言葉は空気の振動で、のどの筋肉をコントロールすることで作られる、それより前に、脳には言語野がなければならない」
「なにいってんの、あんた、宇宙の存在を前に、そんなこと言ってなんになる」
「だけど、科学を信じられないとなると、人間はなにを信じたらいいんだ」
「お星さま、ここだと地球を信じなさいよ、悪いようにはしないと思うよ」
「そういわれても、人間は未来を考えることのできる生き物で、このままじゃ、未来を予測することができなくなって、自信が揺らぎ、生きていけない」
「人間が生きていけなくたっていいじゃない、なぜ人間がいなければいけないの、進化に息詰まって、逆に退行し始めている生き物なんていらないでしょう、我々のように、単純な体の構造の方が発展性があるのよ、エントロピーが高いのよ、固まっちゃったらおしまいね」
そういわれてしまうの、なさけないが、しょげるしかない。その通りなのだ。人間はものを発明したのはいいが、体と頭を退化させてしまったのだ。
「まあ、人間さんも太陽をあがめて、星の輝きに感謝して、地球を信じなさい、そうすりゃあ、悪いようにはしないって」
水クラゲはそういうと、ひゅーっとUFOのように空の上に飛んで行ってしまった。
「おーい、餌くれ」
家の中から大きな声が聞こえた。
だれだろう、なかにもどると、水槽の中から、猫のフニャが、金魚の餌を全部食っちまって、叫んでいる。
「金魚の餌入れてくれ」
水の中から僕をみつめて言っている。
「猫の餌いれてやろうか」
「あんなもん食いたくねえ、さっき、金魚の奴が戻ってきて、猫の餌をみんな食っちまったよ」
「あたいにも、えさちょうだい」
ランチュウのフトヒメの奴が、空気をふわふわ舞ってきて要求した。
金魚まで人の言葉を話すようになりやがった。
水槽に金魚の餌をまいてやり、猫の皿にかりかりをいれてやった。
さて、暗い日曜日のメロディーが頭の中にながれてきた。今日は日曜日、会社には行かない。会社はあるのだろうか。
PCを開いた。
いきなり、画面に「崩壊」の字が現れた。カタストロフィー、画面がだんだん暗くなり、消えていった。
ネットの世界は消失した。
玄関から外にでてみた。
道を高足蟹が歩いてくる。後ろからついてくるのは、いろいろな種類のカニだ。花咲ガニ、毛蟹、越前ガニ、モクズガニ、カラッパ、弁慶ガニ、稚児ガニ、
カニの行列はどこに行くんだ。
「よお、人間、カーニバルにいこうぜ」
「なにのカーニバル」
「俺たちのだよ」
「遠いの」
「駅に行く通りにあるよ」
カニのお祭りとは、北海道のカニ祭りぐらいしかしらない。カニを売っているんだ。うまいんだ。
「高足ガニが顔をちかづけてきた」
「なに考えていやがる、俺たちを食うことだろ、馬鹿いうなよ」
はさみをふりあげた。僕を食べるつもりだろうか。
「人間なんかうまいわけないだろ」
カニが集まってきて、僕の頭の毛をしゃきしゃききりはじめた。よしてくれよ、そういったって聞かない。坊主にされた。
カニたちは歩いて行っちまう。僕はあとを追いかけた。駅に通じる道の脇にたまに寄るスコッチハウスがある。
カニたちはその店のドアを開けると中に入っていく、中から、いつものマスターの声がきこえる。いらっしゃいませときこえてきた。
なんでここがカーニバルだろう。
中を覗くと、カニたちが椅子の上にすわっている。
「スルメちょうだい」といっている。
「カニのバルだ」
高足蟹がそういった。
なんだ、そうなのか、僕も一杯のもうかなと、空いていた椅子に腰掛けると、マスターが、「カニさんたちのおかげで繁盛してます」
とスルメを僕の前においた。スルメはイカの干した奴だ。イカが見たら怒るだろうな、と思っていると、ドアが開いて、イカが入ってきた。
イカがいすに座ると、マスターがスルメをおいた。
いいのだろうか。イカがスルメをかじった。
「うまいね、このスルメ」といった。蟹たちも食べている。僕も食べよう。
口にいれて、ありゃと思った。
カンピョウじゃないか。
「カニさんのお気に入りで、イカさんもお好きなようで」
人間のマスターはすっかり、この世にとけ込んでいる。商売はこういう風じゃなければだめなのだ。
「いつものちょうだい」
ウイスキーのロックだ。
カニやイカも「それくれ」と叫んでいる。
マスターはみんなの前に、ロックをおいた。
「氷ってこういうつかいかたもあるのね」
タラバガニの奴は、グラスの中の氷をしげしげとながめて、爪の先でかき回した。爪についたウイスキーのしずくを先口に入れると、
「あら、たまごが産みたくなりそう」
と、目をぱちぱちさせた。
「それは、角です」
マスターが説明をする。
「四角いウイスキーなの、丸いのないの」
「酒ならあります」
「それちょうだい、ロックで」
角をなめ終わったタラバガニがいった。マスターが「酒のロックとは新しいのみ方です」といいながら、棚から白鶴酒パック、まるをとった。
「この氷がいいのよ」そういいながら、氷を爪でかき回し、酒を口に運んだ。
「あら、これが酒なの、なるいわね、甘いし、私、やっぱりウイスキーかな」
「ウオッカはどうです、ロシアですよ」
マスターはタラバガニが寒いところにいることを知っていたのでそう言ってみた。
「古いわよ、あそこいや」
タラバガニはウイスキーがほしいと言った。マスターはオールドパーをだした。
僕はやっと角のロックを飲み終えたところだ。
ごちそうさまと挨拶をして店をでた。
あらもう帰るの、カニたちがはさみを振ってくれた。
駅にむかった。空には魚が飛んでいる。道には海老や海鼠が歩いている。
あ、道の脇の植え込みの上で、蚊柱ができている。いや、おかしいな、蚊は水の中で暮らしているはずだ。近寄って見ると、ちょっちょっと動いている。蚊の動きではない。どこかでみたことがある。
蚊にしては小さすぎる。何だろうと、見つめていると、いきなり、目の前が拡大された。
蚊柱だと思ったら、ミジンコじゃないか。玉ミジンコが集まって、空中で上下のダンスを踊っている。
れれ、なんで視野が拡大されたんだ。周りを見たらいつもの目になった。
いつの間にか自分の目に拡大機能がそなわった。ほら、最近のデジタルカメラは、光学的な拡大機能と、デジタルによる拡大機能をそなえていて、両方をあわせると、さらに倍の拡大ができる。デジタルの拡大機能と言うことは、人に当てはめると、脳にはいった情報を脳の拡大機能がそうすることになる。脳にその機能が備われば、拡大鏡はいらない。そういえば老眼鏡だっていらない。頭の中のズーム機能で大きくすることができるわけだ。どうも自分の脳に、視覚における脳のズーム機能がそなわったようだ。ということは、音だってデジタルによる拡大、脳による拡大があったって、いいだろう。
どうも僕の頭の中にズーム能力が生まれたらしい。音を高くしたいと思ったら、高く聞こえた。もしやと思って、画像をモノクロにしたいと思ってみたら、見える世界が白黒になった。ひゃ、おもしろい。セピアにしてみた。見えてきた駅舎が古い趣のある建物になった。
元に戻れと念じたら、いつもの画像になった。
さらに考えた。透視機能はないのか。そう思ったら、あった、前から歩いてきたカニの殻が透き通って、肉だけが見えた。うまそ。おっといけない、だが女性がきたらどうする。きているものの中身がみんなみえる。うひょ、っと思ったのだが、女性が全くいないことにきがついた。
あのスコッチバーは、マスターしかいなかったが、前はかわいい助手がいた。
女性が消えている。地球の陸に残っているのは人間の男だけだ。女性はどこにいった。
商店街をのぞいてみた。コンビニ、菓子屋、立ち食い蕎麦屋、宝くじ売場、女性の店員さんがまるっきりいない。宝くじ売場にいた二人の女性もいなくなっているので、だあれもいない。
そうだ、交番にちょっとかっこういい女性の警察官がいた。のぞいてみた。髭を生やした警官が一人でぽつんと立っている。
スクールバスが駅にきた。降りてくるのは男の子ばっかりだ。よく見かける二人用の赤ちゃんの乳母車を押して、男性がやってきた。いつもは奥さんが押し、買い物にくる。男と女の二卵性双生児だときいたが、のぞくと一人しかいない。
女性がいなくなった。空には魚が飛んでいる。駅の屋根の上にたくさんの海星がむらがっている。この駅は古い駅舎を改造して、昔の部分は木と瓦でできている。瓦にこけが生えていたがそれを食べているのだろう。
家に戻った。テレビをつけると、ニュースをやっていた。いつもは出てくる女性のキャスターがいない。池の中にいる猫を映し出している。字幕に「みんな男」とある。雄のまちがいじゃないのか」と思ったら、耳の後ろから「雄と男の使い分けは生き物差別だぞ、英語なんて元々差別していない、日本だけじゃないか」と言う声が聞こえた。
振り向くと、耳の脇にタコが浮かんでいる。
「どこからきたんだ」
「相模湾」
「あんたさん、雄、いや男かい」
「そうだよ」
「女のタコはどこにいったんだい」
「そんなことしるかい、いなくなっちまったんだ、せっかく、発情期になって、これからプロポーズの踊りをしようと思っていたら消えちまった」
「人も女がいなくなった、他の動物たちもそうなんだ、これじゃ、種が絶えちまうな」
「どうだろうね、この世界をつくったやつが、なにか考えをもっているんだろう」
「誰が作ったんだ、この世を」
「俺でもあり、あんたでもあり、誰かでもある」
タコの奴、とんち問題をだしやがった。
「神様か」
「神とな、自分がこの世を作っていることを認めるのが怖い人間が作り出した架空の生き物だな」
「くらげが、神は星だといっていた、星が作ったとね」
「そう、星または神が作った宇宙に生き物がいて、生き物の一生は、その生き物が作るこの世なんだ」
「この世は俺が作っているとしたら、なんであんたがいるんだ」
「俺もこの世を作っている、あんたに見えている生き物はそれぞれの世を作っている。それが折り重なっているだけだ、あんたが死ねばあんたの宇宙はなくなる、だけど俺の宇宙は残っている。そういう仕組みなんだ」
なんだかだまされているようでもあるが、真実でもあるような気がする。ハロウィーンからおかしくなった。それが変化している、海や湖に陸の生き物がうつった。海の生き物が土と空気の中にうつった。動物たちが人の言葉をしゃべるようになり、女性、女、雌がいなくなった。次は何だ。
水槽の中の猫が、決まっているじゃないかと僕を見ている。タコの奴が水槽の中から外を見ている猫のフニャに、宙に浮かんだまま墨をふっかけた。墨がガラスに跳ね返って、空中を浮遊し、僕の顔にかかった。
しょうがねえタコだ。
手を伸ばして、タコをつかもうとしたら、天井の方に浮遊して、玄関の方から出て行ってしまった。
水槽の中の猫のフニャが笑っている。
金魚のフトヒメが家にもどってきた。
こいつは雌だったはずだが。
「昔はな、俺たちはたまに変わるんだよ、今は男だ」
金魚も性転換するのか。
「どうでもいいんだそんなこと、それよりあんた、そろそろいかなくていいんかい」
「どこへ」
「女たちが待っているところだよ」
「墓場か」
僕は女性たちは墓の中に入ってしまったと思っていた。
「陰気な奴だな、もっと広々としたところでまってるぜ」
猫のフニャもそういった。
とたんに、地球が見えた。
あれ、どこにいるんだ。月も見えるし太陽も見える。
僕は手をばやばやさせた。体が動く。何にも着ていない。素っ裸だ。
「おーい、こっちよ、最初の男がきたわ」
そう呼ばれた。
声の方を見ると、白い小さなものがたくさん浮遊している。ミジンコのように見える。
ここは宇宙だ。月と地球の間に自分は浮かんでいる。
一生懸命、手を動かすと、ミジンコのように見えた白いものは、女たちだった。真空の中に浮かんで、手をふっている。近づくと、みんな女だった。裸の女たちが数百人、宇宙空間に浮かんで僕を待っていた。
女たちが一斉においでおいでをした。
いきなり僕は裸の女たちに取り囲まれた。
地球のほうを見ると、金魚のフトヒメと猫のフニャが飛んできた。
離れたところに、金魚が数百匹浮かんで尾鰭をひらひらさせている。そこにフトヒメは引っ張られていった。そこからちょっといったところに、猫の集団が浮かんでいる。フニャはそこに引っ張られていく
「さー出発よ」
数百人の女たちに囲まれて、僕はどこかに連れて行かれるようだ。
「すてきな星をさがしましょう、アダム」
一人の女が言った。
なにがアダムだ。え、僕がアダム!
と、やっと気がついた。こうやって新たな生命が、選ばれた星に誕生するんだ。
これが星、神がやっていることなのか。
アダムとイブは二人じゃない。アダムは一人でも、イブは何百人もいるんだ。冗談じゃない、僕はまだどうやって子供を作るかも知らないんだ。
「やだー」
と叫んだ。
何百人もの裸の女が、一人の男を囲んで、宇宙の中を漂っていくのを、フトヒメとフニャが笑って見ていた。
生命誕生裏話


