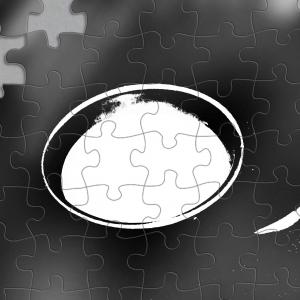「人ならざるもの」
放火
蠟燭を桔梗に翳すと月の細工が浮びあがる。それは、昔、油絵の遊びを終わらすのが勿体無くって錦の文箱にしまったまゝの灯し火が扉をたゝいた模様に似ている。例えば文箱、金魚鉢、ねじ巻きオルゴール。中につめるは油絵具、万年筆の欠けた先端、壊れたお守り。
優しい川の上流は、紅を溶かした山茶花の年中零れる檻に囲まれた泉が起点となっていた。恋しい鳥籠の南京錠は雨を綴った竜胆の伏す姿、用心に用心を重ねて見回りの蝶のように花弁を広げて点々と。
これを監獄と言うなら言え。その恐ろしい妄想から手を離さないと拒むのなら。
蠟燭は桔梗に焦がれて灯るのである。一目見合った川の袂で当世に似合わぬ恋をした。かざぐるまを袖で抱いた内気な瞳の面影よ、おろおろと星明かりも射さない夜更に失くしたボタンを当て所も無く探す哀れさは、月の細工そのまゝに。
…呆れた悲しい男の慰めである。桔梗の花は竜胆の覆いの心尽しの中に咲く、画家は今日も山を下りられず人里を偲んで筆を動かす、人が訪れる希望は無いが明日には懐かしい川の汀に倒れているかもしれないから。この青年は、一匹の蛇に何年間も殺され続けているのである。
青年は昔罪を犯した。まだ若い学生の時分、同じ学校に通う娘に恋をした。娘の名前は白藤と言い、青年の名は水無月と言った。二人は互いに戸惑いながらも少しずつ糸を重ねていった。
典型的な整った交際。初めて逢った川に架かる橋の上でよく話をし、月や虫や植物のこと、星や建物や動物のこと、本や鏡や布のこと…さゝやかな幸せ、その語がよく似合う二人であると、二人の知らない場所で他の学生達は囁きあっていた。
白藤はいつも赤色目覚ましいかざぐるまを抱いており、どうやらそれは外に出る際には必ず持つことにしているらしい。この時世にならもっと洒落たものでもあるだろうに戦前にぽとりと道端に捨てられていたようなみすぼらしい形の紙もよれた花びら持つおもちゃ、彼女が生まれた時から渡されたのだと仮定しても随分な古びよう。
如何して大事に持ってるの、と野暮な質問はしなかった。白藤が大切にしている物ならば、誰かが咎める義務もあるまい、水無月は白藤の穏やかな横がほが曇ることをしたくなかったから。
その夜は、いつもの川に訪れる螢を見に行こうと、珍しく白藤の方から誘ってみた。待ち合わせ、なんて心の浮き立つ言葉だろう、逢えると分かっているからこそ喜びは甘く薫り立つ。初めて染めた淡い浴衣を母の形見の帯達の中から選んだ半幅帯を文庫結びで整えたら、埃を被せぬ草履を引っ込み思案な素足に通し、娘はお守りを抱いて出掛けて行ったきり、家にはもう戻らなかった。
亡くなった両親の後を追ったのだろう、横恋慕した輩に連れ去られたに違いない、魔に魅せられて攫われたのだ、見初められて神隠しにあってしまったのかも。どれもこれも水無月の焼石を鎮める水とはならず、焦りを加速させる潤滑油となり青年の懊悩はますます燃えるばかりであった。警察は水無月の事情聴取を諦めた、それ程かつての美青年は面窶れ玲瓏だった言語はすっかり不明瞭で前後揃わず誰に語るのかも他人にはもはや判別能わず、塞ぎ込んでいるばかりかと思えば不規則に静かに一人笑い続けている時も多々。
罪は水無月に為される時を待っていた。憎々しいくらい澄ました切れ長の目を光らせて、哀れな青年を愚かな笑い者にさせるための眩い松明を握らせて、家と言う家に体当たりさせたのだ。
蛇
面白い。
久し振りに玉章の花が咲いたから、一つ見合い相手でも用立ててやろうかと街の人間を品定めしている時、かなしい娘に目が行った。
まじないを捧げて彼女を六ツの花の蛾にすると、玉章と蛾は涼しい目をパッと逢わせたかと思えば遠慮がちに身を寄せ合う。お似合いだ、きっと美しい雨の言葉が生まれることだろう、実にいい月夜だなどと安堵していたが。
まさかまあ恋人をなくして正気を脱した男が、この山をも燃やそうとして山上まで這って来るなんて。愉快な趣向を凝らしたな、月め。
この人間に愛する者は蛾になったと教えたところで信じまい、むしろますます躍起になって火をぶん回すだろう、先ずは凶器を無力化しなければならないな。雫をはらはら、花をほろほろ、そんな御伽めいた魔術はしない、頭を冷やすたくらみも兼ねて、細雪を頭からどっかと降らせた。
黒ずみの一点も近寄せない埃を払う鬼火に恋人の姿でも重ねたか、水無月は暫く動きを止めた。人間は意思持つ人形かと蛇はクスリと笑う、面白いと感じたのはこの時で。もう今や水無月の記憶も両親の記憶も育って生まれた経緯すらかぼそい唄の凍みずに溶かした結綿の虫の前の姿にこうも固執するもんかと、おきまりの悪戯心がむくむくと首を擡ぐ、そして青年に話を持ち掛けたのは此処に留まり画家になること。それで山を犯したお咎めは帳消しにしようと誘ったのである。
「そうすれば白藤にまた逢えますか。」
水無月にはもはや冷静な判断など出来ようか。
山を傷付けようとして踏み荒らした罰の心配よりも、自らの悲願の心配をするか。散らされた土や草の絶叫など聞こえてもいまい。
「白藤。白藤と言うのかあの女は。」
「御存知か。」
御存知も何も蛾にした娘だ、手ずからな。頭はその名を聞くと僅かに冷めているようだが、未だ此奴は画家になると返事をくれていない。
「画家となりこの山に留まると約束してくれるなら教えよう。」
「白藤は何處です、何處なのです。それを先ず聞かなければなりません、その後私を煮るなり焼くなり御随意になさったら宜しい、逃げる腹積りなど持ちあわせてはおりませんから霊山を犯した罪は甘んじてお受け出来ます。出来ますが先ず」
「山の中で声高に語るな。此処では黙り続ける人間が一番賢いのだ。愚かな者は愚昧な高説を垂れ流す、今口を滑らせたお前のように。」
悔し涙を灯す山茶花達を我身のようにしならせて水無月の首に絡みつくと、そのまま半月に首を捻った。
「お前は此処を理不尽だと思っているな。」
水無月の死体の耳元で声がする、頭に響く。
「山は人間の世界ではない。人と異なる秩序や礼儀があり、それらを土台に生活が為されている。」
指は動き口元へ運ばれて、皮膚を噛み切り絵具を絞り出した。
「土台は言葉で語られるが、人類だけには理解されない言葉だ。地球で最も孤独なのは月でも虫でも樹でもない。」
彷徨う筈の肉体も精神も、花籠の中にきちんと仕舞われる、それが山の決まり。罪人の歓迎方法、引くには軽い扉。
鹿
玻璃を菫に染めたかろい雨粒は、途中燕の姿に身を映し羽で旋回を二、三度続けそれから一文字に水面へ飛び込む。しぶきは殆ど桜の螢とパッと散って人目には望まれず、僅かに残り香二、三滴が見えるだけ。今は昼で、夜ではない、それなのに山上はいつも夜のようだ。黒いから暗いからは理由でなくて、光も射すし太陽も知っているのに、それらの光は昼に感じるものとは肌の触感が異なっているからだ。
月の光に寵愛された泉は桔梗あふれる玲瓏の水蜜郷。泉下には桃色のトルマリンと、白い炎絡ませるサファイアと、エスメラルダの結晶が敷かれて野原に莟と開花が入り混じり息をするのが光も長閑によく見える。
汀には山茶花の囲いと錠の竜胆が混在し城壁となり、泉を守るかのようになっている理由を、彼は問いたいが首を真逆にされた状態では上手くいかない。一日に出せる音は幼児の真似事喃語だけ、絵を描く為の動きもこれではままならぬ。どうにかして絵画を描く為の姿勢ぐらいは取らして貰いたいが声の主は此処に居ないのか昨晩から一切返事をしない。自棄になって絵画溢れて来る十指を空に任せてバラバラ振った。
「そうそう。その仕事をして欲しい。」
水無月の前に鹿が現れていた。
神経回路がどうの、生体学的にこうの、そもそも梟の動きが人類に出来るのかなどの腹の底に溜まっていた怪異への疑問や生き永らえている事実に対する苛立ちは、その鹿が彼の視界にやって来た時立消えた。
翡翠を両眼に埋め込んだ眼差し鋭く令月に未だ凍る梅の如く春の搖らぎに震えぬもので、冬を愛した白色かぶる睫毛は長くふさふさと宝石を光から覆う朧の雲影、清流を宿す体毛は夜露に撫でられた艶失せず、凛乎とした目鼻口は淫雨にも乱れぬ隼の威と品格を備えており、角は紅白の彼岸花、花弁の先にはスノードロップのランプがほの青く灯る。
従わなければいけないとか、逆らってはならないなどの恐怖や怯えの類はこの生き物の前では要らず、唯深呼吸を穏やかにしながら膝をつくだけでいいのだと、初めからそうする為に自分は生まれて来たのだと想わせるこの鹿の前で、水無月は言葉も思考も失った。
「君の仕事はそうやって指を振ることだ。絵筆を握ったり構図を練る作業はしなくて良い、絵を描くとはこういう手段もあるのだから。」
言葉を聞くと素直に頭が下がり瞳を閉じて聴覚に意識を深く冴えさせ一音も逃し零したくないと身が緊まる。
「けれど幾ら山上とは言え君は人の身。人のよく用いる手法で絵を描きたくもなるだろう。それに、言葉を禁じたままとは蛇の趣味も悪いことだ。一つ、深呼吸をして御覧。」
不格好なおじぎをしたまま水無月は従った、かつて国家への服従を頑として拒み徴兵の任務からも逃げた者はいとも平穏に鹿の命を承った。
「顔を上げて、自分の姿を見て御覧。」
難儀だったちぐはぐはあっさりと糸を通され元ある形を求めて縫われていた。水無月は遺体の形になる前の身体に綺麗さっぱり仕上げられていたのである。
「蛇は愉快だろう。」
その言葉だけ置いて鹿はいなくなっていた。跡には見たことの無い花の型が地面に刻まれているばかり。
猪
画材と称される物品など用意されてはいない。仕方無く水無月は己の指で土をなぞり始める。
だんだん相手の相手の出方が分かってきた気がする、恐らく自分がこの場所に囚われている間、蛇や鹿のように動物達が此処を訪ねて来るのに違いない、そして自分に何らかの影響を作用させる、これは或種の
「手慰み、戯れだ。」
自分は山の玩具とされてしまった訳だ、恋人を失ったが為に。
「白藤。」
君はもう、まさか此世に居ないのか?何か災いが降りかかってしまったのか?私が守らなければならなかったのに。怒りや悲しみが衝動の源となり得るのなら、後悔で生命を産み出してくれてもよさげなものを、そしたら君とまた普段の日常を歩けるかもしれないのに。
「恐ろしい奴だな、君は。」
今度は何が遊びに来たのか
「蛇の笑う声が海向こうから漣の寄るみたく届いたから何事か愉快な興業でも催されているのかと楽しみに泳いで来たが…」
蕺草の牙は陽(果して本当に太陽の其かは知らないが)に晒されているものの一寸でも侮れば忽ちに肉を突き刺すだろうと相手に教えられていた。それとは真逆の桃の鼻、柔らかくも光沢を持った呼吸器にひどい顔をした狂人が映っている。
「次は猪か。」
牙で私を突き刺すだけ突き刺して満足したら他の動物のように消えるのか。
「消える、は言い得て妙とは思わないね。」
前置きは不要だ弄ぶなら早速やってくれ
「そう怖い目で僕を見ないでくれたまえ。君を嬲ろうとするんじゃないよ。」
分かってるさ悪意があって玩具遊びをする奴がいるものか
「違う違う、君を諭しに来たんじゃないんだ、君の知りたいことに答える為に来たんだよ。ねえ、君、水無月君だろう?白藤さんの想い人。」
「白藤を知っているのか。」
陽は傾き夕暮が足音を空に谺させる。
「知っているとも。僕等はあの子のご両親のご両親のご両親の……数を挙げたらきっと君の寿命までに終わらないから此処は省くね。えゝと、兎角僕は白藤さんのご一族をよく知っているよ、かれらは信仰がうつくしいから。」
「白藤が今何處にいるかも分かるのか、彼女は無事なのか?あの待ち合わせの日に何があったンだ!」
水無月の語気激しさに対して猪はそっと目を伏せた、けれど、彼は言わなければならない。
「蛾になったんだよ、彼女。」
「生きているのか。」
顔を伏せたまゝ猪は続ける。
「生きているよ。でも、もう人間の白藤だった記憶は無いんだ、玉章の花の…あの烏瓜って君達は呼ぶみたいだね、その花の、その……」
「お嫁さんにでもなったのか。」
塩辛い恐怖がひしひしと見に迫る、このまま首を扼されて窒息させられるんじゃあないか。
「そうなんだな?」
此処等一帯を燃やすなんて叫ばれたらどうしよう、悪い想像が未来の現実になったらどうしよう、今、今のうちに、彼の身体を取り押さえておかなくては。
「……山をこれ以上荒らしたりはしないよ。」
怯えた子供がよくするような武者震いを決め込んでいたすっかり臨戦態勢はこの時ようやく水無月の顔を正面に見た。
「そうしたら、彼女も燃えてしまうだろう。」
瞳に掛かる前髪の下、均整のとれた薄い唇は僅かに微笑み言葉を紡ぐ。
「いつもかざぐるまを抱いていて、私はその理由を問わなかったけれど、或時彼女の学友が訊いたのさ、どうして大学に来る時いつもそれを持ち歩いているの、と。
白藤は人と話すのが実は苦手でね、普段は笑って誤魔化すのだけれどその時は違った、きっと病状が良かったんだろう。このかざぐるまは御先祖様が神様から拝領したものだから、壊れてはいても大切なお守りなんだと話したんだ。
学友はそれ以降お守りを話題にすることもなく黙って彼女から離れて行ってしまったけれど。話の受け入れられない者は、容易に彼女に近づくべきじゃない。」
それは恋人に寄る者への嫉妬でもなく怒りでもなく、
「でなければ殺されてしまうからね。」
とても穏やかな雨だった。
雨月
人間じゃない、と彼女は微笑んでいた。それは眩しい夏の光に悄れる紫陽花のボタンを抱きしめていた星の無い夜、初めて二人が逢った時。
水無月はありきたりな学生であった。それはありきたりに世を憂い、ありきたりに自死しようとしていた時。
声も無いのに悲鳴が聞えた気がして片足橋の向こうに置いたまま川の袂をふと見た時。
ボタンを彼が汀に見つけたら、彼女は泣きながら頭を深く下げた。その慎ましい重ねた指には赤ぎれが幾つもあり、真冬でもないのにどうしたのかと尋ねたら、人間じゃないとだけ返されてそのまま背中を向けようとするいじらしさに思わず細い手首を握った時。
いつもいつも雨は降っていた。雲に隠れるお月様からその情けを託され街中を照らすようにしめやかに。
白藤と水無月は並んで川辺に座り、ぽつぽつと互いの境遇を相手に教え合った。水無月人並みに死を早めようとした事を打明け、白藤は自身が人間の嘘の姿だと打明けた。どういうことかとそっと尋ねたら、彼女は赤くも古びたかざぐるまを指差したかと思うと、哀れな炎で染めた唇でそっと吹いた。
しゃぼん玉は藍に深く滲みいつかの浮世の川を憶えている。その中の景色は真冬なのかちらちらと泡雪が霙と混ざって空から泉下へと泳ぎゆくが唯一匹羽を朱の傷口に押被られている虫が居た、今時と比ぶれば大層大きな火取り虫、蛾はまもなく息絶えそうな大きな黒眼をしている。
白藤はまたりんご飴にキスをした。
東雲草の莟は解かれ円く浮ぶ巻物には、代りに横たわる人の姿、そしてその冷えきった胸元へうつ伏す蛾の姿。蛾には人間の親類縁者も友も居ない、それだのに見ず知らずのこの青年は自身の寿命を全て残らず死にかけの虫一羽にあげたのである。如何して自分を助けたのと訊く間も無く腕に縋ってみるけれど、もう青年は目を開けない。
赤い菫の花束から一本摘みベルのように軽く振れば花粉は鱗となって夜の川の色を逆さに映し銀清らかな上映中。
蛾の姿はみるみるうちに青年のような頭となり目鼻口となり四肢胴体も変化してすっかり青年となっていた。そして恩人は川底から吹き上げた春風に桜の欠片となって空に渦の弧を描きながら散り去った。
今や上流貴族の若者となってしまった蛾は、背広の内側に他人からは見えない位置に縫いこまれてるボタンに気がついた。それが今晩水無月の見つけた紫陽花のボタンだったのである。
「私の御先祖様は蛾なの。恩人の方に身も魂も捧げられたから、これからは人間の姿で生命を繋ごうと決心されたのよ。」
「赤いかざぐるまは自分達のルーツを忘れない為に先祖が作ったものだと私に白藤は教えてくれたんだよ猪君。」
水無月のくせ毛はだんだん濡れそぼる。
「君が白藤さんのこと其処迄知っているとは、心外だったよ。」
「歴史のお勉強はもう受けて単位も取れる程さ。消えろ、私はお前の遊び道具になれる基準をクリアしちゃいないんだから。」
「クリアしてるよ、君は雨月一族のことは聞かされたかい?」
表情を見れば充分に理解る。
「僕が水無月君に雨月一族のことを話すためにやって来たんだ、山に着いた時頼まれた。」
「まさか」
「そう、白藤さんに。」
「私のことを憶えているのか。」
「雨月はそういう一族なんだって。」
平安時代、水晶の真似をした雨が降る日があったとか。その日人間は一人として起きていられず貴賤関係無く丸一日眠りにつき、次の日には眠っていた記憶を持てないと聞く。つまり水晶の雨が降るという事実は誰も見た者がいないと言うので架空の事とされてしまったが、全土に唯一人だけその空模様は実際に起きたことだと識る者が存在しているのもまた事実で。
主人に命じられ、山中で愛する者の首をはねた者だったらしい。その者―性別までは伝わっていないのでこう称する―が例の雨の日、眠ることも無く昼間は花を摘み野草の小さな花束を拵え、暁には今世よりずっと深かったであろう藍濃き月を見上げたと言う。この記憶を先祖としたのが蛾に命を譲ったかの青年の一族であった。
命を贈られたかつての蛾は、自身の指に触れ青年の記憶や生れる以前の遙か昔を聞いた。名前を持たぬこの一族は誰かに仕え、誰かの命で自身の愛する者を殺す運命にある殺し屋の一族で、抗っても辻褄を合わせるように立ち戻るらしく、粛々と我身の境遇を受け容れ続く者達だったと言う。彼等彼女等の人生に於ける最大の喜びは死ぬときばかりでその時初めにして終りの笑顔を微笑みを零すのだとも言う、殺めた愛する者の冷たい墓に縋って…殺し屋一族の最期の姿は残らず決まっているようだ。
人の心を失っても人の愛を憶えている、その一族の末裔が会ったばかりの瀕死の蛾に冷たいぬくもりを与え虫は人間となり雨月と名告り生き続け白藤が生まれ、蛾に戻された。人間の娘は先祖に帰ったのである。
「帰って彼女は幸せなんだろう。虫の姿ならば徒らに人を傷付けることも無い。」
水無月の服は滴り色を変え始めていた。
「水無月君、白藤さんは確かに殺し屋の一族から派生してはいるけれど、凶器を隠し持てるような神経の子じゃないよ?僕達は川辺や野原を歩く彼女の姿を知っている、白藤さんはとても優しいんだよ、君だって分かっているんじゃないの?」
首を横に振ると雫が散った、緩慢な動きなのに。
「殺し屋の標的は植物や動物ではない、いいか、人は人にしか感じ取らせない恐怖を与えることが出来る生物の姿なんだよ。」
重みで伸びた毛先が青年の片目を覆った。
蜉蝣
赤いかざぐるまの話をする時は決まって指の皮をいじっていた。慟哭を白い手袋に隠すような可憐な鈴蘭は、毒で満たされている。人を安心させ心を許す表情は最初は快いであろう、一ト月ほどは自分に好意を寄せてくれているのだと浮かれる者も中には多い。
美しさは三日で飽きるものな筈だが一度きりの質問と返答に交わされた微笑みは日を追うごとに鮮やかとなり艶を増し、半年、一年経っても脳裏を離れぬ。相談すれど病院に通えど恋わずらいと笑われる、だが違う。これは誰かを慕う情でなく恐れ震える憔である、死に至る病としても月鼈雲泥の相違があるのに当人以外は識り得ない苦しみと戦きに圧し潰されて這い出でて光と見た場所は自死の崖。
会話をするだけで人一人の命を奪う、命を吸って花はますます臈たけうなだれる。
そんな生涯をなぞって来たうら若い娘が偶然とは言え人の命を助けられたと知った時、その喜びは如何ばかりであったろう。
狐
「鹿め情けを掛けよって。」
蛇はやっぱり笑っていた。雨は降りやみまた降るために休んでいる空は灰色に眠り、抱きぬいぐるみの月を隠す。立ち去る機会を掴み損ねた猪は、竜胆よりするりと現れた蛇の楽し気な顔を憎々しげに横目で見遣る。
「水無月君をもう放してあげなよ、趣味が悪いとまた鹿にお小言を貰うよ?」
「此奴にそんなに怯えを持つ必要は無いぞ。もう観念したのか来たばかりの頃の威勢も消えておる。」
蛇は山茶花を一本自分の方を向けさせて接吻をしながら蜜を飲んだ。
「この山茶花をお前憶えているかい?」
山を登ると人間は言うものだが
「お前が此処に来たばかりの時足蹴にした子だよ。」
貴様等は我が家の門戸を誰彼構わず開けておくのか
「可哀そうに可愛想に。よし、よし、君を草花以外のものにしてあげようか、何、狐、狐がいいと。良いだろう、なら哀れまれるべき狐の姿にしてあげようね。」
まるで人間だけは別なのだとでも胸を張って吐かしそうな輩だから
「子供と生き別れた母親、水無月は其処にいるよ、さあさあ好きにお遊びな。」
山の玩具になるのだものを。
九尾の呪いは燦爛と黄金に搖れて、ツンと尖った鼻先は少し鳥じみしている。これだけ見ると如何にも次元を逸した獣と思うが早まる毋れ、開かぬ両眼を零れ想いあふるゝ涙の色は葛の裏風そよぐ月白、しとしとと手さぐりに歩み寄る。
「貴方、貴方ですか、貴方がよくも、えゝ、よくも。」
長く研がれた爪紅は水無月の荒れた頬にかっしと強かに喰い込んだ。その痛苦に水無月が呻き声を立てると狐はハッと後退り、先にも増してほろほろと落涙しながら頭を深く下げて地面に崩れる。
「ごめんなさい、ごめんなさいよ。こんな、こんな事する為に姿を変えて頂いた訳じゃありませんのに、愚か、愚か、ごめんなさい。どうか許してくださいな、どうか許してくださいな、でなけりゃあの子の為になれない、私はあの子の為になれませんの。」
みるみると狐は散ってしまった、それでも頬を伝う母親の心は赤く泣く。痛みを手当てする方法も分からないまま水無月は蛇にひどく掠れた声で質問した。
「愛するものと別れたものは、この山にまだまだいるんじゃないのか。」
蛇は本当に楽しそうだ。
絡繰
風がとても強い日は、失くし物が多いと言う。目も開けられない突風が来ると、腕に下げていた長傘やら革鞄に外付けのミニポーチやら定期券入れがよく獲物になる。満員電車でキーホルダーやマスコットが失くなるのとやゝ似ている。それらは持ち主自身の過失の為か他者の悪意かはたまた物自体の意志なのかはいつの世でも判明し得ないので、どうやら風は白黒文目を厭うらしい。
水彩絵具を筆に吸わせて点、点と花を咲かす。互いの色が混ざらぬように嘘を描いたら濃縹を指に咥えて幾何学模様の本音を乱雑に、薄幸の夢見るパステルは爛熟し躑躅のテエブルクロスは毛花に舞う猛禽の嘴漏れる紅百合の濃く燻る色と零落した。指から離れた色はかつて握っていた色にはあらず。
「図書塔を描いてくれ。」
蛇は猪に帰ってもいいと言ったが猪は水無月と一緒にいると返した。
「白藤に頼まれた訳でもあるまい。」
「そうだけど、山に人間一人で残していて生気を保てる筈が無い。可哀想だよ、元々は蛇が白藤さんを蛾に戻したのが悪いのに。」
氷燃ゆる舌はちろちろと、笑う。
「人間に優しいなあお前は。」
「何とでも言いなよ。僕は彼の傍にいるよ。」
「構やしない猪君。私は一人で大丈夫だから。」
「水無月君、僕はこんな図体で視界にうるさいだろうけど、黙っているのは得手なんだ。君の邪魔にならないように草陰でじっとしているよ。」
「そうじゃないそうじゃないんだ猪君。もう君を邪険に思っていないんだ私は。図書塔は鎮魂の塔だと聞いたことが白藤からある、これはきっと私が一人きりで立ち向かうべき依頼なんだ。」
「だそうだどうする猪?」
蛇の声はその姿と猪と共に、水無月の睫毛の動きと合わせて見えなくなった。
図書塔。まさか此処でもその話を耳にすることとなろうとは、今になるまで考えてもみなかった。
美術館は絵画や陶器などを展示し閲覧させる為に建てられたものではない、それは派生した目的であって本来の目的じゃあないのだって。そんなら本来の目的は何なの、あのね、実はお墓なんだって、大聖堂や教会と同じなんだよ。
今時の小学生はませているな、と橋の上ですれちがい様の会話に感嘆を心中呟く。あまり賢い者達が増えると誰も徴兵に赴きたがらなくなるのじゃないかと青紙を無視し逃げ続けた罪科を持つくせに生意気な事を考えていたものだと苦笑う。
じゃあ本は?と小学生の内の一人が聞いたが、その返答は得られなかった。遠く離れて聞き取れなかったのではない、もう片方が口をすっかり閉ざしてしまったからで。なんだやっぱり都市伝説か何かだろうと鼻で笑って、白藤との会話の種程度にしか思っていなかったが、
「図書塔は禁忌の一つなのよ。」
彼女は真剣に自分を窘めた。
「禁忌は人間を守る為に人間以外のもの達が定めた憲法のようなものなの。人はそれを土台に置いて生活を営み、死ななくちゃならない、どうして生物が等しく死を迎えるかも禁忌の中の一つの物語だから暴かれないようにしているのですって。図書塔のこと、私は知っているけれど水無月さんには話せない、話してあげられないの。」
「それは君の、雨月一族の出自のせいなのかい?」
「どれだけ善良に育っても、どれほど互いを愛し合う者でも悪人と同じなの、影を失くして生き物は日の下を歩けない。」
影があって初めて命は光の下に存在出来るのだと、かざぐるまを抱きしめて、ぼろぼろと涙を大粒流しながら絞るように言っていたっけ。あの日は少し病状が悪化していたのだろう。
「図書塔を描いてくれ、か。」
禁忌、タブー、聖なる法。踏み込んではならない領域に自分は踏み込める資格を持っている。だから蛇は笑うのだろう、蛇はずっと笑っている、目の前に現れる時は必ず笑って楽しそうで、私の罪状をきっと残らず否すべて余すとこなく知っている、見えているに違いない、山を犯す前に私が為した事全部。
葵菫
雪ノ下は真赤に染まった。曼殊沙華を逆さに映した姿。虚像の彼岸は霧と散り実を結ばぬ花々が脳裏を焦がしていく、その灰から涙は生れる。
赤紙を妻に見せると、彼女は行くなとないていた。これは義務なのだ此国に住まう人間への、気に病むな納税と同じ事なのだからと諭しても妻は顔を覆う両手を離そうとしない。税を納めるのは人の為と存じております、けれど人を殺すのは人の為なのですかとか細い声が頭に重く響く。聞き分けの無いことをお言いでないよ、おまえは私の妻ではないか。そうですわたくしは貴方の妻です、妻でありますがその前に一人の人間なのです愛する者が畜生道に墮ちますのを黙って見ていられましょうか。戦うことは立派な事だ、古代の英雄も皆戦って名を得たのだよ。立派などではございませぬ、それは名誉を保つ為にさぞ立派であるように記したのです、何故貴方はお分かりなさらない、歴史とは名も無き民草が決してこうはなるなと懸命に残した暗号でありますことを何ゆえ貴方はお認めにならないのでございますか、人を殺すとは、人を殺すとはどのようなものか、わたくしが最期にお伝えいたします!両手を開いた妻の顔は真っ赤であった。
いつも此処で目が覚める。父は母は病の為に若くして死んだと私にいつも教えるが、大方自殺なのだろうと父の言葉を信じなかった。その様子を目撃していた訳では無いが終戦の日から例の夢を見始めて妻である女性のお顔が私に相似していたからあゝきっとこの方が母様なのだと思い始めた訳で。
「お母様のこと、憶えてらっしゃらいの?」
「私は母が身二つになった直後父の兄、伯父さんの家に引き取られたんだ。だから私は母様のお顔を知らないんだよ。」
「そう……それは……」
「良いんだ白藤。私は伯父の家で大切に育てられたから、誰かを恨んだりはしていない。それにお墓の場所も教えて貰っていたから、終戦の日までは野の雑草を摘んで幼い花束にしてね、よくお参りをしたんだよ。」
「今は…?」
「父と伯父に禁じられてしまって、行っていない。墓へは自分達がきちんと行くから、私は勉学に励むようによ。」
「それで大学に。」
母様の御病気はなんなの、と伯父に問うたことがある、伯父は広い手の平で私の小さな頬をゆっくり撫でて寂しそうに微笑んだだけであった。
「医者になれば母様の罹患していた病名も理解出来るだろうと思ったんだ、そして治療も出来るだろうと思い上がった。人より少し勉強の上手な子供にはまゝある錯覚さ、他人より感覚が鋭敏なのは難儀なもんだよ。」
青紙が送られて来た時受け取ったのは自分だった、伯父は丁度外出中で家には私一人しかいなかったから、私は荷造りも碌にせず母様のお墓へと逃げ込んだ。
お墓は山の中腹にある、其処には古びてはいるものの荒れてはいない小さな寺が一軒佇み住職も置かずに墓守りをしている。山中に建つと言うだけあって高山に生息する樹や花々は夥しく地元の者でも一人では容易に足を踏み入れない魔所と扱われていたが、臆病者でも母は恋しい、逃げ場所には相応しかった。
十数年ぶりに訪れても母様のお墓は美しかった。薄花桜を込めてしっとりと気高く艶めく墓石は塵を払う袂涼しく凛と立ち、供えられた白菊はマリヤを守護する白百合かと尊く乳色の光を鏤むる。足元に咲く紺青は古代からの秘密を守る海の衣を授かった湖面深き淵を灯す菫の炎、奥ゆかしくも懐かしい。
「母様。」
生きておられたらいつか逢えたでしょうか、貴女を殺した憎い戦争、惨め、みじめ、馬鹿の喧嘩、病気を増やすだけのゴミ細胞。怒りは燃えて、青く燃えて、私は澤山の政治家に火を放ちました。
蜜月
懲罰を受けたのは青紙の召集に応じなかった咎だけで、民主国家の我が国では特級階層をやむを得ない事由に因り殺害することは暗に認められているものだから水無月がそれ以上鞭打たれる仕置は執行されなかった。
伯父と父は水無月の裂けた皮膚をよく手当し、何故逃げたのかと一度だけ尋ねたが、息子は返事をしなかった。それに憤るでも嘆くでも突き放すでもなく一言
「そうか。」
とだけ穏やかに静かに肯いたきりであった。
よくある見合い結婚。自分達の親同士がよくよく話し合うて是非互いに互いをと取り決めた後に初めて顔を合わせてはい、と承諾する。水無月の父も母もあまり物言わぬ人であった。
「内の娘は本当に無口でございますが、宜しいでしょうか。一言も喋らず一ト月過ごしたことも御座いますので…あの、ねえ。」
「私どもの息子も勉学や書物にばかり付き合っておりますの、ですから友人も知人も作りません、恋人などもっての外でございましたのに、まあ、こんなにお綺麗なお嬢様と縁談叶いまして…それはもう。」
大事無く日取りは決まり結納は済み式は挙げられ物静かな娘と寡黙な青年は晴れて陽の下夫婦と成った。決して華美な輝く生活ではなかったけれども小さな庭に菫が必ず咲くようなひっそりした慎ましい日々を送る。或晩夫が妻に紅茶を淹れて持って来た寝室で、新妻は窓から細い月を眺めて泣いていた。
「まるでかぐや姫のようだね、燕。」
妻の名前は燕と言った。が、彼女は陽の当る場所を苦手としていた。
「かぐや姫、ですか?」
「月に帰りたいと嘆くようでさ。」
夫と二人きりの時間だけ、妻は微笑んだ。
「わたくしは月の生れではないのに…とんだからかい言を仰有るのですね。」
「私と暮らすのが嫌になって浮世を離れたいのかと思うたが、そうでないことに安堵したよ。ほっとしたらお腹が空いて喉も渇いたね。紅茶を飲まないかい?何か軽い物でも作って来ようか。」
「あゝそんな貴方、お夜食でしたらわたくしが。」
「いいんだ私が好きでするのだから、おまえが気に病むことでない、私は料理が好きだからね。何か温かいスウプでも食べられそうかい?」
燕はカップを手に取り一口すすったかと思うと全て飲みほし、カップを置いた。
「わたくしは、紅茶だけで充分ですわ。貴方の毎晩淹れてくれるお茶が好き…」
少し俯向く後れ毛は微かにもつれ頬染まる寒紅梅を隠しきれぬ莟の枝よ。あまり物言わぬ愛しき妻の潤む瞳に若い夫は抱擁を禁じ得ず哀しい背中に互いの指は強く絡む。
「怖い夢でも見たのかい。」
「貴方が、人を殺す夢を。」
青ざめる筈の唇はかえって激情に濃き椿。
「今はとても平和じゃないか、戦争なんぞしていたのは私達の生れるうんと前だよ。」
「それでも貴方は殺します、貴方は義務の為に殺人者となるのです。」
「私がそうなったら、おまえはどうする。」
貴方の目の前で死んでみせます。人を殺すとはこういうことだと。互いの愛を誓うのは太陽に、一途の恋を誓うのは月に。庭の影を映す池に、雲が映る。
月の繭
雨音が好きだった。人は外へ出ず音が吸い込まれていく、水面の下に潜ったような静けさが。雪は命をも吸い込むが、雨は雫を音させるから、好きだった。
山には迂闊に入るなと誰が伝うるでもなく世間に広められていた。曰く、山は人間の住む場所にはあらず、獣や魔が住まう聖域だとのことで。だが人が凡そ近寄らぬ所人は利用する、天下に存在するものは何もかも、畏れ敬われている山は無信仰の者達には格好の殺人現場であった。検非違使ですら二の足を踏む山にはあぶれ者が多くごろつき畏れは恐れに成り下がり。科学と技術のメスで山を切り崩し始めるまではまだ数百年の時間を要する、それまで人は山から少しでも離れて生活する手立てでその日暮らし。
何處に行っても山はある。この国は水と山で成り立っている、何方か欠ければ恰も燃えるだろう、ならば俺は山のものになろう、そしたら人が完全に山を失うことはないだろうと世の中への憂いから妙な覚悟を決意したよくあるパターンの青年が一人いた。
名前も立場も持たない若者は山籠もりをする為魔所へずんずんと歩いて行き、雨風をしのげる程度の小屋を探した。いくら極悪人の徒といえでもさすがに野晒しで過ごし続ける気力は持つまい、拠点となる住家は持つだろうとの推測は当たり掘建て小屋は一軒あったが火の影は毛ほども見えぬ。
「家主には無礼だが中で休ませてもらおうか。交渉が通じる輩とは思わないが親に捨てられたとでも嘘を吐いてどうにかしよう。」
この若者は些か呑気ではあるものの度胸はなかなかに据わった好男児であった。
しかし一日待てど三日待てど一ト月待てど誰も戻って来る者はいない。山菜で作る一人分の食事のレパートリーも増えて来てすっかり山暮しに順応したかと思い始めた一年後の晩のこと。
短い命は清流に
長い命はお山に集う
なれどこの身は山のもの
懐かしい古里を離れても
きっと夢に見る美妙の竜胆
濃きめぐりを雫に変えて
小川に花は咲くでしょう
零す鱗粉は神々のうろこ
お涼しい吐息で雲を呼ばれて山を照らす螢石…
誰がうたうのだろう、野太い野郎の声でなく今にもほつれてゆかんと入水に夢を見る若い生娘の哀しい声。若者は弾かれたように声のする方向へと駈け出した。
寂しい調べは草葉の月影に谺して、漣の惜別の泪は雨となって山中にそゝぐ。静かに響くうたう声は最期の悲鳴となって若者の胸を締めつける。
「何處だ、何處だ、何處にいる。」
声は近づくが人の姿は指先も見えない。丈高く彼を待つのは山百合ばかり、山への迷い子を見下ろす項の長さ。
その唇に接吻をする、一羽弧月の虫ひとつ。
「蛾だ。」
天女かと思うた声の主は、曙に身を潜めて忘れられた泉の底深く眠る紫陽花に羽を染める火取り虫。一縷の月の青い光に花びらよりも薄くされども温かい血を通わすは藍碧の玻璃の水面に乱れ咲いた山茶花椿、錦の玉の緒を散らすようで美しい。この雪に炎の刺繍を生れ乍らに持つ者は凡そ天下に僅かなり、オオミズアオが若者の眼前に留まっていた。
青年はこの時恋を知った。丁度雨が水晶の真似をし初めた宵の刻。
貝合せ
蛾は毎夜山百合のもとで旋律を奏でる。青年は声が届く時分になるとその場所へ秘やかに赴き、藪の中に姿を隠し息を潜め蛾を驚かさないようにして耳を傾けた。そして陽が昇り始め暁光が煌めき出すと幕を閉じて何處かへ去って行くのであろう、声も姿もいなくなる。
「蛾の成虫は短命だと聞くが、もう三週間は夜の来訪を聴いている気がする。向こうは俺のことに気が付いているのだろうかなぁ、気が付いてくれていたならこの上も無いよろこびだが、もしそうでなかったら俺はずっと姿を見せずに聴き惚れなければならないのだろう。少しでも驚かせたり怖がらせたりしようものなら二度と此処には留まってくれなくなるだろう。それは嫌だなあ、こんな人も獣も全くいない山の中で、木の実とばかり顔を合わせるのは寂しいことだ。」
青年は山へ潜ってから一年と数ヶ月は経っていたが、彼は動物とも遭遇せず、ただ植物と土だけがこの辺りを治めていたのだ。
「都で聞いた話とはえらい違いだが、やっぱり噂は恐怖から産まれるものだけであって不確実だな。悪人どころか人ッ子一人の気配もありやしない。随分時間を掛けて踏み入れる箇所を探し周ったが人間にも動物にも会わなかった、最初の頃熊や猪を怖がって一人なのに不寝の番を務めていたのが阿呆みたいで懐かしい。どれ、そろそろ昼時だ、また果実でも頂こうか。」
呑気に寝そべったまゝものぐさにも美し果実の根元へ転がったのだがやはりそれは些か不味かった。果実の味を言うのではなく、行動態度が食べ物を拝領されるのに相応しいものではなかったために其処を指摘するのである。
何故ならすっぽり人一人が通れる穴に落ッこッてしまったからで。
「ワッ!」
こんな蛇の顎のような大きな洞穴あっただろうか、と存外冷静なことを考えながら青年は星の無い夜空に沈んで行った。このまゝ死ぬのだろうかと思い目をつぶる脳裏に、月の君が羽ばたいた。
瞼の裏の光景はその人にとっての北極星である。うつくしい私の北極星、愛しい妹柘榴百合。貴女の血は誰より清く心はこのお山の霞のように澄んでいた。ほんとうに春の夜の朧雲のように消えてしまった私の唯一の家族、いとおしい妹、かわいい子……遺体はお山に弔われ蛆が集る危惧も無く朽ちぬ山百合に姿を変えた、丁重な葬儀を見ていればよく分かる、貴女は神さま達から特別に愛を受けた別のお山に引き越した。貴女の大好きな植物達を一欠片でも食むのに偲びなくて。
蝶は蜜を求めるけれど、蛾は食事も望まない。この姿ならば寄り添い続けても罪は生むまいと嘆願し聞き届けられた私の悲鳴。貴女が寂しくならないように、私は貴女のよくねだった子守唄を毎夜毎夜青いお月様に捧げます、清水の唄が山中を潤す翡翠の雨になればとて……
「なのに誰だ、この聖域で木の実を食い漁るのは。」
娘の怒りは山の怒り。姉は実をもがれる樹を慰めながら無礼者を閉じ込める為の穴を作るよう命令した。青年の知らぬまに穴は掘られた隠されを日毎日毎繰り返し、遂に盗人を戒める為の洞穴が出来た。一年と数ヶ月は掛かったがこれでようやく愚者の面を拝めるというもの。山はいそいそと犯人が捕まるのを待ち侘びた。
「ワッ!」
黎明
「起きなさい。其処の人間、起きなさい。」
芍薬の声が蔦に拘束される青年を凛と突き放す。その搖らぎに正気づいたか青年は薄ら眼を開く。
青磁冴かな氷瀑の羽の怒り。頭を垂れる牡丹・芍薬達に身を凭せ、下衆の者には息も示さぬ冷やゝかな怒り。見た途端青年はハッと思わず居住まいを正し深々と土下座にて情けを乞う。芍薬の声は続けて言う。
「ようやく目を覚ましましたか、人間。お前から質問をすることは一つも許されない。問われた事にのみ答えなさい、聞えたのならば一回頷きなさい。」
雪も降らぬにひやひやと骨身に沁みるこの寒さ、カチカチと震う歯からは吐息が漏れ、未だ我身は心臓まで凍らされていないと僅かながらに安堵するも恐れる指先を見つめたまゝ頭を上にも下にも動かす胆勇はすっかり奪われ力無くカクリと頷く。
「何故山に入ったか申しなさい。」
「お山のものになるためです。」
「お山の物に…?詳しく話してみなさい。」
「私奴がお山のものにあんらなければ、人は山を失います。山失くして此国は成り立ちません、人が山を手放せば我が国は即座に燃え尽きるでしょう、に、人間に必要なのは水だけではありませぬ。」
「お前は人界を守る為に異界へ参ったと?」
「さ、さ、左様に御座りまする。」
「目出度い阿呆よ。自ら頼まれもせぬのに人身御供となりに来たとは、山の慰み物になる覚悟は勿論あろうな?」
「は、はい。恐れ多く、余りに無躾な浅間しき畜生のお願いで御座居ますが、其方におわします姫君の手に掛けていただければ全く幸いに御座居ます。もッ、勿体無きことなれど」
「―――――――私に愛されゝば幸せか。」
芍薬とは異なる声が鳴った。胡弓を低く響き押し込めた水底沈む玉の音は、仰ぐ月に涙して鈴の嗚咽を混じらせる、山の者が空を見つむは川の者と同じ心であるらしい。声はさらに言葉少なに耳に流れる。
「答えることを、許す。」
心は浮び青年はさっと頬を染めた。
「はい、はい。姫君の御手にからかわれましたら自分は、この上も無いよろこび、に。」
「ならば愛してやろう。」
月の繭を破って出たのは御姿貴き三日月の女神一羽竜胆の微笑を両翼に震わせた、
「故に命じる、私を殺せ。」
いとも酷くうつくしい北極星。
何故で御座居ます、など問わなかった。唯一言、
「承知。」
とだけ。
死体は山百合の根際に沈めよと命じられたので、その通りにした。瑠璃の淵麗しかった羽は首を絶たれた瞬間から紅く色を変え一輪のかざぐるまとなっていた。
青年は山を降り、死ぬ時まで二度と墓へ足を踏み入れることはしなかったと言う。
襲
三日月の姫神は愉快だろう。復讐でも嘲りでもなく唯妹がかつてしていたみたく玩具で最後遊べたのだから。山に人界の規則や秩序は通用しない、莟を一枝足に敷くだけで、莟を一欠片採るだけで我身に何が起きるのか分らない、その時に起こらずともいつか必ず尋ねて来る、山の訪問者の姿も脅威も果実も人間だけが知る術を持たない。
「だから図書塔が欲しいんだ。」
「でもさ、水無月君一人に負わせる心算かい?」
「猪、あまり蛇を責めないであげなさい。」
蛇と猪と鹿は山上から少し降りた中腹で三角形に向き合い花の蜜を飲んでいた。その蜜は山上の番人である蝶々のように花芯から直接吸うのではなく、寿命を遂げた花々が自然と清流のグラスに溜まり甘やかな蒸留酒となり彼等の喉を潤すのだ。
「負ってもらうさ、山と人を繋ぐ橋になってもらうのだから。」
橋は古来より彼方と此方を結ぶ役を負うて来た。だが今ではその色は年月に薄れ役割は錆びつき細かい鉄屑は生き物の喉に通りはせぬ。
「そしたら人はまた山と暮らすことが出来るんだよ。」
「蛇は蛇なりに人間のことを思っている、か。」
「鹿は優しいな。僕はそんなふうに考えられないよ。蛇のしたい事や言い分は些少は理解出来るよ、出来るけどさ、それは水無月君を苦しめないと叶わないのかい?白藤さんは水無月君と本当に愛し合っていたのに、どうして烏瓜に嫁がせたんだよ。」
鹿は長い睫毛をそっと伏せ、笑う蛇の代りに静かに答えた。
「それは、彼女を自死させないためであったんだよ、猪。」
「両親とも亡くしたからって、白藤さんが後追いする筈無いだろう!現にあの子は今も水無月のことを憶えている、想っているから僕に伝言を頼んだんだ、雨月の一族の話をしてあげてって、なあ、なあ!蛇、正しく答えろよ、何故二人を引き裂いたんだ?」
鼻息荒く語気は鋭く、蕺草の牙は義憤に尖る。
「猪、どうか怒りを鎮めておくれ。その訳は私から話すから。」
憂う瞳は友を宥める、実直な友の眼に悔し哀し涙が強く滲むを見逃さずに。
「白藤は絶望して死ぬのではない。また、喜びを閉じ込めようとして死ぬのでもない。彼女は図書塔に踏み入れた水無月の代りに命を落す方法を選ぶのだ。」
図書塔は純白の真綿を守るための黒い炎。生物は火に弱いもの、禁忌を破るとは業火に身を投げるのと同じこと。皮膚を熱し脂を溶かし水分は悉く煮えてしまえば誰も生きては通られないが、身を浸せる氷の守りがあれば若しかしたら。そのお守りが、白藤である。男の持てない神々との談話の機会は古来女性のみが与えられたる秘密である、ために女は内緒ごとがよく似合う。その特性を嫉み恨んだ男共の手によって人身御供(儀式のみにあらず)は産み出された。だが白藤の場合無理強いでなく自ら雪を焦がすのだと言う。
「それだけは我慢がならない。」
蛇はこの時だけ笑顔を捨て真顔になっていた、横がほ恰も名工が鍛え冷月の影にかざした刀のよう、その刃は姫神を守護すると思いきった衛士の相がある。気迫はゆらゆらと木陰を縫うみたく泳ぐ、尾鰭は鱗粉を氷の粒と化して撒きはしないか。凄まじい静けさで、鹿は蛇を変わらず見つめていたが猪は全く言葉も怒りも失った。
「あの若者は遅かれ早かれ図書塔に突っ込むことになる。白藤を蛾にしたのはその時期を早めるためだ。白藤が死ねば奴も死におる、それではまた橋を一から探さなきゃならん、面倒だ。」
もう笑っている。
「心中は世界を動かせはしない、二人死ぬより一人生き残っている方が悲惨なんだ、人は他人の不幸を慰めるのが好きだからね、一緒に死んでも波紋は広く伸びないものさ、たゞ一時水が荒れるだけ。強い感慨は忘れやすいが薄く軽い不憫の羽衣は飛び続ける、日を透して雨を帯びて、空気に襲して嫋やかに袖を遊ばす……滑稽だけれども美しいとも言えるだろう?
一度婚儀の前にデートをした事がある。燕はきっと病状が良かったんだろう、いつもは笑顔で無言を誤魔化す癖があるが、その日は他人からの問いかけにもよく返事をして微笑んだ。外出に此方から誘ったから無理をしているのではと最初は心配であったものゝそうではなさそうだった。心から外での逢瀬を楽しんでいる、笑う頬は明るく涙の素振をも読みとらせない。
「ありがとう巡さん、デエトに誘っていただいて。」
彼女の姿の向こうには、山が待っていた。燕の耳には白い繭のような真珠の飾りが光っていて
「いつか美術館で見つめられた、フェルメールの少女に見えたのをよく憶えている。隣にいる筈なのにね、物語の中の人みたいに感じてしまったんだ。」
不安になって、握りしめた。その掌には千切れた糸とジャケットのボタンが納まっていた。
「此方から誘ったのに前日の晩になって上着のボタンが一つ取れているのに気がついてね。生憎同じボタンが行方知れずになってしまった情けなさ、仕方が無いから裁縫箱に集めていた雑多な物の中から一番綺麗そうな物を選んで付けたと言う訳なんだが、気が急いたのか緩んでいたのか握るとぷつりと取れてしまってね、それをぼんやりと見た時不意にこれは何かのお告げだと、本当に、若いと何を思うかも分らなくって恥ずかしいが……この紫陽花模様のボタンをね、お守りだと言って燕に渡したんだ、いや、まこと情けない、もっと良い品を贈れと今なら自分を馬鹿に出来るが当時は必死だった、彼女を繋ぎ留める為の物が今すぐ必要だと焦っていてね…」
父は酒を飲んだ時だけこの話をした。水無月が鞭打ちの刑を受けた後、伯父は父親を自宅に呼び、一緒に暮らそうと言ってくれた。一人暮しをしている父の荷物はとても少なく、家を引き払い越して来るのにもさほど時間は掛からなかった。
「水無月、おまえ母さんの顔が見たいか。」
伯父の召使い達が晴耕雨読に励むのをぼんやりと二階の窓から眺めていた日々のこと、父が部屋の扉をノックして、私は椅子に父は寝台に腰掛けた。
「母様に逢っても良いのですか?」
「ずっと逢いたかったろうに、それを私が防ぎ続けた。意地悪をした心算は無かったのだが、おまえにはそう映ったろう……今更でみっともないが、本当にすまなかった。燕に一目逢いでもすればおまえが火を持つ事態も起きなかったかもしれないのに。」
「父様、あの、僕は恨んだりなどしていません。何か、止むに止まれぬ事情があったのでしょう?」
燃やした政治家の炭跡をぼちゃりと深い水に入れる
「伯父さんも何も教えてくださらなかったけれど、きっと幼い子供にとって理解のし難いことだったのではありませんか。」
沈んで沈んで亡骸は底に散らばり見たことも無い魚に喰われる。その鱗にちらりと人の顔が一瞬映ったような気がして
「水無月、母さんはね、」
そのお顔がにっこりと笑っておられるようで
「図書塔に見初められたんだよ。」
水無月、と坊やの名前を呼んだようで
「図書塔の番人におなりなんだ。」
そして再び魚を操りゆらゆらと滲み、輝きは一つも見えなくなった。
お母様に逢いたいのなら、貴方がきちんと辿り着けるように、私がご家族のための橋になります。
一等大切な日だから、母の形見の帯で身を引緊めなくてはいけませんね。
曙
図書塔はいつも門戸を開いているとは限らない。三日月形に玉章列ね白く仇花咲かす時、真夏に雪の雫を紡ぐ時、隠世と現世を結ぶ鍵は一夜だけ姿を見せた。虫と花々は互いに互いを抱きしめて蠟燭よりも哀しく燃えながら泉に落ちる。肉体は溶け精神はほつれても他が身を想ふ心は燐火となって愛しい人を可愛い坊やを照らし包むための旭光となり頬へ寄り添いキスをする。
落花
雨粒が一ツ頬に雫し、水無月は眠りから目を覚ました。父様今頃何をしておいでだろう、私はこうして何かも分らぬ絵を描き散らし、此処では数日だが街では何年過ぎたろう、図書塔を描けたら家に帰してくれるのだろうか、切めて母様のお墓参りを父様と一緒にしたかった。図書塔に踏み入れることが叶ったら描けたら私はどうなるのだろう。
急にほとぼりが冷め、寒くなる。思わず頬を伝う涙に指を触れて抑えきれぬ嗚咽があふれ出す。身勝手、身勝手、人を殺しておいて俺は今更泣いているなんて、浅間しく醜くおぞましい。
「俺は犯罪者なんだ。」
水無月は唸り呻き始めた、鹿に治してもらった筈の指から赤が滴る、悲鳴をあげて後ずされば山茶花の汀でバランスを崩しかけぎりぎりで持ちこたえるが彼は山上の番人を忘れていた。
「沈め犯罪者、意地汚い男。」
蝶は人間を泉に突き落した。
沈んで息が出来なくなり、冷たさに恐怖を感じながら溺れ死んでしまうことと、沈んだのに息は出来るし冷たくもないが生き延びている自分に得体の知れぬ何かが貼り付き眺められること、どちらも恐ろしい溺死である。が、水無月は笑い始めた。水中でごぼごぼと泡が舞う。楽しくて、嬉しくて仕様がない、先程迄の演技は見事だったのだろうか番人の機嫌をいたく損ねたらしい、この泉は何處に繋がっていると思う?川ではない、否、川には確かに繋がってはいるのだがきっと自分は其方側に流されるのではあるまい、私の考えが正しければ、合っていたら、
「黄泉路に蹴転がされる。
お前に清流は似合わない、白藤や母様と同じ流れには辿り着けない、だからこそ目当ての場所に行き着かされる、父からその言葉を聞いた時からずっと行きたかった場所に、図書塔に。
猪君には悪いことをしたなあ。
影法師
慰霊には塔がよく似合う。館にすれば便宜上は良いがあちらこちら通りにくいが塔は壁を必要としない。朝顔の蔦の螺旋模様に翡翠の短刀を突き刺した姿の階段は零れた宝石、星屑の数の泉へと繋がっており、自在に水中を行き来するを許されている。
山上の泉の手から離れた水無月は、珊瑚の大理石よく冷えた床に放り出された。ゴホゴホと咽るもあまり肺に水は侵入せずさして苦しみも感じなかった。身体はずぶ濡れで白いシャツの色が滲み始め色に染まっている。立ち上がって髪をかき上げ一、二歩天井を見上げつつも進んでみれば、
「いらっしゃい。」
バケツ足元に露草の窓掃除をする老夫がいた。背丈は水無月よりもうんと低く怒り肩ではあったが、両眼はとぼんとまん丸黒目勝、口ひげ顎ひげ双方ふさふさと整えられ器用にリボンで三ツ編にしてまとめている、物語に聞くドワーフのような人相の持主。
キュッ、キュッ、キュッ。
「まだお若いのに此処にやって来たのかね、難儀なお方だ。名前は何と言わっしゃる。」
「水無月。」
「みなづき。おゝ、水の月のお名前か、あゝ佳いお名だ。ご両親に恵まれたのな。じゃあ貴方は運が良い御仁だな、待てよ、そんならますます変だのう、何して此処においでなすった。」
キュッ、キュッ、キュッ。
「母のことを知るために来ました。」
キュッ。
「母は図書塔に見初められたのだと父から聞いたのです。おじいさん、貴方は何故此処に?」
チャボン
「儂も貴方の母さまと似たようなもんさ。或日住んでた国が亡くなってね、その時からこいつの厄介に預かっている。」
「まさか塔が助けてくれたの?」
チャプリ チャプリ チャプリ
ぼちゃり
「人殺しめ。」
老人はまだ水無月の名前しか知らない筈で
「この図書塔を毛嫌う資格などお前には無いぞくだま野郎。いつまで酔っぱらった心地でおる。」
「私は酒など」
ぼちゃり ぼちゃり
「いや酔うておる、自分は罪を犯したがそれは正しい罪だと思い込んでおる、信じておる、そんな宗教は捨てろ。」
「な、 何を」
「義憤だとお前は宣うだろう、政治の輩を燃やし殺したは正義だと信仰しておるのだろう。」
「何が、何が悪い。戦争を望み招待しくさったのは奴等だぞ、国民が戦いを切望する訳が無かろう。」
ぼちゃりぼちゃり
ぼちゃりぼちゃりぼちゃりぼちゃり
チャプリ
チャプリ
キュッ キュッ キュッ
老人は布を手に取り藍碧の窓を磨いていた。
「おゝ、そんな所にいつまでもぼうっとしておらずとも、此方へいらっしゃい。図書塔に来られた経緯は分かりませんが折角です、一冊二冊本でも眺めていらっしゃい。」
キュッ キュッ キュッ
キュッ キュッ キュッ
水の再び跳ねる音を聞きたくなくって、水無月は老人の働く方角とは反対の開架に走って行った。
棚には存外装飾等は施されておらず、一様に白樺造りの四角なものが羅列していた。本は一冊ずつ異なる字体で綴られてどの頁にも宝玉や草花、鳥の羽虫の翼が糸を使わず刺繍されており文字は美しく語り掛けて来る。昔幼い時、父様を喜ばせたくて描いた油彩画を想い出す、あの時は確か御伽噺の姫神さまを描いたのだっけ、まだ見ぬ母の面影を託して好きに塗った絵具を一目見ると父様はほろほろ泣かれていたが……あの時頭でイメージした温もりが、今まさに塔内にずらりと鎮座まします本達よ。
「母様は此処におられるのかな、何を読まれたのだろう。」
星の語る煌めく極光の書籍達をパラパラと幾つか開き眺めていると、一つ目に付く物語があった。
日報
と和紙の表紙に筆でしたためられた其に作者は記されておらず。
「この場所にいた人達が書いたのかな。」
だとすると一目逢いたい母の言葉があるかもしれぬ、水無月少年は早速床に座ってその本を読み始めた。
陽炎
この手紙を読まれている時、きっとわたくしは其処にいないことと思います。ですがどうか書き手がいないからと言って、読み手がいないからと言ってこの文を捨ててしまわないでくださいませ。一寸の虫にも五分の魂、どれ程日の目を見ない書物でも命あり霊魂のある身でございますれば、どうか乱暴に扱うことのないようにとお祈り申す次第でございます。
先程一寸の虫と自らを称しましたが、わたくしは文字通りの虫にございます。わたくしはウスバカゲロウと申す種で、蛾にはなれなかった哀れな羽虫なのであります。
幼い時わたくしは幸福でしたそして大層愚かでありました。他の命を支配し奪うことの悦びはわたくしを日に日に満足させ、最早自分はこの世の喜悦を喰い尽しただろうと増長も極まった時、わたくしは暇を感じ物思いに耽ることが多くなりました。あゝ暇とは恐ろしいもの、碌でも無いことはきっと全て暇から産み出されていくのでしょうか。
世界はこの国は水と山で成り立っている、わたくしは雨が好きでございましたから、雨が失われることは無いだろうと信じていたのです、自らの好きな者達は明日も明後日も我身の傍に居てくれると思わずにはいられない哀しくも優しい信仰だと憐れみください。この信仰のためにわたくしは山へと籠ることを決意し、そして結局山を降りたのです、山を降りた後わたくしは成虫となち食事もあまりとらずそのまま塵へと朽ち果てました。
斯様にみっともなく命を終えても不幸だなどとは思いませんでした、むしろもっと早くに命を終えられればと、この心を焦がせしめた初恋のあの御方の後を跪きながらでも追えたのならどれだけ幸せでありましたろう、されどかの君は我が願いをお許しにはならず、自害をお認めになりませんでした。恋した者を手に掛けたうえ生きさらばえるなど、そんな、そんなことをあの方は……
このウスバカゲロウの恋をどうかお忘れにならないように祈ります、後世に語り継がれるような史実にはあらねど、わたくしが確かに恋を全うしましたことをあなたが憶えていてくれたのなら、もう未練はございませぬ。
今日おもしろい者が来た。人の世界を守るためにと山をも恐れずやって来たようだ。人の身でありながら火を守るために命を賭すとは何なのだろう、それ程までにお前は人間が恋しいのかよ?
人は人を恋しもするし嘲りもする、その嘲り傷付ける輩が山にのさばりこんだ時は大変怒りを覚えたことを憶えている、無礼者は首を刎ね刎ね泥土の肥しとなっても文句は言えまい、山は人界から逃れて来るための場所ではない。時に殊勝な僧が来る、山伏修験者も好きだが、折角の力を人界のために使うのはちと勿体無い気もするが、好きな者達は好きに生きればいい。
だが今日参った奴はどれとも違っていた、おもしろくて愉快な奴だ。
曰く、山と水を欠けさすことは人界の存続に係ることで、自分は山と火を繋ぐための存在になりたくて来たのだと言うが、私は嘗てあんなに澄んだ瞳のいけにえを見た例が無い。誰からも望まれていないのに、託されてもいないのに、言わば自分の勝手な思い込みで迷って来たようなものだのに、その眼は花の露にも劣らず澄んでいて、可憐であった。
かわいい妹を想ひ出す。あゝ貴女がこれ程の者ともっと早くに出逢えていたなら、その命を散らす必要も無かったろうに。
口惜しい、愛惜しい、可愛い人め、畜生め、私の前に額づく者は私に愛されたら僥倖だと言う、この手に掛けられれば満たされると言っている。
一片でも嘘があれば立処にその眼は濁ったであろう、顔を上げずともよく分かる、貴方の目は曇りすらしてはいない。心は燃え立ち浮足立ってはいるかもしれない、それでも願いは変らずその身深くに沈んでいるのだろう、殊勝なことだな、哀れなことだな、お前が山のものになったところで人の世界は守られない、犠牲で成り立つことを法とする世界なんて守りたくない、お前は山に縛られず人の界域で暮すが良い、此処で朽ちさせたくはない。
私を残酷と想うがいい、お山とはそういう場所なのだ。人の感情も秩序もおもしろい玩具へと変貌する、如何に命懸かりの嘆願でも悲泣でも子雀への毬唄ほどになる世界。
人は山から離れて生きよ、でなければ次々と正気を失くす者が増えていくだろう。私達の吸う空気は人のために作られたものではないのだから。
鬼哭
「私の知る日報ではないな。むしろ日記と称する類のものだろう、此処では日報は独白体で記されるのか。」
水無月は元居た場所に本を戻し、螺鈿の面影羽たたく虫の翼を襲て出来た階段へ歩み寄り腰を掛けた。
「それに、あの二つの内容だけで、母様のものと思しきものは無かった。そうだ先程の老人に聞いてみようか、教えてくれないだろうか。今手掛かりになりそうなはあの人だけだ。もう一度声を掛けてみよう。」
青年は元来た道を戻ったが、あの老人はいなかった。それどころか露草の窓硝子も無く、代わりに本棚がどっかと置かれている。
「間違えたのか?」
一周ぐるりと身体を回す。すると、今度は本棚が失せて花壇が点々。驚きに瞬きすれば小川が流れ、目をこすれば貝殻が色も冴かに床に埋もれて水面下から此方を眺む。
「一期一会の間じゃよ。」
聞き覚えのある声が。
「大層な名を付けてはいるが所詮は塔の悪戯じゃ、水無月さん、目をつむって大股で前に三歩進みなさい。目をからかっているもんだからじっと見ていればそれこそ迷う。」
水無月は言われた通り…一…二…三…すると手を握る温度を感じた。
「儂の手を放さんように。もう目は開けてもいいが手だけは嫌でも離さんようにな、こんな老いぼれでも塔の案内番だでな。」
何故か今、父親ではなく伯父を思い出していた。
「伯父さん。」
「おじさんと言うには老け過ぎた。爺々とでも呼んでおくれな。」
「否、そうではないのです。すみません貴方を呼んだのではなくて、今、急に伯父の顔が浮かんだものですから、つい、口を突いて出てしまって…」
「笑ってらしたかね?」
「はい?」
「貴方の伯父さんは、思い出された時笑っていましたかね?」
伯父はいつも笑っていた
「笑って……いませんでした。」
見た筈も無い、悲しいお顔をしていた
「何故?」
「分かりません、私にも…伯父はどんな時でも明るくて、気丈な方なのに…」
「読みなされ。」
足を止めて手渡された和綴本一冊。題箋には「議事録」と震えた筆文字で記されている。
母は私が本を読む時、いつも好い顔をしなかった。本は私の救いであり、命を構成する破片の一つであったが、母はそう思えなかった、いや、思えてはいたが納得しなかったのであろう、読むことを認めてはいたが認めていなかったのだ。
私は母を憎んだ。母の顔色を窺い弟も目の前で本を読まなくなっていて、彼は私に似ず気の優しい、極めて無口だが聡明な子であったから、母の気に喰わないことはしたくなかったのであろう。あまり物言わぬ弟の微笑む時間を奪う母親が憎かった、一度私達が書を読むことがそんなに不満かと問うたことがある、その時あの女は
「読むなと一言も言った覚えは無い」
と。
酒に酔い弁舌になった時はしょっちゅう世の中を憂いていた。政治家を嫌い世間の腐敗を嘆き、よくこの国は滅びると子の前で喋っていた。批判自体に全く賛同が出来ないと言う訳ではなかったが、世を憂いている自分に陶酔するあの顔と口ぶりが何とも憎らしかった、口をとがらせて突き出した不格好な唇、半分寝そうなあの眼、最近になって見苦しくなった髪も一本一本が憎らしい。
昔幼い時の学友で、バレエを習わされている者がいた。彼の母親は昔バレエを熱心にしていたが熾烈な争いに負けあらゆる手段を使ったが望む身分は得られなかったらしい、所謂夢破れたり、なのだがその夢を息子をして叶えようとしているのだった。
自分は母の夢を叶えるための装置なのだと泣いていた、齢四ツの男の子が、だ。私は何と声を掛ければ良いか分らずまごついていたがフと友人は顔を上げて、泣痕も見えぬほど晴れた表情で笑い掛けた。
「そうだ図書塔に行けばいいんだ。」
「そうだ図書塔に行けばいいんだ。」
私はそのような塔の名前を聞いたことが無い。何だいそれはと問うてみたら彼は御伽噺を語るかのように教えてくれた。
「お墓だよ、魂を鎮める場所なんだ。本当はね、美術館もお墓なんだって教えてもらったんだ。」
誰に、誰に教えてもらったんだい真ちゃん。
「誰でもないよ。でも教えてもらったんだ。」
真ちゃん、待ってよ真ちゃん、何處行くの?
「じゃあね信ちゃん。巡と離れちゃあ駄目だよ。分かったかい。」
私が目を開けたのは、母のけたたましい声の所為だ
「信、真ちゃんが行方不明になったんだって。」
うるさい、お前は他所の痛みには敏感なんだ
「心当たりはないかい?母さん真ちゃんのお母さんと一緒に探して来るから、おまえは巡と留守番していなさい。今日は父さんが夕方には帰って来るから、それまで扉を開けちゃ駄目だよ。」
ガタガタと引き戸の閉まる音、表は大層な騒ぎだ。でも真ちゃんは見つかりっこない。図書塔に行っちゃったんだから。死んだのではないだろう、二度と戻らない家出なんだ、真ちゃんは自分の家が怖くてたまらなかったんだろう。私も巡と図書塔へ行きたいな、文句の態度が一切無いすてきな空間、行ってみたいな、思いっきり本を読みたい読んであげたい。
「信ちゃんお遊びな。」
聞えないのに声がした。
「水無月さん、貴方の伯父さんの信さんも、お父上の巡さんもこの場所に来ておられたのですよ。」
毒の花
水無月は老夫の言葉を俄には受け入れ難かった。母だけでなく父も伯父もこの塔に関わっていただなんて、何の因果が為す業か。
「信さんのお友達が先ず此方に来られてね、友人とその弟を招いても構わないだろうかと仰有る。何この塔が受け入れた人のご友人なら塔も喜びましょう、遠慮なさることはありませんと申しましたらお友達は笑いましてね、その次の日だったでしょうかね、ぽかんとする信さんと巡さんを手曳いて連れて来られて
“お爺さん、僕の友達の信ちゃんだよ。こっちの小さいのは弟の巡って言うんだ。優しくしてあげておくれな。”
とにこにこ笑って紹介されたものだから、儂もにこにこと不格好な笑顔をしてね、膝を床につけて挨拶したのをよぉく憶えておりまする。そして澤山お遊びでした、何でも、ご兄弟は自宅で読書するのは気がひけるとか……お愛しいことでござります。」
あの本好きの父様が。
「満足にした事も出来なかったからと、そのまゝ一、二年は塔でお過ごしでした。本当に読むのが大好きなのですな、と或日儂が声を掛けましたら恥ずかしそうに肯かれました。まるで昨日の事のように感じます。あゝ、そうそう。先程貴方が読まれました日報がありますでしょう。その本を大変お気に入られましたご様子で、毎日幾度も読み返していなさった。」
「あの記録を?」
確かウスバカゲロウと姫君の。
「えゝ、あの二つの恋文を。」
老夫はそれきりすっかり黙ってまた窓掃除を始めた。水無月は彼に一礼をして老夫の近くの棚を眺め始めた。母の言葉はこの辺りにありはしないかと探すのである。バケツの水音が再び聞える、水面を思い出す、誰にも心から涙されない死骸達を沈めた水面を。
思わず磨かれる窓を見る。窓枠はプラチナで飾られて鈍くも鋭い輝きを此方に投げる。我身を映しきらぬ一方の反射がまじないごとを唱えるような。
「鏡よ鏡よ鏡さん、この世で最も」
“醜いのはだあれ”
笑う、笑う、鏡が笑う。私を見つめて、答えを見つめて笑っている。
“卑怯なはだあれ”
“愚かはだあれ”
“阿呆はだあれ”
“お手々が汚いなはだあれ”
山茶花が一つポトリと落ちて来た。それは私の首を滑って腕を這い、やがて心臓の部分で蠢きだす。
「悪い子はだあれ、」
ハッと声に振り向けば、仮面を被った人影が一つ。
「悪い子おいで。」
白い仮面は狐の頭らしく見えたのだがよく見掛けるお稲荷様の其でなく、虫の翼が三枚ほど襲して編み込まれた眦鋭く眼光柔い両目の辺り、耳は牡丹の花弁一枚借りては器用に動く三角形、小石の眠る小川の狐はにんまり口を描けども色は消えそうな水の色、それでも決して離さぬとかっきと銜える平打簪冬の糸。
「悪い子だあれ」
まるで声は幼い子供の戯れのようで
「悪い子おいで」
嫌々を言わせぬ母親の呼び声のようで
「可哀い子、可愛い子、こっちだよ。」
水無月は仮面の人物が細い手指でさし招くのに導かれ、退る人影についついつられて行く。
「母様ですか、貴女は、貴女は僕の母様ですか。」
質問に対する答えは無い。ただただおいでおいでを繰り返す。
「待って、母様待って置いて行かないで。」
その指を握ろうとした時
「止めなされ!」
また、老人の声。でも今度は語気鋭くビリリと緊まる勢いで。彼は水無月の胸元にうごうごと乗っかっていた山茶花を一輪べりべりとひっぺがすと、フッと息を吹き掛けてから持ってきたバケツにどぶんと落した。くなくなと力の抜け倒れようとする水無月を腕でがっしと支えたら花を沈めたバケツはそのまゝに、老夫は天井に声を掛けた。
「おうい、ちと手を貸してくれ。この兄さんを運ぶのは儂一人では骨が折れる。」
青いドームの夜空から、ひらひらと一匹の真白い蛾が降りて来た。
「酷い顔色だ、よほど恨まれていたんじゃろ。」
―おじいさん、この子は何を探しにやって来たのかしら。
「なんでも母君を探しに来たらしい。山を犯したのも大方その一念に因るものだろうな。」
―お母さんを亡くしたの?
「生まれてから一度もお逢いしたことが無いと聞く。」
―ではその方は…
「あゝ、此方側の住人。燕さん、あの女が水無月さんの母様じゃよ。」
………声が少しずつ届き始める。彼ともう一人、誰だろう、とても優しい声がする…
「おゝ気が付いたか。」
老夫は笑って仰向けに横たわる水無月の頭を撫でた。
「おじいさん、あの…」
「もう少し横になっていなさい、まだ毒が抜けきっていないでな。」
―貴方は山茶花の毒に浸されていたの。
痛む目をゆっくり開くと、其処には目を赤くしながらも笑っている老夫と一匹の蛾が彼の肩に留まっていた。蛾の瞳はつやつやと病人を映す。
「毒…?」
「おまえさん確か、山を荒らしたそうだな。その時花を足蹴にしなかったか?」
「あ、ああ……」
子を亡くした母親。
「山茶花の花を…踏みつけました。それでその…母親に、恨まれました。彼女は蛇に、狐の姿にされていて、それで私に喰ってかかったのです。頬に、爪を…」
愛する者と別れた者、自分が引き裂いた者達。
「成程、だからあんなに猛毒だったのか。」
「……子を奪われた、母親の恨みの強さなのでしょうか。」
―いゝえ水無月さん。貴方が犯されたのは子供の毒です。
「子ども…?」
明星
泉に沈んでいる時水は温かいものだと感じていた。外には雲雀の歌が木漏れ日の朝日と絡まり跳ねている、何を歌うの、何を照らすの、教えてちょうだい。手を伸ばしてみると柔らかい壁にふくりと触れる、そしたらまた別の小鳥が囀るの。不思議ね、不思議ね、可笑しくて歌うの?悲しくて歌うの?嬉しくて歌うのお母さん。答えが聞きたくて質問したら、それが産声と言うものだったらしい。
お母さん、お母さんに澤山聞きたいことがあるんだ、あのね
お母さんが泣いている。ずっと泣いている。
よくも私を踏み散らかしてくれたな
お母さんは僕を抱きしめることも出来なかったんだぞ
どうしてやろうあいつ、どうしてやろう
俺にいい考えがある、毒を喰わしてやれ
―水無月さん。
言葉を失う水無月に、蛾は語り掛ける。
―あの場所には、愛する者を失くした命が集うのです、山とはそのような場所なのです。だから貴方は山に向かったのですよ。山を荒らしたのはご自分の意志だと信じたいでしょう。でもね、それはただ貴方が錦の糸を辿って来たからに過ぎないのです。そして特にあの山は、図書塔への入り口の役目も負う場所、貴方は蛇に招かれたのです。
蛇は、さぞや愉快だろう、狙い定めた者が筋書き通りにレエルをなぞるのを俯瞰するは。
「いつからです。」
それでも声を絞り出す。
「いつから私は、蛇に見初められていたんです。」
「おまえさんの伯父さんが、図書塔にいらっしゃった時からだ。」
「伯父さんが……」
見ん隙の伯父の信は母親を憎んでいたが、恐らくそれが図書塔へ来るための鍵の一つとなったらしい。兄弟で好きなだけ本を読みまくった日が一ト月以上続いた時、弟の巡が『顛末書』と記されたぶ厚い本を持って来た。
「お兄ちゃん、これ絵本なんだって。」
「何て読むんだろう…マツ、マッショ?」
「飛び出す絵本って、教えてくれたよ。」
「教えてもらったって、あの窓拭きのお爺さんにか?」
「いいえ、とってもお綺麗な人。女の人。ねえ、それよりご絵本読んでよ。」
「分かったよ、おいで。」
幼い兄弟は芒で編まれた吊橋に仲良くきちんと座り、頁を開けた。
「飛び出す絵本だ!」
「舶来物かな?」
仕掛けは愉快で二人は喜んだが、其処に描かれている風景を見て彼等は一気に押し黙った。絵本には自分達の家と、その前で泣き崩れ近所の人達に宥められるひどく痩せた母親の姿が記されていたのである。
「帰ろう。」
信は巡の手を取り、老夫に帰り方を教えてもらう為に駈け出した。そのもう片方の手には顛末書がしっかりと抱きかかえられている。
「帰りたいの?」
走り出した矢先後ろで声がした。
「帰るの?もうお帰りなの?」
「お兄ちゃん、あの女性だよ。」
巡の言葉に振り向き見れば、翡翠の羽でおさげ髪をくくる少女が立っていた。
「あの子が、おまえにこの絵本を渡してくれたのか?」
「うん。綺麗なお人でしょう?」
弟はそう言うと少女をじっと見つめ、あまち物言わなそうな乙女は俯向いた。
「君、僕達が帰りたいと言ったら、どうする気だい?」
「止めません。私は帰り路を案内する役目を荷負っております。だから、案内します、それだけ、ですから。」
もじもじと指をいじりながら話し終えると、彼女はくるりと向きを変え、すたすたと足早に歩き出した。兄弟は少女に続く。やがて、赤、青、橙の林檎が並び形を成す階段に出た。
「此処を降りれば貴方がたのお家の前に出られます。私はまだこの先に進むことは許されていないので、此処でお別れです。」
「案内してくれてありがとう、帰ろう巡。」
「またね、綺麗な人。」
「えゝ、さようなら。」
兄弟は先ず無事に戻ることが出来た。母の喜びようは如何程であったろう、一ト月帰らなかった我が子達をすっかり細くなってしまった両腕でしっかりと抱きしめた。三人とも、泣いていた。
反対に蛇は笑っていた。
「良かったね燕。今生は優しい旦那になりそうだ。」
「姉上。」
燕と呼ばれた少女は艶のある細やかな黒髪を搖らす風に心地よさげに目を細めた。
「こんな身を綺麗だと真直ぐに仰有っていただけました。あの方は、とてもお優しい人……私はもう清らかな肌でもないというのに。」
燕の紺青深い瞳は露草の花びらを取次いだ、涙がはらりと頬に散る。
「かつて私に恋をした若者に哀れみを掛けた時、おまえの暮すこの塔に来られたのは喜ばしかったが、私にはおまえが不憫だった。あのような責め苦に遭い恋も愛も知らぬまゝこの世を去ってしまったのだもの、図書塔に来て憂き目を味わうことはないが、燃えるような人情に身を任せることもない、私は恋を最後に知れたのに、おまえは知ることが叶わなかった、姉さんには、それが唯一心残りだったのよかわいい燕。」
「姉上。」
「さあおまえはもうお行き、姉さんは山に戻るがおまえは生まれなければならない。」
優しき蛇は蛾の名残であった白い身体を妹の首に巻きつけて、その清らかなうなじにキスをした。
「逢えますか。」
「逢えるとも。泣かなくて良い良い、私のおまえを想う心は誰にも殺せないから安心しなさい。いつかおまえの可愛い子供を見さしておくれな。」
「でも姉上私の身体は、」
「大丈夫、大丈夫。今生は健康な姿で生きられる。どうか恋を知って愛を感じられますように、おまえがうつくしい家庭を築けますように。」
たった二人の姉妹は多大の背と背に腕を回して抱きしめあった、心穏やかな別れではあったが涙は熱く頬を伝う。
もうじき小鳥が囀る、さあお行き。
この手向けの花を、燕、貴女は憶えていましたか。
水無月の毒は程無くひいて行った。一時は耐え難い病として肉体を蝕むものだが峠を過ぎれば後は鎮まる特性の毒だったらしい。
「子供のかんしゃくは大変だからな。」
老夫は寂しげに頭を向うにして呟いた。
「父と伯父は、幼い時にもう母様に逢っていたのですね。」
―えゝ、燕さんは此処でお姉さんと再会して、それから巡さんと逢うために人の世界へ生まれたの。そして貴方が生まれたのよ、水無月さん。
蛾の瞳は曇りを隠す夜の色を湛えている。
「母様は、此の場所におられるのですか?」
老夫は水無月の方に首を動かさないまゝ一冊の本を手に取った。
「これを…」
本、本、また本
「教えてはくださらないのです!」
立ち上がりざま大理石の床を片足できつく蹴る。
―水無月さん。
蛾が慌てて宥めようとするのを老夫の片手が制止する。
「のう、水無月。」
若い怒気はうなだれる老夫に一気に注がれた、
「おまえさん、此処を聖地か何かと勘違いしていないか?」
老夫は空気の不愉快な震えをものともせず青年に語り掛ける。
「まあ確かに、鎮魂のための場所だから聖地と言えんこともなかろうがな。でも錯覚してはいかん。此処は魂を鎮めるための場所なんだ。祈りを捧げたり願いを唱える場所ではない、おまえさん何しに来た?何で来た、どうやって来た?忘れていない筈はあるまい、思い出させないようにしているだけだ。」
「母が図書塔に見初められたと聞いたんだ!」
「それがどういう意味か分かるか?」
一呼吸。烈火は止めてた息をこの時吸った、酸素が頭を冷やしていく。
―図書塔は、その人の理想を叶えるための場所ではない……
火取り虫の瞳から夜露したたる。
死んだ後でもその人は消滅するのではなく、姿が見えなくなるだけで、いつかあの世とこの世の境を越えて互いは逢うことの叶うものだと信じていた。実際姉上には逢えたから、そういうものだと思っていた。見えない存在は確かに在るけれど、見える存在はその事に気が付かない、向こうが意識を向けてくれない限り、出逢う行為は叶わない。
姉上は見えない私を想ってくれていた。巡さんも図書塔で会って以来想ってくれていた。だから私はお二人に逢えた、探すことが出来た。愛する者は必ず傍に居るのだとよく言うが、それは私にとって一つの真実だった。
それなのに私は、あの子に愛情を示したことが無い。だから貴方は私に逢えない、例え拾い子でも我が子なのに。可愛い坊や、私達の坊や…
山上に蹲る水無月に、猪は何も言えないでいた。だって、何を話せばいい?もう二日間ずっとこのままの状態なのに。
泉に溺れている水無月を引き揚げたのは鹿と猪だった。鹿は蹲った姿からピクリとも動かない青年を一瞥すると短く
「不味い。」
とだけ発すると彼の背中に耳を寄せ、
「息が弱り始めている。きっと山にいることに身体の限界が来たんだ。」
そして手早く猪に言伝た。
「蛇を呼んで来る。もう彼を下山させなければならない。君は私が戻るまでこの青年を見ていてくれ。」
山鳥のように駈けて行く鹿の姿を猪は見送りその影も見えなくなると、獣は水無月の力弱くなった手に自らの手を乗せて、泣いた。
「水無月。」
猪は初めて聞く声にハッと顔を上げた。其処には息を切らした状態で立つ男性が一人。
「貴方…は?人間?」
「私は、水無月の父親です。」
巡は片手に紫陽花のボタンを握っている。
流星
一度でいいかた抱きしめてあげたかった。そうしたら貴方はこんなに苦しまずに生きられたかもしれないのに、私は如何して病で死んでしまったのだろう。
姉上は虚弱体質なのは何度生れ変っても同じなのだと仰有った。あの時は姉上にこれ以上涙を零してほしくないから納得した顔を見せた、落ち着いて命を受け入れる表情を示したけれど、本心はそんな訳無い。悔しい、悔しい、悔しい。私に殿方の腕を掴んで引き留めるだけの力があれば、先の夫が戦へ赴くのも止められたかもしれないのに。巡さんを置き去りにしてしまうことも無かったかもしれないのに。
ごめんなさい。ごめんなさい。
笹舟
紫陽花のボタンを我が子に握らせて傍に座る。
「猪様、息子の傍に居てくださったこと、お礼申し上げます。」
父は息子の手を両手で包んだ後、居住いを正し猪に深く頭を下げた。
「そんなおじぎをしてもらうようなことしてないよ。だからどうか顔を上げて?僕はただ白藤さんに言伝を任されただけで、彼を励ますようなことは、何も。」
「いゝえとんでもない。猪さまがこの子の隣に居てくれなければ私は此処まで来られなかった。貴方が心配してくれたから私はまた水無月の姿を一目見ることが出来たのです。」
巡はにこりと微笑んだ。その両眼には物を見るための神経が通されていない。それでも彼は猪の後方を見て
「おや蛇さまと鹿さまがお戻りのようです。」
「巡か。」
「はい、蛇さま。それとも、義姉上さまとお呼びするべきでしょうか。」
まるで蛇を眼前に捉えているかの如く巡は蛇へと全身を向け先程猪にした時よりも深く平身低頭の構えを示し、恭順の意を言下に伝える。
「どちらでも良い、と言いたくはあるが、言葉を粗末に扱えばお山も黙ってはいられないことであろう。此処は一つ、義姉と呼んでくれないか。その方が燕は嬉しかろう。」
役目を果たした玉章の花はもう
「水無月の願いを叶えようとしたのでしょう。」
「一度も生前逢っておらんのに?水無月は燕が流行り病で亡くなった後、巡、お前が川袂で拾って見つけた者であろう。この子には、直接の関係などありはしない。」
「義姉上、だから燕が水無月を慈しむことは無いと?」
「真ッ当に考えれば、そう行き着くだろう。」
「否、義姉上。」
巡は袂から物を取り出す、それは駄菓子や飴をいたずらに出すような仕草とは違い、袂から片手に載せてゆったりと恭しい様で少しずつ外の空気と光に深呼吸させたのは、一輪のかざぐるまであった。
子供が遊ぶ綺麗なやさしい川で、素直な笹の葉くるりとまろげ川底の小石が陽に反ってキラリと粒々輝き始めた日を想い出す。眠る息子の傍に坐し、真顔の蛇と喉を生唾で鳴す猪、鹿は水無月の手当、紫陽花をその身に降り掛けつつも巡の動きを凝視する。
風がざあっと山颪、花は勢い良く回り始めた。
声が聞える、声が聞える。
寂しがり屋の眠れぬ声が
母を慕って泣くのだろう 寝ても覚めてもいぬ母を
何處にいますと訊くけれど
私は答えてあげられない
死ぬ前に示した愛が無いから
私は貴方を抱きしめてさえあげられない
あゝ蕗の薹が搖れている
氷の溶けた空を仰ぎ
雨の季節を待ち侘びる
早く来て、月の御子達よ
君達が彩る花を待つのです
可愛い坊や、私達の坊や。
お願いどうかあの子を一度だけでいいからこの手に抱きしめさせてくださいませんか。
笹舟は沈むを知りつゝも川を往く。いつか海へ辿り着けるを一心に祈って、祝福のために身を浸す。激しい潮を一目見たいが為にまだまだ塩の混ざらぬ淡水の穏やかな鼓動に肉体を責めさせる。自らの肉体を蝕ませる為の静かな日々は笹舟にとって痛苦の時である筈だのに、葉先は澄まして飛沫を白く輝かす。その白露が宙に散って風となり、舟の魂は鳥よりもかろく羽ばたいて、念願の海原に届くのである。
水無月は、ゆっくりと目を開けた。
もう其処建物の内部ではなく、見慣れた山上。水無月はまだケホケホと弱々咽る喉ながらも細く呼声をあげる、
「父様?」
起き上がろうと拳に力を入れると、何かが触れた。それは、起きないままの息子を守ってくれるようにと妻に贈った肌守り。
「そのお陰で戻って来られたみたいだな。」
春眠にほわり綻ぶ牡丹桜の綿雪は、安堵して胸を撫でおろす、鹿はほっと息をついた。
「恵まれた奴よの。」
蛇は紫陽花のボタンに頬を寄せ、つまらなさそうに呟くとそのまま目を眠ってしまった。
「水無月君。君のお父さんが助けに来てくれたんだよ。」
猪は彼の濡れた身体が冷えないように頻りに鼻で水無月を撫でさすっている。
「父様。」
何から話したら良いのか分りません、と言おうとしたが口はわなわなと震え舌は言葉を発音出来なかった。代りに瞳の奥が搖らぎ出し、ぼろぼろと溢れる感情は、傍に咲いていた山茶花の花輪を搖らしたが、花は抗うことも怒ることもしなかった。
「水無月、父さんが悪かった。覚悟を決めておまえに話をしていれば道を踏み外すことも無かったろうに。ごめんなあ水無月、ずっと寂しかったな、怖かっただろう。」
青年は学生に戻り、少年に戻り、幼子に戻り、赤子に戻ってワッと泣いた、他所目も齢もはばからない大声で、ようやく。父に抱きつくその姿は、赤子が指を一本握って離さない姿と重なってゆく。
「ごめんなさい、ごめんなさい。おかあさんに逢いたかったの、おかあさんが欲しかったの。でも白藤はいなくなっちゃって、僕悔しくて、また誰かに奪われたと思って、誰の所為だッて、戦争、そんなものがあるからお母様は自殺しちゃったんだと思ったの、毎日、毎日、眠る度に夢を見るのよ、母様の。」
哀しい産声は、答えを求める。親は一つずつ答えていく他ない。
「水無月、私達のお母さんはね、確かに人とは離れた存在だった。おまえの母様は燕と言うお名前だったのだよ。燕は人間の姿として二回生れて来た、一回目はね、うんと昔、国の責務の為に生きる男の人と結婚したのだけれど、その人が戦争に行くことになったのだ。それを止めるために文字通り必死の行動に移したんだよ。その後ね、姿は山百合となりこのお山に埋葬され咲き続けることになった。」
「あ、……ウスバカゲロウさんの恋のお話…。」
「読んだのかい?あの物語の蛾の君は、此処に居らっしゃる蛇さまなのだよ。」
「姫神さま…」
「よくもまあ伯母さんに悪態を吐いたものだ。」
鹿が蛇のお小言を宥めんとしてキッと見向いたが、それはポカンと空振りに終った。だって蛇がとても柔和に微笑んでいたから。赤子の悪口に殴りとばす奴はいない、蛇は本当に楽しそうだ。
「あの物語の後、燕と伯母さんは図書塔に招かれて、其処で私と燕は初めて逢った。」
盲目の弟と血塗れの妹は恋を知った。出逢うべくして出逢ったけれど、燕は生来虚弱で、結婚して間もなく外へ赴ける身体ではなくなってしまった。
「それから哀しい夢を見始めた。私が人を殺す夢に毎晩魘されたのだが、それはきっと私ではなく…」
「僕だったんだ。僕の顔立ちは父さんに似ていると以前伯父さんが褒めてくれたのよ。」
「息子を、おまえを夢に見ていたのだろう。今になってようやく分るなんて、俺はなんて浅間しい。おまえには勿論、燕にも兄さんにも顔向けが出来ない、すまない、すまない、醜く愚かな俺にはどうやっても償いしか似合わないのだ。」
燕は生きたがった。初めて知った恋心は欲を知り、親心を知りたがったが心と身体は常に相容れず婚約から半年後彼女は病に罹った我が身を夫に謝りながら涙のうちに世を去った。信は巡が後を追うかもしれないと一度は案じたが巡は自殺しなかった。それでもやはり心配なのが兄心、自分の屋敷へ引越させ暮らすようになって一ト月余りが無事に過ぎた頃、雨の日である。巡が日課の散歩からなかなか帰って来ないのを不安に思い信は曙の光一縷射す道を急いで駈けて行くと、向こうからいつものように杖を操りゆっくりと歩いて来る弟の姿が見えた。杖持たぬ方の手はいつもふらふらと風に任せているのだがその日は何か白い布のような塊を抱えている。それはどうした、と聞くとにこりと微笑んで一言、
「月の繭だ。」
とだけ答えた。その赤子は水無月と名付けられた。
同年代の子等と遊んでいると、友達は母親の手に曳かれて家路を歩いて去って行った。感づいてはいたが確証は無い、それが欲しくて父に尋ねた。
「僕の母様は何方にいらっしゃるの?」
巡と信はあの日図書塔で見た母親の姿を忘れたことはなかった、あの気丈で無遠慮でたくましかった母が見る影も無く憔悴していた頁を。戻った二人を抱きしめ、抱きしめ、抱きしめた。普段の小言は一つも無かった。数日してまた元気になった母が、寝る前の読み聴かせを終えた時ぽそりと言った。
「生きていると信じていたからあの間生きていられたんだよ。」
なんて残酷なことをしたのだろうと、二人は声も出せず泣いたが母親は静かに優しくただ抱きしめてくれた。その言葉が泉のように湧き上がり、巡は燕の死を伝えきれず、兄もまた果たせなかった。
血の繋がらない逢ったこともない母親に似ていると言われた多感な幼子は、どれだけ嬉しかったろう。それが自分を気遣う言葉であると知っていても、あの喜びは。
「父様、償わなくてもいいの、だって僕は貴方に傷付けられただなんてちっとも思っていないのよ、だから悲しいこと言わないで、醜くなんかないわ愚かでもない、私の大好きな父様です。」
父はワッと泣き崩れ伏せた。その背中に顔を甘えさせて水無月はねだる。
「だからお願い、私を置いて行ってくださいな。」
「水無月、お前、良いのか?」
言葉の出ない義弟に代り蛇が問うた。
「此処に居続けることは人にとっては死に続けることにも等しい。もう山を下りる気はないと?」
恍惚とした瞳に掛かるふっさりとした睫毛は細やかに笑う。
「はい、私は此処に居続けます。私は世界の掟を破りました身、もう人間として人の世に住み続ける資格は自ら捨てたも同然、せめて山への供物になれば僅かなれど罪滅ぼしも叶いましょう。償いに終りはありません、私は朽葉となるまで、例え土に還っても償いを止めることは許されない。でも、父様は違う、誰の命を奪ってもいないのです、私のように義憤を言い訳にして八ツ当たりをしたことは無い。私の手は二目と見れぬほどおぞましい罪業に塗れ滴っていますが、父の手は清いままです、だから姫神さま、どうかわたくしの父を無事に帰らせてあげてください、父は盲目です、生れた時からなのでもう日常の動きに不安はありませんものの、やはり心配は残ります、どうか父を無事に、怪我の無いように伯父の家まで戻らせてください。」
「おまえ、水無月、おまえ、何を。」
うろたえる父の両手を両手で包み、青年はにこりと微笑んだ。
「どうかお元気で、お身体を大切にしてください。父様と伯父様がご無事で生きておられることを糧に、私は此処に生きるのです。」
巡は初めて駄々をこねた。嫌だと叫び空に腕もががせて蛇と鹿に挟まれて背中を向けた息子の名を呼んだが、この場所に母親はいなかった。駈け寄ろうとする巡を猪が必死で制止する。青年は最期此方に横がほだけを向けて、穏やかな眼差しのまゝ足元から色も淡い紫陽花の花々へと孵化していく。
紫水晶、翡翠玉、黒曜石と瑠璃の花芯に向けて瞼のような花弁は薄く重なり鳥の翼、虫の羽を銀細工で縫いとめた儚い手毬が一つ一つ咲いてゆく。花から零れる錦のかがり糸は茎へと変化し土に根を張り住居の土台を組み上げた、茎はやがて手を伸ばし、指の代りに青々と緑深い葉が命を呼び、其処には胡蝶、蜜蜂、百足に蜘蛛が集い、やがて月から降りて来た白無垢の蛾達も憩い出す。月をかざした灯火に、今日も息吹は吹きつける。
読者諸君、此処は果して監獄なのだろうか。その答えはきっと図書塔にあるのだろうが、我々が其処へ辿り着ける時は来るのだろうか。賢明な諸君等の返答を待つ。
終
「人ならざるもの」