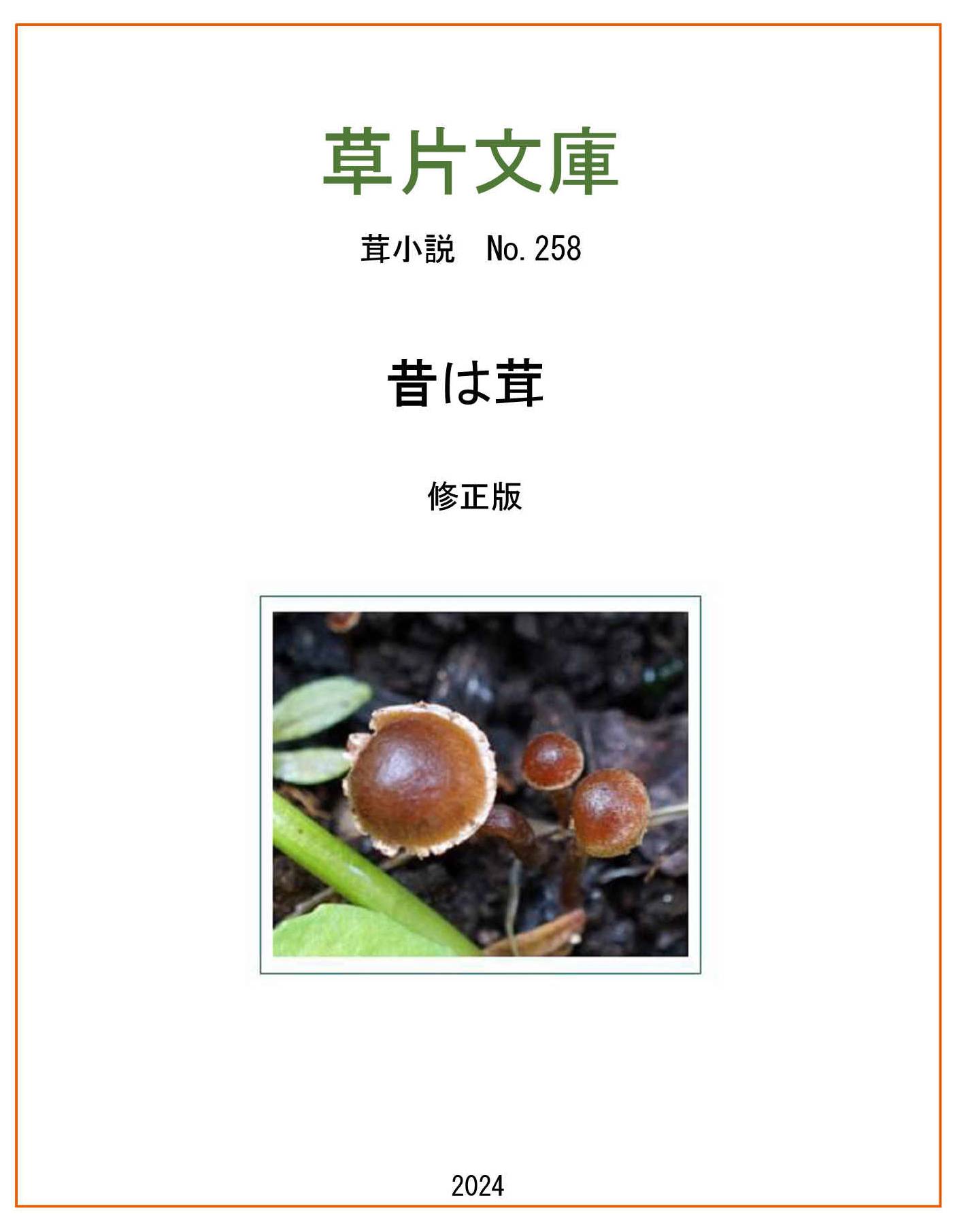
昔は茸
現実的指小説
「茸の中に人が入っていくんだ。おもしろかったよ」
動物園に茸の写真を撮りに行った夫が、帰ってきていきなり言ったことである。おかしくなったんじゃないかと思った。
夫は定年退職して、好きなカメラをもって旅行をするのが趣味である。最近、庭にはえた茸を見て、写真機をもちだし、やたら撮っていたと思ったら、その写真を友達の植物学者に見せたら、ほめられたと言って、茸にこり始めた。
年はまだそんなにいっていない。来年後期高齢者である。男性の平均寿命が83。それと比べればまだまだ若い。人によって違うのはわかるが、うちの夫はまだぼけないと思っていたのだが。
友人のだんなさんが、六十代で痴呆になりかかっていて、なんだかうちの旦那が心配になってきたところだ。
「あなた、なにがその茸に人が入るのをみたの」。聞きなおした。
てっきり別の意味があるのだと思ったのだ。
「いや、高校生くらいの女の子だった。友達二人ときていたんだけど、一人が茸に入っちまったんで、あわててもう一人も入っていった。
それで、その茸の写真をたくさんとった。何という茸か調べようと思う」
と、彼は真顔で、カメラのディスプレーに撮った茸を映し出した。傘が赤色で、柄の白いかわいらしい茸だ。かわいい虫かなににかが茸にとりついたのでそう言ったたのだろうか。だけど、茸に虫が付いていない。とするとあとはなんだろう。
何か言った方がいいのだろうか。
「この茸ちいちゃそうね」
人など入るはずはない。
「うん、そうだな、五センチくらい」
「なぜ、その子たちがはいるところの写真をとらなかったの」
「いや撮りたかったな、きれいな茸だから写真を撮ろうと用意をしていたら、女の子たちが通りかかって、
『あ、いいのがあった、ここからにしよう』っていって、一人の女の子が指で赤い傘をもちあげると、頭からすーっとはいっていって、もう一人もあわててすーっとはいてしまった。吸い込まれるとき白いパンツが見えた」
なにがパンツなの、むかしはこんなことをいう人ではなかった。
「なに言ってるの、女の子たちは高校生でしょう、背の高さは150はあるでしょう」
「うん、今の高校生の女の子も男の子も背がた高くなったね」
「それで5センチの茸にどうやってはいるの」
もうはっきり聞いてしまった。
「あの子たち、茸のうまれかわりかもね」
「生まれ変わりだと、どうして150センチが5センチの中に入れるの」
「おまえ知っているかい、猫好きは生まれる前は猫科の動物だっていうんだ」
「だれがいったの」
「どこかのおぼうさん」
「私がむかしバラのはなだったら、バラのなかにはいれるの」
「きっとね、だけどおまえはバラじゃないね、どっちかというと、芙蓉だな、顔大きいもん」
余計なお世話だ。まあ、芙蓉も好きだが。
主人はまじめな顔で話ている。いいのだろうか。理論物理の教授だったのだから気になる。これが文学部の教授だったら、聞き流していたかもしれないのだが。
その日、夕食は、茸のはいった料理にした。たまたま生きのいい丹波のシメジが手には入ったので、その茸を入れて肉じゃがをつくった。まずかっただろうか。
テーブルで亭主の顔を見ていたら、「肉じゃがにシメジか、めずらしい」と言いながら、箸でつまんで、茸の柄の切り口をちらっと見ると、口に入れた。そのあとは、いつものように普通に食べた。
ちょっと気になったようでもあるが、普段どおりだ。
「この茸しゃきしゃきしていてうまいね」
それを聞いて、現実がわかっていると、ちょっと安心した。
「明日も動物園にいって写真を撮ってくる」
夫は、一年間動物園フリーパスの券をもっている。
その日も家に帰ると、「黄色い茸に小学生の男の子が入っていったよ、やっぱり前世が茸だった人は多いんだね」と言った。
私はとりあえずうなずいておいた。
「茸の中にはなにがあるのかね、俺も小学生のように指で黄色い茸の傘を持ち上げようとしたら、ぽろっとかけちまった。わるいことしたな」
写真機のディスプレーに黄色い茸をだした。その茸もかわいらしい茸だ。
「傘が欠けいるじゃない」
「これも、写真を撮ったところに、小学生がきて、はいっちまった、そのあとこわしちゃったんだ、小学生がでてこれないと大変だと思ったんだけど、大丈夫ぶだった」
「どういうこと」
「ほかのところで見つけた黄色い茸からでてきた」
「なにそれ、それじゃ昨日の高校生もでてきたの」
「それは見ていないな、小学生の入った黄色い茸は、キリンの放し飼いのところで撮ったんだけど、虎の檻のあるところも黄色いのが生えていて、写真を撮ろうとしたら、小学生が出てきた。きっとつながってたんだ。昨日の女子校生たちも、どこかに生えていたピンクの茸からでたにちがいないね」
「そうなのね」
とりあえずうなずいておいた。
「俺も茸に入ってみたいもんだ、前世は茸じゃなかったんだろうな、生えている茸に触っても傘は開かなかった」
「あなたはなんだってんでしょうね」
「植物じゃないかもしれない」
「どうして」
「マタタビの粉をなめたくなる」
うちの雄猫のおにぎりのためにマタタビの粉が買ってある。おにぎりは18歳と年寄りで、たまに食欲がおちる。そういうときにマタタビをやると、床にこすりついて、ゴロンゴロンした後に、食欲がもりもりになる。
「それじゃ、猫だったの」
「かもしれない」
「私、赤井さんの芙蓉のに触ってみたけど、花の中に入れなかったわよ」
近くに住んでいる人だ。
「芙蓉じゃなかったのだね」
まじめな顔をして言っている。やっぱり誰かに相談しようか。その前に明日、動物園に一緒に行ってみよう。
「あなた、明日も動物園にいくの」
「うん、そのつもり」
「私もついていっていいかな」
「いいよ、ウオーキングにもなるしね」
こういうところはまともだ。
ということで、次の日、主人のあとをついて、動物園にいった。入場料は老人は安い。だが主人のもっている一年のパス券は、入場料の三倍の値段で買える。それで、それを買った。ただし、次の時までに、パス券には顔写真を貼っておかなければならない。
主人はなれたもので、入ると園内の地図など見ずに、
「今日は鳥園のある方にいく、あっちは自然が多いから、茸もたくさんでるよ」
そう言いながら、歩き始めた。
「ほら、そこにも茸があるよ」
主人が指さした、植え込みの下に茶色いちいさい茸がいくつも生えている。
確かに自然を利用した動物園だけのことはある。
鷲などの大型の猛禽類が一緒くたにはいっているとてつもなく大きな檻が見えてきた。
「大きな鳥かごね」
「うん、あの先の林のような丘に茸や野草が生えているんだ」
「こんなにいいとこがあるんだったら、もっと早くにくればよかった」
「一年パスも買ったんだから、これからでもくるといい」
主人は動物園の端にある小さな林にはいったとたん、しゃがんで、写真機を構えた。その先には白いかわいらしい茸が固まってはえていた。
「この茸たちかわいいわね」
「うん」
主人はシャッターをパシャパシャ押す。一つの茸を撮り終えると、次の被写体を探して林の中を歩く。
林の中には茸だけではなく、さまざまな野草が生はえている。半分赤くなった実を上に向けて立っているまむし草が目立つ。
その中でもとても立派なものを主人が指さした。
「ずいぶん大きいな、写真を撮っておこう」
彼はカメラを構え、まむし草の姿を撮した。
緑色の粒々が混じったまむし草の赤い実は充実していてきれいだ。一つ一粒がつやつやと光っている。
きれいだ。触ってみよう。
見ていた主人があっと声を上げた。
「はいっちまった」
一緒にきた奥さんが、まむし草の実を指でもちあげると、中に飛び込んだ。
「あいつは、前世がまむし草だったんだ」
男は奥さんはどこかに生えているまむし草から出てくるだろうと、また茸をさがしはじめた。
奥さんはまだ戻ってこない。
今日はずいぶん茸の写真がとれた。写真機のバッテリーが少なくなった。あいつは時間が経てば必ず戻ってくる。男は全く気にせず動物園からでた。
家につき、玄関を開けた。
あれ、鍵がかかっていない。
なかから、帰ったのと声がして、奥さんが顔をだした。
「先に帰ってたのか」
「なに、今日はずーっと家にいるわよ」
男は奥さんが、まむし草の中に入ったのを覚えていないみたいだと思った。
居間にいってガラス戸を開けて庭をみた。
おや、イチジクの木の下に、小さなまむし草の葉がゆれている。いつのまにまむし草が生えたのだろう。ピンクの傘の茸がその脇に生えている。
「おまえ、庭のまむし草からでたんだな、動物園のまむし草とつながっているんだね、中はどんなになっていたんだい」
それを聞いた奥さんは電話口に行った。
「ほらお前、この間茸に入った高校生の女の子二人、庭のピンクの茸から出てきたよ、門から外に行ってしまった」
奥さんはをいそいで、電話のボタンをプッシュした。
「もしもし、精神科に予約入れたいのですが、いえ、私ではありません、主人です、75歳です、はい老人性だと思います、あ、神経内科にかかった方がいいですか、それではそちらの外来をお願いします」
彼は電話をかけている奥さんをぼーっと見ていた。
昔は茸


