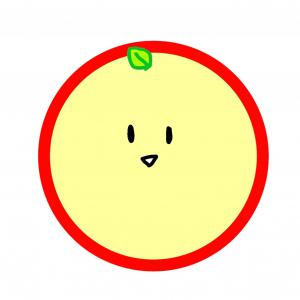マイファーストアップルパイ
マイファーストアップルパイ
これは、小さな国の、小さな町の、偉大なふたりのお話。あっ、よかったらそこのお方、ゆっくり聞いてやってくださいね。
この町のとあるところに、大きくそびえる山があり、そのふもとにはリン・りんりんという女の子が住んでいました。りんりんは毎日素敵におうちを作りかえたり、素敵にダラダラしたり、近所の素敵な山へ散歩に行ったりして過ごします。そして夜になって、暖かな部屋の丸くて素敵なテーブルにつくと、そこで赤いノートを開いて日記をしたためます。そこにはこう書いてありました。
「今日はいわきのお山に雪が降って、粉砂糖をふるったケーキのようで美味しそうでした。きっと青々とした爽やかな甘みがあることでしょう。」
さて、とノートを閉じたりんりんは、りんごの総柄の羽毛布団に寝転がり、そばがらの枕に赤い頬を押し当てて眠りました。
朝方、りんりんは夢を見ました。そこにはこの国を治める天使の、アップルシードさまが出てきました。天使さまは空高くからりんりんを見下ろして、りんごの枝葉で作られた冠からステッキを出して言いました。
「りんりん、よく聞いてね。この山の素晴らしさは、この町の誇りですね。その素晴らしさを広めて、あなたの大好きなりんごも持って、いろんな人に会いにいきましょう。きっと皆、あなたを快く迎えてくれますよ」
天使さまはそう言って、ステッキを一振り。すると暖かな風が吹き、それに乗って甘い香りがするのをりんりんは感じました。それはりんりんが大好きな、りんごの香りです。また、天使さまの声が聞こえます。
「この香りを辿っていけば、きっと巡り合いますよ。道中気をつけて、素敵な出会いに溢れますように」
りんりんが目を覚ますと、なぜだかカーテンが開いていて朝日が真っ直ぐに彼女の元に差し込みました。そこから見えるいわきのお山の雄大な姿に、りんりんは固く誓います。
「天使さま、私はきっと、この町のりんごとあのお山の素敵さをみんなに広めますね!」
こうして、りんりんは旅行の準備をし始めました。
同じ頃違う町では、ひとりの男の子が躍起になってベッドの上でバタついていました。
「どうしよう、これじゃありんごの良さは全然発揮されないよ! わからない……調味料も火加減も、まったくレシピと同じなのに……いったい何が違うんだ!」
男の子は元から赤い顔をますます赤くして、なんとも美味しそうな顔つきです。おっと、こんなことを言っているのを聞かれては怒られてしまいますね。
強い心でりんご料理に精を出す彼は、名を藤崎りん吾と言いまして、この町のお友達に美味しいりんご料理を食べてもらうことを楽しみに暮らしています。べつに料理人というわけではないのですが、この世界のすべてのりんごを美味しいと信じて、さらに美味しい食べ物にしていきたいと思っているのです。
ところが、彼はさっきのようにいつも悩んでいます。というのもこの町のりんごは、調理をするよりも生でそのまま食べる方が、なんだか美味しく感じてしまうからです。洗って切っただけのしゃりりとした涼しさ、まろやかなのにくどくない甘味、滴るほどのジュース。他にもたくさん魅力があります。
あるときは簡単にコンポートにしようと、りん吾は砂糖やレモンを足してじっくりコトコト煮込みました。それはそれはりんごの甘味を引き立たせた素晴らしいものが出来ましたが、彼にはなんとなく、ちがうのです。
「もっとりんごの旨味や爽やかさ、食感を活かしたものにしたいのに、うまくいかないな。次はどうしよう……」
りん吾はそのまま眠りついてしまいました。もどかしさと悲しさ、自分への腹立たしさから、目から果汁を浮かべて、しくしくと眠りました。
次の朝は少し冷え、ベッドの上でぷるると震えて彼は起きました。毛布を被り直しながら窓へ向かうときれいに結露して、少しの間、指先でりんごを描いて遊びました。
外へ出るとうっすらもやがかっており、近所の木々がたわわにつゆを実らせているのが見えます。そのつゆがほんのわずかの太陽光に照らされるとまるで宝石のように輝いて、りん吾がはっと目を見開いた時、雨のように落ちました。
雨の匂いに乗って、玄関先に置いていたりんごがふわりと香りました。
「そうだ……りんごはこんなに美味しいのに、それを使った料理が負けるなんて、あるわけない。もっと美味しくしなきゃ、意味がない! 諦めちゃいけない。いけないんだ……」
りん吾は、彼のお手手の果汁が搾り出されそうなほど拳を握り、決意しました。
「これはきっと神様の思し召しだ。神様、ぼくは頑張ります。ありがとうございます……!」
りん吾はそうして暖炉を炊き、暖かな香りの中で次のレシピを考え始めました。
ある日りんりんは、自分の町より少し東へ向かっていました。くる日もくる日も、自分のりんごと誰かのりんごを交換こして、美味しく食べてはお礼を言ってまわりました。
その時、少し遠くの方からとてもよい香りがして、りんりんは足を止めました。
「あれは……焼き菓子だ! なんの焼き菓子だろう、りんごにお似合いなお菓子だろうか」
わくわくしながら彼女がその家へ行くと、窓から中の様子が見えます。そこでは、オーブンに向かって真剣な顔つきをしたりんごがありました。
「ごめんください、お忙しいですか?」
窓をふたつ叩きましたが、中のりんごは気付きません。忙しいのかな。あとでまた来ようかな。でも、今出ていけば、あのオーブンの中の美味しいお菓子に出会えないかもしれない。
りんりんはそう考えて、玄関へ回りました。ピンポンを一度、二度、三度目に、不機嫌そうな家主が現れました。
「なんだ、押し売りならいらねぇぞ、今俺は忙しいんだから帰っておくれ」
「こんにちは! りんりんと申します! 美味しそうな香りがしたので、りんりんのりんごと交換こして、一緒に食べたいなーと思いまして! ほら、これ!」
りんりんはつややかで真っ赤なりんごをひとつ見せました。頭のてっぺんからお尻の真ん中まで赤いそれに家主は目を丸くします。
「これは……! お前、山のふもとから来たか?」
「そう! よくわかったねぇ!」
家主のりんごは名を名乗り、りんごが好きなやつに悪いやつはいないと言ってりんりんを招き入れました。
キッチンとダイニングが一緒になったその部屋は、木目の綺麗な家具が並び、彫り込みの草木模様が見事でした。椅子の背には、りすやうさぎが木の実を食べている様子が、細かく彫られています。
「わぁ! 素敵な家だねぇ、りんりん、素敵なもの大好きなの!」
「そりゃよかった。お茶かコーヒー、どっちがいい」
「ミルクコーヒーがいい! ありがとう!」
りんりんがにっこり笑うと、じゃあ俺はブラックだ、とりん吾も笑いました。
「りん吾は、今何を焼いているの?」
差し出されたこぎん刺しのコースターとランチョンマットの布の目を数えながらりんりんは尋ねます。だってこれから何を食べるかわからなければ、気持ちを作ることができません。美味しいものを食べる前はそのお料理のことをよく考えて、誠意を持って食べなければいけない。りんりんは元よりそう考えていました。
しかしりん吾はその言葉を聞いて顔を曇らせ、途端に顔のつやつやワックスがくすんでしまいました。
「あぁ……パイを、焼いてるんだ。けど何度も失敗してて、今日も美味いかどうかわからねぇ……せっかく来たのに悪りぃな……」
りん吾はブラックコーヒーのカップを口元に当てたまま、ふうふうするだけで飲めなくなってしまってしまいました。よほど悲しいのでしょう、ぼうっとしたまま、なかなかりんりんの方を向きません。
「そうなんだぁ、りんりんはお菓子作ったことないけど、むずかしいんだねえ」
あぁ、とりん吾は遠い目で返事をしてくれますが、りんりんも手持ち無沙汰になってしまって、椅子の背もたれのうさぎの背中を撫でて遊び始めてしまいました。
チン、とオーブンのベルが鳴り、ふたりははっとしました。パイが焼きあがったのです。
ふたりは走り出してオーブンの元へ向かいます。もっとも、コーヒーの入ったカップはこぼさないように細心の注意を払った上で。
「りん吾、出来たよ!」
「わかってるよ、出すか……」
いよいよその時が来ました。
ふたりが緊張しすぎて心臓が飛び跳ねそうになっているところに、りんりんは思いつきました。そういえばなんのパイを焼いているのか、聞くのを忘れてしまったのです。お魚なのか、お肉なのか、お野菜、くだもの……なにが来るでしょう。手に汗握る戦いがここにもありました。そしてもし、りん吾の思った出来上がりでなかった場合、彼女はどうしたらいいのでしょうか。
鉄の扉をりん吾がフックで開けると、ふくらんだ熱の塊が顔いっぱいにぶつかるのがわかります。
「ぶわ! あっつい!」
りんりんは慣れない出来事に驚いてしまいました。柔らかい毛並みが熱と湿気でチリチリです。りん吾は冷や汗なのか果汁なのかわからないくらい汗だくで、中のパイを取り出します。
そっと、やけどに注意しながらテーブルに運び、彼は言いました。その声はうわずるのを我慢するような、ほっとしたような声色です。
「成功……かも……」
焼き色の美しい、まるまるとしたパイがそこにはありました。すっとんきょうな声をあげてりんりんが飛び跳ねると、りん吾もだんだん嬉しくなります。
「でっ、でも、食べてみないとわかんねぇから」
「食べよう! 早く!」
すぐさま彼はうなずき、包丁を手に取って呼吸を整えます。円の真ん中を通るように刃先をぴったり合わせて、そのまま一気に切り落としました。
急げ急げと言わんばかりに六等分にわけ、うちひとつをりんりんに、自分はもうお皿に盛る時間も惜しいというようにフォークに持ち替えます。りんりんもありがとうを言う暇もなく、そのパイに釘付けになりました。ふたりはそっと手を合わせて、無言でいただきますを言いました。
ひとくち食べて、ふたりは顔を見合わせます。
それはとても芳醇なバターの香りにりんごの甘酸っぱい香りがくるくると溶け込んで、焼きたてのしっとりした優しい食感に身も心も安心してしまいます。カスタードクリームのささやかな甘みがりんごを色濃く引き出して高級感を醸し出し、主張しすぎず、けれど自分のすべきことがわかっているいるそのりんごは、すべてにおいて高品質で、価値という言葉の意味も凌駕するほどの存在感を得ています。
これは、りんごという果物の話ではなく、りんごがりんごであるためのパイだということが、ふたりはよくわかりました。
りんりんは目を輝かせながらふたくちめを頬張ります。それ自体が、言葉よりも何倍も美味しさを伝えていて、ぼうっとしたままのりん吾にもきちんと伝わりました。
「美味しい……」
「りん吾! すごいよ、すっごく美味しいよ!」
放心状態のりん吾に、りんりんは興奮しながら肩を揺さぶります。美味しい美味しいとどんどん食べ進めるりんりんに、りん吾もまた、うんうんと顔をほころばせます。
「りんりんね、いろんな人に、このアップルパイ食べてもらいたい! りん吾も行こう!」
ふたきれ目を自分のお皿にうつしながらりんりんは楽しげです。
「えっ、ど、どこに?」
「いろんなとこ!」
こうしてふたりは仲良しになり、ふたりでりんごとりんご料理を広める旅に出ることにしました。
マイファーストアップルパイ