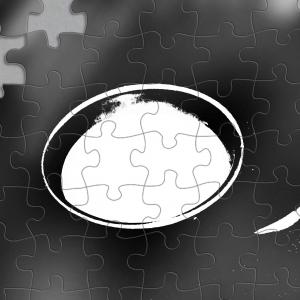「ガーデニング」
ガーネット
月には枝葉が咲いていて、紅い躑躅が実っていた。柘榴をからかうようなしたたりが地上に落とされることも無く、昨日までは白百合だった筈の月の中で渦を巻いて溺れて笑っているのを街の中で見つけてしまった。
天井の空はいつも灰色がかったガス灯の靄の色、雑閙は決まりきった黒の色、蒸気をかぶる鉄橋や明滅ばかりの赤信号、錆びても動く時計の音が幾度も幾度も反響するプラットホームは煙を吸って煙を吐き、酔いどれ男や戯れ女のその場限りの世辞と混ざる。
街は常に飢えている、笑える人間をいつも欲しがり、笑わない者まで笑わせる。笑っては渇くその咽頭に熟れて腐爛した果汁は毎日そそがれ、もう人々は街を出ては暮らせられない肉体へと変質させられているのだが、
いつでもセオリーから外れた存在が生きているのもまあ事実。空を仰いで天体を見つめる行為など、この青年以外し得ないであろう。
青年の与えられた名前はトネリコ。誰が産み落としたのかも分からない素裸の姿で一人きり、トネリコの葉に血塗れの状態で包まれていたから街の人々にそう呼ばれるようになったらしい。
彼の名前のもととなった樹は何處かの神話では大層神聖で立派な意味を持つのだが、生憎この街ではその教養は一つも功を成さないので、まだ引き裂かれた肌着の方に男も女も目を向け涎を垂らすのだ。こんな街で青年がこの齢になるまで生きられたのは所謂奇跡というのに相違ない。
トネリコは声の出せない者であった。その為他人よりも街の空気を吸う量が少なくて済んだ経緯もあったからかは不明だが、青年はまだ酔うには至っていない。
彼は瞬いた。月は白百合だった。紅いきれなど一縷も這ってはいない。枝葉も雫も存在していなかったかのように、真っさらないつもの月が街を見下ろしていた。
トパーズ
歯車、蒸気、鉄屑、結果の喧噪。街の生態を示すには此等四つの言葉で足る、好きなように四つの言葉をくっ付けて落書をすれば良いだけの話だがそれでは万一にも街の汚さが今一つ取り上げられないかもしれない。美しい想像をされない為に、僅かながら街の様相を記しておこう。
街には先ず固有名詞が付与されていない。住民達は育ち暮らす場所の名前も知らされずに、唯街、としか言えないのである。最も街の名前を知りたいと考える者は一人も居ないのだが。
街には蒸気式機関車を有する駅が一つあり、プラットホームは蒸気広場とあだ名されている。列車は煙やら蒸気やらを絶やさずモクモクと吐き、前にも後ろにも左右にもちっとも進まないでいつもその場でエネルギーを噴出させてばかり居る。その呼気には磁石の微粒な破片が細かにサラサラと組み込まれており、大層のどごしが堪らなく心地良いのだとか。
広場には人が集うもの、そうあるべきと街が定めたパズルの穴場に人々は今日ももつれこむ。歌う者もあれば踊る者もあるがその二種類だけ、音楽は酒で爛れた呻きによく似た笑い声、物言わぬ植物が土足で住処に踏み込まれて華麗なステップの下で押し黙りながら絶えているのを分かっているのに知らないで広場は毎日興業喝采で倦むこともせず。灰色がかったガス灯の靄は一人として街から誰も出そうとしない。
けれどトネリコは出たがった。この饐えた粘膜のような街を出て、いつかドブ溝に捨てられていた何處かの神話に描かれた空を見てみたかった。それが美しかろうが醜かろうが些事である。他を知りたい、外を見たい、予期せぬ何かがあったとしても。トネリコは今日も白百合の月を仰ぎ跪き、両手を胸の前で組んで祈る、明日は雨が降るだろう。
アクアマリン
雨が降る日は沈黙の日だ。人々は一言も発さないまま雨止んでまた晴れるまで眠り続ける日だからだ。トネリコは傘を持たずに街へ繰り出す。
(雨はいい、やさしい。勿論優しさばかりではないけれど、それでも。)
青年は多感な時期だった。自分の声がどんな音かは知らないが自分の心の声は知っている。
(何處へ行こう、折角の雨だもの。次いつ来てくれるかは分らない。今日にでも街を出てしまおうかな。)
街から出て行った人は今までに居たの?
誰に教わったでもなしに青年は文字が読めたし書くことも知っていた、筆跡は恰も菖蒲の水茎玲瓏として月へ捧ぐ玉章宛らであるがその一筆はこの齢になるまで一度も返事を聞かなかった、この街で言葉は脆くて役立たず。
(汽車は留まり続けるのが仕事だから、乗って外へ出ることは不可能だろう、けれど此処に車はおろか馬車も無いし自転車も。乗り物に頼らず自分の足だけで離れることは可能なのか?そもそも、出口のような門は設けられているのだろうか。)
駅をぼんやり眺めてみると、黒々とした体躯は水に洗われ煙草のヤニやら引っ搔かれ傷やら吐瀉物やらは見る影も無く溶かされて、水底にかつて沈んだ古代の遺跡の声でも聞いたのだろうか艶々とした冷たい鉄が白霧の中で深く息を吐いた。
(列車は本当に留まり続けるのが仕事なのかな。)
誰も教えてはくれなかったけれど知ってる俗説に疑いを持つと、蒸気が再度ふかされる。
(君も若しかして街を出たいんじゃない?)
そう思った途端列車は呼吸を止めてしまった、点くかと感じたライトもふっつり。
雨はまだ降り止まない。
トネリコは街の端をぐるりと周れば門や扉などがあるのではないかと考え、中心部である駅から離れ街を囲う塀に向かい歩き始めた。黒い金魚鉢を逆さまにした世界で動くものは唯一人きり、雨の雫に色は無いと破れた本には書かれていたが景色は深い青を慕う。この時だけは、此処は本当に昔泉に沈んだ太古の街跡かなにかではないかしらと常々錯覚するも、それは汚された本にあった御伽のはなし、心を慰めるための物語で。
(外の世界は本の中のような場所なのかな、それとも街よりもっと酷いのかな。)
塀へは覚悟していたより案外すぐに辿り着けた。硝子板は日々の乱痴気騒ぎにも関わらず擦り傷一つ付けられていない、青年はまっさらだが向うを透かさない玻璃に指先をふれた。
セレナイト
月が白い。淡雪のつめたい花弁がほっそりとしなって瞳に溜まった露を落とす、落とした上からまた一つ、また一つとほろほろ糸は散りかかる。
雨月の花の真下にて空を仰ぐ身のトネリコは、濡れる地面に背中を預けて紫陽花の園の中で目を覚ました、此処は街ではない。
恥じらふうすくれなゐの頬を染めた乙女の血で育まれたであろう紅色の鱗は縁取りも目覚ましく空を仰ぐ光の瞳。交じる好奇と憂愁は紫淡い微笑みの鳥毛を打襲ねてふっくらと照らされる閨の内。恋い焦がるる泉の深い藍を忘れられず空に染めた青い羽は自らを花であることも捨てて蜜を吸う。年中開けぬ瞼をこの時ばかりの雨糸を頼りに瞬かせる紫陽花の場所、トネリコが寝転がって居たのは正しく其処であった。
(花しかない。人も、建物も、何も…)
噤んだ口ではおーいと誰かへ呼び掛けることも出来ない。
(此処が、外?此処は街の中ではないのかな。)
上半身だけ起き上り見回してみても、街の影は一つも見当たらない、だけでない。紫陽花達が見上ぐる空を見てみれば、白い月と向い合う形で紅い躑躅が果実を垂らす。
(あ!)
驚いたら、もう居ない。やはり街で仰いだのと寸分違わぬ見慣れた月、けれどあの紅は
(まさか、此処は街?)
自分は街の外に出たのではなく、街の内側に居るだけではないかと彼は考えた訳で。それならば一瞬だけ咲いた天体も振り続ける雨にも理由が付くが、理屈が納得しない。
(街にはまだ自分の見たことの無い場所があったのか?でも此処は、植物が主人公のようなこんな穏やかな場所、一片とて落ちてはいなかった筈。あれば忽ちあの硫黄がさらに腐ったような磁石片の餌食とされていただろうに。)
「此処は街だよ。」
後ろから声がした。振り向くと一人の娘が立っている。彼女のワンピースは月から恵まれた色をしており、ふわりとした裾と袖には暗緑の唐草が慎ましく縋る。絹が包む身体はほっそりと紫陽花に雲隠れしそうで心許無いが両眼は眦長く大きな黒目を認めたがらない鋭さを残月に曝していて、トネリコは少したじろいだ。眼光の威に退るばかりでなく、もう片方の瞳に見つめられていると感じたからで…娘の片一方の目はザクロが実っていた。
(君は誰?)
トネリコはこの時自分の声が欲しいと心底祈った。
「…喋られないのか。」
娘は青年の心中を察することは出来ないようで、自身の伝えたいことを話し始める。
「私はこの場所の住民、住み込みで此処を守る役目を成す者。守ると言うのは、一本足りとも外に花が連れて行かれないように見張り、動くことだ。普段は人間が来ることの無い位置にあるけれど、時折お前のような人間らしからぬ人間が迷いこむ。それを元居た所へ帰すのも私の仕事だ、だからお前を家に戻してやる。
娘の最後の言葉を聞きトネリコは慌てて首を横に振った、戻るだなんてとんでもない。
(折角あの場所以外の場所に来られたのに、また同じ所に行くなんて!)
「捨てられた小動物のようだな。」
娘はトネリコの必死さにクスリと笑い目を細めた。其処に先刻までの棘は無く、可憐な乙女だけが綻んでいる。
「戻りたくなさそうだが、生憎此処に置いてやることは出来ないんだ。だから他の場所に送ってやろう。」
パチリと指を鳴らしながら、もう一方の手を緩やかに振っていた。
モリオン
一歩一歩を踏みしめる、土に体重を刻みつける、乱れた隊列と嘲られぬように、隙を与えてしまわぬように、足下の土を踏みつけ高らかに歩兵は進むのか。
この場所には一本の樹があった。トネリコは紫陽花の園で娘に別れを告げられた後、この柊の木にひっかかった状態で地面を行く軍の行進を眺めていた。
(どの人も帽子を深く被っているからどんな表情をしているかは分らないな。この人達は誰もが寸分違わないで歩いているけれど何處へ向っているのだろう。)
見回しても建物らしき物体は無く柊以外の植物も生えていない。あるのは果てのない反物みたく続く行軍と赤茶化た地面だけで、人間も空も黙っている。
(声を出すことも出来ないし、柊の葉を搖らして音を鳴らしたら何方か気がついてくれるだろうか。)
持ち前の好奇心で葉を摺ろうとしてみたら、
「どんな音を立てても軍は止まらないよ、やめときな。」
大きな羽の生えた青年に呼び止められた。青年の顔にはお札が一枚貼られており、手足はすっぽりと大きく厚めのオーバーコートに包まれていた、そして背中には湖面に映った三日月のような黄色い羽。
「驚いた表情をしてどうしたんだ?まさか翼を持つ者と喋るのは初めて?ならまあ、仕方ないか。」
空気をゆったり羽が打つ、その波紋は地面には届かず制帽の辺りで吸われている。
「地面をよく見て御覧。」
呼吸の恩恵を受けられない存在は音を響かせることも叶わず、呻く。或日急に足場が消滅して突き落とされた瞬間の顔、その顔が幾つも幾つも連なっており、額らしき位置にはアルファベットと数字を大小組み合わせられた番号がちらついていた。
「此処もまた、街なんだ。君、声は出せないようだけど筆談は出来るかい?何も知らずに来てしまったみたいだから、君が良ければ質問に答えてあげたいんだけれど。」
トネリコは紙とペンを服から取り出すと、早速青年への問いを書き始めた。
「自分が居た場所は街と呼ばれている場所だったけれど、街の中にはこんな所はなかったんだ。街を出たくて端まで歩いて、硝子に手を触れたら見知らぬ場所で目が覚めた。其処は紫陽花の園だったみたいで、女性が一人居た。その人はその場所が街だと教えてくれた。でも、街には花が薫る場所なんて隙間ほども無かったのに。あと、月が紅くて、」
伝えたいことが鳴り止まない。まとまりのない内容を次へ次へと話していくが、青年は途中で遮ることはしなかった。
「でも瞬きをしたらすぐに元通りの白い月なんだ。どうして紅い躑躅が見えたんだろう、あの街だからそう見えたのかな。」
「君は街の全体像を知らないんだね。」
トネリコが手に疲れを感じてしばらく立ち止まった時、羽の青年はようやく口を開いた。
「全体像?」
「そう。それが分かったら、君の疑問はきっと解ける筈だよ。」
「如何したら分かるの?」
「他の街にも行ってみたらいい。まだまだ頭の中がごちゃごちゃで靄の内に立っているように感じるかもしれないけれど、それは決して間違いや過ちではないから安心してね。」
そして彼は手を振った。
コーラル
海は書物を記さない。身の内に昔々の遺跡を抱えていても、それが何であるのか、誰が住まっていたのか、何故自分の腕に抱えたのかを海は文字に起こさない。それはきっと、海が命をもらってから今日未来に到る迄、海は何一つとして物事や生命の存在した記憶を忘れないから、忘れられないからで、そして文字の代りに話す言葉や浮べる表情が人間の耳や目に聞えない見えないからで。
だからいつも海は沈黙と呼ばれている。海は黙って何をも語り得ず、ただ其処に居るだけなのだというイメージが大いなるものへと昇華されてしまったのだ。海はいつも孤独であった。
人間が望む記憶や答えを一つ漏らさず身の内にしまってあるのに、それを語れども唄えども伝わらない。やきもきして行動に移そうとすればそれは天災となって生物の命を奪うばかり、雫がまた増えて、腕の中にしまわれてゆく。海には思いの丈を伝える手段が生来与えられていなかったのだ。
この搖れる哀しみをどうすればいい?押しやっても押しやっても戻って来るこの嘆きをどうすればいい?恵まれたものである筈の海は日に日に塞ぎ込むようになり、海の生き物達は皆残らず海の心配をしていたが、人々は一向に凪にならない海を怒り狂っているのだと恐れ、鎮める為にと祭礼を挙げ、供物として珊瑚の王冠を捧げ納めた。
海にはそれが、とても嬉しかったのだ。片思いの恋人からの贈り物は、いつだって初心な心をときめかせるもの、生涯捨てぬ初恋はこの時初めて伝わったのだと海は微笑み凪が訪れた。
(これは海が人を恋した世界なのか。)
トネリコは海中の遺跡に交じっていた空の水槽の中から外海を眺めていた。水槽は見馴れない硝子製だったが伽藍と内は広く、一見して建物に見てとれる物だった。
(この場所は海に沈んだものなのかな、それとも海中で暮しをしていたのかな。)
壁にはかつて祈りのシンボルでも描かれていたであろうかすり傷の跡が生々しい。
(此処も喧噪の街の地層なんだろう。もはや土でもないけれど。)
彼は生物の一匹も居ない冴えた海中で乙女の言葉を反芻した。
(自分の目に見えていないだけ、か。)
生者には実体があり、死者には実体が無いとどの本でもよく雄弁に語られていたが、あの紫陽花の花々や柊の枝々が死したものとは感じなかった。
(実体の無い生者、実体のある死者。)
緩く重くなる瞼を閉じ、湧水のように考えた。
(喧噪の街も、もしかしたら誰かの地層なのかもしれない。でもその誰かって何だろう。)
潜るばかりの旅は、何處へ連れて行く気だろう。たった一粒の時間の中で。
アメジスト
空には月が重なっていた。見馴れた雪の色と、見馴れない紺絣、濃ゆい雪の色でそれぞれに染められた三日月二人の横がほは睦みキスをする心中者同士の最後の微笑によく似ている。
(今の月は紅く実らないのかな)
トネリコは葡萄の蔦に包まれていた、と言うのも蔦が真珠貝の形を組んだ所に枝葉が結綿を敷き詰めるように籠められている、その場所に座っていたからなのだ。
(月は白いものだと信じていた)
毎日祈りを捧げてきて白百合だとばかり信じていた丸い天体は、地層が違えば他の面を輝かす多面体の姿をしていた。月も原石の一つだったとトネリコは街に潜って初めて気づいたが、どの本にもそのような記述はされていなかったので無理もない話である。
「迷子だね?」
今度はどのような人だろうと声の方角を振り向くと、何も居ない。
「わたしの姿が見えないだろう?」
トネリコは頷いた。
(そう言えば前に、可愛い物語を読んだことがある。姿を見せたり消したり出来る猫、いつもニタニタ笑っている猫。)
ぬるりとそれは姿を現す、
「今猫を想像したね?御覧、私の姿が目視出来るだろう。」
大きな猫。トネリコの背丈の三倍の大きさで太陽のような黄金の眼玉は鋭く燃えており、黒と白の斑模様がペティナイフ身体全身を覆う。ケタリと笑う口元は吹雪を起こす準備でもあるかカチカチと磨がれて涎を待っていた。
「物騒なことを考えたろう?大丈夫取って喰ったりなんてしないからね、イメージしてみなさい。なんだっていい、君が可愛らしい、怖くないと思うものを思うんだ。」
あのお話にはトランプの女王サマが登場したっけ
「ほうら、もうこれで怖くないだろう?」
トネリコの座る膝元にはふっくらとした鳩によく似たトランプカードが一枚ぽつん。
「此処も、街ですか?」
書かれた文字をためつすがめつ見た後、カードは答えた。
「どう思う?」
質問に質問で返すのは、と少々納得がいかないが。
「街だと思います。」
「そうかい?じゃあそうなのだろうね。」
カードはぽん、と狸になった。
「失礼なことを思ったな?」
狸は水色の蜜蜂になった。
「中々センスが良いじゃないの?」
四回繰り返したら流石に掴めて来るのかもしれなくて
「あなたは、実体が無いのですか?」
「実体かい?何を以て実体とするのかは知らないが、まあ多分不正解として突き放すには惜しい解答だね。もっと正確に言うならば、決まった姿が無いんだよ、わたしにはね。」
「どんな姿にでもなれるのですか?」
「先刻見たろう?こわぁい猫にも可愛らしい女王陛下にも動物だろうが昆虫だろうが色味だってオーダーメイド、お手のものさ。」
青年は瞳を輝かせた。でもそれと同時に
「此処はきっと君の思っているような場所じゃないぜ。」
軽やかだった羽音がパタリと止めて、蜜蜂は空の月二つを見やる。
来た時と変らぬ二つの星、見馴れた雪と見馴れない雪。
「此処は迷子には優しくない場所なんだ。だから早く帰りなさい。」
紅蓮荒波混ざった澤山の手が一瞬だけ見えたのは
オパール
頬を掠めた冷たさが、なかなか治まらない痛い鼓動を伝い太い息を青年に吐かせている。月、月はともがく目に、肌馴染んだ白百合がそっと触れた。
(帰って来た?)
縮こませ強張っていた手足を徐ろに伸ばし、背筋をほっと緩めて周りを見れば、雨が降っている喧噪の街。雫を被る機関車の横に青年は横たわる。
(君もきっとそうだったんだね。)
疲れきった身体をそのまゝに、青年はその日初めて家の外で眠りについた。
明日には雨も上がるだろう、人々も目を覚ますのだろう、そして無意識に重ねていくのだ、いつか若芽がめぶくまで。
終幕
「ガーデニング」