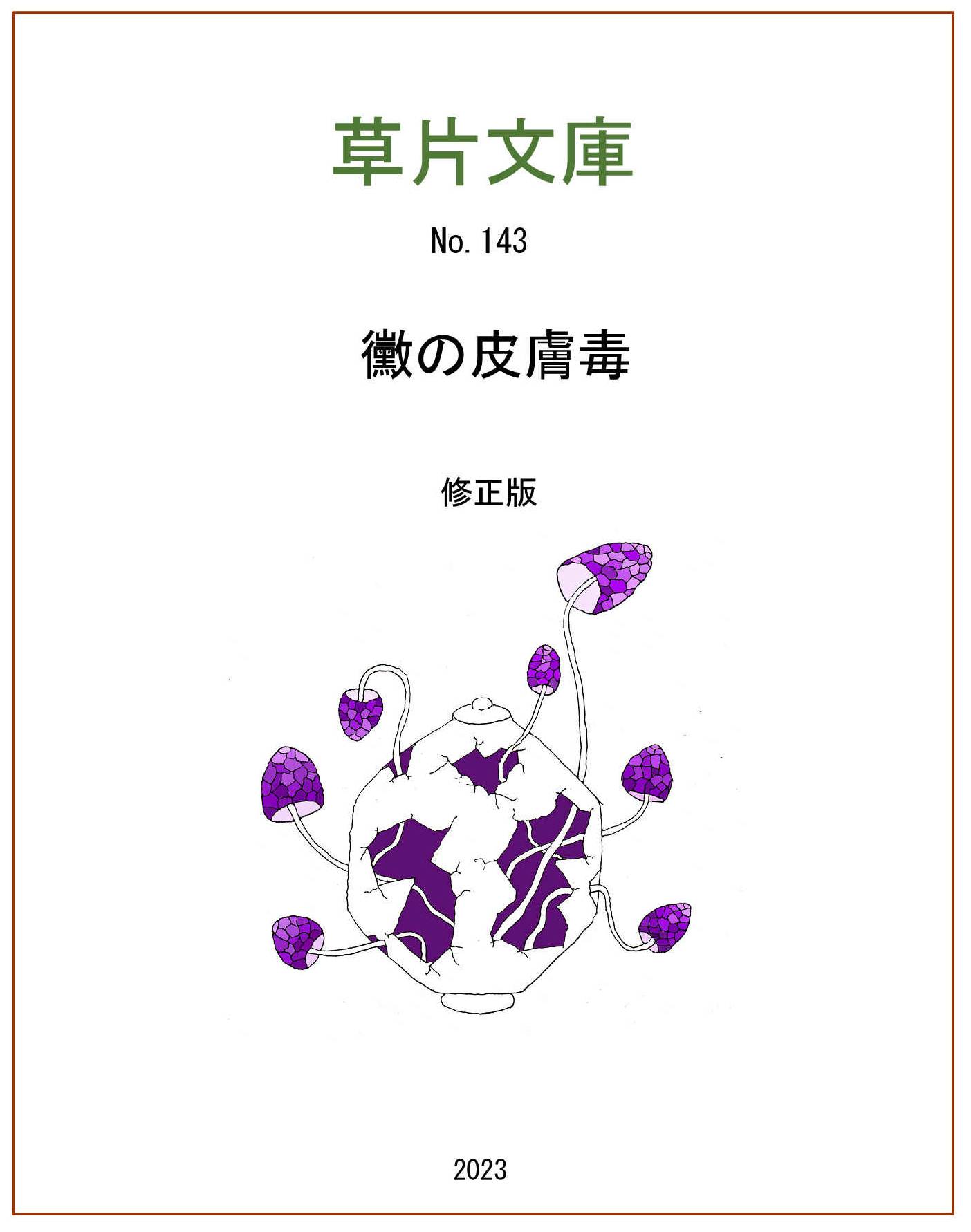
黴の皮膚毒
探偵小説です。
警視庁刑事課調査支援分析センター分室、第八研究室のスタッフが集まって、定例のミーティングを行っている。といっても、いつものように、誰が議事進行役なのかわからないほどいいかげんな、よくいうと、自由にまとまった会議である。本来、室長であり警視正というれっきとした肩書きを持っている薩摩冬児が取り仕切るところなのだが、椅子にふんぞり返って、目をつぶっている。ただ寝てしまっているわけではなさそうだ。
第八研究室には、過去の奇妙な犯罪や出来事のファイルがあつまっており、今起きているおかしな事件も時々刻々とはいってくる。彼らはその豊富な資料と、それぞれのもつ興味と能力をもとに、事件の担当者にアドバイスしたり、場合によっては中心となって、事件を解決に導く、そんな役割を持つ部署である。
書籍、特に日本の古文書について、その世界で一目おかれている人物でもある、古書羊貴(ふるほんようき)が、「奇妙な死体という江戸の冊子にはね、変な死体を見たという人の話がたくさんでていておもしろいよ」と手にある和とじ本をみなに見せている。
「どんなの」
すぐに興味を持つのが、化学博士の称号をもつ吉都希紅子である。
「二本の腕が足のところに生え、腕のところに足がある死体が土手に転がっていたとか、額にもう一つ眼がある死体を山の中で見たとか、朽ちた家の中にカビの生えた女が転がっていたとかね」
そのとき、寝ているのかと思われた室長の薩摩が目を開けて、
「なんだい、そのカビの生えた女ってのは、死んでいないのかい」と口をはさんだ。きちんと聞いていたようだ。
「その本には、梅雨時に山を越えたとなり町に使いにいくため、竹林の脇を歩いていた男が、もう人の住んでいないと思われた崩れ落ちそうな家の前を通ったとき、家の中から苦しそうなうめき声が聞こえたので、開いていた入り口から土間に入ると、すり切れた畳の上に敷かれた、薄い布団の上に裸の若い女が息絶え絶えで、しぼりだすように声をもらしていたとあります、生きている女です、ただ、全身に白いカビが生え、すえた匂いが女から漂い、近寄るのはとてもできず、もうすぐ息が絶えそうにも思え、手を合わせて、早々に立ち去ったとあります」
「人間にかびが生えるのかね」
薩摩の疑問に、フランス文学を学び、看護師の資格をもっている、高胎蓉子が「水虫だってカビの仲間ですよ」と答えた。
「それじゃ人に生えても不思議はねえか、白カビっていやあ、チーズだ、人間がチーズになるのか」
薩摩のめちゃめちゃな発想にみんな笑って終わりかと思ったら、宙夜が
「女の失踪事件がたくさんあるけど、そのなかで、なんだかカビ臭いのがいくつかありますね」と言った。宙夜は地学のプロで、宝石の結晶の研究をやっていた物理屋でもある。
「なんだそのカビ臭いというのは」
「少し前に失踪届がだされたという女のことですけど、チーズケーキ屋をしていたということです」とファイルをみなの前に置いた。
「何だ、チーズだからカビか、まったく」
室長の薩摩がほらみろカビはチーズだという顔をした。
それからがこの研究室のめんめんの底じからだ。関係がないと思われるところをつなげていく。
「鎌倉の小さなケーキ屋の奥さんで、年は35です、名前は岩谷美恵」
宙夜が画面に女性を映し出した。
「きれいな人ね、化粧をほとんどしていないようだけど、肌のきめが細かくて、粉をふいているように白いわね」
画面を拡大した。確かに、絹が粉になったような肌だ。
「主人が急にいなくなったと、警察に届けてきていて、もう一月になります。このケーキ屋は開店して5年です」
「5年というと、定着したほうね、きっとおいしいのよ、若い人がしゃれたパン屋や、趣味の店を鎌倉でだしたいのよ、続かせるのは難しいでしょうけど」
「そうですね、主人の水谷康平がIT関係の会社をやめて始めたようです、大手のIT企業で若くしてサブリーダーになっていましたが、副業を推奨していたこともあり、趣味で奥さんと一緒に菓子づくりの専門学校にかよい、高じて鎌倉で開業したそうです」
「それじゃ、東京の人」
「鎌倉に行く前は、月島のマンションに住んでいましたが、いなくなった奥さんは秋田の人で、主人は土佐の出身です」
「ほかに失踪した女性で同じようなのがあるの」
「毎年、7ー8万の人が行方不明になり、以外と男性が女性の倍までは行かないまでも多い、男性は金銭が絡むことが多いけど、女性は性のことが多い。年齢別に見ると、老人、特に認知症煩っている人が多くなっていますけど、小学生の子供がなんと年間1000人近くです、中学高校の思春期の子も多いですね、学業問題や家庭の問題によるものですが、年が上になると、痴情のもつれと、まあ、駆け落ちならいいのですが、殺人事件に巻き込まれることもあります、ところが、全く理由が見つからない失踪事件に絞ると、そんなに多くはない、本人とは関係ない事件に巻き込まれてしまったと考えられか、完全犯罪をねらったものかなどになるわけです」
「宗教は関係あるでしょう」
「そうですね、地方の小さな宗教にはいり、みつからなくなるということもあるようですけど、そういったばあい、それまでの本人の言動なりを解析すると、わかるものですが、たとえば、このチーズケーキ屋の奥さんは、ご主人、友人、知人、もちろん両親兄弟の話を聞いても、病気、宗教、社会的なもの、異性関係などすべて除外できるケースなのです、考えられるのは本人にとっても、周りにとっても、全く思いつかないような出来事が関係してくることが多いと思います」
「それで、そのケーキ屋さんの女性はどうなったの」
「鎌倉の警察の方で努力しているようですが、手がかりはなにもないようです」
「宙夜君、そこまで調べたということは、興味があんだろう」
室長のどら声に、「はあ、まあ」と彼は答えた。
「調べてみたらいい、なにかでてくるかもしれんよ、鎌倉の警察に行って手伝うかい」
「そりゃいいですけど」
結局、その件は宙夜の仕事になった。スタッフ全員で、過去十年で解明できなかった女性の行方不明事件を洗い出すことに着手した。
宙夜は鎌倉にでかけ警察で詳しく話を聞いた。チーズ屋の主人と失踪した奥さんの関係はとてもよく、女性は明るい人でメンタルにどうのこうのといった問題はない。店をよくしようと張り切っていたそうで、近所の人たちへの聞き込みでも、自分からどこかにいってしまうようなことは考えられないという。担当の刑事の天野は、鎌倉のそういった店は有名な寺の近くにあることが多く、観光客がふらっとよってくれることを期待しているので、日本中から老若男女が店をおとずれることもあり、そういった中に誘拐犯人がいるとすると、洗い出すのは大変だという話だった。
「それで、いなくなったのに気がついたのはいつごろなのですか」
「午後の3時ごろだそうです、チーズケーキは仕込などは別として、朝5時頃からつくりはじめて、8時頃にはできているそうで、奥さんも一緒にやるそうです、そのあと、自分たちの朝食をとり、十時の開店の準備は奥さんがやっているそうです、その日、ご主人はアレルギー症状のため、午後二時に市内の病院にいっています。戻ったら奥さんの姿がたがなく、店が開いたままだったそうです。ちょっとどこかにいったのだろうと、待っていても帰ってこないのでおかしいと、行きそうな近くの家に電話で聞いたが、どこもきていないということで、すぐに警察に電話をしたということでした。急用で出かけるにしても、店の鍵はかけるだろうし、書き置きもするだろうと言っていました」
「店は荒らされていなかったのですね」
宙夜は状況についてすでにファイルを読んでいたが改めて聞いた。
「レジの金も盗まれていなかったし、全く変わりがなかったということです」
「ケーキもそのままですか」
「主人のいうには、ケーキが2ピース売れていたようです、ケーキの小さな箱が一つなかったそうです」
「客は一人だったわけですね」
「はい、もし誘拐だとして、その客も犯人候補から除外できません、買ったあとに、ほかに誰もいないとわかって、車に押し込んで連れ去ったということも十分考えられます、きれいな人ですから」
宙夜もきれいな人というところが気になっていた。ただのきれいではなく、あの真珠の粉を吹きかけたような白い頬だ。第八研究室のスタッフは、毎日事件に関わっている人間の顔を何十人とPCの画面に映し出している。それは犯人の可能性のある人間だったり、被害者の人間だったりする。宙夜も今までたくさん女性の写真を見たが、肌の美白で頭に残った女性である。
「どうして調査室が動きだしたのでしょう、何か特異的なことがありましたか」
まだ若い天野刑事が宙夜にたずねた。
「いえ、この女性の履歴、主人の履歴、家族たちの状況も全く問題ないのです、そのような女性がいなくなったということは、特殊な組織が動いた犯罪か、個人的な一方的な情の絡んだ犯罪か、ということになりそうで、個人的なものであれば、どこかにほころびがありますから、いずれ解決につながる何かが見つかると思いますが、特殊な組織ですと、隠そうと細かく立ち回るでしょうから、暴くのは難しい、それに一回だけの犯行でおわらず、目的を果たすまで、何度も続ける可能性があります。そういったことから、うちの研究室で、検討した結果、お手伝いをすると決まったわけです、違うところで同じような事件をおこす可能性がありますから」
「そういった例があるのですか」
天野刑事はなかなかするどい。
「そうですね、海外に女性が売られる事件がありました。同じ傾向の顔かたちをした、また年齢も同じくらい、そういった十代の女性をアジアのある国の組織がねらって、日本の犯罪組織に依頼したものでした」
「その女性たちはどうなったんですか」
「アジアの国の裏組織で働かされていました、ちょっと悲惨な状態でしたが、事件は解決して、みな日本に戻りました、我々の研究室の情報解析が一助になりました」
「そうなんですか、今度はもう三十を過ぎた女性ですから、目的はなんでしょうね」
「わかりませんが、いきなり消えてしまった女性はたくさんいます、鎌倉の事件の詳細を把握した上で、過去または今失踪している女性のことを調べ直すつもりです、それによって、鎌倉の女性の件も見えてきますし、もし組織的な犯罪なら、組織の顔も見えるようになります」
「なるほど、その通りですね」
「僕はまず、観光客のような格好で、店をおとずれてみたいのですが、きっと、ご主人は一人で店を開けていらっしゃるでしょう」
「よくおわかりになりましたね」
「大事な奥さんがいなくなったのだから、たいそう心配でしょう、仕事をやって気を紛らわせることでもしないと、つらいと思います」
「おっしゃる通りで、ご主人は三日ほど店をあけなかったのですが、今は一生けんめいチーズケーキ作りにはげんでいますよ、痛ましい感じだ」
宙夜は鎌倉警察の宿泊室に三日の予約をした。
明くる日、宙夜はいつもとは違う出立ちになった。ジーンズをはき、伊達メガネをかけて、北鎌倉の駅をおりた。名月院に行く道をいくと、かなり手前で左に折れる道があり、その道沿いに店があるはずだ。角までくると赤い矢印の看板があり、琴屋、ケーキとある。道の反対側にも同じ看板が立っている。名月院にいく人、帰る人へのアピールだ。手書きのようだ。
宙夜が左に曲がると、すぐのところに南京下見の薄青色に塗られた小さな店が見えた。けばけばしさのない、大正色の家だ。9時開店なので、もう開いているだろう。入り口は自動ドアではなく、ガラスの引き戸である。駄菓子屋の雰囲気もある。外から見るとガラスケースの中にいくつかのケーキが見える。白いチョコレートが被してある四角い長いケーキがこの店でよく知られているもののようだ。同じデコレーションで丸いものがある。基本的にはその二つで、あとはそれを切ったものがおいてある。
宙夜が戸を開けると、戸の内側についている小さな鈴がなった。中に入ると同時に、中肉中背の男が、伏せ眼がちに宙夜を見て、いらっしゃいませと口にした。やはりどこか元気がないのと、ただ客を見るだけの目つきではない、おそらく奥さんの失踪に関係がないかという探りの眼なのだろう。
「名月院にいくんだけど、看板見たら、うまそうだと思ったから来てみたんだ、朝飯食わなかったから、ここじゃ食えないの」
主人は観光客かと気をゆるめたようだ。
「いいですよ、そのテーブルでどうぞ」
小さな丸テーブルに、椅子が二つおいてある。奥さんがいれば花瓶に花をさして店を明るくしているのだろう。
「ブレンドのコーヒーしかないのですけど、お出しはできます」
「あ、それいいね、ケーキはこれ」
宙夜は丸いホールケーキを切った、三角のものを指さした、750円とある。決して高くはない。
「かわいい家だったんで、すぐわかったよ、いい青色だね」
主人はそれを聞くと少し顔がほころんだ。
「近くに澁澤龍彦の家があるんですよ、南京下見のいい家で、まねをしたのです」
そう言いながら主人は、コーヒーの用意をしている。
「澁澤って渋沢栄一」
宙夜は仲間の古書(ふるほん)が澁澤のマニアで、北鎌倉に家があると、雑誌を見せてくれたことがあり、本は何冊か読んだことがあるので知っていた。だが話を続けるために知らないふりをした。
「いえ、フランス文学者で、もうなくなっているのですけど、マニアの方がたくさんいます」
「お宅もそのマニア?」
「澁澤の小説は読みました、おもしろかったのですけど、僕はマニアじゃありません、家内が好きですので」
ショーウインドウからケーキを皿の上にのせ、テーブルの方へ持ってきた。
「おすわりください、珈琲はすぐできますから」
「鎌倉は始めてでね、昨日は鎌倉駅の近くを歩いたんだが、人が多い、通天閣通りみたいだ」
「大阪からいらしったのですか」
「うん、友達んちに泊まって、鎌倉見物」
「お友達といっしょじゃないのですか」
「あいつは働いているから、夜だけつきあってくれてんだ」
コーヒーが運ばれてきた。宙夜はすでにケーキを口に運んでいる。
「うまい、さすがだねえ、それで、何で琴屋っていうの、ずいぶん古い名前じゃん、鎌倉歩くとさ、小さなケーキやパン屋、手作りのものの店がたくさんあるね、でもみんなカタカナの名前でさ、琴屋っていうのはなんだか、京都みてえだよな」
主人は笑顔になった。
「ええ、鎌倉も古都ですからね、家内がお琴をやっていたこともあって、古都から琴にしたわけです」
「へー、しゃれてるね、これうまい、もう一つもらおうかな」
「ありがとうございます、コーヒーよかったらおかわりいれます」
「コーヒー、なんぼ、値段書いたのないからさ」
「300円です、二杯めはサービスします」
「やすいね、客たくさん来たときどうするの、テーブル一つじゃん」
「いつもは店の前にテーブルをいくつかだします、家内がしています」
「奥さんがやっているんだ、きょうはいないの」
彼の顔が一瞬曇った。
「ちょっと具合が悪くて」
宙夜は主人が本当になにも知らないようだと確信した。やはり、奥さんの関係をあたるか、それとも全く行きずり事件か。
「チーズケーキはあんたが作ってんの」
「そうです、修行しました」
「むずかしいんでしょ」
「いいチーズを選ぶのが一番大事なんです」
「どうやってチーズ探したの」
「作っているところを回って、食べてみて、これがいいというものでチーズケーキ作ってみて、という具合に繰り返して、みつけたものです」
「へー、大変だ、どこのチーズを使ってるの、北海道」
「いえ、土佐のチーズ屋さんです」
「土佐、あの酒好きの殿さんがいた、山内蓉堂だよな、あそこの酔鯨って酒飲んだけど、あまいよね、うまいけど、チーズもできるんだ、どこでも買えるの」
「大阪はしりませんが、東京には出していないようです、あまりたくさん作っていないし、ただ、日本酒もつくっていて、それは全国で売ってます」
「なんて酒」
「私は日本酒を飲まないのですけど、おもしろい名前です、風渦、かぜうず、です、何でも、室戸台風からつけたようです」
「探して飲んでみよう」
「お酒がお好きですか」
「うん、なんでも、さて、うまかった、おいくら」
「千八百えんです」
「帰りにまたよるよ、あいつに買ってやろう」
「おまちしています」
宙夜は店をでて、名月院にはいかずに、北鎌倉の駅に戻った。駅の反対側の道をちょっと歩くと、小さなはんこ屋にはいった。
古書から、北鎌倉の駅の近くに、おもしろいはんこ屋があって、主人ははんこを彫る傍ら、地元のラジオのパーソナリティーをやっているということを聞いた。
宙夜は石の結晶の研究をしてきた人間で、石のことは詳しい。その知識をもとに事件を解決に導いたこともある。個人的にも石が好きで、はんこ屋においてある石を見たかったし、自分の印を作るのも悪くないと思ったからだ。
小さな店内には印の材料になる石が棚においてあった。
「いらっしゃい」
作業をしていた主人、お兄ちゃんといった方がいい男が、宙夜に声をかけた。
「なにつくりたいの、遊びのはんこ楽しいよ」
宙夜もそれをきいて、それもそうだと思って、「うん」と答えた。
棚の上にあるくすんだ緑の中に赤い部分のある、特異的な四角柱の石が目に留まった。篆刻に使う石は掘りやすい、ちょっと柔らかな性質をもっていて、いろいろなところから掘り出され、名前がつけられている。そのへんは石の専門家である宙夜もよくは知らない。
「そいつは、鶏血石だよ、田黄石と芙蓉石と印材三宝といって、名のしれた石だよ、もっと赤いのが多いと高いけど、そいつは一部だから安いよ、でもいい景色だからお買い得だよ」
言葉は現代のお兄ちゃんだが、眼が鋭い光をもっている。宙夜を値踏みしているようだ。
「中国の昌化とモンゴルしかでない石だよ、石英と粘土、それに辰砂の赤」
そういわれると宙夜にもわかる。
「硫化水銀か」と思わずつぶやくと、聞こえたと見えて、はんこ屋の主人が、「お、詳しいね」と手を止めて、あらためて宙夜を見た。
宙夜はそれに関してはなにもいわず、「これでつくってもらおうかな、楕円のある」と返した。
「いいのがあるよ、なに彫るの」
「名前」
「だけど、確か高かったな」
主人はすわったまま、脇においてある、引き出しから、箱に入った石を取り出した。
濃い黒がかった赤がほとんどの楕円の石だ。
「これ、珍しいんで、五万するんだよ」
宙夜が驚いた様子を見せないのに驚いて、主人は無言で差し出した宙夜の手に石をのせた。
宙夜は指で摘まんでみて、「これもらう」と返したので、また主人はびっくりした。
「名前彫るの」
宙夜がうなずくと、これにかいてと、ボールペンと紙をよこした。宙夜が書いて渡すと、「大きな名前だこと、これ名字、名、どっち」と宙夜を見た。
「名字」
財布から五万円引き出すと、
「あ、できてからもらうことにしてるの、取りにくるならそのときでいいし、振り込み先を書いた請求書と一緒に送るから、それでもいいよ」
なかなか良心的である。
「珍しい名字だ、始めてだな、申込書かいてくれるかな、送った方がいいのかな、一月ぐらいかかるけど」と用紙をくれた。
「今ね、名月院にいく途中の琴屋でチーズケーキ食べてきたけど、うまかった、あそこの主人どこで修行したのかな」
宙夜がきりだすと、
「あそこうまいでしょ、どこで修行したのか聞いたけど忘れえたな、でもこだわってるから、チーズが違うね」
「主人一人でやってるのかな、珈琲もうまかった」
「奥さんいなかったの、奥さんがいつもコーヒーいれてるよ、いい奥さんでね、おれなんかがいくと、ケーキの失敗したのもおまけで食わしてくれる、主人もいい人だよ、なかいいよな、うらやましい限りだよ」
「よくいくんだ」
「うん、うちのもよく行くよ、色の白い人でね、コーヒーカップを差しだした手を見るとさ、粉が吹き出してるようにさらさらしているんだ、ほら、桃の薄い皮の表面みたいでさ、俺なんて固い石さわってっから、ああいう手なんか触りたいなんておもうくらいだよ」
悪い話はなさそうだ。
「さわったんじゃない」
「と、とんでもない、うちのやつの友達だからさ、それに、そういった感じの奥さんじゃなくてね」
このはんこ屋もしゃべりは砕けているが、きまじめな人間のようだ。勘が良さそうだから、あまり深く聞いて変に思われたらまずい。
「それじゃ、できたら電話くれれば取りにくるから、よろしく」
「はい、いいはんこ作るから、ありがとうございました」
宙夜ははんこ屋をでると、ケーキ屋にむかった。事件を解決するには鎌倉でケーキ屋の周りをかぎ回っても、なにもでない。行き釣りの犯行ならば、当時の観光客のことなどは天野刑事が調べているだろうから、それに任せておいた方が良さそうだ。警視庁に戻ることにした。
「あ、本当に来てくれたんですね」
琴屋にいくと、主人がうれしそうな顔になった。
「うん、ホールの長いのと、丸いのちょうだい、友達にやるんだ」
「両方ですか、ありがとうございます」
主人は二つの手提げ袋にそれぞれをいれて、宙夜にわたした。
宙夜はケーキを受け取ると、
「名月院もよかったよ、ケーキもうまかったし、鎌倉はいいね」
「またきてください」
「うん」
宙夜は店の外にまで出てきた主人に見送られて、駅に向かった。駅の反対側にでると、待っていたタクシーにのり、鎌倉署にむかった。ちょっと大阪弁はうまくなかったなと反省している。
「え、ケーキいただいていいんですか」
天野刑事がうれしそうに紙袋を受け取った。
「それで、これから警視庁にもどります、すみませんが、宿泊室の予定キャンセルしてください」
「何かわかったんですか」
「いえ、ケーキ屋さんの周りを調べてもなにもでそうもないので、むしろ、研究室にもどって、同様の事件がないか詳しく洗ってみます」
「そうですか、私もあの主人と話していて、行きずりの事件だと思いました、それで、昨日お話ししたとおり、奥さんがいなくなった頃のあのあたりに止まっていた車や、おかしな挙動をしていた人物などの聞き込み調査をしているところです、全く手がかりはありませんが」
「それが重要なところかもしれません、大変だと思いますが、もし何かわかったら、連絡いただきたいと思います、こちらの方でも何かわかったら連絡します」
「はい、よろしくお願いします」
「それで、一つ調べていただきたいのですが」
「なんでしょうか」
「奥さんは病気を持っていましたか」
「ご主人が至って元気だったと話していました」
「お子さんはいないのですね、ほしくはなかったのでしょうか」
「そういったデリケートな話はしていないのですが、なにかかかわりがありそうですか」
「いえ、かかりつけの医者に様子を聞いておくのもいいのかと思います、女性の体のことは主人にはあまり相談しないものです、子供がほしいなら、どうしてできないのか、女性として気になるでしょう、どこかの婦人科で受診しているかもしれません」
「あ、そうですね、主人にかかりつけの医者がないかどうか、尋ねてみます、見落としていました、ありがとうございます」
天野刑事は深々とお辞儀をした。
「またきますので」
宙夜はその足で鎌倉駅にむかった。
「なんだ、もう戻ってきたのか、大した事件じゃなかったのか」
室長の薩摩が部屋にはいってきたジーパン姿の宙夜に声をかけた。
「ケーキ屋を調べてもなにもでないと思います。行きずりの犯行かどうかは別にして、僕の勘では自分から姿をくらましたのではなくて、連れ去られた可能性が高いと思います、もし計画的な犯行なら、奥さん自身も知らない、奥さんの持っている何かが原因だと思います」
「ほう、相当の美人だが、そういうことかい」
「いえ、確かに美人ですが、それとは違うと踏んでいます、今向こうの刑事にかかりつけの医者があるかどうか聞いてもらっています、子供がないので、必ず医者にはかかっていると思います」
「たしかにな、だけど、それと失踪と関係があるとしたら、子供ができない体で悲観していなくなったということも考えられるな」
「いえ、主人と話してみて、二人の間にそういったことでの隠しごとはないだろうと思いました」
「そうか、ご苦労」
「そこのケーキかってきましたよ」
「おー気がきくな」
それぞれのデスクで仕事をしていた仲間が、顔をあげた。吉都希紅子が「お茶入れまーす」と立ちあがった。「それじゃ、ケーキをきるわ」、高胎蓉子が自分の椅子からはなれた。女性がお茶の用意をすると決まっているわけではない。この部屋では男たちもお茶の用意をする。ただ、男がお茶をいれると、だらだら、のろのろしていて、うまそうじゃない。今回は女性たちが、ケーキをはやく食べたかったから、率先して立ち上がったにすぎない。もっとも、室長の男である薩摩は、男のなかにいれられていない。どさっとしていて、動かない薩摩牛と思われている。
宙夜は自分のデスクでPCを立ち上げた。
女性の、それに、原因がある程度わかっているものをのぞいた行方不明者で、10年間に絞り込んだものを画面にだした。二百人以上いる。それをこの一年に絞った。すると二十人ほどになった。
顔写真を並べてみる。赤ん坊もいる。中学生以上にした。それに70以上の高齢者ものぞいた。すると15人ほどになった。鎌倉琴屋の奥さんもはいっている。その女性たちの顔をアップしてみた。奥さんと同じ様な雰囲気の顔、または肌をもった女性はいなかった。
この検索では絞れない。
「コーヒーにしたわよ」
希紅子の声が聞こえた。会議や面談にも使うテーブルの上に、コーヒーがめいめいのコップにはいっている。
ケーキが切り分けられて運ばれてきた。「おいしそうよ」、高胎が席についているみなの前にケーキをおいた。
おかれたところですぐに口に入れたのは、もちろん、薩摩である。「うん、うん」といって、コーヒーを飲んだ。
「コレは収穫だ」
と残っているケーキをほうばった。
「あと、一つもらっていいんだよな」
ホールケーキは片側五つに切られているので、そういうことになる。
「確かにおいしい」ほかの連中も口を動かす。宙夜は店でたっぷり食べたので、一つ食べたところで、ケーキ屋の主人について話して聞かせた。
「それじゃ、手がかりなしなんだ」
希紅子が遠慮なく言う。
「そうなんだ、奥さんは美人でいい人、夫婦仲はとてもいいという評判で、ただ、ケーキ屋と親しいはんこ屋の主人が言うには、特段に肌がきれいだそうだ、それは写真でもそう感じるよ、それで、似たような失踪事件がないか、一年間を調べたけど、顔写真からはなにも出てこなかった」
「もっと昔まで調べたらどうだろう、失踪事件だけじゃなくて、未遂もいれたほうがいいんじゃない」
そう言ったのは、いつもあまりしゃべらない古本だ、日本の古文書解読の一人者だが、最近は幻想小説や推理小説も楽しんでいるようだ。彼が言うように、誘拐を企てても必ずしもうまく行くとは限らない、未遂事件まで幅を広げる必要がある。ただ、そこまでやると、すさまじい人数になる。
「そうですね、まずもっと昔までしらべます、さて、僕はケーキ屋でたくさん食べたから、一つでいいですから、室長たべてください」
そういってコーヒーを飲み干すと、宙夜また自分のデスクにもどった。
「うん、食ってやるか」
そう言う前に、薩摩の手が宙夜の残したケーキの一切れに伸びている。
宙夜はデスクで、五年間までさかのぼって顔写真をだした。百名近いが、判断の速い宙夜にとって、そんなに苦にならない数だろう。
電話が鳴った。ほかの連中はまだケーキを楽しんでいる最中だ、宙夜が自分のデスクの電話に切り替えた。
受話器をあげると、鎌倉の天野刑事からだった。
「あ、先ほどはお世話になりました、なにかわかりましたか」
「はい、ケーキ屋の奥さんがいっていた婦人科病院がわかりました。鎌倉市内の個人病院です」
宙夜は病院の名と電話番号を書き取った。
「医者とは話したのでしょうか」
「ちょっとですが、やはり、子供を作りたいということで相談にきたそうで、それから年に数度見てもらいに来たそうですが、本人のからだはとても丈夫なようです、乳ガン検診もそこでやってますが、全く問題ないようです、やはり、肌がとてもきれいな方だと医者も驚いていました、不妊の問題は、ご主人のほうを調べた方がいいと進言したそうで、その後、奥さんから、自然に子供ができるのをまつということでした」
「主人が病院にいったかわかりました」
「直接聞きませんでした、しかしアレルギーでかよっている病院の医者と話をしました。誘拐だとすると、主人も犯人の候補からすぐはずすわけにはいかないので、様子を聞きました。医者は彼がかなりひどいアレルギー体質で、あそこにケーキ屋をかまえたときからの患者だということです、カビに弱くて、よく気管支や肺が炎症を起こすので、薬を出しているということです、ほかにないか聞いたところ、子供ができないということは医者も聞いていたということですが、一度、血液検査のときに男性ホルモンの量を測ったことがあるそうですが、正常値だったそうです」
「それでは子供ができないのは彼が原因というわけではないのですね」
「いえ、そのことも医者にききましたが、ホルモンが正常でも、精子を作る能力は調べなければわからないそうです、それはしていないようです」
「詳しい情報ありがとうございました、今、女性の行方不明者の検索をかけているところです、何かわかったら、連絡します」
「よろしくお願いします」
「ありがとうございました」
電話をきった。
宙夜は五年間の行方不明の女性たちの写真を順にみていった。顔写真は本人の特長をとらえた一番いい写真を選んであるはずである。場合によっては一人五枚、十枚と撮影角度の違うものなどがストックされている。肌のきめの細かいと言うキーワードだけをたよりに、勘で、さらに詳しくみる必要のある女性をピックアップしていった。
ごちそうさまあ、希紅子の声が聞こえて、宙夜が顔を上げると、みな会議用の机から離れるところだった。
「おいしかったわよ」
高胎が自分のデスクに戻って宙夜に声をかけた。室長はもう自分のデスクでふんぞりかえっている。
宙夜はなにもいわずに、写真に眼をむけた。すでに四十名ほど終わっていて、その中の三人ほどえらびだしていた。さらに進めていく。
一時間後には、百名の中から十二人ほどの女性の顔がPCの画面にそろった。彼はそれぞれの失踪時のファイルを開いてチェックをした。さらに二人にしぼった。一人は名古屋の酒屋の奥さんで、4年前、主人が酒の配達に行っている間にいなくなっている。年は二十五、結婚したばかりで、まだ子供はいない。自分からいなくなるような状況ではないし、事故に会いそうな場所ではない、健康で色白の美人、主人は元気なサッカーの好きなスポーツマン。ただ皮膚アレルギーで皮膚科にかよいはじめたところ、とあった。もう一人は東京都内の独り者のデパート勤めの女性だ。やはり色白で、会社の健康診断でも健康そのものとある。
都内の事件となると取っつきやすい、その女性のファイルを開いた。女性の名は蓮峰しおん。
サービス部門の女性で、五年前に、35歳でいなくなっている。新宿のデパートで、店内の案内係をしており、主任補佐のベテランだった。この年だと、店の隅々まで知っていることだろう。物産展の案内を担当した次の日、休暇を取り、あけても出てこないことから上司である主任の要請から、デパート側が彼女のマンションに警察官との同行をいらいした。その結果、鍵が開いており、本人はいなかった。脱いだ衣服がベッドの上にちらかっており、風呂場に向かった様子が見て取れたが、風呂にはいった形跡はなかったとあった。
両親、知人などの聞き取り、当然前日、デパートを引けてからの足取りなどを調べたが、全く手がかりがなく、自分から失踪する理由も見つからないことから、誘拐の線で調べられたが、現在も行方はわからず、新たな情報を探しているところとあった。
新宿署だ。赤間刑事担当である。
宙夜は赤間刑事に電話を入れた。
「警視庁捜査支援分析センターの宙夜です、五年前の新宿デパートの案内係にいた蓮峰しおんの行方不明のことでお電話しました」
「赤間です、あの件はまったく進展しておりませんで、何か情報がありましたでしょうか」
「いえ、今、鎌倉のケーキ屋の奥さんが行方不明になっていて、そのことを調べていますが、蓮峰しおんという女性と一つだけ共通点があったので、お電話した次第です、あとで鎌倉のファイルを開くPWを送ります」
「といいますと」
「肌が似ているのです」
ふつうの刑事だと、このようなことをいうと、なんだこいつはと、軽くあしらわれるのが常であるが、赤間刑事は、
「考えても見ませんでしたが、一度お話しいただけますでしょうか、明日、本庁の方に出かけます、宙夜刑事は明日いらっしゃいますか」
「はい」
「朝、直接そちらに行きますのでよろしくお願いします」
とまじめに受け答えしてくれた。
次の日、赤間刑事は9時ちょっと過ぎに、第八研究室に現れた。どちらかというと小太りで、薩摩警視を小型にした様な体型だ。
部屋にはいると、「新宿署の、赤間です、宙夜刑事と約束しております」と、深々と頭を下げた。スタッフがみんな彼を見た。あらかじめくることは話してある。
七三に分けた短い髪、四角い赤ら顔に丸い鼻とつぶらな眼、大きめの口。人なつっこそうだ。
宙夜がデスクから立ち上がって、赤間刑事に「宙夜です、わざわざすみません」と挨拶をして、薩摩室長のところに連れて行った。
「いや、ごくろうさまです、よろしくお願いします」
薩摩が会議用のテーブルに案内した。
「支援室というところに始めてきました、コンピューターだらけですね」
「ええ、データー解析が主な仕事ですから、世界中の犯罪のデーターを見ることができます、日本の明治からの奇妙な事件などもほとんどデータ化してあります」
「それで、そのう、肌が白いということなど全く気にしていなかったので、驚いてもう一度、蓮峰しおんの顔を眺めました、確かにどこかほかの女性と違う様な気がします、もう、手がかりがまったくなくて、私が刑事なりたてのときにはじめて遭遇したものですから、なんとしてでも見つけだそうとあがいていたところなんです」
赤間刑事はカバンからタブレットを取り出すと、画面上で、蓮峰しおんの顔をアップにした。
「ほら、上は毛のはえぎわから顎の先まで、両耳の間、しみやほくろ一つない、この写真は化粧をしていない状態のものです」
たしかにそうだ。宙夜もノートパソコンをもってきて開いた。そこまで、ケーキ屋の水谷美恵の顔をみていない。大写しになった彼女の顔には、やはり凹みの一つも写っていない。
宙夜はかなり色の白い、吉都希紅子の顔を見た。離れたところにいるが、小さなほくろが耳のしたにあるのが見える。
「確かにそうですね、それで、蓮峰しおんはどういう女性だったのでしょうか」
赤間刑事は彼女の捜査結果をタブレット画面に呼び出した。
「ずいぶん調べました。とても健康な人だったようですが、実はこの5年の間にご両親がなくなられています。父親は82、母親は79でした。一人っ子で、遅い子供だったようです。
昨日電話をいただいて、ファイルをもう一度よんだのですが、母親の話で、子供の頃から色が白い子で、髪を洗ってやると、洗面器の水が緑っぽくなったと言うことが書いてあります。このことに関して私は全く気にとめていませんでしたが、これはなんでしょうね、宙夜さんの電話で改めて気がついたことです」
「鎌倉の水谷美恵さんは、そういったことはないようでした、やはり健康できれいな人ということです、ご主人はアレルギーで、よく気管支炎や肺炎を起こしていたようです、蓮峰さんは独身でしたね、男関係はどうでした」
「その点もしらべました、デパートに十年以上つとめていましたから、上司や同僚だった人がたくさんいますが、男の話はしたことがないし、少なくとも仕事仲間とそういう仲になったということもなかったようです。あれだけの美人ですから、なにもないのがかえって不思議だと思って、かなり調べましたがみつかりませんでしたね」
「でた大学ではどうでした」
「そこまでは調べませんでした、大学から続いている女性の友達というのはいないようです」
「失踪した前日はデパートのもようしもの場で案内をしていたとありますね」
「ええ、土佐の物産展をやっていたとあります、その日のことは案内係の主任の人が詳しくはなしてくれました、特別気になる出来事はないと思います」
宙夜は土佐ときいて、鎌倉琴屋の主人の出身が土佐で、土佐のチーズを使っていると言っていたことを思い出した。
「土佐のチーズなども売っていたのでしょうね」
「そのときに、チラシなどもここに取り込んであります、売っているものと店の名前がでています。やはり酒が売れていたようです。チラシではチーズの名前はなかったと思います」
画面に会場の案内図もでた。確かに酒屋が多いが、乳製品はない。
「彼女は店内の案内係で、いつもは1階のメインの案内場でしたが、その日はもようしもの場の担当者二人がインフルエンザで、臨時にそちらを担当したようです」
「物産展は何日間ですか」
「三日間でした、二日はその場にいたのですが、アルバイトがはいり、三日目の日曜日は休暇をとっています、独身だったこともあり、有給休暇がずいぶんたまっていたと当時の主任がいっていました、とても優秀な女性だったようです」
「いなくなったのは日曜日ですか」
「そうだと思います」
「マンションから忽然と消えたような形になっていますが、誰かが進入したあとがありましたか」
「靴のあととか、指紋とかは全く残っていませんでした、犯人は用意周到です」
「鎌倉の事件でもそのようです、手がかりはまったくなし、もっとも鎌倉の場合には、犯罪と決まった訳じゃないのですが、交友関系も鎌倉警察署で調べています、蓮峰さんはどうでした」
「当然異性関係も調べました。周りの人は彼女の男性関係のことは知らないようです、少なくとも、職場内につきあうほどの男性はいなかったようです。かなりの美人ですから、男性が放っておくはずはないと思い、彼女の持ち物からわりだしました。家にあった写真の中から男性の写っているものをさがしたところ、一人で写っている男性の写真が一枚ありました。江ノ島のようでした。写真に日付があり、デパートに勤めて5年ほどした頃のものでした。彼女の手帳の住所録にあった男の名前をピックアップして、調べたところ、その男性と連絡がつきました。もう結婚して子供のあるひとです。その男性の話では結婚前提につきあっていったのですが、3年つきあって、その男性の体調が悪くなり、肺炎を繰り返すようになって、養生する必要もあり、つきあいをやめてそのままになったということでした」
「どこで知り合った人なのでしょう」
「IT関係につとめていた男で、電気量販店のコンピューター売場で知り合ったようです、彼女がノートパソコンを選んでいたときに、彼も探していて、手に取ってみていたパソコンを戻すのを待っていた彼女に声をかけたことがきっかけだそうで、結局二人とも同じPCを買ったということです」
「その男性は元々からだが弱かったのですか」
鎌倉のケーキ屋の主人も肺炎をよくおこしている。なにかひっかかった。
「そういうことはなかったようです」
「彼女とつきあうようになってから、肺炎をおこしたわけですか」
「そのようです、本人は仕事がのってきたときで、徹夜もよくしたようで、そのためだろうと言っていました」
「そうですか、共通点は相手の肺炎ですね、鎌倉の失踪した女性の主人も肺炎をよく起こすらしい」
「肺炎がなにか関係があるのでしょうか」
「わかりません、ともかくちょっと似た事件です、わざわざ来ていただいて、ありがとうございました、何かわかりましたら、連絡します」
「いえ、私どももいき詰まっています、これからもよろしくお願いします」
「その、女性の大学時代のことはおしらべになりましたか」
「いえ、そこまでは調べませんでした、身持ちのいい女性のようでしたので」
赤間刑事が帰ったあと、赤間刑事が送ってくれたファイルの蓮峰しおんの学歴を読んだ。とある私大の経済学部をでている。成績はかなりいいほうだ。大学での活動の記録はない。彼女の持っていた写真類もファイルにあった。大学時代の写真を見る。そこにタビランと書かれた袋に入っていた写真があった。旅の記念写真のようだ。かなりの数がある。撮影場所がわかる、見ていくと、必ず彼女の隣に写っている男がいた。
宙夜はその男が大学時代の蓮峰しおんの彼ではないかと目星をつけた。この男にシオンのことが聞けると、手がかりがあるかもしれない。しかし、警察としてどこまで動けるか。
宙夜は希紅子の主人に相談するのがベストだと判断した。吉都希紅子の主人、吉都可也は、巣鴨の探偵事務所「庚申塚探偵事務所」の探偵をしている。生物学の修士をでてから演劇をしていたちょっと変わった男だ。この探偵事務所所長の詐貸美漬は薩摩警視と大学時代の友人で、いくつかの事件を一緒に解決し、事務所に対して警視総監から感謝状まで贈られている。第八研究室のメンバーは探偵事務所の人たちとよく飲み会をする。詐貸の奥さん、野霧も探偵を手伝っているが、何冊も本を書いている小説家でもある。
「吉都さん、そういうわけで、ご主人に仕事たのめるかな」
宙夜は室長に許可をもらって、探偵事務所に蓮峰シオンの彼らしき男について調べてもらうことにしたのである。
「いいわよ、今探偵事務所暇そうよ、猫さがしの依頼もないみたい」
いくえしれずの猫の捜索が得意な探偵事務所である。
その結果は一週間後にでた。
吉都可也が直接第八研究室に来てくれた。
「宙夜さん、久しぶり」
奥さんの希紅子も同席して吉都から話をきいた。
「大学にいって、学生課に、蓮峰しおんについて聞いてきました。両親からの依頼で失踪した本人の捜索のためということで協力してもらえました」
警察から直接より民間人の方が聞き出しやすいことが多い。うそも方便だが、警察ではなかなか使えない。
「タビランと言う旅のサークルにいたということがはっきりして、サークルにあった昔の名簿の写しをとらせてくれました。二年まで彼女はサークルに在籍していたようです、隣に写っているのは近藤政夫、法学部二年遅れで卒業」
「二年もおくれたのですか」
「病気ですね、肺炎と結核」
また肺炎だ。
「そのせいもあったのでしょうか、国家試験には合格できず、卒業してからはもう受けていないようです、現在、新宿でスコッチバーをやっています」
「詐貸所長みたいよね」
希紅子が笑った。庚申塚探偵事務所の所長、詐貸美漬は大学時代に法律試験を合格した優秀な人だったが、とある事情で大学も辞め、バーテンなどをしながら、最後は探偵事務所を始めた男である。
「デパートから近いところだね、もしかしたら蓮峰はそこに行っていた可能性あるね」
「そのスコッチバーにいってみました」
「さすが、吉都さん」
「近藤政夫はいい人でしたよ、奥さんと子供がいます。彼女が行方不明になっていることは知りませんでした。偶然彼女がそのバーに来て驚いたことや、そのあと、たまですが寄ってくれたそうです、好きなウイスキーは決まっていたそうで、かなり酒の強い人だとも言っていました。ここ何年もこないので、結婚でもしたのかと思っていたそうです、いなくなって手がかりがなくて探しているところだと言ったところ、大学時代のことをくわしく話してくれました。彼女は汗が緑色になるちょっと不思議な体質だと言ってました」
「なにからなにまで調べてくださって、助かりました」
「まだあるのです、最後にきたのはもう五年も前だけれど、若い男性と中年の男性と一緒にきたということでした、ふたりは物産展にきている土佐の作り酒屋の人だったそうです、風渦と言う日本酒を売っているところです」
「すごい情報です、土佐がキーワードだと思っていたら、ここでもはっきりした」
赤間刑事には連絡しなければならない。
「吉都さんきていたの、美漬のやつ元気かな」
いつの間にか薩摩室長が立っている。
「元気です、所長も薩摩さんどうしているかみてきてとか言ってましたから」
「おう、それなら、神無月にいくか」
神無月は巣鴨にあるいきつけの飲み屋である。
「いきましょう」
大きな声を上げたのは希紅子だ。
その夜は巣鴨にいくことになった。
その前に片づけておかなければならないことがある。宙夜は赤間刑事に、新宿のスコッチバーのマスターが、大学時代の蓮峰しおんの恋人だったこと、物産展に出展していた、土佐の蔵元の人をスコッチバーにつれてきたこと、それがいなくなる直前のことだったことを電話で話し、詳しいことはメイルで送信した。
その上で、土佐の風渦と言う日本酒を作っている醸造所をネットで調べた。
その酒屋は室戸蔵といって、チーズもつくっており、室戸チーズとして、どちらかというと、菓子やパンの生産会社に納入している。
宙夜は鎌倉の天野刑事に電話をした。
「それで、琴屋の主人に、チーズの仕入先を聞けばいいですね、すぐ電話で聞いて折り返し連絡します」
鎌倉ケーキ屋のチーズの仕入先を聞いてもらったわけだ。
天野刑事からすぐに返事があった。
「宙夜さん、土佐の室戸チーズというチーズ屋さんだそうです、店を始める前ですから5年以上前ということになると思いますが、夫婦で室戸のそのチーズ屋に行ったことがあるそうです、本来は酒屋さんで、そのころ、新たな日本酒もつくろうとしていたそうです」
つながってきた。室戸蔵を探ってみる必要がある。宙夜は天野刑事に新宿での出来事をかいつまんで話し、詳細はメイルで送った。さらに、新宿署の赤間刑事と連絡を取るように天野刑事に書いた。同じことを赤間刑事にも連絡し、室戸蔵を調べにいくときには自分も行くことを伝えた。両者にはっきりするまで、土佐の警察には連絡しないように言った。もし室戸蔵の誰かが関係しているとすると、土佐の警察の動向は監視している可能性があるからである。
その日の夕方、巣鴨の神無月で、庚申塚探偵事務所の連中と飲んだ。後期高齢者の主人と二十歳以上離れている奥さんの姫子さんが営んでいる店だ。
みなそれぞれ好きなものを飲んでいる。
「吉都さんに助けてもらって、鎌倉の女性の失踪事件、解決に一歩前進です」
宙夜が希紅子の旦那に言った。薩摩も「いや、いつもありがとうございます」と頭をさげた。
吉都は頭をかきながら、「いえ、そんな」とどもりながら、「酒とチーズを作っているというと、その酒屋には麹に詳しいのがいると思いますよ、青カビなんかは麹と同じ様な働きをするんです」
吉都は生命科学出身だから詳しい。薩摩がそれを聞いて、
「俺のカビなんとかならんか」
と声を上げた。
みんなが薩摩を見た。薩摩が自分の足の先を指さしている。
「ああ、水虫ですか」
吉都が薩摩の大きな靴の先を見る。
「かいくてたまらんよ、こんな虫飼いたくねえ」
「かわゆくてたまらんと、聞こえたよ」
探偵事務所所長の詐貸が笑った。
「ばかいえ、こんなもん、かわいいはずがねえ、足の先に住み着いちまった」
吉都も笑いながら、「薩摩さんの足の指がすきなんでしょう」とめずらしく冗談をとばした。
「古文書にもカビの生えた人のことがかいてありましたが、かびの生えやすい人っているんですか」
古書が吉都に尋ねた。それには看護師の資格を持っている高原が答えた。
「そりゃあ、ありますよ、免疫の弱っている人や不潔にしている人」
「はは、薩摩は不潔にしている人だ」
詐貸が遠慮なく言い放つ。
「アルコールで消毒しな」
神無月の主人が薩摩に言って、姫さんが焼酎をもってきた。
「からだに入ったアルコールは消毒になるんかい」
「脂肪になるだけかも」
詐貸が薩摩の出っ張った腹を突っついた。
「こら、おしたら、下から固形物がでちまう」
「きったねえな、ふたりとも」
神無月のじいさんがカウンターからどなった。
「股間部はいんきん、足や爪は水虫、頭はしらくも、それいがいはたむし、なまえがちがってもみな白癬菌が皮膚をたべているわけよ、真菌類ね」
看護婦の資格のある高胎が説明する。
「真菌類って、キノコの仲間でしょ」
希紅子が亭主の吉都可也にたずねている。
「そうだよ、カビもそうだよ、くっついたものを分解して栄養にするんだ」
「じゃあ、水虫は足の指を分解して食べているんだ」
「うん」
「室長、白癬菌を逮捕しなさい」
希紅子が叫んだ。薩摩はどっしりとかまえて、「だけどなあ、白癬菌の手ってどこだ、手錠がはめられんよ」
いつもの冗談を言う。
「あ、室長さんうまいうまい」
喜んで手をたたいたのは、詐貸の妻、作家でもある野霧である。ビールをもう二杯飲み干している。
「チーズを作る青カビは真菌類なの」
希紅子が聞く。
「うん」
「青カビが白癬菌みたいにからだにとっつくことあるの」
薩摩が可也にきいた。
「聞いたことはないけど、ないって言い切れないでしょうね、遺伝子が変異した奴が皮膚に取っつくと」
「そうなると、青カビが指から生えるのか、もしかしたら、キノコつくったりしてね」
希紅子が薩摩室長を見た。
「そんな話を書いている素人がいるわよ、草片文庫って人、自分で話を作って、絵を入れて本作っているのよ」
野夢が話し始めた。野霧は探偵事務所であつかった事件を題材にして、何冊も本をだしている。なかなかの評判で、今、猫の腹に宝石を隠して密輸入をした事件を小説にしている。
「茸は死んだ生き物を分解して、土や空気に戻してくれる、地球の掃除人ね、カビもそうね、彼らがいなければ、動物や植物の死体で地球が埋もれてしまうわよ」
「石灰岩は珊瑚の作った住みかが石になったものです、人間はそれをセメントにして、自分の住みかをたて、町を作っています、石油もそうです、小さな生き物たちは、死んでからも我々が生きることを助けてくれている」
宙夜は石の専門家だ。
「そんで、人間の死体はなんか訳にたつかい」
室長がそういうと、高胎が、
「土に埋めれば、肥料になりますけど、火葬にすると、二酸化炭素は出すし、空気を汚すし、たいした役にたちませんね」
というと、古書が、
「江戸の本に、動物の死体に茸を植え付けて、増やして食べたと言う話が載っています、中でも人間の死体から生えた茸は美味とかいてありますね」
「ほんとにあった話なの」
野霧が身を乗り出した。
「死体の活用、という読本ですから、お話ですね」
そういった会話が閉店までつづいた。
次の日、宙夜がPCをあけると、赤間刑事から、現在の室戸蔵について連絡がはいっていた。
室戸蔵は日本酒「風渦」に加えて、アルコール度のたかい「狂風」という酒を限定発売していて、とても人気があるということだった。チーズも種類が増え、ブルーチーズが出荷されているということであった。
社長は北海道の大学出身の農学博士、チーズの発酵の菌類研究をした内間蔵人で、現在41歳、一時、大学の助教をしていたが、父親の酒屋を継ぐために土佐にもどり、室戸に酒造施設とチーズづくりの施設をつくった。土佐に戻る少し前に奥さんを病気で亡くしている。
会社の室戸蔵は代々その店の番頭だった家柄の唐井勝が切り盛りしている。彼は杜氏でもある。社員十八名をうまく束ねて、経営はとてもいい。年間の売り上げは一億近くあり、社員はかなり優遇されている。
そういった内容だった。
さらに、鎌倉の天野刑事から連絡が入った。
新宿書の赤間刑事と相談したが、ケーキ屋で室戸蔵のチーズを使っていることもあり、赤間刑事が土佐の警察著と連絡したいと言っているという内容だった。
宙夜は室長の薩摩と相談して、赤間刑事から土佐の警察署に連絡してもらうことにして、第八研究室としては、その様子をきいてから動くことにした。
「宙夜君、やっぱり、土佐に出張してもらわなければならんな、なにかでたら、赤間さんと天野さんと一緒にいってきたらいい」
室長にそういわれた宙夜は、
「他の人と行く前に、僕が見てきていいですか」
と答えた。
「いいよ、だけど、赤間さんと天野さんの顔を立ててやってよね」
今まで宙夜が動くと、一人で解決してしまうことが多かったことから、室長からでた他警察への配慮の言葉である。
「様子見に行くことにします、まだ、可能性がみえてきただけで、室戸蔵がこの件と関係がなさそうだったら、みんなで行くのはばからしいと思います」
宙夜としては、被害者と思われる女性の肌から推測したことが、全く意味のないことだったら申し訳ないという気持ちがあったのだろう。
「そうだな、いつでもいってこいよ」
薩摩に言われた。
二日後に、赤間刑事から、室戸警察署の山内刑事と連絡をしたこと、その刑事のいうことには、室戸蔵の社長をはじめ、社員たちの評判はとてもよく、高知市にある店は繁盛しているし、問題あるような行動の報告はないと言うことだった。大都市で行われる物産展にはよく出店していて、関東、関西方面のデパートには年にかなりの回数でかけているという。
鎌倉の水谷の奥さんが失踪した日には、茅ヶ崎の物産展に来ているということだった。新宿の件でも物産展のさなかだった。宙夜は早く土佐に行こうと思った。
室戸蔵の社長、内間蔵人と、番頭、すなわち専務の唐井勝の顔写真を確認した。
土佐竜馬空港に降り立った宙夜は、あらかじめ手配しておいたレンタカーで室戸の町にむかった。海沿いの国道55号線、土佐東街道を走った。室戸に行くのには土佐くろしお鉄道を使っても奈半里からバスか車になる。かなり不便なところで、車を借りるしかなかった。二時間弱で室戸岬に行くことができる。
その日は幸い天気がよかった。海の景色を眺めながらの運転は、東京の空の見えないようなコンクリートの隙間を走るのとは違う。広い道ではないが、気持ちよく車をとばし、西の川、東の川をすぎ、室戸市にはいる。室津川沿いにちょっと先に行くと、山の上に室戸中央公園があるが、その麓あたりに室戸蔵の醸造施設と、ちょっと小高いところに、社長の家があるはずである。
海岸沿いの道から町中にはいり、室津川をすぎて、少し行ったところで国道55号線を離れ、町中の道を室戸中央公園に向かった。
蛇行する道の途中に醸造施設と、ちょっと離れて社長の家があった。
宙夜は醸造施設の近くに車を止めると、煉瓦で作られた建物の入り口にむかった。道の脇に「室戸蔵醸造所」と矢印のかかれた小さな木の看板がたっているだけである。地味な感じをうける。石畳の道が建物の方に続いている。
敷地内に入ると、広い駐車場があり、車がたくさん止まっていた。社員のものだろう。醸造所の前の広場から、細い道が上に続き、その先にかなり大きなやはり煉瓦で作られた社長の家が見える。
敷地への入り口に守衛所があるわけではなく、宙夜は玄関のところまで誰に会うこともなくいきついた。玄関も開け放たれ、作られている酒と、チーズが展示されてあるだけだ。
入り口におかれた木の机に、用事の方は呼び鈴を押すようにと書かれた紙が張ってある。
昔ながらのチンである。
宙夜が押すと、事務員姿の中年の女性がいらっしゃいませとでてきた。
「何かご用でしょうか」
若い格好の宙夜を見て、事務の女性は不思議そうな顔をした。
「あの、ここは見学できないのでしょうか」
そう言うと、女性は少し安心したように、
「あ、見学希望の方でしたか、あの、予約制になっておりまして」
申しわけなさそうに言った。
「ここで、酒は売っていないのですか」
「はい、あいにくここでは売っておりません、店の本店は高知の方にございますが、室戸岬の灯台に行く道沿いに、サンドイッチの店をだしておりまして、うちのチーズを使った、室戸サンドをめしあがれます。そこにおみやげ用の日本酒がおいてあります、ちょうど、社長もそちらに昼食をしにいったところです」
宙夜は場所をきいてから、サンドイッチ店にむかった。
室戸チーズ直営の店はすぐわかった。林の前に、室戸チーズサンド、軽食と書かれた看板のある駐車場があった。何台かの乗用車が止まっている。その中で灰色の中型トラックが目立っている。空冷装置の吹き出し口があるから冷凍冷蔵車だ。
宙夜は駐車場に車を止め、林の中に続く小道を歩いた。木々に囲まれた奥に煉瓦づくりの北欧風の建物が見える。そこがレストランだ。小鳥のさえずりが聞こえてくる錯覚におちいるほど静かだ。建物の中に入ると、以外と広い店内と、反対側の林を切り開いた広々とした草原が見える。そこにはいくつもの丸テーブルが見え、すでに何人かの客が食事をしている。
いらっしゃいませと、受付にいた女の子が宙夜を見た。
「おひとりですか」
彼はうなずいて、窓のテーブルでコーヒーカップを口にしている男性二人に目を留めた。
「どこでもお好きなところにどうぞ、外でしたら、ここで注文をうかがっておきます」
宙夜はチーズとハムを挟んだフランスパンとコーヒーを頼んで、外のテーブルを指差した。
「すぐにお持ちしますので、おかけになってお待ちください」
そういわれて宙夜は外にでた。
二人の男性の風下のテーブルを選ぶと腰掛け、ヘッドホンを耳に当てた。音楽を聴くためではない。外の音が倍増するヘッドホンである。
背を見せている中年の男がちょっと振り返って宙夜を見た。前に座っているのはまだ若い男だ。宙夜はそれが室戸蔵の社長と番頭であることがわかった。
宙夜はテーブルの上にヘッドホンとつながっている、一見PC3プレーヤのような小型録音器機をおいた。
ウエートレが、室戸チーズサンドができるまで少しお待ちください、と水をおいていった。注文を受けてからつくるようだ。
宙夜は器機のダイヤルを回した。社長と番頭の会話が手に取るように聞こえる。
「やはり、黒カビでチーズを作ってみたいんだ、どんな味なるか」
若い社長の声である。
「若、一度失敗してるじゃないですか、黒カビはむかないのではないですか」
「クロコージカビは、向いているはずだよ、前に使ったクロコージカビがよくなかっただけだろう、うまい酒がつくれるのじゃないかな、チーズはわからないけど」
宙夜は餅や壁に生える黒カビしか知らない。
「探すのは大変です、いつみつかるかわかりませんが、気にしておきましょう」
「今度のだめだったのはどこかに捨てなければ」
「若はそういうことには気を使わないでください、私が万事やりますから」
「もう少し調べたら捨てよう」
何の話だろうか。
「捨てたあとのカプセルはまた使えますか」
「ああ、僕が滅菌するよ」
カプセルとは何だろう。工場にあるものなのだろうか。もしそうなら、番頭がいらなくなったのを捨てに行くというのはどういうことだろう。工場の係りの者がやればいいことじゃないか。とすると、工場にあるものではないということになる。
高知の室戸蔵本店にあるはずはないとすると、社長の家だろう。あの家も三階建てでずいぶん立派だ。家庭用とは思えない大きさだ。あの社長は農学博士だ。自分の家に研究室を持っていても不思議はない。その辺の確認をすべきだろう。それに、番頭が何かを捨てに行くという、やはり、室戸署とは連絡を取らなければ前に進まない。
運ばれてきたチーズサンドを食べ終えると、コーヒーを飲んで、二人の会話を聞いた。そろそろ二人の会話も終わりそうだと思ったとき彼らより先に店をでた。
駐車場の車の中で、鎌倉署の天野刑事と新宿署の赤間刑事と連絡をとった。自分の想像から室戸蔵をにらんだのだが、全く関係がないと迷惑になると思い、室戸に来ていることをつげ、まだはっきりはしないが、調べてみる価値はありそうなことを話した。その上で、室戸署と連絡をして、室戸蔵の社長の建物を設計した事務所を割り出してもらい、研究室のような部屋があるかないか確認をしてもらえないか伝えた。
そうこうしていると、二人が店から出てきた。二人は駐車場の冷蔵車にのりこんだ。着いたときに眼に留まった灰色の冷凍車だ。運転席にはいったのは番頭である。会社の車には宣伝のため、会社名やマークなりを入れるものだ。この車には文字がなく、ただの灰色である。奇妙である。
冷凍車はすぐに駐車場からでて室戸蔵醸造所のほうにむかった。宙夜もあとについた。二人の車は室戸醸造所の入り口を通り越し、もう少し先の小道にはいった。宙夜は車を止め降りた。あまり車や人が通らない道のようで、落ち葉がかなりたまっている。車ではいると目立ちそうだ。宙夜は見通せる場所まで歩くことにした。ほんの三分も登ると木陰から社長の家が見えた。下の道から、醸造所を通らず、直接社長の家に行く道だった。
宙夜は車に戻り、醸造所の下に車を移動した。車からでて醸造所の門を入ると社長の家の前に灰色の車が止まっているのが見えた。
木の間を通って社長の家に近づいた。家の周りの様子を調べ、低姿勢で冷凍冷蔵車に近づくと、車の下に潜り込み、ポケットからだしたものを車体の一部につけた。粘着テープでしっかりと覆うと車から離れ、林の中を抜けて自分の車にもどった。
車の中でパソコンを開き操作をすると、画面に日本地図がでて小さな赤い点が点滅しているのが確認できた。拡大すると室戸岬の自分のいるあたりの地図が現れ、さらに拡大すると社長の家のあたりに赤い点滅がでた。宙夜は冷凍車に探知機をとりつけたのだ。
それだけ確認すると予約をいれてあるホテルにむかった。
ホテルについて部屋にはいったとき、室長から電話がはいった。
「宙夜、探知機を使っただろう、希紅子がみつけたよ、なにしてる」
「室戸蔵の社長のところにとめてある冷凍車にとりつけました、社長と番頭が何かたくらんでいます、冷蔵車がどこに行くか見てみたいと思います」
「そうか、こっちでもフォローするよ、動いたらどこに向かったか君に知らせる」
「たすかります、鎌倉の天野刑事と、新宿の赤間刑事にこちらに来たことは知らせました、室戸署に連絡を頼んであります。室戸蔵の社長の家はおそらく研究室も持っていて何かをしています」
「あやしいわけだ」
「そう思いました」
「君がそう思うなら、きっとそうだろう、こちらでできることがあったら、いってくれな、出張は期限なしで認めるよ」
「ありがとうございます」
電話はきれた。
部屋のデスクでPCを開くと探知用の地図を開いた。
天野刑事からスマホに連絡が入っていた。室戸署の小泉刑事に調べてもらったところ、建築した会社がわかり、地下に社長用の研究室があるそうです、カビ専門家が研究できるような施設になっていると言うことです。危険物貯蔵の許可も取り付けてあるみたいです。おそらくアルコール類を使うのだ思います。中に入っている機械についてはまったくわからないそうです、この会社はとても評判のいい、室戸町にとっても大変ありがたい存在とのことです、とあり、室戸警察の電話番号が記されてあった。宙夜さんのことは伝えてあります、とあった。
宙夜は室戸署の小泉刑事に電話をいれこう話した。
「鎌倉の天野刑事から連絡もらいました、よろしくお願いします、新宿署の赤間刑事からも電話がいきましたでしょうか、二人の女性の失踪事件ですが、まだ、全く犯人像がでてこなくて、たまたま、二つの事件に、チーズと土佐というキーワードが浮かび、室戸蔵がでてきただけで、何の関わりもないかもしれません、内偵段階で、相手方に迷惑になるといけませんので、そちらで調査をしていただく必要はありません、情報だけいただければたすかります」
その夜、室戸蔵の車の動きをチェックしていたが、いつも社長の家においてあるようで、あれから全く動いていない。
朝になって、車で醸造所近くまでいって社長の家を見ると、冷凍車はそのままであった。番頭は醸造所駐車場においてある自分の車で家に戻ったのだろう。
三日後のことである。めずらしく夜の七時に冷凍車が動き始めた。
PCの画面でおいかけると、見せのある高知とは違う方向に走っている。どこかの物産展に行くにしては時間がおかしい。徳島を通って、鳴門、須磨を通っている。名古屋方面か。
名古屋で北区の酒屋の奥さんが行方不明になっていることを思い出した宙夜はファイルを開いて酒屋の住所を調べた。名古屋まで行くのなら七時間はかかるだろう、すでに三時間、あと四時間だ。今十時、宙夜は室長の個人の携帯番号に電話を入れた。
「おお、宙夜、まだ寝ておらんよ、テレビの時代劇見てたんだ。ん、室戸蔵の車を追いかけたいのか、名古屋にいくかもしれんわけだ、愛知県警本部に電話をいれておいてやるよ」
薩摩はそういってくれた。
五分ほどたって、宙夜は愛知県警察本部に電話を入れた。薩摩は連絡をしていてくれたようだ。夜勤の追跡担当者が、取り付けた探知装置のメーカー型番と個体番号をきいてきた。こちらで追いかけます、ということだった。
宙夜はそれらを教えるとともに、背景を話した。なにも起きないかもしれないことを伝えると、担当者は、「なにも起きないのが一番です、今までも空振りは80%です、ご安心ください」といわれた。礼を言って、PCの画面に目を移した。予想通り、名古屋に行くようだ。そうだとすると、あと二時間ほどはなにもおきないだろう。それにしても、室戸蔵の番頭はタフである。赤い点が止まらない。トイレにもいかず、ただひたすら走っている。
宙夜はコーヒーを飲んだ。テレビでは深夜番組が始まっている。
愛知県警察本部から連絡が入っている。宙夜のPCは画面を半分に区切って使うことができる。名古屋署から覆面パトカーを出す用意ができているということだった。礼を書いて、また画面に目をやった。
今十二時半、もうすぐ名古屋市内だ。車はかなりのスピードをだしている。画面の地図を名古屋市内に拡大した。赤い点は名古屋城の方向に進んでいる。さらに拡大をすると、名古屋城の脇の道をすすんでいく、北区の名城公園あたりだ。名古屋の奥さんがいなくなった酒屋とは違う方向だが生活圏にはいっている地域である。
名城公園を過ぎたところで、突然赤い点がとまった。地図上の黒川とかかれている小さな川のあたりだ。
宙夜がグーグルの地域の地図にかえてみていると連絡が入った。二時近い。
名古屋北警察署の前城刑事とある。
驚いたことに、遺体遺棄で室戸蔵専務、唐井勝を逮捕したとあった。明日名古屋北署の方に来てほしいという。すぐに室戸署に連絡をして、当直担当者に室戸蔵の社長、内間蔵人が自宅を出ないように見張ることをたのみ、名古屋のほうには朝できるだけ早く行くと返事を書いた。
やはり何かあった、ほっとした思いである。宙夜はシャワーを浴びてベッドにはいった。
明くる日、なにも食べずに5時にホテルをでて、レンタカーを奈半利駅におくと、名古屋に向かった。奈半利から岡山まで一度乗り換えて3時間ちょっと、岡山から新幹線で名古屋まで3時間ほど、全部で6時間ちょっと、午前中につくことができるだろう。
電車の中で朝食や追加睡眠をとった宙夜はほぼ12時に名古屋についた。
タクシーで名古屋北署についたのは12時半だった。宙夜は応接室に通された。
待っていると、中背の小太りの男が、
「宙夜刑事さんですか、前城です」
とはいってきた。
「宙夜です、驚きました、死体遺棄というのは、行方不明の酒屋の女性でしょうか」
「その通りです、こちらの方が驚きました、全く手がかりがなくて、お蔵入りにしたくないと、がんばっていたところです、まさか、警視庁の方が捜査をしていたとは思いませんでした」
「実は鎌倉では最近、新宿では五年前に消えてしまった女性がいて、名古屋の酒屋の奥さんもふくめ、みな色が白い肌のきれいな人で、調べていくと、酒とチーズ、それに土佐というキーワードがでてきたところから、室戸蔵がうかびあがったので、調べにいっていたところです」
「すごい推理ですね」
「室戸署には室戸蔵の社長の見張りをたのんだのですが」
「われわれも室戸市の警察署に連絡しました。すでに身柄を確保しているものと思います」
「それで、番頭の内間が死体を遺棄したわけですか」
「はい、本署の覆面パトカーが冷蔵車をみつけ追跡したところ、うちの署の近くにある、黒川のわきで冷蔵車がとまり、運転手が後部から袋を取り出して中のものを土手から下に落としました、その場で尋問をして、身柄を確保した上で、捨てたものを確認したわけです。女の死体でした。水の中ではなく、縁の土の部分に引っかかっていました、今、署の死体処置の部屋においてあります、検死係りも来ております、すぐごらんになりますか」
地下の遺体安置の部屋に案内された。ワゴンの上に裸の女がのっている。女性の検視官がまっていた。
女はきれいに洗われていて、白い毛に覆われていた。いや、毛ではないカビだ。
「はじめからカビが生えていたのですか」
宙夜の質問に検視官が答えた。
「そうなんです、強いカビなんです、シャワーで洗ってもおちません、今、このカビの検査をしてもらうため微生物研究所に資料を送ったところです、この肌を見てください、色は白いけどしわしわです、だけど死んで2ヶ月の肌です」
宙夜が驚いた。
「誘拐されて4年近くですね、ということは、つい最近まで生きていて死んだから捨てた」
「そうだと思います」
「死んでからカビが生えたのですか」
「わかりません、カビが殺したのかもしれません」
「だが、なんで、誘拐した場所の近くに捨てにきたのでしょう、海の中に沈めた方が見つかりにくい」
「まだわからないのですが、捨てにきた内間の考えではなさそうで、社長の命令だそうです」
「社長はもう捕まっているわけですね、家宅捜索ははじまっているのでしょうか」
「室戸署の方でやっているはずです、室戸署の小泉刑事がいっています」
「酒屋のご主人には連絡がいったのですね」
「今日の朝はやく、すでに遺体の確認をしてもらいました、ずいぶんしょげていました、きれいな奥さんでしたしね」
三人ともきれいな女性だった。ふっとそのとき、宙夜はあと二人の女性はまだ生きているかもしれないと思った。
「すぐ室戸岬にもどりたいのですけど、一番早く行く方法は電車でしょうか」
「しらべてみましょう」
前城刑事は小牧空港のダイアをみてくれた。
「朝早くなら高知にとんでいますね、明日の朝8時前の飛行機があります、1時間で高知につきますよ」
「ありがとうございます、だけど今日中にもどりたいので、電車で行きます」
「まってください、車が出せるか聞いてみます」
刑事は本部に電話をして事情を話した。
「あいている車はないようです、ハイヤーで行かれた方がいいと思います、この際ですから費用はでると思います。電車では乗り継の関係で相当時間がかかるばあいがありますから」
宙夜は相づちをうった。
すぐに前城刑事が手続きをとってくれた。
室戸警察のほうにはすぐ戻ることを連絡した。
ハイヤーの中で、ことの次第を第八研究室に連絡をした。室長からは鎌倉署と新宿署に連絡を入れてくれると返事が来た。
しばらくすると、鎌倉署の天野刑事と新宿署の赤間刑事が明日向かう予定といってきた。第八研究室からもだれかいかせるということだった。
車の中で今回の出来事を時間をおってPCにうちこんでいった。
プロの運転はさすがである。夜の9時には高知にまできていた。
宙夜は運転手に指図をして室戸蔵の社長に家にむかわせた。高台にある社長のレンガ館の道路には警察の車両がとまっていた。
宙夜は警察手帳を警備担当の警官に見せ、ハイヤーごとわき道から直接社長の家にいった。救急車も来ている。
ハイヤーを帰し、警官に警視庁からきたことを告げると、奥から第八研究室の古書が刑事と思しき人と出てきた。
「宙夜さん、ご苦労様、これで解決ですよ、こちら室戸警察の小泉刑事」
「このたびはありがとうございました、すごいことがここで行われていることがわかりました」
古書と小泉刑事が笑顔で迎えてくれた。
「生きていましたか」
「え、よくそれがわかったね」
古書が驚いた顔をした。
「鎌倉で誘拐された水谷さんは生きていた、ただ新宿で誘拐された蓮峰さんはミイラのようになっていた」
「かびが生えていたのでしょう」
「それもわかったの、すごいね、蓮峰さんは無惨だったな、青かびに覆われていてね、岩谷さんは白カビがはえはじめたところだった、岩谷さんは先の救急車ですでに病院に運ばれている、さらにもう一体死体があったんだ、赤いカビにおおわれているのが」
宙夜は古書と小泉のあとをついて、地下一階に貯蔵された日本酒のビンをみながら地下二階の研究室におりた。
そこにはカプセルに入った青カビの生えたミイラがあった。蓮峰さんだろう。もう一つのカプセルに干からびた赤カビの生えた遺体があった。
「これは誰」
宙夜の質問に小泉刑事が答えた。
「社長の内間の奥さん、病気でなくしたのを埋葬しないで、酒の発酵材料としたようです」
「え」
宙夜は思わず聞き返した。
「珍しい赤カビだそうだ、社長の内間が言っていたよ、カビの生える体質があるそうだ、皮膚がそうできているということだ」
古書は古文書にカビの生えた人のことが書かれていることを知っている。
「だけどね、社長は奥さんをとても大事にしていて、死んでしまったのを悲しんで、手元に起きたい一心で火葬しなかった。死体をかくしていたんだそうだ。カビが生えてきて、奥さんの贈り物だとおもって利用したようだ。チーズにしたんだ。番頭に名古屋の女性の死体を元の場所の近くに捨てさせたのも、女性の主人が新聞に深く悲しんでいることが報道されているのを読んでいたからだと言っていたよ、どこかちぐはぐだね」
「鎌倉の奥さん助かってよかった」
宙夜はつぶやいた。
「ほんとだなー、きれいだったよ、真っ白の肌にきれいなまだ短い白いカビが一面にはえていて、オブジェのようだった」
古書が見たことを説明した。
「名古屋の酒屋の奥さんは生きたまま白カビをはやしてカプセルに保存されていたのだけど、白カビの出す毒に負けて死んでしまったようだ」
「社長が女性たちの肌にカビを植え付けたわけですね」
宙夜がきくと、古書が首を横に振った。
「ちがうらしい、元々カビのいる皮膚を持っている女を選んで誘拐したようだ」
「カビの生える体質ってあるんだ」
「そうみたいだ、今、社長は室戸署の方で尋問をうけている、あらざらいしゃべっているそうだ、元々研究者だから、ずいぶん細かいところまで覚えていて話しているようだよ」
小泉刑事もうなずいて、「そうなんです、さっきも尋問している刑事から連絡がきたのですが、とても繊細で、やはり偏っている人間で、目的を果たすことに眼をとられていて、そういう女を誘拐したようです、生かしたままカビを生やした方がいいということで、カプセルの中で生かしておいて、必要なだけ、カビの生えた皮膚を削り取って使っていたということです」
「おそろしいことだよね」
研究者の独善性を怖いと思った。一方、奥さんをなくしたときの反動かもしれないとも思った。
「古書さん、いつまでこちらにいます」
「宙夜君のおかげでいくつもの未解決の失踪事件が明らかになったわけだし、僕に後かたづけをしてこいということだったから、鎌倉と新宿の人たちが明日きたらバトンタッチして帰る。室長がいうには、宙夜には休暇をやると言ってたよ、明日連絡してみたら」
「はいそうします、僕も明日東京に帰ることにします」
「名古屋北署の前城刑事からも連絡がきたよ、関係署の方たちと一緒にこの事件は解決されると思うよ」
宙夜はパトカーで今日の朝まで泊まっていたホテルにおくってもらった。空いている部屋にもう一泊した。あとは古書さんにまかせておこう。急に眠気がおそってきた。
明くる日、宙夜は午後に東京に戻った。その足で警視庁にいくと、第八研究室の面々に「ご活躍ご苦労様でした」とからかいかねぎらいかわからない出迎えをうけた。
「いや、よくやったよ、これで三人の女性失踪事件が解決し、一人は命も助かった」
薩摩もまじめにほめた。
「おみやげは」
そういったのは、吉都希紅子である。
「話のみやげだけ」
宙夜は今までのことを三人にきかせた。
「一週間もすれば、全容がわかるだろう、そうしたら、いっぱいのもうかな」
いっぱいとは一杯じゃなくて沢山ということだ。薩摩がまた神無月に行きたいと言っているわけである。
そして、本当に一週間後、つぎつぎと室戸事件の報告が第八研究室にとどいた。
まず一報は鎌倉警察署、天野刑事からである。ケーキ屋の奥さん、水谷美恵は白カビ退治の薬を注射することで意識が回復したそうである。茅ヶ崎の地方物産展で関東に来ていた室戸蔵の番頭、唐勝が自分のところのチーズを使っている店を、しのびで周っていたときのこと、鎌倉のケーキ屋でカビの体質の美恵を見つけ、誘拐することを思いついたということだった。美恵の皮膚には白いカビが寄生していて、弱いながら毒素をとばしていたことから、主人がときどき肺炎をおこし、病院にかかる羽目になっていたということである。
新宿の赤間刑事からも連絡があり、デパートの土佐物産展で出展していた室戸蔵の社長の内間と番頭の唐井が、会場担当だった連峰しおんがカビ体質だと気づき、絞殺して連れさったということである。そのころは死体にカビをはやさせて酒やチーズにしたてていたということだった。その後は生きた人間にの皮膚を切り取るという方法にかわっていったようだ。
学生時代にしおんの恋人だった男は、新宿のスコッチバーのバーテンになっており、今回の解決に重要な情報をもたらしてくれたのだが、やはり肺炎をおこし体調をわるくして、司法試験をあきらめ、留年もしている。それは彼女の皮膚に潜在していたカビのためであった。
名古屋北署の城前刑事の連絡では、生きたままカビの培養をされた最初の犠牲者が名古屋の酒屋の奥さんで、4年間生きたまま、カビのついた皮膚を切り取られていたということだった。切り取られるとき痛かったろうなとおもったが、おそらく痛みは感じなかったのではないかと専門家はいっているということだった。しかしカビの出す毒素がたまり死に至ったということである。
巣鴨の飲み屋「神無月」に集まったのは、宙夜が研究室にもどって、二週間たった土曜日になってしまった。そのころ室戸蔵の事件はほぼ全容があきらかになっていた。
警視庁八公の五人と巣鴨の庚申塚探偵事務所の三人、全員が集まり、宙夜の話を聞いた。
庚申塚探偵事務所所長の妻であり、作家の野霧はビールの大ジョッキをぐいっとあけると、
「今までの毒の話、小説にしていいでしょうか」
と言った。
「もちろん」
みんながそれぞれの器をもちあげて、「お願いしまーす」と声をそろえた。
神無月の亭主と姫子さんが笑った。
「印税またはいるなあ」
薩摩がうなった。
それを聞いた宙夜は、鎌倉のはんこ屋に自分の印をもらいに行くことを思い出した。ついでにあのケーキ屋さんによろう。あの主人喜んでいるだろうな。
黴の皮膚毒


