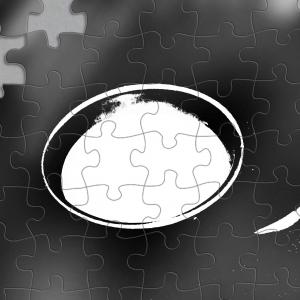「時雨」
雪は野原に
花は水に
散っては溶ける春の景
なつかしさを包み持ち
とほくの頂から撒くのだろう
音も鳴らない白金の鈴
ただ一人には聞えけり
時雨の柳は何を見る
白露重ねて滴らせども
その葉が何を掴めよう
雪は野原に
花は水に
散れば其処に姿は無く
溶けた面影のなつかしや
あてどもなく歩きたしが
柳は深く根を降らす
土に深く根を閉ざす
せめてこの葉が鳥と化ければ
わずかな命火の下であれど
切なく望む処へとゆけるものを
甘く苦しい星のちらつき
仮初とても忘るるものかと
君に抱かれしこの胸も
ふるえる肢もまるで我がものにあらずして
瞳動かぬ君の眼に
からめ取られてしまったようで
あの逢瀬の一瞬から体は思う通りに動かず
いつでもまたあの瞳に燃やされている
この頬に雫したたる君の泪
触れたる指は今でも悲しく
轢かれて死んだ陽炎の胡蝶に
届かぬ文の使ひを頼んで
「時雨」