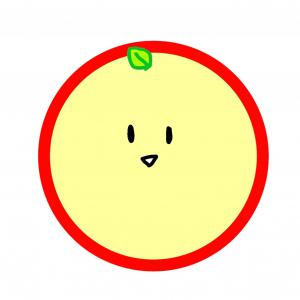ときめきの丘
ある夜、私の元に招待状が届きました。初夏の涼しげな風が吹き、月も山の向こうに大きく見えた美しい夜でした。そのカードは私の部屋の窓にこっそりと差し込んであり、そこからはすずらんの爽やかな香りがほんのりと漂いました。私は不審がることもなくつい興味本位でそれを手に取り、カードの文面を読みました。
「あなたに相応しい男になりました、明日の夜、迎えに参ります」
水色に縁取ったそのカードは、なんの変哲もないインクで書かれてあるようで、裏面には一輪のすずらんと、「あなたの私から」と外国の言葉で記載していました。誰かしら、とようやく考え及んだ時、執事が呼ぶ声がしました。私はそのまま部屋の中に戻り、窓を閉めました。
妹はまだ五歳で、やんちゃな盛りの中に気高さを持っています。よく私にお姫様の話をせがみ、絵本と共に私の部屋へ訪れては枕を抱きしめながら私の話を聞いています。その姿はなんとも愛らしく、感情を込めて話せば話すほど、彼女を喜ばせることができます。
すると、妹はトマトスープを飲んでいた手を止め、話しかけてきました。
「おねえさま、マリーは今日、おとうさまのところで寝なければいけないの。おとうさまったら、マリーがいないとさみしくってしかたがないそうですの。だからおねえさまの部屋へは明日うかがいますね」
さも、すべてのものから愛されているといった口ぶりで妹は悲しそうに私に語りかけ、その報告に私は少し迷いました。明日は誰かが私を迎えにくるはずで、妹と絵本を読んでいる暇はないのです。
「そう……それは残念だわ。ただ、お姉さまは明日の夜、予定が出来るかもしれなくて……」
「なに、どこか出かけるのか」
父が話に割って入ってきました。普段はにこにことお優しいお顔をされているのに、娘たちのことで知らないことがあるとこうして不機嫌になるのです。私は後ろに立つ執事のマロンに視線を這わせ、マロンはそれに対してにっこりと笑いました。
「旦那様、お嬢様は明日ご友人とお散歩に出かけるそうなのです。私がご一緒しますのでどうかお許しください」
マロンはこの家で二番目に長い執事で、父も信頼しています。私はごめんね、とマロンに目配せし、マロンもなんでもない風に笑いました。
約束の夜はとても晴れていて、未だ満月ではないものの、ほとんどの地上を照らしていました。草木は眠り、昼はさかんに飛び交っていたモンシロチョウも、葉の裏で休んでいます。
私は緊張で、部屋の中でうろうろしていました。窓を開けベランダへ出ると、庭の様子がよく見えます。マロンは部屋の前で不審なことがないか見張ってくれています。まさか、連れ去られたりなんてことはないでしょうね。迎えに、とは、私はどうなってしまうのかしら。あることないこと考えては歩いたり立ち止まったりしました。
そこへ、月の光が燦燦と輝き出しました。雲もなく、星がそれを助けるように瞬き、目を奪われました。
「こんばんは、待っていてくださったんですね」
少し低い、若々しい声が聞こえました。けれども姿は見えません。思わず辺りを見回しました。
「僕です、あの時助けていただいた、リリーと申します」
私は何のことだか分からずに、けれども神秘的な光に包まれて声も出ず、狼狽えました。
「そう、あなたと同じ名前なんです。運命的ですね」
その声は、心の中に聞こえているようでした。リリーという男性を私は存じ上げませんでしたし、手をお貸しした記憶もありません。
「僕と一緒に行きましょう。あなたを一生お守りして、幸せにいたします」
「あっ……あなたはどなたですか……」
「……お忘れですか? あなたが執事と散歩されていた時、馬に食べられそうになった私を助けてくださったのです」
彼は悲しそうな声で私を諭しますが、なかなか思い出すことができません。マロンが不審な音に気付き、部屋に入ってきました。大きな刺股と気合の入った声で、だれだ、と叫びます。
「マロン、待って。この方私とお会いしたことがあると言うのよ」
私はいきさつを話し、マロンにも思い出してもらうよう助けを求めました。
「馬……リリーと言うんですか」
マロンは警戒を緩めぬまま記憶を辿り、そしてとうとう思い出しました。
それは、私が五歳の時のことだそうです。馬に乗ってマロンと従者の三人でお花見に行こうとした途中、道端にすずらんの多く咲いているところに出くわしました。私は喜びいさんで馬から降り、近くですずらんの道を歩きました。その時です。馬がそのすずらんを食べはじめてしまいました。
「あっ! だめよ!」
私は馬の顔を力尽くで押し戻しました。馬はしゅんとした顔をしましたがすぐに離れてくれました。
私はすずらんに向き直り、よかった、とその頭を撫でました。それからまた、私たちは少し先の広場へ向かって歩き出したのです。
「あのときの、すずらん……」
「そうです、思い出してくださいましたか!」
すずらんはなんとも嬉しそうな声をあげて再会を喜びました。
「僕はあなたに相応しい、強く優しい男になりました。僕と共に暮らしてください。あなたを永遠にお守りし、幸せにいたします」
声はいつからか姿形を成し、私より背の高い男性になりました。私はこれまで会ったことのないような凛々しい方で、月の光に照らされた姿に見惚れてしまいます。
少しの間、音のない世界に私は包まれました。人生の岐路に立たされて足がすくんでしまったのです。私はここで、この方と共に生きるかこの家で過ごすかを決めなければいけないのでしょうか。それは私にとってとても大きな決断で、どちらかを選ばなければならないなんて荷が重すぎます。
つい、涙がこぼれました。するとすずらんは私に近寄り、長い指でそれをすくいとります。
「こわいことはありません。あなたは私と共にこの世の永遠を生きて、ご家族の皆さんを守りながら暮らすのです。僕をどうか、信じてください」
その瞳の強さ、深い青が、私の心を揺さぶりました。私は一歩踏み出し、彼の胸へ抱かれます。彼は私をそっと抱きしめ、ほおを撫でました。優しく暖かな指で触れられて、これまでの不安が吹き飛んだ気がします。
マロンは私たちをひやひやした目で見つめていましたが、私はわかりました。
「マロン」
私の声に、マロンははっとしてこちらを見つめ直します。私は続けました。
「私、すずらんと一緒に行くわ。きっと大丈夫、私、幸せになれる」
「お嬢さま……」
「マロン、ありがとう。お父さまとマリーにもよろしくね」
私がそう言うとすずらんもうなずいて、ぎゅっと私を抱きしめなおして飛び立ちました。
空は少し白み、朝が来るようです。陽の光がじわじわと温度を高め、新しい日常を明るく照らします。初夏のある朝、リリーとすずらんは別の街のふたりの家へたどり着きました。そこは多くの花の咲く家で、なかでもすずらんの花はりんりんと可愛らしい音を鳴らしながら咲いています。ふたりはここで幸せに暮らし、永遠を過ごしました。
ときめきの丘