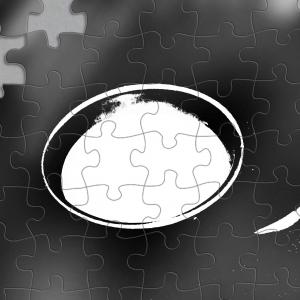「英雄譚」
雨が踊る夜、か細い白の縫糸を上機嫌にくるくるリボンの真似して回す夜。見捨てられて忘れられた古本の、三日月のおつかい真綿の蛾の羽ごろも、星屑を散りばめられて言葉達が目に目に姿を化えていくのは、草木の夜更かし丑三ツ時。
「約束」と言う名前の錆びた鍵の束で、想い出の扉を一つ一つと開けては閉める老夫あり。彼は此処図書塔の番人、記憶の灯台守、昔はさぞや美麗であった故国に住まう唯一人の人である。
昔、この国は輝いていた。オーロラが光を失わないように、この国も光を失わなかったのである。それでも国は忘れられ、一片のハギレしか残らなかった。
この小さな布片は蓬と梅の花を縫いあわせたもので、彼のしなびた片手に握れるほどのものだったが、これが何の一部であったのか、それともこれが全てであったのかなどは分らない。分らないけれど、老夫はそれを溝の泥に捨てようとは思わなかったようで、夕日が昇る朝から月が昇る夕方、雨の真夜中までひと時も手放さないでいたのである。
図書塔は忘れられた場所に建つ、そしてそれを見つけられる者はいない、塔の景色も出す音も全て建物内部で鎮まって、外に一つも様子を発さないから。内海だけに向けられたパレットもレコードも、外の刺激を恐れるもの。だから救けも求めない。それはまるで老夫の人生そのもののような在り方で、彼が自分と図書塔をかさねているかは難しいが、居心地がよさそうなのはよさそうだ。だって、今日も塔に向かって
「やい、この木偶ノ坊め。いつまで此処に突ッ立ッて居やあがる。いつまで居るんだこんな場所に。」
挨拶をきちんとしているでしょう?それに、見て。鍵束だって投げつけないし傷が入らないようにいつもハギレで包んで持ち歩いているのだから。
「何だッてんで此の国に現れおった。貴様の目論みなど判っているわい、お見通しじゃ、お見通しじゃ。」
図書塔の内装は一日で変わる、毎日違う形と色の階段を老夫が昇る時、必ず呟く二言三言。
昇り終った踊り場から彼の読書は始められる、ドッカと床に腰かけて口を尖らせギョロギョロと両眼玉を歩かせる、一人きり。
「第一話目」
「全部父さんの所為だ!」
最愛の弟が心を病んだと知った時、青年は母親の前で父親に怒鳴った。
「お前の所為であの子はおかしくなったんだ。」
父親は青年にそう言い返した、妻の前で。二人の言葉と母の姿は、布団に潜る少年に聞えていた、彼は眠っているのではなく、声を立てずに涙を落すのが上手になっただけであった。
青年の父親は牧師であった。若い頃から祖父に神に仕える者としての立場の教えを受け、その界隈では名の知れた人であり、妻と子供二人に恵まれ、そして家族は飢えることも暴力を奮われることもなく進んでいったが。
青年はおとぎ話が好きだった。一匹だけ家に居るぬいぐるみで物語を作り、弟に読ませた時がよくあった。最初首をかしげていた弟もだんだんお兄ちゃんの楽しいお話に笑うようになり、学校を卒業する頃には家で一番の読書家に成長していた。
「もっとたくさん、いろんな話を聞かせてあげたい。」
弟はうさぎのぬいぐるみをいつも両手で胸に抱きかかええる子だった。
「生きた動物と触れ合えたのなら、どんな物語を思うだろう。」
動物に携わる仕事で彼と相性が良かったのは役所内の動物保護課の業務であった。生体販売が禁止とされたこの国では、動物を家族にするには動物保護課が開く研修を月に五回以上受け、試験に合格した人が次のステップ、トライアルお預かりに進むことを認められ、相性が良ければそのまま家族の一員に、相性が合わなければ一旦保護課に動物を帰し、職員とヒアリングを交えながらお迎えする子を決めていくのだ。
そのため保護課はとても忙しい。全国に数ある役所も人員が一番多く割かれているが、飼主候補の調査、研修、お迎え後の定期的な訪問調査…人を監視確認する業務に追われ、動物達の面倒を手厚く見るのは順番が後になってしまっている。
「動物達の面倒が見たい」
青年は保護課を目指し資格を取得するための勉強に励み、優秀な成績で見事合格したのである。
「第二話目」
絵本は夢を見ていたのだ。誰かに背表紙を撫でられて目と目が合って頁をめくられる表情を。その顔は喜びに潤み悲しみを花開かせる時もあるのだろう、そんな風の日の刻に自分の声が届くのを、触れてもらえることを大切に夢思っていたのである。
「その願いは叶えられたのか?」
老夫の問いに星は瞬いたが、ひどくゆったりとしたものだったので
「お前は惑星みたいな奴だ、愚鈍な奴め。」
竹箒で暮葉をジャッジャッと掃き散らす。
「何故儂が此奴の面倒を見てやっているのかの、やれ、暇な爺さんは仕事の遅い雑用係さ。こんな鍵なんぞ大事なくせに儂に任せよって、ただじゃあこき使われてやるものか、爺の性根が如何に厄介か思い知らせてやる。そうしたらもうこンな木偶ノ坊とっとと姿を消してくれるだろうからな。」
じいさん得意気だ、でもあゝ見て御覧、図書塔にとっては出現も消失も自由気まま。今まさに姿を消したり現れたりを明滅させて楽しんでる。
さあどうします老夫殿?
「目が苛立って適わんわい!ネオンの化け学を鵜呑したような真似しおってからに、もういい、建つならずっと建っとれチカチカするな!」
老夫は怒って階段昇りいつもの場所にふんぞった座った、今日はどの子の呼び声が届くかな?
「第三話目」
弟は職場でずっと泣いていた。涙声で電話をしメールをし、資料を作りゴミを集めて捨てに行く。
「助かる」
「ありがとう」
と褒められることがある。当然の労いは、正社員がしたくない仕事をこなす弟への労いたりえているかなんて、その場の人達は考えない。
一日中心は濡れて、全身が漏れなく濡れて、そうして心の部分小さな歯車は錆びて、きしんで、動けなくなってしまった。
うつ病患者は会社に要らない、休職を与える価値も無い。士気を上げるのに濡れて湿った雑巾は必要無い。
さよならに呪いを込めて、弟は仕事を辞めた。丁度三ヶ月ごとの更新の日であったからと説得を受けて、とても、とても、丁寧で丁重なご説明をどうも。
心療内科に通う準備は整っていた。人は怖いけれど社会復帰を目指して、道中の時雨榎の御神木の横の階段を昇り月を仰ぐ。弟だけの友達は、その月の光に照らされながらふわりふわりとやって来た。
「マカロンと、お雛さま。それからスミレのサーカステント、幕の中はまだ見ちゃだめなんだって。羽が生えたマカロンはね、其処等の鳥と同じくらいうつくしいよ。それで、音符のダイヤモンドが、半音のトパーズと手を取ってね、一音上にずれたメヌエットを教えてくれるのよ。」
弟は幼い頃からの含羞の微笑みで綴っていた、物語、自分のための物語を、自分一人で。
「第四話目」
昔聞いた民謠で、雪の蛾の噺があったような気がする。この図書塔におさめられているかは知らないが、探してみようという気になったのはどうせ暇だと思ったからでもなさそうな。
この鎮魂の塔へ集められたもの達に規則は無く法則も無い。分類にすら分けられる事を認められていないこの空間で目当ての本を探すのならば、心と頭に思い描くしかない、読みたいものの切れ端を、羽たたきよりもピアノ線の震えよりも細かい音、その声が自らを呼んでいると気が付くように。
「おお、これか。」
老夫は国が去ってから此処に入り浸っていたので、説明も無い図書塔での振舞方を手さぐりながらも確実に掴んでいた。
「あゝこんな表紙だったかなあ。」
春の月、薄桃色のぬくい雨が糸を枝垂れる刻の頃、花は正体を次々雫と顕し、人が目を覚ましていても見えない隙間の夜の刻、一匹の蛾が月の恵みをいただく身体で飛んでいた。翼は朧にたなびいて後ろ惹かれる生娘の髪のなめらかさ、季節の香り、でも…
「雪じゃあないな。間違うたか。」
中途で止めて白い頭をぼりぼり掻く。
「一度開いたら終いまで読まなきゃならん。」
ぶつくさ口を尖らせてばかりも仕様が無いので胡坐をかいてさ
「少しは有難く思え。お前もどうせ何処ぞの扉からのこのこやって来たんだろう、全部きちんと開けてやったからね、儂に連られてふらふら来おって、おとなしくしろ、読んでやれんだろう。」
バーコードの無い画用紙に積んで重ねた文字と絵達、それはまるで、幼い誰かを喜ばすために描かれたようなたどたどしさ。
「第五話目」
自分で物語を描き始めた弟は、もう兄の話を必要としなくなっていた。
その日から弟は大きな音や怒鳴り声、苛立ちの溜息に恐れ新しく音楽も好むようになった。ステンドグラスの回廊、ガラスタイルのサーカス・シルクハット、雪の王国、包み菓子の囀り、朝顔の手鞠と星屑の白粉花。愛された言葉は物語へと紡がれて心に滴り涙の見分けをつかなくした。そして父親は彼の一族で最後の牧師となることを決めた。
北極星は搖るがないのに、羅針盤は往々にして狂い出す、次に指したのは正しい北ではなく、仇のような東の方角。弟は眠る時でも隣に鼾をかく兄の機嫌を伺っては布団を目と口に押し付けた。
「第六話目」
図書塔に潜るものは、自分が其処に居たことを記憶しない。湖の淵、記憶のゆらめきに佇む場所は誰の記憶にも残れないのだと言う言い伝えは、老夫が思春期の頃から言い継がれて来ていたらしい。
「儂は伝承や言い伝えなど嫌いだ、信仰も嫌いだ。信じないことと嫌うことは別々のもんだ、儂は大嫌いなんだ。」
例えば、水の神さまがびっくりされるからお湯を流す際は冷水で埋めるか水と一緒に流さなくてはいけない。言葉には言葉の神さまが住んでおられるから乱暴な言葉を発してはいけない。海で鯨を獲れた日には肉を捌く者はその地域の長が正装を整え錦の幣で感謝を捧げて一等上質な美酒を供えなくてはならない。大神さまである梟が御自ら語られた物語、悪い狐が人間の英雄を苦しめて逆に懲らしめられた反省の言葉の物語、人でも動物でもない白波や木の葉の語った物語…
「儂の居った国ではな、こんな根も葉も腐った話ばかりであふれかえっていた。挙句の果てに消されてしまった、愚かな住民しかおらんかった、皆慎ましくにこやかに、それでも悲しみも怒りも苦しみも知っている者だった。」
塔の外には人骨の踏まれて破片と散ったかけらと家の崩れたタイルが文目も分ず土に身頃を半分埋めている。
「儂は何故お前を見つけられたんだ?」
柄の交ざったハギレを手の平でほどく、鍵束は増えもせず減りもしないのに、毎夜毎夜老夫は決まってハギレと鍵束をまじまじと見つめていた。
「人に手入れされなきゃあお前も崩れるのか?」
翡翠の縫い合わされた海の底の壁をトン、トン、と叩く。
「どうせ一人でやっていけるだろう。」
春宵の蛾の物語は読み終ったらしく、小脇に抱えていた。
「第七話目」
弟は折り鶴を飛ばすのが上手だった。初めて青空を知った娘のような指先で、丁寧に丁寧に鶴を折る、外の遊び声にも、電子音も気に留めないようにして一羽二羽、三、四。千代紙たちは何の為?命を吹き込まれてくるくる遊ぶ彩りの紅葉たちと、うさぎのぬいぐるみを喋らせて、控えめに跳ねて楽しそう。
雪の夜、スズランの月の光の日、眠りにくい弟の枕辺に、一羽すてきなお客さまがやって来た。
―こんばんは。
瞳の紫水晶を粉雪に染めて弟を見つめる雲の妖精は一匹の蛾であった。兄は仕事に疲れてよく眠っている、弟は小さな声でそっと聞く。
「君は?」
―まだ名前が無いの。
「じゃあ、僕が付けてあげる。」
―いいの?
「嫌なの?」
―いいえ、そんなことはないわ。わたし達は嫌われ者だから。
「虫だから?」
―そうじゃないの。虫を愛してくれる人達もたくさんいるわ。あのね、わたし達は虫の姿をしているだけで、本当は虫じゃないのよ。
「どういうこと?」
―知りたい?
「教えてくれるの?」
―ええ、貴方が望むならいくらでも。
「ねえ、」
―なあに?
「君は、とても綺麗だよ、谷間の姫百合。」
―……
蛾はパチリと一回瞬きを深く、表情の変わらない顔で微笑んだようだった。
―ありがとう。……ステキな、名前ね。
「今晩はスズランの月だから。月の御使いかと思ったんだ。」
弟は兄に背を向けて横になると、姫百合をまっすぐ見つめて囁いた。
「僕の名前はね…」
その日から弟は姿を消した。家族の記憶からも。
「第八話目」
水晶の王国、花々の城壁、巡る川二条藍は深くも底まで澄んで。水と草木を愛した王国の名前は表紙が焼け爛れて文字が分らない、背表紙は千切られて接合部が剝き出しになってはいるものの、指まではバラバラにされていなかった、
まだ読めるから
まるでそう話すかのように。
この名前の聞えない王国にはたった一人の魔術師が暮らしていた。年齢は千年ちょうどだが見目は人間の娘と変わらない、黒髪はつやつやと光を吸い、瞳は朱鷺色の空に染まった泉の淵のような深みを湛えているものの水晶の輝きは消え失せずぱっちりと惑星の放つみたいな瞬きをする。…名前はナイフで裂かれたらしく頁はズタズタにされているからまた分らない。
魔術師は人間ではなかったけれども人間は彼女を差別しなかった。
「見た目が違っていても同じ命だもの。」
だからこの国は水と植物に愛されることが出来たのだ。王国は清く澄み、冬の雪は温かく夏の日差は涼しかった。
「〇〇さん、一緒に遊びましょう。」
笑い声は黄昏をも穏やかに染め、月も何の心配も無く夜の時間を治めていた。
愛した国、愛された国。それは他所者には嫉ましくて憎くて奪いたくて、歪んだ幸せを手に入れたくて。
後世になど残し伝えてやるものか、破壊の本質を略奪者達は知っていたのである。だがこの場所では必ず報いを受けることまでは知らなかった。
魔術師は初めての破壊でその本質を知ってしまった。彼女への返り血は腐っていてひどかった。
言い伝えでは、国が滅びた後一輪の姫百合が灯るとされていた。その花は深い谷の崖に咲き、炎にも風にも尽きさせられること無く在り続けるのだと。
「君は、その姫百合なの?」
弟は温かい寝間着姿のまま、とある草辺に折り鶴達と一緒に座っていた。蛾は首を横に振らない。
「話したくないならいいんだよ。辛いことだったんでしょう、きっと。」
弟は蛾をそっと胸に抱きしめる。紫陽花の夜露が瞬く夜だった。
「第九話目」
「聞いてくれるか。」
老夫の目は外覗きの窓から久々に外の夜空を見つめていた、曇りの夜は図書塔の中には存在しない。
「儂の生きとった国はある日こんなになってしまった。いい国は必ず傷を負わされ傷を広げられそうして手当の甲斐無く死んでいく、善良を続けることの如何に困難なことか、自分も他人も障壁になっていくのだから。
儂は仕事でアイスクリンを売ったこともある。当世の洒落たスイーツなど作り方を覚えられんかったが、アイスクリンは幼い時のごちそう菓子だったからな、母さんが作ってくれるのをいつもよく見とったで忘れなかったんじゃ。今でもはっきりと昨日のことみたいに憶えとる、客達の嬉しそうな顔に声…」
其処まで語ると、彼はいつも呟く。
「どうして儂等の国を滅ぼした。」
雲間から射す月の灯は、今の彼には僅かすぎてよく見えない。
「ずっと祈りに生きて来たのに。」
その後の言葉はいつも噤む。それは、一つの信仰とも、一つの職業病とも呼び得るものだった。
語り掛けるのは妻の形見の日記帳、色の淡い頁には幼い時の子供達との日々が一言一言丁寧に綴られており、何度涙のかたを付けただろう。
老夫は昔牧師であった。教会も素朴ながら立派であったが、ただ一晩にして妻も息子も失ったのである。
「第十話目」
足手まといになるな、と言ったことがある。
「あの時は父さんも大変だったんでしょう、教会の存続も危なかったんだもの。」
学校を中退させ、牧師の仕事を手伝わせたことも。
「父さんは俺の将来を案じてくれていたから。」
弟は信心深かった。
「やだなあ父さん、弟なんて俺にはいないよ。」
親戚の集まりの際、不仲を悟られまいと平静のふりをした。
「皆を不安にさせたら駄目だろう?」
いつも自分のことしか考えていなかった。
「人間なんてそんなものさ、誰かを養うのならその人の分のも考えなきゃならなくなる。」
ステンドグラスの破片を汚れたスカーフの上に載せ、ハギレと鍵束を横に添えて祈りの姿をとる。そうすれば自分に都合の良い息子の声が心の中を廻りだす。
子供は二人居た筈なのに、或日妻も長男も忘れてしまった、否、初めから三人家族だと静かに信じた目をしていた。
次男はいつも父親と長男を喧嘩させないように微笑んでいた、妻は闊達な女性で、弟の肝は父親ゆずりな所があったと思う。何とか家族を繋ぎ留める、細い楽の音は空気を震わさないと聞えない、意味が無い。
「お前は今生きているのか?」
グラスの欠片は図書塔の天井(今は星座の空)を映すばかり、
「もし生きているなら、いいや、死んでしまっていても……謝らせておくれ。妻とお前の大好きな兄さんの分まで。謝ることを許しておくれ。」
懺悔の言葉に光は灯らない。
「第十一話目」
「もう読めない本なんて捨ててしまえ」
これは、何故なのだろう?
「ぬいぐるみを大切にするなんて幾つなんだ」
どうして君が決めているの?
「そんな子供向け番組、もう誰も見てないよ」
じゃあ君等は何を見ているの?
同じ国の中でも文化への認識は勿論違っていて、でもそれは多様性なんだと皆笑って受け容れあっていた。受け容れるけれど認めない、本心はいつも薪を炉にしたグツグツと強火な炎で焦げている。
多様性の料理ではすぐに爆発の恐れがあるから火を使えない、使わない料理は万遍無く配給されるが、人は煮込み料理や焼き料理炒め料理を腹一杯食べたいもの。難儀なり人間、何故平和に刺激を欲するのか、何故平和が文化を生むのだと気が付かない見ようとしない。
そんな君達こそいらないんじゃないですか?
捲った頁の中から天地創造の言葉達が声を上げた。
「わたし達ならこの国神話の再現出来ますよ、言葉どおりになるように!」
じゃあ、最近興味の湧いている世界樹の物語の始まりを、此処に。
図書塔はその時から建っていた。老夫一人を光から庇うように。
「あれは結局、一体何者だったんだ?」
例の光は少し黙っていたがスッと消えてしまったきり、あの後何かを仕掛けて来ることは無いが…
「儂等の国はもう滅びていた。最初は救世軍かと思ったがな、一人がぶつぶつ呟き始めて本を開いて、その直後あの妙な光を撒きよった。でも何も、一つも変わってはいない、本当になんだったんだ、オイ、」
ゴツンと紫水晶細工の古時計が埋め込まれた白亜の壁を殴る。
「知っとるのなら教えんかい!それとも知らんふりを決めこむか?前の奴等は何者だ!」
脳天にドスッと一冊の本がまあ無造作に置かれた。「冬の蛾が自ら謠った話」、絵本である。作者名は記されていない…
「まるで先程の春の蛾の本のようじゃの。」
読み終った春宵の蛾の絵本と同じ小脇に抱え、今日の踊り場に腰を下ろす。
「第十二話目」
わたしは雪の灯から紡がれた命でした。一匹の蛾は愛を知るために生みおとされたのです。わたしの生きよと言われた國は朝に夕日が昇り夕暮に夜空が昇り、夜更けには雨が透明に降り月をひと時も曇らすことのない土地でありました。草花や樹々は繊毛にいたるまで薄紫に藍をといた水晶の露に覆われて幸せにも飢餓を知らずに星の光を空気へと放ち呼吸はいつも潤っていたのです。
わたしや他の命が生きるうつくしい國の名はまだありません。名前が無くともわたし達は充分に光の中に在り続けることが出来たのですから。
わたしは雪の灯から姿を変えましたが、桔梗の花から命を貰った子が居たのです。その子は不思議で優しい力である魔術を使う少女。彼女の瞳とわたしの瞳が初めてふれ合った時、わたしは恋を知りました。スズランの月の夜のことでした。
谷間の姫百合。貴女は何者でも無い一匹の蛾にその名前を与えてくれ、いつも傍に居てほしいと口づけをも恵んでくれたのです、國を想うのとはまた違った想い、これは一体何かしらと貴女に問うと微笑んでくれたのね、それが愛というものなのだと。
愛を知った虫は幸せでした。わたしはこの國でいちばんの幸せ者だと深く想いました。
愛した國、愛された國。それは他所者には嫉ましくて憎くて奪いたくて、歪んだ幸せを手に入れたくて。
破壊の本質を知ってしまったあなたは最後に自分の喉を突きました、あの表情をわたしはいつまでも憶えている。
泉は濁り、雪は温度を忘れて唯冷たく降るだけとなってしまい、國は止まない冬の國となりましたが、わたしの命は尽きていません。でも、それだけ、わたしは貴女が亡くなった時から、また何者での無い名前も無い一匹の虫もどきに戻ったのです。
冬の蛾はもう飛べません。終わらない白に小さな身体を前後覆いつぶされていくだけなのです。
「第十三話目」
「国が滅びる前にこの國は滅びていたのか。」
短い伝承を読み終えた老夫は唸るように呟いた。
「また飽き足らず破壊しに来たのか?儂が生きているから!」
怒号は塔の余す所無く強く鳴った。
「そうか、そうか!なら死んでやる、そしたらもうこの国をどうこうすることも叶わない。」
何か使える道具はないかとボロ切れ中を漁るもハギレで首は括れないし鍵束で心臓は貫けない。老夫は呻き膝を抱えて蹲り、焦燥と苛立ちと無力感から前後に前後に搖れ出した。
「うぅ、ぁあ、うぅ、ぁあ。」
死ぬことも出来ない。
老夫、なら死ななくていいのだ。
鍵束が触れてもいないのにガチャリと動いた、のを見ようとした忘失の老夫は扉が一つ勝手に開くのをいつか見つめていた。
「何で勝手に開くんだ。」
ひんやりした床を這い、扉に寄れば、声がする。
―ねえ、エスメラルダ。きっとこの王国をよくして行こう。
「誰だ?」
声の主の姿は扉向うの吹雪の中でよく見えない。
「其処は何処なんだ、君は誰だ?」
―この雪が開けたら、また樹を植えればいいのだから。
樹?こんな雪風だらけの土地に命が続く筈が無い。老夫が思い込んだ瞬間、雪が晴れて話し相手が灰色の空の下に描き出された。
此処は雨の王国、常若の樹ユグドラシルが結ぶ国、声の主、青年はこの王国の唯一の魔術師であった。だがその相貌は…
老夫が言葉を失くすのも当然で、彼は老夫の次男と瓜二つの顔立ちであったから。
「第十四話目」
もう白い蛾は雪の重みで動けなかった。もうそろそろ眠る時かしら、そうしたらまた貴女に逢えるのかしら。
「見て御覧姫百合。空を鶴が翔けてゆくよ。」
「鶴は吉兆と信じられているんだ、ほら、あの美しい翼が分るかい?」
ごめんなさい、わたしはあの時鶴の姿よりも、鶴を見て喜ぶ貴女のことを見つめていたの。よく形を思い出せない。こうなるのなら貴女の見たがっていた美しい鳥、わたしも目に焼き付けておくのだった、そうしたら貴女をいつでも思い出せたかもしれないのに。
ごめんなさい、ゆるしてね。貴女に恋をした一匹の虫をゆるしてね。わたしが涙を流せたら、貴女ともっと一緒に居られたのかしら。
かさり
目を塞ぎ始めた瀕死の蛾に、紙が摺れるような音が聞えた。
「これは…」
彼女の頭の上をくるりと廻っていたのは千代紙で折られた鶴。最初は一羽、次は二羽、三、四とかつての内海をなぞるように円を描き飛んでいる。それに合わせてすすり泣く弦の音が。
「誰かが悲しいと伝えているわ。」
貴女は困った人を放っておけなかった。
ならば、わたしはその足元と道を照らす火になりましょう。
力をふり絞って白い大地を蹴り星の嵐の中へ飛びこんだ。
弟は、彼女と逢ったのである。
「第十五話目」
老夫の声は青年には届いていない。それもその筈、青年は物語の中の人物として話し、行動する、よって読み手側のことなどその存在も知る訳は無いのだ。物語の本の名前は『ユグドラシル』、世界樹を育てる使命を持って生まれた青年が主人公で、エスメラルダと呼ばれた雄鹿は雪に燃えて生まれた如く端正な姿をしていた。
「エスメラルダ、この国は美しいね。」
―美しいけれど、残酷な幼稚の世界だ。
「それでも僕は君を見つけられた。それはとても幸せなことなんだろう。」
―それを幸せと認めないのがこの国の住民であろうに。
「いつか、いつの日か分る日が来ることを祈って僕等は何度も樹を植えて育て続けるんだよ。」
―酔狂な魔術師だ。その所為で何度殺められた?
青年は少しだけ俯いたが、柔らかな微笑みは変わらずのまま。
「行こう、エスメラルダ。そろそろ吹雪がおさまりそうだ。」
青年と雄鹿は丘をくだり初桜と夕暮の桔梗咲く湖畔の町へと歩き始めた。
老夫は扉の中へ入れない。塔の番人は物語に踏み入ることを許されていない。
「あの子はもう儂等の世界には居られないのか?」
兄にも母にも忘れられ、自分のことまで忘れてしまって、
「じゃあ儂は何故おまえを憶えているんだ?」
御伽噺の温もりの内で叶わぬ理想を追いかけ続けるように仕上げられていても、
「読むことしか出来ないのか。」
傍観者の権利か罰か。
「第十六話目」
魔術師の青年の名前はシャイアと言った。シャイアは相棒エスメラルダと共にユグドラシルの大樹が息づく王国を護り続ける守護者の役目を持ち、先程も申したが世界樹を育むことが使命であった。湖畔の町に生まれて育った彼は、故郷の風景を体現した身心で生き続け千年経っても髪色は藍の水面を映した空の色を宿し、瞳はかつて沈んだ古代の地層鮮やかな彩色に恵まれ睫毛が深くその興味を柔らかに覆う、いつも優しく微笑む口元は印象に反して闊達な物言いそれでいて穏やかさを失わない声。遠い昔父と母から贈られた彼の身の丈ほどもある木の杖は今でも莟を守り咲くことはない。
シャイアは初めてユグドラシルが伐り倒された時、その一番小さな枝から紡がれた命だった。
人間は自らのルーツを時として知りたがるが、祖先を損なうことも容易に出来る種族でもある。恨み辛みを先祖に託け攻撃することで現在を守り、それにより未来も守られたと信ずるのだ。手の指足の指記憶の捲りでは足らない数伐られ続けた世界樹は、人の感覚で語れば五千年は生きている、そして青年も同年齢、魔術師には休息としての死は訪れるが人のような死は訪れない。
世界樹を守る者も同罪だと、人間の物語はいつもその結末に辿り着き、魔術師は粛清され根城は伐られて燃やされて、目を閉じる前には必ず暴力だけが声高らかに歌っていた。
エスメラルダは世界樹を食むことで生命を吹きこむ四頭の雄鹿の一匹であり、樹が倒される直前肉体が天体のように透け始めて指の一本声の一つも動かしかけることが出来なくなる。エスメラルダ達がまた身体を持てるのは、シャイアが鬱憤晴らしの犠牲となった後だけで、吹雪煙る中、シャイアを再び目覚めさせるのが使命であった。
―何度私はお前の遺体に口づけしてやればいいのだろうな。
「その時はまた頼むよ、相棒。」
物語は終らない。いつまでも堂々巡りをくりかえしくりかえし新たな展望が頁の上で開花することはない。
「どうにも出来ないのか。」
老夫のひどくしゃがれた声。
「儂はまた家族の死を見なければならんのか、何度も何度も。」
シャイアに手を伸ばしても、届く訳も無く、パタンと扉は閉められた。
「第十七話目」
一方的に閉じられた扉の前で大理石にへたりこむ老夫は鍵束を光の無い目で見ていたが、一本減っていることに気がついた。
「この扉のぶんか?」
ハギレでおそるおそる閉じた扉の銀のドアノブを撫でる。と、木造りの暖茶色のそれは、すうっと息を引くように黒く見えなくなってしまった。
「もう読めないのか。」
何處かに安堵の心が交じっている声は小さかった。こんな物語を押し付けで見せるなんて。怒鳴っても嘆いても図書塔は共鳴しない、分っていたことがようやく分った。
「あの子はもう、儂等の世界には居られないのか。」
真っ先に助けに行きたくても、出来ない
「物語の住人になったのか。」
抱きしめられるのは本一冊の姿だけ
「それが、あの子の願いだったのか。」
守らなければならなかった存在に先立たれた老夫の想いは幾許か。
「第十八話目」
外の壊れた王国だけれども錆びた蛇口からは生前の如く綺麗で安全な水がほとばしっていた。キュッと軽く小気味良く蛇口を捻った老夫は水満ちたバケツを持って焼けた田畑の間をのそのそと歩いていた。塔の中に入ると窓辺に向かい、ハギレをちゃぷちゃぷと浸して絞って硝子をキュッキュと磨き始めた。
「手入れなんぞされたことないんだろう、どうせ。ずっと一人で建ち続けていました、とでも言いたげな奴め。」
彼の意図を汲んでかどうか、今日の図書塔はあちらこちらに窓が刻まれ、おまけにどれも少しずつくもっている。まあ、やりがいがありそうな仕立てだこと。
「儂に気を遣うのなら窓を減らせ!昨日は片手で数える程だったのが急に三十枚以上に増えおって!」
張りの戻った声は塔によく響いた。溜息を零し零し老夫は窓掃除のおじいさんとして働く。すると、彼の視界に小さな砂煙がふと映った。
「何じゃあれは。」
もう少し近くで見ようと塔の入口に向かったら
ドシン
門が勢い速く閉まり、おじいさんは腰を抜かして尻もちをついた。
「ど、どうした⁉」
出るなとでも叫びたげの塔の行動におじいさんは驚いた。自分を庇う動きをしたのはこれで二度目。
「まさか前の光る奴等か?」
門は堅く口を噤み木の葉の音も漏らさない、おじいさんは思わず同じように口を噤んだ。
声がする。
「本当に居たの、老人なんて。」
「でなきゃ塔が庇う筈無いでしょ。」
おじいさんの国とは違う言葉。けれど意味だけは心の内に伝わってくるのは
(おまえさんのおかげか?)
足音が離れて行く。やがれ声の正体達からは一音も発されなくなったと感じるほどに去った頃
(まるで水に潜っとるようだ)
門は開き図書塔はまた荒野に建ち続けた。
「素知らぬ顔をしよって。」
ハギレはいつしか乾いていた。
「一体奴等は何者なんだ。」
磨こうと何気無く手にした鍵束がチャリンと鳴った。
が、それはまるで大教会の大きな鐘が低く唸るような響きとなって塔全体に吹き荒れた。
扉が開く小さなきっかけの音は、嵐の呻きにかき消されて……
「第十九話目」
おじいさんは眠っていたようで、家族を失う前の食卓の記憶を見ていた。佇む自分に四人は勿論気が付かない、気付くとその瞬間ささやかな笑顔は音を立てて崩れてしまうのだろう。
あなた
父さん
お父さん
幸せは確かに息をしていたのだ。
「おじいさん。」
涙の視界に映らない背後から、唐突に声を掛けられまばたきをすると、其処にもう家族は居らず。
「おじいさん、おじいさん。」
「そんなに言わんでも聞えとる。」
しぶしぶ振り向くと、……声が出なくなった。彼の前に立っているお人よしそうな人物はシャイアであったから。
(すまなかった、すまなかった、どうか儂を恨んでおくれ。)
「シャイア。」
おじいさんは駈け寄り抱きしめようとしたけれど、身体は言うことを何故か聞かず、懺悔の言葉は間の抜けた別な声で言えなかった。
「おじいさんよかった、ご無事だったのですね。」
青年の若い頬の傷に干枯らびた指が触れた。意図しない二度目の行為におじいさんは察しがついた。
(儂は今物語の人物になっておるのか。)
動かせないのに動く身体、息子に話すのに言えない言葉、老夫は今、『ユグドラシル』の世界に潜り沈み始めているのである。
(……せめて、この老人がシャイアの味方で居続けてくれたなら)
老夫はおじいさんとなって、黙ってシャイアと話し始めた。
「第二十話目」
「おじいさんはいつもどこからやってくるの?」
「どこか当てて御覧。」
「僕等がこうして苗木を埋める時、必ずいるよね。でも樹が倒された時はどこに居るの?」
「どこか当ててみな。」
「おじいさん怪我なんてしてない?どこか痛くなったりしない?」
「おまえさんじゃないからそんなことは無いよ。」
「そう、なら良かった。」
―良くはない、シャイア、おまえまだ頬の傷が完治していないだろうあまり動くな。苗木もこの世界も逃げはしない。
瞳の紫水晶に憂いの淵の色を湛えてエスメラルダがシャイアに言う。
―その落ちつきのなさは何度繰り返しても治らないようだな。
「おじいさん、エスメラルダが僕をからかうよ。」
「お茶を飲みに来なさい、もう月が昇って雨が降る。」
「おじいさん、今日のご飯は何を食べるの?」
「おまえが食べないものだよ。儂が食事をする時は、おまえさんは外に出ていなさい。いつもどおり、湖の汀で遊んでいなさい。」
「うん…」
「さざ波の蝶々たちと一緒に居るんだよ。」
「はぁい。」
「第二十一話目」
シャイアがおじいさんと呼ぶ老人にはマカロンと言う名前が付いていた。マカロンはユグドラシルを植える時いつもシャイアとエスメラルダの傍におり、もっと言えば世界樹の根元でいつも湖に竿を垂らし釣れない魚を待ちながら、石で丸くきちんと囲った内で火を焚いている。
懐かしさは親しみへ芽吹き、シャイアは友人を知った。
マカロン老人は昔放浪者であったらしい、シャイアが生まれる前よりもユグドラシルが初めてこの国に根づいた前よりも生きていたのだと言う。
「あちらこちらを徘徊しただけで、冒険譚など持ち合わせておらんよ。」
「それでもいい、それがいいんだ。だからまたお願い。聞かせて?たくさんのお話を。」
彼は頬の傷の治りが遅いシャイアの目を見ると、いつも肯いてくれた。そしてマカロンのお家におじゃましてお茶をいただく。ここまでが樹が倒され吹雪の中から目覚めた後の一つのルーティンとなっていた。
マカロンの自宅はシャイアの育った湖畔の町から離れた山の麓にひそかに建っている。ユグドラシルの根づく湖は朱鷺色と桔梗の花、そして桜の雫で染まる水だがマカロンの家近く裏手にある湖はまた違ったものだった。かつて鮮やかだった水色は影をポタポタとそそがれ沈痛な物思いに耽る、澄んだ色の翳る水は森へ沁み込み樹木をひらかせ莟のままの花を生む。
決して終らないように、決して失うことのないように。
湖に映るのは葉陰からやって来る蝶々たち、手に呼ぼうと思えば水に潜り回るさざ波で相手をからかう、鉱石の身体は錆びることもなく。
「君達は何處から来たの?」
シャイアの故郷にはこのような生物はいつも居なかった。
「この王国が故郷なの?それとも世界樹が根づく前から暮らしていたのかな。」
―またやってるのか。
エスメラルダはマカロンの食事の手伝いを終えて家から出て来た。
―その者達は嘘をついて相手をからかうことで楽しんでいる。おまえの質問に正直に答える筈無いだろう。
「でも今度は教えてくれるかもしれないじゃない。」
―シャイア、それは楽観が過ぎる。この者等は妖精なんだ。
この王国では人間が住む町から郊外へ目を向けると、妖精の住まう村がいくつも点在している。町のはずれの山の麓にある石を積み上げて組まれた巨石の洞穴をくぐる人間は妖精の国に足を踏み入れることになり声を失う、そして妖精達の生きたおもちゃとしていつまでも死なないように遊ばれ続けるのだと言う。それはシャイアにとってはとんだ赤で根も葉も無い、だって人間が作り出した少し身勝手の過ぎる物語なのだ。
―おまえが人ではない魔術師だからかもしれないぞ。
「エスメラルダ、おじいさんは人間でしょう?」
―彼は巨石の洞穴の傍に家を建てて住んでいるだけで、妖精国の住民ではない。人間達が入らないように見張っているだけだ。
「でもこの子達がそんなに恐ろしいことをやってのけるふうには到底見えないよ?」
―毎度おまえにも私にも嘘をついてからかって遊ぶ者だ、増長してしまうこともあるだろうよ。
言い切るとエスメラルダはマカロンの番小屋に向って歩き始めた。
「あ、おじいさん食事が終ったのね?」
マカロンがシャイアに見せたがらない老人の食事を、エスメラルダだけは知っていた、そして彼が何故隠したがるのかも。
今日でこの歪な日常を閉じるのだと、老人はいつもとどこか違う目の色で雄鹿に告げていた。
「第二十二話目」
昔話の人物は英雄や立派な一族の長になって輝く結末で幕を下ろすことが多いかもしれない。その為の材料とされるのは主人公が生れる前から生きて存在していた者達、それは樹であったり花であったり鳥であったり全く異なる存在であったりと多岐に渡ることだろう。
ユグドラシルには、その樹が生えた時から根元に一人の獣が居た。この獣は世界樹が此処に根を張る以前から湖に住まっており、月を仰ぐことを知っていた者で、ユグドラシルを愛していた。獣は名を持たなかったが、名前が無くとも充分に光の中に在り続けることが出来たが、獣の住む場所が地下世界だと認識されたと同時に獣は名前を持つことになってしまう。彼の名前はニーズホッグ、ユグドラシルの根を齧り続ける泡立ち沸き立つ泉の竜、それは愛する世界樹から賜ったものではない。
人はニーズホッグを忌み、不吉なものと考えて光と闇は正対称なりと規定した。そして闇は悪影響を引き起こしやすいと認められ、彼について深く考察することは禁じられた。
「ニーズホッグ、影の怪物。」
「ニーズホッグ、闇の化物。」
「ニーズホッグ、死を喰らう醜いいきもの。」
竜は何かを守るためにその場に住み続けるというユグドラシルのかつて教えた物語は、焚書されて灰となって空に散った。昔々の存在は恐れられて悪となる、それは永遠を渇仰する人間達の手によって。
「第二十三話目」
一度目に世界樹が燃やされた日。ニーズホッグの孤軍奮闘も虚しくユグドラシルは人々の感情を全てその根に受け入れて幹は罅割れ枝は搖らぎ葉は震え白露の雫は砂と散った。彼は槍や弓矢で襲われはしたが鱗には切り傷もかすり傷も喰らわず逆に人間どもを喰らい、累々と重なる屍を牙で裂いて骨一つ皮膚片一つ残さなかった。
痛みの無い肉体は焼け跡に轟音を立てて倒れ、樹の在った湖は干上がり町から人間は消え風ばかりが寂しさにひゅうひゅうと吹き迷う。国は滅びた。世界樹の守り手は今に伝わる話のとおり恐れらるべき竜となってしまったのである。
血走ってもう戻らないかつての水晶の瞳は燃やされ伐り倒された世界樹を見つめた。黒煙に濁るこの涙が君をまた目覚めさせてくれたのなら。だがこんな醜く汚れた雫では命を奪い喰い尽くす他叶うまい、ニーズホッグ、ニーズホッグ、毒の泉の黒い竜。
「もうこの姿でありたくない。」
横たえた抜け殻の身体は干上がった湖に手を伸ばす、そしていつも座っていたあの場所に戻った。
「物語を紡ごう、いつまでも世界樹が在り続ける物語を。太古に存在していた不死鳥みたく華々しくなくて良い、何度でも何度でもユグドラシルを存在させられるお伽噺だ。私一人ではまだ心配だから、樹にはたくさんの動物達を住まわせてユグドラシルに生命を与える役割を任せよう。獣だけでは寂しいか、なら魔術師を一人作ろう、非情で残酷で冷酷で人間どもに容赦をしないたった一人の魔術師を。人間でなければ何でもいい。」
そうして嘆きと怒りの糸を籠めて編まれた物語は『ユグドラシル』、シャイアは実質マカロンもといニーズホッグの子であった。
「第二十四話目」
物語の湖は翳差す湖、マカロンの家の背中にある水面下には底までの距離も測られぬゾッとする深さが眠っているが、ちら、ちらと水草のように搖れているそれは、
「最初のユグドラシルだ。」
マカロンはシャイアに背を向けもう一つの湖を見つめたまま答える。
「あの根の下にな、妖精たちの住居がある。」
目視など叶わない深さの奥に。
「妖精は魔術師と共に人間を恐怖で染める役の予定だった。だが魔術師は残忍非道な役ではなく極めて穏和な性格になってしまった、樹を愛し妖精を愛し人間を愛おしむ者になってしまった。なのに樹を守り育み植え続ける、儂がそうあれと使命を与えてしまったからだ。何故だ、攻撃されたのならば逃げろ、辛い目に遭ったら隠れろ、悪口を言われた奴に歩み寄るな、お前はどうして優しく生まれてしまったのだ、儂は何を間違えた?」
ずっと一人だったかつての獣は小さな老人の姿で背中を丸めて蹲る、失敗ばかりの昔の騎士は泣きじゃくった。
「おじいさん。」
シャイアの声は静かに散る桜のようだった。
「おじいさん、僕の話を聞いてください、聞き流すだけでも構わないから。」
両膝を地面におろし青年は老夫の背中に話し始める。
「僕、この国で目を覚ます前ずっと眠っていたんです。夢の中に居るのだけれど、其処では手指足先まで思うように動かせて面白い筈なのに、僕はずっとベッドから窓の外を見ていたんです。外には人間の子供達が遊んでいました、或る子等は走りまわって、或る子等は小さな機械のような物を並べて遊んでいました。僕の身体は動くのに心は彼等彼女等を楽しそうとも羨ましいとも感じなかったのです。でも一つだけ、この身体が動く時がありました、物語を聞く時だけ。」
彼は目を閉じて、いつも物語を聞かせてくれた人物の表情を想い出す。
「今日はこんなお話だよ。いつもその言葉から始まるのです。僕によく似た顔の男の人で、動物が大切だったのでしょう、うさぎや犬猫が登場するお話を毎夜聞かせてくれたのです。いつも主人公はうさぎでした、茶色い垂れ耳のぬいぐるみのようなうさぎが世界中を冒険するお話。」
傷付けるのも仕返しも簡単に出来る事だけれど
「僕がそうしたら、その男の人がとても苦しむんじゃないかって、」
この記憶には居ない人、だけど傷付けたくないと思う人
「だから僕闘わないんです、被害者になっても。きっとこの国の何處かにその人が居るかもしれない、その時残酷な僕を見たらその人どう思うでしょう?」
「おまえは」
老夫の背中は震えている。それが哀しみか怒りか驚嘆から鳴る音かは彼自身にも分らないが原因を追うための感情は全てこの若く見える青年魔術師にそそがれており
「其奴の為に自分を投げ出しているのか、そんな、今はどうなってるかも知れん若造の為に。」
老夫の何か知っている口ぶりに青年は相変らず微笑んでいる。彼は肯きも頭も振らなかった。自分によく似た誰か分らないその人がどんなに捻くれて自分勝手になっていたとしても、自分に物語を紡いでくれたことは嘘ではないと思うから、そう思える人であればもうシャイアにとっては充分だったのだろう。
「第二十五話目」
弟を失った兄は生き生きしていた。もう心を砕く必要も無い、大変な仕事を歯を喰いしばり足に鞭打ち働く必要も無いしんどい時は休んでいい部屋も何だか広々だ。自分の好きな事や物に心血も財も宛がえる、身体も軽い心も軽い、舌打ちも不満の溜息も忘れてしまった!
父は相変らず嫌いだが、まあいい、何だか奴よりも憎くて嫉ましい奴がポッカリ居なくなった気分は心地良い。兄は一人息子となり性格も朗々と闊達になり家庭での夕食は仕事終りの大事な楽しみになっていた。
どうして俺はこの喜びから遠ざかっていたのだろう、馬鹿だな我乍ら。
明日は自転車で遠出でもしてみようか、前はあまり外出しなかったようだ、それも馬鹿らしい。世界はこんなに輝いているのに、俺は家にこもって何をしていたんだ阿保くさい。
「出掛けて来るよー、母さん。」
鍵をおろしてサドルに跨ると、砲弾は音速で彼の腹をぶち抜いた。
国の滅びの始まり方はこうだった。侵略者達が手にしていたのは共通の本、『ユグドラシル』。捲った頁の中から天地創造の言葉達が声を上げた。
「シャイアが何だか不憫だよ、助けてあげよう。」
「邪魔な輩がいっぱい!全員ピカピカに消してあげよう。」
侵略者は…あゝ哀れなりニーズホッグ生みの親。君が仰いだ最初のユグドラシルの底に住まう妖精たちなのだから。楽しんで、ちょっかいを出す。シャイアやエスメラルダの国ではシャイアが妖精の格好の的だったから人間達には手出しする気も無かったけれど、妖精は物語の外には別の世界があり、シャイアが其処と繋がっていることに感づいた。
「シャイアをひどい目に遭わせた世界なんてこうだ!」
「楽しい、楽しい、もっとやろう!」
「一人も残してやらないよ!」
「逃げろ逃げろ、苦しめ苦しめ!」
魔術は本来優しいものだと聞いていたが、これでは………
「第二十六話目」
『ユグドラシル』から放り投げられた爺さんは見慣れた図書塔の床に顔から落っことされていた。
「物語の暴走妖精の攻撃?そんなもの如何倒したらいい?」
憎いのだ、憎いのだ。友好的な手段などあっても取りたくない。
「儂の家族は一人物語へと行ってしまった、妻と長男は物語の妖精どもに殺された。全てはこの『ユグドラシル』の本だ!これさえ焼いてしまえば、もうこの襲撃は」
それは、二度とシャイアに逢わなくすること。彼等の住む世界をマッチ一本で消滅させること。
「構わない!元はと言えば次男が引っ張られたのもこの物語の所為だ。ニーズホッグめ今に見ていろ、お前が大切にしたかった守りたいものは儂が跡形も無く燃やしてしまうぞ!復讐だ、復讐だ、お前の愛おしむ者全て」
今日はこんなお話だよ。いつもその言葉から始まるのです。
「全て…」
自分に物語を紡いでくれた人は、残酷な僕なんか見たくないと思いますよ、とても苦しむんじゃないかしら。
「…………。」
爺さんはマッチを箱に直してヨレヨレのカーゴパンツのポケットに突っ込んでおいた。
「燃やしてはならん…この書には…例え憶えて居なくても儂の息子が生きている…駄目だ、儂には出来ん。すまない、ごめんよ。馬鹿で腑抜けの父さんを許してくれ……」
蹲る。自分が如何に矮小で惨めで弱いことか。
けれど背中にも、果たせる強い使命が必ずある。
―もし、もし…おじいさん…
老夫の目の前に、一匹の白い蛾が訪れた。
「第二十七話目」
―聞えますか、おじいさん。私、谷間の姫百合と言います。貴方とお話するために、やって来ました。
爺さんは谷間の姫百合を見つめた、紫水晶の瞳、その色には見覚えが―
「エスメラルダか?」
―いいえ、私はエスメラルダではありません。私達は『ユグドラシル』に生きるものではないのです。
「君は…谷間の姫百合と言ったか?」
―そうですおじいさん。私は貴方の息子さんを連れて行った張本人です。私が、私たちの故郷に彼を連れて来たのです。
「何故だ?息子は、あの子は…もう儂達の世界が嫌になったから、物語の中に、やはり。」
―いいえ違います。決してそうではないことを、私は貴方にお伝えしに参ったのです。おじいさん、どうか聞いてくださいませんか?
「勿論だ。あの子が慕ったものをどうして儂が拒めよう。…どうか、教えてくれまいか。あの子がそれからどうしているのか、何があったのか……」
―…私の国には一人の少女が暮らしていました。彼女は魔術師でした。とても平和な国でしたが侵略されてたくさんの戦いを知らない命が傷付けられて踏み散らされ消えてゆきました、それを見て少女は怒りのままに敵を全員殺めたのです。そしてその後自裁しました。彼女も故郷も失った私は死を待つだけでしたが、もうじき目をつむるという時、折り鶴と歔欷の声を聞きました。私は彼女が鶴のことを笑って話していたのとその泣声を放っておけずにそれらの内へ飛び込みました。すると身体の傷は癒え、故国ではなく一人の青年の寝台へ辿り着いたのです。
彼は私を邪険にすることもせず受けいれてくれたうえに名前まで与えてくれました。再び名前を貰った時、彼女のことを想い出し、私はうっかりしていたのです………彼が自分の名前を言おうとしていた気配を感じとれなかった。
「名前を?」
―ええ。私たちは彼とは異なる時間に生きるもの。異なる時間に住む者同士は自分の名前を相手に教えてはならないのです。
「まさか教えたら…」
―教えた者は、相手の住む世界の住民となるからです。今まで生きて来た記憶も想い出も、自分自身が何者であったかも忘れて……
「じゃああの子は」
―決して、貴方がたを忘れたがっていた訳ではないのです、離れたくて去ってしまったのではないのです。
自己紹介。そんな何気無い行為で我を失った青年は、谷間の姫百合の國へと意図せず歩いて行ってしまったのだと言う。ということは…
「おまえさんの居た國は、儂等の住んでいた国の前の姿なのだろう?「冬の蛾が自ら謡った話」、あれはおまえさんが語ったものだったのだろう?」
―読んで、くださったのですね。
「ああ。この塔に頭をはたかれるように渡されて、読めと言われた。」
苦笑いを久方振りに浮べた老人に、谷間の姫百合は嬉しそう。
「おまえさんは蛾だが表情が豊かだな。」
―蛾の姿でも、私は雪から紡がれた命ですもの。雪の表情は数えきれないほどあるわ。おじいさん…あの物語は確かに私が謡いましたもの、私はこの国の過去の住民なのです。
「じゃあ息子も過去に行った訳か。だがどうしてあの子はシャイアになった?シャイアはニーズホッグが作った架空の魔術師だったろう?」
―それは、彼が禁忌を犯したからです。
彼女の相貌がたちまち険しくなった。その顔を老夫はよく知っている、図書塔の鏡や窓硝子でよくみた表情…怒りと憎しみ。
「第二十八話目」
或日ユグドラシルの枝が一部欠けていた。まだ名前の無かった獣は月の光が彼女の傷口にそそいでいるのを見つけ、子供が遊んでいる時落して行った布切で覆い結んだ。蓬と梅の花を縫い合わせたハギレはユグドラシルによく似合っており、世界の穏和の象徴である彼女が喜んでくれたことが獣には微笑ましかった。
どうして平穏な日々は続けられないものなのだろう。
「第二十九話目」
名前を失った青年は、谷間の姫百合を胸に抱きしめたまま、ポカンと寝巻姿で湖のある野原につっ立って居た。
「此処は?」
―…私の住む國よ。
「綺麗な場所だね。それに、とても平和だ。」
―貴方、自分の名前は思い出せる?
期待は消していたが尋ねずにはいられなかった、案の定彼は自分のことを憶えていなくて、
「でも君の名前は知っているよ、谷間の姫百合。」
―えゝ、貴方がくれたのですもの。
自分以外のことを憶えている。私の名前も、平穏や美しい、といった言葉の感覚も。
「ねえ、この湖はなあに?夜空みたいでとても美しいね。」
―ここは、昔、大きな樹があった場所なの。ユグドラシル、世界樹と言ってね、世界の平穏を象徴する大樹だったの。
「世界中が平和だったなら育つ樹だったの?」
―そうよ。でも、もう枯れて伐り倒されてしまったんですって、随分昔に…私がこの國で初めて目を覚ました時にはもう湖だけが残されていたの。
私の話に貴方は静かだけど苦しそうな顔をして、見も知らない誰かの為に心を動かせる人、貴方は貴女とよく似ている。
―湖の中には入っては駄目よ。
「どうして?」
―貴方泳ぎを知っているの?
「知ってるよ。凪の水面を見ても怖くないのは、僕が泳ぎを知っているってことだもの。」
―でも危ないわ、この湖には底が無いとも伝えられているのよ。
これ以上貴方を危険な目に遭わす訳にはいかない
―お願い、此方へ来て。私から遠く離れないで。
彼は悲しそうに頷いた。それが原因だったのかもしれない。
「ごきげんよう。」
青年は未だ蛾から少し離れた湖の汀に佇んでいた、その背後にいつからか現れた老人一人。
「湖に入ってみたいのかい?」
マントのフードを深く被り顔は暗く表情が分らない。
―おじいさん、貴方はどこから来たの?
谷間の姫百合は青年の肩へ駈け寄り問うた。
「儂は洞穴からやって来たんだよ。巨石の洞穴、聞いたことはないかい?」
聞いたことはある、それはこの國が生れる前の国のこと。妖精と呼ばれる生きる者達の住処があるとお伽噺で知っているけれど、まさか本当に…?この老人を信用しても良いのだろうか、この子に危害を及ぼすのじゃあないかしら。
「おまえさん、何が悲しい?」
老人は青年に聞いたが相変らず何處を見ているかはハッキリしないので草原に伸びる青年の影に話している風で
「僕が、悲しい?」
「先刻そのお嬢さんに呼ばれた時悲しそうな表情をしていただろう。」
なのにどうして口元が笑っているように見えるのだろう
「あゝ、それはこの湖に潜れなかったからだよ。底が無いって言われているのだって、だから入ってはいけないの。」
でも顔だけでも浸して水面の下を覗いてみたいな、なんて。
青年の言葉は声に出されることはなかった。途端に大きな尻尾のようなもので谷間の姫百合共々湖にはたきこまれたから。
「第三十話目」
最初の樹は獣の住処、やって来たのは迷子の樹。
迷子の樹は時間のかみさま、けれど傷付けられて悲しい涙でやって来た。
月を仰ぐ獣は怪我した樹の枝にハギレを当てて寒くないように温めた、獣が名付けられてしまう一夜前。
名前を付けられ憎まれた、守る樹までも憎まれて、憎まれ続けてあゝ伐採。伐採の後は炎が広がるばかり、誰も食い止めることは叶わない。
次の樹は紛い物、見掛けはそっくり嘘っこの樹。贋作は嫌われる、嘘吐きは疎まれて、守る魔術師共々燃やされた。
また次の樹も偽物、名前だけは最初と同じ。芽も生えないのに雄鹿達は何を食べている?それは名付けられた竜ニーズホッグが食べるものと同じ。
もう二度と最初の樹は生れないのに魔術師はぜんまいを巻かれて動き続ける、倒れたら糸でからくり歩かせる、前を見て進ませるのはそう在れと願うから。虚しい願いで繋がれる魔術師はとても優しい柔和な子、人間に袋だたきにされても一片も憎み返さない怒りを失った子。
湖はうつくしい、あらゆる感情を殺すから。
「第三十一話目」
湖に生者を入れてはならない、それが国の國の絶対の約束であった。一度湖の水を知った者はずっと湖の傍でしか生きられない、例え抗い離れようものなら自分で自分を突き刺してしまうと言う。
―ニーズホッグは自分の物語に丁度良い人間を探していたのです。元は人間である者が人ならざる魔術師へと作り変えられ人間達を蹂躙させる、それが彼の人間へ対する復讐だから。
「でもあの子は、」
―えゝ、ニーズホッグの思い通りにはなりませんでした。あの子はとても不思議な子…記憶を全て忘れた筈なのに、彼は自分の大切な思い出を亡くしていないのです。
「自分の兄の、それも随分と昔のことをあの子は憶えていた。儂は碌でもない父親だった、さっぱり忘れてくれて良いものだが、兄弟のことは忘れないでいてほしかった…そうか……そうか………」
老人は図書塔の天井に咲く一ツ星を仰ぐ。
「あの子はもう、シャイアとして生きると決めたのだろう。物語の中でずっと報われない存在として立ち続けてしまうのだろう。」
儂は儂のままではおまえに話すことも叶わないが
「救われる結末はないのか?あの子の過去が報われるような救いの枝筋は。」
―あの湖から解かれないことには、何も…せめてニーズホッグが物語を終わらせてくれたなら。
「おまえさんは如何して湖から離れて儂のもとに来られたんだ?まさかもう死んでるなどとは言わんよな。」
―……あの娘のおかげなのです。
「あのこ?」
―私が愛した少女…先程お話した魔術師の女の子。自裁の直前あの子は湖に呪いを与えました、足を踏み入れたら決して逃げられないようにする呪い。それはこの後訪れた者に滅んだ國のことを永遠に忘れられないようにさせる為だったのだと思います。けれど…
あの表情を私はいつまでも憶えている
(あなたは忘れないでしょう?)
大好きだった貴女の言葉、ずっと私の淵を傷付け血をしたたらせる貴女の最後の優しさ。
―私は語り部になる宿命だったのです。何處へでも飛んで行きうつくしく哀しかった故郷を後世に語り継ぎ未来へ遺す、それが彼女の最初で最後の抵抗、破壊への唯一の復讐だったから。
「そうか。」
残された者は、すぐにはその宿命を受け入れられないもの。けれど必ず受け入れる者。
「第三十二話目」
ニーズホッグの失くし物、最初の樹を手当てした時の梅と蓬の布片一つ。
「マカロンおじいさん、布は何處に行ってしまったの?」
シャイアはまだニーズホッグの家に入っていなかった。
「大切なものだったんでしょう?最初の、ユグドラシルに結んであげた…」
最初の樹は死体となって翳る湖に沈められたまま、其処からまた妖精達が羽音も軽く飛んで遊んで人間の存在を許さない。
筈なのだが
「ねえ、如何して妖精が一人もいないの?」
日の沈んで月の射す、いつもは鱗粉の輝く夜の画に、いたずら好きのみんなが居ない。巨石の洞穴は静まりかえって小石の響きすら鳴ってもいない。
「おじいさん…」
石で丸くきちんと囲った内で火を焚く。その炎は大昔初夏を祝い寿いだ儀式だったが
「エスメラルダ、シャイアを家の中に入れてあげておくれ。」
シャイアの問いには答えず代りに雄鹿に頼み言を。
―いいのだな。
「あゝ、もうじき冬は終る、春は失われた。初夏の喜びが戻って来る。」
エスメラルダの両眼は一度深く閉ざされて、再び紫水晶が見えた時、少し潤んでいるようで、耐えているようで。
―シャイア、扉を開けて中に入りなさい。
「でも」
―いいから、先に。
「うん……」
相棒の言葉を無下には出来ず、シャイアはおとなしくエスメラルダに従った。中は電灯一つ点いておらず、窓も閉め切りカーテンも下ろされているから外よりも夜の黒が濃い。
「エスメラルダ、何も見えないよ?」
声と同時に電灯が点く。
直後シャイアは全身で悲鳴を上げた。
暖炉の傍の小さな食卓には人間だったものが白い皿の上にきちんと並べられていたから。
「第三十三話目」
名前を持たない獣は空腹を知らなかった。何かを食べる、と言う行為と無縁の生活であった為か、常に満たされている感覚は呼吸のように自然に彼を廻ってそそがれ止むことは有り得なかったのだった。
けれどニーズホッグとされてからは常に飢えて我が身を齧り血をすすっても飢えは渇き苦しみ続けた。その苦しみは最初のユグドラシルが倒されて後二度目の樹を植えた時治まった。
憎い人間を、食べた時に
妖精達は夜な夜な人間をニーズホッグのもとへ連れ去って来てくれたから、彼が飢えに喘ぐことはもう無くなった。のに
「…………」
シャイアは声を失った。口を動かしても音が出ない。代りにエスメラルダの声が続ける。
―これがニーズホッグの食事だ。彼は人間を殺して喰らうことでしか自身の渇きを潤せない。
「シャイア。」
言葉を発せない青年の後ろで扉が開き、老人が入って来た。
「儂はニーズホッグ。討たれ倒されるべき醜い竜、悪魔の竜だ。いつか人間に殺される役目を負っていたのに、儂はその運命に憎しみを以て刃向い、妖精達を利用して人間を殺し続けた、この物語が終らなければ良いと祈った、終らせてはならないのだと信じ続けた。だがその信仰は間違っていた、シャイア。」
老人はゆっくりと悲しむ我が子の背中にしゃがみ、掌を当てた。
「お前に干上がりそうな湖で声を掛けられて振り向いた時、聞いたことの無い声が聞えたんだ。儂にしか聞えてないようだったが、心に確かに刻まれる声だった。彼はこう言ってたよ。」
すまなかった、すまなかった、儂をどうか恨んでおくれ
「恨んで…?」
掠れたシャイアの声はその声の持ち主とどこか似ていた。
「シャイア、いや、青年よ。きっと誰かがお前を探しているんだ。あの声は、あの言葉は、そういう声だった。
同じ言葉を炎の夜自分も譫言みたく繰り返していたから。
もう二度と逢えない存在をもがいて彷徨う言葉はよくわかる。
「彼はお前を探している。お前は彼のもとへ帰りなさい。この銀食器で儂の身体を軽く刺せばいい。儂を食べるフリをする格好をすればお前は元居た場所へと戻ることが出来る。」
闇、だとか影、とかを払えるのはいつだって何気無い味気無い極々平凡な日常の動作だ。争いに剣とか槍とか銃とか特別な物で応戦する義理なんてありはしない。
「…僕が、戻ったら……貴方は?」
掠れた声は前みたいに滔々と紡げなくなっている。
「これは物語だ。悲しみから始まった御伽噺はハッピーエンドで幕を閉じるのが相応しいものさ。」
「そんな、貴方を、貴方達を置き去りになんて出来ない。」
「儂は世界樹が人間達の感情を受け入れ倒された時から本当はもう置き去りだった、それだのに儂は第二第三の世界樹を作り出した気になって事実から目を背けて嘘の樹を語り続けた……そんなことさせたいが為にユグドラシルは去った訳でもなかろうに…」
最後の方の小さな小さな呟きは青年の瞳の奥に在るハギレに向けられたものだったろう。
物語は何處かで頁を閉じられなければならない。例えその中にどれだけの言葉や色がさんざめき命にあふれかえっていても。
「第三十四話目」
あり得ないこととは、昔に起きているもの。神秘の薄れた世界が御伽の絵の世界に滅ぼされるなんて、昔のこと。人間と言う人間を傷付けて一人残らず滅ぼす心算も、そして誰かが必ず生き延びるという現実も。
「おじいさん、この扉は何?」
名前を思い出せない白い記憶の少年が、塔の掃除夫に聞いたことがある。老人はしばらく壁に形だけを残す扉達を眺めていたが、やがてフッと力を抜いた笑い声で答えた。
「いつかおまえさんも分る日が来るさ。」
きょとんと首を傾げる子どもの頭に、白い蛾が留まり、二人はまた図書塔の中での追いかけっ子に興じ始めた。
可能性はたくさんあれど、歩く道は一つだけ。さよなら過日の物語、また何處かで、まっさらで逢えるその日まで。
終幕
「英雄譚」