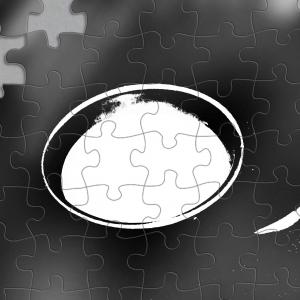「氷の遺志」
「一枚岩の軍人さん」
呼びとめたのは十五の娘
背中にまわした片手には
仕事の痕の血でも握っているのだろう
しかも娘のものでなく
殺めた相手の血であろう
「氷の軍人さん、こんにちは」
森の入り口には木がしなる
媚びるようにアーチを組んで
娘は自然の門の真中に立っている
切れ長なふたえ 何が重なる
そんなに綺麗な羽衣を
無粋な赤の迷彩で塗りつぶすなど
「氷の軍人さん、こんにちは」
薄く笑う桜桃の唇
歯は白く覗く
―本音か?
問うてみる
「本音だよ」
娘は眼をつむり 微かに笑った
その長い睫毛は微かに震えた
然れど涙は目に見えず
娘は心より
自分が泣くことを許してはいないのだろう
頬にこの手が近づけば
彼女は体温にびくりと怯え
隠してた短刀で腕を刺した
これがこの子の苦しみか
彼女の鋭かった瞳は搖れ始めた
孤独な使命に支えられていた華奢な背中を
壊れないように抱きしめた
あわれ硝子で傷だらけのさ迷い子
ここが君の居場所になればと願って
氷は溶けて
死にかけの花を包み始めた
「氷の遺志」